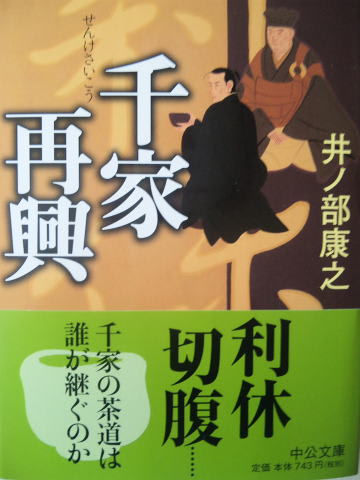受付会場は熱気でむんむん。集まった人たちは総勢80人余り。
「おーい、写真屋」と声を掛けてくれたのは上深川のTさん。
いつもの通りの挨拶言葉は嬉しい台詞。
写真家でなくて写真屋だ。
心に響くものだから、ところどころで自己紹介の際に使わせてもらっている。
八島のⅠさん、田原の里のOさん、同田原のOさん、北野のTさん、丹生のSさん、生駒のTさん、同生駒のTさん、白石のFさん、奈良市のAさんら多数が舞っていた、ではなく開始時間を待っていた。
いずれも取材地でたいへんお世話になった人ばかりである。
その場には紅一点の女史もおられた。和田のOさんだ。
存知している人たちは他にも多数おられたがご挨拶もできる時間もなく若草の間会場にあがった。
あがったといっても座敷ではなく洋間である。
テーブルは八つ。それぞれに名前が掲げられている。
「チャンガラカン」、「翁舞」、「火取り」、「大踊り」、「鬼はしり」、「祭文語り」、「題目立」に「太鼓踊り」だ。
行事の名称を付けたテーブル名。粋なものだと感心する。

会場に設えたスクリーンにそれらの行事を示す映像が映し出された。
どこかで観たような映像だと思った。
一枚、一枚、順番に映し出された映像は、県立民俗博物館で平成24年7月から11月にかけて企画展示された『大和の祭りと芸能-神を祭り、歌い踊った大和人のハレの世界』であった。
そのすべてではないがごく一部。
列席者関係の映像だけだったのか主役の鹿谷勲氏に聞く時間もなく始まった会場の猿沢荘は、昭和29年(1954)に地方職員共済組合県支部の保養施設として開業した。

猿沢荘はその名の通り、興福寺階段下にある猿沢池のすぐ近くにある宿泊旅館。
大規模に改修されてリニューアルオープンしたのは平成19年であったが、激化してきた低価格ホテル競争によって客足は伸びなかった。
苦しくなった組合運営での継続は難しく、今年の8月末にはやむなく廃業すると新聞報道が伝えていた。
猿沢池は存じているが、私は県職でもない。
これまで利用することもなかった。
この日の宴は県職員であった鹿谷勲氏の退職祝賀会。
『お疲れさん、これからもがんばろ会』の副題をもつ。

中央のテーブルに広げられたご馳走が並ぶ。
これらはわざわざ東京から取り寄せた江戸前鮒佐(ふなさ)の佃煮商品。
特別に頼んでおいたそうだ。
鮒佐は佃煮専業150年の老舗店。
伝統の江戸風味を味わってほしいと取り寄せたと後日に聞いたが、食べることを失念していた。
鹿谷氏との始めての出合いは三輪の初えびすで行われている「御湯の神事」である。
平成15年2月のころだ。
それまで知ってはいるものの遭遇したのは始めてであった。
鹿谷氏の著書に『やまとまつり旅―奈良の民俗と芸能』がある。
平成13年10月に大和崑崙企画から発刊されたご本である。
発売されたことを産経新聞が報じていた。
その切り抜きは今でも大切に購入した『やまとまつり旅』に綴じている。
平成13年のころの私は大和民俗に心を奪われつつあったころだが、民間企業のサラリーマン時代だった時期でもある。
休日には知った祭りや行事を拝見したくてちょこちょこと出かけていた。
ちょこちょこだから詳しくは知らない大和の祭りや行事。
それがどっさり書かれてあった『やまとまつり旅』に感動したのである。
感激した胸のときめきは礼状にしたためた。
『先月初めに産経新聞に紹介され、本屋さんに注文してやっと手に入れることができました。ならの祭りや行事を解説している本は古本屋さんにもなく、新刊本もなく本当にありがたく思いました。高名な神社や寺の行事は多くの本が出版されていますが、地域や村で行われているものは見つかりませんでした。読んで感じるのは少子化に伴って村々で昔から延々と続けられている行事を、これからも残していくことが難しい時代です。室生田口水分では、小学校が廃校になったので、ますます難しくなりました。今年始めて女性の笛や小太鼓役が担っていることがその一端をあらわしています。私は奈良に移り住んで20年になりますが、これだけ沢山の祭りや行事があることを知ったのは、ごく最近のことで写真にできるだけ残していきたいと思い、撮っては自分のホームページに登載している次第です。ただ現役のサラリーマンなので、撮影活動は休日に限られているので、何十年もかかるのではと思っています。もしよろしければ私のホームページも見ていただければ幸いに存じます。まずは御礼まで。「ならグルグル散歩」』は、いま読み返してみればファンレターのような文面になっている。
自己紹介をして名刺を手渡した祭場の三輪。
礼状を送ったことも伝えたが記憶にないようだった。
送付先は出版社であった。
ご本人には伝えられなかったようだが、大和崑崙企画の編集者からお礼のメールをいただいたことだけは確かだ。
続編が出版されることはなかった『やまとまつり旅』である。
三輪でお会いしたときは県教育委員会文化財保存課であったが、その年の4月には平城遷都1300年記念事業に携わることになっていたようだ。
その後の私は大和の民俗行事に没頭したいがために平成14年9月に民間企業を早期定年で退職した。
鹿谷氏と再びお会いしたのは平成17年に県立民俗博物館に異動してからのことだ。
実はそれ以前にもお会いしている。
川上村の「森と泉の源流館」スタッフからお誘いを受けた第八回いろりばた教室でのことだ。
川上村の民俗芸能をメインテーマに語られた太鼓踊りと盆踊り。
呼称、歴史、編成、絵馬資料等様々な角度から解説され、私にとっては大変勉強になった講演会。
今後の民俗行事取材にたいへん参考になる内容であった。
その年の4月に異動された県立民俗博物館。
長くなったおつきあいは、そこから始まった。
「県立民俗博物館は大和郡山市が所在地。できうる限り集めてほしい」と願われた。
それから数年かけて取材した大和郡山の祭りと行事は、博物館初のロビー写真展になった。
平成20年6月のことだ。
県下一円も取材してきたが、多くは大和郡山。
その後も継続してきた結果が2回目のロビー写真展。
平成21年10月に開催してくださった。
その年の7月に初著書である淡交社刊『奈良大和路の年中行事』に協力してくださった。
この本のことは未だに褒めてくださる春日大社の岡本彰夫権宮司。
恐縮するけどありがたい言葉である。
2回目の大和郡山の祭りと行事展を取材した産経新聞に応えていた鹿谷氏の言葉がある。
「田中さんのきめ細やかな取材活動に基づく情報収集力は、学芸員の数に限りがある博物館ではできないこと」と評価すると報道された。
大和郡山の祭りと行事写真展はさらに発展して企画展となった。
平成22年のことである。
その後は大和の民俗を捉えるカメラマンによる「私がとらえた大和の民俗」に発展継承された。
なにかとお役に立ってきた県立民俗博物館。
平成25年3月を最後に県職員を退職された鹿谷氏とのつきあいは今後も続くであろう。
この日の宴は題して「これからもがんばろ会」。
田原の里の三人が祝いのダイビキを披露してくださった。

これまでにも数か所で拝見したトーヤ家の祝い唄。
この場で拝見するとは思ってもみなかった。
突然のダイビキ披露に、心を引き締めて再びスタートラインに立ったと思ったがんばろ会。
会場をあとにしようと思った場におられた若い男性。
もしかと思って声を掛けたら鹿谷氏の息子さんだった。
おそるおそる聞いた出身高校名。
なんと我が家の次男と同じ高校である。
何年か前に次男が言った。
高校の卒業名簿に「鹿谷」の名があると言っていた。
どうやら同じクラスの同級生。
次男の名を伝えたが覚えていないと話す。
我が家の次男も同じくそう言っていた。
特徴がないのか、お互いに記憶がないようだ。
奇遇な出合いは息子たちには伝わらなかったようである。
(H25. 6. 1 SB932SH撮影)