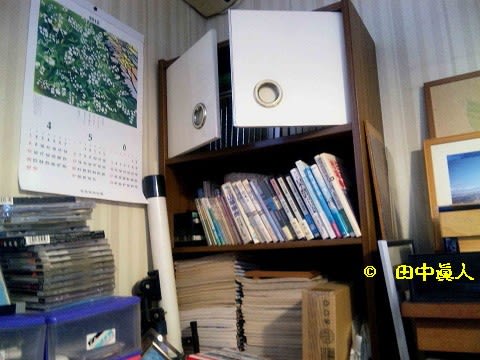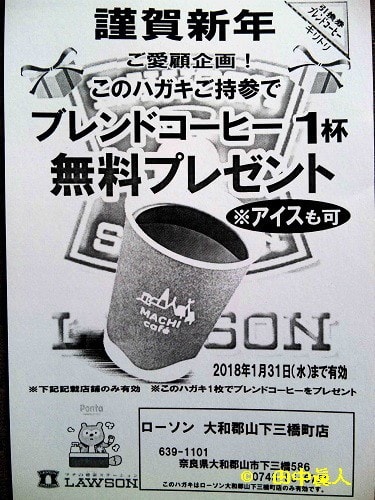型番はOCV-JX12。
とうとう廃棄処分することにしたソニーパソコン。
長年、愉しませてくれたデジタル画面もそっくり含めて我が家を出ていく。
かーさんが依頼した破棄用品回収古物商奈良クリーンが来られた。
廃棄物は、中庭にある鉄製の物置。
中身は園芸用の道具に使い古しの諸々。
下部の土台は、雨水ですっかり錆びれて斜めに傾いた。
扉はギクシャクして外れたままに放置。
そのうち大風がやってきて扉がぶっ飛ぶ。
ただ、中庭は植物がいっぱい。
梅の木から山椒の木に南天もある。
それら樹木が支えてくれて大事に至らなんだ。
ただ、放置してから何年も経てばえげつない状態になっていた。
力仕事ができなくなった私に代わってスチールパイプ製の棚の分解はかーさんが実行した。
やっかいなことに、分解は途中まで。
ねじ山、ボルト山が潰れてしまい分解はできない。
叩き壊す大きなハンマーもない。
諦めたところに見つけた古物商。記してあった電話をかけてお願いしたらすぐに来てくれた。
中庭でやっさ、もっさしている古物商の顔を見て・・・・・あれぇ、である。
なんとその男性は顔見知り。
なんで、と聞けば、数年前から知人に教わって商売をしている、というKさん。
金属製のねじ山が潰れており、解体不能の物置。
なんとかしたいが、本日は専用道具がない。
取り急ぎ、急がねばならない次の顧客さんへ・・。
午後4時に終わる予定が、延長戦に突入したから本日作業はそこまで。
回収は、明日以降に来ます、と来訪予定と電話で告げたKさん。
これまで当地区の行事写真を撮ってもらっているから、料金無用と・・。
そんなんあかんから、と伝えても・・受け取る気はない、という。
翌日の午後3時半。
ありがとう、と廃棄処分のお礼に柿のプレゼントを玄関前に置いていた。

Kさんの気持ち、むちゃ嬉しいけど、支払いは来月末に行われる大晦日行事のときまでに・・。
(H30.11.19 SB932SH撮影)
(H30.11.20 SB932SH撮影)
とうとう廃棄処分することにしたソニーパソコン。
長年、愉しませてくれたデジタル画面もそっくり含めて我が家を出ていく。
かーさんが依頼した破棄用品回収古物商奈良クリーンが来られた。
廃棄物は、中庭にある鉄製の物置。
中身は園芸用の道具に使い古しの諸々。
下部の土台は、雨水ですっかり錆びれて斜めに傾いた。
扉はギクシャクして外れたままに放置。
そのうち大風がやってきて扉がぶっ飛ぶ。
ただ、中庭は植物がいっぱい。
梅の木から山椒の木に南天もある。
それら樹木が支えてくれて大事に至らなんだ。
ただ、放置してから何年も経てばえげつない状態になっていた。
力仕事ができなくなった私に代わってスチールパイプ製の棚の分解はかーさんが実行した。
やっかいなことに、分解は途中まで。
ねじ山、ボルト山が潰れてしまい分解はできない。
叩き壊す大きなハンマーもない。
諦めたところに見つけた古物商。記してあった電話をかけてお願いしたらすぐに来てくれた。
中庭でやっさ、もっさしている古物商の顔を見て・・・・・あれぇ、である。
なんとその男性は顔見知り。
なんで、と聞けば、数年前から知人に教わって商売をしている、というKさん。
金属製のねじ山が潰れており、解体不能の物置。
なんとかしたいが、本日は専用道具がない。
取り急ぎ、急がねばならない次の顧客さんへ・・。
午後4時に終わる予定が、延長戦に突入したから本日作業はそこまで。
回収は、明日以降に来ます、と来訪予定と電話で告げたKさん。
これまで当地区の行事写真を撮ってもらっているから、料金無用と・・。
そんなんあかんから、と伝えても・・受け取る気はない、という。
翌日の午後3時半。
ありがとう、と廃棄処分のお礼に柿のプレゼントを玄関前に置いていた。

Kさんの気持ち、むちゃ嬉しいけど、支払いは来月末に行われる大晦日行事のときまでに・・。
(H30.11.19 SB932SH撮影)
(H30.11.20 SB932SH撮影)