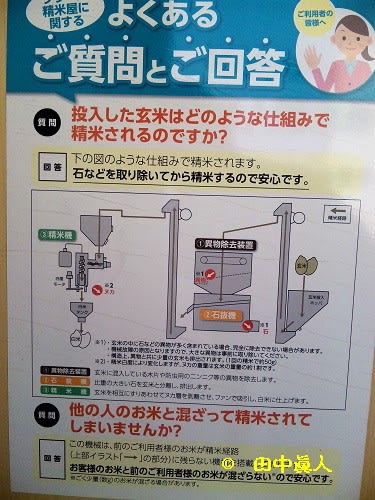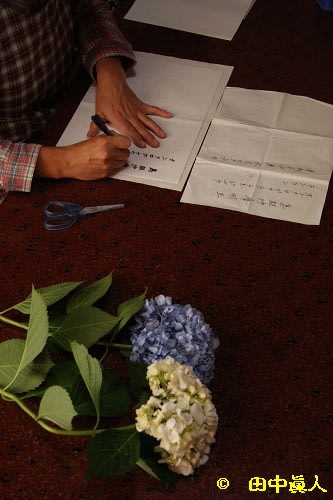出原眞さんが写真展をしているとFBが伝えていた。
展示会場は橿原市の今井町。
会場所在地はわかったが、教えてもらった今井西環濠駐車場までは歩いて10分ほど。
つい先月の平成30年4月15日に利用できるようになった環濠に黄色い花が咲いていた。
美しいアサザの花だった。
それに魅了されて来た道を戻っていく。
今井町の通りは軽自動車が通れるくらいの道幅。
趣きのある今井町集落に馴染みの人がいる。
今でも暮らしているのか、久しく会っていないから消息不明だったが、FBに突如として出現した名前。
同姓同名の可能性もあるが、メッセンジャーをしたが反応は返ってこなかった。
今井町のどこか、ある筋。
随分前の記憶ではどこの筋であったのか、まったく記憶がないが、ふと目に着いた郵便受け。
名前シールが貼ってあったからわかった彼の住まい。
たしか私より数年下の年齢であるが、定年は満了しているだろう。
ドアを引いてみれば動く。
呼び鈴がない家はそうせざるを得ないドア開け声かけ。
大きな声で何度かしてみたが反応はなかった。
ドアの向こうは奥行きが広い。
間口は一般的だが、奥行きがそうとう向こうになる。
何十年も前に一度訪れたW家。
修築するにも町全体が指定されているから勝手なことはできない。
景観状態を守りつつ、保護もしなければならない伝統的町屋の景観条件が「重要伝統的構造物群保存地区」選定。
平成5年12月8日に文化庁登録(※平成29年11月現在)された今井町は暮らすのも難しく難儀すると云っていたが・・。
彼の住まいする丁は3丁目。
さらに東へ行けば4丁目。

ふと見上げた玄関の表札掲げる輪っかはどこかで見たことのあるようなモノだ。
小型のそのモノは何かの材料で編んだ輪形状。
それに幣を付けている。
貴重な民俗史料になると思って画像記録。

拡大してみれば藁細工ではないことがわかる。
何かの葉っぱ。
・・・カヤの葉ではないだろうか。
そうであれば大阪・能勢町の天王区で拝見した茅の輪と同じである。
飾っていたお家は通りのすべてではなく数軒。
一軒、一軒見てきた軒数は4軒も。

色合い、風合いに手造り感のある茅の輪はずいぶんと年数が経ったと思われる。
崩れ方は経年劣化なのか。
前年なのかその前からずっと掛けているのか。
所有者に聞かなければならないが・・聞取り時間がないから諦めて、写真展会場の「にぎわい邸」に向かう。
さまざまなイベントにギャラリーや癒しの貸しスペースを提供する「にぎわい邸」。
施設は民間であろう。
写真展を見終わっておられた当主と思われる女性に尋ねてみる。
見たこともない形であるが、元会社の知人のW家はご存じだった。
筋違いの棟には伊勢講がある。
講の持ち物を持ちまわる営みは知っているが、この輪っかは見たことがないという。
もし、わかるようであればご一報いただきたく名刺を渡しておいたら、二日後の17日に携帯メールで伝えてくださった。
行事は6月30日に地元今井町の春日神社で行われる夏越の祓いだった。
茅の輪潜りをした参拝者は神事を終えてから、真菰で作られた小型の茅の輪を持ち帰って玄関に掲げるということだった。
ありがたい行事情報によって見立て判断は間違っていなかった。
良ければ行事も拝見したいと伝えたら、どうぞ、である。
またひとつ、奈良県内の民俗を記録させていただける。
ありがたく日程調整した。
ネットでさらに調べた今井町の伝統行事。
7月7日に春日神社で行われる行者講や7月15日の太神宮さん、7月23日・24日の地蔵講もあるとわかった。
今井町はだんじりが出る秋の祭りが有名らしいが、こうしたあまり関心が寄せられない民俗はすごく貴重だと思っている。
機会があれば是非とも取材させていただきたいものだ。
(H30. 5.13 SB932SH撮影)
展示会場は橿原市の今井町。
会場所在地はわかったが、教えてもらった今井西環濠駐車場までは歩いて10分ほど。
つい先月の平成30年4月15日に利用できるようになった環濠に黄色い花が咲いていた。
美しいアサザの花だった。
それに魅了されて来た道を戻っていく。
今井町の通りは軽自動車が通れるくらいの道幅。
趣きのある今井町集落に馴染みの人がいる。
今でも暮らしているのか、久しく会っていないから消息不明だったが、FBに突如として出現した名前。
同姓同名の可能性もあるが、メッセンジャーをしたが反応は返ってこなかった。
今井町のどこか、ある筋。
随分前の記憶ではどこの筋であったのか、まったく記憶がないが、ふと目に着いた郵便受け。
名前シールが貼ってあったからわかった彼の住まい。
たしか私より数年下の年齢であるが、定年は満了しているだろう。
ドアを引いてみれば動く。
呼び鈴がない家はそうせざるを得ないドア開け声かけ。
大きな声で何度かしてみたが反応はなかった。
ドアの向こうは奥行きが広い。
間口は一般的だが、奥行きがそうとう向こうになる。
何十年も前に一度訪れたW家。
修築するにも町全体が指定されているから勝手なことはできない。
景観状態を守りつつ、保護もしなければならない伝統的町屋の景観条件が「重要伝統的構造物群保存地区」選定。
平成5年12月8日に文化庁登録(※平成29年11月現在)された今井町は暮らすのも難しく難儀すると云っていたが・・。
彼の住まいする丁は3丁目。
さらに東へ行けば4丁目。

ふと見上げた玄関の表札掲げる輪っかはどこかで見たことのあるようなモノだ。
小型のそのモノは何かの材料で編んだ輪形状。
それに幣を付けている。
貴重な民俗史料になると思って画像記録。

拡大してみれば藁細工ではないことがわかる。
何かの葉っぱ。
・・・カヤの葉ではないだろうか。
そうであれば大阪・能勢町の天王区で拝見した茅の輪と同じである。
飾っていたお家は通りのすべてではなく数軒。
一軒、一軒見てきた軒数は4軒も。

色合い、風合いに手造り感のある茅の輪はずいぶんと年数が経ったと思われる。
崩れ方は経年劣化なのか。
前年なのかその前からずっと掛けているのか。
所有者に聞かなければならないが・・聞取り時間がないから諦めて、写真展会場の「にぎわい邸」に向かう。
さまざまなイベントにギャラリーや癒しの貸しスペースを提供する「にぎわい邸」。
施設は民間であろう。
写真展を見終わっておられた当主と思われる女性に尋ねてみる。
見たこともない形であるが、元会社の知人のW家はご存じだった。
筋違いの棟には伊勢講がある。
講の持ち物を持ちまわる営みは知っているが、この輪っかは見たことがないという。
もし、わかるようであればご一報いただきたく名刺を渡しておいたら、二日後の17日に携帯メールで伝えてくださった。
行事は6月30日に地元今井町の春日神社で行われる夏越の祓いだった。
茅の輪潜りをした参拝者は神事を終えてから、真菰で作られた小型の茅の輪を持ち帰って玄関に掲げるということだった。
ありがたい行事情報によって見立て判断は間違っていなかった。
良ければ行事も拝見したいと伝えたら、どうぞ、である。
またひとつ、奈良県内の民俗を記録させていただける。
ありがたく日程調整した。
ネットでさらに調べた今井町の伝統行事。
7月7日に春日神社で行われる行者講や7月15日の太神宮さん、7月23日・24日の地蔵講もあるとわかった。
今井町はだんじりが出る秋の祭りが有名らしいが、こうしたあまり関心が寄せられない民俗はすごく貴重だと思っている。
機会があれば是非とも取材させていただきたいものだ。
(H30. 5.13 SB932SH撮影)