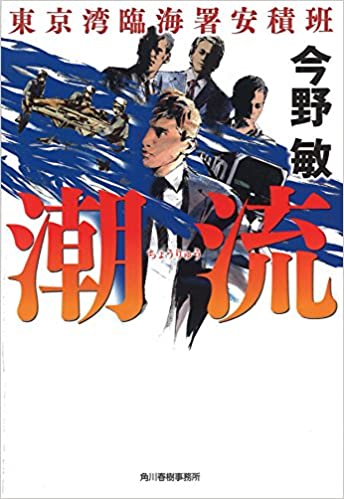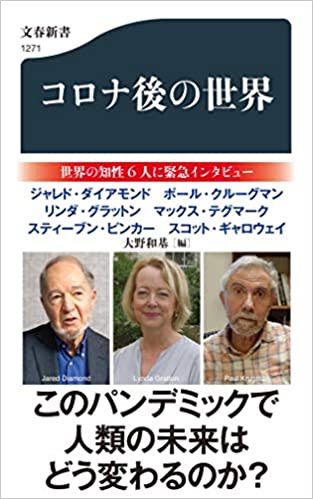『呪護』は鬼龍光一シリーズの前作を含め第5作になります。
出雲族を祖とする鬼道衆に属する鬼龍光一は陰の気が凝り固まって怒りや性欲に憑りつかれたようになる「亡者」の退治を生業とする祓い師で、黒づくめの服装がトレードマーク。同じく出雲族のトミノアビヒコを先祖とする奥州勢の安倍孝景は白づくめの服装に銀髪がトレードマーク。この黒白コンビが怪奇の分野を担い、現実主義の極みと言える警察側に属する警視庁生活安全部・少年事件課・少年事件第三係の巡査部長、富野輝彦が主人公で、怪奇物語に警察小説という器を与える役割を果たしています。
しかし、この富野輝彦もトミノアビヒコの直系トミ氏に連なる者で、本人は自覚していないのですが、霊能系の能力を秘めているらしく、また、鬼龍と孝景と共に奇妙な体験を重ねるうちに、法律に基づく現実と霊能的観点から見た現実の狭間で悩み、だんだんと一般常識や警察などが見ているものだけが真実とは言えないことに気付いていきます。
本来がちがちの現実主義者である富野輝彦がだんだんと変化していく様がこのシリーズの味わい深さの1つです。富野の存在なくして警察と霊能系の接点はあり得ないので、要の存在であり、その点が単なる怪奇ものとは違う魅力でもあります。
さて、本作は都内の私立高校で、男子生徒が教師を刺すという傷害事件をめぐる物語です。警視庁少年事件課の富野が取り調べを行ったところ、加害少年は教師に教われていた女子生徒を助けようとしたと供述したのに対して、女子生徒の口からは全く異なる事実が語られる。その学校で「適合者」であるその教師と性交する儀式によって法力を得るために必要だったという。
天台宗系の密教・台密に連なるセクトと真言密教・東密の系譜を引き継ぐセクトが東京守護のための結界を巡って攻防を繰り広げていることが傷害事件の背景だった可能性があり、富野は鬼龍たちと真実を探る捜査を始める---。
なかなかスケールの大きい呪術的仕掛や結界の話が非常に面白いです。
その一方で、刺された教師は強制性交等罪で起訴されるのか、淫行条例違反で罰せられるのか、議論され、「被害者」がいないケースで十把一絡げに「淫行」と決めつけ裁くことの意味に疑問が投げかけられ、警察小説らしい現実感ががっちり組み込まれているその絶妙な怪奇と警察のバランスがすばらしいです。
ぜひご一読あれ。
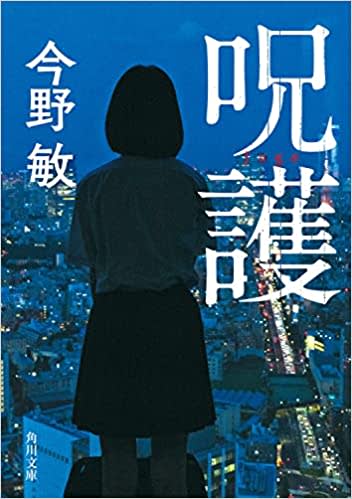
安積班シリーズ
隠蔽捜査シリーズ
警視庁強行犯係・樋口顕シリーズ
ST 警視庁科学特捜班シリーズ
「同期」シリーズ
横浜みなとみらい署 暴対係シリーズ
鬼龍光一シリーズ
奏者水滸伝