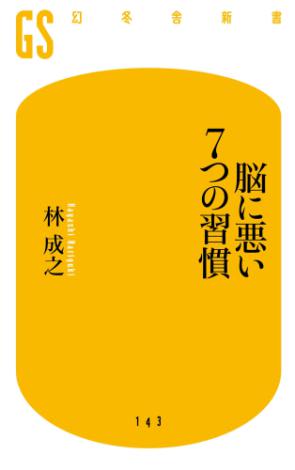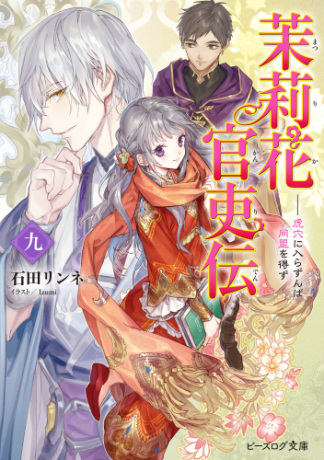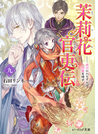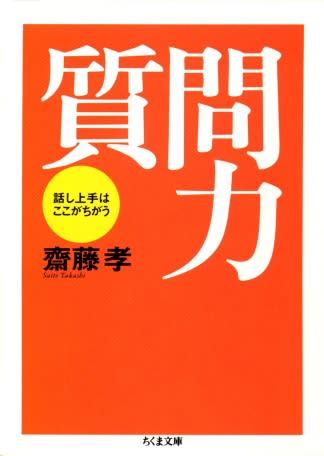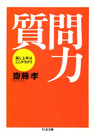audiobook で聞き放題対象になっていたので1.5倍速で本書を聴いてみました。
脳に悪い7つの習慣とは、
(1)「興味がない」と物事を避けることが多い、
(2)「嫌だ」「疲れた」とグチを言う、
(3)言われたことをコツコツやる、
(4)常に効率を考えている、
(5)やりたくないのに、我慢して勉強する、
(6)スポーツや絵などの趣味がない、
(7)めったに人をほめない。
これらをやめるだけで頭の働きが倍増する理由を、脳のしくみからわかりやすく解説しています。
このところ脳科学関係の動画を見たり本を読んだりしていたので知っていることも結構あったのですが、順序だった説明で分かりやすく非常に勉強になりました。
内容を自分なりにまとめると、脳の本能は「生き(のび)たい」「知りたい」「仲間になりたい」という欲求で成り立っている。
記憶には作業記憶(ワーキングメモリーと言われることも多い)の他に体験記憶、エピソード記憶、学習記憶、運動記憶の4種類がある。そのうちいわゆる「記憶力」として重要なのは体験記憶、エピソード記憶、学習記憶の3つ。
まず、脳はあらゆる外界からの刺激を作業記憶にとどめて、作業が終了した後あるいはしなくても自分にとって(特に自分の生存と報酬)重要かどうかを判断し、重要でないと判断されたものは長期記憶に移行することなく消えていく。記憶が形成されるには、3つのルートがある。
「好き」「興味」:入ってきた情報に対して、A10神経群というところで好き・嫌いのレッテルが貼られ、好きのレッテルのついた情報では思考が進み、イメージ記憶として残る。
または「自分にとって嬉しい」と思える情報に対しては、報酬系の神経群が活性化されてやはり長期記憶に残りやすい。報酬系は損得の判断の場合もあるが、基本的には「仲間になりたい」本能に従った利他的な欲求、たとえば、「社会に貢献できる」「誰かを助けられる」などの見通しの方が、利己的な欲求よりも強く反応する。
または心を込めてしたこと。強い自主性に基づいて「これをしよう」と思って取り組んだことは記憶に残る。
この3つのうち最初の「好き」「興味」は入り口として重要であり、ここで「嫌い」「面倒くさい」というネガティブなレッテルが貼られてしまうと後の2つのルートも閉ざされてしまう。だから、まずはどんなことにも興味を持ち、好きになる、楽しいと思うことが重要。
興味深いと思ったのは、ネガティブな言葉や愚痴を言うことによって脳の力がどんどん衰えるということ。それは、様々な情報に対して「嫌い」のレッテルを貼ることに相当するので、記憶も思考も生まれなくなるのだという。
考えたことは随時文章や図にしてまとめると、もやもやと頭の中だけで考えているよりもずっと脳が活性化されるため、記憶力・思考力の向上につながるということが文中で指摘されていましたが、これに関しては最近とみに実感していますね。ブログなど公なところでは書けないようなことも個人的な日記のようなものに書きつけることで考えが整理され、新たな気づきがあり、精神的にも安定を維持しやすくなります。
本書の最後にはチェックリストがあり、自分がどれだけ脳に悪い習慣を克服できたかをチェックできるようになっています。これだけでもすごく価値がありますね。
<iframe style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" frameborder="0" src="https://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=tf_til&t=mikakodeuts05-22&m=amazon&o=9&p=8&l=as1&IS1=1&detail=1&asins=B00CZCWBNU&linkId=2395cdf5e8ee49b7f1be27b78b317985&bc1=ffffff<1=_blank&fc1=333333&lc1=0066c0&bg1=ffffff&f=ifr"> </iframe>