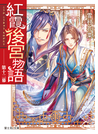表紙が『仏教と民俗 仏教民俗学入門』そっくりですが、内容も一部重なる部分があります。
目次
1 聖というもの(一) 隠遁性と苦行性と遊行性と
2 聖というもの(二) 呪術性と集団性と世俗性と
3 聖の勧進と唱導 勧進性と唱導性
4 高野浄土
5 高野聖のおこり
6 祈親上人定誉
7 小田原聖教懐と別所聖人
8 覚鑁と別所聖
9 仏厳房聖心と初期の往生者
10 高野聖の文学
11 新別所の二十四蓮社友
12 鎌倉武士と高野聖
13 高野聖・西行
14 俊乗房重源と高野聖
15 明遍と蓮華谷聖
16 法燈国師覚心と萱堂聖
17 千手院聖と五室聖
18 高野聖の末路
目次を見ればおおよそ見当がつくかと思いますが、高野聖の起源と実態とその変遷を説明しており、門外漢には少々詳しすぎるきらいがあります。
重要なポイントとしては、高野聖が教学仏教とは無関係に民衆と関係を結び、民衆のための仏教を説いて廻国し、多くの寺院の建立・修復のための勧進を行うことによって日本の仏教を経済的文化的に支えたということが挙げられます。
彼らは勧進のために唱導、念仏会、踊念仏などを民衆の教化活動の一環として行ったため、各地に残される盆踊りや花笠踊りなどの庶民芸能の基礎を築き、また、平家物語などの文学を広める役割を果たしました。
聖は半聖半俗の妻帯僧が多かったため、教学無知の点も含めて学僧から蔑視されていましたが、結局のところ僧侶のほとんどが聖化、つまり妻帯僧となることで、差別自体が意味をなさなくなったとのことです。なぜ日本の仏教僧侶は妻帯が一般的なのか、その起源がこうした高野聖たちの活動にあったわけですね。
庶民の宗教的要求は現生の幸福と来世の安楽という二面性を持つとともに、呪術的な原始宗教性を濃厚に持っていたため、これに応えるように発展した高野聖たちの教化活動が、現在の日本の庶民仏教が本来の仏教の教義とはかけ離れた別物の信仰になってしまっていることの一因になっているようです。
この本を読むことで、私が長年抱いていた日本仏教に対する疑問のいくつかが解消されました。