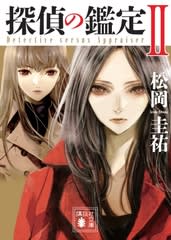長谷川幸洋著『日本国の正体 政治家・官僚・メディア-本当の権力者は誰か』(講談社・現代プレミアブック)は2009年6月発行で、割と古い本なので紙書籍の新刊ではもう入手しづらくなっています。私が読んだのは電子書籍版です。
長谷川幸洋氏は元【官僚のポチ】(=記者クラブ付き新聞記者)の視点から官僚とメディアの関係、官僚と政治家の関係と支配構造を分析しています。目次は以下の通りです。
第1章 官僚とメディアの本当の関係
新聞は何を報じているか
不可解な事件
霞が関の補完勢力になった新聞
転向の理由
政権を内側からみるということ
第2章 権力の実態
政治家と官僚
「増税」をめぐるバトル
財務官僚の変わり身
福田首相の本心
事務次官等会議
第3章 政策の裏に企みあり
「政策通」の現実
カネは国が使うべきか、国民が使うべきか
定額給付金は「ばらまき」か
「官僚焼け太り予算」を点検する
政策立案の手法
「専務理事政策」とはなにか
第4章 記者の構造問題
記者はなぜ官僚のポチになるのか
真実を報じる必要はない?
「特ダネ」の落とし穴
記者は道具にすぎない
官僚にとっての記者クラブ
第5章 メディア操作を打破するために
霞が関幻想
先入観としての「三権分立」
「政府紙幣発行問題」の顛末
記者が陥る「囚人のジレンマ」
報道の力を取り戻すために
表題となっている問い「本当の権力者は誰か?」の答えは「官僚」です。選挙という洗礼を受けない官僚集団が自分たちの都合のよい政策(天下り先確保)を作成し、事務次官等会議で各省の「調整」をし、そこで可決されたもののみを閣議に上げるため、閣議、更に国会審議が形骸化しているという指摘です。
天下り先が確保できる政策を「専務理事政策」といい、新しい独立法人を作り、先輩官僚を理事の座に天下りさせ、予算をそこに回すことができる官僚が「優秀」とされる制度ができあがっており、そこに民主的抑制が全くきいていないことが大きな問題点です。
そして、官僚は自らに都合のよい政策を「特ダネ」として特定の記者クラブ所属の記者に売り、その宣伝を請け負わせ、記者を代理人として使っている実態。記者は記者クラブ勤務のため、殆ど独自の調査を行わなず、官僚が記者クラブに流す情報を垂れ流すだけの記事を書くことに始終してしまう傾向が強いらしい。記者クラブを追放されたくないから、官僚を怒らせるような突っ込んだ質問や批判はおのずとしなくなり、飼いならされてしまうことで「官僚のポチ」と化してしまう。
報道の力を取り戻すために著者は記者クラブの廃止と通信社との分業(通信社は速報、新聞は調査報道)を提案しています。
官僚批判自体は別に新しいことではありませんが(未だに改善されていないのがむしろ驚き)、本書は政治家との関係だけでなく、メディアとの関係も分析しているので、興味深く読ませてもらいました。
この本が発行されてから7年弱。【報道の力】はますます弱まっていると言えます。毎年国境なき記者団によって発表される報道の自由度ランキングを見ると、安倍政権になってから悪化の一途をたどっています。別に民主党政権を擁護するつもりはありませんが、少なくともその当時日本は報道の自由度ランキング12位でした。2016年度のランキングは昨年度よりさらに11位下がって72位となりました。先進国の中ではイタリアを除くと最下位です。
デービッド・ケイ特別報告者(米国)が4月19日、暫定的な調査結果を公表しましたが、そこでも記者クラブは批判の対象でした。調査結果の内容は、日本語メディアの中では東京新聞の記事「「特定秘密保護法は報道に重大な脅威」 国連報告者が初調査」が一番詳しいようでした。
以下東京新聞より引用:
国連のデービッド・ケイ特別報告者の暫定調査結果の詳細は以下の通り。
【メディアの独立】 放送法三条は、放送メディアの独立を強調している。だが、私の会ったジャーナリストの多くは、政府の強い圧力を感じていた。
政治的に公平であることなど、放送法四条の原則は適正なものだ。しかし、何が公平であるかについて、いかなる政府も判断するべきではないと信じる。
政府の考え方は、対照的だ。総務相は、放送法四条違反と判断すれば、放送業務の停止を命じる可能性もあると述べた。政府は脅しではないと言うが、メディア規制の脅しと受け止められている。
ほかにも、自民党は二〇一四年十一月、選挙中の中立、公平な報道を求める文書を放送局に送った。一五年二月には菅義偉(よしひで)官房長官がオフレコ会合で、あるテレビ番組が放送法に反していると繰り返し批判した。
政府は放送法四条を廃止し、メディア規制の業務から手を引くことを勧める。
日本の記者が、独立した職業的な組織を持っていれば政府の影響力に抵抗できるが、そうはならない。「記者クラブ」と呼ばれるシステムは、アクセスと排他性を重んじる。規制側の政府と、規制される側のメディア幹部が会食し、密接な関係を築いている。
こうした懸念に加え、見落とされがちなのが、(表現の自由を保障する)憲法二一条について、自民党が「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」との憲法改正草案を出していること。これは国連の「市民的及び政治的権力に関する国際規約」一九条に矛盾し、表現の自由への不安を示唆する。メディアの人たちは、これが自分たちに向けられているものと思っている。
【歴史教育と報道の妨害】 慰安婦をめぐる最初の問題は、元慰安婦にインタビューした最初の記者の一人、植村隆氏への嫌がらせだ。勤め先の大学は、植村氏を退職させるよう求める圧力に直面し、植村氏の娘に対し命の危険をにおわすような脅迫が加えられた。
中学校の必修科目である日本史の教科書から、慰安婦の記載が削除されつつあると聞いた。第二次世界大戦中の犯罪をどう扱うかに政府が干渉するのは、民衆の知る権利を侵害する。政府は、歴史的な出来事の解釈に介入することを慎むだけでなく、こうした深刻な犯罪を市民に伝える努力を怠るべきではない。
【特定秘密保護法】 すべての政府は、国家の安全保障にとって致命的な情報を守りつつ、情報にアクセスする権利を保障する仕組みを提供しなくてはならない。
しかし、特定秘密保護法は、必要以上に情報を隠し、原子力や安全保障、災害への備えなど、市民の関心が高い分野についての知る権利を危険にさらす。
懸念として、まず、秘密の指定基準に非常にあいまいな部分が残っている。次に、記者と情報源が罰則を受ける恐れがある。記者を処分しないことを明文化すべきで、法改正を提案する。内部告発者の保護が弱いようにも映る。
最後に、秘密の指定が適切だったかを判断する情報へのアクセスが保障されていない。説明責任を高めるため、同法の適用を監視する専門家を入れた独立機関の設置も必要だ。
【差別とヘイトスピーチ】 近年、日本は少数派に対する憎悪表現の急増に直面している。日本は差別と戦うための包括的な法整備を行っていない。ヘイトスピーチに対する最初の回答は、差別行為を禁止する法律の制定である。
【デジタルの権利】 インターネット上の自由の分野で、日本がいかに重要なモデルを示しているか強調したい。政府の介入度合いが極めて低いのは、表現の自由への政府のコミットメントを表している。
政府は盗聴に関連した法律やサイバー空間のセキュリティーの新たな取り組みを検討しているが、自由の精神や通信の安全、オンライン上の革新性が保たれることを望んでいる。
【市民デモを通じた表現の自由】 日本には力強く、尊敬すべき市民デモの文化がある。国会前で数万人が抗議することも知られている。それにもかかわらず、参加者の中には、必要のない規制への懸念を持つ人たちもいる。
沖縄での市民の抗議活動について、懸念がある。過剰な力の行使や多数の逮捕があると聞いている。特に心配しているのは、抗議活動を撮影するジャーナリストへの力の行使だ。
・・・以上引用・・・
国連のプレスリリース「日本:国連の人権専門家、報道の独立性に対する重大な脅威を警告」はこちら。
ドイツ語メディアの中ではハンデルスブラットが一番詳しい記事(「国連は日本を批判:報道?決して自由ではない」)を出していました。大まかな点は東京新聞のまとめと一致しますが、興味深いのは、ハンデルスブラットはケイ氏がメディア自身の責任を指摘したことをきちんと報じているのに対して、東京新聞の記事では曖昧に濁されていることです。
「問題は日本の政治家がメディアに影響を与えようとすることではない。そのような攻撃はどの民主主義国家にも起こる。メディア自身がメディアの傷つきやすさに対してかなりの部分責任を負っているのだ」ということと、「もし日本のジャーナリストが会社ごとに細分化された組合ではなく、ジャーナリスト同士の連帯と自己統制および自身の独立性のためのもっと総括的な組織を持っていたならば、政府の影響力に対して抵抗することがもっと容易にできただろう」というケイ氏の指摘がハンデルスブラットではそのまま引用され、それを阻害している記者クラブという制度、それによって二分化されている日本のメディアの実態―スキャンダルを比較的自由にすっぱ抜く週刊誌等と記者クラブという形で省庁に張り付いているメジャーメディア―が詳しく報じられています。
英語ができる方はぜひオリジナルの記者会見をご覧になってください。YouTubeのビデオ「David Kaye: "The Freedom of Expression in Japan"」はこちらから。
政府と大手メディア幹部が定期的に会食しているという異常事態も、日本ではなぜかスルーされているように見受けられますが、これは本当に危機的状況です。このままでは報道の自由、すなわち報道の力が失われていく一方です。民主主義国家として恥ずべき事態と言えるでしょう。
民主主義国家において当然保障されるべき国民主権は情報の公開がなければ成り立ちません。情報公開は政府・行政の管轄ですが、それを調査して報道するのはメディアの役割です。日本では情報公開性は特定秘密保護法などにより制限され、大手メディアは記者クラブで飼いならされ、政府・行政機関を監視する役割を「自主規制」によって早々に放棄してしまっています。これによって民主主義を支える重要な柱が骨抜きにされてしまっているという自覚を日本人は持つべきでしょう。選挙に行くばかりが民主主義ではありません。選挙の結果選ばれた政府がやりたい放題していいということではありません。世の中には「選ばれた政府を批判するのはもっての外」と考えている人たちが居るようですが、それは民主主義の本質を理解していない証拠でしょう。選挙は政党にその後の政策を「丸投げ」することではありません。真の民主主義は常にシビリアンコントロールを要求します。そのための情報公開であり、報道の自由であり、集会の自由なのです。それらが保障されなくなっている日本は既に民主主義国家ではありません。