つい先日たまたまドイツの長期失業者(1年以上無職の者)に関する統計を見かけました。ドイツ連邦統計局のサイト「Statista.de」で公開されたものです。それによると過去10年間で長期失業者の数が50万人減り、また全失業者に占める長期失業者の割合も40.7%から34.9%に減ったとのことです。

この減った「50万人」の中には、職に就くことなく年金受給年齢に達したために「失業者」とカウントされなくなった人たちが多く含まれています。統計的な意味の「失業者」とは単なる無職者ではなく、労働局に「求職中」である届け出を出し、失業手当などの何らかの支援を受ける人たちのうち、職業(再)訓練などのプログラムに参加していない人たちを指しています。
この定義での「失業」が長期化する典型例は55歳以上の労働者です。このため、過去5年間の平均収入から算出される第1種失業手当の受給はこの年齢層には2年間支給されます。55歳未満の場合の支給期間は1年間のみで、それを過ぎても就職ができない場合は、俗に「ハルツ4」と呼ばれる第2種失業手当が支給されます。これは、就労可能者に支給される生活保護の一種ですが、そのように呼ばれないのはシュレーダー政権時に実施された「アゲンダ2010」プログラムによる生活保護と失業手当の統合改革によります。この改革以降「生活保護(Sozialhilfe)」の受給者は就労不能な者(病人や障碍者、高齢者などでその他の保護が受けれない者)に限定されています。
「アゲンダ2010」が提唱された当時(2003年)、ドイツの失業者は500万人を超え、失業率は10.5%でした。経済は停滞し、ドイツは「ヨーロッパの病人」とさえ言われていました。現在好景気に沸き、3年連続財政黒字を計上しているドイツからは想像もできないかもしれませんが、とにかく失業者対策が喫緊の政治課題だったのです。「保護が手厚すぎる」というのはまだましな批判でしたが、「働けるのにさぼってる怠け者」「金食い虫」「社会の寄生虫」などの失業者バッシングも盛んに行われました。
そして現在、失業率はわずか5.4%、2018年6月現在で228万人です。

州別に見ると以下のようになります。数字は失業率のパーセンテージで、カッコ内の数字は前年同月の失業率を表します。出典は労働局サイト。

最も失業率が高いのはブレーメン州の9.7%。船舶業の衰退から産業構造の変革が進まずなかなか浮上できない地域です。次が首都のあるベルリン州の7.9%。
旧東独5州の失業率平均が6.6%なのに対して、旧西独11州の平均は5%なので、いかにも東西格差がある感じですが、私の住むノルトライン・ヴェストファーレン州(人口最大の州)の失業率は6.7%で、旧東独平均を上回ります。上の地図を先入観なくパッと見ればお分かりかと思いますが、あるのは東西格差ではなくむしろ南北格差です。
それはともかくとして、ドイツのサクセスストーリーが本当に「アゲンダ2010」によるものなのか諸説があります。実は「アゲンダ2010」は全く無関係の労使協定による実質賃金上昇の抑制によって国際競争力が増したという説もあります(Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg, and Alexandra Spitz-Oener, "From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany’s Resurgent Economy", Journal of Economic Perspectives—Volume 28, Number 1—Winter 2014)。その賃金上昇抑制はすでに1995年に始まっていたので、「アゲンダ2010」とは無関係というわけです。
名目賃金の上昇率だけ見ると、1992年以降概ね上昇し続けたと言えますが(例外は1997、2003、2005年)、実質賃金(名目賃金から物価上昇率を差し引いた賃金)はほぼ横ばいです。下のグラフは1992~2017年の名目賃金の上昇率を表しています。

実質賃金がほぼ横ばいなら、生活がよくはならなくても苦しくもなってないということのはずですが、それはあくまでも「平均」の話で、実は所得格差が拡大しつつあり、「2015年度の下の方の40%の実質賃金は、1995年度のそれよりも低くなっている」と昨年経済事務次官のマティアス・マハニクが警鐘を鳴らしました(Süddeutsche Zeitung, 22. August 2017, "Deutschland hat ein Lohnproblem(ドイツには賃金問題がある)")。要するに低所得層40%は、好景気の恩恵に預かれないばかりか、逆に生活が苦しくなっており、場合によっては仕事を掛け持ちするなどして、何とか生活しているわけです。それに対して上位60%は一部かなりの実質賃金の上昇があったと言います。上位60%は割と広範なので、「富める者はますます富み、貧しいものはますます貧しく」とは言い切れませんが、40%の人たちが置いてきぼりになっているのは確かのようです。
好景気の中、所得格差が拡大し、貧困問題が深刻化する現在のドイツでは、少なくなった失業者はもはやスケープゴートではなくなっています。むしろ忘れ去られていると言っていいほど話題になりません。失業者が減った背景には好景気ばかりでなく、ミニジョブやパートタイムなどを含む低賃金労働者が規制緩和によって増加したこともあります。日本の非正規労働者の割合ほどではありませんが。
現在のスケープゴートは言うまでもなく難民です。昨年の連邦議会選挙でついに連邦議会入りし、野党第一党となったAfDがその荒んだ空気の象徴と言えます。
それにしても、2015年秋から2016年春までのいわゆる「難民危機」の間なら難民バッシングや難民排斥的政策を求めるのも分からなくはないのですが、バルカンルートが封鎖されてからは、ドイツまで来る難民は激減しました。難民危機の間は1日で1万人前後の難民がドイツに流入していましたが、今年の新規難民登録は1か月で1万人ちょっとです(出典は連邦統計局サイト)。
今リビア沖で救出された難民たちの受け入れをイタリアやマルタが拒否して、右往左往の挙句にスペインが入港を認めるなど、難民問題の焦点は地中海に移行しており、既にドイツの問題ではなくなったと言えます。それなのになぜ夏季休会直前の数週間与党内、メルケル首相のCDUとゼーホーファー内相のCSUの間で難民問題について激しいバトルが繰り広げられたのでしょうか?そしてバイエルン州首相マルクス・ゾーダー(CSU)が州のイニシアチブで隣国のオーストリアとの国境の警備強化や難民送還問題を激しく取り上げる理由は何でしょうか?
理由として考えられるのは、まずバイエルン州議会選挙のための布石として、CSUがAfD票を取り戻そうとAfDの主張を横取りしているという側面です。CSUはよく「CSUより右に合法的な政党なし」ということを主張してきました。この主張は、AfDという今のところ合法的な政党の存在によって崩されてしまっています。このため、より右寄りになることでAfDに「不満票」を入れた有権者をCSUに惹きつける戦略を取ったわけですが、あまりにも執拗な難民問題バトルは逆効果だったようで、CSUの支持率は下がり、CSU元党首のホルスト・ゼーホーファーの政治家ランキングはがた落ちしました。
もう一つの理由として考えられるのは、国民の目を難民問題に向けることで他の問題から目を逸らさせようとしている政治的意図です。内政問題から目を背けさせるために外敵を作り、それに対して国民を団結させるというのは歴史的によくある政治の常套手段とも言うべきものです。しかし現在ヨーロッパには適した「外敵」が国としては存在しません。その代わりイスラム系テロリストと難民がその役割を果たしていると言えるのではないでしょうか。イスラム系テロリストのスリーパーは既に数年または十何年も前に国内に入っていましたから、「外国籍危険人物の祖国送還」が検討され、新たにそうした危険人物が流入して来ないように入国管理を強化することが検討されるわけです。それらが対策の必要な問題であることは確かですが、これほど国会議論や国民的議論の比重を占めるに値するものであるかどうかについては疑問を差し挟む余地があると思います。
少子化、医師不足や教師不足、介護士・介護ヘルパー不足、所得格差や子供の貧困、老後の貧困などの深刻な内政問題があるのに、そこに割かれる議論の時間や報道の比重が少なすぎる気がします。
「難民」というスケープゴートは、社会の不満分子、特に置いてきぼりにされている下層40%(の少なくとも一部)のガス抜きに利用されている側面もあるようにも思えます。

にほんブログ村

にほんブログ村
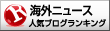
海外ランキング


















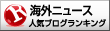




 (購入は
(購入は


