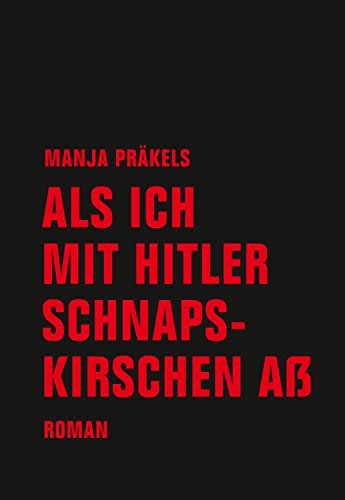Marc-Uwe Kling の『QualityLand クォリティランド』は、現在のアルゴリズムのはびこるデジタル社会を究極まで推し進めた未来社会の中で Nutzloser(役立たず)のレッテルを貼られている主人公 Peter Arbeitsloser(ペーター・ジョブレス)の幸せでない生活とそこから芽生える反発心をコミカルに描くSF風刺小説です。
しゃべる自動運転車、家のドア、家電、Ohrwurm(耳の虫・耳鳴り)と呼ばれるアシスタント、注文しなくても届く品物、世界観・考え方に合わせて提示されるニュースや広告等々。そこに描かれる近未来の世界は、まさにデジタル化の進む社会が向かっている方向です。
このようなIoTを極めた世界を描き出すことで様々な社会批判が可能だと思いますが、マルク=ウヴェ・クリングはコメディアンとしての才能を遺憾なく発揮してすべてを不条理で滑稽な「ふざける」方向に振り切り読者を笑わせます。
Peter Arbeitsloserはある日世界で一番人気のある通販会社TheShopからピンク色のイルカ型バイブレーターを受け取り、なぜそんなものが配達されたのか理由もわからず、使い道もないので返品を試みたものの、TheShop側は「システムは間違わない」という頑なな態度を貫き、一切返品を受け付けません。そこで一般人であれば諦めて商品を捨てるなり人にあげるなりして処分してしまうでしょうが、彼は諦めずに何とか返品して、TheShopのシステムの間違いを認めさせようとします。
一方でクォリティランド大統領の予想死期が迫っていたため、大統領選挙の準備が進められているのですが、候補者の一人は差別主義者のコック、対立候補は何とアンドロイド。
アンドロイドの John of Us は選挙運動でベーシックインカムの導入や富裕層に対する増税などインテリな左派政治家を彷彿とさせる政策をとうとうと説き、論理的にまともなことを言うほど世論調査での支持率が下がっていく事態に直面します。オルタナティブファクトやフェイクニュースに影響されるネット住民の行動原理そのままですね。
また、John of Us の属する政党 Fortschrittspartei(進歩党)の党員である Martyn Vorstand の私生活も描かれます。子どものために買ったなぜか4種の武術をこなせる子守ロボット、妊娠中の妻に付き添って検診に行き、生まれてくる娘の未来予想図が提示され、遺伝子操作を勧められるなど怖くて笑えないシーンもあります。
主にこの3つのラインが交互に語られ、少しずつ絡んでいき、クライマックスですべてが1つの事件に収束していくストーリー構成です。
しゃべるカンガルー(なぜか共産主義者)の登場する『Die Känguru Chroniken カンガルークロニクル』も不条理で可笑しかったですが、こちらは2000年代のドイツの情勢に詳しくないと分からない部分も多いのに対して、『QualityLand クォリティランド』の方はGAFAが支配的な社会の住人であれば理解または想像できる世界で展開されるストーリーなので日本人にもとっつきやすい内容です。
邦訳も出ていますが、B2程度のドイツ語力があれば原文も何とか読めると思います。
不条理なドタバタが一体どこへ行きつくのか気になって、どんどん読み進められるのではないでしょうか。

邦訳『クォリティランド』をAmazonで購入する。