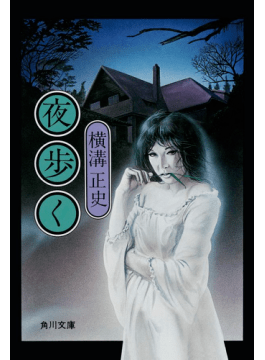トレドには2018年10月1日にマドリードから日帰りで行きました。
マドリードからは、トレドへの日帰りバスツアーがたくさん出ていますが、私たちはAVEに乗りたいというのもあって単独でトレドに行きました。運賃は一人片道10.30€。アトーチャ駅から30分ちょっと。近くてもマドリード県ではなく、カステラ・ラ・マンチャ自治州の首都です。
切符はもちろん駅の窓口や自販機でも買えますが、私たちはRenfeのインターネットサイトから購入しました。後から分かったのですが、Renfeのスマホ用アプリもあり、多言語対応の質はインターネットのサイトよりもずっと上です。ところが同じトレド行きの電車の切符は12€以上で販売されていました。駅の自販機ではどうなのか分かりませんが、ネットで買うのが安上がりかもしれません。
AVE乗り場へは切符を提示し、荷物検査を受けてからでないと入れないようになっています。面倒ですがテロに巻き込まれる危険を考えれば、仕方ないとあきらめもつきます。

AVEのシートは非常にゆったりとしており、どんな肥満体でも余裕で座れそうな感じです( ´∀` )

さて、古都トレドは1986年に、UNESCO世界文化遺産に登録されましたが、その理由とは、現代化をまぬがれ、古代ローマから西ゴート王国、後ウマイヤ朝、スペイン黄金時代といった2千年紀にわたる文明の痕跡を残していること、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教による異文化の混合がムデハール建築に示されていることなどが評価されたとのこと。
旧市街はタホ川に三方囲まれた高台にあり、町全体が博物館と呼ばれています。西ゴート王国時代から教会会議の開催場所となり、トレド司教座の権威が高かったとのことですが、後ウマイヤ朝においての地位はどの程度だったのかは分かりません。1086年にアルフォンソ6世によってキリスト教徒の手に奪還され、リコンキスタの節目の一つとなり、その後のリコンキスタの動きにトレド司教の意向が影響していきます。
12~13世紀にトレド翻訳学派という学者集団が活躍した地としても知られています。イスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒の共同作業によって、古代ギリシア・ローマの哲学・神学・科学の文献がアラビア語からラテン語に翻訳され、この成果が中世西ヨーロッパの12世紀ルネサンスに大きな刺激を与えたと言われています。
先述のようにトレドは三方を川に囲まれており、両岸とも一部崖のような渓谷になっているため、川側から高台にある街を攻めることは困難を極めます。こうした地理的な特徴によって防衛しやすかったというのも繁栄のカギだったのではないでしょうか。マドリードが首都と定められてからはゆっくりと衰退の道を辿ったらしいですが、現在は観光客で大変賑わっており、住民にとっては悩ましい状況なのではないかと思います。
私はリウマチ性関節炎の症状がそれとは知らずに出ていて体調不良だったため、あまりたくさんは見ていないのですが、全体的な印象として、タホ川の対岸から見るトレドの街並みは素晴らしいですが、実際に街中に入ると狭い中を観光客と車が溢れていて非常に空気が悪く、また、急な坂が多いため、ほんの少しの距離を移動するにもかなり難儀する感じでした。
それで一番気に入ったのは世界遺産の中には含まれていないネオムデハール様式で19世紀に建てられたトレド駅舎だったりします。









この駅前広場には観光バスが待ち構えています。1つは他のところでもよく見かける赤い観光バスで、乗り降りし放題24€とかです。もう1つは地元企業らしく、トレドのパノラマ展望ができるよう対岸を走るバスツアー+地図+徒歩のガイド付きツアー(ビサグラ門集合)の3点セットで12€。私たちは後者を選択して、まずはパノラマ展望を堪能しました。











タホ川にかかる古い橋は2つあり、駅や王城に近い東側の橋はPuente de Alcántara(アルカンタラ橋)、反対(西)側のはPuente de San Martin(サンマルチン橋)。アルカンタラ橋は紀元後2世紀、ローマ帝国のトラヤヌス皇帝時代に建設された約200mの長さの石橋です。もちろん戦争があるたびに破壊されたりしているので、ローマ時代の姿そのままというわけではありませんが、アーチ形の基本構造は保持されています。この橋は長いこと唯一の街への入り口でした。14世紀後半になって、西側のサンマルチン橋がトレド大司教Pedro Tenorioによって建てられ、アルカンタラ橋に並ぶ西側の入り口となりました。こちらのアーチ橋はアーチの長さが40mに及ぶ、中世の橋としては大きなものです。
さて、パノラマバスツアー終了後、サンパブロ修道院跡のわきの駐車場で降ろされた私たちは長いエスカレーターを登って旧市街地に入りました。



長いエスカレーターは駐車場の中ですが、途中で外の道路に出られるところがあり、そこから見える景色をパチリ。

エスカレーターを登り切ったところから階段を数段登ると大きなテラスがあり、そこにカフェ(Terraza del Miradero)があったので早速休憩。オレンジのフレッシュジュースを頂きました。

ジュース二つに10€は割高だとは思いますが、まあ、眺めの良い「場所代」込だと思えば。
休憩後は取りあえず散策。まずは王城(現在軍事博物館とカスティーリャ・ラ・マンチャ州立図書館が入っている)方へ。Plaza de Zocodoverという広場に出ます。


そして王城Alcázarのところを左折して、少し低い位置にあるMirador del Alcázarへ。対岸に士官学校が見えます。



そしてまた昇り。



この王城(Alcázar)は何度も破壊と再建が繰り返され、スペイン内戦の際には共和国派によって要塞として利用されていました。このため、建築物として見る価値があるのかどうか少々疑問です。軍事博物館や図書館に用のない私たちは外側を見ただけでスルーしました。
そして狭い路地を下ってトレド大聖堂の方へ向かいました。



狭い路地を抜けると急にちょっと開けた広場。劇場前広場でした。

この劇場のすぐ近くのレストラン「El Rey Toledo」というところでランチ。例によって前菜・メイン・デザートの3点メニュー(Menu del dia)です。お味の方は中の上と言ったところでしょうか。






屋外席はちょっとしたパティオのように何本かの木の下で、上でも下でも雀がおこぼれに預かろうと待ち構えていました。


ランチを終えて、トレド大聖堂に向かいました。地図で見るとトレド旧市街の中心に位置しています。元は街最大のモスクが建っていたところにリコンキスタで奪還後教会を建てた、という典型的なパターンです。
90mの高さの塔が聳え、身廊・側廊合わせて5つを備えたスペインカトリックの総本山にして、セビリア大聖堂に次ぐスペインで2番目に大きい教会は1226~1493年の間にスペイン風ゴシック様式で建てられました。20人以上の芸術家によって掘られた木製祭壇(1500~04)と聖歌隊席、エルグレコやゴヤを始めとするスペイン画家の絵画コレクションなどが見ものです。
私たちは徒歩ツアーの時間が差し迫っていたのと、入場料7€をなんとなく払いたくなかったという理由で外から見ただけですルーしてしまいました。エルグレコの絵画に興味のある人なら多分外せない観光スポットなのでしょうけど、私たちはこれまで行く先々でたくさん大聖堂を見てきてますので、よっぽど変わったものでない限り高い入場料を払ってまで教会を見ようとは思わなくなっています。




徒歩のガイド付きツアーは17時にPuerta de Bisagra(ビサグラ門)に集合でした。


門の中にパティオがあります。


ここからガイドなしには入れない領域に入り、狭い階段を登って、人がやっと一人通れる程度の通路を通り、階段ではなくはしごで、途中ロープはしごになっているのをこわごわ上ると展望台に出ます。




このトレド北部を守るための城壁は、一部西ゴート王国、一部モーロ人支配時代のものです。そこにあるビサグラ門は10世紀初頭まで遡る馬蹄型アーチの門の上にカルロス5世が1550年に建てさせたものです。これだけ状態のよい立派な門も珍しいと思います。
ガイド付きツアーというのはこの門だけでした。随分とまた小さな「ツアー」ですよね。「なーんだ」とがっかりしましたが、本格的な徒歩ツアーできるような体調ではなかったのでそれでもよかったかも。
この後、サンチアゴ・デル・アラベル教会とやらのわきを通って坂を上がり、Puerta del Solという門へ。
Iglesia Santiago del Arrabal


Puerta del Sol(太陽門)は12~14世紀に建設されたムデハール様式の門です。

太陽門よりもさらに上に位置するPuerta de Valmardón(バルマルドン門)は10世紀に建設された門で、トレド最古の門の一つ。


この門をくぐった後ろにあるのが元モスクの教会Cristo de la Luz。やはり10世紀(999年)のイスラム建築です。

私たちはここで「見学」を終え、レストランを求めてPlaza de Zocodoverという広場に戻ったのですが、マクドナルドなどのファーストフード店しかないことに絶望し、さらに街中の飲食店を探す気にはなれなかったので、21:30発のマドリード行きの最終電車に問題なく乗れるように結局バスツアーの終点だった駐車場へ戻り、そこから駅の方に向かって少し歩き、大きなロータリーの近くにあった簡単な食堂「Canelita in Rama」で食べました。観光客が行くようなお店のようには思えませんが、お味の方はなかなかよく、値段も手ごろで、店員が非常に親切でした。




こうして私たちはトレドの日帰り旅行を終え、翌日の午後にドイツへ帰りました。
リウマチ性関節炎で指や手首そして膝が痛んで辛い旅行となってしまいました。トレドもあまり見て回れなかったのが残念です。でもだからと言ってもう一度行きたいかというと、そうでもないです。やはり観光客が多過ぎることと、狭いのに車の交通量が多くて空気が非常に悪いことが大きなマイナスポイントです。
次のスペイン旅行ではセゴビアとコルドバに行こうと思ってます。