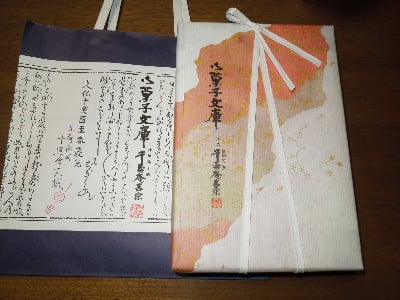参院選の前に、と急遽公開!【対談】上野千鶴子(社会学者)×福田和香子、奥田愛基、牛田悦正(SEALDs) 対話/SEALDs×上野千鶴子 - atプラスweb ohtabooks.com/at-plus/entry/… #atプラス @atplus_webさんから
— 上野千鶴子 (@ueno_wan) 2016年7月9日 - 00:22
トラウマの重さとそこはかない希望 『トラウマ』 宮地尚子 | WAN: wan.or.jp/book/?p=6668 「〈何者〉にもならなくてもいいということ。それがトラウマからもたらされる想像力や創造性の帰着点」「それがまた新たな想像力や創造性の原点となる」
— B-WAN (@b_bwan) 2016年7月9日 - 08:17
猪瀬元知事が実名入り告発 “伏魔殿”都庁と都議会に大激震 nikkan-gendai.com/articles/view/… #日刊ゲンダイDIGITAL
— 寺町みどり (@midorinet002) 2016年7月9日 - 10:31
参院選 あす投票 有権者の「知る義務」/待機児童対策 子育てどう支えるのか/増税と有権者 先送り体質を変える時 goo.gl/kpbafZ
— 寺町みどり (@midorinet002) 2016年7月9日 - 17:24
16/7/9 中日春秋(中日新聞朝刊コラム) chunichi.co.jp/article/column…
— 全国市民オンブズマン連絡会議事務局 (@ombudsman_jp) 2016年7月9日 - 17:08
公職選挙法が改められ、十八歳未満の子どもは共に投票所に入ることができるようになった。「親と一緒に投票所に行ったことがある」生徒の六割近くが、「投票に行く」と答えた。 #ombuds
DV被害者を守る「シェルター」の厳しい実情 人命を守る活動に予算が十分に下りない | 家庭 - 東洋経済オンライン toyokeizai.net/articles/-/739… @Toyokeizaiさんから
— 寺町みどり (@midorinet002) 2016年7月9日 - 17:37
くらしナビ・ライフスタイル:改憲 「家族助け合い」は弊害も - 毎日新聞 mainichi.jp/senkyo/article…
— 寺町みどり (@midorinet002) 2016年7月9日 - 17:41


























 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。