ローマ帝国のあり方を根本的に変えたディオクレティアヌスが前巻であった。
根本的に変えたというのは、皇帝が4人。つまり4頭政によって「パスクロマーナ」ローマ帝国の安全保障を図ろうとしたことである。
この試みは成功した。
ローマ帝国は周囲の蛮族が襲来をするのを防ぐことができたのであった。
しかし、その代償として国防にかかる負担である税が増えた。
そして、ディオクレティアヌスは引退をするのである。
これもこれまでとは違った形である。
で、ディオクレティアヌスは新たに皇帝を指名し第2次4頭政を始める。
ディオクレティアヌスは大御所政治をするのではなく、本当に引退をする。
ところが、このあたりからおかしくなる。
皇帝になりたい人間、つまり我こそは皇帝になる資格があると思う人が立ち上がり、一時は6人もの皇帝が乱立し、争いが始まるのである。
蛮族という外敵の心配が無くなったと思ったら、内乱なのである。
もっとも内乱の最中であっても蛮族の侵入があったりするのであるが・・・
この乱立、内乱を制したのはコンスタンティヌスである。
本書は「最後の努力」の第2部として「コンスタンティヌスの時代」である。
コンスタンティヌスは第2次4頭政の正帝コンスタンティウス・クロルスの長子であるが母が微賎であり、父が皇帝の娘と再婚したとき、母ともに体よく追い払われている。
そういう境遇であったことと、胸に秘めているものや能力があったことからなのだろう、彼は父が亡くなったあと正帝を目指す。
内乱を制するのである。
これまで、ローマ帝国の歴史を読んできた。また中国の歴史の本も読んだ。
このなかで、多く登場するのは「敗北者」である。
最後の最後まで勝利者であるのは非常に難しいことである。
一時的に勝利者になっても、次なる勝利者に敗れ去る者が殆どなのである。
敗北者たちは勝っている時に何かが足りない、或いは勝ちすぎる、さらには勝ったあとが良くない。
最後の最後まで勝ち続ける人は、やっぱりどこか違う。
何が違うのか。
思うに、行くときはまっしぐらに行くし、我慢すべきところは徹底してガマンする。
そしてはるか遠くを望んでことにあたるところだ。
さらに「運」である。運をつかむ強さがあるというところである。
コンスタンティヌスはそれがあった、と思う。
コンスタンティヌスには、勝者となっただけでなく、歴史上すごく大きなことをしている。
「キリスト教」を公認した。ということである。
ローマ帝国の神は、日本の神と同じように「八百万の神」のようであり、帝国を大きくしていく過程において多くの神を認めてきた。
多人種、多民族、多文化、そして多宗教のローマ帝国においては、誰が何を信じようと、ローマの共同体に従っていることを求めてきた。
しかし、キリスト教は唯一神であり、他の神を認めるわけにはいかない。
そのあたりがローマ帝国においてときどきキリスト教が迫害される要因であった。
それをコンスタンティヌスは公認をしたのである。(厳密にいえば彼一人ではないのであるが)
また、彼は信仰心からキリスト教を公認したではないようである。
そのあたりは第3部に詳しいようである。
ともかくこの2部では、勝利者であり続けるには、ということを教えてもらえる。
「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。

根本的に変えたというのは、皇帝が4人。つまり4頭政によって「パスクロマーナ」ローマ帝国の安全保障を図ろうとしたことである。
この試みは成功した。
ローマ帝国は周囲の蛮族が襲来をするのを防ぐことができたのであった。
しかし、その代償として国防にかかる負担である税が増えた。
そして、ディオクレティアヌスは引退をするのである。
これもこれまでとは違った形である。
で、ディオクレティアヌスは新たに皇帝を指名し第2次4頭政を始める。
ディオクレティアヌスは大御所政治をするのではなく、本当に引退をする。
ところが、このあたりからおかしくなる。
皇帝になりたい人間、つまり我こそは皇帝になる資格があると思う人が立ち上がり、一時は6人もの皇帝が乱立し、争いが始まるのである。
蛮族という外敵の心配が無くなったと思ったら、内乱なのである。
もっとも内乱の最中であっても蛮族の侵入があったりするのであるが・・・
この乱立、内乱を制したのはコンスタンティヌスである。
本書は「最後の努力」の第2部として「コンスタンティヌスの時代」である。
コンスタンティヌスは第2次4頭政の正帝コンスタンティウス・クロルスの長子であるが母が微賎であり、父が皇帝の娘と再婚したとき、母ともに体よく追い払われている。
そういう境遇であったことと、胸に秘めているものや能力があったことからなのだろう、彼は父が亡くなったあと正帝を目指す。
内乱を制するのである。
これまで、ローマ帝国の歴史を読んできた。また中国の歴史の本も読んだ。
このなかで、多く登場するのは「敗北者」である。
最後の最後まで勝利者であるのは非常に難しいことである。
一時的に勝利者になっても、次なる勝利者に敗れ去る者が殆どなのである。
敗北者たちは勝っている時に何かが足りない、或いは勝ちすぎる、さらには勝ったあとが良くない。
最後の最後まで勝ち続ける人は、やっぱりどこか違う。
何が違うのか。
思うに、行くときはまっしぐらに行くし、我慢すべきところは徹底してガマンする。
そしてはるか遠くを望んでことにあたるところだ。
さらに「運」である。運をつかむ強さがあるというところである。
コンスタンティヌスはそれがあった、と思う。
コンスタンティヌスには、勝者となっただけでなく、歴史上すごく大きなことをしている。
「キリスト教」を公認した。ということである。
ローマ帝国の神は、日本の神と同じように「八百万の神」のようであり、帝国を大きくしていく過程において多くの神を認めてきた。
多人種、多民族、多文化、そして多宗教のローマ帝国においては、誰が何を信じようと、ローマの共同体に従っていることを求めてきた。
しかし、キリスト教は唯一神であり、他の神を認めるわけにはいかない。
そのあたりがローマ帝国においてときどきキリスト教が迫害される要因であった。
それをコンスタンティヌスは公認をしたのである。(厳密にいえば彼一人ではないのであるが)
また、彼は信仰心からキリスト教を公認したではないようである。
そのあたりは第3部に詳しいようである。
ともかくこの2部では、勝利者であり続けるには、ということを教えてもらえる。
「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。











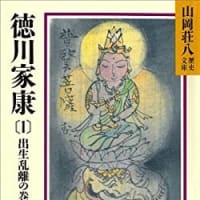
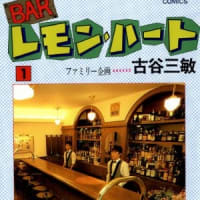
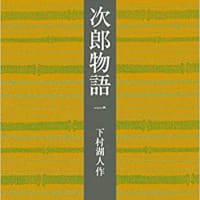
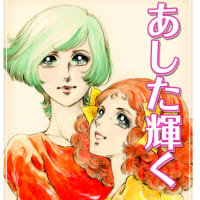
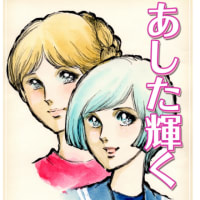
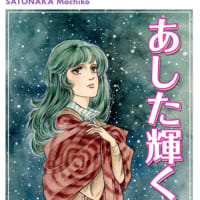
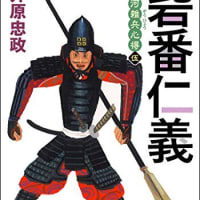
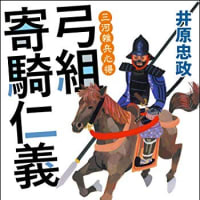
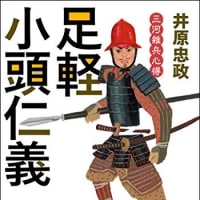
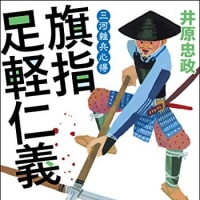




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます