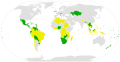PCR検査という言葉を見聞きしない日はない。毎日毎日何十回も耳にしたり、目にするんじゃないだろうか。いまや日常会話にも登場する言葉である。じゃあ、一体それは何なんだ、少なくとも「PCR」って何だろうか。それぐらいは知りたいと思って、その事は前に書いた。polymerase chain reactionの略。チェイン・リアクションで「連鎖反応」だ。DNAポリメラーゼという酵素を利用して、DNAサンプルの特定箇所を簡単に増幅させる方法である。なんてことをいくら書いても、僕もよく判らないから止める。じゃあ、このPCR検査を発明した人は誰だろうか。

非常に有名な人らしいが、それは生命科学分野に詳しい人の場合だろう。ほとんどの人は全然知らないと思う。PCR検査を発明したのは、アメリカのキャリー・マリス(1944~2019)という人で、1993年にノーベル化学賞を受賞した。「奇人」として知られる人だそうで、自伝が福岡伸一氏によって「マリス博士の奇想天外な人生」と題して出版されている。(原著は1998年、翻訳は2000年。)2004年にハヤカワ文庫に入って、今年第6刷になったけど、ほとんどの人は知らないよね。僕も新聞の書評で知って、読んでみようかと思った。
先の生没年を見れば判るように、マリス博士は2019年に亡くなっている。毎月僕は前月の訃報をまとめているから、マリス博士についても書いているのだろうか。見てみたら、その月はアメリカでトニ・モリスン(ノーベル文学賞を受けた黒人女性作家)やピーター・フォンダ(俳優)が亡くなっていたが、マリス博士は書いてなかった。そもそも日本ではマスコミに載らなかったようで、それじゃあ僕が知りようがない。だけど、その時期は新聞記者なんかでも「PCR検査の発明者」なんて言われても、何それ?だったんだろう。
でもマリス博士の訃報は日本でもっと大きく報じられても良かった。それは「日本国際賞」というのをノーベル賞受賞直前に受賞していたからである。これは賞金5千万円で、円建てなのでドルでいくらかはすぐには不明だった。お金が必要な事情があったのに、インターネットもスマホもなかったから当時は不便だったのだ。マリス博士は一度も大学に職を得たことがない。それどころか有名研究所や大企業にも所属したことがない。さらにLSD体験を公言したりしてノーベル委員会には受けが悪いよと忠告されていた。だから、自分はノーベル賞は取れないと思っていた。
PCR検査は「ドライブ・デート中にひらめいた」という「伝説」の真偽が最初に明かされる。ホントにその通りで、途中で車を止めて計算を始めてしまった。マリス博士は結婚離婚を繰り返したことでも知られ、その時の恋人とはその後別れることになった。その当時は、こんな簡単な検査法はすでに誰かが見つけてるに違いないと考えて、むしろ失恋の方が重大事だった。勤めていたベンチャー企業でも受けが悪く、最初は誰も信じなかった。しかし、調べてもそんな発明の論文は誰も書いてないようだった。いくつかの試行錯誤はあったものの、PCR検査が完成した技法となって、それによって「分子生物学の革命」が始まったのだ。
そして日本国際賞を受けて、皇居で歓迎会が開かれた。マリス博士は美智子皇后(当時)に「スウィーティー」(かわい子ちゃん)と呼びかけた。おいおい、ホントかよ。そして皇后との会話が明かされるが、実に興味深いではないか。次にノーベル賞を受けることになった。博士は知らせを受けた後で、サーフィンに出かけてしまった。マスコミが駆けつけた時、サーフボードを持った写真が撮られたのはそういう事情である。(画像の本の表紙にあるもの。)
 (ノーベル賞を受賞する)
(ノーベル賞を受賞する)
その時にホワイトハウスに招かれたが、クリントン大統領に麻薬疑惑を聞こうとして失敗。そこで当時保険制度改革に取り組んでいたヒラリー夫人に、オーストラリアの保険制度を質問した。どうせ本人は知るわけないと思ったら、たちどころに説明されたので驚いた。そして今度はアイルランドの保険制度も聞いてみたら、それも答えられた。すっかり才気に感心してしまうのだが、要するにマリス博士という人は皇后とかファーストレディに関わらず女性には声を掛けずにはいられないタイプなのである。その後有名なO・J・シンプソン裁判に弁護側の助言者として関わるが、テレビで有名になった女性検事にも裁判が終わったら夕食に誘うつもりだったなんて書いている。
なかなかとんでもないヤツで、こんな面白い本はないなという出だしなんだけど、実はそれは途中まで。その後どんどん奇人変人ぶりがエスカレートしていく。LSD体験とか、別荘で起こった「未知との遭遇」、星座占いの話などになっていく。そしてエイズはHIVで起こるという説は証明されていないと力説。フロンによるオゾン層破壊や地球温暖化説も証明されていないという話が続く。そういう説を唱える人がいるのは知ってるし、「環境ホルモン」など後に否定されるものもあるから、確かにいろんな説があってもいい。でも面白い「自伝」だなと読んでいると、突然「陰謀論」のようになるのは勘弁。思った以上に奇人で、「奇書」だった。(そんなマリス博士のことだから、「死因に疑問あり」とか新型コロナ流行の前に死んだのは暗殺だなどの説を唱える人もいるようだ。)

非常に有名な人らしいが、それは生命科学分野に詳しい人の場合だろう。ほとんどの人は全然知らないと思う。PCR検査を発明したのは、アメリカのキャリー・マリス(1944~2019)という人で、1993年にノーベル化学賞を受賞した。「奇人」として知られる人だそうで、自伝が福岡伸一氏によって「マリス博士の奇想天外な人生」と題して出版されている。(原著は1998年、翻訳は2000年。)2004年にハヤカワ文庫に入って、今年第6刷になったけど、ほとんどの人は知らないよね。僕も新聞の書評で知って、読んでみようかと思った。
先の生没年を見れば判るように、マリス博士は2019年に亡くなっている。毎月僕は前月の訃報をまとめているから、マリス博士についても書いているのだろうか。見てみたら、その月はアメリカでトニ・モリスン(ノーベル文学賞を受けた黒人女性作家)やピーター・フォンダ(俳優)が亡くなっていたが、マリス博士は書いてなかった。そもそも日本ではマスコミに載らなかったようで、それじゃあ僕が知りようがない。だけど、その時期は新聞記者なんかでも「PCR検査の発明者」なんて言われても、何それ?だったんだろう。
でもマリス博士の訃報は日本でもっと大きく報じられても良かった。それは「日本国際賞」というのをノーベル賞受賞直前に受賞していたからである。これは賞金5千万円で、円建てなのでドルでいくらかはすぐには不明だった。お金が必要な事情があったのに、インターネットもスマホもなかったから当時は不便だったのだ。マリス博士は一度も大学に職を得たことがない。それどころか有名研究所や大企業にも所属したことがない。さらにLSD体験を公言したりしてノーベル委員会には受けが悪いよと忠告されていた。だから、自分はノーベル賞は取れないと思っていた。
PCR検査は「ドライブ・デート中にひらめいた」という「伝説」の真偽が最初に明かされる。ホントにその通りで、途中で車を止めて計算を始めてしまった。マリス博士は結婚離婚を繰り返したことでも知られ、その時の恋人とはその後別れることになった。その当時は、こんな簡単な検査法はすでに誰かが見つけてるに違いないと考えて、むしろ失恋の方が重大事だった。勤めていたベンチャー企業でも受けが悪く、最初は誰も信じなかった。しかし、調べてもそんな発明の論文は誰も書いてないようだった。いくつかの試行錯誤はあったものの、PCR検査が完成した技法となって、それによって「分子生物学の革命」が始まったのだ。
そして日本国際賞を受けて、皇居で歓迎会が開かれた。マリス博士は美智子皇后(当時)に「スウィーティー」(かわい子ちゃん)と呼びかけた。おいおい、ホントかよ。そして皇后との会話が明かされるが、実に興味深いではないか。次にノーベル賞を受けることになった。博士は知らせを受けた後で、サーフィンに出かけてしまった。マスコミが駆けつけた時、サーフボードを持った写真が撮られたのはそういう事情である。(画像の本の表紙にあるもの。)
 (ノーベル賞を受賞する)
(ノーベル賞を受賞する)その時にホワイトハウスに招かれたが、クリントン大統領に麻薬疑惑を聞こうとして失敗。そこで当時保険制度改革に取り組んでいたヒラリー夫人に、オーストラリアの保険制度を質問した。どうせ本人は知るわけないと思ったら、たちどころに説明されたので驚いた。そして今度はアイルランドの保険制度も聞いてみたら、それも答えられた。すっかり才気に感心してしまうのだが、要するにマリス博士という人は皇后とかファーストレディに関わらず女性には声を掛けずにはいられないタイプなのである。その後有名なO・J・シンプソン裁判に弁護側の助言者として関わるが、テレビで有名になった女性検事にも裁判が終わったら夕食に誘うつもりだったなんて書いている。
なかなかとんでもないヤツで、こんな面白い本はないなという出だしなんだけど、実はそれは途中まで。その後どんどん奇人変人ぶりがエスカレートしていく。LSD体験とか、別荘で起こった「未知との遭遇」、星座占いの話などになっていく。そしてエイズはHIVで起こるという説は証明されていないと力説。フロンによるオゾン層破壊や地球温暖化説も証明されていないという話が続く。そういう説を唱える人がいるのは知ってるし、「環境ホルモン」など後に否定されるものもあるから、確かにいろんな説があってもいい。でも面白い「自伝」だなと読んでいると、突然「陰謀論」のようになるのは勘弁。思った以上に奇人で、「奇書」だった。(そんなマリス博士のことだから、「死因に疑問あり」とか新型コロナ流行の前に死んだのは暗殺だなどの説を唱える人もいるようだ。)