 荒れた指にはさまれた煙草の煙がたよりなく荒涼とした冬の景色にとけこみ、しわのめだつ顔から一筋の涙が流れていく。。。
荒れた指にはさまれた煙草の煙がたよりなく荒涼とした冬の景色にとけこみ、しわのめだつ顔から一筋の涙が流れていく。。。冒頭のワンシーンだが、ハリウッド女優の不自然なくらいの若造り(←やっぱり若いといより”若造り”だよね)のつるつるお肌を見慣れていると、レイ役を演じたメリッサ・レオの化粧をしないささくれた顔は演技をする前にすでに何かを語っている。男の顔は履歴書という言葉もあるが、すっかり所帯やつれした彼女の顔にはそれほど高い教育を受けてはいない、生活に困窮しているこどものいる中年女性(主婦)、の生活暦が顔にしわとともにきざまれている。
映像は車の座席に座っているナイトガウンをはおったレイから、開けっぱなしのダッシュボードに流れいていき、そこからなけなしの虎の子の貯金が盗まれたのだと察せられる。まさか、大事な金を盗んだのが、彼女の夫だとは思わなかったのだが。そんな窮地にたった彼女が働く店が「1ドルショップ」。私も便利でたまには100円ショップを利用することがあるのだが、時々あのたくさんの品物がある豊かさとつくりのチープな貧しさのギャップに、気持ちが沈むことがある。100個売れても売上は100ドル、1000個売れても所詮1000ドルじゃないか、と、私など考えがちだが、それでも、真面目に働いて何とか約束どおりに正社員に登用されたいレイの必死さが伝わってきて、同じ女性としてすっかり同情する。やがて彼女の必死さが、そして2人の息子を養い育てていかなければならないぎりぎりの暮らしぶりが、セント・レジスのカナダから米国へ凍った河を車で不法移民を運ぶ犯罪に手をそめていく過程もリアルに描かれていて、凍った風景そのものだ。このレイを中心とした景色に重要な役割を与えられたのが、犯罪に誘ったモホーク族のライラ(ミスティ・アパーム)だった。凍った河を車で移動するには数々のポイントがあり、それは生死を分かつ命がけの仕事。一緒に運命共同体の車に乗っているうちに、何かをあきらめたかのようなライラと、生活のために新しいトレーラハウスを購入しようと働くレイの共犯関係は、彼女たちを結びつけるこどもを核に友情へと育っていく。
彼女達の住んでいる賃貸のトレーラーハウスの家賃は、300ドル程度とか。時給600円程度で働いていると思われるレイの夢の新築のトレーラハウスでさえ40万円だが、それすらなかなか手に届かない。大型の液晶テレビも実はレンタル。クリスマスプレゼントを買うお金も乏しい。世界で最も裕福な米国だが、*)貧困率は14.3%となり、7人にひとりが貧困状態にあるという。彼女たちの暮らしぶりが特別ではないはずだが、米国ではこれまでなかなか貧困層をベースとした映画はあまりなかった。映画資金を提供する側の算盤には、不適切ということだろうか。そんな米国の貧困層の断面を描いている点と、それぞれこどものために命がけの綱渡りのような犯罪に手をそめていくハラハラドキドキ感は、シングルマザーの母親の貧しい日々がサスペンスだったという監督の言うとおりである。また運ぶ荷物である人間の彼らの人生もここでは語られていないが、その存在で様々な波紋を残している。
母親であること、育てなければいけないこどもの存在、それらを連帯に最後は相手を思いやり助け合う姿には、白人と先住民、凍った河のような国境はない。
*)09年の貧困基準は、4人家族の年収が2万1954ドルを下回る世帯とされている。










 1975年4月27日、30歳のケマルは婚約者のためにジェニー・コロンの高級バックを買おうととあるブティックに入った。彼は一族で経営する輸入会社の社長を務める青年実業家、結婚が近い婚約者のスィベルは賢く可愛く、誰もがうらやむお似合いの理想的なカップルだった。彼の人生はまさしく何のかげりもなく前途洋洋。ところが、その店ですっかり存在すら忘れかけていた遠縁の娘、18歳のフュスンと運命的な再会をしてしまった。美しく、しかも官能的なフュスンの魅力にすっかりとりつかれてしまったケマルが、望みどおりに人生最高の美しい黄金の輝きのような時間を過ごしたのは、1975年5月26日、月曜日のことだった。。。
1975年4月27日、30歳のケマルは婚約者のためにジェニー・コロンの高級バックを買おうととあるブティックに入った。彼は一族で経営する輸入会社の社長を務める青年実業家、結婚が近い婚約者のスィベルは賢く可愛く、誰もがうらやむお似合いの理想的なカップルだった。彼の人生はまさしく何のかげりもなく前途洋洋。ところが、その店ですっかり存在すら忘れかけていた遠縁の娘、18歳のフュスンと運命的な再会をしてしまった。美しく、しかも官能的なフュスンの魅力にすっかりとりつかれてしまったケマルが、望みどおりに人生最高の美しい黄金の輝きのような時間を過ごしたのは、1975年5月26日、月曜日のことだった。。。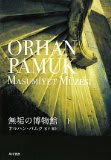 さて、「雪」のカルスというアナトリアの国境の町から、舞台は再び、パムクの生まれ育ったイスタンブルに移したことは重要だと考える。東洋と西洋の文明が融合するイスタンブルで、ケマルとスィベルは婚約したことをきっかけに肉体関係に進み、尚且つ、結婚を控えて風光明媚な別荘で一緒に暮らすようになる。今から、35年前のトルコでだ。彼らの愛情物語のライフスタイルは、近代的な西欧化の象徴として友人たちにうらやましがられ、社交界の人々にも賞賛される。しかし、ケマルがフュスンへの執着から婚約を破棄したら、彼は店番女に頭がいかれて、スィベルは結婚もしないで同棲していた単なる破廉恥な女に成り下がる。同棲がかっこよく素敵に見えるのも、破廉恥な行いに墜ちるのも、1975年のイスタンブルでは鏡像のようなものだ。スィベルは、愛とは同じようなクラスの者だけで成立するような感情と主張する。決して、店番女とケマルのような裕福な男は結ばれないと怒る。パムクの描く様々な異国の風習やノスタルジックな風景の中でさまようケマルの魂の彷徨は、現代日本女性の私だけでなく欧米人の視点からは実にエキゾチックで新鮮に映るはずだ。
さて、「雪」のカルスというアナトリアの国境の町から、舞台は再び、パムクの生まれ育ったイスタンブルに移したことは重要だと考える。東洋と西洋の文明が融合するイスタンブルで、ケマルとスィベルは婚約したことをきっかけに肉体関係に進み、尚且つ、結婚を控えて風光明媚な別荘で一緒に暮らすようになる。今から、35年前のトルコでだ。彼らの愛情物語のライフスタイルは、近代的な西欧化の象徴として友人たちにうらやましがられ、社交界の人々にも賞賛される。しかし、ケマルがフュスンへの執着から婚約を破棄したら、彼は店番女に頭がいかれて、スィベルは結婚もしないで同棲していた単なる破廉恥な女に成り下がる。同棲がかっこよく素敵に見えるのも、破廉恥な行いに墜ちるのも、1975年のイスタンブルでは鏡像のようなものだ。スィベルは、愛とは同じようなクラスの者だけで成立するような感情と主張する。決して、店番女とケマルのような裕福な男は結ばれないと怒る。パムクの描く様々な異国の風習やノスタルジックな風景の中でさまようケマルの魂の彷徨は、現代日本女性の私だけでなく欧米人の視点からは実にエキゾチックで新鮮に映るはずだ。 1968年のペンシルベニア州クレアトン。町の製鉄所の煙突から吐き出された煙がただようくすんだ空の下、マイケル(ロバート・デ・ニーロ)、ニック(クリストファー・ウォーケン)、スティーブン(ジョン・サヴェージ)、スタン(J・カザール)、アクセル(チャック・アスペグラン)の5人の若者が、ふざけあいながら勤務をおえた工場からふざけあいなからなじみのバーに向かっていく。今夜は、スティーヴンの結婚式が開かれるだけでなく、ベトナムに徴兵されるマイケル、ニック、そして花婿のスティーヴンの歓送会もかねていた。教会では白い花を飾り、ウエディングケーキが用意され、ピンクのドレスを着たブライズメイドたちが華やかなはじけるような笑い声を挙げて式場にかけつけていく。(以下、内容にふれています。)
1968年のペンシルベニア州クレアトン。町の製鉄所の煙突から吐き出された煙がただようくすんだ空の下、マイケル(ロバート・デ・ニーロ)、ニック(クリストファー・ウォーケン)、スティーブン(ジョン・サヴェージ)、スタン(J・カザール)、アクセル(チャック・アスペグラン)の5人の若者が、ふざけあいながら勤務をおえた工場からふざけあいなからなじみのバーに向かっていく。今夜は、スティーヴンの結婚式が開かれるだけでなく、ベトナムに徴兵されるマイケル、ニック、そして花婿のスティーヴンの歓送会もかねていた。教会では白い花を飾り、ウエディングケーキが用意され、ピンクのドレスを着たブライズメイドたちが華やかなはじけるような笑い声を挙げて式場にかけつけていく。(以下、内容にふれています。) 悲劇的なニックの死を迎えて、葬儀の後、彼らはなじみのバーに集う。誰もが涙を堪え、お互いをいたわりあい、ニックのために乾杯をする。そして彼らが歌うのが、"God bless America”だった。実は、これまで、私はこの作品をベトナム戦争を題材にした戦争映画というくくりで観ていたのだが、少し違うように感じ始めている。ロシアから新大陸アメリカに渡って来た彼らだったのだが、ここでも貧しく生活は苦しかった。しかし、彼らが住む町は同じロシア系移民たちで独自の文化を継承し、地域のコミュニティがお互いに助け合い支えあうぬくもりのある暮らし。スティーブンの結婚式で必要な手作りのウェディングケーキを運ぶ、分厚い眼鏡をかけた老女たちの笑顔から、そんなこの町のあり方と住民たちのかかわり方が想像される。そんな彼らにとって、もう帰る故郷は、帰る家は、結局このアメリカという国以外にはないのだ。戦場に向かうニックが、森の木が好きだ、家に帰ってきたいという想いに友が歌う”God bless America, ・・・My home sweet home”が重なっていく。戦争というよりも、ベトナム戦争で傷つき、若く希望の光を失っていくアメリカという国を描いている映画なのだ。
悲劇的なニックの死を迎えて、葬儀の後、彼らはなじみのバーに集う。誰もが涙を堪え、お互いをいたわりあい、ニックのために乾杯をする。そして彼らが歌うのが、"God bless America”だった。実は、これまで、私はこの作品をベトナム戦争を題材にした戦争映画というくくりで観ていたのだが、少し違うように感じ始めている。ロシアから新大陸アメリカに渡って来た彼らだったのだが、ここでも貧しく生活は苦しかった。しかし、彼らが住む町は同じロシア系移民たちで独自の文化を継承し、地域のコミュニティがお互いに助け合い支えあうぬくもりのある暮らし。スティーブンの結婚式で必要な手作りのウェディングケーキを運ぶ、分厚い眼鏡をかけた老女たちの笑顔から、そんなこの町のあり方と住民たちのかかわり方が想像される。そんな彼らにとって、もう帰る故郷は、帰る家は、結局このアメリカという国以外にはないのだ。戦場に向かうニックが、森の木が好きだ、家に帰ってきたいという想いに友が歌う”God bless America, ・・・My home sweet home”が重なっていく。戦争というよりも、ベトナム戦争で傷つき、若く希望の光を失っていくアメリカという国を描いている映画なのだ。 某年某月某日、、、あるヴァイオリニストのリサイタルを聴いていた時のことだった。
某年某月某日、、、あるヴァイオリニストのリサイタルを聴いていた時のことだった。
 今年は大逆事件から、100年がたつ。幸徳秋水、森近運平、宮下太吉、菅野スガら24名の社会主義者が、明治天道暗殺計画を企てたと事件を捏造されて、冬の寒い日に死刑を処刑されたのは、歴史の教科書にも掲載されていて、日本人なら誰でも知っているだろう。それでは、同時代に彼らや大杉栄らと交流し、社会主義者として生きぬいた堺利彦という名前を知っているかと問われたら、私は知らなかった。ましてや、大逆事件後の弾圧の社会主義冬の時代に、彼が、「売文社」を興して文章の代筆から翻訳、コピーライターの仕事までこなして文を売り、ユーモアと筆の力で生き抜いたことも知らない。彼らは非業な死のかわりに歴史に革命家としてその名前を刻んだが、堺利彦はたまたま事件の最中に投獄されていて獄中にいたために命拾いをして、64歳で畳の上で脳溢血で亡くなったためだろうか、まさに「売文社」は命がけの道楽だったにも関わらず、彼の名前と功績は、歴史のかげにすっかり埋没して忘れ去られてしまった。これまでも、古本屋を探索して闇に埋もれた史実を発掘してきた歴史の考古学者のような著者の黒岩比佐子さんは、この事実に「義憤にかられた」と言う。そんな黒岩さん自身の”文章を売ってきた”人生の集大成のような、渾身の一冊が本書である。
今年は大逆事件から、100年がたつ。幸徳秋水、森近運平、宮下太吉、菅野スガら24名の社会主義者が、明治天道暗殺計画を企てたと事件を捏造されて、冬の寒い日に死刑を処刑されたのは、歴史の教科書にも掲載されていて、日本人なら誰でも知っているだろう。それでは、同時代に彼らや大杉栄らと交流し、社会主義者として生きぬいた堺利彦という名前を知っているかと問われたら、私は知らなかった。ましてや、大逆事件後の弾圧の社会主義冬の時代に、彼が、「売文社」を興して文章の代筆から翻訳、コピーライターの仕事までこなして文を売り、ユーモアと筆の力で生き抜いたことも知らない。彼らは非業な死のかわりに歴史に革命家としてその名前を刻んだが、堺利彦はたまたま事件の最中に投獄されていて獄中にいたために命拾いをして、64歳で畳の上で脳溢血で亡くなったためだろうか、まさに「売文社」は命がけの道楽だったにも関わらず、彼の名前と功績は、歴史のかげにすっかり埋没して忘れ去られてしまった。これまでも、古本屋を探索して闇に埋もれた史実を発掘してきた歴史の考古学者のような著者の黒岩比佐子さんは、この事実に「義憤にかられた」と言う。そんな黒岩さん自身の”文章を売ってきた”人生の集大成のような、渾身の一冊が本書である。 俳優の中には、どんな役柄にもなりきり器用にこなせるカメレオンのようなタイプの役者もいる。そんな才能ある役者の抜群の演技力に感嘆させられることも多い。
俳優の中には、どんな役柄にもなりきり器用にこなせるカメレオンのようなタイプの役者もいる。そんな才能ある役者の抜群の演技力に感嘆させられることも多い。