今年の9月1日、うだるような猛暑の一日がはじまろとうしている早朝、始業前の浪速区役所前に長蛇の列ができている。ドアが開くと我先にと殺到していく先に、職員が用意しているのは現金が入った茶封筒でぎっしりと箱に入って並んでいる。私は知らなかったのだが、毎月、1日は生活保護受給日だそうだ。40代の単身者は、12万円程度の保護費が支給される。
最後のセーフティネットと言われる「生活保護」に、ここ数年、異変が起こっている。昨日のETV特集は、知られざる大阪市の生活保護の実態を報道していた。不景気もあいまって、最近、生活保護受給世帯が激増していて、1990年代半ばのバブル時代の倍を超えて、今や受給者数は全国135万世帯187万人にも膨れ上がっている。増える一方の、生活保護費は国や地方自治体の財政を逼迫もしている。特に深刻なのが大阪市で、受給者人口13万6600人で、この数字は市民の20人に1人が生活保護を受けている計算になる。平成22年度に計上した生活保護費は2863億円!なんと市税収入の半分になるという。大阪市はどうなっているのかと驚いたのだが、もっと驚かされあきれたのは、受給者を利用して市民の血税を搾取する貧困ビジネスの実態である。
生活保護受給者へのインタビューで浮かんだのは、”悪徳”と言ってもよいような不動産会社とその会社に密着した医療機関の手口である。ある男性Aさんが紹介されて住んでいるアパートは、築数10年もたつ相当古いアパートで、トイレは一応水洗だが、今時見かける事がなくなったタンクが上にあり、チェーンをひっぱって水を流す方式のトイレ。勿論、とても狭い。家賃は42000円。この家賃は、生活保護費が申請できる上限だそうだ。
別のBさんは、千葉県船橋駅前でホームレスをしていたのだが、不動産業者に声をかけられてワゴン車に乗せられ、他の人たちと一緒に大阪に連れてこられた。不動産業者が全国の路上生活者を集めて、大阪の狭いアパートの入居させ、生活保護を受給させて家賃を取り立てる。4畳半程度の質素な部屋で、ここでも家賃は42000円。敷金、礼金、最低限の生活用品も市から支給されている。
それだけでなく、Cさんは不動産業者と提携している病院に糖尿病で1年以上も入院し、退院したらこれをすべて服用したら逆に副作用で病気を併発するのではないかと思うくらいの薬の山を病院から支給されている。診断書には便秘症などと病名?も書かれているのだが、勿論、医療費の請求先は大阪市の税金を直撃。このように生活保護受給者専門のような病院が、大阪市には34ヶ所あるという。確かにセイフティーネットの機能として「生活保護」は必要だが、一見、健康そうな受給者を利用する不動産業者、医療機関の実態を知ったら、大阪市民でなくても怒りを覚える。
このような非常事態に危機感を募らせる平松邦夫市長は、昨年、市役所に「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」を起ち上げ、激増の実態の背景を調べ、解決策を模索している。民間企業のノウハウを導入して、受給者に履歴書の書き方や面接試験の受け方などを指導して就労支援もしているのだが、不景気もあいまって再就職は困難を極める。大阪市が税金を投入して支援して就職できた人が1193人、ようやく自立できた人(保護廃止)はわずか28人。その一方で、派遣きりなのであらたに生活保護に落ちて申請した人は1万人を超えた。本当に大変なことになっている!
最後のセーフティネットと言われる「生活保護」に、ここ数年、異変が起こっている。昨日のETV特集は、知られざる大阪市の生活保護の実態を報道していた。不景気もあいまって、最近、生活保護受給世帯が激増していて、1990年代半ばのバブル時代の倍を超えて、今や受給者数は全国135万世帯187万人にも膨れ上がっている。増える一方の、生活保護費は国や地方自治体の財政を逼迫もしている。特に深刻なのが大阪市で、受給者人口13万6600人で、この数字は市民の20人に1人が生活保護を受けている計算になる。平成22年度に計上した生活保護費は2863億円!なんと市税収入の半分になるという。大阪市はどうなっているのかと驚いたのだが、もっと驚かされあきれたのは、受給者を利用して市民の血税を搾取する貧困ビジネスの実態である。
生活保護受給者へのインタビューで浮かんだのは、”悪徳”と言ってもよいような不動産会社とその会社に密着した医療機関の手口である。ある男性Aさんが紹介されて住んでいるアパートは、築数10年もたつ相当古いアパートで、トイレは一応水洗だが、今時見かける事がなくなったタンクが上にあり、チェーンをひっぱって水を流す方式のトイレ。勿論、とても狭い。家賃は42000円。この家賃は、生活保護費が申請できる上限だそうだ。
別のBさんは、千葉県船橋駅前でホームレスをしていたのだが、不動産業者に声をかけられてワゴン車に乗せられ、他の人たちと一緒に大阪に連れてこられた。不動産業者が全国の路上生活者を集めて、大阪の狭いアパートの入居させ、生活保護を受給させて家賃を取り立てる。4畳半程度の質素な部屋で、ここでも家賃は42000円。敷金、礼金、最低限の生活用品も市から支給されている。
それだけでなく、Cさんは不動産業者と提携している病院に糖尿病で1年以上も入院し、退院したらこれをすべて服用したら逆に副作用で病気を併発するのではないかと思うくらいの薬の山を病院から支給されている。診断書には便秘症などと病名?も書かれているのだが、勿論、医療費の請求先は大阪市の税金を直撃。このように生活保護受給者専門のような病院が、大阪市には34ヶ所あるという。確かにセイフティーネットの機能として「生活保護」は必要だが、一見、健康そうな受給者を利用する不動産業者、医療機関の実態を知ったら、大阪市民でなくても怒りを覚える。
このような非常事態に危機感を募らせる平松邦夫市長は、昨年、市役所に「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」を起ち上げ、激増の実態の背景を調べ、解決策を模索している。民間企業のノウハウを導入して、受給者に履歴書の書き方や面接試験の受け方などを指導して就労支援もしているのだが、不景気もあいまって再就職は困難を極める。大阪市が税金を投入して支援して就職できた人が1193人、ようやく自立できた人(保護廃止)はわずか28人。その一方で、派遣きりなのであらたに生活保護に落ちて申請した人は1万人を超えた。本当に大変なことになっている!










 1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドに侵攻して第二次大戦の火蓋を切るという歴史的な事件のかげで、この国では「遺伝病子孫予防法」に関する新しい政令が下された。それによって、障碍児や入院中の精神病患者たちが軍によって特殊な施設に移送され、殺された。敗戦までの犠牲者の数は7万人にもなると言われている。ナチスによる全面戦争開始の合図のための安楽死計画、それはこれまでの”低価値者”の断種手術を発展させてナチスによる優生政策の到達点とも言える。後に世界を驚かせたこの事件を題材にした
1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドに侵攻して第二次大戦の火蓋を切るという歴史的な事件のかげで、この国では「遺伝病子孫予防法」に関する新しい政令が下された。それによって、障碍児や入院中の精神病患者たちが軍によって特殊な施設に移送され、殺された。敗戦までの犠牲者の数は7万人にもなると言われている。ナチスによる全面戦争開始の合図のための安楽死計画、それはこれまでの”低価値者”の断種手術を発展させてナチスによる優生政策の到達点とも言える。後に世界を驚かせたこの事件を題材にした 第2部、ついに・・・ついに完結!かっ?
第2部、ついに・・・ついに完結!かっ? xtc4241さまのブログで映画『ブラック・スワン』公開情報を知ったのだが、主人公のバレエリーナを演じるナタリー・ポートマンがおそろしくはまり役だと感じる。クラシックのバレエリーナーとして身体能力は必須だが、容姿に求められるのは、努力で補うことは叶わない美貌とバランスのよい手足の長さは勿論だが、何よりも華奢で小柄な体型は重要である。それに、豊満な胸は10代の姫君を踊るにはむしろ邪魔である。迫力あるハリウッド女優は、やまのようにいるが、確かに知性的な品のあるコンパクトなカラダのナタリー・ポートマンは、生まれながらのバレエリーナの雰囲気がある。
xtc4241さまのブログで映画『ブラック・スワン』公開情報を知ったのだが、主人公のバレエリーナを演じるナタリー・ポートマンがおそろしくはまり役だと感じる。クラシックのバレエリーナーとして身体能力は必須だが、容姿に求められるのは、努力で補うことは叶わない美貌とバランスのよい手足の長さは勿論だが、何よりも華奢で小柄な体型は重要である。それに、豊満な胸は10代の姫君を踊るにはむしろ邪魔である。迫力あるハリウッド女優は、やまのようにいるが、確かに知性的な品のあるコンパクトなカラダのナタリー・ポートマンは、生まれながらのバレエリーナの雰囲気がある。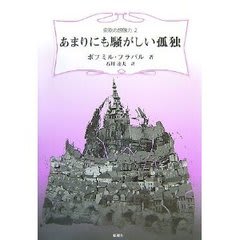 「35年間、僕は故紙に埋もれて働いている──これは、そんな僕のラブ・ストーリーだ。」
「35年間、僕は故紙に埋もれて働いている──これは、そんな僕のラブ・ストーリーだ。」 「僕のリーベ」
「僕のリーベ」 取材で訪問した国は31年間で約150カ国、移動距離にすると地球を約180週、1959年から1990年まで続いたテレビ番組のために一年の半分を海外で取材のために生活してきた。今だったら、映画の『マイレージ、マイライフ』でジョージ・クルーニー演じるライアンより先に航空会社の"コンシェルジェ・キー"をゲットしたかもしれないこのトンデル方は、「兼高かおる世界の旅」でナレーター、ディレクター兼プロデューサーを勤めていた兼高かおるさんご本人の近著である。これほどの長寿番組なのだからおそらく人気も高く良質な番組だったのだろうが、残念なことに私は観た記憶がないのである。兼高かおるさんの事も殆ど知らないのだが、これほど多くの国を訪問した方なのだから、何か特別な見識や意見をお持ちなのではないだろうかと期待して本を開いた。
取材で訪問した国は31年間で約150カ国、移動距離にすると地球を約180週、1959年から1990年まで続いたテレビ番組のために一年の半分を海外で取材のために生活してきた。今だったら、映画の『マイレージ、マイライフ』でジョージ・クルーニー演じるライアンより先に航空会社の"コンシェルジェ・キー"をゲットしたかもしれないこのトンデル方は、「兼高かおる世界の旅」でナレーター、ディレクター兼プロデューサーを勤めていた兼高かおるさんご本人の近著である。これほどの長寿番組なのだからおそらく人気も高く良質な番組だったのだろうが、残念なことに私は観た記憶がないのである。兼高かおるさんの事も殆ど知らないのだが、これほど多くの国を訪問した方なのだから、何か特別な見識や意見をお持ちなのではないだろうかと期待して本を開いた。 今年最も観たかった映画が、2009年カンヌ国際映画祭でパルムドール大賞に輝いたミヒャエル・ハネケ監督の最新作『白いリボン』。受賞の報道から待ち続けること1年あまり。そして、先日、ようやく鑑賞することができた私の個人的な感想は、この映画は今年度最高の映画だったということだ。
今年最も観たかった映画が、2009年カンヌ国際映画祭でパルムドール大賞に輝いたミヒャエル・ハネケ監督の最新作『白いリボン』。受賞の報道から待ち続けること1年あまり。そして、先日、ようやく鑑賞することができた私の個人的な感想は、この映画は今年度最高の映画だったということだ。 ここから本題に入るが、ハネケらしいと言えば、彼ほど人間の心の闇を情け容赦なく暴き立てる不快な監督はいない。私たちがかろうじて、理性という衣装を着て隠している、海老蔵並みの高慢さや嘘、悪意、偽善、暴力性をひきずりだしてその醜い裸体をさらす、と言ったら人間不信者になるのだろうか。ハネケ作品を観ていると、100%善の人やまたその逆の人もいないように、私たちはかろうじて均衡を保ち、なんとかつつがなく平穏に生きている、もしくは生きていると思い込んでいるということに気がつく。本作も嫌らしくも、村たちの底にある悪が次々とうかびあがり、連鎖反応のように不穏な暗い空気がただよってくる。しかし、これまで個人の人間性の深淵を徹底的に追求してきたのだが、本作では個の集合体としての全体主義にせまることであらたな普遍性をうちだしている。私たちは時代からナチス台頭の萌芽をそこに見ることになるのだが、これは過去の歴史をふりかえる映画ではない。劉暁波氏のノーベル平和賞受賞に対する中国のふるまいを見るにつれ、悪しき全体主義を考えさせられる。また、それは厳格な支配階級と被支配階級の関係が硬直した社会の恐怖にもつながっていく。ここでハネケは、神という偶像の力を借りて人を支配する人間を描くことで神の存在すらも否定している。最後に流れる賛美歌の美しさが胸にせまってきて、やはり恐るべし作家ハネケと感嘆のため息をのみこんだ。
ここから本題に入るが、ハネケらしいと言えば、彼ほど人間の心の闇を情け容赦なく暴き立てる不快な監督はいない。私たちがかろうじて、理性という衣装を着て隠している、海老蔵並みの高慢さや嘘、悪意、偽善、暴力性をひきずりだしてその醜い裸体をさらす、と言ったら人間不信者になるのだろうか。ハネケ作品を観ていると、100%善の人やまたその逆の人もいないように、私たちはかろうじて均衡を保ち、なんとかつつがなく平穏に生きている、もしくは生きていると思い込んでいるということに気がつく。本作も嫌らしくも、村たちの底にある悪が次々とうかびあがり、連鎖反応のように不穏な暗い空気がただよってくる。しかし、これまで個人の人間性の深淵を徹底的に追求してきたのだが、本作では個の集合体としての全体主義にせまることであらたな普遍性をうちだしている。私たちは時代からナチス台頭の萌芽をそこに見ることになるのだが、これは過去の歴史をふりかえる映画ではない。劉暁波氏のノーベル平和賞受賞に対する中国のふるまいを見るにつれ、悪しき全体主義を考えさせられる。また、それは厳格な支配階級と被支配階級の関係が硬直した社会の恐怖にもつながっていく。ここでハネケは、神という偶像の力を借りて人を支配する人間を描くことで神の存在すらも否定している。最後に流れる賛美歌の美しさが胸にせまってきて、やはり恐るべし作家ハネケと感嘆のため息をのみこんだ。 審査委員長が映画『ピアニスト』でカンヌ主演女優賞を受賞したイザベル・ユベールという事情が今度こそパルムドール賞、という下馬評どおりになったが、ハネケの集大成とも言える本作の美しく完璧な映像の前に、そんな揶揄は一掃されたはずだ。審査される監督と審査委員長の親しい事情を受賞の情実に結び付けたいマスコミに「とにかく素晴らしい映画を選んだだけ」とイザベル・ユベールは見事に打ち返し、「映画のテーマとの距離のとり方が完璧。メッセージを送ろうとするのではなく、物事を静かに描写している。」と称賛したそうだが、おっしゃるとおり!
審査委員長が映画『ピアニスト』でカンヌ主演女優賞を受賞したイザベル・ユベールという事情が今度こそパルムドール賞、という下馬評どおりになったが、ハネケの集大成とも言える本作の美しく完璧な映像の前に、そんな揶揄は一掃されたはずだ。審査される監督と審査委員長の親しい事情を受賞の情実に結び付けたいマスコミに「とにかく素晴らしい映画を選んだだけ」とイザベル・ユベールは見事に打ち返し、「映画のテーマとの距離のとり方が完璧。メッセージを送ろうとするのではなく、物事を静かに描写している。」と称賛したそうだが、おっしゃるとおり!