 ”あの時代”・・・たくさんのデモ、内ゲバ、政治的挫折、そして死。
”あの時代”・・・たくさんのデモ、内ゲバ、政治的挫折、そして死。アメリカの女性作家ボビー・アン・メイソンの著書「インカントリー」では、60年代に憧れる17歳の娘に
「いい時代じゃなかったのよ。いい時代じゃなかったなんて思わないことね」
とシックスティーズ60年代世代の母親が諭しているそうだ。
”あの時代”、1968年から72年にかけて朝日新聞社に勤務して「週刊朝日」「朝日ジャーナル」の記者だった川本三郎さんの回想録が本書である。
同じタイトルの映画『マイ・バック・ページ』が自伝的映画だとしたら、本書はまさに川本さん自身が体験した苦くも厳しい青春の蹉跌である。それは、彼にとっては、長い間忘れようとしていた時代だが(私には逃げようとしていた時代に思える)、しかし、一度しっかり向き合って”総括”しなければ永遠に”あの時代”から彼は自由になれない。
前半は、あの時代に川本青年を通り過ぎた若者たちが語られている。映画にも登場した「週刊朝日」のモデルを務めた保倉幸恵、センス・オブ・ギルティを議論する米国からきた記者スティーブ、日比谷高校の早熟で美青年のM君と彼の恋人。そして、戦争で両腕と両脚を失った50歳ぐらいの取材相手の男性。国会周辺ではデモがあり、羽田空港では機動隊と学生が衝突し、東大安田講堂陥落、ヒッピーが歌い、熱気に包まれた時代の中で、「記者」という特権で安全な場所で傍観者でいることに疑問を感じた川本青年の前に現れたのが、「赤衛軍」を名乗るKだった。その後の顛末は、映画と殆ど同じで23日間留置所に入れられ、犯人隠匿及び証拠隠滅罪で有罪判決を受けるまでが後半。
当初、いかがわしいKだったが彼を思想犯として考え「取材源の秘匿」にこだわり、川本さんが頑固にジャーナリストのモラルにこだわった背景には、山本義高や滝田修らが知的エリートであり、彼らが自らの社会的意味を自己否定してゆく姿に清潔さを感じていて、同じく東大出身の川本さんなりのKに対するある種の負い目や同情が事件に傾斜していったのではないだろうか。社内でも孤立していく彼を気の毒だとは思うが、様々な点で、ジャーナリストとして考えが浅く、意固地になり甘かったとしか言いようがない。本書を改めて読んで、この状況下で、共犯者にされなかっただけでもよかったと私には思える。しかし、それは今の世代の、社会経験がそれなりにあるオトナの私だから言えることだ。
重要なことはあの時代の川本さんの行動や考え方の是非を説いたり、批判することではない。ジャーナリストを志し、就職浪人までして入社した朝日新聞を懲戒解雇され、事件後は政治について語ることを川本さんは禁じてきた。その資格がないからだ。それも当然の報いだ。何の罪もない人がひとり亡くなっているのだ。それでも、大きな、大きな挫折の後に生きていく場所は文学しかなかった川本さんだが、評論や映画批評では活躍されているのは周知のとおり。人間、何とかやっていけるものだ。
映画化に際し、監督も脚本家も1972年当時まだ生まれていなかった若い世代であることに意味があることがわかった。何故ならば、川本さんはあの時代はいい時代じゃなかったが、誰もが他者のことを考えるかけがえのない”われらの時代”だったと言う。60年代世代の後、私たちはそんな”われらの時代”をずっと見失っている。
■アーカイヴも
・映画『マイ・バック・ページ』
・「小説家たちの休日」










 今年の秋も、ウィーン・フィルが黄金の輝きを運んでやってくるようだ。今日は、そのチケットゲットの大事な日。何とか、ようやく!念願のウィーン・フィルに行けそうだ。しかも、嬉しいことに*サントリーホール25周年を記念した特別価格です・・・ということらしい。それは兎も角、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の設立は1842年。今日まで続くオーケストラの中でも最も歴史がある。(ベルリン・フィルは1882年創立)その伝統あるウィーン・フィルと同じ年にニューヨーク・フィルハーモックも産声をあげていたとは、ちょっと意外な感じがしたは、おそらく私だけではないだろう。しかも、更に米国はオーケストラ大国だったことにも。しかし、今日私たちが聴いている音楽のオーケストラのスタイルが19世紀に成立したという経緯や、クラシック音楽の本場、ドイツのユダヤ人音楽家が戦争中に米国に移住してきたことや、ロシアの音楽家も革命後に亡命してきて名教師になっていたことなどを考えると、現代の米国のオーケストラが高い能力と実力をもち、ヨーロッパを凌駕する魅力も備えていることも当然の流れかもしれない。資本力もばっちりあるし。
今年の秋も、ウィーン・フィルが黄金の輝きを運んでやってくるようだ。今日は、そのチケットゲットの大事な日。何とか、ようやく!念願のウィーン・フィルに行けそうだ。しかも、嬉しいことに*サントリーホール25周年を記念した特別価格です・・・ということらしい。それは兎も角、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の設立は1842年。今日まで続くオーケストラの中でも最も歴史がある。(ベルリン・フィルは1882年創立)その伝統あるウィーン・フィルと同じ年にニューヨーク・フィルハーモックも産声をあげていたとは、ちょっと意外な感じがしたは、おそらく私だけではないだろう。しかも、更に米国はオーケストラ大国だったことにも。しかし、今日私たちが聴いている音楽のオーケストラのスタイルが19世紀に成立したという経緯や、クラシック音楽の本場、ドイツのユダヤ人音楽家が戦争中に米国に移住してきたことや、ロシアの音楽家も革命後に亡命してきて名教師になっていたことなどを考えると、現代の米国のオーケストラが高い能力と実力をもち、ヨーロッパを凌駕する魅力も備えていることも当然の流れかもしれない。資本力もばっちりあるし。

 気さくに笑顔でインタビューに応じる彼は、ごく普通のサッカー青年という感じなのだが、サントリーホールにずらりと並べられた打楽器を自分で位置を決めてねじの調節を始める。10種類ほどの様々なタイプの打楽器が彼の周囲を取り囲んでいて、それだけでも壮観な印象。真剣な表情で、ひとつひとつ楽器のねじを巻き、位置を調節していく。この作業は、絶対に自分で行い、1時間程度の時間をかけるとのこと。その作業の意味は、演奏がはじまりたちどころに判明した。左手と右手で別々の楽器をたたいたり、と、まさに瞬間芸の連続である。しかも、後ろにある楽器を演奏することもあり、テリトリーが広いのである。だから、めちゃくちゃ忙しい。
気さくに笑顔でインタビューに応じる彼は、ごく普通のサッカー青年という感じなのだが、サントリーホールにずらりと並べられた打楽器を自分で位置を決めてねじの調節を始める。10種類ほどの様々なタイプの打楽器が彼の周囲を取り囲んでいて、それだけでも壮観な印象。真剣な表情で、ひとつひとつ楽器のねじを巻き、位置を調節していく。この作業は、絶対に自分で行い、1時間程度の時間をかけるとのこと。その作業の意味は、演奏がはじまりたちどころに判明した。左手と右手で別々の楽器をたたいたり、と、まさに瞬間芸の連続である。しかも、後ろにある楽器を演奏することもあり、テリトリーが広いのである。だから、めちゃくちゃ忙しい。 先月亡くなられた俳優の児玉清さんは、読書家としても知られていたが、切り絵制作も生涯の趣味だったそうだ。その切り絵を始めたきっかけは、学習院大学を卒業後、東宝ニューフェースに合格するものの、長かった大部屋暮らし時代に生活費の足しにとはじめたことがきっかけとのこと。切り絵というものが生活費になった時代があったとは意外な感もしたが、”向上心と努力の紳士”という弔辞にふさわしい児玉さんらしい趣味だと感じた。
先月亡くなられた俳優の児玉清さんは、読書家としても知られていたが、切り絵制作も生涯の趣味だったそうだ。その切り絵を始めたきっかけは、学習院大学を卒業後、東宝ニューフェースに合格するものの、長かった大部屋暮らし時代に生活費の足しにとはじめたことがきっかけとのこと。切り絵というものが生活費になった時代があったとは意外な感もしたが、”向上心と努力の紳士”という弔辞にふさわしい児玉さんらしい趣味だと感じた。 革の手袋をはめた精悍な表情をした三島由紀夫と、当時、”慎太郎カット”という髪型が若者たちに大流行したという石原慎太郎が並んで、ビルの屋上からなにやら眺めている。この写真を撮影した樋口進氏によると、ある日の歌舞伎座でファンから「慎太郎刈りの真似をしている」と言われた三島は、「俺がこの髪型の元祖だ」と烈火の如く怒ったそうだ。このエピソードを、著者の川島三郎さんは、たかが髪型ぐらいで怒る三島を「何よりもオリジナリティを大事にしている誇り高い作家」と感想を述べている。そして、しかしたかが髪型にこだわるところに、見られ続けた作家の真骨頂と批評する。本書は、1922年生まれ、文士たちの写真を撮り続けた写真家、樋口進さんの写真に短いキャプションがそえられ、1944年生まれの川本さんの文章が4ページ、という構成になっている。とりあげられた作家は、川本さんの研究対象でもある1879年生まれの永井荷風が、浅草ロック座の裸の踊り子たちに囲まれた写真にはじまり、生まれた年代順に1932年生まれの江藤淳まで、すでに鬼籍に入られた65人の文士の素顔をとらえた昭和文壇実録である。
革の手袋をはめた精悍な表情をした三島由紀夫と、当時、”慎太郎カット”という髪型が若者たちに大流行したという石原慎太郎が並んで、ビルの屋上からなにやら眺めている。この写真を撮影した樋口進氏によると、ある日の歌舞伎座でファンから「慎太郎刈りの真似をしている」と言われた三島は、「俺がこの髪型の元祖だ」と烈火の如く怒ったそうだ。このエピソードを、著者の川島三郎さんは、たかが髪型ぐらいで怒る三島を「何よりもオリジナリティを大事にしている誇り高い作家」と感想を述べている。そして、しかしたかが髪型にこだわるところに、見られ続けた作家の真骨頂と批評する。本書は、1922年生まれ、文士たちの写真を撮り続けた写真家、樋口進さんの写真に短いキャプションがそえられ、1944年生まれの川本さんの文章が4ページ、という構成になっている。とりあげられた作家は、川本さんの研究対象でもある1879年生まれの永井荷風が、浅草ロック座の裸の踊り子たちに囲まれた写真にはじまり、生まれた年代順に1932年生まれの江藤淳まで、すでに鬼籍に入られた65人の文士の素顔をとらえた昭和文壇実録である。 作家の井伏鱒二は「わたしは平凡な言葉を美しいと思ふやうになりたい」という言葉を残した。
作家の井伏鱒二は「わたしは平凡な言葉を美しいと思ふやうになりたい」という言葉を残した。 今日、世界中の人々が観る映画の8割が、ハリウッド映画だそうである。マイケル・ダグラスではないが、映画は航空産業に次ぐアメリカ第二の輸出産業。ハリウッド映画を意識的に避けている私ですら、もしかして鑑賞本数の半分は米国産!?ハリウッド映画は、何も考えなくてもよい娯楽映画としてはよくできているし、アメリカという国を考えさせてくれるのでやはり好きな映画も多く、お疲れモードの時はついつい私もハリウッドになびくのだろう。しかし、本書の著者、狩野良規氏は、ハリウッド映画のやばいところは、映画がアメリカ的価値観の発露の場となり、難しいことなしに映画を楽しみながらいつのまにか米国流世界観とイデオロギーの価値観がすりこまれてしまうところだと主張している。確かに、やばいっす。本書は、映画産業においては残りの2割のなかで、巨大な資本もなくマイノリティにおしやられながらも、すぐれたイギリスからやってきた銀幕の中にあるイギリス的なるものの考察で成り立っている。
今日、世界中の人々が観る映画の8割が、ハリウッド映画だそうである。マイケル・ダグラスではないが、映画は航空産業に次ぐアメリカ第二の輸出産業。ハリウッド映画を意識的に避けている私ですら、もしかして鑑賞本数の半分は米国産!?ハリウッド映画は、何も考えなくてもよい娯楽映画としてはよくできているし、アメリカという国を考えさせてくれるのでやはり好きな映画も多く、お疲れモードの時はついつい私もハリウッドになびくのだろう。しかし、本書の著者、狩野良規氏は、ハリウッド映画のやばいところは、映画がアメリカ的価値観の発露の場となり、難しいことなしに映画を楽しみながらいつのまにか米国流世界観とイデオロギーの価値観がすりこまれてしまうところだと主張している。確かに、やばいっす。本書は、映画産業においては残りの2割のなかで、巨大な資本もなくマイノリティにおしやられながらも、すぐれたイギリスからやってきた銀幕の中にあるイギリス的なるものの考察で成り立っている。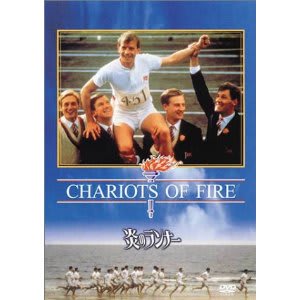 イギリス文学、演劇学、映画論の専門家の狩野良規さんの熱~い大作
イギリス文学、演劇学、映画論の専門家の狩野良規さんの熱~い大作 なにやら気になる表紙の絵画は、エヴァ・ゴンザレスEva Gonzalèsの「イタリア人座の桟敷席」1874年。
なにやら気になる表紙の絵画は、エヴァ・ゴンザレスEva Gonzalèsの「イタリア人座の桟敷席」1874年。