 1955年、反核運動をはじめた原子物理学者たちによる、彼らの”良心”ともいうべき「ラッセル=アインシュタイン宣言」が発表された。
1955年、反核運動をはじめた原子物理学者たちによる、彼らの”良心”ともいうべき「ラッセル=アインシュタイン宣言」が発表された。日本の湯川秀樹も署名しているこの宣言では、核兵器が世界の人類を抹殺するかもしれないと訴えている。宣言のおよそ20年前にさかのぼること、1938年、ドイツの科学者オットー・ハーン、フリッツ・ストラスマンは、中性子をウラン235の原子核に当てると原子核が分裂して巨大なエネルギーを生むことを発見した。この科学的発見は、科学者の手から離れ、戦争という有事に軍事に利用され、原子爆弾という大量殺戮兵器となり、アメリカは巨額の経費と人員を投入した成果を、ヒロシマ、そして更にプラトニウム型原子爆弾をナガサキに投下することで確認した。
日本は世界唯一の被爆国だ。この原爆投下という人類史の汚点においては、日本は被害者である。しかし、原爆製造を試みたのは、アメリカだけではなかった。日本でも理化学研究所の仁科芳雄研究室では、2000万円以上(現在に換算すると300億円)の研究費を支給されて製造を軍や政府から要請されていたのだった。
「マッチ箱ひと箱の大きさで大都市が吹き飛ぶ」
当時の日本には、こんな噂がささやかれていたそうだ。戦局が厳しくなり、疲弊しきった日本人には、この噂、つまり大量殺戮兵器がひそやかに期待されつつあり、一方、陸軍将校達はこの噂を本物にすべく、研究室を訪問しては仁科博士を矢のように督促をしていた。戦争という状況下においては、加害者、被害者ともに兵器が勝敗とは別に、人々にどのような結果をもたらすかの人間性の視点はなかったといえよう。不思議なことに、日本で可能な爆弾が、アメリカで先に製造されて吹き飛ぶのが東京になる、という考えは生まれていなかった。
しかし、肝心のウラン鉱石が入手できないことや、設備面など、仁科博士は当初より完成は無理だと予想していた。著者によると、逆に成功しなかったことで、日本の科学者たちは20世紀の原子物理学者としての良心を守ることが出来たということになる。それでは、何故、仁科博士があえて原爆製造の「ニ号研究」に若い研究者をつかせていたのだろうか。まず、何よりも、貴重な人材を、兵士として戦場に送り、戦死させたくなかったからとみるべきだろう。そして、戦時研究という名のもとに多くの予算がつき研究活動が行えたことや、戦争が終わった後に、海外の学者たちから遅れていないように科学者としてのプライドもあった。そして、ひそやかに平和目的には、大きなエネルギーを貯えることができて月への旅行が夢ではなくなると考えていた。軍部との交渉は、自分ひとりが矢面に立ち、若い研究者をまきこむことはいっさいなかったという。親方と慕われた仁科博士の門下生から巣立った湯川秀樹、朝永振一郎氏はノーベル賞を受賞して華やかな表舞台にはばたいていった。
本書は、保坂氏が昭和50年代に日本の原爆製造に関心をもって関わった軍人、科学者、技術将校のインタビューをまとめた「あの戦争から何を学ぶのか」という著書の一部をほりおこしてあらたに執筆された経緯をもつ。その動機は、昨年の3月11日の震災による。著者は「ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ」と並列で語られることにおおいなる疑問をもち、本質的に歴史的な意味合いが違うことを理解するために、この本を世におくったそうだ。日本は、20世紀前半に原子爆弾の製造に挑み、後半は平和利用として原子力発電にとりくんできた。本来は人類の叡智である科学も、政治や軍事に翻弄され、これ以上にない悪夢にもなりうることを充分に知っている。いつでも、科学的発見の果実の使い分けを司るのは、国家なのだろうか。インタビューを受けた殆どの方たちが、すでに物故者となっていることを考えると全体的に読みどころがいくつもあり、それ故に焦点が拡散している感もあるが、今のこの時に、本書を刊行した意義はある。
冒頭の「ラッセル=アインシュタイン宣言」の2年後の科学会議に出席した朝永振一郎は、どういう使い方をすれば悪になるか、また善用がどれだけ好ましいものであり、悪用がどれだけ破壊的なものであるかの正しい評価は科学者が行いえるものであり、科学者の任務は法則の発見に終わるのではなく、善悪の影響の評価、結論を人々に発信し、正しい判断までみとどけなければいけないと呼びかけている。ポツダム会談の時、日本にはもう戦う力がないことは、チャーチルもトルーマン、スターリンも充分にお互いに認識していた。それにも関わらず、原爆がヒロシマに投下された。日本の息の根をとめるというよりも、戦後社会の枠組みを作るため、戦勝国として優位にたつためのショーの舞台がヒロシマになった。そして、続いてナガサキへも。
8月7日の夜、調査団の一員として広島に向かう前日、仁科博士は門弟に手紙を書いて送っている。そこに書かれている「米英の研究者は日本の研究者、即ち理研の49号館の研究者に対して大勝利を得たのである。これは、結局に於いて、米英の研究者の人格が49号館の研究者の人格を凌駕してゐるといふことに尽きる」という言葉から科学者のどのような煩悶を受けとめるか、それは日本の未来を占うと私は考える。










 昔のコンサートや演奏者の音楽批評を読んでいると、よく”バリバリ演奏する”という表現に出会う。
昔のコンサートや演奏者の音楽批評を読んでいると、よく”バリバリ演奏する”という表現に出会う。 全世界で25億ドルを超える大ヒットとなった『スパイダーマン』から5年たち、新たな視点で描かれた『アメイジング スパイダーマン』が6月30日から世界に先駆けて公開されている。今年は、1962年にマーベル社から原作のコミックが登場して50年となる記念の年にあたる。7月3日封切りの全米だけですでに3500万ドル(約27億9000万円)の興行収入を、たたきだしていて、本年度の大ヒットを予感させてくれる。
全世界で25億ドルを超える大ヒットとなった『スパイダーマン』から5年たち、新たな視点で描かれた『アメイジング スパイダーマン』が6月30日から世界に先駆けて公開されている。今年は、1962年にマーベル社から原作のコミックが登場して50年となる記念の年にあたる。7月3日封切りの全米だけですでに3500万ドル(約27億9000万円)の興行収入を、たたきだしていて、本年度の大ヒットを予感させてくれる。 2011年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故は、遠く離れたドイツの原子力の歴史に終止符をうった。福島からはるか遠く、1万キロメートルの離れたドイツのエネルギー政策は大転換をしたのだった。ドイツ連邦議会は、2011年6月30日に原子力法の改正案を可決し、22年12月31日までに原子力発電所を完全に廃止することを決定した。ドイツのアンゲラ・メルケル首相はこれまで保守政党CDUの方針にそって原発推進派だったのに、事故からわずか3ヶ月目のこの”転向”に世界は驚いた。政治的な嗅覚に鋭く、変わり身の早さに定評がある首相にしても、この素早い寝返りには私にとっても印象に残るできごとだった。著者によると、メルケル首相はこの時の連邦議会で、政治家としても物理学者としても敗北を認める演説を行っているそうだ。
2011年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故は、遠く離れたドイツの原子力の歴史に終止符をうった。福島からはるか遠く、1万キロメートルの離れたドイツのエネルギー政策は大転換をしたのだった。ドイツ連邦議会は、2011年6月30日に原子力法の改正案を可決し、22年12月31日までに原子力発電所を完全に廃止することを決定した。ドイツのアンゲラ・メルケル首相はこれまで保守政党CDUの方針にそって原発推進派だったのに、事故からわずか3ヶ月目のこの”転向”に世界は驚いた。政治的な嗅覚に鋭く、変わり身の早さに定評がある首相にしても、この素早い寝返りには私にとっても印象に残るできごとだった。著者によると、メルケル首相はこの時の連邦議会で、政治家としても物理学者としても敗北を認める演説を行っているそうだ。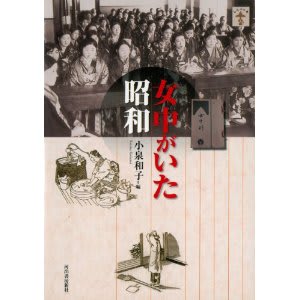 偉大なるオペラ作曲家、ジャコモ・プッチーニと聞いてもすぐにわからない方もいるだろう。しかし、映画『眺めのいい部屋』でも素晴らしく効果的に使用されていたのもプッチーニの「わたしのお父さん」だったように、有名なアリアは映画やCMに頻繁に登場するから、旋律にはなじみを覚える方も多いと思う。プッチーニほど、時代をこえて愛されるオペラをつくった作曲家はいないのではないだろうか。
偉大なるオペラ作曲家、ジャコモ・プッチーニと聞いてもすぐにわからない方もいるだろう。しかし、映画『眺めのいい部屋』でも素晴らしく効果的に使用されていたのもプッチーニの「わたしのお父さん」だったように、有名なアリアは映画やCMに頻繁に登場するから、旋律にはなじみを覚える方も多いと思う。プッチーニほど、時代をこえて愛されるオペラをつくった作曲家はいないのではないだろうか。 本日のコンサートは、開演前にプレトークありか・・・。
本日のコンサートは、開演前にプレトークありか・・・。 名画再発見!の日本映画編。
名画再発見!の日本映画編。