 我が偏愛なるヴァイオリニストのマキシム・ヴェンゲーロフがやってくる。又、今年もやってくる!
我が偏愛なるヴァイオリニストのマキシム・ヴェンゲーロフがやってくる。又、今年もやってくる!前回おそるおそる聴いた時は、肩の故障から彼は完全に復活していた。(我が偏向的なブログを検索したが、記念すべきコンサートにも関わらずきちんと更新していなかった。残念)会場全体が、彼の復活を心から喜ぶ雰囲気に包まれていたのが嬉しい。しかしながら、汗をかくようような名演奏が気のせいか、ブランクを一気に縮めるかのように疾走気味で、少々慌しく感じて素敵な余韻がなかった記憶がある。
さて、今年の5月のヴェンゲーロフ・フェスティバル。東京での会場は、おなじみのサントリーホール。あいまに葉加瀬太郎さんとのジョイント・コンサートの突然の企画にはおろろいたが、主催者側の都合でどういうわけか中止となってしまったらしい。そんな情報をネットで気がついてしまったからのこの日までの数日間。まさか、もしや、という心配でいっぱいだった。握手会の最中にA×Bのメンバー約2名がファンからノコギリで襲れちゃったという事件が発生して、今後はもう握手会が開催されないかもしれないと本気で心配する30歳後半のファン心理とそれほど変わらないかもしれない。予定どおりの時刻に、サントリーホールの会場が華やかに客を迎え入れた時は、心底ほっとした。
ところで、今日のフェスティバルは、ポーランド室内管弦楽団の指揮者もかねている。(指揮者のギャラ分を節約しているためか、それほどまでは高くないチケットのお値段を、妙に納得した)前半のモーツァルトは、まさしくモーツァルトらしく、モーツァルトだった。美しい音はかわらず、優雅で、気品もあり、それでいてちょっとしたチャーミングな遊び心を感じさせる。才能と自信と貫禄がつけば、優れたヴァイオリニストはこんな演奏ができるのか。そうではない。レーピンや五嶋みどりさんとは違う個性の音楽家だから、マキシム・ヴェンゲーロフだからこんな美しくも魅力的なモーツァルトが生まれ変わったかのような演奏ができるのだ。モーツァルトを演奏するにあたり、誰がベストかというのではなく、それがまぎれもなく彼の個性なのである。
後半は当初の予定からプログラムに変更があり、マスネの「タイースの瞑想曲」がチャイコフスキーの「メロディ」と「瞑想曲」へ。たまたま職場の女性に、最近、彼女のイメージから「タイースの瞑想曲」をお薦めしていたこともあり、少々がっかりしたのだが、このプログラムの構成はツボをついていた。彼が、旧ソ連出身だったということを思い出させるような憂愁なメロディーをバランスのよい歌心で奏で、特に「憂鬱なセレナーデ」の演奏後に、聴衆の一部の拍手をすかさず制したかと思うと、流れるように続けて「懐かしい土地の思い出」の演奏をはじめた。とても贅沢なプログラムとなった。ただひとつ、惜しいかな、ポーランド室内管弦楽団の演奏がさえなかった。マキシム・ヴェンゲーロフのテクニックも音楽性があまりにも素晴らしいため、逆に伴奏の貧弱さがめだってしまった。
余談だが、”魔弓”と伝えられる彼の右手の薬指にきらりと光る指輪。彼は一昨年、ロシア出身のヴァイオリニストのイリア・グリンゴルツのお姉さまと結婚していた。しかも、あっというまに2児のオヤジになっていたのだった!現在、イスラエルでも英国でもなくモナコ在住。ま、それは兎も角、今年で40代を迎えるのだが、円く熟すよりも益々演奏が若々しくなっていると感じてもいる。
------------------------------- 5月26日 サントリーホール ---------------------------------
Maxim Vengerov with ポーランド室内管弦楽団 ヴェンゲーロフ・フェスティバル 2014
モーツァルト:
・ヴァイオリン協奏曲第3番
・ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」
チャイコフスキー:
・憂鬱なセレナード作品26
・「懐かしい土地の思い出」~スケルツォ作品42-2
・「懐かしい土地の思い出」~メロディ作品42-3
・「懐かしい土地の思い出」~瞑想曲作品42-1
・ワルツ・スケルツォ作品34
サン=サーンス:
・ハバネラ作品83
・序奏とロンド・カプリチオーソ作品28
■アンコール
・ブラームス:ハンガリー舞曲第1番










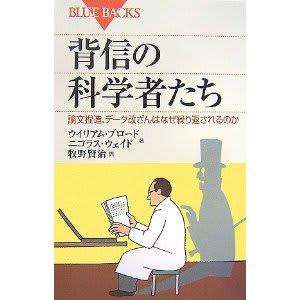 1981年、下院議員の若きアルバート・ゴア・ジュニアは、深い怒りをこめて「この種の問題が絶えないひとつの原因は、科学界において指導的地位にある人々が、これらの問題を深刻に受け止めない態度にある。」とざわめく法廷を制した。通称、
1981年、下院議員の若きアルバート・ゴア・ジュニアは、深い怒りをこめて「この種の問題が絶えないひとつの原因は、科学界において指導的地位にある人々が、これらの問題を深刻に受け止めない態度にある。」とざわめく法廷を制した。通称、 4月16日、 理研の笹井芳樹副センター長によるstap細胞の論文問題に関する会見を見た小保方さんは、尊敬する笹井さんにご迷惑をかけたと泣いたそうだ。男だったら泣くか、それをご丁寧に発信する有能な弁護集団の世間の同情を誘うかのような意図もしらじらしいのだが、なんだかお2人が水面下で結託して、山梨大学の若山照彦教授に微妙に罪をなすりつけようとしているのを感じたのは、私だけではなかったのではないだろうか。
4月16日、 理研の笹井芳樹副センター長によるstap細胞の論文問題に関する会見を見た小保方さんは、尊敬する笹井さんにご迷惑をかけたと泣いたそうだ。男だったら泣くか、それをご丁寧に発信する有能な弁護集団の世間の同情を誘うかのような意図もしらじらしいのだが、なんだかお2人が水面下で結託して、山梨大学の若山照彦教授に微妙に罪をなすりつけようとしているのを感じたのは、私だけではなかったのではないだろうか。 近頃、諸般の事情から更新が滞りがちなる我がブログ。
近頃、諸般の事情から更新が滞りがちなる我がブログ。 野球に例えたら、打率は何割になるのであろうか。私にとっては、5割を超える打率で快調にヒットを飛ばしている、いやルーキーの時から飛ばし続けているのが福岡ハカセのエッセイである。本1冊単位ではなく短いエッセイものの1本1本を、その内容の充実度とレベルの高さで測ると、ページをめくる度に、心が躍り、清冽に目を開かれる。某ノーベル賞候補作家の新作が出版される度に、特別に駅の構内で店員さんが声をはりあげて宣伝して売っているイベントを横目に、新作を切望して待っている作家のひとりが福岡ハカセである。
野球に例えたら、打率は何割になるのであろうか。私にとっては、5割を超える打率で快調にヒットを飛ばしている、いやルーキーの時から飛ばし続けているのが福岡ハカセのエッセイである。本1冊単位ではなく短いエッセイものの1本1本を、その内容の充実度とレベルの高さで測ると、ページをめくる度に、心が躍り、清冽に目を開かれる。某ノーベル賞候補作家の新作が出版される度に、特別に駅の構内で店員さんが声をはりあげて宣伝して売っているイベントを横目に、新作を切望して待っている作家のひとりが福岡ハカセである。