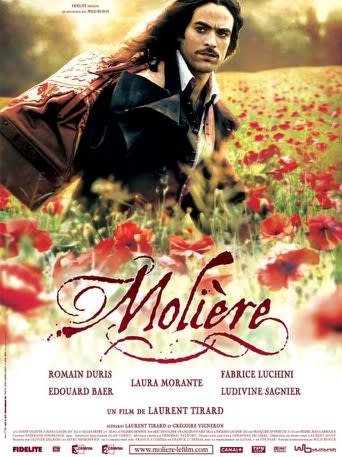 フランス人の180万人もの動員して観客満足度96%!
フランス人の180万人もの動員して観客満足度96%!この本国では大ヒットしたが、日本ではプチ不発に終わったのがコメディの恋愛映画『モリエール、恋こそ喜劇』である。フランス人と日本人の笑いのセンスは、多少違うのか?
ところで、フランスが誇る17世紀の劇作家のモリエールの本名は、ジャン=バティスト・ポクラン(Jean-Baptiste Poquelin)。フランス人にとっては、本名の方もよく知られているのだろうが、日本人にはあまりなじみのない長い名前は劇中にもしばしば登場して、慣れるまで多少の時間を要した。それは兎も角、かのモリエールは若かりし頃に旗揚げした劇団が経営難に陥って、破産宣告を受けて投獄をされている。まだ無名の22歳の時、再び破産で投獄されたモリエールは、釈放された後、数ヶ月間、忽然と姿を消していたという。どの伝記にも空白のこの期間、彼はいったいどこで何をしていたのだろうか。
こんな数ヶ月間の隙間から創造されたニッチな隙間産業のような本作は、なるほどとびきりお茶目なコメディ映画に仕上がっている。喜劇が得意だったモリエールに負けず劣らず、現代の映画監督や脚本家のセリフや構成はセンスも抜群でうまい!
モリエール(ロマン・デュリス)は、借金返済の肩代わりに、とある資産家の商人ジョールダン氏(ファブリス・ルキーニ)が社交界に君臨する生意気なセリメーヌ(リュディヴィーヌ・サニエ)に取り入るために身分を隠して働く役割を引き受けることになってしまったのだった。しぶしぶ手入れの行き届いた美しい館についていくモリエールを迎えたのは、おまぬけなジョールダン氏にもったいないくらいの賢夫人のエルミール(ラウラ・モランテ)。熟女マダムの知性と賢さ、美貌にいつしかひかれていくモリエールだったのだが。。。
とってもとってもお金持ちなのだが貴族という身分にコンプレックスをもち、しかも身の程知らずにもなんとか若い娘のセリメーヌにお近づきになろうと涙ぐましい策を弄するジョールダンを演じた俳優は、そこに立っているだけで体型も含めて日本の中年オジサンとそっくり同じで笑える。オジサンの生態と行動は、古今東西あい変らずか。浮気を必死に画策しながら実は詐欺師にだまされている”お人よし”というキャラが、喜劇を倍増して憎めない。そういえば、cocueというフランス語もあった。必死で他の女性にとりいろうと無駄な努力をしている一方で、妻を若い男性に寝取られてしまうのだが、にくめないお人よしのキャラがモリエールを凌駕していると思う。このおっさんこそ、最高の主人公だ。さりげない性的なユーモアも、わかる人にはわかるところがフランス風。
ところで、せっかく練られた脚本も、我が国内ではいまひとつ不発だったのは、やはりモリエールの作品が日本人にはそれほど周知されていないからではないだろうか。せめてモリエールの戯曲「町人貴族」や「人間ぎらい」のベースがあれば、もっと映画の中のウィットやひねられたユーモアを楽しめたのに、と思うとちと惜しい気がする。それはさておき、英国にはシェークスピアがいたが、フランスにはモリエールがいた!
監督:ロラン・ティアール
2007年フランス製作










 「父さんの手紙はぜんぶおぼえた」
「父さんの手紙はぜんぶおぼえた」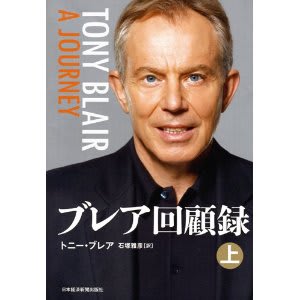 1997年5月から2007年6月まで英国の首相を務めたトニー・ブレアの回顧録の原文は、「A Journey 」である。
1997年5月から2007年6月まで英国の首相を務めたトニー・ブレアの回顧録の原文は、「A Journey 」である。 シュトゥットガルト国立音楽大学およびザルツブルク・ モーツアルテウム国立音楽大学修士課程首席卒業。
シュトゥットガルト国立音楽大学およびザルツブルク・ モーツアルテウム国立音楽大学修士課程首席卒業。  小澤征爾さんと村上春樹さん。
小澤征爾さんと村上春樹さん。 現代音楽を担う素晴らしいピアニスト、ピエール=ロラン・エマールが、あのバッハ晩年の未完の傑作「フーガの技法」を録音した!これは、クラシック音楽界としてはちょっとした事件にも近い。
現代音楽を担う素晴らしいピアニスト、ピエール=ロラン・エマールが、あのバッハ晩年の未完の傑作「フーガの技法」を録音した!これは、クラシック音楽界としてはちょっとした事件にも近い。