憲法学者であり、法哲学者でもある東大名誉教授の小林直樹氏が亡くなった。
15年ほど前、Y新聞の書評にすっかり惚れ込んで読んだ小林氏の「法の人間学的考察」を思い出した。内容は忘却の彼方に消えてしまったが、確かにこの本に深く深く入り込んで“熟読”したことは、私の中に宝として静かに残っていると思う。
そんなわけで、以下当時のブログを再現。
訃報から検索して初めて拝んだ小林氏の在りし日の肖像は、元級友の伝えるとおり端正を絵に描いたようだった。
〈2005年7月26日〉弊ブログより
明日がいよいよ最後の検察審査会。この半年間の事件や事故の概要が走馬灯のようにめぐってくる。
前群の方達が任務をおえた日の、感慨深そうな、達成感に満ちて、それでいてちょっと寂しそうな表情を思い出す。当事者、被害者の方やご遺族の感情を考えると、感慨深いと自己満足におちてはいけないと戒めたりもするのだが。
或る日突然舞い込んだ、候補者に選ばれたという連絡。それからまもなく、さらに候補者に入り、ついに招集状がやってきた。その時から、最後の日はこの本の話をしたいと決めていた。一昨年の8月、読売新聞の1本の書評が目にとまった。その「法の人間学的考察」 という本の短い書評を読み終えた後、深い感動をおぼえ、地元の公立図書館にリクエストして、早速お買い上げいただいた。その本との出会いが、まるでこの仕事を導いたような不思議な気持ちがした。
この著書に関しては、あまりにも書評が素晴らしいので、私は何も感想を書かないでおこう。ただ、書評どおりの壮大な「知の饗宴」に圧倒され、感動させられ、「法」の哲学につかまったということだ。
昨年高校の同窓会の席で、W大学法学部に進学した(元?)男子と、著者の小林直樹さんの話題があがった。彼はさすがに小林氏の名前を知っていた。教わったことはないらしいが。。。
高名な法学者であること。顔立ちも整い、スタイルもよく、運動神経もよくてテニスも上手であること。あの時代は、そういう育ちのよい人がいた時代だ。
この言葉は、鮮烈だった。
評者・橋本五郎さんの書評↓
■「法の人間学的考察」 小林 直樹著------------------------------------------------
壮大な「知の饗宴」
拝啓 小林直樹様
今回のご著書に心から敬意を表したくペンをとりました。書名から、和辻哲郎の『人間の学としての倫理学』や尾高朝雄の『法の窮極に在るもの』を意識されているとは推測していましたが、スケールの壮大さに圧倒されました。
哲学や倫理学、歴史学、政治学だけでなく、物理学や生物学、天文学などの学問成果も駆使し、法の根底にあるものを導き出そうとされています。さながら「知の饗宴(きょうえん)」の趣があり、失礼ながら、まもなく82歳になる方の著作とは思われない若々しさに満ちています。
法について、存在論、時間論、空間論、価値論、構造論、機能論、文明論などあらゆる角度から先人の業績を洗い直しておられます。その幅の広さに加え、最も心打たれたのは「なぜ法なのか」「なぜ人は正義を求めるのか」「なぜ人間だけが尊厳を主張できるのか」というように、根源的な問いを発しながら、すべてに自説を披瀝(ひれき)されていることです。
歴史とは何か。「理性と反理性とが糾(あざな)える縄のごとく、正負・明暗の彩りをなして織りあげてきたものと見るのが、正確な認識に近い」
死刑廃止論をどう考えるか。「法には正義の理念を実現すべき使命があり、正義の原則に従い、“問うべき責任を問う”結果として、死刑を科するのは、まさに『人間を人間らしく扱う』ゆえんではないだろうか」
一つ一つ説得力をもって響きました。法には「当為の規範」としての性格と、強制力で当為を実現する「力のシステム」の両面があるが、その根底には矛盾に満ちた人間存在があると繰り返し説いておられます。そして天使と悪魔の「中間的な存在」である人間を常に複眼的に見つめ、立体的に全体として捉(とら)えて法を考え、行う必要を力説しておられますが、とても充実した気持ちで読み終えました。心から感謝し、ますますのご活躍をお祈り致します。 敬具
評者・橋本五郎(読売新聞本社編集委員) / 読売新聞 2003.08.31 -------------------------------
さすがに”種蒔く人”岩波である。売れる本より、知の財産になるような本を出版している。12000円は、決して高くない。電車の中で立ち読むするには、ちょっと腕が疲れるが、「ハリーポッター」よりずっとはらはらする。
橋本五郎氏は、インテリジェンスなお仕事をしているにもかかわらず?、その笑顔は2代めの商売人に見える方である。そしてともすれば、知性というシックな表彰に陥りがちな新聞書評から、いつも人の機微がさりげなくのぞく名編集委員である。文章、は人を語るのである
15年ほど前、Y新聞の書評にすっかり惚れ込んで読んだ小林氏の「法の人間学的考察」を思い出した。内容は忘却の彼方に消えてしまったが、確かにこの本に深く深く入り込んで“熟読”したことは、私の中に宝として静かに残っていると思う。
そんなわけで、以下当時のブログを再現。
訃報から検索して初めて拝んだ小林氏の在りし日の肖像は、元級友の伝えるとおり端正を絵に描いたようだった。
〈2005年7月26日〉弊ブログより
明日がいよいよ最後の検察審査会。この半年間の事件や事故の概要が走馬灯のようにめぐってくる。
前群の方達が任務をおえた日の、感慨深そうな、達成感に満ちて、それでいてちょっと寂しそうな表情を思い出す。当事者、被害者の方やご遺族の感情を考えると、感慨深いと自己満足におちてはいけないと戒めたりもするのだが。
或る日突然舞い込んだ、候補者に選ばれたという連絡。それからまもなく、さらに候補者に入り、ついに招集状がやってきた。その時から、最後の日はこの本の話をしたいと決めていた。一昨年の8月、読売新聞の1本の書評が目にとまった。その「法の人間学的考察」 という本の短い書評を読み終えた後、深い感動をおぼえ、地元の公立図書館にリクエストして、早速お買い上げいただいた。その本との出会いが、まるでこの仕事を導いたような不思議な気持ちがした。
この著書に関しては、あまりにも書評が素晴らしいので、私は何も感想を書かないでおこう。ただ、書評どおりの壮大な「知の饗宴」に圧倒され、感動させられ、「法」の哲学につかまったということだ。

昨年高校の同窓会の席で、W大学法学部に進学した(元?)男子と、著者の小林直樹さんの話題があがった。彼はさすがに小林氏の名前を知っていた。教わったことはないらしいが。。。
高名な法学者であること。顔立ちも整い、スタイルもよく、運動神経もよくてテニスも上手であること。あの時代は、そういう育ちのよい人がいた時代だ。
この言葉は、鮮烈だった。
評者・橋本五郎さんの書評↓
■「法の人間学的考察」 小林 直樹著------------------------------------------------
壮大な「知の饗宴」
拝啓 小林直樹様
今回のご著書に心から敬意を表したくペンをとりました。書名から、和辻哲郎の『人間の学としての倫理学』や尾高朝雄の『法の窮極に在るもの』を意識されているとは推測していましたが、スケールの壮大さに圧倒されました。
哲学や倫理学、歴史学、政治学だけでなく、物理学や生物学、天文学などの学問成果も駆使し、法の根底にあるものを導き出そうとされています。さながら「知の饗宴(きょうえん)」の趣があり、失礼ながら、まもなく82歳になる方の著作とは思われない若々しさに満ちています。
法について、存在論、時間論、空間論、価値論、構造論、機能論、文明論などあらゆる角度から先人の業績を洗い直しておられます。その幅の広さに加え、最も心打たれたのは「なぜ法なのか」「なぜ人は正義を求めるのか」「なぜ人間だけが尊厳を主張できるのか」というように、根源的な問いを発しながら、すべてに自説を披瀝(ひれき)されていることです。
歴史とは何か。「理性と反理性とが糾(あざな)える縄のごとく、正負・明暗の彩りをなして織りあげてきたものと見るのが、正確な認識に近い」
死刑廃止論をどう考えるか。「法には正義の理念を実現すべき使命があり、正義の原則に従い、“問うべき責任を問う”結果として、死刑を科するのは、まさに『人間を人間らしく扱う』ゆえんではないだろうか」
一つ一つ説得力をもって響きました。法には「当為の規範」としての性格と、強制力で当為を実現する「力のシステム」の両面があるが、その根底には矛盾に満ちた人間存在があると繰り返し説いておられます。そして天使と悪魔の「中間的な存在」である人間を常に複眼的に見つめ、立体的に全体として捉(とら)えて法を考え、行う必要を力説しておられますが、とても充実した気持ちで読み終えました。心から感謝し、ますますのご活躍をお祈り致します。 敬具
評者・橋本五郎(読売新聞本社編集委員) / 読売新聞 2003.08.31 -------------------------------
さすがに”種蒔く人”岩波である。売れる本より、知の財産になるような本を出版している。12000円は、決して高くない。電車の中で立ち読むするには、ちょっと腕が疲れるが、「ハリーポッター」よりずっとはらはらする。
橋本五郎氏は、インテリジェンスなお仕事をしているにもかかわらず?、その笑顔は2代めの商売人に見える方である。そしてともすれば、知性というシックな表彰に陥りがちな新聞書評から、いつも人の機微がさりげなくのぞく名編集委員である。文章、は人を語るのである










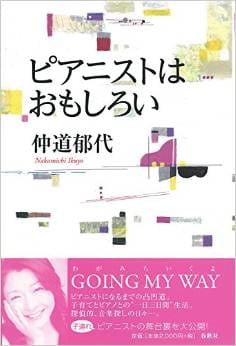 「なかみちいくよだが、まだまだ、わがみちいくよには到達できない」
「なかみちいくよだが、まだまだ、わがみちいくよには到達できない」 いよっっ、名人芸!
いよっっ、名人芸! こんな名人芸の音楽家目、管楽器科、木管楽器属、オーボエ種のもぎぎさんの余技と対照的なのが、同じ音楽家にくくられるが、指揮者の矢崎彦太郎さんの「指揮者かたぎ」である。率直に一言、矢崎さんの文章はうまい。知性的でありながら、詩人のような静かな情感もあり、余韻が残る文章である。矢崎さんのお父様は、本の編集者で鎌倉で育った。思い出の中に、父親の知り合いとして川端康成や、やはり鎌倉在住の往年の女優との思い出が登場する。
こんな名人芸の音楽家目、管楽器科、木管楽器属、オーボエ種のもぎぎさんの余技と対照的なのが、同じ音楽家にくくられるが、指揮者の矢崎彦太郎さんの「指揮者かたぎ」である。率直に一言、矢崎さんの文章はうまい。知性的でありながら、詩人のような静かな情感もあり、余韻が残る文章である。矢崎さんのお父様は、本の編集者で鎌倉で育った。思い出の中に、父親の知り合いとして川端康成や、やはり鎌倉在住の往年の女優との思い出が登場する。 近頃、諸般の事情から更新が滞りがちなる我がブログ。
近頃、諸般の事情から更新が滞りがちなる我がブログ。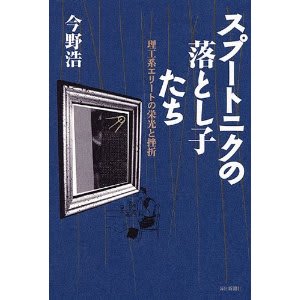 1957年10月、世界初の人工衛星「スプートニク1号」が打ち上げられた。
1957年10月、世界初の人工衛星「スプートニク1号」が打ち上げられた。 その昔、、、大学サークルの一室で先輩たちの角栄論議に耳を傾けていた。
その昔、、、大学サークルの一室で先輩たちの角栄論議に耳を傾けていた。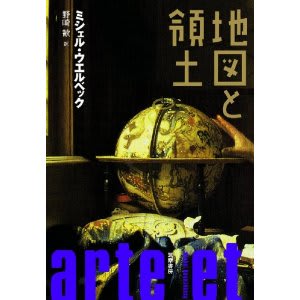 ジェドは、1976年生まれの美術家。
ジェドは、1976年生まれの美術家。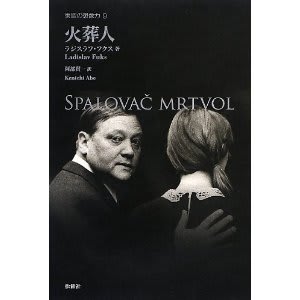 何かを警戒しているかのように、後ろを振り返りながら、髪の長い娘の背中をそっと押す紳士。
何かを警戒しているかのように、後ろを振り返りながら、髪の長い娘の背中をそっと押す紳士。 1999年10月5日、アップルの新製品発表会でのことだった。
1999年10月5日、アップルの新製品発表会でのことだった。 古くは文豪ゲーテ、新しきは経済学者マルクスや哲学者ニーチェ、ビスマルク首相まで真剣で決闘をしていた!
古くは文豪ゲーテ、新しきは経済学者マルクスや哲学者ニーチェ、ビスマルク首相まで真剣で決闘をしていた!