 世界最高峰のオーケストラのひとつであるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の次期音楽監督が決まった。
世界最高峰のオーケストラのひとつであるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の次期音楽監督が決まった。音楽ファンにとっては一大事件の人事であるが、その栄誉あるポジションを獲得したのは、若いバイエルン州立歌劇場音楽総監督でロシア出身のキリル・ペトレンコ氏。予想外の結果に少し拍子抜けを感じたのは、私だけだろうか。
この感覚は、私の中では大本命だったできる李克強を超えて、ただの太子党のひとりだった習近平が2013年に中国の国家主席に選任された意外感を思い起こした。けれども、私の意外感が、そもそも中国や権力闘争や”力”に縁のない者の浅い感想だったことを知らせてくれたのが本書だ。朝日新聞の気鋭のシャーナリストが、ペンでなく足と汗でたどりついた、たった1回、日本人指揮者がベルリン・フィルを振る舞台にたっただけで大騒ぎしてくれる日本のマスコミには想像もつかないような、権力闘争の果てに13億分の1の中国皇帝になった男と、その闘争が描かれている。
愛人たちが暮らす村でのカーチェース、ハーバードに留学している習近平の一人娘の姿を卒業式でとらえ、といった出だしこそ、テレビの企画ものとさして変わらない印象であるが、後半になっていくとすさまじい中国の権力闘争に第一級のクライムサスペンスを見ているような勢いとおそろしさがある。
エリート中のエリートのオーラを放っていた李克強を追い落とし浮上したのも、長い長い院政で胡錦濤を支配して縛り付けてきた老獪な江沢民の壮絶な権力闘争の妥協の産物だったのだろうか。それも確かにある。しかし、国務院副総裁まで勤めた父の習仲勲が、文化大革命中に失脚し16年間も獄中で迫害され、自身も16歳であまりにも貧しい寒村の下放されて洞窟暮らし。辛苦をなめながらも村人たちと交流し、その後清華大学に進学し、指導者になるには軍人の関係も必要と教わり、人民解放軍専属に人気歌手と見合い結婚。
一方、李克強は北京大学時代から優等生ぶりを発揮し、猛勉強で常にトップ、留学を夢見て英語の辞書を手離さなかった彼が、最難関校の切符を手にした頃に、共青団の幹部に1万人をまとめられるのはあなただけとくどかれれて、迷った末に政治家となった。その後、次々と最年少で昇格し、胡錦濤とは兄弟のような関係だった。1997年の党大会では、李克強が中央委員会の候補となっていたにも関わらず、習近平は、151人の最下位の候補者だったという。
しかし、遅れてきたダークホースにもならなかった習近平が頂点にたったのも、虎視眈々と用意周到に地盤を固めていったこともあるが、やはりそれもすさまじき権力闘争が”妥協ではなく”、生まれるべくして生まれた第7代国家主席だったことが、本書から伝わってくる。市民、政界、権力者に近づいて生々しい中国ルポをものにした著者の「現場主義」には、私はやはり敬意を表したいと思う。
「李克強が優秀なのは確かだが、同じくらい頭脳明晰な党員は、我が党にはいくらでもいる。そのたくさんの優秀な党員をまとめる”団結力”が最高指導者にとって重要。」という党関係者の見方は、説得力がある。しかし、それにしてもこんな中国と中国人を相手にする日本の総理大臣のひ弱さと自己中心的な幼さには不安と情けなさを感じる。
さて、ベルリンフィルの音楽監督の選任は、実は5月に開催された123人の選挙資格を有する団員による選挙と長い議論では結果がでなかった。ドイツ出身のクリスティアン・ティーレマン、バイエルン放送交響楽団首席指揮者を務めるマリス・ヤンソンス、若手のアンドリス・ネルソンス、まさかのベネズエラ出身のグスターボ・ドゥダメルといった名だたる候補者が浮上したが、年齢、保守的、他の楽団との契約等、さまざまな理由や事情から決定打がなかったそうだ。政治には、時の女神もいるのかも。










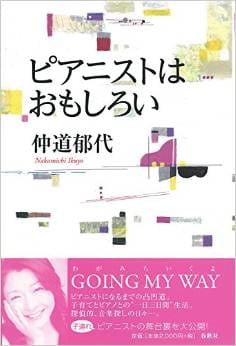 「なかみちいくよだが、まだまだ、わがみちいくよには到達できない」
「なかみちいくよだが、まだまだ、わがみちいくよには到達できない」