ノーベル賞の選考委員会は3人の受賞理由について、「3人の発明は革命的で、20世紀は白熱電球の時代だったが、21世紀はLEDによって照らされる時代になった。誰もが失敗してきたなか、3人は成功した。世界の消費電力のおよそ4分の1が照明に使われるなか、LEDは地球環境の保護にも貢献している。LEDは電力の供給を受けにくい環境にある世界の15億人の生活の質を高める大きな可能性を秘めている」とコメントしています。
さて、こんなビッグニュースが飛びこんだけれど、ほぼ10年前の我が拙いブログから再掲載。
*****************
2005年1月11日 「スレイブ中村さんは勝ったのか」 ********************************************
本日、一番ホットな話題はこれでしょう。
<青色発光ダイオード>和解成立 日亜化学が中村修二さんに8億4000万円の支払い
発明の対価はその発明者か、給料をあげて生活の保障と研究の場を与えた企業にあるのか、さまざまな議論をよび、また次々と報われなかった発明者の訴訟を起こすきっかけとなった裁判が今日決着した。
【中村さんのコメント】和解額には全く納得していないが、弁護士の助言に従って勧告を受け入れることにした。問題のバトンを後続のランナーに引き継ぎ、本来の研究開発の世界に戻る
【日亜化学】当社の主張をほぼ裁判所に理解して頂けた。特に青色LED発明が1人ではなく、多くの人々の努力・工夫の賜物(たまもの)とご理解頂けた点は大きな成果と考える
中村さんにとっては、和解金額としては当初の200億円を大きく下回るということを正当な評価と受け入れにくく納得はしていない。しかし、そもそもは売られたケンカで自身の発明まで封じ込めようとした日亜化学の行為に端をなしたわけで、和解を受け入れて今後は研究活動に専念したいというのはもっともだろう。
ひるがえって日亜化学は、発明が多くの人々の努力の成果という理解が判決に反映されたといっているがどうであろうか。東京高裁の指摘は、日亜化学の経営を考慮した日本的な財界人たちもほっと胸をなでおろせるラインにソフトランディングしたという見方もできるのではないか。
【弁護側】当初の2万円のご褒美からすると国内史上の最高額を支払われることから成功した
弁護士としては、中村さんの胸中はともかくとして、これだけの話題性充分、金額も大きい訴訟でこのような結果に至ったことは充分成果があったと満足できるだろう。知名度もあがり、知的所有権を争う訴訟依頼も増えるかもしれない。もしかしたら一番の勝利者は行列ができるかもしれない弁護軍団だったのだろうか。
ノーベル賞に近い研究者と言われる中村修二さんの発明した青色発光ダイオードが、半永久的な光源をもたらすということで画期的で莫大な利益をもたらすことは事実。
そして大企業の優秀なチームが見向きもしなかった別の方法で、たった一人で、会社の行事も欠席し、変人扱いされ、装置から手作りして生み出したブレイクスルー。それは報奨金のあつさだけでは量れない素晴らしい研究の成果である。
【北城恪太郎経済同友会代表幹事】発明対価は、企業と従業員の間の合理性を持った事前の合意によって決められるべきだ
今後は企業も研究者との事前のお約束は必要だ。まるで結婚するときに離婚したときの条件をかわすハリウッドのように。
**********************
2005年1月13日「続報:スレイブ中村さん怒る」**************************************************
~日々是好日~の管理人さまより
>当初の報奨金である「社長賞」が2万円。これはいかがなものでしょう
と私のコメントへの上記のレスがついていたが。「社長賞」2万円。まさにスレイブな金額だ。
日亜化学というところは、今でこそ全国区の仲間入りをしているが、元々の出自は四国の田舎の中小企業。それに当時の日本社会においては、ソニーなどの一流企業でも、社員の優れた発明に対する報奨金はアッパー100万円程度だったような記憶がある。今回の訴訟で慌てて報奨金制度を見直しして金額をひきあげた企業も多いが、日本的な企業と従業員の関係は欧米諸国ほどスマートととはいえない。
それに、そもそも熱心で集中力はあるが、変人で扱いにくい社員が掘り起こした成果がノーベル賞に近くとてつもない金鉱だったと、理解できる役員もいなかったのではないか。
江崎玲於奈さんのお話しであったが、たとえば米国というのは、優れた成果をだしたとしても、乗ったタクシーの運転手よりもお客の研究者の報酬が低かったら運転手よりも評価されない社会だと。
これは、大リーグの野球選手の契約金と実力が比例するという簡単な図式をあてはめるとわかりやすい。それもどうなのかと、清貧を尊しとする日本人には疑問に感じる部分もあるが、(実際、選手への高額な年棒のために経営難になった野球チームもあるから)かの国でそういう感性が肌にあった中村修二さんにとっては、本来あるべき社会と映るのも納得する。
「実力にある研究者はアメリカへ来い!」
自分に自信があり、野望と大志を抱く若者は太平洋を渡れ、、、と私も応援したい。
それにしても中村さん、全くの無名のいち社員時代から、言いたいことを言い、やりたいことをやり、スレイブナカムラと揶揄されても魂までは決してスレイブではなかった!
*******************************************************************************************************
この間、アメリカに飛び立った中村さんは国籍も米国となっていたのは、ちょっとした衝撃だった。理由として、米国籍でないと軍から予算がおりないからとのこの方にとってはごく当たり前のことだった。
「技術立国日本」
こんな某首相の聞こえだけのよい音頭が聞こえてくるが、その掛け声の虚しさを背中に、研究者たちは活躍の場を海外に求めていくのだろうか。
・・・とりあえず、おめでとう中村さん。
■番外の小話
・
クラシックを聴く人は紅茶党
 世界最高峰のオーケストラのひとつであるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の次期音楽監督が決まった。
世界最高峰のオーケストラのひとつであるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の次期音楽監督が決まった。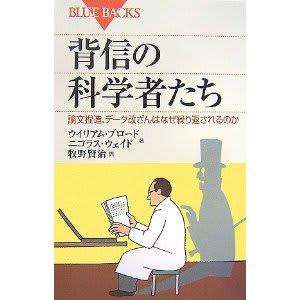 1981年、下院議員の若きアルバート・ゴア・ジュニアは、深い怒りをこめて「この種の問題が絶えないひとつの原因は、科学界において指導的地位にある人々が、これらの問題を深刻に受け止めない態度にある。」とざわめく法廷を制した。通称、ジョン・ロング事件でのできことだった。 論文の盗用、データーの捏造、改ざんをしていたのは、あのOさんだけではなかった。
1981年、下院議員の若きアルバート・ゴア・ジュニアは、深い怒りをこめて「この種の問題が絶えないひとつの原因は、科学界において指導的地位にある人々が、これらの問題を深刻に受け止めない態度にある。」とざわめく法廷を制した。通称、ジョン・ロング事件でのできことだった。 論文の盗用、データーの捏造、改ざんをしていたのは、あのOさんだけではなかった。 先日、来日したマイケル・サンデル教授の「ハーバード白熱教室」が、9月26日(日)22時より「ハーバード白熱教室@東京大学」として放映されるそうだ。
先日、来日したマイケル・サンデル教授の「ハーバード白熱教室」が、9月26日(日)22時より「ハーバード白熱教室@東京大学」として放映されるそうだ。 自分探しの旅、そんな旅があるようだが、女性がパリに短期留学するのといったいどこが違うのだろうか。
自分探しの旅、そんな旅があるようだが、女性がパリに短期留学するのといったいどこが違うのだろうか。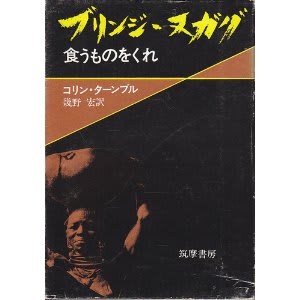 人類学の目的のひとつは、社会組織の基本的な原理を発見すること。
人類学の目的のひとつは、社会組織の基本的な原理を発見すること。 お金をおろすのに、電車賃代を節約して5駅先の銀行まで自転車で30分かけて行く。真冬でもYシャツ1枚で、猛烈に働き、内緒話を廊下中に聞こえるような大声で話す。新調160センチ程度だが、体重は70キロの男性。こんな男が結婚したいと見合いを繰り返しているうちに、勿論、断れまくり、解くのが難解な「NP困難」とまで言われるようになった。
お金をおろすのに、電車賃代を節約して5駅先の銀行まで自転車で30分かけて行く。真冬でもYシャツ1枚で、猛烈に働き、内緒話を廊下中に聞こえるような大声で話す。新調160センチ程度だが、体重は70キロの男性。こんな男が結婚したいと見合いを繰り返しているうちに、勿論、断れまくり、解くのが難解な「NP困難」とまで言われるようになった。 今年の夏も猛暑、酷暑でただ生きて呼吸をしているだけのような日々だった。(不思議と、食欲だけは衰えないのがせめてもの救い?)この炎天下、チェロをかついでいる人、ヴァイオリンを背負っている方をみかけると、本気で行き倒れにならないかと余計な心配をしてしまう。こんな光景にいつも思うのは、ピアニストは楽器を持たなくてすむから荷物が少なくて、なんて身軽なのだろう、、、ということだ。地方のホールに行っても、スタインウエイさまがお待ちしているではないか。
今年の夏も猛暑、酷暑でただ生きて呼吸をしているだけのような日々だった。(不思議と、食欲だけは衰えないのがせめてもの救い?)この炎天下、チェロをかついでいる人、ヴァイオリンを背負っている方をみかけると、本気で行き倒れにならないかと余計な心配をしてしまう。こんな光景にいつも思うのは、ピアニストは楽器を持たなくてすむから荷物が少なくて、なんて身軽なのだろう、、、ということだ。地方のホールに行っても、スタインウエイさまがお待ちしているではないか。 にわかには信じがたい某楽器商により行状が次々と暴かれていて、まさに悪代官による弱いものいじめの構図なのだが、結局、芸術系は良い仕事をする人が残っていき人々に感謝されるものだと思う。実際、高木さんは運命の女神が微笑むような幸運をひきよせホロヴィッツ愛用のピアノを購入し、ピアノをコンサートホールに運び貸しだしを行っている。彼に全幅の信頼をおくピアニストや音楽関係者も多いだろう。私はテレビドラマの「半澤直樹」が好きだが、実社会での「倍返し!」というのは難しい。本書は、様々な嫌がらせをした某企業への「倍返し」のようなものだと言ってしまえば、辛口批評だろうか。
にわかには信じがたい某楽器商により行状が次々と暴かれていて、まさに悪代官による弱いものいじめの構図なのだが、結局、芸術系は良い仕事をする人が残っていき人々に感謝されるものだと思う。実際、高木さんは運命の女神が微笑むような幸運をひきよせホロヴィッツ愛用のピアノを購入し、ピアノをコンサートホールに運び貸しだしを行っている。彼に全幅の信頼をおくピアニストや音楽関係者も多いだろう。私はテレビドラマの「半澤直樹」が好きだが、実社会での「倍返し!」というのは難しい。本書は、様々な嫌がらせをした某企業への「倍返し」のようなものだと言ってしまえば、辛口批評だろうか。