1989年、「クラウディオ・アバドがカラヤンの後任としてベルリン・フィルの首席指揮者に選出された」というニュースが、
当時の音楽界に大きな驚きをもって迎え入れられた、そうだ。
・・・そうなのか。カラヤン時代を知らない私は、クラディオ・アバド=ベルリン・フィルにすっかりなじんでいたのだが。
こんな時なので、4月末までベルリン・フィルのデジタル・コンサートホールの一部を無料で視聴できた。
そのなかから、選んだのがドキュメンタリーの今は亡きクラウディオ・アバドの首席指揮者としての最初の1年間を追った1990年製作のドキュメンタリーだったのだが、これは本当に大正解だった。
ところで、クラディオ・アバドClaudio Abbadoとはいかなる指揮者なのか。
私の乏しい知識では、ある方に教えていただいたのだが、あのヴィクトリア・ムローヴァと恋人関係にあった方。(ビデオで録画したおふたりが共演した渋いブラームスのVn協奏曲を本当に何度も愛聴していたので、あの地味~なヴァイオリニストと指揮者の情熱的な関係には衝撃を受けたことを懐かしく思い出す。)
クラシック音楽が3度の飯よりも好き、私にとって音楽は生きていくのにかかせない大切な友でありながら、指揮者の区別は顔以外は全くできない。ただ、最近、世界の著名オーケストラのコンサートマスター51人のインタヴュー集である「世界のコンサートマスターは語る」という著書で、最後にコンマスが自分の所属するオケの首席指揮者や音楽監督を語る記述に魅了された。世界のコンマスたちは、指揮者の個性や“やり方”を分析し、彼らを信頼して自信をもって我がマエストロを紹介していた。その指揮者の多様性と才能に目をみはられた。
さて、このドキュメンタリーは、様々な指揮者の候補から、オケの団員楽員による選挙という民主的方法から10月8日に選ばれた“ダークホース”という文字が当時の新聞をにぎわしていたのがわかる。そのダークホースが車に乗って、栄光の舞台カラヤンサーカス(ツィルクス・カラヤーニ)に向かっている。何と言ってもカラヤンの前も後もベルリン・フィルの音楽監督は、名実ともにあらゆる意味で現代最高の地位であり椅子である。最初、電話を受けたとき、すでに世界トップクラスとしてその名が轟いたアバドですら、2分間電話を握りしめ声がでなかったそうだ。晴れやかな喜びのオーラに包まれたアバドの物腰、そして祖父が音楽学者だと語る姿に育ちの良さを感じた。
改めて調べたところ、1933年ミラノに生まれたクラディオ・アバドは、イタリアの名門音楽一家の出身。やはりそうか、若々しく端正で、飾らない自然体の姿に名門出身の品格に納得。
やがて車はホールに到着して、インタビューを受ける前にカラヤンが長年使用していた控室に入る。「初めてこの部屋に入る」とつぶやく彼に、付き添ったスタッフの「これからは客演指揮者にも使用してもらう」という声に、これまでのカラヤンの帝王ぶりが伝わる。窓からひろがるのは、まさに1989年11月9日に壁が崩壊されたベルリンの風景である。就任記念公演の準備がすすむ。曲はマーラーの交響曲第一番ニ長調「巨人」。難しいが、素晴らしい選曲ではないだろうか。そして、協奏曲のソリストに選ばれたのが、東ベルリン出身の10代のピアニストのジーリ・シュニッツ。しかし、彼女を紹介するのにピアニストという肩書は、まだなじまない。何故ならば、彼女自身が語るところによると、東ドイツでは演奏するチャンスがないのだそうだ。アバドのモーツァルトを弾いてほしいというリクエストに応えて、本番では純白のシャツに長い髪を後ろで三つ編みできりりと結び、しなやかでほっそりと華奢な指から清々しい珠玉の音楽がころがっていく。
「やはり自分は“君臨”するタイプの指揮者の方が好きだ」という楽団の意見もあり。それでも、東西統一の新しい時代とともに、民主主義で選んだクラディオ・アバドとベルリン・フィルの高揚感と期待と、何よりも未来へのあかるい希望を感じるドキュメントだった。
調印式でフラッシュをあびるアバドと関係者たち。ようやくアバドが契約書にサインしたのは、1990年9月1日のことだった。
監督:ボブ・アイゼンハルト, スーザン・フレムケ, ピーター・ゲルプ
当時の音楽界に大きな驚きをもって迎え入れられた、そうだ。
・・・そうなのか。カラヤン時代を知らない私は、クラディオ・アバド=ベルリン・フィルにすっかりなじんでいたのだが。
こんな時なので、4月末までベルリン・フィルのデジタル・コンサートホールの一部を無料で視聴できた。
そのなかから、選んだのがドキュメンタリーの今は亡きクラウディオ・アバドの首席指揮者としての最初の1年間を追った1990年製作のドキュメンタリーだったのだが、これは本当に大正解だった。
ところで、クラディオ・アバドClaudio Abbadoとはいかなる指揮者なのか。
私の乏しい知識では、ある方に教えていただいたのだが、あのヴィクトリア・ムローヴァと恋人関係にあった方。(ビデオで録画したおふたりが共演した渋いブラームスのVn協奏曲を本当に何度も愛聴していたので、あの地味~なヴァイオリニストと指揮者の情熱的な関係には衝撃を受けたことを懐かしく思い出す。)
クラシック音楽が3度の飯よりも好き、私にとって音楽は生きていくのにかかせない大切な友でありながら、指揮者の区別は顔以外は全くできない。ただ、最近、世界の著名オーケストラのコンサートマスター51人のインタヴュー集である「世界のコンサートマスターは語る」という著書で、最後にコンマスが自分の所属するオケの首席指揮者や音楽監督を語る記述に魅了された。世界のコンマスたちは、指揮者の個性や“やり方”を分析し、彼らを信頼して自信をもって我がマエストロを紹介していた。その指揮者の多様性と才能に目をみはられた。
さて、このドキュメンタリーは、様々な指揮者の候補から、オケの団員楽員による選挙という民主的方法から10月8日に選ばれた“ダークホース”という文字が当時の新聞をにぎわしていたのがわかる。そのダークホースが車に乗って、栄光の舞台カラヤンサーカス(ツィルクス・カラヤーニ)に向かっている。何と言ってもカラヤンの前も後もベルリン・フィルの音楽監督は、名実ともにあらゆる意味で現代最高の地位であり椅子である。最初、電話を受けたとき、すでに世界トップクラスとしてその名が轟いたアバドですら、2分間電話を握りしめ声がでなかったそうだ。晴れやかな喜びのオーラに包まれたアバドの物腰、そして祖父が音楽学者だと語る姿に育ちの良さを感じた。
改めて調べたところ、1933年ミラノに生まれたクラディオ・アバドは、イタリアの名門音楽一家の出身。やはりそうか、若々しく端正で、飾らない自然体の姿に名門出身の品格に納得。
やがて車はホールに到着して、インタビューを受ける前にカラヤンが長年使用していた控室に入る。「初めてこの部屋に入る」とつぶやく彼に、付き添ったスタッフの「これからは客演指揮者にも使用してもらう」という声に、これまでのカラヤンの帝王ぶりが伝わる。窓からひろがるのは、まさに1989年11月9日に壁が崩壊されたベルリンの風景である。就任記念公演の準備がすすむ。曲はマーラーの交響曲第一番ニ長調「巨人」。難しいが、素晴らしい選曲ではないだろうか。そして、協奏曲のソリストに選ばれたのが、東ベルリン出身の10代のピアニストのジーリ・シュニッツ。しかし、彼女を紹介するのにピアニストという肩書は、まだなじまない。何故ならば、彼女自身が語るところによると、東ドイツでは演奏するチャンスがないのだそうだ。アバドのモーツァルトを弾いてほしいというリクエストに応えて、本番では純白のシャツに長い髪を後ろで三つ編みできりりと結び、しなやかでほっそりと華奢な指から清々しい珠玉の音楽がころがっていく。
「やはり自分は“君臨”するタイプの指揮者の方が好きだ」という楽団の意見もあり。それでも、東西統一の新しい時代とともに、民主主義で選んだクラディオ・アバドとベルリン・フィルの高揚感と期待と、何よりも未来へのあかるい希望を感じるドキュメントだった。
調印式でフラッシュをあびるアバドと関係者たち。ようやくアバドが契約書にサインしたのは、1990年9月1日のことだった。
監督:ボブ・アイゼンハルト, スーザン・フレムケ, ピーター・ゲルプ











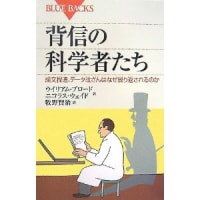

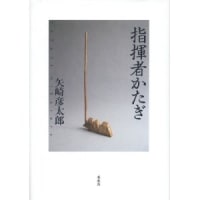
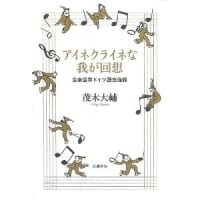
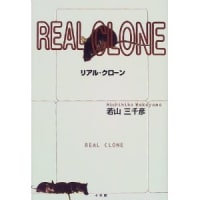
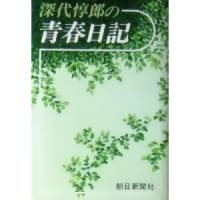
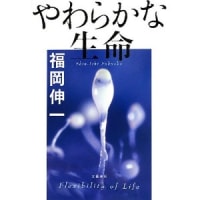
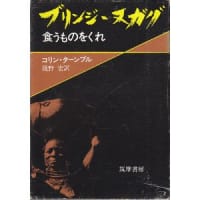
BPOはKarajanが連れてきたころは何度も聴きに行きました。
彼とBPOの関係が緩んできてからというものは聴きに行っていません。
したがってアッバード時代もラトル時代も知りません。
Karajanは確かに大向こうをうならせる指揮者でした。
とりわけ感動したのはヴェルレクでした。
フレーニ、バルツァ、ギャウロフとまだ新人だったリマがテノールの代演でした。
最初は高校生の頃名古屋での公演でしたが、いまでもTil EugenspiegelのEbのクラリネットが耳に残っています。(1950年代の後半でした。)あれはことによったらWPOだったかもしれませんが、伊勢湾台風のすぐ後に来日したのですが、切符が買えませんでした。
しかし伊勢湾台風のチャリティのコンサートの切符が手に入りました。
なかでもHaydnの104番が記憶に残っています。
歴史学者の磯田道史様の言葉をちょっと長いですが、紹介したいと思います。
「論文引用数が多い研究に、効率的、集中的に」予算をつけるのは危険です。
・・・平時はやらないニッチな「研究の多様性」がなければ、いざという時、
大変なことになります。知性や学問は百科事典に似て多彩な項目が
全部そろっていることが力です。
科学や政策の話かと思っていましたが、歴史学者の知見に感服しました。
感染症の対策にまさか歴史学が役に立つとは、
ご自分でも思うほどだそうです。
カラヤンとの幸福なお話をありがとうございます。
カラヤンの功績は多方面でとても大きいと思います。
彼の指揮は、私のような大衆が期待するとおりの演奏を多彩にオールマイティに演奏したと思っています。
>伊勢湾台風のチャリティのコンサート
そういのがあったのですね。
本当に日本は災害が多い国ですね。