 本作は本国では20万人もの観客を動員したそうだが、日本では地味な単館ロードショーでたいして大きな評判にもならずに終わっていたような気がする。実際、私も友人に薦められたのにも関わらず、今頃DVDで観ているし。しかし、断言するが 『仕立て屋の恋』『髪結いの亭主』で究極の愛を描いたフランスの監督パトリス・ルコントの最高傑作だ!
本作は本国では20万人もの観客を動員したそうだが、日本では地味な単館ロードショーでたいして大きな評判にもならずに終わっていたような気がする。実際、私も友人に薦められたのにも関わらず、今頃DVDで観ているし。しかし、断言するが 『仕立て屋の恋』『髪結いの亭主』で究極の愛を描いたフランスの監督パトリス・ルコントの最高傑作だ!その男、ミラン(ジョニー・アリディ)はさびれたリゾート地に列車に乗ってやってきた。スリムな体躯に着古した皮ジャンをはおり、眼光鋭い中年のその男は、一目見てアウトローな男だとわかる。日が暮れかけてシャッターの閉まっている商店街で唯一開いていた薬局に入り、頭痛薬を求めるミランは、そこで身なりのよい初老の紳士マネスキエ(ジャン・ロシュホール)と出会う。その偶然の出会いがもたらした、ふたりの男の3日間。ふたりの男が一緒に過ごした3日間。何から何まで正反対で対照的なふたり。寡黙な傍観者として女性に好かれたいと語るマネスキエは、定年退職をした元フランス語の教授で、生まれた時から大きく居心地のよい屋敷に住む。次から次への沈黙を恐れるような彼の饒舌に少々うんざりしているミランこそは寡黙な男で、15年間サーカスのスタントマンとして働ていた経験のある流れ者。定職もなければ、定まった住居もない。しかし、彼らにも共通点はある。それは、孤独であること。そして、自分の人生に疲れていること。彼らはいつしかお互いの人生にひかれていくようになるのだったが・・・。
すべてにおいて、余計な演出も会話も削除されたシンプルな進行は、スタイリッシュささえ感じられる。蒼く淡い色調の映像が、孤独なふたりの心象風景を表現しているような美しさがあり、朗読される詩、ギターの物憂げな音色とシューマンのピアノ曲が彩っていく。そして、ふたりの会話のひとつひとつ、映像の一場面ごとが絶妙であたかもいぶし銀のような趣がある。
ミランは、夕食の時にマネスキエにある願い事をする。それは、生まれてから一度も履いたことのない室内履きを試してみたいということだ。早速、いそいそと室内履きを持ってきてミランにはかせて悦にいるマネスキエ。「いいもんだな」と呟くミランに、これまでの落ち着きと安らぎのなかった彼の人生がすけてみえてくる。その一方で、たった一度、パリに行った経験しかないマネスキエは、カバンひとつをもって列車に乗って放浪の旅に出ることに憧れているが、それが叶わない理由があった。そんなふたりの人生が交錯していき、邸宅の鍵と旅行カバンを交換する夢をそれぞれにみるようになる。人生の曲がり角、踊り場にたった時、或いは、自分に残された人生がもう短いと悟った時、もうひとつの人生があったかもしれない、別の人生を考えることは誰にでもありそうだ。なんともせつなく、身につまされるような気持ちになる。
友情というには、あまりにも儚かったふたりの3日間。孤独が互いをよびよせて、ひかれていくふたりの魂。究極の愛を描いたルコントは、本作で男の究極のダンディズムを描いている。ミラン役を演じたジョニー・アリディは、かってはフランスのプレスリーとまで呼ばれたロック界の大御所で、パトリス・ルコントの作品に出演することを熱望していたそうだが、まさに彼のために用意されたような役だった。人生の夢を失いかけた男の悲哀をそのたたずまいだけで演じたのは、お見事であり、こういう男に女性は色気を感じるものだ。勿論、ルコント作品の常連であり、大ベテランのジャン・ロシュホールの表情のわずかな動きですべてを語る演技にもひきこまれた。ラストの場面、ふたりの男の瞳の淡く透明な水色が、なんともの哀しく映っていたことか。才能ある監督によるフランス映画らしい完成度の高い1本である。
監督・パトリス・ルコント
2002年フランス製作
■アーカイヴ
・『親密すぎるうちあけ話』











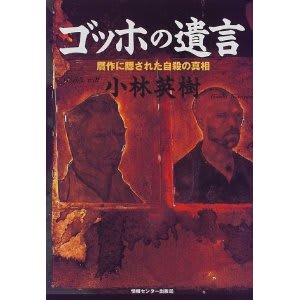 ゴッホの絵の本物を、初めて観た時の衝撃は忘れられない。
ゴッホの絵の本物を、初めて観た時の衝撃は忘れられない。 モーツァルトが若くして亡くなった理由に、幼い頃から父レオポルドに連れられて、ヨーロッパ中を悪路にゆられて馬車で演奏旅行をした時の無理がたたったのだという説がある。
モーツァルトが若くして亡くなった理由に、幼い頃から父レオポルドに連れられて、ヨーロッパ中を悪路にゆられて馬車で演奏旅行をした時の無理がたたったのだという説がある。 何年か前、トヨタ自動車がスポンサーだった「地球街道」という上質の旅番組があった。芸能人の方が夢をかなえる旅というコンセプトは、それぞれに素敵だったのだが、最もうらやましい旅人だったのは、財津和夫さんだ。それは「フェリーニへの道!」
何年か前、トヨタ自動車がスポンサーだった「地球街道」という上質の旅番組があった。芸能人の方が夢をかなえる旅というコンセプトは、それぞれに素敵だったのだが、最もうらやましい旅人だったのは、財津和夫さんだ。それは「フェリーニへの道!」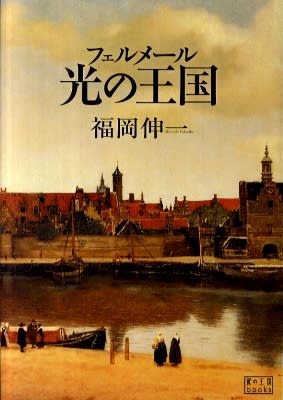 私はフェルメールの絵に会いたかったのか、福岡伸一さんの名文に会いたかったのか。
私はフェルメールの絵に会いたかったのか、福岡伸一さんの名文に会いたかったのか。 ベラスケスに並ぶスペインが誇る宮廷画家フランシスコ・デ・ゴヤは、1746年に小さな田舎町フェンデトードスでメッキ職人の息子として生まれる。早くから画家を志し、14歳の頃から地元の画家の元で絵画を学び、やがて40歳で国王カルロス3世の画家となり、1789年には新王カルロス4世の首席宮廷画家の地位をえて、頂点を極める。エスコラピオス修道会の宗教学校で出会った親友のマルティン・サパテールに宛てた当時の手紙には(ゴヤは筆まめだったそうだが)、「国王夫妻以下、僕を知らない人はいない」と成功を自慢している。また自信たっぷりに、仕事の依頼が絶えないことも嬉しげに彼に伝え、むしろ遅咲きだったゴヤは「我々に残された年月はすくないのだから、大いに楽しく生きるべきだ。」と、そこには、野心と成功の美酒に酔う姿がうかがい知れるのだが、1792年頃から、不運にも聴覚を失っていく。しかし、失われた音のかわりに観察者としての鋭い感性が「裸のマハ」「カルロス4世の家族」「マドリード、1808年5月3日」「黒い絵」など、次々と代表作を産み、宮廷画家として後世に名を残す以上の仕事を成したのも、沈黙の夜に囚われてからのことだった。
ベラスケスに並ぶスペインが誇る宮廷画家フランシスコ・デ・ゴヤは、1746年に小さな田舎町フェンデトードスでメッキ職人の息子として生まれる。早くから画家を志し、14歳の頃から地元の画家の元で絵画を学び、やがて40歳で国王カルロス3世の画家となり、1789年には新王カルロス4世の首席宮廷画家の地位をえて、頂点を極める。エスコラピオス修道会の宗教学校で出会った親友のマルティン・サパテールに宛てた当時の手紙には(ゴヤは筆まめだったそうだが)、「国王夫妻以下、僕を知らない人はいない」と成功を自慢している。また自信たっぷりに、仕事の依頼が絶えないことも嬉しげに彼に伝え、むしろ遅咲きだったゴヤは「我々に残された年月はすくないのだから、大いに楽しく生きるべきだ。」と、そこには、野心と成功の美酒に酔う姿がうかがい知れるのだが、1792年頃から、不運にも聴覚を失っていく。しかし、失われた音のかわりに観察者としての鋭い感性が「裸のマハ」「カルロス4世の家族」「マドリード、1808年5月3日」「黒い絵」など、次々と代表作を産み、宮廷画家として後世に名を残す以上の仕事を成したのも、沈黙の夜に囚われてからのことだった。 住居は、小さな街ヴォルフスブルク市にある3LDKのマンションにひとり住まい。独身!
住居は、小さな街ヴォルフスブルク市にある3LDKのマンションにひとり住まい。独身! 今年もノーベル賞発表の季節がやってきて静かに去っていった。残念ながら日本人の受賞者はいなかったが、最もノーベル賞に近い男、あとはノーベル賞だけと言われているのが山中伸弥氏である。昨年、NHKスペシャルでその山中さんを迎えて放映された
今年もノーベル賞発表の季節がやってきて静かに去っていった。残念ながら日本人の受賞者はいなかったが、最もノーベル賞に近い男、あとはノーベル賞だけと言われているのが山中伸弥氏である。昨年、NHKスペシャルでその山中さんを迎えて放映された