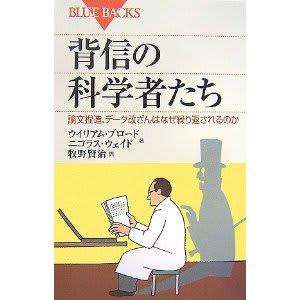 1981年、下院議員の若きアルバート・ゴア・ジュニアは、深い怒りをこめて「この種の問題が絶えないひとつの原因は、科学界において指導的地位にある人々が、これらの問題を深刻に受け止めない態度にある。」とざわめく法廷を制した。通称、ジョン・ロング事件でのできことだった。 論文の盗用、データーの捏造、改ざんをしていたのは、あのOさんだけではなかった。
1981年、下院議員の若きアルバート・ゴア・ジュニアは、深い怒りをこめて「この種の問題が絶えないひとつの原因は、科学界において指導的地位にある人々が、これらの問題を深刻に受け止めない態度にある。」とざわめく法廷を制した。通称、ジョン・ロング事件でのできことだった。 論文の盗用、データーの捏造、改ざんをしていたのは、あのOさんだけではなかった。「それでも地球が回っている」
あまりにも有名なこのセリフを後世に残し、科学者という肩書きを崇高に格上げしたガリレオ・ガリレイの実験結果は、再現不可能で今日では実験の信頼性に欠けているとみなされている。又、偉大な科学者であるアイザック・ニュートンは『プリンキピア』で研究をよりよく見せるため偽りのデータを見事なレトリックと組み合わせて並べていたし、グレゴール・メンデルの有名なエンドウ豆の統計は、あまりにも出来すぎていて改ざんが疑われる、というよりも本当に改ざんしていたようだ。しかし、いずれもこれらの行為は、ニュートンもメンデルも信頼性を高めるための作為であり、都合のよい真実を集めていたわけで、科学的真理の発見にはおおいに貢献していたとも言える。”悪意”もなかったようだし。
しかし、現代ではいかなる科学的な事実であろうとも、論文の捏造は許されるものではない。そもそも、”悪意”の定義を議論することすら見当違いであることを、本書を読んでつくづく実感する。仮に、もし仮にstap細胞が本当に存在していたとしても、論文のデータを改ざんしたり捏造したりする行為が水に流されて、最終的に結果オーライというわけにはいかない。それが、一般社会通念とは違う科学というグローバルスタンダードの戦場なのだ。
いつかはばれる。化石を捏造した犯人がいまだに謎である推理小説のようなピルトダウン事件、サンバガエルを使って嘘の実験データで強引にラマルク学説を支持したポール・カンメラー事件(余談だが、彼はアルマ・マーラーに恋をして結婚に応じないならば亡き夫・マーラーの墓前でピストル自殺をすると迫ったそうだ)、データを捏造して驚異的な論文を生産していたハーバード大学のダーシー事件、論文を盗用しまくって研究室を渡り歩いたアルサブティ事件。次々と背信の科学者たちが途絶えることがない。
本書に登場する事件を読む限りでは、いつかは偽造がばれるだろうと素人にも思えるのだ。結局、嘘に嘘を積み重ねることは、無理があり破綻せざるをえない。それにも関わらず、ミスコンダクトは繰り返されていく。何故なのだろうか。
たとえば、1960年代、全く新しい星がケンブリッジ大学の博士課程の大学院生ジョスリン・ベル・バーネルによって発見された。しかしながら、「ネイチャー」に掲載された論文の筆頭者は、最大の功労者である彼女ではなく、師匠のアントニー・ヒューイッシュだった。教え子の手柄をとった彼が、後にノーベル物理学賞を受賞すると”スキャンダル”と非難された。おりしも、金沢大学では教え子の大学院生が書いた論文を盗用していたという事件が発覚したが、ここまで悪質ではなくとも、それに近い話はそれほど珍しくない。科学の専門化、細分化がすすむにつれ、多額の助成金が必要となり、予算をとってくるベテラン科学者と、彼らの下でもくもくと実験作業を行う若手研究者。ベテランが予算をとってくるから研究できるのであり、逆に駒のように働いてくれるから研究者は真理に近づけるのである。iPS細胞でノーベル賞を受賞した山中教授と、当時大学院生だった高橋和利さんのようなよい師弟関係ばかりではない。
実は、本書は1983年に米国で出版された科学ジャーナリストによる本である。そんな昔の本なのに、登場する実際の捏造事件は、今回のstap細胞問題に重なる点が多いことに驚いた。優れた研究室で、次々と画期的な論文を連発するが、本人しか再現できないマーク・スペクター事件。stap細胞作成には、ちょっとしたコツとレシピが必要だと微笑んだ方を思い出してしまった。「リアル・クローン」の中でも、著者が再現性が重要と何度も繰り返していた。大物実力者のサイモン・フレクスナー教授の支持を受けて、充分な審査を受けることなく次々と論文を発表してもてはやされていたが、今ではすっかり価値をなくしてしまったがらくたのような研究ばかりで科学史から消えていった野口英世。
ところで、気になるのが、次の記述である。
「若手の研究者がデータをいいかげんに取り扱ったことが明るみに出ると、そのような逸脱行為によって信用を傷つけられた研究機関は、事態を調査するための特別委員会を組織することが責務であると考える。しかし、そうした委員会は結局、予定された筋書きに従って行動するのである。委員会の基本的な役割はその科学機関のメカニズムに問題があるわけではないことを外部の人びとに認めさせることにあり、形式的な非難は研究室の責任者に向けられるが、責任の大部分は誤ちを犯した若い研究者に帰されるのが常である。」
そして改ざんの予防策として、「論文の執筆者は署名する論文に全責任を負うべきである」とも。今回の茶番も、Oさんひとりの責任ではなく、そもそも科学者としての資質も能力も欠けている人を採用し、バックアップしたブラックSさんの責任も重いのではないだろうか。
・「リアル・クローン」若山三千彦著
・ミッシング・リンクのわな










 4月16日、 理研の笹井芳樹副センター長によるstap細胞の論文問題に関する会見を見た小保方さんは、尊敬する笹井さんにご迷惑をかけたと泣いたそうだ。男だったら泣くか、それをご丁寧に発信する有能な弁護集団の世間の同情を誘うかのような意図もしらじらしいのだが、なんだかお2人が水面下で結託して、山梨大学の若山照彦教授に微妙に罪をなすりつけようとしているのを感じたのは、私だけではなかったのではないだろうか。
4月16日、 理研の笹井芳樹副センター長によるstap細胞の論文問題に関する会見を見た小保方さんは、尊敬する笹井さんにご迷惑をかけたと泣いたそうだ。男だったら泣くか、それをご丁寧に発信する有能な弁護集団の世間の同情を誘うかのような意図もしらじらしいのだが、なんだかお2人が水面下で結託して、山梨大学の若山照彦教授に微妙に罪をなすりつけようとしているのを感じたのは、私だけではなかったのではないだろうか。 野球に例えたら、打率は何割になるのであろうか。私にとっては、5割を超える打率で快調にヒットを飛ばしている、いやルーキーの時から飛ばし続けているのが福岡ハカセのエッセイである。本1冊単位ではなく短いエッセイものの1本1本を、その内容の充実度とレベルの高さで測ると、ページをめくる度に、心が躍り、清冽に目を開かれる。某ノーベル賞候補作家の新作が出版される度に、特別に駅の構内で店員さんが声をはりあげて宣伝して売っているイベントを横目に、新作を切望して待っている作家のひとりが福岡ハカセである。
野球に例えたら、打率は何割になるのであろうか。私にとっては、5割を超える打率で快調にヒットを飛ばしている、いやルーキーの時から飛ばし続けているのが福岡ハカセのエッセイである。本1冊単位ではなく短いエッセイものの1本1本を、その内容の充実度とレベルの高さで測ると、ページをめくる度に、心が躍り、清冽に目を開かれる。某ノーベル賞候補作家の新作が出版される度に、特別に駅の構内で店員さんが声をはりあげて宣伝して売っているイベントを横目に、新作を切望して待っている作家のひとりが福岡ハカセである。 国内でその敷居の高さだでなく、内容の信頼度もトップレベルの出版社、岩波書店から「科学」という雑誌が出版されている。毎月の刊行で、金額は本体1333円プラス消費税。あっという間に消えていく雑誌も多い中、本書は1931年に物理学者の石原純と寺田寅彦によって創刊されて以来、科学の進展を80年以上も見つめてきた。その「科学」が、科学者たちや科学にかかわりの深い方たちに、自分の人生において最も心に残る本、研究への道を進むきっかけになった本、あるいは後輩たちに伝えたい本・・・、「心にのこる本」として連載されていたものをまとめたのが、本書である。
国内でその敷居の高さだでなく、内容の信頼度もトップレベルの出版社、岩波書店から「科学」という雑誌が出版されている。毎月の刊行で、金額は本体1333円プラス消費税。あっという間に消えていく雑誌も多い中、本書は1931年に物理学者の石原純と寺田寅彦によって創刊されて以来、科学の進展を80年以上も見つめてきた。その「科学」が、科学者たちや科学にかかわりの深い方たちに、自分の人生において最も心に残る本、研究への道を進むきっかけになった本、あるいは後輩たちに伝えたい本・・・、「心にのこる本」として連載されていたものをまとめたのが、本書である。 毎度おなじみの福岡ハカセのエッセイを続けて2冊読んでみた。
毎度おなじみの福岡ハカセのエッセイを続けて2冊読んでみた。 ところで、これだけ次々と書く本、書く本のすべてが売れまくっている福岡ハカセの著作物の中で、初版3000部で終わり、そのまま消えて絶版となった本がある。化学同人という小さいが化学・生物系にはおなじみの出版社から上梓された
ところで、これだけ次々と書く本、書く本のすべてが売れまくっている福岡ハカセの著作物の中で、初版3000部で終わり、そのまま消えて絶版となった本がある。化学同人という小さいが化学・生物系にはおなじみの出版社から上梓された 表紙を眺めているだけでなんだか楽しい。ひまわりの花に見られる二種類の螺旋(時計回りが34本、反時計回りが21本)、DNAの2重螺旋構造の図、ボルボックス、メンデルの法則で使ったえんどう豆、裏表紙に登場するのはアンモナイト、ゾウリムシにダーウィンの肖像画。ここまではすぐにわかった。最後に残った鳥の絵は、ダーウィンフィンチだろうか。はるか昔?の高校と、大学の一般教養で生物を学んだ記憶がかろうじて残っている私にとって、これらの生物学的な意味をなす絵はおなじみである。特別に理工学系にすすんだわけではない私のような者を対象とした一般読者向けの、近頃耳になじみつつある”ポピュラーサイエンス”ものの典型が本書になる。
表紙を眺めているだけでなんだか楽しい。ひまわりの花に見られる二種類の螺旋(時計回りが34本、反時計回りが21本)、DNAの2重螺旋構造の図、ボルボックス、メンデルの法則で使ったえんどう豆、裏表紙に登場するのはアンモナイト、ゾウリムシにダーウィンの肖像画。ここまではすぐにわかった。最後に残った鳥の絵は、ダーウィンフィンチだろうか。はるか昔?の高校と、大学の一般教養で生物を学んだ記憶がかろうじて残っている私にとって、これらの生物学的な意味をなす絵はおなじみである。特別に理工学系にすすんだわけではない私のような者を対象とした一般読者向けの、近頃耳になじみつつある”ポピュラーサイエンス”ものの典型が本書になる。 独断と偏見を許していただければ、宇宙飛行士ほどかっこいい職業はそうそうないのではないのではないだろうか。
独断と偏見を許していただければ、宇宙飛行士ほどかっこいい職業はそうそうないのではないのではないだろうか。 モニターで観察される彼らは、名前ではなくゼッケンをつけたAからのアルファベットで審査される。ところが、そのゼッケンを早速間違えてつけてしまった方がいる。一番若いYさんだ。そんな些細なミスも宇宙では命とりになりかねないので、こんなところでもマイナス評価がつく。毎日1時間ずつかけて折り紙で100羽の千羽鶴を折るテストでは、ストレスへの耐用性を見られる。こういうのだったら、女性は得意かも。できるだけ同じ色に、という指定を読み落して折り紙を交ぜてしまいあせるAさん。後半頑張ったが、目標まで届かなかった。テストを続けていくうちに冷静沈着な大西卓也さん、さりげなくリーダーシップを発揮する油井亀美也さんが審査員の印象に残っていく。審査委員長のそろそろ日本人の中から宇宙船の船長をだしたいという希望が、今回の試験のポイントだろうか。
モニターで観察される彼らは、名前ではなくゼッケンをつけたAからのアルファベットで審査される。ところが、そのゼッケンを早速間違えてつけてしまった方がいる。一番若いYさんだ。そんな些細なミスも宇宙では命とりになりかねないので、こんなところでもマイナス評価がつく。毎日1時間ずつかけて折り紙で100羽の千羽鶴を折るテストでは、ストレスへの耐用性を見られる。こういうのだったら、女性は得意かも。できるだけ同じ色に、という指定を読み落して折り紙を交ぜてしまいあせるAさん。後半頑張ったが、目標まで届かなかった。テストを続けていくうちに冷静沈着な大西卓也さん、さりげなくリーダーシップを発揮する油井亀美也さんが審査員の印象に残っていく。審査委員長のそろそろ日本人の中から宇宙船の船長をだしたいという希望が、今回の試験のポイントだろうか。 ”コペルニクス的転回”の通称「コペ転」という言葉は、旧制中学より始まり、現役高校生まで脈々と継承されている。この意味をあえて説明するまでもなく、天動説が信じられた時代に、宗教の謀反を起こすかのような地動説は、まさに科学革命だった。その地動説を誰よりも早く発見したコペルニクスが出版した『天球の回転について』は、アーサー・ケラーによって、実際は誰も読まなかったワーストセラー本という烙印を長らく押されていた。ところが、著者のオーウェン・ギンガリッジがエジンバラ王立天文台で偶然手にしたこの『回転について』初回版には、最初から最後まで入念に読みこなして、副次的な仮説まで入り込んだ形跡を思わせるたくさんの書き込みがあったのだ。そしてこの本の持ち主が、残されたイニシャルからコペルニクスの次世代の傑出した数理天文学者エラスムス・ラインホルトであることを想像する。ギンガレッジ氏に衝撃が走った。それ以降30年に渡って、世界中に散った『回転について』を探索することになるのである。”誰も読まなかった”コペルニクスの本をめぐって、ふたつの物語が交錯する。それは、『回転について』の本を読みつづけていった人々の物語と、検閲のために豊富な蔵書を誇るバチカン宮殿内の書庫、鉄のカーテンの向こう、旧共産圏の図書館、また或る時はイギリス貴族の館まで現存する601冊の本を探索する著者の30年に渡る長い旅の物語である。
”コペルニクス的転回”の通称「コペ転」という言葉は、旧制中学より始まり、現役高校生まで脈々と継承されている。この意味をあえて説明するまでもなく、天動説が信じられた時代に、宗教の謀反を起こすかのような地動説は、まさに科学革命だった。その地動説を誰よりも早く発見したコペルニクスが出版した『天球の回転について』は、アーサー・ケラーによって、実際は誰も読まなかったワーストセラー本という烙印を長らく押されていた。ところが、著者のオーウェン・ギンガリッジがエジンバラ王立天文台で偶然手にしたこの『回転について』初回版には、最初から最後まで入念に読みこなして、副次的な仮説まで入り込んだ形跡を思わせるたくさんの書き込みがあったのだ。そしてこの本の持ち主が、残されたイニシャルからコペルニクスの次世代の傑出した数理天文学者エラスムス・ラインホルトであることを想像する。ギンガレッジ氏に衝撃が走った。それ以降30年に渡って、世界中に散った『回転について』を探索することになるのである。”誰も読まなかった”コペルニクスの本をめぐって、ふたつの物語が交錯する。それは、『回転について』の本を読みつづけていった人々の物語と、検閲のために豊富な蔵書を誇るバチカン宮殿内の書庫、鉄のカーテンの向こう、旧共産圏の図書館、また或る時はイギリス貴族の館まで現存する601冊の本を探索する著者の30年に渡る長い旅の物語である。