
近頃では、国際コンクールと言っても数々あるが、4年に一度のチャイコフスキー国際コンクールは世界中が注目し、華やかさも抜群のコンクールである。(ショパン国際コンクールもNHKが毎回特集番組を組むせいか、話題性が抜群だがピアノに限られている。)しかも、今年はあのヴァレリー・ゲルギエフのおっさんが組織委員長に就任して
様々な改革をこころみた結果の入賞者。ジャパン・アーツが栄えある優勝者を集めてガラ・コンサートを主催した。声楽部門については、優勝者の韓国人ではなく3位に入賞したロシア人
コンクールに出場するということは、これから世界の音楽界というひのき舞台で活躍したいという目的なのだろうが、実力から言えばもう完全にプロ、というよりも演奏家としての活動をはじめて経験もあるが、更にキャリアをグレードアップするためのはずみとして優勝暦を加えることが参加動機なのだろうか。
最初に登場したのはエレーナ・グーセワさん。シンプルで清楚な白いドレスが、ロシア風大柄な体型によく映えていて、髪型、雰囲気とともにまさに「エフゲニー・オネーギン」のタチアーナになりきっている。私は映画版『オネーギンの恋文』でタチアーナ役を演じたリヴ・タイラーのイメージが強くて華奢な体型よりも、骨格のがっしりした女性の方が好み。25歳という声楽家にしては若々しく、しかも容姿も美しいエレーナ・グーセワさんが、手紙の場面を見事に歌い上げたので、サントリーホールぐらいのキャパシティだったら、やはりロシアのオペラものは容姿もふさわしいロシア人の方が観客には説得力があるかもしれない。声の美しさよりも、厚みを感じる歌手である。
次はヴァイオリン部門で2位(1位なし)で聴衆賞を受賞したセルゲイ・ドガージン君。
独特のテンポ感で”オレ様千秋”状態でオケを制する。チャイコフスキーのVn協奏曲を常々”演歌もの”と感じている私には、セルゲイ君の内省的なテンポと様式には今ひとつのりきれないものがある。それは、東京交響楽団も一緒じゃないか?おっと、オケとあっていないじゃんとはっとする部分もあるが、指揮者の高関健さんの不安げな一瞥を弱冠23歳の若造のセルゲイ君はものともせずに跳ね返し、「大丈夫、おまえこそしっかり振れ」というアイコンタクトの会話が聞こえてきた。(と、勝手に思っているのだが・・・)今回のコンクールの審査のポイントを「説得力ある演奏」と解説したゲルギエフ氏の”説得力ある演奏”を感じたのも彼の演奏だったが、又、同時に1位に少し届かなかったのもその説得の内容ではないか、とも感じた。しかし、とても魅力的なヴァイオリニストであることは間違いない。
休憩をはさんで後半は、チェロ部門で優勝したナレク・アフナジャリャン君。アルメニア出身だそうだが、おなじみの「ロココの主題による変奏曲」を、彼は、曲想にふさわしく、かろやかにそしてエレガントに弾いている。こんなにもチェロの音が優雅だったとは。ナレク君はオレ様タイプというよりも、良い意味での自己陶酔型のように見える。ロストロポーヴィッチ財団から奨学金を授与されているそうだが、このまま演奏活動と人生経験を積んで、スラヴァのような大家に成長するのが楽しみな逸材である。
最後は、やはりピアノ部門。なんたって、チャイコフスキーのピアノ協奏曲は演奏時間も長いが、フィナーレを飾るにふさわしい堂々たる大曲。
どうやらダニール・トリフォノフ君のコンサート4公演付き、おまけにファン・ミーティングと称した写真撮影もあるらしい「スイス・イタリア9日間」(35万円)ツアーのチラシには、”驚異の20歳”と書いてある。まあ、よくある宣伝文句だとさして気にもとめていなかったのだが、あまりにも有名な冒頭の出だしの彼の確信のある演奏には、二階席から思わず身をのりだしてしまった。音がとても綺麗なのだ。輝くばかりの音の粒にポリーニを連想したのだが、そういえば、遠目で確認したピアノは
ファツィオーリだった。これぞ、まさに説得力のある演奏。そればかりではない、気迫に満ちた音が会場一杯に一気に広がっていく。まだ若い竹のようなスタイルのどこから、こんなに響く音量がでるのだろう。プログラムをよく見ると、彼は全部門を通てグランプリを受賞している。
来日した演奏者は、全員、聴衆賞を受賞しているのだが、それにしても、いずれも顔が小さく、スリムで脚が長く長身でコンサート・スーツが決まっているイケ面ばかり。女子的には、クラシック界の「
イケメン・パラダイス」だったのは想定外だった。そんな彼らと並ぶ指揮者の高関さんが、まるで猿の惑星からやってきたようにも感じる。(失礼!)今回のコンクールでは、残念なことに日本人が誰も本選に残らなかったのも話題のひとつ。 1975年に初めてエリザベート王妃国際コンクールで審査員を務めた時のピアニストの安川加寿子さんが、「日本人が本当に人を感銘させる演奏ができるようになるまであと半世紀かかるだろう」と言った言葉を思い出したのだった。
余談だが、コンサートに先立ちインタビューをした音楽ジャーナリストの伊熊よし子さんによると、彼らの素顔を「全体的に非常に思慮深く視野が広く、バランスのとれた人間性の持ち主」であり、自分の心の声をしっかりことばにできる能力と主張する力を備えていることに感動したというエピソードが印象に残る。やはり、音楽と対話をしながら世界の頂点をめざす者はちょっと違うようだ。
-------2011年9月8日「2011年第14回チャイコフスキー国際コンクール 優勝者ガラ・コンサート」サントリーホール--------
ⅩⅣInternational Tchaikovsky Competition Winners'
ダニール・トリフォノフ Daniil Trifonov 【グランプリ、ピアノ部門第1位、聴衆賞】
セルゲイ・ドガージン Sergey Dogadin 【ヴァイオリン部門第2位(1位なし)、聴衆賞】
ナレク・アフナジャリャン Narek Hakhnazaryan 【チェロ部門第1位、聴衆賞】
エレーナ・グーセワ Elena Guseva(ソプラノ/Soprano) 【声楽部門・女声第3位、聴衆賞】
■オール・チャイコフスキー・プログラム
All Tchaikovsky Program
歌劇「エフゲニー・オネーギン」~手紙の場面
エレーナ・グーセワ【声楽部門・女声 第3位・聴衆賞】
“Letter Scene” from “Eugene Onegin”
Soprano: Elena Guseva
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
セルゲイ・ドガージン【ヴァイオリン部門第2位(1位なし)・聴衆賞】
Violin Concerto in D major op.35
Violin: Sergey Dogadin
ロココの主題による変奏曲 イ長調 作品33
ナレク・アフナジャリャン【チェロ部門第1位・聴衆賞】
Rococo Variations in A major op.33
Cello: Narek Hakhnazaryan
ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23
ダニール・トリフォノフ【グランプリ・ピアノ部門第1位・聴衆賞】
Piano Concerto No.1 in B-flat minor op.23
Piano: Daniil Trifonov
指揮:高関健 管弦楽:東京交響楽団
■こんなアーカイブとアンコールも
・
チャイコフスキー国際コンクールの幕がおりる
・
ファツィオーリという世界最高のピアノ
・
「第13回チャイコフスキー国際コンクール 入賞者ガラ・コンサートジャパンツアー」
 1968年12月10日、雨が降る師走の朝、白バイ警官に扮した”男”が現金輸送中のセドリックに近づき「爆弾が仕掛けられている」と警告して、4人の行員を退避させている間に車をのっとり逃走した。強奪した金額は3億円。20世紀最大の謎と言われていまだに解決されていない「3億円事件」。その真犯人は、女子高校生。彼女の名前は中原みすず。
1968年12月10日、雨が降る師走の朝、白バイ警官に扮した”男”が現金輸送中のセドリックに近づき「爆弾が仕掛けられている」と警告して、4人の行員を退避させている間に車をのっとり逃走した。強奪した金額は3億円。20世紀最大の謎と言われていまだに解決されていない「3億円事件」。その真犯人は、女子高校生。彼女の名前は中原みすず。









 モスクワ(CNN) ロシアのメドベージェフ大統領は24日、与党「統一ロシア」党大会での演説で、来年3月の大統領選の候補者としてプーチン首相を支持すべきだと述べた。プーチン氏はこれを受け、今年12月の下院選後、首相ポストはメドベージェフ氏が引き継ぐべきだと語った。
モスクワ(CNN) ロシアのメドベージェフ大統領は24日、与党「統一ロシア」党大会での演説で、来年3月の大統領選の候補者としてプーチン首相を支持すべきだと述べた。プーチン氏はこれを受け、今年12月の下院選後、首相ポストはメドベージェフ氏が引き継ぐべきだと語った。 この映画の宣伝チラシには、”『ヒトラーの贋札』のスタッフが贈る謎と緊張が連続するサスペンス・ミステリー”という言葉が踊っている。
この映画の宣伝チラシには、”『ヒトラーの贋札』のスタッフが贈る謎と緊張が連続するサスペンス・ミステリー”という言葉が踊っている。 これほど作品の内容に先行して、映画を撮った監督自身の生涯が話題になる人もそうそういないだろう。
これほど作品の内容に先行して、映画を撮った監督自身の生涯が話題になる人もそうそういないだろう。 あの頃の私は、本当におばかだった。時々、当時の自分を振り返ると布団の中にもぐってぎゃ~~っっと絶叫したくなる。けれども、あの頃の友人、先輩、後輩たちは私に負けず劣らず、いや私以上にもっとおおばか者だったと思っている。あの頃、ついこの間まで制服がよく似合う女子コウコウセーだったのに、桜の季節とともに大学生になりキャンパスを意気揚々と闊歩していた。
あの頃の私は、本当におばかだった。時々、当時の自分を振り返ると布団の中にもぐってぎゃ~~っっと絶叫したくなる。けれども、あの頃の友人、先輩、後輩たちは私に負けず劣らず、いや私以上にもっとおおばか者だったと思っている。あの頃、ついこの間まで制服がよく似合う女子コウコウセーだったのに、桜の季節とともに大学生になりキャンパスを意気揚々と闊歩していた。 東京では、およそ毎日30公演ほどの音楽会が開かれていて、ひとつの街としてはその数は世界一だそうだ。個人的にも、それがTOKYOを離れたくない理由ともなっているのだが、今から70年前の1940年代の日本では、なんとあるピアニストがコンサートの依頼を受けたところ、畳の上に足をはずしたピアノが置かれ、前に座布団が置いてあったそうだ。そんなクラシック音楽に関しては発展途上国のような状況でピアニストとして生きていくのもそざかし大変だったろうが、幼い頃からパリで育ち、パリ国立高等音楽院をわずか15歳で1等賞で卒業して帰国したばかりの新進ピアニストのとまどいを察するとあまりにも気の毒である。そのピアニストは、安川加壽子さん。さまざまな国際的なコンクールで審査員を務め、ピアニストの音楽暦で師事した方の名前によくみかけていた名前だ。本書は、小学生時代、そして高校時代に安川さんの指導を受けた同じくピアニスト青柳いづみ子さんによる評伝である。
東京では、およそ毎日30公演ほどの音楽会が開かれていて、ひとつの街としてはその数は世界一だそうだ。個人的にも、それがTOKYOを離れたくない理由ともなっているのだが、今から70年前の1940年代の日本では、なんとあるピアニストがコンサートの依頼を受けたところ、畳の上に足をはずしたピアノが置かれ、前に座布団が置いてあったそうだ。そんなクラシック音楽に関しては発展途上国のような状況でピアニストとして生きていくのもそざかし大変だったろうが、幼い頃からパリで育ち、パリ国立高等音楽院をわずか15歳で1等賞で卒業して帰国したばかりの新進ピアニストのとまどいを察するとあまりにも気の毒である。そのピアニストは、安川加壽子さん。さまざまな国際的なコンクールで審査員を務め、ピアニストの音楽暦で師事した方の名前によくみかけていた名前だ。本書は、小学生時代、そして高校時代に安川さんの指導を受けた同じくピアニスト青柳いづみ子さんによる評伝である。 近頃では、国際コンクールと言っても数々あるが、4年に一度のチャイコフスキー国際コンクールは世界中が注目し、華やかさも抜群のコンクールである。(ショパン国際コンクールもNHKが毎回特集番組を組むせいか、話題性が抜群だがピアノに限られている。)しかも、今年はあのヴァレリー・ゲルギエフのおっさんが組織委員長に就任して
近頃では、国際コンクールと言っても数々あるが、4年に一度のチャイコフスキー国際コンクールは世界中が注目し、華やかさも抜群のコンクールである。(ショパン国際コンクールもNHKが毎回特集番組を組むせいか、話題性が抜群だがピアノに限られている。)しかも、今年はあのヴァレリー・ゲルギエフのおっさんが組織委員長に就任して 東野圭吾さんは、名実ともに人気作家である。
東野圭吾さんは、名実ともに人気作家である。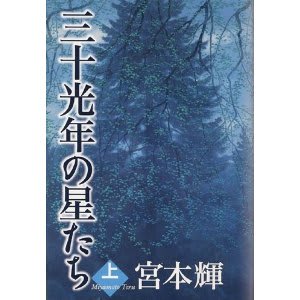 今から5年前、
今から5年前、 作家の宮本輝氏は、幅広い読者を獲得している圧倒的なストーリーテラー作家。本書は毎日新聞の連載小説としてスタートしたのだが、すでに9回も連載小説を残し、他にも連載小説を抱えていて疲れきっていた宮本さんは、体の悲鳴にお断りする予定だったそうだ。そんな氏を奮い立たせたのは、30年前の若造が作家としての決意を語った時の、ある人の「お前の決意をどう信じろというのか、30年後の姿を見せろ」という言葉だった。片時も消えなかったその言葉が、たいした学歴も、それほどの仕事での成果もない、これまで自分なりにしか頑張れなかった頼りない30歳の無職の青年が、佐伯老人をはじめ様々な人とめぐりあい、30年後をめざして、懸命に自分の人生という樹木を育てていこうという作品を生み出したのだと思う。仁志は、どこにでもいそうな今時の草食系の青年。そんな仁志に美質を見つけ出し育てようとする佐伯老人の姿に、昔だったら、そんな役割は企業の上司や先輩、怖いお局様、地域社会の住民だったのではないだろうか。何とせちがらい世の中になったことか。仁志を中心に、多少ご都合主義な観もなきにしもあらずだが、人それぞれに30年先をめざして希望を感じる良書である。11本目の新聞連載小説のオファーも早々にくるだろう。
作家の宮本輝氏は、幅広い読者を獲得している圧倒的なストーリーテラー作家。本書は毎日新聞の連載小説としてスタートしたのだが、すでに9回も連載小説を残し、他にも連載小説を抱えていて疲れきっていた宮本さんは、体の悲鳴にお断りする予定だったそうだ。そんな氏を奮い立たせたのは、30年前の若造が作家としての決意を語った時の、ある人の「お前の決意をどう信じろというのか、30年後の姿を見せろ」という言葉だった。片時も消えなかったその言葉が、たいした学歴も、それほどの仕事での成果もない、これまで自分なりにしか頑張れなかった頼りない30歳の無職の青年が、佐伯老人をはじめ様々な人とめぐりあい、30年後をめざして、懸命に自分の人生という樹木を育てていこうという作品を生み出したのだと思う。仁志は、どこにでもいそうな今時の草食系の青年。そんな仁志に美質を見つけ出し育てようとする佐伯老人の姿に、昔だったら、そんな役割は企業の上司や先輩、怖いお局様、地域社会の住民だったのではないだろうか。何とせちがらい世の中になったことか。仁志を中心に、多少ご都合主義な観もなきにしもあらずだが、人それぞれに30年先をめざして希望を感じる良書である。11本目の新聞連載小説のオファーも早々にくるだろう。