金融政策というのは、本当に上手くいかないね。中国のインフレのことである。緩やかな引き締めは、さっぱり効かず、景気が翳っても、なお加速する。おそらく、バブルが弾け、不況に突入して、ようやく勢いが鎮まるという展開をたどるだろう。まあ、経済運営をしていれば、誰しも経験することなのだよ。
経済というのは、教科書にあるのとは違って、正のフィードバックが働く。物価が上がり始めると、人々は早めに物資を入手しようと行動するので、物価上昇自体が、その理由になってしまう。そうした行動は、短期的には利益があるように見えても、物価が収まった後までの長期を見通せば、不合理なものだ。それでも、人間は、持ち時間に制約があるから、待てずに、そうしてしまうのである。
したがって、ある程度、インフレが加速してしまうと、急激な金融引き締めを行って、フィードバックを断ち切るしかなくなる。フィードバックが消えると、経済は一気に勢いを失うから、不況へと突っ込んでしまう。ちょうど良い頃合に収めるのは至難の業だ。例とすれば、ボルカーFRB議長時代の米国が挙げられよう。
ボルカー議長は、インフレの制圧には成功したものの、景気も非常に悪化したし、不動産融資をしていた貯蓄投資組合(S&L)の破綻も招いた。今の中国で、インフレ制圧を行えば、不動産バブルが弾け、開発を進めてきた地方政府が苦境に陥ることは必定だろう。こういうジレンマにも立たされるわけである。
インフレを抑える有効な手段としては、「元高不況」を演出することであろう。元を大幅に高めれば、輸入物価を冷やし、輸入物資が急増するから、インフレには有効だ。輸出産業の投資と所得の増加に大きくブレーキがかかるが、これも効果を発揮することになる。むろん、輸出企業は不況に見舞われるが、大きな貿易黒字を出している中国には、いずれ必要なことである。
逆に言えば、中国の元高政策は、遅すぎ、小さすぎたのである。日本の1980年代の例を挙げると、前半に輸出主導で成長を果たした後、円高不況に見舞われるものの、それは一時的なもので済み、物価安定と内需拡大によって、大型の好景気を経験した。日本が成功したのは、たまたまであり、目先の企業利益に左右されて、正しいマクロ政策が採れないのは、お互い様かもしれない。
経済が正のフィードバックを持ち、非線形的に動くことは、なかなか分かってもらえない。中国は、正のフィードバックを甘く見て、物価安定への為替レートの重要さを過小評価し、緩い金融政策で何とかしようとして失敗した。日本はと言えば、正のフィードバックによって、輸出から内需へと波及して、自然に成長が加速するルートを、余りに早い緊縮財政で潰している。インフレとデフレで悩みは逆だが、経済が分かっていない点では、同じなのである。
(今日の日経)
住宅ローン金利優遇継続も幅は圧縮。福島第一、廃炉まで数十年。社説・幼保一体改革。短期国債、買越額最高に、金利の日米逆転で。銀行新規制、中とシンガは攻勢。中国ジレンマ、6月消費者物価6.4%上昇。半導体、最先端品にシフト。秋入学、大学国際化実るか。謎かがく・発生過程で基本構造出現。三浦哲郎が描いた東北。読書・インテリジェンス、日本農業の真実、昭和天皇とワシントンを結んだ男。国道45号が全通。シリコンバレーにラーメン。九電、低い問題意識。
※徐々に撤退することが重要。※有利な制度を入れる改革でなければ寄り付かんよ。※日本が金利高になるとは。※中国の自己資本は有効なのかね。※久々に技術で巻き返しだ。※入学時期だけでなく、国際経験をさせることに積極的でないと。※道路の官僚は迅速だ。誰も評価しないから、誉めとくよ。※こういう意識では、改革は不能かも。
経済というのは、教科書にあるのとは違って、正のフィードバックが働く。物価が上がり始めると、人々は早めに物資を入手しようと行動するので、物価上昇自体が、その理由になってしまう。そうした行動は、短期的には利益があるように見えても、物価が収まった後までの長期を見通せば、不合理なものだ。それでも、人間は、持ち時間に制約があるから、待てずに、そうしてしまうのである。
したがって、ある程度、インフレが加速してしまうと、急激な金融引き締めを行って、フィードバックを断ち切るしかなくなる。フィードバックが消えると、経済は一気に勢いを失うから、不況へと突っ込んでしまう。ちょうど良い頃合に収めるのは至難の業だ。例とすれば、ボルカーFRB議長時代の米国が挙げられよう。
ボルカー議長は、インフレの制圧には成功したものの、景気も非常に悪化したし、不動産融資をしていた貯蓄投資組合(S&L)の破綻も招いた。今の中国で、インフレ制圧を行えば、不動産バブルが弾け、開発を進めてきた地方政府が苦境に陥ることは必定だろう。こういうジレンマにも立たされるわけである。
インフレを抑える有効な手段としては、「元高不況」を演出することであろう。元を大幅に高めれば、輸入物価を冷やし、輸入物資が急増するから、インフレには有効だ。輸出産業の投資と所得の増加に大きくブレーキがかかるが、これも効果を発揮することになる。むろん、輸出企業は不況に見舞われるが、大きな貿易黒字を出している中国には、いずれ必要なことである。
逆に言えば、中国の元高政策は、遅すぎ、小さすぎたのである。日本の1980年代の例を挙げると、前半に輸出主導で成長を果たした後、円高不況に見舞われるものの、それは一時的なもので済み、物価安定と内需拡大によって、大型の好景気を経験した。日本が成功したのは、たまたまであり、目先の企業利益に左右されて、正しいマクロ政策が採れないのは、お互い様かもしれない。
経済が正のフィードバックを持ち、非線形的に動くことは、なかなか分かってもらえない。中国は、正のフィードバックを甘く見て、物価安定への為替レートの重要さを過小評価し、緩い金融政策で何とかしようとして失敗した。日本はと言えば、正のフィードバックによって、輸出から内需へと波及して、自然に成長が加速するルートを、余りに早い緊縮財政で潰している。インフレとデフレで悩みは逆だが、経済が分かっていない点では、同じなのである。
(今日の日経)
住宅ローン金利優遇継続も幅は圧縮。福島第一、廃炉まで数十年。社説・幼保一体改革。短期国債、買越額最高に、金利の日米逆転で。銀行新規制、中とシンガは攻勢。中国ジレンマ、6月消費者物価6.4%上昇。半導体、最先端品にシフト。秋入学、大学国際化実るか。謎かがく・発生過程で基本構造出現。三浦哲郎が描いた東北。読書・インテリジェンス、日本農業の真実、昭和天皇とワシントンを結んだ男。国道45号が全通。シリコンバレーにラーメン。九電、低い問題意識。
※徐々に撤退することが重要。※有利な制度を入れる改革でなければ寄り付かんよ。※日本が金利高になるとは。※中国の自己資本は有効なのかね。※久々に技術で巻き返しだ。※入学時期だけでなく、国際経験をさせることに積極的でないと。※道路の官僚は迅速だ。誰も評価しないから、誉めとくよ。※こういう意識では、改革は不能かも。










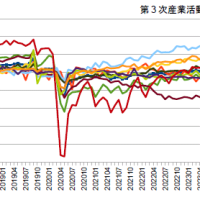















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます