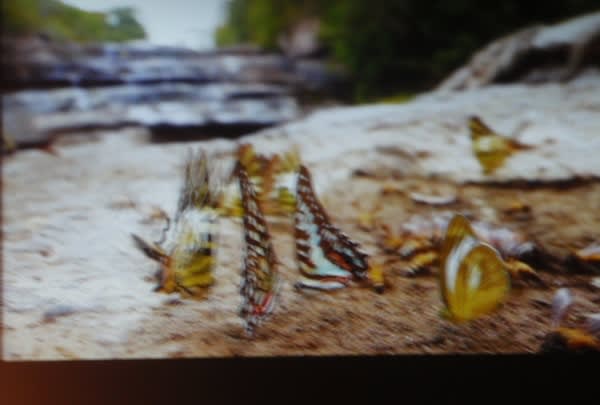今日の花


和水仙は12月からずっと咲いています。ぼちぼち終わりかなと思って撮ってみました。二種あります。


早春の椿はいいものです。
昨日土曜日には久しぶりで松山に行ってきました。せっかく遊びに行くのだからいい天気でと願っていましたが、雨は朝早く上がったものの曇り空で肌寒い一日でした。
今日は皆さんを大島から松山までの船旅にご案内いたします。天気も悪くカメラも海用のコンデジの撮影なので画像はよくありませが一時間の船旅をお楽しみください。
(こんな天気の悪い寒い日にデッキに出ている人は私以外一人もいませんでした。)
柳井から来た伊保田発8時30分の三津浜港行き防予フェリーに乗ります。

和田の辺りでフェリーを追い越しました。

伊保田のフェリー乗り場

丁度同じ時刻に情島渡船も着きました。降りてきたのは子供たちばかりです。

町営情島渡船 せと丸


接岸です


乗船しました


大島 伊保田の集落を離れます

客室はご覧の通り

両源田の沖 海鵜が休んでいます

周防大島の東端 瀬戸ヶ鼻
ここは大島と情島との海峡でとても潮の流れの速い所です。潮の流れの速い所は魚のえさも豊富でとても良い漁場です。シーズンにはフェリーが通行しにくいくらい釣り船が沢山出ます。

大島の東端の南側にある片山島が見えます。この島の周囲もよい漁場で何度か釣りに行ったことがあります。この島には捨てられて野生化したヤギが住んでいて近くから見ると大きな樹木以外はすべて食べられていて公園に木が生えているような下草のない光景に驚かされます。

瀬戸の対岸の情島 集落が少し見えます。

怒和島 遠くに見えるのは中島

二神島

大島は遠ざかって行きます。

由利島 が見えてきました。 小さな島なのに雲のお帽子をかぶっています。


二神島を通り過ぎます。

大島ははるか彼方へ 松山が近くなりました。

手前の釣島と向こうの輿居島が見えてきました。 もうすぐ三津浜港です。


輿居島の急斜面にあるみかん畑です。 ブルーのネットが掛けてあるみかん畑は南津海かもしれません。この島では南津海が作られています。

松山の工場地帯が見えてきました。

反対側は高浜港の方です。


梅津寺(ばいしんじ)方面、以前はここに小さな遊園地があって観覧車が遠くからでも見えたものです。私も子供が小さい頃はよく行きました。

不景気とは言うものの立派なプレジャーボートがたくさん保管されています。

三津浜港


松山市に着きました。いよいよ上陸です。
「なにしに行ったんだ」と気になる方もあるやもしれません。実は蝶々関連です。

やっぱりねー

帰りの船が付きました。午後8時30分
お疲れさまでした。