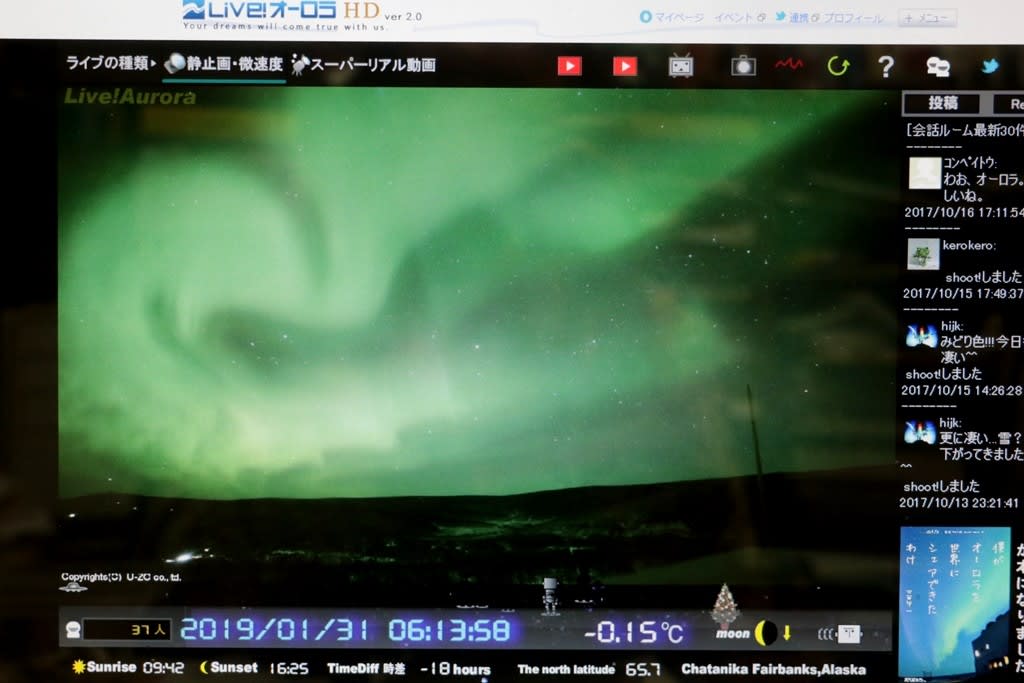今日の花



なんと庭にバラが咲いています。
今日は少し暗いお話です。
一月に一回の眼科の病院に通っていますが、楽しいことでない上に、今日は残念なことに曇り空に時々小雨の降るあいにくの天気でした。
治療について少し詳しくお話しします。今回の治療は先月に続いて2回目の眼球注射です。感染症を防ぐため3日前から抗生剤の目薬(レボフロキサシン)を一日4回さしています。加齢性黄斑変性への治療薬は今は何種類かあるようですが、この度使っている薬はアイリーア硝子体内注射液40mg/mLを0.5mL4週間隔で2回となっています。4週間前に注射した薬は効果があったようで今回の検査では網膜細胞と基底の間に溜まっていた体液は無くなっていました。しかし黄斑中心部に小さなふくらみが残っていて正常な状態にまでは至っていませんでした。今日2回目の注射をして、4週間後に検査を受けねばなりません。その時に正常に戻っていたらしばらく治療はお休みします。この病気はなかなか完治することは無いようでまた再発することはあるようです。困ったことです。皆さんも気を付けてくださいね。
徳山へ通い始めて1年半になります。1年半前にはJR徳山駅は改修中で至る所工事現場という感じでしたが、駅舎は完成して今は駅前の広場がもう少しで出来上がるところまで工事が進んでいます。そして1年半前には周南市市役所が建設工事中でしたがもう建物は完成したようです。駐車場の工事をやっていますがもうすぐすべての工事は終りそうですね。駅から病院までの道を毎度歩きますが、道路わきにいろんな樹種の街路樹が植えてあり季節ごとに楽しむことができました。今は冬ですので落葉樹は裸で面白くありません。常緑樹の街路樹もありますので今日は主にそういうものを撮ってきました。徳山の街で見事な街路樹はやはりみゆき通の中央分離帯に植えてあるクスノキとヒマラヤシーダでしょうか。ヒマラヤシーダはほとんど樹高が10mに達していると思われます。ヒマラヤシーダは本来1本立ちする木なのになぜか途中で一度切ってあって複数本に枝分かれしています。不思議なことに途中で切らないで1本で伸びた部分もあるのですがどうしてでしょうね。交差点に近い所の中央分離帯にはクスノキが植えてあります。クスノキは高く伸びて行く樹ではありません。交差点の空間に向かって枝を広げています。これらの街路樹は戦後に街の整備をした時に植えられたものかもしれませんが大きくよく育っています。当時の街づくりの計画に携わった人たちは100年後の街の姿を考えていたのでしょうか。本当にいい街になったと思います。でも今は車社会ですから運転している時には街路樹を楽しむ余裕はありませんよね。私は1本1本樹を見上げながら歩きます。1年半も徳山の街に通うと通りの樹たちをかなり覚えたような気がします。
加齢性黄斑変性について

若い網膜の組織は強い紫外線にも耐えられるのでしょうが年とってくると問題が起こるようです。

黄斑と呼ばれる網膜の中心部分は光が最も集中するところです。そこの組織が老化してくると血流が悪くなりそれを補うために新生血管と言う脆い血管ができます。網膜と基底部分の間で新生血管が破れて急に出血することがあります。私の場合こうして発病しました。見えている画像の真ん中部分が黒くなり見えなくなりました。これにはびっくりしました。

1月頃の状態です。出血はありませんが黄斑部分が浮き上がっていて基底部との間に水が溜まっていました。
それまでの数か月はカルナクリンという末梢血管を拡張する効果のある薬を服用していました。その飲み薬だけでは症状の改善は見られなかったので、眼球内の硝子体に直接注射する方法に切り替えました。

注射針を眼球に挿しますので傷口からの感染症があると大変なことになります。注射の時にも目を丁寧に洗って殺菌しますが注射の日の前後三日間は抗生剤の目薬を使います。
そして、注射の翌日の朝一番で診察を受けて経過がうまくいっているかどうかを確認します。今朝は地元の眼科のお医者さんに見ていただきました。異常は見られなかったので安心しましたが、お医者さんと雑談しているとお医者さんが目の注射のことを聞いて来ました。お医者さんは患者に目の注射をしたことはあるが自分で目に注射されたことは無いそうで、注射の時に痛いかどうか聞いて来ました。そこで、私はもう7回も注射をしているのでお医者さんに体験談として詳しくお話ししました。先生は私は怖くてとても注射は受けられないと言われたのを聞いて、なんだか変な気持になりました。皆様もできることならこんな体験はしない方がいいですよね。
でもお医者様と現代の医療技術のお蔭で私の目は不自由なく見えています。今回の検査では正常な右目も黄斑変性の左目もともに視力は1.2を保っています。ご安心ください。
治療のお話はこれくらいで置いて、街路樹と周南市の変わって行く姿を撮ってきましたのでちょっとだけ見てください。
駅前広場



みゆき通りと新庁舎






中央分離帯の街路樹





クリスマスごろから正月明けまでこの分離帯の街路樹にはイルミネーションが付けられます。でも私は夜まで街にいませんので点灯したところを見たことはありません。
もう何度、徳山の街をブログに載せたことでしょうね 。