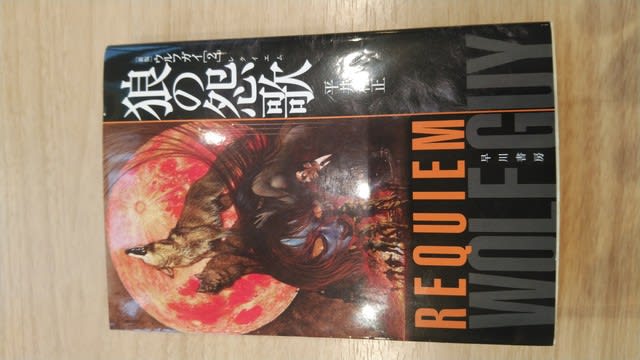昨晩は久しぶりに寝落ち(>_<)。
で、書こうと思っていたことなど。
BJ今月号の鈴木英史先生のコラムがとても印象的。
昨年後藤洋先生からバトンタッチ。
後藤先生のかなり辛口のテイストからどう変わるんだろうと興味深く毎月読んでいたけれど、
鈴木先生もやっぱり辛口w。
パイパーズに掲載された下野竜也氏のインタビュー記事を取り上げて、
コンクール課題曲、特にマーチ(の抱える問題点)についてかなり深く突っ込んでいらっしゃる。
納得することばかりなのだけれど、特に最後の辺りに
「若い世代と話していると曲の『イメージ』の話になることが多い。」とあり、
その「イメージ」について尋ねてみると、
「物語とか情景とか」と返ってくることが多いとか。
そこでは、当然のように理論/理屈(とりわけ和声)が後回しにされがち。
要はそういう曲ばかり演奏し、そういう練習ばかりしている訳だ。
前にも書いたことがあるけれど、例えばシェーンベルクの『主題と変奏』。
言ってみれば理屈優先の曲で、そこには物語性の欠片もないが、逆に言えばそれ故の美しさがある。
かの古典的名曲、ホルストの第一組曲第一楽章も、「シャコンヌ」という形式できっちりとまとめられていて、
そこに物語や情景が絡む要素はない。
一昨年の全日本吹奏楽コンクール大学の部で見事金賞を受賞した創価大学。
指揮はご存じ伊藤康英先生。
課題曲の『ワルツ』がそれは素晴らしい演奏だったので、そのことをFBに書いたところ、
何と伊藤先生ご本人から返信が(驚)!?
確かそこには「理論的に考えられる音楽表現の方法をやり尽くし」た結果、
あのような演奏が生まれたのだ、という内容の事が書いてあったと思う。
作曲家の言葉だけに非常に説得力があり、また十二分に納得できた。
今年の課題曲Ⅲ『ぼくらのインベンション』を書かれた宮川彬良さんも、
この作品は音楽理論(和声)に基づいて書かれた、という旨の発言をされている。
私自身和声に関しては分からないことの方が多いので(苦笑)、未だ勉強中である。
頭でっかちになることなく、一方で感覚に流され過ぎることもない姿勢で、
これからも音楽に臨んでいきたいと思っています。