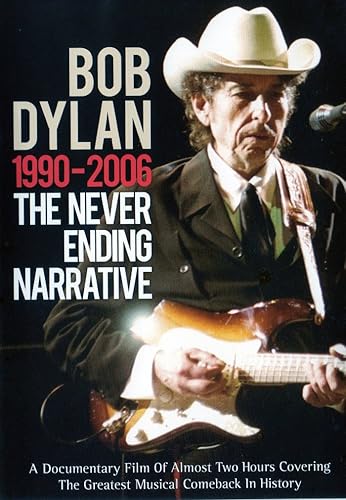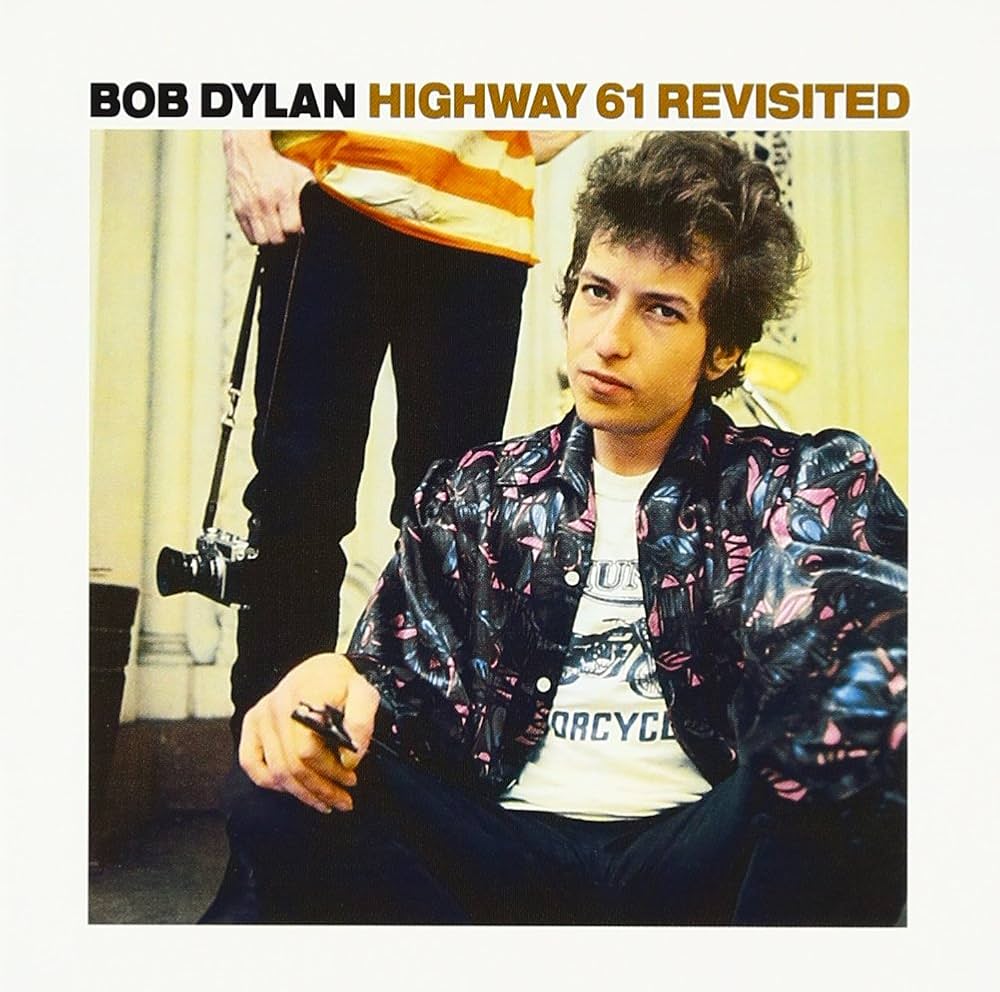ということで石田組。

まず殆ど満員となった客席にビックリ!
追っかけで遠方からきている方々も多そう。

前半はシベリウスとグリーグ。
タイトルこそ聞いたことはあっても、ほとんど知らない曲ばかり。
しかし、面白く聴けたのも確か。
組長が時にリードし、時に引っ込み、そのバランスが絶妙。
こちらに背を向けて弾いているVaのお三方、特にトップの方が凄く引き込んでいるのが伝わってきた。
後半、バルトークの『ルーマニア民俗舞曲』はコンクールの自由曲に取り上げたこともあるのでよく知っているが、
自在なテンポ、うねるようなリズムが圧巻。
組長他の軽妙なMC(笑)を挟んで、映画音楽やロックへ。
弦楽によるロックといえば、遥か昔からクロノスSQで聴いている。

(初めて『紫の煙』を聴いた時はぶっ飛んだっけ【苦笑】)
最近ではモルゴーアSQの『21世紀の精神異常者たち』もお気に入り。

まず殆ど満員となった客席にビックリ!
追っかけで遠方からきている方々も多そう。

前半はシベリウスとグリーグ。
タイトルこそ聞いたことはあっても、ほとんど知らない曲ばかり。
しかし、面白く聴けたのも確か。
組長が時にリードし、時に引っ込み、そのバランスが絶妙。
こちらに背を向けて弾いているVaのお三方、特にトップの方が凄く引き込んでいるのが伝わってきた。
後半、バルトークの『ルーマニア民俗舞曲』はコンクールの自由曲に取り上げたこともあるのでよく知っているが、
自在なテンポ、うねるようなリズムが圧巻。
組長他の軽妙なMC(笑)を挟んで、映画音楽やロックへ。
弦楽によるロックといえば、遥か昔からクロノスSQで聴いている。

(初めて『紫の煙』を聴いた時はぶっ飛んだっけ【苦笑】)
最近ではモルゴーアSQの『21世紀の精神異常者たち』もお気に入り。

石田組が奏でるクイーンやツェッペリンやD.パープルは、全く奇をてらわず、真正面から弦楽器でロックに挑んでいる。
そしてそれが悉くツボにはまっている感じ。
実に気持ちよく盛り上がる。
それにしてもロックと弦楽というのは意外と相性がいいと実感する。
最初に始めたクロノスが如何に偉大だったか(数年前の来日中止が惜しまれてならない…)。
で、石田組の演奏を聴きながら、私が大好きなディランのことをふと考えた。
ディランの曲を弦楽にアレンジできるかな?
ファンとしては、言葉(リリック)なしのディランの曲というのがどうにもイメージできない。
魅力的なメロディーは決して少なくないとは思うのだが、どうかなあ(^^;)?
何はともあれ、アンコール(3曲!)も含めて十二分に楽しませてもらった。

早速組長の音源をあれこれ探しているところ。
まずは正統派の「どクラシック」をきちんと聴いてみようw
PS1 鑑賞終わり↓

LvB:VaとVcのための作品集
かなり渋めの内容だが、演奏は面白い。
LvBがVaのためにこんなにたくさん書いているとは思わなかった。
贔屓目抜きに、ハイドン-モーツァルトーベートーヴェンーシューベルトーシューマンーブラームスと続くドイツ・オーストリア系作曲家の室内楽作品を聴くのは楽しいな(^^)b
PS2 今日届いた音源×2@Amazon↓

まずは正統派の「どクラシック」をきちんと聴いてみようw
PS1 鑑賞終わり↓

LvB:VaとVcのための作品集
かなり渋めの内容だが、演奏は面白い。
LvBがVaのためにこんなにたくさん書いているとは思わなかった。
贔屓目抜きに、ハイドン-モーツァルトーベートーヴェンーシューベルトーシューマンーブラームスと続くドイツ・オーストリア系作曲家の室内楽作品を聴くのは楽しいな(^^)b
PS2 今日届いた音源×2@Amazon↓