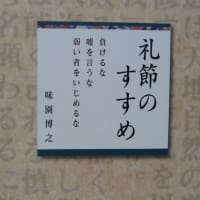第2512号 27.11.13(金)
.
文厥(そ)の祥(しょう)を定む。『詩経』
.
人間、文徳を修めていれば、自然その人に祥、すなわちしあわせがきめられていく。182
.
【コメント】解説では、〈人間、文徳を修めて〉とありますが、人間を国家と読み替えてもいいのではないでしょうか。
今朝のテレビ報道でも、オリンピック選手のドーピング問題が取りざたされていました。国ぐるみ、国家総動員で違法行為を平然と行い、そして御山の大将は個人がしたことであって、国家には関係がないと嘯いています。
.
御山の大将が、国ぐるみでないと幾ら弁明しようが、独裁国家である以上、世界中の人々はWADAを信用していることでしょう。
.
それと対比して私が、人間の師表と仰いでいる菅原兵治先生、菅臥牛先生だったら天道に背くことはしてはならないと厳しい訓戒をすることでしょう。『大学味講』『農士道』等々、ブログでもご紹介させて戴き、その英明さに蒙を啓かせられています。これこそが大和の国が誇る、「民が主」の国でありましょう。これは野党が言う「民主」とは異なるのです。
.
私が電電に入社した頃は社会主義協会というのが巾を聞かせていたものです。あれから半世紀、それらを主導した労組のトップで人格的に括目に値する人格者と思える人間は皆無でした。ドーピング問題で槍玉にあげられている御山の大将と五十歩百歩でした。
.
昨夜の空手道の御稽古も真面目に取り組みました。『南洲翁遺訓』の子供版・「誓いのことば」を拝誦するようになってから、子供たちが生き生きとしてきたように思えるのです。
.
菅臥牛先生は途方もない偉い先生なのですが、私が毎回、菅臥牛先生と菅原先生のことをお話するものですから、子供たちのあこがれの的になっているようです。
.
明日は超、超多忙の一日になるようです。早朝から「暁の学問館」、そして空手道指導、そして宮川小学校児童クラブでの『南洲翁遺訓』のご紹介、そして帰宅したら本部道場の空手道指導ということになっています。70年間私のメニューはこういうことでした。
----------------
『臥牛菅実秀』(第50回)
.
同じ安政四年、世子忠恕は政事見習いとして荘内に下り、実秀もこれに従って鶴岡に帰ってきた。忠恕は多くの士卒をひきいて荘内の山野を馳駆して狩をし、また藩校致道館の学生に課題を与えて詩文を募るなど、将来の藩主としての器を磨いていた。忠恕は宋の司馬光が撰んだ『資治通鑑』二百九十四巻を愛読して、人物を観る眼を養っていたと伝えられており、忠恕に寄せる一潘の期待も非常に深かったのであるが、翌安政五年、わづか二十才で江戸で病んで没した。
実秀は、その二十代のすべてを小姓となり近習となって仕えた世子を失う悲嘆を味わわなければならなかった。
------------------
『論語』(第445)
.
子曰はく、色にして内荏(うちじん)なるは、諸を小人に譬ふれば、其れ猶穿ユの盗の如きか。
.
孔子が言うには、『うわべばかり偉そうに構えていて内心卑怯未練の人物は、これを細民に譬えてみると、平気な顔をしながら内心ビクビクもののコンコン泥棒のようなものじゃ。』
--------------
『農士道』(第327回)
.
日本精神と「ひの本」の心であるといったが、そはかかる意味に於てのものであって、西洋的思想が主として「ひの末」する作用なるに対して、日本精神は「ひの本」するはたらきに其の特長を有するといふことなのである。然し日本精神は「ひの本」するはたらきを特徴とするからといって、「ひの末」のはたらきが全然無いといふのでは勿論ない。若し「ひの本」のはたらきのみで、全然「ひの末」のはたらきが無いとしたならば、かかるものは已に造化の生ける生命より離脱せる残骸の化石に過ぎない。
--------------
山本七平著『帝王学』より
.
新釈漢文大系『貞観政要』は、十五年前購入した際読んだのですが、昨晩は『帝王学』を繙いてみました。その中の「六正・六邪」の人物評価法の一部をご紹介致します。
.
「六正」とは、1.聖臣、2.良臣、3.忠臣、4.智臣、5.貞臣、6.直臣とあります。詳細の説明は略します。
「六邪」とは、1.見臣、2.諛臣、3.姦臣、4.讒臣、5.賊臣、6.亡国の臣とあります。
5.賊臣とは、自分に都合のよいように基準を定め、自分中心の派閥をつくって自分を富ませ、勝手に主人の命令を曲げ、それによって自分の地位や名誉を高める。これが「賊臣「である。
.
「賊臣」の解説を読み、遠近の周囲にこのような人がいるのではと、思いを巡らしています。
『南洲翁遺訓』を座右に置く我々は、刊行の精神を冒涜するようなことをしてはならないと肝に銘じています。
-------------
.
文厥(そ)の祥(しょう)を定む。『詩経』
.
人間、文徳を修めていれば、自然その人に祥、すなわちしあわせがきめられていく。182
.
【コメント】解説では、〈人間、文徳を修めて〉とありますが、人間を国家と読み替えてもいいのではないでしょうか。
今朝のテレビ報道でも、オリンピック選手のドーピング問題が取りざたされていました。国ぐるみ、国家総動員で違法行為を平然と行い、そして御山の大将は個人がしたことであって、国家には関係がないと嘯いています。
.
御山の大将が、国ぐるみでないと幾ら弁明しようが、独裁国家である以上、世界中の人々はWADAを信用していることでしょう。
.
それと対比して私が、人間の師表と仰いでいる菅原兵治先生、菅臥牛先生だったら天道に背くことはしてはならないと厳しい訓戒をすることでしょう。『大学味講』『農士道』等々、ブログでもご紹介させて戴き、その英明さに蒙を啓かせられています。これこそが大和の国が誇る、「民が主」の国でありましょう。これは野党が言う「民主」とは異なるのです。
.
私が電電に入社した頃は社会主義協会というのが巾を聞かせていたものです。あれから半世紀、それらを主導した労組のトップで人格的に括目に値する人格者と思える人間は皆無でした。ドーピング問題で槍玉にあげられている御山の大将と五十歩百歩でした。
.
昨夜の空手道の御稽古も真面目に取り組みました。『南洲翁遺訓』の子供版・「誓いのことば」を拝誦するようになってから、子供たちが生き生きとしてきたように思えるのです。
.
菅臥牛先生は途方もない偉い先生なのですが、私が毎回、菅臥牛先生と菅原先生のことをお話するものですから、子供たちのあこがれの的になっているようです。
.
明日は超、超多忙の一日になるようです。早朝から「暁の学問館」、そして空手道指導、そして宮川小学校児童クラブでの『南洲翁遺訓』のご紹介、そして帰宅したら本部道場の空手道指導ということになっています。70年間私のメニューはこういうことでした。
----------------
『臥牛菅実秀』(第50回)
.
同じ安政四年、世子忠恕は政事見習いとして荘内に下り、実秀もこれに従って鶴岡に帰ってきた。忠恕は多くの士卒をひきいて荘内の山野を馳駆して狩をし、また藩校致道館の学生に課題を与えて詩文を募るなど、将来の藩主としての器を磨いていた。忠恕は宋の司馬光が撰んだ『資治通鑑』二百九十四巻を愛読して、人物を観る眼を養っていたと伝えられており、忠恕に寄せる一潘の期待も非常に深かったのであるが、翌安政五年、わづか二十才で江戸で病んで没した。
実秀は、その二十代のすべてを小姓となり近習となって仕えた世子を失う悲嘆を味わわなければならなかった。
------------------
『論語』(第445)
.
子曰はく、色にして内荏(うちじん)なるは、諸を小人に譬ふれば、其れ猶穿ユの盗の如きか。
.
孔子が言うには、『うわべばかり偉そうに構えていて内心卑怯未練の人物は、これを細民に譬えてみると、平気な顔をしながら内心ビクビクもののコンコン泥棒のようなものじゃ。』
--------------
『農士道』(第327回)
.
日本精神と「ひの本」の心であるといったが、そはかかる意味に於てのものであって、西洋的思想が主として「ひの末」する作用なるに対して、日本精神は「ひの本」するはたらきに其の特長を有するといふことなのである。然し日本精神は「ひの本」するはたらきを特徴とするからといって、「ひの末」のはたらきが全然無いといふのでは勿論ない。若し「ひの本」のはたらきのみで、全然「ひの末」のはたらきが無いとしたならば、かかるものは已に造化の生ける生命より離脱せる残骸の化石に過ぎない。
--------------
山本七平著『帝王学』より
.
新釈漢文大系『貞観政要』は、十五年前購入した際読んだのですが、昨晩は『帝王学』を繙いてみました。その中の「六正・六邪」の人物評価法の一部をご紹介致します。
.
「六正」とは、1.聖臣、2.良臣、3.忠臣、4.智臣、5.貞臣、6.直臣とあります。詳細の説明は略します。
「六邪」とは、1.見臣、2.諛臣、3.姦臣、4.讒臣、5.賊臣、6.亡国の臣とあります。
5.賊臣とは、自分に都合のよいように基準を定め、自分中心の派閥をつくって自分を富ませ、勝手に主人の命令を曲げ、それによって自分の地位や名誉を高める。これが「賊臣「である。
.
「賊臣」の解説を読み、遠近の周囲にこのような人がいるのではと、思いを巡らしています。
『南洲翁遺訓』を座右に置く我々は、刊行の精神を冒涜するようなことをしてはならないと肝に銘じています。
-------------