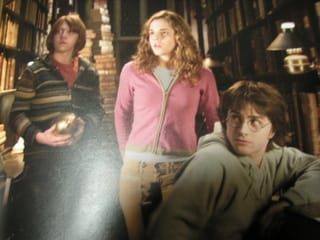同志社女子大学音楽学科オペラクラスの卒業公演「フィガロの結婚」を、京田辺キャンパスにある新島記念講堂に、内モンゴルからのかわいい留学生、ナランゴリと一緒に鑑賞に行きました。
毎年、卒業年度の学生が出演するのだが、衣装、舞台、装置、道具、照明などと歌の伴奏のオーケストラ、その他を合わせた総合芸術としてのオペラとして、多くの音楽科の学生らと卒業生、大阪音大の有志やプロの声楽家たちの協力も得て、公演がなされているのである。
昨年は、フィガロの結婚に出演していた女子学生の一人が、その後の痛ましいJR福知山線の電車脱線転覆事故で亡くなったこともあって、今年で19回目の公演は例年と違う思いも感じられた。
この「フィガロの結婚」はモーツァルトの作曲であり、今年は生誕250周年ということもあり、いっそう出演者や関係者に強い思いがあったのではないかと、観客席からも感じていたのである。
伯爵をはじめ、フィガロ、バルトロ、アントニオなどの男性役は、大学の先生や声楽家たちが演じているのだが、女性役の伯爵夫人、スザンナ、ケルビーノたちは、女子学生たちが何人かで一役を演じているのである。
四幕に及ぶ長時間の舞台は登場人物の複雑な関係性とストーリーの難解さもあって、まだ日本に来て一年しかたっていない留学生には、日本語の歌の歌詞もわかりにくく理解できず上演途中も、つまらなそうな表情になることがあった。
舞台鑑賞を終えてから、友人と一緒にお茶をしてから、ナランゴリと我が家に戻り、前から頼まれていた「五線譜学習」を、家人がピアノで彼女にイロハから教えることとなった。
中国内モンゴル出身のナランゴリは、あの馬頭琴も演奏するし歌も歌うし、モンゴルやウイグルの民族舞踏もする音楽好きなのだが、中国の故郷での学生時代や舞踏芸術団で習ったり使用した楽譜は、五線譜ではなく数字を書いた独特の特殊な譜面だったそうであり、西洋式の五線譜音階がよく読めないのだそうだ。
そこでピアノを使って、初めてト音記号や音符の長さや音階などを、実際に音を出しながら学ぶ機会となったのである。
白い鍵と黒い鍵の位置を確認しながら、ハ長調のドを確認してドレミファを順に弾き、音と共に音符で表記しながら♯や♭や休符も学んだ。
日本の子ども達は誰もが小学校の音楽の授業で教えられ、五線譜の音符は読めるはずなのだが、意外や中国での音楽教育は少し前までは、まだ五線譜を使っていなかったのである。
彼女は日本で日本語を学び、来年には日本の大学で教育を受けて、いずれは故郷に帰って、日本語や音楽を教えたいとの夢を持っているので、現代音楽の表記方法である五線譜を学ぶことは必要なのであった。
「フィガロの結婚」の日本語によるオペラは、まだ難解だったようだが、まず五線譜と音楽記号や呼称をピアノで学ぶことから、より音楽の幅が彼女の脳裏と心に広がっていくことだろうと、私は楽しみに見守っていくつもりである。
ひょっとしたら、「フィガロの結婚」以上に、彼女にとっては、初めての五線譜の音階も難しいのかもしれない。
毎年、卒業年度の学生が出演するのだが、衣装、舞台、装置、道具、照明などと歌の伴奏のオーケストラ、その他を合わせた総合芸術としてのオペラとして、多くの音楽科の学生らと卒業生、大阪音大の有志やプロの声楽家たちの協力も得て、公演がなされているのである。
昨年は、フィガロの結婚に出演していた女子学生の一人が、その後の痛ましいJR福知山線の電車脱線転覆事故で亡くなったこともあって、今年で19回目の公演は例年と違う思いも感じられた。
この「フィガロの結婚」はモーツァルトの作曲であり、今年は生誕250周年ということもあり、いっそう出演者や関係者に強い思いがあったのではないかと、観客席からも感じていたのである。
伯爵をはじめ、フィガロ、バルトロ、アントニオなどの男性役は、大学の先生や声楽家たちが演じているのだが、女性役の伯爵夫人、スザンナ、ケルビーノたちは、女子学生たちが何人かで一役を演じているのである。
四幕に及ぶ長時間の舞台は登場人物の複雑な関係性とストーリーの難解さもあって、まだ日本に来て一年しかたっていない留学生には、日本語の歌の歌詞もわかりにくく理解できず上演途中も、つまらなそうな表情になることがあった。
舞台鑑賞を終えてから、友人と一緒にお茶をしてから、ナランゴリと我が家に戻り、前から頼まれていた「五線譜学習」を、家人がピアノで彼女にイロハから教えることとなった。
中国内モンゴル出身のナランゴリは、あの馬頭琴も演奏するし歌も歌うし、モンゴルやウイグルの民族舞踏もする音楽好きなのだが、中国の故郷での学生時代や舞踏芸術団で習ったり使用した楽譜は、五線譜ではなく数字を書いた独特の特殊な譜面だったそうであり、西洋式の五線譜音階がよく読めないのだそうだ。
そこでピアノを使って、初めてト音記号や音符の長さや音階などを、実際に音を出しながら学ぶ機会となったのである。
白い鍵と黒い鍵の位置を確認しながら、ハ長調のドを確認してドレミファを順に弾き、音と共に音符で表記しながら♯や♭や休符も学んだ。
日本の子ども達は誰もが小学校の音楽の授業で教えられ、五線譜の音符は読めるはずなのだが、意外や中国での音楽教育は少し前までは、まだ五線譜を使っていなかったのである。
彼女は日本で日本語を学び、来年には日本の大学で教育を受けて、いずれは故郷に帰って、日本語や音楽を教えたいとの夢を持っているので、現代音楽の表記方法である五線譜を学ぶことは必要なのであった。
「フィガロの結婚」の日本語によるオペラは、まだ難解だったようだが、まず五線譜と音楽記号や呼称をピアノで学ぶことから、より音楽の幅が彼女の脳裏と心に広がっていくことだろうと、私は楽しみに見守っていくつもりである。
ひょっとしたら、「フィガロの結婚」以上に、彼女にとっては、初めての五線譜の音階も難しいのかもしれない。