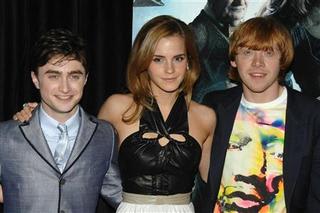昨日の夜、我が夫婦にとっての今年のクリスマスプレゼントとして、劇団四季が演ずるミュージカル最新作『サウンド・オブ・ミュージック』を大阪駅近くのハービスENT7階にある「大阪四季劇場」に見に行きました。
50年近く前になったと思われる、あの有名なジュリー・アンドリュースが主演した家庭教師マリアと、オーストリアの海軍大佐のお父さんと七人の子どもたちの「トラップ・ファミリー」が織り成す、悲喜こもごものテンポのあるストーリーと音楽を中心に危機を乗り越えていく物語として、本格的なミュージカル映画として日本でも公開されて以来、ペギー葉山さんが日本語訳として作詞した「ドレミの歌」をはじめとする親しみのある名曲を中心に大人気となった作品であるが、原作は向こうの作品であるにもなのにも関わらず、とっても素敵で温かな心地よい展開で、日本人によるプロミュージカル専門劇団の舞台として実現したのである。
劇団四季によるミュージカルの舞台は、ほぼ十年前から数回鑑賞しているのだけれど、今回ほど前もって舞台のイメージを抱きながら劇場へと足を運んだことはなかったのではないかと思えるほど、インターネットのHPなどの前評判や鑑賞した人たちの感想なども事前に見ていたこともあって、期待は大という感じであったのだが、期待に違わずといった約2時間半のパフォーマンスを楽しませていただいた。
私たちは、以前にも劇団四季によるミュージカルとして、「ライオンキング」に始まり、「美女と野獣」「オペラ座の怪人」「夢から醒めた夢」「アイーダ」「ウエストサイドストーリー」を鑑賞した覚えがあり、劇団四季の演ずるミュージカルは大好きで一定の信頼と期待をいつも持って行くのだが、事前にチケットを購入して今回も同様な気持ちと共に会場へと向かったのだが、今回は初めてチケットレスのインターネット予約で、携帯電話に返信された予約完了のメールは来ていたが、当日会場受付で果たしてうまく入場できるのかと妻は心配していたらしく、入場までは少し緊張気味であった。
久しぶりの四季のミュージカル鑑賞だったが、前から5列目くらいの席だったこともあって、よく舞台が見えたこともあってか、たぶん7作目だと思われるこの「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台は、ストーリーの親しみやすさ、分かりやすさも手伝って、鑑賞後の感動は今までにないほど素晴らしいものであり、とても楽しく心温まる観劇となった。
当然、あの有名なサウンドの歌の数々が舞台では次から次へと歌われたのだが、マリア先生を演じた笠松はるさん、トラップ大佐の村俊英さんを中心に、七人兄弟の長女リーズルを演じた脇野綾弓さんや修道院長を演じた秋山知子さんたちの歌は、とても心を洗われるとでも言っていいほどの透き通った歌声と声量、そして強く大きな意思を感じるほどの響きがあって、他の子どもたちのかわいくて一生懸命の歌声とは、また異なったプロの歌い手としての誇りと自信がみなぎっている様で、さすが四季の劇団員としてのたくさんの練習と鍛えられた日々を感じるほど、見事な出来栄えであった。
この様な素晴らしい感動の舞台を制作する劇団四季の中心に、あの浅利慶太さんがいるのだが、この「サウンド・オブ・ミュージック」が大阪で日本人によるミュージカルとしてと公演されるに至るまでに、長年の準備と共に、多くのクリエイティブスタッフ、すなわちリチャード・ロジャース作曲、オスカー・ハマースタイン2世はもとより、脚本、オーケストラ、ダンス、振り付け、舞台装置や衣装、デザイン、そして演出という多くのスタッフや技術、専門家が指導し、制作がされたことを思うと、舞台の完成度が多くの観客の感動を呼ぶに至っていることは自明の理だと感心するものであった。
最後に、カーテンコールの後に会場の観客も含めて皆で歌った「ドレミの歌」をはじめ、あのスイスやオーストリアの山々に咲く「エーデルワイス」を思わせる曲、そして、「マリア」「私のお気に入り」「「もうすぐ17歳」「さよなら またね」「すべての山へ登れ」など、数々の名曲が脳裏に走馬灯の如く蘇って来る感じで、帰宅途中の電車でも、そして翌朝を迎えた今朝の起き抜けにも、拙いけれどメロディーを今にも口ずさんでしまいたいほどの衝動を覚えるほどの感動であったことは間違いない。
余談だが、公演終了後のカーテンコールでは、何度も舞台狭しと出演者が登場し、お礼の挨拶を繰り返していたのだが、あのかわいらしい七人兄弟の長女リーズルを除く6人の子どもたちは、最後の舞台には姿を見せなかったので、少し寂しいというか物足りなさを感じたのだが、18歳未満の子どもたちの深夜労働を禁ずる法のためなのかと納得しながら、やはり「サウンド・オブ・ミュージック」の主役は、マリア先生と7人の子どもたちであると強く感じたのであった。
50年近く前になったと思われる、あの有名なジュリー・アンドリュースが主演した家庭教師マリアと、オーストリアの海軍大佐のお父さんと七人の子どもたちの「トラップ・ファミリー」が織り成す、悲喜こもごものテンポのあるストーリーと音楽を中心に危機を乗り越えていく物語として、本格的なミュージカル映画として日本でも公開されて以来、ペギー葉山さんが日本語訳として作詞した「ドレミの歌」をはじめとする親しみのある名曲を中心に大人気となった作品であるが、原作は向こうの作品であるにもなのにも関わらず、とっても素敵で温かな心地よい展開で、日本人によるプロミュージカル専門劇団の舞台として実現したのである。
劇団四季によるミュージカルの舞台は、ほぼ十年前から数回鑑賞しているのだけれど、今回ほど前もって舞台のイメージを抱きながら劇場へと足を運んだことはなかったのではないかと思えるほど、インターネットのHPなどの前評判や鑑賞した人たちの感想なども事前に見ていたこともあって、期待は大という感じであったのだが、期待に違わずといった約2時間半のパフォーマンスを楽しませていただいた。
私たちは、以前にも劇団四季によるミュージカルとして、「ライオンキング」に始まり、「美女と野獣」「オペラ座の怪人」「夢から醒めた夢」「アイーダ」「ウエストサイドストーリー」を鑑賞した覚えがあり、劇団四季の演ずるミュージカルは大好きで一定の信頼と期待をいつも持って行くのだが、事前にチケットを購入して今回も同様な気持ちと共に会場へと向かったのだが、今回は初めてチケットレスのインターネット予約で、携帯電話に返信された予約完了のメールは来ていたが、当日会場受付で果たしてうまく入場できるのかと妻は心配していたらしく、入場までは少し緊張気味であった。
久しぶりの四季のミュージカル鑑賞だったが、前から5列目くらいの席だったこともあって、よく舞台が見えたこともあってか、たぶん7作目だと思われるこの「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台は、ストーリーの親しみやすさ、分かりやすさも手伝って、鑑賞後の感動は今までにないほど素晴らしいものであり、とても楽しく心温まる観劇となった。
当然、あの有名なサウンドの歌の数々が舞台では次から次へと歌われたのだが、マリア先生を演じた笠松はるさん、トラップ大佐の村俊英さんを中心に、七人兄弟の長女リーズルを演じた脇野綾弓さんや修道院長を演じた秋山知子さんたちの歌は、とても心を洗われるとでも言っていいほどの透き通った歌声と声量、そして強く大きな意思を感じるほどの響きがあって、他の子どもたちのかわいくて一生懸命の歌声とは、また異なったプロの歌い手としての誇りと自信がみなぎっている様で、さすが四季の劇団員としてのたくさんの練習と鍛えられた日々を感じるほど、見事な出来栄えであった。
この様な素晴らしい感動の舞台を制作する劇団四季の中心に、あの浅利慶太さんがいるのだが、この「サウンド・オブ・ミュージック」が大阪で日本人によるミュージカルとしてと公演されるに至るまでに、長年の準備と共に、多くのクリエイティブスタッフ、すなわちリチャード・ロジャース作曲、オスカー・ハマースタイン2世はもとより、脚本、オーケストラ、ダンス、振り付け、舞台装置や衣装、デザイン、そして演出という多くのスタッフや技術、専門家が指導し、制作がされたことを思うと、舞台の完成度が多くの観客の感動を呼ぶに至っていることは自明の理だと感心するものであった。
最後に、カーテンコールの後に会場の観客も含めて皆で歌った「ドレミの歌」をはじめ、あのスイスやオーストリアの山々に咲く「エーデルワイス」を思わせる曲、そして、「マリア」「私のお気に入り」「「もうすぐ17歳」「さよなら またね」「すべての山へ登れ」など、数々の名曲が脳裏に走馬灯の如く蘇って来る感じで、帰宅途中の電車でも、そして翌朝を迎えた今朝の起き抜けにも、拙いけれどメロディーを今にも口ずさんでしまいたいほどの衝動を覚えるほどの感動であったことは間違いない。
余談だが、公演終了後のカーテンコールでは、何度も舞台狭しと出演者が登場し、お礼の挨拶を繰り返していたのだが、あのかわいらしい七人兄弟の長女リーズルを除く6人の子どもたちは、最後の舞台には姿を見せなかったので、少し寂しいというか物足りなさを感じたのだが、18歳未満の子どもたちの深夜労働を禁ずる法のためなのかと納得しながら、やはり「サウンド・オブ・ミュージック」の主役は、マリア先生と7人の子どもたちであると強く感じたのであった。