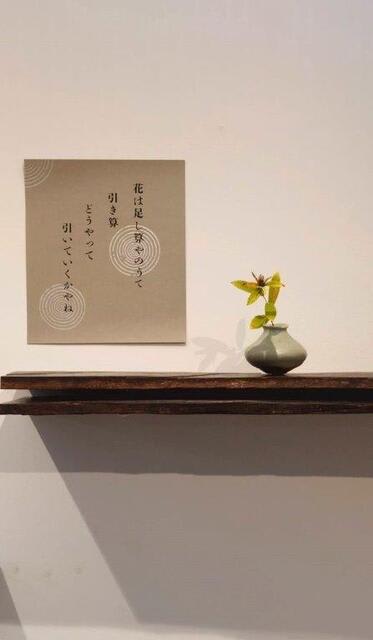どうにも下町に惹かれてしまうのは自分に流れる血脈というものであろう。
この日は両国。江戸のころ両国広小路というと見世物や芝居小屋があり、少し離れるとお屋敷街があったそうで、本所松坂町の吉良邸などもその一つ。

この日は両国。江戸のころ両国広小路というと見世物や芝居小屋があり、少し離れるとお屋敷街があったそうで、本所松坂町の吉良邸などもその一つ。

回向院の前が広小路。そもそも火災のために大きく道をとった。
火事と喧嘩は江戸の華なんていうが、それほど多かったのだろう。
この前を右手、西へと歩けばすぐに両国橋、その下を流れる隅田川。
その手前にあるのがどぜうの店「桔梗屋」。


関西にゃこのどぜうというものが無い。なんで他に旨いものがいっぱいあるのに、よりによって泥鰌など食わなきゃならんのや、というところか。ときに見ることはあっても、もっと細っこい釘のような泥鰌だった気がする。
昔から鰻は高価なものと決まっていたから、庶民の知恵として安価で精の付くどぜうが江戸東京の暮らしの一部に入り込んでいたのだろう。

酒で締めて、あらかじめ下煮してあるから火が通ったらすぐ食える。
千住ネギを山盛り鍋に放り込むのがコツ。どぜうとタレのうまみでネギを
火事と喧嘩は江戸の華なんていうが、それほど多かったのだろう。
この前を右手、西へと歩けばすぐに両国橋、その下を流れる隅田川。
その手前にあるのがどぜうの店「桔梗屋」。


関西にゃこのどぜうというものが無い。なんで他に旨いものがいっぱいあるのに、よりによって泥鰌など食わなきゃならんのや、というところか。ときに見ることはあっても、もっと細っこい釘のような泥鰌だった気がする。
昔から鰻は高価なものと決まっていたから、庶民の知恵として安価で精の付くどぜうが江戸東京の暮らしの一部に入り込んでいたのだろう。

酒で締めて、あらかじめ下煮してあるから火が通ったらすぐ食える。
千住ネギを山盛り鍋に放り込むのがコツ。どぜうとタレのうまみでネギを
食うようなものだ。金のない時分、ネギ・タレ・ネギ・タレでいつまでも
ねばったものだ。


さき鍋っていって開きになったものもあるが、アタシは丸鍋が好み。

鯉のあらいは美しい

なぜか淡水魚の店だがさらしくじらなんてのがある。
ちょっと口を変えるのにいい。酢味噌。

鰻の肝焼き。山椒をふりかけて

名代の玉子焼き。うやうやしく蓋物なんぞで出てくる。
この甘めの味付けがいかにも東京の老舗っぽい

柳川なべと、どぜう汁で白いご飯にした。
どぜう汁、好きなんだ。

若い時分は駒形どぜう、飯田屋によく行った。
どぜうにも酒にも興味の薄い連れ合いは、うな重

東京っぽく、べったら漬け
こういう甘味もおつなもの。

うちの会ったこともない爺さんは本所のお屋敷に奉公していたそうで、
近年この男の行状がいろいろ明らかになってきた。周りに迷惑をかけ、
結局奉公先もクビになり、 東京にもいられなくなり処払い同然に
名古屋から関西へと逃げ落ちて来たらしい。
爺さんも若き日は洋々と本所両国深川界隈を肩で風切っていただろう。
どぜうでも食って酒かっくらっては怪気炎をあげていただろうから、
子孫からのオマージュでもある。あの世で達者でやってくれぃ。

できうることなら、そんな爺さんの性格を受け継がないまま、平穏無事に
人生を終えたいものである。
名古屋から関西へと逃げ落ちて来たらしい。
爺さんも若き日は洋々と本所両国深川界隈を肩で風切っていただろう。
どぜうでも食って酒かっくらっては怪気炎をあげていただろうから、
子孫からのオマージュでもある。あの世で達者でやってくれぃ。

できうることなら、そんな爺さんの性格を受け継がないまま、平穏無事に
人生を終えたいものである。