今日11月25日は憂国忌(三島由紀夫の命日)ということで、コチラのサイトにその案内が載っていましたが、どんな人たちが、どれくらい集まったのでしょうかねー?
同サイトには、その実行委員会の発起人のリストもありましたが、いかにもという名前が多々ある中で、「あれ、この人も」という名前もチラホラ(立松和平とか)。
私ヌルボ、個人的に思い起こせば、三島事件のニュース自体にはさほど衝撃を受けませんでした。
それよりも、1970年の同じ日に、ニューヨークのイーストリヴァーでアルバート・アイラーの死体が発見されたという事件の方がずっとショッキングだったと思います。
※もしかして、今も命日にアイラー特集をやってるようなジャズ喫茶があるのでは、と思って探したら、案の定ありましたね。稲毛のJazz Spot CANDYという店。(→コチラ。) 毎年やってるようです。
翌1971年5月3日には高橋和巳39歳で世を去りました。・・・いろんなことが思い出されます。
それから40年あまり経った今、世の中はどう変わったのでしょうか?
「この国には何でもある。本当にいろいろなものがあります。だが、希望だけがない」(村上龍の「希望の国のエクソダス」)という認識は、とっくに常識化してしまったようです。
11月20日に届いた「週刊文春」メールマガジン。アンケートの設問が「野田佳彦、安倍晋三、石原慎太郎 あなたが総理にふさわしいと思うのは誰ですか?」というもの。
以前流行った「究極の選択」みたいです。「俺を怒らせたいのかっ!?」って感じですねー。・・・しかしこれが現実。
韓国でも大統領選挙が間近に迫っています。(12月19日投票) しかし木村幹神戸大教授のtwitter(→コチラ)によると、今回の特色は「盛り上がっていないこと」だそうです。23日出馬取り止めを発表した安哲秀氏にたいする「シンドローム」も、日本のマスコミの思い入れ(?)ほどには盛り上がってなかったようで・・・。韓国の政治風土も、近年大きく変わってきているようです。
日本でも、すでにポピュリズムが効かなくなってきているという観測もあるようです。はや橋下市長も賞味期限が切れかかってるという気配も漂ってきている、かな?
マスコミもしょーもない政党の離合集散をくだくだしく追っかけてばかりいないで、「原発」「改憲」「TPP」等々の争点についてわかりやすく解説するとともに、各立候補(予定)者がそれらにどんな意見を持っているかをきっちり伝えてほしい、と切に望んでいます。(同じ政党内でもバラバラのようだし、個人ごとにリストを作っておくれでないかい?)
さて、今日の「毎日新聞」の読書欄を紹介、・・・する前に、気持ちが明るくなった記事をまずとりあげておきます。
<隣国のホンネ・日中民間対話>シリーズの第3回で、「白か黒か、未熟な世論 人権活動家・何培蓉さんに聞く」というもの。(今のところ→コチラで読むことができます。) 何培蓉(か・ばいよう)さんは盲目の人権活動家・陳光誠の脱出劇を支えた人権活動家の女性です。もともと英語教師で「ごく普通の中国人でした」という彼女は決して「妥協を排する闘士」ではなく、「民主の実現は、妥協するプロセスであるべきだと思うのです」と語っています。また反日デモについても、「人々が政治に参加することは良い現象ですが、(略奪行為などの)過激行為が起きたことは世論が未熟な証拠です」とも。(反中国で熱くなってる一部の日本人の対極ではないですか。)
・・・私ヌルボ、民主主義の少年期における清新さを彼女に感じました。民主主義の老年期にある日本の私たちは、昔を懐かしむか、「大人になったら(そんなに素晴らしいものでもないことが)わかるよ」とシニカルな言をとばすしかないのでしょうか・・・。
ほとんど記事にしない時事放談めいた文章をたらたら書き連ねてしまいました。
やっと本題、「毎日新聞」の読書欄です。
※とりあえずは「毎日jp」で読むことができますが、恒久的には→コチラのサイトで朝・読・毎・産の4紙の書評のバックナンバーを読むことができます。
今回は、伊東光晴先生による「ノーベル経済学賞の40年 上・下」(トーマス・カリアー著)の評はとてもためになったし、ヌルボが目を瞠った「ひとたばの手紙から」を著した尊敬すべき俳人・宇多喜代子さんが「今週の本棚:好きなもの」で好きなものとして「絵巻・緑茶・宝塚歌劇」の3つをあげていたのも興味深く読みました。しかし、17歳の時に見た小林一三の眼光を記憶に留めているとはねー・・・。
で、ようやくタイトルに掲げた尹相仁ほか著、舘野・蔡星慧訳「韓国における日本文学翻訳の64年」(出版ニュース社.4200円)について。この本の説明文だけで知らなかった重要な事実が次の2点。
①日本文学が戦後、韓国に再登場するのは1960年の4月革命以後。強力な排日政策を進めていた李承晩が失脚して対日文化政策が変化したため。読み物に飢えていた一般読者が日本文学の復権を求め、出版資本がそれに応えた。
②60年代半ばに三浦綾子「氷点」がベストセラーになった。三浦人気は、戦後にキリスト教が韓国社会に対して果たした役割とも関わる。
※三浦綾子の小説が韓国で多くの読者を得たことは知っていましたが、少し前に本ブログ記事で紹介した浅見雅一・安廷苑「韓国とキリスト教」(中公新書)にはそのことは書いてなかったし、私ヌルボも思いつきませんでした。
また、
③90年代以降の経済成長後の韓国の若者たちが、村上春樹作品の主人公たちに自身の自画像や理想形を見出した。
・・・という指摘もあるそうです。
そして、翻訳された作品の目録も付いているそうで、これはなかなか意義のある書物といえそうです。横浜市立図書館では目下「準備中」。早く現物を見たいものです。
もう1つ。<浪花の歌う巨人・パギやん>こと趙博さんが「パギやんの大阪案内 ぐるっと一周 [環状線]の旅」(高文研.1890円)を出しました。おもしろそう! これも読むぞ!!
同サイトには、その実行委員会の発起人のリストもありましたが、いかにもという名前が多々ある中で、「あれ、この人も」という名前もチラホラ(立松和平とか)。
私ヌルボ、個人的に思い起こせば、三島事件のニュース自体にはさほど衝撃を受けませんでした。
それよりも、1970年の同じ日に、ニューヨークのイーストリヴァーでアルバート・アイラーの死体が発見されたという事件の方がずっとショッキングだったと思います。
※もしかして、今も命日にアイラー特集をやってるようなジャズ喫茶があるのでは、と思って探したら、案の定ありましたね。稲毛のJazz Spot CANDYという店。(→コチラ。) 毎年やってるようです。
翌1971年5月3日には高橋和巳39歳で世を去りました。・・・いろんなことが思い出されます。
それから40年あまり経った今、世の中はどう変わったのでしょうか?
「この国には何でもある。本当にいろいろなものがあります。だが、希望だけがない」(村上龍の「希望の国のエクソダス」)という認識は、とっくに常識化してしまったようです。
11月20日に届いた「週刊文春」メールマガジン。アンケートの設問が「野田佳彦、安倍晋三、石原慎太郎 あなたが総理にふさわしいと思うのは誰ですか?」というもの。
以前流行った「究極の選択」みたいです。「俺を怒らせたいのかっ!?」って感じですねー。・・・しかしこれが現実。
韓国でも大統領選挙が間近に迫っています。(12月19日投票) しかし木村幹神戸大教授のtwitter(→コチラ)によると、今回の特色は「盛り上がっていないこと」だそうです。23日出馬取り止めを発表した安哲秀氏にたいする「シンドローム」も、日本のマスコミの思い入れ(?)ほどには盛り上がってなかったようで・・・。韓国の政治風土も、近年大きく変わってきているようです。
日本でも、すでにポピュリズムが効かなくなってきているという観測もあるようです。はや橋下市長も賞味期限が切れかかってるという気配も漂ってきている、かな?
マスコミもしょーもない政党の離合集散をくだくだしく追っかけてばかりいないで、「原発」「改憲」「TPP」等々の争点についてわかりやすく解説するとともに、各立候補(予定)者がそれらにどんな意見を持っているかをきっちり伝えてほしい、と切に望んでいます。(同じ政党内でもバラバラのようだし、個人ごとにリストを作っておくれでないかい?)
さて、今日の「毎日新聞」の読書欄を紹介、・・・する前に、気持ちが明るくなった記事をまずとりあげておきます。
<隣国のホンネ・日中民間対話>シリーズの第3回で、「白か黒か、未熟な世論 人権活動家・何培蓉さんに聞く」というもの。(今のところ→コチラで読むことができます。) 何培蓉(か・ばいよう)さんは盲目の人権活動家・陳光誠の脱出劇を支えた人権活動家の女性です。もともと英語教師で「ごく普通の中国人でした」という彼女は決して「妥協を排する闘士」ではなく、「民主の実現は、妥協するプロセスであるべきだと思うのです」と語っています。また反日デモについても、「人々が政治に参加することは良い現象ですが、(略奪行為などの)過激行為が起きたことは世論が未熟な証拠です」とも。(反中国で熱くなってる一部の日本人の対極ではないですか。)
・・・私ヌルボ、民主主義の少年期における清新さを彼女に感じました。民主主義の老年期にある日本の私たちは、昔を懐かしむか、「大人になったら(そんなに素晴らしいものでもないことが)わかるよ」とシニカルな言をとばすしかないのでしょうか・・・。
ほとんど記事にしない時事放談めいた文章をたらたら書き連ねてしまいました。
やっと本題、「毎日新聞」の読書欄です。
※とりあえずは「毎日jp」で読むことができますが、恒久的には→コチラのサイトで朝・読・毎・産の4紙の書評のバックナンバーを読むことができます。
今回は、伊東光晴先生による「ノーベル経済学賞の40年 上・下」(トーマス・カリアー著)の評はとてもためになったし、ヌルボが目を瞠った「ひとたばの手紙から」を著した尊敬すべき俳人・宇多喜代子さんが「今週の本棚:好きなもの」で好きなものとして「絵巻・緑茶・宝塚歌劇」の3つをあげていたのも興味深く読みました。しかし、17歳の時に見た小林一三の眼光を記憶に留めているとはねー・・・。
で、ようやくタイトルに掲げた尹相仁ほか著、舘野・蔡星慧訳「韓国における日本文学翻訳の64年」(出版ニュース社.4200円)について。この本の説明文だけで知らなかった重要な事実が次の2点。
①日本文学が戦後、韓国に再登場するのは1960年の4月革命以後。強力な排日政策を進めていた李承晩が失脚して対日文化政策が変化したため。読み物に飢えていた一般読者が日本文学の復権を求め、出版資本がそれに応えた。
②60年代半ばに三浦綾子「氷点」がベストセラーになった。三浦人気は、戦後にキリスト教が韓国社会に対して果たした役割とも関わる。
※三浦綾子の小説が韓国で多くの読者を得たことは知っていましたが、少し前に本ブログ記事で紹介した浅見雅一・安廷苑「韓国とキリスト教」(中公新書)にはそのことは書いてなかったし、私ヌルボも思いつきませんでした。
また、
③90年代以降の経済成長後の韓国の若者たちが、村上春樹作品の主人公たちに自身の自画像や理想形を見出した。
・・・という指摘もあるそうです。
そして、翻訳された作品の目録も付いているそうで、これはなかなか意義のある書物といえそうです。横浜市立図書館では目下「準備中」。早く現物を見たいものです。
もう1つ。<浪花の歌う巨人・パギやん>こと趙博さんが「パギやんの大阪案内 ぐるっと一周 [環状線]の旅」(高文研.1890円)を出しました。おもしろそう! これも読むぞ!!












![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)
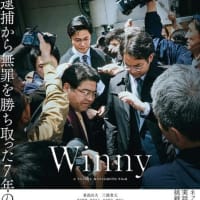
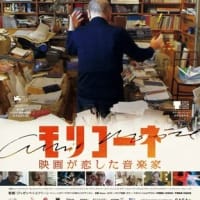
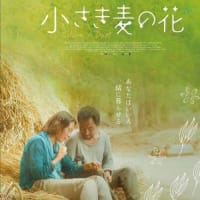
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)






つまりそういう発言や意識の持ちようや態度(父親や男子の所与とされてきた権利に背くこと)が社会的に許容されつつあり、言い換えれば、つまりそれほど、「家族」というイデオロギーが劇作の原点であったたため(これもいまいち分かり切らないんですけども)、それに代替する「物語テンプレート」として「キリスト教」がそこにあてがわれている気がしています。
そこに今回の三浦綾子が人気があったという話は、キリスト教がどこまでも不人気な日本から眺めてみれば、それは何か皮肉な輸出入という気がしませんか。
どうして家族について考えることが劇作要素になりうるかは、私にもしばらく不可解な考えの題材でした。それはおそらく、個人について考えることがほぼタブーで、個はすべて家族と共同体について奉仕することによって初めて認められたという社会の仕組みから来るのかな。よって村上春樹のような、個人性が前提になった叙述方法がとにかく斬新なものとして受け止められたということ、でしょうか。
個人的には、キリスト教にもたれかったものはもう、勘弁して欲しい、と思っているんですが、韓国の社会の言説は、ドキュメンタリーから創作物までそれにあふれている。これ、現代レベルの創作の営為では、テンプレートに依存するということはとにかく、良くないかも、と想っていますが。
私の図式的な理解では、「家族(≒家父長制度)」は伝統社会の基礎単位で、韓国では90年代以降その伝統的な社会が急速に変貌してきて、実生活でも文学においても、伝統や家族から孤絶した個人が一挙に前面に出てきた、と考えています。
で、「キリスト教」が「家族」というイデオロギーに代替する「物語テンプレート」としてあてがわれてきたとのお考えは、私としては初めて接する所説でした。一般的な理解とみていいのでしょうか? 家父長制→個人主義の過渡期??
しかし、依然として韓国では「キリスト教にもたれかったものはもう、勘弁して欲しい」と仰る方はかなりの少数派なんでしょうね。
※キリスト教というテンプレートに問題がある、というのではなく、テンプレートに依存するということ自体がよくない、ということですね。で、新たな拠り所の構築が即ち文学的営為につながっていく、ということでしょうか・・・。
※「7年の夜」は、三浦綾子「氷点」の「殺人犯の娘であることが氷点=罪であるとする設定」と共通するところがあります。
※「氷点」は、むしろドラマとして、それもストーリー展開のおもしろさ(通俗性)で人気を集めたと思います。むしろ「塩狩峠」の方が読書好きの人の感動をよんだのではないでしょうか。いずれにしろ、日本ではキリスト教と一線を画した上で読まれ、評価されてきたようです。
ここで何か具体例、となると映画「シークレット・サンシャイン」がいいかもしれません。あれは映画の紹介のされ方か、狂信と狂気、みたいな感じだったので、「そうかー」と思って恐る恐る観てみると、実際はそれとも多少ズレている。かと言って、信者のニーズに答えられないキリスト教組織を批判しているとも解釈できず、個人的には旧式な共同体社会を脱しつつも、それへの代替物がないための苦、と解釈したら、監督がそのインタビューで「普通の人生を生きる普通の人が、その生の意味の無さに悩む話のつもりで撮った」とあっさり述べている。
創作の営みにテンプレート依存は怠惰で安易な作品ばかりを産むことになるので何にしても良くないと考えます。キリスト教テンプレートがある程度定着した観のあるのが韓国文化とすれば、それに対して、「精神医療」や「脳神経科学」を出来るだけ大衆向け(セルフヘルプ風)に釈明・叙述して物語のテンプレートにするのは、英語圏(いやどこでもか)の文学の現在の流行りとなり、それについての問題が指摘されることもしばしばです。
「韓国における日本文学翻訳の64年」はとにかく私も読まなければ、と思った次第です。
私は宗教とはおよそ無縁な人間ですが、宗教に立脚した作品が必ずしも安易とは思いません。むしろ宗教と真正面から対峙し、それをタタキ台として、物事の意味や価値観といったものを追求していった名作は数多くあるし、逆に宗教のテンプレートを持っていなくても怠惰で安易な作品はさらにたくさんそこらへんにあふれているし・・・。(テンプレートを、逃避、思考停止の道具としての枠組みと理解すれば、仰るとおりだと思います。)
昨年買ったまま置きっぱなしになっていたものを思い出して読み始めたのですが、面白くて一気に(といっても10日くらいかかりましたが...)読みました。
でも、いつも感じる違和感みたいなものも...
韓国の映画や小説って「家族」「血のつながり」をテーマにしたものがヤケに多いような気がします。
もちろん、どの国でも家族をテーマにした作品は多いんでしょうが、ドラマなんかだとやたらに「財閥の御曹司と貧乏人」のような構図も多いようです。(はっきり言い切れないのは、別に統計をとっているわけでもないからですが)
それもテンプレートというところなんでしょうかね。
「家族愛」を扱ったものはある程度理解可能(?)なんですが、「跡継ぎ・後継者である息子」だとか「血脈」だとか、韓国の一般の人達は実際のところどのように感じているものなのか?
血のつながりをやたらに重視する考え方は、当然「世襲」を正当化することになるし、財閥一家のような、いままさに韓国で問題になっているような富の偏在・貧富の差につながっていくと思うのですが。
血がつながっているのだから、という理由である程度公的な性格を持っている企業を何の疑問もなく相続したりだとか、逆に「親が犯罪を犯したから子供にも罪がある」という考え方が、ある種の宿命論や諦観につながっているのだとしたら、とても嫌だなーと。
その発想がさらに歴史問題にもつながっているのかもしれません。
血のつながりを重視するというのは、ドラマ等を見るかぎりでは韓国ではふつうのようですね。いや、世界的に見るとむしろ日本人の血縁関係に対する意識が相当に稀薄なのではないかとも思いますが・・・。
また、時代によっても違うのではないかと・・・。たとえば横溝正史の探偵小説等では、伝統社会のドロドロした血のつながりが大きな意味を持っていましたね。
韓国ドラマの「財閥の御曹司と貧乏人」という毎度おなじみの設定には、現実の格差社会の反映とともに、たしかに伝統的な血筋の重視の表われかもしれませんね。連続ドラマの最初の方で出生の秘密から子ども時代が当たり前のように描かれたりしていて・・・。「氏より育ち」という言葉がありますが、韓国ではどちらも重視しているようにも思います。日本ではどちらも不可触領域の「プライバシー」に触れそうなので避けられる傾向が強いようですが・・・。(橋下市長の出自問題は論外としても。) 「朴槿恵が朴正煕元大統領の政権下で弾圧された被害者らに謝罪した」というニュースに(たぶん)相当数の日本人が違和感を感じるのも、そこらへんと関係があるのかもしれません。(もしかしたら歴史認識問題も?)
しかし、日本の戦後社会で血縁関係といったものが相対的に弱くなってきたのと同様に、現在の韓国も変わってきているのではないかと思っています。