関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
22.榛名神社 (高崎市榛名山町)
23.大森神社 (高崎市下室田町)
24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)
25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)
26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)
27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)
22.榛名神社

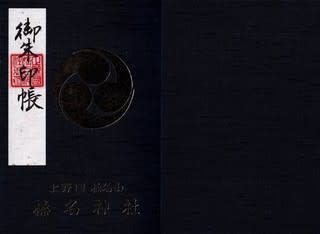
公式Web
高崎市榛名山町849
主祭神:火産霊神、埴山姫神
式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社
御朱印揮毫:榛名神社
・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。


赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。
榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。
社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。
下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。
『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。
戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。
慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。
江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。
榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。
高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。
また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。
江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。
ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。


-----------------------------------------------------
御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。
榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。
この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。
いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。
「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。
『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。
また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。
元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。
なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。
同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。
まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)
”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。
柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。
また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。
↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。
榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。
『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」
「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。
また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。
ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。
榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。
つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。
この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。
『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。
源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。
さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。
以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。
八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。
-----------------------------------------------------




講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。
随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。
奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。
神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。




対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。
手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。


石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。
信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。




彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。
あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。


神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。
本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。
本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。
御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。
国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。
祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。
境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。
ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。
御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。
23.大森神社
高崎市下室田町919
主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社
御朱印揮毫:大森神社

御朱印


【写真 上(左)】 境内掲示
【写真 下(右)】 参道と拝殿
現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。
■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より
国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら
「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」
これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。
伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。
「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))
主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命
國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。
國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。
國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。
『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。
武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。
また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。
以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。
なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。
滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。
向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 神楽殿
【写真 下(右)】 拝殿
社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。
参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。
拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。
軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。


【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿
【写真 下(右)】 水引虹梁中備


【写真 上(左)】 木鼻(右)
【写真 下(右)】 木鼻(左)
千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。
水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。
虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。
海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。
向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。


【写真 上(左)】 拝殿向拝
【写真 下(右)】 拝殿扁額
本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 金鑽神社
摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。
手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。
御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。
通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。
24.中嶋稲荷神社
高崎市下室田町1219
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:中嶋稲荷神社
この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。
とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

 【写真 上(左)】 神社への道
【写真 上(左)】 神社への道
【写真 下(右)】 鳥居の扁額
そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。
拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。
鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。


【写真 上(左)】 鳥居と拝殿
【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印
石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。
拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。
由緒書はなく創祀などは不明です。
御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。
25.矢背負稲荷神社
高崎市下室田町3293
主祭神:
旧社格:
御朱印揮毫:稲荷大明神


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。
鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。
しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。
その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)
武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。
永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。
この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。
鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。
遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。
鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。
4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。
上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。
その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。
創祀にはもう一説あるようです。
里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。
白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)
里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。
里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。
里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。
とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。
発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。
室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。
家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。
また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。
永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。
以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。
しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。
いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。
それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)
26.根古屋天満宮
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋天満宮

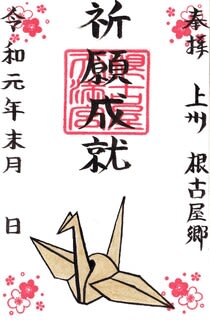
【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。
城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。
「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。
御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。
27.根古屋道祖神
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)
矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)
そちらの道祖神の御朱印かと思われます。
道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。
矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。
絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。
下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。
道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。


【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居
【写真 下(右)】 鳥居
集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。
この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 参道からの拝殿
そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。
ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。
あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。
階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。
登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。
切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。
水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。


【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮
【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額
根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。
「天満宮」の扁額が掲げられています。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ ノーサイド - 松任谷由実
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
22.榛名神社 (高崎市榛名山町)
23.大森神社 (高崎市下室田町)
24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)
25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)
26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)
27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)
22.榛名神社

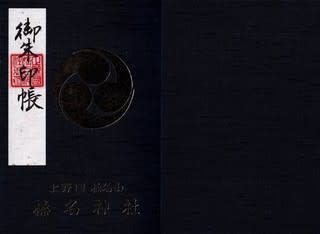
公式Web
高崎市榛名山町849
主祭神:火産霊神、埴山姫神
式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社
御朱印揮毫:榛名神社
・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。


赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。
榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。
社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。
下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。
『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。
戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。
慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。
江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。
榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。
高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。
また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。
江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。
ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。


-----------------------------------------------------
御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。
榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。
この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。
いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。
「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。
『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。
また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。
元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。
なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。
「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。
同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。
まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)
”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。
柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。
また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。
↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。
榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。
『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」
「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。
また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。
ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。
榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。
つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。
この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。
『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。
源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。
さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。
以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。
八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。
-----------------------------------------------------




講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。
随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。
奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。
神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。




対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。
手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。


石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。
信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。




彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。
あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。


神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。
本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。
本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。
御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。
国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。
祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。
境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。
ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。
御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。
23.大森神社
高崎市下室田町919
主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社
御朱印揮毫:大森神社

御朱印


【写真 上(左)】 境内掲示
【写真 下(右)】 参道と拝殿
現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。
■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より
国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら
「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」
これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。
伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。
「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))
主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命
配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命
國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。
國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。
國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。
『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。
武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。
また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。
以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。
なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。
滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。
向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 神楽殿
【写真 下(右)】 拝殿
社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。
参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。
拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。
軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。


【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿
【写真 下(右)】 水引虹梁中備


【写真 上(左)】 木鼻(右)
【写真 下(右)】 木鼻(左)
千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。
水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。
虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。
海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。
向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。


【写真 上(左)】 拝殿向拝
【写真 下(右)】 拝殿扁額
本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 金鑽神社
摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。
手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。
御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。
通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。
24.中嶋稲荷神社
高崎市下室田町1219
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:中嶋稲荷神社
この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。
とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

 【写真 上(左)】 神社への道
【写真 上(左)】 神社への道【写真 下(右)】 鳥居の扁額
そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。
拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。
鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。


【写真 上(左)】 鳥居と拝殿
【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印
石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。
拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。
由緒書はなく創祀などは不明です。
御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。
25.矢背負稲荷神社
高崎市下室田町3293
主祭神:
旧社格:
御朱印揮毫:稲荷大明神


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。
鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。
しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。
その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)
武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。
永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。
この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。
鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。
遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。
鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。
4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。
上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。
その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。
創祀にはもう一説あるようです。
里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。
白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)
里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。
里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。
里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。
とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。
発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。
室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。
家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。
また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。
永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。
以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。
しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。
いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。
それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)
26.根古屋天満宮
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋天満宮

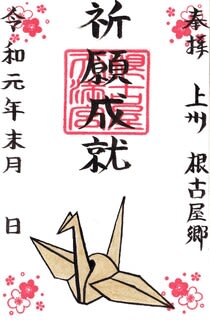
【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。
城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。
「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。
御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。
27.根古屋道祖神
高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)
主祭神:
旧社格:
御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)
矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)
そちらの道祖神の御朱印かと思われます。
道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。
矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。
絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。
下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。
道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。


【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居
【写真 下(右)】 鳥居
集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。
この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 参道からの拝殿
そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。
ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。
あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。
階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。
登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。
切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。
水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。
本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。


【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮
【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額
根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。
「天満宮」の扁額が掲げられています。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ ノーサイド - 松任谷由実
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)
12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)
13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)
14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)
15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)
16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)
17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺
高崎市箕輪町西明屋247
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。
寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。
観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。
平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。
明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。
また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。
この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。
ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。
伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。
こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。
御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。
12.黒髪山神社
榛東村広馬場3615
主祭神:大山祇命


〔 御朱印 〕
中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。
榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。
榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。
主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。
神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。
大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。
群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。
相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。
相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。
「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。
雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。
駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。
木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。
拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。
境内には有栖川宮神社も鎮座します。
祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。
御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。
13.威徳山 常楽院 長松寺
吉岡町漆原1284
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神
札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)


【写真 上(左)】 長松寺本堂
【写真 下(右)】 長松寺観音堂
〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。
左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。
その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。
新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。
寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。
当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。
上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。
ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。
矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。
境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。
山門をくぐると境内正面に本堂。
本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。
タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。
境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。
駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。
朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。
観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。
見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。
御朱印は庫裡にていただきました。
ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。
14.玉輪山 龍傳寺
渋川市半田1124
曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第19番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。
左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。
こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。
境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。
天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。
天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。
などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。
境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。
御朱印は庫裡にて拝受。
ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。
御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。
15.慈眼山 福聚院 神宮寺
渋川市有馬1301
天台宗 御本尊:釈迦如来
札所:新上州三十三観音霊場第30番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。
右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。
このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。
中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。
またまた話が逸れました。
新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。
天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。
天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。
神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。
(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)
有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。
信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。
当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。
こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。
(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)
明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。
お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社
御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。
また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。
16.威徳山 無量寿院 眞光寺
渋川市並木町748
天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)
札所:群馬郡三十三観音霊場第10番
札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)


〔 御朱印 〕
中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。
右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。
ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。
平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。
中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。
名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。
境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。
御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。
周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。
高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。
また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。
観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。
西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。
17.渋川八幡宮
渋川市渋川甲1
主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后


〔 御朱印 〕
中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。
こちらでは御朱印帳も購入しました。
紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳
渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。
義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。
義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。
その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。
八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。
境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。
子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。
境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。
御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。
こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺
渋川市金井甲1965
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。
応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。
当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)
樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。
こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。
参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。
また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ 見えない月 - 藤田麻衣子
■ 夢の途中 - KOKIA
■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)
12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)
13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)
14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)
15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)
16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)
17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺
高崎市箕輪町西明屋247
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。
寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。
観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。
平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。
明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。
また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。
この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。
ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。
伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。
こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。
御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。
12.黒髪山神社
榛東村広馬場3615
主祭神:大山祇命


〔 御朱印 〕
中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。
榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。
榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。
主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。
神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。
大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。
群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。
相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。
相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。
「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。
雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。
駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。
木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。
拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。
境内には有栖川宮神社も鎮座します。
祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。
御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。
13.威徳山 常楽院 長松寺
吉岡町漆原1284
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神
札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)


【写真 上(左)】 長松寺本堂
【写真 下(右)】 長松寺観音堂
〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。
左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。
その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。
右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。
新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。
寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。
当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。
上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。
ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。
矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。
境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。
山門をくぐると境内正面に本堂。
本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。
タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。
境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。
駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。
朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。
観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。
見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。
御朱印は庫裡にていただきました。
ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。
14.玉輪山 龍傳寺
渋川市半田1124
曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第19番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。
左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。
こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。
境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。
天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。
天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。
などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。
境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。
御朱印は庫裡にて拝受。
ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。
御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。
15.慈眼山 福聚院 神宮寺
渋川市有馬1301
天台宗 御本尊:釈迦如来
札所:新上州三十三観音霊場第30番
札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)


〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕
中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。
右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。
関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。
このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。
中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。
またまた話が逸れました。
新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。
天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。
天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。
神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。
(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)
有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。
信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。
当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。
こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。
(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)
明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。
お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社
御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。
また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。
16.威徳山 無量寿院 眞光寺
渋川市並木町748
天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)
札所:群馬郡三十三観音霊場第10番
札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)


〔 御朱印 〕
中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。
右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。
ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。
平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。
中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。
名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。
境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。
御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。
周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。
高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。
また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。
観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。
西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。
17.渋川八幡宮
渋川市渋川甲1
主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后


〔 御朱印 〕
中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。
こちらでは御朱印帳も購入しました。
紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳
渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。
義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。
義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。
その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。
八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。
境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。
子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。
境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。
御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。
こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺
渋川市金井甲1965
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番


〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。
応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。
当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)
樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。
こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。
参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。
また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ 見えない月 - 藤田麻衣子
■ 夢の途中 - KOKIA
■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第12番
現徳山 妙見寺
公式Web
北区西ヶ原2-9-5
日蓮宗
御首題
第12番は、日蓮宗の妙見寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、つぎの記載があります。
・ 正中山法華経寺大荒行堂の大験者、慈徳院日陽上人が昭和9年(1934年)荒川区尾久に草創された妙見堂教会が昭和19年(1944年)当地に疎開移転して開山。
・第2世として法燈を承継された慈正院日慶上人が昭和22年(1946年)、日蓮宗門より現徳山妙見寺の寺号公称を認可される。
・昭和57年(1982年)、老朽化した本堂と書院を再建落慶。
・第2世日慶上人は正中山大荒行堂加行700日、第3世の慈昌院日観上人も正中山第四行の修法師で檀信徒の方々から信仰を集めている。
山門には「日蓮宗祈祷所」が立額され、公式Webにも「日蓮宗祈祷所『妙見寺』は日蓮宗伝統の祈祷を受け継ぎ、全国の方々の幸福に寄与します。」と掲載されています。


【写真 上(左)】 飛鳥山公園の紅葉
【写真 下(右)】 山門
本郷通りから北に少し入ったところ、飛鳥山公園に面した緑濃い立地です。
山門はおそらく薬医門ないし高麗門で、小ぶりながら存在感があります。


【写真 上(左)】 斜めから山門
【写真 下(右)】 山門主門まわり
降り棟の外側が本瓦葺、内側が桟瓦葺、掛瓦も太くてどっしりとした質感。
右の柱に「日蓮宗祈祷所」、左の柱には寺号の板標が掲げられ、正面には「現徳山」の山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
境内には八大竜王碑、浄行菩薩、不動明王、稲荷社などが鎮座し、パワスポ的な雰囲気を感じます。
稲荷社奥の2階の入母屋造妻入りの建物が本堂のように見えますが、定かではありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の棟飾り


【写真 上(左)】 浄行菩薩
【写真 下(右)】 庫裡
御首題は山門くぐって左の階段をのぼった庫裡にて拝受しました。
滝野川寺院めぐりの御朱印も御首題で授与されます。
ご不在の場合もあるので、事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第12番の御朱印(御首題)
【下(右)】 通常の御首題
滝野川寺院めぐりの御朱印は御首題で、「滝野川寺院めぐり第十二番寺」の札所印が捺されています。
通常の御首題にこの札番はなく、構成も若干異なります。
第13番
北龍山 法音寺
北区栄町14-9
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
第13番は、真宗大谷派の法音寺です。
第13番で一旦京浜東北線の東側に出ます。
田端駅から上中里駅にかけてのJR京浜東北線北側にはJR尾久車両センター(尾久客車操車場)があって、都内有数の交通分断エリアとなっています。
第12番妙見寺からだと上中里駅東側の跨線橋を渡り、さらに梶原踏切か上中里さわやか橋経由のルートが順当かと思います。


【写真 上(左)】 上中里さわやか橋からのJR尾久車両センター
【写真 下(右)】 山門からの山内
西ヶ原から京浜東北線の線路を渡って栄町に入ると、路地が入り組む下町的な町並みとなり、法音寺も路地の一角にあります。
妙見寺からの距離はさほどではありませんが、跨線橋を渡ったり、街の雰囲気が変わったりで、けっこう遠く感じました。
なお、法音寺の最寄り駅は都電荒川線の「梶原」駅となります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 掲示版
『滝野川寺院めぐり案内』によると、当寺はもと富山県下新川郡新屋にあり、上京された釈法忍師は明治40年(1907年)、滝野川に居住されて布教活動に着手。
大正13年(1924年)、この地に本堂を建立され法音寺説教所を開設。
東京大空襲で本堂を焼失しましたが、昭和24年(1949年)には正式に寺号を取得、昭和30年(1955年)には本堂を再建し、現在に至ります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂見上げ
こぢんまりとした境内正面に立派な本堂。
入母屋造銅板葺流れ向拝。水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配しています。
参拝時、ご住職はご不在で大黒さんの対応をいただきました。
「真宗なので御朱印は出されていない。」とのことでしたが、納経帳をお見せし、滝野川寺院めぐりを巡拝中との主旨をお話しすると、「それであれば」とお受けいただき、御朱印(というか参拝記念)に準ずるものを納経帳にいただけました。
ご親切な対応をいただき、ありがとうごさいました。
ただし、今回だけの特例対応であったかもしれず、拝受した「おしるし」は掲載を控えます。
第14番
思惟山 浄業三昧寺 正受院
北区滝野川2-49-5
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番、北豊島三十三観音霊場第23番
第14番は、浄土宗の正受院です。
法音寺から赤羽駅のガードをくぐり、王子神社下の緑ゆたかな音無親水公園を抜けてのアプローチとなります。
下町の住宅街から一転、渓谷を抜けて台地に登るこのコースは変化に富み、この巡拝のハイライトともいえる道のり。
正受院は滝野川に面していますが北側滝野川岸からの参道はないので、一旦滝野川をはなれ、南側の住宅地から回り込むかたちとなります。


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 不動尊への道標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、室町時代末、弘治年間(1555-1558年)に大和國宇多郡滝門の奥の功曽久という所から夢告に従って来られた学仙坊法印が、王子七滝のひとつ「不動の滝」で修行され、滝野川から1体の不動尊像をすくい上げました。
法印は不動堂を建立され、のちに弘法大師の御作といわれ信仰を集めるこの不動尊像を安置されたのが当寺の開創とされます。
慶長年間(1596-1615年)に円誉上人が入寺されて浄土宗となりました。
浄土宗のお寺様ながら、人々のこのお不動様に対する信仰は篤く、「瀧不動尊」とも呼ばれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号18/114)に以下の記述があります。
「「浄土宗芝増上寺末 思惟山三昧寺ト号ス 弘治年中大和國宇多郡龍門ノ奥功曾久ト云所ニ學仙坊と云僧住し 不動即我ノ密法ヲ修スル事年アリ 靈夢ヲ得テ當國ニ来リテ當寺ヲ草創セリ 其年タマタマ洪水アリテ砌ノ川中ヨリ弘法大師作ノ不動ヲ得タリ 其後又旅僧来テ一軀ノ不動ヲ授クシモノ今堂中ニ安置スル處ナリ 學仙坊は弘治三年三月四日寂ス 其墳墓庭ノ小山ノ上ニアリテ五輪塔ナリ 其後寂阿了山ト云僧堂舎ヲ再建ス 文禄三年九月三日圓譽光道本堂再建ノ棟札アリ 本尊阿彌陀ハ行基ノ作ニテ坐身長二尺五分此餘惠心作ノ彌陀像一軀を置 撞鐘 古鐘ナリシカ文政三年改鑄スト云 不動堂 弘法大師作ノ立像ヲ置 観音堂 西國札所第四番観音の寫と云 瀧 本堂の脇峽下ニアリ病者ツトイ来テ浴セリ」
慈眼堂(赤ちゃんの納骨堂)があり、「赤ちゃん寺」として知られています。


【写真 上(左)】 鐘楼門
【写真 下(右)】 参道
狭い路地から意外に長い参道がつづきます。
しばらく行くと鐘楼門。下を石積みのアーチにし、上に木造建築を構えるいわゆる「竜宮門」で、おそらく入母屋屋根桟瓦葺で水引虹梁を置いています。
軒裏の垂木はめずらしい扇垂木だと思います。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
正面が本堂。入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝の均整がとれた仏堂。
水引虹梁両端に獅子と貘の彫刻木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
正面桟唐戸の上に「思惟山」の扁額。
本堂前には江戸時代の探検家近藤重蔵(守重)の甲冑姿の石像が鎮座します。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂上部
本堂向かって左の渓谷寄りには不動堂。
入母屋造桟瓦葺唐破風向拝で、水引虹梁両端に獅子彫刻の木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
唐破風の鬼板や兎毛通の仕上げも精緻で見応えがあります。
本堂右手の客殿や庫裡もしっとりと風情ある構えを見せています。
境内には不動尊の露仏が数座御座し、やはりお不動様とのゆかりがふかいお寺だと思います。
なお、「不動の滝」(泉流の滝)は現存していません。
『江戸名所図会』
「正受院の本堂の後、坂路を廻り下る事、数十歩にして飛泉あり、滔々として硝壁に趨る、此境ハ常に蒼樹蓊欝として白日をさゝえ、青苔露なめらかにして人跡稀なり」
境内はしっとりと落ち着いた雰囲気があり、↑で描写された面影をいまも遺しています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。書置はなく、ご住職ご不在の場合もあるので事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 御本尊の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」の揮毫と三寶印とその左横に「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印。左上に印判(不明)。
左上には「瀧不動」の揮毫、左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印がなく、上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番(「西國四番寫」の札所印)の札所印が捺されていました。
第15番
瀧河山 松橋院 金剛寺
北区滝野川3-88-17
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第43番、荒川辺八十八ヶ所霊場第16番、北豊島三十三観音霊場第31番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第28番、弁財天百社参り第52番、豊島六地蔵霊場第4番
第15番は、真言宗豊山派の金剛寺です。
第14番正受院から第16番結願の寿徳寺までは滝野川に沿うかたちで立地し、ひときわ風情のあるところです。
このあたりは江戸時代から紅葉の名所で、とくに金剛寺は「もみじ寺」の別称があります。


【写真 上(左)】 滝野川の紅葉-1
【写真 下(右)】 滝野川の紅葉-2
滝野川沿いの遊歩道脇には、音無さくら緑地、音無もみじ緑地があり、音無さくら緑地では旧石神井川の流路跡、音無もみじ緑地ではかつての江戸の名所であった松橋辨財天周辺の様子をしのぶことができます。

【写真 下(右)】 音無もみじ緑地
『滝野川寺院めぐり案内』によると、金剛寺は弘法大師が東国巡錫の折、石神井川(滝野川)にさしかかり、対岸へ渡る橋がなかったため川岸の松を切り倒して一本橋(松橋)を渡され、その際にその松の木で不動明王の尊像一躯を彫られて石上に安置されたのが草創とされています。
治承四年(1180年)10月、伊豆国で挙兵し、石橋山での敗戦ののち安房に逃れて再挙を図られた源頼朝公は、府中の六所明神(大國魂神社)へ向かう途中、滝野川松橋に布陣し、東方千住方面からの敵をここで迎え撃ち大勝利を収めたとされます。
その折、頼朝公は金剛寺に戦勝祈願したことから寄進など寺の興隆に尽くしたとされます。
一時荒廃したものの、天文年間(1532-1555年)に阿闍梨宥印が北条氏康の賛意を得て再興。
江戸時代には、八代将軍吉宗公が滝野川流域に紅葉の植林を奨励したこともあって、江戸近郊を代表する紅葉の名所となり、金剛寺は「もみじ寺」と呼ばれて秋の庶民の参詣・行楽の場として広く親しまれました。
その様子は広重の『名所江戸百景』や『東都名所』など多くの錦絵に描かれています。
また、金剛寺一帯は、豊島氏支族滝野川氏の居館滝野川城跡ともいわれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗田端村與楽寺門徒 瀧河山松橋院ト号ス 本尊不動ハ坐像ニテ長一尺餘弘法大師ノ作ト云 縁起の●ニ當所ハ弘法大師達遊歴ノ古蹟ニシテ 其頃手ツカラ此像ヲ彫刻アリテ假ニ石上ニ安ス 今其石ヲ不動影向石ト称シテ境内ニ現存シ 疾病ノモノ此石ニ水ヲソソキテ其水を服スレハ立所ニ平癒スト云 又治承年中右大将頼朝境内辨財天信仰ノ餘リ堂舎建立 及ヒ田園ヲモ寄附アリシニ 其後兵火ニ焼レ強盗ニ田園を掠メ奪ハレ 宗門タニ定カナリシヲ、天文ノ頃阿闍梨宥印ト云僧是ヲ歎キ 北條氏康ヘ訴ヘ永ク眞言ノ道場ニ復スト云 影向石 三箇ノ石ヲ重置 是縁起ニ云ヘル不動ノ像ヲ安置セル處ナリ 辨財天社 弘法大師作坐身長七寸ノ像ヲ安シ 別ニ護摩ノ灰ニテ作レル像ヲモ置リ 地蔵堂 大黒天 本堂ノ後ノ方岩窟ノ中ニ安置ス」
「辨財天 峽下ノ洞中ニ安ス長一尺ノ石像ニテ松橋辨天ト号ス 弘法大師ノ作 當時此地ニ松橋ト云橋アリシ故地名ヲオハセテ唱トイヘリ 松橋ノ名ハ前ニ云ル如ク源平盛衰記ニ見エテ舊キ地名ナリ 治承ノ頃頼朝此辨天ヲ帰依ノ餘リ太刀ヲ寄附アリシ由縁起ニ載タレト今是ヲ失ナヘリ 洞中ニ文保三年三月ト彫タル古碑一基アリ 恵比須毘沙門石像紫の楓 紅葉ノ秋紫色ヲ帶ル故此名アリ」


【写真 上(左)】 旧松橋辨財天周辺
【写真 下(右)】 江戸名所図絵(松橋辨財天窟)
〔松橋辨財天〕
金剛寺は辨天様ともゆかりのふかいお寺です。
かつての滝野川は金剛寺付近で蛇行しており、その崖には辨天の滝がかかり、崖下にあった洞窟には辨財天が祀られていました。
この辨天様は弘法大師の御作ともいわれ、松橋辨天または岩屋辨天と呼ばれて信仰を集めました。
この辨天様は、源頼朝公が戦勝を祈願し太刀一振を奉納し、戦勝ののちに辨財天の堂舎を建立、田園の寄進をしたとも伝えられています。
滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』で犬塚信乃の母手束が子授けを祈った「滝野川なる岩屋殿」と記した岩屋がこの松橋辨天とされています。
辨天の滝は昭和初期に枯れ、昭和33年(1958年)の狩野川台風で辨天様の洞窟は崩壊し、一部は昭和50年(1975年)前後まで残っていたようですが、その後の護岸工事や流路改修の際に取り壊され、現在は音無もみじ緑地となっています。
現地の案内版より引用抜粋してみます。
「『江戸名所図絵』には『この地は石神井河の流れに臨み、自然の山水あり。両岸高く桜楓の二樹枝を交へ、春秋ともにながめあるの一勝地なり。』」「崖下の岩屋の中には弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。また、現在都営住宅が建っている付近の崖に瀧があり、弁天の滝と呼ばれていました。」
『新編武蔵風土記稿』によると、崖下洞窟内の「松橋辨財天(岩屋辨財天)」/弘法大師作長一尺ノ石像とは別に、金剛寺境内(崖上)にも「弘法大師作坐身長七寸ノ辨天像」が安置されていた様ですが、詳細はよくわかりません。
ただし、松橋辨天の崖下洞窟も金剛寺の領地内であったようなので、金剛寺=松橋辨天と捉えられていたのでは。
松橋辨天は江戸市内でもよく知られており、江戸三十三ヶ所弁財天霊場、弁財天百社参りの札所となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 紅葉寺の寺号標


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 西國霊場札所標
江戸時代からの行楽地とあって、金剛寺周辺はいまでも華やいだ雰囲気が感じられます。
入母屋造桟瓦葺の薬医門。扁額は「瀧河山」。頭貫部梁先の雲形木鼻がダイナミック。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
参道正面、階段の上に本堂向拝。
入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝。向かって左手手前に修行大師が御座します。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に本蟇股を配しています。
正面桟唐戸の上に「金剛寺」の扁額。
虹梁に金色の彫刻を置いた、名刹らしい堂々たる向拝です。


【写真 上(左)】 辨天堂
【写真 下(右)】 辨天堂扁額
本堂向かって右手に宝形造銅板葺の辨天堂と坐像の地蔵尊が御座します。
弁天堂の御本尊は松橋辨天の系譜を引かれるお像でしょうか。
手入れの行き届いた境内で、落ち着いて参拝ができます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 滝野川七福神
御朱印は本堂向かって左手の庫裡(客殿?)にて、ご丁寧なご対応をいただき拝受しました。

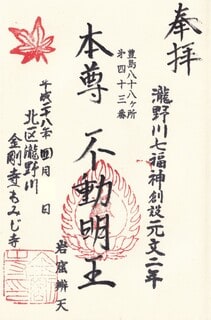
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第15番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第43番の御朱印
中央に「本尊 不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「滝野川寺院めぐり第十五番寺」と「滝野川七福神創設元文二年」の印判。左上に「豊島八十八ヶ所第四十三番」と「もみじ」の印判。左下に「岩窟辨天」の印判。
左下に寺号の印判と寺院印が捺されています。
豊島霊場の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十五番寺」の印判がなく、印判の位置も若干異なります。
「松橋辨天」の御朱印については伺っていませんが、Web上で見当たらないこと、既存の御朱印に「岩窟辨天」の印判があることから、おそらくは授与されていないと思います。
なお、「滝野川七福神」は、金剛寺境内に祀られている七福神をさすようです。
第16番
南照山 観音院 寿徳寺
北区滝野川4-22-1
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第17番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第12番、大東京百観音霊場第80番、北豊島三十三観音霊場第32番
ついに結願の16番。真言宗豊山派の寿徳寺です。
金剛寺とは反対側の滝野川の左岸にあります。


【写真 上(左)】 川沿いの遊歩道
【写真 下(右)】 滝野川橋
金剛寺から寿徳寺への順路には音無もみじ緑地があり、滝野川沿いの遊歩道の紅葉も綺麗で、歩いていて楽しいところです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、寿徳寺は寿永年間(1182-1185年)、梶原氏の家臣であった早船・小宮の両氏が梶原氏と不和になり落ち延びる途中で、海中から拾いあげた観世音菩薩を滝野川の北岸沿いの堂山の地に小堂を設け安置したのが創建と伝わります。
本尊は谷津子育観音と親しまれ、新撰組の近藤勇、および隊士の菩提寺としても知られています。
境外地には谷津大観音、近藤勇の墓所(JR埼京線「板橋」駅前)があります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
なお、『新編武蔵風土記稿』の「寿福寺」は誤植です。
「新義真言宗田端村東覺寺門徒、南照山観音院ト号ス 本尊子安観音」


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 近藤勇の碑


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 西國霊場札所碑
住宅地のなか、ぽっかりと開けた一角に立地し、境内も広々としています。
門外左手に不動堂。境内左手に修行大師像が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め右からの本堂
正面に昭和41年(1966年)落慶の本堂。
両脇に仁王尊像を置いた石段の上に、アーチ形の屋根をもつ独特なつくりの朱色の建物。
正面向拝部に「南照山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
寺伝によると、秘仏の御本尊、谷津観音は蓮華座に坐り、両手で乳児を膝の上に抱えている姿で、指を阿弥陀如来と同じ弥陀の定印に結んでおられるそうです。
本堂の向かって右にある護摩堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁と向拝柱を備え、これは以前の本堂とのこと。


【写真 上(左)】 旧本堂(護摩堂)
【写真 下(右)】 乳が垂れている銀杏
境内に切株から芽吹いている銀杏は、かつては巨木で、この樹の皮をはいで本尊に供え、祈願した後に煎じて飲むと母乳が良く出るようになるという信仰がありました。
正岡子規の高弟として知られる俳人、河東 碧梧桐の句
- 秋立つや子安詣での花の束 -
が残されており、明治に入っても谷津観音への子安詣では盛んであったことがうかがわれます。
山内には、独特の雰囲気を放つインド仏も露座しています。


【写真 上(左)】 インド仏
【写真 下(右)】 滝野川と谷津大観音
谷津大観音は山内から少しくはなれた滝野川の河岸、観音橋のたもとに御座しています。
右手与願印、左手に蓮華をもたれるおだやかな表情の銅製の坐像です。
観音橋から寿徳寺に向かい登っていく坂を「観音の坂」といいます。
現地案内標には「観音橋の北から寿徳寺へ登る坂です。坂名は、坂上にある寿徳寺に谷津観音の名で知られる観音様がまつられているからです。江戸時代には大門通とも呼ばれていました。」とあります。(北区教育委員会)


【写真 上(左)】 観音橋と谷津大観音
【写真 下(右)】 谷津大観音
御朱印は本堂向かって右手奥の庫裡にて拝受しました。
ご丁寧なご対応をいただき、「滝野川十六番満願」の揮毫もいただきました。
やはり「滝野川寺院めぐり」の巡拝者は少ないとのことでした。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第16番(満願)の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第12番の御朱印
中央に御本尊聖観世音菩薩の種子「サ」・「子育 谷津観音」の揮毫と「谷津子育観音」の印判。右上に聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。左下に寺号の揮毫と寺院印。右に「滝野川十六番満願」の揮毫をいただきました。
豊島霊場の御朱印とは、札番の揮毫が異なります。
これで滝野川寺院めぐりは結願です。
北区の落ち着いた街区を巡るこの巡拝コース、札所構成も変化に富んでいて、知名度は低いですがおすすめだと思います。
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 孤独な生きもの - KOKIA
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第12番
現徳山 妙見寺
公式Web
北区西ヶ原2-9-5
日蓮宗
御首題
第12番は、日蓮宗の妙見寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、つぎの記載があります。
・ 正中山法華経寺大荒行堂の大験者、慈徳院日陽上人が昭和9年(1934年)荒川区尾久に草創された妙見堂教会が昭和19年(1944年)当地に疎開移転して開山。
・第2世として法燈を承継された慈正院日慶上人が昭和22年(1946年)、日蓮宗門より現徳山妙見寺の寺号公称を認可される。
・昭和57年(1982年)、老朽化した本堂と書院を再建落慶。
・第2世日慶上人は正中山大荒行堂加行700日、第3世の慈昌院日観上人も正中山第四行の修法師で檀信徒の方々から信仰を集めている。
山門には「日蓮宗祈祷所」が立額され、公式Webにも「日蓮宗祈祷所『妙見寺』は日蓮宗伝統の祈祷を受け継ぎ、全国の方々の幸福に寄与します。」と掲載されています。


【写真 上(左)】 飛鳥山公園の紅葉
【写真 下(右)】 山門
本郷通りから北に少し入ったところ、飛鳥山公園に面した緑濃い立地です。
山門はおそらく薬医門ないし高麗門で、小ぶりながら存在感があります。


【写真 上(左)】 斜めから山門
【写真 下(右)】 山門主門まわり
降り棟の外側が本瓦葺、内側が桟瓦葺、掛瓦も太くてどっしりとした質感。
右の柱に「日蓮宗祈祷所」、左の柱には寺号の板標が掲げられ、正面には「現徳山」の山号扁額。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
境内には八大竜王碑、浄行菩薩、不動明王、稲荷社などが鎮座し、パワスポ的な雰囲気を感じます。
稲荷社奥の2階の入母屋造妻入りの建物が本堂のように見えますが、定かではありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の棟飾り


【写真 上(左)】 浄行菩薩
【写真 下(右)】 庫裡
御首題は山門くぐって左の階段をのぼった庫裡にて拝受しました。
滝野川寺院めぐりの御朱印も御首題で授与されます。
ご不在の場合もあるので、事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第12番の御朱印(御首題)
【下(右)】 通常の御首題
滝野川寺院めぐりの御朱印は御首題で、「滝野川寺院めぐり第十二番寺」の札所印が捺されています。
通常の御首題にこの札番はなく、構成も若干異なります。
第13番
北龍山 法音寺
北区栄町14-9
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
第13番は、真宗大谷派の法音寺です。
第13番で一旦京浜東北線の東側に出ます。
田端駅から上中里駅にかけてのJR京浜東北線北側にはJR尾久車両センター(尾久客車操車場)があって、都内有数の交通分断エリアとなっています。
第12番妙見寺からだと上中里駅東側の跨線橋を渡り、さらに梶原踏切か上中里さわやか橋経由のルートが順当かと思います。


【写真 上(左)】 上中里さわやか橋からのJR尾久車両センター
【写真 下(右)】 山門からの山内
西ヶ原から京浜東北線の線路を渡って栄町に入ると、路地が入り組む下町的な町並みとなり、法音寺も路地の一角にあります。
妙見寺からの距離はさほどではありませんが、跨線橋を渡ったり、街の雰囲気が変わったりで、けっこう遠く感じました。
なお、法音寺の最寄り駅は都電荒川線の「梶原」駅となります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 掲示版
『滝野川寺院めぐり案内』によると、当寺はもと富山県下新川郡新屋にあり、上京された釈法忍師は明治40年(1907年)、滝野川に居住されて布教活動に着手。
大正13年(1924年)、この地に本堂を建立され法音寺説教所を開設。
東京大空襲で本堂を焼失しましたが、昭和24年(1949年)には正式に寺号を取得、昭和30年(1955年)には本堂を再建し、現在に至ります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂見上げ
こぢんまりとした境内正面に立派な本堂。
入母屋造銅板葺流れ向拝。水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配しています。
参拝時、ご住職はご不在で大黒さんの対応をいただきました。
「真宗なので御朱印は出されていない。」とのことでしたが、納経帳をお見せし、滝野川寺院めぐりを巡拝中との主旨をお話しすると、「それであれば」とお受けいただき、御朱印(というか参拝記念)に準ずるものを納経帳にいただけました。
ご親切な対応をいただき、ありがとうごさいました。
ただし、今回だけの特例対応であったかもしれず、拝受した「おしるし」は掲載を控えます。
第14番
思惟山 浄業三昧寺 正受院
北区滝野川2-49-5
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番、北豊島三十三観音霊場第23番
第14番は、浄土宗の正受院です。
法音寺から赤羽駅のガードをくぐり、王子神社下の緑ゆたかな音無親水公園を抜けてのアプローチとなります。
下町の住宅街から一転、渓谷を抜けて台地に登るこのコースは変化に富み、この巡拝のハイライトともいえる道のり。
正受院は滝野川に面していますが北側滝野川岸からの参道はないので、一旦滝野川をはなれ、南側の住宅地から回り込むかたちとなります。


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 不動尊への道標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、室町時代末、弘治年間(1555-1558年)に大和國宇多郡滝門の奥の功曽久という所から夢告に従って来られた学仙坊法印が、王子七滝のひとつ「不動の滝」で修行され、滝野川から1体の不動尊像をすくい上げました。
法印は不動堂を建立され、のちに弘法大師の御作といわれ信仰を集めるこの不動尊像を安置されたのが当寺の開創とされます。
慶長年間(1596-1615年)に円誉上人が入寺されて浄土宗となりました。
浄土宗のお寺様ながら、人々のこのお不動様に対する信仰は篤く、「瀧不動尊」とも呼ばれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号18/114)に以下の記述があります。
「「浄土宗芝増上寺末 思惟山三昧寺ト号ス 弘治年中大和國宇多郡龍門ノ奥功曾久ト云所ニ學仙坊と云僧住し 不動即我ノ密法ヲ修スル事年アリ 靈夢ヲ得テ當國ニ来リテ當寺ヲ草創セリ 其年タマタマ洪水アリテ砌ノ川中ヨリ弘法大師作ノ不動ヲ得タリ 其後又旅僧来テ一軀ノ不動ヲ授クシモノ今堂中ニ安置スル處ナリ 學仙坊は弘治三年三月四日寂ス 其墳墓庭ノ小山ノ上ニアリテ五輪塔ナリ 其後寂阿了山ト云僧堂舎ヲ再建ス 文禄三年九月三日圓譽光道本堂再建ノ棟札アリ 本尊阿彌陀ハ行基ノ作ニテ坐身長二尺五分此餘惠心作ノ彌陀像一軀を置 撞鐘 古鐘ナリシカ文政三年改鑄スト云 不動堂 弘法大師作ノ立像ヲ置 観音堂 西國札所第四番観音の寫と云 瀧 本堂の脇峽下ニアリ病者ツトイ来テ浴セリ」
慈眼堂(赤ちゃんの納骨堂)があり、「赤ちゃん寺」として知られています。


【写真 上(左)】 鐘楼門
【写真 下(右)】 参道
狭い路地から意外に長い参道がつづきます。
しばらく行くと鐘楼門。下を石積みのアーチにし、上に木造建築を構えるいわゆる「竜宮門」で、おそらく入母屋屋根桟瓦葺で水引虹梁を置いています。
軒裏の垂木はめずらしい扇垂木だと思います。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
正面が本堂。入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝の均整がとれた仏堂。
水引虹梁両端に獅子と貘の彫刻木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
正面桟唐戸の上に「思惟山」の扁額。
本堂前には江戸時代の探検家近藤重蔵(守重)の甲冑姿の石像が鎮座します。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂上部
本堂向かって左の渓谷寄りには不動堂。
入母屋造桟瓦葺唐破風向拝で、水引虹梁両端に獅子彫刻の木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
唐破風の鬼板や兎毛通の仕上げも精緻で見応えがあります。
本堂右手の客殿や庫裡もしっとりと風情ある構えを見せています。
境内には不動尊の露仏が数座御座し、やはりお不動様とのゆかりがふかいお寺だと思います。
なお、「不動の滝」(泉流の滝)は現存していません。
『江戸名所図会』
「正受院の本堂の後、坂路を廻り下る事、数十歩にして飛泉あり、滔々として硝壁に趨る、此境ハ常に蒼樹蓊欝として白日をさゝえ、青苔露なめらかにして人跡稀なり」
境内はしっとりと落ち着いた雰囲気があり、↑で描写された面影をいまも遺しています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。書置はなく、ご住職ご不在の場合もあるので事前TELがベターかもしれません。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 御本尊の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」の揮毫と三寶印とその左横に「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印。左上に印判(不明)。
左上には「瀧不動」の揮毫、左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印がなく、上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番(「西國四番寫」の札所印)の札所印が捺されていました。
第15番
瀧河山 松橋院 金剛寺
北区滝野川3-88-17
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第43番、荒川辺八十八ヶ所霊場第16番、北豊島三十三観音霊場第31番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第28番、弁財天百社参り第52番、豊島六地蔵霊場第4番
第15番は、真言宗豊山派の金剛寺です。
第14番正受院から第16番結願の寿徳寺までは滝野川に沿うかたちで立地し、ひときわ風情のあるところです。
このあたりは江戸時代から紅葉の名所で、とくに金剛寺は「もみじ寺」の別称があります。


【写真 上(左)】 滝野川の紅葉-1
【写真 下(右)】 滝野川の紅葉-2
滝野川沿いの遊歩道脇には、音無さくら緑地、音無もみじ緑地があり、音無さくら緑地では旧石神井川の流路跡、音無もみじ緑地ではかつての江戸の名所であった松橋辨財天周辺の様子をしのぶことができます。

【写真 下(右)】 音無もみじ緑地
『滝野川寺院めぐり案内』によると、金剛寺は弘法大師が東国巡錫の折、石神井川(滝野川)にさしかかり、対岸へ渡る橋がなかったため川岸の松を切り倒して一本橋(松橋)を渡され、その際にその松の木で不動明王の尊像一躯を彫られて石上に安置されたのが草創とされています。
治承四年(1180年)10月、伊豆国で挙兵し、石橋山での敗戦ののち安房に逃れて再挙を図られた源頼朝公は、府中の六所明神(大國魂神社)へ向かう途中、滝野川松橋に布陣し、東方千住方面からの敵をここで迎え撃ち大勝利を収めたとされます。
その折、頼朝公は金剛寺に戦勝祈願したことから寄進など寺の興隆に尽くしたとされます。
一時荒廃したものの、天文年間(1532-1555年)に阿闍梨宥印が北条氏康の賛意を得て再興。
江戸時代には、八代将軍吉宗公が滝野川流域に紅葉の植林を奨励したこともあって、江戸近郊を代表する紅葉の名所となり、金剛寺は「もみじ寺」と呼ばれて秋の庶民の参詣・行楽の場として広く親しまれました。
その様子は広重の『名所江戸百景』や『東都名所』など多くの錦絵に描かれています。
また、金剛寺一帯は、豊島氏支族滝野川氏の居館滝野川城跡ともいわれています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗田端村與楽寺門徒 瀧河山松橋院ト号ス 本尊不動ハ坐像ニテ長一尺餘弘法大師ノ作ト云 縁起の●ニ當所ハ弘法大師達遊歴ノ古蹟ニシテ 其頃手ツカラ此像ヲ彫刻アリテ假ニ石上ニ安ス 今其石ヲ不動影向石ト称シテ境内ニ現存シ 疾病ノモノ此石ニ水ヲソソキテ其水を服スレハ立所ニ平癒スト云 又治承年中右大将頼朝境内辨財天信仰ノ餘リ堂舎建立 及ヒ田園ヲモ寄附アリシニ 其後兵火ニ焼レ強盗ニ田園を掠メ奪ハレ 宗門タニ定カナリシヲ、天文ノ頃阿闍梨宥印ト云僧是ヲ歎キ 北條氏康ヘ訴ヘ永ク眞言ノ道場ニ復スト云 影向石 三箇ノ石ヲ重置 是縁起ニ云ヘル不動ノ像ヲ安置セル處ナリ 辨財天社 弘法大師作坐身長七寸ノ像ヲ安シ 別ニ護摩ノ灰ニテ作レル像ヲモ置リ 地蔵堂 大黒天 本堂ノ後ノ方岩窟ノ中ニ安置ス」
「辨財天 峽下ノ洞中ニ安ス長一尺ノ石像ニテ松橋辨天ト号ス 弘法大師ノ作 當時此地ニ松橋ト云橋アリシ故地名ヲオハセテ唱トイヘリ 松橋ノ名ハ前ニ云ル如ク源平盛衰記ニ見エテ舊キ地名ナリ 治承ノ頃頼朝此辨天ヲ帰依ノ餘リ太刀ヲ寄附アリシ由縁起ニ載タレト今是ヲ失ナヘリ 洞中ニ文保三年三月ト彫タル古碑一基アリ 恵比須毘沙門石像紫の楓 紅葉ノ秋紫色ヲ帶ル故此名アリ」


【写真 上(左)】 旧松橋辨財天周辺
【写真 下(右)】 江戸名所図絵(松橋辨財天窟)
〔松橋辨財天〕
金剛寺は辨天様ともゆかりのふかいお寺です。
かつての滝野川は金剛寺付近で蛇行しており、その崖には辨天の滝がかかり、崖下にあった洞窟には辨財天が祀られていました。
この辨天様は弘法大師の御作ともいわれ、松橋辨天または岩屋辨天と呼ばれて信仰を集めました。
この辨天様は、源頼朝公が戦勝を祈願し太刀一振を奉納し、戦勝ののちに辨財天の堂舎を建立、田園の寄進をしたとも伝えられています。
滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』で犬塚信乃の母手束が子授けを祈った「滝野川なる岩屋殿」と記した岩屋がこの松橋辨天とされています。
辨天の滝は昭和初期に枯れ、昭和33年(1958年)の狩野川台風で辨天様の洞窟は崩壊し、一部は昭和50年(1975年)前後まで残っていたようですが、その後の護岸工事や流路改修の際に取り壊され、現在は音無もみじ緑地となっています。
現地の案内版より引用抜粋してみます。
「『江戸名所図絵』には『この地は石神井河の流れに臨み、自然の山水あり。両岸高く桜楓の二樹枝を交へ、春秋ともにながめあるの一勝地なり。』」「崖下の岩屋の中には弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。また、現在都営住宅が建っている付近の崖に瀧があり、弁天の滝と呼ばれていました。」
『新編武蔵風土記稿』によると、崖下洞窟内の「松橋辨財天(岩屋辨財天)」/弘法大師作長一尺ノ石像とは別に、金剛寺境内(崖上)にも「弘法大師作坐身長七寸ノ辨天像」が安置されていた様ですが、詳細はよくわかりません。
ただし、松橋辨天の崖下洞窟も金剛寺の領地内であったようなので、金剛寺=松橋辨天と捉えられていたのでは。
松橋辨天は江戸市内でもよく知られており、江戸三十三ヶ所弁財天霊場、弁財天百社参りの札所となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 紅葉寺の寺号標


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 西國霊場札所標
江戸時代からの行楽地とあって、金剛寺周辺はいまでも華やいだ雰囲気が感じられます。
入母屋造桟瓦葺の薬医門。扁額は「瀧河山」。頭貫部梁先の雲形木鼻がダイナミック。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
参道正面、階段の上に本堂向拝。
入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝。向かって左手手前に修行大師が御座します。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に本蟇股を配しています。
正面桟唐戸の上に「金剛寺」の扁額。
虹梁に金色の彫刻を置いた、名刹らしい堂々たる向拝です。


【写真 上(左)】 辨天堂
【写真 下(右)】 辨天堂扁額
本堂向かって右手に宝形造銅板葺の辨天堂と坐像の地蔵尊が御座します。
弁天堂の御本尊は松橋辨天の系譜を引かれるお像でしょうか。
手入れの行き届いた境内で、落ち着いて参拝ができます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 滝野川七福神
御朱印は本堂向かって左手の庫裡(客殿?)にて、ご丁寧なご対応をいただき拝受しました。

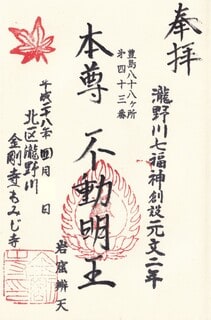
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第15番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第43番の御朱印
中央に「本尊 不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「滝野川寺院めぐり第十五番寺」と「滝野川七福神創設元文二年」の印判。左上に「豊島八十八ヶ所第四十三番」と「もみじ」の印判。左下に「岩窟辨天」の印判。
左下に寺号の印判と寺院印が捺されています。
豊島霊場の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十五番寺」の印判がなく、印判の位置も若干異なります。
「松橋辨天」の御朱印については伺っていませんが、Web上で見当たらないこと、既存の御朱印に「岩窟辨天」の印判があることから、おそらくは授与されていないと思います。
なお、「滝野川七福神」は、金剛寺境内に祀られている七福神をさすようです。
第16番
南照山 観音院 寿徳寺
北区滝野川4-22-1
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第17番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第12番、大東京百観音霊場第80番、北豊島三十三観音霊場第32番
ついに結願の16番。真言宗豊山派の寿徳寺です。
金剛寺とは反対側の滝野川の左岸にあります。


【写真 上(左)】 川沿いの遊歩道
【写真 下(右)】 滝野川橋
金剛寺から寿徳寺への順路には音無もみじ緑地があり、滝野川沿いの遊歩道の紅葉も綺麗で、歩いていて楽しいところです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
『滝野川寺院めぐり案内』によると、寿徳寺は寿永年間(1182-1185年)、梶原氏の家臣であった早船・小宮の両氏が梶原氏と不和になり落ち延びる途中で、海中から拾いあげた観世音菩薩を滝野川の北岸沿いの堂山の地に小堂を設け安置したのが創建と伝わります。
本尊は谷津子育観音と親しまれ、新撰組の近藤勇、および隊士の菩提寺としても知られています。
境外地には谷津大観音、近藤勇の墓所(JR埼京線「板橋」駅前)があります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。
なお、『新編武蔵風土記稿』の「寿福寺」は誤植です。
「新義真言宗田端村東覺寺門徒、南照山観音院ト号ス 本尊子安観音」


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 近藤勇の碑


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 西國霊場札所碑
住宅地のなか、ぽっかりと開けた一角に立地し、境内も広々としています。
門外左手に不動堂。境内左手に修行大師像が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め右からの本堂
正面に昭和41年(1966年)落慶の本堂。
両脇に仁王尊像を置いた石段の上に、アーチ形の屋根をもつ独特なつくりの朱色の建物。
正面向拝部に「南照山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
寺伝によると、秘仏の御本尊、谷津観音は蓮華座に坐り、両手で乳児を膝の上に抱えている姿で、指を阿弥陀如来と同じ弥陀の定印に結んでおられるそうです。
本堂の向かって右にある護摩堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁と向拝柱を備え、これは以前の本堂とのこと。


【写真 上(左)】 旧本堂(護摩堂)
【写真 下(右)】 乳が垂れている銀杏
境内に切株から芽吹いている銀杏は、かつては巨木で、この樹の皮をはいで本尊に供え、祈願した後に煎じて飲むと母乳が良く出るようになるという信仰がありました。
正岡子規の高弟として知られる俳人、河東 碧梧桐の句
- 秋立つや子安詣での花の束 -
が残されており、明治に入っても谷津観音への子安詣では盛んであったことがうかがわれます。
山内には、独特の雰囲気を放つインド仏も露座しています。


【写真 上(左)】 インド仏
【写真 下(右)】 滝野川と谷津大観音
谷津大観音は山内から少しくはなれた滝野川の河岸、観音橋のたもとに御座しています。
右手与願印、左手に蓮華をもたれるおだやかな表情の銅製の坐像です。
観音橋から寿徳寺に向かい登っていく坂を「観音の坂」といいます。
現地案内標には「観音橋の北から寿徳寺へ登る坂です。坂名は、坂上にある寿徳寺に谷津観音の名で知られる観音様がまつられているからです。江戸時代には大門通とも呼ばれていました。」とあります。(北区教育委員会)


【写真 上(左)】 観音橋と谷津大観音
【写真 下(右)】 谷津大観音
御朱印は本堂向かって右手奥の庫裡にて拝受しました。
ご丁寧なご対応をいただき、「滝野川十六番満願」の揮毫もいただきました。
やはり「滝野川寺院めぐり」の巡拝者は少ないとのことでした。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第16番(満願)の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第12番の御朱印
中央に御本尊聖観世音菩薩の種子「サ」・「子育 谷津観音」の揮毫と「谷津子育観音」の印判。右上に聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。左下に寺号の揮毫と寺院印。右に「滝野川十六番満願」の揮毫をいただきました。
豊島霊場の御朱印とは、札番の揮毫が異なります。
これで滝野川寺院めぐりは結願です。
北区の落ち着いた街区を巡るこの巡拝コース、札所構成も変化に富んでいて、知名度は低いですがおすすめだと思います。
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 孤独な生きもの - KOKIA
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第7番
光明山 照徳院 円勝寺
北区中里町3-1-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:南無阿彌陀佛(六字御名号)
江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番
第7番は、浄土宗の円勝寺です。
鎌倉期の文永年間(1264-1275年)、浄土宗第2祖鎮西正宗國師の弟子信阿聖法の開山と伝わる古刹です。
一時荒廃しましたが文明年間(1469-1487年)、香誉上人が中興
戦国時代までは(江戸城)曲輪内龍ノ口(和田倉門の周辺)にあり、のちに当地に移転したと伝わります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号104/107)に以下の記述があります。
「浄土宗芝増上寺末 光明山照徳院ト号ス 本尊彌陀ハ立像長ニ尺許慈覚大師ノ作ト云 開山僧信阿聖法弘安九年二月十五日寂 御入國ノ頃ハ御曲輪内龍ノ口辺ニアリシト云 勢至堂 佛師春日ノ作レル立身ノ勢至ヲ前立トシ故アツテ三尊彌陀ヲ内佛ニ安ス 鐘楼 正徳二年新鋳ノ鐘ヲカク 御腰掛松 古木ハ枯テ植纏シモノナリ相伝フ慶長ノ頃此辺御遊猟ノ時當寺ヘ成ラセラレ此松ニ御腰ヲ掛サセラレシ故此名アリ 又此時寺領五石ノ御朱印ヲ賜ヒシガ五石松トモ称ズトイヘリ 其御朱印ハ後年回録ニカカリ烏有トナリ地所ハ今ニ領セリ」
江戸名所図会には「圓照寺 五石松」として載っています。(参考資料)
慶長の頃、家康公が御放鷹の折に当寺にお成り、上の由来をもってこの地の名所となっていたようですが(「家康公の腰掛け松」とも云われたらしい)、いまは残されていないようです。
寺宝として、護良親王の鉄冠、知恩院宮第6世尊超法親王の名号などを蔵します。
石州流茶道の流れをくむ伊佐家代々の墓所(→ 文化財説明板伊佐家の墓/北区飛鳥山博物館資料)で、茶道と所縁のふかいお寺です。
筆者は茶道の心得はまったくありませんが、茶道の流派について少しく勉強してみました。
茶道の流派の多くは、武野紹鴎の門人か千利休の直弟子の流れとされています。
(以下、系譜については諸説あるようです。)
■ 利休七哲
千利休には利休七哲(りきゅうしちてつ、蒲生氏郷、細川忠興(三斎)、古田重然(織部)、芝山宗綱(監物)、瀬田正忠(掃部)、高山長房(右近/南坊)、牧村利貞(兵部))と称される高弟があり、ここからつながる流派があります。
細川忠興(三斎)→ 三斎流(一尾流)、御家流
古田重然(織部)→ 織部流 、遠州流、小堀遠州流、大和遠州流、上田宗箇流、御家流
■ 千道安の流れ(堺千家系)
・宗和流 流祖、金森重近(宗和)は千利休の門下、長近の養子金森可重は千道安の門下とされる。加賀藩にて隆盛。
・石州流 流祖、片桐石州は千道安門下の桑山宗仙に師事。
・石州流怡渓派
・石州流伊佐派 怡渓派の伊佐家の系譜につながるとされる。
※他に石州流として数派あり
・鎮信流 流祖は肥前平戸藩四代藩主松浦鎮信公。石州流・宗和流の流れ。
・不昧流 流祖は松平不昧公(治郷公)。不昧公は石州流怡渓派三代伊佐幸琢から石州流怡渓派を学んだため、石州流不昧派と称されることがある。
■ 千宗旦の流れ(宗旦流)
・三千家 千利休の後妻の連れ子である千少庵の系統
・表千家 不審庵 宗旦の三男の系統。江戸千家もこの流れ。
・裏千家 今日庵 宗旦の四男の系統
・武者小路千家 官休庵 宗旦の二男の系統
・宗旦四天王 宗旦の門弟のうち、とくに活躍した4人にちなむ流派
・宗徧流 流祖は山田宗徧。
・庸軒流 流祖は藤村庸軒。
・普斎流 流祖は杉木普斎。
※ 久須美疎安にちなむ流派は不詳
★ 柳営茶道(武家茶道四派)
江戸幕府で重んじられた武家茶道。「武家茶道四派」とも称され、現在も柳営会により啓蒙活動が営まれ、護国寺などで定例の茶会が催されています。
・旧磐城平藩主安藤家御家流
・小堀遠州流
・石州流伊佐派(石州流怡渓派の流れ)
・鎮信流
柳営(武家)茶道はいずれも利休七哲、ないし千道安の流れで、円勝寺とゆかりのふかい石州流怡渓派・伊佐派も江戸幕府と深いつながりがありました。
伊佐家は代々”幸琢”(こうたく)を名乗り、五代にわたって江戸幕府の数寄屋頭を勤めました。
数寄屋頭とは幕府の職名で、若年寄に属し、殿中の茶礼・茶器などを司り、数寄屋坊主を統轄したとされます。
怡渓宗悦(いけいそうえつ)は大徳寺二五三世に就かれた後、江戸の広尾祥雲寺や品川東海寺に入られた高僧で、茶人としても名高く、『石州流三百ヶ条註解』を著されて石州流怡渓派の派祖とされます。
なお、怡渓宗悦は関東大震災を契機に品川から世田谷烏山に移転した高源院の開山とされます。(高源院の御朱印はこちらに掲載しています。)
数寄屋頭初代の伊佐幸琢(半々庵)は怡渓宗悦より皆伝を受けた高弟で、以後五代にわたって幕府の御数寄屋頭となり石州流怡渓派の名を高めました。
不昧流の流祖、松平不昧公(治郷公)が、三代伊佐幸琢(半寸庵)から石州流怡渓派を学ばれたことからも、柳営茶道における伊佐家(石州流怡渓派)の権威のほどがうかがわれます。


【写真 上(左)】 「第二中里踏切」
【写真 下(右)】 参道入口
JR山手線の唯一の踏切「第二中里踏切」のすぐそばにある寺院です。
踏切のよこから伸びる参道は銀杏の並木、大ぶりな降り棟、袖塀を備えた立派な薬医門のおくに本堂が姿を見せています。


【写真 上(左)】 勢至菩薩碑
【写真 下(右)】 秋の参道
参道脇に「厄除 大勢至菩薩霊●」と刻まれた石碑があります。
『新編武蔵風土記稿』によると、かつて山内に勢至堂があり春日仏師による立身の勢至菩薩が祀られていたとされるので、これに因むものかと思われます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
山手線の線路に近いものの、山内には古刹特有の落ち着いた空気が流れています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、鬼板部、降り棟、隅棟、稚児棟すべての棟飾りに経の巻獅子口を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ


【写真 上(左)】 木鼻の獅子(左)
【写真 下(右)】 木鼻の獅子(右)
水引虹梁木鼻では、彫りの深い獅子が睨みをきかせています。
頭貫上に出三つ斗、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上に「光明山」の扁額。
扁額後ろの小壁にも彫り物が置かれ、向拝両脇の格子窓は奥に花頭窓を繰抜くなど芸が細かいです。


【写真 上(左)】 扁額と中備の龍
【写真 下(右)】 扁額
本堂右手の墓所、伊佐家の墓石には初代、二代半寸庵の和歌と俳句が刻まれています。
(文化五年(1808年)十一月銘)
- 出る日も入る日も遠き霊鷲山 またゝくひまに入相のかね -
初代 半寸庵知當


【写真 上(左)】 本堂手前から庫裡方向
【写真 下(右)】 庫裡
本堂左手の庫裡の方に進むと、さらに奥ゆかしい佇まいに。
こちらは、滝野川寺院めぐり第7番、江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番の3つの札所を兼ねておられますが、いずれも巡拝者は多いとは思われません。
しかし、ご住職は心あたたまるご対応で、御朱印の揮毫についてしきりに謙遜なさっておられましたが、素晴らしい筆致の御朱印を授与いただけました。
丸みを帯びた六字御名号は、祐天上人の御名号、徳本上人の「徳本文字」を彷彿とさせる筆致です。
当寺は、幡随意上人、祐天上人、徳本上人などの墨跡を蔵されるとのことなので、ご住職は六字御名号墨跡の研究をされているのかもしれません。
江戸・東京四十四閻魔参り第36番の札所で、閻魔様の御縁日の16日にも参拝しましたが、現在は閻魔大王の御朱印はお出しになられていないとのことです。

● 滝野川寺院めぐり第7番の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫と梵字九字の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左上に勢至菩薩の種子「サク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「勢至菩薩」を含む印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第七番寺」の札所印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
中央の梵字九字の内容は、不勉強につきよくわかりません。
御朱印にも勢至菩薩が登場されるので、やはりこのお寺様において勢至菩薩は格別の尊格なのかもしれません。
(寺宝として秘仏の大勢至菩薩像を蔵されます。また、勢至菩薩は浄土宗の根本所依教典である「観無量寿経」で説かれ、法然上人を勢至菩薩の化身(勢至菩薩は法然上人(幼名は勢至丸)の本地身)とする信仰もあって、浄土宗でもなじみのふかい尊格です。)


【上(左)】 御本尊(札所無申告)の御朱印
【下(右)】 閻魔大王御縁日(十六日)の御朱印
御本尊の御朱印は、滝野川寺院めぐりと同様の構成で、札所印は捺されていません。
閻魔大王御縁日の御朱印は、御本尊の御朱印と同じ内容です。
第8番
平塚山 案烙院 城官寺
公式Web
北区上中里1-42-8
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:阿弥陀如来
御府内八十八箇所第47番、豊島八十八ヶ所霊場第47番、江戸八十八ヶ所霊場第47番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番
第8番は、真言宗豊山派の城官寺です。
寺伝(当寺公式Web)によると、筑紫安楽寺の僧侶が諸国巡礼の折、当寺に宿泊した際に阿弥陀如来像を置き安楽院(安楽寺)と称し浄土宗の寺として創建。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号102/107)に以下の記述があります。
「(平塚明神社別當)城官寺 新義真言宗大塚護国寺末 平塚山安楽院ト号ス 本尊阿彌陀ハ赤栴檀ニテ坐身長一尺許 毘首羯摩ノ作と云 臺座ハ瑠璃ニテ造ル 是昔筑紫安楽寺ノ本尊ナリシカ 彼寺の僧回國ノ時當寺ニ旅宿シ故有テ是ヲ附属セシヨリ安楽寺ト称ス 其頃迄ハ浄土宗ナリシカ寛永十一年社領修理アリシ時、金剛佛子ヲ請シテ別當タラシメシヨリ、今ノ宗門ニ改ムト云(以下略)」
江戸時代、山川貞久(城官)という幕府仕えの鍼灸師が真言宗寺院として再興したと伝わります。
山川貞久(城官)は、三代将軍徳川家光公が病に倒れた時、平塚明神(現在の平塚神社)に治癒を日夜祈った。その霊験もあってか家光公の病は快癒し、貞久(城官)は私財を投じて平塚明神を再建、さらに寛永十一年(1634年)には平塚神社の別当として当寺を再興したとされます。
寛永十七年(1640年)、家光公が鷹狩りで当地を訪れた際、平塚神社の豪華さに驚き、村長に造営者を尋ねたところ、貞久(城官)による家光公平癒祈願と社殿再建のくだりが説明されました。
これを聞いた家光公は貞久(城官)を呼び、平塚神社と当寺の所領として五十石、さらに貞久(城官)に知行地として二百石を与え、寺号を平塚山 城官寺 安楽院とすべく命じたとされます。
享保三年(1718年)寂の真恵を法流開基として、現在に至ります。
当寺には、江戸幕府に奥医師として仕えた多紀・桂山一族の墓と山川貞久一族の墓があります。
奥医師には、典薬頭・奥医師・御番医師・寄合医師・小普請医師などが置かれ、奥医師は内科が多紀氏、外科は桂川氏が世襲しました。
当寺再興の山川貞久(城官)も鍼灸師ですから、当寺は医術とふかい所縁をもつことになります。
別当を勤めた平塚神社とは神仏分離により分かれましたが、少しく触れてみます。
御祭神は八幡太郎 源義家命、賀茂次郎 源義綱命、新羅三郎 源義光命の源家三兄弟で、三兄弟を一社で祀る例はめずらしいかと思います。
略縁起によると、創立は平安後期元永年中、八幡太郎義家公が奥州征伐の凱旋途中にこの地を訪れ領主豊島近義に鎧一領を賜われました。近義は拝領した鎧を清浄な地に埋め塚を築いて自城の鎮守として祀りました。平坦な塚だったので平塚と呼ばれ、三兄弟にちなんで平塚三所大明神として崇められました。
家光公の時代、上記の病平癒の件もあって再建され、家光公もたびたび参詣に訪れたとされます。
徳川家は源氏姓、新田氏流を名乗り、新田氏流(上野源氏)の祖は源義家公の三男義国公ですから、家光公が源家三兄弟をご祭神とする平塚神社を尊崇されたのも故あることかもしれません。


【写真 上(左)】 平塚神社の境内
【下(右)】 平塚神社の御朱印
当寺の最寄り駅はJR京浜東北線「上中里」駅か東京メトロ「西ケ原」駅。
いずれも都内屈指の閑散駅で、都内育ちでも知らない方が多いのでは?(わたしも寺社巡りをはじめて、はじめて降りました。)
ただし、周辺には寺社が意外に多いので、御朱印巡りの際には便利な駅といえましょう。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
人通りもまれな閑静な住宅地に、突如としてあらわれる立派な山門は桟瓦葺の四脚門。
「平塚山」の扁額は、当寺三百年を記念して書かれた当時の内閣総理大臣田中角栄氏の筆によるものとのこと。
山門前には御府内霊場第四十七番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 ???
全体に開放的であかるい雰囲気のお寺です。
正面に本堂。寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 向拝拝み部
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「城官寺」。格天井。扁額上の小壁に大瓶束と彫刻からなる笈形。
向拝屋根には経の巻獅子口と兎毛通を置く、存在感のある仏堂です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所の札所なので、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番の御朱印は、現在のところ授与されていないそうです。

● 滝野川寺院めぐり第8番の御朱印
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右下に「滝野川寺院めぐり 第八番寺」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
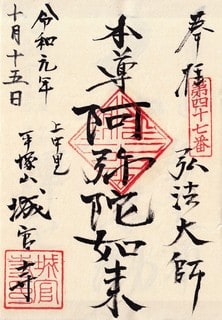
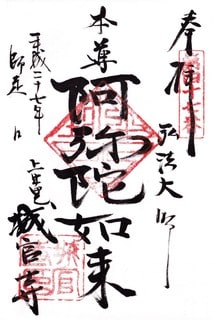
【上(左)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「本尊 阿弥陀如来」と「弘法大師」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右に「第四十七番」の札所印。左下に山号と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右上に「第四十七番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
滝野川寺院めぐりの御朱印とは札所印がことなるのみです。
第9番
佛寶山 西光院 無量寺
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王・弘法大師
御府内八十八箇所第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第59番、大東京百観音霊場第81番
第9番は、真言宗豊山派の無量寺です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所第59番の札所なので、認知度は比較的高いと思います。
また、こちらは江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺で、もともと参詣者の多い寺院とみられます。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル、古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ、常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ」
「寺寶 紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅」
「七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス 末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社」
「阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛 寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス」
創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
また、北区設置の説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺域を有していたといわれ、当寺が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺境内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」が表され、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったことがうかがわれます。
大正三年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現社地)に遷座されています。


【写真 上(左)】 七社神社の社頭
【写真 下(右)】 七社神社の境内
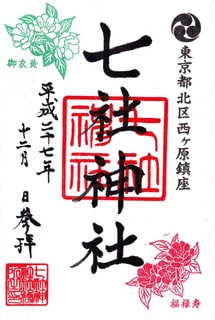

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)
【下(右)】 七社神社の御朱印
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅であり、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
現在でも、落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に台地上を辿ります。
第七番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅方面からだと本郷通りを越えての道順となるので、本郷通りからかなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門だと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある参道です。
緑ゆたかな境内は手入れも行き届き、枯淡な風情があります。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院だと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
本堂には阿弥陀如来坐像と、御本尊である不動明王像が御座します。
この阿弥陀如来像は、江戸時代に、江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂の中には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置されており、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標も建っており、札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるので、この「雷除けの本尊」が札所本尊かもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
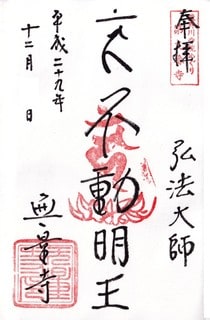
● 滝野川寺院めぐり第9番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「滝野川寺院めぐり 第九番寺」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

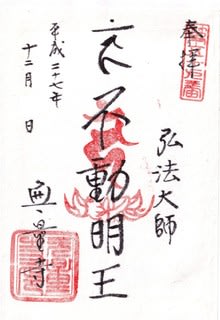
【上(左)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第59番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀如来第3番の御朱印
中央に「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三番」の札所印。右に「西ヶ原」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
第10番
補陀山 補陀落寿院 昌林寺
北区西ケ原3-12-6
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
御朱印尊格:末木観音
江戸六阿弥陀霊場(末木観音)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番、北豊島三十三観音霊場第19番
第10番は、曹洞宗の昌林寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、開創・開山・開基などは不詳。行基菩薩の作とされる末木観世音菩薩を御本尊とする。応永年間(1394~1428年)に鎌倉公方足利持氏公が再興し、禅刹に改め祥林寺と号した。その後江戸橋場総泉寺4世の宗最和尚が中興開山となり、昌林寺に改称。太田道灌公の寄進を受けて伽藍を善美とし、彫刻物はすべて左甚五郎の作と伝わる。明治十六年(1883年)曹洞宗大本山永平寺の61世絶海天真禅師がご入山され御隠寮となり、太政大臣三条実美公は当山の風光を賞して「百花一覧之台」と賛した。などの寺歴が記されています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「禅宗曹洞派橋場總泉寺末 補陀山ト号ス 古ハ補陀楽壽院ト号セシヲ應永十八年足利持氏再營シテ祥林寺ト改メ 文明十一年太田道灌田園二十四町を寄附セリ 其後大永五年丙丁ニ罹リシ後本山四世勝庵宗最中興シテ今ノ文字ニ改ム 此僧ハ天文十三年七月十五寂ス 本尊正観音ハ行基ノ作ニテ 六阿彌陀彫刻ノ時同木ノ末木ヲ以テコノ像ヲ作リシユヘ 末木ノ観音と号と云 昔ハ本堂ノ造リモ壮厳ヲ盡セシニヤ 今ノ堂ニ用ル所ノ扉獅子牡丹桐鳳凰等ノ彫刻最工ニシテ 近世ノモノニアラス是左甚五郎ノ作ニテ先年火災ノ時僅ニ残リシモノト云」
昌林寺は江戸(武州)六阿弥陀ゆかりの木残の末木観音様として知られています。
江戸(武州)六阿弥陀は、行基菩薩が一本の霊木から刻み上げた7体の阿弥陀仏と1体の観音様を参拝する阿弥陀巡りで、江戸時代、とくに春秋の彼岸に女性を中心に大流行したとされます。
五番常楽院の縁起、三番無量寺・木残昌林寺の寺伝、足立区資料、および「江戸の3 つの「六阿弥陀参」における「武州六阿弥陀参」の特徴」から創祀を辿ってみます。
その昔この地に「足立の長者」(足立庄司宮城宰相とも)という人がおり、年老いて子がないことを憂いて、熊野権現に祈ると女の子を授かりました。
「足立姫」と呼ばれたこの子は容顔麗しく、見るものはみな心を奪われたといいます。
成長した姫は「豊嶋の長者」(豊島左衛門尉清光とも)に嫁いだものの、誹りを受けて12人(6人とも)の侍女とともに荒川に身を投げ命を絶ってしまいました。
足立の長者はこれを悲しみ、娘や侍女の菩提のために諸国の霊場巡りに出立しました。
紀州牟宴の郡熊野権現に参籠した際、霊夢を蒙り1本の霊木を得て、これを熊野灘に流すと、やがてこの霊木は国元の熊野木(沼田の浦とも)というところに流れ着きました。
この霊木は不思議にも夜ごと光を放ちましたが、折しもこの地を巡られた行基菩薩は(この霊木は)浄土に導かんがための仏菩薩の化身なるべしと云われ、南無阿弥陀仏の六字の御名号数にあわせて霊木から六体の阿弥陀如来像を刻し、余り木からもう一体の阿弥陀仏、さらに残った木から一体の観音菩薩像を刻まれそれを姫の遺影として与えました。
後にこれら七体の阿弥陀仏と一体の観音像は近隣の寺院に祀られ、以降、女人成仏の阿弥陀参りとしてとくに江戸期に信仰を集めました。
『滝野川寺院めぐり案内』の無量寺の頁に「江戸近郊を歩くこのミニ巡礼は、表向きは信心とはいうものの、実際は世代家族の同居が当たり前だった時代の、年に2回のストレス解消とレクリエーションの一石二鳥の効果を狙ったものであった。まさに庶民が、日常生活の中から考えた知恵だったのであろう。」と記載されていますが、江戸の年中行事を描いた『東都歳時記』や『江戸名所図絵』でも複数取り上げられていることからも、そのような側面が大きかったと思われます。
滝野川寺院めぐりの無量寺、与楽寺、昌林寺の3寺は江戸六阿弥陀の札所と重複します。
また、桜の名所であった王子・飛鳥山、紅葉の名所として知られた滝野川、つつじの名所の駒込染井など、滝野川寺院めぐりの周辺エリアが江戸時代のレクリエーションの名所ときれいに重なっていることがわかります。
昌林寺の末木観世音菩薩については、『江戸名所図会』に、「本尊末木観世音菩薩は、開山行基菩薩の作なり。往古六阿弥陀彫刻の折から末木を以って作りたまひしとぞ。」と記され、江戸(武州)六阿弥陀との関連が裏付けられています。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標
谷田川通りから少し入った住宅街のなかにこぢんまりと整った山内。
山門脇に上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第5番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め左から本堂
入母屋造本瓦様の銅板葺で、軒下に向拝を付設しています。
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に「補陀山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
朱の欄干と横長の花頭窓が印象的な本堂の手前には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標と昭和62年造立の百寿観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 百寿観世音菩薩
【写真 下(右)】 本堂扁額
メジャー霊場の札所ではありませんが、最近は「江戸六阿弥陀」巡拝者も増えているのか、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は、「江戸六阿弥陀」の参拝でも捺されているようです。

● 滝野川寺院めぐり第10番の御朱印
中央に「末木観音」の揮毫と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に「滝野川寺院めぐり 第十番寺」の札所印で、札所無申告で授与されると思われる「藤井寺寫 西國第五番」の上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は捺されていません。
左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀(木残)の御朱印
中央に「本尊 末木観世音菩薩」の印判と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印の札所印「藤井寺寫 西國第五番」の札所印が捺されています。
左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
滝野川霊場の御朱印では「末木観音」の揮毫。江戸六阿弥陀と観音霊場の御朱印では「本尊 末木観世音菩薩」の印判の様式にて授与されるようです。
第11番
明王山 大聖寺 不動院
北区西ヶ原3-23-2
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第53番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番、北豊島三十三観音霊場第29番
第11番は、真言宗豊山派の不動院です。
第10番昌林寺から谷田川通り沿いに少し歩くと不動院です。
ここで通りの由来となった「谷田川」について少し考えてみます。
谷田川はいまはすべて暗渠となり地図上から辿るのは困難ですが、世の中には奇特な方がおられ、かつての谷田川を辿る紀行がWebでいくつかみつかるので、そちらも参考にさせていただきまとめてみます。
谷田川はかつての石神井川とみる説もありますが、多くの説は染井霊園の北側ないし巣鴨あたりを源流とする別の流れと.みています。
そこから西ヶ原銀座通りに入り、染井銀座商店街~霜降銀座商店街と流れます。
本郷通りの「霜降橋」交差点は、谷田川にかかっていた橋名のなごりとされています。
ここからはほぼ谷田川通りに沿って、池之端の不忍池をめざして下っていきます。
谷田川通りは不忍通りのすぐ東側を走っています。
JR駒込駅の東側あたりで山手線内に入り、西日暮里駅の西側を通って、谷中と千駄木のあいだを流れます。根津駅から谷中への登り口にあたる大黒屋煎餅の下あたりを流れ、池之端辺で不忍池に流れ込みます。
ここで気づいたのは、「滝野川寺院めぐり」は、ほぼ旧谷田川に沿って札所が置かれているということです。
JR田端駅南側から旧古河庭園にかけては高台にあり、その名もずばり「田端高台通り」が走っています。
また、旧古河庭園から王子・飛鳥山にかけても高台で、ふるくは「御殿山」と呼ばれていました。なので、田端駅から王子駅にかけてのJRの南側はすべて高台にあります。
谷田川はこの高台の南側下を沿うように流れていました。
「滝野川寺院めぐり」の札所は一部の例外をのぞいて、この高台と旧谷田川のあいだの南傾地に位置しています。
寺社は崖線に沿って置かれる例が多いので、こちらも例外ではありません。
第1番与楽寺~第7番円勝寺は、すべて「田端高台通り」と旧谷田川のあいだにあり、南傾斜面をトラバースしていくので、大きな高低差はありません。
第8番城官寺は「御殿山」まわりの高台にあり、そこから旧谷田川の流れに近い第9番無量寺の山門までは、急なくだりとなります。
旧谷田川沿いの第10番昌林寺、第11番不動寺を経て、ふたたび「御殿山」エリアにある第12番妙見寺に向けて登りがつづきます。
以上のとおり、第8番城官寺から第12番妙見寺にかけては、地形的にも変化に富んだ巡拝を味わうことができます。
不動院の開創については『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「同宗田端村與樂寺門徒明王山ト號ス 本尊不動開山僧海善 元和六年六月六日寂」
開山は海善和尚(元和六年(1620年)遷化)。その後は数度の火災により寺伝が焼失し詳細は不明のようです。
また、『新編武蔵風土記稿』に「阿彌陀堂。西國二十三番攝州勝尼寺寫の観音を相殿とす。」とあるので、不動明王が御座す本堂のほかに阿弥陀堂があって、そちらに西國二十三番(上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番)の札所本尊の観音様が祀られていたのかもしれません。
同書によると、当初は田端与楽寺の末でしたが、『滝野川寺院めぐり案内』によると、昭和16年(1941年)、総本山長谷寺に本寺換えをしています。
『滝野川寺院めぐり案内』には、当寺御本尊のお不動様ゆかりの逸話が記されています。
先の終戦直後、一帯は焼け野原となりましたが、いち早く境内に小屋(お堂)が建てられました。あるときこの小屋(お堂)に賊が侵入し、堂守をされていた慈信和尚の御母堂に刃物を突きつけました。そのとき、どこからともなく人の近づく足音が聞こえ、賊は一物もとらずに退散したそうです。
件の賊は後年、本人の努力と関係者の指導よろしきを得て立派に更正し、平和な一生を全うしたそうです。
このことが近辺に伝わり、当寺のお不動様は「魔除け不動」として信者さんの信仰を集めているそうです。


【写真 上(左)】 豊島霊場札所標
【写真 下(右)】 寺号標
山門向かって右側に「弘法大師」と豊島霊場が一体となった石碑、右手に寺号標と真新しい六地蔵が御座します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 山門付近から山内
本堂は昭和51年建立の鉄筋建てで、手前の階段をのぼった2階正面が向拝となっています。
本堂下には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第23番の札所標がありました。


【写真 上(左)】 本堂下
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 西国霊場札所標
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて授与いただけます。
最近巡拝者が増えているといわれる豊島八十八ヶ所霊場の第53番の札所なので、御朱印授与は手慣れておられ、書置のご用意もありました。
参拝時、ご住職はご不在で豊島霊場の御朱印ならば書置に札所印を捺してすぐにお出しになれるとのことでしたが、滝野川霊場の札所印は所在不明とのこと。
郵送をお願いすると快くお受けいただいたので、郵送にて拝受しました。
(ちなみに、筆者は宛先を書いて切手を貼り、郵送のお願い文書と御朱印用紙を同封した返信用の封筒を持ち歩いています。)


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第53番の御朱印
中央に「不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の荘厳体種子「カンマン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「豊島八十八ヶ所第五十三番」の札所印。
左上に「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判。
左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
豊島霊場御朱印との違いは「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判の有無のみです。
(第12番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 茜色の約束 - 森恵
■ 夢の大地 - Kalafina
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。
第7番
光明山 照徳院 円勝寺
北区中里町3-1-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:南無阿彌陀佛(六字御名号)
江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番
第7番は、浄土宗の円勝寺です。
鎌倉期の文永年間(1264-1275年)、浄土宗第2祖鎮西正宗國師の弟子信阿聖法の開山と伝わる古刹です。
一時荒廃しましたが文明年間(1469-1487年)、香誉上人が中興
戦国時代までは(江戸城)曲輪内龍ノ口(和田倉門の周辺)にあり、のちに当地に移転したと伝わります。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号104/107)に以下の記述があります。
「浄土宗芝増上寺末 光明山照徳院ト号ス 本尊彌陀ハ立像長ニ尺許慈覚大師ノ作ト云 開山僧信阿聖法弘安九年二月十五日寂 御入國ノ頃ハ御曲輪内龍ノ口辺ニアリシト云 勢至堂 佛師春日ノ作レル立身ノ勢至ヲ前立トシ故アツテ三尊彌陀ヲ内佛ニ安ス 鐘楼 正徳二年新鋳ノ鐘ヲカク 御腰掛松 古木ハ枯テ植纏シモノナリ相伝フ慶長ノ頃此辺御遊猟ノ時當寺ヘ成ラセラレ此松ニ御腰ヲ掛サセラレシ故此名アリ 又此時寺領五石ノ御朱印ヲ賜ヒシガ五石松トモ称ズトイヘリ 其御朱印ハ後年回録ニカカリ烏有トナリ地所ハ今ニ領セリ」
江戸名所図会には「圓照寺 五石松」として載っています。(参考資料)
慶長の頃、家康公が御放鷹の折に当寺にお成り、上の由来をもってこの地の名所となっていたようですが(「家康公の腰掛け松」とも云われたらしい)、いまは残されていないようです。
寺宝として、護良親王の鉄冠、知恩院宮第6世尊超法親王の名号などを蔵します。
石州流茶道の流れをくむ伊佐家代々の墓所(→ 文化財説明板伊佐家の墓/北区飛鳥山博物館資料)で、茶道と所縁のふかいお寺です。
筆者は茶道の心得はまったくありませんが、茶道の流派について少しく勉強してみました。
茶道の流派の多くは、武野紹鴎の門人か千利休の直弟子の流れとされています。
(以下、系譜については諸説あるようです。)
■ 利休七哲
千利休には利休七哲(りきゅうしちてつ、蒲生氏郷、細川忠興(三斎)、古田重然(織部)、芝山宗綱(監物)、瀬田正忠(掃部)、高山長房(右近/南坊)、牧村利貞(兵部))と称される高弟があり、ここからつながる流派があります。
細川忠興(三斎)→ 三斎流(一尾流)、御家流
古田重然(織部)→ 織部流 、遠州流、小堀遠州流、大和遠州流、上田宗箇流、御家流
■ 千道安の流れ(堺千家系)
・宗和流 流祖、金森重近(宗和)は千利休の門下、長近の養子金森可重は千道安の門下とされる。加賀藩にて隆盛。
・石州流 流祖、片桐石州は千道安門下の桑山宗仙に師事。
・石州流怡渓派
・石州流伊佐派 怡渓派の伊佐家の系譜につながるとされる。
※他に石州流として数派あり
・鎮信流 流祖は肥前平戸藩四代藩主松浦鎮信公。石州流・宗和流の流れ。
・不昧流 流祖は松平不昧公(治郷公)。不昧公は石州流怡渓派三代伊佐幸琢から石州流怡渓派を学んだため、石州流不昧派と称されることがある。
■ 千宗旦の流れ(宗旦流)
・三千家 千利休の後妻の連れ子である千少庵の系統
・表千家 不審庵 宗旦の三男の系統。江戸千家もこの流れ。
・裏千家 今日庵 宗旦の四男の系統
・武者小路千家 官休庵 宗旦の二男の系統
・宗旦四天王 宗旦の門弟のうち、とくに活躍した4人にちなむ流派
・宗徧流 流祖は山田宗徧。
・庸軒流 流祖は藤村庸軒。
・普斎流 流祖は杉木普斎。
※ 久須美疎安にちなむ流派は不詳
★ 柳営茶道(武家茶道四派)
江戸幕府で重んじられた武家茶道。「武家茶道四派」とも称され、現在も柳営会により啓蒙活動が営まれ、護国寺などで定例の茶会が催されています。
・旧磐城平藩主安藤家御家流
・小堀遠州流
・石州流伊佐派(石州流怡渓派の流れ)
・鎮信流
柳営(武家)茶道はいずれも利休七哲、ないし千道安の流れで、円勝寺とゆかりのふかい石州流怡渓派・伊佐派も江戸幕府と深いつながりがありました。
伊佐家は代々”幸琢”(こうたく)を名乗り、五代にわたって江戸幕府の数寄屋頭を勤めました。
数寄屋頭とは幕府の職名で、若年寄に属し、殿中の茶礼・茶器などを司り、数寄屋坊主を統轄したとされます。
怡渓宗悦(いけいそうえつ)は大徳寺二五三世に就かれた後、江戸の広尾祥雲寺や品川東海寺に入られた高僧で、茶人としても名高く、『石州流三百ヶ条註解』を著されて石州流怡渓派の派祖とされます。
なお、怡渓宗悦は関東大震災を契機に品川から世田谷烏山に移転した高源院の開山とされます。(高源院の御朱印はこちらに掲載しています。)
数寄屋頭初代の伊佐幸琢(半々庵)は怡渓宗悦より皆伝を受けた高弟で、以後五代にわたって幕府の御数寄屋頭となり石州流怡渓派の名を高めました。
不昧流の流祖、松平不昧公(治郷公)が、三代伊佐幸琢(半寸庵)から石州流怡渓派を学ばれたことからも、柳営茶道における伊佐家(石州流怡渓派)の権威のほどがうかがわれます。


【写真 上(左)】 「第二中里踏切」
【写真 下(右)】 参道入口
JR山手線の唯一の踏切「第二中里踏切」のすぐそばにある寺院です。
踏切のよこから伸びる参道は銀杏の並木、大ぶりな降り棟、袖塀を備えた立派な薬医門のおくに本堂が姿を見せています。


【写真 上(左)】 勢至菩薩碑
【写真 下(右)】 秋の参道
参道脇に「厄除 大勢至菩薩霊●」と刻まれた石碑があります。
『新編武蔵風土記稿』によると、かつて山内に勢至堂があり春日仏師による立身の勢至菩薩が祀られていたとされるので、これに因むものかと思われます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
山手線の線路に近いものの、山内には古刹特有の落ち着いた空気が流れています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、鬼板部、降り棟、隅棟、稚児棟すべての棟飾りに経の巻獅子口を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ


【写真 上(左)】 木鼻の獅子(左)
【写真 下(右)】 木鼻の獅子(右)
水引虹梁木鼻では、彫りの深い獅子が睨みをきかせています。
頭貫上に出三つ斗、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上に「光明山」の扁額。
扁額後ろの小壁にも彫り物が置かれ、向拝両脇の格子窓は奥に花頭窓を繰抜くなど芸が細かいです。


【写真 上(左)】 扁額と中備の龍
【写真 下(右)】 扁額
本堂右手の墓所、伊佐家の墓石には初代、二代半寸庵の和歌と俳句が刻まれています。
(文化五年(1808年)十一月銘)
- 出る日も入る日も遠き霊鷲山 またゝくひまに入相のかね -
初代 半寸庵知當


【写真 上(左)】 本堂手前から庫裡方向
【写真 下(右)】 庫裡
本堂左手の庫裡の方に進むと、さらに奥ゆかしい佇まいに。
こちらは、滝野川寺院めぐり第7番、江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番の3つの札所を兼ねておられますが、いずれも巡拝者は多いとは思われません。
しかし、ご住職は心あたたまるご対応で、御朱印の揮毫についてしきりに謙遜なさっておられましたが、素晴らしい筆致の御朱印を授与いただけました。
丸みを帯びた六字御名号は、祐天上人の御名号、徳本上人の「徳本文字」を彷彿とさせる筆致です。
当寺は、幡随意上人、祐天上人、徳本上人などの墨跡を蔵されるとのことなので、ご住職は六字御名号墨跡の研究をされているのかもしれません。
江戸・東京四十四閻魔参り第36番の札所で、閻魔様の御縁日の16日にも参拝しましたが、現在は閻魔大王の御朱印はお出しになられていないとのことです。

● 滝野川寺院めぐり第7番の御朱印
中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫と梵字九字の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左上に勢至菩薩の種子「サク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「勢至菩薩」を含む印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第七番寺」の札所印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
中央の梵字九字の内容は、不勉強につきよくわかりません。
御朱印にも勢至菩薩が登場されるので、やはりこのお寺様において勢至菩薩は格別の尊格なのかもしれません。
(寺宝として秘仏の大勢至菩薩像を蔵されます。また、勢至菩薩は浄土宗の根本所依教典である「観無量寿経」で説かれ、法然上人を勢至菩薩の化身(勢至菩薩は法然上人(幼名は勢至丸)の本地身)とする信仰もあって、浄土宗でもなじみのふかい尊格です。)


【上(左)】 御本尊(札所無申告)の御朱印
【下(右)】 閻魔大王御縁日(十六日)の御朱印
御本尊の御朱印は、滝野川寺院めぐりと同様の構成で、札所印は捺されていません。
閻魔大王御縁日の御朱印は、御本尊の御朱印と同じ内容です。
第8番
平塚山 案烙院 城官寺
公式Web
北区上中里1-42-8
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:阿弥陀如来
御府内八十八箇所第47番、豊島八十八ヶ所霊場第47番、江戸八十八ヶ所霊場第47番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番
第8番は、真言宗豊山派の城官寺です。
寺伝(当寺公式Web)によると、筑紫安楽寺の僧侶が諸国巡礼の折、当寺に宿泊した際に阿弥陀如来像を置き安楽院(安楽寺)と称し浄土宗の寺として創建。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号102/107)に以下の記述があります。
「(平塚明神社別當)城官寺 新義真言宗大塚護国寺末 平塚山安楽院ト号ス 本尊阿彌陀ハ赤栴檀ニテ坐身長一尺許 毘首羯摩ノ作と云 臺座ハ瑠璃ニテ造ル 是昔筑紫安楽寺ノ本尊ナリシカ 彼寺の僧回國ノ時當寺ニ旅宿シ故有テ是ヲ附属セシヨリ安楽寺ト称ス 其頃迄ハ浄土宗ナリシカ寛永十一年社領修理アリシ時、金剛佛子ヲ請シテ別當タラシメシヨリ、今ノ宗門ニ改ムト云(以下略)」
江戸時代、山川貞久(城官)という幕府仕えの鍼灸師が真言宗寺院として再興したと伝わります。
山川貞久(城官)は、三代将軍徳川家光公が病に倒れた時、平塚明神(現在の平塚神社)に治癒を日夜祈った。その霊験もあってか家光公の病は快癒し、貞久(城官)は私財を投じて平塚明神を再建、さらに寛永十一年(1634年)には平塚神社の別当として当寺を再興したとされます。
寛永十七年(1640年)、家光公が鷹狩りで当地を訪れた際、平塚神社の豪華さに驚き、村長に造営者を尋ねたところ、貞久(城官)による家光公平癒祈願と社殿再建のくだりが説明されました。
これを聞いた家光公は貞久(城官)を呼び、平塚神社と当寺の所領として五十石、さらに貞久(城官)に知行地として二百石を与え、寺号を平塚山 城官寺 安楽院とすべく命じたとされます。
享保三年(1718年)寂の真恵を法流開基として、現在に至ります。
当寺には、江戸幕府に奥医師として仕えた多紀・桂山一族の墓と山川貞久一族の墓があります。
奥医師には、典薬頭・奥医師・御番医師・寄合医師・小普請医師などが置かれ、奥医師は内科が多紀氏、外科は桂川氏が世襲しました。
当寺再興の山川貞久(城官)も鍼灸師ですから、当寺は医術とふかい所縁をもつことになります。
別当を勤めた平塚神社とは神仏分離により分かれましたが、少しく触れてみます。
御祭神は八幡太郎 源義家命、賀茂次郎 源義綱命、新羅三郎 源義光命の源家三兄弟で、三兄弟を一社で祀る例はめずらしいかと思います。
略縁起によると、創立は平安後期元永年中、八幡太郎義家公が奥州征伐の凱旋途中にこの地を訪れ領主豊島近義に鎧一領を賜われました。近義は拝領した鎧を清浄な地に埋め塚を築いて自城の鎮守として祀りました。平坦な塚だったので平塚と呼ばれ、三兄弟にちなんで平塚三所大明神として崇められました。
家光公の時代、上記の病平癒の件もあって再建され、家光公もたびたび参詣に訪れたとされます。
徳川家は源氏姓、新田氏流を名乗り、新田氏流(上野源氏)の祖は源義家公の三男義国公ですから、家光公が源家三兄弟をご祭神とする平塚神社を尊崇されたのも故あることかもしれません。


【写真 上(左)】 平塚神社の境内
【下(右)】 平塚神社の御朱印
当寺の最寄り駅はJR京浜東北線「上中里」駅か東京メトロ「西ケ原」駅。
いずれも都内屈指の閑散駅で、都内育ちでも知らない方が多いのでは?(わたしも寺社巡りをはじめて、はじめて降りました。)
ただし、周辺には寺社が意外に多いので、御朱印巡りの際には便利な駅といえましょう。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
人通りもまれな閑静な住宅地に、突如としてあらわれる立派な山門は桟瓦葺の四脚門。
「平塚山」の扁額は、当寺三百年を記念して書かれた当時の内閣総理大臣田中角栄氏の筆によるものとのこと。
山門前には御府内霊場第四十七番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 ???
全体に開放的であかるい雰囲気のお寺です。
正面に本堂。寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 向拝拝み部
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「城官寺」。格天井。扁額上の小壁に大瓶束と彫刻からなる笈形。
向拝屋根には経の巻獅子口と兎毛通を置く、存在感のある仏堂です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所の札所なので、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番の御朱印は、現在のところ授与されていないそうです。

● 滝野川寺院めぐり第8番の御朱印
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右下に「滝野川寺院めぐり 第八番寺」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
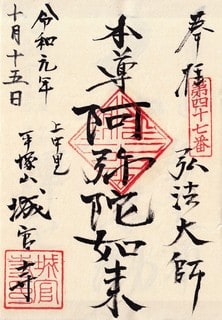
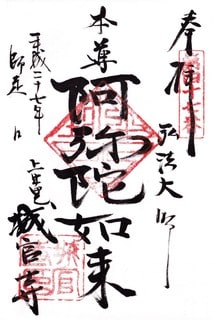
【上(左)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「本尊 阿弥陀如来」と「弘法大師」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右に「第四十七番」の札所印。左下に山号と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右上に「第四十七番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
滝野川寺院めぐりの御朱印とは札所印がことなるのみです。
第9番
佛寶山 西光院 無量寺
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王・弘法大師
御府内八十八箇所第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第59番、大東京百観音霊場第81番
第9番は、真言宗豊山派の無量寺です。
メジャー霊場、御府内八十八箇所第59番の札所なので、認知度は比較的高いと思います。
また、こちらは江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺で、もともと参詣者の多い寺院とみられます。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル、古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ、常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ」
「寺寶 紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅」
「七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス 末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社」
「阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛 寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス」
創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
また、北区設置の説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺域を有していたといわれ、当寺が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺境内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」が表され、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったことがうかがわれます。
大正三年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現社地)に遷座されています。


【写真 上(左)】 七社神社の社頭
【写真 下(右)】 七社神社の境内
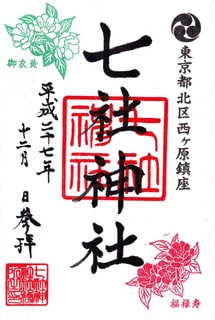

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)
【下(右)】 七社神社の御朱印
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅であり、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
現在でも、落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に台地上を辿ります。
第七番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅方面からだと本郷通りを越えての道順となるので、本郷通りからかなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門だと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある参道です。
緑ゆたかな境内は手入れも行き届き、枯淡な風情があります。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院だと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
本堂には阿弥陀如来坐像と、御本尊である不動明王像が御座します。
この阿弥陀如来像は、江戸時代に、江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂の中には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置されており、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標も建っており、札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるので、この「雷除けの本尊」が札所本尊かもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
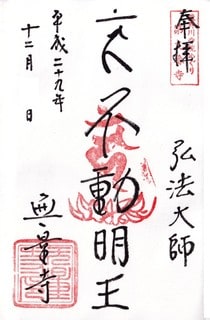
● 滝野川寺院めぐり第9番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「滝野川寺院めぐり 第九番寺」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

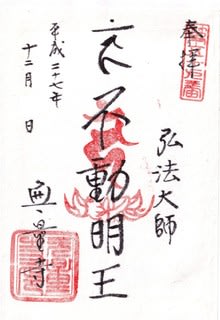
【上(左)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第59番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀如来第3番の御朱印
中央に「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三番」の札所印。右に「西ヶ原」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
第10番
補陀山 補陀落寿院 昌林寺
北区西ケ原3-12-6
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
御朱印尊格:末木観音
江戸六阿弥陀霊場(末木観音)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番、北豊島三十三観音霊場第19番
第10番は、曹洞宗の昌林寺です。
『滝野川寺院めぐり案内』には、開創・開山・開基などは不詳。行基菩薩の作とされる末木観世音菩薩を御本尊とする。応永年間(1394~1428年)に鎌倉公方足利持氏公が再興し、禅刹に改め祥林寺と号した。その後江戸橋場総泉寺4世の宗最和尚が中興開山となり、昌林寺に改称。太田道灌公の寄進を受けて伽藍を善美とし、彫刻物はすべて左甚五郎の作と伝わる。明治十六年(1883年)曹洞宗大本山永平寺の61世絶海天真禅師がご入山され御隠寮となり、太政大臣三条実美公は当山の風光を賞して「百花一覧之台」と賛した。などの寺歴が記されています。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「禅宗曹洞派橋場總泉寺末 補陀山ト号ス 古ハ補陀楽壽院ト号セシヲ應永十八年足利持氏再營シテ祥林寺ト改メ 文明十一年太田道灌田園二十四町を寄附セリ 其後大永五年丙丁ニ罹リシ後本山四世勝庵宗最中興シテ今ノ文字ニ改ム 此僧ハ天文十三年七月十五寂ス 本尊正観音ハ行基ノ作ニテ 六阿彌陀彫刻ノ時同木ノ末木ヲ以テコノ像ヲ作リシユヘ 末木ノ観音と号と云 昔ハ本堂ノ造リモ壮厳ヲ盡セシニヤ 今ノ堂ニ用ル所ノ扉獅子牡丹桐鳳凰等ノ彫刻最工ニシテ 近世ノモノニアラス是左甚五郎ノ作ニテ先年火災ノ時僅ニ残リシモノト云」
昌林寺は江戸(武州)六阿弥陀ゆかりの木残の末木観音様として知られています。
江戸(武州)六阿弥陀は、行基菩薩が一本の霊木から刻み上げた7体の阿弥陀仏と1体の観音様を参拝する阿弥陀巡りで、江戸時代、とくに春秋の彼岸に女性を中心に大流行したとされます。
五番常楽院の縁起、三番無量寺・木残昌林寺の寺伝、足立区資料、および「江戸の3 つの「六阿弥陀参」における「武州六阿弥陀参」の特徴」から創祀を辿ってみます。
その昔この地に「足立の長者」(足立庄司宮城宰相とも)という人がおり、年老いて子がないことを憂いて、熊野権現に祈ると女の子を授かりました。
「足立姫」と呼ばれたこの子は容顔麗しく、見るものはみな心を奪われたといいます。
成長した姫は「豊嶋の長者」(豊島左衛門尉清光とも)に嫁いだものの、誹りを受けて12人(6人とも)の侍女とともに荒川に身を投げ命を絶ってしまいました。
足立の長者はこれを悲しみ、娘や侍女の菩提のために諸国の霊場巡りに出立しました。
紀州牟宴の郡熊野権現に参籠した際、霊夢を蒙り1本の霊木を得て、これを熊野灘に流すと、やがてこの霊木は国元の熊野木(沼田の浦とも)というところに流れ着きました。
この霊木は不思議にも夜ごと光を放ちましたが、折しもこの地を巡られた行基菩薩は(この霊木は)浄土に導かんがための仏菩薩の化身なるべしと云われ、南無阿弥陀仏の六字の御名号数にあわせて霊木から六体の阿弥陀如来像を刻し、余り木からもう一体の阿弥陀仏、さらに残った木から一体の観音菩薩像を刻まれそれを姫の遺影として与えました。
後にこれら七体の阿弥陀仏と一体の観音像は近隣の寺院に祀られ、以降、女人成仏の阿弥陀参りとしてとくに江戸期に信仰を集めました。
『滝野川寺院めぐり案内』の無量寺の頁に「江戸近郊を歩くこのミニ巡礼は、表向きは信心とはいうものの、実際は世代家族の同居が当たり前だった時代の、年に2回のストレス解消とレクリエーションの一石二鳥の効果を狙ったものであった。まさに庶民が、日常生活の中から考えた知恵だったのであろう。」と記載されていますが、江戸の年中行事を描いた『東都歳時記』や『江戸名所図絵』でも複数取り上げられていることからも、そのような側面が大きかったと思われます。
滝野川寺院めぐりの無量寺、与楽寺、昌林寺の3寺は江戸六阿弥陀の札所と重複します。
また、桜の名所であった王子・飛鳥山、紅葉の名所として知られた滝野川、つつじの名所の駒込染井など、滝野川寺院めぐりの周辺エリアが江戸時代のレクリエーションの名所ときれいに重なっていることがわかります。
昌林寺の末木観世音菩薩については、『江戸名所図会』に、「本尊末木観世音菩薩は、開山行基菩薩の作なり。往古六阿弥陀彫刻の折から末木を以って作りたまひしとぞ。」と記され、江戸(武州)六阿弥陀との関連が裏付けられています。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標
谷田川通りから少し入った住宅街のなかにこぢんまりと整った山内。
山門脇に上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第5番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め左から本堂
入母屋造本瓦様の銅板葺で、軒下に向拝を付設しています。
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に「補陀山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
朱の欄干と横長の花頭窓が印象的な本堂の手前には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標と昭和62年造立の百寿観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 百寿観世音菩薩
【写真 下(右)】 本堂扁額
メジャー霊場の札所ではありませんが、最近は「江戸六阿弥陀」巡拝者も増えているのか、御朱印対応は手慣れておられます。
滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は、「江戸六阿弥陀」の参拝でも捺されているようです。

● 滝野川寺院めぐり第10番の御朱印
中央に「末木観音」の揮毫と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に「滝野川寺院めぐり 第十番寺」の札所印で、札所無申告で授与されると思われる「藤井寺寫 西國第五番」の上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は捺されていません。
左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀(木残)の御朱印
中央に「本尊 末木観世音菩薩」の印判と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。
左上に上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印の札所印「藤井寺寫 西國第五番」の札所印が捺されています。
左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
滝野川霊場の御朱印では「末木観音」の揮毫。江戸六阿弥陀と観音霊場の御朱印では「本尊 末木観世音菩薩」の印判の様式にて授与されるようです。
第11番
明王山 大聖寺 不動院
北区西ヶ原3-23-2
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:不動明王
豊島八十八ヶ所霊場第53番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番、北豊島三十三観音霊場第29番
第11番は、真言宗豊山派の不動院です。
第10番昌林寺から谷田川通り沿いに少し歩くと不動院です。
ここで通りの由来となった「谷田川」について少し考えてみます。
谷田川はいまはすべて暗渠となり地図上から辿るのは困難ですが、世の中には奇特な方がおられ、かつての谷田川を辿る紀行がWebでいくつかみつかるので、そちらも参考にさせていただきまとめてみます。
谷田川はかつての石神井川とみる説もありますが、多くの説は染井霊園の北側ないし巣鴨あたりを源流とする別の流れと.みています。
そこから西ヶ原銀座通りに入り、染井銀座商店街~霜降銀座商店街と流れます。
本郷通りの「霜降橋」交差点は、谷田川にかかっていた橋名のなごりとされています。
ここからはほぼ谷田川通りに沿って、池之端の不忍池をめざして下っていきます。
谷田川通りは不忍通りのすぐ東側を走っています。
JR駒込駅の東側あたりで山手線内に入り、西日暮里駅の西側を通って、谷中と千駄木のあいだを流れます。根津駅から谷中への登り口にあたる大黒屋煎餅の下あたりを流れ、池之端辺で不忍池に流れ込みます。
ここで気づいたのは、「滝野川寺院めぐり」は、ほぼ旧谷田川に沿って札所が置かれているということです。
JR田端駅南側から旧古河庭園にかけては高台にあり、その名もずばり「田端高台通り」が走っています。
また、旧古河庭園から王子・飛鳥山にかけても高台で、ふるくは「御殿山」と呼ばれていました。なので、田端駅から王子駅にかけてのJRの南側はすべて高台にあります。
谷田川はこの高台の南側下を沿うように流れていました。
「滝野川寺院めぐり」の札所は一部の例外をのぞいて、この高台と旧谷田川のあいだの南傾地に位置しています。
寺社は崖線に沿って置かれる例が多いので、こちらも例外ではありません。
第1番与楽寺~第7番円勝寺は、すべて「田端高台通り」と旧谷田川のあいだにあり、南傾斜面をトラバースしていくので、大きな高低差はありません。
第8番城官寺は「御殿山」まわりの高台にあり、そこから旧谷田川の流れに近い第9番無量寺の山門までは、急なくだりとなります。
旧谷田川沿いの第10番昌林寺、第11番不動寺を経て、ふたたび「御殿山」エリアにある第12番妙見寺に向けて登りがつづきます。
以上のとおり、第8番城官寺から第12番妙見寺にかけては、地形的にも変化に富んだ巡拝を味わうことができます。
不動院の開創については『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「同宗田端村與樂寺門徒明王山ト號ス 本尊不動開山僧海善 元和六年六月六日寂」
開山は海善和尚(元和六年(1620年)遷化)。その後は数度の火災により寺伝が焼失し詳細は不明のようです。
また、『新編武蔵風土記稿』に「阿彌陀堂。西國二十三番攝州勝尼寺寫の観音を相殿とす。」とあるので、不動明王が御座す本堂のほかに阿弥陀堂があって、そちらに西國二十三番(上野王子駒込辺三十三観音霊場第23番)の札所本尊の観音様が祀られていたのかもしれません。
同書によると、当初は田端与楽寺の末でしたが、『滝野川寺院めぐり案内』によると、昭和16年(1941年)、総本山長谷寺に本寺換えをしています。
『滝野川寺院めぐり案内』には、当寺御本尊のお不動様ゆかりの逸話が記されています。
先の終戦直後、一帯は焼け野原となりましたが、いち早く境内に小屋(お堂)が建てられました。あるときこの小屋(お堂)に賊が侵入し、堂守をされていた慈信和尚の御母堂に刃物を突きつけました。そのとき、どこからともなく人の近づく足音が聞こえ、賊は一物もとらずに退散したそうです。
件の賊は後年、本人の努力と関係者の指導よろしきを得て立派に更正し、平和な一生を全うしたそうです。
このことが近辺に伝わり、当寺のお不動様は「魔除け不動」として信者さんの信仰を集めているそうです。


【写真 上(左)】 豊島霊場札所標
【写真 下(右)】 寺号標
山門向かって右側に「弘法大師」と豊島霊場が一体となった石碑、右手に寺号標と真新しい六地蔵が御座します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 山門付近から山内
本堂は昭和51年建立の鉄筋建てで、手前の階段をのぼった2階正面が向拝となっています。
本堂下には、上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第23番の札所標がありました。


【写真 上(左)】 本堂下
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 西国霊場札所標
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて授与いただけます。
最近巡拝者が増えているといわれる豊島八十八ヶ所霊場の第53番の札所なので、御朱印授与は手慣れておられ、書置のご用意もありました。
参拝時、ご住職はご不在で豊島霊場の御朱印ならば書置に札所印を捺してすぐにお出しになれるとのことでしたが、滝野川霊場の札所印は所在不明とのこと。
郵送をお願いすると快くお受けいただいたので、郵送にて拝受しました。
(ちなみに、筆者は宛先を書いて切手を貼り、郵送のお願い文書と御朱印用紙を同封した返信用の封筒を持ち歩いています。)


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第53番の御朱印
中央に「不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の荘厳体種子「カンマン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「豊島八十八ヶ所第五十三番」の札所印。
左上に「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判。
左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
豊島霊場御朱印との違いは「滝野川寺院めぐり第十一番寺」の印判の有無のみです。
(第12番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ 茜色の約束 - 森恵
■ 夢の大地 - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
■ 完成版です。3編に分けて再構成しました。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。

「根岸古寺めぐり」の面白さに味をしめて(笑)、つぎに狙ったのが「滝野川寺院めぐり」で、2017年12月に結願しています。
平成5年7月1日開創の比較的新しい霊場なので、札所配置が整っていて容易に順打ちができます。しかも範囲が広くないので徒歩で巡拝できるのも魅力です。
ただし、一般的な認知度はほとんどなく、ある札所のお寺さんによると「滝野川寺院めぐりの御朱印を求められたのは数年ぶり」とのことでした。
宗派横断的な滝野川仏教会が開創された霊場で宗派は多彩なため、一冊の御朱印帳でまとめて集印していくとすこぶるバラエティに富んだ内容となります。
第1番 宝珠山 地蔵院 與楽寺
真言宗豊山派 北区田端1-25-1
第2番 白龍山 寿命院 東覚寺
真言宗豊山派 北区田端2-7-3
第3番 寿徳山 萬栄寺
真宗大谷派 北区田端5-7-7
第4番 教風山 普光院 大久寺
法華宗陣門流 北区田端3-21-1
第5番 薬王山 遍照寺 光明院
真言宗豊山派 北区田端3-25-5
第6番 和光山 興源院 大龍寺
真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4
第7番 光明山 照徳院 円勝寺
浄土宗 北区中里町3-1-1
第8番 平塚山 安楽院 城官寺
真言宗豊山派 北区上中里1-42-8
第9番 仏宝山 西光院 無量寺
真言宗豊山派 北区西ヶ原1-34-8
第10番 補陀山 補陀楽寿院 昌林寺
曹洞宗 北区西ケ原3-12-6
第11番 明王山 大聖寺 不動院
真言宗豊山派 北区西ヶ原3-23-2
第12番 現徳山 妙見寺
日蓮宗 北区西ヶ原2-9-5
第13番 北龍山 法音寺
真宗大谷派 北区栄町14-9
第14番 思惟山 浄業三昧寺 正受院
浄土宗 北区滝野川2-49-5
第15番 瀧河山 松橋院 金剛寺
真言宗豊山派 北区滝野川3-88-17
第16番 南照山 観音院 寿徳寺
真言宗豊山派 北区滝野川4-22-1
今回は気合いを入れて、御朱印帳は順打ちで集印してみました。
この方法がよかったのか、札所印が残っていない札所さんでも札番の揮毫をいただくなど、度々ご配慮をいただきました。

第5番光明院の御朱印と第4番大久寺の御首題
16の札所の多くは豊島八十八ヶ所などの現役霊場と重複しているので、ご住職がいらっしゃれば御朱印の拝受はさほどむずかしくはありません。ただ、豊島八十八ヶ所の札所じたいがご不在率が高いので、集印のための出直し参拝は必須かと思います。
日蓮宗と法華宗陣門流の札所がありますが、いずれも快く御首題を授与いただけました。
真宗大谷派の札所がふたつ。うちひとつは「御朱印を出されていない。」とのことでしたが、御朱印帳に参拝記念となるようなものを授与いただけました。
この真宗大谷派の札所は例外対応をいただいたかもしれず、ひょっとすると集印は15に留まる可能性もありますが、当初は2~3箇寺はいただけないものと覚悟していたので、予想以上の拝受数となりました。
札所印が16寺のうち13寺でいただけたのも想定外の収穫(?)で、あまり使われていないためか、印影はどれも綺麗です。
ガイドブックとして、滝野川仏教会が平成5年7月に発行された「滝野川寺院めぐり案内」があります。
いくつかの札所で在庫をご確認いただきましたが、いずれも在庫はなく、北区立滝野川図書館でお借りしてコピーをとりました。
このガイドによると、「『滝野川寺院めぐり』は、滝野川仏教会の会員寺院を、宗派にとらわれることなく巡拝するコースです。」「高齢化がすすむなか、心のゆとりを求める方々が増えています。豊島八十八カ所巡りや江戸六阿弥陀詣りなど、昔からすでに設けられている寺院めぐりをする方は、むしろ増加しています。今回の『滝野川寺院めぐり』は、全国に地域仏教会が沢山あるなかで、組織を巡拝コースに置きかえて、社会と寺院とのコミュニケーションを深めようとする初めての試みであると自負しております。」とあります。
たしかに、平成5年の時点で地域仏教会主導の霊場開創は、先駆的な動きだと思います。
札所は北区内を流れる石神井川に沿って、またいくつかは武蔵野台地の北縁に立地します。
このあたりの石神井川の流れは変化に富み、武蔵野台地にあがっても緑の多い住宅街がつづく風光明媚なところです。
江戸期から桜の名所として名を馳せた飛鳥山もエリア内に含みます。
札所もしっとり落ち着いたお寺さんが多く、ご不在出直し参拝も苦にならない感じがします。(おのおの駅から近いのも心理的に楽。)
これから、発願寺から16番の結願寺まで連載パターンで順繰りにご案内していきたいと思います。
---------------------------------
滝野川寺院めぐりの札所の多くは、昭和22年(1947年)3月15日 、旧 東京35区が22区に再編されたことに伴い北区に統合され消滅した旧 滝野川区域に立地します。
「滝野川」は、石神井川の別称で、このあたりの石神井川の流れが「滝の様に勢いよく」流れていたことに由来するといわれます。
当時の面影は、音無親水公園や音無さくら緑地で偲ぶことができます。
音無さくら緑地の案内看板にはつぎのように書かれています。
「石神井川は大部分が台地上を流れているため、ゆるやかな流れの区間が多いのですが、板橋区加賀から下流になると渓谷状となり、水流もかなり急になります。そのため、昔はこの一帯の石神井川は滝野川とその名を変えて呼ばれ、飛鳥山のあたりでは、この地を愛した徳川吉宗のふるさとにちなみ、音無川とさらに名を変えて呼ばれていました。ごうごうと音をたて、流れる川を音無川と呼んだところに、この地と将軍吉宗との深い関係が読み取れます。」
また、このあたりには、王子七滝(王子の七瀑)という名勝がありました。
不動の滝(正受院境内)、稲荷の滝(王子稲荷社の別当寺金輪寺境内)、名主の滝(現 名主の滝公園内)、弁天の滝(金剛寺内松橋弁天境内)、権現の滝(王子神社の別当寺金輪寺内の王子権現境内)などで、いくつかは、滝野川寺院めぐりの札所境内にありました。
江戸期から、王子飛鳥山は桜の名所、滝野川は紅葉の名所として知られ、神社仏閣参詣と併せ日帰りで楽しめる行楽地として親しまれていました。
「吉宗は『春は花、秋は紅葉』の例えにならい、飛鳥山に桜を植えさせる一方で、石神井川の両岸に紅葉を植えさせました。文化文政の頃には、滝野川の紅葉は江戸中に知られ、江戸名所図絵にも『楓樹の名所として其の名遠近に高し』と述べられています。」(音無さくら緑地の案内看板より)
その様子は、錦絵で楽しむ江戸の名所/国立国会図書館Webなどの資料でも情緒ゆたかにあらわされています。


【上(左)】 『飛鳥山』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『飛鳥山はな見』/広重(広重画帖)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
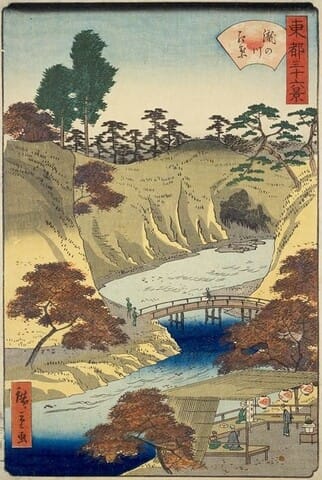

【上(左)】 『滝野川紅葉』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『王子滝の川』/広重(東都名所)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
滝野川寺院めぐりは、JR田端駅からはじまります。
田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。
ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)
この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。
芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。
第1番
宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
朱印尊格:地蔵菩薩
御府内八十八箇所第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、江戸八十八ヶ所霊場第56番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
発願の第1番は、真言宗豊山派の與楽寺です。
弘法大師の建立とも伝わり、慶安元年(1648年)に寺領20石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、寺歴は相当に古そうです。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔當寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ、翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ、是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト伝フ 開山ヲ秀榮ト云」「鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク」「阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ」「九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云」
複数の霊場の札所を兼ねておられ、とくに御府内八十八箇所と武州江戸六阿弥陀で参拝される方が多いのでは。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番の札所です。
武州江戸六阿弥陀霊場は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木・末木で刻した阿弥陀仏と聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、江戸期には女人成仏の阿弥陀仏としてあがめられ、とくに春秋の彼岸に盛んに巡拝されていたようです。(武州江戸六阿弥陀については、第10番昌林寺の記事をご参照ください。)
なお、「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
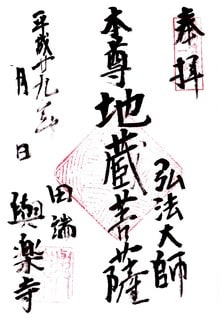
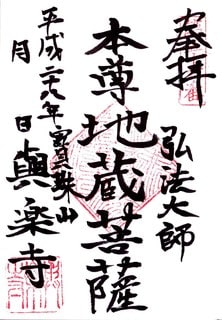
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第1番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第56番の御朱印

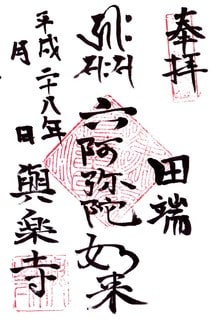
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第56番の御朱印
【下(右)】 武州江戸六阿弥陀霊場第4番の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 地蔵菩薩」の揮毫と三寶印の捺印、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第1番」の札所印。
尊格構成は御府内霊場や豊島霊場など、弘法大師霊場と同様です。
こちらに限らず、滝野川寺院めぐりの御朱印は弘法大師霊場の構成に近く、御朱印尊格は御本尊となる例が多いようです。
なお、武州江戸六阿弥陀霊場の御朱印は、中央上部に阿弥陀如来の種子(キリーク)、右に聖観世音菩薩の種子(サ)、左に勢至菩薩の種子(サク)が揮毫された阿弥陀三尊様式で、この霊場の御朱印で複数みられるものです。
第2番
白龍山 寿命院 東覚寺
北区田端2-7-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
朱印尊格:不動明王
御府内八十八箇所第66番、豊島八十八ヶ所第66番、江戸・東京四十四閻魔参り第35番、谷中七福神(福禄寿)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第29番、江戸八十八ヶ所霊場第66番、九品仏霊場第2番(上品中生)、閻魔三拾遺第5番
第2番は、真言宗豊山派の東覚寺です。
第1番與楽寺からほどなく東覚寺に到着です。
複数の霊場札所を兼ね、「赤紙仁王尊」でも知られる寺院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「與楽寺末白龍山壽命院ト号ス 寺領七石の御朱印ヲ附セラル 本尊不動ハ弘法大師の作ナリ」
延徳三年(1491年)源雅和尚が神田筋違橋(現在の万世橋付近)に創建。その後根岸御印田を経て、慶長の初め(1600年頃)にこの地に移転したと伝わります。


【写真 上(左)】 赤紙仁王尊と明王堂
【写真 下(右)】 奉納された草鞋
区画整理が進んだ広々とした街区に、赤紙を貼られた赤紙仁王尊の出現はインパクトがあります。
この赤紙仁王尊(区の指定文化財)は寛永十八年(1641年)の背銘があり、当時江戸市中に流行していた疫病を鎮めるため宋海上人が願主建立されたもので、赤紙を自分の患部と同じところに貼って願をかけると霊験ありと信じられ、いまもたくさんの赤紙が貼られています。
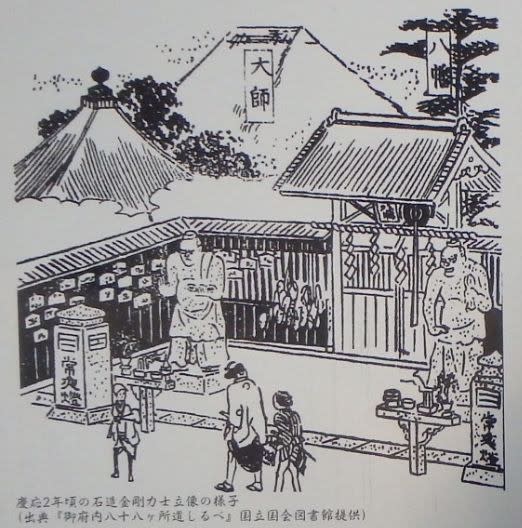
【絵図】 慶応2年頃の石像金剛力士像の様子(北区教育委員会の現地説明板より/出典『御府内八十八ヶ所道しるべ』/国立国会図書館提供)
ときどき赤紙を剥がすそうですが、剥がす前のタイミングだと石造の仁王尊は赤紙に貼り尽くされほとんどお姿が見えません。
病が治癒すると草履を供えるとされ、仁王尊の脇にはたくさんの草履が奉納されています。
この赤紙仁王尊は門前の明王堂(護摩堂)参道に御座しますが、もともとは当寺が別当を務めた田端八幡神社の参道に安置されていたと伝わります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は新しいですが本瓦葺、二軒の平行垂木を備えた立派なものでおそらく薬医門。
正面本堂左手前の修行大師像と金色の金剛界大日如来坐像、向拝欄干には御本尊不動明王の御真言とお大師様の御寶号が掲げられ、保守本流の真言宗寺院の空気感。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「白龍山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 札所標
本堂左手客殿前には金色の阿弥陀如来坐像、その奥に「九品佛第二番 阿弥陀如来」と西國廿九番(上野王子駒込辺三十三観音霊場、札所本尊馬頭観世音菩薩)の札所標が並びます。
九品佛霊場は江戸時代開創の古い霊場で発願は巣鴨の真性寺、結願は板橋の智清寺。東覚寺は第2番で上品中生の阿弥陀如来です。
両霊場ともに御朱印の有無をお伺いしましたが、いずれもお出しになられていないとのことでした。


【写真 上(左)】 鼓翼(はばたき)平和観音像
【写真 下(右)】 馬頭観世音
庫裡に回り込む手前に、鼓翼(はばたき)平和観音像と馬頭観世音菩薩が御座します。
馬頭観世音菩薩は三面八臂の坐像で、髻に馬頭をいだかれた憤怒相です。
馬頭観世音菩薩は観世音菩薩にはめずらしい憤怒尊で、「馬頭明王」と呼ばれることもあります。
この立派な馬頭観世音菩薩は、上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所本尊なのかもしれません。
本堂裏には回遊式の庭園があり、庭内に諸仏が安置されています。
- むらすずめ さわくち声も もも声も つるの林の つるの一声 -
太田蜀山人 / 雀塚の石塔
こちらは江戸・東京四十四閻魔参り第35番の札所で、御縁日に参拝したところ閻魔大王の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印をいただきました。
閻魔大王は奪衣婆とともに、本堂内に御座されているそうです。
また、歴史ある谷中七福神の福禄寿尊天をお祀りされます。
この福禄寿尊天は、もとは通称「六角山」にあった六角堂(西行庵)に西行法師坐像とともに祀られていたもので、明治に入って当寺に遷座されました。
毎年正月には本堂で御開帳されています。
御朱印は、向かって左裏手の寺務所で拝受します。
こちらも御府内霊場や谷中七福神などメジャー霊場の札所となっているので、揮毫いただけることが多そう。
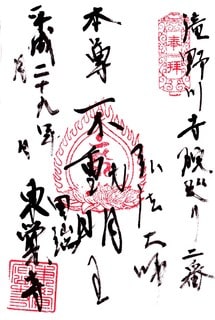

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第2番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第66番の御朱印

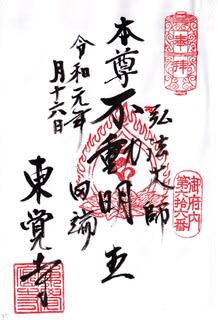
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第66番の御朱印
【下(右)】 閻魔様の御縁日に拝受した御本尊の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 不動明王」の揮毫と種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、「滝野川寺院めぐり 第2番」の札所印はお持ちでないとのことでしたが、ご厚意で揮毫の札番をいただけました。ありがとうございました。
尊格構成は、札所印をのぞいて御府内霊場や豊島霊場などの弘法大師霊場と同様です。
なお、東覚寺が別当を務めていた田端八幡神社(北区田端2-7-2、お隣り)でも御朱印を授与されています。

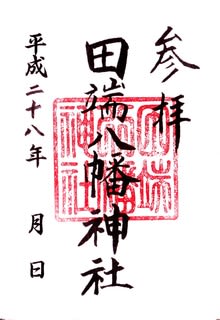
【写真 上(左)】 田端八幡神社拝殿
【下(右)】 田端八幡神社の御朱印
第3番
寿徳山 萬榮寺
北区田端5-7-7
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:不可思議光如来


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 寺号標
第3番は、真宗大谷派の萬榮寺です。
この霊場は第3番、第4番に至って一気にマニアック度(?)が高まりますが、これは宗派によるところが大きいと思います。
第3番は真宗大谷派、第4番は法華宗陣門流で、いずれも霊場札所としての例は多くはありません。とくに真宗大谷派、法華宗陣門流とつづく霊場はほとんど例がないのでは。
宗派を超えた、地域仏教界開創の霊場ならではの札所展開といえましょう。
真宗は教義的に御朱印を授与されない寺院が多く(名刹で参拝記念的なスタンプはけっこう出されている)、この宗派の檀家寺に御朱印授与のお願いをすることはいつもは避けますが、霊場札所となると話は別です。
三浦二十八不動尊霊場、三浦二十一ヶ所薬師霊場、行徳・浦安三十三観音霊場、甲斐百八霊場などで真宗寺院が札所となっている例があり、実際、これまでに御朱印を拝受しています。
萬榮寺は、新潟県西蒲原郡中之口村六分の円明寺他4箇寺の東京在住の壇信徒をまとめるために設立された真宗大谷派萬榮教会が前身の、真宗大谷派の寺院です。
こじんまりとした境内。
本堂は近代建築で様式はよくわかりませんが、葡萄茶色の柱と梁が印象的な二層の建物で、上層の屋根妻部には鬼板と猪ノ目懸魚を備えています。
御本尊の阿弥陀如来立像は寄木造で、衣部に金箔、48本の光背を備えられ、江戸時代後期の作といわれています。
御朱印授与は、ベルを鳴らしてのお願いとなります。
こちらは以前お伺いしたときはご不在、今回もお取り込み中のようでしたが快く授与をいただけました。

● 滝野川寺院めぐり第3番の御朱印
御朱印は中央に「南無不可思議光如来」の揮毫と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第三番寺」の札所印。
真宗の「正信偈」に「南無不可思議光」とあり、「不可思議光」は阿弥陀仏の「智慧」をあらわすそうですから、尊格としては阿弥陀(無量光)如来で、真宗ならではの御朱印(?)のようにも思えます。
第4番
教風山 普光院 大久寺
北区田端3-21-1
法華宗陣門流
朱印尊格:御首題
第4番は、法華宗陣門流の大久寺です。
日蓮聖人を開祖(宗祖・高祖)とし、妙法蓮華経を依拠教典とする宗旨(広義の法華宗)には多くの流れ(門流)があり、その差異を理解するのは甚だ困難ですが、大きくは「所依の妙法蓮華経を構成する二十八品前半の『迹門』、後半の『本門』の関係解釈」、「釈迦をもって本仏とするか、日蓮聖人をもって本仏とするか」により分流しているようです。
前者で「一致派」と「勝劣派」に分かれ、法華宗陣門流は「勝劣派」の、日陣門流(本成寺派)の流れになるものとみられます。
((広義の)法華宗は総じて教義解釈に厳格で、これにより細かく門流が分かれているので、素人が表面的に理解するのは不可能かと思います。)
「勝劣派」には原則御首題を授与されない門流もあるようですが、法華宗陣門流と法華宗本門流は比較的授与例が多いように思われます。
文禄元年(1592年)大久保相模守忠世が一族の菩提を弔うため、越後の名僧・日英上人を招聘、開祖として小田原に創建され、寛永七年(1630年)江戸下谷車坂に移転の後、明治三十六年(1903年)に当地に移転したとされます。
大久保家との所縁がふかく、「おおくぼでら」とも呼ばれているようです。
伊勢亀山藩石川家に養子となっていた忠隣の二男忠総の流れで、石川家の菩提寺でもあります。
また、大正三年(1914年)に田端の上台寺を合併しています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
さほど広くはないものの、緑が多く手入れの行き届いた境内。
正面に昭和34年(1959年)建立の本堂。入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟、隅棟、稚児棟、掛瓦のバランスがよく、整った印象の建物です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
水引虹梁両端に禅宗様の雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「教風山」の扁額。向拝両脇に花頭窓、小壁の欄間に菱格子と、向拝まわりもきっちり整った印象です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内
境内には、昔日参拝者を集めた日蓮聖人の伊豆法難の際の「腰掛石」がいまも残ります。
こちらは以前にも御首題をいただいておりますが、そのときも今回もたいへん丁重なご対応をいただきました。
ただし、札所の場合も尊格は御首題なので、ご住職ご不在時は出直し参拝になろうかと思われます。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第4番の御首題
【下(右)】 御首題
御首題は、中央にお題目と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と宗派+寺院の印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第四番寺」の札所印が捺されています。
こちらは以前にも御首題を拝受していますが、そのときは御首題をお願いしたので札所印の捺印はありません。
第5番
薬王山 遍照寺 光明院
北区田端3-25-5
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第9番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第20番
第5番は、霊場札所の保守本流、真言宗豊山派の光明院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「同宗西ヶ原村無量寺末薬王山遍照寺ト号ス本尊大日 薬師堂 聖徳太子ノ作ノ薬師ヲ置ク立像長一尺五寸 観音堂」
天正十九年(1591年)の検地水帳に白髭神社の別当として「光明院」の名があり、創建はそれ以前と推定されますが詳細は不明。
寺伝は寛文四年(1664年)、朝海法印による再建を伝えます。
古くは医王山、白髭山の山号を号し無量寺の末寺でした。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
閑静な住宅街にあるこのお寺さんは光明院幼稚園を併設されていて、平日昼間の境内は園児たちが元気に遊びまわり、当然のことながら門扉は固く閉ざされています。
1回目、豊島霊場の参拝でお伺いしたときは時間が遅く、園児や親御さんもおおむね帰宅して落ち着いていましたが、2回目、滝野川霊場の参拝時はちょうど帰宅時で境内は園児と母親達で大盛況。ここに男性1人で踏み込むのは相当気合い?が要りそうですが、このときは連れ同伴だったので大手を振っての?参拝です。
(じつはこの日、2人併せて平日休をとり、昼過ぎに東京国立博物館の運慶展に赴いたのですが、あまりの大混雑に嫌気がさし、一旦滝野川霊場の参拝に回り、少しく空いてきた夕刻から突入したのでした。)
参道は幼稚園側にありますが、高麗門の格子戸は閉まっていて入れません。
本堂側に回り込むと開き戸(幼稚園出入口)があり、門脇のインターフォンから参拝の許可をいただきます。
いずれも通用門そばに先生がおられたので、お声掛けすると快く本堂(庫裡)にご案内いただけました。(3回目は、たしかインターフォンを鳴らしたかと思います。)
3度ともご住職、大黒さんにお会いできましたが、温厚で上品なお人柄のように感じられました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 左手からの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
昭和50年(1975年)再建の本堂はコンクリ造で寄棟造銅板葺流れ向拝。
コンクリ造のためか向拝柱はなし。細部の意匠が効いていて、コンクリ造のお堂にありがちな無機質感はありません。
ただし、かなり離れたところに柵があり賽銭箱もないので、お参りはいささかしにくいです。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内の西國第20番を示す札所碑
1回目、豊島霊場のときはスムーズに御朱印を拝受できましたが(最近、豊島霊場の巡拝者が増えている模様)、2回目に滝野川寺院めぐりの御朱印を申告すると、いささか驚かれたご様子でした。
やはり、滝野川寺院めぐりの参拝者はすこぶる少ないそうです。
3回目、上野王子駒込辺三十三観音霊場に至っては、大黒さんは??モードでしたが、「西國20番」と言い直すと合点がいかれたらしく、無事、ご住職から御朱印を拝受できました。
本堂手前の観音様(札所碑あり)が札所本尊ではないか、との由でした。
上野王子駒込辺三十三観音霊場じたいが正式名称ではなく(東都歳時記に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」とある)、御朱印授与の札所も少ないですが、北区のある札所寺院様によると、最近、この霊場で申告されるケースが増えている感じがする、との由。
御府内、豊島などのメジャー霊場には参画されていない寺院も複数含まれているので、復活があるとうれしいです。(廃寺が複数ありますが・・・)
↑の札所印や、谷中の長安寺(第22番)で本堂扁額横に「西國三十三ヶ所寫」の札所板が掲げられていることなどから、「西國三十三ヶ所寫(観音)参り」とされていた可能性があります。
また、府内七薬師霊場第2番札所との情報がありますが、この霊場じたい調べがついておらず、現在のところ詳細不明です。(東都七仏薬師とは異なるようです。)

● 滝野川寺院めぐり第5番の御朱印
中央に「大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に院号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第五番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印をのぞいて豊島霊場と同様です。


【上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場第9番の御朱印
【下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音(西國写)霊場第20番の御朱印
第6番
和光山 興源院 大龍寺
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第21番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第17番、御府内八十八箇所第13番(不詳)
第6番は、真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ、天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置 八幡社 村ノ鎮守トス 稲荷社」
創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興し、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂露天
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れた対応です。
滝野川寺院めぐりの御朱印についても、特段驚かれた風はありませんでした。
こちらはWeb上で、「弘法大師第13番」の札所印(揮毫)の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
近年メジャー霊場化している御府内八十八箇所は、番外等の札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院がリストされています。
御府内第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺で、龍生院に引き継がれたとされていて、大龍寺との関連は不詳です。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
なお、真言宗霊雲寺派総本山の霊雲寺は、御府内八十八箇所の第28番の札所となっています。
真言宗霊雲寺派は東都を拠点とする宗派で、その霊雲寺派が江戸の弘法大師霊場である御府内八十八箇所の一画を占めているのは、頷けるものがあります。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第6番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第21番の御朱印
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に寺号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第六番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印と種子「ア」の様式が豊島霊場とは異なります。
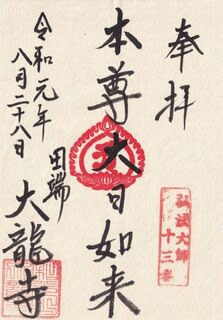
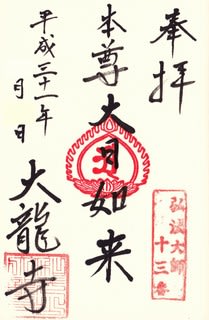
【上(左)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(御朱印帳)
(第7番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ I Will Be There with You ~日本語版~ - 杏里
■ 空に近い週末 - 今井美樹
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。
この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。

「根岸古寺めぐり」の面白さに味をしめて(笑)、つぎに狙ったのが「滝野川寺院めぐり」で、2017年12月に結願しています。
平成5年7月1日開創の比較的新しい霊場なので、札所配置が整っていて容易に順打ちができます。しかも範囲が広くないので徒歩で巡拝できるのも魅力です。
ただし、一般的な認知度はほとんどなく、ある札所のお寺さんによると「滝野川寺院めぐりの御朱印を求められたのは数年ぶり」とのことでした。
宗派横断的な滝野川仏教会が開創された霊場で宗派は多彩なため、一冊の御朱印帳でまとめて集印していくとすこぶるバラエティに富んだ内容となります。
第1番 宝珠山 地蔵院 與楽寺
真言宗豊山派 北区田端1-25-1
第2番 白龍山 寿命院 東覚寺
真言宗豊山派 北区田端2-7-3
第3番 寿徳山 萬栄寺
真宗大谷派 北区田端5-7-7
第4番 教風山 普光院 大久寺
法華宗陣門流 北区田端3-21-1
第5番 薬王山 遍照寺 光明院
真言宗豊山派 北区田端3-25-5
第6番 和光山 興源院 大龍寺
真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4
第7番 光明山 照徳院 円勝寺
浄土宗 北区中里町3-1-1
第8番 平塚山 安楽院 城官寺
真言宗豊山派 北区上中里1-42-8
第9番 仏宝山 西光院 無量寺
真言宗豊山派 北区西ヶ原1-34-8
第10番 補陀山 補陀楽寿院 昌林寺
曹洞宗 北区西ケ原3-12-6
第11番 明王山 大聖寺 不動院
真言宗豊山派 北区西ヶ原3-23-2
第12番 現徳山 妙見寺
日蓮宗 北区西ヶ原2-9-5
第13番 北龍山 法音寺
真宗大谷派 北区栄町14-9
第14番 思惟山 浄業三昧寺 正受院
浄土宗 北区滝野川2-49-5
第15番 瀧河山 松橋院 金剛寺
真言宗豊山派 北区滝野川3-88-17
第16番 南照山 観音院 寿徳寺
真言宗豊山派 北区滝野川4-22-1
今回は気合いを入れて、御朱印帳は順打ちで集印してみました。
この方法がよかったのか、札所印が残っていない札所さんでも札番の揮毫をいただくなど、度々ご配慮をいただきました。

第5番光明院の御朱印と第4番大久寺の御首題
16の札所の多くは豊島八十八ヶ所などの現役霊場と重複しているので、ご住職がいらっしゃれば御朱印の拝受はさほどむずかしくはありません。ただ、豊島八十八ヶ所の札所じたいがご不在率が高いので、集印のための出直し参拝は必須かと思います。
日蓮宗と法華宗陣門流の札所がありますが、いずれも快く御首題を授与いただけました。
真宗大谷派の札所がふたつ。うちひとつは「御朱印を出されていない。」とのことでしたが、御朱印帳に参拝記念となるようなものを授与いただけました。
この真宗大谷派の札所は例外対応をいただいたかもしれず、ひょっとすると集印は15に留まる可能性もありますが、当初は2~3箇寺はいただけないものと覚悟していたので、予想以上の拝受数となりました。
札所印が16寺のうち13寺でいただけたのも想定外の収穫(?)で、あまり使われていないためか、印影はどれも綺麗です。
ガイドブックとして、滝野川仏教会が平成5年7月に発行された「滝野川寺院めぐり案内」があります。
いくつかの札所で在庫をご確認いただきましたが、いずれも在庫はなく、北区立滝野川図書館でお借りしてコピーをとりました。
このガイドによると、「『滝野川寺院めぐり』は、滝野川仏教会の会員寺院を、宗派にとらわれることなく巡拝するコースです。」「高齢化がすすむなか、心のゆとりを求める方々が増えています。豊島八十八カ所巡りや江戸六阿弥陀詣りなど、昔からすでに設けられている寺院めぐりをする方は、むしろ増加しています。今回の『滝野川寺院めぐり』は、全国に地域仏教会が沢山あるなかで、組織を巡拝コースに置きかえて、社会と寺院とのコミュニケーションを深めようとする初めての試みであると自負しております。」とあります。
たしかに、平成5年の時点で地域仏教会主導の霊場開創は、先駆的な動きだと思います。
札所は北区内を流れる石神井川に沿って、またいくつかは武蔵野台地の北縁に立地します。
このあたりの石神井川の流れは変化に富み、武蔵野台地にあがっても緑の多い住宅街がつづく風光明媚なところです。
江戸期から桜の名所として名を馳せた飛鳥山もエリア内に含みます。
札所もしっとり落ち着いたお寺さんが多く、ご不在出直し参拝も苦にならない感じがします。(おのおの駅から近いのも心理的に楽。)
これから、発願寺から16番の結願寺まで連載パターンで順繰りにご案内していきたいと思います。
---------------------------------
滝野川寺院めぐりの札所の多くは、昭和22年(1947年)3月15日 、旧 東京35区が22区に再編されたことに伴い北区に統合され消滅した旧 滝野川区域に立地します。
「滝野川」は、石神井川の別称で、このあたりの石神井川の流れが「滝の様に勢いよく」流れていたことに由来するといわれます。
当時の面影は、音無親水公園や音無さくら緑地で偲ぶことができます。
音無さくら緑地の案内看板にはつぎのように書かれています。
「石神井川は大部分が台地上を流れているため、ゆるやかな流れの区間が多いのですが、板橋区加賀から下流になると渓谷状となり、水流もかなり急になります。そのため、昔はこの一帯の石神井川は滝野川とその名を変えて呼ばれ、飛鳥山のあたりでは、この地を愛した徳川吉宗のふるさとにちなみ、音無川とさらに名を変えて呼ばれていました。ごうごうと音をたて、流れる川を音無川と呼んだところに、この地と将軍吉宗との深い関係が読み取れます。」
また、このあたりには、王子七滝(王子の七瀑)という名勝がありました。
不動の滝(正受院境内)、稲荷の滝(王子稲荷社の別当寺金輪寺境内)、名主の滝(現 名主の滝公園内)、弁天の滝(金剛寺内松橋弁天境内)、権現の滝(王子神社の別当寺金輪寺内の王子権現境内)などで、いくつかは、滝野川寺院めぐりの札所境内にありました。
江戸期から、王子飛鳥山は桜の名所、滝野川は紅葉の名所として知られ、神社仏閣参詣と併せ日帰りで楽しめる行楽地として親しまれていました。
「吉宗は『春は花、秋は紅葉』の例えにならい、飛鳥山に桜を植えさせる一方で、石神井川の両岸に紅葉を植えさせました。文化文政の頃には、滝野川の紅葉は江戸中に知られ、江戸名所図絵にも『楓樹の名所として其の名遠近に高し』と述べられています。」(音無さくら緑地の案内看板より)
その様子は、錦絵で楽しむ江戸の名所/国立国会図書館Webなどの資料でも情緒ゆたかにあらわされています。


【上(左)】 『飛鳥山』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『飛鳥山はな見』/広重(広重画帖)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
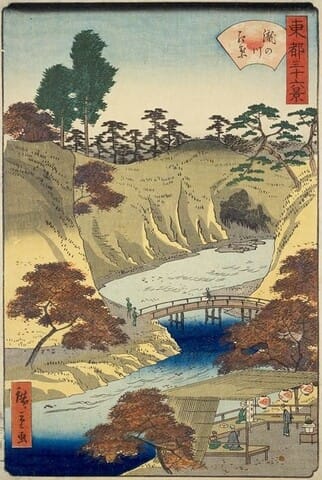

【上(左)】 『滝野川紅葉』/広重(東都三十六景)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
【下(右)】 『王子滝の川』/広重(東都名所)(国立国会図書館ウェブサイトから転載)
滝野川寺院めぐりは、JR田端駅からはじまります。
田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。
ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)
この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。
芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。
第1番
宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
朱印尊格:地蔵菩薩
御府内八十八箇所第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、江戸八十八ヶ所霊場第56番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
発願の第1番は、真言宗豊山派の與楽寺です。
弘法大師の建立とも伝わり、慶安元年(1648年)に寺領20石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、寺歴は相当に古そうです。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔當寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ、翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ、是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト伝フ 開山ヲ秀榮ト云」「鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク」「阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ」「九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云」
複数の霊場の札所を兼ねておられ、とくに御府内八十八箇所と武州江戸六阿弥陀で参拝される方が多いのでは。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番の札所です。
武州江戸六阿弥陀霊場は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木・末木で刻した阿弥陀仏と聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、江戸期には女人成仏の阿弥陀仏としてあがめられ、とくに春秋の彼岸に盛んに巡拝されていたようです。(武州江戸六阿弥陀については、第10番昌林寺の記事をご参照ください。)
なお、「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
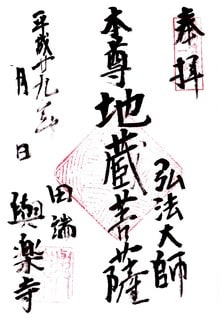
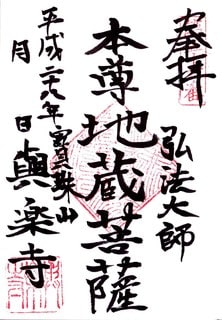
【上(左)】 滝野川寺院めぐり第1番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第56番の御朱印

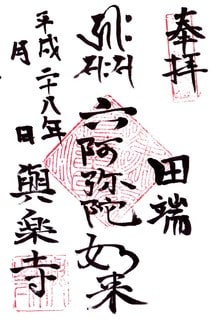
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第56番の御朱印
【下(右)】 武州江戸六阿弥陀霊場第4番の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 地蔵菩薩」の揮毫と三寶印の捺印、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第1番」の札所印。
尊格構成は御府内霊場や豊島霊場など、弘法大師霊場と同様です。
こちらに限らず、滝野川寺院めぐりの御朱印は弘法大師霊場の構成に近く、御朱印尊格は御本尊となる例が多いようです。
なお、武州江戸六阿弥陀霊場の御朱印は、中央上部に阿弥陀如来の種子(キリーク)、右に聖観世音菩薩の種子(サ)、左に勢至菩薩の種子(サク)が揮毫された阿弥陀三尊様式で、この霊場の御朱印で複数みられるものです。
第2番
白龍山 寿命院 東覚寺
北区田端2-7-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
朱印尊格:不動明王
御府内八十八箇所第66番、豊島八十八ヶ所第66番、江戸・東京四十四閻魔参り第35番、谷中七福神(福禄寿)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第29番、江戸八十八ヶ所霊場第66番、九品仏霊場第2番(上品中生)、閻魔三拾遺第5番
第2番は、真言宗豊山派の東覚寺です。
第1番與楽寺からほどなく東覚寺に到着です。
複数の霊場札所を兼ね、「赤紙仁王尊」でも知られる寺院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「與楽寺末白龍山壽命院ト号ス 寺領七石の御朱印ヲ附セラル 本尊不動ハ弘法大師の作ナリ」
延徳三年(1491年)源雅和尚が神田筋違橋(現在の万世橋付近)に創建。その後根岸御印田を経て、慶長の初め(1600年頃)にこの地に移転したと伝わります。


【写真 上(左)】 赤紙仁王尊と明王堂
【写真 下(右)】 奉納された草鞋
区画整理が進んだ広々とした街区に、赤紙を貼られた赤紙仁王尊の出現はインパクトがあります。
この赤紙仁王尊(区の指定文化財)は寛永十八年(1641年)の背銘があり、当時江戸市中に流行していた疫病を鎮めるため宋海上人が願主建立されたもので、赤紙を自分の患部と同じところに貼って願をかけると霊験ありと信じられ、いまもたくさんの赤紙が貼られています。
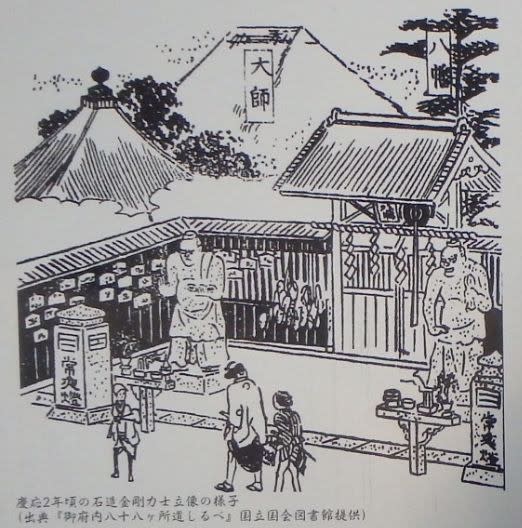
【絵図】 慶応2年頃の石像金剛力士像の様子(北区教育委員会の現地説明板より/出典『御府内八十八ヶ所道しるべ』/国立国会図書館提供)
ときどき赤紙を剥がすそうですが、剥がす前のタイミングだと石造の仁王尊は赤紙に貼り尽くされほとんどお姿が見えません。
病が治癒すると草履を供えるとされ、仁王尊の脇にはたくさんの草履が奉納されています。
この赤紙仁王尊は門前の明王堂(護摩堂)参道に御座しますが、もともとは当寺が別当を務めた田端八幡神社の参道に安置されていたと伝わります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は新しいですが本瓦葺、二軒の平行垂木を備えた立派なものでおそらく薬医門。
正面本堂左手前の修行大師像と金色の金剛界大日如来坐像、向拝欄干には御本尊不動明王の御真言とお大師様の御寶号が掲げられ、保守本流の真言宗寺院の空気感。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「白龍山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 札所標
本堂左手客殿前には金色の阿弥陀如来坐像、その奥に「九品佛第二番 阿弥陀如来」と西國廿九番(上野王子駒込辺三十三観音霊場、札所本尊馬頭観世音菩薩)の札所標が並びます。
九品佛霊場は江戸時代開創の古い霊場で発願は巣鴨の真性寺、結願は板橋の智清寺。東覚寺は第2番で上品中生の阿弥陀如来です。
両霊場ともに御朱印の有無をお伺いしましたが、いずれもお出しになられていないとのことでした。


【写真 上(左)】 鼓翼(はばたき)平和観音像
【写真 下(右)】 馬頭観世音
庫裡に回り込む手前に、鼓翼(はばたき)平和観音像と馬頭観世音菩薩が御座します。
馬頭観世音菩薩は三面八臂の坐像で、髻に馬頭をいだかれた憤怒相です。
馬頭観世音菩薩は観世音菩薩にはめずらしい憤怒尊で、「馬頭明王」と呼ばれることもあります。
この立派な馬頭観世音菩薩は、上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所本尊なのかもしれません。
本堂裏には回遊式の庭園があり、庭内に諸仏が安置されています。
- むらすずめ さわくち声も もも声も つるの林の つるの一声 -
太田蜀山人 / 雀塚の石塔
こちらは江戸・東京四十四閻魔参り第35番の札所で、御縁日に参拝したところ閻魔大王の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印をいただきました。
閻魔大王は奪衣婆とともに、本堂内に御座されているそうです。
また、歴史ある谷中七福神の福禄寿尊天をお祀りされます。
この福禄寿尊天は、もとは通称「六角山」にあった六角堂(西行庵)に西行法師坐像とともに祀られていたもので、明治に入って当寺に遷座されました。
毎年正月には本堂で御開帳されています。
御朱印は、向かって左裏手の寺務所で拝受します。
こちらも御府内霊場や谷中七福神などメジャー霊場の札所となっているので、揮毫いただけることが多そう。
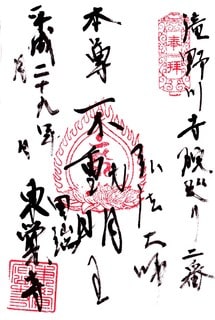

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第2番の御朱印
【下(右)】 御府内八十八箇所第66番の御朱印

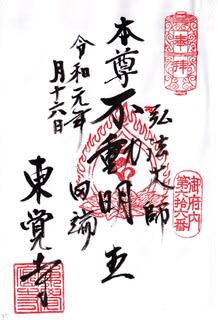
【上(左)】 豊島八十八ヶ所第66番の御朱印
【下(右)】 閻魔様の御縁日に拝受した御本尊の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 不動明王」の揮毫と種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、「滝野川寺院めぐり 第2番」の札所印はお持ちでないとのことでしたが、ご厚意で揮毫の札番をいただけました。ありがとうございました。
尊格構成は、札所印をのぞいて御府内霊場や豊島霊場などの弘法大師霊場と同様です。
なお、東覚寺が別当を務めていた田端八幡神社(北区田端2-7-2、お隣り)でも御朱印を授与されています。

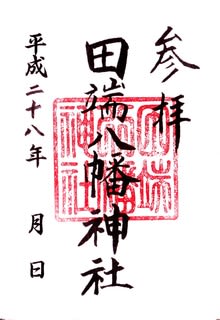
【写真 上(左)】 田端八幡神社拝殿
【下(右)】 田端八幡神社の御朱印
第3番
寿徳山 萬榮寺
北区田端5-7-7
真宗大谷派
御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:不可思議光如来


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 寺号標
第3番は、真宗大谷派の萬榮寺です。
この霊場は第3番、第4番に至って一気にマニアック度(?)が高まりますが、これは宗派によるところが大きいと思います。
第3番は真宗大谷派、第4番は法華宗陣門流で、いずれも霊場札所としての例は多くはありません。とくに真宗大谷派、法華宗陣門流とつづく霊場はほとんど例がないのでは。
宗派を超えた、地域仏教界開創の霊場ならではの札所展開といえましょう。
真宗は教義的に御朱印を授与されない寺院が多く(名刹で参拝記念的なスタンプはけっこう出されている)、この宗派の檀家寺に御朱印授与のお願いをすることはいつもは避けますが、霊場札所となると話は別です。
三浦二十八不動尊霊場、三浦二十一ヶ所薬師霊場、行徳・浦安三十三観音霊場、甲斐百八霊場などで真宗寺院が札所となっている例があり、実際、これまでに御朱印を拝受しています。
萬榮寺は、新潟県西蒲原郡中之口村六分の円明寺他4箇寺の東京在住の壇信徒をまとめるために設立された真宗大谷派萬榮教会が前身の、真宗大谷派の寺院です。
こじんまりとした境内。
本堂は近代建築で様式はよくわかりませんが、葡萄茶色の柱と梁が印象的な二層の建物で、上層の屋根妻部には鬼板と猪ノ目懸魚を備えています。
御本尊の阿弥陀如来立像は寄木造で、衣部に金箔、48本の光背を備えられ、江戸時代後期の作といわれています。
御朱印授与は、ベルを鳴らしてのお願いとなります。
こちらは以前お伺いしたときはご不在、今回もお取り込み中のようでしたが快く授与をいただけました。

● 滝野川寺院めぐり第3番の御朱印
御朱印は中央に「南無不可思議光如来」の揮毫と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と寺院印、右上に「滝野川寺院めぐり 第三番寺」の札所印。
真宗の「正信偈」に「南無不可思議光」とあり、「不可思議光」は阿弥陀仏の「智慧」をあらわすそうですから、尊格としては阿弥陀(無量光)如来で、真宗ならではの御朱印(?)のようにも思えます。
第4番
教風山 普光院 大久寺
北区田端3-21-1
法華宗陣門流
朱印尊格:御首題
第4番は、法華宗陣門流の大久寺です。
日蓮聖人を開祖(宗祖・高祖)とし、妙法蓮華経を依拠教典とする宗旨(広義の法華宗)には多くの流れ(門流)があり、その差異を理解するのは甚だ困難ですが、大きくは「所依の妙法蓮華経を構成する二十八品前半の『迹門』、後半の『本門』の関係解釈」、「釈迦をもって本仏とするか、日蓮聖人をもって本仏とするか」により分流しているようです。
前者で「一致派」と「勝劣派」に分かれ、法華宗陣門流は「勝劣派」の、日陣門流(本成寺派)の流れになるものとみられます。
((広義の)法華宗は総じて教義解釈に厳格で、これにより細かく門流が分かれているので、素人が表面的に理解するのは不可能かと思います。)
「勝劣派」には原則御首題を授与されない門流もあるようですが、法華宗陣門流と法華宗本門流は比較的授与例が多いように思われます。
文禄元年(1592年)大久保相模守忠世が一族の菩提を弔うため、越後の名僧・日英上人を招聘、開祖として小田原に創建され、寛永七年(1630年)江戸下谷車坂に移転の後、明治三十六年(1903年)に当地に移転したとされます。
大久保家との所縁がふかく、「おおくぼでら」とも呼ばれているようです。
伊勢亀山藩石川家に養子となっていた忠隣の二男忠総の流れで、石川家の菩提寺でもあります。
また、大正三年(1914年)に田端の上台寺を合併しています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
さほど広くはないものの、緑が多く手入れの行き届いた境内。
正面に昭和34年(1959年)建立の本堂。入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟、隅棟、稚児棟、掛瓦のバランスがよく、整った印象の建物です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
水引虹梁両端に禅宗様の雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「教風山」の扁額。向拝両脇に花頭窓、小壁の欄間に菱格子と、向拝まわりもきっちり整った印象です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内
境内には、昔日参拝者を集めた日蓮聖人の伊豆法難の際の「腰掛石」がいまも残ります。
こちらは以前にも御首題をいただいておりますが、そのときも今回もたいへん丁重なご対応をいただきました。
ただし、札所の場合も尊格は御首題なので、ご住職ご不在時は出直し参拝になろうかと思われます。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第4番の御首題
【下(右)】 御首題
御首題は、中央にお題目と印(内容不明)、右下に寺号の揮毫と宗派+寺院の印。
右下に「滝野川寺院めぐり 第四番寺」の札所印が捺されています。
こちらは以前にも御首題を拝受していますが、そのときは御首題をお願いしたので札所印の捺印はありません。
第5番
薬王山 遍照寺 光明院
北区田端3-25-5
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第9番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第20番
第5番は、霊場札所の保守本流、真言宗豊山派の光明院です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「同宗西ヶ原村無量寺末薬王山遍照寺ト号ス本尊大日 薬師堂 聖徳太子ノ作ノ薬師ヲ置ク立像長一尺五寸 観音堂」
天正十九年(1591年)の検地水帳に白髭神社の別当として「光明院」の名があり、創建はそれ以前と推定されますが詳細は不明。
寺伝は寛文四年(1664年)、朝海法印による再建を伝えます。
古くは医王山、白髭山の山号を号し無量寺の末寺でした。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
閑静な住宅街にあるこのお寺さんは光明院幼稚園を併設されていて、平日昼間の境内は園児たちが元気に遊びまわり、当然のことながら門扉は固く閉ざされています。
1回目、豊島霊場の参拝でお伺いしたときは時間が遅く、園児や親御さんもおおむね帰宅して落ち着いていましたが、2回目、滝野川霊場の参拝時はちょうど帰宅時で境内は園児と母親達で大盛況。ここに男性1人で踏み込むのは相当気合い?が要りそうですが、このときは連れ同伴だったので大手を振っての?参拝です。
(じつはこの日、2人併せて平日休をとり、昼過ぎに東京国立博物館の運慶展に赴いたのですが、あまりの大混雑に嫌気がさし、一旦滝野川霊場の参拝に回り、少しく空いてきた夕刻から突入したのでした。)
参道は幼稚園側にありますが、高麗門の格子戸は閉まっていて入れません。
本堂側に回り込むと開き戸(幼稚園出入口)があり、門脇のインターフォンから参拝の許可をいただきます。
いずれも通用門そばに先生がおられたので、お声掛けすると快く本堂(庫裡)にご案内いただけました。(3回目は、たしかインターフォンを鳴らしたかと思います。)
3度ともご住職、大黒さんにお会いできましたが、温厚で上品なお人柄のように感じられました。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 左手からの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝見上げ
昭和50年(1975年)再建の本堂はコンクリ造で寄棟造銅板葺流れ向拝。
コンクリ造のためか向拝柱はなし。細部の意匠が効いていて、コンクリ造のお堂にありがちな無機質感はありません。
ただし、かなり離れたところに柵があり賽銭箱もないので、お参りはいささかしにくいです。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 境内の西國第20番を示す札所碑
1回目、豊島霊場のときはスムーズに御朱印を拝受できましたが(最近、豊島霊場の巡拝者が増えている模様)、2回目に滝野川寺院めぐりの御朱印を申告すると、いささか驚かれたご様子でした。
やはり、滝野川寺院めぐりの参拝者はすこぶる少ないそうです。
3回目、上野王子駒込辺三十三観音霊場に至っては、大黒さんは??モードでしたが、「西國20番」と言い直すと合点がいかれたらしく、無事、ご住職から御朱印を拝受できました。
本堂手前の観音様(札所碑あり)が札所本尊ではないか、との由でした。
上野王子駒込辺三十三観音霊場じたいが正式名称ではなく(東都歳時記に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」とある)、御朱印授与の札所も少ないですが、北区のある札所寺院様によると、最近、この霊場で申告されるケースが増えている感じがする、との由。
御府内、豊島などのメジャー霊場には参画されていない寺院も複数含まれているので、復活があるとうれしいです。(廃寺が複数ありますが・・・)
↑の札所印や、谷中の長安寺(第22番)で本堂扁額横に「西國三十三ヶ所寫」の札所板が掲げられていることなどから、「西國三十三ヶ所寫(観音)参り」とされていた可能性があります。
また、府内七薬師霊場第2番札所との情報がありますが、この霊場じたい調べがついておらず、現在のところ詳細不明です。(東都七仏薬師とは異なるようです。)

● 滝野川寺院めぐり第5番の御朱印
中央に「大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に院号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第五番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印をのぞいて豊島霊場と同様です。


【上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場第9番の御朱印
【下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音(西國写)霊場第20番の御朱印
第6番
和光山 興源院 大龍寺
北区田端4-18-4
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部大日如来
朱印尊格:胎蔵大日如来
豊島八十八ヶ所霊場第21番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第17番、御府内八十八箇所第13番(不詳)
第6番は、真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺です。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)に以下の記述があります。
「眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ、天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置 八幡社 村ノ鎮守トス 稲荷社」
創建は慶長年間(1596-1615年)。
当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興し、現寺号に改称しているようです。
俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑
こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。
山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。
主門上部に「和光山」の扁額。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 右手からの本堂露天
本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。
すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。
正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。
身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。
このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れた対応です。
滝野川寺院めぐりの御朱印についても、特段驚かれた風はありませんでした。
こちらはWeb上で、「弘法大師第13番」の札所印(揮毫)の御朱印がみつかります。
一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。
Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。
近年メジャー霊場化している御府内八十八箇所は、番外等の札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。
しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。
通常、第13番は三田の龍生院がリストされています。
御府内第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺で、龍生院に引き継がれたとされていて、大龍寺との関連は不詳です。
御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。
仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。
淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。
なお、真言宗霊雲寺派総本山の霊雲寺は、御府内八十八箇所の第28番の札所となっています。
真言宗霊雲寺派は東都を拠点とする宗派で、その霊雲寺派が江戸の弘法大師霊場である御府内八十八箇所の一画を占めているのは、頷けるものがあります。


【上(左)】 滝野川寺院めぐり第6番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第21番の御朱印
中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左下に寺号の揮毫と寺院印、右下に「滝野川寺院めぐり 第六番寺」の札所印が捺されています。
御朱印の構成は、札所印と種子「ア」の様式が豊島霊場とは異なります。
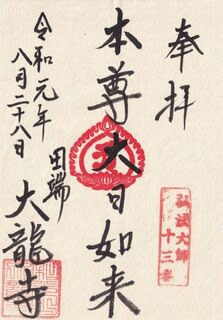
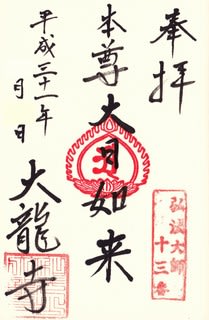
【上(左)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第13番の御朱印(御朱印帳)
(第7番へつづく)
-----------------------------------------------
滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)
滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)
滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)
【 BGM 】
■ I Will Be There with You ~日本語版~ - 杏里
■ 空に近い週末 - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 四万温泉周辺の御朱印
2020/12/05 更新UP
さらに追記します。
境内・山内の様子について、補強UPしました。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
------------------------------
2020/05/16UP
すこし追加&追記します。
このエリアは真田氏、海野氏など、武田信玄公とゆかりのふかい武家の本拠地なので、信玄公にちなむ事跡などを補強してリニューアルします。
(→ 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印)
------------------------------
2019/04/12UP


先日、ふるさと納税でゲットした地域券があったので、ひさびさに草津&四万に泊まってきました。
御朱印もいただいてきましたので、草津&四万周辺でいただける御朱印をご紹介します。
吾妻エリアは吾妻三十三番観音霊場や三原(谷)三十四所観音札所などの古い霊場はあるものの、その札所の多くは廃寺や山中のお堂で、この霊場でいただける御朱印はほとんどありません。
複数の現役霊場が重複する県央(前橋・高崎)や東毛(伊勢崎・桐生・太田・館林など)エリアとくらべると、授与所はどうしても少なくなります。
それでも、神社も含めるとそれなりの数は揃いますので、草津のアプローチベースとなる長野原町、同じく四万の中之条町も併せてご紹介してみます。
今回は2発目の四万温泉です。少し離れますが、高山村、東吾妻町、そして渋川市の吾妻川沿いの寺社もご紹介します。
※こちらでご紹介する寺社は札所でない寺院やご不在気味の神社を含みます。参拝時、ご不在で御朱印が拝受できない可能性があることを予めお断りしておきます。
〔2019年4月〕
四万に泊まり、さらに御朱印をいただきましたのでリニューアルUPします。
第1回目(草津温泉編)は、→こちら
・四万~草津温泉間の寺社については↑をご覧ください。
第3回目(伊香保温泉編)は、→こちら
・高崎市~渋川市の利根川右岸、および倉渕方面の寺社については↑をご覧ください。
【四万温泉周辺で拝受できる御朱印】
東京方面から四万に入るとき、ふつうは関越道渋川伊香保ICで降り、R17~R353(長野街道)というルートをとりますが、わたしはたいてい前橋ICか駒寄スマートICで降りて榛名東麓を北上し、県道35(通称「日陰道」)を経由してアプローチします。
この「日陰道」沿いに鎮座する神社からご紹介をはじめます。
01.甲波宿禰神社





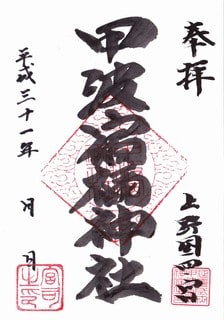
渋川市川島1287
御祭神:速秋津彦命、速秋津姫命
式内社論社、上野國十二社のうち、四之宮
旧社格:郷社
朱印尊格:甲波宿禰神社
・中央に社名印と「甲波宿禰神社」の揮毫。
右下に「上野国四宮」の揮毫と「延喜式内甲波宿禰神社之印」、左下には宮司之印が捺されています。
お湯のよさで知られる金島の「富貴の湯」にもほど近い、川島地区に鎮座する神社で「かわすくねじんじゃ」と読みます。
上野國十二社では、一之宮貫前神社(富岡市)、二之宮赤城神社(前橋市)、三之宮伊香保神社(渋川市)に次ぐ四之宮に列格し、高い格式をもつ古社です。
御祭神は古事記では「水戸神」とも記され、水や川とのゆかりが深い神格とされます。
また、延喜式神名帳には「上野國群馬郡 甲波宿禰神社」と記され、当社は式内社論社とされます。
甲波宿禰神社はこの周辺にあと二社(東吾妻町箱島と渋川市行幸田)あり、箱島の甲波宿禰神社も式内社論社とされています。
また、渋川市祖母島に鎮座する武内神社も式内社論社とされます。
行幸田の甲波宿禰神社は諸説ある模様で、詳細は不詳です。
祖母島に鎮座し、建内宿禰命を御祭神とする武内神社も「上野國群馬郡 甲波宿禰神社」の論社とされますが、なぜ武内神社が甲波宿禰神社の論社に位置づけられているかは諸説があるようです。(「宿禰」がキーワードという説あり。)
川や水にゆかりのふかい神社は三社構成(例.宗像大社や丹生川上神社)の例があり、甲波宿禰神社もその例に当たるという説もあります。
この説をとる人も、甲波宿禰神社(川島)、甲波宿禰神社(箱島)、武内神社(祖母島)(「島」がキーワードという説あり)の三社を挙げることが多いようです。
いずれにしても、このあたりで川といえば吾妻川ですから、吾妻川との深いつながりが考えられます。
なお「神道集」の第四十一「上野国第三宮伊香保大明神事」によると、延喜式内社の「甲波宿禰神社」の当初の祭神は上野国の目代(国司代理)で有馬に拠った伊香保大夫の女房(宿禰大明神)で、本地は千手観世音菩薩とされています。
(神道集については伊香保温泉周辺の御朱印-2(後編))中、「19.船尾山 等覚院 柳澤寺」をご参照ください。)
神社下の宮司様宅まではのどかな住宅地ですが、参道に入ると俄然空気が変わります。
さすがに上野國四之宮、式内社論社というべきか。
参道石段登り口の左右に石の標柱。少し登って右手に社号標。
その先には石造藁座つきの神明鳥居。
さらに登ると狛犬一対。なかなか均整のとれた狛犬です。
正面に拝殿。入母屋造流れ向拝銅板葺で、千木と堅魚木を置いています。
向かって左手の桜がちょうど満開で、趣を添えていました。
向拝は水引虹梁木鼻に貘、正面向きに獅子の彫刻。中備に龍の彫刻。
海老虹梁、手挟ともに立体感あふれる見事な彫刻が施されています。
正面桟唐戸、扁額は社号「甲波宿禰神社」。
拝殿内の算額は、安政七年(1856年)奉納で、市の重要文化財に指定されています。
神さびた境内には、神明社、諏訪神社などの境内社が鎮座します。
御朱印は宮司様宅に書置のものが用意されていました。
02.密教山 如音院 顕徳寺





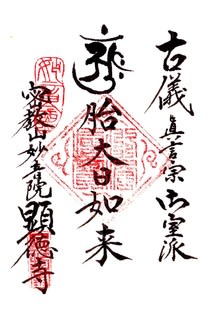
東吾妻町原町432
真言宗御室派 御本尊:胎蔵(界)大日如来
札所:吾妻三十三番観音霊場第13番
札所本尊:正観世音菩薩(旧 寶玉山 光原寺)
東吾妻町原町にある密教寺院です。
吾妻エリアに密教寺院は多くなく、しかも東日本では比較的めずらしい御室派(古義真言宗)なので、寺院マニアは外せないお寺さんでは?
天正十年(1582年)、甲州武田氏の滅亡直前、真田昌幸は武田氏当主武田勝頼に甲斐を捨て、自領の岩櫃城へ移り武田氏の再興を図ることを進言し容れられました。
昌幸は、勝頼の居館「古谷御殿」を用意して待ちましたが、勝頼は天目山で自刃し武田氏は滅亡しました。
この「古谷御殿」が巌下寺潜龍院という寺となり、さらに移築されて開基されたのがこの顕徳寺と伝わります。(顕徳寺の護摩堂が移築された「古谷御殿」とされます。)
今回、御朱印を広く授与されていない寺院については、拝受していてもご紹介は控えました。こちらも迷いましたが、このような歴史的な由来をもち、一応観音霊場の札所でもあり、書置き御朱印もご用意されていたのでご紹介します。
(※こちらのお寺様は、現在御朱印を授与されていないというWeb情報があります。)
しっとり落ち着きのある山内。
「古谷御殿」の移築とされる護摩堂(本堂)は、側面から撮った写真がなく詳細不明ですが、妻入りのような感じがします。
妻入りだとすると、入母屋造で唐破風向拝。
屋根の棟飾りに経の巻獅子口。唐破風に鬼板と兎毛通。
水引虹梁の装飾は簡素ですが、中備に寺号「顕徳寺」の扁額を掛け、上部梁の上に大瓶束と見事な彫刻を置く笈形という意匠です。
なんとなく変わったイメージの仏殿で、造詣が深い人が見れば見どころはたくさんあるのかもしれません。
本堂向かって左手にある観音堂は吾妻三十三番観音霊場第13番札所の可能性がありますが掲示類はなく詳細不明。
こちらも入母屋造妻入りで唐破風向拝の様な感じがします。
向拝部の破風が唐破風と千鳥破風を折衷したような特異な形状で、端正な経の巻獅子口が意匠的に効いています。
身舎に対して屋根が大ぶりで、力感を感じる仏堂です。
御朱印は庫裡にて揮毫書置きのものを拝受しました。
【御本尊の御朱印】
中央に御本尊、胎蔵(界)大日如来の荘厳体種子「アーンク」と「胎大日如来」の揮毫と三寶印。右に「古儀真言宗 御室派」の揮毫。
左に山号・院号・寺号の揮毫と寺院印の捺印があります。
御本尊尊格の揮毫は、もはや「『胎蔵』大日如来」でさえなく、「『胎』大日如来」となっています。(下記参照)
種子「アーンク」(阿字五点具足)は通種子「ア」の荘厳体で、胎蔵大日如来が尊格となる御朱印じたいが少ないため、そうそう見ることができません。
密教的に深い意味が込められた御朱印に思われ、筆致の冴えもすばらしいです。
〔胎蔵(界)について/ご参考〕
密教にはその宇宙観をあらわすふたつの代表的な曼荼羅があります。
大日如来の理徳(慈悲)をあらわす胎蔵(界)曼荼羅と大日如来の智徳をあらわす金剛界曼荼羅で、両者を併せて「両界曼荼羅」ないし「両部曼荼羅」といいます。
胎蔵(界)は大日経により説かれ、金剛界は金剛頂経で説かれるものです。(両部の大経)
仏教の入門書などでは、対比的にわかりやすいため、「胎蔵界」「金剛界」とされる例が多いです。
「金剛界」は金剛頂経で「世界」として説かれるので、「金剛界」の表現に疑義はありませんが、「胎蔵(界)」は教典の原語には「世界」に当たる言葉が入っていないため、とくに真言宗系寺院では、「界」を入れずに「胎蔵曼荼羅」ないし、正式名「大悲胎蔵曼荼羅」とされることが多いようです。
また、原語に「大悲胎蔵生」とあることから、「胎蔵生」とされることもあります。
大日如来は、胎蔵(界)大日如来と金剛界大日如来がおられ、おのおの印相、種子、真言などが異なります。
金剛界大日如来は智拳印を、胎蔵界大日如来は法界定印を結びますが、智拳印の方が特徴があるのでわかりやすいです。
03.大宮巌鼓神社






東吾妻町原町811
御祭神:日本武尊、弟橘姫命、素盞鳴尊、保食神 外合祀神社祭神
旧社格:郷社
朱印尊格:大宮巌鼓神社 印判
・中央に社名印、「宮司之印」の捺印と「大宮巌鼓神社」の印判。右上に「上州原町鎮座」の印判が捺されています。
神社御朱印です。
東吾妻町の中心地、原町の市街地に鎮座し「おおみやいわづつみじんじゃ」と読みます。
旧郷社に列格して社格は高く、原町一円の鎮守社のようです。
社歴は千年を超えるとされますが、創祀由緒は詳らかではありません。
日本武尊と上妻姫の御子、大若宮彦(巌鼓尊/巌鼓大明神)も祀るという説もあります。
実際、拝殿扁額には「巌鼓大明神」とありました。
また、古くから信仰の対象とされてきた四万奥の稲包山は、山頂に奥宮、登山口のゆずりは地区に中宮の稲裹神社(いなつつみじんじゃ)、そして大宮巌鼓神社を里宮とするという説もあるようです。
社頭に「郷社 大宮巌鼓神社」の社号標と扁額付きの朱塗りの明神鳥居。
参道石段を登って石造台輪鳥居。正面が拝殿です。
境内はこぢんまりとしていますが、古社特有の厳かな空気に満ちています。
神明社、八幡宮、宇婆神社など数座の境内社が鎮座します。
入母屋造平入りで向拝部唐破風。軒下の朱塗りの意匠が効いて、華やいだ感じのある拝殿です。
水引虹梁の端部木鼻に彫刻(二面)。中備にはおそらく龍の彫刻ですが、前面に「正一位大宮 巌鼓大明神」の扁額がかかっているのでよくわかりません。
身舎の斗栱は、おそらく三手先はあり三重の尾垂木を備える豪壮なものです。
本殿は囲いに囲まれよく見えませんが、正面に懸魚らしきものがあり、屋根の形状からしても流造ではなく、春日造のような感じがします。
御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れ(印判)をいただきました。
04.寶満山 白雲閣 林昌寺
寺院情報(さなだんごの旅)








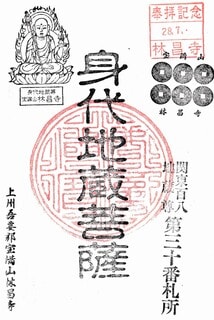
中之条町伊勢町1002
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:関東九十一薬師霊場第45番、関東百八地蔵尊霊場第30番、吾妻三十三番観音霊場第17番、第24番、第26番、第27番、第29番、第30番(以上6ヶ所?)
札所本尊:宝満薬師如来(関東九十一薬師霊場第45番)、身代地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第30番)
南北朝時代創建、戦国時代に真田幸隆の弟、矢沢薩摩守頼綱によって再建され、以降真田氏のもとで寺勢を伸ばした中之条の名刹。
山号は寶満山。院号ではなく、「白雲閣」というめずらしい閣号です。
境内の目通り3.8メートルのしだれ桜の古木でも名を知られています。
矢沢頼綱は真田頼昌の三男とされ、真田幸隆の弟にあたります。
天文十年(1541年)の「海野平の戦い」で敗れ、諏訪氏の斡旋を受けて武田信虎の麾下に入りました。
以降、武田方として活躍し、永禄六年(1563年)の真田氏の岩櫃城攻略でも功を立て、岩櫃城代を勤めたとされます。
以降、幸隆、信綱、昌幸に従って吾妻郡の守将として重きをなし、沼田城代にも任じられ、北条方の数度にわたる沼田城攻撃を能く凌いで天正十七年(1589年)の豊臣秀吉の命による沼田城明け渡しまで沼田城を守り抜きました。
この沼田城における矢沢頼綱の戦巧者ぶりは、真田昌幸が上田城で徳川勢を退けた「神川合戦」、昌幸が上田に徳川秀忠の大軍を釘付けにした「第二次上田合戦」と並び賞されています。
矢沢家は上田でも真田家の家老職を務め、明治維新を迎えたとされます。
創建時は天台宗と伝わりますが、現在は曹洞宗に属しています。
中之条町は吾妻三十三番観音霊場の中心エリアで複数の札所がありましたが、廃寺が多く、うち6ヶ寺ほどの札所本尊が林昌寺に移られているようです。
ただ、不思議なことに林昌寺じたいはもともとの札所ではなく、この霊場の御朱印も授与されていないようです。
山門は入母屋造三間一戸八脚、上層に高欄を回す堂々たる楼門で三手先の斗栱を備えています。
上層に「白雲閣」の扁額。大棟には六連銭(真田六文銭)の紋。
脇間、木格子の内には阿像・吽像の金剛力士像が安置されています。
さらに石段を登ると正面に本堂。入母屋造平入りで、正面やや左寄りに別建てで唐破風屋根の向拝を置いています。
こちらも大棟には六連銭(真田六文銭)の紋、向拝唐破風の鬼板も六連銭(真田六文銭)の紋入りです。
三間の梁行をもつ大規模な向拝は、さすがに大寺の風格。
現況、関東九十一薬師霊場と関東百八地蔵尊霊場の札所を兼ねています。
このふたつの霊場はともに出版社主導という異色の成り立ちで、兼務の札所もすくなくありませんが、こちらも兼務札所となっています。
関東九十一薬師霊場の札所本尊は、仁王門北向佛殿内に御座す立像の「宝満薬師如来」です。
このお薬師様は、嵩山の麓、飛地境内の薬師堂に御座す有名な「嵩山石薬師」のお前立とも伝わっているようです。
関東百八地蔵尊霊場の札所本尊は、本堂左脇に御座す座像の「身代地蔵菩薩」です。
このお地蔵様は、矢沢頼綱が戦陣で身代わりとなって戦死した家臣の供養のため建立した「身代地蔵尊」にちなむ尊像とされています。
御朱印は庫裡にて2つの霊場と御本尊のものを拝受。
【御本尊の御朱印】
中央に三寶印と「南無釈迦牟尼佛」の印判。
右に釈迦牟尼佛の御影印。左下には山号寺号の印が捺されています。
真田氏所縁の寺院らしく、寺紋は六連銭(真田六文銭)で、こちらの印判も捺されています。
【関東九十一薬師霊場の御朱印】
中央に三寶印(御本尊御朱印とは異なるもの)と「宝満薬師如来」の印判。
左上に薬師如来の御影印。右下に「関東九十一薬師第四十五番霊場」の札所印。左下には山号寺号の印。六連銭(真田六文銭)の印判も捺されています。
【関東百八地蔵尊霊場の御朱印】
中央に三寶印(御本尊御朱印と同じもの)と「身代地蔵菩薩」の印判。
左上に地蔵菩薩の御影印。右下に「関東百八地蔵尊第三十番札所」の札所印。左下には山号寺号の印。六連銭(真田六文銭)の印判も捺されています。
05.長岡山 清見寺


中之条町中之条746
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第26番札所
札所本尊:聖観世音菩薩
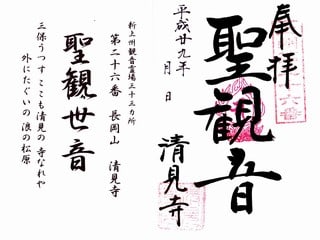
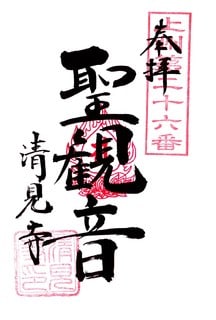
【写真 上(左)】 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
【新上州三十三観音霊場の御朱印】
・中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と「聖観音」の揮毫。
右上に「上州第二十六番」の札所印。左下には寺号の揮毫と印判が捺されています。
専用納経帳(差し替え式)、御朱印帳書入れとも同様の内容です。
長禄二年(1458年)開創。慶長元年(1596年)、京都知恩寺から入られた岌山和尚の再興となる浄土宗の古刹。
寺号は原則音読みですが、こちらも音読みで「せいけんじ」となります。
御本尊が聖観世音菩薩となっている資料もありますが、阿弥陀如来のようです。
札所本尊は平成8年に中興四百年を記念して庫裡前に建立された大聖観世音菩薩とみられます。
駐車場は広く、すぐ上に庭園、そのおくに観音霊場の札所本尊とみられる立像の観音様が御座します。
石垣に囲まれたお城のような石段を登っていきます。
正面に本堂。入母屋造桟瓦葺流れ向拝付き。
向拝・身舎とも、ところどころ朱色に塗られ、華やかなイメージの彩色ですが全体にスクエアできっちり端正なつくり。
瓦屋根の照りが強く、降り棟、隅棟、稚児棟の曲線が見事です。
向拝正面の扁額は寺号「清見寺」。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受。新上州三十三観音霊場は比較的メジャーなので、手慣れた対応です。
なお、御本尊・阿弥陀如来の御朱印は授与されていないようです。
06.龍水山 珠光院 善福寺

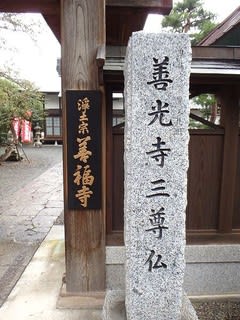




中之条町山田571
浄土宗 御本尊:善光寺式三尊仏
札所:吾妻三十三番観音霊場第15番、第16番
札所本尊:十一面観世音菩薩
朱印尊格:南無阿弥陀佛(御本尊の御朱印) 直書(筆書)
・中央に三寶印と六字御名号「南無阿弥陀佛」の揮毫。右上に御本尊、阿弥陀如来の種子「キリーク」の印判と「善光寺式三尊佛」の揮毫。
浄土宗寺院の御朱印で種子印判使用のものはめずらしくないですが、三寶印と種子印ダブル捺しのものはめずらしいと思います。
左下には寺号の揮毫と山号・寺号の印判が捺されています。
中之条市街地から沢渡方向に離れた浄土宗寺院。
慶永元年(1342年)の創建で、日本48体の善光寺如来第45番の尊像を安置したと伝えられている古刹です。現在は増上寺末となっています。
全国善光寺会の会員寺院でもあります。
全国善光寺会の会員寺院は御朱印を授与されるところが多く、また、全国善光寺会公式Webにも御朱印授与の有無が掲載されています。
善福寺については、授与の有無欄がブランクとなっていますが、快く授与いただけました。
ただ、メジャーな札所ではないのでご不在はいたしかたなしかと。わたしも2回目の参拝で拝受できました。
御本尊は、鎌倉時代中期の作と伝わる一光三尊形式の善光寺式阿弥陀如来。通常は秘仏で12年に一度午年のご開帳です。
山門横にある観音堂には、吾妻三十三番観音霊場第15番札所の法華山長岡寺(車堂)と16番札所の明星山光圓寺の観世音菩薩が遷座されて御座します。
前者は十一面観世音菩薩のようです。
山内入口に立像の地蔵尊造と六地蔵尊。「善光寺三尊仏」の石標。
山門は切妻造本瓦葺の高麗門で、梁に山号「龍水山」の扁額、柱に「善福寺」の寺号板を掲げます。
正面が本堂。入母屋造壁板張り銅板葺流れ向拝付きで庫裡と繋がっています。
本堂の斜向かいに建つ観音堂は、宝形造鉄板葺で身舎は古色を帯びています。
正面に「十五番 車堂」の堂号とご詠歌を刻した扁額で、みるからに観音霊場札所の佇まい。
向拝柱には第16番の御詠歌も掲げられていました。
御朱印は庫裡で拝受しました。
御本尊の御朱印で、観音霊場のものは現在授与されていないそうです。
07.和利宮吾妻神社






中之条町横尾1354-1
御祭神:大穴牟遲神ほか
旧社格:郷社
朱印尊格:和利宮 吾妻神社
・中央に社名印と「和利宮 吾妻神社」の揮毫。「吾妻神社」は大きく、「和利宮」は小さめに揮毫されています。
神社御朱印です。
吾妻総鎮守ともいわれ旧郷社の高い格式を有する古社ながら、旧記古文書が文化九年に焼失したため創祀ははっきりしていないようです。
由緒書によると、もともとは約300m南西の御洗水山頂上に鎮座され、現社地はその遙拝地だったが参拝が容易な現社地に奉遷されたとの由。
また、嵩山南麓の地(現、親都神社)から御洗水山頂上に遷座ののち、現社地に奉遷との伝承もみられるようです。
嵩山は吾妻地方屈指の霊山で、こちらの里宮にあたるとの説もあります。
一方、『神道集』中の「児持山之事」伝承とのつながりを指摘する説もみられます。
「児持山之事」伝承の発端は伊勢国で、その主人公のひとり加若次郎和理は「児持(吾妻)七社」(児持山大明神・半手木(破敵)大明神・鳥頭大明神・和理大明神・山代大明神・駒形大明神・白専女大明神)のうち和理大明神(和利宮?)になられたという説があります。
御洗水山頂上は現在の伊勢町伊勢宮の裏とされ、伊勢国とのつながりも連想されるところです。
さらに、嵩山を「わりのたけ」とも称し、親都神社は江戸時代「和利宮」と称していたなど、複雑な由緒来歴を有しているようです。
また、由緒書にある「本社ノ社名ハ中古以前ニアリテハ和流宮ト称シ奉レリ、蓋シ和流ハ唐流ニ対スル大和流ノ義ニシテ」という記載も気になるところです。
ふつう「吾妻」(あがつま)の地名の発祥は日本武尊(倭建命)の「吾嬬はや」に依るものとされますが、それだけでは納まらない奥の深さを感じます。
明治維新以前は和利宮ないし割宮とされていましたが、維新を契機に村社6社、無格社18社、境内末社127社、合計151社を合祀して吾妻神社となったようです。
御祭神は大穴牟遲神ほかとされています。
社頭に社号標と朱塗りの明神鳥居で「吾妻神社」の扁額が掛けられています。
参道向かって右手に神楽殿、正面に拝殿。
拝殿は入母屋造銅板葺で、大ぶりな千鳥破風をおこし、鬼板と兎毛通を置いています。
本殿は垣に囲まれよく見えないですが、流造銅板葺で四手先と思われる組物とその間に彫られた彩色彫刻が見事です。
脇障子の彫刻も精緻な仕上がり。海老虹梁や手挟の彫刻もすさまじく立体感を帯びています。
こちらの資料(くまがやねっと)によると、武州玉井村(現熊谷市)に生まれ、花輪村石原吟八に師事し、主に寛政年間(1789-1801年)~文政年間(1818-1831年)に名作を遺した小林源太郎とその父源八の手によるものとのこと。
御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れをいただきました。
08.親都神社






中之条町五反田220
御祭神:素戔嗚尊(須佐之男命)
旧社格:不詳(郷社という情報あり)
朱印尊格:親都神社 揮毫印刷?
・中央に社名印と独特な字体で「親都神社」の揮毫(印刷だと思う)があります。
そば処で有名な「道の駅たけやま」のそばにある古社で「ちかとじんじゃ」と読みます。
かつてこの地は吾妻の主城、岩櫃城の出城である嵩山城が築かれていたところで、一帯は城下町として、「親都千軒」といわれるほどの繁栄をみせたそうです。
城主は上杉方の吾妻斎藤氏でしたが、戦国期の永禄六年(1563年)に、岩櫃城が甲斐・武田方の真田・鎌原勢の攻勢を受けて落城。永禄八年(1565年)には激戦の末、嵩山城も落ち、往年の賑わいは失われたものとみられます。
この落城の戦死者を弔うため、嵩山に百観音が建立されたものと伝わります。
もともと、嵩山は古代から祖先の霊魂を祀る山とされる霊山で、天狗伝承も伝わってパワスポ的な要素には事欠きません。
親都神社の境内に由緒書は見当たらず、公的なWeb情報もほとんどとれませんが、そのわりに民間の情報は多く、しかもその内容は錯綜気味です。
複数の情報をまとめてみると、
・親都神社は霊山、嵩山自体を御神体としている。
・南北朝時代に編纂された「神道集」によると、嵩山の祭神は和理大明神。
・和理大明神は、嵩山山頂の奥社、麓の親都神社、里宮の和利宮で祭られている
・和理大明神は、『神道集』中の「児持山之事」伝承につながる「児持(吾妻)七社」のうちの一柱である。
・和利宮はもともと親都神社の場所に祀られていたが、御手洗山に遷座され、さらに現在の吾妻神社の境内地に遷座された。
・和利宮が遷座されたため、地元五反田の住民達は須佐之男命の分霊を勧請して氏神とした。
ここから推察するに、やはり複雑な由緒来歴を有しているようです。
なお、「道の駅たけやま」のWebには、「嵩山の神和利大明神として子持山の神を妻とし、鳥頭明神を子供として吾妻地方の中心的な神となっていた」と、神々の縁起を集めた『神道集』には記されています。」との表記があり、嵩山と和利(理)大明神のふかいつながりが窺われます。
参道は、駐車場(道の駅)の反対側にあります。
石段の参道で「親都神社」の社号標、明神鳥居、さらに登った正面に拝殿。
嵩山を背後に仰ぐかたちで参道、拝殿、本殿が配置されていることがわかります。
木々に囲まれて神さびた趣きの境内。摂社は少なく、シンプルに嵩山を拝している感じがします。
拝殿は入母屋造銅板葺身舎桁行三間で、ボリューム感にあふれた唐破風向拝を備えます。
水引虹梁端部に二面の木鼻彫刻。上部に斗栱。中備に蟇股。正面は桟唐戸でその上に「正一位親都大明神」の扁額。
向かって右手に切妻造平入りの建物を連結しています。
本殿は覆屋に納められ、よくわかりませんでした。
境内のケヤキの巨木は「親都神社の大ケヤキ」として県の天然記念物に指定され、御神木として信仰されています。
御朱印は書置のものを「道の駅たけやま」で拝受できます。
保管分がなくなった場合、簡単には補充できないような感じもあるので、事前に電話確認がベターかと思います。
09.熊野山 関松院 泉龍寺



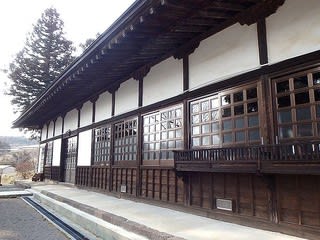

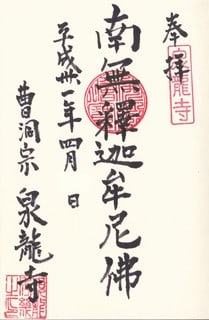
高山村大字尻高甲1939
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛(御本尊の御朱印) 直書(筆書)
・中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。
右上に「泉龍寺」の印判。右下に宗派、寺号の揮毫と寺院印の捺印があります。
禅寺の本流的な御朱印かと思います。
高山村にある曹洞宗の古刹。
境内掲示の由来記によると、大同年間に弘法大師が開かれた名刹で、慶長三年月夜野の嶽林寺五世関室傳察禅師を開山として迎えて改宗されたとあります。
徳川三代将軍家光公より二十石の御朱印を賜り、五年に一度江戸城の将軍に御年禮(の登城)をする習わしであったとのこと。
名刹らしく、杉並木に囲まれた長い参道。
石段を登って一間一戸の薬医門ないし高麗門で風格があります。
正面に本堂。入母屋造銅板葺の端正な仏堂で、向拝部が向かって左手に寄っているので、梁行の意匠はシンメトリではありません。
また、本堂裏手には源頼朝公が浅間山麓に巻狩りに出向かれた際、泉龍寺で休憩され自ら植えられたという高野槙があり、「泉龍寺の高野槙」として県の天然記念物に指定されています。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書き入れいただけました。
こちらは札所ではないですが、古刹で、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
ただし、御朱印の授与をお願いするといささか驚かれた風もあったので、御朱印を乞う参拝者は多くないかと思われます。
10.熊野山 福蔵寺 (北向観世音)



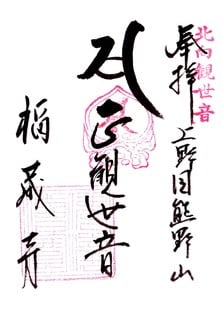
高山村尻高乙1260
天台寺門宗 御本尊:正観世音菩薩
朱印尊格:正観世音(御本尊の御朱印) 書置(筆書)
・中央に御本尊、正観世音菩薩の種子「サ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判・揮毫と「正観世音」の揮毫。
右に「北向観世音」の印判と山号の揮毫。左に寺号の揮毫と三寶印の捺印があります。
「北向観世音」として親しまれる高山村の天台修験系の寺院です。
永保元年(1081年)、修験者熊野坊による開創とされます。
新田氏支族里見義候により再興、室町時代初期、上野国平井の関東管領山内上杉氏の執事白井長尾氏の一族長尾尻高氏が祈祷寺にしたと伝わります。
長尾尻高氏は、白井長尾景春(伊玄入道重国)の子重儀が尻高左馬頭を称したことに始まるとされます。
応永十年(1403年)、重国は尻高城を築き重儀を城主に据え、重儀は尻高姓を名乗って尻高左馬頭重儀となりました。
爾来、この地は尻高氏の領地となりましたが、戦国時代に入ると山内上杉氏と甲斐から進出した武田氏の勢力がぶつかるところとなり、尻高氏も戦乱に巻き込まれていきました。
上杉方は岩櫃城の斎藤氏、武田方は小県の真田氏、三原の鎌原氏が代表格で、尻高氏は斎藤氏に属して真田・鎌原勢と対峙しました。
永禄六年(1563年)、武田方の真田・鎌原勢の攻撃により岩櫃城は落城、城主斎藤憲広は越後に逃れました。
憲広の子憲宗と弟虎城丸が支城の嵩山城に籠って再挙を図ると、尻高氏もこれに加わりました。
永禄八年(1565年)、嵩山城は真田氏の調略によって落城、尻高氏は武田方に降ったものの再び上杉方に転じたとされ、天正二年(1574年)武田方の真田幸隆は尻高城を攻めました。
尻高勢は奮戦したものの、ついに城は落ち、城主尻高景家は越後に落ちのびたとも伝わります。
一族の尻高義隆は、後年猿ケ京に籠もりましたが、武田・真田方の岩櫃城代の矢沢薩摩守に攻められて、ここに上州の尻高勢は滅亡したとされます。
北斗信仰にもとづき北方に向いて御座す「北向観世音」は、安産・子育て等にご利益ありとして参拝客を集めています。
修験の寺らしく、神変大菩薩(役行者)も御座します。また、5㎞ほど離れた「瀧の下不動尊」の護持もされているようです。
御本尊は、修験寺ではめずらしい正観世音菩薩です。
境内には朱塗りの灯籠や、地蔵尊、不動尊などが御座し、修験寺らしい雰囲気。
本堂前の一対の狛犬は、神仏混淆の歴史を物語るものか。
本堂は入母屋造本瓦葺唐破風向拝付きの豪壮な仏堂で、大棟から一気に引き降ろされる降り棟とくっきりとした掛瓦の対比が見事。
水引虹梁はシンプルですが、唐破風兎毛通の後ろに金色の龍が潜んでいます。
海老虹梁、桟唐戸、正面の扁額は「厄除観世音」です。
御朱印は庫裡にて揮毫書置きのものを拝受しました。
11.揚水山 舞台院 宗本寺





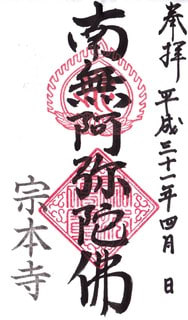
中之条町下沢渡494
浄土宗 御本尊:阿弥陀三尊
朱印尊格:南無阿弥陀佛(御本尊の御朱印) 書置(筆書)
・こちらは札所ではないので、御朱印は御本尊のもの(御名号)になります。
・中央に阿弥陀如来の種子「キリーク」の印判と三寶印の捺印。六字名号「南無阿弥陀佛」の揮毫。左下に寺号印の捺印。
06.善福寺のところで「浄土宗寺院の御朱印で種子印判使用のものはめずらしくないですが、三寶印と種子印ダブル捺しのものはめずらしいと思います。」と書きましたが、こちらもそのパターン。このエリアではこれが標準なのかもしれません。
応永元年(1394年)創建とされる浄土宗の古刹で、四万温泉、日向見薬師堂の護持をされています。
芝増上寺直末の格式を誇り、細い路地がらみのアプローチからは想像のつかない立派な伽藍を構えています。
石段参道の途中に朱い冠木門。さらに進むと寺号標でその先の石段を登り切ると本堂前です。
本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を付設し、この向拝の彫刻が出色です。
水引虹梁の端部に貘と獅子の木鼻彫刻。中備に二頭の相対する龍。兎毛通にも精緻な彫刻が施されています。
本堂の欄間彫刻(町指定重要文化財)は高瀬忠七、萩原平蔵、定運などの名工によるもので、この向拝の彫刻もこれら名工の手によるものかもしれません。
格天井には鳥の画、正面に寺号「宗本寺」の扁額。
本堂向かって左手の開山堂はおそらく入母屋造妻入り、軒下二軒繁垂木の均整のとれたつくりです。
御朱印は庫裡で拝受。ご住職はお出かけでしたが、寺庭さんから書置の御朱印をいただけました。
なお、こちらでは日向見薬師堂の御朱印も授与されています。
12.日向見薬師堂






中之条町四万4371
宗派不詳(現在、浄土宗寺院が護持) 御本尊:薬師如来
四万川に沿って南北に長い四万温泉の最奥の湯場、日向見にある薬師堂です。
古来、数多の湯治客から「湯前薬師」として尊崇を集めた薬師如来が御座します。
『四万の病を癒す霊泉』、四万温泉にふさわしい尊格といえましょう。
四万温泉の開湯伝承に碓氷貞光説があります。
永延三年(989年)頃、源頼光の家臣、碓氷貞光が越後から四万奥の木の根峠を越えて日向見に至った際、心を静め夜通し読経していると一人の童子があらわれ、「あなたの読経の真心に感心し四万の病気を治す温泉を与えよう、われはこの山神である」旨を告げられた。
気がつくと傍らには効能あらたかな温泉が湧き出でていたが、これが「日向見御夢想の湯」で、これを奇瑞として建立されたのが日向見薬師堂とされます。
いまの薬師堂は慶長三年(1598年)、時の領主、真田信幸の武運長久を願って建てられたといわれ、現存する県内最古の寺院建築とされる国の重要文化財です。
お堂前にある標柱に「国宝 日向見薬師堂」とあるのは、戦前、本堂が国宝に指定されていた名残です。
手前にあるのは「お籠堂」(町指定文化財)で、お薬師様の信者が病気平癒を願って参籠したお堂です。
寄棟造茅葺、外壁は真壁造り板張りで、中央を本堂への参道が貫く構造となっています。
その先が現存する県最古(慶長三年(1867年)、桃山時代)の御堂建築とされる本堂です。
桁行・梁間ともに三間、寄棟造茅葺、外壁真壁造り板張り。向拝柱のない四方浜縁です。
軒下は二軒の平行垂木、正面には「薬師堂」の扁額が掲げられています。
境内には、摩耶姫伝説に由縁し、縁結び、子宝に霊験のある「摩耶不動」も御座します。
(→四万温泉公認キャラクター「摩耶姫ちゃん」)
日向見薬師堂の宗派は不詳ですが、現在は中之条町下沢渡の浄土宗寺院、揚水山 宗本寺の管理下にあるようです。
御朱印は、書置タイプのものが参道手前の喫茶「あづまや」で拝受できます。
2016年2月拝受時は印判、2017年6月拝受時は揮毫のものでした。最近、ハンコから墨書きのものに変更されたそうです。
拝受者から「墨書き揮毫御朱印」のオファーがあったのでしょうか? たしかに女性客の多い四万温泉では御朱印ニーズが高そうです。
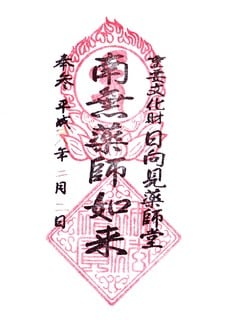

【写真 上(左)】 日向見薬師堂の御朱印(旧)
【写真 下(右)】 日向見薬師堂の御朱印(新)
【印判御朱印(以前授与)】
中央に御本尊、薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と三寶印。「南無薬師如来」の印判。
右に「重要文化財 日向見薬師堂」の寺号。左下に寺号関係の揮毫印判がなく、寺院御朱印としてはめずらしい様式です。
【印判御朱印(現在授与)】
中央に御本尊、薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と三寶印。「薬師如来」の揮毫。
こちらは右下に寺号の印判、左上に「奉拝」の揮毫も入って、寺院御朱印として標準的な様式です。(種子印・三寶印のダブル捺しと寺院印なしは、ややイレギュラーですが・・・)
2019年4月の花祭りに参拝しました。
なんと思いがけず御開帳されていて御尊像を直に拝めました。
せっかくの御開帳なのでお堂の軒におられたお坊様に御朱印を乞うと、「今日は花祭りなので特別な御朱印」との由。
わたしは限定御朱印にはほとんど興味がないのですが、御開帳となると話は別で有り難く拝受しました。書置御朱印です。
【花祭りの限定御朱印】

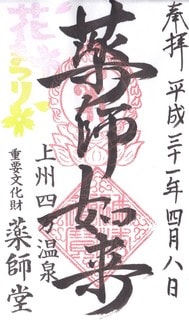
中央に御本尊、薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と三寶印。「薬師如来」の揮毫。
通常御朱印とのちがいは左上に「花まつり」のカラー印判があるかないかだけですが、「薬師如来」の揮毫に筆致の冴えが感じられます。
13.青麻山 薬王寺






中之条町四万4372-1
法華宗
御首題 書置(筆書)
・御首題は揮毫書置きタイプで、お題目のほか、所縁の尊格が揮毫されています。
流麗な筆致で見応えがあります。
日向見の高級宿「つるや」の山手にある法華宗の寺院。
新宿・左門町の陽雲寺のご住職が四万・日向見で療養されて完治を得、この日向見の地に薬王寺を建立されたそうです。
「つるや」はこの薬王寺の宿坊として誕生したとのことで、いまでも密接な関係があるようです。(つるやの「鶴」は法華宗の宗紋「鶴」に由来するとの由。)
日向見薬師堂に向かう道の手前右手に石段の参道。参道手前に御題目と寺号が刻まれた石標があります。
石段を登り切ると山門。これを抜けるとさらに数段の石段があってその先に本堂。
撮影した写真の構図が悪くいまいちよくわかりませんが、入母屋妻入りのお堂に唐破風の向拝を付設したような構造では。
海老虹梁に挟まれた身舎拝み部に「薬王大菩薩」「青麻大権現」の扁額を配した奉納額が掛けられています。
御首題(法華宗なので御首題となります)は、つるやの帳場で拝受できます。
境内には霊水「薬王水(御法水)」が湧いています。
なお、日向見のお宿「つるや」では「日向見ご利益巡り」と称して、薬王寺、日向見薬師堂、摩耶不動の3ヶ所を紹介しています。
なお、中之条町四万には吾妻三十三番観音霊場第21番の法平山 萬福寺(札所本尊:正観世音菩薩)があるはずですが、Webではまったく情報がとれませんでした。
今度現地で当たってみたいと思います。


宿泊は自家源泉*の「渓声の宿 いずみや」にとりました。
いかにも四万らしい滋味のあるお湯をかけ流しで、食事や接客のレベルもなかなかでした。
これで、現時点で入浴可能な四万の源泉はおそらくすべてクリアしたかと思います。(自家源泉を持ち日帰り不可の「竹葉館」が難物でしたが、お宿へのヒアリングによると現在は「四萬館の湯」を使っているそうで、こちらもクリアかと。)
源泉マニア的にはクリア。それでも、これを書きながらまたぞろ行きたくなっている四万温泉。やはりすばらしい湯場だと思います。
*)使用源泉は、「泉屋の湯」。
2019年4月は「四万グランドホテル」に泊まりました。
じつは、ここのバイキングはレベルが高く、しかも湯巡りパスポ(税込540円)を買うと四万たむらの風呂にも入れるので、もう5回ほども泊まっています。
じつは、ここの7階のメルヘン風呂は展望浴場ながらすこぶるお湯がよく、さりげに気に入っていますが、これについては稿を改めます。
(つうか、四万の共同浴場や旅館はほとんど制覇しているのですが、これをみると、レポComing Soon!多すぎ! おいおい温泉レポを再開し、フォローしたいと思います。(ここ数年、こればっかしじゃが・・・(笑))
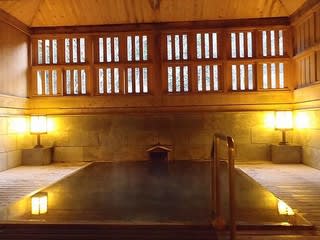

【写真 上(左)】 四万たむらの「御夢想の湯」
【写真 下(右)】 四万たむらの「森のこだま」
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
さらに追記します。
境内・山内の様子について、補強UPしました。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
------------------------------
2020/05/16UP
すこし追加&追記します。
このエリアは真田氏、海野氏など、武田信玄公とゆかりのふかい武家の本拠地なので、信玄公にちなむ事跡などを補強してリニューアルします。
(→ 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印)
------------------------------
2019/04/12UP


先日、ふるさと納税でゲットした地域券があったので、ひさびさに草津&四万に泊まってきました。
御朱印もいただいてきましたので、草津&四万周辺でいただける御朱印をご紹介します。
吾妻エリアは吾妻三十三番観音霊場や三原(谷)三十四所観音札所などの古い霊場はあるものの、その札所の多くは廃寺や山中のお堂で、この霊場でいただける御朱印はほとんどありません。
複数の現役霊場が重複する県央(前橋・高崎)や東毛(伊勢崎・桐生・太田・館林など)エリアとくらべると、授与所はどうしても少なくなります。
それでも、神社も含めるとそれなりの数は揃いますので、草津のアプローチベースとなる長野原町、同じく四万の中之条町も併せてご紹介してみます。
今回は2発目の四万温泉です。少し離れますが、高山村、東吾妻町、そして渋川市の吾妻川沿いの寺社もご紹介します。
※こちらでご紹介する寺社は札所でない寺院やご不在気味の神社を含みます。参拝時、ご不在で御朱印が拝受できない可能性があることを予めお断りしておきます。
〔2019年4月〕
四万に泊まり、さらに御朱印をいただきましたのでリニューアルUPします。
第1回目(草津温泉編)は、→こちら
・四万~草津温泉間の寺社については↑をご覧ください。
第3回目(伊香保温泉編)は、→こちら
・高崎市~渋川市の利根川右岸、および倉渕方面の寺社については↑をご覧ください。
【四万温泉周辺で拝受できる御朱印】
東京方面から四万に入るとき、ふつうは関越道渋川伊香保ICで降り、R17~R353(長野街道)というルートをとりますが、わたしはたいてい前橋ICか駒寄スマートICで降りて榛名東麓を北上し、県道35(通称「日陰道」)を経由してアプローチします。
この「日陰道」沿いに鎮座する神社からご紹介をはじめます。
01.甲波宿禰神社





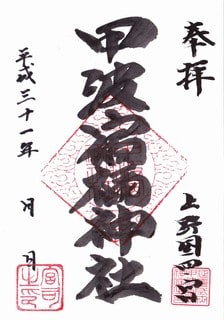
渋川市川島1287
御祭神:速秋津彦命、速秋津姫命
式内社論社、上野國十二社のうち、四之宮
旧社格:郷社
朱印尊格:甲波宿禰神社
・中央に社名印と「甲波宿禰神社」の揮毫。
右下に「上野国四宮」の揮毫と「延喜式内甲波宿禰神社之印」、左下には宮司之印が捺されています。
お湯のよさで知られる金島の「富貴の湯」にもほど近い、川島地区に鎮座する神社で「かわすくねじんじゃ」と読みます。
上野國十二社では、一之宮貫前神社(富岡市)、二之宮赤城神社(前橋市)、三之宮伊香保神社(渋川市)に次ぐ四之宮に列格し、高い格式をもつ古社です。
御祭神は古事記では「水戸神」とも記され、水や川とのゆかりが深い神格とされます。
また、延喜式神名帳には「上野國群馬郡 甲波宿禰神社」と記され、当社は式内社論社とされます。
甲波宿禰神社はこの周辺にあと二社(東吾妻町箱島と渋川市行幸田)あり、箱島の甲波宿禰神社も式内社論社とされています。
また、渋川市祖母島に鎮座する武内神社も式内社論社とされます。
行幸田の甲波宿禰神社は諸説ある模様で、詳細は不詳です。
祖母島に鎮座し、建内宿禰命を御祭神とする武内神社も「上野國群馬郡 甲波宿禰神社」の論社とされますが、なぜ武内神社が甲波宿禰神社の論社に位置づけられているかは諸説があるようです。(「宿禰」がキーワードという説あり。)
川や水にゆかりのふかい神社は三社構成(例.宗像大社や丹生川上神社)の例があり、甲波宿禰神社もその例に当たるという説もあります。
この説をとる人も、甲波宿禰神社(川島)、甲波宿禰神社(箱島)、武内神社(祖母島)(「島」がキーワードという説あり)の三社を挙げることが多いようです。
いずれにしても、このあたりで川といえば吾妻川ですから、吾妻川との深いつながりが考えられます。
なお「神道集」の第四十一「上野国第三宮伊香保大明神事」によると、延喜式内社の「甲波宿禰神社」の当初の祭神は上野国の目代(国司代理)で有馬に拠った伊香保大夫の女房(宿禰大明神)で、本地は千手観世音菩薩とされています。
(神道集については伊香保温泉周辺の御朱印-2(後編))中、「19.船尾山 等覚院 柳澤寺」をご参照ください。)
神社下の宮司様宅まではのどかな住宅地ですが、参道に入ると俄然空気が変わります。
さすがに上野國四之宮、式内社論社というべきか。
参道石段登り口の左右に石の標柱。少し登って右手に社号標。
その先には石造藁座つきの神明鳥居。
さらに登ると狛犬一対。なかなか均整のとれた狛犬です。
正面に拝殿。入母屋造流れ向拝銅板葺で、千木と堅魚木を置いています。
向かって左手の桜がちょうど満開で、趣を添えていました。
向拝は水引虹梁木鼻に貘、正面向きに獅子の彫刻。中備に龍の彫刻。
海老虹梁、手挟ともに立体感あふれる見事な彫刻が施されています。
正面桟唐戸、扁額は社号「甲波宿禰神社」。
拝殿内の算額は、安政七年(1856年)奉納で、市の重要文化財に指定されています。
神さびた境内には、神明社、諏訪神社などの境内社が鎮座します。
御朱印は宮司様宅に書置のものが用意されていました。
02.密教山 如音院 顕徳寺





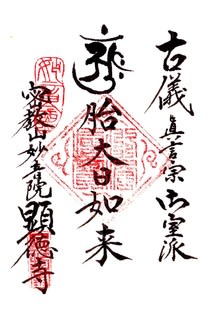
東吾妻町原町432
真言宗御室派 御本尊:胎蔵(界)大日如来
札所:吾妻三十三番観音霊場第13番
札所本尊:正観世音菩薩(旧 寶玉山 光原寺)
東吾妻町原町にある密教寺院です。
吾妻エリアに密教寺院は多くなく、しかも東日本では比較的めずらしい御室派(古義真言宗)なので、寺院マニアは外せないお寺さんでは?
天正十年(1582年)、甲州武田氏の滅亡直前、真田昌幸は武田氏当主武田勝頼に甲斐を捨て、自領の岩櫃城へ移り武田氏の再興を図ることを進言し容れられました。
昌幸は、勝頼の居館「古谷御殿」を用意して待ちましたが、勝頼は天目山で自刃し武田氏は滅亡しました。
この「古谷御殿」が巌下寺潜龍院という寺となり、さらに移築されて開基されたのがこの顕徳寺と伝わります。(顕徳寺の護摩堂が移築された「古谷御殿」とされます。)
今回、御朱印を広く授与されていない寺院については、拝受していてもご紹介は控えました。こちらも迷いましたが、このような歴史的な由来をもち、一応観音霊場の札所でもあり、書置き御朱印もご用意されていたのでご紹介します。
(※こちらのお寺様は、現在御朱印を授与されていないというWeb情報があります。)
しっとり落ち着きのある山内。
「古谷御殿」の移築とされる護摩堂(本堂)は、側面から撮った写真がなく詳細不明ですが、妻入りのような感じがします。
妻入りだとすると、入母屋造で唐破風向拝。
屋根の棟飾りに経の巻獅子口。唐破風に鬼板と兎毛通。
水引虹梁の装飾は簡素ですが、中備に寺号「顕徳寺」の扁額を掛け、上部梁の上に大瓶束と見事な彫刻を置く笈形という意匠です。
なんとなく変わったイメージの仏殿で、造詣が深い人が見れば見どころはたくさんあるのかもしれません。
本堂向かって左手にある観音堂は吾妻三十三番観音霊場第13番札所の可能性がありますが掲示類はなく詳細不明。
こちらも入母屋造妻入りで唐破風向拝の様な感じがします。
向拝部の破風が唐破風と千鳥破風を折衷したような特異な形状で、端正な経の巻獅子口が意匠的に効いています。
身舎に対して屋根が大ぶりで、力感を感じる仏堂です。
御朱印は庫裡にて揮毫書置きのものを拝受しました。
【御本尊の御朱印】
中央に御本尊、胎蔵(界)大日如来の荘厳体種子「アーンク」と「胎大日如来」の揮毫と三寶印。右に「古儀真言宗 御室派」の揮毫。
左に山号・院号・寺号の揮毫と寺院印の捺印があります。
御本尊尊格の揮毫は、もはや「『胎蔵』大日如来」でさえなく、「『胎』大日如来」となっています。(下記参照)
種子「アーンク」(阿字五点具足)は通種子「ア」の荘厳体で、胎蔵大日如来が尊格となる御朱印じたいが少ないため、そうそう見ることができません。
密教的に深い意味が込められた御朱印に思われ、筆致の冴えもすばらしいです。
〔胎蔵(界)について/ご参考〕
密教にはその宇宙観をあらわすふたつの代表的な曼荼羅があります。
大日如来の理徳(慈悲)をあらわす胎蔵(界)曼荼羅と大日如来の智徳をあらわす金剛界曼荼羅で、両者を併せて「両界曼荼羅」ないし「両部曼荼羅」といいます。
胎蔵(界)は大日経により説かれ、金剛界は金剛頂経で説かれるものです。(両部の大経)
仏教の入門書などでは、対比的にわかりやすいため、「胎蔵界」「金剛界」とされる例が多いです。
「金剛界」は金剛頂経で「世界」として説かれるので、「金剛界」の表現に疑義はありませんが、「胎蔵(界)」は教典の原語には「世界」に当たる言葉が入っていないため、とくに真言宗系寺院では、「界」を入れずに「胎蔵曼荼羅」ないし、正式名「大悲胎蔵曼荼羅」とされることが多いようです。
また、原語に「大悲胎蔵生」とあることから、「胎蔵生」とされることもあります。
大日如来は、胎蔵(界)大日如来と金剛界大日如来がおられ、おのおの印相、種子、真言などが異なります。
金剛界大日如来は智拳印を、胎蔵界大日如来は法界定印を結びますが、智拳印の方が特徴があるのでわかりやすいです。
03.大宮巌鼓神社






東吾妻町原町811
御祭神:日本武尊、弟橘姫命、素盞鳴尊、保食神 外合祀神社祭神
旧社格:郷社
朱印尊格:大宮巌鼓神社 印判
・中央に社名印、「宮司之印」の捺印と「大宮巌鼓神社」の印判。右上に「上州原町鎮座」の印判が捺されています。
神社御朱印です。
東吾妻町の中心地、原町の市街地に鎮座し「おおみやいわづつみじんじゃ」と読みます。
旧郷社に列格して社格は高く、原町一円の鎮守社のようです。
社歴は千年を超えるとされますが、創祀由緒は詳らかではありません。
日本武尊と上妻姫の御子、大若宮彦(巌鼓尊/巌鼓大明神)も祀るという説もあります。
実際、拝殿扁額には「巌鼓大明神」とありました。
また、古くから信仰の対象とされてきた四万奥の稲包山は、山頂に奥宮、登山口のゆずりは地区に中宮の稲裹神社(いなつつみじんじゃ)、そして大宮巌鼓神社を里宮とするという説もあるようです。
社頭に「郷社 大宮巌鼓神社」の社号標と扁額付きの朱塗りの明神鳥居。
参道石段を登って石造台輪鳥居。正面が拝殿です。
境内はこぢんまりとしていますが、古社特有の厳かな空気に満ちています。
神明社、八幡宮、宇婆神社など数座の境内社が鎮座します。
入母屋造平入りで向拝部唐破風。軒下の朱塗りの意匠が効いて、華やいだ感じのある拝殿です。
水引虹梁の端部木鼻に彫刻(二面)。中備にはおそらく龍の彫刻ですが、前面に「正一位大宮 巌鼓大明神」の扁額がかかっているのでよくわかりません。
身舎の斗栱は、おそらく三手先はあり三重の尾垂木を備える豪壮なものです。
本殿は囲いに囲まれよく見えませんが、正面に懸魚らしきものがあり、屋根の形状からしても流造ではなく、春日造のような感じがします。
御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れ(印判)をいただきました。
04.寶満山 白雲閣 林昌寺
寺院情報(さなだんごの旅)








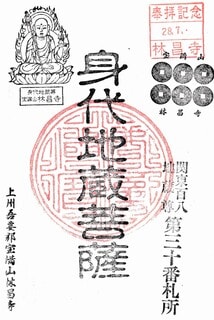
中之条町伊勢町1002
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:関東九十一薬師霊場第45番、関東百八地蔵尊霊場第30番、吾妻三十三番観音霊場第17番、第24番、第26番、第27番、第29番、第30番(以上6ヶ所?)
札所本尊:宝満薬師如来(関東九十一薬師霊場第45番)、身代地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第30番)
南北朝時代創建、戦国時代に真田幸隆の弟、矢沢薩摩守頼綱によって再建され、以降真田氏のもとで寺勢を伸ばした中之条の名刹。
山号は寶満山。院号ではなく、「白雲閣」というめずらしい閣号です。
境内の目通り3.8メートルのしだれ桜の古木でも名を知られています。
矢沢頼綱は真田頼昌の三男とされ、真田幸隆の弟にあたります。
天文十年(1541年)の「海野平の戦い」で敗れ、諏訪氏の斡旋を受けて武田信虎の麾下に入りました。
以降、武田方として活躍し、永禄六年(1563年)の真田氏の岩櫃城攻略でも功を立て、岩櫃城代を勤めたとされます。
以降、幸隆、信綱、昌幸に従って吾妻郡の守将として重きをなし、沼田城代にも任じられ、北条方の数度にわたる沼田城攻撃を能く凌いで天正十七年(1589年)の豊臣秀吉の命による沼田城明け渡しまで沼田城を守り抜きました。
この沼田城における矢沢頼綱の戦巧者ぶりは、真田昌幸が上田城で徳川勢を退けた「神川合戦」、昌幸が上田に徳川秀忠の大軍を釘付けにした「第二次上田合戦」と並び賞されています。
矢沢家は上田でも真田家の家老職を務め、明治維新を迎えたとされます。
創建時は天台宗と伝わりますが、現在は曹洞宗に属しています。
中之条町は吾妻三十三番観音霊場の中心エリアで複数の札所がありましたが、廃寺が多く、うち6ヶ寺ほどの札所本尊が林昌寺に移られているようです。
ただ、不思議なことに林昌寺じたいはもともとの札所ではなく、この霊場の御朱印も授与されていないようです。
山門は入母屋造三間一戸八脚、上層に高欄を回す堂々たる楼門で三手先の斗栱を備えています。
上層に「白雲閣」の扁額。大棟には六連銭(真田六文銭)の紋。
脇間、木格子の内には阿像・吽像の金剛力士像が安置されています。
さらに石段を登ると正面に本堂。入母屋造平入りで、正面やや左寄りに別建てで唐破風屋根の向拝を置いています。
こちらも大棟には六連銭(真田六文銭)の紋、向拝唐破風の鬼板も六連銭(真田六文銭)の紋入りです。
三間の梁行をもつ大規模な向拝は、さすがに大寺の風格。
現況、関東九十一薬師霊場と関東百八地蔵尊霊場の札所を兼ねています。
このふたつの霊場はともに出版社主導という異色の成り立ちで、兼務の札所もすくなくありませんが、こちらも兼務札所となっています。
関東九十一薬師霊場の札所本尊は、仁王門北向佛殿内に御座す立像の「宝満薬師如来」です。
このお薬師様は、嵩山の麓、飛地境内の薬師堂に御座す有名な「嵩山石薬師」のお前立とも伝わっているようです。
関東百八地蔵尊霊場の札所本尊は、本堂左脇に御座す座像の「身代地蔵菩薩」です。
このお地蔵様は、矢沢頼綱が戦陣で身代わりとなって戦死した家臣の供養のため建立した「身代地蔵尊」にちなむ尊像とされています。
御朱印は庫裡にて2つの霊場と御本尊のものを拝受。
【御本尊の御朱印】
中央に三寶印と「南無釈迦牟尼佛」の印判。
右に釈迦牟尼佛の御影印。左下には山号寺号の印が捺されています。
真田氏所縁の寺院らしく、寺紋は六連銭(真田六文銭)で、こちらの印判も捺されています。
【関東九十一薬師霊場の御朱印】
中央に三寶印(御本尊御朱印とは異なるもの)と「宝満薬師如来」の印判。
左上に薬師如来の御影印。右下に「関東九十一薬師第四十五番霊場」の札所印。左下には山号寺号の印。六連銭(真田六文銭)の印判も捺されています。
【関東百八地蔵尊霊場の御朱印】
中央に三寶印(御本尊御朱印と同じもの)と「身代地蔵菩薩」の印判。
左上に地蔵菩薩の御影印。右下に「関東百八地蔵尊第三十番札所」の札所印。左下には山号寺号の印。六連銭(真田六文銭)の印判も捺されています。
05.長岡山 清見寺


中之条町中之条746
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:新上州三十三観音霊場第26番札所
札所本尊:聖観世音菩薩
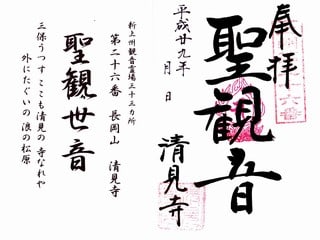
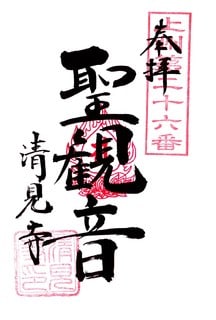
【写真 上(左)】 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
【新上州三十三観音霊場の御朱印】
・中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と「聖観音」の揮毫。
右上に「上州第二十六番」の札所印。左下には寺号の揮毫と印判が捺されています。
専用納経帳(差し替え式)、御朱印帳書入れとも同様の内容です。
長禄二年(1458年)開創。慶長元年(1596年)、京都知恩寺から入られた岌山和尚の再興となる浄土宗の古刹。
寺号は原則音読みですが、こちらも音読みで「せいけんじ」となります。
御本尊が聖観世音菩薩となっている資料もありますが、阿弥陀如来のようです。
札所本尊は平成8年に中興四百年を記念して庫裡前に建立された大聖観世音菩薩とみられます。
駐車場は広く、すぐ上に庭園、そのおくに観音霊場の札所本尊とみられる立像の観音様が御座します。
石垣に囲まれたお城のような石段を登っていきます。
正面に本堂。入母屋造桟瓦葺流れ向拝付き。
向拝・身舎とも、ところどころ朱色に塗られ、華やかなイメージの彩色ですが全体にスクエアできっちり端正なつくり。
瓦屋根の照りが強く、降り棟、隅棟、稚児棟の曲線が見事です。
向拝正面の扁額は寺号「清見寺」。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受。新上州三十三観音霊場は比較的メジャーなので、手慣れた対応です。
なお、御本尊・阿弥陀如来の御朱印は授与されていないようです。
06.龍水山 珠光院 善福寺

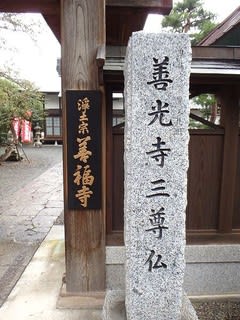




中之条町山田571
浄土宗 御本尊:善光寺式三尊仏
札所:吾妻三十三番観音霊場第15番、第16番
札所本尊:十一面観世音菩薩
朱印尊格:南無阿弥陀佛(御本尊の御朱印) 直書(筆書)
・中央に三寶印と六字御名号「南無阿弥陀佛」の揮毫。右上に御本尊、阿弥陀如来の種子「キリーク」の印判と「善光寺式三尊佛」の揮毫。
浄土宗寺院の御朱印で種子印判使用のものはめずらしくないですが、三寶印と種子印ダブル捺しのものはめずらしいと思います。
左下には寺号の揮毫と山号・寺号の印判が捺されています。
中之条市街地から沢渡方向に離れた浄土宗寺院。
慶永元年(1342年)の創建で、日本48体の善光寺如来第45番の尊像を安置したと伝えられている古刹です。現在は増上寺末となっています。
全国善光寺会の会員寺院でもあります。
全国善光寺会の会員寺院は御朱印を授与されるところが多く、また、全国善光寺会公式Webにも御朱印授与の有無が掲載されています。
善福寺については、授与の有無欄がブランクとなっていますが、快く授与いただけました。
ただ、メジャーな札所ではないのでご不在はいたしかたなしかと。わたしも2回目の参拝で拝受できました。
御本尊は、鎌倉時代中期の作と伝わる一光三尊形式の善光寺式阿弥陀如来。通常は秘仏で12年に一度午年のご開帳です。
山門横にある観音堂には、吾妻三十三番観音霊場第15番札所の法華山長岡寺(車堂)と16番札所の明星山光圓寺の観世音菩薩が遷座されて御座します。
前者は十一面観世音菩薩のようです。
山内入口に立像の地蔵尊造と六地蔵尊。「善光寺三尊仏」の石標。
山門は切妻造本瓦葺の高麗門で、梁に山号「龍水山」の扁額、柱に「善福寺」の寺号板を掲げます。
正面が本堂。入母屋造壁板張り銅板葺流れ向拝付きで庫裡と繋がっています。
本堂の斜向かいに建つ観音堂は、宝形造鉄板葺で身舎は古色を帯びています。
正面に「十五番 車堂」の堂号とご詠歌を刻した扁額で、みるからに観音霊場札所の佇まい。
向拝柱には第16番の御詠歌も掲げられていました。
御朱印は庫裡で拝受しました。
御本尊の御朱印で、観音霊場のものは現在授与されていないそうです。
07.和利宮吾妻神社






中之条町横尾1354-1
御祭神:大穴牟遲神ほか
旧社格:郷社
朱印尊格:和利宮 吾妻神社
・中央に社名印と「和利宮 吾妻神社」の揮毫。「吾妻神社」は大きく、「和利宮」は小さめに揮毫されています。
神社御朱印です。
吾妻総鎮守ともいわれ旧郷社の高い格式を有する古社ながら、旧記古文書が文化九年に焼失したため創祀ははっきりしていないようです。
由緒書によると、もともとは約300m南西の御洗水山頂上に鎮座され、現社地はその遙拝地だったが参拝が容易な現社地に奉遷されたとの由。
また、嵩山南麓の地(現、親都神社)から御洗水山頂上に遷座ののち、現社地に奉遷との伝承もみられるようです。
嵩山は吾妻地方屈指の霊山で、こちらの里宮にあたるとの説もあります。
一方、『神道集』中の「児持山之事」伝承とのつながりを指摘する説もみられます。
「児持山之事」伝承の発端は伊勢国で、その主人公のひとり加若次郎和理は「児持(吾妻)七社」(児持山大明神・半手木(破敵)大明神・鳥頭大明神・和理大明神・山代大明神・駒形大明神・白専女大明神)のうち和理大明神(和利宮?)になられたという説があります。
御洗水山頂上は現在の伊勢町伊勢宮の裏とされ、伊勢国とのつながりも連想されるところです。
さらに、嵩山を「わりのたけ」とも称し、親都神社は江戸時代「和利宮」と称していたなど、複雑な由緒来歴を有しているようです。
また、由緒書にある「本社ノ社名ハ中古以前ニアリテハ和流宮ト称シ奉レリ、蓋シ和流ハ唐流ニ対スル大和流ノ義ニシテ」という記載も気になるところです。
ふつう「吾妻」(あがつま)の地名の発祥は日本武尊(倭建命)の「吾嬬はや」に依るものとされますが、それだけでは納まらない奥の深さを感じます。
明治維新以前は和利宮ないし割宮とされていましたが、維新を契機に村社6社、無格社18社、境内末社127社、合計151社を合祀して吾妻神社となったようです。
御祭神は大穴牟遲神ほかとされています。
社頭に社号標と朱塗りの明神鳥居で「吾妻神社」の扁額が掛けられています。
参道向かって右手に神楽殿、正面に拝殿。
拝殿は入母屋造銅板葺で、大ぶりな千鳥破風をおこし、鬼板と兎毛通を置いています。
本殿は垣に囲まれよく見えないですが、流造銅板葺で四手先と思われる組物とその間に彫られた彩色彫刻が見事です。
脇障子の彫刻も精緻な仕上がり。海老虹梁や手挟の彫刻もすさまじく立体感を帯びています。
こちらの資料(くまがやねっと)によると、武州玉井村(現熊谷市)に生まれ、花輪村石原吟八に師事し、主に寛政年間(1789-1801年)~文政年間(1818-1831年)に名作を遺した小林源太郎とその父源八の手によるものとのこと。
御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れをいただきました。
08.親都神社






中之条町五反田220
御祭神:素戔嗚尊(須佐之男命)
旧社格:不詳(郷社という情報あり)
朱印尊格:親都神社 揮毫印刷?
・中央に社名印と独特な字体で「親都神社」の揮毫(印刷だと思う)があります。
そば処で有名な「道の駅たけやま」のそばにある古社で「ちかとじんじゃ」と読みます。
かつてこの地は吾妻の主城、岩櫃城の出城である嵩山城が築かれていたところで、一帯は城下町として、「親都千軒」といわれるほどの繁栄をみせたそうです。
城主は上杉方の吾妻斎藤氏でしたが、戦国期の永禄六年(1563年)に、岩櫃城が甲斐・武田方の真田・鎌原勢の攻勢を受けて落城。永禄八年(1565年)には激戦の末、嵩山城も落ち、往年の賑わいは失われたものとみられます。
この落城の戦死者を弔うため、嵩山に百観音が建立されたものと伝わります。
もともと、嵩山は古代から祖先の霊魂を祀る山とされる霊山で、天狗伝承も伝わってパワスポ的な要素には事欠きません。
親都神社の境内に由緒書は見当たらず、公的なWeb情報もほとんどとれませんが、そのわりに民間の情報は多く、しかもその内容は錯綜気味です。
複数の情報をまとめてみると、
・親都神社は霊山、嵩山自体を御神体としている。
・南北朝時代に編纂された「神道集」によると、嵩山の祭神は和理大明神。
・和理大明神は、嵩山山頂の奥社、麓の親都神社、里宮の和利宮で祭られている
・和理大明神は、『神道集』中の「児持山之事」伝承につながる「児持(吾妻)七社」のうちの一柱である。
・和利宮はもともと親都神社の場所に祀られていたが、御手洗山に遷座され、さらに現在の吾妻神社の境内地に遷座された。
・和利宮が遷座されたため、地元五反田の住民達は須佐之男命の分霊を勧請して氏神とした。
ここから推察するに、やはり複雑な由緒来歴を有しているようです。
なお、「道の駅たけやま」のWebには、「嵩山の神和利大明神として子持山の神を妻とし、鳥頭明神を子供として吾妻地方の中心的な神となっていた」と、神々の縁起を集めた『神道集』には記されています。」との表記があり、嵩山と和利(理)大明神のふかいつながりが窺われます。
参道は、駐車場(道の駅)の反対側にあります。
石段の参道で「親都神社」の社号標、明神鳥居、さらに登った正面に拝殿。
嵩山を背後に仰ぐかたちで参道、拝殿、本殿が配置されていることがわかります。
木々に囲まれて神さびた趣きの境内。摂社は少なく、シンプルに嵩山を拝している感じがします。
拝殿は入母屋造銅板葺身舎桁行三間で、ボリューム感にあふれた唐破風向拝を備えます。
水引虹梁端部に二面の木鼻彫刻。上部に斗栱。中備に蟇股。正面は桟唐戸でその上に「正一位親都大明神」の扁額。
向かって右手に切妻造平入りの建物を連結しています。
本殿は覆屋に納められ、よくわかりませんでした。
境内のケヤキの巨木は「親都神社の大ケヤキ」として県の天然記念物に指定され、御神木として信仰されています。
御朱印は書置のものを「道の駅たけやま」で拝受できます。
保管分がなくなった場合、簡単には補充できないような感じもあるので、事前に電話確認がベターかと思います。
09.熊野山 関松院 泉龍寺



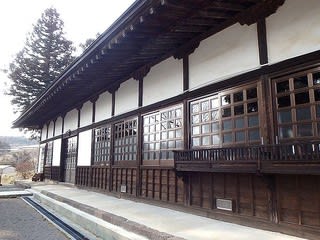

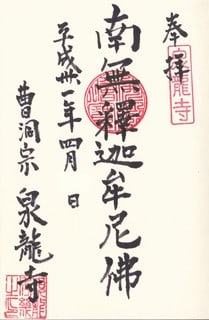
高山村大字尻高甲1939
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛(御本尊の御朱印) 直書(筆書)
・中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。
右上に「泉龍寺」の印判。右下に宗派、寺号の揮毫と寺院印の捺印があります。
禅寺の本流的な御朱印かと思います。
高山村にある曹洞宗の古刹。
境内掲示の由来記によると、大同年間に弘法大師が開かれた名刹で、慶長三年月夜野の嶽林寺五世関室傳察禅師を開山として迎えて改宗されたとあります。
徳川三代将軍家光公より二十石の御朱印を賜り、五年に一度江戸城の将軍に御年禮(の登城)をする習わしであったとのこと。
名刹らしく、杉並木に囲まれた長い参道。
石段を登って一間一戸の薬医門ないし高麗門で風格があります。
正面に本堂。入母屋造銅板葺の端正な仏堂で、向拝部が向かって左手に寄っているので、梁行の意匠はシンメトリではありません。
また、本堂裏手には源頼朝公が浅間山麓に巻狩りに出向かれた際、泉龍寺で休憩され自ら植えられたという高野槙があり、「泉龍寺の高野槙」として県の天然記念物に指定されています。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書き入れいただけました。
こちらは札所ではないですが、古刹で、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
ただし、御朱印の授与をお願いするといささか驚かれた風もあったので、御朱印を乞う参拝者は多くないかと思われます。
10.熊野山 福蔵寺 (北向観世音)



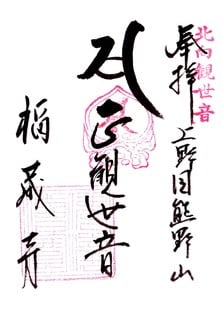
高山村尻高乙1260
天台寺門宗 御本尊:正観世音菩薩
朱印尊格:正観世音(御本尊の御朱印) 書置(筆書)
・中央に御本尊、正観世音菩薩の種子「サ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判・揮毫と「正観世音」の揮毫。
右に「北向観世音」の印判と山号の揮毫。左に寺号の揮毫と三寶印の捺印があります。
「北向観世音」として親しまれる高山村の天台修験系の寺院です。
永保元年(1081年)、修験者熊野坊による開創とされます。
新田氏支族里見義候により再興、室町時代初期、上野国平井の関東管領山内上杉氏の執事白井長尾氏の一族長尾尻高氏が祈祷寺にしたと伝わります。
長尾尻高氏は、白井長尾景春(伊玄入道重国)の子重儀が尻高左馬頭を称したことに始まるとされます。
応永十年(1403年)、重国は尻高城を築き重儀を城主に据え、重儀は尻高姓を名乗って尻高左馬頭重儀となりました。
爾来、この地は尻高氏の領地となりましたが、戦国時代に入ると山内上杉氏と甲斐から進出した武田氏の勢力がぶつかるところとなり、尻高氏も戦乱に巻き込まれていきました。
上杉方は岩櫃城の斎藤氏、武田方は小県の真田氏、三原の鎌原氏が代表格で、尻高氏は斎藤氏に属して真田・鎌原勢と対峙しました。
永禄六年(1563年)、武田方の真田・鎌原勢の攻撃により岩櫃城は落城、城主斎藤憲広は越後に逃れました。
憲広の子憲宗と弟虎城丸が支城の嵩山城に籠って再挙を図ると、尻高氏もこれに加わりました。
永禄八年(1565年)、嵩山城は真田氏の調略によって落城、尻高氏は武田方に降ったものの再び上杉方に転じたとされ、天正二年(1574年)武田方の真田幸隆は尻高城を攻めました。
尻高勢は奮戦したものの、ついに城は落ち、城主尻高景家は越後に落ちのびたとも伝わります。
一族の尻高義隆は、後年猿ケ京に籠もりましたが、武田・真田方の岩櫃城代の矢沢薩摩守に攻められて、ここに上州の尻高勢は滅亡したとされます。
北斗信仰にもとづき北方に向いて御座す「北向観世音」は、安産・子育て等にご利益ありとして参拝客を集めています。
修験の寺らしく、神変大菩薩(役行者)も御座します。また、5㎞ほど離れた「瀧の下不動尊」の護持もされているようです。
御本尊は、修験寺ではめずらしい正観世音菩薩です。
境内には朱塗りの灯籠や、地蔵尊、不動尊などが御座し、修験寺らしい雰囲気。
本堂前の一対の狛犬は、神仏混淆の歴史を物語るものか。
本堂は入母屋造本瓦葺唐破風向拝付きの豪壮な仏堂で、大棟から一気に引き降ろされる降り棟とくっきりとした掛瓦の対比が見事。
水引虹梁はシンプルですが、唐破風兎毛通の後ろに金色の龍が潜んでいます。
海老虹梁、桟唐戸、正面の扁額は「厄除観世音」です。
御朱印は庫裡にて揮毫書置きのものを拝受しました。
11.揚水山 舞台院 宗本寺





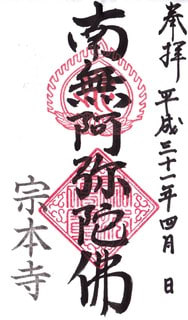
中之条町下沢渡494
浄土宗 御本尊:阿弥陀三尊
朱印尊格:南無阿弥陀佛(御本尊の御朱印) 書置(筆書)
・こちらは札所ではないので、御朱印は御本尊のもの(御名号)になります。
・中央に阿弥陀如来の種子「キリーク」の印判と三寶印の捺印。六字名号「南無阿弥陀佛」の揮毫。左下に寺号印の捺印。
06.善福寺のところで「浄土宗寺院の御朱印で種子印判使用のものはめずらしくないですが、三寶印と種子印ダブル捺しのものはめずらしいと思います。」と書きましたが、こちらもそのパターン。このエリアではこれが標準なのかもしれません。
応永元年(1394年)創建とされる浄土宗の古刹で、四万温泉、日向見薬師堂の護持をされています。
芝増上寺直末の格式を誇り、細い路地がらみのアプローチからは想像のつかない立派な伽藍を構えています。
石段参道の途中に朱い冠木門。さらに進むと寺号標でその先の石段を登り切ると本堂前です。
本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を付設し、この向拝の彫刻が出色です。
水引虹梁の端部に貘と獅子の木鼻彫刻。中備に二頭の相対する龍。兎毛通にも精緻な彫刻が施されています。
本堂の欄間彫刻(町指定重要文化財)は高瀬忠七、萩原平蔵、定運などの名工によるもので、この向拝の彫刻もこれら名工の手によるものかもしれません。
格天井には鳥の画、正面に寺号「宗本寺」の扁額。
本堂向かって左手の開山堂はおそらく入母屋造妻入り、軒下二軒繁垂木の均整のとれたつくりです。
御朱印は庫裡で拝受。ご住職はお出かけでしたが、寺庭さんから書置の御朱印をいただけました。
なお、こちらでは日向見薬師堂の御朱印も授与されています。
12.日向見薬師堂






中之条町四万4371
宗派不詳(現在、浄土宗寺院が護持) 御本尊:薬師如来
四万川に沿って南北に長い四万温泉の最奥の湯場、日向見にある薬師堂です。
古来、数多の湯治客から「湯前薬師」として尊崇を集めた薬師如来が御座します。
『四万の病を癒す霊泉』、四万温泉にふさわしい尊格といえましょう。
四万温泉の開湯伝承に碓氷貞光説があります。
永延三年(989年)頃、源頼光の家臣、碓氷貞光が越後から四万奥の木の根峠を越えて日向見に至った際、心を静め夜通し読経していると一人の童子があらわれ、「あなたの読経の真心に感心し四万の病気を治す温泉を与えよう、われはこの山神である」旨を告げられた。
気がつくと傍らには効能あらたかな温泉が湧き出でていたが、これが「日向見御夢想の湯」で、これを奇瑞として建立されたのが日向見薬師堂とされます。
いまの薬師堂は慶長三年(1598年)、時の領主、真田信幸の武運長久を願って建てられたといわれ、現存する県内最古の寺院建築とされる国の重要文化財です。
お堂前にある標柱に「国宝 日向見薬師堂」とあるのは、戦前、本堂が国宝に指定されていた名残です。
手前にあるのは「お籠堂」(町指定文化財)で、お薬師様の信者が病気平癒を願って参籠したお堂です。
寄棟造茅葺、外壁は真壁造り板張りで、中央を本堂への参道が貫く構造となっています。
その先が現存する県最古(慶長三年(1867年)、桃山時代)の御堂建築とされる本堂です。
桁行・梁間ともに三間、寄棟造茅葺、外壁真壁造り板張り。向拝柱のない四方浜縁です。
軒下は二軒の平行垂木、正面には「薬師堂」の扁額が掲げられています。
境内には、摩耶姫伝説に由縁し、縁結び、子宝に霊験のある「摩耶不動」も御座します。
(→四万温泉公認キャラクター「摩耶姫ちゃん」)
日向見薬師堂の宗派は不詳ですが、現在は中之条町下沢渡の浄土宗寺院、揚水山 宗本寺の管理下にあるようです。
御朱印は、書置タイプのものが参道手前の喫茶「あづまや」で拝受できます。
2016年2月拝受時は印判、2017年6月拝受時は揮毫のものでした。最近、ハンコから墨書きのものに変更されたそうです。
拝受者から「墨書き揮毫御朱印」のオファーがあったのでしょうか? たしかに女性客の多い四万温泉では御朱印ニーズが高そうです。
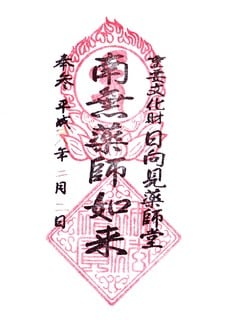

【写真 上(左)】 日向見薬師堂の御朱印(旧)
【写真 下(右)】 日向見薬師堂の御朱印(新)
【印判御朱印(以前授与)】
中央に御本尊、薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と三寶印。「南無薬師如来」の印判。
右に「重要文化財 日向見薬師堂」の寺号。左下に寺号関係の揮毫印判がなく、寺院御朱印としてはめずらしい様式です。
【印判御朱印(現在授与)】
中央に御本尊、薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と三寶印。「薬師如来」の揮毫。
こちらは右下に寺号の印判、左上に「奉拝」の揮毫も入って、寺院御朱印として標準的な様式です。(種子印・三寶印のダブル捺しと寺院印なしは、ややイレギュラーですが・・・)
2019年4月の花祭りに参拝しました。
なんと思いがけず御開帳されていて御尊像を直に拝めました。
せっかくの御開帳なのでお堂の軒におられたお坊様に御朱印を乞うと、「今日は花祭りなので特別な御朱印」との由。
わたしは限定御朱印にはほとんど興味がないのですが、御開帳となると話は別で有り難く拝受しました。書置御朱印です。
【花祭りの限定御朱印】

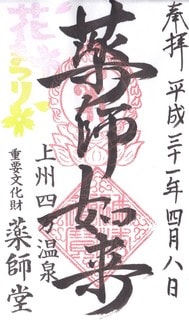
中央に御本尊、薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の印判と三寶印。「薬師如来」の揮毫。
通常御朱印とのちがいは左上に「花まつり」のカラー印判があるかないかだけですが、「薬師如来」の揮毫に筆致の冴えが感じられます。
13.青麻山 薬王寺






中之条町四万4372-1
法華宗
御首題 書置(筆書)
・御首題は揮毫書置きタイプで、お題目のほか、所縁の尊格が揮毫されています。
流麗な筆致で見応えがあります。
日向見の高級宿「つるや」の山手にある法華宗の寺院。
新宿・左門町の陽雲寺のご住職が四万・日向見で療養されて完治を得、この日向見の地に薬王寺を建立されたそうです。
「つるや」はこの薬王寺の宿坊として誕生したとのことで、いまでも密接な関係があるようです。(つるやの「鶴」は法華宗の宗紋「鶴」に由来するとの由。)
日向見薬師堂に向かう道の手前右手に石段の参道。参道手前に御題目と寺号が刻まれた石標があります。
石段を登り切ると山門。これを抜けるとさらに数段の石段があってその先に本堂。
撮影した写真の構図が悪くいまいちよくわかりませんが、入母屋妻入りのお堂に唐破風の向拝を付設したような構造では。
海老虹梁に挟まれた身舎拝み部に「薬王大菩薩」「青麻大権現」の扁額を配した奉納額が掛けられています。
御首題(法華宗なので御首題となります)は、つるやの帳場で拝受できます。
境内には霊水「薬王水(御法水)」が湧いています。
なお、日向見のお宿「つるや」では「日向見ご利益巡り」と称して、薬王寺、日向見薬師堂、摩耶不動の3ヶ所を紹介しています。
なお、中之条町四万には吾妻三十三番観音霊場第21番の法平山 萬福寺(札所本尊:正観世音菩薩)があるはずですが、Webではまったく情報がとれませんでした。
今度現地で当たってみたいと思います。


宿泊は自家源泉*の「渓声の宿 いずみや」にとりました。
いかにも四万らしい滋味のあるお湯をかけ流しで、食事や接客のレベルもなかなかでした。
これで、現時点で入浴可能な四万の源泉はおそらくすべてクリアしたかと思います。(自家源泉を持ち日帰り不可の「竹葉館」が難物でしたが、お宿へのヒアリングによると現在は「四萬館の湯」を使っているそうで、こちらもクリアかと。)
源泉マニア的にはクリア。それでも、これを書きながらまたぞろ行きたくなっている四万温泉。やはりすばらしい湯場だと思います。
*)使用源泉は、「泉屋の湯」。
2019年4月は「四万グランドホテル」に泊まりました。
じつは、ここのバイキングはレベルが高く、しかも湯巡りパスポ(税込540円)を買うと四万たむらの風呂にも入れるので、もう5回ほども泊まっています。
じつは、ここの7階のメルヘン風呂は展望浴場ながらすこぶるお湯がよく、さりげに気に入っていますが、これについては稿を改めます。
(つうか、四万の共同浴場や旅館はほとんど制覇しているのですが、これをみると、レポComing Soon!多すぎ! おいおい温泉レポを再開し、フォローしたいと思います。(ここ数年、こればっかしじゃが・・・(笑))
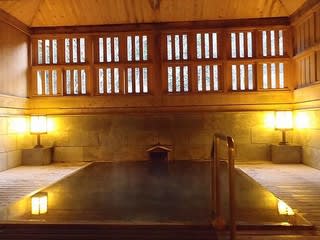

【写真 上(左)】 四万たむらの「御夢想の湯」
【写真 下(右)】 四万たむらの「森のこだま」
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
2020/11/26・2020/09/18 UP
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
また、現在リニューアル中で、構成が錯綜しています。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
信玄公ゆかりの寺社
Vol.1~5でご紹介した以外の、信玄公ゆかりの寺社をご紹介します。
■【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
まずは、Vol.5でご紹介した「信玄公の戦勝祈願依頼文」の祈願先11箇寺のうち、不動明王と毘沙門天以外を御本尊とする寺院をご紹介します。
■ 金剛山 慈眼寺





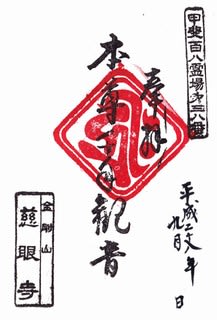
笛吹市資料
笛吹市一宮町末木336
真言宗智山派 御本尊:千手観世音菩薩
札所:甲斐百八霊場第38番、甲斐八十八ヶ所霊場第17番
朱印尊格:本尊 千手観音 印判
札番:甲斐百八霊場第38番印判
・中央に御本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印と中央に「本尊 千手観音」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第三八番」の札所印。左下には山号・寺号の印判が捺されています。
慈眼寺の開山は明確でなく、文明年間(1469年~1486年)に宥日によって中興されたと伝わります。
明治年間に醍醐報恩院末から真言宗智山派智積院に替わっているようです。(資料A)
寺伝には、「武田氏の祈願所として発展し、七堂伽藍があったが、天正十年(1582年)、織田信長勢により焼失」とあるようです。
本堂左手の光明真言の碑は特異なものらしく、真言宗の名刹としての歴史を感じさせます。
信玄公の信仰篤く、信玄公が川中島の戦いに携行された毘沙門天が残されています。(資料A)
当寺には、信玄公の薬師如来への信仰を物語る縁起が伝わります。
慈眼寺の薬師如来縁起(信玄公護身旗の梵字真言に就いて/白石真道氏)
ながくなりますが貴重な文献なので、引用させていただきます。
「甲斐國八代郡自然出現薬師瑠璃光如来縁起夫出現薬師如来といつハ往昔文治年中(1185-1160A.D.)宥日上人と云者菩提の嘉苗を植て六十余州を巡礼する時甲州八代の郡両木八幡宮に通夜す。夢中に神龍現て宥日上人に告て誼く『爰に大石あり。其中に薬師瑠璃光如来います。是を以て汝に附属す』といひ訖て夢覚ぬ。上人希有の想をなし、看に大石あり。『定て此石中に在ん。云何してかこれを得ん』と思議する時、此大石自両に分て佛像忽顕現す。光明十方を照し、異香四方に薫じ、魔宮震動して天花雨の降が如し。上人魂を失ふの信を生じ、皮を剥の誠を致して恭敬供養し、礼拝懺悔す。(略)建久五年(1194A.D.)、武田太郎信義改て堂を建て奥院と号し、如来を安置し奉て国家の繁栄を誓ふ。」
「其後永禄十三年(1570A.D.)武田信玄公川中島に於て越後の兼信と相戦う時、身方 軍兵己に敗績せんとす。是故に玄公智謀尽て佛力を頼み、法印宥空を招き、薬師の法を修せしむ。嗟呼尊哉奇哉八万の夜叉、軍兵の心中に入て猛虎の勢を生じ、十二神将大将の前後を囲で飛龍の駕に似たり。敵陣これを見て忽懼震戦き、旗を捨て逃走り、弦を絶て平降す。是則薬師如来十二神将八万夜叉等の擁護する所以なり。」
「これに依て信玄公、 如来の威光を尊び、 夜叉の冥護を仰ぎ、更に十四問四面の金堂を建て如来を尊重し給て、五百石の福田を附除して供養料とす。しかのみならず、軍中著 用の錦七条の袈裟、且つ具足箱、毘沙門の像等数多宥空法印に施与す。其後、元亀二年(1571A.D.)国中一派の僧侶を集め、 薬師如来の秘法を修せしめて、国泰民安、武運長久を祈る。」
十二神将は薬師如来を守護する神将で、各神将がそれぞれ七千、計八万四千の眷属夜叉を率いるとされています。
↑の縁起からすると、薬師如来の御利益とともに、十二神将の守護も祈願していたものとみられます。
一間一戸入母屋造の流麗な鐘楼門は国の指定重要文化財。
大寺であったことを伝える広い山内に入母屋造茅葺のどっしりとした本堂と庫裡は、地方寺院の伽藍構成をよく伝える例として国の重要文化財に指定されています。
星曼荼羅・梵字法帖などの貴重な寺宝や、信玄公の戦勝祈願依頼文などが遺されています。
戦勝祈願依頼文は、「信州長沼馬上の廻文」ともいわれ、信州長沼の地で信玄公が馬上でしたためたものと伝わります。
甲斐百八霊場第38番の札所で、快く御朱印を授与いただきました。
■ 高橋山 放光寺


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
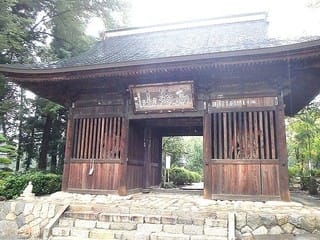

【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 大黒天
【写真 下(右)】 弁財天


【写真 上(左)】 本堂前の門
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂と庫裡(客殿)


【写真 上(左)】 庫裡玄関
【写真 下(右)】 愛染明王堂
公式Web
甲州市藤木2438
真言宗智山派 御本尊:金剛界大日如来
札所:甲斐百八霊場第8番、甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)
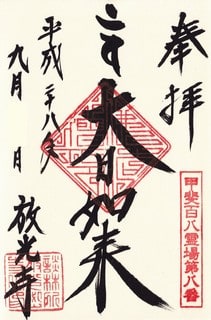
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:大日如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第8番
・中央に三寶印と金剛界大日如来の種子「バン」の種子と「大日如来」の揮毫。
右下に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
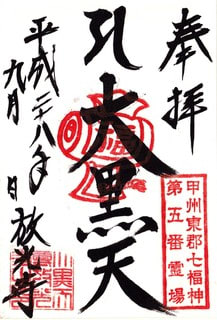
〔甲州東郡七福神(大黒天)の御朱印〕
朱印尊格:大黒天 書置(筆書)
札番:甲州東郡七福神第5番
・中央に札所本尊大黒天の持物「打ち出の小槌」の印判と「大黒天」の種子「マ」と「大黒天」の揮毫。
右下に「甲州東郡七福神第五番霊場」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
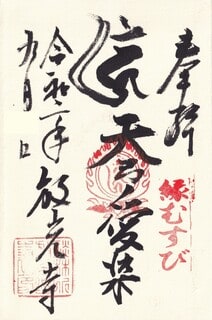
〔天弓愛染明王の御朱印〕
朱印尊格:大黒天 書置(筆書)
札番:甲州東郡七福神第5番
・中央上に愛染明王の種子「ウン」の揮毫。「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「天弓愛染」の揮毫。右に「縁むすび」の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
愛染明王の御朱印は、山梨ではめずらしいものです。
放光寺は元暦元年(1184年)源平合戦で大きな功績をあげた安田義定公が「一ノ谷の戦い」の戦勝を記念して創立したと伝わる、甲斐を代表する名刹です。
寺伝には、「塩山の北方大菩薩の山麓、高橋荘(現在の一ノ瀬高橋)にあった法光山高橋寺を安田氏の館(山梨市小原)に近い牧荘(塩山市藤木)に移し高橋山多聞院法光寺と改め天台宗寺院として大規模に伽藍を建立し安田一門の菩提寺としました。南北朝期になって真言宗に改宗されました。のちに真言宗七談林にも加えられ真言宗の教えを広める根本道場になりました」とあります。(放光寺資料)
すこしく話が逸れますが、義定公は甲斐源氏の興亡において大きな役割を担った武将なので、事跡について簡単にまとめてみます。
義定公は、甲斐源氏の祖とされる源義光(新羅三郎)公の孫源清光公の子(清光の父義清の子説もあり)という名流で、現在の山梨市を中心とした峡東一帯に勢力を張りました。
平家追討の令旨に応じて挙兵し、「富士川の戦い」などでの戦功により遠江国守護に任じられました。(『吾妻鏡』)
寿永二年(1183年)、義定公も平家追討使として東海道から上洛。大内裏守護として京中を守護し、同年8月には従五位下遠江守に叙任しました。
「宇治川の戦い」、「一ノ谷の戦い」と歴戦。とくに「一ノ谷の戦い」では、義経の搦め手軍を率いて奮戦、平経正、平師盛、平教経を討ち取ったと伝わります。
建久二年(1191年)の鶴岡八幡宮法会では、頼朝公御供の筆頭に義定の名がみられ、頼朝公配下のなかでも高い地位を占めていたことがわかります。
建久四年(1193年)、義定公の子、安田義資が罪を得て斬られ、義定公の所領も没収。
翌建久五年(1194年)には義定公みずからが謀反の疑いをうけ、放光寺にて自刃されたと伝わります。
この当時の甲斐源氏には、武田信義、安田義定、一条忠頼らの有力武将がおり、「富士川の戦い」の主力は甲斐源氏であったとみられています。
しかし、義定公は謀反の疑いで自刃、一条忠頼も鎌倉にて酒宴の最中に暗殺、武田信義公の子逸見有義は頼朝公から疎まれ、同じく信義公の子板垣兼信は違勅の罪を問われて配流されるなど、次々と失脚していきました。
当時の甲斐源氏は頼朝公も御せないほどの勢力があり、武士の頭領としての地位を確立するために、頼朝公が甲斐源氏の力を削いでいったという見方が有力です。
以降、甲斐源氏では、武田氏宗家となった信光公の流れと信義公の弟加賀美遠光公から小笠原氏、南部氏が出て、以降勢力をはりました。
小笠原氏、南部氏は江戸時代も大名家として存続しています。(大和郡山藩の柳沢氏、新発田藩主の溝口氏、松前藩主の松前(蠣崎)氏なども甲斐源氏の末裔を称しています。)
義定公は文化に造詣が深く、多くの仏像を勧請され、いまも「木像大日如来」「木像不動明王」など名作とされる仏像が放光寺に残されています。
「天弓愛染明王」は日本最古の天弓愛染明王としてとみに有名です。
また、開基堂に御座す毘沙門天は、義定公ゆかりのお像と伝わります。
信玄公との関係についても寺伝があります。
「武田信玄の時代には、武田家の祈願所となっております。元亀三年三方原の戦いのおり、武田氏は遠州鎌田山医王寺に伝わった大般若経六百巻(南北朝時代の写経)を甲州に移し、当山に奉納しております。」((放光寺資料)
永禄十一年の「信玄公の戦勝祈願依頼文」には「法光寺」とありますが、これは当寺のことかと思われます。
天正十年(1582年)、織田勢の甲州攻めの兵火にかかり堂塔伽藍は焼失しましたが、その後、慶長年間(1599年~1614年)、寛文年間(1661年~1662年)に堂宇が再建されて現存します。
山内はさほど広くはないですが、梅の木が多く、名刹らしい落ちつきがあります。
山門は、駐車場から寺を背に参道を下っていったところにあるので、気づきにくいです。
すこぶる個性的な意匠で、脚数すらわかりませんでした。
扁額もめずらしい梵字のものです。
「高橋山」の扁額が掲げられた仁王門は、入母屋銅板葺桁行三間一戸の単層門、左右に金剛力士像が安置されています。
参道右手に甲州東郡七福神の大黒天と鐘楼、右手の放生池、太鼓橋のさきに弁財天が祀られています。
大黒天は大岩に刻まれた露仏とお堂のなかにも御座します。
公式Webによると、大岩の露仏は、当山鎮守開運大黒天の奥の院本尊で、もともとは北方鍜冶屋橋のたもと笛吹川の東岸に祀られていましたが、橋の改修工事に伴い移座されたようです。
毎年4月29日の大黒天会式では柴燈護摩火渡修行が催され、賑わいをみせるそうです。
本堂前の門も本瓦葺の堂々たるもの。
門をくぐると、桁行九間入母屋銅板葺の本堂と豪壮な庫裏の唐破風が力強い対比をみせています。
有名な「天弓愛染明王」は本堂左手おくのお堂に御座し、間近で拝むことができます。
拝観は有料ですが、仏像群がすばらしくご説明もいただけるので拝観をおすすめします。
拝観前に御朱印帳をお預けすれば、拝観後に揮毫の御朱印を拝受できます。(大黒天は原則書置のようです。)
【 善光寺 】
■ 定額山 浄智院 善光寺(甲斐善光寺/甲州善光寺)
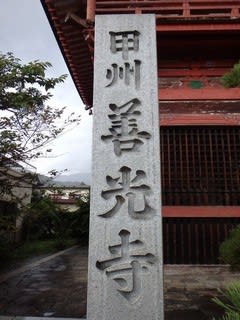



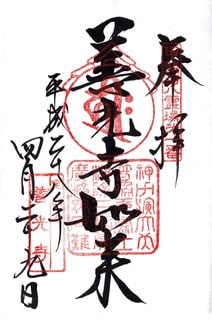

公式Web
甲府市善光寺3-36-1
浄土宗 御本尊:善光寺如来
札所:甲斐百八霊場第1番、甲斐八十八ヶ所霊場第67番、府内観音札所第7番
朱印尊格:善光寺如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第1番印判
信玄公の戦のなかでもとくに名高いのが、信州・川中島周辺で上杉謙信公(長尾景虎)との間で数次にわたり展開された”川中島の戦い”です。
信玄公は第三次の戦いの後の永禄元年(1558年)、善光寺が兵火にかかるのを恐れて、ご本尊の一光三尊阿弥陀如来(善光寺如来)と数々の寺宝を甲府に移し、信濃善光寺の三七世住職・鏡空上人を開基として堂塔を建立されました。
江戸時代には、本坊三院十五庵を有する大寺院として浄土宗甲州触頭を勤め、徳川家位牌所でもあり、現在に至るまで甲府を代表する仏閣として広く参詣客を集めています。
〔境内由来書より(抜粋)〕
「定額山浄智院善光寺は、武田信玄公が 永禄年中 川中島の合戦の折 信濃善光寺が兵火にかかるのを恐れ 本尊阿弥陀如来その他 諸仏 寺宝 大梵鐘に至るまでことごとく甲斐に招来し 大本願第三十七世鏡空上人を開山に迎え 信濃善光寺開基本田善光公追慕の地 ここ板垣の郷に新たに建立せられたものである」
現在の御本尊は、かつての善光寺の本尊の御前立像とされ、秘仏でしたが平成9年からは7年毎に御開帳されています。
公式Webでは現在の御本尊について「当山の御本尊は、建久六年(1195)尾張の僧定尊が、秘仏である信濃善光寺の前立仏として造立したものです。定尊は、如来の夢の告げを得て勧進に行脚し、四万八千余人もの寄進を得たといわれます。
本像は、いわゆる一光三尊式善光寺如来像の中では、在銘最古、かつ例外的に大きな等身像として著名です。」と解説されています。
甲斐善光寺でも「お戒壇廻り」を体験することができます。(有料)
まずは、スケールの大きな山門に圧倒されます。
稀少な五間三戸の楼門で入母屋造銅板葺。外周の擬宝珠高欄が装飾性を高めています。
参道正面に威風を放つ本堂。
金堂とも呼ばれ、屋根の形が東西棟と南北棟でT字(撞木形)を形成する構造(撞木造)で、善光寺特有の様式とされます。
桁行じつに十一間。向拝三間。撞木造で奥行きがあり梁間も七間となっています。
一層唐破風、二層千鳥破風のように見えますが、実は仏殿ではけっこうめずらしい妻入りで、東日本では最大級の木造建築物とされています。
各種の組物、蟇股、木鼻彫刻、連子窓、三花懸魚などを配し、朱塗りの色調と相まってスケール感と装飾性を兼ね備えたつくりとなっています。
ともに宝暦四年(1754年)に焼失し、現在の山門は明和四年(1767年)、本堂は天明五年(1785年)の再建上棟と伝わります。

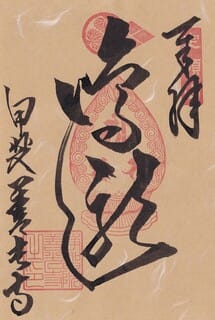
【写真 上(左)】 鳴き龍(授与所でいただいた絵ハガキより)
【写真 下(右)】 鳴き龍の御朱印
御朱印は本堂内の授与所で拝受できます。
見本が出ているのは「善光寺如来」の御朱印だけですが、金堂中陣天井の「鳴き龍」の御朱印も授与されており、申告すると奥から書置の御朱印をお出しいただけます。
オリジナル御朱印帳も頒布されています。
山梨県内では稀少な浄土宗寺院のオリジナル御朱印帳で、寺紋である丸に立葵と武田菱が表裏に配された渋いデザインですが、縦16cm×横11cmの小サイズがいささか残念です。
■ 塩山 向嶽寺
臨黄ネット





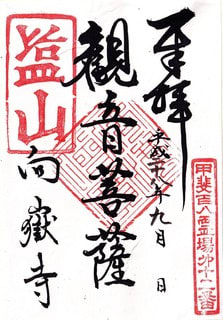
甲州市上於曽2026
臨済宗向嶽寺派本山 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第12番、甲斐八十八ヶ所霊場第74番
朱印尊格:観音菩薩 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第12番印判
・中央に三寶印と札所本尊「観音菩薩」の揮毫。
右下に「甲斐百八霊場第十二番」の札所印。左上に「𥂁山」山号印と寺号の揮毫があります。御本尊は釈迦牟尼佛ですが、札所本尊は観音菩薩となっているようです。
臨済宗向嶽寺派本山の格式を有する名刹で、開山は抜隊得勝(ばっすいとくしょう)禅師〔慧光大円禅師〕です。
各地を遍され、永和四年(1378年)高森(塩山市竹森)の険しい地に庵居された禅師のもとを訪れる僧俗は引きも切らず、武田信成公は塩山の地を寄進し庵を建て、禅師を迎え入れて向嶽庵と称しました。
禅師はこの庵で僧俗の教化に努められ入寂されました。
以降も武田家歴代の帰依を受け、天文十六年(1547年)6月、信玄公は朝廷へ働きかけ、抜隊禅師に「慧光大円禅師」の諡号を賜り、向嶽寺の寺号を定めたとされます。
境内掲示の沿革に「明治五年(1782年)に輪番住職制を改め独住制となり、京都南禅寺の所轄となったが、同四一年管長を置いて名実ともに別派独立の大本山となった。」とあるので、臨済宗のなかで一派をなしたのは明治になってからとみられますが、南禅寺からの別派独立ですから、寺格はすこぶる高いものと思われます。
向嶽寺は、甲府盆地の東北部にこんもりと突き出た小高い山の南麓に抱かれるようにたたずんでいます。
山号の「塩山」は「塩の山(志ほの山)」とも呼ばれ、この北側の山です。
山梨市の笛吹川沿いにある「差出の磯(さしでの磯)」とともに、古くから和歌に詠まれた景勝地です。
「志ほの山」は「さしでの磯」の枕詞で、さらに千鳥や八千代にかかっていくことが多いようです。
- 志ほの山 さしでの磯に すむ千鳥 君が御代をば 八千代とぞなく -
(古今和歌集)
国宝の「絹本著色達磨図」は「八方にらみの達磨」「朱達磨」とも呼ばれ、わが国の達磨図の最高傑作として知られています。(現在は東京国立博物館に寄託)
室町時代建造の中門(総門)や漆喰製瓦屋根の「塩築地」など、貴重な建築物が残っています。
修復なった池泉式庭園も国の名勝に指定されています。
臨済禅の名刹らしく、整った山内には凜とした空気がただよいます。
敷居が高い感じですが、甲斐百八霊場の札所であり、御朱印は快く授与いただけました。
■ 妙亀山 広厳院
公式Web





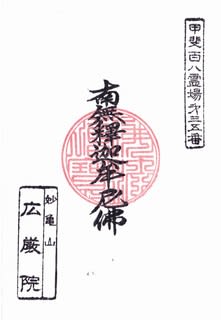
笛吹市一宮町金沢227-1
曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩
札所:甲斐百八霊場第35番、甲斐八十八ヶ所霊場第16番
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛 印判
札番:甲斐百八霊場第35番印判
・中央に三寶印と御本尊「南無釋迦牟尼佛」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第三五番」の札所印。左下に山号・寺号の印が捺されています。
御本尊は聖観世音菩薩ですが、朱印尊格は釈迦牟尼佛となっています。禅宗寺院の御朱印では、御本尊ではなく、宗派本尊の「南無釈迦牟尼佛」で授与される例がときどきみられます。
小田原最乗寺十四世の雲岫宗竜大和尚を開祖、塩田長者降矢対馬守を開基とし、寛正元年(1460年)に開山の曹洞宗の名刹。
甲斐四群(山梨、八代、都留、巨摩)の中央に位置するため、「中山」とも称されます。
寺伝によると、甲斐国守護武田信昌公が文明十九年(1487年)に寺領を寄進して以来、信縄公、信虎公、信玄公、勝頼公と武田家五代の庇護を受けたとされます。
信玄公は、弘治二年(1556年)に祖母崇昌院殿(信縄公妻)の菩提を弔うため寺領十貫文を寄進され、崇昌院殿を開基に準じたと伝わります。
信玄公と曹洞宗のつながりを示す寺院です。
甲府の大泉寺とともに甲斐曹洞宗の大元としての格式があり、県内八百三十寺の末寺を総括、最盛期には八十人の僧を擁する大寺であったと伝わります。
端正な鐘楼、質素な本堂、吊り下がる魚板など、禅寺らしい趣にあふれています。
御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。
■ 調御山 佛陀寺





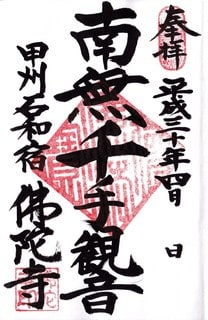
笛吹市石和町市部864
臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩
札所:石和温泉郷七福神(福禄寿)
朱印尊格:南無千手観音 直書(筆書)
・中央に三寶印と御本尊「南無千手観音」の揮毫。
右上に不明な印。左に「甲州石和宿 佛陀寺」の揮毫と寺院印が捺されています。
※石和温泉郷七福神(福禄寿)の御朱印も授与されています。
文永六年(1269年)、わが国の普化宗の開祖法燈円明国師が、亀山天皇の勅令によって建立された禅寺。
天文年間(1540年代)、信玄公が恵林寺から歓堂宗活禅師を請じて臨済宗妙心寺派に改め、寺運はとみに栄えたと伝わります。(境内掲出の寺伝より)
御本尊千手観世音菩薩は行基の作、「調御山」の山号扁額は亀山天皇の御宸筆であると伝えられています。
境内には、幕末の侠客、竹居の安五郎こと吃安の墓があります。
普化宗は禅宗の一派で、建長六年(1249年)南宋に渡った心地覚心が、中国普化宗16代目張参の4人の弟子を伴い帰国して伝来しました。
江戸時代には虚無僧の宗派として位置づけられ、幕府とも結びついたとされますが、明治に入り政府により解体され廃宗となったとされます。(戦後再興。尺八(虚鐸)文化の源流ともみなされている。)
信玄公の臨済宗妙心寺派や恵林寺への帰依を物語る寺院です。
こじんまりとした寺院ですが、石和温泉郷七福神(福禄寿)の札所を務められており、快く御朱印を授与いただけました。
■ 岩泉山 寂静院 光福寺
浄土宗寺院紹介Navi




甲府市横根町1110
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第2番、甲斐国三十三番観音札所第21番、第22番
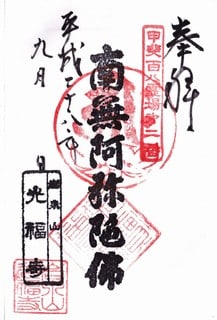
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:南無阿弥陀佛 印判
札番:甲斐百八霊場第2番印判
・中央に御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座)と三寶印と「南無阿弥陀佛」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第二番」の札所印。左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
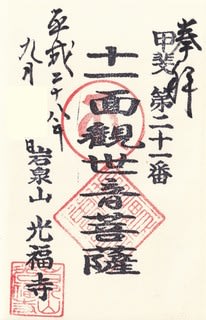
〔甲斐国三十三番観音札所(第21番)の御朱印〕
朱印尊格:十一面観世音菩薩 印判
札番:甲斐国三十三番観音札所第21番
・中央に札所本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印と三寶印と「十一面観世音菩薩」の印判。
右に「甲斐 第二十一番」の札所印。左には山号・寺号の印と寺院印が捺されています。

〔甲斐国三十三番観音札所(第22番)の御朱印〕
朱印尊格:聖観世音菩薩 印判
札番:甲斐国三十三番観音札所第22番
・中央に札所本尊聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印と三寶印と「聖観世音菩薩」の印判。
右に「甲斐 第二十二番」の札所印。左には山号・寺号の印と寺院印が捺されています。
甲斐源氏の祖、新羅三郎義光公が「後三年の役」で奥州で戦死した人々を弔うため、嘉保二年(1095年)、空源法印を開山として建立された寺院で、当初は寂静院ないし横根寺と称しました。
天文十六年(1547年)、信玄公が権少僧都円全を中興開山として再興されました。
慶長十年(1605年)、鎌倉から萬誉助往和尚を迎えて翌十一年知恩院直末に編入、寺号を光福寺と改め浄土宗に改宗しています。
甲斐百八霊場の札所であり、山内2つの観音堂は甲斐国三十三番観音札所に定められています。
■ 護国山 国分寺





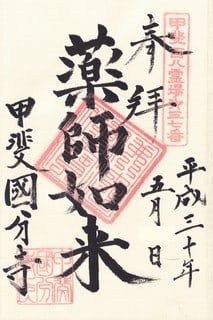
笛吹市一宮町国分197-1
臨済宗妙心寺派 御本尊:薬師如来・阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第37番、甲斐八十八ヶ所霊場第17番
朱印尊格:薬師如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第37番印判
・中央に三寶印と札所本尊「薬師如来」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第三七番」の札所印。左に甲斐國分寺の揮毫と寺院印が捺されています。
笛吹市一宮周辺は、甲斐の国でも早くから拓けた一帯とされており、国分寺も聖武天皇の御代(701年~756年)にこの地に建立されました。
例にもれず甲斐の国分寺も戦国時代までには荒廃してしまいましたが、信玄公が寺領を寄進し復興を手掛けられ、勝頼公の時代に臨済宗に改宗されたと伝わります。
当寺は旧国分寺跡地上にありましたが、旧国分寺跡が国の史跡に指定されたため、現在地にしています。
奈良時代の作と伝わる薬師如来像は、33年に一度の御開帳です。
■ 柏尾山 大善寺
※ 現在、整理中です。
■ 龍湖山 方外院




公式Web
身延町瀬戸135
曹洞宗 御本尊:如意輪観世音菩薩
札所:甲斐百八霊場第98番、甲斐国三十三番観音札所第27番
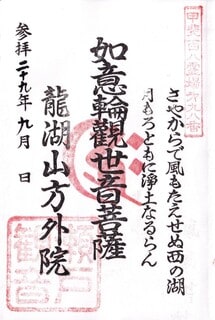
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:如意輪観世音菩薩 印判
札番:甲斐百八霊場第98番
・中央に札所本尊如意輪観世音菩薩の種子「キリク」の御寶印と「如意輪観世音菩薩」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第九八番」の札所印と御詠歌の印。左下には山号・院号の印判と寺院印が捺されています。
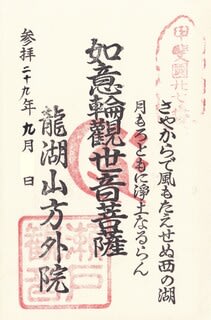
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
朱印尊格:如意輪観世音菩薩 印判
札番:甲斐国三十三番観音札所第27番
・中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリク」の御寶印と「如意輪観世音菩薩」の印判。
右上に「甲斐國廿七番」の札所印と御詠歌の印。左下には山号・院号の印判と寺院印が捺されています。
信玄公と観世音菩薩のゆかりを示す伝承は多くはありませんが、身延の方外院には御本尊如意輪観世音菩薩と信玄公の逸話が伝わっています。
方外院は貞治元年(1362年)、現・身延町の名刹で、南明寺の三世・梅林禅芳禅師によって本栖湖の湖畔に開創されました。山号「龍湖山」は本栖湖に由来するものです。
信玄公の治世、方外院は本栖湖畔(本栖村赤坂)にありました。
信玄公が三河に向けて軍勢を進める途中、寺のそばを通ると雷雨が激しくなり軍を進めることができなくなりました。
淡い火影を見つけてたどり着いたお堂には、微笑みをたたえた如意輪観音菩薩が御座されていました。
信玄公が観音様に祈願するとたちまち雷雨は収まり、軍は無事に三河へ向かうことができました。
信玄公はこの仏恩に謝するため、本栖の地頭・渡辺囚獄に命じてこの観音様を手厚く保護させました。
武田家滅亡の混乱のなか、この観音様も所在を転々とされましたが、慶長二年(1597年)下部・瀬戸の住民が観音様をお迎えしました。
子授けの霊験あらたかで「瀬戸の観音さま」として崇められ、甲斐三十三観音霊場の札所でもあったことから、多くの参拝者を集めます。
行基菩薩の御作とも伝わるこの観音様は、寄せ木法の技法や納衣の曲線などから、平安末期の作(南北朝との説もあり)とみられています。
秘仏ですが、毎年3月18日の御縁日には御開帳されます。
また、身延町資料身延の民話には「方外院本尊の如意輪観世音像は行基の作で、人肌と同じ体温があるという。仏門に入った武田信玄が寺に参詣しその話を聞き、須弥壇に上がって厨子の扉に手をかけようとした瞬間壇下へ投げ落された。信玄は額づいて無礼を詫び、武田菱の使用を許可し御朱印地七石を賜った。(下部町誌)」との逸話があります。
常葉川(本栖みち)沿いの古関集落から、常葉川支流の反木川を少し遡った山ぶかいところにあります。
寺号標には「龍湖山方外院瀬戸観音寺」とあり、 甲斐百八霊場、甲斐国観音霊場の札番が刻まれています。
四脚単層銅板葺で大棟に武田菱三連を置いた山門。すぐおくには三間一戸八脚の楼門で、こちらは大棟に「龍湖山」の山号を置いています。
楼門右横には立派な鐘楼が置かれ、本堂に至る前から豪壮な伽藍配置です。
向拝のない簡素な本堂ですが、山号扁額には青龍を配して存在感を放っています。
正面硝子戸には武田菱、壁面には「一見観音衆罪即滅」というありがたいお言葉が掲げられています。
硝子戸を開くと新たな展開が・・・。
堂内じたいは禅宗様の飾り気のすくないつくりですが、いくつか掲げられた派手やかな「瀬戸観音」の奉納提灯と、なにより正面上部に掲げられた絵馬が強く目を惹きます。
禅寺で観音霊場を兼ねる場合、御本尊は釈迦牟尼佛で別に観音堂があって、観音霊場の札所本尊はそちらに御座し、本堂はシックで観音堂は華やかな例が多いです。
しかし、こちらは御本尊が観音様で札所本尊も兼ねられるため、このような本堂と観音堂が混在するような雰囲気になっているのかと思います。
絵馬は著名なものです。
横19.42メートル、縦2.24メートルにも及ぶ大額で、「方外院千匹馬の大額」と称され、町の有形文化財に指定されています。
総桐材造の額に馬千匹が描かれ、前方の馬には着色が施されて華麗な印象な額です。
安政の飢饉の折、御本尊の信仰篤い老翁に「馬の霊が飢えて稲を食する故、各地より一人一匹の馬を奉納せよ」との霊夢がくだり、馬の奉納にかえて馬の大額を奉納したところ、翌年より豊作となったと伝わります。
絵馬は茨城県出身の渡辺天麗の作で、額に記された奉納者は甲府在住の者までに及び、広範囲に信仰を集めていたことがわかります。
■ 海雲山 寿徳寺


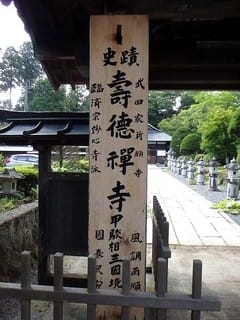



山中湖村平野147
臨済宗妙心寺派 御本尊:地蔵菩薩
札所:郡内三十三番観音霊場第10番
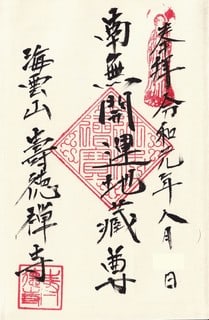
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:南無開運地蔵尊 直書(筆書)
・中央に三寶印と御本尊「南無開運地蔵尊」の揮毫。
右上に開運地蔵尊の御影印。左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔郡内三十三番観音霊場の御朱印〕
朱印尊格:南無聖観世音菩薩 直書(筆書)
札番:郡内三十三番観音霊場第10番印判
・中央に三寶印と札所本尊「南無聖観世音菩薩」の揮毫。
左上に「観音霊場郡内第十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
※郡内三十三番観音霊場第11番山中観音堂の御朱印も、こちらで拝受できます。
山中湖畔にある寺院。郡内三十三番観音霊場の巡拝で伺いましたが、境内の由緒書によると信玄公とのゆかりが深いようです。
境内の由緒書から引用します。
「往古は真言宗にして、弘法大師・空海上人諸国遍歴の砌り、富士の霊山に祈願修法せし折り、営みし草庵を平野坊と称したのが起源と伝えられる。文応元年(1260年)鎌倉五山第一建長興国禅寺より高僧美山玄誉禅師来り山紫水明のこの地に禅寺を建立し、海雲山寿徳寺を開山した。永禄四年(1561年)武田信玄公により、当寺を甲斐・駿河・相模の三国境に位置した要の地であるため国境祈願所と定められ甲州金三十枚の寄進を受ける。本尊地蔵菩薩は信玄公奉納と伝えられ通称、開運地蔵尊と云われています。国境にあるため数度の戦乱には常に兵舎の要に供せられ、特に小田原城に北条氏政攻略のときには後陣を置いたとされている。」
信玄公は、甲相駿三国同盟、甲相同盟など今川氏や北条氏と同盟を結んでいる時期が長く、駿河や相模への侵攻はさほど多くはありません。
信濃侵攻を終えた信玄公は永禄十一年(1568年)から駿河今川領への侵攻を開始し(江尻・駿府方面)、永禄十二年に第二次侵攻(富士郡・伊豆方面)、第三次侵攻(小田原攻め)を経て永禄十三年(1570年)には早くも駿河を完全制圧しました。
その侵攻ルートは、駿河方面へは主に富士川沿いの駿州往還(甲州往還)ないし東河内路、相模方面へは甲州街道ないし丹沢越えで、甲斐と駿河を接する旧鎌倉往還の籠坂峠越えのルートは採られていないようです。
ただし、信虎公の時代には今川氏とのあいだで、籠坂峠を介した戦闘がいくつか記録されています。
強豪今川氏の駿河との国境だけに、国境警備はことに厳重だったと思われ、上記の寺伝にも「小田原城に北条氏政攻略のときには後陣を置いた」とされています。
また、武田家印判状なども所蔵されてます。
富士東麓に寺社は多くなく、しかも信玄公とのゆかりが伝わる寿徳寺の存在は貴重です。
山中湖の湖尻、平野はこれまで何度となく通過していますが、この地にこのような由緒をもつ名刹があるとは知りませんでした。
郡内三十三番観音霊場の札所ですが、この霊場の知名度は高いとはいえず、山中湖で御朱印をいただけるということもほとんど知られていないかと。
禅宗の名刹らしく整った境内。
国際的なプリマドンナとして有名だった三浦環の墓所もあります。
郡内三十三番観音霊場の御朱印授与は札所ごとにまちまちですが、こちらは快く授与いただけました。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
また、現在リニューアル中で、構成が錯綜しています。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
信玄公ゆかりの寺社
Vol.1~5でご紹介した以外の、信玄公ゆかりの寺社をご紹介します。
■【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
まずは、Vol.5でご紹介した「信玄公の戦勝祈願依頼文」の祈願先11箇寺のうち、不動明王と毘沙門天以外を御本尊とする寺院をご紹介します。
■ 金剛山 慈眼寺





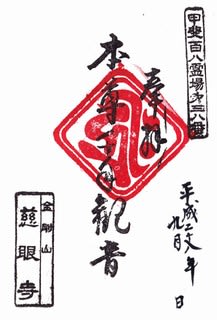
笛吹市資料
笛吹市一宮町末木336
真言宗智山派 御本尊:千手観世音菩薩
札所:甲斐百八霊場第38番、甲斐八十八ヶ所霊場第17番
朱印尊格:本尊 千手観音 印判
札番:甲斐百八霊場第38番印判
・中央に御本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印と中央に「本尊 千手観音」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第三八番」の札所印。左下には山号・寺号の印判が捺されています。
慈眼寺の開山は明確でなく、文明年間(1469年~1486年)に宥日によって中興されたと伝わります。
明治年間に醍醐報恩院末から真言宗智山派智積院に替わっているようです。(資料A)
寺伝には、「武田氏の祈願所として発展し、七堂伽藍があったが、天正十年(1582年)、織田信長勢により焼失」とあるようです。
本堂左手の光明真言の碑は特異なものらしく、真言宗の名刹としての歴史を感じさせます。
信玄公の信仰篤く、信玄公が川中島の戦いに携行された毘沙門天が残されています。(資料A)
当寺には、信玄公の薬師如来への信仰を物語る縁起が伝わります。
慈眼寺の薬師如来縁起(信玄公護身旗の梵字真言に就いて/白石真道氏)
ながくなりますが貴重な文献なので、引用させていただきます。
「甲斐國八代郡自然出現薬師瑠璃光如来縁起夫出現薬師如来といつハ往昔文治年中(1185-1160A.D.)宥日上人と云者菩提の嘉苗を植て六十余州を巡礼する時甲州八代の郡両木八幡宮に通夜す。夢中に神龍現て宥日上人に告て誼く『爰に大石あり。其中に薬師瑠璃光如来います。是を以て汝に附属す』といひ訖て夢覚ぬ。上人希有の想をなし、看に大石あり。『定て此石中に在ん。云何してかこれを得ん』と思議する時、此大石自両に分て佛像忽顕現す。光明十方を照し、異香四方に薫じ、魔宮震動して天花雨の降が如し。上人魂を失ふの信を生じ、皮を剥の誠を致して恭敬供養し、礼拝懺悔す。(略)建久五年(1194A.D.)、武田太郎信義改て堂を建て奥院と号し、如来を安置し奉て国家の繁栄を誓ふ。」
「其後永禄十三年(1570A.D.)武田信玄公川中島に於て越後の兼信と相戦う時、身方 軍兵己に敗績せんとす。是故に玄公智謀尽て佛力を頼み、法印宥空を招き、薬師の法を修せしむ。嗟呼尊哉奇哉八万の夜叉、軍兵の心中に入て猛虎の勢を生じ、十二神将大将の前後を囲で飛龍の駕に似たり。敵陣これを見て忽懼震戦き、旗を捨て逃走り、弦を絶て平降す。是則薬師如来十二神将八万夜叉等の擁護する所以なり。」
「これに依て信玄公、 如来の威光を尊び、 夜叉の冥護を仰ぎ、更に十四問四面の金堂を建て如来を尊重し給て、五百石の福田を附除して供養料とす。しかのみならず、軍中著 用の錦七条の袈裟、且つ具足箱、毘沙門の像等数多宥空法印に施与す。其後、元亀二年(1571A.D.)国中一派の僧侶を集め、 薬師如来の秘法を修せしめて、国泰民安、武運長久を祈る。」
十二神将は薬師如来を守護する神将で、各神将がそれぞれ七千、計八万四千の眷属夜叉を率いるとされています。
↑の縁起からすると、薬師如来の御利益とともに、十二神将の守護も祈願していたものとみられます。
一間一戸入母屋造の流麗な鐘楼門は国の指定重要文化財。
大寺であったことを伝える広い山内に入母屋造茅葺のどっしりとした本堂と庫裡は、地方寺院の伽藍構成をよく伝える例として国の重要文化財に指定されています。
星曼荼羅・梵字法帖などの貴重な寺宝や、信玄公の戦勝祈願依頼文などが遺されています。
戦勝祈願依頼文は、「信州長沼馬上の廻文」ともいわれ、信州長沼の地で信玄公が馬上でしたためたものと伝わります。
甲斐百八霊場第38番の札所で、快く御朱印を授与いただきました。
■ 高橋山 放光寺


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
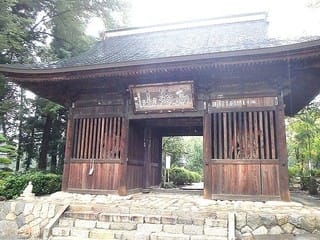

【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 大黒天
【写真 下(右)】 弁財天


【写真 上(左)】 本堂前の門
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂と庫裡(客殿)


【写真 上(左)】 庫裡玄関
【写真 下(右)】 愛染明王堂
公式Web
甲州市藤木2438
真言宗智山派 御本尊:金剛界大日如来
札所:甲斐百八霊場第8番、甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)
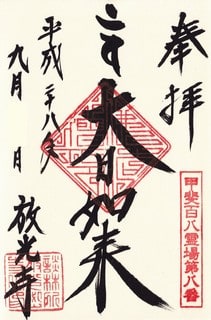
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:大日如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第8番
・中央に三寶印と金剛界大日如来の種子「バン」の種子と「大日如来」の揮毫。
右下に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
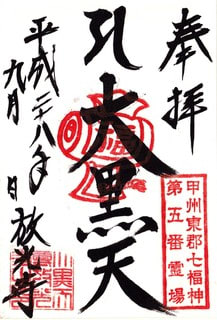
〔甲州東郡七福神(大黒天)の御朱印〕
朱印尊格:大黒天 書置(筆書)
札番:甲州東郡七福神第5番
・中央に札所本尊大黒天の持物「打ち出の小槌」の印判と「大黒天」の種子「マ」と「大黒天」の揮毫。
右下に「甲州東郡七福神第五番霊場」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
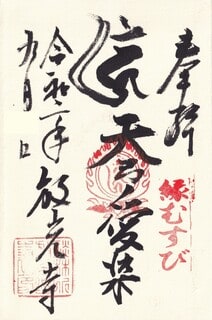
〔天弓愛染明王の御朱印〕
朱印尊格:大黒天 書置(筆書)
札番:甲州東郡七福神第5番
・中央上に愛染明王の種子「ウン」の揮毫。「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「天弓愛染」の揮毫。右に「縁むすび」の印判。
左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
愛染明王の御朱印は、山梨ではめずらしいものです。
放光寺は元暦元年(1184年)源平合戦で大きな功績をあげた安田義定公が「一ノ谷の戦い」の戦勝を記念して創立したと伝わる、甲斐を代表する名刹です。
寺伝には、「塩山の北方大菩薩の山麓、高橋荘(現在の一ノ瀬高橋)にあった法光山高橋寺を安田氏の館(山梨市小原)に近い牧荘(塩山市藤木)に移し高橋山多聞院法光寺と改め天台宗寺院として大規模に伽藍を建立し安田一門の菩提寺としました。南北朝期になって真言宗に改宗されました。のちに真言宗七談林にも加えられ真言宗の教えを広める根本道場になりました」とあります。(放光寺資料)
すこしく話が逸れますが、義定公は甲斐源氏の興亡において大きな役割を担った武将なので、事跡について簡単にまとめてみます。
義定公は、甲斐源氏の祖とされる源義光(新羅三郎)公の孫源清光公の子(清光の父義清の子説もあり)という名流で、現在の山梨市を中心とした峡東一帯に勢力を張りました。
平家追討の令旨に応じて挙兵し、「富士川の戦い」などでの戦功により遠江国守護に任じられました。(『吾妻鏡』)
寿永二年(1183年)、義定公も平家追討使として東海道から上洛。大内裏守護として京中を守護し、同年8月には従五位下遠江守に叙任しました。
「宇治川の戦い」、「一ノ谷の戦い」と歴戦。とくに「一ノ谷の戦い」では、義経の搦め手軍を率いて奮戦、平経正、平師盛、平教経を討ち取ったと伝わります。
建久二年(1191年)の鶴岡八幡宮法会では、頼朝公御供の筆頭に義定の名がみられ、頼朝公配下のなかでも高い地位を占めていたことがわかります。
建久四年(1193年)、義定公の子、安田義資が罪を得て斬られ、義定公の所領も没収。
翌建久五年(1194年)には義定公みずからが謀反の疑いをうけ、放光寺にて自刃されたと伝わります。
この当時の甲斐源氏には、武田信義、安田義定、一条忠頼らの有力武将がおり、「富士川の戦い」の主力は甲斐源氏であったとみられています。
しかし、義定公は謀反の疑いで自刃、一条忠頼も鎌倉にて酒宴の最中に暗殺、武田信義公の子逸見有義は頼朝公から疎まれ、同じく信義公の子板垣兼信は違勅の罪を問われて配流されるなど、次々と失脚していきました。
当時の甲斐源氏は頼朝公も御せないほどの勢力があり、武士の頭領としての地位を確立するために、頼朝公が甲斐源氏の力を削いでいったという見方が有力です。
以降、甲斐源氏では、武田氏宗家となった信光公の流れと信義公の弟加賀美遠光公から小笠原氏、南部氏が出て、以降勢力をはりました。
小笠原氏、南部氏は江戸時代も大名家として存続しています。(大和郡山藩の柳沢氏、新発田藩主の溝口氏、松前藩主の松前(蠣崎)氏なども甲斐源氏の末裔を称しています。)
義定公は文化に造詣が深く、多くの仏像を勧請され、いまも「木像大日如来」「木像不動明王」など名作とされる仏像が放光寺に残されています。
「天弓愛染明王」は日本最古の天弓愛染明王としてとみに有名です。
また、開基堂に御座す毘沙門天は、義定公ゆかりのお像と伝わります。
信玄公との関係についても寺伝があります。
「武田信玄の時代には、武田家の祈願所となっております。元亀三年三方原の戦いのおり、武田氏は遠州鎌田山医王寺に伝わった大般若経六百巻(南北朝時代の写経)を甲州に移し、当山に奉納しております。」((放光寺資料)
永禄十一年の「信玄公の戦勝祈願依頼文」には「法光寺」とありますが、これは当寺のことかと思われます。
天正十年(1582年)、織田勢の甲州攻めの兵火にかかり堂塔伽藍は焼失しましたが、その後、慶長年間(1599年~1614年)、寛文年間(1661年~1662年)に堂宇が再建されて現存します。
山内はさほど広くはないですが、梅の木が多く、名刹らしい落ちつきがあります。
山門は、駐車場から寺を背に参道を下っていったところにあるので、気づきにくいです。
すこぶる個性的な意匠で、脚数すらわかりませんでした。
扁額もめずらしい梵字のものです。
「高橋山」の扁額が掲げられた仁王門は、入母屋銅板葺桁行三間一戸の単層門、左右に金剛力士像が安置されています。
参道右手に甲州東郡七福神の大黒天と鐘楼、右手の放生池、太鼓橋のさきに弁財天が祀られています。
大黒天は大岩に刻まれた露仏とお堂のなかにも御座します。
公式Webによると、大岩の露仏は、当山鎮守開運大黒天の奥の院本尊で、もともとは北方鍜冶屋橋のたもと笛吹川の東岸に祀られていましたが、橋の改修工事に伴い移座されたようです。
毎年4月29日の大黒天会式では柴燈護摩火渡修行が催され、賑わいをみせるそうです。
本堂前の門も本瓦葺の堂々たるもの。
門をくぐると、桁行九間入母屋銅板葺の本堂と豪壮な庫裏の唐破風が力強い対比をみせています。
有名な「天弓愛染明王」は本堂左手おくのお堂に御座し、間近で拝むことができます。
拝観は有料ですが、仏像群がすばらしくご説明もいただけるので拝観をおすすめします。
拝観前に御朱印帳をお預けすれば、拝観後に揮毫の御朱印を拝受できます。(大黒天は原則書置のようです。)
【 善光寺 】
■ 定額山 浄智院 善光寺(甲斐善光寺/甲州善光寺)
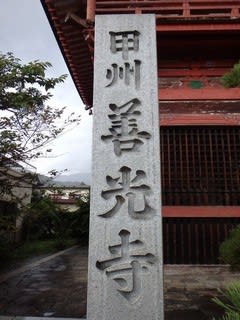



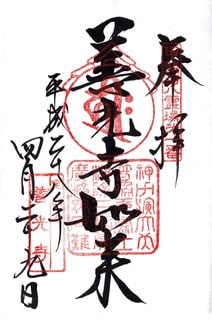

公式Web
甲府市善光寺3-36-1
浄土宗 御本尊:善光寺如来
札所:甲斐百八霊場第1番、甲斐八十八ヶ所霊場第67番、府内観音札所第7番
朱印尊格:善光寺如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第1番印判
信玄公の戦のなかでもとくに名高いのが、信州・川中島周辺で上杉謙信公(長尾景虎)との間で数次にわたり展開された”川中島の戦い”です。
信玄公は第三次の戦いの後の永禄元年(1558年)、善光寺が兵火にかかるのを恐れて、ご本尊の一光三尊阿弥陀如来(善光寺如来)と数々の寺宝を甲府に移し、信濃善光寺の三七世住職・鏡空上人を開基として堂塔を建立されました。
江戸時代には、本坊三院十五庵を有する大寺院として浄土宗甲州触頭を勤め、徳川家位牌所でもあり、現在に至るまで甲府を代表する仏閣として広く参詣客を集めています。
〔境内由来書より(抜粋)〕
「定額山浄智院善光寺は、武田信玄公が 永禄年中 川中島の合戦の折 信濃善光寺が兵火にかかるのを恐れ 本尊阿弥陀如来その他 諸仏 寺宝 大梵鐘に至るまでことごとく甲斐に招来し 大本願第三十七世鏡空上人を開山に迎え 信濃善光寺開基本田善光公追慕の地 ここ板垣の郷に新たに建立せられたものである」
現在の御本尊は、かつての善光寺の本尊の御前立像とされ、秘仏でしたが平成9年からは7年毎に御開帳されています。
公式Webでは現在の御本尊について「当山の御本尊は、建久六年(1195)尾張の僧定尊が、秘仏である信濃善光寺の前立仏として造立したものです。定尊は、如来の夢の告げを得て勧進に行脚し、四万八千余人もの寄進を得たといわれます。
本像は、いわゆる一光三尊式善光寺如来像の中では、在銘最古、かつ例外的に大きな等身像として著名です。」と解説されています。
甲斐善光寺でも「お戒壇廻り」を体験することができます。(有料)
まずは、スケールの大きな山門に圧倒されます。
稀少な五間三戸の楼門で入母屋造銅板葺。外周の擬宝珠高欄が装飾性を高めています。
参道正面に威風を放つ本堂。
金堂とも呼ばれ、屋根の形が東西棟と南北棟でT字(撞木形)を形成する構造(撞木造)で、善光寺特有の様式とされます。
桁行じつに十一間。向拝三間。撞木造で奥行きがあり梁間も七間となっています。
一層唐破風、二層千鳥破風のように見えますが、実は仏殿ではけっこうめずらしい妻入りで、東日本では最大級の木造建築物とされています。
各種の組物、蟇股、木鼻彫刻、連子窓、三花懸魚などを配し、朱塗りの色調と相まってスケール感と装飾性を兼ね備えたつくりとなっています。
ともに宝暦四年(1754年)に焼失し、現在の山門は明和四年(1767年)、本堂は天明五年(1785年)の再建上棟と伝わります。

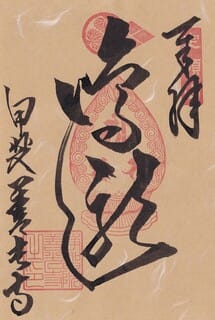
【写真 上(左)】 鳴き龍(授与所でいただいた絵ハガキより)
【写真 下(右)】 鳴き龍の御朱印
御朱印は本堂内の授与所で拝受できます。
見本が出ているのは「善光寺如来」の御朱印だけですが、金堂中陣天井の「鳴き龍」の御朱印も授与されており、申告すると奥から書置の御朱印をお出しいただけます。
オリジナル御朱印帳も頒布されています。
山梨県内では稀少な浄土宗寺院のオリジナル御朱印帳で、寺紋である丸に立葵と武田菱が表裏に配された渋いデザインですが、縦16cm×横11cmの小サイズがいささか残念です。
■ 塩山 向嶽寺
臨黄ネット





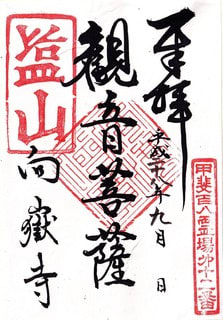
甲州市上於曽2026
臨済宗向嶽寺派本山 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第12番、甲斐八十八ヶ所霊場第74番
朱印尊格:観音菩薩 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第12番印判
・中央に三寶印と札所本尊「観音菩薩」の揮毫。
右下に「甲斐百八霊場第十二番」の札所印。左上に「𥂁山」山号印と寺号の揮毫があります。御本尊は釈迦牟尼佛ですが、札所本尊は観音菩薩となっているようです。
臨済宗向嶽寺派本山の格式を有する名刹で、開山は抜隊得勝(ばっすいとくしょう)禅師〔慧光大円禅師〕です。
各地を遍され、永和四年(1378年)高森(塩山市竹森)の険しい地に庵居された禅師のもとを訪れる僧俗は引きも切らず、武田信成公は塩山の地を寄進し庵を建て、禅師を迎え入れて向嶽庵と称しました。
禅師はこの庵で僧俗の教化に努められ入寂されました。
以降も武田家歴代の帰依を受け、天文十六年(1547年)6月、信玄公は朝廷へ働きかけ、抜隊禅師に「慧光大円禅師」の諡号を賜り、向嶽寺の寺号を定めたとされます。
境内掲示の沿革に「明治五年(1782年)に輪番住職制を改め独住制となり、京都南禅寺の所轄となったが、同四一年管長を置いて名実ともに別派独立の大本山となった。」とあるので、臨済宗のなかで一派をなしたのは明治になってからとみられますが、南禅寺からの別派独立ですから、寺格はすこぶる高いものと思われます。
向嶽寺は、甲府盆地の東北部にこんもりと突き出た小高い山の南麓に抱かれるようにたたずんでいます。
山号の「塩山」は「塩の山(志ほの山)」とも呼ばれ、この北側の山です。
山梨市の笛吹川沿いにある「差出の磯(さしでの磯)」とともに、古くから和歌に詠まれた景勝地です。
「志ほの山」は「さしでの磯」の枕詞で、さらに千鳥や八千代にかかっていくことが多いようです。
- 志ほの山 さしでの磯に すむ千鳥 君が御代をば 八千代とぞなく -
(古今和歌集)
国宝の「絹本著色達磨図」は「八方にらみの達磨」「朱達磨」とも呼ばれ、わが国の達磨図の最高傑作として知られています。(現在は東京国立博物館に寄託)
室町時代建造の中門(総門)や漆喰製瓦屋根の「塩築地」など、貴重な建築物が残っています。
修復なった池泉式庭園も国の名勝に指定されています。
臨済禅の名刹らしく、整った山内には凜とした空気がただよいます。
敷居が高い感じですが、甲斐百八霊場の札所であり、御朱印は快く授与いただけました。
■ 妙亀山 広厳院
公式Web





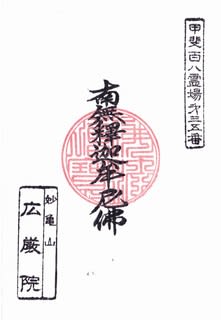
笛吹市一宮町金沢227-1
曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩
札所:甲斐百八霊場第35番、甲斐八十八ヶ所霊場第16番
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛 印判
札番:甲斐百八霊場第35番印判
・中央に三寶印と御本尊「南無釋迦牟尼佛」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第三五番」の札所印。左下に山号・寺号の印が捺されています。
御本尊は聖観世音菩薩ですが、朱印尊格は釈迦牟尼佛となっています。禅宗寺院の御朱印では、御本尊ではなく、宗派本尊の「南無釈迦牟尼佛」で授与される例がときどきみられます。
小田原最乗寺十四世の雲岫宗竜大和尚を開祖、塩田長者降矢対馬守を開基とし、寛正元年(1460年)に開山の曹洞宗の名刹。
甲斐四群(山梨、八代、都留、巨摩)の中央に位置するため、「中山」とも称されます。
寺伝によると、甲斐国守護武田信昌公が文明十九年(1487年)に寺領を寄進して以来、信縄公、信虎公、信玄公、勝頼公と武田家五代の庇護を受けたとされます。
信玄公は、弘治二年(1556年)に祖母崇昌院殿(信縄公妻)の菩提を弔うため寺領十貫文を寄進され、崇昌院殿を開基に準じたと伝わります。
信玄公と曹洞宗のつながりを示す寺院です。
甲府の大泉寺とともに甲斐曹洞宗の大元としての格式があり、県内八百三十寺の末寺を総括、最盛期には八十人の僧を擁する大寺であったと伝わります。
端正な鐘楼、質素な本堂、吊り下がる魚板など、禅寺らしい趣にあふれています。
御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。
■ 調御山 佛陀寺





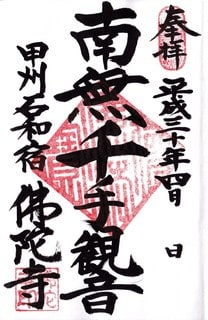
笛吹市石和町市部864
臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩
札所:石和温泉郷七福神(福禄寿)
朱印尊格:南無千手観音 直書(筆書)
・中央に三寶印と御本尊「南無千手観音」の揮毫。
右上に不明な印。左に「甲州石和宿 佛陀寺」の揮毫と寺院印が捺されています。
※石和温泉郷七福神(福禄寿)の御朱印も授与されています。
文永六年(1269年)、わが国の普化宗の開祖法燈円明国師が、亀山天皇の勅令によって建立された禅寺。
天文年間(1540年代)、信玄公が恵林寺から歓堂宗活禅師を請じて臨済宗妙心寺派に改め、寺運はとみに栄えたと伝わります。(境内掲出の寺伝より)
御本尊千手観世音菩薩は行基の作、「調御山」の山号扁額は亀山天皇の御宸筆であると伝えられています。
境内には、幕末の侠客、竹居の安五郎こと吃安の墓があります。
普化宗は禅宗の一派で、建長六年(1249年)南宋に渡った心地覚心が、中国普化宗16代目張参の4人の弟子を伴い帰国して伝来しました。
江戸時代には虚無僧の宗派として位置づけられ、幕府とも結びついたとされますが、明治に入り政府により解体され廃宗となったとされます。(戦後再興。尺八(虚鐸)文化の源流ともみなされている。)
信玄公の臨済宗妙心寺派や恵林寺への帰依を物語る寺院です。
こじんまりとした寺院ですが、石和温泉郷七福神(福禄寿)の札所を務められており、快く御朱印を授与いただけました。
■ 岩泉山 寂静院 光福寺
浄土宗寺院紹介Navi




甲府市横根町1110
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第2番、甲斐国三十三番観音札所第21番、第22番
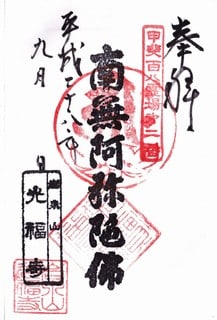
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:南無阿弥陀佛 印判
札番:甲斐百八霊場第2番印判
・中央に御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座)と三寶印と「南無阿弥陀佛」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第二番」の札所印。左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
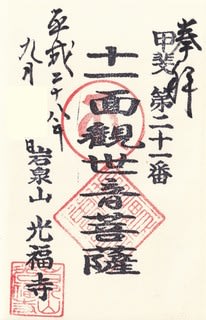
〔甲斐国三十三番観音札所(第21番)の御朱印〕
朱印尊格:十一面観世音菩薩 印判
札番:甲斐国三十三番観音札所第21番
・中央に札所本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印と三寶印と「十一面観世音菩薩」の印判。
右に「甲斐 第二十一番」の札所印。左には山号・寺号の印と寺院印が捺されています。

〔甲斐国三十三番観音札所(第22番)の御朱印〕
朱印尊格:聖観世音菩薩 印判
札番:甲斐国三十三番観音札所第22番
・中央に札所本尊聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印と三寶印と「聖観世音菩薩」の印判。
右に「甲斐 第二十二番」の札所印。左には山号・寺号の印と寺院印が捺されています。
甲斐源氏の祖、新羅三郎義光公が「後三年の役」で奥州で戦死した人々を弔うため、嘉保二年(1095年)、空源法印を開山として建立された寺院で、当初は寂静院ないし横根寺と称しました。
天文十六年(1547年)、信玄公が権少僧都円全を中興開山として再興されました。
慶長十年(1605年)、鎌倉から萬誉助往和尚を迎えて翌十一年知恩院直末に編入、寺号を光福寺と改め浄土宗に改宗しています。
甲斐百八霊場の札所であり、山内2つの観音堂は甲斐国三十三番観音札所に定められています。
■ 護国山 国分寺





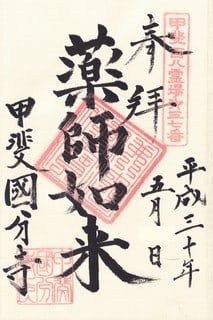
笛吹市一宮町国分197-1
臨済宗妙心寺派 御本尊:薬師如来・阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第37番、甲斐八十八ヶ所霊場第17番
朱印尊格:薬師如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第37番印判
・中央に三寶印と札所本尊「薬師如来」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第三七番」の札所印。左に甲斐國分寺の揮毫と寺院印が捺されています。
笛吹市一宮周辺は、甲斐の国でも早くから拓けた一帯とされており、国分寺も聖武天皇の御代(701年~756年)にこの地に建立されました。
例にもれず甲斐の国分寺も戦国時代までには荒廃してしまいましたが、信玄公が寺領を寄進し復興を手掛けられ、勝頼公の時代に臨済宗に改宗されたと伝わります。
当寺は旧国分寺跡地上にありましたが、旧国分寺跡が国の史跡に指定されたため、現在地にしています。
奈良時代の作と伝わる薬師如来像は、33年に一度の御開帳です。
■ 柏尾山 大善寺
※ 現在、整理中です。
■ 龍湖山 方外院




公式Web
身延町瀬戸135
曹洞宗 御本尊:如意輪観世音菩薩
札所:甲斐百八霊場第98番、甲斐国三十三番観音札所第27番
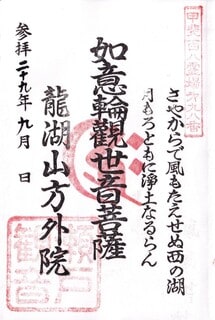
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:如意輪観世音菩薩 印判
札番:甲斐百八霊場第98番
・中央に札所本尊如意輪観世音菩薩の種子「キリク」の御寶印と「如意輪観世音菩薩」の印判。
右上に「甲斐百八霊場第九八番」の札所印と御詠歌の印。左下には山号・院号の印判と寺院印が捺されています。
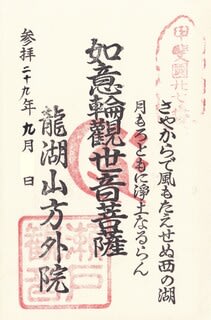
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
朱印尊格:如意輪観世音菩薩 印判
札番:甲斐国三十三番観音札所第27番
・中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリク」の御寶印と「如意輪観世音菩薩」の印判。
右上に「甲斐國廿七番」の札所印と御詠歌の印。左下には山号・院号の印判と寺院印が捺されています。
信玄公と観世音菩薩のゆかりを示す伝承は多くはありませんが、身延の方外院には御本尊如意輪観世音菩薩と信玄公の逸話が伝わっています。
方外院は貞治元年(1362年)、現・身延町の名刹で、南明寺の三世・梅林禅芳禅師によって本栖湖の湖畔に開創されました。山号「龍湖山」は本栖湖に由来するものです。
信玄公の治世、方外院は本栖湖畔(本栖村赤坂)にありました。
信玄公が三河に向けて軍勢を進める途中、寺のそばを通ると雷雨が激しくなり軍を進めることができなくなりました。
淡い火影を見つけてたどり着いたお堂には、微笑みをたたえた如意輪観音菩薩が御座されていました。
信玄公が観音様に祈願するとたちまち雷雨は収まり、軍は無事に三河へ向かうことができました。
信玄公はこの仏恩に謝するため、本栖の地頭・渡辺囚獄に命じてこの観音様を手厚く保護させました。
武田家滅亡の混乱のなか、この観音様も所在を転々とされましたが、慶長二年(1597年)下部・瀬戸の住民が観音様をお迎えしました。
子授けの霊験あらたかで「瀬戸の観音さま」として崇められ、甲斐三十三観音霊場の札所でもあったことから、多くの参拝者を集めます。
行基菩薩の御作とも伝わるこの観音様は、寄せ木法の技法や納衣の曲線などから、平安末期の作(南北朝との説もあり)とみられています。
秘仏ですが、毎年3月18日の御縁日には御開帳されます。
また、身延町資料身延の民話には「方外院本尊の如意輪観世音像は行基の作で、人肌と同じ体温があるという。仏門に入った武田信玄が寺に参詣しその話を聞き、須弥壇に上がって厨子の扉に手をかけようとした瞬間壇下へ投げ落された。信玄は額づいて無礼を詫び、武田菱の使用を許可し御朱印地七石を賜った。(下部町誌)」との逸話があります。
常葉川(本栖みち)沿いの古関集落から、常葉川支流の反木川を少し遡った山ぶかいところにあります。
寺号標には「龍湖山方外院瀬戸観音寺」とあり、 甲斐百八霊場、甲斐国観音霊場の札番が刻まれています。
四脚単層銅板葺で大棟に武田菱三連を置いた山門。すぐおくには三間一戸八脚の楼門で、こちらは大棟に「龍湖山」の山号を置いています。
楼門右横には立派な鐘楼が置かれ、本堂に至る前から豪壮な伽藍配置です。
向拝のない簡素な本堂ですが、山号扁額には青龍を配して存在感を放っています。
正面硝子戸には武田菱、壁面には「一見観音衆罪即滅」というありがたいお言葉が掲げられています。
硝子戸を開くと新たな展開が・・・。
堂内じたいは禅宗様の飾り気のすくないつくりですが、いくつか掲げられた派手やかな「瀬戸観音」の奉納提灯と、なにより正面上部に掲げられた絵馬が強く目を惹きます。
禅寺で観音霊場を兼ねる場合、御本尊は釈迦牟尼佛で別に観音堂があって、観音霊場の札所本尊はそちらに御座し、本堂はシックで観音堂は華やかな例が多いです。
しかし、こちらは御本尊が観音様で札所本尊も兼ねられるため、このような本堂と観音堂が混在するような雰囲気になっているのかと思います。
絵馬は著名なものです。
横19.42メートル、縦2.24メートルにも及ぶ大額で、「方外院千匹馬の大額」と称され、町の有形文化財に指定されています。
総桐材造の額に馬千匹が描かれ、前方の馬には着色が施されて華麗な印象な額です。
安政の飢饉の折、御本尊の信仰篤い老翁に「馬の霊が飢えて稲を食する故、各地より一人一匹の馬を奉納せよ」との霊夢がくだり、馬の奉納にかえて馬の大額を奉納したところ、翌年より豊作となったと伝わります。
絵馬は茨城県出身の渡辺天麗の作で、額に記された奉納者は甲府在住の者までに及び、広範囲に信仰を集めていたことがわかります。
■ 海雲山 寿徳寺


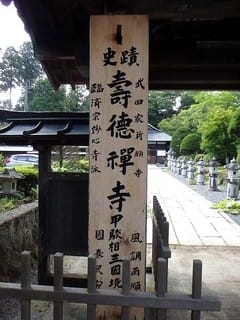



山中湖村平野147
臨済宗妙心寺派 御本尊:地蔵菩薩
札所:郡内三十三番観音霊場第10番
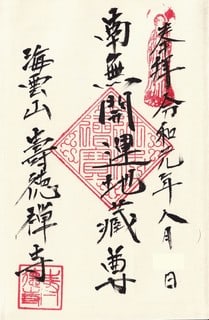
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:南無開運地蔵尊 直書(筆書)
・中央に三寶印と御本尊「南無開運地蔵尊」の揮毫。
右上に開運地蔵尊の御影印。左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔郡内三十三番観音霊場の御朱印〕
朱印尊格:南無聖観世音菩薩 直書(筆書)
札番:郡内三十三番観音霊場第10番印判
・中央に三寶印と札所本尊「南無聖観世音菩薩」の揮毫。
左上に「観音霊場郡内第十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
※郡内三十三番観音霊場第11番山中観音堂の御朱印も、こちらで拝受できます。
山中湖畔にある寺院。郡内三十三番観音霊場の巡拝で伺いましたが、境内の由緒書によると信玄公とのゆかりが深いようです。
境内の由緒書から引用します。
「往古は真言宗にして、弘法大師・空海上人諸国遍歴の砌り、富士の霊山に祈願修法せし折り、営みし草庵を平野坊と称したのが起源と伝えられる。文応元年(1260年)鎌倉五山第一建長興国禅寺より高僧美山玄誉禅師来り山紫水明のこの地に禅寺を建立し、海雲山寿徳寺を開山した。永禄四年(1561年)武田信玄公により、当寺を甲斐・駿河・相模の三国境に位置した要の地であるため国境祈願所と定められ甲州金三十枚の寄進を受ける。本尊地蔵菩薩は信玄公奉納と伝えられ通称、開運地蔵尊と云われています。国境にあるため数度の戦乱には常に兵舎の要に供せられ、特に小田原城に北条氏政攻略のときには後陣を置いたとされている。」
信玄公は、甲相駿三国同盟、甲相同盟など今川氏や北条氏と同盟を結んでいる時期が長く、駿河や相模への侵攻はさほど多くはありません。
信濃侵攻を終えた信玄公は永禄十一年(1568年)から駿河今川領への侵攻を開始し(江尻・駿府方面)、永禄十二年に第二次侵攻(富士郡・伊豆方面)、第三次侵攻(小田原攻め)を経て永禄十三年(1570年)には早くも駿河を完全制圧しました。
その侵攻ルートは、駿河方面へは主に富士川沿いの駿州往還(甲州往還)ないし東河内路、相模方面へは甲州街道ないし丹沢越えで、甲斐と駿河を接する旧鎌倉往還の籠坂峠越えのルートは採られていないようです。
ただし、信虎公の時代には今川氏とのあいだで、籠坂峠を介した戦闘がいくつか記録されています。
強豪今川氏の駿河との国境だけに、国境警備はことに厳重だったと思われ、上記の寺伝にも「小田原城に北条氏政攻略のときには後陣を置いた」とされています。
また、武田家印判状なども所蔵されてます。
富士東麓に寺社は多くなく、しかも信玄公とのゆかりが伝わる寿徳寺の存在は貴重です。
山中湖の湖尻、平野はこれまで何度となく通過していますが、この地にこのような由緒をもつ名刹があるとは知りませんでした。
郡内三十三番観音霊場の札所ですが、この霊場の知名度は高いとはいえず、山中湖で御朱印をいただけるということもほとんど知られていないかと。
禅宗の名刹らしく整った境内。
国際的なプリマドンナとして有名だった三浦環の墓所もあります。
郡内三十三番観音霊場の御朱印授与は札所ごとにまちまちですが、こちらは快く授与いただけました。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
2020/11/26 UP
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
2020/04/30 UP
つづきです。
〔 信玄公の信仰 〕
つぎに信玄公が信仰されていた尊格という視点から、まとめてみたいと思います。
『甲陽軍鑑』には神社仏閣、尊格についての記述が数多くありますが、まだ読破していないので、現時点で情報がとれている寺院についてのみです。
わかり次第、追記します。
【 山梨岡神社 】
■ 山梨岡神社





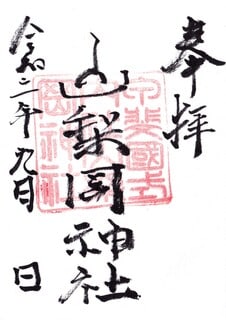
山梨県神社庁資料
笛吹市春日居町鎮目1096
御祭神:大山祇神、高龗神、別雷神
旧社格:式内社(小)論社、郷社
授与所:境内社務所(TELにてお伺い)
御朱印揮毫:山梨岡神社
山梨岡神社は古代に創建され、式内社論社に比定される甲斐国有数の古社です。
御祭神は、大山祇神、高龗神、別雷神の三柱で、当初は背後の御室山そのものが神として崇められていたともみられます。
山梨県神社庁資料には「人皇十代崇神天皇の御代、国内に疫病の流行や災害が多発し、これを憂ひた天皇の勅命により背後の御室山中腹に創祀される。後十三代成務天皇の御代に麓の山梨の群生林を切り開いて現在地に遷座され山梨岡神社と号す。」とあり、「山梨」の地名発祥の地と伝えられます。
旧社地には御室山古墳があります。
御室山で行われる山焼き「笈形焼」は、日本有数の規模をもつそうです。
「古くは山梨明神・山梨権現・日光権現とも称せられ武田家累代の祈願所として篤く崇敬された。」「古来より伝はる太々神楽は、武田信玄公出陣の際戦勝を祈願して奉納された神楽として伝へられてゐる。」(山梨県神社庁資料)とあり、武田家や信玄公の尊崇の篤さがうかがわれます。
武田軍出陣の際に戦勝祈願の社参がなされたという記録が複数あり、躑躅ヶ崎館の氏神とする史料もあるようです。
笛吹市の資料にも「武田家累代の氏神として崇拝され、武田信玄が出陣のたびに、戦勝祈願をしたといわれています。」とあります。
当社には、「虁(き)ノ神」という神獣の像が祀られています。
「状は牛の如く、身は蒼くて角がなく、足は一つ。」(『山海経』)
虁ノ神は、雷神、水神、魔除けの神として信仰を受け、徳川将軍家から夔ノ神の神札が大奥や御三家、旗本らに差し出されたという記録があり、夔ノ神信仰が広まったとみられています。
また、「山梨(やまなしの)岡」は、古来名所歌枕として知られ、
- 甲斐かねに咲にけらしな足引きの やまなし岡の山奈しの花 - 能因法師
という歌が残っています。
上の由緒を裏付けるように、信玄公ゆかりの宝物や行事がいまも残ります。
「武田家より譲り受けた『社参状』は、諏訪大社上社の神主あてに武田信玄が出した文書です。『穴山梅雪等が宝鈴を鳴らすために諏訪神社上社を訪れる』といった内容が書かれています。」「社参状とともに武田信玄から譲り受けた『椀』2個も保管されています。椀には武田菱(武田家の家紋)等が描かれています。」「『禁制を書いた板』には御室山でかってに木を切ったりする事を禁止すると書かれています。」(以上、笛吹市資料より)
また、当社に伝わる「太々神楽」(だいだいかぐら)二十四種の舞のうち、二十番目の「四剣の舞」は”信玄公出陣の神楽”とも称され、信玄公が戦さの勝利を願い奉納させた神楽だといわれています。(笛吹市資料)
国道140号からおくまった御室山の山裾に鎮座します。
参道右手に天然記念物「山梨岡神社のフジ」の藤棚。
参道橋を渡ると空気が変わり、式内社(論社)ならではの神さびた雰囲気が漂っています。
正面に桁行五間入母屋造桟瓦葺の拝殿、右手に神楽殿、その裏手には御室山信仰を思わせる一画があります。
本殿は室町時代末の建立とそれ国の重要文化財に指定されています。桁行二間の隅木入春日造杮葺、片流れ向拝付とのことです。
御朱印は境内社務所に連絡先が書いてあったので、TELするとご神職においでいただけ授与いただけました。
ご多忙のところ、ありがとうございました。
【 八幡神 (八幡大菩薩)】
八幡神は、源義家公が石清水八幡宮で元服して自らを八幡太郎と称されたことから清和源氏の崇敬が厚く、甲斐源氏の多くも氏神として祀りました。
Vol.1でご紹介した武田八幡宮や(甲斐國総社/宮前)八幡神社はその好例ですが、山梨市に鎮座される大井俣窪八幡神社もまた、武田家とのゆかりが深いお社です。
【 (大井俣)窪八幡神社 】
山梨県神社庁資料






公式Web
山梨市北654
御祭神:誉田別尊(中殿)、足仲彦尊(北殿)、息長足姫尊國魂大神命(南殿)
旧社格:式内社(小)論社、県社
元別当:八幡山 神宮寺(山梨市北)
授与所:境内社務所(不定期、事前問合せがベター)
朱印揮毫:大井俣神社 窪八幡宮 直書(筆書)〔令和元年5月拝受〕
朱印揮毫:大井俣 窪八幡神社 直書(筆書)〔平成28年9月拝受〕
社伝によると、清和天皇の勅願により貞観元年(859年)、宇佐神宮の八幡三神を音取川(今の笛吹川)の中島(大井俣)の地へ勧請、水害により現社地に遷座されました。
甲斐源氏、ことに本流武田家代々の氏神として崇敬され社殿が整えられました。
信虎公、信玄公の崇敬も篤く、信虎公は天文八年(1539年)の厄年に鳥居を寄進し、その際には信玄公が当社に代参されています。
天文十四年(1545年)には直筆とされる歌仙絵(板絵著色三十六歌仙図)を奉納、翌天文十五年には三条夫人も社参されています。
本殿の金箔は弘治三年(1557年)の川中島合戦に際して信玄公が捺させたものと伝わり、木造狛犬六駆、鐘楼も信玄公の寄進・再建によるものとされています。
当社は文化財の宝庫として知られています。
・一の鳥居(室町後期、木造両部鳥居、重文、現存する国内最古の木造鳥居)
・神門(室町後期、四脚門切妻造檜皮葺、重文)
・摂社若宮八幡神社本殿(室町中期、三間社流造檜皮葺、重文)
・拝殿(室町後期、桁行十一間切妻造檜皮葺、重文)
・本殿(室町後期、桁行十一間流造檜皮葺、重文)
とくに本殿は三間社流造の三社を間に一間をおいて横に連結した形状で、わが国に現存する最大の流造本殿とみられているそうです。
---------------------------------------------
八幡神が武田軍の軍陣で祈願された例として、「三方ヶ原の戦い」前の信玄公自作とされる歌が知られています。
元亀三年(1572年)秋、西上の軍を起こした信玄公は伊那口から徳川領の遠江に侵入し、徳川方の本多・内藤偵察隊を「一言坂の戦い」で一蹴。
つづいて要衝・二俣城を落とし、家康公が拠る浜松城を素通りして西上をつづけるかの動きをとりました。
『甲陽軍鑑』によると、二俣城進発の際、信玄公はつぎのような歌を八幡神に捧げたとされています。
- ただたのめたのむ八幡の神風に 浜松が松は倒れざらめや -
武田軍の浜松城攻めを想定していた家康公は、城の目の前を敵軍が通過するという事態に直面しました。
浜松城籠城を唱えた家臣もいましたが、家康公は「たとへば人あってわが城内を踏通らむに、咎めであるべきや、いかに武田か猛勢なればとて、城下を蹂躙しておし行くを、居ながら傍観すべき理なし、弓箭の恥辱これに過ぎじ、後日に至り、彼は敵に枕上を踏越されしに、起きもあがらでありし臆病者よと、世にも人にも嘲られむこそ、後代までの恥辱なれ、勝敗は天にあり、兎にも角にも戦をせではあるべからず」との名言を発し、出撃を命じたと伝わります。(→東照宮御実紀附録巻二(国会図書館資料のP.28))
三方ヶ原の台地にのぼった武田軍は、徳川・織田連合軍の進撃を察知すると、やにわに軍の向きを変え、悠々と魚鱗の陣を敷いて徳川・織田連合軍を迎え撃ったとされます。
連合軍は武田軍に撃破され、浜松城に退いたというのが、家康公の数少ない敗戦といわれる「三方ヶ原の戦い」です。
「徳川家康三方ヶ原戦役画像(「顰(しかみ)像」)」(徳川美術館所蔵)は、家康公が三方ヶ原の敗戦直後に自戒のため描かせたとする伝承があります。
「慢心を戒めるために敗戦時の自身の姿を描かせ、自戒のために座右に置いた」という人生訓は、この絵とともに後世に広く伝えられ、信玄公の戦さの強さもまた、人口に膾炙することとなりました。
信玄公ゆかりの八幡神社は県内外にまだまだ事例があると思いますので、わかり次第追記します。
【 諏訪明神 】
信玄公の諏訪明神信仰をもっともよく示すのは、武田家の重宝であり信玄軍の軍旗である「諏訪神号旗」(御旗)でしょう。
「諏訪神号旗」は、「孫子の旗」とともに武田の軍旗として用いられたとされ、「諏訪法性旗」「諏訪明神旗」「諏訪梵字旗」と呼称される3種の旗の総称です。
なかでも「諏訪法性旗」は信玄公直筆と伝わります。
現在、「諏訪神号旗」甲州市塩山の雲峰寺、恵林寺などに所蔵されており、詳細は各々の記事をご参照願います。
側室とされた諏訪御料人は、諏訪大社上社の大祝、諏訪頼重公の息女であり、諏訪御料人が産んだ世継ぎの勝頼公もこの血筋を継いで、武田家の家督相続以前は諏訪四郎勝頼と称されました。
信玄公と諏訪大社大祝家はこのような結びつきもあります。
Web上では、信玄公が諏訪大社上社に度々戦勝祈願をしたという記事が複数みつかりますが、いまのところ史料が見当たらないので、確認できたら追記します。
(諏訪大社の御朱印は、別編の「武田勝頼公編」でのご紹介を考えているので、ここではふれません。)
2019年5月、長野県立歴史館は永禄十年(1567年)、信玄公が諏訪大社内にあった寺院に宛てて新たな寄付を約束した公的な文書(朱印状)の入手を公表しています。
寺院名の確認ができないのですが、この寺院が諏訪大社と深い関係にあるとすると、信玄公のお諏訪様信仰を間接的に裏付けるものになるかと思います。
■ 白華山 慈雲寺
公式Web




長野県諏訪郡下諏訪町東町中606
臨済宗妙心寺派 御本尊:千手千眼観世音菩薩
札所:伊那諏訪八十八ヶ所第18番、諏訪郡百番霊場西21番
朱印尊格:圓通閣 書置(筆書)
札番:なし
・中央に御本尊、千手千眼観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「圓通閣」の揮毫。
右上に扁額にちなむ?印。左には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
正安二年(1300年)、諏訪大社下社大祝金刺満貞の願意を受けて、来朝僧一山一寧国師により開山された下諏訪の名刹で、「下社春宮の鎮護を目的に建てられた鬼門寺」という説もあります。
寺伝によると、天文六年(1537年)の火災の折、当時の住職天桂玄長禅師は甲斐の恵林寺住職も兼務され信玄公の帰依を受けており、その縁により信玄公の支援復興がなされたため、信玄公が当寺の中興開基とされています。
また、信玄公が川中島合戦に向かう際に当寺を訪れ、矢を除ける念力のある石「矢除石」の御札を授かったという伝承もあります。
信玄公と諏訪大社との間接的なつながりを示す寺院とみられます。
■ 南宮大神社
山梨県神社庁資料


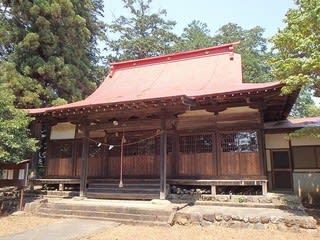
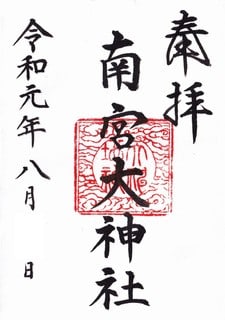
韮崎市大草町上條東割790
御祭神:大己貴命、事代主命、建御名方命、金山彦命
旧社格:郷社
授与所:若宮八幡宮社務所(韮崎市若宮1-4-14)
朱印揮毫:南宮大神社 直書(筆書)
韮崎市大草町鎮座の南宮大神社も信玄公ゆかりの神社とされています。
現地掲示の由緒書によると「諏訪明神すなわち建御名方命を主祭神とし、大己貴命・事代主命・金山彦命を配祀する」「社記によれば、新羅三郎義光が甲斐任国の時崇敬して社壇を造営したといい、武田太郎信義、その嫡男一条次郎忠頼も篤く崇敬し、武田一条氏が武川地方に封ぜられると、当社を産土神として崇敬し、その支族の武川衆諸氏も協力して当社に奉仕した史料を伝えている。また武田信玄は当社の禰宜(神主)に対し、 府中八幡宮に二日二晩参篭し、武田家武運長久と領内安穏の祈祷をすることを命じた。」
府中八幡宮は甲斐の総社的な神社で、こちらへの参篭依頼は直接的に諏訪信仰を示すかどうかは微妙ですが、信玄公と韮崎の諏訪系神社の交渉を示すものではあると思います。
■ 諏訪南宮大神社
山梨県神社庁資料
笛吹市境川町寺尾4023
御祭神:建御名方命、金山彦命
旧社格:村社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は非授与の模様です。
山梨県神社庁の資料によると、治承年間(1177年~1181年)に沙弥厳尊が創建、その後曽根氏が代々造営し、天正年間までは二社別殿にて近在第一の社として栄えました。
天正以後に古宮の地より現社地に遷られました。
曽根氏は清和源氏・源清光公の子である曾禰(曽根)禅師厳尊を祖とし八代郡曾禰に拠った名族で、曽根内匠(昌世)は信玄公の側近、奥近習六人衆に数えられていますが、その嫡子・曽根周防守は永禄八年(1565年)の義信事件に加担した科で断罪されています。
曽根内匠(昌世)は武田家滅亡後も存命し、武田遺臣が家康公に提出した「天正壬午甲信諸士起請文」のまとめ役を果たしたとみられています。
武田家の信仰篤く、本殿扉には武田逍遙軒信網自筆寄進の松杉桜菊其外四季の草花を配した本殿扉絵があります。
信玄公の川中島戦祈願状一章は、本殿扉絵とともに市の文化財に指定されています。
■ 松原諏方神社
公式Web
長野県小海町大字豊里4319
御祭神:建御名方命、事代主命、下照比売命
旧社格:郷社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
天智天皇600年代の御宇の創立と伝わる中信・松原湖の古社で、上社と下社からなります。
信玄公の崇敬篤く、何度も信玄直筆の祈願文が届き祈願し出陣したと伝わります。
上社境内には、国の重要文化財「野ざらしの鐘」(県下最古)があり、「武田信昌(信玄公の曽祖父)が佐久地方に侵入した際の落合慈壽寺からの戦利品で、松原諏方神社に奉納した物です。」(社伝より)
■ 船形神社
山梨県神社庁資料
北杜市高根町長沢2606
御祭神:建御名方命
旧社格:郷社
※未参拝です。参拝次第、追記します。
北杜市高根町には当社と小池の船形神社があり、小池の船形神社は本務社の諏訪神社(北杜市高根町蔵原1844 )で拝受できるようですが(要事前連絡)、当社については御朱印情報は得られていません。
北杜市高根町あたりは、武田軍が信濃侵攻の折に通過したエリアですが、高根町長沢には信玄公が武運長久を祈願し神領二石八斗を寄進したという(山梨県神社庁資料)、船形神社が鎮座しています。
御祭神は建御名方命、以前は諏訪明神と呼ばれたとあり、この寄進も信玄公の諏訪明神への信仰を物語るものとみられています。
■【 浅間神社 】
■ 冨士御室浅間神社
公式Web




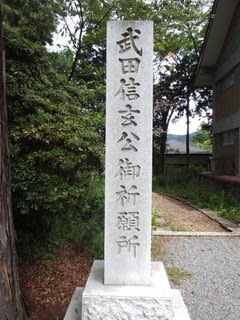
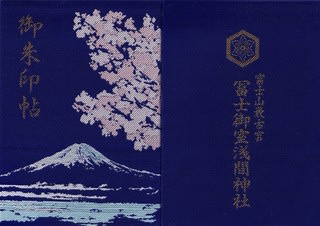
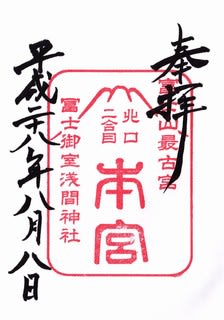
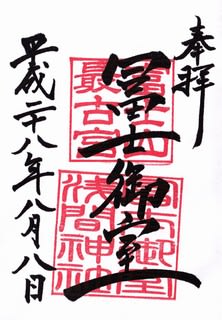
富士河口湖町勝山3951(里宮)
御祭神:木花開耶姫命
旧社格::県社 別表神社
授与所:里宮境内社務所
朱印揮毫:里宮:冨士御室 直書(筆書)
朱印揮毫:二合目本宮:北口二合目本宮 直書(筆書)
文武天皇三年(699年)藤原義忠により霊山富士二合目に奉斉され、富士山最古の社と伝わります。富士噴火のため焼失し、その後しばしば再興・増設されました。
天徳二年(958年)には、村上天皇により、氏子の祭祀の利便のため河口湖南岸に里宮が創建され、中世には修験道、近世には富士講と結びついて発展したとされます。
戦国期には武田家三代に渡り崇敬を受け、信玄公直筆の安産祈願文をはじめ多くの宝物がいまも所蔵されています。
信玄公直筆の安産祈願文は、信玄公が武田・北条・今川の三国同盟のため北条氏政に嫁がせた長女黄梅院の安産を願って、弘治三年(1557年)当社に奉納された願文です。
また、富士河口湖指定文化財の武田不動明王(木像)は、信玄公の目刻と伝わります。
黄梅院は母を三条夫人とし、天文二三年(1554年)12歳で北条氏康公の嫡男・氏政公に嫁ぎ、氏政公との間に北条家五代目当主、氏直公をもうけています。
永禄十一年(1568年)12月、信玄公の駿河侵攻を受けて三国同盟は破綻し、黄梅院は甲斐に送り返されました。
甲斐では甲府の大泉寺住職の安之玄穏を導師に出家したともいわれ、永禄十二年(1569年)6月17日、27歳で逝去されました。
信玄公は巨摩郡竜地(現・甲斐市龍地)に黄梅院の菩提寺黄梅院を建立して葬され、墓碑が現存しています。
夫の氏政公は武田氏と再び同盟した後の元亀二年(1571年)、箱根早雲寺の塔頭に同じく黄梅院を建立し、彼女の分骨を埋葬したと伝わります。
■ 北口本宮冨士浅間神社
公式Web






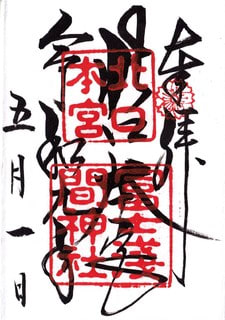



【写真 上(左)】 信玄公再建と伝わる「東宮本殿」
【写真 下(右)】 冨士登山道吉田口(北口)

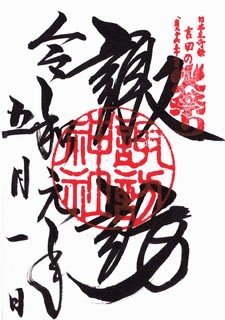
【写真 上(左)】 諏訪神社
【写真 下(右)】 諏訪神社の御朱印
富士吉田市上吉田5558
御祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神
旧社格::県社 別表神社
授与所:境内社務所
朱印揮毫:北口本宮冨士浅間神社 北口本宮 直書(筆書)
朱印揮毫:諏訪神社:諏訪 直書(筆書)
景行天皇四0年(西暦110年)、日本武尊ご東征の折、大塚丘に浅間大神と日本武尊をお祀りして創建と伝わります。
天応元年(781年)、富士山の噴火があり、甲斐国主の紀豊庭朝臣が卜占し、延暦七年(788年)、大塚丘の北方に社殿を建立。これが現社地で、浅間大神をお遷しし大塚丘には日本武尊をお祀りしました。
平安期以降、山岳信仰が広まり、各地で修験道が盛んになるにつれ当地でも富士講が組織されました。
大宝元年(701年)、初めての富士登山者は修験道の開祖とされる役小角(神変大菩薩)とされ、富士講の開祖とされる藤原角行師は天正五年(1577年)に登山されています。
貞応二年(1233年)北条義時公が造営し、永禄四年(1561年)に信玄公が再建されたという社殿「東宮本殿」が現存します。
信玄公は当社に安産や病気平癒を祈願するなど崇敬篤く、川中島の合戦の際には「東宮本殿」を再建され戦勝を祈願したと伝わります。
境内社の諏訪神社は「勧請された年代が明らかになっていない大変古いお社であり、この地域の元々の土地神とされています。当社周辺地域の字(あざ)名も「諏訪の森」と呼ばれており、さらに当社の祭典「吉田の火祭り」は諏訪神社の例祭でもあります。」(公式Webより)
こちらの諏訪神社と信玄公とのゆかりは、現在のところ情報がとれておりません。
信玄公は、調略活動に「透波」や「三ツ者」といった”忍びの者”を使いましたが、領内の山岳信仰の拠点の山伏や御師も登用したとされます。
吉田エリアの浅間神社は「富士御師」を組織していたので、単なる信玄公の祈願信仰の対象のみならず、調略活動とも切り離せないものだったかも知れません。
※甲斐国一宮 浅間神社については、Vol.2でご紹介しています。
■【 飯縄大権現 】
飯縄大権現とは、信濃国上水内郡の飯縄山(飯綱山)に対する山岳信仰の本尊で、神仏習合の尊格です。
戦勝の神として、足利義満公、細川政元公、上杉謙信公、武田信玄公など中世のそうそうたる武将に深く信仰されました。
飯縄山に本拠する修験は「飯縄修験」と呼ばれ、「千日太夫」と称する行者が代々その長を務めました。
信玄公の時代の「千日太夫」は、信玄公により安曇郡から移された仁科氏が務めていたとされます。
仁科氏は、信濃国安曇郡の名族で、さまざまな流れが伝わっています。
戦国期の当主で森城主、仁科盛能(道外)は信濃守護・小笠原長時と縁戚関係にあり、当初は小笠原氏や村上氏と連携して武田に抗していました。
天文十七年(1548年)の塩尻峠の戦い(信玄公と小笠原長時の戦い)の前に戦線離脱して小笠原氏と袂を分かち、天文十九年(1550年)(天文二二年とも)に仁科上野介を介して武田氏に臣従しています。(『高白斎記』)
以降、仁科氏は武田方に帰属しましたが、永禄四年(1561年)第四次川中島の戦いの折の一族の内紛などで上杉氏についたとする説もあります。
このあたりの動静は不詳のようですが、仁科盛能(道外)、盛政と家督は嗣がれ、盛政の代で仁科氏嫡流は断絶したという説があります。
信玄公は、この仁科氏の名跡を自らの五男に継がせました(仁科五郎盛信)。
なお、「仁科氏系譜」によると、仁科盛政の子、盛孝と盛清は信玄公の許しを経て「千日太夫」の養嗣となり、天正六年(1578年)に勝頼公から「仁科勘十郎」を世襲名として与えられ、神官として明治維新まで存続したとされます。
すこしく話がとびますが、仁科五郎盛信は、武田家の戦いを語るうえで欠かせない人物なのでご紹介します。
仁科五郎盛信は、弘治三年(1557年)、母を油川夫人とし信玄公五男として生まれました。
油川氏は武田氏一門で、油川夫人は油川信守の息女とされます。
信玄公の側室として嫁し、盛信のほか葛山信貞・松姫(織田信忠婚約者)・菊姫(上杉景勝正室)をもうけました。
永禄四年(1561年)、信玄公の意向を受けて仁科氏の名跡を継ぎ、仁科氏の通字である「盛」の偏諱を受け継いで、勝頼公の時代も仁科一族を率いて信越国境を守りました。
勝頼公と織田・徳川勢力との対立が激化すると、居城の安曇・森城のほかに伊那の高遠城主を兼任しました。
天正十年(1582年)2月、織田軍による甲州征伐が始まり、盛信が守る高遠城は織田勢五万の大軍に包囲されました。
攻将、織田信忠は盛信に降伏を勧告しましたが、盛信はこれを拒否。高遠城は織田軍の猛攻を受け、盛信は奮闘の後、自刃したと伝わります。
享年26。墓所は高遠の桂泉院、高遠城鎮護の寺としても伝わる古刹です。
武田家の終焉に際して一族・重臣の逃亡や寝返りが続くなか、高遠城において最後まで奮戦、討死した盛信の戦いは、武田武士の気概を示すものとしていまに伝えられています。
信玄公の飯縄信仰を伝える史跡として、長野市富田の飯縄神社(皇足穂命神社)があります。
全国に祭祀されている飯縄神社の惣社で、奥宮は飯縄山頂上に鎮座します。
公式Webに詳しい由緒書が掲載されていますので、武田家関連の箇所を抜粋引用します。
「飯縄大明神は代々千日大夫と通称した修験者によって奉仕されていました。戦国争乱中の武将からも厚く信仰され、弘治三年(1557年)芋井の葛山城(長野市)を攻略した武田晴信(信玄)は、飯縄大明神の神官千日大夫に対し安堵状を与え、武田家の武運長久を祈らせました。また功績によって、元亀元年(1570年)には、芋井を中心に沢山の所領を寄進しております。また伝承では元亀頃飯縄神社里宮を荒安村に造営したといわれています。天正八年(1580年)閏三月、武田勝頼は千日大夫あての朱印状をもって、里宮の造営と遷宮を行っております。このようにして飯縄大明神の里宮が荒安村にでき、千日大夫もまた居を据え、門前百姓も定まりました。」
■ 飯縄神社(皇足穂命神社)
公式Web
長野県長野市富田380
御祭神:大己貴命、事代主命、建御名方命、金山彦命
旧社格:式内社(小) 郷社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は奥宮のものも授与されているようですが、期間限定とのWeb情報があります。
■ 金剛山 普門寺
公式Web
相模原市緑区中沢200
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:武相卯歳四十八観音霊場第25番
※授与されている御朱印は武相卯歳四十八観音霊場第25番のみとのこと。(御開帳時以外も授与。)
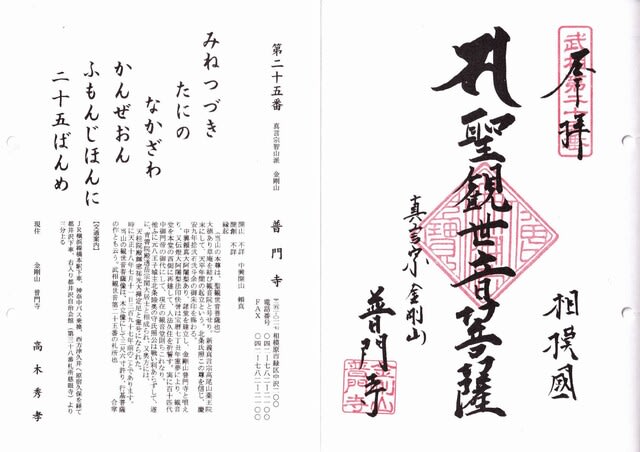
〔武相卯歳四十八観音霊場の御朱印(専用納経帳)〕
朱印尊格:聖観世音菩薩
札番:武相卯歳四十八観音霊場第25
・見開き綴じ込みのタイプです。右が御朱印、左が札所案内です。
中央上に聖観世音菩薩の種子「サ」の種子と「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「武相第二十三番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
相模原市中沢の普門寺も信玄公の飯縄信仰を伝える宝物を所蔵しています。
普門寺は天平年間(729〜748年)、行基により創立されたと伝わる古刹で、「額に武田菱の紋所を掲げ、信玄公に篤く尊信せられ、当山の栄隆を計らんがため信州飯綱山より持ち来たりて奉祀せらるると伝えられる『飯縄大権現』の尊像」(寺伝より)がお祀りされています。
地元中沢村の鎮守神の別頭寺院として、「中沢の普門寺」と称され親しまれてきたとのことです。


【写真 上(左)】 飯縄大権現堂の参道
【写真 下(右)】 飯縄大権現堂からの眺め
飯縄大権現堂は、観音堂左手奥の石段百四十七段を登った高みにあり、津久井湖方面の眺望が見事です。
このあたりは、甲斐の郡内から流れ下る相模川(桂川)が相模原に入るところで、戦略的にも要衝であった感じがします。


【写真 上(左)】 飯縄大権現堂
【写真 下(右)】 飯縄大権現堂の向拝部
御神木のスダジイなど、うっそうと繁る木立のもと、桁行四問、梁間三問の拝殿、一間四面の本殿からなる権現造銅板葺のお社が鎮座します。
拝殿の軒は深く、向拝柱は軒下に収まっています。
向拝脇の軒下には奉納された天狗と烏天狗のお面が掛けられ、正面桟唐戸の上には扁額(解読できず)が掲げられています。
飯縄大権現の尊像は、火焔を背負い白狐に乗られる飯縄大権現のお姿ですが、不動明王の顔立ちをされ、額には武田菱の紋所を掲げられています。
信玄公が信州飯綱山よりに持ち来たりて奉祀せらるると伝わり、信玄公の尊信篤かった尊像と伝わります。
戦の神、農業の神、繭の神として信仰され、一月十四日の例祭日には繭玉が奉納され、今日でも諸願成就の神様として信仰されています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 仁王門
普門寺は、相模原の西端、津久井湖の北側の複雑な地形の場所にあります。
山門から観音堂、本堂にかけては南傾の明るい境内です。
参道は玉垣に囲まれ、親柱は寺号標と「武相卯歳観音霊場 第二十五番目札所」の札所碑を兼ねています。
参道石段正面の仁王門は三百年前頃の造営で、三門一戸八脚の単層門で山号「金剛山」の扁額。
照りの強い堂々たる屋根の大棟には金色の武田菱が輝いています。
両脇間に御座す二体の仁王さまは、運派系の仏師、全慶の作といわれる力感あるお姿です。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 改修中の観音堂
仁王門の正面に観音堂、右手に本堂がありますが、観音堂は参拝時大がかりな改修中で仮囲いが組まれ、そばには近寄れませんでした。
掲示によると「本事業は2023年4月に行われる『第23回武相卯歳観音御開扉』に合わせた整備完了を目指します。」とのこと。
観音堂は市の登録有形文化財で、桁行三間、梁間四間(手前一間外陣、奥三間内陣)の宝形造で、見るからに観音堂の佇まい。
向拝は流れ向拝のように見えますが、一文字葺き簑甲と思われる端部の仕上げが印象に残ります。
水引虹梁両端に彫刻の木鼻と上に斗栱、中備に板蟇股、身舎斗間には間斗束らしきものが見えます。
観音堂御本尊の木造の聖観世音菩薩立像は、行基の作とも伝えられ、市の指定有形文化財です。
神奈川県に残るすぐれた藤原彫刻の一つともいわれ、「武相卯歳四十八観音霊場第25番」の札所本尊です。原則として卯歳の総開帳以外は秘仏とされているようです。
観音堂右手の本堂は桁行七間の寄棟造(入母屋造平入?)で、宝形造の観音堂とバランスのとれた対比を見せています。
御本尊の不動明王は江戸時代の作と伝えられ、背後山上の飯縄大権現の本地仏です。
庫裡玄関には武相観音霊場の汎用御朱印帳用の書置が用意されていましたが、わたしは専用納経帳で拝受しているので、奥から専用用紙のものをお出しいただきました。
なお、授与されている御朱印は、武相卯歳四十八観音霊場第25番のみとのことです。
■ 加賀美山 法善護国寺
公式Web

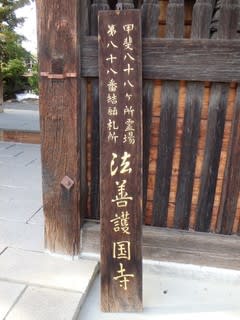

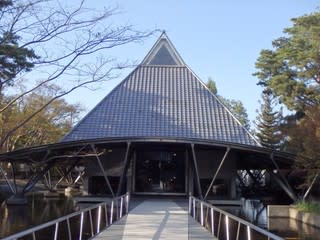

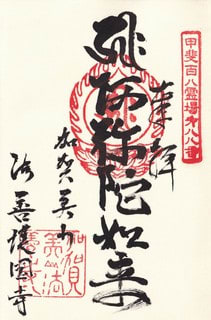
南アルプス市加賀美3509
高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第88番、甲斐八十八ヶ所霊場第88番
朱印尊格:阿弥陀如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第88番印判
・中央に御本尊、阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「阿弥陀如来」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第八八番」の札所印。左には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
若草町加賀美(現・南アルプス市加賀美)にある法善護国寺(法善寺)は武田八幡宮の元別当寺で、武田氏の始祖、武田信義公の弟加賀美遠光公の館跡とされ、甲斐源氏(信濃源氏)とのゆかり深い高野山真言宗の古刹です。
弘法大師霊場の甲斐八十八ヶ所霊場では第88番の結願所となっており、甲斐国内の真言宗で重要な地位を占めていたことが。
こちらには寺宝として信玄公の祈願文が所蔵されています。
これは元亀三年(1572年)4月の祈願文で、「今年一年間は越軍(上杉謙信軍)が、信濃、上野の二国に兵を動かすことのないように」という祈願で、本願成就の暁には「法華経百部の読経をもって飯縄大権現に献じます」と結ばれているそうです。
元亀三年は信玄公が西上の兵をあげられた年です。
過ぎる元亀二年(1571年)10月、信玄公は北条氏政公と和睦し、武田・北条の同盟が復活しました。
西上にあたっての信玄公の懸念は上杉の動き(出兵中に背後をつかれること)だけになり、そのような状況を受けての願文とみられています。
「本願成就」は「上洛」をさし、これを「信玄公上洛の願文」とみる説もあります。
大寺の風格をもち、本堂、不動明王殿のほか諸堂を擁します。
甲斐百八霊場第88番の札所で、御朱印は雰囲気のある庫裡で快く授与いただけました。
■【 戸隠大権現 】
■ 戸隠神社
公式Web
長野県長野市戸隠3690
御祭神:天手力雄命
旧社格:旧国幣小社
※以前参拝していますが、御朱印は未拝受です。参拝次第、追記します。
御神体を戸隠山とされると伝わる北信の古社。
ふるくから霊場として全国に知られ、平安末期末期の『梁塵秘抄』には「四方の霊験所は、伊豆の走井、信濃の戸隠、駿河の富士山、伯耆の大山…」とあります。
中世以降は、密教と神道の神仏習合の戸隠山 勧修院 顕光寺として隆盛、多くの修験者や参詣者を集めました。
戦国期には武田、上杉両軍の戦の影響が大きく、混乱を招いたと伝わります。
明治の神仏分離により、戸隠山 顕光寺は寺を分離して神社となりいまに至ります。
当社には信玄公直筆とされる「奉納祈願文(武田晴信願状)」が宝物として所蔵されています。
これは永禄元年(1558年)に奉納された「信濃一円の掌握と上杉の滅亡を戸隠中院大権現に祈願した願状」とされます。
■【 愛宕権現 】
愛宕権現は山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の神号で、イザナミを垂迹神、(勝軍)地蔵菩薩を本地仏とします。
明治の神仏分離前は、軍神、塞神、天狗信仰が習合した複雑な尊格で、戦国時代にはことに(本地?)将軍地蔵菩薩が軍神とされ信仰されていたようです。
愛宕権現の総本社、京都市右京区嵯峨愛宕町の愛宕神社(江戸期以前は白雲寺)はその若宮に火の神であるカグツチ(迦遇槌命、火之迦具土神)を祀り、火伏せ・防火の神として尊崇を集め、全国の愛宕権現も火伏せ・防火の神として祀られる例が多いです。
愛宕町の愛宕神社は明治以前には「愛宕権現(社)」「愛宕勝軍(大)権現」「愛宕勝軍地蔵権現」などと呼ばれていました。
創祀年代は不明ですが、信玄公の命令により、古府中の聖道小道路に躑躅ヶ崎館の鬼門守護のため祀り、相模国愛宕山から地蔵菩薩を招来して安置したことが始まりと伝えられています。(現地看板、山梨県神社庁史料)
なお、甲府の北に連なる山々は「愛宕山」と通称されますが、この愛宕山と愛宕神社の関連は定かではありません。
甲府五山の円光院には信玄公が信仰された「勝軍地蔵尊像」が奉安されており、信玄公の勝軍地蔵尊像信仰を示すものとされます。
躑躅ヶ崎館の鬼門守護とあわせ、信玄公の軍神としての信仰も受けていたことが伺われます。
■ 愛宕神社
山梨県神社庁資料





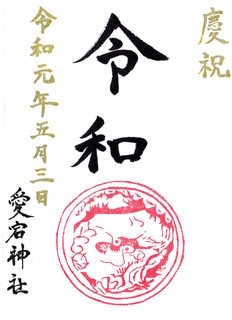
甲府市愛宕町134
御祭神:火之迦具土神、建御名方神、日本武尊
旧社格:村社
授与所:境内下社務所
朱印揮毫:令和 愛宕神社 直書(筆書) ※改元記念の御朱印
■【 三宝荒神 】
■ 真如山 良林寺 華光院

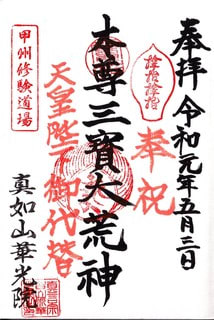

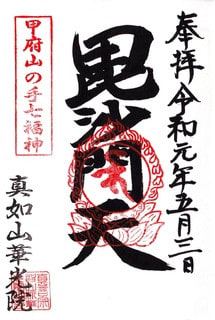
甲府市元紺屋町33
真言宗智山派 御本尊:三宝大荒神
札所:山の手七福神めぐり(毘沙門天)
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:本尊 三寶大荒神 直書(筆書)
・中央に種子の御寶印(火焔宝珠)。三寶荒神の種子は「バン」とみられますが、この御朱印の種子は「バン」ではありません。「バン」の荘厳体の「バーンク」にも見えますが、定かではありません。中央に「本尊 三寶大荒神」の揮毫。右上と中央の印判は不詳。左には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
令和に入って3日目の拝受だったので、「奉祝」「天皇陛下御代替」の揮毫があります。
左上の「甲州修験道場」の印判は、修験寺としての歴史を示すものです。
〔山の手七福神めぐり(毘沙門天)の御朱印〕
・中央に種子の御寶印(火焔宝珠)。毘沙門天の種子は「ベイ」で、この御朱印の種子は「ベイ」のようにも見えますが、定かではありません。中央に「毘沙門天」の揮毫。左上に「甲府山の手七福神」の印判。左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
由緒によると御本尊は弘法大師のお作と伝わる三宝荒神で、大永年中(1521年~1528年)に信虎公が荒神堂を建て、堂守に山伏を置いたのがはじまりとされています。
後に信玄公が現在地へ移され荒神堂と別当寺を建立、紀州根来寺の弘尊法印を別当寺住職に招いて祈願所とされたといいます。
三宝荒神は、火伏せの神、かまどの神として広く信仰される尊格で、仏教では守護神、護法神とされています。
神仏習合、山岳信仰、民間信仰の流れのなかでも広く信仰をあつめる尊格ということもあってか、すこぶる複雑な性格をもたれる尊格といわれます。
仏教では文殊菩薩、不動明王、歓喜天と同体(本地)とされる説があるので、(垂迹)神として祭祀されることがあります。
信玄公は荒神堂と別当寺を建立されたとありますから、神社(荒神堂)で三宝荒神を祀り、別に別当寺があったとみられますが、現在は華光院の御本尊が三宝荒神となっており、廃仏毀釈の折になにかしらの経緯があったのかもしれません。
信玄公は調略の名手であり、もっとも忍者を活用した戦国武将として知られています。
武田家の忍者(忍びの者)は、「透波」(すっぱ)と呼ばれ、天文十九年(1550年)の村上義清との戦さ「砥石崩れ」で透波を統括していた板垣信方と甘利虎泰の両名将を失ってのちに「三ツ者」(みツもの)として再編成されたといわれます。
間見、見方、目付の三つの任務を果たしたため「三ツ者」と呼んだとされます。
忍びの者は、各地を移動する僧侶や修験者に身を変えて(あるいは修験者・山伏を雇い入れて)活動したとされ、「透波」や「三ツ者」も例外ではなかったようです。
修験者や山伏は、山岳信仰や神仏習合と密接にかかわりますから、上で述べた、飯縄、戸隠、愛宕、そして三宝荒神などの尊格と信玄公の関係は、単なる祈願信仰の対象だけでなく、調略活動とも切り離せないものだったかも知れません。
まぁ、「透波」や「三ツ者」の詳細はほとんど残されていないので(残された時点で失格でしょう)、その裏付けは難しいのですが・・・。(『甲陽軍艦』には、「三ツ者」は信玄公の家臣である「諸国御使者衆」の配下にあったという記載があります。)
修験寺らしく、4月の第2日曜日には山伏による火渡り祈願が行われています。
太子堂は聖徳太子の像を祀ったもので、柳沢吉里が大和郡山に転封となったとき甲府城内より移したものです。現在は堂内に毘沙門天も祀られています。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
2020/04/30 UP
つづきです。
〔 信玄公の信仰 〕
つぎに信玄公が信仰されていた尊格という視点から、まとめてみたいと思います。
『甲陽軍鑑』には神社仏閣、尊格についての記述が数多くありますが、まだ読破していないので、現時点で情報がとれている寺院についてのみです。
わかり次第、追記します。
【 山梨岡神社 】
■ 山梨岡神社





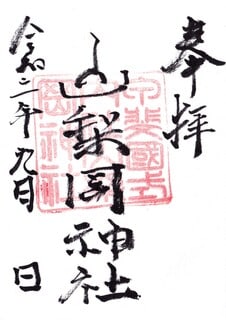
山梨県神社庁資料
笛吹市春日居町鎮目1096
御祭神:大山祇神、高龗神、別雷神
旧社格:式内社(小)論社、郷社
授与所:境内社務所(TELにてお伺い)
御朱印揮毫:山梨岡神社
山梨岡神社は古代に創建され、式内社論社に比定される甲斐国有数の古社です。
御祭神は、大山祇神、高龗神、別雷神の三柱で、当初は背後の御室山そのものが神として崇められていたともみられます。
山梨県神社庁資料には「人皇十代崇神天皇の御代、国内に疫病の流行や災害が多発し、これを憂ひた天皇の勅命により背後の御室山中腹に創祀される。後十三代成務天皇の御代に麓の山梨の群生林を切り開いて現在地に遷座され山梨岡神社と号す。」とあり、「山梨」の地名発祥の地と伝えられます。
旧社地には御室山古墳があります。
御室山で行われる山焼き「笈形焼」は、日本有数の規模をもつそうです。
「古くは山梨明神・山梨権現・日光権現とも称せられ武田家累代の祈願所として篤く崇敬された。」「古来より伝はる太々神楽は、武田信玄公出陣の際戦勝を祈願して奉納された神楽として伝へられてゐる。」(山梨県神社庁資料)とあり、武田家や信玄公の尊崇の篤さがうかがわれます。
武田軍出陣の際に戦勝祈願の社参がなされたという記録が複数あり、躑躅ヶ崎館の氏神とする史料もあるようです。
笛吹市の資料にも「武田家累代の氏神として崇拝され、武田信玄が出陣のたびに、戦勝祈願をしたといわれています。」とあります。
当社には、「虁(き)ノ神」という神獣の像が祀られています。
「状は牛の如く、身は蒼くて角がなく、足は一つ。」(『山海経』)
虁ノ神は、雷神、水神、魔除けの神として信仰を受け、徳川将軍家から夔ノ神の神札が大奥や御三家、旗本らに差し出されたという記録があり、夔ノ神信仰が広まったとみられています。
また、「山梨(やまなしの)岡」は、古来名所歌枕として知られ、
- 甲斐かねに咲にけらしな足引きの やまなし岡の山奈しの花 - 能因法師
という歌が残っています。
上の由緒を裏付けるように、信玄公ゆかりの宝物や行事がいまも残ります。
「武田家より譲り受けた『社参状』は、諏訪大社上社の神主あてに武田信玄が出した文書です。『穴山梅雪等が宝鈴を鳴らすために諏訪神社上社を訪れる』といった内容が書かれています。」「社参状とともに武田信玄から譲り受けた『椀』2個も保管されています。椀には武田菱(武田家の家紋)等が描かれています。」「『禁制を書いた板』には御室山でかってに木を切ったりする事を禁止すると書かれています。」(以上、笛吹市資料より)
また、当社に伝わる「太々神楽」(だいだいかぐら)二十四種の舞のうち、二十番目の「四剣の舞」は”信玄公出陣の神楽”とも称され、信玄公が戦さの勝利を願い奉納させた神楽だといわれています。(笛吹市資料)
国道140号からおくまった御室山の山裾に鎮座します。
参道右手に天然記念物「山梨岡神社のフジ」の藤棚。
参道橋を渡ると空気が変わり、式内社(論社)ならではの神さびた雰囲気が漂っています。
正面に桁行五間入母屋造桟瓦葺の拝殿、右手に神楽殿、その裏手には御室山信仰を思わせる一画があります。
本殿は室町時代末の建立とそれ国の重要文化財に指定されています。桁行二間の隅木入春日造杮葺、片流れ向拝付とのことです。
御朱印は境内社務所に連絡先が書いてあったので、TELするとご神職においでいただけ授与いただけました。
ご多忙のところ、ありがとうございました。
【 八幡神 (八幡大菩薩)】
八幡神は、源義家公が石清水八幡宮で元服して自らを八幡太郎と称されたことから清和源氏の崇敬が厚く、甲斐源氏の多くも氏神として祀りました。
Vol.1でご紹介した武田八幡宮や(甲斐國総社/宮前)八幡神社はその好例ですが、山梨市に鎮座される大井俣窪八幡神社もまた、武田家とのゆかりが深いお社です。
【 (大井俣)窪八幡神社 】
山梨県神社庁資料






公式Web
山梨市北654
御祭神:誉田別尊(中殿)、足仲彦尊(北殿)、息長足姫尊國魂大神命(南殿)
旧社格:式内社(小)論社、県社
元別当:八幡山 神宮寺(山梨市北)
授与所:境内社務所(不定期、事前問合せがベター)
朱印揮毫:大井俣神社 窪八幡宮 直書(筆書)〔令和元年5月拝受〕
朱印揮毫:大井俣 窪八幡神社 直書(筆書)〔平成28年9月拝受〕
社伝によると、清和天皇の勅願により貞観元年(859年)、宇佐神宮の八幡三神を音取川(今の笛吹川)の中島(大井俣)の地へ勧請、水害により現社地に遷座されました。
甲斐源氏、ことに本流武田家代々の氏神として崇敬され社殿が整えられました。
信虎公、信玄公の崇敬も篤く、信虎公は天文八年(1539年)の厄年に鳥居を寄進し、その際には信玄公が当社に代参されています。
天文十四年(1545年)には直筆とされる歌仙絵(板絵著色三十六歌仙図)を奉納、翌天文十五年には三条夫人も社参されています。
本殿の金箔は弘治三年(1557年)の川中島合戦に際して信玄公が捺させたものと伝わり、木造狛犬六駆、鐘楼も信玄公の寄進・再建によるものとされています。
当社は文化財の宝庫として知られています。
・一の鳥居(室町後期、木造両部鳥居、重文、現存する国内最古の木造鳥居)
・神門(室町後期、四脚門切妻造檜皮葺、重文)
・摂社若宮八幡神社本殿(室町中期、三間社流造檜皮葺、重文)
・拝殿(室町後期、桁行十一間切妻造檜皮葺、重文)
・本殿(室町後期、桁行十一間流造檜皮葺、重文)
とくに本殿は三間社流造の三社を間に一間をおいて横に連結した形状で、わが国に現存する最大の流造本殿とみられているそうです。
---------------------------------------------
八幡神が武田軍の軍陣で祈願された例として、「三方ヶ原の戦い」前の信玄公自作とされる歌が知られています。
元亀三年(1572年)秋、西上の軍を起こした信玄公は伊那口から徳川領の遠江に侵入し、徳川方の本多・内藤偵察隊を「一言坂の戦い」で一蹴。
つづいて要衝・二俣城を落とし、家康公が拠る浜松城を素通りして西上をつづけるかの動きをとりました。
『甲陽軍鑑』によると、二俣城進発の際、信玄公はつぎのような歌を八幡神に捧げたとされています。
- ただたのめたのむ八幡の神風に 浜松が松は倒れざらめや -
武田軍の浜松城攻めを想定していた家康公は、城の目の前を敵軍が通過するという事態に直面しました。
浜松城籠城を唱えた家臣もいましたが、家康公は「たとへば人あってわが城内を踏通らむに、咎めであるべきや、いかに武田か猛勢なればとて、城下を蹂躙しておし行くを、居ながら傍観すべき理なし、弓箭の恥辱これに過ぎじ、後日に至り、彼は敵に枕上を踏越されしに、起きもあがらでありし臆病者よと、世にも人にも嘲られむこそ、後代までの恥辱なれ、勝敗は天にあり、兎にも角にも戦をせではあるべからず」との名言を発し、出撃を命じたと伝わります。(→東照宮御実紀附録巻二(国会図書館資料のP.28))
三方ヶ原の台地にのぼった武田軍は、徳川・織田連合軍の進撃を察知すると、やにわに軍の向きを変え、悠々と魚鱗の陣を敷いて徳川・織田連合軍を迎え撃ったとされます。
連合軍は武田軍に撃破され、浜松城に退いたというのが、家康公の数少ない敗戦といわれる「三方ヶ原の戦い」です。
「徳川家康三方ヶ原戦役画像(「顰(しかみ)像」)」(徳川美術館所蔵)は、家康公が三方ヶ原の敗戦直後に自戒のため描かせたとする伝承があります。
「慢心を戒めるために敗戦時の自身の姿を描かせ、自戒のために座右に置いた」という人生訓は、この絵とともに後世に広く伝えられ、信玄公の戦さの強さもまた、人口に膾炙することとなりました。
信玄公ゆかりの八幡神社は県内外にまだまだ事例があると思いますので、わかり次第追記します。
【 諏訪明神 】
信玄公の諏訪明神信仰をもっともよく示すのは、武田家の重宝であり信玄軍の軍旗である「諏訪神号旗」(御旗)でしょう。
「諏訪神号旗」は、「孫子の旗」とともに武田の軍旗として用いられたとされ、「諏訪法性旗」「諏訪明神旗」「諏訪梵字旗」と呼称される3種の旗の総称です。
なかでも「諏訪法性旗」は信玄公直筆と伝わります。
現在、「諏訪神号旗」甲州市塩山の雲峰寺、恵林寺などに所蔵されており、詳細は各々の記事をご参照願います。
側室とされた諏訪御料人は、諏訪大社上社の大祝、諏訪頼重公の息女であり、諏訪御料人が産んだ世継ぎの勝頼公もこの血筋を継いで、武田家の家督相続以前は諏訪四郎勝頼と称されました。
信玄公と諏訪大社大祝家はこのような結びつきもあります。
Web上では、信玄公が諏訪大社上社に度々戦勝祈願をしたという記事が複数みつかりますが、いまのところ史料が見当たらないので、確認できたら追記します。
(諏訪大社の御朱印は、別編の「武田勝頼公編」でのご紹介を考えているので、ここではふれません。)
2019年5月、長野県立歴史館は永禄十年(1567年)、信玄公が諏訪大社内にあった寺院に宛てて新たな寄付を約束した公的な文書(朱印状)の入手を公表しています。
寺院名の確認ができないのですが、この寺院が諏訪大社と深い関係にあるとすると、信玄公のお諏訪様信仰を間接的に裏付けるものになるかと思います。
■ 白華山 慈雲寺
公式Web




長野県諏訪郡下諏訪町東町中606
臨済宗妙心寺派 御本尊:千手千眼観世音菩薩
札所:伊那諏訪八十八ヶ所第18番、諏訪郡百番霊場西21番
朱印尊格:圓通閣 書置(筆書)
札番:なし
・中央に御本尊、千手千眼観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「圓通閣」の揮毫。
右上に扁額にちなむ?印。左には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
正安二年(1300年)、諏訪大社下社大祝金刺満貞の願意を受けて、来朝僧一山一寧国師により開山された下諏訪の名刹で、「下社春宮の鎮護を目的に建てられた鬼門寺」という説もあります。
寺伝によると、天文六年(1537年)の火災の折、当時の住職天桂玄長禅師は甲斐の恵林寺住職も兼務され信玄公の帰依を受けており、その縁により信玄公の支援復興がなされたため、信玄公が当寺の中興開基とされています。
また、信玄公が川中島合戦に向かう際に当寺を訪れ、矢を除ける念力のある石「矢除石」の御札を授かったという伝承もあります。
信玄公と諏訪大社との間接的なつながりを示す寺院とみられます。
■ 南宮大神社
山梨県神社庁資料


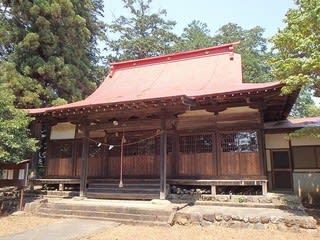
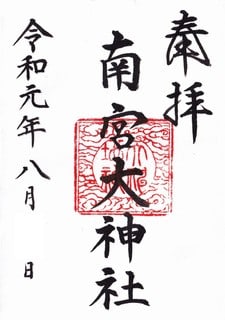
韮崎市大草町上條東割790
御祭神:大己貴命、事代主命、建御名方命、金山彦命
旧社格:郷社
授与所:若宮八幡宮社務所(韮崎市若宮1-4-14)
朱印揮毫:南宮大神社 直書(筆書)
韮崎市大草町鎮座の南宮大神社も信玄公ゆかりの神社とされています。
現地掲示の由緒書によると「諏訪明神すなわち建御名方命を主祭神とし、大己貴命・事代主命・金山彦命を配祀する」「社記によれば、新羅三郎義光が甲斐任国の時崇敬して社壇を造営したといい、武田太郎信義、その嫡男一条次郎忠頼も篤く崇敬し、武田一条氏が武川地方に封ぜられると、当社を産土神として崇敬し、その支族の武川衆諸氏も協力して当社に奉仕した史料を伝えている。また武田信玄は当社の禰宜(神主)に対し、 府中八幡宮に二日二晩参篭し、武田家武運長久と領内安穏の祈祷をすることを命じた。」
府中八幡宮は甲斐の総社的な神社で、こちらへの参篭依頼は直接的に諏訪信仰を示すかどうかは微妙ですが、信玄公と韮崎の諏訪系神社の交渉を示すものではあると思います。
■ 諏訪南宮大神社
山梨県神社庁資料
笛吹市境川町寺尾4023
御祭神:建御名方命、金山彦命
旧社格:村社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は非授与の模様です。
山梨県神社庁の資料によると、治承年間(1177年~1181年)に沙弥厳尊が創建、その後曽根氏が代々造営し、天正年間までは二社別殿にて近在第一の社として栄えました。
天正以後に古宮の地より現社地に遷られました。
曽根氏は清和源氏・源清光公の子である曾禰(曽根)禅師厳尊を祖とし八代郡曾禰に拠った名族で、曽根内匠(昌世)は信玄公の側近、奥近習六人衆に数えられていますが、その嫡子・曽根周防守は永禄八年(1565年)の義信事件に加担した科で断罪されています。
曽根内匠(昌世)は武田家滅亡後も存命し、武田遺臣が家康公に提出した「天正壬午甲信諸士起請文」のまとめ役を果たしたとみられています。
武田家の信仰篤く、本殿扉には武田逍遙軒信網自筆寄進の松杉桜菊其外四季の草花を配した本殿扉絵があります。
信玄公の川中島戦祈願状一章は、本殿扉絵とともに市の文化財に指定されています。
■ 松原諏方神社
公式Web
長野県小海町大字豊里4319
御祭神:建御名方命、事代主命、下照比売命
旧社格:郷社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
天智天皇600年代の御宇の創立と伝わる中信・松原湖の古社で、上社と下社からなります。
信玄公の崇敬篤く、何度も信玄直筆の祈願文が届き祈願し出陣したと伝わります。
上社境内には、国の重要文化財「野ざらしの鐘」(県下最古)があり、「武田信昌(信玄公の曽祖父)が佐久地方に侵入した際の落合慈壽寺からの戦利品で、松原諏方神社に奉納した物です。」(社伝より)
■ 船形神社
山梨県神社庁資料
北杜市高根町長沢2606
御祭神:建御名方命
旧社格:郷社
※未参拝です。参拝次第、追記します。
北杜市高根町には当社と小池の船形神社があり、小池の船形神社は本務社の諏訪神社(北杜市高根町蔵原1844 )で拝受できるようですが(要事前連絡)、当社については御朱印情報は得られていません。
北杜市高根町あたりは、武田軍が信濃侵攻の折に通過したエリアですが、高根町長沢には信玄公が武運長久を祈願し神領二石八斗を寄進したという(山梨県神社庁資料)、船形神社が鎮座しています。
御祭神は建御名方命、以前は諏訪明神と呼ばれたとあり、この寄進も信玄公の諏訪明神への信仰を物語るものとみられています。
■【 浅間神社 】
■ 冨士御室浅間神社
公式Web




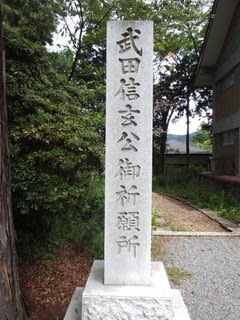
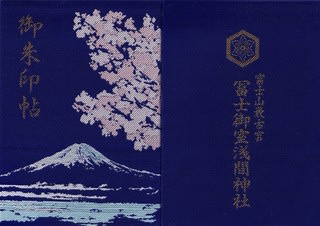
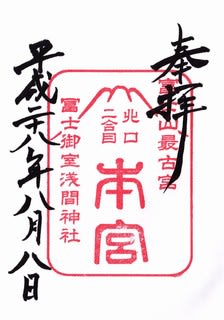
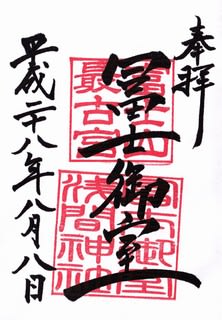
富士河口湖町勝山3951(里宮)
御祭神:木花開耶姫命
旧社格::県社 別表神社
授与所:里宮境内社務所
朱印揮毫:里宮:冨士御室 直書(筆書)
朱印揮毫:二合目本宮:北口二合目本宮 直書(筆書)
文武天皇三年(699年)藤原義忠により霊山富士二合目に奉斉され、富士山最古の社と伝わります。富士噴火のため焼失し、その後しばしば再興・増設されました。
天徳二年(958年)には、村上天皇により、氏子の祭祀の利便のため河口湖南岸に里宮が創建され、中世には修験道、近世には富士講と結びついて発展したとされます。
戦国期には武田家三代に渡り崇敬を受け、信玄公直筆の安産祈願文をはじめ多くの宝物がいまも所蔵されています。
信玄公直筆の安産祈願文は、信玄公が武田・北条・今川の三国同盟のため北条氏政に嫁がせた長女黄梅院の安産を願って、弘治三年(1557年)当社に奉納された願文です。
また、富士河口湖指定文化財の武田不動明王(木像)は、信玄公の目刻と伝わります。
黄梅院は母を三条夫人とし、天文二三年(1554年)12歳で北条氏康公の嫡男・氏政公に嫁ぎ、氏政公との間に北条家五代目当主、氏直公をもうけています。
永禄十一年(1568年)12月、信玄公の駿河侵攻を受けて三国同盟は破綻し、黄梅院は甲斐に送り返されました。
甲斐では甲府の大泉寺住職の安之玄穏を導師に出家したともいわれ、永禄十二年(1569年)6月17日、27歳で逝去されました。
信玄公は巨摩郡竜地(現・甲斐市龍地)に黄梅院の菩提寺黄梅院を建立して葬され、墓碑が現存しています。
夫の氏政公は武田氏と再び同盟した後の元亀二年(1571年)、箱根早雲寺の塔頭に同じく黄梅院を建立し、彼女の分骨を埋葬したと伝わります。
■ 北口本宮冨士浅間神社
公式Web






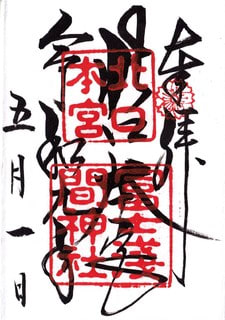



【写真 上(左)】 信玄公再建と伝わる「東宮本殿」
【写真 下(右)】 冨士登山道吉田口(北口)

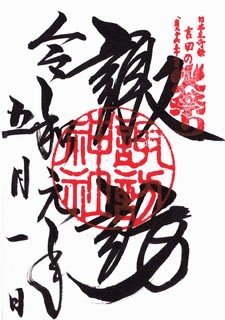
【写真 上(左)】 諏訪神社
【写真 下(右)】 諏訪神社の御朱印
富士吉田市上吉田5558
御祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神
旧社格::県社 別表神社
授与所:境内社務所
朱印揮毫:北口本宮冨士浅間神社 北口本宮 直書(筆書)
朱印揮毫:諏訪神社:諏訪 直書(筆書)
景行天皇四0年(西暦110年)、日本武尊ご東征の折、大塚丘に浅間大神と日本武尊をお祀りして創建と伝わります。
天応元年(781年)、富士山の噴火があり、甲斐国主の紀豊庭朝臣が卜占し、延暦七年(788年)、大塚丘の北方に社殿を建立。これが現社地で、浅間大神をお遷しし大塚丘には日本武尊をお祀りしました。
平安期以降、山岳信仰が広まり、各地で修験道が盛んになるにつれ当地でも富士講が組織されました。
大宝元年(701年)、初めての富士登山者は修験道の開祖とされる役小角(神変大菩薩)とされ、富士講の開祖とされる藤原角行師は天正五年(1577年)に登山されています。
貞応二年(1233年)北条義時公が造営し、永禄四年(1561年)に信玄公が再建されたという社殿「東宮本殿」が現存します。
信玄公は当社に安産や病気平癒を祈願するなど崇敬篤く、川中島の合戦の際には「東宮本殿」を再建され戦勝を祈願したと伝わります。
境内社の諏訪神社は「勧請された年代が明らかになっていない大変古いお社であり、この地域の元々の土地神とされています。当社周辺地域の字(あざ)名も「諏訪の森」と呼ばれており、さらに当社の祭典「吉田の火祭り」は諏訪神社の例祭でもあります。」(公式Webより)
こちらの諏訪神社と信玄公とのゆかりは、現在のところ情報がとれておりません。
信玄公は、調略活動に「透波」や「三ツ者」といった”忍びの者”を使いましたが、領内の山岳信仰の拠点の山伏や御師も登用したとされます。
吉田エリアの浅間神社は「富士御師」を組織していたので、単なる信玄公の祈願信仰の対象のみならず、調略活動とも切り離せないものだったかも知れません。
※甲斐国一宮 浅間神社については、Vol.2でご紹介しています。
■【 飯縄大権現 】
飯縄大権現とは、信濃国上水内郡の飯縄山(飯綱山)に対する山岳信仰の本尊で、神仏習合の尊格です。
戦勝の神として、足利義満公、細川政元公、上杉謙信公、武田信玄公など中世のそうそうたる武将に深く信仰されました。
飯縄山に本拠する修験は「飯縄修験」と呼ばれ、「千日太夫」と称する行者が代々その長を務めました。
信玄公の時代の「千日太夫」は、信玄公により安曇郡から移された仁科氏が務めていたとされます。
仁科氏は、信濃国安曇郡の名族で、さまざまな流れが伝わっています。
戦国期の当主で森城主、仁科盛能(道外)は信濃守護・小笠原長時と縁戚関係にあり、当初は小笠原氏や村上氏と連携して武田に抗していました。
天文十七年(1548年)の塩尻峠の戦い(信玄公と小笠原長時の戦い)の前に戦線離脱して小笠原氏と袂を分かち、天文十九年(1550年)(天文二二年とも)に仁科上野介を介して武田氏に臣従しています。(『高白斎記』)
以降、仁科氏は武田方に帰属しましたが、永禄四年(1561年)第四次川中島の戦いの折の一族の内紛などで上杉氏についたとする説もあります。
このあたりの動静は不詳のようですが、仁科盛能(道外)、盛政と家督は嗣がれ、盛政の代で仁科氏嫡流は断絶したという説があります。
信玄公は、この仁科氏の名跡を自らの五男に継がせました(仁科五郎盛信)。
なお、「仁科氏系譜」によると、仁科盛政の子、盛孝と盛清は信玄公の許しを経て「千日太夫」の養嗣となり、天正六年(1578年)に勝頼公から「仁科勘十郎」を世襲名として与えられ、神官として明治維新まで存続したとされます。
すこしく話がとびますが、仁科五郎盛信は、武田家の戦いを語るうえで欠かせない人物なのでご紹介します。
仁科五郎盛信は、弘治三年(1557年)、母を油川夫人とし信玄公五男として生まれました。
油川氏は武田氏一門で、油川夫人は油川信守の息女とされます。
信玄公の側室として嫁し、盛信のほか葛山信貞・松姫(織田信忠婚約者)・菊姫(上杉景勝正室)をもうけました。
永禄四年(1561年)、信玄公の意向を受けて仁科氏の名跡を継ぎ、仁科氏の通字である「盛」の偏諱を受け継いで、勝頼公の時代も仁科一族を率いて信越国境を守りました。
勝頼公と織田・徳川勢力との対立が激化すると、居城の安曇・森城のほかに伊那の高遠城主を兼任しました。
天正十年(1582年)2月、織田軍による甲州征伐が始まり、盛信が守る高遠城は織田勢五万の大軍に包囲されました。
攻将、織田信忠は盛信に降伏を勧告しましたが、盛信はこれを拒否。高遠城は織田軍の猛攻を受け、盛信は奮闘の後、自刃したと伝わります。
享年26。墓所は高遠の桂泉院、高遠城鎮護の寺としても伝わる古刹です。
武田家の終焉に際して一族・重臣の逃亡や寝返りが続くなか、高遠城において最後まで奮戦、討死した盛信の戦いは、武田武士の気概を示すものとしていまに伝えられています。
信玄公の飯縄信仰を伝える史跡として、長野市富田の飯縄神社(皇足穂命神社)があります。
全国に祭祀されている飯縄神社の惣社で、奥宮は飯縄山頂上に鎮座します。
公式Webに詳しい由緒書が掲載されていますので、武田家関連の箇所を抜粋引用します。
「飯縄大明神は代々千日大夫と通称した修験者によって奉仕されていました。戦国争乱中の武将からも厚く信仰され、弘治三年(1557年)芋井の葛山城(長野市)を攻略した武田晴信(信玄)は、飯縄大明神の神官千日大夫に対し安堵状を与え、武田家の武運長久を祈らせました。また功績によって、元亀元年(1570年)には、芋井を中心に沢山の所領を寄進しております。また伝承では元亀頃飯縄神社里宮を荒安村に造営したといわれています。天正八年(1580年)閏三月、武田勝頼は千日大夫あての朱印状をもって、里宮の造営と遷宮を行っております。このようにして飯縄大明神の里宮が荒安村にでき、千日大夫もまた居を据え、門前百姓も定まりました。」
■ 飯縄神社(皇足穂命神社)
公式Web
長野県長野市富田380
御祭神:大己貴命、事代主命、建御名方命、金山彦命
旧社格:式内社(小) 郷社
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は奥宮のものも授与されているようですが、期間限定とのWeb情報があります。
■ 金剛山 普門寺
公式Web
相模原市緑区中沢200
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:武相卯歳四十八観音霊場第25番
※授与されている御朱印は武相卯歳四十八観音霊場第25番のみとのこと。(御開帳時以外も授与。)
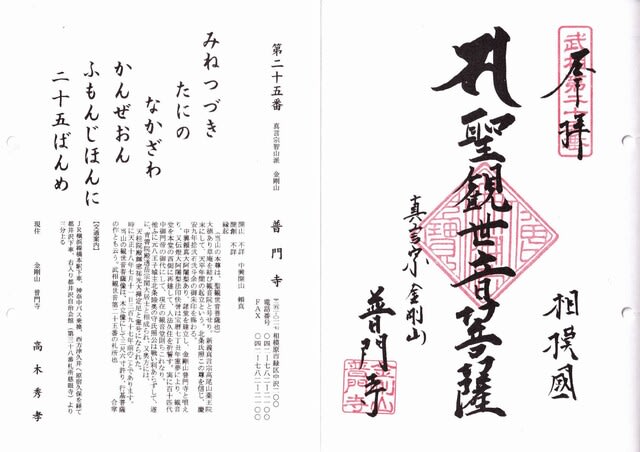
〔武相卯歳四十八観音霊場の御朱印(専用納経帳)〕
朱印尊格:聖観世音菩薩
札番:武相卯歳四十八観音霊場第25
・見開き綴じ込みのタイプです。右が御朱印、左が札所案内です。
中央上に聖観世音菩薩の種子「サ」の種子と「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「武相第二十三番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
相模原市中沢の普門寺も信玄公の飯縄信仰を伝える宝物を所蔵しています。
普門寺は天平年間(729〜748年)、行基により創立されたと伝わる古刹で、「額に武田菱の紋所を掲げ、信玄公に篤く尊信せられ、当山の栄隆を計らんがため信州飯綱山より持ち来たりて奉祀せらるると伝えられる『飯縄大権現』の尊像」(寺伝より)がお祀りされています。
地元中沢村の鎮守神の別頭寺院として、「中沢の普門寺」と称され親しまれてきたとのことです。


【写真 上(左)】 飯縄大権現堂の参道
【写真 下(右)】 飯縄大権現堂からの眺め
飯縄大権現堂は、観音堂左手奥の石段百四十七段を登った高みにあり、津久井湖方面の眺望が見事です。
このあたりは、甲斐の郡内から流れ下る相模川(桂川)が相模原に入るところで、戦略的にも要衝であった感じがします。


【写真 上(左)】 飯縄大権現堂
【写真 下(右)】 飯縄大権現堂の向拝部
御神木のスダジイなど、うっそうと繁る木立のもと、桁行四問、梁間三問の拝殿、一間四面の本殿からなる権現造銅板葺のお社が鎮座します。
拝殿の軒は深く、向拝柱は軒下に収まっています。
向拝脇の軒下には奉納された天狗と烏天狗のお面が掛けられ、正面桟唐戸の上には扁額(解読できず)が掲げられています。
飯縄大権現の尊像は、火焔を背負い白狐に乗られる飯縄大権現のお姿ですが、不動明王の顔立ちをされ、額には武田菱の紋所を掲げられています。
信玄公が信州飯綱山よりに持ち来たりて奉祀せらるると伝わり、信玄公の尊信篤かった尊像と伝わります。
戦の神、農業の神、繭の神として信仰され、一月十四日の例祭日には繭玉が奉納され、今日でも諸願成就の神様として信仰されています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 仁王門
普門寺は、相模原の西端、津久井湖の北側の複雑な地形の場所にあります。
山門から観音堂、本堂にかけては南傾の明るい境内です。
参道は玉垣に囲まれ、親柱は寺号標と「武相卯歳観音霊場 第二十五番目札所」の札所碑を兼ねています。
参道石段正面の仁王門は三百年前頃の造営で、三門一戸八脚の単層門で山号「金剛山」の扁額。
照りの強い堂々たる屋根の大棟には金色の武田菱が輝いています。
両脇間に御座す二体の仁王さまは、運派系の仏師、全慶の作といわれる力感あるお姿です。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 改修中の観音堂
仁王門の正面に観音堂、右手に本堂がありますが、観音堂は参拝時大がかりな改修中で仮囲いが組まれ、そばには近寄れませんでした。
掲示によると「本事業は2023年4月に行われる『第23回武相卯歳観音御開扉』に合わせた整備完了を目指します。」とのこと。
観音堂は市の登録有形文化財で、桁行三間、梁間四間(手前一間外陣、奥三間内陣)の宝形造で、見るからに観音堂の佇まい。
向拝は流れ向拝のように見えますが、一文字葺き簑甲と思われる端部の仕上げが印象に残ります。
水引虹梁両端に彫刻の木鼻と上に斗栱、中備に板蟇股、身舎斗間には間斗束らしきものが見えます。
観音堂御本尊の木造の聖観世音菩薩立像は、行基の作とも伝えられ、市の指定有形文化財です。
神奈川県に残るすぐれた藤原彫刻の一つともいわれ、「武相卯歳四十八観音霊場第25番」の札所本尊です。原則として卯歳の総開帳以外は秘仏とされているようです。
観音堂右手の本堂は桁行七間の寄棟造(入母屋造平入?)で、宝形造の観音堂とバランスのとれた対比を見せています。
御本尊の不動明王は江戸時代の作と伝えられ、背後山上の飯縄大権現の本地仏です。
庫裡玄関には武相観音霊場の汎用御朱印帳用の書置が用意されていましたが、わたしは専用納経帳で拝受しているので、奥から専用用紙のものをお出しいただきました。
なお、授与されている御朱印は、武相卯歳四十八観音霊場第25番のみとのことです。
■ 加賀美山 法善護国寺
公式Web

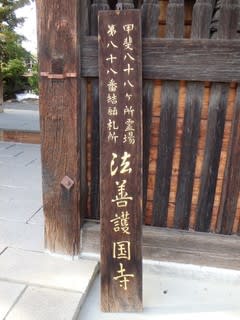

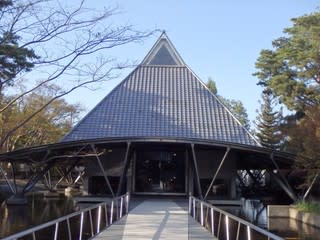

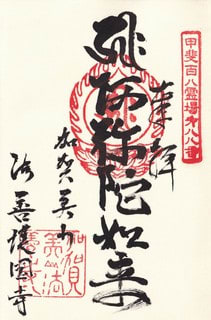
南アルプス市加賀美3509
高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第88番、甲斐八十八ヶ所霊場第88番
朱印尊格:阿弥陀如来 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第88番印判
・中央に御本尊、阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「阿弥陀如来」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第八八番」の札所印。左には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
若草町加賀美(現・南アルプス市加賀美)にある法善護国寺(法善寺)は武田八幡宮の元別当寺で、武田氏の始祖、武田信義公の弟加賀美遠光公の館跡とされ、甲斐源氏(信濃源氏)とのゆかり深い高野山真言宗の古刹です。
弘法大師霊場の甲斐八十八ヶ所霊場では第88番の結願所となっており、甲斐国内の真言宗で重要な地位を占めていたことが。
こちらには寺宝として信玄公の祈願文が所蔵されています。
これは元亀三年(1572年)4月の祈願文で、「今年一年間は越軍(上杉謙信軍)が、信濃、上野の二国に兵を動かすことのないように」という祈願で、本願成就の暁には「法華経百部の読経をもって飯縄大権現に献じます」と結ばれているそうです。
元亀三年は信玄公が西上の兵をあげられた年です。
過ぎる元亀二年(1571年)10月、信玄公は北条氏政公と和睦し、武田・北条の同盟が復活しました。
西上にあたっての信玄公の懸念は上杉の動き(出兵中に背後をつかれること)だけになり、そのような状況を受けての願文とみられています。
「本願成就」は「上洛」をさし、これを「信玄公上洛の願文」とみる説もあります。
大寺の風格をもち、本堂、不動明王殿のほか諸堂を擁します。
甲斐百八霊場第88番の札所で、御朱印は雰囲気のある庫裡で快く授与いただけました。
■【 戸隠大権現 】
■ 戸隠神社
公式Web
長野県長野市戸隠3690
御祭神:天手力雄命
旧社格:旧国幣小社
※以前参拝していますが、御朱印は未拝受です。参拝次第、追記します。
御神体を戸隠山とされると伝わる北信の古社。
ふるくから霊場として全国に知られ、平安末期末期の『梁塵秘抄』には「四方の霊験所は、伊豆の走井、信濃の戸隠、駿河の富士山、伯耆の大山…」とあります。
中世以降は、密教と神道の神仏習合の戸隠山 勧修院 顕光寺として隆盛、多くの修験者や参詣者を集めました。
戦国期には武田、上杉両軍の戦の影響が大きく、混乱を招いたと伝わります。
明治の神仏分離により、戸隠山 顕光寺は寺を分離して神社となりいまに至ります。
当社には信玄公直筆とされる「奉納祈願文(武田晴信願状)」が宝物として所蔵されています。
これは永禄元年(1558年)に奉納された「信濃一円の掌握と上杉の滅亡を戸隠中院大権現に祈願した願状」とされます。
■【 愛宕権現 】
愛宕権現は山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の神号で、イザナミを垂迹神、(勝軍)地蔵菩薩を本地仏とします。
明治の神仏分離前は、軍神、塞神、天狗信仰が習合した複雑な尊格で、戦国時代にはことに(本地?)将軍地蔵菩薩が軍神とされ信仰されていたようです。
愛宕権現の総本社、京都市右京区嵯峨愛宕町の愛宕神社(江戸期以前は白雲寺)はその若宮に火の神であるカグツチ(迦遇槌命、火之迦具土神)を祀り、火伏せ・防火の神として尊崇を集め、全国の愛宕権現も火伏せ・防火の神として祀られる例が多いです。
愛宕町の愛宕神社は明治以前には「愛宕権現(社)」「愛宕勝軍(大)権現」「愛宕勝軍地蔵権現」などと呼ばれていました。
創祀年代は不明ですが、信玄公の命令により、古府中の聖道小道路に躑躅ヶ崎館の鬼門守護のため祀り、相模国愛宕山から地蔵菩薩を招来して安置したことが始まりと伝えられています。(現地看板、山梨県神社庁史料)
なお、甲府の北に連なる山々は「愛宕山」と通称されますが、この愛宕山と愛宕神社の関連は定かではありません。
甲府五山の円光院には信玄公が信仰された「勝軍地蔵尊像」が奉安されており、信玄公の勝軍地蔵尊像信仰を示すものとされます。
躑躅ヶ崎館の鬼門守護とあわせ、信玄公の軍神としての信仰も受けていたことが伺われます。
■ 愛宕神社
山梨県神社庁資料





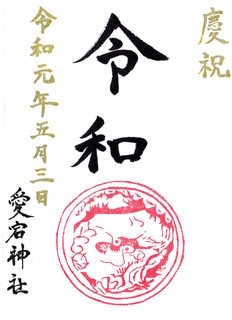
甲府市愛宕町134
御祭神:火之迦具土神、建御名方神、日本武尊
旧社格:村社
授与所:境内下社務所
朱印揮毫:令和 愛宕神社 直書(筆書) ※改元記念の御朱印
■【 三宝荒神 】
■ 真如山 良林寺 華光院

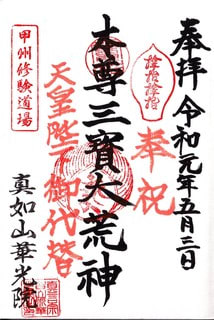

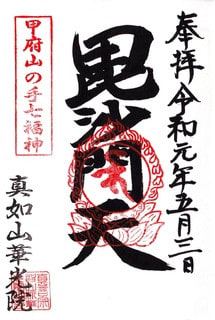
甲府市元紺屋町33
真言宗智山派 御本尊:三宝大荒神
札所:山の手七福神めぐり(毘沙門天)
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:本尊 三寶大荒神 直書(筆書)
・中央に種子の御寶印(火焔宝珠)。三寶荒神の種子は「バン」とみられますが、この御朱印の種子は「バン」ではありません。「バン」の荘厳体の「バーンク」にも見えますが、定かではありません。中央に「本尊 三寶大荒神」の揮毫。右上と中央の印判は不詳。左には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
令和に入って3日目の拝受だったので、「奉祝」「天皇陛下御代替」の揮毫があります。
左上の「甲州修験道場」の印判は、修験寺としての歴史を示すものです。
〔山の手七福神めぐり(毘沙門天)の御朱印〕
・中央に種子の御寶印(火焔宝珠)。毘沙門天の種子は「ベイ」で、この御朱印の種子は「ベイ」のようにも見えますが、定かではありません。中央に「毘沙門天」の揮毫。左上に「甲府山の手七福神」の印判。左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
由緒によると御本尊は弘法大師のお作と伝わる三宝荒神で、大永年中(1521年~1528年)に信虎公が荒神堂を建て、堂守に山伏を置いたのがはじまりとされています。
後に信玄公が現在地へ移され荒神堂と別当寺を建立、紀州根来寺の弘尊法印を別当寺住職に招いて祈願所とされたといいます。
三宝荒神は、火伏せの神、かまどの神として広く信仰される尊格で、仏教では守護神、護法神とされています。
神仏習合、山岳信仰、民間信仰の流れのなかでも広く信仰をあつめる尊格ということもあってか、すこぶる複雑な性格をもたれる尊格といわれます。
仏教では文殊菩薩、不動明王、歓喜天と同体(本地)とされる説があるので、(垂迹)神として祭祀されることがあります。
信玄公は荒神堂と別当寺を建立されたとありますから、神社(荒神堂)で三宝荒神を祀り、別に別当寺があったとみられますが、現在は華光院の御本尊が三宝荒神となっており、廃仏毀釈の折になにかしらの経緯があったのかもしれません。
信玄公は調略の名手であり、もっとも忍者を活用した戦国武将として知られています。
武田家の忍者(忍びの者)は、「透波」(すっぱ)と呼ばれ、天文十九年(1550年)の村上義清との戦さ「砥石崩れ」で透波を統括していた板垣信方と甘利虎泰の両名将を失ってのちに「三ツ者」(みツもの)として再編成されたといわれます。
間見、見方、目付の三つの任務を果たしたため「三ツ者」と呼んだとされます。
忍びの者は、各地を移動する僧侶や修験者に身を変えて(あるいは修験者・山伏を雇い入れて)活動したとされ、「透波」や「三ツ者」も例外ではなかったようです。
修験者や山伏は、山岳信仰や神仏習合と密接にかかわりますから、上で述べた、飯縄、戸隠、愛宕、そして三宝荒神などの尊格と信玄公の関係は、単なる祈願信仰の対象だけでなく、調略活動とも切り離せないものだったかも知れません。
まぁ、「透波」や「三ツ者」の詳細はほとんど残されていないので(残された時点で失格でしょう)、その裏付けは難しいのですが・・・。(『甲陽軍艦』には、「三ツ者」は信玄公の家臣である「諸国御使者衆」の配下にあったという記載があります。)
修験寺らしく、4月の第2日曜日には山伏による火渡り祈願が行われています。
太子堂は聖徳太子の像を祀ったもので、柳沢吉里が大和郡山に転封となったとき甲府城内より移したものです。現在は堂内に毘沙門天も祀られています。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
2020/11/26・2020/09/08 UP
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
「武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印」の第1編は武田信玄公です。
信玄公ゆかりの寺社は検索するとたくさん出てきます。
なので数回にわけてまとめてみます。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
武田信玄公は、甲斐国守護武田家第18代武田信虎公の嫡男で、甲斐(州)武田家第19代の当主です。
戦国時代最強の武将とも目され、越後国の上杉謙信公(長尾景虎)との川中島の戦いはつとに知られています。
本国甲斐に加え、信濃、駿河、西上野、遠江、三河、美濃、飛騨などの一部を領し、西上を企図されたもののその途上で病没されました。大正四年、贈従三位。
諱は晴信、通称は太郎。「信玄」は出家後の法名で、正式には「徳栄軒信玄」と伝わります。
甲斐武田氏は、清和源氏(→武田氏系図)義光流、代々甲斐国守護をつとめた名族で、発祥の地は北巨勢郡武田村とされています。(常陸国説もあり)
■ 武田八幡宮





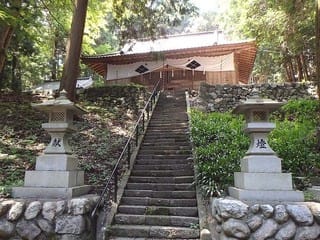



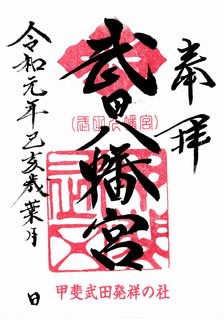
公式Web
韮崎市神山町北宮地1185
御祭神:誉田別命、息長足姫命、足仲津彦命、武田武大神
旧社格:県社
元別当:法善護国寺(南アルプス市加賀美)
授与所:参道左手社務所(原則書置)
朱印揮毫:武田八幡宮 書置(筆書)
この地には武田八幡宮が鎮座します。旧社格は県社と格式の高い神社です。
社伝には「弘仁十三年およそ千二百年前の八二二年嵯峨天皇の勅命により武田王の祠廟を遷座し同時に九州宇佐宮を合祀し創建された古社」とあり、甲斐武田家の初代当主、武田信義公以降は甲斐武田家の氏神として代々尊崇を受けました。
信虎公、信玄公による社殿再建の記録も残されています。
また、別当寺の法善護国寺(南アルプス市加賀美)は甲斐源氏の一族、加賀美氏の館跡とされ、武田氏歴代の祈願所として信玄公の帰依も篤かったと伝わります。(→ Vol.4で後述します)
真新しい社号標には大きな武田菱。
参道正面、石垣の上に石鳥居が据えられているめずらしい社頭。石垣横の階段を昇っての参拝となります。
県指定文化財の鳥居は高さ2.48メートルとさほど高さはない石造台輪鳥居ですが、転び(傾斜)をもつ太い柱は胴張り(中央部のふくらみ)もあって、特異な存在感を放っています。
踊り場の神楽殿を回り込み、もうひと昇りすると拝殿です。
そのおくの本殿は天文十年(1541年)、武田家当主となった信玄公が再建されたもの。
三間流造檜皮葺の風格あるつくりで、国の重要文化財に指定されています。
南側の若宮八幡神社の神殿は県文化財に指定されています。
御朱印は参道登り口向かって左手の社務所に書置が用意されていますが、用意分が捌けていることもあり、拝受はタイミング次第かもしれません。
■ 為朝神社
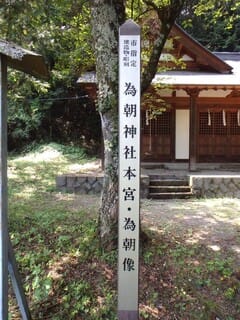



(一社)韮崎市観光協会Web
韮崎市神山町北宮地
御祭神:源為朝公
※御朱印は授与されていないとみられます。
武田八幡の本殿向かって左手の山道を数分辿ると(熊除けフェンスの脇を進みます。けっこう恐い(笑))、左手(武田八幡からみると南側)に為朝神社が鎮座しています。
剛勇無双を謳われた鎮西八郎源為朝公を祀った神社で、八幡太郎義家公の流れの為朝公を祀るお社が、新羅三郎義光公流の甲斐源氏武田氏発祥の地に祀られているのは、なんとなく不思議な感じもします。
韮崎市設置の現地案内板から抜粋引用してみます。
「為朝神社は、鎮西八郎源為朝を祀った神社で、元暦元年(1185年)に武田太郎信義が社殿を建立し、為朝の画像と大長刀を納め神霊を祀った。文化十三年(1816年)源氏の直系深沢文兵衛源直房等が、その衰退を憂い、昔日の面影を再興したものである。古来、疱瘡除けの神として四方民の信仰厚く(以下略)」
これだけでは、信義公がこの地に為朝公をお祀りした理由がよくわかりません。
Web検索してみると、韮崎市観光協会の資料に「源為朝は保元元年(1156年)に伊豆大島に島流しをされましたが、その後に鬼二匹を従え武田信義のもとに身を寄せ『武田為朝』を名乗ったという伝説があります。」とありました。
二匹の鬼さんについてはさらにもっと詳しい逸話もみつかりましたが(→https://design-archive.pref.yamanashi.jp/oldtale/10487.html)、利用規定がうるさそうなので引用もリンクもやめときます。(それにしても公的なコンテンツの利用って、どうしてこんなに煩雑なんだろう。しかも書いてある意味よくわかんないし・・・。これじゃふつうの人は面倒くさくて利用しないと思う。)
また、こちらの資料には、「『裏見寒話』では、武田八幡宮の南に『鍋山八幡』の存在を記している。『裏見寒話』では『鍋山八幡』を源為朝伝説に付会した説を取り、これは白山神社・為朝神社に比定される可能性が考えられている。」と記されています。(『裏見寒話』は、甲府勤番士・野田市左衛門成方が著したとされる甲斐国見聞記)
『甲斐国志』によると、武田八幡の南側にあった白山城は、武田信義公が居館武田館の要害として山手に築城し、『寛政重修諸家譜』によれば、「白山城」は青木氏(のちに山寺氏)が領有し、八代信種が「鍋山砦」を守備したとあり、位置関係から「白山城」=「鍋山砦」とする説があります。
また、白山城の名は、山中に鎮座する白山権現に由来するとされています。
白山城背後の尾根には烽火(狼煙)台がふたつあり、信玄公の狼煙台探索の関係で訪れる人もいそうです。
青木氏は武川衆、八代信種は浅利信種をさすと思われます。
上記の為朝神社再興の深沢氏ですが、Wikipediaによると三流(諏訪氏族、清和源氏佐竹氏族、清和源氏秋山氏族)あるとされ、「源氏の直系」および位置関係から清和源氏秋山氏族が考えられます。
しかしこの流れの深沢氏の本拠は峡東で、深沢氏の城館とされた深沢城(館)は御殿場市にありました。
八代信種にしても本拠は八代郡(峡東)で、どうしてこの地に係わりがあるのかは不明です。(武川郷は武田郷のすぐ北なので、武川衆の青木氏による守護は自然です。)
片側に千鳥破風の向拝を配した均整のとれた拝殿。蟇股の龍の彫刻も勢いがあります。
向拝のある向かって左が拝殿、右の社殿には異様に迫力のある為朝公像が鎮座しています。
武田神社とはやや異なる空気が流れ、一足伸ばして参拝するのもよろしいかと。(ただし熊に注意。)
---------------------------------------------------
甲斐武田氏の流れはいくつかあり、複数の本拠地が伝わりますが、嫡流とされる第5代(7代、2代とも)当主、武田信光公は甲斐国唯一の御厨である石禾御厨(いさわのみくりや)に拠られたとされます。
当地(石和郷)にはもともと景行天皇の弟君 稚城瓊入彦命が行宮を建てられ、命に随行してこの地を治めた和邇臣氏が一族の始祖、天足彦国押人命と稚城瓊入彦命を一族の氏神として合祀したお社がありました。
信光公は鎌倉の鶴岡八幡宮をこのお社に勧請合祀され「国衙八幡宮」(現在の石和八幡宮)と称し、代々武田家の氏神として崇敬されました。
■ 石和八幡神社(石和八幡宮、国衙八幡宮)





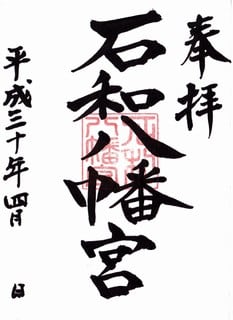
山梨県神社庁資料
笛吹市石和町市部1094
御祭神:応神天皇、比売大神、神功皇后、天足彦国押人命、稚城瓊入彦命
旧社格:村社
授与所:境内社務所
朱印揮毫:石和八幡宮 直書(筆書)
山梨県神社庁の資料には、「建久三年(1192年)、石和五郎信光(武田信光)が鎌倉幕府創建における功績により甲斐國河東半國の守護職となり、石和に政庁として居館を構へた際、鎌倉鶴岡八幡宮を勧請合祀し甲斐源氏の氏神として国衙八幡宮と改め、後に石和八幡宮と称した。」「以後武田氏を宗家とする甲斐源氏一門の崇敬厚く、正治二年(1200年)より永正十六年(1519年)に武田信虎が甲府躑躅ヶ崎に居館を移すまでの約三二〇年間、弓馬に秀で将軍や執権北条氏の指南役を務めた武田信光の武技に因み甲斐源氏一門の射法相伝の儀式は全て当社にて行はれたと伝へられ、現在例大祭に合はせて流鏑馬神事が奉納されてゐる。」とあります。
■ 建久三年(1192年)、鎌倉鶴岡八幡宮を勧請合祀した折、将軍源頼朝公より当宮に贈られたと伝わる一首(境内掲示)
- うつしては 同じ宮居の神垣に 汲みてあふかむ 美たらしの水 -
石和市街のほぼ中心にあり、温泉街からも近く駅からも歩ける距離です。
石和の日帰りできる温泉はかなり制覇しており、再三訪れているのですがこちらは初めての参拝となります。
国道411号に面した社頭。石造参道橋に朱塗りの立派な両部鳥居。鳥居扁額の「八幡宮」の「八」の字は八幡神の神使である鳩がかたちどられています。
そのおくに二つめの参道橋と随神門。随神門は現存する唯一の往年の建築物で、切妻鉄板葺三間一戸で八脚単層、左右に随身像を安置しています。
社殿は朱塗りの真新しいもの。本殿、幣殿、拝殿ともに平成18年に不慮の火災により焼失、平成21年に再建されました。
御朱印は拝殿向かって左手の社務所にて拝受できますが、一度お参りしたときはご不在で、二度目の参拝で拝受できました。事前TEL確認がベターかもしれません。
■ (甲斐國総社/宮前)八幡神社



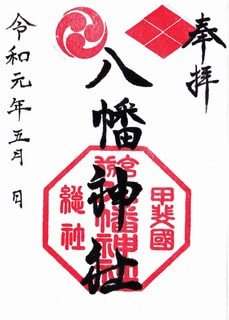
山梨県神社庁資料
甲府市宮前町6147
御祭神:誉田別命、息長帯姫命、姫大神
旧社格:県社・(甲斐國総社)
授与所:愛宕神社社務所(甲府市愛宕町134)
朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)
※御朱印は愛宕神社(甲府市愛宕町134)にて拝受できます。
永正十六年(1519年)、信虎公が古府中(甲府)に館を移された際、氏神も隣地(甲府市峯本)に遷座され、信玄公の治世に甲斐国内の惣社となりました。
(山梨県神社庁資料には「府中八幡として永禄三年神家五ヶ条の条目を賜はり、甲斐国九筋百六十四社の神主をして二日二夜ずつ二人交替に社詰参籠して国家安泰を祈願する番帳を賜る。」とあります。)
文禄四年(1595年)、浅野長政が甲府城を築城する際、現在の宮前町(旧古府中町)へ奉遷し、以降も甲斐国総社として崇敬されたと伝わります。
明治には、県内県社の第一号に列せられています。
南向きの明るい境内。社頭に真新しい石灯籠と石造の明神鳥居。社号標には「甲斐総社 八幡神社」とあります。
狛犬一対、灯籠一対。向拝前には立派なしめ縄。武田菱つきの拝殿幕が張られることもあるようです。
左手に少し離れて朱塗りの神楽殿。
大正九年、協賛者からの寄附により社殿等を再建したものの、昭和二十年7月の甲府空襲で焼失。現在の社殿は戦後の再建です。(空襲前の写真はこちらに掲載されています。)
〔 夢見山伝説 〕
夢見山はここから離れていますが、なぜか境内に説明板がありました。信玄公ゆかりの内容なので抜粋引用します。
「武田信虎公が夢見山に登ったとき、急に眠くなり石を枕に寝入ってしまった。すると夢に1人の男が現われ『今、甲斐国主として誕生した男児は、曽我五郎の生まれかわりである』と告げた。ほどなく生まれた若君(後の信玄公)を勝千代と名付けた。
勝千代の右手は握ったままで、心配した信虎が天桂和尚に相談すると、和尚も同じ夢を見たといい、夢の男は『その子の右手には金龍の目貫一片がある。城東の池で洗えば右手は開く」と告げたという。信玄公の右手を池で洗うと手は開き中から目貫が出てきたという。」
目貫とは、刀の柄を刀身につける釘で、生まれながらにして武具を手にされていた信玄公の戦の強さを物語るものといえるかもしれません。
■ (峯本鎮座)八幡神社

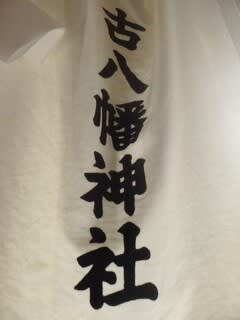


山梨県神社庁資料
甲府市古府中町1529
御祭神:誉田別神、媛神(宗像三女神)、息長帯姫神(誉田別神の母)
旧社格:村社
※御朱印は授与されていないようです。
山梨県神社庁資料によると、永正十六年(1519年)信虎公が躑躅ヶ崎に館を築造された時、城中守護神として勧請し、文禄年間(1593年~1596年)の甲府城築城の際に八幡山の南麓に移転しました。
当時の峯本組の住民等が旧社地に同神を祀って村の鎮護氏神とし、「古八幡」と敬称したと伝わります。
武田神社の南西にある相川小学校の体育館そば、峰本自治会館の棟つづきのお社に鎮座しています。
峰本自治会館玄関前に「峰本古八幡神社」の社号板とその横に由来書があるものの、奥まった立地で鳥居もないので、知らない人間はまず気づかないかと思います。
由来書に創祀・来歴が詳細に記されているので一部引用してみます。
「ここ峰本自治会館奥、棟続きのお社に祀る『峰本古八幡神社』は、私たちの産土神・鎮守の神であります。この神社は、石和五郎信光が鎌倉の鶴ヶ岡八幡宮を石和の館に勧請して国衙八幡宮と称したのが始まりといわれています。永正十六年(1519年)、武田信虎が府をつつじが崎に築く時、館の西側に移され府中八幡と称されました。(相川小学校校舎の西南部) 武田氏滅亡後、甲府城築城の際、お城鎮守の八幡宮として今の宮前町に移されたのです。当時の村人は、旧社地(古府中村峰本)に社を祀り古八幡神社と敬称し、氏神として尊崇してきました。明治十六年に相川小学校を開校するに当たり、八幡様は校舎の西側に移され、昭和三十一年には相川小学校体育館の建設が社のある『松の間』と称した敷地に決定し、八幡様は体育館南側に遷座することになりました。(以下略)」
自治会館の左脇からおくの本殿横に直接詣でる参道がつけられており、拝殿の扉をくぐって参拝します。
形からすると、めずらしい妻側からの参拝となります。
神前幕には「古八幡神社」の文字と武田菱紋、幕の上には花菱紋が刻されています。
小ぢんまりとしたお社ながら、甲斐源氏の氏神、国衙八幡宮の本流筋である八幡様の尊厳をひしひしと感じます。
■ 御崎神社



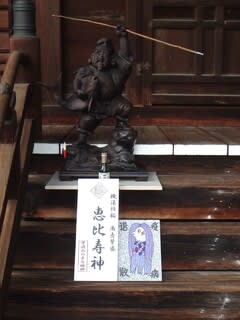
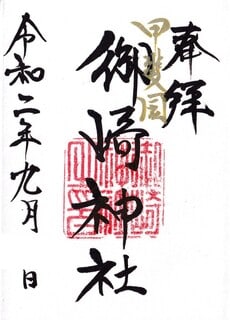
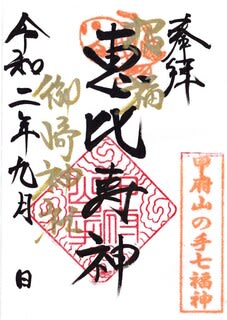
山梨県神社庁資料
甲府市美咲2-10-34
御祭神:稚産霊神、保食神、大国主神
旧社格:村社、式内社・宇波刀神社の論社として考える説あり
札所:甲府山の手七福神めぐり(恵比寿神)
授与所:拝殿右手奥の社務所(神職ご自宅)
朱印揮毫:御崎神社 直書(筆書)
朱印揮毫:恵比寿神 直書(筆書)
武田宗家の石和館の守護神、御崎神社は、甲府躑躅ヶ崎館への移転にともない躑躅ヶ崎館三の郭内に遷座され、武田家によって尊崇されたと伝わります。
御崎神社は武田家滅亡後も存続し、文禄三年(1594年)甲府城築城の際に現社地に遷座され、甲府城の守りと甲府北部一帯の氏神と定められて篤く尊崇されています。
山梨県神社庁資料によると由緒は以下のとおりです。
甲斐武田氏が石和へ居を構えた折にその守護神として居館内に祀られ、永正十六年(1520年)、信虎公が石和から躑躅が崎に居を移し築城された際に三の郭内に神殿を建立されて御遷座、武田家代々の尊崇を集めました。
天正三年(1575年)城外の西南、塔岩地内に再建、文禄三年(1594年)甲府城築城の際に現社地に御遷座、甲府城の守りと甲府北部一帯の氏神と定められています。
徳川家康公の甲斐国内巡視の際、当社に参拝の折に御崎大相撲を上覧され、これより御崎大相撲は甲斐国三相撲の一つとして有名になったとされます。
住宅地の道路が社頭で、そこから参道が延びています。
参道途中に小ぶりの鳥居、そのおくに立派な御神門。
境内は社頭からは想像もつかないほど広々としています。
参拝中、住民の方のすがたもちらほら。地域に溶け込んでいる神社のような感じがしました。
甲府山の手七福神めぐり(恵比寿神)の札所で、拝殿向かって左手に恵比寿神像が御座します。時節柄「アマビエ」の画額も。
甲府山の手七福神めぐりは、甲府市が平成31年の開府500年を記念して北部七寺社に七福神をお祀りし開創した出来たての七福神霊場で、各札所のご対応はどちらも親切です。
御朱印は拝殿向かって右手奥の社務所(神職ご自宅)にて快く授与いただけました。
---------------------------------------------------
信玄公は大永元年(1521年)11月3日、甲斐国守護・武田信虎公の嫡長子として生誕されました。
母は信虎公の正室で、西郡の有力国人大井信達の娘・大井夫人。
(信虎公、大井夫人については、別編でまとめてみたいと考えています。)
信玄公生誕の地は、躑躅ヶ崎館の詰城である要害山城、または積翠寺とされます。
■ 万松山 積翠寺




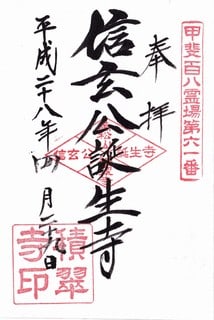
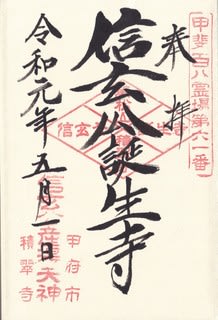
【写真 上(左)】 以前いただいた御朱印
【写真 下(右)】 令和初日の御朱印
甲府市上積翠寺町984
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第61番
朱印尊格:信玄公誕生寺 書置(筆書)/直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第61番印判
開祖は行基とされ、南北朝時代に夢窓疎石の高弟竺峰を中興開山としたという古刹で石水寺とも。
大永元年(1521年)10月、駿河国今川家臣福島正成率いる軍勢が甲府に攻め入り、信虎公は甲府近郊の飯田河原の合戦で福島勢を撃退。
この時期、懐妊されていた大井夫人は要害山城に退いていたといわれ、信玄公はここで生誕されたと伝わります。
幼名を”勝千代”と伝える説もあります。
信玄公生誕時にその産湯を汲んだとされる井戸が残っており、山手には産湯天神が祀られています。
頂上の要害山城本丸には、東郷平八郎元帥の揮毫による「武田信玄公誕生之地」の碑が建っています。
本堂裏手には夢窓疎石の作と伝わる庭園が残されています。
〔積翠寺由緒書〕(山内掲出)
当寺は臨済宗妙心寺末にして行基菩薩の開創による鎌倉時代夢窓国師の弟子竺峰和尚中興開山なり 大永元年(1521年)福島兵庫乱入の節(飯田河原の合戦)信虎夫人当寺に留り期に臨み一男子を産むこれ即ち信玄なり 境内に産湯の天神産湯の井戸あり堂西に磐石あり高さ八九尺泉これに激して瀑となるよりて石水寺の寺名になり村名になると甲陽軍鑑に伝う 積翠寺庭園は夢窓国師の築庭なり 寺宝に信玄像及び天文十五年後奈良天皇の勅使として下向せられし三條四辻二卿と拙寺にて催せられし信玄公の和漢联句一連並に良純王親王より仰岩和尚に贈られし書簡等々現存す
〔武田信玄和漢連句の説明書〕(山内掲出、抜粋)
天文十五年(1546年)信玄は、後奈良天皇の勅使として甲斐におもむいた三条西大納言実澄・四辻中納言季遠と東光寺鳳栖・宝泉寺湖月らを加えた十数名を当寺に迎え和漢連句を催した。この時の一巻が当寺に寄進され、寺宝として現存している。和漢連句は、五・七・五の和句と呼ばれる和歌と漢句と呼ばれる五言の漢詩を続けた連歌の一首であり、当時流行った知的な遊びであった。信玄が京都文化を積極的に移入したことや、武芸とともに文芸にも関心があっただけでなく和歌や漢詩の優れた作者であったことを示す貴重な資料である。
--------------------------------
信玄公の歌にゆかりの逸話は『甲陽軍艦』品第九「信玄公御歌の會之事」(→国会図書館DC)にも載せられています。
永禄九年(1566年)、一連寺にて武田家の歌会が催される際、京から権大納言今出川(菊亭)晴季公が甲斐に下向されていたものの、信玄公は「われらの相伴に晴季公を招くのは作法に反し、ぶしつけであろう」と、晴季公を招くことを躊躇われました。
当日朝、晴季公が一連寺にあらわれ「御歌の会が催されるのに参上しないのは傍若無人(失礼)であろう。」と急遽歌会に加わられ、信玄公はたいそう喜ばれたといいます。
その際、晴季公に供するお膳について、わざわざ円光院まで使いを出して確認されたとあり、信玄公が細かな心配りをされる武将であった証左ともされています。
このとき信玄公が詠まれた歌は
たちならぶかひこそなけれさくら花 松に千とせの色はならはで
このときの歌会の御相伴衆、御次衆、給仕・配膳役には信廉公、勝頼公、信豊公、河窪信実、穴山信君、一条信龍、長坂長閑、土屋昌次、曽禰昌世、真田昌幸、三枝守友など、錚々たる武将の名がみられ、信玄公のみならず、武田家臣も幅広く歌に親しんでいたことがうかがわれます。
時宗の名刹、稲久山 一連寺は名族一条氏とのゆかりがふかいので、別にご紹介しますが、写真と御朱印だけ上げておきます。

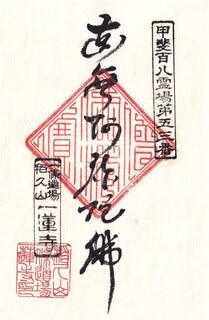
--------------------------------
武田宗家は代々甲斐守護職を継いだとされますが(異説あり)、信玄公の先々代、第17代当主信縄公の治世あたりまでは、下克上の流れを受けて同族の逸見氏、油川氏、守護代の跡部氏などが台頭し勢力を張りました。
有力国人の小山田氏(都留)、大井氏(西郡)、穴山氏(南部)なども独自の勢力を保ち、甲斐国内は一枚岩とはいえない状況でした。
また、隣国の強豪、今川氏は西郡の大井氏を後押しして、度々甲斐国内に攻め入ったという記録があります。
このような混沌とした状況に終止符を打ったのが信虎公で、それを代表する戦いが゛飯田河原の合戦゛といわれます。
信虎公は一万五千の今川勢をわずか二千の武田勢で打ち破ったとされ、以降、和睦もあって今川勢の甲斐侵入を許していません。
信玄公はこの勝ち戦゛飯田河原の合戦゛のさなかに生誕され、数年後には信虎公が他国へ初めて兵を出しているので、まさに武田家に隆盛をもたらした嫡子ということができるかもしれません。
【 武田家と重宝 】
〔 御旗楯無 〕
清和源氏の名族である甲斐武田家には、代々総領に相伝された「御旗楯無」(みはたたてなし)という重宝が伝わります。
「御旗」とは甲斐源氏の祖、新羅三郎源義光公の先代、鎮守府将軍頼義公が天喜四年(1056年)後冷泉天皇から下賜された日章旗(日の丸御旗)で現在、甲州市塩山の名刹、雲峰寺に所蔵されています。
この旗は「現存する最古の日章旗(日の丸の旗)」とみられています。
「楯無」とは、義光公以来、甲斐源氏の惣領武田氏の家宝として相伝された鎧で、小桜のの紋をあしらった小札(こざね)で大袖や草摺が威されているところから「小桜韋威鎧」(こざくらかわおどしよろい)とも称され、現在、甲州市塩山の菅田天神社に所蔵され、国宝に指定されています。(→文化庁国指定文化財データベース)
また、源氏八領(清和源氏に代々伝えられたという八種の鎧)のひとつとされています。
ふたつの重宝は武田家内で神格化され、御旗楯無に対して「御旗楯無も御照覧あれ」と誓い出陣したと伝わります。
信玄公ゆかりの宝物として、「諏訪神号旗」「信玄公馬印旗」「孫子の旗」もよく知られています。
〔 諏訪神号旗 〕
諏訪神号旗については、「信玄公護身旗の梵字真言に就いて/白石真道氏」という貴重な文献があるので、こちらも参照してまとめてみます。
「諏訪神号旗」は、「孫子の旗」とともに武田の軍旗として用いられたとされ、「諏訪法性旗」「諏訪明神旗」「諏訪梵字旗」と呼称される3種の旗の総称です。
いずれも信玄公の諏訪明神信仰を物語るものとされ、塩山の裂石山雲峰寺所蔵の諏訪神号旗は信玄公直筆と伝わります。
■ 諏訪法性旗(戦勝記念旗)
黒地に赤字で「南無諏方南宮法性上下大明神」と書かれています。信玄公が戦勝毎に雲峰寺の観音堂に奉納されたものと伝わります。
長さ1.23丈、横幅1.6尺。
13旒。明治維新以前には17旒あったとされています。
塩山の裂石山雲峰寺および恵林寺に所蔵されています。
※恵林寺については後述します。
■ 諏訪明神旗
赤地に金字で「諏方南宮上下大明神」と書かれています。
裂石山雲峰寺および金櫻神社に所蔵されています。
■ 諏訪梵字旗(信玄公の護身旗)
赤地に金字で「諏方南宮上下大明神」と書かれ、周囲に63の黒文字の梵字が配されています。
長さ1丈、横幅1.5尺。
1旒。裂石山雲峰寺に所蔵されています。
〔 信玄公馬印旗 〕
「信玄公馬印旗」は、武田の家紋である「花菱」が縦に3連、赤地に黒で染め抜かれた軍旗で、本陣に在る大将の馬側に立ててその所在を示す目標としたものとされます。
一般に武田家の家紋として知られているのは「武田菱」といわれる割菱紋ですが、「信玄公馬印旗」では花菱紋がつかわれています。
花菱紋は武田家の”控え紋” ”副紋”とされるもので、戦国の武将では軍旗に使用した例も複数みられるようです。
裂石山雲峰寺に所蔵されています。
〔 孫子の旗 〕
「孫子の旗」は、俗に「風林火山」の旗ともいわれ、
疾如風徐如林侵
掠如火不動如山
(疾(と)きこと風の如く、徐(しず)かなること林の如く、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如し)という孫子の「軍争編」から引かれた文が紺地に金文字であらわされた軍旗で、恵林寺住職快川紹喜の揮毫によるものとされます。
時代劇などでは、武田軍の象徴として必ず出てくるものです。
長さ1.26丈、横幅1.6尺。紺地に金文字で両面打抜き。
6旒。明治維新以前には9旒あったとされています。
裂石山雲峰寺および恵林寺に所蔵されています。
雲峰寺宝物殿で目にしたとき、現物の存在感に圧倒されるとともに、諏訪梵字旗(信玄公の護身旗)の63字の梵字が気になりました。
これについては、「信玄公護身旗の梵字真言に就いて/白石真道氏」という文献で検討されていますので、まとめてみます。
筆者のお考え
1.主文の「大明神」は、諏訪神社の主祭神たる建御名方命であることは明か。
2.「南宮」というは正確には「上諏方南宮」であることが明か。そして上諏訪の南方の宮といえば諏訪神社の上社を指すこととなる。(一宮慈眼寺に奉納されている錦七条の袈裟(信玄公が川中島にて着用)の裏に「上諏方南宮法性大明神」の墨書献文があることから)
ただし、上社は彦神(建御名方命)を主祭神とするに対し、下社は姫神たる八坂乃売命を主祭神とするから「南宮」という限り、下社は含まれないし「上下大明神」といえば南宮というのがおかしいのではないか。という疑問も呈されています。
3.「諏方大明神として垂迩された本地の明王は何様であろうか。」と、諏訪大明神の本地に注目され、「それは恐らく毘沙門天王ではなかろうか。」とされ、「諏方大明神の本地身を毘沙門天王と見たとすれば神佛両道の信仰が統一されたことともなる」とされています。
併せて「毘沙門天王は北方守護の武神、財神として民衆の人気を鍾めていたが、(中略)北面分担の毘沙門天王が武人に尊崇されたのも亦自然であつた。」とも言及されています。
4.実際、「左行梵字上から5字は「『毘沙門(天王)の為に(帰命す)』と読まれる」とされ、「下端の4字(3語)は金剛部(又は忿怒部)諸尊の咒の結句にしばしば現れる慣用句であるから、この一咒は毘沙門天王の咒と見て差支ない。」とされています。
5.「第二咒は前述の毘沙門天の咒と見られるが、第一咒はどうであろう? この中に神名らしいものが2字(1語)づつ3度出ている。この語は『Sedhyim』としか読めない。これは『諏方神』という和名をそのまま梵咒に挿入したものかも知れない。そんな例が常用普通真言集などにも見えている。しかし『帰命吉祥天女』と読むのかも知れない。」
6.「若しこの女神(吉祥天女)を指すとなれば、それは諏方明神妃たる八坂刀売命の本地身と見た為と考えられる。」
7.「梵咒の意味は結局よく解らない。(中略)すべてを悟性のみによつて解決するの要はない。諏方大明神の威力を被り、毘沙門天王の法力が通じて、軍兵の志気が揚ればよい訳である。それ故、護身旗の梵咒はそれだけで十分の効果を発揮し得たのである。」と締められています。
いま、Web上で諏訪大明神の本地を調べてみると、建御名方命は普賢菩薩、八坂刀売神は千手観世音菩薩としている資料が多くみつかります。
Vol.4でも触れますが、信玄公は毘沙門天への信仰篤く、軍陣の守り本尊として刀八毘沙門天像を護持されていました。(現・円光院所蔵)
また、信玄公が戦勝祈願依頼文を奉納された11寺のひとつ御坂町の大野寺(現・福光園寺)には、仏師・蓮慶の作と伝わる見事な吉祥天像が祀られています。
吉祥天は毘沙門天の妻とされます。
なので、諏訪大明神の主文字と、その周囲に信玄公の軍陣守り本尊である毘沙門天とその妻の吉祥天の梵字を配して護身旗とした、という考え方もあるかもしれません。
■ 裂石山 雲峰寺







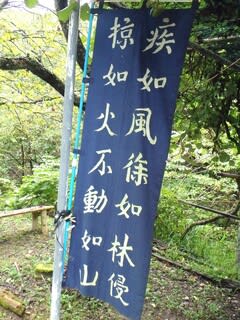
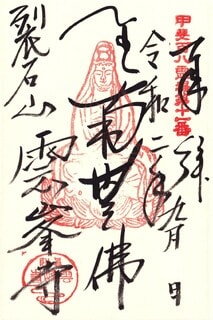
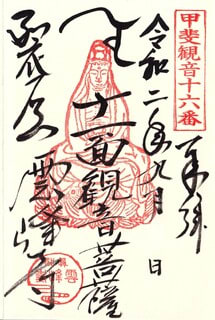
公式Web
甲州市塩山上萩原2678
臨済宗妙心寺派 御本尊:十一面観世音菩薩(裂石観音)
札所:甲斐百八霊場第11番、甲斐国三十三番観音札所第16番、甲斐八十八ヶ所霊場第75番
〔甲斐百八霊場第11番の御朱印〕
朱印尊格:南無佛・十一面観世音菩薩(裂石観音) 直書(筆書)
・中央に御本尊十一面観世音菩薩(裂石観音)の御影印と「南無佛」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第十一番」の札所印。左には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
〔甲斐国三十三番観音札所第16番の御朱印〕
朱印尊格:十一面観音菩薩(裂石観音) 直書(筆書)
・中央に御本尊十一面観世音菩薩の御影印と「十一面観音菩薩」の揮毫。右上に「甲斐観音十六番」の札所印。左には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
寺号の文字は2種で「峯」と「峰」でことなり、これは趣向を凝らすため敢えて変えられたとのことです。
寺伝によると、行基が修行に訪れた同年6月17日の夜、霊雲が当山の上にまたたき、山谷大いに震い、高さ十五米余の山中の大石がにわかに真二つとなるや、石の裂け目から萩の大樹が生え、石の上には十一面観世音菩薩が出現されました。
この奇瑞を目の当たりにした行基は、萩の大樹から十一面観世音菩薩の尊像を刻し一庵に奉祀したのが当山の開創とされます。
開創当初は天台宗、のちに禅宗へと転じ、甲斐の鬼門を護る甲斐源氏の武運長久の祈願寺として深く崇敬されました。
室町時代には恵林寺住職の絶海中津が観音堂改修の浄財勧募を行っており、恵林寺とは深い関係にあったものとみられます。
天文年間(1532年~1554年)の火災にて諸堂を焼失、その再興に向けて信虎公が印判状(現存)を与え、紹謹禅師をはじめとする寺僧を励ましたと伝わります。
永禄元年(1558年)、信玄公が武運長久祈願文を納めているので、この頃には再建されていたとみられ、現在の本堂、庫裏、書院、仁王門(いずれも重要文化財)はこの時期の建立と考えられています。
天正十年(1582年)、勝頼公は一族とともに天目山の合戦で敗れ自刃、武田家は滅びましたが、その折、家臣たちが武田家再興を期して重宝をひそかに当山へ納めたといわれています。
参道階段から昇ると、木々が鬱蒼と茂り禅宗の古刹の雰囲気にあふれています。
階段上部、木立の下に古色を帯びた仁王門。一戸三間八脚の単層入母屋造茅葺、仁王像二体を安置し、木鼻・懸魚にも彫刻を備えて古刹の山門にふさわしい佇まい。
本堂は正面四十尺の堂々たる構えで、入母屋造檜皮葺に重厚な唐破風向拝を附設した均整のとれた意匠。
向拝の二重梁正面には上下の蟇股を配し(上:板蟇股、下:本蟇股)、上の板蟇股には武田家の花菱紋が刻されています。
また、拝殿破風上には金色の徳川家三つ葉葵紋が配されています。
本堂向かって右手の庫裡も存在感があります。正面三六尺、単層切妻造茅葺の大建築。
均整のとれた曲線をひく破風と懸魚、桟唐戸上部の二段二連の連子欄間がいいアクセント。
正面梁上中央の板蛙股には、武田家の花菱紋が存在感を放っています。
夕方遅くにお伺いしたのですが、ご住職は快く宝物殿をお開けになられ、御朱印2通の揮毫をいただいたのちは、当山について貴重なご説明をいただきました。ありがとうございました。
境内のエドヒガンザクラは樹齢七百年、「峰のサクラ」と称される古木で、開花の時期(4月下旬)に再訪したいと想います。
■ 菅田天神社





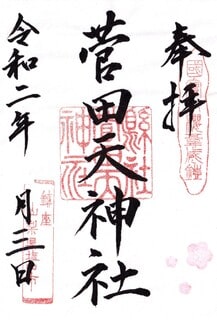
山梨県神社庁資料
甲州市塩山上於曽1054
御祭神:素盞嗚尊、五男三女神、菅原道真公
旧社格:県社
授与所:随神門左手手前の社務所
朱印揮毫:菅田天神社 書置(筆書)
武田家の重宝で国宝の「楯無」(小桜韋威鎧 兜・大袖付)を所蔵する、塩山の格式ある天神社です。
社記によると、承和九年(842年)甲斐国司藤原伊(太)勢雄が勅命により甲斐少目飯高浜成に命じての創建とされます。
寛弘元年(1004年)には菅原道真公を相殿に祀り、以来、菅田天神社と称します。
新羅三朗義光以来甲斐源氏の鎮守とされて篤い尊崇を受け、甲府の鬼門にあたることから鬼門鎮護として、永久年間(1113年~1118年)、武田氏第5代当主信光公が社殿を造営し、陣中の守護たる神器楯無鎧を社殿に納め置き、同族である於曽氏に守護させたと伝わります。
「楯無」は、当地於曽郷に拠った於曽氏によって厚く守護され、武田家は大事あるごとに出納を命じたといいます。
なお、於曽氏は、甲斐源氏の一族である加賀美遠光の子光経(於曽五郎)、光俊(於曽五郎)の流れとされています。
「新羅三朗義光甲斐守として任国以来武田家の守護神として代々崇あり。(中略)武田陣中守護たる神器楯無鎧の威を恐れ当神社は府の鬼門に当り神徳霊妙なるを以て本社々殿に納め於曽氏をして守護せしめ其崇敬厚く(以下略)」(山梨県神社庁資料より)
〔 境内由緒書より 〕
指定文化財 国宝
昭和二十七年十一月二十二日 指定
工 芸 小桜韋威鎧兜大袖付 一領
一の鳥居は石造の稲荷(台輪)鳥居、二の鳥居は朱塗りの両部鳥居で、そのおくに朱塗りの灯籠とやはり朱塗りの随神門が見えます。
参道の奥行きはさほどではないものの、さすがに旧県社らしい風格を備えています。
随神門は切妻造銅板葺、桁行三間一戸の八脚単層門で木部朱塗り。左右に随身像が安置されています。
随神門をくぐると左手に新羅宮。石標には「武田の始祖新羅三郎義光之を継承す」とあり、別の石碑には「国寶 小櫻韋威鎧」とあります。
参道橋を渡り階段を昇ると正面に拝殿。向かって右手に神楽殿、境内社。
拝殿は入母屋造正面千鳥破風銅板葺の正面1間向拝付で木部朱塗り。
こちらも社叢の緑に朱塗りが映えています。
拝殿左手前には神札授与所がありますが、通常御朱印は随神門左手前の社務所にて授与されているようです。
お伺いしたときは社務所のベルを押しても応答なしでしたが、しばらく境内を撮影していると、掃除をされている方を見かけたのでお伺いすると、快く書置の御朱印を授与いただけました。
■ 金櫻神社





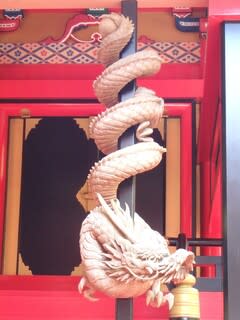

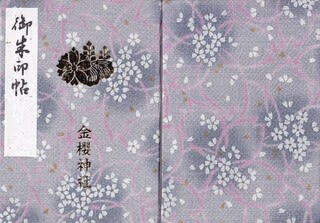
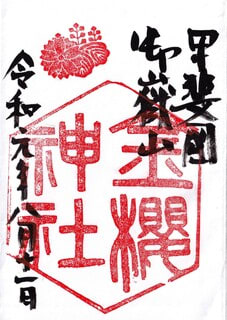
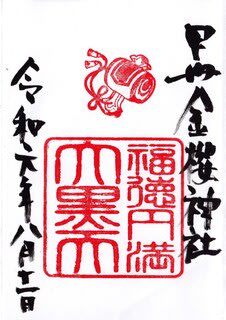
公式Web
甲府市御岳町2347
御神体:金峰山
御祭神:少名彦命、大己貴命、須佐之男命、日本武尊、櫛稲田媛命
旧社格:式内社(小)論社、県社
授与所:境内授与所、オリジナル御朱印帳は境内売店にて頒布
朱印揮毫:甲斐國御嶽山 直書(筆書)
朱印揮毫:甲州金櫻神社 直置(筆書)
「諏訪神号旗」のひとつ「諏訪明神旗」を所蔵する名勝、昇仙峡の上に鎮座する古社です。
社伝によると、第十代崇神天皇の御代(約2000年前)、各地に疫病が蔓延した折、諸国に神を祀って悪疫退散と万民息災の祈願をし、甲斐国では金峰山山頂に少彦名命を鎮祭されたのが当社の起源とされます。
その後第十二代景行天皇の時、日本武命が東国巡行の折山頂に須佐之男命と大己貴命を合ネ巳され国土平安を祈願されました。
第二十一代雄略天皇の御代、金峰山より現社地に遷され里宮としての金櫻神社が創立されました。
よって、金峰山山頂に本宮、当社は里宮にあたり、御神体は金峰山とされます。
第四十二代文武天皇の二年(約1270年前)、大和国吉野山金峰山より蔵王権現を勧請して神仏両道の神社となり、日本三御嶽三大霊場としてその信仰は関東一円をはじめ、遠く越後佐渡、信濃、駿河にまで及んだといわれます。
古くから日本における水晶発祥の地として火の玉・水の玉のご神宝と、金の成る木と言われる御神木「鬱金の櫻」は有名で、渓谷美を誇る昇仙峡の遊覧も相まって従前より多くの参拝客を集めています。
社記に「以金為神以櫻為霊」という言葉があり、「金櫻」の社号もここから出たものとみられています。
多くの寄進による荘厳な社殿と中宮には見事な蟇股の牡丹の唐草、本殿の左甚五郎の作と伝わる昇竜・降竜はつとに有名でしたが、残念ながら昭和30年12月の失火によりその多くを失っています。
幸いにも焼失を免れた社宝のうち、能面と大胴は勝頼公よりの奉納、小胴は仁科五郎盛信公の奉納とされています。
諏訪明神旗については、公式Webに下記のような記載があります。
「金櫻神社の宝物として『諏方南宮上下大明神の旗』があります。この度、その旗が絹で作られているためこれ以上痛まないようにと綺麗に表装されました。この旗は武田信玄に由来するものでございます。詳しいことは現在分かりませんが、元々金櫻神社は武田家代々の祈願所だったので、この旗が納められていたと思われます。」
昇仙峡周辺は、御朱印スポットとしても人気のあるところです。(詳細は → こちら)
この人気は、水晶の大きな印判を目の前で捺していただける金櫻神社の御朱印が大きく寄与しているのでは。
金櫻神社、夫婦木神社、夫婦木神社姫の宮、黒戸奈神社(黒平町、御朱印は金櫻神社にて)、天台山羅漢寺(御朱印は「食事処一休」(県営グリーンライン駐車場隣)にて)の5寺社の御朱印を拝受できますが、金櫻神社、夫婦木神社、夫婦木神社姫の宮は時季によっては授与待ちがあり、黒戸奈神社は金櫻神社から車でもかなり遠く、天台山羅漢寺は「食事処一休」から遊歩道沿経由で歩けますが、それなりに距離&高低差があるので、全御朱印ゲットを目論む方は時間に余裕をもたれた方がいいかと思います。
【 ご参考/昇仙峡周辺の御朱印 】
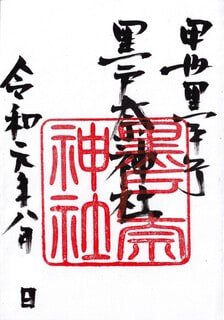
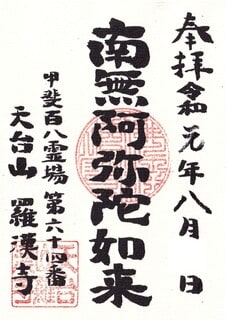
【写真 上(左)】 黒戸奈神社(黒平)
【写真 下(右)】 天台山羅漢寺
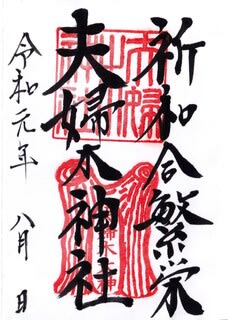
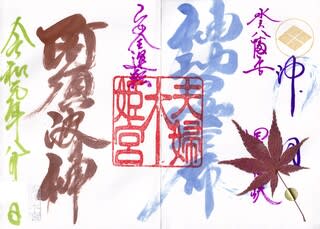
【写真 上(左)】 夫婦木神社
【写真 下(右)】 夫婦木神社姫の宮
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
「武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印」の第1編は武田信玄公です。
信玄公ゆかりの寺社は検索するとたくさん出てきます。
なので数回にわけてまとめてみます。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
武田信玄公は、甲斐国守護武田家第18代武田信虎公の嫡男で、甲斐(州)武田家第19代の当主です。
戦国時代最強の武将とも目され、越後国の上杉謙信公(長尾景虎)との川中島の戦いはつとに知られています。
本国甲斐に加え、信濃、駿河、西上野、遠江、三河、美濃、飛騨などの一部を領し、西上を企図されたもののその途上で病没されました。大正四年、贈従三位。
諱は晴信、通称は太郎。「信玄」は出家後の法名で、正式には「徳栄軒信玄」と伝わります。
甲斐武田氏は、清和源氏(→武田氏系図)義光流、代々甲斐国守護をつとめた名族で、発祥の地は北巨勢郡武田村とされています。(常陸国説もあり)
■ 武田八幡宮





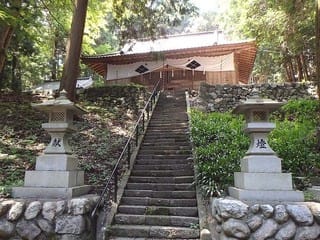



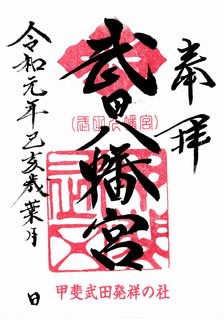
公式Web
韮崎市神山町北宮地1185
御祭神:誉田別命、息長足姫命、足仲津彦命、武田武大神
旧社格:県社
元別当:法善護国寺(南アルプス市加賀美)
授与所:参道左手社務所(原則書置)
朱印揮毫:武田八幡宮 書置(筆書)
この地には武田八幡宮が鎮座します。旧社格は県社と格式の高い神社です。
社伝には「弘仁十三年およそ千二百年前の八二二年嵯峨天皇の勅命により武田王の祠廟を遷座し同時に九州宇佐宮を合祀し創建された古社」とあり、甲斐武田家の初代当主、武田信義公以降は甲斐武田家の氏神として代々尊崇を受けました。
信虎公、信玄公による社殿再建の記録も残されています。
また、別当寺の法善護国寺(南アルプス市加賀美)は甲斐源氏の一族、加賀美氏の館跡とされ、武田氏歴代の祈願所として信玄公の帰依も篤かったと伝わります。(→ Vol.4で後述します)
真新しい社号標には大きな武田菱。
参道正面、石垣の上に石鳥居が据えられているめずらしい社頭。石垣横の階段を昇っての参拝となります。
県指定文化財の鳥居は高さ2.48メートルとさほど高さはない石造台輪鳥居ですが、転び(傾斜)をもつ太い柱は胴張り(中央部のふくらみ)もあって、特異な存在感を放っています。
踊り場の神楽殿を回り込み、もうひと昇りすると拝殿です。
そのおくの本殿は天文十年(1541年)、武田家当主となった信玄公が再建されたもの。
三間流造檜皮葺の風格あるつくりで、国の重要文化財に指定されています。
南側の若宮八幡神社の神殿は県文化財に指定されています。
御朱印は参道登り口向かって左手の社務所に書置が用意されていますが、用意分が捌けていることもあり、拝受はタイミング次第かもしれません。
■ 為朝神社
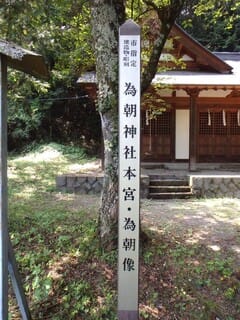



(一社)韮崎市観光協会Web
韮崎市神山町北宮地
御祭神:源為朝公
※御朱印は授与されていないとみられます。
武田八幡の本殿向かって左手の山道を数分辿ると(熊除けフェンスの脇を進みます。けっこう恐い(笑))、左手(武田八幡からみると南側)に為朝神社が鎮座しています。
剛勇無双を謳われた鎮西八郎源為朝公を祀った神社で、八幡太郎義家公の流れの為朝公を祀るお社が、新羅三郎義光公流の甲斐源氏武田氏発祥の地に祀られているのは、なんとなく不思議な感じもします。
韮崎市設置の現地案内板から抜粋引用してみます。
「為朝神社は、鎮西八郎源為朝を祀った神社で、元暦元年(1185年)に武田太郎信義が社殿を建立し、為朝の画像と大長刀を納め神霊を祀った。文化十三年(1816年)源氏の直系深沢文兵衛源直房等が、その衰退を憂い、昔日の面影を再興したものである。古来、疱瘡除けの神として四方民の信仰厚く(以下略)」
これだけでは、信義公がこの地に為朝公をお祀りした理由がよくわかりません。
Web検索してみると、韮崎市観光協会の資料に「源為朝は保元元年(1156年)に伊豆大島に島流しをされましたが、その後に鬼二匹を従え武田信義のもとに身を寄せ『武田為朝』を名乗ったという伝説があります。」とありました。
二匹の鬼さんについてはさらにもっと詳しい逸話もみつかりましたが(→https://design-archive.pref.yamanashi.jp/oldtale/10487.html)、利用規定がうるさそうなので引用もリンクもやめときます。(それにしても公的なコンテンツの利用って、どうしてこんなに煩雑なんだろう。しかも書いてある意味よくわかんないし・・・。これじゃふつうの人は面倒くさくて利用しないと思う。)
また、こちらの資料には、「『裏見寒話』では、武田八幡宮の南に『鍋山八幡』の存在を記している。『裏見寒話』では『鍋山八幡』を源為朝伝説に付会した説を取り、これは白山神社・為朝神社に比定される可能性が考えられている。」と記されています。(『裏見寒話』は、甲府勤番士・野田市左衛門成方が著したとされる甲斐国見聞記)
『甲斐国志』によると、武田八幡の南側にあった白山城は、武田信義公が居館武田館の要害として山手に築城し、『寛政重修諸家譜』によれば、「白山城」は青木氏(のちに山寺氏)が領有し、八代信種が「鍋山砦」を守備したとあり、位置関係から「白山城」=「鍋山砦」とする説があります。
また、白山城の名は、山中に鎮座する白山権現に由来するとされています。
白山城背後の尾根には烽火(狼煙)台がふたつあり、信玄公の狼煙台探索の関係で訪れる人もいそうです。
青木氏は武川衆、八代信種は浅利信種をさすと思われます。
上記の為朝神社再興の深沢氏ですが、Wikipediaによると三流(諏訪氏族、清和源氏佐竹氏族、清和源氏秋山氏族)あるとされ、「源氏の直系」および位置関係から清和源氏秋山氏族が考えられます。
しかしこの流れの深沢氏の本拠は峡東で、深沢氏の城館とされた深沢城(館)は御殿場市にありました。
八代信種にしても本拠は八代郡(峡東)で、どうしてこの地に係わりがあるのかは不明です。(武川郷は武田郷のすぐ北なので、武川衆の青木氏による守護は自然です。)
片側に千鳥破風の向拝を配した均整のとれた拝殿。蟇股の龍の彫刻も勢いがあります。
向拝のある向かって左が拝殿、右の社殿には異様に迫力のある為朝公像が鎮座しています。
武田神社とはやや異なる空気が流れ、一足伸ばして参拝するのもよろしいかと。(ただし熊に注意。)
---------------------------------------------------
甲斐武田氏の流れはいくつかあり、複数の本拠地が伝わりますが、嫡流とされる第5代(7代、2代とも)当主、武田信光公は甲斐国唯一の御厨である石禾御厨(いさわのみくりや)に拠られたとされます。
当地(石和郷)にはもともと景行天皇の弟君 稚城瓊入彦命が行宮を建てられ、命に随行してこの地を治めた和邇臣氏が一族の始祖、天足彦国押人命と稚城瓊入彦命を一族の氏神として合祀したお社がありました。
信光公は鎌倉の鶴岡八幡宮をこのお社に勧請合祀され「国衙八幡宮」(現在の石和八幡宮)と称し、代々武田家の氏神として崇敬されました。
■ 石和八幡神社(石和八幡宮、国衙八幡宮)





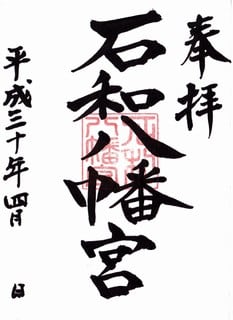
山梨県神社庁資料
笛吹市石和町市部1094
御祭神:応神天皇、比売大神、神功皇后、天足彦国押人命、稚城瓊入彦命
旧社格:村社
授与所:境内社務所
朱印揮毫:石和八幡宮 直書(筆書)
山梨県神社庁の資料には、「建久三年(1192年)、石和五郎信光(武田信光)が鎌倉幕府創建における功績により甲斐國河東半國の守護職となり、石和に政庁として居館を構へた際、鎌倉鶴岡八幡宮を勧請合祀し甲斐源氏の氏神として国衙八幡宮と改め、後に石和八幡宮と称した。」「以後武田氏を宗家とする甲斐源氏一門の崇敬厚く、正治二年(1200年)より永正十六年(1519年)に武田信虎が甲府躑躅ヶ崎に居館を移すまでの約三二〇年間、弓馬に秀で将軍や執権北条氏の指南役を務めた武田信光の武技に因み甲斐源氏一門の射法相伝の儀式は全て当社にて行はれたと伝へられ、現在例大祭に合はせて流鏑馬神事が奉納されてゐる。」とあります。
■ 建久三年(1192年)、鎌倉鶴岡八幡宮を勧請合祀した折、将軍源頼朝公より当宮に贈られたと伝わる一首(境内掲示)
- うつしては 同じ宮居の神垣に 汲みてあふかむ 美たらしの水 -
石和市街のほぼ中心にあり、温泉街からも近く駅からも歩ける距離です。
石和の日帰りできる温泉はかなり制覇しており、再三訪れているのですがこちらは初めての参拝となります。
国道411号に面した社頭。石造参道橋に朱塗りの立派な両部鳥居。鳥居扁額の「八幡宮」の「八」の字は八幡神の神使である鳩がかたちどられています。
そのおくに二つめの参道橋と随神門。随神門は現存する唯一の往年の建築物で、切妻鉄板葺三間一戸で八脚単層、左右に随身像を安置しています。
社殿は朱塗りの真新しいもの。本殿、幣殿、拝殿ともに平成18年に不慮の火災により焼失、平成21年に再建されました。
御朱印は拝殿向かって左手の社務所にて拝受できますが、一度お参りしたときはご不在で、二度目の参拝で拝受できました。事前TEL確認がベターかもしれません。
■ (甲斐國総社/宮前)八幡神社



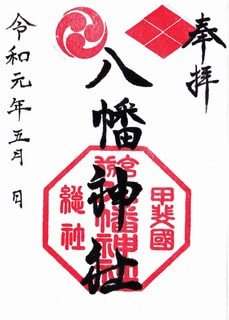
山梨県神社庁資料
甲府市宮前町6147
御祭神:誉田別命、息長帯姫命、姫大神
旧社格:県社・(甲斐國総社)
授与所:愛宕神社社務所(甲府市愛宕町134)
朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)
※御朱印は愛宕神社(甲府市愛宕町134)にて拝受できます。
永正十六年(1519年)、信虎公が古府中(甲府)に館を移された際、氏神も隣地(甲府市峯本)に遷座され、信玄公の治世に甲斐国内の惣社となりました。
(山梨県神社庁資料には「府中八幡として永禄三年神家五ヶ条の条目を賜はり、甲斐国九筋百六十四社の神主をして二日二夜ずつ二人交替に社詰参籠して国家安泰を祈願する番帳を賜る。」とあります。)
文禄四年(1595年)、浅野長政が甲府城を築城する際、現在の宮前町(旧古府中町)へ奉遷し、以降も甲斐国総社として崇敬されたと伝わります。
明治には、県内県社の第一号に列せられています。
南向きの明るい境内。社頭に真新しい石灯籠と石造の明神鳥居。社号標には「甲斐総社 八幡神社」とあります。
狛犬一対、灯籠一対。向拝前には立派なしめ縄。武田菱つきの拝殿幕が張られることもあるようです。
左手に少し離れて朱塗りの神楽殿。
大正九年、協賛者からの寄附により社殿等を再建したものの、昭和二十年7月の甲府空襲で焼失。現在の社殿は戦後の再建です。(空襲前の写真はこちらに掲載されています。)
〔 夢見山伝説 〕
夢見山はここから離れていますが、なぜか境内に説明板がありました。信玄公ゆかりの内容なので抜粋引用します。
「武田信虎公が夢見山に登ったとき、急に眠くなり石を枕に寝入ってしまった。すると夢に1人の男が現われ『今、甲斐国主として誕生した男児は、曽我五郎の生まれかわりである』と告げた。ほどなく生まれた若君(後の信玄公)を勝千代と名付けた。
勝千代の右手は握ったままで、心配した信虎が天桂和尚に相談すると、和尚も同じ夢を見たといい、夢の男は『その子の右手には金龍の目貫一片がある。城東の池で洗えば右手は開く」と告げたという。信玄公の右手を池で洗うと手は開き中から目貫が出てきたという。」
目貫とは、刀の柄を刀身につける釘で、生まれながらにして武具を手にされていた信玄公の戦の強さを物語るものといえるかもしれません。
■ (峯本鎮座)八幡神社

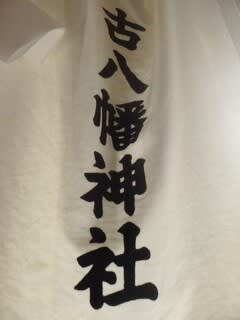


山梨県神社庁資料
甲府市古府中町1529
御祭神:誉田別神、媛神(宗像三女神)、息長帯姫神(誉田別神の母)
旧社格:村社
※御朱印は授与されていないようです。
山梨県神社庁資料によると、永正十六年(1519年)信虎公が躑躅ヶ崎に館を築造された時、城中守護神として勧請し、文禄年間(1593年~1596年)の甲府城築城の際に八幡山の南麓に移転しました。
当時の峯本組の住民等が旧社地に同神を祀って村の鎮護氏神とし、「古八幡」と敬称したと伝わります。
武田神社の南西にある相川小学校の体育館そば、峰本自治会館の棟つづきのお社に鎮座しています。
峰本自治会館玄関前に「峰本古八幡神社」の社号板とその横に由来書があるものの、奥まった立地で鳥居もないので、知らない人間はまず気づかないかと思います。
由来書に創祀・来歴が詳細に記されているので一部引用してみます。
「ここ峰本自治会館奥、棟続きのお社に祀る『峰本古八幡神社』は、私たちの産土神・鎮守の神であります。この神社は、石和五郎信光が鎌倉の鶴ヶ岡八幡宮を石和の館に勧請して国衙八幡宮と称したのが始まりといわれています。永正十六年(1519年)、武田信虎が府をつつじが崎に築く時、館の西側に移され府中八幡と称されました。(相川小学校校舎の西南部) 武田氏滅亡後、甲府城築城の際、お城鎮守の八幡宮として今の宮前町に移されたのです。当時の村人は、旧社地(古府中村峰本)に社を祀り古八幡神社と敬称し、氏神として尊崇してきました。明治十六年に相川小学校を開校するに当たり、八幡様は校舎の西側に移され、昭和三十一年には相川小学校体育館の建設が社のある『松の間』と称した敷地に決定し、八幡様は体育館南側に遷座することになりました。(以下略)」
自治会館の左脇からおくの本殿横に直接詣でる参道がつけられており、拝殿の扉をくぐって参拝します。
形からすると、めずらしい妻側からの参拝となります。
神前幕には「古八幡神社」の文字と武田菱紋、幕の上には花菱紋が刻されています。
小ぢんまりとしたお社ながら、甲斐源氏の氏神、国衙八幡宮の本流筋である八幡様の尊厳をひしひしと感じます。
■ 御崎神社



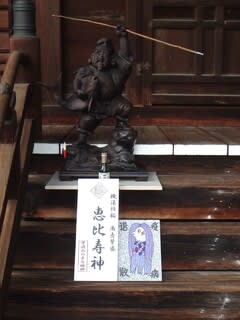
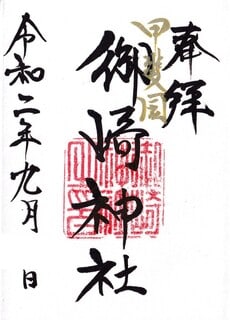
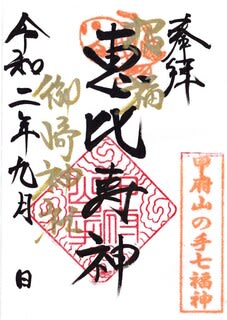
山梨県神社庁資料
甲府市美咲2-10-34
御祭神:稚産霊神、保食神、大国主神
旧社格:村社、式内社・宇波刀神社の論社として考える説あり
札所:甲府山の手七福神めぐり(恵比寿神)
授与所:拝殿右手奥の社務所(神職ご自宅)
朱印揮毫:御崎神社 直書(筆書)
朱印揮毫:恵比寿神 直書(筆書)
武田宗家の石和館の守護神、御崎神社は、甲府躑躅ヶ崎館への移転にともない躑躅ヶ崎館三の郭内に遷座され、武田家によって尊崇されたと伝わります。
御崎神社は武田家滅亡後も存続し、文禄三年(1594年)甲府城築城の際に現社地に遷座され、甲府城の守りと甲府北部一帯の氏神と定められて篤く尊崇されています。
山梨県神社庁資料によると由緒は以下のとおりです。
甲斐武田氏が石和へ居を構えた折にその守護神として居館内に祀られ、永正十六年(1520年)、信虎公が石和から躑躅が崎に居を移し築城された際に三の郭内に神殿を建立されて御遷座、武田家代々の尊崇を集めました。
天正三年(1575年)城外の西南、塔岩地内に再建、文禄三年(1594年)甲府城築城の際に現社地に御遷座、甲府城の守りと甲府北部一帯の氏神と定められています。
徳川家康公の甲斐国内巡視の際、当社に参拝の折に御崎大相撲を上覧され、これより御崎大相撲は甲斐国三相撲の一つとして有名になったとされます。
住宅地の道路が社頭で、そこから参道が延びています。
参道途中に小ぶりの鳥居、そのおくに立派な御神門。
境内は社頭からは想像もつかないほど広々としています。
参拝中、住民の方のすがたもちらほら。地域に溶け込んでいる神社のような感じがしました。
甲府山の手七福神めぐり(恵比寿神)の札所で、拝殿向かって左手に恵比寿神像が御座します。時節柄「アマビエ」の画額も。
甲府山の手七福神めぐりは、甲府市が平成31年の開府500年を記念して北部七寺社に七福神をお祀りし開創した出来たての七福神霊場で、各札所のご対応はどちらも親切です。
御朱印は拝殿向かって右手奥の社務所(神職ご自宅)にて快く授与いただけました。
---------------------------------------------------
信玄公は大永元年(1521年)11月3日、甲斐国守護・武田信虎公の嫡長子として生誕されました。
母は信虎公の正室で、西郡の有力国人大井信達の娘・大井夫人。
(信虎公、大井夫人については、別編でまとめてみたいと考えています。)
信玄公生誕の地は、躑躅ヶ崎館の詰城である要害山城、または積翠寺とされます。
■ 万松山 積翠寺




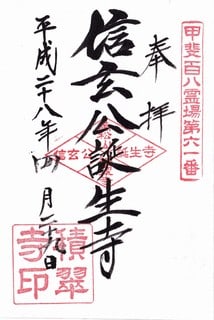
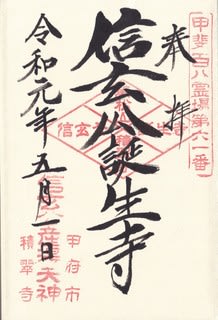
【写真 上(左)】 以前いただいた御朱印
【写真 下(右)】 令和初日の御朱印
甲府市上積翠寺町984
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第61番
朱印尊格:信玄公誕生寺 書置(筆書)/直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第61番印判
開祖は行基とされ、南北朝時代に夢窓疎石の高弟竺峰を中興開山としたという古刹で石水寺とも。
大永元年(1521年)10月、駿河国今川家臣福島正成率いる軍勢が甲府に攻め入り、信虎公は甲府近郊の飯田河原の合戦で福島勢を撃退。
この時期、懐妊されていた大井夫人は要害山城に退いていたといわれ、信玄公はここで生誕されたと伝わります。
幼名を”勝千代”と伝える説もあります。
信玄公生誕時にその産湯を汲んだとされる井戸が残っており、山手には産湯天神が祀られています。
頂上の要害山城本丸には、東郷平八郎元帥の揮毫による「武田信玄公誕生之地」の碑が建っています。
本堂裏手には夢窓疎石の作と伝わる庭園が残されています。
〔積翠寺由緒書〕(山内掲出)
当寺は臨済宗妙心寺末にして行基菩薩の開創による鎌倉時代夢窓国師の弟子竺峰和尚中興開山なり 大永元年(1521年)福島兵庫乱入の節(飯田河原の合戦)信虎夫人当寺に留り期に臨み一男子を産むこれ即ち信玄なり 境内に産湯の天神産湯の井戸あり堂西に磐石あり高さ八九尺泉これに激して瀑となるよりて石水寺の寺名になり村名になると甲陽軍鑑に伝う 積翠寺庭園は夢窓国師の築庭なり 寺宝に信玄像及び天文十五年後奈良天皇の勅使として下向せられし三條四辻二卿と拙寺にて催せられし信玄公の和漢联句一連並に良純王親王より仰岩和尚に贈られし書簡等々現存す
〔武田信玄和漢連句の説明書〕(山内掲出、抜粋)
天文十五年(1546年)信玄は、後奈良天皇の勅使として甲斐におもむいた三条西大納言実澄・四辻中納言季遠と東光寺鳳栖・宝泉寺湖月らを加えた十数名を当寺に迎え和漢連句を催した。この時の一巻が当寺に寄進され、寺宝として現存している。和漢連句は、五・七・五の和句と呼ばれる和歌と漢句と呼ばれる五言の漢詩を続けた連歌の一首であり、当時流行った知的な遊びであった。信玄が京都文化を積極的に移入したことや、武芸とともに文芸にも関心があっただけでなく和歌や漢詩の優れた作者であったことを示す貴重な資料である。
--------------------------------
信玄公の歌にゆかりの逸話は『甲陽軍艦』品第九「信玄公御歌の會之事」(→国会図書館DC)にも載せられています。
永禄九年(1566年)、一連寺にて武田家の歌会が催される際、京から権大納言今出川(菊亭)晴季公が甲斐に下向されていたものの、信玄公は「われらの相伴に晴季公を招くのは作法に反し、ぶしつけであろう」と、晴季公を招くことを躊躇われました。
当日朝、晴季公が一連寺にあらわれ「御歌の会が催されるのに参上しないのは傍若無人(失礼)であろう。」と急遽歌会に加わられ、信玄公はたいそう喜ばれたといいます。
その際、晴季公に供するお膳について、わざわざ円光院まで使いを出して確認されたとあり、信玄公が細かな心配りをされる武将であった証左ともされています。
このとき信玄公が詠まれた歌は
たちならぶかひこそなけれさくら花 松に千とせの色はならはで
このときの歌会の御相伴衆、御次衆、給仕・配膳役には信廉公、勝頼公、信豊公、河窪信実、穴山信君、一条信龍、長坂長閑、土屋昌次、曽禰昌世、真田昌幸、三枝守友など、錚々たる武将の名がみられ、信玄公のみならず、武田家臣も幅広く歌に親しんでいたことがうかがわれます。
時宗の名刹、稲久山 一連寺は名族一条氏とのゆかりがふかいので、別にご紹介しますが、写真と御朱印だけ上げておきます。

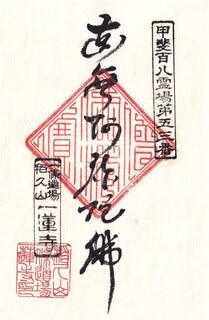
--------------------------------
武田宗家は代々甲斐守護職を継いだとされますが(異説あり)、信玄公の先々代、第17代当主信縄公の治世あたりまでは、下克上の流れを受けて同族の逸見氏、油川氏、守護代の跡部氏などが台頭し勢力を張りました。
有力国人の小山田氏(都留)、大井氏(西郡)、穴山氏(南部)なども独自の勢力を保ち、甲斐国内は一枚岩とはいえない状況でした。
また、隣国の強豪、今川氏は西郡の大井氏を後押しして、度々甲斐国内に攻め入ったという記録があります。
このような混沌とした状況に終止符を打ったのが信虎公で、それを代表する戦いが゛飯田河原の合戦゛といわれます。
信虎公は一万五千の今川勢をわずか二千の武田勢で打ち破ったとされ、以降、和睦もあって今川勢の甲斐侵入を許していません。
信玄公はこの勝ち戦゛飯田河原の合戦゛のさなかに生誕され、数年後には信虎公が他国へ初めて兵を出しているので、まさに武田家に隆盛をもたらした嫡子ということができるかもしれません。
【 武田家と重宝 】
〔 御旗楯無 〕
清和源氏の名族である甲斐武田家には、代々総領に相伝された「御旗楯無」(みはたたてなし)という重宝が伝わります。
「御旗」とは甲斐源氏の祖、新羅三郎源義光公の先代、鎮守府将軍頼義公が天喜四年(1056年)後冷泉天皇から下賜された日章旗(日の丸御旗)で現在、甲州市塩山の名刹、雲峰寺に所蔵されています。
この旗は「現存する最古の日章旗(日の丸の旗)」とみられています。
「楯無」とは、義光公以来、甲斐源氏の惣領武田氏の家宝として相伝された鎧で、小桜のの紋をあしらった小札(こざね)で大袖や草摺が威されているところから「小桜韋威鎧」(こざくらかわおどしよろい)とも称され、現在、甲州市塩山の菅田天神社に所蔵され、国宝に指定されています。(→文化庁国指定文化財データベース)
また、源氏八領(清和源氏に代々伝えられたという八種の鎧)のひとつとされています。
ふたつの重宝は武田家内で神格化され、御旗楯無に対して「御旗楯無も御照覧あれ」と誓い出陣したと伝わります。
信玄公ゆかりの宝物として、「諏訪神号旗」「信玄公馬印旗」「孫子の旗」もよく知られています。
〔 諏訪神号旗 〕
諏訪神号旗については、「信玄公護身旗の梵字真言に就いて/白石真道氏」という貴重な文献があるので、こちらも参照してまとめてみます。
「諏訪神号旗」は、「孫子の旗」とともに武田の軍旗として用いられたとされ、「諏訪法性旗」「諏訪明神旗」「諏訪梵字旗」と呼称される3種の旗の総称です。
いずれも信玄公の諏訪明神信仰を物語るものとされ、塩山の裂石山雲峰寺所蔵の諏訪神号旗は信玄公直筆と伝わります。
■ 諏訪法性旗(戦勝記念旗)
黒地に赤字で「南無諏方南宮法性上下大明神」と書かれています。信玄公が戦勝毎に雲峰寺の観音堂に奉納されたものと伝わります。
長さ1.23丈、横幅1.6尺。
13旒。明治維新以前には17旒あったとされています。
塩山の裂石山雲峰寺および恵林寺に所蔵されています。
※恵林寺については後述します。
■ 諏訪明神旗
赤地に金字で「諏方南宮上下大明神」と書かれています。
裂石山雲峰寺および金櫻神社に所蔵されています。
■ 諏訪梵字旗(信玄公の護身旗)
赤地に金字で「諏方南宮上下大明神」と書かれ、周囲に63の黒文字の梵字が配されています。
長さ1丈、横幅1.5尺。
1旒。裂石山雲峰寺に所蔵されています。
〔 信玄公馬印旗 〕
「信玄公馬印旗」は、武田の家紋である「花菱」が縦に3連、赤地に黒で染め抜かれた軍旗で、本陣に在る大将の馬側に立ててその所在を示す目標としたものとされます。
一般に武田家の家紋として知られているのは「武田菱」といわれる割菱紋ですが、「信玄公馬印旗」では花菱紋がつかわれています。
花菱紋は武田家の”控え紋” ”副紋”とされるもので、戦国の武将では軍旗に使用した例も複数みられるようです。
裂石山雲峰寺に所蔵されています。
〔 孫子の旗 〕
「孫子の旗」は、俗に「風林火山」の旗ともいわれ、
疾如風徐如林侵
掠如火不動如山
(疾(と)きこと風の如く、徐(しず)かなること林の如く、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如し)という孫子の「軍争編」から引かれた文が紺地に金文字であらわされた軍旗で、恵林寺住職快川紹喜の揮毫によるものとされます。
時代劇などでは、武田軍の象徴として必ず出てくるものです。
長さ1.26丈、横幅1.6尺。紺地に金文字で両面打抜き。
6旒。明治維新以前には9旒あったとされています。
裂石山雲峰寺および恵林寺に所蔵されています。
雲峰寺宝物殿で目にしたとき、現物の存在感に圧倒されるとともに、諏訪梵字旗(信玄公の護身旗)の63字の梵字が気になりました。
これについては、「信玄公護身旗の梵字真言に就いて/白石真道氏」という文献で検討されていますので、まとめてみます。
筆者のお考え
1.主文の「大明神」は、諏訪神社の主祭神たる建御名方命であることは明か。
2.「南宮」というは正確には「上諏方南宮」であることが明か。そして上諏訪の南方の宮といえば諏訪神社の上社を指すこととなる。(一宮慈眼寺に奉納されている錦七条の袈裟(信玄公が川中島にて着用)の裏に「上諏方南宮法性大明神」の墨書献文があることから)
ただし、上社は彦神(建御名方命)を主祭神とするに対し、下社は姫神たる八坂乃売命を主祭神とするから「南宮」という限り、下社は含まれないし「上下大明神」といえば南宮というのがおかしいのではないか。という疑問も呈されています。
3.「諏方大明神として垂迩された本地の明王は何様であろうか。」と、諏訪大明神の本地に注目され、「それは恐らく毘沙門天王ではなかろうか。」とされ、「諏方大明神の本地身を毘沙門天王と見たとすれば神佛両道の信仰が統一されたことともなる」とされています。
併せて「毘沙門天王は北方守護の武神、財神として民衆の人気を鍾めていたが、(中略)北面分担の毘沙門天王が武人に尊崇されたのも亦自然であつた。」とも言及されています。
4.実際、「左行梵字上から5字は「『毘沙門(天王)の為に(帰命す)』と読まれる」とされ、「下端の4字(3語)は金剛部(又は忿怒部)諸尊の咒の結句にしばしば現れる慣用句であるから、この一咒は毘沙門天王の咒と見て差支ない。」とされています。
5.「第二咒は前述の毘沙門天の咒と見られるが、第一咒はどうであろう? この中に神名らしいものが2字(1語)づつ3度出ている。この語は『Sedhyim』としか読めない。これは『諏方神』という和名をそのまま梵咒に挿入したものかも知れない。そんな例が常用普通真言集などにも見えている。しかし『帰命吉祥天女』と読むのかも知れない。」
6.「若しこの女神(吉祥天女)を指すとなれば、それは諏方明神妃たる八坂刀売命の本地身と見た為と考えられる。」
7.「梵咒の意味は結局よく解らない。(中略)すべてを悟性のみによつて解決するの要はない。諏方大明神の威力を被り、毘沙門天王の法力が通じて、軍兵の志気が揚ればよい訳である。それ故、護身旗の梵咒はそれだけで十分の効果を発揮し得たのである。」と締められています。
いま、Web上で諏訪大明神の本地を調べてみると、建御名方命は普賢菩薩、八坂刀売神は千手観世音菩薩としている資料が多くみつかります。
Vol.4でも触れますが、信玄公は毘沙門天への信仰篤く、軍陣の守り本尊として刀八毘沙門天像を護持されていました。(現・円光院所蔵)
また、信玄公が戦勝祈願依頼文を奉納された11寺のひとつ御坂町の大野寺(現・福光園寺)には、仏師・蓮慶の作と伝わる見事な吉祥天像が祀られています。
吉祥天は毘沙門天の妻とされます。
なので、諏訪大明神の主文字と、その周囲に信玄公の軍陣守り本尊である毘沙門天とその妻の吉祥天の梵字を配して護身旗とした、という考え方もあるかもしれません。
■ 裂石山 雲峰寺







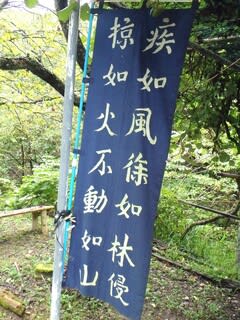
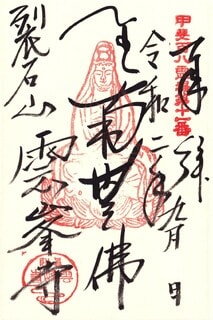
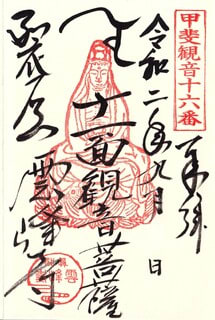
公式Web
甲州市塩山上萩原2678
臨済宗妙心寺派 御本尊:十一面観世音菩薩(裂石観音)
札所:甲斐百八霊場第11番、甲斐国三十三番観音札所第16番、甲斐八十八ヶ所霊場第75番
〔甲斐百八霊場第11番の御朱印〕
朱印尊格:南無佛・十一面観世音菩薩(裂石観音) 直書(筆書)
・中央に御本尊十一面観世音菩薩(裂石観音)の御影印と「南無佛」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第十一番」の札所印。左には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
〔甲斐国三十三番観音札所第16番の御朱印〕
朱印尊格:十一面観音菩薩(裂石観音) 直書(筆書)
・中央に御本尊十一面観世音菩薩の御影印と「十一面観音菩薩」の揮毫。右上に「甲斐観音十六番」の札所印。左には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
寺号の文字は2種で「峯」と「峰」でことなり、これは趣向を凝らすため敢えて変えられたとのことです。
寺伝によると、行基が修行に訪れた同年6月17日の夜、霊雲が当山の上にまたたき、山谷大いに震い、高さ十五米余の山中の大石がにわかに真二つとなるや、石の裂け目から萩の大樹が生え、石の上には十一面観世音菩薩が出現されました。
この奇瑞を目の当たりにした行基は、萩の大樹から十一面観世音菩薩の尊像を刻し一庵に奉祀したのが当山の開創とされます。
開創当初は天台宗、のちに禅宗へと転じ、甲斐の鬼門を護る甲斐源氏の武運長久の祈願寺として深く崇敬されました。
室町時代には恵林寺住職の絶海中津が観音堂改修の浄財勧募を行っており、恵林寺とは深い関係にあったものとみられます。
天文年間(1532年~1554年)の火災にて諸堂を焼失、その再興に向けて信虎公が印判状(現存)を与え、紹謹禅師をはじめとする寺僧を励ましたと伝わります。
永禄元年(1558年)、信玄公が武運長久祈願文を納めているので、この頃には再建されていたとみられ、現在の本堂、庫裏、書院、仁王門(いずれも重要文化財)はこの時期の建立と考えられています。
天正十年(1582年)、勝頼公は一族とともに天目山の合戦で敗れ自刃、武田家は滅びましたが、その折、家臣たちが武田家再興を期して重宝をひそかに当山へ納めたといわれています。
参道階段から昇ると、木々が鬱蒼と茂り禅宗の古刹の雰囲気にあふれています。
階段上部、木立の下に古色を帯びた仁王門。一戸三間八脚の単層入母屋造茅葺、仁王像二体を安置し、木鼻・懸魚にも彫刻を備えて古刹の山門にふさわしい佇まい。
本堂は正面四十尺の堂々たる構えで、入母屋造檜皮葺に重厚な唐破風向拝を附設した均整のとれた意匠。
向拝の二重梁正面には上下の蟇股を配し(上:板蟇股、下:本蟇股)、上の板蟇股には武田家の花菱紋が刻されています。
また、拝殿破風上には金色の徳川家三つ葉葵紋が配されています。
本堂向かって右手の庫裡も存在感があります。正面三六尺、単層切妻造茅葺の大建築。
均整のとれた曲線をひく破風と懸魚、桟唐戸上部の二段二連の連子欄間がいいアクセント。
正面梁上中央の板蛙股には、武田家の花菱紋が存在感を放っています。
夕方遅くにお伺いしたのですが、ご住職は快く宝物殿をお開けになられ、御朱印2通の揮毫をいただいたのちは、当山について貴重なご説明をいただきました。ありがとうございました。
境内のエドヒガンザクラは樹齢七百年、「峰のサクラ」と称される古木で、開花の時期(4月下旬)に再訪したいと想います。
■ 菅田天神社





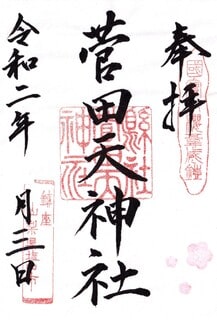
山梨県神社庁資料
甲州市塩山上於曽1054
御祭神:素盞嗚尊、五男三女神、菅原道真公
旧社格:県社
授与所:随神門左手手前の社務所
朱印揮毫:菅田天神社 書置(筆書)
武田家の重宝で国宝の「楯無」(小桜韋威鎧 兜・大袖付)を所蔵する、塩山の格式ある天神社です。
社記によると、承和九年(842年)甲斐国司藤原伊(太)勢雄が勅命により甲斐少目飯高浜成に命じての創建とされます。
寛弘元年(1004年)には菅原道真公を相殿に祀り、以来、菅田天神社と称します。
新羅三朗義光以来甲斐源氏の鎮守とされて篤い尊崇を受け、甲府の鬼門にあたることから鬼門鎮護として、永久年間(1113年~1118年)、武田氏第5代当主信光公が社殿を造営し、陣中の守護たる神器楯無鎧を社殿に納め置き、同族である於曽氏に守護させたと伝わります。
「楯無」は、当地於曽郷に拠った於曽氏によって厚く守護され、武田家は大事あるごとに出納を命じたといいます。
なお、於曽氏は、甲斐源氏の一族である加賀美遠光の子光経(於曽五郎)、光俊(於曽五郎)の流れとされています。
「新羅三朗義光甲斐守として任国以来武田家の守護神として代々崇あり。(中略)武田陣中守護たる神器楯無鎧の威を恐れ当神社は府の鬼門に当り神徳霊妙なるを以て本社々殿に納め於曽氏をして守護せしめ其崇敬厚く(以下略)」(山梨県神社庁資料より)
〔 境内由緒書より 〕
指定文化財 国宝
昭和二十七年十一月二十二日 指定
工 芸 小桜韋威鎧兜大袖付 一領
一の鳥居は石造の稲荷(台輪)鳥居、二の鳥居は朱塗りの両部鳥居で、そのおくに朱塗りの灯籠とやはり朱塗りの随神門が見えます。
参道の奥行きはさほどではないものの、さすがに旧県社らしい風格を備えています。
随神門は切妻造銅板葺、桁行三間一戸の八脚単層門で木部朱塗り。左右に随身像が安置されています。
随神門をくぐると左手に新羅宮。石標には「武田の始祖新羅三郎義光之を継承す」とあり、別の石碑には「国寶 小櫻韋威鎧」とあります。
参道橋を渡り階段を昇ると正面に拝殿。向かって右手に神楽殿、境内社。
拝殿は入母屋造正面千鳥破風銅板葺の正面1間向拝付で木部朱塗り。
こちらも社叢の緑に朱塗りが映えています。
拝殿左手前には神札授与所がありますが、通常御朱印は随神門左手前の社務所にて授与されているようです。
お伺いしたときは社務所のベルを押しても応答なしでしたが、しばらく境内を撮影していると、掃除をされている方を見かけたのでお伺いすると、快く書置の御朱印を授与いただけました。
■ 金櫻神社





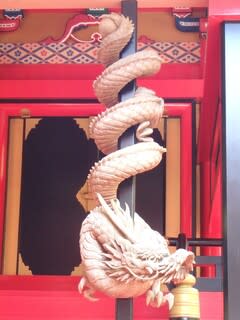

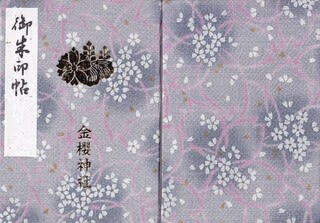
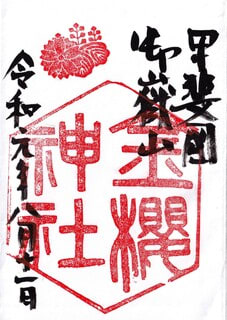
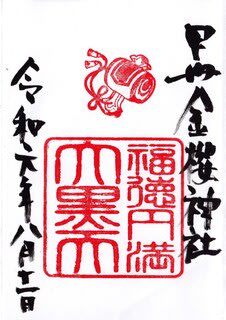
公式Web
甲府市御岳町2347
御神体:金峰山
御祭神:少名彦命、大己貴命、須佐之男命、日本武尊、櫛稲田媛命
旧社格:式内社(小)論社、県社
授与所:境内授与所、オリジナル御朱印帳は境内売店にて頒布
朱印揮毫:甲斐國御嶽山 直書(筆書)
朱印揮毫:甲州金櫻神社 直置(筆書)
「諏訪神号旗」のひとつ「諏訪明神旗」を所蔵する名勝、昇仙峡の上に鎮座する古社です。
社伝によると、第十代崇神天皇の御代(約2000年前)、各地に疫病が蔓延した折、諸国に神を祀って悪疫退散と万民息災の祈願をし、甲斐国では金峰山山頂に少彦名命を鎮祭されたのが当社の起源とされます。
その後第十二代景行天皇の時、日本武命が東国巡行の折山頂に須佐之男命と大己貴命を合ネ巳され国土平安を祈願されました。
第二十一代雄略天皇の御代、金峰山より現社地に遷され里宮としての金櫻神社が創立されました。
よって、金峰山山頂に本宮、当社は里宮にあたり、御神体は金峰山とされます。
第四十二代文武天皇の二年(約1270年前)、大和国吉野山金峰山より蔵王権現を勧請して神仏両道の神社となり、日本三御嶽三大霊場としてその信仰は関東一円をはじめ、遠く越後佐渡、信濃、駿河にまで及んだといわれます。
古くから日本における水晶発祥の地として火の玉・水の玉のご神宝と、金の成る木と言われる御神木「鬱金の櫻」は有名で、渓谷美を誇る昇仙峡の遊覧も相まって従前より多くの参拝客を集めています。
社記に「以金為神以櫻為霊」という言葉があり、「金櫻」の社号もここから出たものとみられています。
多くの寄進による荘厳な社殿と中宮には見事な蟇股の牡丹の唐草、本殿の左甚五郎の作と伝わる昇竜・降竜はつとに有名でしたが、残念ながら昭和30年12月の失火によりその多くを失っています。
幸いにも焼失を免れた社宝のうち、能面と大胴は勝頼公よりの奉納、小胴は仁科五郎盛信公の奉納とされています。
諏訪明神旗については、公式Webに下記のような記載があります。
「金櫻神社の宝物として『諏方南宮上下大明神の旗』があります。この度、その旗が絹で作られているためこれ以上痛まないようにと綺麗に表装されました。この旗は武田信玄に由来するものでございます。詳しいことは現在分かりませんが、元々金櫻神社は武田家代々の祈願所だったので、この旗が納められていたと思われます。」
昇仙峡周辺は、御朱印スポットとしても人気のあるところです。(詳細は → こちら)
この人気は、水晶の大きな印判を目の前で捺していただける金櫻神社の御朱印が大きく寄与しているのでは。
金櫻神社、夫婦木神社、夫婦木神社姫の宮、黒戸奈神社(黒平町、御朱印は金櫻神社にて)、天台山羅漢寺(御朱印は「食事処一休」(県営グリーンライン駐車場隣)にて)の5寺社の御朱印を拝受できますが、金櫻神社、夫婦木神社、夫婦木神社姫の宮は時季によっては授与待ちがあり、黒戸奈神社は金櫻神社から車でもかなり遠く、天台山羅漢寺は「食事処一休」から遊歩道沿経由で歩けますが、それなりに距離&高低差があるので、全御朱印ゲットを目論む方は時間に余裕をもたれた方がいいかと思います。
【 ご参考/昇仙峡周辺の御朱印 】
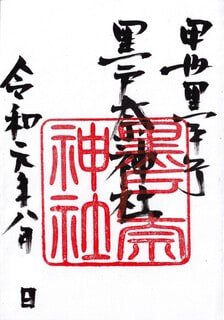
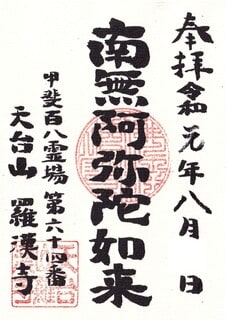
【写真 上(左)】 黒戸奈神社(黒平)
【写真 下(右)】 天台山羅漢寺
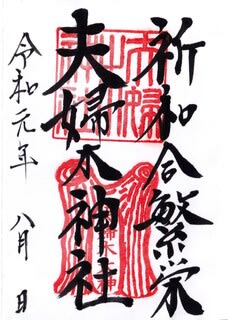
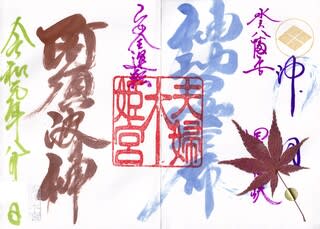
【写真 上(左)】 夫婦木神社
【写真 下(右)】 夫婦木神社姫の宮
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
2020/11/23 UP
Vol.2が字数制限に引っかかったので、Vol.2AとVol.2Bに分割しました。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
■ 三社神社




→山梨県神社庁資料
甲斐市竜王188
御祭神:木花開耶姫命、大物主命、大国主命
旧社格:村社
※御朱印は授与されていないとみられます。
大御幸祭で一宮、二宮、三宮の三社の御輿が御渡され、川除の祈願が執り行われる神社です。
〔 境内説明板および山梨県神社庁資料より 〕
天長二年(825年)秋、甲斐の国中地方に大水害が発生した際(大水禍を蒙り狭野一朝にして荒蕪地と化し、人畜の死傷算なく、又悪疫流行す。/山梨県神社庁資料)、時の国司文屋秋津が朝廷にその惨状を奏上、勅旨に依り(甲斐)国内代表社として、浅間神社、美和神社、玉諸神社の神官に命じ神璽を行幸して水防祈願を此の地に於て行ったと伝わる古社です。
以来、明治七年(1874年)までは毎年四月第二亥の日に甲斐国一宮浅間神社、二宮美和神社、三宮玉諸神社の三社が合同して各社から御輿等が御渡し、信玄堤(龍王川除)上で水防の神事として御幸祭が行われてきました。(里人相計りて三社神社の御祭神を勧請せしめ創立す。/同上)
貞享三年(1686年)の本殿建立寺に「御旅殿」とされていることから、この頃までの当社は、御旅所(神社の祭礼巡行の際、神輿が途中で休憩・宿泊する場所、ないしは神幸の目的地を指し、通常、御旅所に神輿が着くと御旅所祭が執り行われる。)の性格が強かったことがうかがわれます。
北方茅が岳からの山裾が釜無川に接する要地。釜無川・信玄堤を西に、竜王用水を足元に、南向きに鎮座します。
石造の台輪鳥居は転び(傾斜)をもつ太い柱で、存在感があります。桃山時代の造立とみられ市の指定文化財です。扁額には「三社大明神」とあります。
階段を昇って正面の拝殿は入母屋造銅板葺で均整のとれた意匠。
現在の本殿は「御旅殿」の名で貞享三年(1686年)に建立され、宝永四年(1707年)三社明神社として修造されています。
桁行三間、梁間二間のゆったりとした三間社流造で、一宮、二宮、三宮を祀るための規模をもっているとされています。
社殿まわりは立木がすくなくスペースがあり、大御幸祭の神事に備えたものかとみられます。
■ 三社諏訪神社


【写真 上(左)】 鳥居と境内(左奥が諏訪神社)
【写真 下(右)】 三社神社の拝殿


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 諏訪神社
→山梨県神社庁資料
甲府市上石田2-29-2
御祭神:木花咲耶姫命、大国主命、大国玉命、建御名方命
旧社格:村社
※御朱印授与情報は未確認です。
大御幸祭で一宮、二宮、三宮の三社の御輿が御渡されていた神社です。
上石田の住宅地の路地に面して鎮座しますが、境内は相応の広さをもちます。
社頭から向かって右が三社神社、左が諏訪神社です。
三社神社の石造鳥居は反増で貫の抜けがなく、台輪と亀腹と高さのある根巻をもち、柱間が狭いわりに高さがあるという独特な形状で、種類はよくわかりません。
鳥居の扁額は摩耗がはげしく判読できませんでした。
狛犬、社殿ともに基礎材で嵩上げされたかたちになっており、これは浸水に備えたものかもしれません。
拝殿は入母屋造銅板葺唐破風向拝付き。水引虹梁に木鼻、中備に板蟇股。
桟唐戸の上に「三社諏訪大神」の扁額。
本殿は一間社流造で二軒の平行垂木に複数の飾り懸魚を備え、蓑甲の仕上げがテクニカル。
右手の諏訪神社の鳥居は足太の台輪鳥居でこちらも扁額の判読不能でしたが、境内縁起書きによると「諏訪大明神」とのこと。
狛犬一対、正面に石造の祠。
境内縁起書によると、かつては社殿がありましたが明治七年火災で焼失したようです。
<境内縁起書(抜粋)>
・三社諏訪神社
「諏訪神社と三社神社が隣接して祀られていたが、明治七年諏訪神社は火災にて焼失。明治十年三社神社に合祀してから以来三社諏訪神社と申す。」
・三社神社
「天長年間毎年のように豪雨に見舞われ釜無川は洪水氾濫しとその水勢は玉幡、下河原、上石田その他下流の低地全域におよびその惨状はみるかぎりもない有様だった。時の国守文屋秋津は朝廷に奏上、勅旨に依り、一宮浅間神社祭神(木葉開姫命)、二宮美和神社祭神(大巳貴命)、三宮玉幡多神社祭神(大国主命)の三つの宮の分霊を合祀せよといい三社神社が建立されました。その後歴代の国守(知事)が祭主となり県民一丸となって、本宮から竜王・上石田と御輿が御渡され、水害・火災・悪疫の退散その他五穀豊穣を祈願しました。」
また、山梨県神社庁資料には「天長三年大洪水があり、甲斐国一宮浅間、二宮美和、三宮国玉の三神を勧請し鎮座、同年三月水防祭を行ふといふ。それより三社神社と称し四月十五日の祭儀には三社の神輿の神幸があったるも、明治七年よりは浅間神社のみとなる。」
とあり、大御幸祭の御輿が竜王の三社神社ののちに御渡されていた可能性があります。
(御幸祭で三社の御輿の御旅所として機能したのかもしれません。)
□〔追記〕
一宮浅間神社の公式Webに「大神幸祭は、甲斐国第一大祭と称され、社記によれば天長二年(八二五年)以来旧四月第二の亥の日、甲斐市竜王三社神社に神幸の上、川除祭(水防祭)を執り行って来たが、明治以後四月一五日と改め本社にて例大祭執行の後、同所及び甲府市上石田三社神社に神幸。(現在は竜王三社神社のみ)片途約6里(24km)に及ぶ行程であり現在、二宮、三宮も同所に神幸している。」とあり、以前は上石田の三社神社にも神幸されていたことが裏付けられます。
上石田は国中屈指の暴れ川、荒川と貢川の合流地点にあります。
釜無川の氾濫で流れ込んだ濁流をこの地点で南流する荒川に落とし込むことができれば、これ以東(国中の主要エリア)への浸水を防ぐことができます。
荒川は奥秩父の国師岳を源流とし、昇仙峡を形成して甲府市内へ流れ下る急流で、甲府盆地にたびたび水害をもたらしました。
昭和34年(1959年)の伊勢湾台風でも氾濫し大きな被害を受けましたが、市街地を縦断し河川改修がむずかしいため、昭和61年(1986年)春、上流に荒川ダムが完成整備されました。
荒川と貢川の合流地点のすぐ下流にある甲府市相生の住吉山 千松院は、武田家が荒川の水難よけの寺として建立したとされ、荒川の水害がいかに深刻であったかがうかがわれます。
■ 住吉山 千松院

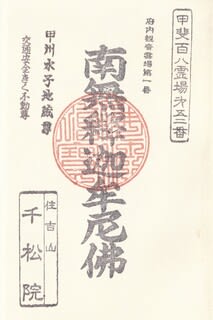
公式Web
甲府市相生3-8-9
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第52番、府内観音札所第1番
〔甲斐百八霊場第52番の御朱印〕
朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 印判
・中央に三寶印と御本尊「南無釈迦牟尼佛」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第五二番」と「府内観音札所第一番」の札所印。左には甲州水子地蔵尊、交通安全きく不動尊の印判と寺院印が捺されています。
創建は天正年間(1573年~1591年)。
かつて境内に水の安全を祈る住吉神社の祠もありましたが、関東大震災で崩壊してしまったとのこと。
甲府の住吉神社では、甲府市住吉の住吉神社が有名ですが、同社Webには「人皇第四十五代聖武天皇の御代(七二四)荒川の川辺高畑村内に鎮座するも甲斐源氏武田太郎信義公の願望にて 稲積荘一条郷に奉勧請」とあり、わざわざ旧社地を「荒川の川辺」と明記しているので、荒川の川除けと住吉神社はもともとつながりがあるのかもしれません。
現在は水子供養の寺として有名ですが、かつては府内観音札所第1番札所(振り出しの寺)として、巡礼者で賑わったようです。
また、甲府城の鬼門除けとして伝わる白狐に乗った不動明王も本堂に祀られています。
甲府の中心部に堂々たる山門を構えています。
おそらく薬医門と思われる八脚三間三戸の単層門で、「住吉山」の扁額。
二軒の平行垂木を配し、木戸門までもが本瓦葺の豪勢な門です。
本堂向かって左手前に聖観世音菩薩の石造立像。こちらは、関東大震災で崩壊してしまった観音堂(の観音さま)を平成元年に建立復興されたもので、府内観音霊場第一番(振り出し)の観音さまとなっています。
本堂はおそらく宝形造で銅板葺。屋根上に相輪を構えています。伏鉢、九輪、水煙、竜車、宝珠を備える伽藍様式に則ったものです。
向拝部正面はサッシュ扉ですが、両脇の花頭窓が意匠的に効いています。
拝みの扁額は院号「千松院」。
境内には、「府内観音札所第一番」を示す標識や御詠歌碑がいくつかありましたが、甲斐百八霊場第52番を示すものは見当たりませんでした。
考えてみれば、「府内観音札所第一番」の方がはるかに古い札所ですから、当然かもしれません。
〔 大御幸祭と三社神社の御祭神 〕
→山梨県神社庁の三社神社の資料には「里人相計りて三社神社の御祭神を勧請せしめ創立す。四月十五日の一宮浅間神社三社神社間三十キロの大御幸祭は県下一の大祭なり。」とあります。
また、多数の資料に「甲斐国の一宮浅間神社(笛吹市)、二宮美和神社(笛吹市)、三宮玉諸神社(甲府市)から各祭神が渡御し、この地で水防祈願を行うために置かれた神社と伝えられています。」とあります。
一宮、二宮、三宮から水防祈願のために御祭神が勧請されたとすると、木花開耶姫命(甲斐国一宮 浅間神社)、大物主命(美和神社)は符合しますが、大国主命が符合するには、玉諸神社の御祭神・國魂大神命(国玉大明命)と大国主命が同体か近い神格と考える必要があります。
國魂大神命(国玉大明命)は謎の多い神格のようですが、字と音の通じる多摩の大社、大國魂神社の御祭神・大國魂大神は出雲の大国主神と御同神とされるので、この系譜が考えられるかもしれません。
一方、→山梨県神社庁の三社諏訪神社の資料には「甲斐国一宮浅間、二宮美和、三宮国玉の三神を勧請し鎮座、同年三月水防祭を行ふといふ。」とあります。三社から勧請された御祭神は木花咲耶姫命、大国主命、大国玉命とみられます。金刀比羅宮のWeb資料には「大物主神は、大国主神(おおくにぬしのかみ)の和魂(にぎみたま)に当たる神さま」とありますので、軽々には考えられませんが、大神幸祭は、木花咲耶姫命、大国主神、大国主神の和魂(大物主神)がお渡りになるという性格のお祭りなのかもしれません。
〔 信玄公、信玄堤と御幸祭 〕
甲府盆地はもともと水害の多い土地柄でした。
東に笛吹川、西に釜無川と御勅使川が流れ、これらの河川が氾濫すると、濁流が甲府盆地に流れ込みました。
なかでも、釜無川と御勅使川が合流する盆地西北の竜王付近は氾濫の常襲地帯で、この場所の治水は甲斐国の歴代の課題でした。


【写真 上(左)】 信玄堤説明板
【写真 下(右)】 築堤本陣の碑


【写真 上(左)】 信玄堤から上流(北)方向
【写真 下(右)】 信玄堤から下流(南)方向
信玄堤に設置されている「信玄堤から見た山々」に載っている山は、櫛形山(2052m)、農鳥岳(3026m)、辻山(2585m)、鳳凰三山(2762m~2841m)、甲斐駒ヶ岳(2966m)などで、軒並み2000mを越え、御勅使川が屈指の急流であることがわかります。


【写真 上(左)】 聖牛と釜無川
【写真 下(右)】 対岸御勅使川方向
「幹川となる釜無川は、竜王を扇頂にして、約90°の角度を持って東側から南側へと扇状地を形成している。釜無川は、この扇頂の竜王から盆地内へと乱流し、結果として東側へと広大な扇状地を形成してきたのである。したがって、甲府盆地の治水安全度を向上させるには、まず釜無川の盆地内への切れ込みを防止する必要があり(以下略)」(甲斐武田の治水策の問題点とその限界 - 御勅使川分流の終焉 -/岩屋隆夫氏 2005)以下「資料B」)
「(甲斐武田が考案したのが)築立地点の右岸側に強固な石積み堤防を配置しながら御勅使川の幹川河道を徐々に東北東へと移し、この先にある龍岡台地の南端を掘り込んで「新堀」を開削することによって河道を固定して、これに加えて、釜無川合流点の直上流に「十六石」という巨岩を配して御勅使川の洪水流が釜無川左岸の韮崎火砕流台地、別名「高岩」に当たるよう導いたのである。」
「高岩を直撃するようになった釜無川と御勅使川の洪水流は、高岩に当たって右岸側へと反転し、その反転した先に本御勅使川から分流する前御勅使川の洪水流を当てて揉み合わせ、そうすることによって洪水流の勢いを削いだのである。」
「一方、釜無川右(左?)岸には、扇頂から下流に向かって強固な堤防が築かれた。信玄堤である。」(以上、資料Bより)
→ 御勅使川流路換えのための石積出しなど


【写真 上(左)】 聖牛の模型-1
【写真 下(右)】 聖牛の模型-2
この信玄公の治水策は、永禄二年(1559年)から明治二十九年(1896年)の大水害まで、じつに三百年以上にも渡って甲府盆地を護りぬきました。
しかも明治二十九年(1896年)の大水害の原因は、1800年頃から深刻化した(本)御勅使川の河道土砂埋積((前)御勅使川への分流不全)という、信玄公の時代には予見できなかった事柄が大きいとみられています
「この1896(明治29)年水害によって、信玄堤は築堤以来、初めて破堤した。甲府盆地の治水の要というべき信玄堤が破堤したのであるから、甲府市民など地域住民にとって驚愕すべき事態になったであろうことは想像に難くない。しかも、信玄堤の決壊は明治以降もこの1896(明治29)年水害の1回しか無い。」(資料B)
この明治二十九年の信玄堤破堤の衝撃は、別の資料からもうかがえます。(→ 信玄堤と御幸祭 - 近世・近代甲斐国における武田信玄顕彰 -/中野賢治氏 2020年以下、資料C)
同年11月、竜王村長・陳情委員が連名で内務大臣に提出した陳情書です。要所を抜粋引用します。(資料Cからの孫引きです)
「其急流激湍、県下危険ノ第一ニ位セリ、縦横奔注毎ニ惨害ヲ極メシヲ以テ武田氏ノ時ニ至リ、堅牢無比ノ堤防、及ヒ前囲トシテ石瘤数十本ヲ築造シ、防禦ノ大策ヲ画シ、百年ノ長計ヲ講セラル」
「信玄公築造ノ堤防ヲ本堤トシ、表囲ニハ一番ヨリ五番ニ至ル土出堤防ヲ設ケ、大聖牛・中聖牛・大枠・中枠、其他種々ノ方法ヲ行ヒ防禦セシヲ以テ、其工事ハ古ク天文年間ノ施設ナルニモ係ハラス、爾来歳月ノ久シキ、未ダ曽テ信玄堤防ノ破壊セシヲ聞カズ」
「(明治二十九年)九月八日ヨリ猛雨連日、河水為メニ暴漲シ、激浪奔騰、危機一髪ノ間ニ在リ、是ニ於テ人民昼夜ヲ分タス只管防禦ニ尽力セシモ、終ニ其効ヲ奏セス、十二日午前八時、改修堤防ニ破壊ヲ生ジ、午前十時ニ至リ延長百七十余間ヲ流失シ、加之信玄堤防ノ一部同時ニ決潰セリ」
「安危存亡ノ関係スル所、実ニ県下大半ニ及フノ要衝ナレハ、現今ノ如キ設計ニテハ下流町村幾万ノ生霊、一日モ枕ヲ高フスルコト能ハサルノ悲境ニ淪落セサル可ラサルコト予想セラル、以上開陳スル所ノ実況ヲ洞察シ、衷情ヲ容納シ、速ニ堅牢不抜、万代無窮ノ工事ヲ設計セラレンコト至願切望ノ至リニ堪ヘス」
要約すると、天文年間の堤防にもかかわらず一度も決壊したことのない信玄堤が一部とはいえ決壊したとあっては、一日も枕を高くして(安眠)することはできず、速やかに堅牢で万代安全な堤の補強工事を切望します、といったところでしょうか。
また、この陳情書には「追伸書」が付されています。要点を引用します。
「三百三十年来未タ曽テ決損シタルコトナキ信玄堤防ノ之ニ継テ決壊シ、災害ヲ三中郡筋各村ヘ臻シタルハ、一見実ニ奇変ト云ハサルヲ得ス」
「堅牢ナル信玄堤ハ優ニ此滔流ヲ反溌シ得テ、堤内各村ハ無難ナリシナラント雖モ、不幸改修堤ハ旧四番堤ノ起点ニ於テ信玄堤ニ連接シ、其状恰カモ不規則ナル楕円形ヲ為セシヲ、以テ前陳ノ如ク改修堤ノ一部決壊セルニ於テハ、其決所ヨリ浸入スル滔流ハ、盤中ニ入ルカ如ク出ルニ路ナク、為メニ旋転渦廻シテ信玄堤ノ最低所ヲ求メテ超然奔逸スルニ至レリ(略)終ニ堅牢不抜ノ信玄堤ハ其一部ヲ決壊スルニ至リタリ(略)堅牢ナル修築工事ヲ設計セラルヽニハ、単ニ復旧工事ヲ以テ足レリトセス、希クハ前陳決壊当時ノ実況ヲ審ニ洞察セラレ、堅牢ナル信玄堤ノ効用ヲ全カラシメラレンコトヲ切望ノ至リニ堪エズ」
要約すると、堅牢な信玄堤は優に濁流を押し返していたが、信玄堤と連続する改修堤防により信玄堤に当たった水流が出口を失いすべなく決壊に至ったとし、信玄堤自体は堅牢なので、信玄堤を活かすかたちで改修工事を進めてほしいと嘆願している、というところでしょうか。
一部決壊したとはいえ、住民の信玄堤に対する信頼はなお根強いものがあったことがうかがわれ、実際、信玄堤は残されて別に改修堤防が設けられ、信玄堤公園付近は二重堤防になっています。


【写真 上(左)】 釜無川河原の聖牛
【写真 下(右)】 信玄堤と大御幸祭三社の位置関係
資料Cは、このような信玄堤の決壊への衝撃が、明治三十六年の竜王武田神社の改築に深く関わっていると推察しています。
■ 竜王武田神社


【写真 上(左)】 神明神社社頭
【写真 下(右)】 神明神社拝殿(右手奥が武田神社)


【写真 上(左)】 武田神社
【写真 下(右)】 武田神社拝殿
→山梨県神社庁資料
甲斐市竜王2089(神明神社境内鎮座)
御祭神:武田晴信公
※御朱印授与情報は未確認です。
竜王下宿の神明神社境内に鎮座する、武田信玄公を祀る神社です。
資料Cでは、『町村取調書/名所旧跡補足』(大正五年)の「信玄祠。信玄堤畔ニアリ、古昔ハ一片ノ石龕、茂林光密竹ノ間ニ没シ、里人猶其存在ヲ知ラザルモノアリシガ、明治八年有志相謀リ、樹ヲ伐リ地ヲ拓キ祠堂ヲ造営セリ、規模大ナラズト雖モ結構完美ヲ極ム」を挙げ、「『信玄堤畔』に所在することなどから、この『信玄祠』が現在の竜王武田神社を指すものとみられる。」としています。
また、『龍王村史』には「武田信玄の恩沢をたたへて、従来信玄堤の附近に信玄を祭神とした武田神社があつたが、明治維新の際に免租屋敷は悉く有租地となると共に、段々荒廃し、社殿も失ひ、祭儀も行ふことが出来なくなつたので、明治三十六年、同村斎藤源六・久保田辨二郎・青柳徳太郎・丹沢益蔵・輿石龜五郎等の信徒総代が発起して、此所に社殿改築の計画が進められた。」とあります。
つまり、明治八年、信玄堤畔に祀られた信玄祠を、明治二十九年の信玄堤破堤を受けて明治三十六年、(現社地に?)竜王武田神社として改築したという見立てです。
古府中町の武田神社の創建は大正八年(1919年)、これに対して竜王の信玄祠の創祀は明治八年(1875年)、竜王武田神社の「改築」でも明治三十六年(1903年)ですから、古府中の武田神社よりも古い歴史をもつということになります。
(この点は、→このサイトでも指摘されています。)
甲斐市竜王下宿の信玄堤のすぐ下、神明神社の境内に鎮座します。
神明神社の神明造の社殿の右手おくに、ひっそりと鎮座しています。
社頭にしめ縄のかかった門柱と、石の社号標には「武田神社」とあります。
降棟を備えた一間の方形造?で、小振りながら存在感ある社殿です。
暗くなってからの参拝だったので、装飾など詳細は不明ですが、水引虹梁の両端に木鼻、海老虹梁、桟唐戸の構えだったと思います。


武田神社のさらに堤防寄りに「お水神さん」が祭られていました。
信玄堤にゆかりの水神様で、由来書もあったので抜粋引用します。
「この堤防は武田信玄公が築堤したもので世に言う信玄堤であります。明治二十九年に破堤されるまで約三百五十年の永きにわたり洪水を防いだ立派な堤防であります。この所は明治二十九年に堤防が決壊した地点であります。その時に国や県、地元住民により堤防を修復すると同時に、明治三十三年八月一日に水防の神を現時点に奉安いたしました。以来、約100年の間平穏無事に過して参りました。このことはひとえにこのお水神さんのご加護の賜であると信じて、地元住民は毎年祭礼を執り行い、敬愛の念を捧げて現在に至っております。この度、竜王芦安線橋梁工事に当りこの尊いお水神さんを新たなこの地に遷座いたしました。これからはこのお水神さんをなお一層崇拝し水防の誠を末永く尽くして参りたいと考えております。 平成六年九月一日」
住民の方々の信玄堤に対する感謝と、水防への願いが伝わってくる内容です。
ところで、資料Cの筆者は「史料のなかでも、御幸祭と武田信玄との関係に触れるものは少なかった。」とされ、明治二十年代以降、大御幸祭と信玄公のかかわりを示す資料が増えることを指摘されています。
大御幸祭と武田公の関係を示す資料として「明治二八年の内務省訓令第三号をうけて行われた社寺調査」資料を例示し、以下の内容を挙げられています。
1.三社神社は武田信光公(1162~1248年)の代から武田家との関係があった。
2.大御幸祭は信玄公が創設したものとし、祭道中での「オコシヨウメンシヨウ」という囃子言葉も、信玄公の時代に「御輿名将」と言っていたのが訛ったものだとしている。
明治二十年代から始まる釜無川堤防改修は、当初、信玄堤を破壊し改修堤防に置き換える
計画であったとみられています。しかし、実際には信玄堤は残され、改修堤防と信玄堤の二重堤防という形となりました。
これについて資料Cの筆者は、「このとき、竜王信玄堤が失われるかもしれないという危機感が、武田信玄を介して、竜王信玄堤と御幸祭を結びつけることになったのではなかろうか。さらに決壊に至り、再建の過程で竜王信玄堤が失われるかもしれないという危機感が拍車をかけ、御幸祭は竜王信玄堤の保存を訴える一つの方法として利用されるようになっていたのであろう。」と考察されています。
おそらくはそういうことなのかもしれません。
ただし、大御幸祭の主役?である三社(一宮、二宮、三宮)は、上記のとおり、歴代武田家、あるいは信玄公の尊崇を受けていたことは明らかなので、間接的に大御幸祭に係わっていたという見方は許されるかと思います。
【 甲府と風水 】
風水については専門に扱う方がおられ、いろいろな説があるのですが、↑をまとめているうちになんとなく感じたことがあるので、書いてみます。
風水にもとづく都市計画では、「四神=山川道澤」策が代表例とされています。
「四神相応」ともいわれ、北には山岳があって玄武が棲み、東には河川(流水)があって青龍が棲む。西には大道があって白虎が棲み、南には湖沼・低地(または海)があって朱雀が棲む。という地勢です。
昨今は空前の風水ブーム、城郭ブームなので、甲府(躑躅が崎館)の風水もさぞや研究されているかと思いきや、意外と関連Webはみつかりませんでした。
なので、地図を頼りに個人的に推測してみます。
北の山岳は、背後の要害城からつづく奥秩父の山々。そこには霊山・金峰山も含まれています。
東の河川は笛吹川。奥秩父から流れ出る清流が盆地を潤しています。
西の大道は北方面に甲州街道、南方面に駿州(甲州)往還。甲州街道は下諏訪で中山道に合流し京に至ります。駿州(甲州)往還も駿河国内で東海道に合流し、京に至ります。
南の湖沼は盆地南部。甲府には「蹴裂伝説」「湖水伝説」(かつて甲府盆地は湖であった。)が残っており、符合します。(蹴裂伝説に関連する神社として、宝の穴切大神社、中央の甲斐奈神社、下向山の佐久神社、石和の佐久神社、市川の蹴裂神社などが知られています。)
これをみると、甲府(躑躅が崎館)は、風水に叶った地勢となっていることがうかがわれます。
しかし、気になる点もあります。
西の山岳(南アルプス)と河川(釜無川・御勅使川)の勢いがすこぶる強いことです。
山が高ければ、当然そこから流れ下る河川の勢いも激しくなります。実際、御勅使川はわが国有数の急流として知られ、その名も水害の際に朝廷から遣わされた「勅使」にちなむといういわくつきのものです。
信玄堤のあった竜王町は「有富山慈照寺に湧く竜王水に由来」という説もありますが、一般には釜無川・御勅使川の治水との関連が想像されるところかと。
信玄公はこの強すぎる河川(龍)を鎮めるために、信玄堤を築き堤道を通して風水を整え、川除けの祭事である大御幸祭をつづけた、という見方もできるかもしれません。
【 蹴裂伝説 】
甲府盆地には、「蹴裂伝説」(湖水伝説)という伝説が残っています。
甲府市資料などを参考にまとめてみます。
蹴裂(けさく)伝説とは、地形の変化変遷や人による地形の改変(干拓など)を伝える伝説をいい、日本各地に残っています。
甲府の「蹴裂伝説」は湖にかかわるものなので、「湖水伝説」とも呼ばれます。
はるか昔、甲府の地は一面の湖水でした。
地蔵菩薩がこの様子をご覧になり、「この水を排して陸地にしたら、人も住めるし田畑もできる。なんとかならぬものか。」とお二方の神様に相談をされました。
これを聞かれた神様たちは「いかにも道理」と賛成され、ひとりの神様が山の端を蹴破って、もうひとりの神様は山に穴を開け、水路を開いて湖水を富士川へ落とされました。
これを見ていたお不動様は、「わたしも一役」とばかり川瀬を造り手伝われました。
この二仏二神のおかげで、甲府の土地は湖の底から現われました。
山を蹴破った神様は蹴裂大明神、山に穴を開けた神様は穴切大明神、計画をされたお地蔵様は国母地蔵尊、川瀬を造られたお不動様は瀬立不動尊と伝わります。
石和の佐久神社の由緒(山梨県神社庁資料)などによると、「天手力雄命が大岩を裂いて水を涸らし現在の地となした」という伝承もあります。
また、下向山の佐久神社の由緒(山梨県神社庁資料)には「彦火火出見尊の後裔向山土本毘古王は媛靖天皇の勅命により国造として甲斐に入国一面の湖水を切り開き平土を得、住民安住の地を確保した功績は偉大なるもの(略)佐久大明神として祀られた」とあります。
甲府の「蹴裂伝説」は異説も多く錯綜しているのですが、「天手力雄命に関係のある山土本毘古王=佐久大明神=蹴裂大明神」と仮定すると、二仏二神に関係するとみられる寺社はつぎのとおりとなります。
・蹴裂大明神:市川の蹴裂神社、下向山の佐久神社、石和の佐久神社
・穴切大明神:宝の穴切大神社
・国母地蔵尊:国母の上条(稲積)地蔵尊、東光寺(町)の稲積(国母)地蔵尊
・瀬立不動尊:笛吹市境川「藤垈の滝」の芹沢不動尊
※ 「藤垈の滝」は、古来、すぐ向かいにある万亀山 向昌院(甲斐百八霊場第45番)の禊ぎの場であったと伝わります。


【写真 上(左)】 蹴裂神社
【写真 下(右)】 蹴裂神社からの笛吹川と釜無川方面


【写真 上(左)】 下向山佐久神社社頭
【写真 下(右)】 下向山佐久神社


【写真 上(左)】 藤垈の滝と芹沢不動尊
【写真 下(右)】 芹沢不動尊

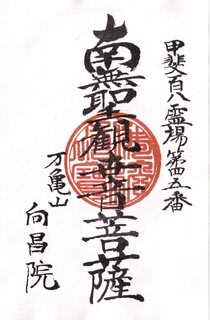
【写真 上(左)】 万亀山 向昌院
【写真 下(右)】 万亀山 向昌院の御朱印
これとは別に、稲積神社、韮崎市旭町の苗敷山穂見神社、甲府市中央の甲斐奈神社も「蹴裂伝説」ないしは「疏水工事による開拓」とのゆかりをもつとされます。


【写真 上(左)】 稲積神社
【写真 下(右)】 稲積神社の御朱印


【写真 上(左)】 甲斐奈神社
【写真 下(右)】 甲斐奈神社の御朱印
稲積神社の社伝には、「湖岸を切り開き湖水を富士川に落として」国を拓かれたのは四道将軍武淳川別命で、当社はその国土の「蒼生愛撫、五穀豊穣、祈願のため、丸山に奉斎」されたとあります。
苗敷山穂見神社には「甲斐の国が洪水により湖水と化した時、鳳凰山に住む大唐仙人が、蹴裂明神と力を併せ南山を決削して水を治め平野とし、里に住む山代王子がこの地を耕し、稲苗を敷き民に米作りの道を教えた。大唐仙人を国立大明神、山代王子を山代王子権現として 両神を山頂に祀り苗敷山と呼んだ。」との創祀が伝わっているようです。(→出所)
「蹴裂伝説」の二仏二神のうち、信玄公との関連が見つかったのは、国母の上条地蔵(法城寺)、穴切大神社のふたつです。
■ 国母の上条地蔵(上條法城寺)


→甲府市資料(国母稲積地蔵立像)
甲府市国母8-12-27(児童公園内)
※御朱印授与情報は未確認です。
甲陽軍鑑品第四(国会図書館DC、コマ番号17/265)に「蹴裂伝説」についての記載があります。
「上條法城寺には洛北さがの策諺和尚御座候 此法城寺は甲州上古は湖なりと聞 上條ぢぞうぼさつの御誓にて南の山をきりて一國の水悉とく富士川へ落つるにより甲州國中平地と成て今如件なり さるに拠て上條ぢぞうだう(堂)とは申せ共 寺號をば法城寺と申す 此文字は水去リテ土ト成ルと云うとはり也 法城寺破れば甲州はすいび(衰微)也 末代迄も甲州持侍は此寺上條法城寺を建立有べし 此の寺に策諺和尚五年の間住み給ひ候」
策諺和尚は、恵林寺に住持されていた惟高和尚とともに、信玄公に臨済宗妙心寺関山派での修行を薦め、長禅寺の岐秀元伯への参禅を促したとされる高僧です。(『甲陽軍鑑』)
法城寺は、「蹴裂伝説」ゆかりの上条地蔵尊を祀る寺院で、上条地蔵尊が甲斐国の治水を守護される重要なお地蔵様として信仰されていたことがわかります。
甲府市資料には、行基が治水策を施し、お地蔵様を刻して篠原の岡(甲斐市篠原)に法城寺を建立、治水祈願をされて祀ったとあります。
上記資料には「(法城寺の地蔵尊は、)平安時代に新羅三郎義光公により国母に移され、のちに信虎公が武田氏館の近くに移され、さらに天正年間に東光寺村に移されましたが、昭和20年の空襲によって焼失してしまいました。現在の(国母地蔵の)像は、武田氏が館の近くに移したときに、代仏として残した像であると伝えられています。」とあります。
現在も地域の信仰を集め、甲府市の市指定文化財に指定されています。
東光寺西方山中の「稲積地蔵」が「国母の上条地蔵」であるという説もみられます。
■ 穴切大神社






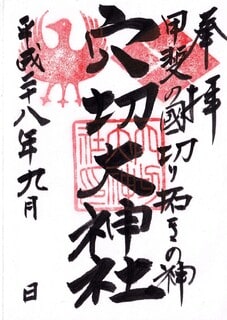
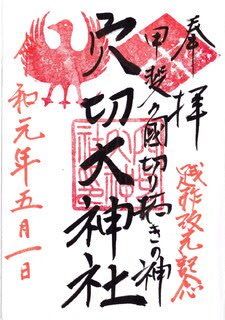
【写真 上(左)】 通常の御朱印
【写真 下(右)】 令和初日の記念御朱印
→山梨県神社庁資料
甲府市宝2-8-5
御祭神:大己貴命、少彦名命、素盞鳴命
旧社格:式内社(小)論社、郷社
授与所:境内授与所
朱印揮毫:穴切大神社 直書(筆書)
※オリジナル御朱印帳も頒布されています。
当社に係わる山梨県神社庁資料には「その頃の甲斐の国中は大半湖水にて、時の国司巡見して湖水が引かば跡地は良き田にならうと、朝廷に奏聞して裁可を得、その上国造神に座します。大己貴命に祈願をこめて(略)富士川より南海に水を落すに成功した。為に湖水の大半が退き今日の如き良田数多を見るに至った。これ偏に御神助の賜と勅命を以て勧請、穴切大明神と奉称、国中鎮護の神と崇敬されるやうになった。」とあります。
御祭神は大己貴命、少彦名命、素盞鳴命で、開拓工事の際、国司が祈願をこめたのが大己貴命で、のちに「穴切大明神」と奉称した、という文脈だと思います。
ただし、「蹴裂伝説」の穴切大明神を祭祀していたという説もあるようです。
信玄公との関係は、資料Aに「神宝には信玄が使用したと伝えられるわん、武田信勝所持と伝える面」とあり、「箱棟には武田菱がみられ、勝頼ないしは他の武田一族の造営ではないかともいわれる。」ともあります。
社頭の社号標、石造明神鳥居の扁額ともに「穴切大神社」。
随神門は入母屋造三間一戸の堂々たる楼門で、境内説明板によると寛政六年(1794年)に下山大工の竹下源蔵を棟梁に建立、彫刻は諏訪立川流(宮彫りの流派)初代和四郎富棟の手になるもので、とくに動植物の彫刻に優れ、甲府市の文化財に指定されています。
神楽殿は銅板葺の向唐破風が見事。箱棟にはたしかに金色の武田菱が輝いています。
神楽殿の前には、なぜかヤタガラスとおぼしきイラストがある「ラッキーゴール」が置いてあるのですが、熊野信仰と特段の結びつきが認められない当社に、なぜヤタガラスがいるかは不明。
「蹴裂伝説」の「蹴る」からサッカーゆかりの神社となり、日本サッカー協会(JFA)のシンボルマークは「ヤタガラス」なので、「蹴裂伝説」つながりかとも思いましたが、この記事をみるとそうでもなさそうです。
ただし、「サッカー神社」として有名らしく、カラスの木像も伝わっているそうなので、それによってヤタガラスをゆかりとされているような感じがします。
ヤタガラスは御朱印にも登場します。
八咫烏の印と武田菱が並んで捺されているのは、なんとなく不思議な感じもしますが、甲斐源氏の祖とされる源義清公が甲斐目代として平塩に館を構えたとき守護神として祀ったのは熊野神社なので、あながちご縁がないとはいえないと思います。
オリジナル御朱印帳も武田菱とヤタガラスをモチーフとしています。
本殿は檜皮葺の一間社流造。各所に桃山時代の特徴を残し、国の重要文化財に指定されています。
本殿は近寄れないですが、正面上部の斗栱、垂木、手挟まわりの彩色は遠目からも見事です。
こちらも大棟や箱棟に金色の武田菱が燦然と輝いています。
拝殿はコンクリ造の近代的なもの、新旧いろいろ入りまじり、面白い雰囲気の境内でした。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
Vol.2が字数制限に引っかかったので、Vol.2AとVol.2Bに分割しました。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
■ 三社神社




→山梨県神社庁資料
甲斐市竜王188
御祭神:木花開耶姫命、大物主命、大国主命
旧社格:村社
※御朱印は授与されていないとみられます。
大御幸祭で一宮、二宮、三宮の三社の御輿が御渡され、川除の祈願が執り行われる神社です。
〔 境内説明板および山梨県神社庁資料より 〕
天長二年(825年)秋、甲斐の国中地方に大水害が発生した際(大水禍を蒙り狭野一朝にして荒蕪地と化し、人畜の死傷算なく、又悪疫流行す。/山梨県神社庁資料)、時の国司文屋秋津が朝廷にその惨状を奏上、勅旨に依り(甲斐)国内代表社として、浅間神社、美和神社、玉諸神社の神官に命じ神璽を行幸して水防祈願を此の地に於て行ったと伝わる古社です。
以来、明治七年(1874年)までは毎年四月第二亥の日に甲斐国一宮浅間神社、二宮美和神社、三宮玉諸神社の三社が合同して各社から御輿等が御渡し、信玄堤(龍王川除)上で水防の神事として御幸祭が行われてきました。(里人相計りて三社神社の御祭神を勧請せしめ創立す。/同上)
貞享三年(1686年)の本殿建立寺に「御旅殿」とされていることから、この頃までの当社は、御旅所(神社の祭礼巡行の際、神輿が途中で休憩・宿泊する場所、ないしは神幸の目的地を指し、通常、御旅所に神輿が着くと御旅所祭が執り行われる。)の性格が強かったことがうかがわれます。
北方茅が岳からの山裾が釜無川に接する要地。釜無川・信玄堤を西に、竜王用水を足元に、南向きに鎮座します。
石造の台輪鳥居は転び(傾斜)をもつ太い柱で、存在感があります。桃山時代の造立とみられ市の指定文化財です。扁額には「三社大明神」とあります。
階段を昇って正面の拝殿は入母屋造銅板葺で均整のとれた意匠。
現在の本殿は「御旅殿」の名で貞享三年(1686年)に建立され、宝永四年(1707年)三社明神社として修造されています。
桁行三間、梁間二間のゆったりとした三間社流造で、一宮、二宮、三宮を祀るための規模をもっているとされています。
社殿まわりは立木がすくなくスペースがあり、大御幸祭の神事に備えたものかとみられます。
■ 三社諏訪神社


【写真 上(左)】 鳥居と境内(左奥が諏訪神社)
【写真 下(右)】 三社神社の拝殿


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 諏訪神社
→山梨県神社庁資料
甲府市上石田2-29-2
御祭神:木花咲耶姫命、大国主命、大国玉命、建御名方命
旧社格:村社
※御朱印授与情報は未確認です。
大御幸祭で一宮、二宮、三宮の三社の御輿が御渡されていた神社です。
上石田の住宅地の路地に面して鎮座しますが、境内は相応の広さをもちます。
社頭から向かって右が三社神社、左が諏訪神社です。
三社神社の石造鳥居は反増で貫の抜けがなく、台輪と亀腹と高さのある根巻をもち、柱間が狭いわりに高さがあるという独特な形状で、種類はよくわかりません。
鳥居の扁額は摩耗がはげしく判読できませんでした。
狛犬、社殿ともに基礎材で嵩上げされたかたちになっており、これは浸水に備えたものかもしれません。
拝殿は入母屋造銅板葺唐破風向拝付き。水引虹梁に木鼻、中備に板蟇股。
桟唐戸の上に「三社諏訪大神」の扁額。
本殿は一間社流造で二軒の平行垂木に複数の飾り懸魚を備え、蓑甲の仕上げがテクニカル。
右手の諏訪神社の鳥居は足太の台輪鳥居でこちらも扁額の判読不能でしたが、境内縁起書きによると「諏訪大明神」とのこと。
狛犬一対、正面に石造の祠。
境内縁起書によると、かつては社殿がありましたが明治七年火災で焼失したようです。
<境内縁起書(抜粋)>
・三社諏訪神社
「諏訪神社と三社神社が隣接して祀られていたが、明治七年諏訪神社は火災にて焼失。明治十年三社神社に合祀してから以来三社諏訪神社と申す。」
・三社神社
「天長年間毎年のように豪雨に見舞われ釜無川は洪水氾濫しとその水勢は玉幡、下河原、上石田その他下流の低地全域におよびその惨状はみるかぎりもない有様だった。時の国守文屋秋津は朝廷に奏上、勅旨に依り、一宮浅間神社祭神(木葉開姫命)、二宮美和神社祭神(大巳貴命)、三宮玉幡多神社祭神(大国主命)の三つの宮の分霊を合祀せよといい三社神社が建立されました。その後歴代の国守(知事)が祭主となり県民一丸となって、本宮から竜王・上石田と御輿が御渡され、水害・火災・悪疫の退散その他五穀豊穣を祈願しました。」
また、山梨県神社庁資料には「天長三年大洪水があり、甲斐国一宮浅間、二宮美和、三宮国玉の三神を勧請し鎮座、同年三月水防祭を行ふといふ。それより三社神社と称し四月十五日の祭儀には三社の神輿の神幸があったるも、明治七年よりは浅間神社のみとなる。」
とあり、大御幸祭の御輿が竜王の三社神社ののちに御渡されていた可能性があります。
(御幸祭で三社の御輿の御旅所として機能したのかもしれません。)
□〔追記〕
一宮浅間神社の公式Webに「大神幸祭は、甲斐国第一大祭と称され、社記によれば天長二年(八二五年)以来旧四月第二の亥の日、甲斐市竜王三社神社に神幸の上、川除祭(水防祭)を執り行って来たが、明治以後四月一五日と改め本社にて例大祭執行の後、同所及び甲府市上石田三社神社に神幸。(現在は竜王三社神社のみ)片途約6里(24km)に及ぶ行程であり現在、二宮、三宮も同所に神幸している。」とあり、以前は上石田の三社神社にも神幸されていたことが裏付けられます。
上石田は国中屈指の暴れ川、荒川と貢川の合流地点にあります。
釜無川の氾濫で流れ込んだ濁流をこの地点で南流する荒川に落とし込むことができれば、これ以東(国中の主要エリア)への浸水を防ぐことができます。
荒川は奥秩父の国師岳を源流とし、昇仙峡を形成して甲府市内へ流れ下る急流で、甲府盆地にたびたび水害をもたらしました。
昭和34年(1959年)の伊勢湾台風でも氾濫し大きな被害を受けましたが、市街地を縦断し河川改修がむずかしいため、昭和61年(1986年)春、上流に荒川ダムが完成整備されました。
荒川と貢川の合流地点のすぐ下流にある甲府市相生の住吉山 千松院は、武田家が荒川の水難よけの寺として建立したとされ、荒川の水害がいかに深刻であったかがうかがわれます。
■ 住吉山 千松院

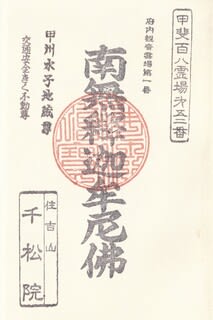
公式Web
甲府市相生3-8-9
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第52番、府内観音札所第1番
〔甲斐百八霊場第52番の御朱印〕
朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 印判
・中央に三寶印と御本尊「南無釈迦牟尼佛」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第五二番」と「府内観音札所第一番」の札所印。左には甲州水子地蔵尊、交通安全きく不動尊の印判と寺院印が捺されています。
創建は天正年間(1573年~1591年)。
かつて境内に水の安全を祈る住吉神社の祠もありましたが、関東大震災で崩壊してしまったとのこと。
甲府の住吉神社では、甲府市住吉の住吉神社が有名ですが、同社Webには「人皇第四十五代聖武天皇の御代(七二四)荒川の川辺高畑村内に鎮座するも甲斐源氏武田太郎信義公の願望にて 稲積荘一条郷に奉勧請」とあり、わざわざ旧社地を「荒川の川辺」と明記しているので、荒川の川除けと住吉神社はもともとつながりがあるのかもしれません。
現在は水子供養の寺として有名ですが、かつては府内観音札所第1番札所(振り出しの寺)として、巡礼者で賑わったようです。
また、甲府城の鬼門除けとして伝わる白狐に乗った不動明王も本堂に祀られています。
甲府の中心部に堂々たる山門を構えています。
おそらく薬医門と思われる八脚三間三戸の単層門で、「住吉山」の扁額。
二軒の平行垂木を配し、木戸門までもが本瓦葺の豪勢な門です。
本堂向かって左手前に聖観世音菩薩の石造立像。こちらは、関東大震災で崩壊してしまった観音堂(の観音さま)を平成元年に建立復興されたもので、府内観音霊場第一番(振り出し)の観音さまとなっています。
本堂はおそらく宝形造で銅板葺。屋根上に相輪を構えています。伏鉢、九輪、水煙、竜車、宝珠を備える伽藍様式に則ったものです。
向拝部正面はサッシュ扉ですが、両脇の花頭窓が意匠的に効いています。
拝みの扁額は院号「千松院」。
境内には、「府内観音札所第一番」を示す標識や御詠歌碑がいくつかありましたが、甲斐百八霊場第52番を示すものは見当たりませんでした。
考えてみれば、「府内観音札所第一番」の方がはるかに古い札所ですから、当然かもしれません。
〔 大御幸祭と三社神社の御祭神 〕
→山梨県神社庁の三社神社の資料には「里人相計りて三社神社の御祭神を勧請せしめ創立す。四月十五日の一宮浅間神社三社神社間三十キロの大御幸祭は県下一の大祭なり。」とあります。
また、多数の資料に「甲斐国の一宮浅間神社(笛吹市)、二宮美和神社(笛吹市)、三宮玉諸神社(甲府市)から各祭神が渡御し、この地で水防祈願を行うために置かれた神社と伝えられています。」とあります。
一宮、二宮、三宮から水防祈願のために御祭神が勧請されたとすると、木花開耶姫命(甲斐国一宮 浅間神社)、大物主命(美和神社)は符合しますが、大国主命が符合するには、玉諸神社の御祭神・國魂大神命(国玉大明命)と大国主命が同体か近い神格と考える必要があります。
國魂大神命(国玉大明命)は謎の多い神格のようですが、字と音の通じる多摩の大社、大國魂神社の御祭神・大國魂大神は出雲の大国主神と御同神とされるので、この系譜が考えられるかもしれません。
一方、→山梨県神社庁の三社諏訪神社の資料には「甲斐国一宮浅間、二宮美和、三宮国玉の三神を勧請し鎮座、同年三月水防祭を行ふといふ。」とあります。三社から勧請された御祭神は木花咲耶姫命、大国主命、大国玉命とみられます。金刀比羅宮のWeb資料には「大物主神は、大国主神(おおくにぬしのかみ)の和魂(にぎみたま)に当たる神さま」とありますので、軽々には考えられませんが、大神幸祭は、木花咲耶姫命、大国主神、大国主神の和魂(大物主神)がお渡りになるという性格のお祭りなのかもしれません。
〔 信玄公、信玄堤と御幸祭 〕
甲府盆地はもともと水害の多い土地柄でした。
東に笛吹川、西に釜無川と御勅使川が流れ、これらの河川が氾濫すると、濁流が甲府盆地に流れ込みました。
なかでも、釜無川と御勅使川が合流する盆地西北の竜王付近は氾濫の常襲地帯で、この場所の治水は甲斐国の歴代の課題でした。


【写真 上(左)】 信玄堤説明板
【写真 下(右)】 築堤本陣の碑


【写真 上(左)】 信玄堤から上流(北)方向
【写真 下(右)】 信玄堤から下流(南)方向
信玄堤に設置されている「信玄堤から見た山々」に載っている山は、櫛形山(2052m)、農鳥岳(3026m)、辻山(2585m)、鳳凰三山(2762m~2841m)、甲斐駒ヶ岳(2966m)などで、軒並み2000mを越え、御勅使川が屈指の急流であることがわかります。


【写真 上(左)】 聖牛と釜無川
【写真 下(右)】 対岸御勅使川方向
「幹川となる釜無川は、竜王を扇頂にして、約90°の角度を持って東側から南側へと扇状地を形成している。釜無川は、この扇頂の竜王から盆地内へと乱流し、結果として東側へと広大な扇状地を形成してきたのである。したがって、甲府盆地の治水安全度を向上させるには、まず釜無川の盆地内への切れ込みを防止する必要があり(以下略)」(甲斐武田の治水策の問題点とその限界 - 御勅使川分流の終焉 -/岩屋隆夫氏 2005)以下「資料B」)
「(甲斐武田が考案したのが)築立地点の右岸側に強固な石積み堤防を配置しながら御勅使川の幹川河道を徐々に東北東へと移し、この先にある龍岡台地の南端を掘り込んで「新堀」を開削することによって河道を固定して、これに加えて、釜無川合流点の直上流に「十六石」という巨岩を配して御勅使川の洪水流が釜無川左岸の韮崎火砕流台地、別名「高岩」に当たるよう導いたのである。」
「高岩を直撃するようになった釜無川と御勅使川の洪水流は、高岩に当たって右岸側へと反転し、その反転した先に本御勅使川から分流する前御勅使川の洪水流を当てて揉み合わせ、そうすることによって洪水流の勢いを削いだのである。」
「一方、釜無川右(左?)岸には、扇頂から下流に向かって強固な堤防が築かれた。信玄堤である。」(以上、資料Bより)
→ 御勅使川流路換えのための石積出しなど


【写真 上(左)】 聖牛の模型-1
【写真 下(右)】 聖牛の模型-2
この信玄公の治水策は、永禄二年(1559年)から明治二十九年(1896年)の大水害まで、じつに三百年以上にも渡って甲府盆地を護りぬきました。
しかも明治二十九年(1896年)の大水害の原因は、1800年頃から深刻化した(本)御勅使川の河道土砂埋積((前)御勅使川への分流不全)という、信玄公の時代には予見できなかった事柄が大きいとみられています
「この1896(明治29)年水害によって、信玄堤は築堤以来、初めて破堤した。甲府盆地の治水の要というべき信玄堤が破堤したのであるから、甲府市民など地域住民にとって驚愕すべき事態になったであろうことは想像に難くない。しかも、信玄堤の決壊は明治以降もこの1896(明治29)年水害の1回しか無い。」(資料B)
この明治二十九年の信玄堤破堤の衝撃は、別の資料からもうかがえます。(→ 信玄堤と御幸祭 - 近世・近代甲斐国における武田信玄顕彰 -/中野賢治氏 2020年以下、資料C)
同年11月、竜王村長・陳情委員が連名で内務大臣に提出した陳情書です。要所を抜粋引用します。(資料Cからの孫引きです)
「其急流激湍、県下危険ノ第一ニ位セリ、縦横奔注毎ニ惨害ヲ極メシヲ以テ武田氏ノ時ニ至リ、堅牢無比ノ堤防、及ヒ前囲トシテ石瘤数十本ヲ築造シ、防禦ノ大策ヲ画シ、百年ノ長計ヲ講セラル」
「信玄公築造ノ堤防ヲ本堤トシ、表囲ニハ一番ヨリ五番ニ至ル土出堤防ヲ設ケ、大聖牛・中聖牛・大枠・中枠、其他種々ノ方法ヲ行ヒ防禦セシヲ以テ、其工事ハ古ク天文年間ノ施設ナルニモ係ハラス、爾来歳月ノ久シキ、未ダ曽テ信玄堤防ノ破壊セシヲ聞カズ」
「(明治二十九年)九月八日ヨリ猛雨連日、河水為メニ暴漲シ、激浪奔騰、危機一髪ノ間ニ在リ、是ニ於テ人民昼夜ヲ分タス只管防禦ニ尽力セシモ、終ニ其効ヲ奏セス、十二日午前八時、改修堤防ニ破壊ヲ生ジ、午前十時ニ至リ延長百七十余間ヲ流失シ、加之信玄堤防ノ一部同時ニ決潰セリ」
「安危存亡ノ関係スル所、実ニ県下大半ニ及フノ要衝ナレハ、現今ノ如キ設計ニテハ下流町村幾万ノ生霊、一日モ枕ヲ高フスルコト能ハサルノ悲境ニ淪落セサル可ラサルコト予想セラル、以上開陳スル所ノ実況ヲ洞察シ、衷情ヲ容納シ、速ニ堅牢不抜、万代無窮ノ工事ヲ設計セラレンコト至願切望ノ至リニ堪ヘス」
要約すると、天文年間の堤防にもかかわらず一度も決壊したことのない信玄堤が一部とはいえ決壊したとあっては、一日も枕を高くして(安眠)することはできず、速やかに堅牢で万代安全な堤の補強工事を切望します、といったところでしょうか。
また、この陳情書には「追伸書」が付されています。要点を引用します。
「三百三十年来未タ曽テ決損シタルコトナキ信玄堤防ノ之ニ継テ決壊シ、災害ヲ三中郡筋各村ヘ臻シタルハ、一見実ニ奇変ト云ハサルヲ得ス」
「堅牢ナル信玄堤ハ優ニ此滔流ヲ反溌シ得テ、堤内各村ハ無難ナリシナラント雖モ、不幸改修堤ハ旧四番堤ノ起点ニ於テ信玄堤ニ連接シ、其状恰カモ不規則ナル楕円形ヲ為セシヲ、以テ前陳ノ如ク改修堤ノ一部決壊セルニ於テハ、其決所ヨリ浸入スル滔流ハ、盤中ニ入ルカ如ク出ルニ路ナク、為メニ旋転渦廻シテ信玄堤ノ最低所ヲ求メテ超然奔逸スルニ至レリ(略)終ニ堅牢不抜ノ信玄堤ハ其一部ヲ決壊スルニ至リタリ(略)堅牢ナル修築工事ヲ設計セラルヽニハ、単ニ復旧工事ヲ以テ足レリトセス、希クハ前陳決壊当時ノ実況ヲ審ニ洞察セラレ、堅牢ナル信玄堤ノ効用ヲ全カラシメラレンコトヲ切望ノ至リニ堪エズ」
要約すると、堅牢な信玄堤は優に濁流を押し返していたが、信玄堤と連続する改修堤防により信玄堤に当たった水流が出口を失いすべなく決壊に至ったとし、信玄堤自体は堅牢なので、信玄堤を活かすかたちで改修工事を進めてほしいと嘆願している、というところでしょうか。
一部決壊したとはいえ、住民の信玄堤に対する信頼はなお根強いものがあったことがうかがわれ、実際、信玄堤は残されて別に改修堤防が設けられ、信玄堤公園付近は二重堤防になっています。


【写真 上(左)】 釜無川河原の聖牛
【写真 下(右)】 信玄堤と大御幸祭三社の位置関係
資料Cは、このような信玄堤の決壊への衝撃が、明治三十六年の竜王武田神社の改築に深く関わっていると推察しています。
■ 竜王武田神社


【写真 上(左)】 神明神社社頭
【写真 下(右)】 神明神社拝殿(右手奥が武田神社)


【写真 上(左)】 武田神社
【写真 下(右)】 武田神社拝殿
→山梨県神社庁資料
甲斐市竜王2089(神明神社境内鎮座)
御祭神:武田晴信公
※御朱印授与情報は未確認です。
竜王下宿の神明神社境内に鎮座する、武田信玄公を祀る神社です。
資料Cでは、『町村取調書/名所旧跡補足』(大正五年)の「信玄祠。信玄堤畔ニアリ、古昔ハ一片ノ石龕、茂林光密竹ノ間ニ没シ、里人猶其存在ヲ知ラザルモノアリシガ、明治八年有志相謀リ、樹ヲ伐リ地ヲ拓キ祠堂ヲ造営セリ、規模大ナラズト雖モ結構完美ヲ極ム」を挙げ、「『信玄堤畔』に所在することなどから、この『信玄祠』が現在の竜王武田神社を指すものとみられる。」としています。
また、『龍王村史』には「武田信玄の恩沢をたたへて、従来信玄堤の附近に信玄を祭神とした武田神社があつたが、明治維新の際に免租屋敷は悉く有租地となると共に、段々荒廃し、社殿も失ひ、祭儀も行ふことが出来なくなつたので、明治三十六年、同村斎藤源六・久保田辨二郎・青柳徳太郎・丹沢益蔵・輿石龜五郎等の信徒総代が発起して、此所に社殿改築の計画が進められた。」とあります。
つまり、明治八年、信玄堤畔に祀られた信玄祠を、明治二十九年の信玄堤破堤を受けて明治三十六年、(現社地に?)竜王武田神社として改築したという見立てです。
古府中町の武田神社の創建は大正八年(1919年)、これに対して竜王の信玄祠の創祀は明治八年(1875年)、竜王武田神社の「改築」でも明治三十六年(1903年)ですから、古府中の武田神社よりも古い歴史をもつということになります。
(この点は、→このサイトでも指摘されています。)
甲斐市竜王下宿の信玄堤のすぐ下、神明神社の境内に鎮座します。
神明神社の神明造の社殿の右手おくに、ひっそりと鎮座しています。
社頭にしめ縄のかかった門柱と、石の社号標には「武田神社」とあります。
降棟を備えた一間の方形造?で、小振りながら存在感ある社殿です。
暗くなってからの参拝だったので、装飾など詳細は不明ですが、水引虹梁の両端に木鼻、海老虹梁、桟唐戸の構えだったと思います。


武田神社のさらに堤防寄りに「お水神さん」が祭られていました。
信玄堤にゆかりの水神様で、由来書もあったので抜粋引用します。
「この堤防は武田信玄公が築堤したもので世に言う信玄堤であります。明治二十九年に破堤されるまで約三百五十年の永きにわたり洪水を防いだ立派な堤防であります。この所は明治二十九年に堤防が決壊した地点であります。その時に国や県、地元住民により堤防を修復すると同時に、明治三十三年八月一日に水防の神を現時点に奉安いたしました。以来、約100年の間平穏無事に過して参りました。このことはひとえにこのお水神さんのご加護の賜であると信じて、地元住民は毎年祭礼を執り行い、敬愛の念を捧げて現在に至っております。この度、竜王芦安線橋梁工事に当りこの尊いお水神さんを新たなこの地に遷座いたしました。これからはこのお水神さんをなお一層崇拝し水防の誠を末永く尽くして参りたいと考えております。 平成六年九月一日」
住民の方々の信玄堤に対する感謝と、水防への願いが伝わってくる内容です。
ところで、資料Cの筆者は「史料のなかでも、御幸祭と武田信玄との関係に触れるものは少なかった。」とされ、明治二十年代以降、大御幸祭と信玄公のかかわりを示す資料が増えることを指摘されています。
大御幸祭と武田公の関係を示す資料として「明治二八年の内務省訓令第三号をうけて行われた社寺調査」資料を例示し、以下の内容を挙げられています。
1.三社神社は武田信光公(1162~1248年)の代から武田家との関係があった。
2.大御幸祭は信玄公が創設したものとし、祭道中での「オコシヨウメンシヨウ」という囃子言葉も、信玄公の時代に「御輿名将」と言っていたのが訛ったものだとしている。
明治二十年代から始まる釜無川堤防改修は、当初、信玄堤を破壊し改修堤防に置き換える
計画であったとみられています。しかし、実際には信玄堤は残され、改修堤防と信玄堤の二重堤防という形となりました。
これについて資料Cの筆者は、「このとき、竜王信玄堤が失われるかもしれないという危機感が、武田信玄を介して、竜王信玄堤と御幸祭を結びつけることになったのではなかろうか。さらに決壊に至り、再建の過程で竜王信玄堤が失われるかもしれないという危機感が拍車をかけ、御幸祭は竜王信玄堤の保存を訴える一つの方法として利用されるようになっていたのであろう。」と考察されています。
おそらくはそういうことなのかもしれません。
ただし、大御幸祭の主役?である三社(一宮、二宮、三宮)は、上記のとおり、歴代武田家、あるいは信玄公の尊崇を受けていたことは明らかなので、間接的に大御幸祭に係わっていたという見方は許されるかと思います。
【 甲府と風水 】
風水については専門に扱う方がおられ、いろいろな説があるのですが、↑をまとめているうちになんとなく感じたことがあるので、書いてみます。
風水にもとづく都市計画では、「四神=山川道澤」策が代表例とされています。
「四神相応」ともいわれ、北には山岳があって玄武が棲み、東には河川(流水)があって青龍が棲む。西には大道があって白虎が棲み、南には湖沼・低地(または海)があって朱雀が棲む。という地勢です。
昨今は空前の風水ブーム、城郭ブームなので、甲府(躑躅が崎館)の風水もさぞや研究されているかと思いきや、意外と関連Webはみつかりませんでした。
なので、地図を頼りに個人的に推測してみます。
北の山岳は、背後の要害城からつづく奥秩父の山々。そこには霊山・金峰山も含まれています。
東の河川は笛吹川。奥秩父から流れ出る清流が盆地を潤しています。
西の大道は北方面に甲州街道、南方面に駿州(甲州)往還。甲州街道は下諏訪で中山道に合流し京に至ります。駿州(甲州)往還も駿河国内で東海道に合流し、京に至ります。
南の湖沼は盆地南部。甲府には「蹴裂伝説」「湖水伝説」(かつて甲府盆地は湖であった。)が残っており、符合します。(蹴裂伝説に関連する神社として、宝の穴切大神社、中央の甲斐奈神社、下向山の佐久神社、石和の佐久神社、市川の蹴裂神社などが知られています。)
これをみると、甲府(躑躅が崎館)は、風水に叶った地勢となっていることがうかがわれます。
しかし、気になる点もあります。
西の山岳(南アルプス)と河川(釜無川・御勅使川)の勢いがすこぶる強いことです。
山が高ければ、当然そこから流れ下る河川の勢いも激しくなります。実際、御勅使川はわが国有数の急流として知られ、その名も水害の際に朝廷から遣わされた「勅使」にちなむといういわくつきのものです。
信玄堤のあった竜王町は「有富山慈照寺に湧く竜王水に由来」という説もありますが、一般には釜無川・御勅使川の治水との関連が想像されるところかと。
信玄公はこの強すぎる河川(龍)を鎮めるために、信玄堤を築き堤道を通して風水を整え、川除けの祭事である大御幸祭をつづけた、という見方もできるかもしれません。
【 蹴裂伝説 】
甲府盆地には、「蹴裂伝説」(湖水伝説)という伝説が残っています。
甲府市資料などを参考にまとめてみます。
蹴裂(けさく)伝説とは、地形の変化変遷や人による地形の改変(干拓など)を伝える伝説をいい、日本各地に残っています。
甲府の「蹴裂伝説」は湖にかかわるものなので、「湖水伝説」とも呼ばれます。
はるか昔、甲府の地は一面の湖水でした。
地蔵菩薩がこの様子をご覧になり、「この水を排して陸地にしたら、人も住めるし田畑もできる。なんとかならぬものか。」とお二方の神様に相談をされました。
これを聞かれた神様たちは「いかにも道理」と賛成され、ひとりの神様が山の端を蹴破って、もうひとりの神様は山に穴を開け、水路を開いて湖水を富士川へ落とされました。
これを見ていたお不動様は、「わたしも一役」とばかり川瀬を造り手伝われました。
この二仏二神のおかげで、甲府の土地は湖の底から現われました。
山を蹴破った神様は蹴裂大明神、山に穴を開けた神様は穴切大明神、計画をされたお地蔵様は国母地蔵尊、川瀬を造られたお不動様は瀬立不動尊と伝わります。
石和の佐久神社の由緒(山梨県神社庁資料)などによると、「天手力雄命が大岩を裂いて水を涸らし現在の地となした」という伝承もあります。
また、下向山の佐久神社の由緒(山梨県神社庁資料)には「彦火火出見尊の後裔向山土本毘古王は媛靖天皇の勅命により国造として甲斐に入国一面の湖水を切り開き平土を得、住民安住の地を確保した功績は偉大なるもの(略)佐久大明神として祀られた」とあります。
甲府の「蹴裂伝説」は異説も多く錯綜しているのですが、「天手力雄命に関係のある山土本毘古王=佐久大明神=蹴裂大明神」と仮定すると、二仏二神に関係するとみられる寺社はつぎのとおりとなります。
・蹴裂大明神:市川の蹴裂神社、下向山の佐久神社、石和の佐久神社
・穴切大明神:宝の穴切大神社
・国母地蔵尊:国母の上条(稲積)地蔵尊、東光寺(町)の稲積(国母)地蔵尊
・瀬立不動尊:笛吹市境川「藤垈の滝」の芹沢不動尊
※ 「藤垈の滝」は、古来、すぐ向かいにある万亀山 向昌院(甲斐百八霊場第45番)の禊ぎの場であったと伝わります。


【写真 上(左)】 蹴裂神社
【写真 下(右)】 蹴裂神社からの笛吹川と釜無川方面


【写真 上(左)】 下向山佐久神社社頭
【写真 下(右)】 下向山佐久神社


【写真 上(左)】 藤垈の滝と芹沢不動尊
【写真 下(右)】 芹沢不動尊

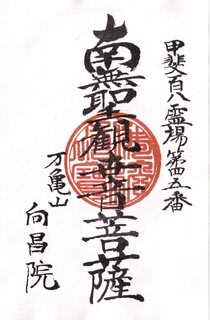
【写真 上(左)】 万亀山 向昌院
【写真 下(右)】 万亀山 向昌院の御朱印
これとは別に、稲積神社、韮崎市旭町の苗敷山穂見神社、甲府市中央の甲斐奈神社も「蹴裂伝説」ないしは「疏水工事による開拓」とのゆかりをもつとされます。


【写真 上(左)】 稲積神社
【写真 下(右)】 稲積神社の御朱印


【写真 上(左)】 甲斐奈神社
【写真 下(右)】 甲斐奈神社の御朱印
稲積神社の社伝には、「湖岸を切り開き湖水を富士川に落として」国を拓かれたのは四道将軍武淳川別命で、当社はその国土の「蒼生愛撫、五穀豊穣、祈願のため、丸山に奉斎」されたとあります。
苗敷山穂見神社には「甲斐の国が洪水により湖水と化した時、鳳凰山に住む大唐仙人が、蹴裂明神と力を併せ南山を決削して水を治め平野とし、里に住む山代王子がこの地を耕し、稲苗を敷き民に米作りの道を教えた。大唐仙人を国立大明神、山代王子を山代王子権現として 両神を山頂に祀り苗敷山と呼んだ。」との創祀が伝わっているようです。(→出所)
「蹴裂伝説」の二仏二神のうち、信玄公との関連が見つかったのは、国母の上条地蔵(法城寺)、穴切大神社のふたつです。
■ 国母の上条地蔵(上條法城寺)


→甲府市資料(国母稲積地蔵立像)
甲府市国母8-12-27(児童公園内)
※御朱印授与情報は未確認です。
甲陽軍鑑品第四(国会図書館DC、コマ番号17/265)に「蹴裂伝説」についての記載があります。
「上條法城寺には洛北さがの策諺和尚御座候 此法城寺は甲州上古は湖なりと聞 上條ぢぞうぼさつの御誓にて南の山をきりて一國の水悉とく富士川へ落つるにより甲州國中平地と成て今如件なり さるに拠て上條ぢぞうだう(堂)とは申せ共 寺號をば法城寺と申す 此文字は水去リテ土ト成ルと云うとはり也 法城寺破れば甲州はすいび(衰微)也 末代迄も甲州持侍は此寺上條法城寺を建立有べし 此の寺に策諺和尚五年の間住み給ひ候」
策諺和尚は、恵林寺に住持されていた惟高和尚とともに、信玄公に臨済宗妙心寺関山派での修行を薦め、長禅寺の岐秀元伯への参禅を促したとされる高僧です。(『甲陽軍鑑』)
法城寺は、「蹴裂伝説」ゆかりの上条地蔵尊を祀る寺院で、上条地蔵尊が甲斐国の治水を守護される重要なお地蔵様として信仰されていたことがわかります。
甲府市資料には、行基が治水策を施し、お地蔵様を刻して篠原の岡(甲斐市篠原)に法城寺を建立、治水祈願をされて祀ったとあります。
上記資料には「(法城寺の地蔵尊は、)平安時代に新羅三郎義光公により国母に移され、のちに信虎公が武田氏館の近くに移され、さらに天正年間に東光寺村に移されましたが、昭和20年の空襲によって焼失してしまいました。現在の(国母地蔵の)像は、武田氏が館の近くに移したときに、代仏として残した像であると伝えられています。」とあります。
現在も地域の信仰を集め、甲府市の市指定文化財に指定されています。
東光寺西方山中の「稲積地蔵」が「国母の上条地蔵」であるという説もみられます。
■ 穴切大神社






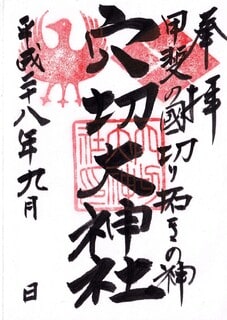
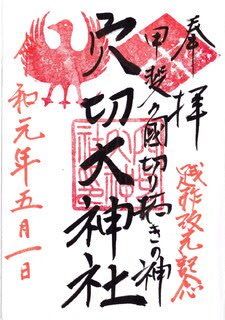
【写真 上(左)】 通常の御朱印
【写真 下(右)】 令和初日の記念御朱印
→山梨県神社庁資料
甲府市宝2-8-5
御祭神:大己貴命、少彦名命、素盞鳴命
旧社格:式内社(小)論社、郷社
授与所:境内授与所
朱印揮毫:穴切大神社 直書(筆書)
※オリジナル御朱印帳も頒布されています。
当社に係わる山梨県神社庁資料には「その頃の甲斐の国中は大半湖水にて、時の国司巡見して湖水が引かば跡地は良き田にならうと、朝廷に奏聞して裁可を得、その上国造神に座します。大己貴命に祈願をこめて(略)富士川より南海に水を落すに成功した。為に湖水の大半が退き今日の如き良田数多を見るに至った。これ偏に御神助の賜と勅命を以て勧請、穴切大明神と奉称、国中鎮護の神と崇敬されるやうになった。」とあります。
御祭神は大己貴命、少彦名命、素盞鳴命で、開拓工事の際、国司が祈願をこめたのが大己貴命で、のちに「穴切大明神」と奉称した、という文脈だと思います。
ただし、「蹴裂伝説」の穴切大明神を祭祀していたという説もあるようです。
信玄公との関係は、資料Aに「神宝には信玄が使用したと伝えられるわん、武田信勝所持と伝える面」とあり、「箱棟には武田菱がみられ、勝頼ないしは他の武田一族の造営ではないかともいわれる。」ともあります。
社頭の社号標、石造明神鳥居の扁額ともに「穴切大神社」。
随神門は入母屋造三間一戸の堂々たる楼門で、境内説明板によると寛政六年(1794年)に下山大工の竹下源蔵を棟梁に建立、彫刻は諏訪立川流(宮彫りの流派)初代和四郎富棟の手になるもので、とくに動植物の彫刻に優れ、甲府市の文化財に指定されています。
神楽殿は銅板葺の向唐破風が見事。箱棟にはたしかに金色の武田菱が輝いています。
神楽殿の前には、なぜかヤタガラスとおぼしきイラストがある「ラッキーゴール」が置いてあるのですが、熊野信仰と特段の結びつきが認められない当社に、なぜヤタガラスがいるかは不明。
「蹴裂伝説」の「蹴る」からサッカーゆかりの神社となり、日本サッカー協会(JFA)のシンボルマークは「ヤタガラス」なので、「蹴裂伝説」つながりかとも思いましたが、この記事をみるとそうでもなさそうです。
ただし、「サッカー神社」として有名らしく、カラスの木像も伝わっているそうなので、それによってヤタガラスをゆかりとされているような感じがします。
ヤタガラスは御朱印にも登場します。
八咫烏の印と武田菱が並んで捺されているのは、なんとなく不思議な感じもしますが、甲斐源氏の祖とされる源義清公が甲斐目代として平塩に館を構えたとき守護神として祀ったのは熊野神社なので、あながちご縁がないとはいえないと思います。
オリジナル御朱印帳も武田菱とヤタガラスをモチーフとしています。
本殿は檜皮葺の一間社流造。各所に桃山時代の特徴を残し、国の重要文化財に指定されています。
本殿は近寄れないですが、正面上部の斗栱、垂木、手挟まわりの彩色は遠目からも見事です。
こちらも大棟や箱棟に金色の武田菱が燦然と輝いています。
拝殿はコンクリ造の近代的なもの、新旧いろいろ入りまじり、面白い雰囲気の境内でした。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
2020/11/23 追記更新UP
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
2020/04/18 UP
つづきです。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
【 躑躅ヶ崎館と武田神社 】
信虎公は永正十六年(1519年)、甲府の北部に館(躑躅ヶ崎館)を築かれ、石和から甲府(府中)に武田家の本拠を移されました。
信玄公は一貫してこの躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)を本拠とされました。
「城」ではなく「館」です。
信玄公治世時に、他国から甲斐に侵入を許したことはほとんどなく、館への居住は信玄公の強さの象徴(城を築く必要がなかった)とする見方もありますが、躑躅ヶ崎館は信虎公による築館であり、この見方は単純すぎるかも・・・。
(信玄公の名言とされる「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」の影響が強いと思う。)
ただし、古府中周辺にまったく城を築かなかったわけではなく、要害山城と湯村山城がいわゆる”詰めの城”として知られています。
躑躅ヶ崎館の規模は東西約280m、南北約180m、面積は14,000坪超とみられ、外濠、内濠、空濠の3つの濠を擁します。
多数の曲輪を置いた中世式の武家館で、館の南には主だった家臣の館を配しています。
館の周辺に家臣を配する様式は、主君(大名)の中央集権の証ともされます。
武田神社社頭の掲示板には、家臣の館を示す説明図が掲示されており、以下の名前が認められます。
武田逍遥軒、小山田信茂、土屋右兵衛尉、横田備中守、穴山伊豆守、高坂弾正忠、真田弾正忠、甘利備前守、内藤修理亮、板垣駿河守、原加賀守、三枝勘解由、多田淡路守、馬場美濃守、山県三郎右兵衛尉、曾根下野守、小幡織部正、諸角豊後守、武田左馬助信繁、秋山伯耆守、一条右衛門大夫(信龍)、飯富兵部少輔、金丸肥前守・・・。
いずれも武田二十四将と重なる錚々たる武将です。
これらの館はおおむね躑躅ヶ崎館(現・武田神社)から甲府駅まで伸びる武田通り沿いの現在の山梨大学あたりまで配置され、以南は要法寺、宮前八幡、御崎神社、法華寺などの寺社が多い町割りとなっています。
『勝山記』によると、躑躅ヶ崎館移転直後の永正十七年(1520年)春、栗原氏・大井氏・逸見氏らの有力国人は甲府への集住に抵抗し甲府を退去した事件が伝えられていますが以降安定し、武田家の本拠として定着しました。
武田家滅亡後、天正十八年(1590年)に徳川家臣、平岩親吉によって南方に甲府城が築城されると甲府の政務の中心はそちらに移り、躑躅ヶ崎館は破却され、館跡は「古城」「御屋形跡」と称されました。
躑躅ヶ崎館の館跡の一部は、現在武田神社となっています。
■ 武田神社










【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 令和初日のものすごい御朱印行列(拝受せず)




公式Web
甲府市古府中町2611
御祭神:武田信玄公
旧社格:県社・別表神社
授与所:境内授与所
朱印揮毫:武田神社(印判)
※信玄公立御姿、信玄公座御姿の切り絵御朱印も授与されています。
躑躅ヶ崎館の跡地に大正八年(1919年)、信玄公を御祭神として創建された神社。
公式Webの由緒には「大正天皇のご即位に際し信玄公墓前に従三位追贈が奉告されたのを契機に、ご遺徳を慕う県民に武田神社ご創建の気運が沸き上がり、官民一体となった「武田神社奉建会」が設立され、浄財によって大正8年には社殿が竣工、4月12日のご命日には初の例祭が奉仕されました。」と記されています。(同Webから引用)
歴史は浅いものの、さすがに信玄公をお祀りする神社、県内有数の大社として多くの参拝客を集めて賑わいをみせています。
駐車場は点在してかなりの台数あるのですが、オンシーズンには周辺道路が渋滞気味となるので、オフシーズンないし平日の参拝がベターかと。
石垣に壕を構えた豪壮なつくりは、武家の館を彷彿とさせるもの。
社号標は「武田神社」、石灯籠一対、朱塗りの神橋の向こうに階段と鳥居が見えます。
社頭右手に並ぶ掲示物は内容が充実しているので、興味のあるかたは必読かと。
石造の明神鳥居に「武田神社」の扁額。拝殿前にもう一基見える鳥居も石造明神鳥居です。
参道左手の立派な手水舎の水盤は武田菱をかたどったもの。参道沿いに並ぶ灯籠も武田菱の意匠で、あたりはすでに武田色一色です。
拝殿前鳥居の前を向かって左手に進むと、武田水琴窟、名水「姫の井戸」、厳かな神楽殿「甲陽武能殿」とそのおくに榎天神社が鎮座します。
拝殿は入母屋檜皮葺の唐破風向拝付きで、おそらく桁行六間ではないかと思います。ただし、左横の菱和殿(祈願所)と屋根付き渡り廊下で連結しています。
中門、祝詞舎、流造の本殿とつづく社殿は、様々な意図をもって構成されたものとみられます。(→ 武田神社についての研究)
今回参拝時の社前の奉納飾り樽は「武田菱」と「太冠」(太冠酒造/南アルプス市)、「武田菱」という銘柄はきいたことがないので、奉納用の特別銘柄かもしれません。
拝殿左手おくの宝物殿には武田家ゆかりの品々が収蔵されています。
なかでも社宝の太刀「吉岡一文字」(鎌倉時代末期)は、明治十三年(1880年)、時の太政大臣三条実美公が、信玄公正室が三条家の出身だったことに因み当社に寄進されたもので国の重要文化財に指定されています。
なお、代表的な武田二十四将図とされる当社所蔵の武田二十四将図(江戸中期作)もこちらに収蔵されています。
御朱印は、拝殿右手の授与所にて授与いただけます。
信玄公ゆかりの勝運神社として知られ、数種の御朱印を授与されている県内有数の人気御朱印スポットで、週末などは行列発生もみられるようです。
切り絵作家百鬼丸さんの「立御姿」「座御姿」の御朱印(書置のみ)が人気で、武田菱、楯無、軍扇に富士山がデザインされた御朱印帳も人気が高いです。(→公式Webの御朱印情報)
【 信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~ 】
信玄公は国内統治に数多の事績を残され、名君として知られています。
そのひとつが信玄堤です。
急峻な山々に囲まれた甲府盆地は古来より水害に悩まされ、盆地底部はもともと笛吹川と釜無川の氾濫原であったとみなされるほどです。
とくに南アルプスから流れ下る御勅使川(釜無川の支流)は有数の暴れ川で、大雨ごとに氾濫を起こし、濁流は盆地西部、場合によっては国中(甲府南部から笛吹市あたり)まで流れ込んだといわれます。
信玄公はこれを防ぐため、御勅使川と釜無川の合流点である甲斐市竜王あたりに当時の最新技術を駆使して堤を築き、流路を替えて、以降大規模な氾濫は収まったとされます。
甲府盆地の水害に関連して、平安時代から大神幸祭(おみゆきさん/御幸さん)という水防祈願の行事が伝わります。
大神幸祭は明治に入り一宮浅間神社だけで行われるようになりましたが、平成15年に従前どおりの三つの神社による御幸が復活し、現在も4月に執り行われています。
大神幸祭については笛吹市の資料に詳しいので、抜粋引用します。
「大神幸祭は、甲斐国の一宮浅間神社、二の宮美和神社、三の宮玉諸神社の三つの神社の神々が釜無川左岸の三社神社へ神輿でお渡りになり(神幸)、川除(水害除け)の神事を行うお祭りです。天長二年(825年)に甲斐国が度重なる洪水に悩まされている様子を国司の文屋秋津が朝廷に報告したところ、朝廷から勅使が派遣され三つの神社による大神幸祭が行われるようになったといわれています。」「武田信玄も治水には大変な力を注ぎ、信玄堤をはじめとした様々な水防施設を造りました。川除の神事が行われる三社神社はこの信玄堤にあるため、信玄も大神幸祭に力を入れていた様子がうかがわれます。(中略)
大神幸祭を行っていた神社に対する信玄の信仰は篤く、数々のゆかりの品が奉納されています。」


【写真 上(左)】 おみゆきさん(信玄堤説明板より)
【写真 下(右)】 宝暦年間のおみゆきさん(同上)
また、信玄堤の説明板には「昔は一ノ宮(浅間神社)二ノ宮(美和神社)三ノ宮(玉諸神社)から御輿が出る三社合同の共祭でしたが、明治3年(1870年)からは、一ノ宮のみのお祭りになりました。浅間神社に伝わる江戸時代の絵巻物によるとその行列は当時の十万石の大名行列と同じぐらいの規模であったといわれています。」と記されています。
大神幸祭にかかわる甲斐国の一宮、二宮、三宮についてご紹介します。
■ 甲斐国一宮 浅間神社







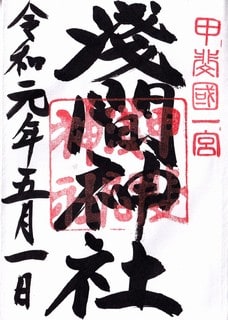
公式Web
笛吹市一宮町一ノ宮1684
御祭神:木花開耶姫命
旧社格:式内社(名神大)論社、国幣中社、甲斐国一宮、別表神社
授与所:境内社務所授与所
朱印揮毫:浅間神社、山宮(2種) いずれも直書(筆書)
甲斐国の一宮で、式内社(名神大)論社、国幣中社、別表神社というすこぶる高い社格を有する古社で「あさまじんじゃ」と呼びます。
社伝(公式Web)によると、もともとの本宮(元宮)は、現・摂社で山宮川の水源である神山の麓に第十一代垂仁天皇八年(約2千年前)から鎮座される山宮(神社)のようで、山宮(神社)に祀られていた木花開耶姫命、大山祇神、瓊々杵命の3柱のうち、貞観七年(865年)の富士山大噴火の翌年に木花開耶姫命が当社一宮(里宮)に遷座されたようです。
摂社・山宮(神社)の御祭神は以降、大山祇神、瓊々杵命の2柱となっています。
永禄元年(1558年)には信玄公が大檀那となって摂社山宮神社の本殿を再建されたという記録が残っており、この本殿は、市内に残されている数少ない中世建築とされています。
一宮の境内には山宮(神社)の遙拝所が設けられ、御朱印も授与されています。
甲斐国一宮だけに武田氏からの崇敬も篤く、信玄公ゆかりの文書も伝わっています。
天文十九年(1550年)、後奈良天皇の筆による「紺紙金泥般若心経」を信玄公は自筆の包み紙を付けて浅間神社に奉納されています。
「甲斐國 国土安穏万民和楽」。般若心経の末尾に記された後奈良天皇の御宸筆は、信玄公の忠誠と国守(信玄公)督励の意で特筆されたものと伝わります。
信玄公自筆の包紙には、「人皇百五代御柏原天皇第一王子今上皇帝宸筆 勅筆奉納神前般若心経一巻 天文十九年庚戌卯月廿日、大膳大夫晴信」と記されています。(資料A)
浅間神社は神仏混淆していた事例が多いですが、この神前への般若心経奉納もそれを示すものかと思われます。
奈良の長谷から移植した桜を奉納した際(上記御宸筆心経奉納の際とも)に詠まれた和歌の短冊も残されています。
- うつし植る初瀬の花のしらゆふを かけてそ祈る神のまにまに -
また、信玄公奉納の国次の太刀や條目、古文書も残されています。
一の鳥居は甲州街道に面して設置、社頭にある石造明神鳥居は二の鳥居です。
社号標には「国幣中社浅間神社」とあります。
その先に重厚な三間一戸の随神門。右手には山宮神社の遙拝所。
通常は随神門のおくには拝殿が見えるのですが、こちらは神楽殿が見えています。
拝殿は左手に鎮座します。つまり、参道は拝殿前で右90度に曲がっていることになります。(正確には拝殿から正面方向にも参道が延びているのでTの字型の参道。)
拝殿が向いている向きは富士山ではなく、むしろ山宮の方向で、これにはなんらかの意味があるのかもしれません。
拝殿は入母屋造銅板葺に唐破風向拝を附属し、さすがに一宮の貫禄。
拝殿に向かって右手おくには境内社が鎮座されており、干支参りもできるようになっています。
一宮なので参拝者も多く、御朱印は授与所で授与され、オリジナル御朱印帳も頒布されています。
■ 甲斐国一宮元宮 山宮神社


【写真 上(左)】 一宮浅間神社境内の山宮神社の遙拝所
【写真 下(右)】 山宮神社の御朱印


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 けもの避け柵
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 本殿


【写真 上(左)】 本殿正面蟇股の彫刻と斗栱
【写真 下(右)】 夫婦杉
公式Web
ふえふき観光ナビ
笛吹市一宮町一ノ宮1133(1705)
御祭神:大山祇神、天孫瓊々杵命
旧社格:(式内社(名神大)論社、国幣中社、甲斐国一宮、別表神社)
授与所:甲斐国一宮 浅間神社社務所授与所
現在は一宮浅間神社の摂社となっていますが、もともとは浅間神社の元宮(本宮)であったとされる格の高い神社です。
社伝(公式Web)によると、当社は山宮川の水源である神山(こうやま)の麓に第十一代垂仁天皇八年(約2千年前)から鎮座されるお社で、当初祀られていた木花開耶姫命、大山祇神、瓊々杵命の3柱のうち、貞観七年(865年)の富士山大噴火の翌年に木花開耶姫命が里宮(一宮浅間神社)に遷座されたようです。
よって現在の御祭神は以降、大山祇神、天孫瓊々杵命の2柱となっています。
永禄元年(1558年)には信玄公が大檀那となって本殿を再建されたという記録が残っており、笛吹市内に残されている数少ない中世建築とされています。
一宮浅間神社の境内には当社の遙拝所が設けられ、御朱印も授与されていますが、出向いて参拝しました。
一宮浅間神社から南東の方向に約2kmほど、甲州街道を渡った山側の山林のなかに鎮座まします。
↑上記の住所をナビに入れてもおそらく正確には表示しないと思います。
山宮は一宮町一ノ宮の飛び地に所在し、そもそも地番は振られていないのかもしれません。
一宮浅間神社からだと甲州街道の「石」交差点を直進し、しばらく行った山宮川そばの細い路地を左折します。(路地手前の広い道ではありません。)
住宅地のなかの細い路地を道なりに登っていくとぶどう畑となり、道の分岐に石造の台輪鳥居が見えてきます。ここが参道入口です。
鳥居のおくにけもの避け柵があり、これを抜けてのお参りとなります。
柵に取り付けられた「この付近にクマ出没注意」の看板が異様に気になります(笑)
参道まわりはまったくの山林、人気もないので、心配な方はクマ除けの鈴でも持参した方がいいかも。
台輪鳥居の扁額には「山宮大明神」とあります。
参道は一直線なので迷うことはありませんが、拝殿までは丸太の階段数分の登りがつづきます。
拝殿は入母屋ないし寄棟造の平入り、簡素なつくりで目立った装飾類はみあたりません。
その裏手に国指定文化財の本殿があります。
永禄元年(1558年)信玄公の再建とされる社殿で、一間社隅木入春日造檜皮葺。
装飾はさほど多くはないものの、蟇股の彫刻が精緻で、檜皮葺の屋根の曲線も品格があります。
本殿のうしろには夫婦杉。樹高およそ37m、目通り幹囲は左側5.3m右側5mという巨木で、圧倒的な存在感があります。
現在でも本社「山宮」に対して浅間神社を「里宮」と呼び、毎年4月のおみゆきさんのひと月前の3月に山宮御幸祭りが行われ里宮から山宮へ神輿が渡御することからみても、祭祀上重要な地位を占める神社であることがわかります。
■ 美和神社





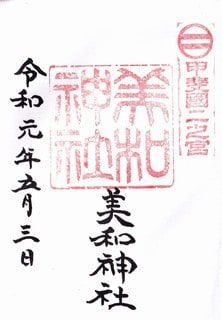
山梨県神社庁資料
笛吹市御坂町二之宮1450-1
御祭神:大物主命
旧社格:県社、甲斐国二宮、国史見在社
授与所:境内
朱印揮毫:美和神社 直書(筆書)
大和国の大神(大三輪)神社から勧請され、尾上郷の杵衡神社へ遷された後に新たに当地に遷座され、一条天皇の御代に甲斐国二宮の号を賜ったとされます。(遷座については、当社を式内社論社と目する異説あり)
勧請は景行天皇のころ、甲斐国造の塩海足尼によるものと伝わります。
「文徳天皇の時従五位下勲十二等の神階、一条天皇の時二の宮との宮号、御宇多天皇の時正一位勲一等勅額を受ける」(資料A)の来歴が残るようです。
歴代の武田家惣領が武運長久、子孫繁栄を祈願して尊祟したとされ、社領が寄進されています。
信玄公が元服の際に身に着けられた「赤札紅糸素懸胴丸佩楯付」という甲冑(初着の甲冑)、信玄公、義信公親子連名の寄進とされる「板絵著色三十六歌仙図」の板絵、信玄公関連文書などの社宝が伝わっています。三十六歌仙図は駿河の絵師、沼津与太郎忠久の永禄六年(1563年)作の優品と伝わります。
また、信玄公正室の三条夫人も具足を奉納されたと伝わります。
所蔵する木造大物主神立像は平安時代の作とされる一木造の優品で、国重要文化財に指定されています。
毎年2月に行われる湯立神事は、元禄年間(1688年~1704年)に始められたとされ、現存する県内唯一の湯立神事として知られています。
長々と伸びる参道、広い境内は、当社の格式の高さを物語るもの。
端正な流造瓦葺千鳥破風向拝付拝殿は、社叢に囲まれ厳かな佇まい。
神前の奉納飾り樽は、笛吹市御坂町の「腕相撲」でした。
御朱印については、わたしの参拝時には拝殿内にご神職がおられたので揮毫御朱印を拝受できましたが、常駐はされていないかもしれません。
■ 玉諸神社






山梨県神社庁資料
甲府市国玉町1331
御祭神:國魂大神命
旧社格:式内社(小)論社、県社、甲斐国三宮
授与所:愛宕神社社務所(甲府市愛宕町134)
朱印揮毫:玉諸神社 直書(筆書)
社伝によると、もとは酒折宮北方の御室山山上に祀られ、その後、日本武尊が東征の帰路に発生した水害を収めるため現社地に珠を埋め、その上に杉(玉室杉)を植え依り代として国玉大神を祀られると洪水は鎮まったため社が築かれたとされます。
清和天皇の貞観五年官幣を賜り勅願所となって、延喜式式内社に列せられたとされます。
甲斐国三宮として崇敬され、信玄堤近くの三社神社(甲斐市竜王)・三社諏訪神社(甲府市上石田)まで、一宮浅間神社、二宮美和神社とともに渡御する川除祭(水防祭、御幸祭)が古くから行われています。
武田氏から崇敬を受けて社殿が造営されたと伝えられますが、兵火で焼失したとされます。
〔境内の由緒書より(抜粋)〕
「甲斐源氏の祖・清和天皇貞観五年(863)神前に官幣を賜り勅願所となり、延喜式に所載され式内社に列せられた、この頃より中央から任命される国司の巡拝する順により一宮、二宮の称号が生じ当社は三番目、甲斐国三宮と称され篤く崇敬を受け(以下略)」
→山梨県神社庁資料
なお、大御幸祭の際に御渡りされる玉諸神社の御輿は、とくに「ぼんぼこさん」と呼ばれています。
住宅地のなかにたたずむ社頭は、石垣、生垣を配した整ったもの。
社号標は「玉諸神社」。一の鳥居は朱塗り稚児柱瓦葺屋根付きの立派な両部鳥居、奥に見える二の鳥居は神額付きの石造明神鳥居です。
参道左手の神楽殿は整ったつくりで、懸魚、二重梁に蟇股などの意匠が施されています。
神楽殿背後の社務所横のショーケースには当社所蔵の資料類が展示されています。
正面の拝殿は銅板葺唐破風向拝付の真新しいもの。一見、入母屋造に見えますが背後の本殿と石の間(幣殿)らしき構築物でつながっているので権現造かもしれません。
通常は非常駐で、御朱印は愛宕神社社務所(甲府市愛宕町134)にて拝受できます。
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
2020/04/18 UP
つづきです。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
【 躑躅ヶ崎館と武田神社 】
信虎公は永正十六年(1519年)、甲府の北部に館(躑躅ヶ崎館)を築かれ、石和から甲府(府中)に武田家の本拠を移されました。
信玄公は一貫してこの躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)を本拠とされました。
「城」ではなく「館」です。
信玄公治世時に、他国から甲斐に侵入を許したことはほとんどなく、館への居住は信玄公の強さの象徴(城を築く必要がなかった)とする見方もありますが、躑躅ヶ崎館は信虎公による築館であり、この見方は単純すぎるかも・・・。
(信玄公の名言とされる「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」の影響が強いと思う。)
ただし、古府中周辺にまったく城を築かなかったわけではなく、要害山城と湯村山城がいわゆる”詰めの城”として知られています。
躑躅ヶ崎館の規模は東西約280m、南北約180m、面積は14,000坪超とみられ、外濠、内濠、空濠の3つの濠を擁します。
多数の曲輪を置いた中世式の武家館で、館の南には主だった家臣の館を配しています。
館の周辺に家臣を配する様式は、主君(大名)の中央集権の証ともされます。
武田神社社頭の掲示板には、家臣の館を示す説明図が掲示されており、以下の名前が認められます。
武田逍遥軒、小山田信茂、土屋右兵衛尉、横田備中守、穴山伊豆守、高坂弾正忠、真田弾正忠、甘利備前守、内藤修理亮、板垣駿河守、原加賀守、三枝勘解由、多田淡路守、馬場美濃守、山県三郎右兵衛尉、曾根下野守、小幡織部正、諸角豊後守、武田左馬助信繁、秋山伯耆守、一条右衛門大夫(信龍)、飯富兵部少輔、金丸肥前守・・・。
いずれも武田二十四将と重なる錚々たる武将です。
これらの館はおおむね躑躅ヶ崎館(現・武田神社)から甲府駅まで伸びる武田通り沿いの現在の山梨大学あたりまで配置され、以南は要法寺、宮前八幡、御崎神社、法華寺などの寺社が多い町割りとなっています。
『勝山記』によると、躑躅ヶ崎館移転直後の永正十七年(1520年)春、栗原氏・大井氏・逸見氏らの有力国人は甲府への集住に抵抗し甲府を退去した事件が伝えられていますが以降安定し、武田家の本拠として定着しました。
武田家滅亡後、天正十八年(1590年)に徳川家臣、平岩親吉によって南方に甲府城が築城されると甲府の政務の中心はそちらに移り、躑躅ヶ崎館は破却され、館跡は「古城」「御屋形跡」と称されました。
躑躅ヶ崎館の館跡の一部は、現在武田神社となっています。
■ 武田神社










【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 令和初日のものすごい御朱印行列(拝受せず)




公式Web
甲府市古府中町2611
御祭神:武田信玄公
旧社格:県社・別表神社
授与所:境内授与所
朱印揮毫:武田神社(印判)
※信玄公立御姿、信玄公座御姿の切り絵御朱印も授与されています。
躑躅ヶ崎館の跡地に大正八年(1919年)、信玄公を御祭神として創建された神社。
公式Webの由緒には「大正天皇のご即位に際し信玄公墓前に従三位追贈が奉告されたのを契機に、ご遺徳を慕う県民に武田神社ご創建の気運が沸き上がり、官民一体となった「武田神社奉建会」が設立され、浄財によって大正8年には社殿が竣工、4月12日のご命日には初の例祭が奉仕されました。」と記されています。(同Webから引用)
歴史は浅いものの、さすがに信玄公をお祀りする神社、県内有数の大社として多くの参拝客を集めて賑わいをみせています。
駐車場は点在してかなりの台数あるのですが、オンシーズンには周辺道路が渋滞気味となるので、オフシーズンないし平日の参拝がベターかと。
石垣に壕を構えた豪壮なつくりは、武家の館を彷彿とさせるもの。
社号標は「武田神社」、石灯籠一対、朱塗りの神橋の向こうに階段と鳥居が見えます。
社頭右手に並ぶ掲示物は内容が充実しているので、興味のあるかたは必読かと。
石造の明神鳥居に「武田神社」の扁額。拝殿前にもう一基見える鳥居も石造明神鳥居です。
参道左手の立派な手水舎の水盤は武田菱をかたどったもの。参道沿いに並ぶ灯籠も武田菱の意匠で、あたりはすでに武田色一色です。
拝殿前鳥居の前を向かって左手に進むと、武田水琴窟、名水「姫の井戸」、厳かな神楽殿「甲陽武能殿」とそのおくに榎天神社が鎮座します。
拝殿は入母屋檜皮葺の唐破風向拝付きで、おそらく桁行六間ではないかと思います。ただし、左横の菱和殿(祈願所)と屋根付き渡り廊下で連結しています。
中門、祝詞舎、流造の本殿とつづく社殿は、様々な意図をもって構成されたものとみられます。(→ 武田神社についての研究)
今回参拝時の社前の奉納飾り樽は「武田菱」と「太冠」(太冠酒造/南アルプス市)、「武田菱」という銘柄はきいたことがないので、奉納用の特別銘柄かもしれません。
拝殿左手おくの宝物殿には武田家ゆかりの品々が収蔵されています。
なかでも社宝の太刀「吉岡一文字」(鎌倉時代末期)は、明治十三年(1880年)、時の太政大臣三条実美公が、信玄公正室が三条家の出身だったことに因み当社に寄進されたもので国の重要文化財に指定されています。
なお、代表的な武田二十四将図とされる当社所蔵の武田二十四将図(江戸中期作)もこちらに収蔵されています。
御朱印は、拝殿右手の授与所にて授与いただけます。
信玄公ゆかりの勝運神社として知られ、数種の御朱印を授与されている県内有数の人気御朱印スポットで、週末などは行列発生もみられるようです。
切り絵作家百鬼丸さんの「立御姿」「座御姿」の御朱印(書置のみ)が人気で、武田菱、楯無、軍扇に富士山がデザインされた御朱印帳も人気が高いです。(→公式Webの御朱印情報)
【 信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~ 】
信玄公は国内統治に数多の事績を残され、名君として知られています。
そのひとつが信玄堤です。
急峻な山々に囲まれた甲府盆地は古来より水害に悩まされ、盆地底部はもともと笛吹川と釜無川の氾濫原であったとみなされるほどです。
とくに南アルプスから流れ下る御勅使川(釜無川の支流)は有数の暴れ川で、大雨ごとに氾濫を起こし、濁流は盆地西部、場合によっては国中(甲府南部から笛吹市あたり)まで流れ込んだといわれます。
信玄公はこれを防ぐため、御勅使川と釜無川の合流点である甲斐市竜王あたりに当時の最新技術を駆使して堤を築き、流路を替えて、以降大規模な氾濫は収まったとされます。
甲府盆地の水害に関連して、平安時代から大神幸祭(おみゆきさん/御幸さん)という水防祈願の行事が伝わります。
大神幸祭は明治に入り一宮浅間神社だけで行われるようになりましたが、平成15年に従前どおりの三つの神社による御幸が復活し、現在も4月に執り行われています。
大神幸祭については笛吹市の資料に詳しいので、抜粋引用します。
「大神幸祭は、甲斐国の一宮浅間神社、二の宮美和神社、三の宮玉諸神社の三つの神社の神々が釜無川左岸の三社神社へ神輿でお渡りになり(神幸)、川除(水害除け)の神事を行うお祭りです。天長二年(825年)に甲斐国が度重なる洪水に悩まされている様子を国司の文屋秋津が朝廷に報告したところ、朝廷から勅使が派遣され三つの神社による大神幸祭が行われるようになったといわれています。」「武田信玄も治水には大変な力を注ぎ、信玄堤をはじめとした様々な水防施設を造りました。川除の神事が行われる三社神社はこの信玄堤にあるため、信玄も大神幸祭に力を入れていた様子がうかがわれます。(中略)
大神幸祭を行っていた神社に対する信玄の信仰は篤く、数々のゆかりの品が奉納されています。」


【写真 上(左)】 おみゆきさん(信玄堤説明板より)
【写真 下(右)】 宝暦年間のおみゆきさん(同上)
また、信玄堤の説明板には「昔は一ノ宮(浅間神社)二ノ宮(美和神社)三ノ宮(玉諸神社)から御輿が出る三社合同の共祭でしたが、明治3年(1870年)からは、一ノ宮のみのお祭りになりました。浅間神社に伝わる江戸時代の絵巻物によるとその行列は当時の十万石の大名行列と同じぐらいの規模であったといわれています。」と記されています。
大神幸祭にかかわる甲斐国の一宮、二宮、三宮についてご紹介します。
■ 甲斐国一宮 浅間神社







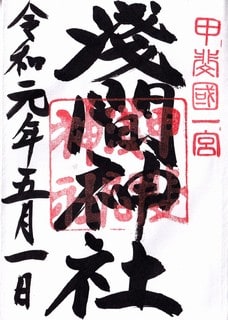
公式Web
笛吹市一宮町一ノ宮1684
御祭神:木花開耶姫命
旧社格:式内社(名神大)論社、国幣中社、甲斐国一宮、別表神社
授与所:境内社務所授与所
朱印揮毫:浅間神社、山宮(2種) いずれも直書(筆書)
甲斐国の一宮で、式内社(名神大)論社、国幣中社、別表神社というすこぶる高い社格を有する古社で「あさまじんじゃ」と呼びます。
社伝(公式Web)によると、もともとの本宮(元宮)は、現・摂社で山宮川の水源である神山の麓に第十一代垂仁天皇八年(約2千年前)から鎮座される山宮(神社)のようで、山宮(神社)に祀られていた木花開耶姫命、大山祇神、瓊々杵命の3柱のうち、貞観七年(865年)の富士山大噴火の翌年に木花開耶姫命が当社一宮(里宮)に遷座されたようです。
摂社・山宮(神社)の御祭神は以降、大山祇神、瓊々杵命の2柱となっています。
永禄元年(1558年)には信玄公が大檀那となって摂社山宮神社の本殿を再建されたという記録が残っており、この本殿は、市内に残されている数少ない中世建築とされています。
一宮の境内には山宮(神社)の遙拝所が設けられ、御朱印も授与されています。
甲斐国一宮だけに武田氏からの崇敬も篤く、信玄公ゆかりの文書も伝わっています。
天文十九年(1550年)、後奈良天皇の筆による「紺紙金泥般若心経」を信玄公は自筆の包み紙を付けて浅間神社に奉納されています。
「甲斐國 国土安穏万民和楽」。般若心経の末尾に記された後奈良天皇の御宸筆は、信玄公の忠誠と国守(信玄公)督励の意で特筆されたものと伝わります。
信玄公自筆の包紙には、「人皇百五代御柏原天皇第一王子今上皇帝宸筆 勅筆奉納神前般若心経一巻 天文十九年庚戌卯月廿日、大膳大夫晴信」と記されています。(資料A)
浅間神社は神仏混淆していた事例が多いですが、この神前への般若心経奉納もそれを示すものかと思われます。
奈良の長谷から移植した桜を奉納した際(上記御宸筆心経奉納の際とも)に詠まれた和歌の短冊も残されています。
- うつし植る初瀬の花のしらゆふを かけてそ祈る神のまにまに -
また、信玄公奉納の国次の太刀や條目、古文書も残されています。
一の鳥居は甲州街道に面して設置、社頭にある石造明神鳥居は二の鳥居です。
社号標には「国幣中社浅間神社」とあります。
その先に重厚な三間一戸の随神門。右手には山宮神社の遙拝所。
通常は随神門のおくには拝殿が見えるのですが、こちらは神楽殿が見えています。
拝殿は左手に鎮座します。つまり、参道は拝殿前で右90度に曲がっていることになります。(正確には拝殿から正面方向にも参道が延びているのでTの字型の参道。)
拝殿が向いている向きは富士山ではなく、むしろ山宮の方向で、これにはなんらかの意味があるのかもしれません。
拝殿は入母屋造銅板葺に唐破風向拝を附属し、さすがに一宮の貫禄。
拝殿に向かって右手おくには境内社が鎮座されており、干支参りもできるようになっています。
一宮なので参拝者も多く、御朱印は授与所で授与され、オリジナル御朱印帳も頒布されています。
■ 甲斐国一宮元宮 山宮神社


【写真 上(左)】 一宮浅間神社境内の山宮神社の遙拝所
【写真 下(右)】 山宮神社の御朱印


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 けもの避け柵
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 本殿


【写真 上(左)】 本殿正面蟇股の彫刻と斗栱
【写真 下(右)】 夫婦杉
公式Web
ふえふき観光ナビ
笛吹市一宮町一ノ宮1133(1705)
御祭神:大山祇神、天孫瓊々杵命
旧社格:(式内社(名神大)論社、国幣中社、甲斐国一宮、別表神社)
授与所:甲斐国一宮 浅間神社社務所授与所
現在は一宮浅間神社の摂社となっていますが、もともとは浅間神社の元宮(本宮)であったとされる格の高い神社です。
社伝(公式Web)によると、当社は山宮川の水源である神山(こうやま)の麓に第十一代垂仁天皇八年(約2千年前)から鎮座されるお社で、当初祀られていた木花開耶姫命、大山祇神、瓊々杵命の3柱のうち、貞観七年(865年)の富士山大噴火の翌年に木花開耶姫命が里宮(一宮浅間神社)に遷座されたようです。
よって現在の御祭神は以降、大山祇神、天孫瓊々杵命の2柱となっています。
永禄元年(1558年)には信玄公が大檀那となって本殿を再建されたという記録が残っており、笛吹市内に残されている数少ない中世建築とされています。
一宮浅間神社の境内には当社の遙拝所が設けられ、御朱印も授与されていますが、出向いて参拝しました。
一宮浅間神社から南東の方向に約2kmほど、甲州街道を渡った山側の山林のなかに鎮座まします。
↑上記の住所をナビに入れてもおそらく正確には表示しないと思います。
山宮は一宮町一ノ宮の飛び地に所在し、そもそも地番は振られていないのかもしれません。
一宮浅間神社からだと甲州街道の「石」交差点を直進し、しばらく行った山宮川そばの細い路地を左折します。(路地手前の広い道ではありません。)
住宅地のなかの細い路地を道なりに登っていくとぶどう畑となり、道の分岐に石造の台輪鳥居が見えてきます。ここが参道入口です。
鳥居のおくにけもの避け柵があり、これを抜けてのお参りとなります。
柵に取り付けられた「この付近にクマ出没注意」の看板が異様に気になります(笑)
参道まわりはまったくの山林、人気もないので、心配な方はクマ除けの鈴でも持参した方がいいかも。
台輪鳥居の扁額には「山宮大明神」とあります。
参道は一直線なので迷うことはありませんが、拝殿までは丸太の階段数分の登りがつづきます。
拝殿は入母屋ないし寄棟造の平入り、簡素なつくりで目立った装飾類はみあたりません。
その裏手に国指定文化財の本殿があります。
永禄元年(1558年)信玄公の再建とされる社殿で、一間社隅木入春日造檜皮葺。
装飾はさほど多くはないものの、蟇股の彫刻が精緻で、檜皮葺の屋根の曲線も品格があります。
本殿のうしろには夫婦杉。樹高およそ37m、目通り幹囲は左側5.3m右側5mという巨木で、圧倒的な存在感があります。
現在でも本社「山宮」に対して浅間神社を「里宮」と呼び、毎年4月のおみゆきさんのひと月前の3月に山宮御幸祭りが行われ里宮から山宮へ神輿が渡御することからみても、祭祀上重要な地位を占める神社であることがわかります。
■ 美和神社





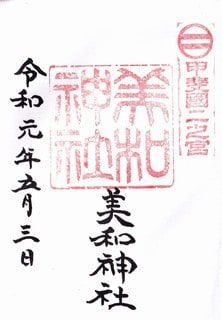
山梨県神社庁資料
笛吹市御坂町二之宮1450-1
御祭神:大物主命
旧社格:県社、甲斐国二宮、国史見在社
授与所:境内
朱印揮毫:美和神社 直書(筆書)
大和国の大神(大三輪)神社から勧請され、尾上郷の杵衡神社へ遷された後に新たに当地に遷座され、一条天皇の御代に甲斐国二宮の号を賜ったとされます。(遷座については、当社を式内社論社と目する異説あり)
勧請は景行天皇のころ、甲斐国造の塩海足尼によるものと伝わります。
「文徳天皇の時従五位下勲十二等の神階、一条天皇の時二の宮との宮号、御宇多天皇の時正一位勲一等勅額を受ける」(資料A)の来歴が残るようです。
歴代の武田家惣領が武運長久、子孫繁栄を祈願して尊祟したとされ、社領が寄進されています。
信玄公が元服の際に身に着けられた「赤札紅糸素懸胴丸佩楯付」という甲冑(初着の甲冑)、信玄公、義信公親子連名の寄進とされる「板絵著色三十六歌仙図」の板絵、信玄公関連文書などの社宝が伝わっています。三十六歌仙図は駿河の絵師、沼津与太郎忠久の永禄六年(1563年)作の優品と伝わります。
また、信玄公正室の三条夫人も具足を奉納されたと伝わります。
所蔵する木造大物主神立像は平安時代の作とされる一木造の優品で、国重要文化財に指定されています。
毎年2月に行われる湯立神事は、元禄年間(1688年~1704年)に始められたとされ、現存する県内唯一の湯立神事として知られています。
長々と伸びる参道、広い境内は、当社の格式の高さを物語るもの。
端正な流造瓦葺千鳥破風向拝付拝殿は、社叢に囲まれ厳かな佇まい。
神前の奉納飾り樽は、笛吹市御坂町の「腕相撲」でした。
御朱印については、わたしの参拝時には拝殿内にご神職がおられたので揮毫御朱印を拝受できましたが、常駐はされていないかもしれません。
■ 玉諸神社






山梨県神社庁資料
甲府市国玉町1331
御祭神:國魂大神命
旧社格:式内社(小)論社、県社、甲斐国三宮
授与所:愛宕神社社務所(甲府市愛宕町134)
朱印揮毫:玉諸神社 直書(筆書)
社伝によると、もとは酒折宮北方の御室山山上に祀られ、その後、日本武尊が東征の帰路に発生した水害を収めるため現社地に珠を埋め、その上に杉(玉室杉)を植え依り代として国玉大神を祀られると洪水は鎮まったため社が築かれたとされます。
清和天皇の貞観五年官幣を賜り勅願所となって、延喜式式内社に列せられたとされます。
甲斐国三宮として崇敬され、信玄堤近くの三社神社(甲斐市竜王)・三社諏訪神社(甲府市上石田)まで、一宮浅間神社、二宮美和神社とともに渡御する川除祭(水防祭、御幸祭)が古くから行われています。
武田氏から崇敬を受けて社殿が造営されたと伝えられますが、兵火で焼失したとされます。
〔境内の由緒書より(抜粋)〕
「甲斐源氏の祖・清和天皇貞観五年(863)神前に官幣を賜り勅願所となり、延喜式に所載され式内社に列せられた、この頃より中央から任命される国司の巡拝する順により一宮、二宮の称号が生じ当社は三番目、甲斐国三宮と称され篤く崇敬を受け(以下略)」
→山梨県神社庁資料
なお、大御幸祭の際に御渡りされる玉諸神社の御輿は、とくに「ぼんぼこさん」と呼ばれています。
住宅地のなかにたたずむ社頭は、石垣、生垣を配した整ったもの。
社号標は「玉諸神社」。一の鳥居は朱塗り稚児柱瓦葺屋根付きの立派な両部鳥居、奥に見える二の鳥居は神額付きの石造明神鳥居です。
参道左手の神楽殿は整ったつくりで、懸魚、二重梁に蟇股などの意匠が施されています。
神楽殿背後の社務所横のショーケースには当社所蔵の資料類が展示されています。
正面の拝殿は銅板葺唐破風向拝付の真新しいもの。一見、入母屋造に見えますが背後の本殿と石の間(幣殿)らしき構築物でつながっているので権現造かもしれません。
通常は非常駐で、御朱印は愛宕神社社務所(甲府市愛宕町134)にて拝受できます。
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印」の目次など
以前UPした「武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印」ですが、その後ネタが増えたので追記していきます。
書いた本人でもごちゃごちゃになってきたので、目次をつくりました。
以前は、信玄公編がVol.1~Vol.6の構成でしたが、Vol.1~Vol.9とし、現在のVol.6をVol.6~Vol.9に分割していきます。
しばらくは構成が錯綜するかもしれません。
--------------- 目次 ---------------
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 (甲斐武田氏と寺社/信玄公の生誕/武田家と重宝)
【 甲斐武田氏と寺社 】
・武田八幡宮 (韮崎市神山町)
・為朝神社 (韮崎市神山町)
・石和八幡神社 (笛吹市石和町)
・(甲斐國総社/宮前)八幡神社 (甲府市宮前町)
・(峯本鎮座)八幡神社 (甲府市古府中町)
・御崎神社 (甲府市美咲2-10-34)
【 信玄公の生誕 】
・万松山 積翠寺 (甲府市上積翠寺町)
(・稲久山 一連寺(甲府市太田町))
【 武田家と重宝 】
〔 御旗楯無 〕
・菅田天神社 (甲州市塩山上於曽)
〔 諏訪神号旗 〕
・裂石山 雲峰寺 (甲州市塩山上萩原)
・金櫻神社 (甲府市御岳町)
【 ご参考/昇仙峡周辺の御朱印 】
・金櫻神社、夫婦木神社、夫婦木神社姫の宮、黒戸奈神社(黒平町)、天台山羅漢寺
■ Vol.2A (躑躅ヶ崎館と武田神社/信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~)
【 躑躅ヶ崎館と武田神社 】
・武田神社 (甲府市古府中町)
【 信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~ 】
・甲斐国一宮 浅間神社 (笛吹市一宮町一ノ宮)
・山宮神社〔一宮浅間神社の元宮〕 (笛吹市一宮町一ノ宮)
・甲斐国二宮 美和神社 (笛吹市御坂町二之宮)
・甲斐国三宮 玉諸神社 (甲府市国玉町)
■ Vol.2B (躑躅ヶ崎館と武田神社/信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~)
・三社神社 (甲斐市竜王)
・三社諏訪神社 (甲府市上石田)
・住吉山 千松院 (甲府市相生)
・竜王武田神社 (甲斐市竜王)
・お水神さん (甲斐市竜王)
【 甲府と風水 】
【 蹴裂伝説 】
・穴切大神社 (甲府市宝)
・上条地蔵 (甲府市国母) / 稲積(国母)地蔵 (甲府市東光寺)
・(市川の蹴裂神社、下向山の佐久神社、石和の佐久神社、笛吹市境川の芹沢不動、稲積神社、苗敷山穂見神社、甲府市中央の甲斐奈神社)
■ Vol.3 (信玄公と甲府五山)
【 信玄公と甲府五山 】
・瑞雲山 長禅寺 (甲府市愛宕町)
・法蓋山 東光寺 (甲府市東光寺)
〔武田義信公〕
〔諏訪頼重公〕
・定林山 能成寺 (甲府市東光寺町)
・瑞巖山 円光院 (甲府市岩窪町)
・金剛福聚山 法泉寺 (甲府市和田町)
■ Vol.4 (信玄公の信仰-1)
【 信玄公の信仰 】
【 山梨岡神社 】
・山梨岡神社 (笛吹市春日居町鎮目)
【 八幡神 (八幡大菩薩)】
・(大井俣)窪八幡神社 (山梨市北)
【 諏訪明神 】
・白華山 慈雲寺(長野県下諏訪町)
・南宮大神社 (韮崎市大草町上條東割)
・諏訪南宮大神社(笛吹市境川町寺尾)
・松原諏方神社(長野県小海町)
・船形神社(北杜市高根町長沢)
【 浅間神社 】
・冨士御室浅間神社(富士河口湖町勝山)
・北口本宮冨士浅間神社(富士吉田市上吉田)
【 飯縄権現 】
・飯縄神社(皇足穂命神社) (長野県長野市富田)
・金剛山 普門寺 (神奈川県相模原市緑区中沢)
・加賀美山 法善護国寺 (南アルプス市加賀美)
【 戸隠大権現 】
・戸隠神社 (長野県長野市戸隠)
【 愛宕権現 】
・愛宕神社 (甲府市愛宕町)
【 三宝荒神 】
・真如山 華光院 (甲府市元紺屋町)
■ Vol.5 (信玄公の信仰-2)
【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
【 不動明王 】
・乾徳山 恵林寺 (甲州市小屋敷)
・大滝山 上求寺 (山梨市牧丘町倉科)
・三守皇山 大聖明王寺 (身延町八日市場)
・大聖金剛山 明王寺 (富士川町舂米)
・大野山 福光園寺 (笛吹市御坂町大野)
・松本山 大蔵経寺 (笛吹市石和町松本)
・法性山 玄法院 (甲府市天神町)
・龍本山 不動寺 (群馬県安中市松井田町)
【 毘沙門天 】
・徳和山 吉祥寺 (山梨市三富徳和)
・河浦山 薬王寺 (市川三郷町上野)
・宝塔山 多聞院 (埼玉県所沢市中冨)
(・瑞巖山 円光院 (甲府市岩窪町))
(・熊野神社 (甲州市塩山))
■ Vol.6 (信玄公ゆかりの寺社-1)
【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
・金剛山 慈眼寺 (笛吹市一宮町末木)
・高橋山 放光寺 (甲州市藤木)
【 善光寺 】
・定額山 善光寺(甲斐善光寺/甲州善光寺) (甲府市善光寺)
・塩山 向嶽寺 (甲州市上於曽)
・妙亀山 広厳院 (笛吹市一宮町金沢)
・調御山 佛陀寺 (笛吹市石和町市部)
・岩泉山 光福寺 (甲府市横根町)
・護国山 国分寺 (笛吹市一宮町国分)
・柏尾山 大善寺 (甲州市勝沼町勝沼)
・龍湖山 方外院 (身延町瀬戸)
・海雲山 寿徳寺 (山中湖村平野)
■ Vol.7 (信玄公ゆかりの寺社-2)
【 真宗と信玄公 / 日蓮宗と信玄公 】
【 真宗と信玄公 】
・塩田山 超願寺 (笛吹市一宮町塩田)
・真宗大谷派東本願寺甲府別院 光澤寺 (甲府市相生)
・法流山 入明寺 (甲府市住吉)
【 日蓮宗と信玄公 】
・身延山 久遠寺 (身延町身延)
・武井坊(身延町身延(西谷))
・上行山 要法寺 (甲府市武田)
・大津山 実相寺 (北杜市武川町山高)
■ Vol.8 (信玄公ゆかりの寺社-3)
【 山梨県外のゆかりの寺社 】
【 長野県 】
・生島足島神社 (長野県上田市下之郷)
・新海三社神社 (長野県佐久市田口宮代)
・新海山 上宮寺 (長野県佐久市田口)
・太田山 龍雲寺 (長野県佐久市岩村田)
・一行山 西念寺 (長野県佐久市岩村田)
・寶林山 安養寺 (長野県佐久市安原)
・平林山 千手院 (長野県佐久穂町平林)
・海尻山 醫王院 (長野県南牧村海尻)
・富蔵山 岩殿寺 (長野県筑北村別所)
・横湯山 温泉寺 (長野県山ノ内町平穏)
【 群馬県 】
・榛名神社 (群馬県高崎市榛名山町)
■ Vol.9 (信玄公ゆかりの寺社-4)
【 古長禅寺 】
・瑞雲山 古長禅寺 (南アルプス市鮎沢)
【 恵林寺 】
・乾徳山 恵林寺 (甲州市小屋敷)
書いた本人でもごちゃごちゃになってきたので、目次をつくりました。
以前は、信玄公編がVol.1~Vol.6の構成でしたが、Vol.1~Vol.9とし、現在のVol.6をVol.6~Vol.9に分割していきます。
しばらくは構成が錯綜するかもしれません。
--------------- 目次 ---------------
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 (甲斐武田氏と寺社/信玄公の生誕/武田家と重宝)
【 甲斐武田氏と寺社 】
・武田八幡宮 (韮崎市神山町)
・為朝神社 (韮崎市神山町)
・石和八幡神社 (笛吹市石和町)
・(甲斐國総社/宮前)八幡神社 (甲府市宮前町)
・(峯本鎮座)八幡神社 (甲府市古府中町)
・御崎神社 (甲府市美咲2-10-34)
【 信玄公の生誕 】
・万松山 積翠寺 (甲府市上積翠寺町)
(・稲久山 一連寺(甲府市太田町))
【 武田家と重宝 】
〔 御旗楯無 〕
・菅田天神社 (甲州市塩山上於曽)
〔 諏訪神号旗 〕
・裂石山 雲峰寺 (甲州市塩山上萩原)
・金櫻神社 (甲府市御岳町)
【 ご参考/昇仙峡周辺の御朱印 】
・金櫻神社、夫婦木神社、夫婦木神社姫の宮、黒戸奈神社(黒平町)、天台山羅漢寺
■ Vol.2A (躑躅ヶ崎館と武田神社/信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~)
【 躑躅ヶ崎館と武田神社 】
・武田神社 (甲府市古府中町)
【 信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~ 】
・甲斐国一宮 浅間神社 (笛吹市一宮町一ノ宮)
・山宮神社〔一宮浅間神社の元宮〕 (笛吹市一宮町一ノ宮)
・甲斐国二宮 美和神社 (笛吹市御坂町二之宮)
・甲斐国三宮 玉諸神社 (甲府市国玉町)
■ Vol.2B (躑躅ヶ崎館と武田神社/信玄堤と大神幸祭 ~甲斐國一宮、二宮、三宮~)
・三社神社 (甲斐市竜王)
・三社諏訪神社 (甲府市上石田)
・住吉山 千松院 (甲府市相生)
・竜王武田神社 (甲斐市竜王)
・お水神さん (甲斐市竜王)
【 甲府と風水 】
【 蹴裂伝説 】
・穴切大神社 (甲府市宝)
・上条地蔵 (甲府市国母) / 稲積(国母)地蔵 (甲府市東光寺)
・(市川の蹴裂神社、下向山の佐久神社、石和の佐久神社、笛吹市境川の芹沢不動、稲積神社、苗敷山穂見神社、甲府市中央の甲斐奈神社)
■ Vol.3 (信玄公と甲府五山)
【 信玄公と甲府五山 】
・瑞雲山 長禅寺 (甲府市愛宕町)
・法蓋山 東光寺 (甲府市東光寺)
〔武田義信公〕
〔諏訪頼重公〕
・定林山 能成寺 (甲府市東光寺町)
・瑞巖山 円光院 (甲府市岩窪町)
・金剛福聚山 法泉寺 (甲府市和田町)
■ Vol.4 (信玄公の信仰-1)
【 信玄公の信仰 】
【 山梨岡神社 】
・山梨岡神社 (笛吹市春日居町鎮目)
【 八幡神 (八幡大菩薩)】
・(大井俣)窪八幡神社 (山梨市北)
【 諏訪明神 】
・白華山 慈雲寺(長野県下諏訪町)
・南宮大神社 (韮崎市大草町上條東割)
・諏訪南宮大神社(笛吹市境川町寺尾)
・松原諏方神社(長野県小海町)
・船形神社(北杜市高根町長沢)
【 浅間神社 】
・冨士御室浅間神社(富士河口湖町勝山)
・北口本宮冨士浅間神社(富士吉田市上吉田)
【 飯縄権現 】
・飯縄神社(皇足穂命神社) (長野県長野市富田)
・金剛山 普門寺 (神奈川県相模原市緑区中沢)
・加賀美山 法善護国寺 (南アルプス市加賀美)
【 戸隠大権現 】
・戸隠神社 (長野県長野市戸隠)
【 愛宕権現 】
・愛宕神社 (甲府市愛宕町)
【 三宝荒神 】
・真如山 華光院 (甲府市元紺屋町)
■ Vol.5 (信玄公の信仰-2)
【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
【 不動明王 】
・乾徳山 恵林寺 (甲州市小屋敷)
・大滝山 上求寺 (山梨市牧丘町倉科)
・三守皇山 大聖明王寺 (身延町八日市場)
・大聖金剛山 明王寺 (富士川町舂米)
・大野山 福光園寺 (笛吹市御坂町大野)
・松本山 大蔵経寺 (笛吹市石和町松本)
・法性山 玄法院 (甲府市天神町)
・龍本山 不動寺 (群馬県安中市松井田町)
【 毘沙門天 】
・徳和山 吉祥寺 (山梨市三富徳和)
・河浦山 薬王寺 (市川三郷町上野)
・宝塔山 多聞院 (埼玉県所沢市中冨)
(・瑞巖山 円光院 (甲府市岩窪町))
(・熊野神社 (甲州市塩山))
■ Vol.6 (信玄公ゆかりの寺社-1)
【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
・金剛山 慈眼寺 (笛吹市一宮町末木)
・高橋山 放光寺 (甲州市藤木)
【 善光寺 】
・定額山 善光寺(甲斐善光寺/甲州善光寺) (甲府市善光寺)
・塩山 向嶽寺 (甲州市上於曽)
・妙亀山 広厳院 (笛吹市一宮町金沢)
・調御山 佛陀寺 (笛吹市石和町市部)
・岩泉山 光福寺 (甲府市横根町)
・護国山 国分寺 (笛吹市一宮町国分)
・柏尾山 大善寺 (甲州市勝沼町勝沼)
・龍湖山 方外院 (身延町瀬戸)
・海雲山 寿徳寺 (山中湖村平野)
■ Vol.7 (信玄公ゆかりの寺社-2)
【 真宗と信玄公 / 日蓮宗と信玄公 】
【 真宗と信玄公 】
・塩田山 超願寺 (笛吹市一宮町塩田)
・真宗大谷派東本願寺甲府別院 光澤寺 (甲府市相生)
・法流山 入明寺 (甲府市住吉)
【 日蓮宗と信玄公 】
・身延山 久遠寺 (身延町身延)
・武井坊(身延町身延(西谷))
・上行山 要法寺 (甲府市武田)
・大津山 実相寺 (北杜市武川町山高)
■ Vol.8 (信玄公ゆかりの寺社-3)
【 山梨県外のゆかりの寺社 】
【 長野県 】
・生島足島神社 (長野県上田市下之郷)
・新海三社神社 (長野県佐久市田口宮代)
・新海山 上宮寺 (長野県佐久市田口)
・太田山 龍雲寺 (長野県佐久市岩村田)
・一行山 西念寺 (長野県佐久市岩村田)
・寶林山 安養寺 (長野県佐久市安原)
・平林山 千手院 (長野県佐久穂町平林)
・海尻山 醫王院 (長野県南牧村海尻)
・富蔵山 岩殿寺 (長野県筑北村別所)
・横湯山 温泉寺 (長野県山ノ内町平穏)
【 群馬県 】
・榛名神社 (群馬県高崎市榛名山町)
■ Vol.9 (信玄公ゆかりの寺社-4)
【 古長禅寺 】
・瑞雲山 古長禅寺 (南アルプス市鮎沢)
【 恵林寺 】
・乾徳山 恵林寺 (甲州市小屋敷)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 甲州道中桃太郎伝説御朱印巡り

山梨県東部の郡内地域は、東京から近いですが意外と御朱印がいただきにくいエリアでした。
昨年(令和元年10月7日)に、大月・上野原エリアの6箇寺からなる巡拝コースが開創され、御朱印がいただきやすくなっているのでご紹介します。
大月~上野原周辺には桃太郎の伝説が伝わっており、それにちなむ巡拝です。
御朱印対応時間は9:00~16:00。
パンフには「盆暮れ正月は対応不可」とあり、書置きをご用意されているお寺さんも多いので、お彼岸でも授与いただけるかもしれません。(ただし、授与を保証するものではありません。念のため。)
なお、先月8月に全て拝受しているので、コロナ禍のもとでも御朱印は授与されていると思います。(一時中断、6/1から再開しているようです。)
お寺間の距離はけっこうあるので、徒歩ではきびしいかもしれません。
車であれば、半日あれば結願できるかと思います。
禅宗寺院がメインで、趣きのあるお寺さんが多いです。
また、いくつかのお寺さんでは他の霊場の札所も兼務されており、そちらの御朱印も拝受できるので併せてご紹介します。
なお、郡内三十三番観音霊場は廃寺となった札所もありますが、御朱印を拝受できる札所がかなりあります。
とりあえずは基本情報と、御朱印のみです。
「甲州道中桃太郎伝説御朱印巡り」の御朱印は原則主印が桃の絵で、これに尊格の揮毫が加わるというめずらしいものです。
桃は、古来「邪気を払う」果物といわれています。
桃太郎が鬼退治をするというのも、そういう背景があったのかもしれません。
第1番
飯盛山 青苔寺
山梨県上野原市鶴島611
臨済宗南禅寺派 御本尊:薬師如来
札所:

第2番
熊埜山 西光寺
山梨県上野原市野田尻849
臨済宗建長寺派 御本尊:虚空蔵菩薩
札所:甲斐国三十三番観音札所第31番(旧長福寺)、甲斐八十八ヶ所霊場第7番

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第3番
龍澤山 宝勝寺
山梨県上野原市犬目930
曹洞宗 御本尊:釈迦如来・(犬目観音)
札所:甲斐八十八ヶ所霊場第6番、郡内三十三番観音霊場第23番(旧無量寺)
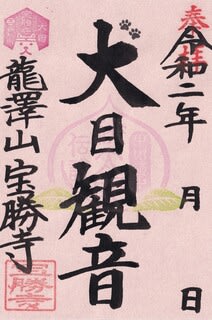
〔甲斐八十八ヶ所霊場の御朱印〕

・葛飾北斎「富嶽三十六景」、歌川広重「不二三十六景」は、この辺りから描いたといわれています。
〔郡内三十三番観音霊場の御朱印〕
・本堂前、「犬目観音」の御朱印よこに「郡内三十三番観音霊場第23番」の説明があったので、札所印はないですが、「犬目観音」の御朱印が霊場御朱印かと思われます。
第4番
石森山 円福寺
山梨県大月市富浜町鳥沢2117
臨済宗建長寺派 御本尊:薬師如来
札所:郡内三十三番観音霊場第22番

〔郡内三十三番観音霊場の御朱印〕

第5番
徳蔵山 妙楽寺
山梨県大月市猿橋町藤崎619
曹洞宗 御本尊:釈迦如来
札所:

第6番
中樹山 浄照寺
山梨県大月市賑岡町奥山1047
浄土真宗本願寺派 御本尊:阿弥陀如来
札所:

〔 関連サイト 〕
・公式Web
・大月市観光協会
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
2020/09/18 UP
寺院をいくつか追加しましたので、リニューアル再UPします。
2020/09/14 UP
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
2020/05/04 UP
つづきです。
■【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
笛吹市一宮町の慈眼寺には「信玄公の戦勝祈願依頼文」が残されています。
これは永禄十一年(1568年)信玄公が越後侵攻にあたって、信州・穂保の長沼城で、甲斐国内の真言宗・天台宗の11の諸大寺に先勝祈願を依頼されたものといわれています。
祈願先としてつぎの11箇寺が伝わっています。
〔 〕は現在の御本尊ないしは現況。
法善寺(法善護国寺)(南アルプス市) 〔阿弥陀如来、Vol.4にてご案内〕
普賢院(山梨市) 〔大井俣窪八幡神社別当・普賢菩薩〕
大野寺(御坂町の現・福光園寺) 〔不動明王〕
薬王寺(市川三郷町) 〔毘沙門天〕
大蔵寺(石和町の現・大蔵経寺) 〔不動明王〕
法光寺(甲州市)・・・現・放光寺とみられる 〔大日如来〕
明王寺(増穂町) 〔不動明王〕
天台宗の喜見寺 〔現況不詳〕
満蔵院(甲府市武田) 〔毘沙門天 or 千手観世音菩薩〕
安楽院 〔現況不詳〕
慈眼寺(一宮町) 〔千手観世音菩薩〕
この祈願ののち、信玄公は北信・飯山城の攻略に成功したため、慈眼寺には赤地金襴の七条袈裟、毘沙門天像、地蔵菩薩像と水晶の数珠が寄進されたとの記録があるようです。
↑の先勝祈願11箇寺の御本尊は、不動明王と毘沙門天が多くなっています。
そこで不動明王と毘沙門天を御本尊とする寺院を先にご紹介し、その後、Vol.6で不動明王と毘沙門天以外を御本尊とする寺院をご紹介します。
■【 不動明王 】
信玄公は不動明王を信仰されていたとされます。
菩提寺恵林寺の明王殿には、信玄公が大僧正位を受けた記念に京の仏師・宮内卿法(斉藤)康清を招き、自らの姿を模刻させて髪毛を像の胸に塗りこめたという「武田不動尊」が御座します。
信玄公の肖像や武田二十四将図には、信玄公を不動明王に模して描かれている例があります。
信玄公生誕の地である要害山城にも「武田不動尊」が祀られています。
不動明王の梵名の「アチャラ」は「動かないもの」、「ナータ」は「守護者」または「尊者」を意味し、「揺るぎなき守護者・尊者」の性格をもたれます。
右手に剣、左手に羂索を握られ、忿怒の形相をとられる力感あふれるお姿で、護摩の御本尊とされる例も多い尊格です。
身延の大聖明王寺の公式Webに、「武田信玄が護摩の本尊、弓箭(きゅうせん)の守護としてこの不動明王を深く尊崇しましたが、信玄の中にそうした勇ましい甲斐源氏の血が脈々として流れていることをよく知っていたからだと思います。」とありますが、まさにそのような流れからの不動尊信仰だったのではないでしょうか。
また、有名な信玄公の旗指物(軍旗)/孫子の旗(風林火山)に、「不動如山」(動かざること山の如し)とあるので、この「不動」の文字が不動明王と重なって、不動明王と信玄公のイメージ的なつながりが、後世さらに強まっていった可能性もあります。
以下、不動明王と信玄公とのつながりが伝わる寺院についてご紹介します。
■ 乾徳山 恵林寺



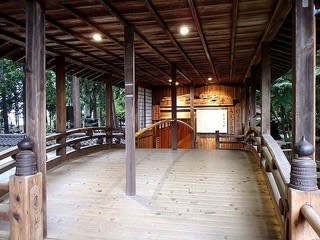
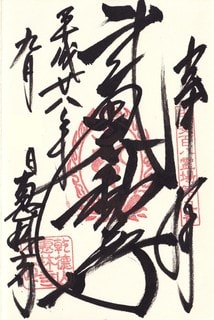
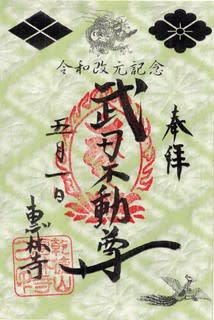
公式Web
甲州市小屋敷2280
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第73番
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第9番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第九番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
甲斐百八霊場の札所本尊は御本尊の例が多いですが、当寺では「武田不動尊」となっています。
〔令和改元記念の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 書置(筆書)
札番:なし
・中央に不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。左上に「武田菱」の紋、中央上におそらく青龍、右上に武田家の控え紋「花菱」の紋
右下におそらく朱雀。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
青龍と朱雀は四神の内ですが、改元にちなんでの配置と思われます。
この御朱印には「甲斐百八霊場第九番」の札所印は捺されておらず、「武田不動尊」単独の御朱印となっています。
(恵林寺の詳細については、別編でご紹介します。)
信玄公の菩提寺で「武田不動尊」が御座する、信玄公とすこぶるゆかりの深い名刹です。
「武田不動尊」は「明王殿」の奥深く御座し、拝観ができます。
当寺の資料には、「この不動明王は、信玄公が京から仏師康清を招聘し、信玄と対面して彫刻させ、信玄自らの頭髪を焼いて彩色させたもので、伝承によると、信玄は剃髪した毛髪を漆に混ぜ、自ら坐像の胸部に刷毛で塗りこめたといわれている。」とあります。
また、『甲陽軍鑑』『甲斐国志』には、信玄公の姿を写した像であるとする伝承が記されています。
『甲斐国志』巻第75原文(国会図書館DC、コマ番号70/75)
「洛ノ佛工康清ヲ召シ対面ニ彫刻セシム其與不動明王相ヒ肖タルヲ以テ螺髪結跏シテ羂索ヲ執ラシメ焼頭髪著色トス 宛然タル忿怒明王ナリ 遂ニ造 金迦羅(矜羯羅)誓多迦(制吒迦二童左右ニ侍立セシム 但し肉法ト與明王同カラス胸臂ニ長毫アルヲ為殊ノミ」
武田不動尊は左手に羂索、右手に剣、背に迦樓羅炎を背負われ、、矜羯羅、制吒迦の二童子を両脇に従えた儀軌どおりの端正なお姿ながら、力感にあふれています。
■ 大滝山 上求寺
山梨市Web資料
山梨市牧丘町倉科5919
真言宗醍醐派 御本尊:不動明王
未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
山梨市のWeb資料には、「本尊の不動明王は寄木造、童子像は一木造で、頭部は耳前で前後に二材を矧ぎ、童子像はほぼ全身を一材から彫出し、面部を矧いで玉眼を篏入したと思われます。面部は欠失しています。火災の光背を背負って立つ、通形の不動明王像です。上半身を強く左にひねる姿は、信玄の願主とする恵林寺武田不動尊像にみられる姿です。」
とあり、信玄公とのゆかりを示唆しています。
また、(財)歴史博物館 信玄公宝物館のWebに「倉科の上求寺の不動尊像も信玄が参拝したという。」という記述があります。
『甲陽軍鑑』品第四(国会図書館DC、コマ番号18/265)に「或時八卦の本尊不動なりとて恵林寺の奥上求寺の不動へ御まいり候由申さるゝ」とあります。
出陣前の卦の守護が不動明王とでたので、信玄公自らわざわざ牧丘・倉科の上求寺まで戦勝祈願の参拝に出向かれるということは、こちらのお不動様への帰依が篤かったとみられます。
『甲陽軍鑑』には、この後段で信玄公と恵林寺の快川和尚の交流を示す一節があります。
-----------------------
大通智勝國師より使僧をたて恵林寺へ御立寄被成べく候由申さるゝ信玄公御返事に近日出陣にて候間歸陣の時分は是非共見舞致すべきとのことにて候重て快川和尚仰こされけるは両袖の櫻やうヽにて此花のもとに一所かまへ待つ奉る間御立より候へかしとかさねヽ使僧なり信玄公きこしめし花と承るにまいらぬは野なりとて恵林寺へ立よりさて國師と一禮なされそれにれうしすずり御座候土屋平八郎をめしてすずりをよせすみをすり候へと被御付其御筆と料紙をとつて則あそばしける
さそはずはくやしからましさくら花 さねこんころはゆきのふるてら
(誘引ずは くやしからまし さくら花 実こんころは 雪のふるてら)
源 信玄
智勝國師此歌をとりて御覧じありてほめ給ひいただき其御短寮衆御覧しありほめて各僧達拝見ありことごとく則座にて和韻なさるゝ(中略)國師の御和韻ばかりかくの分かと承はり及候なり
太守愛櫻蘇玉堂 恵林亦是鶴林寺
(太守櫻を愛す蘇玉堂 恵林もまた是れ鶴林寺)
快川大通智勝國師
-----------------------
信玄公が恵林寺の奥の上求寺に参拝されると聞き、大通智勝國師(快川和尚)は使僧を遣わして「恵林寺へ立ち寄られるように」と誘われたが、信玄公は「近日出陣にて、(出陣から)帰ってのちにお訪ねいたしましょう。」と応えられました。
快川和尚は、「両袖の櫻がようやく咲きかかっているので、この花のもとに一席設けてお待ちいたします。」と重ねて誘われました。
信玄公は「櫻の花のお誘いとお聞きしてお訪ねしないのは野暮(無風流)なり。」と申され、恵林寺に立ち寄られ上の歌のやりとりとなりました。
なお、「鶴林寺」とは、お釈迦様が入滅されたお寺です。
信玄公の風流心と、和歌のたしなみを示す逸話として知られている一節です。
このときの信玄公の和歌はなかなか奥のふかいものとされ、論文(→ 武田信玄の和歌をめぐって - 恵林寺の花の歌 -)が書かれているほどです。
この論文の筆者は、「『伊勢物語』を愛し、その世界を自家薬籠中のものとした信玄は、(略)『和漢朗詠集』の漢詩、(略)『源氏物語』の(略)催馬楽の言葉まで織り込んで、巧みに当座の和歌を詠み上げた。その和歌は、信玄が『真実の国守』になるにふさわしい器量を、師である快川和尚に対して見せつけるものだった。」とまとめられています。
■ 三守皇山 長光王院 大聖明王寺



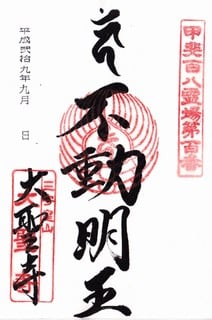
公式Web
身延町八日市場539
真言宗醍醐派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第100番、甲斐八十八ヶ所霊場第35番
朱印尊格:不動明王 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第100番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第百番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
長治二年(1105年)、新羅三郎義光公開基。曾孫に当たる加賀美遠光公が京で甲斐源氏秘伝の「鳴弦の術」をもって魔物を退散させた功により、高倉天皇から宮中清涼殿に御座し、弘法大師御作とも伝わる不動明王像と勅額を賜わり収めたと伝わる名刹。
皇室の繁栄や国家安泰の祈願寺として重用され、宮中からは祈祷のための勅使派遣が行われたと伝わります。
義光公の位牌や木造が祀られ、廟所もこの寺であるとされています。
寺伝には「信玄公は護摩の本尊、弓箭の守護としてこの不動明王を深く尊崇され、祈願寺の一つとして当寺に帰依された」とあります。
源氏正統系図、当時の寺領印書、朱印状、制札など数多くの文化財を擁し、義光公・加賀美遠光公・信玄公の木造および画像などが寺宝として残されています。
弘法大師御作とも伝わる不動明王像の霊験は広く知られていたらしく、江戸時代には三回にわたって当寺御本尊不動明王の江戸「出開帳」が行われたとも伝わります。
成田山新勝寺のお不動様の初回出開帳はこちらの資料によると元禄十六年(1703年)、当山の出開帳は山内掲示資料によると「元禄、宝永、安永そして昭和と過去四度、江戸(東京)に出開帳を行っている」とあるので、当山の出開帳は成田不動尊に匹敵する古さをもつことがわかります。
名刹を物語る広大な山内。寺号標には「高倉天皇 恩賜勅號 三守皇山 長光王院 大聖明王寺」とあります。
慶長三年(1598年)の大火で多くの堂宇を焼失し、現在は、本堂(護摩堂)、客殿(遍照殿)、庫裡などが残ります。
本堂、本堂外陣、庫裡は下山大工の石川杢左衛門によるものとされ(→身延町資料)、さすがに存在感を放っています。
■ 大聖金剛山 息障院 明王寺



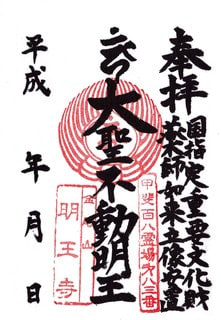
公式Web
富士川町舂米2
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第83番、甲斐八十八ヶ所霊場第37番
朱印尊格:大聖不動明王 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第83番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「カーン/カン」の種子と「大聖不動明王」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第八三番」の札所印と「国指定重要文化財 薬師如来立像安置」の揮毫。左下には山号と寺号の印判が捺されています。
甲府盆地に半月形の大きな山容を見せる櫛形山は、古くは鷹座巣(たかざす)と呼ばれました。
奈良時代の天平神護年間(765年~767年)に伊豆国甲斐国に入られた儀丹行圓上人(藤原不比等ゆかりの人物と伝わる)は、鷹座巣山中の利根川上流にある大滝(儀丹の滝)で日夜苦行を重ね、不動明王の霊像を感得されました。
この御像を御本尊として宝亀元年(770年)開山されたのが明王寺と伝わります。
「平安後期から室町の頃は広大な寺域を誇り、本堂、金堂、五重塔など多くの伽藍が立ち並んでいたそうです。歴代の皇室の勅願を賜り、菊花紋の使用が許され、のちには武田・徳川の祈願寺となり、甲斐の真言七談林の一つです。」(『甲斐百八霊場』より)
永禄十一年の「信玄公祈願先11箇寺」に「明王寺(増穂町)」としてその名がみられ、信玄公の祈願寺の役割を担っていたものとみられます。
甲斐有数の名刹を裏づけるように、「薬師如来立像」(平安初期)「鰐口」(鎌倉時代前期)の寺宝は国重要文化財に指定されています。
■ 大野山 福光園寺






まちのお寺の学校Web
笛吹市御坂町大野2027
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第40番
朱印尊格:不動明王尊 印判
札番:甲斐百八霊場第40番印判
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(火焔宝珠)と「カーン/カン」の種子と「不動明王尊」の印判。
左上に「甲斐百八霊場第四十番」の札所印。左下には山号と寺号の印判と寺院印が捺されています。
古代から栄えた八代郡にある古刹。
創建時期は不明ですが、かつては駒岳山 大野寺と号しました。
山内の観音堂に御座す「香王観音立像」は行基(668年~749年)の作と伝わるので、創建は奈良時代に遡るのかもしれません。
〔山内由緒書より〕
「当寺は推古天皇、御代聖徳太子の創立で行基菩薩が当山に錫を留められ香王観音を彫刻し、仏法結縁の霊場とされた。其の後、弘法大師が留錫され、佛像・教典の名寶を遺された希有の古刹であった。」
平安時代後期の保元二年(1157年)にこの地の領主であった大野対馬守重包により再興とされ、重包を中興開基、賢安上人を中興開山としています。
この地は爾来、甲斐の在庁官人・三枝氏の支配地で、国重要文化財指定の「木造吉祥天及び二天像」は、鎌倉時代の寛喜三年(1231年)に中興三世の良賢を勧進、三枝氏を檀越とし、仏師・蓮慶(運慶の弟子)の作とされています。
坐像の吉祥天は、全国的にもすこぶるめずらしいものです。
永禄十一年の「信玄公祈願先11箇寺」に「大野寺」としてその名がみられ、信玄公の祈願寺の役割を担っていたものとみられます。
御坂の地は、『聖徳太子伝暦』にも「甲斐の黒駒伝承」が記され、当寺にも「甲斐の黒駒」に関する伝承が伝わっているようです。
中世も「御坂牧」「黒駒牧」として軍馬の補給地になっていたとみられ、その点からも戦勝祈願の地として選ばれたのかも知れません。
樹齢900年といわれる杉や樹齢200年の枝垂桜やソメイヨシノが枝を広げて、趣きのある境内。
甲斐百八霊場第40番の札所でもあり、御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。
■ 松本山 大蔵経寺






公式Web
笛吹市石和町松本610
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第3番、石和温泉郷七福神(寿老人)
朱印尊格:不動明王 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第3番印判
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第三番」の札所印。左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
奈良時代の養老六年(722年)、法相宗の行基菩薩を開祖として創建と伝わる甲斐有数の古刹。
かつては松本寺と呼ばれた大寺院で、山内に物部神社を鎮守として勧請したといい、弘法大師が不動明王を彫られ納められたという伝承もあるようです。
応安三年(1370年)、足利三代将軍義満公の庶子、観道上人が中興開山として入山の際、義満公が甲斐の守護武田信成公に命じて七堂伽藍を建立。この中興開山の折から武田家祈願寺になりました。
五層の宝塔を建て、大蔵経を奉納したのが寺号の由縁とされます。
永正十三年(1516年)9月、信虎公と駿河勢との「万力の合戦」にて焼亡、その後復興されました。
永禄十一年(1568年)の信玄公の「先勝祈願11箇寺」のひとつで、「大蔵寺」の寺名で記録されています。
当寺には、川中島合戦にあたり信玄公が戦勝祈願をされたという将軍地蔵菩薩像が祀られています。
御本尊の不動明王座像は伝智証大師作とされ、矜羯羅・制多迦両童子を脇侍に力感あふれるお姿です。
庭園・現代仏画の拝観には拝観料が必要ですが、札所の参拝には必要ありません。
背後に大蔵経寺山を背負って落ち着きのよい山内。
甲斐百八霊場、石和温泉郷七福神の札所であり、御朱印は快く授与いただけました。
■ 法性山 玄法院





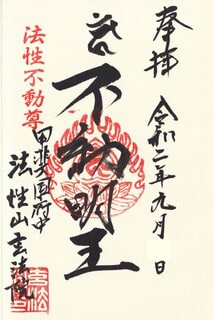
甲府山の手七福神巡礼Web
甲府市天神町2-18
真言宗醍醐派 御本尊:不動明王
札所:山の手七福神めぐり(福禄寿)
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:不動明王 直書(筆書)
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と揮毫と「不動明王」の揮毫。
左上に「法性不動尊」の印判。
左下には「甲斐古府中」と山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。
建久三年(1192年)創立の真言宗醍醐派の修験寺。
寺伝によると、大永年間(1521年~)、信虎公が巨摩郡下黒沢村(高根町)から府中峰本(甲府市相川地区)に移され、信玄公の法名「法性山機山信玄」から山院号を賜り法性山玄法院と称し、武田家三代領主が本尊不動明王に戦勝祈願をした寺とのことです。
「武田家滅亡後は、徳川幕府より現在地の御領を賜り寺を移築し、真言宗醍醐派京都三宝院の末として当山派修験の法流を現在につなげています。」(寺伝)とあり、保守本流?の当山派修験寺であることがわかります。
みずからの法名を賜るというのは、よほど崇敬が篤かった証とも思われ、信玄公の不動明王への信仰の篤さが伺われます。
甲州夢小路の「時の鐘」は、当寺の鐘楼を模し、残されていた写真・鳥瞰図・礎石を基に再現されています。
の外壁といった仕様で、忠実に再現されています。
天神町の住宅街の路地に面しますが、山内は意外に広さがあり、車も停められます。
門柱の寺号標には武田菱と「法性山 玄法院」の刻字。
右手に銘木「玄法院のイチョウ」と稲荷大明神、左手に金毘羅大権現と福禄寿尊が合祀されたお堂と修行大師像。
山梨県立図書館の情報によると、「1533(天文2)年、玄法院の第八代住職が四国讃岐の金毘羅宮にお参りして、その分岐したものを湯村山城の守護神としたと言われる。」とあるので、そちらの金毘羅宮さまとゆかりがあるかもしれません。
狛犬一対、灯籠一対、本堂右手にお前立ちとみられる石造立像の不動明王。
正面扁額は「不動明王」で、開け放たれた堂内には御本尊のお不動さまと護摩壇。いかにも修験寺らしいイメージがあります。
御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受しました。
修験寺は総じて猛々しいイメージがあるのですが、意外と御朱印対応がフレンドリーなお寺さんが多く、こちらでもご親切なご対応をいただきました。
このほか、甲斐市竜地の武田社にも信玄公ゆかりの「武田不動尊」が祀られています。
甲府市元紺屋町の行蔵院の御本尊も「武田不動尊」と称され、御朱印も授与されていますが、こちらは山本勘助とのゆかりが伝えられているので、山本勘助編でご紹介します。
■ 龍本山 松井田院 不動寺






群馬県安中市松井田町松井田987
真言宗豊山派 御本尊:千手観世音菩薩
札所:北関東三十六不動霊場第4番、関東八十八箇所第2番、上州三十三観音霊場第21番、上野之國三十四カ所観音霊場第13番

〔北関東三十六不動霊場の御朱印〕
朱印尊格:不動明王 直書(筆書)
札番:北関東三十六不動霊場第4番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。
右上に「北関東三十六不動霊場第四番」の札所印。左下には院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔関東八十八箇所の御朱印〕
朱印尊格:千手観音 直書(筆書)
札番:関東八十八箇所第2番
・中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+宝珠)と「千手観音」の揮毫。右上に「関東第二番」の札所印。左上に霊場開創二十周年の記念印。
右下に院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

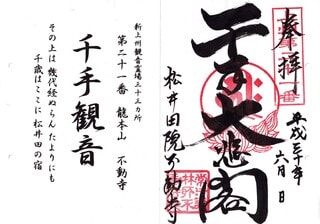
〔上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印書入/専用納経帳)〕
朱印尊格:千手大悲閣 直書(筆書)
札番:上州三十三観音霊場第21番
・中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。
右上に「上州第二十一番」の札所印。
右下に院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用納経帳は、片面に御詠歌が印刷されています。
西毛の名山、妙義山を望む高台に位置し、複数の霊場札所をつとめられる上州の名刹。
複数の霊場ガイドブックに「元亀天正年間に武田信玄公により寺領を賜り」とあり、山内の縁起碑には「元亀・天正年中、武田信玄公不動尊ノ帰依篤く、寺領ヲ賜リ租税ヲ免状シ武田家祈願所ト為ス」と記されています。
また、寺宝として「武田家書状」が所蔵されています。
御本尊は千手観世音菩薩ですが、安中市のWeb情報に「慈猛上人が立ち寄った雷雨の夜、松に大龍が登り、その下に井戸の形の清水が湧いた。そこで不動尊を安置、松井田院と名付けた。松井田の里のいわれという。」とあり、寛元元年(1243年)の慈猛上人による開山時に、すでに地名のいわれとなるような著名な不動明王が祀られていたことがわかります。
慈猛上人は後深草天皇より「留興長老」の号を賜わった高僧で、下野の薬師寺の上座(長老)、下野国司も務められたと伝わります。
当地の城、松井田城は永禄七年(1564年)武田氏の攻勢で開城し、武田氏滅亡までその支配下にありました。
『上野志』(国会図書館DC、コマ番号20/226)に「安中左近将監忠成、騎馬高百十八騎、武田信玄公へ降参。安中の城本領共に甘利左右衛門妹壻に仰せ付けられ候。信州・美濃信玄軍場に詰むるなり。」とあります。
松井田・安中一帯は安中市の領地で、武田氏進出ののちは安中左近将監忠成(景繁)が
信玄公の家臣、甘利左衛門尉(信忠)の妹を娶って武田勢の麾下に入り、信州、美濃方面へ出陣しています。
同寺に伝わる「武田家書状」、あるいは「祈願所」とした日付は定かではありませんが、永禄七年(1564年)以降、松井田・安中周辺は信玄公の支配下にあり、その頃の事柄と考えられます。
江戸時代、十五世秀算僧正は徳川家康公の命により、総本山長谷寺の第四世能化となられ、家光公からも朱印地八十九石余の寺領を拝領したという高い寺格の寺院です。
三門右手の年季入った看板には「北関東三十六不動霊場第四番、上野国観音霊場第十三番」の札所案内。
参道左手の覆堂内に異形の板碑、正面の仁王門(三間一戸切妻造柿葺単層八脚、阿吽二体の仁王像安置)ともに県指定重要文化財です。
仁王門の大棟に三つ置かれた菱紋は武田菱にも見えますが、どうでしょうか。
右手六地蔵の先、参道両側に不動明王三十六童子。階段を昇ると正面が不動堂、左手が本堂です。
本堂は入母屋造銅板葺向拝付で、欄間の龍の彫刻、木鼻の獅子の彫刻ともなかなかの迫力です。
御本尊千手観世音菩薩が御座し、右手の向拝柱に「関東八十八ヵ所霊場第二番」、左手に「上野国順禮札所第十三番」の札所板が掲出されています。
不動堂は入母屋造桟瓦葺向拝付で、大棟、降棟の意匠が見事。向拝欄間の彫刻も手が込んだもの。右手の向拝柱に「北関東三十六不動尊霊場第四番札所」の札所板。
不動堂に御座す不動明王は、鎌倉時代初期、中央仏師の作と推定される精巧なお像で、県重要文化財に指定されています。
御朱印は、北関東三十六不動霊場、関東八十八箇所、上州三十三観音霊場の3種を拝受しています。(上野之國三十四カ所観音については授与不明です。)
メジャー霊場の札所につき、御朱印授与は手慣れたご対応です。
【 毘沙門天 】
毘沙門天は、仏教では天部の仏神で、持国天、増長天、広目天とともに四天王の一尊に数えられます。
四天王は帝釈天に仕え、須弥山の中腹で仏法を守護する役割を担われています。
東方を持国天、南方を増長天、西方を広目天、北方を多聞天(毘沙門天)が守護しています。
単独で祀られることも多く、その場合は毘沙門天と呼ばれ、四天王の一尊や二天門で持国天とともに祀られる場合は多聞天と呼ばれます。
七福神の一尊でもあり、この場合は毘沙門天と呼ばれます。
梵名はヴァイシュラヴァナ。
これは「よく聞く」を意味し、「お釈迦様の説法をもっともよく聞かれた(尊格)」からきているようです。(”多聞天”はここからきているとされる。)
また、クベーラ(インド神話の富と財宝の神)と同体とされ、もともと財宝神の性格をもたれています。
「軍神」という性格は、「多聞天は四天王のリーダー格」「四天王のなかでもっとも強い」という説があり、ここから来ているのかもしれませんが、これは「軍神」の性格が確立されてから後に付会されたものかもしれません。
むしろ、毘沙門天が仕える帝釈天は、戦いの神インドラと同一であり、毘沙門天は夜叉や羅刹といった鬼神を眷属として従えるという立場から、「軍神」のイメージが定着していったのではないでしょうか。
わが国では、信貴山(朝護孫子寺)において聖徳太子が戦勝祈願をされ、毘沙門天王から必勝の秘法を授かり勝利されたという逸話が有名で、以来、毘沙門天=軍神信仰が広まったとされる説があります。
いずれにしても、軍神と財宝神の両面をもたれるすこぶる強力な尊格といえましょう。
戦国武将で毘沙門天信仰の例は少なくないですが、なかでも上杉謙信公が有名で、軍旗にも「毘」の文字をつかわれていました。
信玄公も毘沙門天をふかく信仰されたと伝わります。
「川中島の戦い」は軍神・毘沙門天を信仰する両雄の戦いともいえ、両者譲らぬ激しい戦さとなったこともうなづける感じがします。
信玄公は軍陣の守り本尊として刀八毘沙門天像を信仰されていましたが、この尊像は、現在円光院に所蔵されています。(Vol.3を参照願います。)
また、武田神社内に掲出されている「(躑躅ヶ崎館)東・中曲輪平面想像図」には、館の東北に不動堂と毘沙門堂が掲載され、躑躅ヶ崎館で日頃から両尊の供養がおこなわれていたことがわかります。
信玄公ゆかりの毘沙門天は、ほかにもいくつか伝わります。
■ 徳和山 吉祥寺





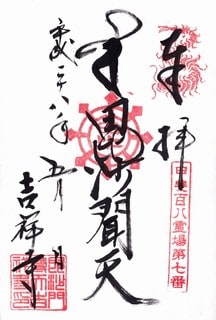
公式Web
山梨市三富徳和2
真言宗智山派 御本尊:毘沙門天
札所:甲斐百八霊場第7番、甲州東郡七福神(毘沙門天)
朱印尊格:毘沙門天 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第7番印判
・中央に札所本尊毘沙門天の御紋印と種子「ベイ」と「毘沙門天」の揮毫。
右上に「大百足」の印。右下に「甲斐百八霊場第七番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
もともと武田氏と毘沙門天のゆかりはあったらしく、武田信光公は承元年間(1207年~1210年)、甲斐源氏守護のため乾徳山のふもとに吉祥寺を建立し、御本尊として毘沙門天を安置されました。
この堂宇は永禄八年(1564年)に信玄公によって再興され、これを示す当時の棟札がいまも寺に保存されていることからも、信玄公の毘沙門天信仰が伺われます。
〔山内掲示/本堂永禄八年再興棟札〕
「大檀越源朝臣晴信奉為武運長久再興之 伏願 家門繁栄武門長久至祝至檮 敬白」
吉祥寺周辺は武田軍の伝令隊としてその名を馳せた「武田百足(むかで)衆」の本拠地で、吉祥寺内陣の欄間には2m以上もある大百足の彫刻があります。
「武田百足衆」を率いた真田兵部丞昌輝は武田二十四将の真田信綱の弟で、武田二十四将に数えられる例もあります。
■ 河浦山 薬王寺




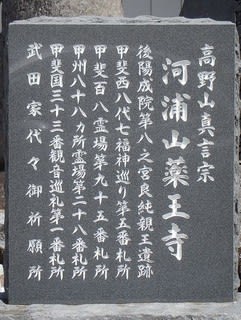


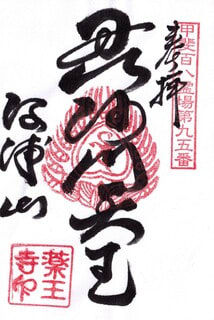


(公社)やまなし観光推進機構Web
市川三郷町上野199
高野山真言宗 御本尊:毘沙門天
札所:甲斐百八霊場第95番、甲斐国三十三番観音札所第1番、甲斐八十八ヶ所霊場第28番、甲斐西八代七福神(恵比寿)
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:毘沙門天王 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第95番
・中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「毘沙門天王」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第九五番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
朱印尊格:十一面観世音菩薩 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第62番
・中央に種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。こちらの札所本尊は十一面観世音菩薩とみられますが、十一面観世音菩薩の種子「キャ」ではありません。
観音霊場発願寺につき、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印をつかわれているのかもしれません。
中央に「十一面観世音」の揮毫。
右上に「甲斐観音第一番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔甲斐西八代七福神(恵比寿)の御朱印〕
朱印尊格:恵比寿大神 書置(筆書)
札番:甲斐西八代七福神第5番(恵比寿)
・中央に恵比寿神ゆかりの持物「鯛」の印と「恵比寿大神」の揮毫。
右上に「甲斐西八代七福神第五番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
天平十八年(746年)、聖武天皇の命により行基菩薩が自ら多聞天像を彫刻し安置したのが始まりとされる古刹。観全僧都の開山とも伝わります。
天長九年(832年)に淳和天皇から、天治元年(1124年)には源義清公からの寺領の寄進の記録が残ります。
中世は武田家から信仰され、とくに信玄公は毘沙門天への帰依篤く、当寺で度々戦勝祈願が行われ、十二天画像や川中島合戦の図などが寄進されています。
御坂山塊が芦川に向けて山裾を落とす複雑な地形に位置し、Pは山内中腹にあるので、表参道から入山するには一旦降りるかたちになります。
複数の札所を兼ねられ、入口に札所を示す石碑があります。
急な階段の上に構える山門は入母屋瓦葺三間一戸の八脚門で風格があります。
めずらしいオハツキイチョウは、国指定の天然記念物に指定されています。
山内左手に甲斐西八代七福神(恵比寿)の御座。
正面の桟瓦葺の建物は、向かって右手が本堂、中央が客殿(八之宮良純親王御座所)、左が庫裡で、入母屋造だと思いますが、客殿は唐破風向拝、庫裡玄関は千鳥破風で棟が連続しており、正確な様式・規模はよくわかりません。
本堂右手のお大師様の前を進むと、観音堂があり、こちらは甲斐国三十三番観音札所第1番の発願所となっています。こちらの札所本尊の十一面観世音菩薩は、もともと町屋にあった大眞寺の御本尊で、明治初期の大眞寺火災ののち、本寺である薬王寺に観音堂を建立し安置された(戦後に再建安置)とのこと。
客殿の上段の間には、八之宮良純親王御座所(御座の間)の一部が保存されています。
親王は、後陽成天皇の第八皇子で京都知恩院の門跡となりましたが、寛永二十年(1643年)故あって甲斐に流され、明歴元年(1655年)から5年間当寺に居住されて後、京に戻られました。
親王が起居されたことからも、寺格の高さが伺われます。
現在、3つの現役札所を兼ねておられ、御朱印は手慣れたご対応にて拝受できます。
南側に隣接して東照宮が鎮座します。
甲斐国の要所、市川郷への東照宮鎮座はいささか不思議な感じもしますが、市川の表門神社は、天正十年(1582年)、家康公甲斐入国の折に本陣が置かれて武運長久を祈願され(御陣場御宮)、慶長十四年(1609年)、徳川幕府により社殿が寄進されているので、そちらとの関連があるのかもしれません。(市川三郷町資料より)
■ 宝塔山 吉祥寺 多聞院






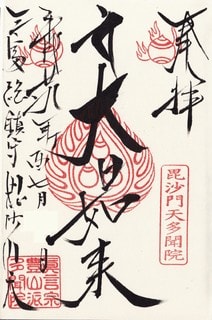


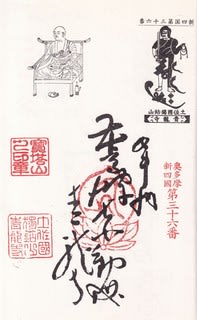
埼玉県所沢市中冨1501
真言宗豊山派 御本尊:金剛界大日如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:大日如来 直書(筆書)
・中央に三つの宝珠と火焔を合わせた印。御本尊金剛界大日如来の種子「バン」の種子と「大日如来」の揮毫。
右下に「毘沙門天多門院」の印。左には「三富総鎮守 毘沙門天」の揮毫と寺院印が捺されています。
〔毘沙門天の御朱印〕
朱印尊格:毘沙門天 直書(筆書)
・中央に三つの宝珠と火焔を合わせた印。毘沙門天の種子「ベイ」と「毘沙門天」の揮毫。
右に「武田信玄公守本尊」の印。左には山号・印号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔奥多摩新四国霊場の御朱印〕
朱印尊格:不詳(不動明王) 専用納経帳に捺印
札番:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
・中央に種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。こちらの札所本尊は不動明王とみられますが、不動明王の種子「カーン/カン」ではありません。五大明王の種子が「キリーク」なので、そちらの御寶印をつかわれているのかもしれません。揮毫(印刷)は不明ですが、「本尊」と「不動」の文字は読み取れます。
左上に御椅子御坐された真如親王様のお大師様の御影。右上に土佐國獨鈷山青龍寺にちなむ御影。右に「奥多摩新四国第三十六番」の札所印。左に多門院の山号印と青龍寺の寺院印が捺されています。
※こちらの札所は当初瑞穂町長岡の開山所内に安置されていましたが、「2013年に多聞院に移管され開眼法要が行なわれた。」との情報があります。(→情報元)
埼玉県所沢市にある多門院には、信玄公ゆかりとされる毘沙門天が祀られています。
この地は江戸時代、川越藩主の柳沢吉保が新田開拓をおこなったところで、吉保は開拓農民の菩提寺多福寺を祈願所として、毘沙門社を建立しました。
寺伝では、毘沙門堂(社)後本尊の毘沙門天は信玄公の守り本尊で、信玄公が戦陣に臨まれるときはいつも兜の中にこの像を納めていたと伝わります。
「信玄公の戦陣守り本尊である毘沙門天像は、甲斐源氏の末裔を称した柳沢吉保の手に渡った」という伝承があり、その伝承ゆかりの御像とみられます。
はじめて参拝したときはこの由来を知らなかったので、境内で武田菱と「信玄公守り本尊」ののぼりを目にしたときは正直おどろきました。(武田軍は吉見の松山城を落としていますが、所沢までは侵攻していないはず。だからこの地に信玄公ゆかりの寺院があるのはナゾでした。)
境内で↑の寺伝を確認、川越藩主の柳沢吉保ゆかりということで納得がいきました。
このほか、塩山(甲州市)の熊野神社には、信玄公の寄進とされる「紙本著色刀八毘沙門天像図」が伝わり、これは信玄公が躑躅ヶ崎館で崇拝されていたものとされています。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
寺院をいくつか追加しましたので、リニューアル再UPします。
2020/09/14 UP
未参拝の寺社を参拝してきましたので追記リニューアルします。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社があります。参拝および御朱印拝受は、各々のご判断にてお願いします。
※文中、”資料A”は、「武田史跡めぐり」/山梨日日新聞社刊をさします。
2020/05/04 UP
つづきです。
■【 信玄公の戦勝祈願依頼文 】
笛吹市一宮町の慈眼寺には「信玄公の戦勝祈願依頼文」が残されています。
これは永禄十一年(1568年)信玄公が越後侵攻にあたって、信州・穂保の長沼城で、甲斐国内の真言宗・天台宗の11の諸大寺に先勝祈願を依頼されたものといわれています。
祈願先としてつぎの11箇寺が伝わっています。
〔 〕は現在の御本尊ないしは現況。
法善寺(法善護国寺)(南アルプス市) 〔阿弥陀如来、Vol.4にてご案内〕
普賢院(山梨市) 〔大井俣窪八幡神社別当・普賢菩薩〕
大野寺(御坂町の現・福光園寺) 〔不動明王〕
薬王寺(市川三郷町) 〔毘沙門天〕
大蔵寺(石和町の現・大蔵経寺) 〔不動明王〕
法光寺(甲州市)・・・現・放光寺とみられる 〔大日如来〕
明王寺(増穂町) 〔不動明王〕
天台宗の喜見寺 〔現況不詳〕
満蔵院(甲府市武田) 〔毘沙門天 or 千手観世音菩薩〕
安楽院 〔現況不詳〕
慈眼寺(一宮町) 〔千手観世音菩薩〕
この祈願ののち、信玄公は北信・飯山城の攻略に成功したため、慈眼寺には赤地金襴の七条袈裟、毘沙門天像、地蔵菩薩像と水晶の数珠が寄進されたとの記録があるようです。
↑の先勝祈願11箇寺の御本尊は、不動明王と毘沙門天が多くなっています。
そこで不動明王と毘沙門天を御本尊とする寺院を先にご紹介し、その後、Vol.6で不動明王と毘沙門天以外を御本尊とする寺院をご紹介します。
■【 不動明王 】
信玄公は不動明王を信仰されていたとされます。
菩提寺恵林寺の明王殿には、信玄公が大僧正位を受けた記念に京の仏師・宮内卿法(斉藤)康清を招き、自らの姿を模刻させて髪毛を像の胸に塗りこめたという「武田不動尊」が御座します。
信玄公の肖像や武田二十四将図には、信玄公を不動明王に模して描かれている例があります。
信玄公生誕の地である要害山城にも「武田不動尊」が祀られています。
不動明王の梵名の「アチャラ」は「動かないもの」、「ナータ」は「守護者」または「尊者」を意味し、「揺るぎなき守護者・尊者」の性格をもたれます。
右手に剣、左手に羂索を握られ、忿怒の形相をとられる力感あふれるお姿で、護摩の御本尊とされる例も多い尊格です。
身延の大聖明王寺の公式Webに、「武田信玄が護摩の本尊、弓箭(きゅうせん)の守護としてこの不動明王を深く尊崇しましたが、信玄の中にそうした勇ましい甲斐源氏の血が脈々として流れていることをよく知っていたからだと思います。」とありますが、まさにそのような流れからの不動尊信仰だったのではないでしょうか。
また、有名な信玄公の旗指物(軍旗)/孫子の旗(風林火山)に、「不動如山」(動かざること山の如し)とあるので、この「不動」の文字が不動明王と重なって、不動明王と信玄公のイメージ的なつながりが、後世さらに強まっていった可能性もあります。
以下、不動明王と信玄公とのつながりが伝わる寺院についてご紹介します。
■ 乾徳山 恵林寺



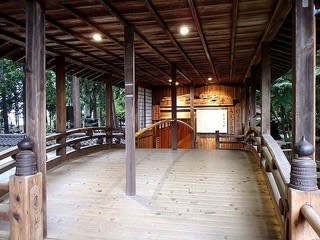
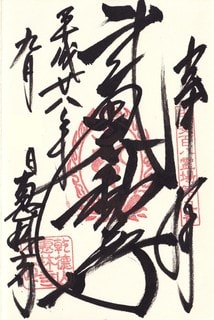
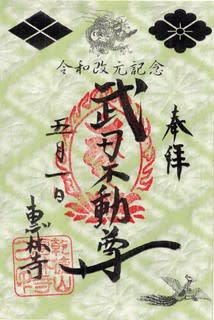
公式Web
甲州市小屋敷2280
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:甲斐百八霊場第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第73番
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第9番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第九番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
甲斐百八霊場の札所本尊は御本尊の例が多いですが、当寺では「武田不動尊」となっています。
〔令和改元記念の御朱印〕
朱印尊格:武田不動尊 書置(筆書)
札番:なし
・中央に不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「武田不動尊」の揮毫。左上に「武田菱」の紋、中央上におそらく青龍、右上に武田家の控え紋「花菱」の紋
右下におそらく朱雀。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
青龍と朱雀は四神の内ですが、改元にちなんでの配置と思われます。
この御朱印には「甲斐百八霊場第九番」の札所印は捺されておらず、「武田不動尊」単独の御朱印となっています。
(恵林寺の詳細については、別編でご紹介します。)
信玄公の菩提寺で「武田不動尊」が御座する、信玄公とすこぶるゆかりの深い名刹です。
「武田不動尊」は「明王殿」の奥深く御座し、拝観ができます。
当寺の資料には、「この不動明王は、信玄公が京から仏師康清を招聘し、信玄と対面して彫刻させ、信玄自らの頭髪を焼いて彩色させたもので、伝承によると、信玄は剃髪した毛髪を漆に混ぜ、自ら坐像の胸部に刷毛で塗りこめたといわれている。」とあります。
また、『甲陽軍鑑』『甲斐国志』には、信玄公の姿を写した像であるとする伝承が記されています。
『甲斐国志』巻第75原文(国会図書館DC、コマ番号70/75)
「洛ノ佛工康清ヲ召シ対面ニ彫刻セシム其與不動明王相ヒ肖タルヲ以テ螺髪結跏シテ羂索ヲ執ラシメ焼頭髪著色トス 宛然タル忿怒明王ナリ 遂ニ造 金迦羅(矜羯羅)誓多迦(制吒迦二童左右ニ侍立セシム 但し肉法ト與明王同カラス胸臂ニ長毫アルヲ為殊ノミ」
武田不動尊は左手に羂索、右手に剣、背に迦樓羅炎を背負われ、、矜羯羅、制吒迦の二童子を両脇に従えた儀軌どおりの端正なお姿ながら、力感にあふれています。
■ 大滝山 上求寺
山梨市Web資料
山梨市牧丘町倉科5919
真言宗醍醐派 御本尊:不動明王
未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
山梨市のWeb資料には、「本尊の不動明王は寄木造、童子像は一木造で、頭部は耳前で前後に二材を矧ぎ、童子像はほぼ全身を一材から彫出し、面部を矧いで玉眼を篏入したと思われます。面部は欠失しています。火災の光背を背負って立つ、通形の不動明王像です。上半身を強く左にひねる姿は、信玄の願主とする恵林寺武田不動尊像にみられる姿です。」
とあり、信玄公とのゆかりを示唆しています。
また、(財)歴史博物館 信玄公宝物館のWebに「倉科の上求寺の不動尊像も信玄が参拝したという。」という記述があります。
『甲陽軍鑑』品第四(国会図書館DC、コマ番号18/265)に「或時八卦の本尊不動なりとて恵林寺の奥上求寺の不動へ御まいり候由申さるゝ」とあります。
出陣前の卦の守護が不動明王とでたので、信玄公自らわざわざ牧丘・倉科の上求寺まで戦勝祈願の参拝に出向かれるということは、こちらのお不動様への帰依が篤かったとみられます。
『甲陽軍鑑』には、この後段で信玄公と恵林寺の快川和尚の交流を示す一節があります。
-----------------------
大通智勝國師より使僧をたて恵林寺へ御立寄被成べく候由申さるゝ信玄公御返事に近日出陣にて候間歸陣の時分は是非共見舞致すべきとのことにて候重て快川和尚仰こされけるは両袖の櫻やうヽにて此花のもとに一所かまへ待つ奉る間御立より候へかしとかさねヽ使僧なり信玄公きこしめし花と承るにまいらぬは野なりとて恵林寺へ立よりさて國師と一禮なされそれにれうしすずり御座候土屋平八郎をめしてすずりをよせすみをすり候へと被御付其御筆と料紙をとつて則あそばしける
さそはずはくやしからましさくら花 さねこんころはゆきのふるてら
(誘引ずは くやしからまし さくら花 実こんころは 雪のふるてら)
源 信玄
智勝國師此歌をとりて御覧じありてほめ給ひいただき其御短寮衆御覧しありほめて各僧達拝見ありことごとく則座にて和韻なさるゝ(中略)國師の御和韻ばかりかくの分かと承はり及候なり
太守愛櫻蘇玉堂 恵林亦是鶴林寺
(太守櫻を愛す蘇玉堂 恵林もまた是れ鶴林寺)
快川大通智勝國師
-----------------------
信玄公が恵林寺の奥の上求寺に参拝されると聞き、大通智勝國師(快川和尚)は使僧を遣わして「恵林寺へ立ち寄られるように」と誘われたが、信玄公は「近日出陣にて、(出陣から)帰ってのちにお訪ねいたしましょう。」と応えられました。
快川和尚は、「両袖の櫻がようやく咲きかかっているので、この花のもとに一席設けてお待ちいたします。」と重ねて誘われました。
信玄公は「櫻の花のお誘いとお聞きしてお訪ねしないのは野暮(無風流)なり。」と申され、恵林寺に立ち寄られ上の歌のやりとりとなりました。
なお、「鶴林寺」とは、お釈迦様が入滅されたお寺です。
信玄公の風流心と、和歌のたしなみを示す逸話として知られている一節です。
このときの信玄公の和歌はなかなか奥のふかいものとされ、論文(→ 武田信玄の和歌をめぐって - 恵林寺の花の歌 -)が書かれているほどです。
この論文の筆者は、「『伊勢物語』を愛し、その世界を自家薬籠中のものとした信玄は、(略)『和漢朗詠集』の漢詩、(略)『源氏物語』の(略)催馬楽の言葉まで織り込んで、巧みに当座の和歌を詠み上げた。その和歌は、信玄が『真実の国守』になるにふさわしい器量を、師である快川和尚に対して見せつけるものだった。」とまとめられています。
■ 三守皇山 長光王院 大聖明王寺



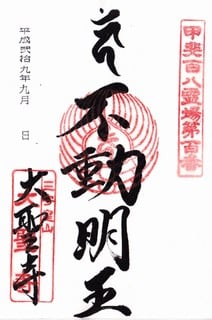
公式Web
身延町八日市場539
真言宗醍醐派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第100番、甲斐八十八ヶ所霊場第35番
朱印尊格:不動明王 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第100番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第百番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
長治二年(1105年)、新羅三郎義光公開基。曾孫に当たる加賀美遠光公が京で甲斐源氏秘伝の「鳴弦の術」をもって魔物を退散させた功により、高倉天皇から宮中清涼殿に御座し、弘法大師御作とも伝わる不動明王像と勅額を賜わり収めたと伝わる名刹。
皇室の繁栄や国家安泰の祈願寺として重用され、宮中からは祈祷のための勅使派遣が行われたと伝わります。
義光公の位牌や木造が祀られ、廟所もこの寺であるとされています。
寺伝には「信玄公は護摩の本尊、弓箭の守護としてこの不動明王を深く尊崇され、祈願寺の一つとして当寺に帰依された」とあります。
源氏正統系図、当時の寺領印書、朱印状、制札など数多くの文化財を擁し、義光公・加賀美遠光公・信玄公の木造および画像などが寺宝として残されています。
弘法大師御作とも伝わる不動明王像の霊験は広く知られていたらしく、江戸時代には三回にわたって当寺御本尊不動明王の江戸「出開帳」が行われたとも伝わります。
成田山新勝寺のお不動様の初回出開帳はこちらの資料によると元禄十六年(1703年)、当山の出開帳は山内掲示資料によると「元禄、宝永、安永そして昭和と過去四度、江戸(東京)に出開帳を行っている」とあるので、当山の出開帳は成田不動尊に匹敵する古さをもつことがわかります。
名刹を物語る広大な山内。寺号標には「高倉天皇 恩賜勅號 三守皇山 長光王院 大聖明王寺」とあります。
慶長三年(1598年)の大火で多くの堂宇を焼失し、現在は、本堂(護摩堂)、客殿(遍照殿)、庫裡などが残ります。
本堂、本堂外陣、庫裡は下山大工の石川杢左衛門によるものとされ(→身延町資料)、さすがに存在感を放っています。
■ 大聖金剛山 息障院 明王寺



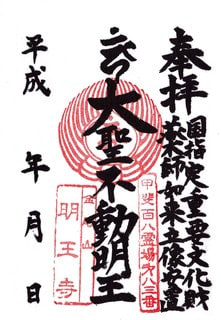
公式Web
富士川町舂米2
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第83番、甲斐八十八ヶ所霊場第37番
朱印尊格:大聖不動明王 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第83番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「カーン/カン」の種子と「大聖不動明王」の揮毫。
右に「甲斐百八霊場第八三番」の札所印と「国指定重要文化財 薬師如来立像安置」の揮毫。左下には山号と寺号の印判が捺されています。
甲府盆地に半月形の大きな山容を見せる櫛形山は、古くは鷹座巣(たかざす)と呼ばれました。
奈良時代の天平神護年間(765年~767年)に伊豆国甲斐国に入られた儀丹行圓上人(藤原不比等ゆかりの人物と伝わる)は、鷹座巣山中の利根川上流にある大滝(儀丹の滝)で日夜苦行を重ね、不動明王の霊像を感得されました。
この御像を御本尊として宝亀元年(770年)開山されたのが明王寺と伝わります。
「平安後期から室町の頃は広大な寺域を誇り、本堂、金堂、五重塔など多くの伽藍が立ち並んでいたそうです。歴代の皇室の勅願を賜り、菊花紋の使用が許され、のちには武田・徳川の祈願寺となり、甲斐の真言七談林の一つです。」(『甲斐百八霊場』より)
永禄十一年の「信玄公祈願先11箇寺」に「明王寺(増穂町)」としてその名がみられ、信玄公の祈願寺の役割を担っていたものとみられます。
甲斐有数の名刹を裏づけるように、「薬師如来立像」(平安初期)「鰐口」(鎌倉時代前期)の寺宝は国重要文化財に指定されています。
■ 大野山 福光園寺






まちのお寺の学校Web
笛吹市御坂町大野2027
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第40番
朱印尊格:不動明王尊 印判
札番:甲斐百八霊場第40番印判
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(火焔宝珠)と「カーン/カン」の種子と「不動明王尊」の印判。
左上に「甲斐百八霊場第四十番」の札所印。左下には山号と寺号の印判と寺院印が捺されています。
古代から栄えた八代郡にある古刹。
創建時期は不明ですが、かつては駒岳山 大野寺と号しました。
山内の観音堂に御座す「香王観音立像」は行基(668年~749年)の作と伝わるので、創建は奈良時代に遡るのかもしれません。
〔山内由緒書より〕
「当寺は推古天皇、御代聖徳太子の創立で行基菩薩が当山に錫を留められ香王観音を彫刻し、仏法結縁の霊場とされた。其の後、弘法大師が留錫され、佛像・教典の名寶を遺された希有の古刹であった。」
平安時代後期の保元二年(1157年)にこの地の領主であった大野対馬守重包により再興とされ、重包を中興開基、賢安上人を中興開山としています。
この地は爾来、甲斐の在庁官人・三枝氏の支配地で、国重要文化財指定の「木造吉祥天及び二天像」は、鎌倉時代の寛喜三年(1231年)に中興三世の良賢を勧進、三枝氏を檀越とし、仏師・蓮慶(運慶の弟子)の作とされています。
坐像の吉祥天は、全国的にもすこぶるめずらしいものです。
永禄十一年の「信玄公祈願先11箇寺」に「大野寺」としてその名がみられ、信玄公の祈願寺の役割を担っていたものとみられます。
御坂の地は、『聖徳太子伝暦』にも「甲斐の黒駒伝承」が記され、当寺にも「甲斐の黒駒」に関する伝承が伝わっているようです。
中世も「御坂牧」「黒駒牧」として軍馬の補給地になっていたとみられ、その点からも戦勝祈願の地として選ばれたのかも知れません。
樹齢900年といわれる杉や樹齢200年の枝垂桜やソメイヨシノが枝を広げて、趣きのある境内。
甲斐百八霊場第40番の札所でもあり、御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。
■ 松本山 大蔵経寺






公式Web
笛吹市石和町松本610
真言宗智山派 御本尊:不動明王
札所:甲斐百八霊場第3番、石和温泉郷七福神(寿老人)
朱印尊格:不動明王 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第3番印判
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第三番」の札所印。左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
奈良時代の養老六年(722年)、法相宗の行基菩薩を開祖として創建と伝わる甲斐有数の古刹。
かつては松本寺と呼ばれた大寺院で、山内に物部神社を鎮守として勧請したといい、弘法大師が不動明王を彫られ納められたという伝承もあるようです。
応安三年(1370年)、足利三代将軍義満公の庶子、観道上人が中興開山として入山の際、義満公が甲斐の守護武田信成公に命じて七堂伽藍を建立。この中興開山の折から武田家祈願寺になりました。
五層の宝塔を建て、大蔵経を奉納したのが寺号の由縁とされます。
永正十三年(1516年)9月、信虎公と駿河勢との「万力の合戦」にて焼亡、その後復興されました。
永禄十一年(1568年)の信玄公の「先勝祈願11箇寺」のひとつで、「大蔵寺」の寺名で記録されています。
当寺には、川中島合戦にあたり信玄公が戦勝祈願をされたという将軍地蔵菩薩像が祀られています。
御本尊の不動明王座像は伝智証大師作とされ、矜羯羅・制多迦両童子を脇侍に力感あふれるお姿です。
庭園・現代仏画の拝観には拝観料が必要ですが、札所の参拝には必要ありません。
背後に大蔵経寺山を背負って落ち着きのよい山内。
甲斐百八霊場、石和温泉郷七福神の札所であり、御朱印は快く授与いただけました。
■ 法性山 玄法院





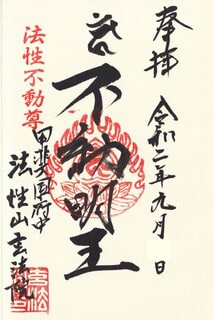
甲府山の手七福神巡礼Web
甲府市天神町2-18
真言宗醍醐派 御本尊:不動明王
札所:山の手七福神めぐり(福禄寿)
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:不動明王 直書(筆書)
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と揮毫と「不動明王」の揮毫。
左上に「法性不動尊」の印判。
左下には「甲斐古府中」と山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。
建久三年(1192年)創立の真言宗醍醐派の修験寺。
寺伝によると、大永年間(1521年~)、信虎公が巨摩郡下黒沢村(高根町)から府中峰本(甲府市相川地区)に移され、信玄公の法名「法性山機山信玄」から山院号を賜り法性山玄法院と称し、武田家三代領主が本尊不動明王に戦勝祈願をした寺とのことです。
「武田家滅亡後は、徳川幕府より現在地の御領を賜り寺を移築し、真言宗醍醐派京都三宝院の末として当山派修験の法流を現在につなげています。」(寺伝)とあり、保守本流?の当山派修験寺であることがわかります。
みずからの法名を賜るというのは、よほど崇敬が篤かった証とも思われ、信玄公の不動明王への信仰の篤さが伺われます。
甲州夢小路の「時の鐘」は、当寺の鐘楼を模し、残されていた写真・鳥瞰図・礎石を基に再現されています。
の外壁といった仕様で、忠実に再現されています。
天神町の住宅街の路地に面しますが、山内は意外に広さがあり、車も停められます。
門柱の寺号標には武田菱と「法性山 玄法院」の刻字。
右手に銘木「玄法院のイチョウ」と稲荷大明神、左手に金毘羅大権現と福禄寿尊が合祀されたお堂と修行大師像。
山梨県立図書館の情報によると、「1533(天文2)年、玄法院の第八代住職が四国讃岐の金毘羅宮にお参りして、その分岐したものを湯村山城の守護神としたと言われる。」とあるので、そちらの金毘羅宮さまとゆかりがあるかもしれません。
狛犬一対、灯籠一対、本堂右手にお前立ちとみられる石造立像の不動明王。
正面扁額は「不動明王」で、開け放たれた堂内には御本尊のお不動さまと護摩壇。いかにも修験寺らしいイメージがあります。
御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受しました。
修験寺は総じて猛々しいイメージがあるのですが、意外と御朱印対応がフレンドリーなお寺さんが多く、こちらでもご親切なご対応をいただきました。
このほか、甲斐市竜地の武田社にも信玄公ゆかりの「武田不動尊」が祀られています。
甲府市元紺屋町の行蔵院の御本尊も「武田不動尊」と称され、御朱印も授与されていますが、こちらは山本勘助とのゆかりが伝えられているので、山本勘助編でご紹介します。
■ 龍本山 松井田院 不動寺






群馬県安中市松井田町松井田987
真言宗豊山派 御本尊:千手観世音菩薩
札所:北関東三十六不動霊場第4番、関東八十八箇所第2番、上州三十三観音霊場第21番、上野之國三十四カ所観音霊場第13番

〔北関東三十六不動霊場の御朱印〕
朱印尊格:不動明王 直書(筆書)
札番:北関東三十六不動霊場第4番
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。
右上に「北関東三十六不動霊場第四番」の札所印。左下には院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔関東八十八箇所の御朱印〕
朱印尊格:千手観音 直書(筆書)
札番:関東八十八箇所第2番
・中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+宝珠)と「千手観音」の揮毫。右上に「関東第二番」の札所印。左上に霊場開創二十周年の記念印。
右下に院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

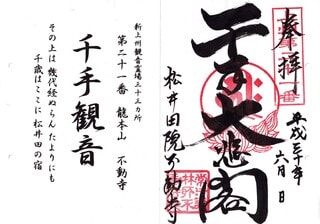
〔上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印書入/専用納経帳)〕
朱印尊格:千手大悲閣 直書(筆書)
札番:上州三十三観音霊場第21番
・中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。
右上に「上州第二十一番」の札所印。
右下に院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用納経帳は、片面に御詠歌が印刷されています。
西毛の名山、妙義山を望む高台に位置し、複数の霊場札所をつとめられる上州の名刹。
複数の霊場ガイドブックに「元亀天正年間に武田信玄公により寺領を賜り」とあり、山内の縁起碑には「元亀・天正年中、武田信玄公不動尊ノ帰依篤く、寺領ヲ賜リ租税ヲ免状シ武田家祈願所ト為ス」と記されています。
また、寺宝として「武田家書状」が所蔵されています。
御本尊は千手観世音菩薩ですが、安中市のWeb情報に「慈猛上人が立ち寄った雷雨の夜、松に大龍が登り、その下に井戸の形の清水が湧いた。そこで不動尊を安置、松井田院と名付けた。松井田の里のいわれという。」とあり、寛元元年(1243年)の慈猛上人による開山時に、すでに地名のいわれとなるような著名な不動明王が祀られていたことがわかります。
慈猛上人は後深草天皇より「留興長老」の号を賜わった高僧で、下野の薬師寺の上座(長老)、下野国司も務められたと伝わります。
当地の城、松井田城は永禄七年(1564年)武田氏の攻勢で開城し、武田氏滅亡までその支配下にありました。
『上野志』(国会図書館DC、コマ番号20/226)に「安中左近将監忠成、騎馬高百十八騎、武田信玄公へ降参。安中の城本領共に甘利左右衛門妹壻に仰せ付けられ候。信州・美濃信玄軍場に詰むるなり。」とあります。
松井田・安中一帯は安中市の領地で、武田氏進出ののちは安中左近将監忠成(景繁)が
信玄公の家臣、甘利左衛門尉(信忠)の妹を娶って武田勢の麾下に入り、信州、美濃方面へ出陣しています。
同寺に伝わる「武田家書状」、あるいは「祈願所」とした日付は定かではありませんが、永禄七年(1564年)以降、松井田・安中周辺は信玄公の支配下にあり、その頃の事柄と考えられます。
江戸時代、十五世秀算僧正は徳川家康公の命により、総本山長谷寺の第四世能化となられ、家光公からも朱印地八十九石余の寺領を拝領したという高い寺格の寺院です。
三門右手の年季入った看板には「北関東三十六不動霊場第四番、上野国観音霊場第十三番」の札所案内。
参道左手の覆堂内に異形の板碑、正面の仁王門(三間一戸切妻造柿葺単層八脚、阿吽二体の仁王像安置)ともに県指定重要文化財です。
仁王門の大棟に三つ置かれた菱紋は武田菱にも見えますが、どうでしょうか。
右手六地蔵の先、参道両側に不動明王三十六童子。階段を昇ると正面が不動堂、左手が本堂です。
本堂は入母屋造銅板葺向拝付で、欄間の龍の彫刻、木鼻の獅子の彫刻ともなかなかの迫力です。
御本尊千手観世音菩薩が御座し、右手の向拝柱に「関東八十八ヵ所霊場第二番」、左手に「上野国順禮札所第十三番」の札所板が掲出されています。
不動堂は入母屋造桟瓦葺向拝付で、大棟、降棟の意匠が見事。向拝欄間の彫刻も手が込んだもの。右手の向拝柱に「北関東三十六不動尊霊場第四番札所」の札所板。
不動堂に御座す不動明王は、鎌倉時代初期、中央仏師の作と推定される精巧なお像で、県重要文化財に指定されています。
御朱印は、北関東三十六不動霊場、関東八十八箇所、上州三十三観音霊場の3種を拝受しています。(上野之國三十四カ所観音については授与不明です。)
メジャー霊場の札所につき、御朱印授与は手慣れたご対応です。
【 毘沙門天 】
毘沙門天は、仏教では天部の仏神で、持国天、増長天、広目天とともに四天王の一尊に数えられます。
四天王は帝釈天に仕え、須弥山の中腹で仏法を守護する役割を担われています。
東方を持国天、南方を増長天、西方を広目天、北方を多聞天(毘沙門天)が守護しています。
単独で祀られることも多く、その場合は毘沙門天と呼ばれ、四天王の一尊や二天門で持国天とともに祀られる場合は多聞天と呼ばれます。
七福神の一尊でもあり、この場合は毘沙門天と呼ばれます。
梵名はヴァイシュラヴァナ。
これは「よく聞く」を意味し、「お釈迦様の説法をもっともよく聞かれた(尊格)」からきているようです。(”多聞天”はここからきているとされる。)
また、クベーラ(インド神話の富と財宝の神)と同体とされ、もともと財宝神の性格をもたれています。
「軍神」という性格は、「多聞天は四天王のリーダー格」「四天王のなかでもっとも強い」という説があり、ここから来ているのかもしれませんが、これは「軍神」の性格が確立されてから後に付会されたものかもしれません。
むしろ、毘沙門天が仕える帝釈天は、戦いの神インドラと同一であり、毘沙門天は夜叉や羅刹といった鬼神を眷属として従えるという立場から、「軍神」のイメージが定着していったのではないでしょうか。
わが国では、信貴山(朝護孫子寺)において聖徳太子が戦勝祈願をされ、毘沙門天王から必勝の秘法を授かり勝利されたという逸話が有名で、以来、毘沙門天=軍神信仰が広まったとされる説があります。
いずれにしても、軍神と財宝神の両面をもたれるすこぶる強力な尊格といえましょう。
戦国武将で毘沙門天信仰の例は少なくないですが、なかでも上杉謙信公が有名で、軍旗にも「毘」の文字をつかわれていました。
信玄公も毘沙門天をふかく信仰されたと伝わります。
「川中島の戦い」は軍神・毘沙門天を信仰する両雄の戦いともいえ、両者譲らぬ激しい戦さとなったこともうなづける感じがします。
信玄公は軍陣の守り本尊として刀八毘沙門天像を信仰されていましたが、この尊像は、現在円光院に所蔵されています。(Vol.3を参照願います。)
また、武田神社内に掲出されている「(躑躅ヶ崎館)東・中曲輪平面想像図」には、館の東北に不動堂と毘沙門堂が掲載され、躑躅ヶ崎館で日頃から両尊の供養がおこなわれていたことがわかります。
信玄公ゆかりの毘沙門天は、ほかにもいくつか伝わります。
■ 徳和山 吉祥寺





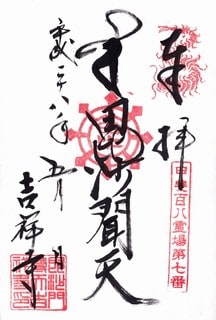
公式Web
山梨市三富徳和2
真言宗智山派 御本尊:毘沙門天
札所:甲斐百八霊場第7番、甲州東郡七福神(毘沙門天)
朱印尊格:毘沙門天 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第7番印判
・中央に札所本尊毘沙門天の御紋印と種子「ベイ」と「毘沙門天」の揮毫。
右上に「大百足」の印。右下に「甲斐百八霊場第七番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
もともと武田氏と毘沙門天のゆかりはあったらしく、武田信光公は承元年間(1207年~1210年)、甲斐源氏守護のため乾徳山のふもとに吉祥寺を建立し、御本尊として毘沙門天を安置されました。
この堂宇は永禄八年(1564年)に信玄公によって再興され、これを示す当時の棟札がいまも寺に保存されていることからも、信玄公の毘沙門天信仰が伺われます。
〔山内掲示/本堂永禄八年再興棟札〕
「大檀越源朝臣晴信奉為武運長久再興之 伏願 家門繁栄武門長久至祝至檮 敬白」
吉祥寺周辺は武田軍の伝令隊としてその名を馳せた「武田百足(むかで)衆」の本拠地で、吉祥寺内陣の欄間には2m以上もある大百足の彫刻があります。
「武田百足衆」を率いた真田兵部丞昌輝は武田二十四将の真田信綱の弟で、武田二十四将に数えられる例もあります。
■ 河浦山 薬王寺




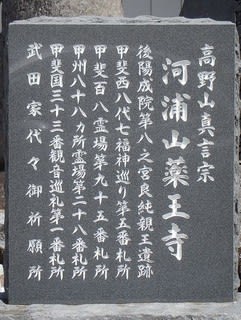


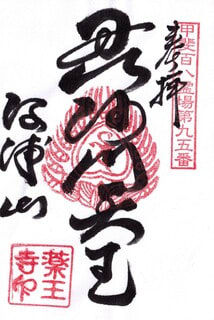


(公社)やまなし観光推進機構Web
市川三郷町上野199
高野山真言宗 御本尊:毘沙門天
札所:甲斐百八霊場第95番、甲斐国三十三番観音札所第1番、甲斐八十八ヶ所霊場第28番、甲斐西八代七福神(恵比寿)
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:毘沙門天王 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第95番
・中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「毘沙門天王」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第九五番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
朱印尊格:十一面観世音菩薩 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第62番
・中央に種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。こちらの札所本尊は十一面観世音菩薩とみられますが、十一面観世音菩薩の種子「キャ」ではありません。
観音霊場発願寺につき、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印をつかわれているのかもしれません。
中央に「十一面観世音」の揮毫。
右上に「甲斐観音第一番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔甲斐西八代七福神(恵比寿)の御朱印〕
朱印尊格:恵比寿大神 書置(筆書)
札番:甲斐西八代七福神第5番(恵比寿)
・中央に恵比寿神ゆかりの持物「鯛」の印と「恵比寿大神」の揮毫。
右上に「甲斐西八代七福神第五番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
天平十八年(746年)、聖武天皇の命により行基菩薩が自ら多聞天像を彫刻し安置したのが始まりとされる古刹。観全僧都の開山とも伝わります。
天長九年(832年)に淳和天皇から、天治元年(1124年)には源義清公からの寺領の寄進の記録が残ります。
中世は武田家から信仰され、とくに信玄公は毘沙門天への帰依篤く、当寺で度々戦勝祈願が行われ、十二天画像や川中島合戦の図などが寄進されています。
御坂山塊が芦川に向けて山裾を落とす複雑な地形に位置し、Pは山内中腹にあるので、表参道から入山するには一旦降りるかたちになります。
複数の札所を兼ねられ、入口に札所を示す石碑があります。
急な階段の上に構える山門は入母屋瓦葺三間一戸の八脚門で風格があります。
めずらしいオハツキイチョウは、国指定の天然記念物に指定されています。
山内左手に甲斐西八代七福神(恵比寿)の御座。
正面の桟瓦葺の建物は、向かって右手が本堂、中央が客殿(八之宮良純親王御座所)、左が庫裡で、入母屋造だと思いますが、客殿は唐破風向拝、庫裡玄関は千鳥破風で棟が連続しており、正確な様式・規模はよくわかりません。
本堂右手のお大師様の前を進むと、観音堂があり、こちらは甲斐国三十三番観音札所第1番の発願所となっています。こちらの札所本尊の十一面観世音菩薩は、もともと町屋にあった大眞寺の御本尊で、明治初期の大眞寺火災ののち、本寺である薬王寺に観音堂を建立し安置された(戦後に再建安置)とのこと。
客殿の上段の間には、八之宮良純親王御座所(御座の間)の一部が保存されています。
親王は、後陽成天皇の第八皇子で京都知恩院の門跡となりましたが、寛永二十年(1643年)故あって甲斐に流され、明歴元年(1655年)から5年間当寺に居住されて後、京に戻られました。
親王が起居されたことからも、寺格の高さが伺われます。
現在、3つの現役札所を兼ねておられ、御朱印は手慣れたご対応にて拝受できます。
南側に隣接して東照宮が鎮座します。
甲斐国の要所、市川郷への東照宮鎮座はいささか不思議な感じもしますが、市川の表門神社は、天正十年(1582年)、家康公甲斐入国の折に本陣が置かれて武運長久を祈願され(御陣場御宮)、慶長十四年(1609年)、徳川幕府により社殿が寄進されているので、そちらとの関連があるのかもしれません。(市川三郷町資料より)
■ 宝塔山 吉祥寺 多聞院






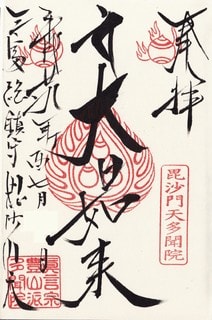


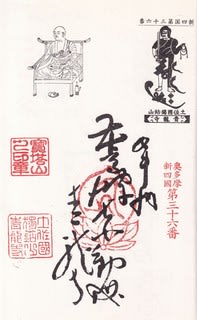
埼玉県所沢市中冨1501
真言宗豊山派 御本尊:金剛界大日如来
札所:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
〔御本尊の御朱印〕
朱印尊格:大日如来 直書(筆書)
・中央に三つの宝珠と火焔を合わせた印。御本尊金剛界大日如来の種子「バン」の種子と「大日如来」の揮毫。
右下に「毘沙門天多門院」の印。左には「三富総鎮守 毘沙門天」の揮毫と寺院印が捺されています。
〔毘沙門天の御朱印〕
朱印尊格:毘沙門天 直書(筆書)
・中央に三つの宝珠と火焔を合わせた印。毘沙門天の種子「ベイ」と「毘沙門天」の揮毫。
右に「武田信玄公守本尊」の印。左には山号・印号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔奥多摩新四国霊場の御朱印〕
朱印尊格:不詳(不動明王) 専用納経帳に捺印
札番:奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第36番
・中央に種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。こちらの札所本尊は不動明王とみられますが、不動明王の種子「カーン/カン」ではありません。五大明王の種子が「キリーク」なので、そちらの御寶印をつかわれているのかもしれません。揮毫(印刷)は不明ですが、「本尊」と「不動」の文字は読み取れます。
左上に御椅子御坐された真如親王様のお大師様の御影。右上に土佐國獨鈷山青龍寺にちなむ御影。右に「奥多摩新四国第三十六番」の札所印。左に多門院の山号印と青龍寺の寺院印が捺されています。
※こちらの札所は当初瑞穂町長岡の開山所内に安置されていましたが、「2013年に多聞院に移管され開眼法要が行なわれた。」との情報があります。(→情報元)
埼玉県所沢市にある多門院には、信玄公ゆかりとされる毘沙門天が祀られています。
この地は江戸時代、川越藩主の柳沢吉保が新田開拓をおこなったところで、吉保は開拓農民の菩提寺多福寺を祈願所として、毘沙門社を建立しました。
寺伝では、毘沙門堂(社)後本尊の毘沙門天は信玄公の守り本尊で、信玄公が戦陣に臨まれるときはいつも兜の中にこの像を納めていたと伝わります。
「信玄公の戦陣守り本尊である毘沙門天像は、甲斐源氏の末裔を称した柳沢吉保の手に渡った」という伝承があり、その伝承ゆかりの御像とみられます。
はじめて参拝したときはこの由来を知らなかったので、境内で武田菱と「信玄公守り本尊」ののぼりを目にしたときは正直おどろきました。(武田軍は吉見の松山城を落としていますが、所沢までは侵攻していないはず。だからこの地に信玄公ゆかりの寺院があるのはナゾでした。)
境内で↑の寺伝を確認、川越藩主の柳沢吉保ゆかりということで納得がいきました。
このほか、塩山(甲州市)の熊野神社には、信玄公の寄進とされる「紙本著色刀八毘沙門天像図」が伝わり、これは信玄公が躑躅ヶ崎館で崇拝されていたものとされています。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 草津温泉周辺の御朱印
2020/05/16 UP
すこし追加&追記します。(08.~)
草津温泉からの帰路に、国道406号・須賀尾峠・浅間隠温泉郷・倉渕経由で高崎に抜けるルートがあり、御朱印を授与される寺院がいくつかあります。
このルートは榛名町室田交差点で榛名神社からの帰路と合流しますので、国道406号の室田交差点までを「草津温泉編」、室田交差点から高崎寄りを「伊香保温泉編」として構成しなおします。
国道406号「室田」交差点から高崎寄りの寺社については→こちら(伊香保温泉編)をご覧ください。
また、渋川方面からの国道353号「大戸口」交差点までの寺社については、→こちら(四万温泉編)をご覧ください。
御朱印情報を得ている東吾妻町の寺院を追加します。
また、このエリアは真田氏、海野氏など、武田信玄公とゆかりのふかい武家の本拠地なので、信玄公にちなむ事跡などを補強してリニューアルします。
(→ 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印)




---------------------------------
2017/10/09 UP
先日、ふるさと納税でゲットした地域券があったので、ひさびさに草津&四万に泊まってきました。
御朱印もいただいてきましたので、草津&四万周辺でいただける御朱印をご紹介します。
(非札所の寺院も多く、現時点でも拝受できるかは定かではありません。)
吾妻エリアには吾妻三十三番観音霊場や三原(谷)三十四所観音札所などの古い霊場はあるものの、それらの札所の多くは廃寺や山中のお堂で、この霊場でいただける御朱印はほとんどありません。
複数の現役霊場が重複する県央(前橋・高崎)や東毛(伊勢崎・桐生・太田・館林など)エリアとくらべると、授与所はどうしても少なくなります。
それでも、神社も含めるとそれなりの数は揃いますので、草津のアプローチベースとなる長野原町、同じく四万の中之条町も併せてご紹介してみます。
1発目は草津温泉です。
第2回目(四万温泉編)は、→こちら
第3回目(伊香保温泉編)は、→こちら
【草津温泉周辺で拝受できる御朱印】
01.大洞山 雲林寺
公式Web





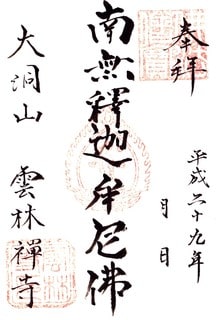
長野原町長野原73
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:三原郷(谷)三十四観音霊場第1番(作道観音堂)
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛 直書(筆書)
札番:なし(御本尊の御朱印)
・中央に御本尊釈迦牟尼佛の種子「バク」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。
左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
※三原(谷)三十四所観音の御朱印は授与されていないようです。
長野原町役場に隣接する曹洞宗の古刹で、信濃国小県郡~吾妻の豪族、海野氏ゆかりの寺です。
弘長三年(1263年)、臨済宗妙心寺派の龍幡和尚が創建されました。
創建時は大字長野原字火打花、その後貝瀬に移り、永禄二年(1559年)、海野幸光が開基となって現在地に伽藍を再建、後閑(安中市上後閑)の長源寺九世為景清春が入られ大洞山雲林寺として開創されました。
長源寺の末寺となっていますが、これは長源寺の為景清春が当山の他、宝昌寺(高崎市)、長伝寺(安中市)、桂霊寺(佐久)を開かれ、長源寺との本末関係が継承されているためと思われます。
当寺の公式Webには、「海野幸光は、西吾妻地方の吾妻川左岸に勢力を持ち、戦国時代に羽根尾城に拠った羽尾景幸の孫である。」とあります。
海野氏、羽尾氏の家系はすこぶる錯綜していて、辿るのがむずかしいですが、Web情報を総合すると、羽尾景幸の子が羽尾幸世で、羽尾幸世の子が、長男幸全、次男幸光、三男輝幸、四男幸昌と続くようです。(これは「幸光が景幸の孫」という寺伝に符合します。なお、海野幸光は羽尾景幸の子で羽尾幸世の弟という説もありますが、幸光・輝幸は兄弟という点は一致しています。)
複雑な経緯があって、次男幸光、三男輝幸は海野姓を名乗って”海野兄弟”として知られています。
幸光は仏教、とくに修験道への帰依が深かったと伝わります。
戦国期、この地は甲斐から侵攻した武田勢と関東管領家の上州の山内上杉勢の勢力がぶつかるところで、武田方に真田幸隆、鎌原氏、上杉方に岩櫃城の斎藤氏が立って、そのはざまで羽尾氏は複雑な動きをとったものとみられます。
真田氏、鎌原氏、羽尾氏ともに滋野姓の同族なので、その駆け引きは同族ゆえよけいに複雑化したのでは。
海野兄弟は、永禄元年(1558年)の頃より岩櫃城主斎藤憲広に仕えて岩櫃城内に居住。
永禄六年(1563年)、真田氏の侵攻による斎藤氏滅亡後は武田方に属し、永禄九年(1566年)岩櫃城城代となり、真田幸隆の配下に入っていたとされます。
その後、海野兄弟は真田家の家督を継いだ真田昌幸に属し、幸光は岩櫃城に拠ったとされます。
天正九年(1581年)、幸光は北条氏に通じたとの疑いを受け、真田、鎌原、湯原氏の軍勢に攻められ、奮戦むなしく討ち死にしたと伝わります。齢75歳。
墓所は旧領羽根尾の北小滝にあります。
国道145号上州街道に面して参道入口。
石造冠木門。寺号標と右に観世音の石碑、左にも石碑があります(揮毫不明)。
うっそうと茂る杉木立の下に、本堂につづく階段が伸び、脇には地蔵尊、観音様などの露仏が御座します。
階段を登り切ると右手に鐘楼、宝篋印塔と六地蔵。左手本堂前の老松がいいアクセント。
入母屋造桟瓦葺の本堂で、左手に寄せて桟唐戸。その上に寺号「雲林禅寺」の扁額。
簡素ながら端正な格子窓が意匠的に効いた、禅寺らしい建築です。
本堂と相対して観音堂。三原郷(谷)三十四観音霊場第1番、打ち始めの「作道観音堂」です。
(おそらく)入母屋造妻入り銅板葺。桟戸木連格子、木鼻に獅子、梁間に龍の彫刻、向拝脇に花頭窓。向拝柱には御詠歌の木板。
さすがに発願所。屋根の照りが強く、勢いを感じる仏堂です。
御朱印は庫裡にて尊格御本尊のものを拝受しました。
ただし、現役札所ではないので、御朱印拝受はタイミング次第かと思います。
02.龍燈山 常林寺




長野原町応桑547
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:三原郷(谷)三十四観音霊場第6番(穴谷観音堂)
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛 直書(筆書)
札番:なし(御本尊の御朱印)
・中央に三寶印の捺印と御本尊「南無釋迦牟尼佛」の揮毫がされています。
また聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印と穴谷観音の印判も捺されているので、三原(谷)三十四所観音札所第6番札所の性格も帯びている御朱印と思われます。
草津とは吾妻川の反対側になりますが、こちらも長野原町のお寺。
滋野氏族鎌原氏の菩提寺で、予想以上に立派な境内と伽藍を構えていました。
鎌原氏は滋野氏族で、ふるくから三原庄に拠り勢力を張りました。
文明年間(1469年~1486年)頃から上野平井城の関東管領山内上杉氏ないし、上杉方の岩櫃城主斎藤氏の支配下にあったと伝わります。
甲斐の武田信玄の信濃侵攻がはじまると、永禄三年(1560年)、鎌原幸重・重澄父子は、真田幸隆の斡旋で信玄に謁見し、斎藤氏を離れて武田方に加わりました。
永禄五年(1562年)斎藤氏と羽尾氏(滋野一族)の攻撃を受けた鎌原氏は、鎌原を保てず佐久へ退去したものの、武田氏・真田氏の支援を得て鎌原領を奪還しました。
永禄六年(1563年)、真田氏は斎藤氏拠る岩櫃城を攻め、難攻不落といわれた岩櫃城をついに落としました。
吾妻郡は真田幸隆の支配下に入り、真田氏の与力として活躍した鎌原氏は岩櫃城代に任ぜられたといいます。
以降、武田・真田軍の将として、武田軍の戦いに臨み、鎌原筑前守は「長篠の戦い」で戦死しています。
武田氏滅亡後も鎌原氏は真田氏に属し、沼田城に入って家老職を務めましたが、沼田真田家の断絶を受けて松代真田家に仕え、以降松代藩士として続いています。
駐車場は庫裡の横にあるので、参道起点は本堂の下に一旦降りていくことになります。
参道階段のぼり口には破風と鬼瓦の遺構。その右手には石造の観音様が御座し、「三原谷三十四番霊場 第六番穴谷観音」の石碑があります。
一面二臂の菩薩形。左手に未開敷蓮華を持たれ、頭髪部の正面に化仏を置かれた蓮華座の結跏趺坐像で、石造の聖観世音菩薩の坐像と思われます。
巨石を両断し刳り抜いたなかに御座される、特徴的なおすがたです。
石段をのぼりきると本堂前。宝篋印塔一対、石灯籠一対。
本堂は入母屋造平入り、向拝格子戸の上に縦書きの寺号扁額。軒下に平三斗と雲斗の組み合わせ。妻部は経の巻獅子口、三ツ鼻懸魚に複数の彫刻を備えています。
禅宗の名刹らしい堂々たる本堂です。
こちらも三原(谷)三十四所観音札所の札所(第6番)で、参道脇に札所本尊の穴谷観音が御座しますが、観音霊場単体の御朱印は授与されていない模様。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
03.鎌原観音堂




嬬恋村鎌原492
曹洞宗(現) 御本尊:十一面観世音菩薩
札所:三原郷(谷)三十四観音霊場第8番
朱印尊格:鎌原観音 直書(筆書)
札番:三原郷(谷)三十四観音霊場第8番印判
・御朱印尊格は御本尊の十一面観世音菩薩。種子「キャ」の御寶印と「鎌原観音」の揮毫に三原(谷)三十四所観音札所の札所印が捺され、観音霊場の御朱印となっています。
この御朱印は三原(谷)三十四所観音札所唯一のものである可能性があります。
草津からは少し離れた嬬恋村のお寺ですが、こちらもご紹介。
天明三年(1783年)の、浅間山(天明の)大噴火(浅間焼け)による土石なだれの際、境内にいた村民を救われた観音さまとして広く信仰を集めています。
爾来、信州善光寺による追善法要が営まれてきたようですが、現在は応桑の常林寺の管理下にあるようです。
鎌原観音堂の北方約200mのところに土石なだれで埋没した延命寺がありました。
このお寺のものとみられる石碑が東吾妻町矢倉の吾妻川の河原で発見され、鎌原観音堂そばに安置されています。
この地から東吾妻町矢倉までは約25㎞。これだけの距離を重い石碑が押し流されたわけで、土石なだれのすさまじさがうかがえます。
石碑には、「浅間山」と記され、延命寺は鎌原村に鎮座されていた浅間大明神の別当と推測されています。
また、鎌原観音堂を旧延命寺の一部とみる説もあります。
三原郷(谷)三十四観音霊場の開創は江戸時代初期とみられています。
延命寺はこの地域屈指の寺院であったらしいので、延命寺と鎌原観音堂の関係がうすければ、延命寺に観音堂を設けて札所とするのが自然です。
しかし、鎌原エリアでは鎌原観音堂のみ札所となっているようなので、鎌原観音堂は延命寺の観音堂であった、という可能性もあるのかもしれません。
観音堂は寄棟造ないし方形造茅葺。向拝部三間のうち中央開放で上部に「かんのんさま」の扁額が掲げられています。
飾り気のすくない仏堂ですが、壁面にはわらじや奉納額、写真などが掲げられ、信仰の篤さが感じられます。
三原(谷)三十四所観音札所の札所(第8番)で、札所板も掲げられています。
嬬恋郷土資料館に隣接し観光客の来訪もあるようで、観音堂右手に授与所があるので御朱印はいただきやすいです。
04.草津山 常楽院 光泉寺






草津町草津442-1
真言宗豊山派 御本尊:薬師如来
札所:関東九十一薬師霊場第44番
朱印尊格:薬師如来 直書(筆書)
札番:なし(御本尊の御朱印)
・関東九十一薬師霊場で申告した御朱印の尊格は御本尊(札所本尊)の薬師如来で、霊場無申告でも同様と思われます。
薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「薬師如来」の揮毫、右上には「日本三薬師」*の印判が捺されています。
*)これは「日本三大温泉薬師」のことだと思われます。あとひとつは有馬の温泉寺ですが、もうひとつは明確に定まっていないようで、光泉寺の公式Webには山中の湯、城崎の湯、道後の湯のいずれかのお薬師様ではないかとの旨の記述があります。
(「日本三大薬湯」(有馬温泉、草津温泉、松之山温泉)にちなむお薬師様だとしたら、松之山温泉の薬師堂でしっくりくるかもしれません。)
吾妻エリアではめずらしい真言宗のお寺で、関東九十一薬師霊場第44番の札所でもあります。
養老五年(721年)行基による開基と伝わり、正治二年(1200年)白根明神の別当寺として草津の領主湯本氏が再建、僧職は鎌倉幕府から地頭職を賜い白根庄の領有を許されていたともされる草津温泉の保守本流的なお寺。
旧郷社、白根神社の別当寺であったことからも、草津温泉における重要なポジションがうかがわれます。
湯本氏はこの地の名門で、木曾義仲に仕え、のちに建久四年(1193年)、源頼朝公が浅間山麓で巻狩りを行った際に案内役となり、湯本の姓と三日月の家紋、そして草津の支配を認められたといいます。
頼朝公の浅間巻狩りは草津温泉の開湯伝承にも数えられますから、湯本氏は草津の開湯にまで遡る古い家柄とみることができます。


〔白旗源泉説明板〕
建久四年(1193年)鎌倉将軍頼朝公が浅間山六里ヶ原の巻狩の折、この草津まで騎馬を進めあれはてた源泉地を改修しみずから入浴されたと伝へられる。以来この湯を御座の湯と呼び、その後いつの頃からか祠を建てて頼朝公を祀った。現在の頼朝宮は天明二年(1782年)八月に改築されたもので、草津温泉伝承(光泉寺蔵温泉奇効記)を今に伝え、草津温泉の入浴客の深い信仰をあつめてきた。
明治二十年、白旗の湯と改称されたが、旧源泉は、この湯畑に沈んでいる小さな湯枠の中と考えられる。草津温泉の開湯伝承につらなる歴史的遺跡である。
-----------------------------------
湯本氏が歴史上活躍するのは戦国時代です。
永禄六年(1563年)、岩櫃城に拠る上杉方の斎藤氏を真田氏が攻め落としましたが、その際、湯本善太夫・三郎兵衛門は真田方につき、勝ち戦の恩賞として草津谷の領有を安堵されたといいます。
湯本善太夫は真田氏同様、甲斐・武田軍の与力となり各地を転戦、長篠の戦いで討死したといいます。
以降、天和元年(1681年)草津谷が天領となるまでこの地を領したとみられています。
湯本氏は真田沼田藩の家老であったとされますが、草津谷が天領となったのは延宝八年(1680年)、真田沼田藩の改易・天領化を受けてとみられます。




湯畑、白旗源泉のすぐ横から山手に登る階段が参道で、観光客も多く入り込んでいます。
階段をのぼると山門。三間一戸の単層、金属葺木部朱塗りで仁王尊が御座す仁王門です。
本堂前向かって右手に奥まって、「遅咲き如来」が御座す釈迦堂。
元禄十六年(1703年)、江戸の医師外嶋玄賀宗静の発願、草津村湯本弥五右衛門が施主となって建立。志賀の夢告にもとづき、桁行二間、梁間二間の四間藁葺で寄棟造。
木部朱塗り、屋根に鬼瓦、藁葺の唐破風向拝を擁し、屋根は起り気味で独特の形状です。
扁額は「釋迦堂」。多彩な枓栱、海老虹梁、木鼻の獅子、蟇股部の彫刻、左右の花頭窓など、意匠的にも見どころがあります。
釈迦堂に御座す釈迦如来は、「遅咲き如来」として知られ、元禄時代東大寺公慶上人の御作です。
本堂は入母屋造金属板葺照り屋根。向拝付き木部朱塗り。扁額は山号「草津山」。
御本尊は薬師如来です。
境内には温泉の守護神「湯善堂」、湯浴み弁財天、湯泉観音、初代熱の湯湯長野島小八郎の碑など、温泉にかかわる尊格や碑が建立されています。
〔湯浴み弁財天略記(境内掲示)〕
養老年間(717年~724年)行基菩薩はこの地にたち眼下に光る泉を見出しそれがただの泉でなく万病にきく温泉であることを喜び薬師如来をまつり光泉寺を開く以来泉は人々の病をいやす慈悲の泉となり今日の草津温泉の源となった
この池はそれにちなみ「慈悲の泉」となずけられ名湯草津温泉に浴し身も心も清浄になった喜びと感謝の姿をあらわす湯浴み弁財天をおまつりした
-----------------------------------
境内左手の趣ある庫裡が授与所です。
御朱印帳も頒布されていますが、御朱印帳を持っていない参拝客には書置御朱印が授与されているようです。
参拝客の多い観光地のお寺にもかかわらず、お寺さんの対応は丁寧なものでした。
05.妙立山 日晃寺



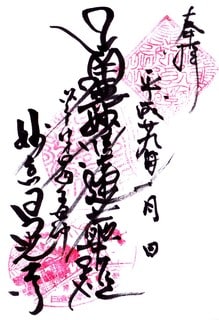
草津町草津540
日蓮宗
御首題
安政四年(1857年)草津祖師堂として創建、昭和3年に日蓮宗草津教会に改称し、昭和21年に身延山の許可を得て妙立山日晃寺(正規の日蓮宗寺院)に昇格したとされる日蓮宗のお寺。
草津温泉の北東に位置するため、温泉街の鬼門鎮守として信仰されていたようです。
吾妻エリアに日蓮宗の寺院は少なく、貴重な御首題を拝受できます。
〔境内の掲示〕
当山わ通稱祖師堂と稱す 延享三年(1747年)一宇建立記念供養碑あり降って弘化年間(1845年~1848年)一堂建立す 草津町鬼門除の祖師として町民の信仰の中心なり 大正年間身延山説教所となり又草津教会を経て昭和二十二年日晃寺と公稱す
-----------------------------------
大阪屋旅館の横手の道を登った桐島屋旅館の手前に参道の階段があります。この周辺に共同浴場はないので、温泉マニアからするとブラインド的な立地です。
参道入口にお題目塔。石段両脇に2つの寺号標はめずらしいと思います。
石段正面に本堂。
本堂の全容が掴めず、しかも庫裡とつながっているので詳細不明ですが、身舎ベースで桁行三間向拝流れ屋根付一間、寄棟造平入りではないかと。
身舎の規模のわりに向拝屋根のせり出しが大きく、雨雪の多い草津の気候を配慮したつくりにも思えました。
ブラインド的立地ながら参拝客は少なくないようで、御首題も手慣れた感じの授与でした。
日蓮宗なので御首題帳にいただきましたが、他宗まじりの御朱印帳の場合、「妙法」となるのか、はたまた授与いただけないのかは不明です。
06.白根神社



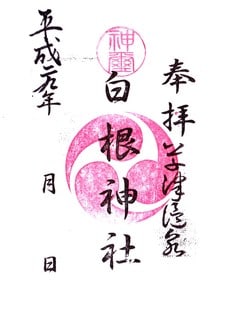
草津町草津538
御祭神:日本武尊
旧社格:郷社
旧別当:光泉寺
授与所:参道階段左手前の蕎麦屋「松美」
朱印揮毫:白根神社 印判
神社御朱印です。
温泉街からだと関の湯の前をさらに下っていくと左手に参道入口があります。
急な階段を登っていくと思いがけず広い境内と立派な社殿にびっくり。
氏子をもたれているかはわかりませんが、旧郷社と社格は高く、鎮守社であればおそらく範囲は草津温泉に留まらないかと思われます。
祭神は日本武尊。白根山を祀る神社で、白根山上に鎮座する本社の遥拝所が明治六年、郷社に列格した際に温泉街を見下ろすこの地に移られたようです。
社頭右手に「(郷社)白根神社」の社号標。その先に総丸材の石造神明系鳥居。
石段をのぼりきると左手に手水舎。その先に両脇に石灯籠が並ぶ参道。
その先に石造明神鳥居で、「白根大明神」の扁額が掲げられています。
さらにその先に狛犬一対。向かって右が「子取り」、左が「玉取り」で、端正な仕上がりです。
拝殿は石積みの上に入母屋造平入りで銅板葺向拝付き。拝殿の扁額は社号「白根神社」。
積雪地らしくがっしりとした向拝。巴紋付きの白地の拝殿幕が厳かな雰囲気を醸し出しています。
うかつにも見逃しましたが、境内には古い共同浴場「鷲乃湯」の由来などが記されている碑があるそうです。


参道階段左手奥には、諏訪大社上社草津白根分社と沼神社が鎮座しています。
御朱印は参道階段左手前の蕎麦屋「松美」にて拝受できます。
御朱印帳に捺していただく印判タイプで、書置があるかは不明なので、御朱印帳持参が確実かと思います。
07.草津穴守稲荷神社
本社の公式Web
草津町西ノ河原公園
御祭神:豊受姫命
授与所:確定情報ではないですが、白根神社参道階段左手前の蕎麦屋「松美」にて拝受できる可能性があります。
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
明治四十年ごろ、東京の山崎染物店の主人が草津へ湯治に通い、病気平癒の記念に常々信仰していた羽田の穴守稲荷をこの場所に分霊し勧請したそうです。
平成13年に草津町内有志により改築されています。
羽田の穴守稲荷と同様、お砂「招福の砂」をいただけるようです。
08.密岩神社



東吾妻町大字郷原1126
御祭神:密岩権現?
授与所:東吾妻町観光協会(JR群馬原町駅構内)か平沢登山口観光案内所
※参拝済ですが、御朱印は未拝受です。上記授与所で、密岩神社、金剛院(観音山不動)、岩櫃城の御城印の3点セットを授与いただけます。
→案内情報
古来よりランドマーク的な岩山は修験の聖地となることが多いですが、上州吾妻の名山、岩櫃山も例外ではありません。
また、この地には上州屈指の堅城、岩櫃城が築かれ、こちらも神仏とのゆかりがあります。
永禄六年(1563年)甲斐・武田方の真田幸隆は、岩櫃城に拠り上杉の麾下にあった斎藤基国を攻め、落城させました。
このとき身ごもっていた基国の奥方は基国とちりぢりになり、岩櫃山の洞穴で子を産み落とし育てました。
奥方は、わが子を里人に託し、夫基国を求めて旅に出ましたが基国と巡り会うこと叶わず、帰り着いた岩櫃山の洞穴の中で落命しました。
すると一筋の煙が立ちのぼり観音様のお姿が現れるとともに、奥方の屍は跡形もなく消え去りました。
奥方の不運を哀れんだ里人たちは、密岩権現として祀り手厚くその霊を慰めました。
奥宮とされるもともとのお社は岩櫃山の中腹にありますが、参道は難路で現在は立ち入り禁止です。
古来、密岩神社を崇敬してきた古屋集落の方々により平成23年(2011年)里宮が設けられ遷座されました。
里宮の地は、岩櫃山が前面に広がる眺望の地で、東吾妻町はパワースポットとしてPRを進めています。
09.瀧峩山 金剛院(観音山不動)
東吾妻町
授与所:東吾妻町観光協会(JR群馬原町駅構内)か平沢登山口観光案内所
※未参拝です。参拝次第、追記します。上記授与所で、密岩神社、金剛院(観音山不動)、岩櫃城の御城印の3点セットを授与いただけます。
→案内情報
岩櫃山の群馬原町寄りにある柳沢城跡(岩櫃城の支城)の下、不動滝のよこにある観音山 不動堂を指しているようで、修験系の寺院とみられます。
1.大洞山 雲林寺を開基した海野(羽尾)幸光は、修験とのかかわりもあったとみられているので、ゆかりの寺院かもしれません。
岩櫃城の鬼門鎮守として建てられたという説もあるようです。
〔 岩櫃城について 〕
古来、この地は吾妻(あがつま)氏の本拠で、岩櫃に拠ったのは、藤原氏秀郷流の吾妻斎藤氏とされます。関東管領・山内上杉家の配下にあり、同族の大野氏とともに吾妻郡に勢力を張りました。
戦国時代の当主は岩櫃城主、斎藤憲広で、郡西の羽尾氏、鎌原氏と領地を巡る駆け引きを繰り返しました。
羽尾氏、鎌原氏ともに信濃の滋野一族の流れで、おおむね羽尾氏は斎藤氏寄り(上杉方)、鎌原氏は真田氏寄り(武田方)であったとみられています。
永禄六年(1563年)、岩櫃城は真田・鎌原勢の攻勢を受けて落城。、城主斎藤憲広は越後(ないし上野)に落ちのびたとされます。
岩櫃城の支城である嵩山城には憲広の子憲宗と弟虎城丸が残り抵抗をつづけましたが、永禄八年(1565年)に攻められて落城。
ながらく上杉方として吾妻に勢力を張った斎藤氏はここに滅亡しました。
以降、岩櫃城は真田氏の支配下に入り、武田氏の版図に組み込まれます。
天正十年(1582年)、織田・徳川軍の甲斐侵攻を受けて劣勢となった主家の武田勝頼を真田昌幸は岩櫃城へ迎え入れ武田家の再興を図ろうとしましたが、これはかなわず武田家は滅亡しました。
その後、岩櫃城は真田信之の支配下に入り、慶長十九年(1614年)に破却されました。
要害の地に建つ典型的な山城で、脚光を浴びたのも戦国時代。
武田家や真田家ゆかりの逸話をもち、戦国武将ファンには見逃せない城ではないでしょうか。
10.(岩下)菅原神社




東吾妻町大字岩下1582
御祭神:菅原道真公
授与所:境内社務所
朱印揮毫:菅原神社 直書(筆書)
由緒などはよくわかりませんが、しっとり落ち着いた神社で、ご神職がいらっしゃれば御朱印を拝受できます。
参拝は木造の明神鳥居(二の鳥居)からとなりました。灯籠一対、狛犬一対。
石段をのぼると三の鳥居で木造の明神鳥居です。拝殿のすぐ下に木造の冠木門。
写真の構図が拙く、いまひとつよくわからないのですが、桁行三間の入母屋造妻入り銅板葺唐破風向拝付きではないかと思います。
向拝梁木鼻は正面獅子、側面貘。梁に雲形の彫刻、梁上に龍、唐破風拝飾に朱雀とみられる彫刻が施されています。
唐破風の鬼板も見事なものです。
向かって右手の神楽殿方向には、千鳥破風が設けられています。
つまり、入母屋の妻入り方向に唐破風の拝殿、平入り方向に拝殿と45度の角度をもって千鳥破風が設けられているという構図です。
この千鳥破風は入母屋破風に近いほど規模が大きく、梅紋入りの鬼板と破風拝飾り、懸魚、破風尻飾りと数々の装飾が施されています。
神楽殿の基礎は拝殿よりむしろ高く、入母屋造銅板葺妻入りで縁高欄をまわしています。
当社は「太々神楽」で有名です。その関係もあって、神楽殿向きに破風を設ける必要があったのかもしれません。
-----------------------------------------
以降は、国道406号(草津街道・信州街道)沿いの寺社のご案内になります。
草津街道(信州街道)は、中山道の高崎宿から分岐し、神山宿、室田宿、三ノ倉宿、大戸宿、本宿、須賀尾宿、長野原宿を経て草津温泉に至る道筋で、中山道ルートにくらべて距離が短いので、北信濃諸藩と江戸の往来や草津温泉への湯治などに多く利用されました。
北信濃、とくに小布施や須坂は菜種油の量産地で、この輸送は主に草津街道(信州街道)経由だったため、この道は「油街道」とも呼ばれ、沿道の宿場町はたいそう栄えたそうです。
東吾妻町大戸には大戸関所があり、現在も関所跡が残ります。
このそばには、大戸の関所を破ったかどで処刑された国定忠治刑死場跡があり、勝負運や脳卒中除けに霊験あらたかといわれる忠治地蔵尊が祀られています。御朱印は授与されていないようです。


【写真 上(左)】 大戸関所跡
【写真 下(右)】 忠治地蔵尊
〔大戸関所跡の説明板〕
大戸関所は、信州街道の要点をおさえる重要な関所で、近世初頭の寛永八年(1632年)に設置された。信州街道は草津温泉を初めとする湯治客。善光寺参り、北信濃の三侯の廻米や武家商人の荷物、各地の産物の輸送路として、中山道を凌ぐ程の活気を呈したともいわれ、江戸と信濃を結ぶ最短距離として重要な街道であった。別名信州道、草津道、善光寺道、大戸廻りとも呼ばれていた。(中略)嘉永三年(1850)年に関所破りの罪を受け侠客国定忠治はこの地で処刑された。映画演劇や講談浪曲でも知られる處である。
-----------------------------------
11.華庭山 天樹院 大運寺




東吾妻町大戸371
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:南無阿弥陀佛 印判
札番:なし(御本尊の御朱印)
・中央に三寶印と六字御名号「南無阿弥陀佛」の印判。
左に山号・寺号と寺院印が捺されています。
榛名の西麓にある浄土宗の名刹。
南北朝時代の興国年間(1340年~1346年)、宝誉上人が京から恵心僧都御作の阿弥陀仏を背負って来られ、大戸村寺原に堂宇を創立、「浄土布教の地」として信者を勧請されたのが開山と伝わります。
天正年間(1573年~1593年)に当地に遷り、大戸・本宿・萩生の三村を檀徒としています。
御本尊は宝冠を戴いた木彫座像で「鎌倉時代の仏像の特徴とされる鋭い衣紋の線が何ともいえず美しいもの」とのことです。(山内掲示より)
「大運寺の本尊」として町指定重要文化財に指定されています。
大運寺は桜の名所として知られており、とくに山門手前の古木のシダレザクラは有名です。
参道入口の総門は、切妻造三間一戸桟瓦葺の四脚の単層門で、薬医門や三棟門のように左右の門に屋根がかかっています。(木戸はないが薬医門の一種か?) 本柱に寺号板。
山門は三門一戸の桟瓦葺、一層に桟瓦葺の屋根を配する堂々たる二重門。
木部朱塗りの華麗な意匠。二層中央の拝部に山号「華庭山」の扁額を掲げています。
さらに石段をのぼると本堂。
桁行八間ほど、入母屋造桟瓦葺唐破風向拝付き。
向拝梁木鼻は正面が獅子、側面が貘。梁上に見事な龍の彫刻。海老虹梁。格子天井。
桟唐戸上桟木連格子窓下桟入子板、長押部に彫刻。上部に寺号「大運寺」の扁額。
破風拝に彫刻、獅子口に経の巻三個と紋章。
規模はさほどではないですが、しっとりと落ち着いたイメージです。
お伺いしたときは丁度法要が始まるところでしたが、「はんこの御朱印紙でよければ」とのお言葉をいただいたので、ご厚意に甘えて拝受しました。
12.諏訪山 東善寺
公式Web




高崎市倉渕町権田169
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
朱印尊格:釋迦牟尼佛 / 英豪大器 直書(筆書)
札番:なし(御本尊・英豪大器の御朱印)
〔御本尊の御朱印〕

・中央に三寶印と御本尊「釋迦牟尼佛」の揮毫。
右上に山号印。左上に小栗上野介忠順のお姿印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔「英豪大器」の御朱印〕

・中央に三寶印と「英豪大器」の揮毫。
右上に小栗上野介●●の揮毫。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
「英豪」とは英雄豪傑、「大器」とは並みはずれて優れた器量を備えた人物をあらわすので、小栗上野介の人となりを示す揮毫かと思われます。
(通常は御本尊の御朱印のみのようです。「英豪大器」の御朱印も所望すると、寺庭さま?は少しく驚かれたご様子でしたが、ネットで見た旨お話しすると納得されておられました。この御朱印は書き手(ご住職)がご不在だと書けないとの由。)
幕末の名奉行、小栗上野介忠順(ただまさ)ゆかりの曹洞宗寺院。
寺伝によると、開創は寛永十年(1633年)。宝永元年(1704年)に権田村が小栗家の知行地となり小栗家との縁が始まりました。
開山は円室存察大和尚、開基は洞庵首座、中興開基は高屋寺殿永山良傑居士(小栗政信公・小栗家五代)と伝わります。
小栗上野介は文政十年(1827年)に生まれ、三河小栗氏第十二代当主で二千七百石の旗本。
攘夷論が主流の幕府内で一貫して開国思想を深め、万延元年(1860年)、遣米使節目付役として日米修好通商条約批准のため米艦ポーハタン号で渡米し、世界一周して帰国。
その後数々の奉行を務め、海外の技術を積極的にとり入れて、幕府の財政再建、洋式軍の整備、横須賀製鉄所(後の横須賀海軍工廠)の建設、仏語学校の建設など数多の事績を残しました。
高崎市倉渕支所の史料には、「『明治の近代化は小栗の敷いたレールの上になされた』といわれるほどの、大きな業績」と記されています。
薩長軍の東征に際して主戦論を唱えるも容れられず、慶応四年(1868年)3月に罷免され領地である上野国権田村の当寺に隠遁。
同年閏4月、東山道総督が追捕し、水沼村鳥川原にて斬首されました。
享年42歳。墓所は養子の又一、殉職の家臣の墓とともに当寺にあります。
落命の地、水沼川原には顕彰慰霊碑が建立されています。
参拝者が多いらしく広い駐車場。
山内入口左右には「渓声便是広長舌」「山色豈非清浄身」(けいせいすなわちこれこうちょうぜつ さんしきあにしょうじょうしんにあらざらんや)の禅語(中国北宋時代の詩人蘇東坡の詩)の石標が掲げられています。
その奥に寺号標。
坂をのぼって手前に庫裡。茶菓子を出されており庭で楽しむことができます。
小栗公遺品館もあり、遺品館・庫裡・本堂の展示資料を有料で拝観できます。
奥に本堂、小栗公と公の朋友栗本鋤雲の銅像、六地蔵、小栗公の墓所とつづきます。
本堂は入母屋造銅板葺正面向拝付き。虹梁に板蟇股、梁両端に斗栱。がっしりとした海老虹梁。扁額は寺号「東善寺」。
桟唐戸上・中桟格子窓下桟入子板。長押部の雲形木板に唐草文様彫刻。
妻部は鬼板、懸魚、狐格子を備え、均整のとれた禅寺らしい本堂です。
13.蓮華院(水沼観音)





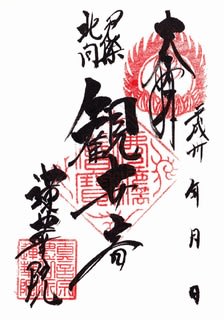
高崎市倉渕町水沼1303
真言宗豊山派 観音堂御本尊:千手観世音菩薩
朱印尊格:観世音 書置(筆書)
札番:なし(観音様の御朱印)
※本堂御本尊の御朱印は不授与とのこと。
・中央に三寶印と「(北向厄除)観世音」の揮毫。
右上に火焔宝珠の印。左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。
名湯で知られるくらぶち相間川温泉のそばにある観音様で知られる真言宗寺院。
山内に由緒書はなく、Web情報もほとんどとれませんが、高崎新聞の記事によると、「本尊の千手観音像は自覚大師(ママ 慈覚大師?)の手によるといわれる秘仏です。節分の日には厄落としの人で賑わいます。」とのこと。
石段の参道の先に朱色の山門とそのおくに観音堂。
山門は切妻造金属板葺の四脚門で、門柱に寺号標。
さらにのぼって観音堂正面、右手に向かい正面が本堂です。
本堂は、入母屋造桟瓦葺向拝付きの渋い意匠、これに対して観音堂は朱塗りの華麗な意匠でふたつのお堂の対比があざやか。
観音堂は独特なつくりです。寄棟造にボリュームのある唐破風をつけたような形状ですが、はたしてそうなのかわかりません。
しかも大棟の部分に共同浴場の湯気抜きのような構築物がついています。
屋根の勾配はすこぶる急で、どことなく兜造りのようなイメージがあります。
向拝梁の木鼻に獅子、梁上には龍の彫刻。正面の桟戸は上段が黒い木連格子、下段が朱と黒の連子で、華々しいイメージのある仏殿です。
山門のたたずまいや観音堂の華やいだ雰囲気からして、かつては相応の参拝客を集めていた感じがあります。
倉渕は道祖神や露仏(とくに馬頭観音)の宝庫で、これは草津(信州)街道のかつての賑わいを示すものかと思います。
14.済度山 龍水院 大福寺






高崎市倉渕町水沼1303
天台宗 御本尊:不動明王
札番:北関東三十六不動霊場第3番
朱印尊格:瀧不動 書置(筆書)
札番:北関東三十六不動霊場第3番印判
※ご不在につき郵送にて拝受しました。前後の札所でも拝受可能というWeb情報あり。
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーンないしカンマン」の御寶印(火焔宝珠)と「瀧不動尊」の揮毫。
右上に「北関東三十六不動霊場第三番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
寺伝によれば、約千二百年前、最澄(伝教大師)が東国を巡錫された折(弘仁八年(817年)~)、榛名の舟尾山寺に立ち寄られ一体の不動明王像を彫り、当寺に堂宇を建立し安置されたと伝わります。
舟尾山寺がはっきりしませんが(柳沢寺?)、当寺御本尊は伝教大師の御作ということになります。
伝教大師は堂宇に納めた不動尊に水を供えようと呪文を唱えられ、手にされた「独鈷」を岩に投げつけたところ、そこから清泉が湧き出したといわれます。
大師曰く「滝に沐浴すれば総じて苦悩を洗い、去りて秘境の極に至ることこの清泉に勝るものなし」とされ、これにより「独鈷泉」とも称されます。
とくに脳病平癒に霊験あらたかとされ、上州のみならず東国近隣にまで「室田の瀧不動尊」として広く知られていたそうです。
こちらは北関東三十六不動尊霊場第3番札所です。
北関東三十六不動尊霊場は、群馬・栃木・茨城の三県にまたがる36の不動明王を巡る不動尊霊場です。
「三密修行の道場」とされ、群馬の寺院は『身密の道場』、栃木の寺院は『口密の道場』、茨城の寺院は『意密の道場』とされています。
(間違えやすいのですが、関東三十六不動尊霊場とは異なります。)
昭和63年4月に開創された比較的新しい霊場で、霊場会が組織され、ほとんどの札所で御朱印も拝受できる模様です。
ただしご不在気味の札所が多い感じもあるので、事前問合せがベターかと思います。
鳥川沿いにあるので、街道からだと下り参道となります。
水とゆかりのふかい不動尊霊場や弁天様霊場でよくみられる形です。
坂道を降りきった山内入口に「瀧不動大福寺」の寺号標と六地蔵。
山内には「独鈷泉」の滝下に御座す露仏の不動尊、不動堂、弁天堂、薬師堂などが点在し、祈願霊場特有のパワスポ的雰囲気が感じられます。
なお、こちらは「下室田町の大福寺の境外仏堂」という情報がありますが、詳らかでありません。
瀧不動本堂は明和四年(1767年)に室田村の名工清水谷仁右衛門藤原貞宴の作と伝えられ、御堂内部に向拝を設けているという特徴があるそうです。
高崎市指定重要文化財に指定されています。
「御堂内部の向拝」はよくわからなかったのですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、唐破風向拝一間付き。
向拝上の扁額は「瀧不動明王」。向拝柱に「北関東三十六不動尊霊場第三番札所」の札所板。
向拝柱が2連あるような変わった形状(奥のは母屋柱かも)で、手前の木鼻は獅子と貘。奥の木鼻は獅子2で、ともに彩色が施されています。
桟唐戸上桟格子窓下桟格子状の入子板。
組物が複雑すぎて正直よくわからないのですが、とりあえず書いてみます。(ぜんぜん違うかもしれません(笑))
尾棰と鬼斗らしきものはあり、少なくとも三手先はあると思います。
地垂木と飛檐垂木が明瞭で密な「二軒繁垂木」。
二重虹梁かどうかは不明ですが、梁は二本で、彩色の浮き彫りがみられます。
手前の向拝柱上部の斗が内側に伸びて小斗が5個見えます。(通四ツ斗?)
二本の梁のあいだは笈形の形状となっていますが、大瓶束はありません。
手挟みに花文様の彩色彫刻。海老虹梁。
不動堂らしい、インパクトのある仏堂です。
納経所はありますが参拝時はご不在だったので、御朱印は後日郵送いただきました。
----------------------------------------
●その他に御朱印を拝受した寺院がいくつかありますが、原則不授与のようなので、こちらでのご紹介は控えます。
----------------------------------------
宿泊は自家源泉*の「ホテルみゆき」にとりました。これで入浴可能で未湯の草津の源泉はおそらくあとふたつだと思います。(いずれもお高いので難物(笑))
*)使用源泉は、みゆき第一源泉・西ノ河原源泉の混合泉


【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
Heaven Beach - Anri / 1982
あまりに懐かしすぎる名曲。いろいろな想い出が詰まっていて感慨なくして聴けぬ。
3:14~のストリングス。時代じゃな(笑)
Heaven Beach、消されちゃったので、とりあえず替わりにこちらを。↓ (直リンならこちらから聴けます。)
ANRI - LONG ISLAND BEACH(1985)
ちと時代が下るけど、1985年「WAVE」からの名バラード。
当時、ドラマティックなバラードを歌わせたら敵無しだったと思う。
海のキャトル・セゾン - とみたゆう子 / 1982
ミルキー・ヴォイスといわれてた甘~いハイトーン。
当時はどちらもひたすら聴いてたもんな~。やっぱり昔からハイトーンフリークだったのかも・・・(笑)
熊田このは 『花』 まねきの湯 16Dec2017
でもって、いまもやっぱりハイトーンフリーク・・・(笑)
熊田このは「手と手」2019/11/04 Birth Day 2MAN LIVE 溝ノ口劇場
1stCD、2019/11/03リリースです。
→熊田このはさんの特集
すこし追加&追記します。(08.~)
草津温泉からの帰路に、国道406号・須賀尾峠・浅間隠温泉郷・倉渕経由で高崎に抜けるルートがあり、御朱印を授与される寺院がいくつかあります。
このルートは榛名町室田交差点で榛名神社からの帰路と合流しますので、国道406号の室田交差点までを「草津温泉編」、室田交差点から高崎寄りを「伊香保温泉編」として構成しなおします。
国道406号「室田」交差点から高崎寄りの寺社については→こちら(伊香保温泉編)をご覧ください。
また、渋川方面からの国道353号「大戸口」交差点までの寺社については、→こちら(四万温泉編)をご覧ください。
御朱印情報を得ている東吾妻町の寺院を追加します。
また、このエリアは真田氏、海野氏など、武田信玄公とゆかりのふかい武家の本拠地なので、信玄公にちなむ事跡などを補強してリニューアルします。
(→ 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印)




---------------------------------
2017/10/09 UP
先日、ふるさと納税でゲットした地域券があったので、ひさびさに草津&四万に泊まってきました。
御朱印もいただいてきましたので、草津&四万周辺でいただける御朱印をご紹介します。
(非札所の寺院も多く、現時点でも拝受できるかは定かではありません。)
吾妻エリアには吾妻三十三番観音霊場や三原(谷)三十四所観音札所などの古い霊場はあるものの、それらの札所の多くは廃寺や山中のお堂で、この霊場でいただける御朱印はほとんどありません。
複数の現役霊場が重複する県央(前橋・高崎)や東毛(伊勢崎・桐生・太田・館林など)エリアとくらべると、授与所はどうしても少なくなります。
それでも、神社も含めるとそれなりの数は揃いますので、草津のアプローチベースとなる長野原町、同じく四万の中之条町も併せてご紹介してみます。
1発目は草津温泉です。
第2回目(四万温泉編)は、→こちら
第3回目(伊香保温泉編)は、→こちら
【草津温泉周辺で拝受できる御朱印】
01.大洞山 雲林寺
公式Web





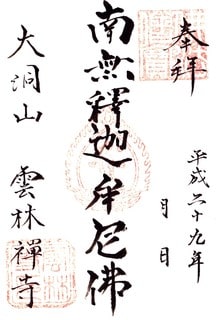
長野原町長野原73
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:三原郷(谷)三十四観音霊場第1番(作道観音堂)
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛 直書(筆書)
札番:なし(御本尊の御朱印)
・中央に御本尊釈迦牟尼佛の種子「バク」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。
左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
※三原(谷)三十四所観音の御朱印は授与されていないようです。
長野原町役場に隣接する曹洞宗の古刹で、信濃国小県郡~吾妻の豪族、海野氏ゆかりの寺です。
弘長三年(1263年)、臨済宗妙心寺派の龍幡和尚が創建されました。
創建時は大字長野原字火打花、その後貝瀬に移り、永禄二年(1559年)、海野幸光が開基となって現在地に伽藍を再建、後閑(安中市上後閑)の長源寺九世為景清春が入られ大洞山雲林寺として開創されました。
長源寺の末寺となっていますが、これは長源寺の為景清春が当山の他、宝昌寺(高崎市)、長伝寺(安中市)、桂霊寺(佐久)を開かれ、長源寺との本末関係が継承されているためと思われます。
当寺の公式Webには、「海野幸光は、西吾妻地方の吾妻川左岸に勢力を持ち、戦国時代に羽根尾城に拠った羽尾景幸の孫である。」とあります。
海野氏、羽尾氏の家系はすこぶる錯綜していて、辿るのがむずかしいですが、Web情報を総合すると、羽尾景幸の子が羽尾幸世で、羽尾幸世の子が、長男幸全、次男幸光、三男輝幸、四男幸昌と続くようです。(これは「幸光が景幸の孫」という寺伝に符合します。なお、海野幸光は羽尾景幸の子で羽尾幸世の弟という説もありますが、幸光・輝幸は兄弟という点は一致しています。)
複雑な経緯があって、次男幸光、三男輝幸は海野姓を名乗って”海野兄弟”として知られています。
幸光は仏教、とくに修験道への帰依が深かったと伝わります。
戦国期、この地は甲斐から侵攻した武田勢と関東管領家の上州の山内上杉勢の勢力がぶつかるところで、武田方に真田幸隆、鎌原氏、上杉方に岩櫃城の斎藤氏が立って、そのはざまで羽尾氏は複雑な動きをとったものとみられます。
真田氏、鎌原氏、羽尾氏ともに滋野姓の同族なので、その駆け引きは同族ゆえよけいに複雑化したのでは。
海野兄弟は、永禄元年(1558年)の頃より岩櫃城主斎藤憲広に仕えて岩櫃城内に居住。
永禄六年(1563年)、真田氏の侵攻による斎藤氏滅亡後は武田方に属し、永禄九年(1566年)岩櫃城城代となり、真田幸隆の配下に入っていたとされます。
その後、海野兄弟は真田家の家督を継いだ真田昌幸に属し、幸光は岩櫃城に拠ったとされます。
天正九年(1581年)、幸光は北条氏に通じたとの疑いを受け、真田、鎌原、湯原氏の軍勢に攻められ、奮戦むなしく討ち死にしたと伝わります。齢75歳。
墓所は旧領羽根尾の北小滝にあります。
国道145号上州街道に面して参道入口。
石造冠木門。寺号標と右に観世音の石碑、左にも石碑があります(揮毫不明)。
うっそうと茂る杉木立の下に、本堂につづく階段が伸び、脇には地蔵尊、観音様などの露仏が御座します。
階段を登り切ると右手に鐘楼、宝篋印塔と六地蔵。左手本堂前の老松がいいアクセント。
入母屋造桟瓦葺の本堂で、左手に寄せて桟唐戸。その上に寺号「雲林禅寺」の扁額。
簡素ながら端正な格子窓が意匠的に効いた、禅寺らしい建築です。
本堂と相対して観音堂。三原郷(谷)三十四観音霊場第1番、打ち始めの「作道観音堂」です。
(おそらく)入母屋造妻入り銅板葺。桟戸木連格子、木鼻に獅子、梁間に龍の彫刻、向拝脇に花頭窓。向拝柱には御詠歌の木板。
さすがに発願所。屋根の照りが強く、勢いを感じる仏堂です。
御朱印は庫裡にて尊格御本尊のものを拝受しました。
ただし、現役札所ではないので、御朱印拝受はタイミング次第かと思います。
02.龍燈山 常林寺




長野原町応桑547
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
札所:三原郷(谷)三十四観音霊場第6番(穴谷観音堂)
朱印尊格:南無釋迦牟尼佛 直書(筆書)
札番:なし(御本尊の御朱印)
・中央に三寶印の捺印と御本尊「南無釋迦牟尼佛」の揮毫がされています。
また聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印と穴谷観音の印判も捺されているので、三原(谷)三十四所観音札所第6番札所の性格も帯びている御朱印と思われます。
草津とは吾妻川の反対側になりますが、こちらも長野原町のお寺。
滋野氏族鎌原氏の菩提寺で、予想以上に立派な境内と伽藍を構えていました。
鎌原氏は滋野氏族で、ふるくから三原庄に拠り勢力を張りました。
文明年間(1469年~1486年)頃から上野平井城の関東管領山内上杉氏ないし、上杉方の岩櫃城主斎藤氏の支配下にあったと伝わります。
甲斐の武田信玄の信濃侵攻がはじまると、永禄三年(1560年)、鎌原幸重・重澄父子は、真田幸隆の斡旋で信玄に謁見し、斎藤氏を離れて武田方に加わりました。
永禄五年(1562年)斎藤氏と羽尾氏(滋野一族)の攻撃を受けた鎌原氏は、鎌原を保てず佐久へ退去したものの、武田氏・真田氏の支援を得て鎌原領を奪還しました。
永禄六年(1563年)、真田氏は斎藤氏拠る岩櫃城を攻め、難攻不落といわれた岩櫃城をついに落としました。
吾妻郡は真田幸隆の支配下に入り、真田氏の与力として活躍した鎌原氏は岩櫃城代に任ぜられたといいます。
以降、武田・真田軍の将として、武田軍の戦いに臨み、鎌原筑前守は「長篠の戦い」で戦死しています。
武田氏滅亡後も鎌原氏は真田氏に属し、沼田城に入って家老職を務めましたが、沼田真田家の断絶を受けて松代真田家に仕え、以降松代藩士として続いています。
駐車場は庫裡の横にあるので、参道起点は本堂の下に一旦降りていくことになります。
参道階段のぼり口には破風と鬼瓦の遺構。その右手には石造の観音様が御座し、「三原谷三十四番霊場 第六番穴谷観音」の石碑があります。
一面二臂の菩薩形。左手に未開敷蓮華を持たれ、頭髪部の正面に化仏を置かれた蓮華座の結跏趺坐像で、石造の聖観世音菩薩の坐像と思われます。
巨石を両断し刳り抜いたなかに御座される、特徴的なおすがたです。
石段をのぼりきると本堂前。宝篋印塔一対、石灯籠一対。
本堂は入母屋造平入り、向拝格子戸の上に縦書きの寺号扁額。軒下に平三斗と雲斗の組み合わせ。妻部は経の巻獅子口、三ツ鼻懸魚に複数の彫刻を備えています。
禅宗の名刹らしい堂々たる本堂です。
こちらも三原(谷)三十四所観音札所の札所(第6番)で、参道脇に札所本尊の穴谷観音が御座しますが、観音霊場単体の御朱印は授与されていない模様。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
03.鎌原観音堂




嬬恋村鎌原492
曹洞宗(現) 御本尊:十一面観世音菩薩
札所:三原郷(谷)三十四観音霊場第8番
朱印尊格:鎌原観音 直書(筆書)
札番:三原郷(谷)三十四観音霊場第8番印判
・御朱印尊格は御本尊の十一面観世音菩薩。種子「キャ」の御寶印と「鎌原観音」の揮毫に三原(谷)三十四所観音札所の札所印が捺され、観音霊場の御朱印となっています。
この御朱印は三原(谷)三十四所観音札所唯一のものである可能性があります。
草津からは少し離れた嬬恋村のお寺ですが、こちらもご紹介。
天明三年(1783年)の、浅間山(天明の)大噴火(浅間焼け)による土石なだれの際、境内にいた村民を救われた観音さまとして広く信仰を集めています。
爾来、信州善光寺による追善法要が営まれてきたようですが、現在は応桑の常林寺の管理下にあるようです。
鎌原観音堂の北方約200mのところに土石なだれで埋没した延命寺がありました。
このお寺のものとみられる石碑が東吾妻町矢倉の吾妻川の河原で発見され、鎌原観音堂そばに安置されています。
この地から東吾妻町矢倉までは約25㎞。これだけの距離を重い石碑が押し流されたわけで、土石なだれのすさまじさがうかがえます。
石碑には、「浅間山」と記され、延命寺は鎌原村に鎮座されていた浅間大明神の別当と推測されています。
また、鎌原観音堂を旧延命寺の一部とみる説もあります。
三原郷(谷)三十四観音霊場の開創は江戸時代初期とみられています。
延命寺はこの地域屈指の寺院であったらしいので、延命寺と鎌原観音堂の関係がうすければ、延命寺に観音堂を設けて札所とするのが自然です。
しかし、鎌原エリアでは鎌原観音堂のみ札所となっているようなので、鎌原観音堂は延命寺の観音堂であった、という可能性もあるのかもしれません。
観音堂は寄棟造ないし方形造茅葺。向拝部三間のうち中央開放で上部に「かんのんさま」の扁額が掲げられています。
飾り気のすくない仏堂ですが、壁面にはわらじや奉納額、写真などが掲げられ、信仰の篤さが感じられます。
三原(谷)三十四所観音札所の札所(第8番)で、札所板も掲げられています。
嬬恋郷土資料館に隣接し観光客の来訪もあるようで、観音堂右手に授与所があるので御朱印はいただきやすいです。
04.草津山 常楽院 光泉寺






草津町草津442-1
真言宗豊山派 御本尊:薬師如来
札所:関東九十一薬師霊場第44番
朱印尊格:薬師如来 直書(筆書)
札番:なし(御本尊の御朱印)
・関東九十一薬師霊場で申告した御朱印の尊格は御本尊(札所本尊)の薬師如来で、霊場無申告でも同様と思われます。
薬師如来の種子「バイ」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「薬師如来」の揮毫、右上には「日本三薬師」*の印判が捺されています。
*)これは「日本三大温泉薬師」のことだと思われます。あとひとつは有馬の温泉寺ですが、もうひとつは明確に定まっていないようで、光泉寺の公式Webには山中の湯、城崎の湯、道後の湯のいずれかのお薬師様ではないかとの旨の記述があります。
(「日本三大薬湯」(有馬温泉、草津温泉、松之山温泉)にちなむお薬師様だとしたら、松之山温泉の薬師堂でしっくりくるかもしれません。)
吾妻エリアではめずらしい真言宗のお寺で、関東九十一薬師霊場第44番の札所でもあります。
養老五年(721年)行基による開基と伝わり、正治二年(1200年)白根明神の別当寺として草津の領主湯本氏が再建、僧職は鎌倉幕府から地頭職を賜い白根庄の領有を許されていたともされる草津温泉の保守本流的なお寺。
旧郷社、白根神社の別当寺であったことからも、草津温泉における重要なポジションがうかがわれます。
湯本氏はこの地の名門で、木曾義仲に仕え、のちに建久四年(1193年)、源頼朝公が浅間山麓で巻狩りを行った際に案内役となり、湯本の姓と三日月の家紋、そして草津の支配を認められたといいます。
頼朝公の浅間巻狩りは草津温泉の開湯伝承にも数えられますから、湯本氏は草津の開湯にまで遡る古い家柄とみることができます。


〔白旗源泉説明板〕
建久四年(1193年)鎌倉将軍頼朝公が浅間山六里ヶ原の巻狩の折、この草津まで騎馬を進めあれはてた源泉地を改修しみずから入浴されたと伝へられる。以来この湯を御座の湯と呼び、その後いつの頃からか祠を建てて頼朝公を祀った。現在の頼朝宮は天明二年(1782年)八月に改築されたもので、草津温泉伝承(光泉寺蔵温泉奇効記)を今に伝え、草津温泉の入浴客の深い信仰をあつめてきた。
明治二十年、白旗の湯と改称されたが、旧源泉は、この湯畑に沈んでいる小さな湯枠の中と考えられる。草津温泉の開湯伝承につらなる歴史的遺跡である。
-----------------------------------
湯本氏が歴史上活躍するのは戦国時代です。
永禄六年(1563年)、岩櫃城に拠る上杉方の斎藤氏を真田氏が攻め落としましたが、その際、湯本善太夫・三郎兵衛門は真田方につき、勝ち戦の恩賞として草津谷の領有を安堵されたといいます。
湯本善太夫は真田氏同様、甲斐・武田軍の与力となり各地を転戦、長篠の戦いで討死したといいます。
以降、天和元年(1681年)草津谷が天領となるまでこの地を領したとみられています。
湯本氏は真田沼田藩の家老であったとされますが、草津谷が天領となったのは延宝八年(1680年)、真田沼田藩の改易・天領化を受けてとみられます。




湯畑、白旗源泉のすぐ横から山手に登る階段が参道で、観光客も多く入り込んでいます。
階段をのぼると山門。三間一戸の単層、金属葺木部朱塗りで仁王尊が御座す仁王門です。
本堂前向かって右手に奥まって、「遅咲き如来」が御座す釈迦堂。
元禄十六年(1703年)、江戸の医師外嶋玄賀宗静の発願、草津村湯本弥五右衛門が施主となって建立。志賀の夢告にもとづき、桁行二間、梁間二間の四間藁葺で寄棟造。
木部朱塗り、屋根に鬼瓦、藁葺の唐破風向拝を擁し、屋根は起り気味で独特の形状です。
扁額は「釋迦堂」。多彩な枓栱、海老虹梁、木鼻の獅子、蟇股部の彫刻、左右の花頭窓など、意匠的にも見どころがあります。
釈迦堂に御座す釈迦如来は、「遅咲き如来」として知られ、元禄時代東大寺公慶上人の御作です。
本堂は入母屋造金属板葺照り屋根。向拝付き木部朱塗り。扁額は山号「草津山」。
御本尊は薬師如来です。
境内には温泉の守護神「湯善堂」、湯浴み弁財天、湯泉観音、初代熱の湯湯長野島小八郎の碑など、温泉にかかわる尊格や碑が建立されています。
〔湯浴み弁財天略記(境内掲示)〕
養老年間(717年~724年)行基菩薩はこの地にたち眼下に光る泉を見出しそれがただの泉でなく万病にきく温泉であることを喜び薬師如来をまつり光泉寺を開く以来泉は人々の病をいやす慈悲の泉となり今日の草津温泉の源となった
この池はそれにちなみ「慈悲の泉」となずけられ名湯草津温泉に浴し身も心も清浄になった喜びと感謝の姿をあらわす湯浴み弁財天をおまつりした
-----------------------------------
境内左手の趣ある庫裡が授与所です。
御朱印帳も頒布されていますが、御朱印帳を持っていない参拝客には書置御朱印が授与されているようです。
参拝客の多い観光地のお寺にもかかわらず、お寺さんの対応は丁寧なものでした。
05.妙立山 日晃寺



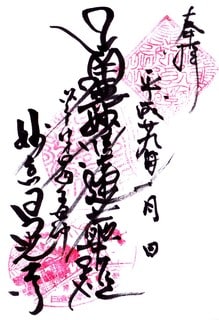
草津町草津540
日蓮宗
御首題
安政四年(1857年)草津祖師堂として創建、昭和3年に日蓮宗草津教会に改称し、昭和21年に身延山の許可を得て妙立山日晃寺(正規の日蓮宗寺院)に昇格したとされる日蓮宗のお寺。
草津温泉の北東に位置するため、温泉街の鬼門鎮守として信仰されていたようです。
吾妻エリアに日蓮宗の寺院は少なく、貴重な御首題を拝受できます。
〔境内の掲示〕
当山わ通稱祖師堂と稱す 延享三年(1747年)一宇建立記念供養碑あり降って弘化年間(1845年~1848年)一堂建立す 草津町鬼門除の祖師として町民の信仰の中心なり 大正年間身延山説教所となり又草津教会を経て昭和二十二年日晃寺と公稱す
-----------------------------------
大阪屋旅館の横手の道を登った桐島屋旅館の手前に参道の階段があります。この周辺に共同浴場はないので、温泉マニアからするとブラインド的な立地です。
参道入口にお題目塔。石段両脇に2つの寺号標はめずらしいと思います。
石段正面に本堂。
本堂の全容が掴めず、しかも庫裡とつながっているので詳細不明ですが、身舎ベースで桁行三間向拝流れ屋根付一間、寄棟造平入りではないかと。
身舎の規模のわりに向拝屋根のせり出しが大きく、雨雪の多い草津の気候を配慮したつくりにも思えました。
ブラインド的立地ながら参拝客は少なくないようで、御首題も手慣れた感じの授与でした。
日蓮宗なので御首題帳にいただきましたが、他宗まじりの御朱印帳の場合、「妙法」となるのか、はたまた授与いただけないのかは不明です。
06.白根神社



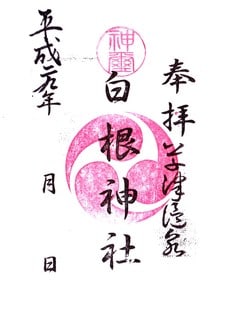
草津町草津538
御祭神:日本武尊
旧社格:郷社
旧別当:光泉寺
授与所:参道階段左手前の蕎麦屋「松美」
朱印揮毫:白根神社 印判
神社御朱印です。
温泉街からだと関の湯の前をさらに下っていくと左手に参道入口があります。
急な階段を登っていくと思いがけず広い境内と立派な社殿にびっくり。
氏子をもたれているかはわかりませんが、旧郷社と社格は高く、鎮守社であればおそらく範囲は草津温泉に留まらないかと思われます。
祭神は日本武尊。白根山を祀る神社で、白根山上に鎮座する本社の遥拝所が明治六年、郷社に列格した際に温泉街を見下ろすこの地に移られたようです。
社頭右手に「(郷社)白根神社」の社号標。その先に総丸材の石造神明系鳥居。
石段をのぼりきると左手に手水舎。その先に両脇に石灯籠が並ぶ参道。
その先に石造明神鳥居で、「白根大明神」の扁額が掲げられています。
さらにその先に狛犬一対。向かって右が「子取り」、左が「玉取り」で、端正な仕上がりです。
拝殿は石積みの上に入母屋造平入りで銅板葺向拝付き。拝殿の扁額は社号「白根神社」。
積雪地らしくがっしりとした向拝。巴紋付きの白地の拝殿幕が厳かな雰囲気を醸し出しています。
うかつにも見逃しましたが、境内には古い共同浴場「鷲乃湯」の由来などが記されている碑があるそうです。


参道階段左手奥には、諏訪大社上社草津白根分社と沼神社が鎮座しています。
御朱印は参道階段左手前の蕎麦屋「松美」にて拝受できます。
御朱印帳に捺していただく印判タイプで、書置があるかは不明なので、御朱印帳持参が確実かと思います。
07.草津穴守稲荷神社
本社の公式Web
草津町西ノ河原公園
御祭神:豊受姫命
授与所:確定情報ではないですが、白根神社参道階段左手前の蕎麦屋「松美」にて拝受できる可能性があります。
※未参拝です。参拝次第、追記します。御朱印は授与されているようです。
明治四十年ごろ、東京の山崎染物店の主人が草津へ湯治に通い、病気平癒の記念に常々信仰していた羽田の穴守稲荷をこの場所に分霊し勧請したそうです。
平成13年に草津町内有志により改築されています。
羽田の穴守稲荷と同様、お砂「招福の砂」をいただけるようです。
08.密岩神社



東吾妻町大字郷原1126
御祭神:密岩権現?
授与所:東吾妻町観光協会(JR群馬原町駅構内)か平沢登山口観光案内所
※参拝済ですが、御朱印は未拝受です。上記授与所で、密岩神社、金剛院(観音山不動)、岩櫃城の御城印の3点セットを授与いただけます。
→案内情報
古来よりランドマーク的な岩山は修験の聖地となることが多いですが、上州吾妻の名山、岩櫃山も例外ではありません。
また、この地には上州屈指の堅城、岩櫃城が築かれ、こちらも神仏とのゆかりがあります。
永禄六年(1563年)甲斐・武田方の真田幸隆は、岩櫃城に拠り上杉の麾下にあった斎藤基国を攻め、落城させました。
このとき身ごもっていた基国の奥方は基国とちりぢりになり、岩櫃山の洞穴で子を産み落とし育てました。
奥方は、わが子を里人に託し、夫基国を求めて旅に出ましたが基国と巡り会うこと叶わず、帰り着いた岩櫃山の洞穴の中で落命しました。
すると一筋の煙が立ちのぼり観音様のお姿が現れるとともに、奥方の屍は跡形もなく消え去りました。
奥方の不運を哀れんだ里人たちは、密岩権現として祀り手厚くその霊を慰めました。
奥宮とされるもともとのお社は岩櫃山の中腹にありますが、参道は難路で現在は立ち入り禁止です。
古来、密岩神社を崇敬してきた古屋集落の方々により平成23年(2011年)里宮が設けられ遷座されました。
里宮の地は、岩櫃山が前面に広がる眺望の地で、東吾妻町はパワースポットとしてPRを進めています。
09.瀧峩山 金剛院(観音山不動)
東吾妻町
授与所:東吾妻町観光協会(JR群馬原町駅構内)か平沢登山口観光案内所
※未参拝です。参拝次第、追記します。上記授与所で、密岩神社、金剛院(観音山不動)、岩櫃城の御城印の3点セットを授与いただけます。
→案内情報
岩櫃山の群馬原町寄りにある柳沢城跡(岩櫃城の支城)の下、不動滝のよこにある観音山 不動堂を指しているようで、修験系の寺院とみられます。
1.大洞山 雲林寺を開基した海野(羽尾)幸光は、修験とのかかわりもあったとみられているので、ゆかりの寺院かもしれません。
岩櫃城の鬼門鎮守として建てられたという説もあるようです。
〔 岩櫃城について 〕
古来、この地は吾妻(あがつま)氏の本拠で、岩櫃に拠ったのは、藤原氏秀郷流の吾妻斎藤氏とされます。関東管領・山内上杉家の配下にあり、同族の大野氏とともに吾妻郡に勢力を張りました。
戦国時代の当主は岩櫃城主、斎藤憲広で、郡西の羽尾氏、鎌原氏と領地を巡る駆け引きを繰り返しました。
羽尾氏、鎌原氏ともに信濃の滋野一族の流れで、おおむね羽尾氏は斎藤氏寄り(上杉方)、鎌原氏は真田氏寄り(武田方)であったとみられています。
永禄六年(1563年)、岩櫃城は真田・鎌原勢の攻勢を受けて落城。、城主斎藤憲広は越後(ないし上野)に落ちのびたとされます。
岩櫃城の支城である嵩山城には憲広の子憲宗と弟虎城丸が残り抵抗をつづけましたが、永禄八年(1565年)に攻められて落城。
ながらく上杉方として吾妻に勢力を張った斎藤氏はここに滅亡しました。
以降、岩櫃城は真田氏の支配下に入り、武田氏の版図に組み込まれます。
天正十年(1582年)、織田・徳川軍の甲斐侵攻を受けて劣勢となった主家の武田勝頼を真田昌幸は岩櫃城へ迎え入れ武田家の再興を図ろうとしましたが、これはかなわず武田家は滅亡しました。
その後、岩櫃城は真田信之の支配下に入り、慶長十九年(1614年)に破却されました。
要害の地に建つ典型的な山城で、脚光を浴びたのも戦国時代。
武田家や真田家ゆかりの逸話をもち、戦国武将ファンには見逃せない城ではないでしょうか。
10.(岩下)菅原神社




東吾妻町大字岩下1582
御祭神:菅原道真公
授与所:境内社務所
朱印揮毫:菅原神社 直書(筆書)
由緒などはよくわかりませんが、しっとり落ち着いた神社で、ご神職がいらっしゃれば御朱印を拝受できます。
参拝は木造の明神鳥居(二の鳥居)からとなりました。灯籠一対、狛犬一対。
石段をのぼると三の鳥居で木造の明神鳥居です。拝殿のすぐ下に木造の冠木門。
写真の構図が拙く、いまひとつよくわからないのですが、桁行三間の入母屋造妻入り銅板葺唐破風向拝付きではないかと思います。
向拝梁木鼻は正面獅子、側面貘。梁に雲形の彫刻、梁上に龍、唐破風拝飾に朱雀とみられる彫刻が施されています。
唐破風の鬼板も見事なものです。
向かって右手の神楽殿方向には、千鳥破風が設けられています。
つまり、入母屋の妻入り方向に唐破風の拝殿、平入り方向に拝殿と45度の角度をもって千鳥破風が設けられているという構図です。
この千鳥破風は入母屋破風に近いほど規模が大きく、梅紋入りの鬼板と破風拝飾り、懸魚、破風尻飾りと数々の装飾が施されています。
神楽殿の基礎は拝殿よりむしろ高く、入母屋造銅板葺妻入りで縁高欄をまわしています。
当社は「太々神楽」で有名です。その関係もあって、神楽殿向きに破風を設ける必要があったのかもしれません。
-----------------------------------------
以降は、国道406号(草津街道・信州街道)沿いの寺社のご案内になります。
草津街道(信州街道)は、中山道の高崎宿から分岐し、神山宿、室田宿、三ノ倉宿、大戸宿、本宿、須賀尾宿、長野原宿を経て草津温泉に至る道筋で、中山道ルートにくらべて距離が短いので、北信濃諸藩と江戸の往来や草津温泉への湯治などに多く利用されました。
北信濃、とくに小布施や須坂は菜種油の量産地で、この輸送は主に草津街道(信州街道)経由だったため、この道は「油街道」とも呼ばれ、沿道の宿場町はたいそう栄えたそうです。
東吾妻町大戸には大戸関所があり、現在も関所跡が残ります。
このそばには、大戸の関所を破ったかどで処刑された国定忠治刑死場跡があり、勝負運や脳卒中除けに霊験あらたかといわれる忠治地蔵尊が祀られています。御朱印は授与されていないようです。


【写真 上(左)】 大戸関所跡
【写真 下(右)】 忠治地蔵尊
〔大戸関所跡の説明板〕
大戸関所は、信州街道の要点をおさえる重要な関所で、近世初頭の寛永八年(1632年)に設置された。信州街道は草津温泉を初めとする湯治客。善光寺参り、北信濃の三侯の廻米や武家商人の荷物、各地の産物の輸送路として、中山道を凌ぐ程の活気を呈したともいわれ、江戸と信濃を結ぶ最短距離として重要な街道であった。別名信州道、草津道、善光寺道、大戸廻りとも呼ばれていた。(中略)嘉永三年(1850)年に関所破りの罪を受け侠客国定忠治はこの地で処刑された。映画演劇や講談浪曲でも知られる處である。
-----------------------------------
11.華庭山 天樹院 大運寺




東吾妻町大戸371
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:南無阿弥陀佛 印判
札番:なし(御本尊の御朱印)
・中央に三寶印と六字御名号「南無阿弥陀佛」の印判。
左に山号・寺号と寺院印が捺されています。
榛名の西麓にある浄土宗の名刹。
南北朝時代の興国年間(1340年~1346年)、宝誉上人が京から恵心僧都御作の阿弥陀仏を背負って来られ、大戸村寺原に堂宇を創立、「浄土布教の地」として信者を勧請されたのが開山と伝わります。
天正年間(1573年~1593年)に当地に遷り、大戸・本宿・萩生の三村を檀徒としています。
御本尊は宝冠を戴いた木彫座像で「鎌倉時代の仏像の特徴とされる鋭い衣紋の線が何ともいえず美しいもの」とのことです。(山内掲示より)
「大運寺の本尊」として町指定重要文化財に指定されています。
大運寺は桜の名所として知られており、とくに山門手前の古木のシダレザクラは有名です。
参道入口の総門は、切妻造三間一戸桟瓦葺の四脚の単層門で、薬医門や三棟門のように左右の門に屋根がかかっています。(木戸はないが薬医門の一種か?) 本柱に寺号板。
山門は三門一戸の桟瓦葺、一層に桟瓦葺の屋根を配する堂々たる二重門。
木部朱塗りの華麗な意匠。二層中央の拝部に山号「華庭山」の扁額を掲げています。
さらに石段をのぼると本堂。
桁行八間ほど、入母屋造桟瓦葺唐破風向拝付き。
向拝梁木鼻は正面が獅子、側面が貘。梁上に見事な龍の彫刻。海老虹梁。格子天井。
桟唐戸上桟木連格子窓下桟入子板、長押部に彫刻。上部に寺号「大運寺」の扁額。
破風拝に彫刻、獅子口に経の巻三個と紋章。
規模はさほどではないですが、しっとりと落ち着いたイメージです。
お伺いしたときは丁度法要が始まるところでしたが、「はんこの御朱印紙でよければ」とのお言葉をいただいたので、ご厚意に甘えて拝受しました。
12.諏訪山 東善寺
公式Web




高崎市倉渕町権田169
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
朱印尊格:釋迦牟尼佛 / 英豪大器 直書(筆書)
札番:なし(御本尊・英豪大器の御朱印)
〔御本尊の御朱印〕

・中央に三寶印と御本尊「釋迦牟尼佛」の揮毫。
右上に山号印。左上に小栗上野介忠順のお姿印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔「英豪大器」の御朱印〕

・中央に三寶印と「英豪大器」の揮毫。
右上に小栗上野介●●の揮毫。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
「英豪」とは英雄豪傑、「大器」とは並みはずれて優れた器量を備えた人物をあらわすので、小栗上野介の人となりを示す揮毫かと思われます。
(通常は御本尊の御朱印のみのようです。「英豪大器」の御朱印も所望すると、寺庭さま?は少しく驚かれたご様子でしたが、ネットで見た旨お話しすると納得されておられました。この御朱印は書き手(ご住職)がご不在だと書けないとの由。)
幕末の名奉行、小栗上野介忠順(ただまさ)ゆかりの曹洞宗寺院。
寺伝によると、開創は寛永十年(1633年)。宝永元年(1704年)に権田村が小栗家の知行地となり小栗家との縁が始まりました。
開山は円室存察大和尚、開基は洞庵首座、中興開基は高屋寺殿永山良傑居士(小栗政信公・小栗家五代)と伝わります。
小栗上野介は文政十年(1827年)に生まれ、三河小栗氏第十二代当主で二千七百石の旗本。
攘夷論が主流の幕府内で一貫して開国思想を深め、万延元年(1860年)、遣米使節目付役として日米修好通商条約批准のため米艦ポーハタン号で渡米し、世界一周して帰国。
その後数々の奉行を務め、海外の技術を積極的にとり入れて、幕府の財政再建、洋式軍の整備、横須賀製鉄所(後の横須賀海軍工廠)の建設、仏語学校の建設など数多の事績を残しました。
高崎市倉渕支所の史料には、「『明治の近代化は小栗の敷いたレールの上になされた』といわれるほどの、大きな業績」と記されています。
薩長軍の東征に際して主戦論を唱えるも容れられず、慶応四年(1868年)3月に罷免され領地である上野国権田村の当寺に隠遁。
同年閏4月、東山道総督が追捕し、水沼村鳥川原にて斬首されました。
享年42歳。墓所は養子の又一、殉職の家臣の墓とともに当寺にあります。
落命の地、水沼川原には顕彰慰霊碑が建立されています。
参拝者が多いらしく広い駐車場。
山内入口左右には「渓声便是広長舌」「山色豈非清浄身」(けいせいすなわちこれこうちょうぜつ さんしきあにしょうじょうしんにあらざらんや)の禅語(中国北宋時代の詩人蘇東坡の詩)の石標が掲げられています。
その奥に寺号標。
坂をのぼって手前に庫裡。茶菓子を出されており庭で楽しむことができます。
小栗公遺品館もあり、遺品館・庫裡・本堂の展示資料を有料で拝観できます。
奥に本堂、小栗公と公の朋友栗本鋤雲の銅像、六地蔵、小栗公の墓所とつづきます。
本堂は入母屋造銅板葺正面向拝付き。虹梁に板蟇股、梁両端に斗栱。がっしりとした海老虹梁。扁額は寺号「東善寺」。
桟唐戸上・中桟格子窓下桟入子板。長押部の雲形木板に唐草文様彫刻。
妻部は鬼板、懸魚、狐格子を備え、均整のとれた禅寺らしい本堂です。
13.蓮華院(水沼観音)





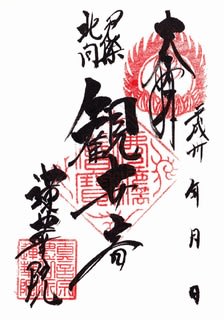
高崎市倉渕町水沼1303
真言宗豊山派 観音堂御本尊:千手観世音菩薩
朱印尊格:観世音 書置(筆書)
札番:なし(観音様の御朱印)
※本堂御本尊の御朱印は不授与とのこと。
・中央に三寶印と「(北向厄除)観世音」の揮毫。
右上に火焔宝珠の印。左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。
名湯で知られるくらぶち相間川温泉のそばにある観音様で知られる真言宗寺院。
山内に由緒書はなく、Web情報もほとんどとれませんが、高崎新聞の記事によると、「本尊の千手観音像は自覚大師(ママ 慈覚大師?)の手によるといわれる秘仏です。節分の日には厄落としの人で賑わいます。」とのこと。
石段の参道の先に朱色の山門とそのおくに観音堂。
山門は切妻造金属板葺の四脚門で、門柱に寺号標。
さらにのぼって観音堂正面、右手に向かい正面が本堂です。
本堂は、入母屋造桟瓦葺向拝付きの渋い意匠、これに対して観音堂は朱塗りの華麗な意匠でふたつのお堂の対比があざやか。
観音堂は独特なつくりです。寄棟造にボリュームのある唐破風をつけたような形状ですが、はたしてそうなのかわかりません。
しかも大棟の部分に共同浴場の湯気抜きのような構築物がついています。
屋根の勾配はすこぶる急で、どことなく兜造りのようなイメージがあります。
向拝梁の木鼻に獅子、梁上には龍の彫刻。正面の桟戸は上段が黒い木連格子、下段が朱と黒の連子で、華々しいイメージのある仏殿です。
山門のたたずまいや観音堂の華やいだ雰囲気からして、かつては相応の参拝客を集めていた感じがあります。
倉渕は道祖神や露仏(とくに馬頭観音)の宝庫で、これは草津(信州)街道のかつての賑わいを示すものかと思います。
14.済度山 龍水院 大福寺






高崎市倉渕町水沼1303
天台宗 御本尊:不動明王
札番:北関東三十六不動霊場第3番
朱印尊格:瀧不動 書置(筆書)
札番:北関東三十六不動霊場第3番印判
※ご不在につき郵送にて拝受しました。前後の札所でも拝受可能というWeb情報あり。
・中央に札所本尊不動明王の種子「カーンないしカンマン」の御寶印(火焔宝珠)と「瀧不動尊」の揮毫。
右上に「北関東三十六不動霊場第三番」の札所印。左には山号の揮毫と寺院印が捺されています。
寺伝によれば、約千二百年前、最澄(伝教大師)が東国を巡錫された折(弘仁八年(817年)~)、榛名の舟尾山寺に立ち寄られ一体の不動明王像を彫り、当寺に堂宇を建立し安置されたと伝わります。
舟尾山寺がはっきりしませんが(柳沢寺?)、当寺御本尊は伝教大師の御作ということになります。
伝教大師は堂宇に納めた不動尊に水を供えようと呪文を唱えられ、手にされた「独鈷」を岩に投げつけたところ、そこから清泉が湧き出したといわれます。
大師曰く「滝に沐浴すれば総じて苦悩を洗い、去りて秘境の極に至ることこの清泉に勝るものなし」とされ、これにより「独鈷泉」とも称されます。
とくに脳病平癒に霊験あらたかとされ、上州のみならず東国近隣にまで「室田の瀧不動尊」として広く知られていたそうです。
こちらは北関東三十六不動尊霊場第3番札所です。
北関東三十六不動尊霊場は、群馬・栃木・茨城の三県にまたがる36の不動明王を巡る不動尊霊場です。
「三密修行の道場」とされ、群馬の寺院は『身密の道場』、栃木の寺院は『口密の道場』、茨城の寺院は『意密の道場』とされています。
(間違えやすいのですが、関東三十六不動尊霊場とは異なります。)
昭和63年4月に開創された比較的新しい霊場で、霊場会が組織され、ほとんどの札所で御朱印も拝受できる模様です。
ただしご不在気味の札所が多い感じもあるので、事前問合せがベターかと思います。
鳥川沿いにあるので、街道からだと下り参道となります。
水とゆかりのふかい不動尊霊場や弁天様霊場でよくみられる形です。
坂道を降りきった山内入口に「瀧不動大福寺」の寺号標と六地蔵。
山内には「独鈷泉」の滝下に御座す露仏の不動尊、不動堂、弁天堂、薬師堂などが点在し、祈願霊場特有のパワスポ的雰囲気が感じられます。
なお、こちらは「下室田町の大福寺の境外仏堂」という情報がありますが、詳らかでありません。
瀧不動本堂は明和四年(1767年)に室田村の名工清水谷仁右衛門藤原貞宴の作と伝えられ、御堂内部に向拝を設けているという特徴があるそうです。
高崎市指定重要文化財に指定されています。
「御堂内部の向拝」はよくわからなかったのですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、唐破風向拝一間付き。
向拝上の扁額は「瀧不動明王」。向拝柱に「北関東三十六不動尊霊場第三番札所」の札所板。
向拝柱が2連あるような変わった形状(奥のは母屋柱かも)で、手前の木鼻は獅子と貘。奥の木鼻は獅子2で、ともに彩色が施されています。
桟唐戸上桟格子窓下桟格子状の入子板。
組物が複雑すぎて正直よくわからないのですが、とりあえず書いてみます。(ぜんぜん違うかもしれません(笑))
尾棰と鬼斗らしきものはあり、少なくとも三手先はあると思います。
地垂木と飛檐垂木が明瞭で密な「二軒繁垂木」。
二重虹梁かどうかは不明ですが、梁は二本で、彩色の浮き彫りがみられます。
手前の向拝柱上部の斗が内側に伸びて小斗が5個見えます。(通四ツ斗?)
二本の梁のあいだは笈形の形状となっていますが、大瓶束はありません。
手挟みに花文様の彩色彫刻。海老虹梁。
不動堂らしい、インパクトのある仏堂です。
納経所はありますが参拝時はご不在だったので、御朱印は後日郵送いただきました。
----------------------------------------
●その他に御朱印を拝受した寺院がいくつかありますが、原則不授与のようなので、こちらでのご紹介は控えます。
----------------------------------------
宿泊は自家源泉*の「ホテルみゆき」にとりました。これで入浴可能で未湯の草津の源泉はおそらくあとふたつだと思います。(いずれもお高いので難物(笑))
*)使用源泉は、みゆき第一源泉・西ノ河原源泉の混合泉


【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
Heaven Beach - Anri / 1982
あまりに懐かしすぎる名曲。いろいろな想い出が詰まっていて感慨なくして聴けぬ。
3:14~のストリングス。時代じゃな(笑)
Heaven Beach、消されちゃったので、とりあえず替わりにこちらを。↓ (直リンならこちらから聴けます。)
ANRI - LONG ISLAND BEACH(1985)
ちと時代が下るけど、1985年「WAVE」からの名バラード。
当時、ドラマティックなバラードを歌わせたら敵無しだったと思う。
海のキャトル・セゾン - とみたゆう子 / 1982
ミルキー・ヴォイスといわれてた甘~いハイトーン。
当時はどちらもひたすら聴いてたもんな~。やっぱり昔からハイトーンフリークだったのかも・・・(笑)
熊田このは 『花』 まねきの湯 16Dec2017
でもって、いまもやっぱりハイトーンフリーク・・・(笑)
熊田このは「手と手」2019/11/04 Birth Day 2MAN LIVE 溝ノ口劇場
1stCD、2019/11/03リリースです。
→熊田このはさんの特集
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




