関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)から
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へ
A.朝夷奈口
鎌倉市の北東側(横横道路「朝比奈IC」)から入るルートで、十二所、浄明寺、二階堂、西御門、雪の下の寺社をご紹介します。
まずはリストです。
1.十二所神社
神奈川県神社庁Web
鎌倉市十二所285
御祭神:天神七柱、地神五柱
旧社格:村社、旧十二所村鎮守


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
「神奈川県神社庁Web」によると、創建は弘安元年(1278年)。
『十二所権現社再建記』には、「天保八年(1837年)明王院別所恵法が社頭再営を志し、氏子三十余軒により天保九年(1838年)、現在地に再建」とあるそうで、明治維新の際、十二所神社と改称しています。
『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項に「熊野社 村の鎮守トス。十二所ノ村名是ニ発起スト云フヘシ。」とあります。
以上から、当初光觸寺境内に熊野社、ないし熊野(十二所)権現社として御鎮座で天保九年(1838年)、現社地に御遷座されたとみられます。
----------
県道204号金沢街道の鎌倉霊園下あたりから鋭角に切り返したあたりにありますが、駐車場はなく、金沢街道沿いの有料Pを利用する必要があります。
滑川の谷筋に面した山肌にあり、十数段の参道階段を昇ると石灯籠一対と端正な石造明神鳥居。その先に入母屋造銅板葺流れ向拝の拝殿。
ちなみに「熊野三所権現」とは、ふつう家津美御子(けつみみこ、スサノオ、本地阿弥陀如来)、速玉(はやたま、イザナギ、本地薬師如来)、牟須美(むすび、イザナミ、本地千手観世音菩薩)をさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。
東京・新宿の十二社の地名も、当地の熊野神社(角筈十二社)に十二所権現を勧請した由緒によるものとされています。
現在の御祭神は「天神七柱・地神五柱」で計十二柱となりますが、こちらが上記の「熊野十二所権現」の神々と符合しているかはわかりません。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、海老虹梁はなく手挟のみ、中備に波の上で踊る二匹の兎の見事な彫刻(波乗り兎)が彫り込まれています。
NPO法人鎌倉ガイド協会「古都鎌倉史跡めぐり」では、この「波乗り兎」の由来を熊野の(兎の)焼身供養に求めています。
熊野権現と兎の所縁については、山口県長門市三隅兎渡谷村の熊野権現の伝承、山形県南陽市の日本三熊野のひとつ熊野神社本殿の「三羽の隠しうさぎ」などが知られていますが、いずれもどうして兎なのかの理由がわからず、当社の兎さんについてもWebで追ってみましたが現時点ではわかりません。

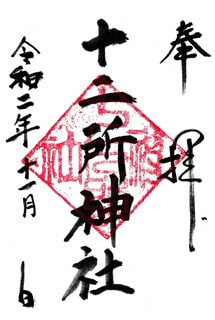
【写真 上(左)】 中備のうさぎの彫刻
【写真 下(右)】 御朱印
向拝正面は桟唐戸(閉扉)で上方に「十二所神社」の扁額。本殿は拝殿に連接し、背後の岩壁に接した(おそらく)切妻造妻入りの覆屋のなかと思われますが詳細不明です。
境内社として本殿後背に山の神、疱瘡神、宇佐八幡、地主神などが御鎮座されます。
通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。
※さすがに鎌倉。しょっぱなからWeb情報があふれています。
以降の寺社はさらに情報量が増えると思いますので、当座は適宜端折ってご紹介します。
2.岩蔵山 長春院 光觸寺
公式Web
鎌倉市十二所793
時宗
御本尊:阿弥陀如来(阿弥陀三尊)
札所:鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番
十二所にある時宗寺院で、通常は「光触寺」と書かれ、もともとは「藤觸山」と号していたようです。境内由緒書、公式Webなどからご由緒を追ってみます。
創建は弘安元年(1278年)、開山は作阿上人、開基は一遍上人と伝わります。作阿上人はもともと真言宗の僧でしたが、一遍上人遊行の途次、一遍上人に帰依して時宗に改めたと伝わります。
御本尊の阿弥陀如来は「頬焼阿弥陀」(ほおやけのあみだ)として知られ、当寺に伝わる『頬焼阿弥陀縁起』によると、鎌倉時代のはじめ、仏師運慶が町の局(まちのつぼね)の求めに応じて阿弥陀三尊像を刻したもので、ある時、町局に仕える万歳法師が盗みの疑いを受け頬に焼印を捺されたましたが、不思議なことに法師の頬には焼痕が残らず運慶作の阿弥陀仏の頬につきました。
たびたび修復しても阿弥陀仏の頬の焼痕はついに消えずにいつしか「頬焼阿弥陀」と呼ばれるようになったとの由。
『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項によると、その後、町の局は出家して比企谷に岩蔵寺という一宇(カナヤキ(火印)堂とも)を建立し、件の阿弥陀三尊像を御本尊として安置。
建長三年(1251年)、町の局はこの阿弥陀さまの前で端然と往生されたと伝わります。
『光触寺阿弥陀三尊像と頬焼阿弥陀縁起』(美術研究第十三集・熊谷宣夫氏)では、この町の局にかかわる縁起譚は、鎌倉時代中期の仏教説話集『沙石集』巻二の「阿彌陀の利益の事」に類似すると述べられ、実際、対照してもほぼ同様の内容のようです。
『新編鎌倉志』でも光觸寺の項で『沙石集』の説話を引用紹介しています。
『新編相模國風土記稿』に「(阿弥陀像の)厨子ハ(足利)持氏寄進ノ物ナリトソ。(足利)尊氏。氏満。満兼。持氏ノ碑アリ。」とあるので、足利氏重代の尊崇を集めたとも考えられます。
複数のWeb記事に、弘安元年(1278年)に岩蔵寺は現在地へと移ったとあるので、この移転時に岩蔵寺を光觸寺と改号し創建とされたのかもしれません。
寄木造漆箔玉眼の御本尊阿弥陀如来像は両脇侍立像(観音・勢至)とともに「木造阿弥陀如来及両脇侍立像」(鎌倉・彫刻・3躯)、として国重要文化財に指定され、「紙本淡彩頬燒阿弥陀縁起」(鎌倉・絵画・2巻)も国重要文化財に指定されています。
観音像は快慶(安阿彌)、勢至像は湛慶作とも伝わる名作で、後醍醐天皇御宸筆の寺号勅額も蔵します。
なお、十二所神社は当寺の境内社でしたが、天保九年(1838年)に現社地に御遷座と伝わります。
----------


【写真 上(左)】 光触寺橋
【写真 下(右)】 入口
金沢街道から滑川にかかる光触寺橋を渡ったすこし東の山ぎわに、鎌倉の古寺らしい落ち着いたたたずまいをみせています。


【写真 上(左)】 寺号標と頬焼阿弥陀の石碑
【写真 下(右)】 札所碑
道から数段の階段。その先に寺号標、「頬焼阿弥陀」の石碑と札所碑。
山門は切妻桟瓦葺梁行二間の四脚門で見上げに山号扁額、門柱に「頬焼阿弥陀」の木銘が掛けられています。
平石敷の曲がり参道で、正面おくに一遍上人のお像がみえます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 一遍上人像
一遍上人お像の手前で参道の向きを変えて正面が本堂、向かって右手に「塩嘗地蔵尊」の覆堂。
本堂はおそらく寄棟造(宝形造かも)で銅板葺流れ向拝。向拝柱はありますが水引虹梁まわりは時宗寺院らしく比較的簡素です。
堂前の天水鉢には、時宗の宗紋「隅切り三」が刻されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 天水鉢
向拝上に「光觸寺」の寺号扁額。正面の障子戸がすこし開けられて堂内がのぞめますが、堂内は暗く仏像配置は定かではありません。

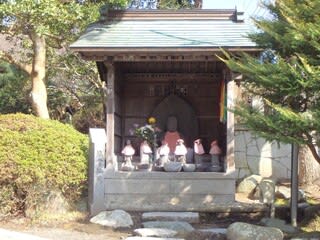
【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 塩嘗地蔵尊
塩嘗地蔵尊の覆堂は手前に六体の石像の六地蔵。おくに光背を背負われた石像の「塩嘗地蔵尊」が御座します。
御朱印は本堂向かって右手の風情ある庭園を回り込んだ庫裡にて拝受しました。お昼時は御朱印授与はお休みのようです。
札所は鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番の3つ。
鎌倉六阿弥陀霊場第6番の札所本尊は、御本尊の「頬焼阿弥陀」とみられます。
〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕
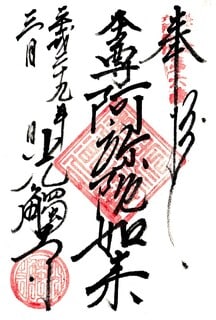
鎌倉三十三観音霊場第7番の札所本尊は、平安時代の作と伝わる定朝様の木造聖観音菩薩立像とみられます。(御本尊脇侍の快慶(安阿彌)作の聖観音も考えられますが、通常、阿弥陀三尊の脇侍の観音様は観音霊場の札所本尊にはなられないので、定朝様木造聖観音ではないでしょうか。)
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
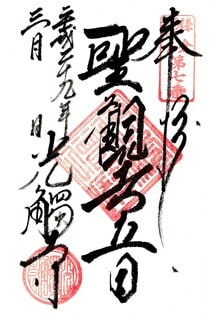
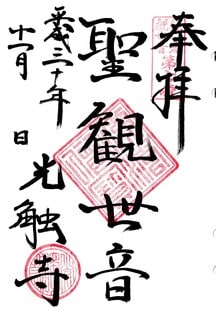
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉二十四地蔵霊場第5番は「塩嘗(鹽甞)地蔵尊」です。
その名称の由来は、『新編鎌倉志』によると、金沢・六浦の塩売りが商いで鎌倉に入るたびに光觸寺境内の石地藏に商売繁盛を願って塩をお供えしていたという説。この石地蔵が金色の光を放っていたのを塩売りが塩を打ちかけると光を放たれなくなったからという説などがあります。
どうやらこちらの石地蔵にはもともと塩を嘗められる、という伝承があったようです。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
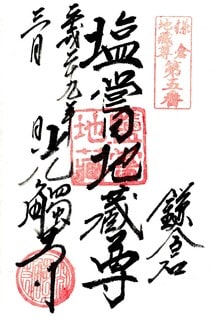
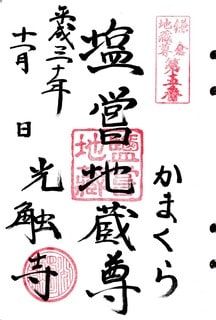
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
↑で、「当座は適宜端折ってご紹介します。」と書きましたが、すこしWeb検索しただけで出てくる出てくる、さすがに鎌倉のお寺です。
検索していくとキリがないので、今後は公式Web、境内由緒書、『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』、国・市の公的資料に絞ってまとめてみたいと思います。
3.飯盛山 寛喜寺 明王院
公式Web
鎌倉市十二所32
真言宗御室派
御本尊:不動明王(五大明王)
札所:鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番
公式Webおよび鎌倉市観光協会資料などによると、嘉禎元年(1235年)、鎌倉四代将軍藤原頼経公により建立。鎌倉将軍発願によって建立された、市内現存の唯一の寺院とのこと。
鎌倉幕府の鬼門の方角に当たる十二所に鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安し、古くから”五大堂”とも呼ばれています。
初代別当は開山の定豪律師(元鶴岡八幡宮別当)。以降、明王院別当職は四箇重職の一つに数えられ、鶴岡八幡宮、永福寺、勝長寿院とならぶ重職とされました。
『吾妻鏡』には、寛喜三年(1231年)、将軍御願寺として五大堂建立の沙汰があり、地相、方角、日時について執権、連署をはじめ、評定衆と陰陽師らが巡検したとあります。
『新編相模國風土記稿』によると、大行寺とも呼ばれたとあり、京の仁和寺直末のようです。
『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』によると、この五大堂の建立にあたってはすこぶる複雑な経緯があったようです。
寛喜三年(1231年)10月、五大堂建立の地として二階堂永福寺、大慈寺等を巡検。
『吾妻鏡』によると10月16日永福寺境内に建立の許可?が下されています。
しかし10月19日に「二階堂ノ地ヲ替ヘラレ甘縄ノ地ヲ巡検アリ。」 とあり、甘縄の地に変更となったようです。
11月18日「五大尊像ヲ造始ラル。」
嘉禎元年(1235年)正月15日、「五代尊堂門木作事始アリ。」
(正月)21日「精舎建立ノ事。是マテ北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」「曰 廿一日。御願五大堂建立事。相州武州。度々巡検。被選鎌倉中之勝地。去年雖被定城太郎甘縄地。猶不相叶。頗思食煩之処。相当干幕府鬼門方有此地。毛利蔵人入道西阿領也。拠為御祈祷。相應之所被点之。即被引地訖。仍今日先総門計被建之。」
↑ どうやら、この記述によると、甘縄の地に決まっていた建立地を幕府の鬼門にあたる毛利蔵人入道の領地(十二社?)に改めて総門を建立したようなのです。
甘縄は、安達義景拠点の地といわれています。
安達義景は、鎌倉幕府の有力御家人で北条氏縁戚でもあったため、宝治合戦(三浦氏の乱・宝治元年(1247年))では執権北条側について三浦氏を滅ぼし勢力を確保しましたが、後に義景の子泰盛は内管領・平頼綱との対立により霜月騒動(弘安八年(1285年))を引き起こし、安達一族は滅ぼされました。
霜月騒動ののち、鎌倉幕府は北条の得宗専制の時代に入ったとされます。
安達義景の正室は北条時房の娘(北条時政の孫)でしたが、側室に甲斐源氏の伴野(小笠原)時長の娘を迎えており、泰盛は小笠原の孫にあたります。
北条氏にとって安達氏はもともと侮りがたい存在であり、大きな勢力をもっていた甲斐源氏とつながりがあることも考えると、気を許せる相手ではなかったのでは。
五大明王は極めて強力な祈願仏であり、この祈願仏を安達氏の本拠・甘縄に置くことは、北条執権家として看過できなかったのかもしれません。
上記で「北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」の”煩”とは、このことをさしているのではないでしょうか。
嘉禎元年(1235年)6月29日、鶴岡八幡宮の定豪律師が導師となり、将軍頼経公が参堂して五大明王像の入佛(開眼)供養がなされて創建。
五大明王とは、不動明王、降三世明王、軍茶利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王(ないし烏枢沙摩明王)をさし、この五尊を供養する修法は”五壇法”と呼ばれ、安産祈願、息災、調伏、異国降伏などを目的として修される大法とされました。
”五壇法”は平安後期から密教寺院で隆盛し、神護寺ではすでに天長年間(824-834年)に五大堂が建立され、承和六年(839年)には東寺講堂の五大明王開眼供養の記録が残っています。
”五壇法”は官寺や有力氏族ゆかりの名刹で修されることが多く、政治的な色合いも強かったものとみられています。
五大堂(明王院)建立にあたり、幾度も候補地の巡検や方位や日時の校量がなされ、仏像の造立にあたっても細心の配慮がうかがわれるのは、このような”五壇法”(あるいは五大明王)の政治的な重みを示しているのではないでしょうか。
また、中世、大法(国家的祈祷・修法)の多くは、真言宗系(東密)では小野、広沢の二流(野沢十二流)で修されたと伝わります。
小野流は山科の小野、広沢流は嵯峨の広沢が語源とされており、現在の真言宗御室派につながる仁和御流は広沢流を代表する流れとして知られ、総本山の仁和寺は門跡寺院として高い格式をもちます。
鎌倉幕府鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安する五大堂(明王院)が真言宗御室派に属するのも、このような背景があってのことかもしれません。
『新編相模國風土記稿』によると、寺域鎮護の神祠(明王院鎮守)として春日社があり、北条時房、泰時等が参会して五大堂の東方に社地を定めたとあります。
春日社の現況は定かではありませんが、鎌倉四代将軍となった頼経公は、左大臣藤原(九条)道家の子で、春日社は藤原氏の氏神とされているので、そのゆかりで勧請されたのかもしれません。
同書によると山内にはかつて北斗堂があり、仁治元年(1240年)の事曳始は北条泰時が監臨。仁治二年10月に「新造北斗堂」。同月の供養には「将軍頼経公参堂」とあります。
北斗堂で修される(とみられる)北斗法は、主に貴人の息災延命のための修法とされますから、鎌倉将軍(あるいは北条氏執権)の息災延命を願っての建立かもしれません。
『新編相模國風土記稿』には、堂内に北斗七星像および一字金輪像が奉安されたとありますので、やはり北斗法が修されたとみられます。
なお、同書には「今廃シテ。堂址モ詳ナラス。」とあり、現存していないようです。
それにしてもやっぱり鎌倉の名刹、あまりにネタが多すぎて、どうしても文章が長くなります。
---------- (こちらは「境内撮影禁止」なので、写真はあまりありません。)


【写真 上(左)】 滑川からの明王院参道
【写真 下(右)】 山内入口
金沢街道明石橋のあたりから少し北側に入った山ふところにあります。
駐車場はなく、金沢街道沿いの有料パーキングを利用する必要があります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 冠木門
山内入口に「五大堂明王院」の寺号標。その先の冠木門から本堂に向かってまっすぐ参道が伸びています。
参道の階段手前に「境内撮影禁止」の掲示があるので、そこから先では撮影しておらず、堂宇などの詳細なレポはできません。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道から本堂-1
絶妙な位置にこんもりと山肌を背負った、南向きの明るい山内です。
背後は「鎌倉アルプス」とも呼ばれる山々に連なり、人気の天園ハイキングコースの登り口でもあります。


【写真 上(左)】 参道から本堂-2
【写真 下(右)】 本堂
参堂正面の本堂は、おそらく寄棟造茅葺きで格子戸に蔀戸を備えたやさしいイメージのつくり。
二棟ならびで、向かって右手が本堂、左手は客殿かもしれません。
参堂左手に叶地蔵、本堂右手に一願水掛不動尊、その手前に観音堂があります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 観音堂


【写真 上(左)】 本堂前
【写真 下(右)】 本堂(右)と客殿?(左)
庭園の設えも風流で、あまりに絵になるので素人カメラマンが殺到、例によって三脚立てまくりの傍若無人な撮影っぷりを展開したため、閉口したお寺さまがやむなく撮影禁止とされたのかも。
(ちなみにこちらのお寺さまの御朱印対応はとても親切です。)
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番の3つです。
また、御本尊の御朱印と、ご縁日には大聖歓喜天の御朱印も授与されています。
鎌倉十三仏霊場第1番の札所本尊は、御本尊の不動明王です。
鎌倉は禅寺が多く、不動明王が御本尊の寺院は意外に多くありません。
鎌倉幕府ゆかりの由緒をもたれるこちらのお不動さまが、鎌倉十三仏霊場第1番(不動明王)の札所本尊となられていることは、なるほど頷けるものがあります。
本堂・御本尊は毎月28日のご縁日に護摩供養がおこなわれ拝観することができます。
〔 御本尊・不動明王の御朱印 〕
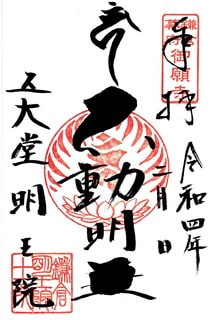
●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。札所印の位置に「鎌倉幕府御願寺」の印が捺されています。
〔 大聖歓喜天の御朱印(ご縁日のみ授与) 〕
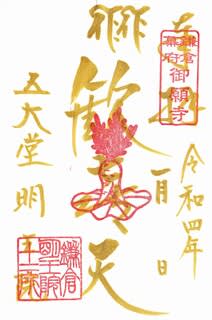
●主印は聖天供の供物、大根(蘿蔔根)の印。双身歓喜天の種子「ギャクギャク」の揮毫があります。
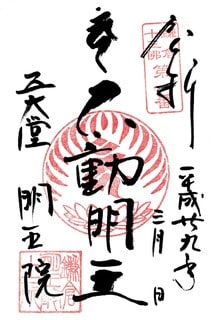
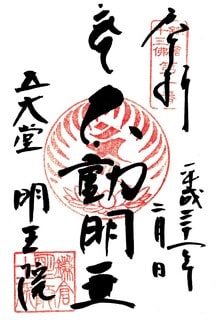
●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+宝珠)
【写真 上(左)】 御朱印帳書入(平成29年)
【写真 下(右)】 御朱印帳書入(平成31年)
鎌倉三十三観音霊場第8番の札所本尊は観音堂に御座す、十一面観世音菩薩です。
写真がないので詳細不明ですが、たしか入母屋造桟瓦葺妻入りで身舎幅を超える大がかりな向拝を備えていたかと思います。
また、障子扉が少し開けられ、堂前には札所板が掲げられていました。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
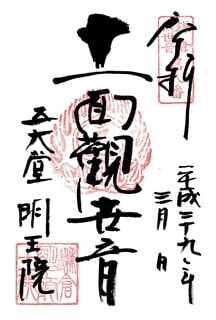
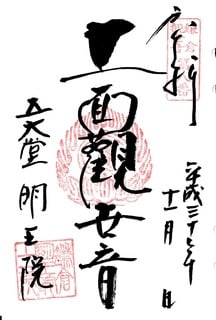
●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と思われます。
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉二十四地蔵霊場番外の札所本尊は参堂左手に御座す、叶地蔵尊です。
ガイドブックなどには載っていないこともありますが、鎌倉二十四地蔵霊場にはふたつの番外札所があります。(番外を含めると26札所)
こちらの叶地蔵尊と、円覚寺塔頭の伝宗庵の地蔵尊(現在は鎌倉国宝館に寄託)で、どちらも御朱印を拝受できます。
叶地蔵尊は露仏の石像ですが、背後に光背、右手に錫杖、左手に宝珠(如意珠)を持たれ蓮華座に座する存在感のあるおすがたです。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
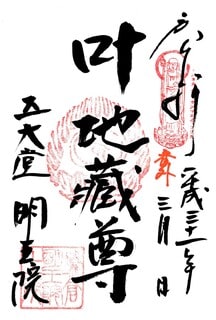
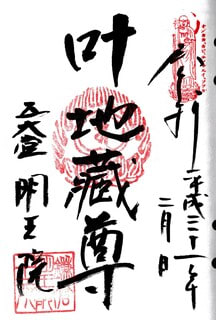
●主印は蓮華座+火焔宝珠+種子の御寶印で、種子は地蔵菩薩の「カ」と思われますがちがうかもしれません。御朱印帳書入の御朱印には「番外」の揮毫があります。
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
御朱印は山内左手の庫裡にて拝受できます。
鎌倉十三仏霊場第1番で、専用納経帳も頒布されています。
鎌倉二十四地蔵霊場の叶地蔵尊は、とくに札所掲示はありませんが、申告すれば快く授与いただけます。
ご縁日などには限定御朱印も授与されているようです。
4.稲荷山 浄妙寺
鎌倉市浄明寺3-8-31
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛(釈迦如来)
札所:御本尊(鎌倉五山第五位)、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)
鎌倉五山第五位の高い寺格をもつ、臨済宗建長寺派の名刹です。
文治四年(1188年)、足利宗家二代当主足利義兼により退耕行勇禅師を開山に創建と伝わります。
退耕禅師は四条氏の出とされる鶴岡八幡宮の供僧で、北条政子や源実朝公にも尊崇された高僧です。
当寺は鎌倉時代作とされる「木造退耕禅師坐像」を所蔵し、国重要文化財に指定されています。
退耕禅師は真言密教を学ばれたのち、鶴岡八幡宮の供僧となられ、永福寺、大慈寺など名刹の別当を務められました。
正治二年(1200年)栄西禅師(日本の臨済宗開祖)鎌倉下向の際、退耕禅師は寿福寺で参禅されたとも伝わり、建永元年(1206年)東大寺大勧進職。
承久元年(1219年)には高野山に金剛三昧院を開創され、禅密兼修の名僧としてその名を残されています。
また、退耕禅師は北条政子出家の際の戒師で、源実朝公の正室御台所坊門信子も禅師のもとで落飾したとされ、鎌倉将軍家の篤い帰依を受けました。
浄妙寺は当初は真言宗で極楽寺と号しました。
建長寺の開山蘭渓道隆(1213-1278年)の弟子、月峯了然が住職のとき臨済宗に改められ、正嘉年間(1257-59年)頃に寺号も浄妙寺と改めました。
中興開基は足利尊氏公の父、貞氏公で、室町時代は鎌倉公方の菩提寺として隆盛し、外門、総門、山門、仏殿、法堂方丈、禅堂、経堂など七堂伽藍を備え多くの塔頭を擁する大寺院であったと伝わります。
『新編鎌倉志』は、中興開基について「按ずるに、源尊氏の父、讃岐守貞氏を、浄妙寺殿貞山道観と号す。元弘元年九月五日逝去、当寺の旦那にて、当寺を修復の御浄妙寺と改めたると見へたり。昔は当寺を極楽寺と号すと。」と記しています。
歴代の往寺として約翁徳倹・高峰顕日・竺仙梵僊・天岸慧広などの名僧を輩出しています。
浄妙寺は鎌倉五山の第五位です。
鎌倉五山とは臨済宗寺院の寺格で鎌倉にある五つの高位の寺院をさし、もとはインドの五精舎十塔所にならって創設されたともいわれています。
京にも五山がありますが、京に先立ち鎌倉で五山が定められたとする説、もともとは鎌倉と京の寺院で構成されていたという説など諸説あるようです。
至徳三年(1386年)、室町幕府三代将軍・足利義満公が南禅寺を別格として五山之上とし、京都の天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺、鎌倉の建長寺、圓覚寺、壽福寺、浄智寺、浄妙寺をそれぞれ五山に決定し、以降固定化しました。
『新編鎌倉志』には、
「至徳三年七月、源義満、五山の座次を定め、建長寺を第一として、京師天竜寺の次也。圓覚寺を第二、壽福寺を第三、浄智寺を第四、浄妙寺を第五とす。是より先、座位の沙汰あらず。」とあります。
----------


【写真 上(左)】 金沢街道からの参道
【写真 下(右)】 山内入口
間違いやすいですが、このあたりの地名は「浄明寺」、寺号は「浄妙寺」です。
かつては寺社から地名をいただく場合、そのままの字を写すことをはばかり、一字を替えて名付けることがあったそうです。こちらもその例かもしれません。
金沢街道沿いに駐車場があり、そこから北に向かってまっすぐ参道が延びています。

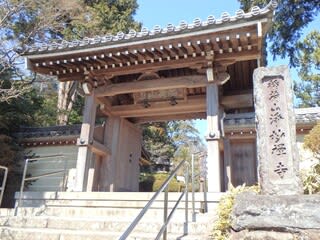
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標と山門
さらに進むと山門。切妻屋根本瓦葺の脇門付き四脚門で、さすがに名刹らしい風格を備えています。
くぐって左脇が拝観受付で、御朱印もこちらで授与されています。
拝観前に御朱印帳をお預けし、拝観後に受け取るシステムで、ご親切な対応をいただけます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 冬の参道-1
【写真 下(右)】 冬の参道-2
低木メイン、南傾のすこぶる明るい山内で、うっそうと幽邃な寺院の多い鎌倉の禅寺では異色ともいえる開放感があります。
かつては七堂伽藍や塔頭を連ねたこの名刹も、いまは総門(山門)、本堂、客殿、庫裏という比較的シンプルな伽藍構成となっています。
境内は国指定史跡に指定されています。


【写真 上(左)】 5月の参道
【写真 下(右)】 本堂下


【写真 上(左)】 5月の本堂
【写真 下(右)】 本堂と客殿?
山門から本堂に向かってまっすぐに参道が延びています。
おそらく寄棟造銅板葺。円筒状の大棟と、起り気味の屋根が美しい本堂です。
左手にある客殿?の入母屋屋根も銅板葺起り気味で、本堂と絶妙なバランスを保ち、本堂身舎右側に設えられた唐破風もいいアクセント。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 客殿?
向拝柱はなく、桁行に格子戸が連なり、中央見上げには鎌倉三十三観音霊場の札所板と「方丈」の扁額が掲げられています。
向拝の扉は開け放たれ、堂内をうかがうことができます。


【写真 上(左)】 本堂向拝-1
【写真 下(右)】 本堂の札所板と扁額


【写真 上(左)】 本堂向拝-2
【写真 下(右)】 左手からの本堂


【写真 上(左)】 右が本堂、左が開山堂
【写真 下(右)】 開山堂扁額
本堂裏手には別棟の開山堂が連接しています。
こちらは、開山塔(祖塔、光明院)の流れを汲む堂宇と思われ、『新編鎌倉志』では、「開山(退耕行勇禅師)の像あり。又源直義像あり。又光明院殿本覺大姉と書たる位牌(裏に法樂寺殿嫡女)」とあり、足利家三代目当主義氏公の院号は法樂寺殿、息女(四条隆親室)の院号は光明院殿と伝わるため、義氏公の息女とのゆかりを説いています。

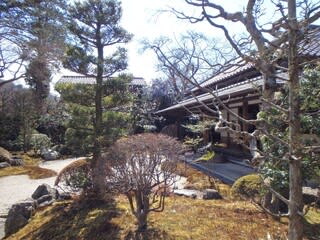
【写真 上(左)】 「喜泉庵」入口
【写真 下(右)】 枯山水庭園と「喜泉庵」


【写真 上(左)】 「喜泉庵」
【写真 下(右)】 「喜泉庵」の軒先
本堂左手に枯山水庭園と茶堂「喜泉庵」があり、枯山水の庭を眺めつつ茶菓をいただくことができます。


【写真 上(左)】 石窯ガーデンテラス
【写真 下(右)】 石窯ガーデンテラスのパン
そこから小道を登っていくと、スコットランド人ガーデンデザイナーが手掛けるイングリッシュガーデンと築90年の洋館を改装したベーカリーレストラン「石窯ガーデンテラス」。
ふつうお寺にイングリッシュガーデンやパン工房はイメージ的に違和感がありますが、このすこぶる明るい浄妙寺の境内では不思議なほどマッチしています。


【写真 上(左)】 直義公墓所への道
【写真 下(右)】 直義公墓所
「石窯ガーデンテラス」から北側に延びる小道は足利直義公の墓所。
小道分岐から西側すぐが6.(浄明寺)熊野神社の社頭になりますが、ゲートがあるのでここから直接熊野神社へは行けません。
ここまで来ると、展望が開け、滑川の谷越しに鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)を望めます。


【写真 上(左)】 ゲートの先が熊野神社の社頭
【写真 下(右)】 衣張山
この辺りは足利直義公ゆかりの史跡があったところで、少しく辿ってみます。
『新編鎌倉志』から浄妙寺山内図を転載します。(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)
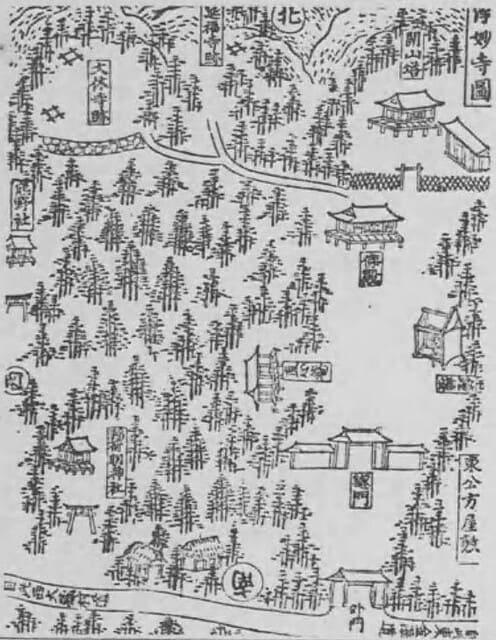
この図をみると、現在の「石窯ガーデンテラス」の北側山手あたりに延福寺、「石窯ガーデンテラス」あたりに大休寺、その西側に熊野社の文字がみえます。
〔延福寺〕
雲谷山と号し、足利尊氏公の兄君で早世した足利左馬助高義公の菩提所とされます。
『新編相模國風土記稿』には「延福寺蹟。浄妙寺域内西北ニアリ。足利左馬頭高義(尊氏ノ兄)。契忍禅尼(讃岐守貞氏側室。高義母)。追福ノ為。爰(ここ)ニ創建シ。山ヲ雲谷ト名ツケ。足菴(麟和尚)ヲ開山粗トスト云フ。観應三年二月廿六日。直義入道恵源。当寺に在テ頓滅セリ。管領成氏ノ時ハ。年々二月。必当寺参詣アル事。廃セシ年代詳ナラス。」
とあり、こちらが足利直義公の終焉の地とされています。
足利直義公は、足利貞氏公の三男で室町幕府初代将軍足利尊氏公の同母弟です。
室町幕府開設・草創に活躍し、「三条殿」と称され卓越した政治的手腕により実質的な幕政の最高指導者であったとみられています。
政治手法は比較的保守的とされ、革新派の執事の高師直との間に確執を生じ、養子の直冬の処遇問題も絡んで観応の擾乱が勃発。薩埵峠の戦いで兄の尊氏に敗れ鎌倉に蟄居の後、急死を遂げたとされます。
禅宗を篤く敬って庇護し、 臨済宗高僧の夢窓疎石(夢窓国師)との対話は『夢中問答集』として出版され、尊氏・夢窓疎石とともに後醍醐天皇の菩提のために天龍寺を創建するなどの功績が残っています。
その死因についてはさまざまな説があり、『新編相模國風土記稿』でも含みのある表現をしていますが、ここでは触れません。
〔大休寺〕
『新編鎌倉志』から引用します。
「熊野山(ゆうやさん)と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。(中略)直義の位牌は浄光明寺にもあり。」
足利直義公の旧宅であり菩提所であったことが記されています。
『新編相模國風土記稿』によると、直義公の創建、月山希一開祖とのこと。
歴史ある名刹だけに境内、近隣に多くの寺社・旧跡が残ります。
浄妙寺の東、芝野には尊氏公の旧宅で代々関東管領の屋敷となった「公方屋敷」がありました。
境内墓地には尊氏公の父、貞氏公の墓と伝わる宝篋印塔もあり、浄妙寺は足利氏とゆかりのふかい寺院です。
山門をくぐらず、右手の道をすすむと鎌足稲荷神社の参道です。
上の浄妙寺山内図では、稲荷明神社は山門向かって左(西側)に記されていますが、鎌足稲荷神社は山門の右手(東側)に位置します。
急な階段を登った先が神さびた境内。木立のなかに一間社流造のお社が御鎮座しています。

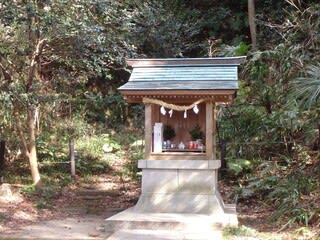
【写真 上(左)】 鎌足稲荷神社参道.
【写真 下(右)】 鎌足稲荷神社
鎌足稲荷神社について、『新編鎌倉志』には「寺の西の岡にあり。浄妙寺の鎮守なり。(中略)往古の縁起うせて、何の御神とも不知といへり。偖(さて)は此御社は、大織冠の御鎮座か。山なる鎮守は、彼霊験の鎌を納められし、鎌倉山是なりとをぼゆるとあり。」とあります。
”大織冠”とは大化三年(647年)から数十年間日本で用いられた冠位(冠位一三階の最高位)で、史上藤原鎌足公だけが授かったとされます。
よって、同書では御祭神は藤原鎌足公であり、このお社が”鎌倉”の地名の発祥であることにまで言及しています。
実際、山内裏山にはいまも「鎌足稲荷」と呼ばれるお社が祀られ、開山堂には「木造藤原鎌足像」が安置されています。
鎌足稲荷神社の由緒書には、ご祭神 稲荷大神とあり、「大織冠藤原鎌足公は乳児の時、稲荷大神さまから鎌を授けられ、以来、常にお護りとして身につけ、大神さまの加護を得られました。(略)大化二年(646年)東国に向かわれ、相模国由井の里に宿泊されました。その夜『あなたに鎌を授けて守護してきたが、今や(蘇我)入鹿討伐という宿願をなし得たから、授けた鎌を我が地に奉納しなさい』との神告があり、お告げのままに鎌を埋納したことによるとされています。」とあります。
これによると、鎌足公は創祀に深く関わられているものの、ご祭神は稲荷大神ということになります。


【写真 上(左)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)参道
【写真 下(右)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)
本寂堂は鎌足稲荷神社参道右手の階段の上にあり、現在の御祭神は三宝荒神です。
『新編相模國風土記稿』には、「荒神。不動ヲ安ス。足利義兼。多年秘崇空海所筆授。荒神及不動二軸。(中略)令佛工運慶彫所夢二尊之頭身。」とあります。
はっきりとはわかりませんが、義兼公が尊崇していた弘法大師空海お筆の荒神および不動尊の霊夢を受け、運慶に命じて二尊の像を彫らせたという内容に思えます。
また、同書によると本寂堂に「藤原鎌足像」が安置されていたようです。
ただし、現在は参道階段が閉ざされているので、階段下からの参拝となります。
また、Web上では、同寺に淡島明神立像が奉安されていることから、婦人病の祈願所とされてきた、という情報もみられます。
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の2つ。
別に御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印を授与されているので御朱印は3種です。
御本尊の釋迦牟尼佛は本堂に御座します。
『新編相模國風土記稿』には「佛殿。古ハ彌陀(立像陳和卿作。是寺伝累記ニ見エタル。二位禅尼カ。白檀ノ阿彌陀ナルヘシ。)ヲ本尊トセシカ今此ヲ外殿ニ置キ釋迦。(是モ寺伝累記ニ見エシ。建暦三年(1213年)実朝カ新造セシ。佛體ナルニヤ。)本尊トス。」とあり、これを信じると当初の佛殿御本尊は阿弥陀如来だった可能性があり、後に、鎌倉三代将軍実朝公新造の釋迦牟尼佛が御本尊となられたことになるます。
〔 御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印 〕
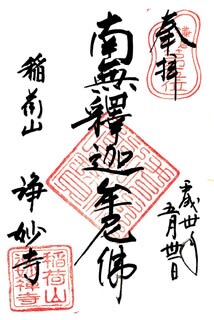
●主印は三寶印、揮毫は「釋迦牟尼佛」で「鎌倉五山第五位」の印判が捺されています。
鎌倉三十三観音霊場第9番の札所本尊は本堂に御座す、聖観世音菩薩です。
上記のとおり本堂向拝に観音霊場の札所板が掲げられています。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
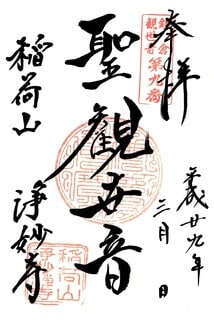
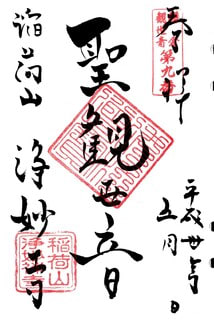
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の札所本尊も御本尊のお釈迦様とみられます。
御本尊(鎌倉五山)の御朱印揮毫は「南無釋迦牟尼佛」、鎌倉十三仏霊場の御朱印揮毫は「釋迦如来」となっています。
「南無」とは”帰依する”というほどの意味で、「釋迦牟尼佛に帰依します」の意をあらわします。
禅宗寺院の御朱印で多くみられる揮毫です。
これに対し「釋迦如来」は禅宗以外の寺院御朱印で比較的よくみられます。
個人的には「釋迦牟尼佛」は釈尊(歴史的な聖者・修行者あるいは仏教の教主としての存在)、「釋迦如来」は如来(浄土を主宰される悟りを開いた佛)の一尊としての釋迦如来をあらわしているような感じがしていますが、ぜんぜん違うかもしれません。
〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕
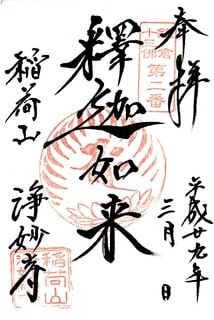
●主印は釋迦如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多いですが、こちらもその様式です。
鎌倉に女子をデートに誘う向きも少なくないかと思いますが、こちらのお寺さんはわりあい空いているし、受付のご対応も親切だし、雰囲気は明るいし、歴史の香りも豊かで、和様それぞれの飲食処も完備のうえに達筆の御朱印もいただけるので、かなりポイントを稼げる(笑)のではないでしょうか。
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。
【 BGM 】
■ 空に近い週末 - 今井美樹
■ Just Be Yourself - 杏里
■ 海のキャトル・セゾン - とみたゆう子
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へ
A.朝夷奈口
鎌倉市の北東側(横横道路「朝比奈IC」)から入るルートで、十二所、浄明寺、二階堂、西御門、雪の下の寺社をご紹介します。
まずはリストです。
1.十二所神社
神奈川県神社庁Web
鎌倉市十二所285
御祭神:天神七柱、地神五柱
旧社格:村社、旧十二所村鎮守


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
「神奈川県神社庁Web」によると、創建は弘安元年(1278年)。
『十二所権現社再建記』には、「天保八年(1837年)明王院別所恵法が社頭再営を志し、氏子三十余軒により天保九年(1838年)、現在地に再建」とあるそうで、明治維新の際、十二所神社と改称しています。
『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項に「熊野社 村の鎮守トス。十二所ノ村名是ニ発起スト云フヘシ。」とあります。
以上から、当初光觸寺境内に熊野社、ないし熊野(十二所)権現社として御鎮座で天保九年(1838年)、現社地に御遷座されたとみられます。
----------
県道204号金沢街道の鎌倉霊園下あたりから鋭角に切り返したあたりにありますが、駐車場はなく、金沢街道沿いの有料Pを利用する必要があります。
滑川の谷筋に面した山肌にあり、十数段の参道階段を昇ると石灯籠一対と端正な石造明神鳥居。その先に入母屋造銅板葺流れ向拝の拝殿。
ちなみに「熊野三所権現」とは、ふつう家津美御子(けつみみこ、スサノオ、本地阿弥陀如来)、速玉(はやたま、イザナギ、本地薬師如来)、牟須美(むすび、イザナミ、本地千手観世音菩薩)をさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。
東京・新宿の十二社の地名も、当地の熊野神社(角筈十二社)に十二所権現を勧請した由緒によるものとされています。
現在の御祭神は「天神七柱・地神五柱」で計十二柱となりますが、こちらが上記の「熊野十二所権現」の神々と符合しているかはわかりません。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、海老虹梁はなく手挟のみ、中備に波の上で踊る二匹の兎の見事な彫刻(波乗り兎)が彫り込まれています。
NPO法人鎌倉ガイド協会「古都鎌倉史跡めぐり」では、この「波乗り兎」の由来を熊野の(兎の)焼身供養に求めています。
熊野権現と兎の所縁については、山口県長門市三隅兎渡谷村の熊野権現の伝承、山形県南陽市の日本三熊野のひとつ熊野神社本殿の「三羽の隠しうさぎ」などが知られていますが、いずれもどうして兎なのかの理由がわからず、当社の兎さんについてもWebで追ってみましたが現時点ではわかりません。

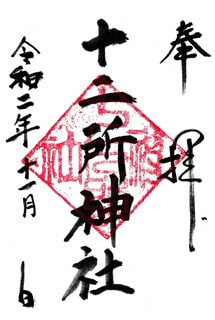
【写真 上(左)】 中備のうさぎの彫刻
【写真 下(右)】 御朱印
向拝正面は桟唐戸(閉扉)で上方に「十二所神社」の扁額。本殿は拝殿に連接し、背後の岩壁に接した(おそらく)切妻造妻入りの覆屋のなかと思われますが詳細不明です。
境内社として本殿後背に山の神、疱瘡神、宇佐八幡、地主神などが御鎮座されます。
通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。
※さすがに鎌倉。しょっぱなからWeb情報があふれています。
以降の寺社はさらに情報量が増えると思いますので、当座は適宜端折ってご紹介します。
2.岩蔵山 長春院 光觸寺
公式Web
鎌倉市十二所793
時宗
御本尊:阿弥陀如来(阿弥陀三尊)
札所:鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番
十二所にある時宗寺院で、通常は「光触寺」と書かれ、もともとは「藤觸山」と号していたようです。境内由緒書、公式Webなどからご由緒を追ってみます。
創建は弘安元年(1278年)、開山は作阿上人、開基は一遍上人と伝わります。作阿上人はもともと真言宗の僧でしたが、一遍上人遊行の途次、一遍上人に帰依して時宗に改めたと伝わります。
御本尊の阿弥陀如来は「頬焼阿弥陀」(ほおやけのあみだ)として知られ、当寺に伝わる『頬焼阿弥陀縁起』によると、鎌倉時代のはじめ、仏師運慶が町の局(まちのつぼね)の求めに応じて阿弥陀三尊像を刻したもので、ある時、町局に仕える万歳法師が盗みの疑いを受け頬に焼印を捺されたましたが、不思議なことに法師の頬には焼痕が残らず運慶作の阿弥陀仏の頬につきました。
たびたび修復しても阿弥陀仏の頬の焼痕はついに消えずにいつしか「頬焼阿弥陀」と呼ばれるようになったとの由。
『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項によると、その後、町の局は出家して比企谷に岩蔵寺という一宇(カナヤキ(火印)堂とも)を建立し、件の阿弥陀三尊像を御本尊として安置。
建長三年(1251年)、町の局はこの阿弥陀さまの前で端然と往生されたと伝わります。
『光触寺阿弥陀三尊像と頬焼阿弥陀縁起』(美術研究第十三集・熊谷宣夫氏)では、この町の局にかかわる縁起譚は、鎌倉時代中期の仏教説話集『沙石集』巻二の「阿彌陀の利益の事」に類似すると述べられ、実際、対照してもほぼ同様の内容のようです。
『新編鎌倉志』でも光觸寺の項で『沙石集』の説話を引用紹介しています。
『新編相模國風土記稿』に「(阿弥陀像の)厨子ハ(足利)持氏寄進ノ物ナリトソ。(足利)尊氏。氏満。満兼。持氏ノ碑アリ。」とあるので、足利氏重代の尊崇を集めたとも考えられます。
複数のWeb記事に、弘安元年(1278年)に岩蔵寺は現在地へと移ったとあるので、この移転時に岩蔵寺を光觸寺と改号し創建とされたのかもしれません。
寄木造漆箔玉眼の御本尊阿弥陀如来像は両脇侍立像(観音・勢至)とともに「木造阿弥陀如来及両脇侍立像」(鎌倉・彫刻・3躯)、として国重要文化財に指定され、「紙本淡彩頬燒阿弥陀縁起」(鎌倉・絵画・2巻)も国重要文化財に指定されています。
観音像は快慶(安阿彌)、勢至像は湛慶作とも伝わる名作で、後醍醐天皇御宸筆の寺号勅額も蔵します。
なお、十二所神社は当寺の境内社でしたが、天保九年(1838年)に現社地に御遷座と伝わります。
----------


【写真 上(左)】 光触寺橋
【写真 下(右)】 入口
金沢街道から滑川にかかる光触寺橋を渡ったすこし東の山ぎわに、鎌倉の古寺らしい落ち着いたたたずまいをみせています。


【写真 上(左)】 寺号標と頬焼阿弥陀の石碑
【写真 下(右)】 札所碑
道から数段の階段。その先に寺号標、「頬焼阿弥陀」の石碑と札所碑。
山門は切妻桟瓦葺梁行二間の四脚門で見上げに山号扁額、門柱に「頬焼阿弥陀」の木銘が掛けられています。
平石敷の曲がり参道で、正面おくに一遍上人のお像がみえます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 一遍上人像
一遍上人お像の手前で参道の向きを変えて正面が本堂、向かって右手に「塩嘗地蔵尊」の覆堂。
本堂はおそらく寄棟造(宝形造かも)で銅板葺流れ向拝。向拝柱はありますが水引虹梁まわりは時宗寺院らしく比較的簡素です。
堂前の天水鉢には、時宗の宗紋「隅切り三」が刻されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 天水鉢
向拝上に「光觸寺」の寺号扁額。正面の障子戸がすこし開けられて堂内がのぞめますが、堂内は暗く仏像配置は定かではありません。

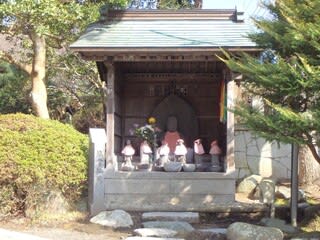
【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 塩嘗地蔵尊
塩嘗地蔵尊の覆堂は手前に六体の石像の六地蔵。おくに光背を背負われた石像の「塩嘗地蔵尊」が御座します。
御朱印は本堂向かって右手の風情ある庭園を回り込んだ庫裡にて拝受しました。お昼時は御朱印授与はお休みのようです。
札所は鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番の3つ。
鎌倉六阿弥陀霊場第6番の札所本尊は、御本尊の「頬焼阿弥陀」とみられます。
〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕
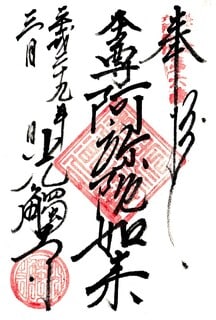
鎌倉三十三観音霊場第7番の札所本尊は、平安時代の作と伝わる定朝様の木造聖観音菩薩立像とみられます。(御本尊脇侍の快慶(安阿彌)作の聖観音も考えられますが、通常、阿弥陀三尊の脇侍の観音様は観音霊場の札所本尊にはなられないので、定朝様木造聖観音ではないでしょうか。)
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
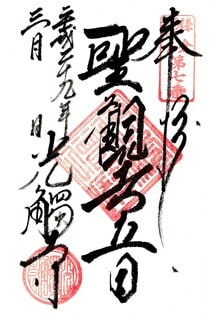
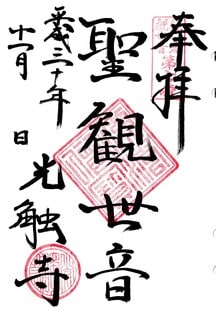
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉二十四地蔵霊場第5番は「塩嘗(鹽甞)地蔵尊」です。
その名称の由来は、『新編鎌倉志』によると、金沢・六浦の塩売りが商いで鎌倉に入るたびに光觸寺境内の石地藏に商売繁盛を願って塩をお供えしていたという説。この石地蔵が金色の光を放っていたのを塩売りが塩を打ちかけると光を放たれなくなったからという説などがあります。
どうやらこちらの石地蔵にはもともと塩を嘗められる、という伝承があったようです。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
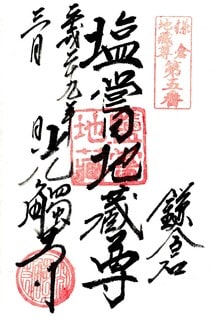
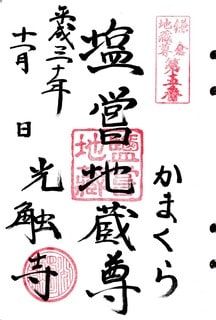
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
↑で、「当座は適宜端折ってご紹介します。」と書きましたが、すこしWeb検索しただけで出てくる出てくる、さすがに鎌倉のお寺です。
検索していくとキリがないので、今後は公式Web、境内由緒書、『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』、国・市の公的資料に絞ってまとめてみたいと思います。
3.飯盛山 寛喜寺 明王院
公式Web
鎌倉市十二所32
真言宗御室派
御本尊:不動明王(五大明王)
札所:鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番
公式Webおよび鎌倉市観光協会資料などによると、嘉禎元年(1235年)、鎌倉四代将軍藤原頼経公により建立。鎌倉将軍発願によって建立された、市内現存の唯一の寺院とのこと。
鎌倉幕府の鬼門の方角に当たる十二所に鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安し、古くから”五大堂”とも呼ばれています。
初代別当は開山の定豪律師(元鶴岡八幡宮別当)。以降、明王院別当職は四箇重職の一つに数えられ、鶴岡八幡宮、永福寺、勝長寿院とならぶ重職とされました。
『吾妻鏡』には、寛喜三年(1231年)、将軍御願寺として五大堂建立の沙汰があり、地相、方角、日時について執権、連署をはじめ、評定衆と陰陽師らが巡検したとあります。
『新編相模國風土記稿』によると、大行寺とも呼ばれたとあり、京の仁和寺直末のようです。
『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』によると、この五大堂の建立にあたってはすこぶる複雑な経緯があったようです。
寛喜三年(1231年)10月、五大堂建立の地として二階堂永福寺、大慈寺等を巡検。
『吾妻鏡』によると10月16日永福寺境内に建立の許可?が下されています。
しかし10月19日に「二階堂ノ地ヲ替ヘラレ甘縄ノ地ヲ巡検アリ。」 とあり、甘縄の地に変更となったようです。
11月18日「五大尊像ヲ造始ラル。」
嘉禎元年(1235年)正月15日、「五代尊堂門木作事始アリ。」
(正月)21日「精舎建立ノ事。是マテ北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」「曰 廿一日。御願五大堂建立事。相州武州。度々巡検。被選鎌倉中之勝地。去年雖被定城太郎甘縄地。猶不相叶。頗思食煩之処。相当干幕府鬼門方有此地。毛利蔵人入道西阿領也。拠為御祈祷。相應之所被点之。即被引地訖。仍今日先総門計被建之。」
↑ どうやら、この記述によると、甘縄の地に決まっていた建立地を幕府の鬼門にあたる毛利蔵人入道の領地(十二社?)に改めて総門を建立したようなのです。
甘縄は、安達義景拠点の地といわれています。
安達義景は、鎌倉幕府の有力御家人で北条氏縁戚でもあったため、宝治合戦(三浦氏の乱・宝治元年(1247年))では執権北条側について三浦氏を滅ぼし勢力を確保しましたが、後に義景の子泰盛は内管領・平頼綱との対立により霜月騒動(弘安八年(1285年))を引き起こし、安達一族は滅ぼされました。
霜月騒動ののち、鎌倉幕府は北条の得宗専制の時代に入ったとされます。
安達義景の正室は北条時房の娘(北条時政の孫)でしたが、側室に甲斐源氏の伴野(小笠原)時長の娘を迎えており、泰盛は小笠原の孫にあたります。
北条氏にとって安達氏はもともと侮りがたい存在であり、大きな勢力をもっていた甲斐源氏とつながりがあることも考えると、気を許せる相手ではなかったのでは。
五大明王は極めて強力な祈願仏であり、この祈願仏を安達氏の本拠・甘縄に置くことは、北条執権家として看過できなかったのかもしれません。
上記で「北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」の”煩”とは、このことをさしているのではないでしょうか。
嘉禎元年(1235年)6月29日、鶴岡八幡宮の定豪律師が導師となり、将軍頼経公が参堂して五大明王像の入佛(開眼)供養がなされて創建。
五大明王とは、不動明王、降三世明王、軍茶利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王(ないし烏枢沙摩明王)をさし、この五尊を供養する修法は”五壇法”と呼ばれ、安産祈願、息災、調伏、異国降伏などを目的として修される大法とされました。
”五壇法”は平安後期から密教寺院で隆盛し、神護寺ではすでに天長年間(824-834年)に五大堂が建立され、承和六年(839年)には東寺講堂の五大明王開眼供養の記録が残っています。
”五壇法”は官寺や有力氏族ゆかりの名刹で修されることが多く、政治的な色合いも強かったものとみられています。
五大堂(明王院)建立にあたり、幾度も候補地の巡検や方位や日時の校量がなされ、仏像の造立にあたっても細心の配慮がうかがわれるのは、このような”五壇法”(あるいは五大明王)の政治的な重みを示しているのではないでしょうか。
また、中世、大法(国家的祈祷・修法)の多くは、真言宗系(東密)では小野、広沢の二流(野沢十二流)で修されたと伝わります。
小野流は山科の小野、広沢流は嵯峨の広沢が語源とされており、現在の真言宗御室派につながる仁和御流は広沢流を代表する流れとして知られ、総本山の仁和寺は門跡寺院として高い格式をもちます。
鎌倉幕府鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安する五大堂(明王院)が真言宗御室派に属するのも、このような背景があってのことかもしれません。
『新編相模國風土記稿』によると、寺域鎮護の神祠(明王院鎮守)として春日社があり、北条時房、泰時等が参会して五大堂の東方に社地を定めたとあります。
春日社の現況は定かではありませんが、鎌倉四代将軍となった頼経公は、左大臣藤原(九条)道家の子で、春日社は藤原氏の氏神とされているので、そのゆかりで勧請されたのかもしれません。
同書によると山内にはかつて北斗堂があり、仁治元年(1240年)の事曳始は北条泰時が監臨。仁治二年10月に「新造北斗堂」。同月の供養には「将軍頼経公参堂」とあります。
北斗堂で修される(とみられる)北斗法は、主に貴人の息災延命のための修法とされますから、鎌倉将軍(あるいは北条氏執権)の息災延命を願っての建立かもしれません。
『新編相模國風土記稿』には、堂内に北斗七星像および一字金輪像が奉安されたとありますので、やはり北斗法が修されたとみられます。
なお、同書には「今廃シテ。堂址モ詳ナラス。」とあり、現存していないようです。
それにしてもやっぱり鎌倉の名刹、あまりにネタが多すぎて、どうしても文章が長くなります。
---------- (こちらは「境内撮影禁止」なので、写真はあまりありません。)


【写真 上(左)】 滑川からの明王院参道
【写真 下(右)】 山内入口
金沢街道明石橋のあたりから少し北側に入った山ふところにあります。
駐車場はなく、金沢街道沿いの有料パーキングを利用する必要があります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 冠木門
山内入口に「五大堂明王院」の寺号標。その先の冠木門から本堂に向かってまっすぐ参道が伸びています。
参道の階段手前に「境内撮影禁止」の掲示があるので、そこから先では撮影しておらず、堂宇などの詳細なレポはできません。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道から本堂-1
絶妙な位置にこんもりと山肌を背負った、南向きの明るい山内です。
背後は「鎌倉アルプス」とも呼ばれる山々に連なり、人気の天園ハイキングコースの登り口でもあります。


【写真 上(左)】 参道から本堂-2
【写真 下(右)】 本堂
参堂正面の本堂は、おそらく寄棟造茅葺きで格子戸に蔀戸を備えたやさしいイメージのつくり。
二棟ならびで、向かって右手が本堂、左手は客殿かもしれません。
参堂左手に叶地蔵、本堂右手に一願水掛不動尊、その手前に観音堂があります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 観音堂


【写真 上(左)】 本堂前
【写真 下(右)】 本堂(右)と客殿?(左)
庭園の設えも風流で、あまりに絵になるので素人カメラマンが殺到、例によって三脚立てまくりの傍若無人な撮影っぷりを展開したため、閉口したお寺さまがやむなく撮影禁止とされたのかも。
(ちなみにこちらのお寺さまの御朱印対応はとても親切です。)
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番の3つです。
また、御本尊の御朱印と、ご縁日には大聖歓喜天の御朱印も授与されています。
鎌倉十三仏霊場第1番の札所本尊は、御本尊の不動明王です。
鎌倉は禅寺が多く、不動明王が御本尊の寺院は意外に多くありません。
鎌倉幕府ゆかりの由緒をもたれるこちらのお不動さまが、鎌倉十三仏霊場第1番(不動明王)の札所本尊となられていることは、なるほど頷けるものがあります。
本堂・御本尊は毎月28日のご縁日に護摩供養がおこなわれ拝観することができます。
〔 御本尊・不動明王の御朱印 〕
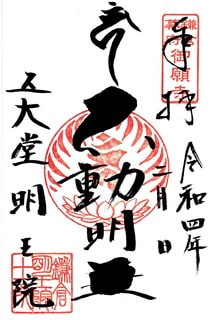
●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。札所印の位置に「鎌倉幕府御願寺」の印が捺されています。
〔 大聖歓喜天の御朱印(ご縁日のみ授与) 〕
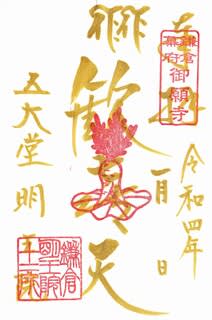
●主印は聖天供の供物、大根(蘿蔔根)の印。双身歓喜天の種子「ギャクギャク」の揮毫があります。
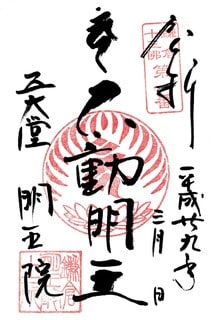
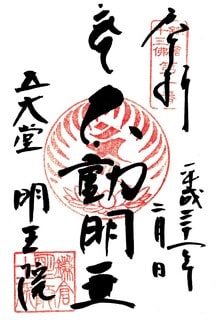
●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+宝珠)
【写真 上(左)】 御朱印帳書入(平成29年)
【写真 下(右)】 御朱印帳書入(平成31年)
鎌倉三十三観音霊場第8番の札所本尊は観音堂に御座す、十一面観世音菩薩です。
写真がないので詳細不明ですが、たしか入母屋造桟瓦葺妻入りで身舎幅を超える大がかりな向拝を備えていたかと思います。
また、障子扉が少し開けられ、堂前には札所板が掲げられていました。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
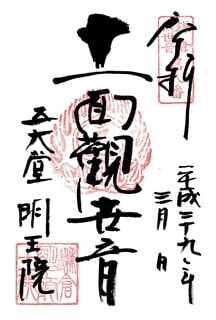
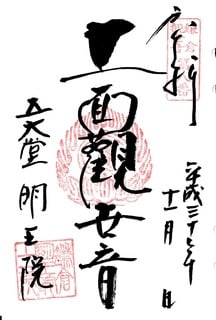
●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と思われます。
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉二十四地蔵霊場番外の札所本尊は参堂左手に御座す、叶地蔵尊です。
ガイドブックなどには載っていないこともありますが、鎌倉二十四地蔵霊場にはふたつの番外札所があります。(番外を含めると26札所)
こちらの叶地蔵尊と、円覚寺塔頭の伝宗庵の地蔵尊(現在は鎌倉国宝館に寄託)で、どちらも御朱印を拝受できます。
叶地蔵尊は露仏の石像ですが、背後に光背、右手に錫杖、左手に宝珠(如意珠)を持たれ蓮華座に座する存在感のあるおすがたです。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
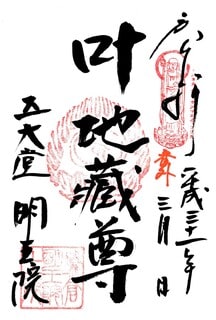
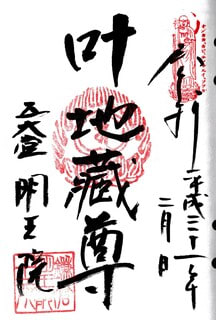
●主印は蓮華座+火焔宝珠+種子の御寶印で、種子は地蔵菩薩の「カ」と思われますがちがうかもしれません。御朱印帳書入の御朱印には「番外」の揮毫があります。
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
御朱印は山内左手の庫裡にて拝受できます。
鎌倉十三仏霊場第1番で、専用納経帳も頒布されています。
鎌倉二十四地蔵霊場の叶地蔵尊は、とくに札所掲示はありませんが、申告すれば快く授与いただけます。
ご縁日などには限定御朱印も授与されているようです。
4.稲荷山 浄妙寺
鎌倉市浄明寺3-8-31
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛(釈迦如来)
札所:御本尊(鎌倉五山第五位)、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)
鎌倉五山第五位の高い寺格をもつ、臨済宗建長寺派の名刹です。
文治四年(1188年)、足利宗家二代当主足利義兼により退耕行勇禅師を開山に創建と伝わります。
退耕禅師は四条氏の出とされる鶴岡八幡宮の供僧で、北条政子や源実朝公にも尊崇された高僧です。
当寺は鎌倉時代作とされる「木造退耕禅師坐像」を所蔵し、国重要文化財に指定されています。
退耕禅師は真言密教を学ばれたのち、鶴岡八幡宮の供僧となられ、永福寺、大慈寺など名刹の別当を務められました。
正治二年(1200年)栄西禅師(日本の臨済宗開祖)鎌倉下向の際、退耕禅師は寿福寺で参禅されたとも伝わり、建永元年(1206年)東大寺大勧進職。
承久元年(1219年)には高野山に金剛三昧院を開創され、禅密兼修の名僧としてその名を残されています。
また、退耕禅師は北条政子出家の際の戒師で、源実朝公の正室御台所坊門信子も禅師のもとで落飾したとされ、鎌倉将軍家の篤い帰依を受けました。
浄妙寺は当初は真言宗で極楽寺と号しました。
建長寺の開山蘭渓道隆(1213-1278年)の弟子、月峯了然が住職のとき臨済宗に改められ、正嘉年間(1257-59年)頃に寺号も浄妙寺と改めました。
中興開基は足利尊氏公の父、貞氏公で、室町時代は鎌倉公方の菩提寺として隆盛し、外門、総門、山門、仏殿、法堂方丈、禅堂、経堂など七堂伽藍を備え多くの塔頭を擁する大寺院であったと伝わります。
『新編鎌倉志』は、中興開基について「按ずるに、源尊氏の父、讃岐守貞氏を、浄妙寺殿貞山道観と号す。元弘元年九月五日逝去、当寺の旦那にて、当寺を修復の御浄妙寺と改めたると見へたり。昔は当寺を極楽寺と号すと。」と記しています。
歴代の往寺として約翁徳倹・高峰顕日・竺仙梵僊・天岸慧広などの名僧を輩出しています。
浄妙寺は鎌倉五山の第五位です。
鎌倉五山とは臨済宗寺院の寺格で鎌倉にある五つの高位の寺院をさし、もとはインドの五精舎十塔所にならって創設されたともいわれています。
京にも五山がありますが、京に先立ち鎌倉で五山が定められたとする説、もともとは鎌倉と京の寺院で構成されていたという説など諸説あるようです。
至徳三年(1386年)、室町幕府三代将軍・足利義満公が南禅寺を別格として五山之上とし、京都の天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺、鎌倉の建長寺、圓覚寺、壽福寺、浄智寺、浄妙寺をそれぞれ五山に決定し、以降固定化しました。
『新編鎌倉志』には、
「至徳三年七月、源義満、五山の座次を定め、建長寺を第一として、京師天竜寺の次也。圓覚寺を第二、壽福寺を第三、浄智寺を第四、浄妙寺を第五とす。是より先、座位の沙汰あらず。」とあります。
----------


【写真 上(左)】 金沢街道からの参道
【写真 下(右)】 山内入口
間違いやすいですが、このあたりの地名は「浄明寺」、寺号は「浄妙寺」です。
かつては寺社から地名をいただく場合、そのままの字を写すことをはばかり、一字を替えて名付けることがあったそうです。こちらもその例かもしれません。
金沢街道沿いに駐車場があり、そこから北に向かってまっすぐ参道が延びています。

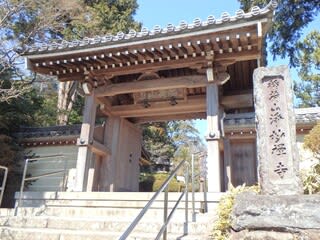
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標と山門
さらに進むと山門。切妻屋根本瓦葺の脇門付き四脚門で、さすがに名刹らしい風格を備えています。
くぐって左脇が拝観受付で、御朱印もこちらで授与されています。
拝観前に御朱印帳をお預けし、拝観後に受け取るシステムで、ご親切な対応をいただけます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 冬の参道-1
【写真 下(右)】 冬の参道-2
低木メイン、南傾のすこぶる明るい山内で、うっそうと幽邃な寺院の多い鎌倉の禅寺では異色ともいえる開放感があります。
かつては七堂伽藍や塔頭を連ねたこの名刹も、いまは総門(山門)、本堂、客殿、庫裏という比較的シンプルな伽藍構成となっています。
境内は国指定史跡に指定されています。


【写真 上(左)】 5月の参道
【写真 下(右)】 本堂下


【写真 上(左)】 5月の本堂
【写真 下(右)】 本堂と客殿?
山門から本堂に向かってまっすぐに参道が延びています。
おそらく寄棟造銅板葺。円筒状の大棟と、起り気味の屋根が美しい本堂です。
左手にある客殿?の入母屋屋根も銅板葺起り気味で、本堂と絶妙なバランスを保ち、本堂身舎右側に設えられた唐破風もいいアクセント。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 客殿?
向拝柱はなく、桁行に格子戸が連なり、中央見上げには鎌倉三十三観音霊場の札所板と「方丈」の扁額が掲げられています。
向拝の扉は開け放たれ、堂内をうかがうことができます。


【写真 上(左)】 本堂向拝-1
【写真 下(右)】 本堂の札所板と扁額


【写真 上(左)】 本堂向拝-2
【写真 下(右)】 左手からの本堂


【写真 上(左)】 右が本堂、左が開山堂
【写真 下(右)】 開山堂扁額
本堂裏手には別棟の開山堂が連接しています。
こちらは、開山塔(祖塔、光明院)の流れを汲む堂宇と思われ、『新編鎌倉志』では、「開山(退耕行勇禅師)の像あり。又源直義像あり。又光明院殿本覺大姉と書たる位牌(裏に法樂寺殿嫡女)」とあり、足利家三代目当主義氏公の院号は法樂寺殿、息女(四条隆親室)の院号は光明院殿と伝わるため、義氏公の息女とのゆかりを説いています。

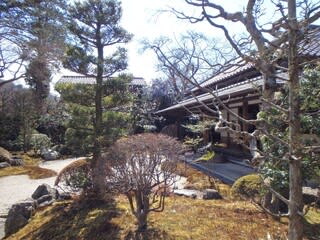
【写真 上(左)】 「喜泉庵」入口
【写真 下(右)】 枯山水庭園と「喜泉庵」


【写真 上(左)】 「喜泉庵」
【写真 下(右)】 「喜泉庵」の軒先
本堂左手に枯山水庭園と茶堂「喜泉庵」があり、枯山水の庭を眺めつつ茶菓をいただくことができます。


【写真 上(左)】 石窯ガーデンテラス
【写真 下(右)】 石窯ガーデンテラスのパン
そこから小道を登っていくと、スコットランド人ガーデンデザイナーが手掛けるイングリッシュガーデンと築90年の洋館を改装したベーカリーレストラン「石窯ガーデンテラス」。
ふつうお寺にイングリッシュガーデンやパン工房はイメージ的に違和感がありますが、このすこぶる明るい浄妙寺の境内では不思議なほどマッチしています。


【写真 上(左)】 直義公墓所への道
【写真 下(右)】 直義公墓所
「石窯ガーデンテラス」から北側に延びる小道は足利直義公の墓所。
小道分岐から西側すぐが6.(浄明寺)熊野神社の社頭になりますが、ゲートがあるのでここから直接熊野神社へは行けません。
ここまで来ると、展望が開け、滑川の谷越しに鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)を望めます。


【写真 上(左)】 ゲートの先が熊野神社の社頭
【写真 下(右)】 衣張山
この辺りは足利直義公ゆかりの史跡があったところで、少しく辿ってみます。
『新編鎌倉志』から浄妙寺山内図を転載します。(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)
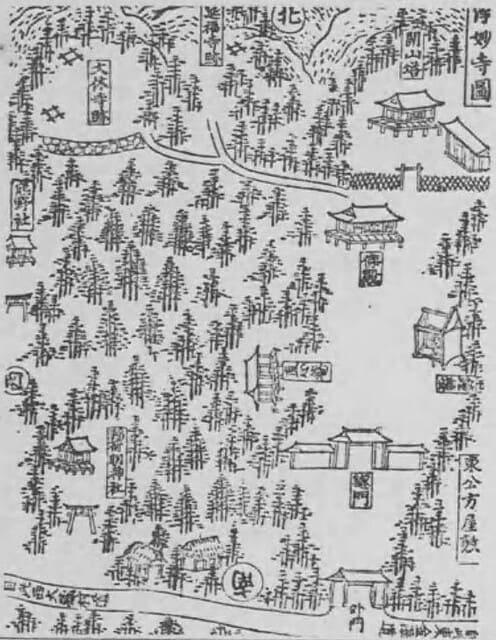
この図をみると、現在の「石窯ガーデンテラス」の北側山手あたりに延福寺、「石窯ガーデンテラス」あたりに大休寺、その西側に熊野社の文字がみえます。
〔延福寺〕
雲谷山と号し、足利尊氏公の兄君で早世した足利左馬助高義公の菩提所とされます。
『新編相模國風土記稿』には「延福寺蹟。浄妙寺域内西北ニアリ。足利左馬頭高義(尊氏ノ兄)。契忍禅尼(讃岐守貞氏側室。高義母)。追福ノ為。爰(ここ)ニ創建シ。山ヲ雲谷ト名ツケ。足菴(麟和尚)ヲ開山粗トスト云フ。観應三年二月廿六日。直義入道恵源。当寺に在テ頓滅セリ。管領成氏ノ時ハ。年々二月。必当寺参詣アル事。廃セシ年代詳ナラス。」
とあり、こちらが足利直義公の終焉の地とされています。
足利直義公は、足利貞氏公の三男で室町幕府初代将軍足利尊氏公の同母弟です。
室町幕府開設・草創に活躍し、「三条殿」と称され卓越した政治的手腕により実質的な幕政の最高指導者であったとみられています。
政治手法は比較的保守的とされ、革新派の執事の高師直との間に確執を生じ、養子の直冬の処遇問題も絡んで観応の擾乱が勃発。薩埵峠の戦いで兄の尊氏に敗れ鎌倉に蟄居の後、急死を遂げたとされます。
禅宗を篤く敬って庇護し、 臨済宗高僧の夢窓疎石(夢窓国師)との対話は『夢中問答集』として出版され、尊氏・夢窓疎石とともに後醍醐天皇の菩提のために天龍寺を創建するなどの功績が残っています。
その死因についてはさまざまな説があり、『新編相模國風土記稿』でも含みのある表現をしていますが、ここでは触れません。
〔大休寺〕
『新編鎌倉志』から引用します。
「熊野山(ゆうやさん)と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。(中略)直義の位牌は浄光明寺にもあり。」
足利直義公の旧宅であり菩提所であったことが記されています。
『新編相模國風土記稿』によると、直義公の創建、月山希一開祖とのこと。
歴史ある名刹だけに境内、近隣に多くの寺社・旧跡が残ります。
浄妙寺の東、芝野には尊氏公の旧宅で代々関東管領の屋敷となった「公方屋敷」がありました。
境内墓地には尊氏公の父、貞氏公の墓と伝わる宝篋印塔もあり、浄妙寺は足利氏とゆかりのふかい寺院です。
山門をくぐらず、右手の道をすすむと鎌足稲荷神社の参道です。
上の浄妙寺山内図では、稲荷明神社は山門向かって左(西側)に記されていますが、鎌足稲荷神社は山門の右手(東側)に位置します。
急な階段を登った先が神さびた境内。木立のなかに一間社流造のお社が御鎮座しています。

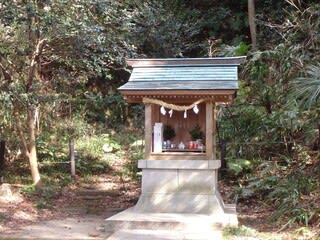
【写真 上(左)】 鎌足稲荷神社参道.
【写真 下(右)】 鎌足稲荷神社
鎌足稲荷神社について、『新編鎌倉志』には「寺の西の岡にあり。浄妙寺の鎮守なり。(中略)往古の縁起うせて、何の御神とも不知といへり。偖(さて)は此御社は、大織冠の御鎮座か。山なる鎮守は、彼霊験の鎌を納められし、鎌倉山是なりとをぼゆるとあり。」とあります。
”大織冠”とは大化三年(647年)から数十年間日本で用いられた冠位(冠位一三階の最高位)で、史上藤原鎌足公だけが授かったとされます。
よって、同書では御祭神は藤原鎌足公であり、このお社が”鎌倉”の地名の発祥であることにまで言及しています。
実際、山内裏山にはいまも「鎌足稲荷」と呼ばれるお社が祀られ、開山堂には「木造藤原鎌足像」が安置されています。
鎌足稲荷神社の由緒書には、ご祭神 稲荷大神とあり、「大織冠藤原鎌足公は乳児の時、稲荷大神さまから鎌を授けられ、以来、常にお護りとして身につけ、大神さまの加護を得られました。(略)大化二年(646年)東国に向かわれ、相模国由井の里に宿泊されました。その夜『あなたに鎌を授けて守護してきたが、今や(蘇我)入鹿討伐という宿願をなし得たから、授けた鎌を我が地に奉納しなさい』との神告があり、お告げのままに鎌を埋納したことによるとされています。」とあります。
これによると、鎌足公は創祀に深く関わられているものの、ご祭神は稲荷大神ということになります。


【写真 上(左)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)参道
【写真 下(右)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)
本寂堂は鎌足稲荷神社参道右手の階段の上にあり、現在の御祭神は三宝荒神です。
『新編相模國風土記稿』には、「荒神。不動ヲ安ス。足利義兼。多年秘崇空海所筆授。荒神及不動二軸。(中略)令佛工運慶彫所夢二尊之頭身。」とあります。
はっきりとはわかりませんが、義兼公が尊崇していた弘法大師空海お筆の荒神および不動尊の霊夢を受け、運慶に命じて二尊の像を彫らせたという内容に思えます。
また、同書によると本寂堂に「藤原鎌足像」が安置されていたようです。
ただし、現在は参道階段が閉ざされているので、階段下からの参拝となります。
また、Web上では、同寺に淡島明神立像が奉安されていることから、婦人病の祈願所とされてきた、という情報もみられます。
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の2つ。
別に御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印を授与されているので御朱印は3種です。
御本尊の釋迦牟尼佛は本堂に御座します。
『新編相模國風土記稿』には「佛殿。古ハ彌陀(立像陳和卿作。是寺伝累記ニ見エタル。二位禅尼カ。白檀ノ阿彌陀ナルヘシ。)ヲ本尊トセシカ今此ヲ外殿ニ置キ釋迦。(是モ寺伝累記ニ見エシ。建暦三年(1213年)実朝カ新造セシ。佛體ナルニヤ。)本尊トス。」とあり、これを信じると当初の佛殿御本尊は阿弥陀如来だった可能性があり、後に、鎌倉三代将軍実朝公新造の釋迦牟尼佛が御本尊となられたことになるます。
〔 御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印 〕
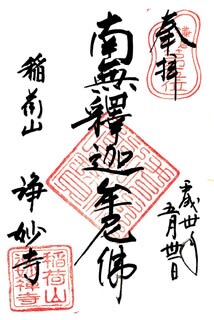
●主印は三寶印、揮毫は「釋迦牟尼佛」で「鎌倉五山第五位」の印判が捺されています。
鎌倉三十三観音霊場第9番の札所本尊は本堂に御座す、聖観世音菩薩です。
上記のとおり本堂向拝に観音霊場の札所板が掲げられています。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
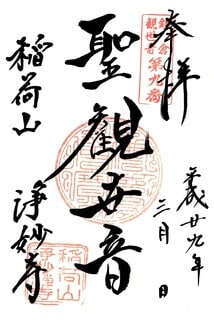
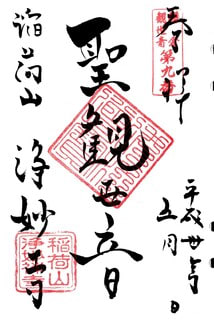
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の札所本尊も御本尊のお釈迦様とみられます。
御本尊(鎌倉五山)の御朱印揮毫は「南無釋迦牟尼佛」、鎌倉十三仏霊場の御朱印揮毫は「釋迦如来」となっています。
「南無」とは”帰依する”というほどの意味で、「釋迦牟尼佛に帰依します」の意をあらわします。
禅宗寺院の御朱印で多くみられる揮毫です。
これに対し「釋迦如来」は禅宗以外の寺院御朱印で比較的よくみられます。
個人的には「釋迦牟尼佛」は釈尊(歴史的な聖者・修行者あるいは仏教の教主としての存在)、「釋迦如来」は如来(浄土を主宰される悟りを開いた佛)の一尊としての釋迦如来をあらわしているような感じがしていますが、ぜんぜん違うかもしれません。
〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕
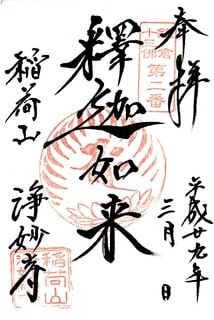
●主印は釋迦如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多いですが、こちらもその様式です。
鎌倉に女子をデートに誘う向きも少なくないかと思いますが、こちらのお寺さんはわりあい空いているし、受付のご対応も親切だし、雰囲気は明るいし、歴史の香りも豊かで、和様それぞれの飲食処も完備のうえに達筆の御朱印もいただけるので、かなりポイントを稼げる(笑)のではないでしょうか。
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。
【 BGM 】
■ 空に近い週末 - 今井美樹
■ Just Be Yourself - 杏里
■ 海のキャトル・セゾン - とみたゆう子
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/01/25 補足UP・2021/01/31 補足UP・2022/01/14 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)
29.白山神社 (高崎市白岩町)
30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)
31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)
32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)
33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)
34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)
35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)
36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)
37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)
38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)
39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)
40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)
41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)
42.菅原社 (高崎市金古町)
28.白岩山 長谷寺(白岩観音)
高崎市白岩町448
金峯山修験本宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格、群馬郡三十三観音霊場第31番
札所本尊:十一面観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第15番)、十一面観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)
坂東三十三箇所(観音霊場)の札所として広く知られている寺院です。
開基・寺歴については諸説あるようです。
坂東三十三箇所の公式Webには、「創立は文武天皇朱鳥年中、開基は役ノ行者」とあります。
『西国秩父坂東観音霊場記図絵』(国会図書館DC、コマ番号183/194)には以下の記述があります。
「武蔵白石山長谷寺の本尊は役の優婆塞からす川の天狗に誘引れて始て山上に登り呪文を唱えしかば十一面の大士現はれしを獨鈷にてはらひたれば大士は柳の枝に止りふたゝび不動明王現れたる姿を刻みて靈石の上に安置せり其後當地の高崎氏が四十二の厄難除に行基大士件の柳を以て此本尊を刻み與へ大難を免しめしなり」
これによると、当寺の開基伝承には役の優婆塞(役の行者)、行基が関係していることがわかります。
また、『新上州・観音霊場三十三カ所』(新上州観音霊場会)には、「(この地は)役の行者の苦行の跡地」とあります。
山内の案内板には、「朱鳥年間(686-696年)に開基されたことが『長谷寺縁起絵巻』に伝えられている。」「鎌倉時代中期・天福年間(1233年)に成立した坂東三十三ヵ所のうち、第十五番の札所となった白岩観音堂へは中世以降、多くの巡礼者たちが訪れた。」とあります。
さらに『坂東観音巡礼』(満願寺教化部)には「寺伝」として下記内容の記載があります。
・孝徳天皇(645-654年)のころ、越後の修験僧・大坊が白山への帰途留錫し、土人形を造顕して祈願することを知らしめて始まる。
・源義家や頼朝、新田義貞などの武将により堂宇の修理がなされる。
・永禄六年(1563年)、武田信玄が箕輪城主・長野業政を攻めたとき兵火にあって消失し、その後山内大坊、世無道上人により再建。
当寺には『上野国群馬郡白岩長谷寺慈眼院縁起』という巻物が伝わっており、原文は確認できていないですが、こちらのWebに記載されているので、要点を抜粋引用させていただきます。
・延暦年間(782-806年)から大同年間(806-810)年にかけては伝教大師最澄や弘法大師も当寺を訪れ、仁寿元年(851年)には在原業平が堂宇を修繕。
・歴代領主や源頼朝、新田義貞、上杉氏などから帰依を受け、天文元年(1532年)上杉憲政が伽藍を整備して隆盛し日本三長谷に数えられた。
・武田の兵火により消失した本堂の再建(天正八年(1580年))を果たしたのは武田勝頼。
金峯山修験本宗は、吉野の金峯山寺を総本山とする修験道系の宗派で、昭和23年(1948年)に立宗されました。
修験道の流れはすこぶる複雑で、教義についても様々な解釈がありますので、詳細については金峯山寺の公式Webをご覧ください。
総本山・金峯山寺の開創は役行者神変大菩薩が白鳳年間(650-654年)に修行に入られ、金剛蔵王大権現を感得されて、このお姿を山桜に刻んで山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)に祭祀されたことと伝えられています。
長谷寺で金剛蔵王大権現を祀られているかは確認できていませんが、役行者は開基として祀られており、上記のとおり、役行者(役ノ尊者)の御朱印の種子は金剛蔵王大権現の種子「ウン」が用いられていると思われます。
関東に金峯山修験本宗の寺院は少なく、品川区二葉の大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)が知られていますが、長谷寺(白岩観音)は札所としては稀少な例では。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道
参道入口に「金峯山 修験本宗 白岩山 長谷寺」の寺号標と石灯籠一対。
参道はすぐに向きを変えて、本堂に向かいます。


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門扁額
左に手水舎、正面に仁王門で、仁王門は切妻造銅板葺、三間一戸の八脚単層門で木部朱塗
り。両脇間に仁王尊像が鎮座し、戸部見上げには「白岩山」の扁額。
むくり気味の屋根が引き締まった印象を与え、高崎市の指定重要文化財に指定されています。
門をくぐると右手に鐘楼、そのおくが寺務所、正面が本堂で、高低差も少なく比較的シンプルな伽藍構成です。


【写真 上(左)】 仁王門内の参道
【写真 下(右)】 開山堂跡地
参道左手には開山堂跡地。
案内板には「長谷寺を開山された修験道の祖『役行者様』の像を安置する堂」で(開山堂建立予定)と記されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 唐破風
本堂(観音堂)は存在感があります。
入母屋造銅板葺で正面に大がかりな唐破風向拝を起こしています。
この唐破風の端部(水引虹梁の上)はすべて彩色の彫刻群で埋め尽くされ、隙間がありません。

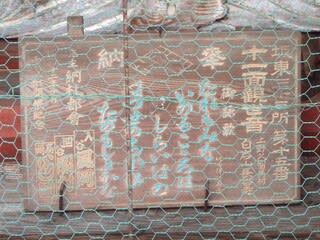
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 坂東霊場の札所板
向拝はふところ深くやや薄暗くなっており、秘仏の多い十一面観世音菩薩が御座す、観音堂らしい佇まいです。
本堂(観音堂)および仁王門は高崎市の指定重要文化財に指定されています。
なお、この本堂(観音堂)は2021年12月に新築落慶し、境内の伽藍構成もいくつか変更されています。


【写真 上(左)】 長谷寺の新本堂-1
【写真 下(右)】 長谷寺の新本堂-2
秘仏の御本尊十一面観音立像は、カヤ材の一木割矧造で平安時代後期(藤原時代)の作とされ、県指定重要文化財に指定されています。
前立像は桧の寄木造で玉眼がはめ込まれ、全体に金箔が施されている仏像で、鎌倉時代末の作と推定され、こちらも県指定重要文化財に指定されています
御朱印は寺務所内の授与所にて拝受できます。
坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格霊場(第23番の次)、役ノ行者(役ノ尊者)の3種の御朱印が授与されています。(現在、役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印の授与は不明。)
〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印(専用納経帳/御朱印帳) 〕
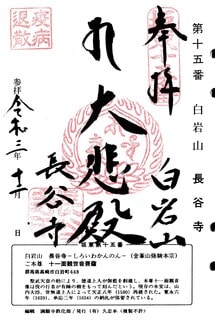
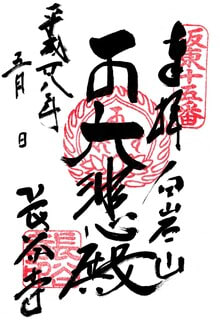
中央に御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の揮毫と三尊の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「大悲殿」の揮毫。
右上には「坂東十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
三尊の種子は、おそらく中央が御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」、右が毘沙門天の種子「ベイ」、左が不動明王の種子「カン/カーン」と思われます。
十一面観世音菩薩と毘沙門天と不動明王の三尊を安置する例はかなりあるので、その様式の種子かと思われます。
(十一面観世音菩薩の脇侍として、毘沙門天と不動明王が御座されている例 → 甲府の青松院)
〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(御朱印帳) 〕
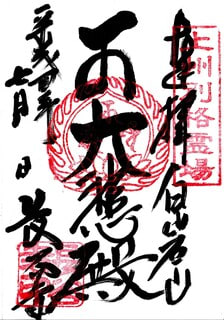
尊格構成は上の坂東霊場と同様です。
右上には「上州別格霊場」の札所印。右下には山号の揮毫があります。
〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(専用納経帳) 〕
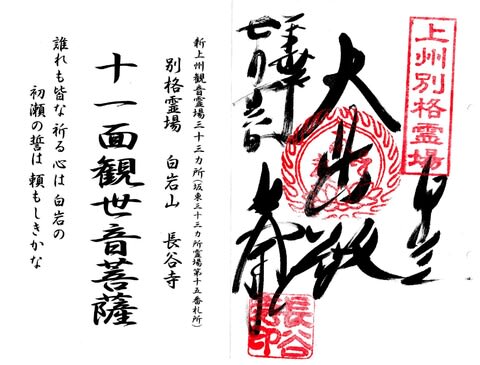
見開き御朱印です。右側は「上州別格霊場」と同様。左側には御本尊の「十一面観世音菩薩」と御詠歌が印刷されています。
〔 役ノ尊者(役ノ行者)の御朱印 〕
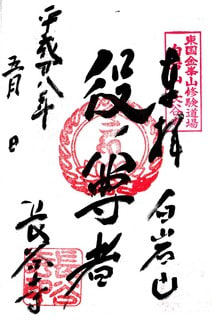
当山の開基とされる役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印です。
中央にはおそらく金剛蔵王権現の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「役ノ尊者」の揮毫。
右上には「東国金峯山修験道場 白岩山 長谷寺」の印。右下には山号の揮毫、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
29.白山神社
公式Web
高崎市白岩町450
御祭神:菊理媛大神
御朱印揮毫:白山神社(印判)
公式Webの社伝(白山記(しらやまき))によると、「白鳳年中白山々 伊邪那美の神を奉祀、守護神とす」。
「白鳳」はいわゆる私年号で、通説では白雉(650-654年)の別称とされます。
加賀の白山はふるくから霊山として崇められ、養老元年(717年)に越前の泰澄大師によって開山。
主峰の御前峰に奥宮が創建され、白山妙理大権現が奉祀されたと伝わります。
白山信仰は神仏混淆(修験道)の色彩が強く、白山妙理大権現(白山権現)は伊弉冊尊の化身、本地仏は十一面観世音菩薩、別当は白山寺(白山本宮)であったと伝わります。
全国の白山神社の総本社、白山比咩神社(石川県白山市)の御祭神は白山比咩大神(=菊理媛尊)、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。
菊理媛大神(ククリヒメ)は、伊弉諾尊(伊邪那岐)および伊弉冉尊(伊邪那美)とふかいかかわりをもつ神様で、国内の一宮一覧である『大日本国一宮記』には「白山比咩神社、下社(本宮)伊弉冊尊、上社(三ノ宮)菊理媛、号白山権現」と記されています。
文明十二年(1480年)、白山寺(白山本宮)が加賀一向一揆の攻撃で焼失し三ノ宮に遷座したこともあいまって、白山信仰と菊理媛の関係については諸説ありますが、江戸時代の多くの書物には白山比咩神と菊理媛は同一神と記されています。
明治初期の神仏分離により修験道としての白山権現は廃され白山比咩神社として改組されましたが、全国の白山権現の多くは白山神社となり、菊理媛神を御祭神としています。(菊理媛神とともに伊弉諾尊、伊弉冉尊を御祭神とする例も多くあり。)
当社社伝には「白山権現の本地である十一面観世音を役の行者小角が背負い、碓日峰(碓氷峠)に至り『どこかに奉祀する霊地はないかと・・・』その地を探し現在の高崎市白岩町にて謹んで祀られる(中略)これが、本尊十一面観世音であり守護神として伊邪那美の神を祀った。これが白山神社になった所以である。」とあります。
永禄六年(1563年)、武田勢による箕輪城攻略の兵火で社殿は消失しましたが、明治二年(1869年)には神仏区画令により(白岩一村の)総鎮守となったといいます。
場所は長谷寺(白岩観音)のすぐとなりです。
参拝時に長谷寺(白岩観音)の駐車場は利用できません。
当社の駐車場はこちらになります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鳥居
長谷寺(白岩観音)の参道入口横から山手方向に登っていきます。
参道起点から鳥居も拝殿も見えるので迷うことはありません。
鳥居は朱塗りの明神鳥居で、高さのある亀腹が目をひきます。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 向拝
正面の拝殿は、入母屋造銅板葺流れ向拝の整った外観。
水引虹梁まわりは拝殿幕でおおわれて詳細不明。身舎にかけて海老虹梁。
向拝正面は桟唐戸で見上げに「白山神社」の扁額が掲げられています。
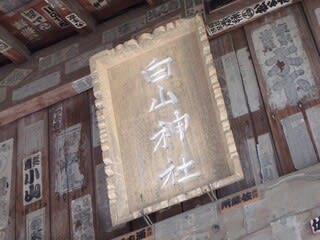

【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 境内社
往年の神仏混淆を物語るように、境内各所に石碑の境内社が祀られています。
こちらは、有名な八王子了法寺の萌えキャラを担当されたとろ美さんが手がけた御朱印帳が有名です。
限定のようですが、はるな式典埋木舎の事務所(高崎市下室田町884-1)で入手できるかもしれません。
通常は非常駐で、拝殿前に書置御朱印が用意されています。
Web情報によると、境内社の大山祇神、北野社、若宮八幡宮、稲荷社、猿田彦大神、蠶影山大神などの御朱印も授与されているようですが、こちらは時期限定かもしれません。
〔 御朱印 〕
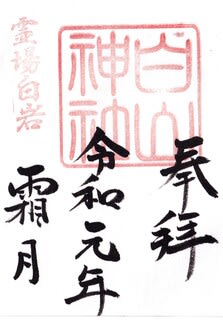
社号印と「霊場白岩」の印が捺されているシンプルな御朱印です。
30.大嶽山 瀧澤寺
公式Web
高崎市箕郷町白川1583
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊
札所:
札所本尊:
高崎市箕郷町の山あいにある曹洞宗寺院。
公式Webの寺伝によると、平城天皇の御代(806-809年)に慈覚大師が開山駐錫の聖地としてこの地に一堂を建立。
不動尊と二童子が安置され、満行山 不入院 瀧澤禅寺と号して開創。
550年後に厚山慶淳和尚が曹洞宗に改宗したとされます。
ここで気になったのは、開創時の「満行山」という山号です。
このエリア(榛名東麓)において、「満行」という名称は格別な意味をもっていると考えられるからです。
以前引用した『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)を当たると、でてきました大嶽山 瀧澤寺の縁起が。
しかも「船尾山炎上譚」にふかくかかわる内容です。
要点を上記論文から引用させていただきます。
・瀧澤寺は古くは天台宗の寺院で慈覚大師円仁の開山。不入の滝がある地に満行山 不入院 瀧澤寺があった。
・天喜四年(1056年)、千葉左衛門常胤は、源頼義公の奥州討伐軍に従ってこの地を過ぎた際、一子相満を修学のため寺に預けた。
・その後、相満が行方知れずとなり、常胤は寺僧が隠したと思い火を放ち一山を焼いたが相満は見つからなかった。
・この時僧が不動尊を擁して難を逃れ、霊夢を得て一堂を結んだのが現在の瀧澤寺だという。(なお、論文筆者は時代的に「常胤」は「常将」であろうと記されている。)
船尾山 柳澤寺の縁起には太夫満行が榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建とあります。
当寺の当初の山号「満行山」、そして上記の縁起からして、太夫満行が榛名山中に創建した"妙見院息災寺"となんらかのゆかりをもつのではないでしょうか。
なお、高崎市資料には、井伊直政の伯父である中野越後守が天正年間(1573-1592年)に再興とあります。
霊場札所ではないありませんが、「曹洞宗ナビ」に「御朱印あり」とあったので、参拝してみました。


【写真 上(左)】 瀧澤寺
【写真 下(右)】 瀧澤寺の本堂
山裾を巧みに利用した山内は奥行きがあり、予想以上に規模が大きく宿坊「紫雲」も併設されています。
入口に二体の石造仁王尊像。
右手の「巡り経蔵」は市指定重要文化財で、白亜の建物の中では、経巻を納めた六角形に区切られた棚が中央の主軸を中心に回る仕組みになっているそうです。
その先に鯉が泳ぐ池と山門。
本堂は入母屋造桟瓦葺で、張り出しの大きな軒唐破風つきの向拝を構えています。
どこを切り取っても純和風のつくりで、宿坊では精進料理を提供し、座禅ができることもあって外国人観光客に受けそう。
実際、サインやWebに英語表記があり、こういう層も受け入れているかもしれません。
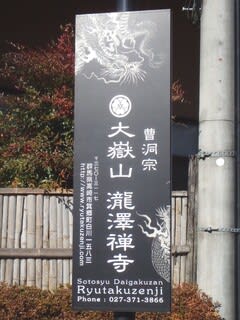
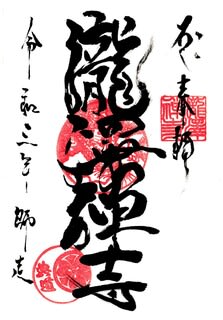
【写真 上(左)】 瀧澤寺のサイン
【写真 下(右)】 瀧澤寺の御朱印
ご住職は気さくな感じの方で、本堂内に上げていただき、堂内のご説明もして下さいました。
本堂欄間の彫刻は明治初期の相沢比吉の作で、目の不自由だった相沢比吉が三年間の時間を要して彫り上げた夫婦龍とのこと。
境内の銀杏の古木から掘り出し、玉を握っているのが男龍。爪の数などのご説明もいただきました。
御朱印は庫裡にて直書いただけました。
31.(箕郷町富岡)飯玉神社
高崎市箕郷町富岡254
主祭神:宇気母智神
旧社格:村社
御朱印揮毫:(箕郷富岡)飯玉神社

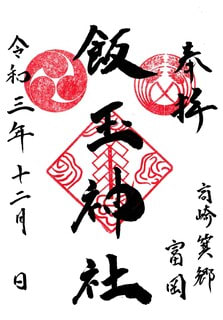
情報が少ないですが、『群馬県群馬郡誌』によると旧村社のようで、御祭神は宇気母智神、創建は寛永六年(1629年)、氏子戸数は115となっています。
所在は車郷村(くるまさとむら)大字富岡で、車郷村は昭和30年(1955年)4月に箕輪町と合併して箕郷町となっています。
鳴沢湖そばの高崎市立車郷小の東側に御鎮座。
石垣に囲まれた社頭。その先に石造りの明神鳥居で「正一位 飯玉大明神」の扁額が掲げられています。
正面に入母屋造桟瓦葺妻入の拝殿。見上げれば妻飾りに蕪懸魚と大棟鬼板には経の巻獅子口。
妻部に向拝を構え、向拝柱、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。
社殿裏手には、数座の境内社が御鎮座。
すぐそばの真福寺観音堂には石神仏群が残り、市指定重要文化財に指定されています。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
32.(生原)北野神社
高崎市箕郷町生原1739-1
主祭神:菅原道真公ほか五柱
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
御朱印揮毫:(生原)北野神社
例大祭の稲荷流獅子舞、”あばれ獅子”で知られる箕郷町生原(おいばら)地区の天神様です。
境内由緒書によると、永禄三年(1560年)の勧請と伝えられ、現在の社殿は、榛名神社の双龍門などで知られる原山の棟梁清水和泉(充賢)と、熊谷の彫刻師小林源太郎の手により文久元年(1861年)に完成。
本殿は木造檜皮葺唐破風造で、昇り龍、降り龍をはじめ精緻な彫刻が施され、市の重要文化財に指定されています。
『群馬県群馬郡誌』によると所在は上郊村大字生原、社格は村社、御祭神は菅原道真公ほか五神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は61で、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
合祀神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十一年字諏訪の無格社諏訪神社・同境内末社一社・字中内出無格社神明宮・字中新田無格社・白山神社を合祀せり」とあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
広めの境内。社頭の石造明神鳥居には「天満宮」の扁額。
石段を数段昇って石灯籠二対の先に、均整のとれた入母屋造本瓦葺流れ向拝軒唐破風の拝殿。
向拝柱、水引虹梁両端正側に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を備えています。
覆屋のなかの本殿は、名工の作で市の重要文化財指定されているだけに見どころ多数ですが、ここでは省略します。
境内社は少ないですが、参道向かって右に庚申塔があります。

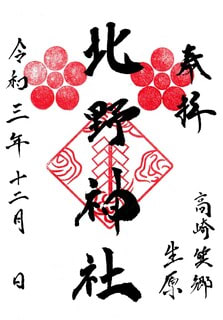
【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
33.(生原)嚴島神社
高崎市箕郷町生原1728-1
主祭神:市杵島姫命
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

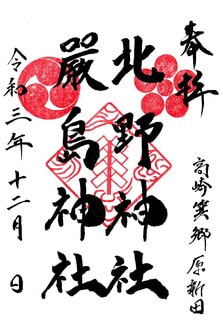
箕郷町原新田(生原二区)に御鎮座の嚴島神社。
境内由緒書には、この地区は元来水利に恵まれていませんが、竜昌寺前のみ清水が湧き湿地をなした唯一の水源地であったので、水信仰の神である弁天様が祀られた旨記載されています。
弁天様は、元亀天正(1570-1593)の昔、川浦氏が柏木沢東谷を開墾した際に立派な石臼を掘り当て、こちらを祀ったことに由来するものとされています。
『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は市杵島姫命、創立は享保年間(1716-1736年)、氏子戸数は60とあります。
(原新田)北野神社から龍昌寺を越えた南側に御鎮座で、駐車スペースはありません。
県道123号に面した社頭に石造の明神鳥居で扁額を掲げていますが読解不能。
その先に石敷の参道が延び、正面にブロック塀に囲まれた銅板葺一間社流造の朱塗りの社殿。
向拝柱、水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を備えています。
社殿の背後はうっそうと茂る竹林で、こちらが件の水源地なのかもしれません。
御朱印は(原新田)北野神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
34.(原新田)北野神社
高崎市箕郷町生原1
主祭神:菅原道真公
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

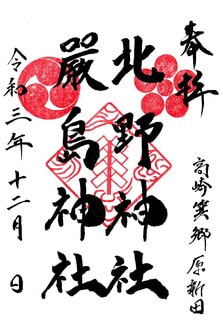
箕郷町生原原新田地区に御鎮座の天神様。
境内に由緒書はなく詳細不明ですが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は菅原道真公、明治23年9月再建、氏子戸数は60とあります。
かなり広い境内で生原2区集会所もあります。社叢がなく、明るい境内です。
切妻造朱色の銅板(?)葺平入りの拝殿で、奥に切妻造妻入の本殿が連接しています。
本殿裏手には、猿田彦大神、御嶽山大権現、秋葉山大権現、古峯神社などの境内社が御鎮座。
御朱印は(生原)嚴島神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
35.(保渡田)白山神社
高崎市保渡田町905
主祭神:菊理比咩命、伊邪那美命
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(保渡田)白山神社


境内に複数の由緒書がありましたが、どれも白山信仰や白山神社総本宮にかかわるもので、当社についての説明はありませんでした。
『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は菊理比咩命、伊邪那美命、創建は明治十六年、氏子戸数は27とあります。
カーナビでは表示されず、勘でたどり着きました。
カインズ箕郷店から東に延びる道を200mほど進んだ交差点に面して御鎮座。
駐車スペースはありません。
道から数段高く、石垣の上が境内です。
朱塗りの明神鳥居に「白山神社」の扁額。
正面に切妻造銅板葺妻入で向拝を付設した社殿。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
36.(保渡田)諏訪神社
高崎市保渡田町1800
主祭神:建御名方神
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(保渡田)諏訪神社


「一人立ち三頭舞」の稲荷流獅子舞で知られる諏訪神社です。
境内に獅子舞の説明板はありましたが、由緒書はありませんでした。
『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は建御名方神、創建は不詳、氏子戸数は71とあります。
保渡田古墳群の西側に御鎮座。
こちらも石垣に囲まれ、道から数段高い境内。
このかたちは境内は広くても物理的に車は止められないので、車でのアクセスは難儀します。
鳥居はなく、社頭に一対の狛犬。
正面に切妻造桟瓦葺平入りの社殿。桟唐戸にしめ縄が張られ、向拝見上げに「諏訪神社」の扁額。
高台にあって日当たりよく、明るい境内です。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
37.(保渡田)榛名神社
高崎市保渡田町乙318
主祭神:火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神
旧社格:村社
御朱印揮毫:(保渡田)榛名神社

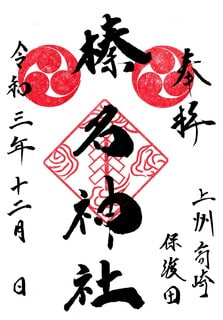
こちらも境内に由緒書はありませんが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は村社、御祭神は火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は55とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
祭神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「火産霊命・波邇夜麻毘賣命・大日孁神・大山祇神を祭神とす」とあります。
また、「明治41年本社境内社一社・字地蔵前無格社神明宮・字新宿無格社三島神社を合併せり」とあります。
おとなりは工場とその駐車場ですが、境内は厳かな空気につつまれています。
こちらも石垣の上に数段高く境内地。
石造の明神鳥居に「村社 榛名神社」の扁額。
社叢に囲まれた参道のおくに切妻造桟瓦葺平入りの拝殿と入母屋造桟瓦葺妻入りの本殿が連接しています。
拝殿より本殿の規模が大きく、拝殿の上に本殿の鬼板が見えます。
境内には数座の境内社が御鎮座。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
38.天王山 薬師院 徳昌寺
高崎市足門町566
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:
元司別当:(足門)八坂神社
なかなか情報がとりにくい寺院ですが、『群馬県群馬郡誌』に「宗派:真言宗、所在:金古村大字足門、創立年月日:不詳、本尊:不動明王、本寺:石山寺、開山:不詳、檀徒戸数103」とあります。

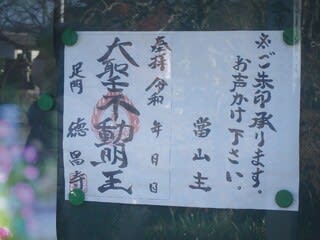
【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御朱印授与掲示
霊場札所ではなくこぢんまりとしたお寺をイメージしていましたが、本瓦葺の立派な山門にびっくり。
山門脇の掲示板に御朱印の見本が掲出されているので、御朱印授与に積極的なお寺さんかと思います。
参道右手に立派な手水舎。左手に地蔵尊。
さらにその先左手に第二次世界大戦中のニューギニア戦線の戦没者を供養する聖観世音菩薩が御座します。
本堂手前左手に宝形造桟瓦葺の聖天堂。
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で向拝柱を備え、向かって右手には修行大師像が御座します。
立派な鐘楼もあり、伽藍は整っています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。
39.(足門)八坂神社
高崎市足門町529
御祭神:須佐之男命、埴山媛命、大雷神、宇迦之御魂神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:天王山 薬師院 徳昌寺(足門、真言宗豊山派)
御朱印揮毫:(足門)八坂神社
境内由来書には、「長元四年(1031年)千葉常将が船尾寺に向かう時この地で八坂神に祈念したのに由来し、永禄年中(1558-1570年)、武田信玄公の箕輪城攻撃の際兵火に罹り社殿焼失とも伝える。しかし、八坂神社の上野国への勧請は鎌倉時代以前の記録はなく、尾張島津八坂御師の上野への布教活動が盛んになる15世紀以後に当地方に勧請されたのであろう。」という興味ぶかい記述があります。
千葉氏は当社の東側、引間町に位置する三鈷山 吉祥院 妙見寺とかかわりをもつとされます。
また、船尾山 等覚院 柳澤寺の縁起にも千葉常将が登場します。
当社は位置的に妙見寺と柳澤寺のあいだにあるので、千葉氏や「船尾山炎上譚」となんらかの関係があったのかもしれません。
生原の満行山 善龍寺(参拝済、御朱印不授与)にも、「永禄六年(1563年)二月箕輪城落城の際、兵火かかり焼失」という伝えがあります。(→情報出所は「古今東西 御朱印と散策」様)
また、同Webによると、箕輪城落城後、信玄公は武田四天王の一人、内藤修理之亮昌秀(昌豊)をして箕輪城の管理に当たらせ、善龍寺の再建を命じ寺号を満行山(当初は神明山)と改めさせた、とあります。
信玄公がどうして善龍寺の山号を「満行山」と改号したのかわかりませんが、結果として生原の地に「満行山」を山号とする武田家ゆかりの寺院が残ったことになります。
なお、善龍寺には内藤修理之亮昌秀の墓も残り、「善龍寺の内藤塚」として高崎市指定史跡に指定されています。
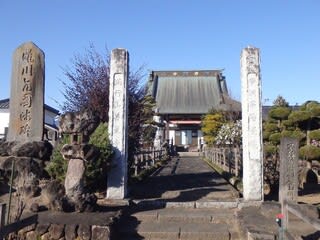

【写真 上(左)】 善龍寺-1
【写真 下(右)】 善龍寺-2
『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字足門、社格は村社、御祭神は須佐之男命、創建は不詳、氏子戸数は130とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
同じく『群馬県群馬郡誌』に、「明治42年9月8日字榛名原に祭祀せる無格社榛名神社・字雷電に祭祀せる無格社雷電神社を合併す。」「本社は諸公の崇敬殊に厚く、慶安二年徳川幕府は三石一斗を社領とし年々国家安穏五穀豊穣の祈願あらせられ(略)高崎領主安藤対馬守崇敬厚く」とあります。
また、境内由来書によると、明治42年に旧稲荷神社も合祀しているようです。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
かなり広い境内で、社頭に「村社 八坂神社」の社号標。石造台輪鳥居には「牛頭天王」の扁額。
拝殿は入母屋造桟瓦葺。向拝柱はなく、正面格子戸の上に「八坂神社」の扁額を掲げています。
本殿の様式はよくわかりませんが、見事な彫刻が施され見応えがあります。


【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
40.鈷守稲荷神社
高崎市金古町1929
御祭神:
旧社格:
御朱印揮毫:鈷守稲荷神社


こちらについては由緒書がなく、『群馬県群馬郡誌』にも記載がないので詳細は不明です。
金陽山 常仙寺の参道に面しているので、こちらからも当たってみましたが、やはり情報は得られませんでした。
亀腹の高い石造の稲荷(台輪)鳥居に「稲荷大明神」の扁額。
すぐ正面に朱塗りの切妻造瓦葺妻入りの社殿で、「金古守稲荷大明神」の扁額。
こぢんまりとしていますが、整った印象のお社です。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
41.金古諏訪神社
高崎市金古町1351
御祭神:建御名方神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
御朱印揮毫:金古鎮守 諏訪大神
『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字金古、社格は村社、御祭神は建御名方神 外八神、創建は不詳、氏子戸数は383とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十二年本社境内末社諏訪社琴平社外十社を合併したり。」とあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
地域の中核社らしくゆったりとした境内。
道路側に参道と社殿、奥側に駐車場という、いささか変わった配置です。
社頭瑞垣の梶の葉紋が、お諏訪様であることを主張しています。
石灯籠一対の先に石造の台輪鳥居で「正一位諏方大明神」の扁額。
正面に狛犬一対と入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風付きの拝殿。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
兎毛通に朱雀(?)の精緻な彫刻と、その上の鬼板は経の巻獅子口で梶の葉紋。
すぐうしろに本殿が連接しています。
摂社末社案内として以下の掲示がありました。
・菅原神社
学問の神様 菅原道真公(天神様)
・上野国十二社
県内の一之宮から十二之宮を勧請
・奥宮(元宮)
諏訪大明神を祀る境内最古の石祠
とくに、上野国十二社(貫前神社(富岡)・赤城神社(前橋)・伊香保神社(渋川)・甲波宿禰神社(渋川)・大国神社(伊勢崎)・榛名神社(高崎)・小祝神社(高崎)・火雷神社(玉村)・倭文神社(伊勢崎)・美和神社(桐生)・賀茂神社(桐生)・宇芸神社(富岡))は見応えがあります。
こちらの太々神楽は二十五座の舞を演じるもので、立派な朱塗りの神楽殿が設えられています。
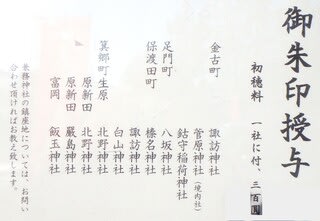
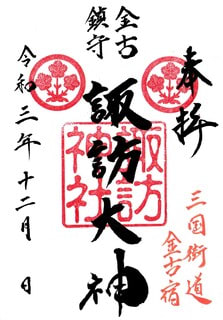
【写真 上(左)】 御朱印授与案内
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は境内授与所にて拝受しました。
周辺の神社の本務社を務められ、当社を含め11社10体の御朱印を授与されています。
42.菅原神社
高崎市金古町1351
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社金古諏訪神社の境内社
御朱印揮毫:菅原社

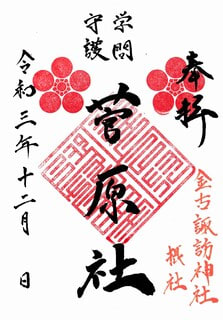
金古諏訪神社の境内社で、御朱印を授与されています。
金古諏訪神社拝殿向かって右手に御鎮座。
金属製の神明鳥居の先に数段高く石祠が二座御鎮座。
「金古の天神様 菅原神社」の表札、「天満宮」「学力向上・受験合格祈願」の赤い幟が建てられ、地域の尊崇篤いことがうかがわれます。
御朱印は金古諏訪神社境内授与所にて拝受しました。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ By Your Side - WISE & Kana Nishino
■ Airport - 今井優子
■ noctiluca - 今井美樹
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/01/25 補足UP・2021/01/31 補足UP・2022/01/14 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)
29.白山神社 (高崎市白岩町)
30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)
31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)
32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)
33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)
34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)
35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)
36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)
37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)
38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)
39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)
40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)
41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)
42.菅原社 (高崎市金古町)
28.白岩山 長谷寺(白岩観音)
高崎市白岩町448
金峯山修験本宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格、群馬郡三十三観音霊場第31番
札所本尊:十一面観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第15番)、十一面観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)
坂東三十三箇所(観音霊場)の札所として広く知られている寺院です。
開基・寺歴については諸説あるようです。
坂東三十三箇所の公式Webには、「創立は文武天皇朱鳥年中、開基は役ノ行者」とあります。
『西国秩父坂東観音霊場記図絵』(国会図書館DC、コマ番号183/194)には以下の記述があります。
「武蔵白石山長谷寺の本尊は役の優婆塞からす川の天狗に誘引れて始て山上に登り呪文を唱えしかば十一面の大士現はれしを獨鈷にてはらひたれば大士は柳の枝に止りふたゝび不動明王現れたる姿を刻みて靈石の上に安置せり其後當地の高崎氏が四十二の厄難除に行基大士件の柳を以て此本尊を刻み與へ大難を免しめしなり」
これによると、当寺の開基伝承には役の優婆塞(役の行者)、行基が関係していることがわかります。
また、『新上州・観音霊場三十三カ所』(新上州観音霊場会)には、「(この地は)役の行者の苦行の跡地」とあります。
山内の案内板には、「朱鳥年間(686-696年)に開基されたことが『長谷寺縁起絵巻』に伝えられている。」「鎌倉時代中期・天福年間(1233年)に成立した坂東三十三ヵ所のうち、第十五番の札所となった白岩観音堂へは中世以降、多くの巡礼者たちが訪れた。」とあります。
さらに『坂東観音巡礼』(満願寺教化部)には「寺伝」として下記内容の記載があります。
・孝徳天皇(645-654年)のころ、越後の修験僧・大坊が白山への帰途留錫し、土人形を造顕して祈願することを知らしめて始まる。
・源義家や頼朝、新田義貞などの武将により堂宇の修理がなされる。
・永禄六年(1563年)、武田信玄が箕輪城主・長野業政を攻めたとき兵火にあって消失し、その後山内大坊、世無道上人により再建。
当寺には『上野国群馬郡白岩長谷寺慈眼院縁起』という巻物が伝わっており、原文は確認できていないですが、こちらのWebに記載されているので、要点を抜粋引用させていただきます。
・延暦年間(782-806年)から大同年間(806-810)年にかけては伝教大師最澄や弘法大師も当寺を訪れ、仁寿元年(851年)には在原業平が堂宇を修繕。
・歴代領主や源頼朝、新田義貞、上杉氏などから帰依を受け、天文元年(1532年)上杉憲政が伽藍を整備して隆盛し日本三長谷に数えられた。
・武田の兵火により消失した本堂の再建(天正八年(1580年))を果たしたのは武田勝頼。
金峯山修験本宗は、吉野の金峯山寺を総本山とする修験道系の宗派で、昭和23年(1948年)に立宗されました。
修験道の流れはすこぶる複雑で、教義についても様々な解釈がありますので、詳細については金峯山寺の公式Webをご覧ください。
総本山・金峯山寺の開創は役行者神変大菩薩が白鳳年間(650-654年)に修行に入られ、金剛蔵王大権現を感得されて、このお姿を山桜に刻んで山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)に祭祀されたことと伝えられています。
長谷寺で金剛蔵王大権現を祀られているかは確認できていませんが、役行者は開基として祀られており、上記のとおり、役行者(役ノ尊者)の御朱印の種子は金剛蔵王大権現の種子「ウン」が用いられていると思われます。
関東に金峯山修験本宗の寺院は少なく、品川区二葉の大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)が知られていますが、長谷寺(白岩観音)は札所としては稀少な例では。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道
参道入口に「金峯山 修験本宗 白岩山 長谷寺」の寺号標と石灯籠一対。
参道はすぐに向きを変えて、本堂に向かいます。


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門扁額
左に手水舎、正面に仁王門で、仁王門は切妻造銅板葺、三間一戸の八脚単層門で木部朱塗
り。両脇間に仁王尊像が鎮座し、戸部見上げには「白岩山」の扁額。
むくり気味の屋根が引き締まった印象を与え、高崎市の指定重要文化財に指定されています。
門をくぐると右手に鐘楼、そのおくが寺務所、正面が本堂で、高低差も少なく比較的シンプルな伽藍構成です。


【写真 上(左)】 仁王門内の参道
【写真 下(右)】 開山堂跡地
参道左手には開山堂跡地。
案内板には「長谷寺を開山された修験道の祖『役行者様』の像を安置する堂」で(開山堂建立予定)と記されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 唐破風
本堂(観音堂)は存在感があります。
入母屋造銅板葺で正面に大がかりな唐破風向拝を起こしています。
この唐破風の端部(水引虹梁の上)はすべて彩色の彫刻群で埋め尽くされ、隙間がありません。

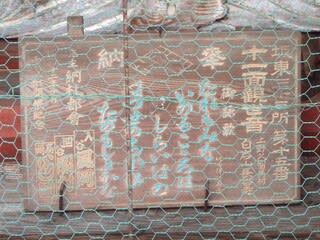
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 坂東霊場の札所板
向拝はふところ深くやや薄暗くなっており、秘仏の多い十一面観世音菩薩が御座す、観音堂らしい佇まいです。
本堂(観音堂)および仁王門は高崎市の指定重要文化財に指定されています。
なお、この本堂(観音堂)は2021年12月に新築落慶し、境内の伽藍構成もいくつか変更されています。


【写真 上(左)】 長谷寺の新本堂-1
【写真 下(右)】 長谷寺の新本堂-2
秘仏の御本尊十一面観音立像は、カヤ材の一木割矧造で平安時代後期(藤原時代)の作とされ、県指定重要文化財に指定されています。
前立像は桧の寄木造で玉眼がはめ込まれ、全体に金箔が施されている仏像で、鎌倉時代末の作と推定され、こちらも県指定重要文化財に指定されています
御朱印は寺務所内の授与所にて拝受できます。
坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格霊場(第23番の次)、役ノ行者(役ノ尊者)の3種の御朱印が授与されています。(現在、役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印の授与は不明。)
〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印(専用納経帳/御朱印帳) 〕
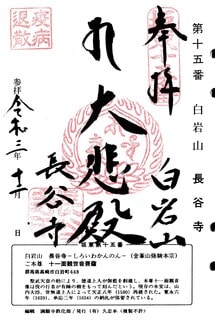
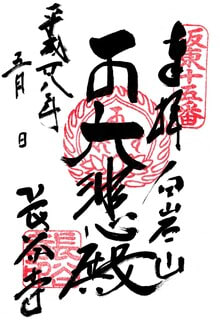
中央に御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の揮毫と三尊の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「大悲殿」の揮毫。
右上には「坂東十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
三尊の種子は、おそらく中央が御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」、右が毘沙門天の種子「ベイ」、左が不動明王の種子「カン/カーン」と思われます。
十一面観世音菩薩と毘沙門天と不動明王の三尊を安置する例はかなりあるので、その様式の種子かと思われます。
(十一面観世音菩薩の脇侍として、毘沙門天と不動明王が御座されている例 → 甲府の青松院)
〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(御朱印帳) 〕
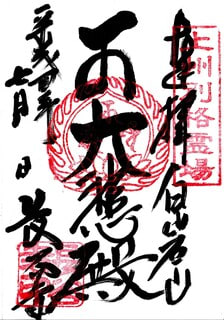
尊格構成は上の坂東霊場と同様です。
右上には「上州別格霊場」の札所印。右下には山号の揮毫があります。
〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(専用納経帳) 〕
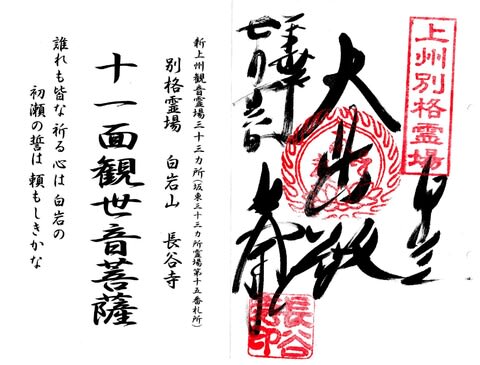
見開き御朱印です。右側は「上州別格霊場」と同様。左側には御本尊の「十一面観世音菩薩」と御詠歌が印刷されています。
〔 役ノ尊者(役ノ行者)の御朱印 〕
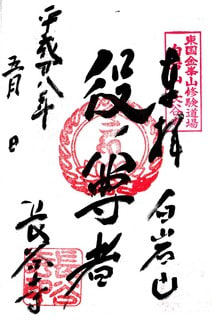
当山の開基とされる役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印です。
中央にはおそらく金剛蔵王権現の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「役ノ尊者」の揮毫。
右上には「東国金峯山修験道場 白岩山 長谷寺」の印。右下には山号の揮毫、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
29.白山神社
公式Web
高崎市白岩町450
御祭神:菊理媛大神
御朱印揮毫:白山神社(印判)
公式Webの社伝(白山記(しらやまき))によると、「白鳳年中白山々 伊邪那美の神を奉祀、守護神とす」。
「白鳳」はいわゆる私年号で、通説では白雉(650-654年)の別称とされます。
加賀の白山はふるくから霊山として崇められ、養老元年(717年)に越前の泰澄大師によって開山。
主峰の御前峰に奥宮が創建され、白山妙理大権現が奉祀されたと伝わります。
白山信仰は神仏混淆(修験道)の色彩が強く、白山妙理大権現(白山権現)は伊弉冊尊の化身、本地仏は十一面観世音菩薩、別当は白山寺(白山本宮)であったと伝わります。
全国の白山神社の総本社、白山比咩神社(石川県白山市)の御祭神は白山比咩大神(=菊理媛尊)、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。
菊理媛大神(ククリヒメ)は、伊弉諾尊(伊邪那岐)および伊弉冉尊(伊邪那美)とふかいかかわりをもつ神様で、国内の一宮一覧である『大日本国一宮記』には「白山比咩神社、下社(本宮)伊弉冊尊、上社(三ノ宮)菊理媛、号白山権現」と記されています。
文明十二年(1480年)、白山寺(白山本宮)が加賀一向一揆の攻撃で焼失し三ノ宮に遷座したこともあいまって、白山信仰と菊理媛の関係については諸説ありますが、江戸時代の多くの書物には白山比咩神と菊理媛は同一神と記されています。
明治初期の神仏分離により修験道としての白山権現は廃され白山比咩神社として改組されましたが、全国の白山権現の多くは白山神社となり、菊理媛神を御祭神としています。(菊理媛神とともに伊弉諾尊、伊弉冉尊を御祭神とする例も多くあり。)
当社社伝には「白山権現の本地である十一面観世音を役の行者小角が背負い、碓日峰(碓氷峠)に至り『どこかに奉祀する霊地はないかと・・・』その地を探し現在の高崎市白岩町にて謹んで祀られる(中略)これが、本尊十一面観世音であり守護神として伊邪那美の神を祀った。これが白山神社になった所以である。」とあります。
永禄六年(1563年)、武田勢による箕輪城攻略の兵火で社殿は消失しましたが、明治二年(1869年)には神仏区画令により(白岩一村の)総鎮守となったといいます。
場所は長谷寺(白岩観音)のすぐとなりです。
参拝時に長谷寺(白岩観音)の駐車場は利用できません。
当社の駐車場はこちらになります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鳥居
長谷寺(白岩観音)の参道入口横から山手方向に登っていきます。
参道起点から鳥居も拝殿も見えるので迷うことはありません。
鳥居は朱塗りの明神鳥居で、高さのある亀腹が目をひきます。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 向拝
正面の拝殿は、入母屋造銅板葺流れ向拝の整った外観。
水引虹梁まわりは拝殿幕でおおわれて詳細不明。身舎にかけて海老虹梁。
向拝正面は桟唐戸で見上げに「白山神社」の扁額が掲げられています。
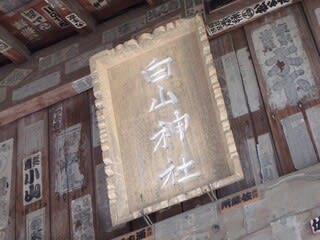

【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 境内社
往年の神仏混淆を物語るように、境内各所に石碑の境内社が祀られています。
こちらは、有名な八王子了法寺の萌えキャラを担当されたとろ美さんが手がけた御朱印帳が有名です。
限定のようですが、はるな式典埋木舎の事務所(高崎市下室田町884-1)で入手できるかもしれません。
通常は非常駐で、拝殿前に書置御朱印が用意されています。
Web情報によると、境内社の大山祇神、北野社、若宮八幡宮、稲荷社、猿田彦大神、蠶影山大神などの御朱印も授与されているようですが、こちらは時期限定かもしれません。
〔 御朱印 〕
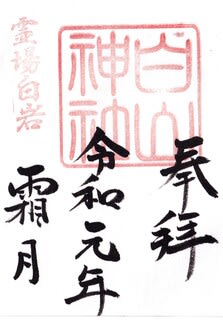
社号印と「霊場白岩」の印が捺されているシンプルな御朱印です。
30.大嶽山 瀧澤寺
公式Web
高崎市箕郷町白川1583
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊
札所:
札所本尊:
高崎市箕郷町の山あいにある曹洞宗寺院。
公式Webの寺伝によると、平城天皇の御代(806-809年)に慈覚大師が開山駐錫の聖地としてこの地に一堂を建立。
不動尊と二童子が安置され、満行山 不入院 瀧澤禅寺と号して開創。
550年後に厚山慶淳和尚が曹洞宗に改宗したとされます。
ここで気になったのは、開創時の「満行山」という山号です。
このエリア(榛名東麓)において、「満行」という名称は格別な意味をもっていると考えられるからです。
以前引用した『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)を当たると、でてきました大嶽山 瀧澤寺の縁起が。
しかも「船尾山炎上譚」にふかくかかわる内容です。
要点を上記論文から引用させていただきます。
・瀧澤寺は古くは天台宗の寺院で慈覚大師円仁の開山。不入の滝がある地に満行山 不入院 瀧澤寺があった。
・天喜四年(1056年)、千葉左衛門常胤は、源頼義公の奥州討伐軍に従ってこの地を過ぎた際、一子相満を修学のため寺に預けた。
・その後、相満が行方知れずとなり、常胤は寺僧が隠したと思い火を放ち一山を焼いたが相満は見つからなかった。
・この時僧が不動尊を擁して難を逃れ、霊夢を得て一堂を結んだのが現在の瀧澤寺だという。(なお、論文筆者は時代的に「常胤」は「常将」であろうと記されている。)
船尾山 柳澤寺の縁起には太夫満行が榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建とあります。
当寺の当初の山号「満行山」、そして上記の縁起からして、太夫満行が榛名山中に創建した"妙見院息災寺"となんらかのゆかりをもつのではないでしょうか。
なお、高崎市資料には、井伊直政の伯父である中野越後守が天正年間(1573-1592年)に再興とあります。
霊場札所ではないありませんが、「曹洞宗ナビ」に「御朱印あり」とあったので、参拝してみました。


【写真 上(左)】 瀧澤寺
【写真 下(右)】 瀧澤寺の本堂
山裾を巧みに利用した山内は奥行きがあり、予想以上に規模が大きく宿坊「紫雲」も併設されています。
入口に二体の石造仁王尊像。
右手の「巡り経蔵」は市指定重要文化財で、白亜の建物の中では、経巻を納めた六角形に区切られた棚が中央の主軸を中心に回る仕組みになっているそうです。
その先に鯉が泳ぐ池と山門。
本堂は入母屋造桟瓦葺で、張り出しの大きな軒唐破風つきの向拝を構えています。
どこを切り取っても純和風のつくりで、宿坊では精進料理を提供し、座禅ができることもあって外国人観光客に受けそう。
実際、サインやWebに英語表記があり、こういう層も受け入れているかもしれません。
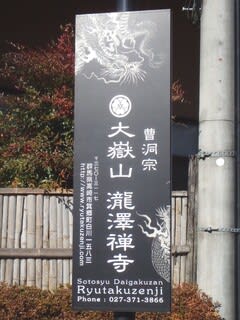
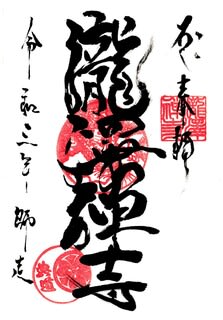
【写真 上(左)】 瀧澤寺のサイン
【写真 下(右)】 瀧澤寺の御朱印
ご住職は気さくな感じの方で、本堂内に上げていただき、堂内のご説明もして下さいました。
本堂欄間の彫刻は明治初期の相沢比吉の作で、目の不自由だった相沢比吉が三年間の時間を要して彫り上げた夫婦龍とのこと。
境内の銀杏の古木から掘り出し、玉を握っているのが男龍。爪の数などのご説明もいただきました。
御朱印は庫裡にて直書いただけました。
31.(箕郷町富岡)飯玉神社
高崎市箕郷町富岡254
主祭神:宇気母智神
旧社格:村社
御朱印揮毫:(箕郷富岡)飯玉神社

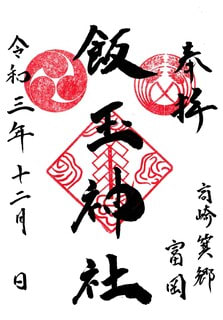
情報が少ないですが、『群馬県群馬郡誌』によると旧村社のようで、御祭神は宇気母智神、創建は寛永六年(1629年)、氏子戸数は115となっています。
所在は車郷村(くるまさとむら)大字富岡で、車郷村は昭和30年(1955年)4月に箕輪町と合併して箕郷町となっています。
鳴沢湖そばの高崎市立車郷小の東側に御鎮座。
石垣に囲まれた社頭。その先に石造りの明神鳥居で「正一位 飯玉大明神」の扁額が掲げられています。
正面に入母屋造桟瓦葺妻入の拝殿。見上げれば妻飾りに蕪懸魚と大棟鬼板には経の巻獅子口。
妻部に向拝を構え、向拝柱、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。
社殿裏手には、数座の境内社が御鎮座。
すぐそばの真福寺観音堂には石神仏群が残り、市指定重要文化財に指定されています。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
32.(生原)北野神社
高崎市箕郷町生原1739-1
主祭神:菅原道真公ほか五柱
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
御朱印揮毫:(生原)北野神社
例大祭の稲荷流獅子舞、”あばれ獅子”で知られる箕郷町生原(おいばら)地区の天神様です。
境内由緒書によると、永禄三年(1560年)の勧請と伝えられ、現在の社殿は、榛名神社の双龍門などで知られる原山の棟梁清水和泉(充賢)と、熊谷の彫刻師小林源太郎の手により文久元年(1861年)に完成。
本殿は木造檜皮葺唐破風造で、昇り龍、降り龍をはじめ精緻な彫刻が施され、市の重要文化財に指定されています。
『群馬県群馬郡誌』によると所在は上郊村大字生原、社格は村社、御祭神は菅原道真公ほか五神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は61で、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
合祀神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十一年字諏訪の無格社諏訪神社・同境内末社一社・字中内出無格社神明宮・字中新田無格社・白山神社を合祀せり」とあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
広めの境内。社頭の石造明神鳥居には「天満宮」の扁額。
石段を数段昇って石灯籠二対の先に、均整のとれた入母屋造本瓦葺流れ向拝軒唐破風の拝殿。
向拝柱、水引虹梁両端正側に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を備えています。
覆屋のなかの本殿は、名工の作で市の重要文化財指定されているだけに見どころ多数ですが、ここでは省略します。
境内社は少ないですが、参道向かって右に庚申塔があります。

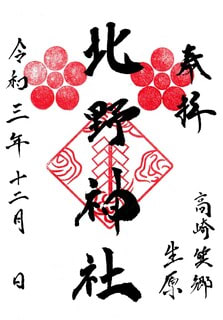
【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
33.(生原)嚴島神社
高崎市箕郷町生原1728-1
主祭神:市杵島姫命
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

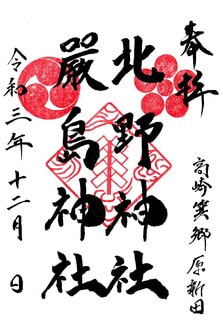
箕郷町原新田(生原二区)に御鎮座の嚴島神社。
境内由緒書には、この地区は元来水利に恵まれていませんが、竜昌寺前のみ清水が湧き湿地をなした唯一の水源地であったので、水信仰の神である弁天様が祀られた旨記載されています。
弁天様は、元亀天正(1570-1593)の昔、川浦氏が柏木沢東谷を開墾した際に立派な石臼を掘り当て、こちらを祀ったことに由来するものとされています。
『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は市杵島姫命、創立は享保年間(1716-1736年)、氏子戸数は60とあります。
(原新田)北野神社から龍昌寺を越えた南側に御鎮座で、駐車スペースはありません。
県道123号に面した社頭に石造の明神鳥居で扁額を掲げていますが読解不能。
その先に石敷の参道が延び、正面にブロック塀に囲まれた銅板葺一間社流造の朱塗りの社殿。
向拝柱、水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を備えています。
社殿の背後はうっそうと茂る竹林で、こちらが件の水源地なのかもしれません。
御朱印は(原新田)北野神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
34.(原新田)北野神社
高崎市箕郷町生原1
主祭神:菅原道真公
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

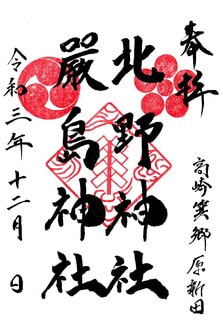
箕郷町生原原新田地区に御鎮座の天神様。
境内に由緒書はなく詳細不明ですが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は菅原道真公、明治23年9月再建、氏子戸数は60とあります。
かなり広い境内で生原2区集会所もあります。社叢がなく、明るい境内です。
切妻造朱色の銅板(?)葺平入りの拝殿で、奥に切妻造妻入の本殿が連接しています。
本殿裏手には、猿田彦大神、御嶽山大権現、秋葉山大権現、古峯神社などの境内社が御鎮座。
御朱印は(生原)嚴島神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
35.(保渡田)白山神社
高崎市保渡田町905
主祭神:菊理比咩命、伊邪那美命
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(保渡田)白山神社


境内に複数の由緒書がありましたが、どれも白山信仰や白山神社総本宮にかかわるもので、当社についての説明はありませんでした。
『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は菊理比咩命、伊邪那美命、創建は明治十六年、氏子戸数は27とあります。
カーナビでは表示されず、勘でたどり着きました。
カインズ箕郷店から東に延びる道を200mほど進んだ交差点に面して御鎮座。
駐車スペースはありません。
道から数段高く、石垣の上が境内です。
朱塗りの明神鳥居に「白山神社」の扁額。
正面に切妻造銅板葺妻入で向拝を付設した社殿。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
36.(保渡田)諏訪神社
高崎市保渡田町1800
主祭神:建御名方神
旧社格:無格社
御朱印揮毫:(保渡田)諏訪神社


「一人立ち三頭舞」の稲荷流獅子舞で知られる諏訪神社です。
境内に獅子舞の説明板はありましたが、由緒書はありませんでした。
『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は建御名方神、創建は不詳、氏子戸数は71とあります。
保渡田古墳群の西側に御鎮座。
こちらも石垣に囲まれ、道から数段高い境内。
このかたちは境内は広くても物理的に車は止められないので、車でのアクセスは難儀します。
鳥居はなく、社頭に一対の狛犬。
正面に切妻造桟瓦葺平入りの社殿。桟唐戸にしめ縄が張られ、向拝見上げに「諏訪神社」の扁額。
高台にあって日当たりよく、明るい境内です。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
37.(保渡田)榛名神社
高崎市保渡田町乙318
主祭神:火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神
旧社格:村社
御朱印揮毫:(保渡田)榛名神社

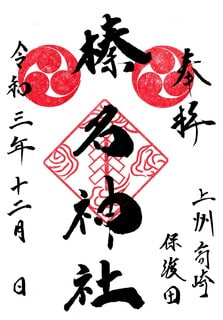
こちらも境内に由緒書はありませんが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は村社、御祭神は火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は55とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
祭神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「火産霊命・波邇夜麻毘賣命・大日孁神・大山祇神を祭神とす」とあります。
また、「明治41年本社境内社一社・字地蔵前無格社神明宮・字新宿無格社三島神社を合併せり」とあります。
おとなりは工場とその駐車場ですが、境内は厳かな空気につつまれています。
こちらも石垣の上に数段高く境内地。
石造の明神鳥居に「村社 榛名神社」の扁額。
社叢に囲まれた参道のおくに切妻造桟瓦葺平入りの拝殿と入母屋造桟瓦葺妻入りの本殿が連接しています。
拝殿より本殿の規模が大きく、拝殿の上に本殿の鬼板が見えます。
境内には数座の境内社が御鎮座。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
38.天王山 薬師院 徳昌寺
高崎市足門町566
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:
元司別当:(足門)八坂神社
なかなか情報がとりにくい寺院ですが、『群馬県群馬郡誌』に「宗派:真言宗、所在:金古村大字足門、創立年月日:不詳、本尊:不動明王、本寺:石山寺、開山:不詳、檀徒戸数103」とあります。

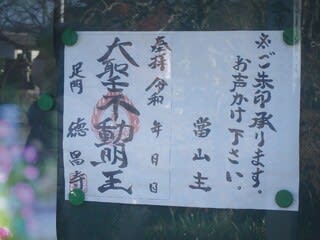
【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御朱印授与掲示
霊場札所ではなくこぢんまりとしたお寺をイメージしていましたが、本瓦葺の立派な山門にびっくり。
山門脇の掲示板に御朱印の見本が掲出されているので、御朱印授与に積極的なお寺さんかと思います。
参道右手に立派な手水舎。左手に地蔵尊。
さらにその先左手に第二次世界大戦中のニューギニア戦線の戦没者を供養する聖観世音菩薩が御座します。
本堂手前左手に宝形造桟瓦葺の聖天堂。
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で向拝柱を備え、向かって右手には修行大師像が御座します。
立派な鐘楼もあり、伽藍は整っています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。
39.(足門)八坂神社
高崎市足門町529
御祭神:須佐之男命、埴山媛命、大雷神、宇迦之御魂神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:天王山 薬師院 徳昌寺(足門、真言宗豊山派)
御朱印揮毫:(足門)八坂神社
境内由来書には、「長元四年(1031年)千葉常将が船尾寺に向かう時この地で八坂神に祈念したのに由来し、永禄年中(1558-1570年)、武田信玄公の箕輪城攻撃の際兵火に罹り社殿焼失とも伝える。しかし、八坂神社の上野国への勧請は鎌倉時代以前の記録はなく、尾張島津八坂御師の上野への布教活動が盛んになる15世紀以後に当地方に勧請されたのであろう。」という興味ぶかい記述があります。
千葉氏は当社の東側、引間町に位置する三鈷山 吉祥院 妙見寺とかかわりをもつとされます。
また、船尾山 等覚院 柳澤寺の縁起にも千葉常将が登場します。
当社は位置的に妙見寺と柳澤寺のあいだにあるので、千葉氏や「船尾山炎上譚」となんらかの関係があったのかもしれません。
生原の満行山 善龍寺(参拝済、御朱印不授与)にも、「永禄六年(1563年)二月箕輪城落城の際、兵火かかり焼失」という伝えがあります。(→情報出所は「古今東西 御朱印と散策」様)
また、同Webによると、箕輪城落城後、信玄公は武田四天王の一人、内藤修理之亮昌秀(昌豊)をして箕輪城の管理に当たらせ、善龍寺の再建を命じ寺号を満行山(当初は神明山)と改めさせた、とあります。
信玄公がどうして善龍寺の山号を「満行山」と改号したのかわかりませんが、結果として生原の地に「満行山」を山号とする武田家ゆかりの寺院が残ったことになります。
なお、善龍寺には内藤修理之亮昌秀の墓も残り、「善龍寺の内藤塚」として高崎市指定史跡に指定されています。
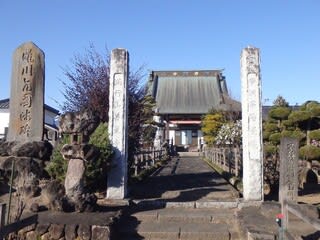

【写真 上(左)】 善龍寺-1
【写真 下(右)】 善龍寺-2
『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字足門、社格は村社、御祭神は須佐之男命、創建は不詳、氏子戸数は130とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
同じく『群馬県群馬郡誌』に、「明治42年9月8日字榛名原に祭祀せる無格社榛名神社・字雷電に祭祀せる無格社雷電神社を合併す。」「本社は諸公の崇敬殊に厚く、慶安二年徳川幕府は三石一斗を社領とし年々国家安穏五穀豊穣の祈願あらせられ(略)高崎領主安藤対馬守崇敬厚く」とあります。
また、境内由来書によると、明治42年に旧稲荷神社も合祀しているようです。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
かなり広い境内で、社頭に「村社 八坂神社」の社号標。石造台輪鳥居には「牛頭天王」の扁額。
拝殿は入母屋造桟瓦葺。向拝柱はなく、正面格子戸の上に「八坂神社」の扁額を掲げています。
本殿の様式はよくわかりませんが、見事な彫刻が施され見応えがあります。


【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
40.鈷守稲荷神社
高崎市金古町1929
御祭神:
旧社格:
御朱印揮毫:鈷守稲荷神社


こちらについては由緒書がなく、『群馬県群馬郡誌』にも記載がないので詳細は不明です。
金陽山 常仙寺の参道に面しているので、こちらからも当たってみましたが、やはり情報は得られませんでした。
亀腹の高い石造の稲荷(台輪)鳥居に「稲荷大明神」の扁額。
すぐ正面に朱塗りの切妻造瓦葺妻入りの社殿で、「金古守稲荷大明神」の扁額。
こぢんまりとしていますが、整った印象のお社です。
御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。
41.金古諏訪神社
高崎市金古町1351
御祭神:建御名方神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
御朱印揮毫:金古鎮守 諏訪大神
『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字金古、社格は村社、御祭神は建御名方神 外八神、創建は不詳、氏子戸数は383とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。
同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十二年本社境内末社諏訪社琴平社外十社を合併したり。」とあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
地域の中核社らしくゆったりとした境内。
道路側に参道と社殿、奥側に駐車場という、いささか変わった配置です。
社頭瑞垣の梶の葉紋が、お諏訪様であることを主張しています。
石灯籠一対の先に石造の台輪鳥居で「正一位諏方大明神」の扁額。
正面に狛犬一対と入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風付きの拝殿。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
兎毛通に朱雀(?)の精緻な彫刻と、その上の鬼板は経の巻獅子口で梶の葉紋。
すぐうしろに本殿が連接しています。
摂社末社案内として以下の掲示がありました。
・菅原神社
学問の神様 菅原道真公(天神様)
・上野国十二社
県内の一之宮から十二之宮を勧請
・奥宮(元宮)
諏訪大明神を祀る境内最古の石祠
とくに、上野国十二社(貫前神社(富岡)・赤城神社(前橋)・伊香保神社(渋川)・甲波宿禰神社(渋川)・大国神社(伊勢崎)・榛名神社(高崎)・小祝神社(高崎)・火雷神社(玉村)・倭文神社(伊勢崎)・美和神社(桐生)・賀茂神社(桐生)・宇芸神社(富岡))は見応えがあります。
こちらの太々神楽は二十五座の舞を演じるもので、立派な朱塗りの神楽殿が設えられています。
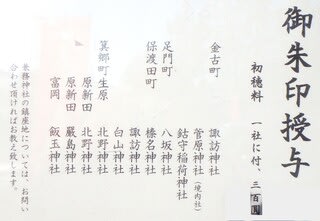
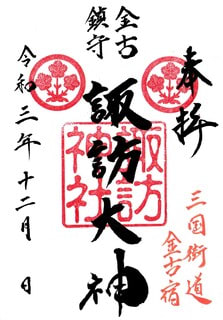
【写真 上(左)】 御朱印授与案内
【写真 下(右)】 御朱印
御朱印は境内授与所にて拝受しました。
周辺の神社の本務社を務められ、当社を含め11社10体の御朱印を授与されています。
42.菅原神社
高崎市金古町1351
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社金古諏訪神社の境内社
御朱印揮毫:菅原社

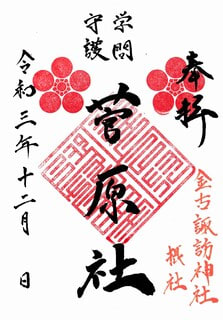
金古諏訪神社の境内社で、御朱印を授与されています。
金古諏訪神社拝殿向かって右手に御鎮座。
金属製の神明鳥居の先に数段高く石祠が二座御鎮座。
「金古の天神様 菅原神社」の表札、「天満宮」「学力向上・受験合格祈願」の赤い幟が建てられ、地域の尊崇篤いことがうかがわれます。
御朱印は金古諏訪神社境内授与所にて拝受しました。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ By Your Side - WISE & Kana Nishino
■ Airport - 今井優子
■ noctiluca - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
お薬師さまの年
■ Again - アンジェラ・アキ
あけましておめでとうございます。
今年は寅年。12年に一度のお薬師さまゆかりの年です。
大医王、医王善逝ともいわれ、衆生を病苦から救う薬師瑠璃光如来の年に、新型コロナが収束することを願います。
今年は各地の薬師如来霊場でご開帳が予定されています。
詳細情報は後日まとめたいと思いますが、まずは年のはじめに上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師さまの御朱印をご紹介してみます。


【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)
【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)


【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)
【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)
せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。
薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。


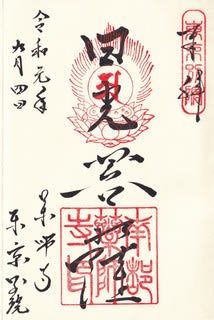
-------------------------------
ことしは世相が明るくなって、
↓ みたいな余裕かました名曲が生まれるといいな・・・。
■ 海 - サザンオールスターズ
■ Music Book - 山下達郎
~ Music Book 開いたら
メロディの雨が 肩をぬらして
Music Book 降りそそぐ
それは さわやかなハーモニーもって 弾む ~
■ YES MY LOVE - 矢沢永吉
■ いっそセレナーデ - 井上陽水
■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里
あけましておめでとうございます。
今年は寅年。12年に一度のお薬師さまゆかりの年です。
大医王、医王善逝ともいわれ、衆生を病苦から救う薬師瑠璃光如来の年に、新型コロナが収束することを願います。
今年は各地の薬師如来霊場でご開帳が予定されています。
詳細情報は後日まとめたいと思いますが、まずは年のはじめに上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師さまの御朱印をご紹介してみます。


【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)
【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)


【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)
【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)
せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。
薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。


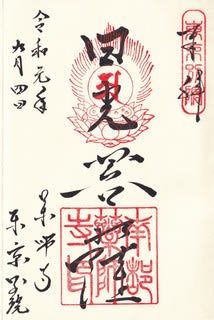
-------------------------------
ことしは世相が明るくなって、
↓ みたいな余裕かました名曲が生まれるといいな・・・。
■ 海 - サザンオールスターズ
■ Music Book - 山下達郎
~ Music Book 開いたら
メロディの雨が 肩をぬらして
Music Book 降りそそぐ
それは さわやかなハーモニーもって 弾む ~
■ YES MY LOVE - 矢沢永吉
■ いっそセレナーデ - 井上陽水
■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
【旧記事】■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPしています。
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔以下は旧記事へのリンクです〕
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3 からのつづきです。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
■ 荒神山 地蔵院 龍昌寺
熊谷市柿沼499
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・『新編武蔵風土記稿』の柿沼村の項に「京都智積院末 中興開山海寶慶長十九年六月十二日寂ス 本尊地蔵ハ恵心ノ作 荒神社 辨天社 稲荷社 聖天社 金毘羅社 観音堂 此堂焼失後イマダ再建ナラス」とあります。
・境内石碑には、慶長年間(1596-1615年)、海宝上人の開基で智積院直末の格院とあり、忍秩父観音霊場の第1番初願所であることからしても、相当の格式をもつ寺院と思われます。
・樹木が少なくすっきり明るい境内。本堂は入母屋造本瓦葺でがっしり大ぶりな流れ向拝を構えています。見事な本瓦葺や格調高い山号扁額から名刹の矜持が感じられます。
・御朱印は庫裡にて忍秩父三十四観音霊場第1番の御朱印を拝受しました。幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印も捺されているので、2札所兼用の御朱印と思われます。
・こちらの忍観音霊場の札所本尊の情報がなく、とりあえず聖観世音菩薩の御真言をあげて参拝しましたが、いただいた御朱印の種子は「キリーク」。ご住職に千手観音か如意輪観音かをお伺いすると、なんと如意輪観世音菩薩とのこと。初番から如意輪観音の観音霊場はあまり記憶にありません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第1番 如意輪観世音菩薩(大悲殿)


※ 幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印あり
■ 天神山 観音院 吉祥寺
熊谷市原島682
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第33番
・『新編武蔵風土記稿』の原島村の項に「埼玉郡上ノ村一乗院末 慶安二年境内観音堂領トシテ十石ノ御朱印ヲ賜フ 中興ノ僧ヲ榮快ト云寛文十三年(1673年)正月二十五日寂ス 本尊大日ヲ安ス 観音堂 十一面観音ヲ安ス 運慶ノ作ナリト云伝フ」とありますが、開基・開山、創建年代等は不明です。
・緑濃いよく整備された境内。山門は本瓦葺。本堂は寄棟造銅板葺で、端正な流れ向拝を置いています。
・御朱印は忍観音霊場のもので、当寺第33番と上奈良の第24番妙音寺を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第33番 十一面観世音菩薩


■ 熊谷山 報恩寺
公式Web
熊谷市円光2-8-1
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・当地の武将、熊谷直実ゆかりの曹洞宗の名刹で、創建について公式Webはつぎのように記しています。
・熊谷直実は一ノ谷の戦いで平家の御曹司、平敦盛を討ち取たことで自責と無常を覚え、京にのぼって法然上人に入門して僧侶(法力房蓮生)となりました。
熊谷に残された家族はこれを悲しみ、直実の妻は病をえて亡くなってしまいます。
そして残された直実の息女、玉津留姫のもとに直実他界の知らせが入りました。
姫は泣き暮らした果てに、仏さまのお力にすがり両親の冥福を祈るほかないと、建暦二年(1212年)に当寺を創建しました。
その後、関東管領上杉能憲が永和四年(1378年)に再建、管領職を継いだ上杉憲方も報恩寺の復興に力を注ぎました。この両者は「中興開基」という呼び名で、現在まで大切にまつられています。
寛永元年(1624年)、上之の龍淵寺第14世萬矢大拶禅師は、あらたに曹洞宗の寺院として開山しました。
・一方、熊谷市資料には「熊谷直実の子直家が、父の没後菩提の為に浄土宗寺院として創建したものと伝わります。」とあり、「本尊は熊谷直実の娘千代鶴姫玉鶴姫の開基・守佛であり、多くの信仰を集めてきました。」という含みのある表現をしています。
・さらに『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡成田龍淵寺末 当寺ハ昔熊谷直実ノ子直家 父ノ没後菩提ノ為ニ起立セル浄土門ノ草庵ニテ 直実カ木像ヲ置シカ 遥ノ後東照宮此邊御遊●之時 由緒ヲ御尋ノ上新ニ熊谷寺ヲ造立セサセラレテ 当所ハ猶其マゝニテオカレシテヲ 其後又一寺ニ取立テ報恩寺ト号ストイヘリ 此説熊谷寺ノ伝ヘト同シカラス 姑両説を記シオケリ 中興開山ヲ萬室察和尚ト云(略)本尊阿彌陀ヲ安ス 佛師安阿彌カ作ト云 其余直実カ女ナリシ千代鶴玉鶴ノ守佛ナリト云 薬師ヲモ安置セリ」とあります。
・たしかに熊谷寺の由緒とは「同シカラス」内容なので、興味のある方は読み比べてみては・・・。
・いずれにしても、徳川家康公も絡んだ熊谷寺との複雑な経緯が感じられます。
・当山の伽藍神として袖引稲荷が祀られ、こちらの御由緒も玉津留姫にかかわるものです。
・熊谷直実には美貌をうたわれたふたりの息女がおりました。姉が玉津留姫、妹が千代鶴姫と伝わります。
・この袖引稲荷は、玉津留姫が内池町の菩薩院にあったお稲荷さまが荒れ果てていたのに心を痛め当山にお移ししたものとされます。
・玉津留姫が戦乱で離れ離れになっていた妹の千代鶴姫に巡り会いたいとお稲荷さまに願をかけたところ夢の中に白狐に乗られた霊神が現れ「これより京に向いて行けば願いは叶うであろう。」とお告げがあり、京に向け出立すると焼津のあたりで袖を引くように千代鶴姫に出会ったため、お稲荷さまの神通力に感激し「袖引稲荷」と呼ぶようになったと伝わります。
・伽藍神の由緒譚の主役も玉津留姫ですから、やはりこのお寺は玉津留姫との所縁がすこぶる強いものとみられます。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。御朱印は御本尊のもののみで札所御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


■ 赤城久伊豆神社
熊谷市石原1007
御祭神:豊城入彦命、大己貴命、大山祇命
旧社格:旧石原村鎮守
元別当:羽黒山 不動院 真宗寺(熊谷市石原)
授与所:境内授与所
・赤城神社と久伊豆神社の合祀(合社)という、北関東ならではの神社です。
・『埼玉の神社』には、「『風土記稿』には『赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす』と載る。これは戦国末期、古くから当地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。」とあります。
・同書によると、赤城神社は、宮城村鎮座の赤城神社から勧請。久伊豆神社は、成田氏の崇敬する神社であった。両社合祀の経緯は「忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという。」とのことです。
・本殿は寛延三年(1750年)建立とされる二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められているとのこと。
秋山藤八正勝、石原吟八郎、前原藤次郎などの名工の名が棟札に残り、その力量を示す建造物として市指定文化財となっています。
・もともとの本殿・拝殿は赤城山に相対するように創建され、久伊豆神社合祀の際に建て替えられ、現在の本殿・拝殿は忍城に相対する形で建っているとのことです。
・参拝時ご不在でしたが、たしか境内にご神職の電話番号が貼り出されており、こちらに連絡すると、お出でになられて無事拝受できました。熊谷七福神(福禄寿)の御朱印は通常不授与の模様です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:赤城久伊豆神社 直書(筆書)


■ 雪渓山 普門院 松巖寺(松岩寺)
公式Web
熊谷市本石1-102
臨済宗妙心寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第2番
・情報があまりとれませんが、公式Webに「慶長元年(1596年)に喜庵西堂和尚によって開創された」とあり、『新編武蔵風土記稿』の石原村の項には「東漸寺ノ末ナリ 本尊観音ヲ安セリ 開山喜庵明暦二年(1656年)十二月七日寂ス」とあるので、江戸時代前期の開山とみられます。
・山門まわりは思いっきり和風の佇まいですが本堂はかなり個性的な意匠の近代建築で、そのコントラストがなかなか強烈です。
・御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受できました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第2番 聖観世音菩薩


■ (鎌倉町)愛宕神社・八坂神社
熊谷市鎌倉町44
御祭神:軻遇突智命、須佐之男命、大市姫命、菅原道真公、事代主命
旧社格:(熊谷うちわ祭りの祭神社)
元別当:大善院
授与所:古宮神社(池上)授与所
・「熊谷うちわ祭」で有名な市内中心部に御鎮座の神社です。
・『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、熊谷うちわ祭の公式Webなどから御由緒を辿ってみます。
・大永年間(1521-1528年)に本山派修験大善院三世行源法印(大膳院)が、山城国愛宕郡御鎮座の愛宕大神を勧請したのが創祀とされます。
・文禄年間(1592-1596年)に市神・八坂・伊奈利の三神を合祀し、「愛宕牛頭天王稲荷合社」として祀られるようになりました。八坂社は京都八坂神社からの勧請と伝わります。
・明治の神仏分離により別当大善院の管理を離れ、社号を愛宕神社に改号。
・昭和20年8月の空襲により当社の社殿も灰燼に帰しましたが、戦後、八木橋デパート前にあった旧社地から現社地に移転し、社殿が再建。
・もともと現社地には宇佐稲荷神社が御鎮座されていましたが、「愛宕様が移ってくるなら少しでも広い方がよかろう」ということで、同社が境内を譲って向かいの社地に遷られたといいます。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「本山派修験 葛飾郡幸手不動院配下 水原山ト号ス 本尊不動ヲ安置ス 愛宕牛頭天王稲荷合社」とあります。
・社号については「愛宕八坂神社」としている資料もありますが、埼玉県神社庁資料では「愛宕神社」となっています。
〔うちわ祭について〕
・江戸中期の寛延三年(1750年)、各寺社毎に行っていた祭りを町内統一の祭りとし、天保元年(1830年)、町衆により愛宕八坂神社の神輿が製作。全町合同の神輿渡御をともなう夏の祭礼は神輿祭りとして定着し、華やかさを増しました。
・もともと、この祭りは、町内各店が客に赤飯をふるまったことで「熊谷の赤飯ふるまい」として評判となっていたところ、明治24年頃(天保年間とも)から泉屋横町の料亭「泉州楼」の主人がうちわを配りはじめ、これがさらに人気を集めて「熊谷うちわ祭」として定着したといいます。
・平成元年建替落成の本殿は入母屋造銅板葺流れ向拝で、両社併記の扁額を掲げています。鳶職とゆかりのふかい神社で、鳶組合の寄進垣も置かれています。
・御朱印は、愛宕神社、八坂神社ともに古宮神社(池上)授与所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.御朱印揮毫:愛宕神社 直書(筆書)


2.御朱印揮毫:八坂神社 直書(筆書)


■ 星河山 千手院 石上寺
熊谷市鎌倉町36
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第3番、熊谷七福神(毘沙門天)
・「熊谷桜」で知られる寺院ですが、お寺としての公式情報は多くありません。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 開山榮光 寛文十一年(1671年)寂ス 開基ハ当所ノ名主新右衛門カ先祖 竹井新左衛門尉信武ナリ 寛永十五年(1638年)九月卒ス 則開山榮光ノ父ナリトイヘリ 本尊千手観音ヲ安置ス 聖徳太子ノ作ト云伝フ座身長一尺二寸 観音堂 毘沙門堂 地蔵堂 千體佛堂。伊勢両社 鹿島社 星川池」とあります。
・Wikipediaには「度重なる荒川の洪水を治めるため、熊谷を支配していた鉢形城主北条氏邦は、天正二年(1574年)松岩寺あたりから石上寺先あたりまで堤を築いた(北条堤)。現在も高所である。築堤後も堤の決壊に繰り返しみまわれ、その加護を願って堤の傍に建てられたのが石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。」との縁起が記載されています。
・当寺は早咲きの熊谷桜で有名です。桜の咲き駆け(早咲き)と源平合戦における熊谷直実公の先駆け(先陣)との掛詞を由来とするそうです。
・また、近年、約400本の白い曼珠沙華(ヒガンバナ)でも知られる花の寺です。
・参道階段の先に入母屋造本瓦葺の本堂。大棟に金色の鴟尾を置き、向拝の桁行五間の堂々たる伽藍です。
・御朱印は庫裡にて親切なご住職から拝受できました。山門横の掲示板に御朱印2種の見本が貼り出されていたので、御朱印に積極的なお寺様かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第3番 千手観世音菩薩(大悲殿)


2.熊谷七福神(毘沙門天)の御朱印

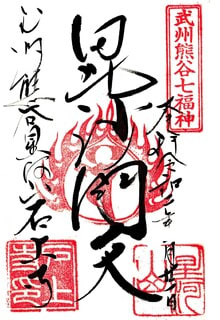
■ 熊野山 千形院 圓照寺
公式Web
熊谷市星川1-1
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:千形神社(熊谷市本町)、熊野神社(高城神社境内社)
・境内掲示および公式Webによると、天禄元年(970年)僧覚榮法師の創立で、熊谷市最古の名刹のようです。
・御本尊は阿弥陀如来。不動明王は「くまがやお不動様」といわれ、全国不動霊場に名をつらねているそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡下中条村常光院末 開山覚榮寂年ヲ伝ヘス 本尊彌陀ヲ安ス 住吉金比羅合社」とあります。
・熊谷の中心部、星川に面して祈願寺らしい華麗な伽藍を構えています。
・境内は広くはないですが、多くの仏像が安置され、それぞれの御前に御真言が掲げられています。
・御朱印は不動明王と聖徳皇太子の2種を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.不動明王の御朱印


2.聖徳皇太子の御朱印


■ (宮町)高城神社
公式Web
熊谷市宮町2-93
御祭神:高皇産霊神
旧社格:県社、延喜式内社、熊谷総鎮守
元別当:星河山 石上寺(鎌倉町)
授与所:境内授与所
・奈良時代以前の創建と伝わる古社で、『延喜式神名帳』に「大里郡一座髙城神社」と記載されている式内社に比定されています。
・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の忍城攻めの際、当社も戦火にかかり社殿を焼失。寛文十一年(1671年)に忍城主・阿部豊後守忠秋により再建されています。
・熊谷総鎮守として地域の尊崇を集め、「節分祭」「胎内くぐり」「酉の市」などが催されています。
〔拝受御朱印〕
・参拝はしていますが、御朱印は拝受していないかもしれません。


■ 藤井山 源宗寺
熊谷市平戸611
曹洞宗
御本尊:薬師如来 観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第5番
・「平戸の大ぼとけ」として知られる曹洞宗寺院です。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「浄土宗 足立郡鴻巣宿勝願寺末 開山源宗寂年ヲ伝ヘス 開基ヲ藤井雅楽助ト云 寛永七年(1630年)六月卒ス 本尊薬師観音ノ二像ヲ安ス 共ニ開山源宗ノ作ナリト云」とあります。
・開創時は浄土宗、現在は曹洞宗なので、いずれかの時点で曹洞宗に改宗されたとみられますが、詳細は不明です。
・熊谷経済新聞(2021.12.9)の記事によると、当寺所蔵の木彫仏像坐像は高さ3.48メートルの薬師如来と、3.93メートルの観世音菩薩で、その大きさから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と呼ばれています。木造寄せ木造りの仏像としては国内最大級とされ、市有形文化財に指定されています。
・本堂は老朽化したため令和3年に再建されています。
・御朱印は忍秩父三十四観音霊場のものを東竹院にて拝受していますが、下記のとおり現在、東竹院は原則御朱印不授与なので、こちらの御朱印も拝受できるかはわかりません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第5番 南無薬師瑠璃光如来 観世音菩薩

※ 画像探索中です。
■ 佐谷田神社
熊谷市佐谷田310
御祭神:誉田別命
旧社格:旧佐谷田村鎮守
元別当:
旧佐谷田村八幡社:藤林山 地蔵院 永福寺(新義真言宗/佐谷田村)
旧戸出村神明社:薬師山 東福院 金錫寺(新義真言宗/戸出村)
旧平戸村他國明神社:平戸山 多寶院 超願寺(真言宗新義/平戸村)
・『埼玉の神社』によると、明治22年に佐谷田と戸出と平戸が合併して佐谷田村となり、これにともない佐谷田の八幡社に、明治40年に戸出の神明社、大正2年に平戸の他國明神社を合祀して成立した神社です。よって、『新編武蔵風土記稿』に当社の記載はありません。(平戸の他國明神社は、後に旧地に戻っています。「長崎平戸の神を祀り他国という」との口碑があるようです。)
・『新編武蔵風土記稿』の佐谷田村の項には「八幡社 (佐谷田)村ノ鎮守 永福寺持」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の戸出村の項には「神明社 社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 別当金錫寺 新義真言宗」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「他國明神社 村ノ鎮守ナリ 祭神詳ナラス 或云佳吉ヲ祀リシ社ナリト云、超願寺持」とあります。
・佐谷田の八幡社については『大里郡神社誌』に、享保七年(1722年)に宗源宣旨を受け正一位になったことや、寛政五年(1793年)に伯家に願い出て八幡宮の神号を受けた時の添え状の記載があります。
・御朱印は佐谷田神社より拝受しましたが、令和3年12月現在、佐谷田神社の本務神社は上之の上之村神社となっており、御朱印も上之村神社での授与かもしれません。(拝殿前書置きの可能性も。)
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:佐谷田神社 筆書


■ 梅籠山 久松寺 東竹院
熊谷市久下1834
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第4番、熊谷七福神(寿老人)
・源平合戦期の武将、久下次郎重光が開基、月擔承水法師が開山となり創建。深谷城主上杉三郎憲賢が中興開基し寛永十九年(1642年)に寺領三十石の御朱印拝領という名刹です。
・『新編武蔵風土記稿』の久下村の項には「下総國結城孝顕寺末 古は天台宗ナリシト云 本尊釋迦 開基ハ久下次郎重光、建久七年(1196年)七月卒ス 又久下権守直光 元久元年(1204年)四月卒ス コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト 東鑑ニ其コトハ見エス 直光ハ熊谷直実ノ姨母ノ夫ナリト載ス 開祖ハ月擔承水法師 安貞元年(1227年)八月示寂 中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郎憲賢ニテ永禄十一年(1568年)七月卒ス 此時ノ僧ヲ的翁文中ト云」との記載があります。
・久下氏については、熊谷市江南文化財センター資料「報告 梅籠山久松寺「東竹院」に関する歴史概要」に詳しく述べられていますが、この資料によると、「久下氏は武蔵国大里郡久下郷を名字の地とする中世武家」で、治承四年(1180)、源頼朝が挙兵すると、久下直光・重光父子は熊谷次郎直実とともに平家方で参戦した。のちに頼朝方に転じて活躍、一ノ谷の合戦などに戦功をあげ、頼朝より伊豆国玉川荘・美作国印庄・丹波国栗作郷などを与えられた。」とのことです。
・御朱印は現在、庫裡前に「御朱印不授与」の旨の掲示があり原則授与されていないそうですが、「忍秩父観音霊場」巡拝中の旨告げると、ご好意で授与いただけました。ただし、これも特例的なご対応で、霊場御朱印も原則不授与かもしれません。
・団体で御朱印の授与を求められることがあり、対応できないのでこのようなかたちにしている、とのことでした。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


2.忍秩父三十四観音霊場第4番 南無釋迦牟尼佛


----------------------------
以降は、荒川を渡った旧・大里郡江南町、大里町の寺社です。
■ 龍谷山 静簡院
熊谷市成沢125(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番
・関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番の札所を務められる曹洞宗の寺院です。
・霊場ガイドおよび山内由緒書を参考に由緒をまとめてみます。
・古くは天台宗寺院の浄閑寺の名刹でしたが一時期衰退。
・大永五年(1525年)に成澤越前守隼人正義佑が当地に武蔵成澤城を築城しました。関東管領上杉憲政の麾下であった成澤氏が、甲斐の武田信玄の侵攻に対処するため活用したとみられています。
・義佑の戦死後、上杉一門武将が守備した関係から深谷城主上杉三郎憲盛によって静簡院が創建されたと伝わります。開基憲盛の墓が寺の裏に奥津城としてあり、浄閑寺跡の石垣も現存しているそうです。
・御本尊は釈迦如来で両脇仏に文殊菩薩・普賢菩薩を安置。内陣には四天王、大間には十六羅漢の額の彫刻があります。
・関東三十三観音霊場の札所本尊の観音様は、山内に露仏として安置されています。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釋迦如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番 徳王観音


■ 高根山 満讃寺
武州路十二支霊場Web
熊谷市小江川827(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州路十二支霊場 辰(普賢菩薩)
・武州路十二支霊場の公式Webによると、開山は江南町野原の文殊寺第五世霊因祖源大和尚。天正四年(1576年)稲垣若狭守重大の臣田村茂平重次を開基とし、弘化二年(1845年)当寺第十九世当付大和尚による中興と伝わります。
・御朱印は庫裡にて武州路十二支霊場拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.武州路十二支霊場 普賢菩薩


■ 東方山 保泉寺
熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。
・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。
・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。
・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内。
・こちらはご縁をいただいて御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 五台山 文殊寺
公式Web
熊谷市江南町野原623(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:文殊師利大菩薩
・「野原の文殊さま」と称され、「京都の切戸(天橋立)文殊」「山形の亀岡文殊」と並んで「日本三体文殊菩薩」のひとつとされる曹洞宗の名刹です。
・公式Webを参考に由緒などをまとめてみます。
・「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵を司る仏様で、古より学業成就の願掛けに多くの人々が訪れます。
・開山は崇芝性岱(そうししょうたい)大和尚(名応五年(1497年)寂)。
・古くは五台山 能満寺という天台宗の古刹でしたが、室町期の文明十三年(1481年)に焼失。二年後に比企郡高見の四ツ山城主、増田四郎重富が再建し、曹洞宗に改めて五台山 文殊寺を号したとされています。
・名刹らしく見どころの多い山内。山門(仁王門)は江戸中期の建築と推定され熊谷市の指定文化財に指定されています。
・御朱印は本堂横の授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 文殊師利大菩薩(文殊尊)


■ (高本)高城神社
熊谷市高本562(旧・大里郡大里町)
御祭神:高皇産霊命
旧社格:村社、延喜式内社(小)論社
元別当:地蔵院(元和四年(1618年)~)
授与所:神社そばのご神職宅
『埼玉の神社』を参考に、御由緒などをまとめてみます。
・創建年代等は不詳ながら、文久三年(1863年)、相上村吉見神社の社家徳永豊洲氏が当社旧社地の地中から「无邪志国・高城神社」とある古代の銅製の鈴を発見したとされ、延喜式神名帳の式内社に比定されています。
・当社の旧社地は村の北方(和田吉野川の流れに近い中街)でしたが川の氾濫で流れが変わって下流の中ノ森(高城街)に流され、これを神慮であるとしてこの地に御遷座となり、昭和45年、中ノ森が河川改修地域となった際に旧社地である中街の現社地へ再び御遷座されています。
・田畑のなかにお社が御鎮座。御遷座を示す説明板も設置されています。
・御朱印はすこし離れたご神職のご自宅そばにて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:高城神社 書置(筆書)


■ 吉見神社
熊谷市相上1(旧・大里郡大里町)
御祭神:天照大神
旧社格:郷社、旧上吉見領総鎮守、旧相上村鎮守
授与所:神社そばのご神職宅
・旧上吉見領二三か村のうちの上・中・下の恩田は「武州恩田御厨」といわれ、伊勢神宮の神領であったことが知られています。『埼玉の神社』では御厨で伊勢神宮を分祀する例は多く知られていることから、当社もこの例の一つとして天照大神を祀ったと考えられるとしています。
・いくつかの創祀伝承が伝わります。和銅六年(713年)御諸別王が当地を巡視した折、不毛の地であることを嘆かれ、各地から里人を移して多里郡(大里郡)を置き、豊かな地となった奉賽として、天照大神ゆかりの筬を御神体として天照大神を祀ったといいます。
・古社らしい厳かな境内。御朱印は、境内向かって右手のご神職宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:吉見神社 書置(筆書)


-----------------------
ここまでくれば東京方面への帰路、関越道・東松山ICも近いです。
結局4編構成となってしまったこの記事、やはり深谷・熊谷は御朱印王国であることを実感しました。
「青天を衝け」ですが、近代ものにしては視聴率健闘したようです。
個人的にはかなり面白く、最後まで視つづけた数少ない大河ドラマとなりました。
最後に、渋沢栄一翁ゆかりの御朱印をご紹介して、この記事を〆たいと思います。
■ 寶登山神社・寶登山神社奥宮
長瀞町長瀞1827
御祭神:神日本磐余彦尊、大山祇神、火産霊神
旧社格:県社、別表神社
元別当:會慶山 地蔵院 玉泉寺(長瀞町長瀞/真言宗智山派)
授与所:境内授与所
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:寶登山神社 直書(筆書)


「青淵ゆかりの地」の印判が捺されています。「青淵」とは渋沢栄一翁の号です。
御朱印揮毫:寶登山奥宮 書置(筆書)


「寶登山は千古の霊場」の印判が捺されています。
これは栄一翁が八十八歳のときに揮毫した軸にちなむもので、参道には栄一翁揮毫の石碑が建立されています。


【写真 上(左)】 栄一翁揮毫の石碑
【写真 下(右)】 宝登山山頂
栄一翁は熊谷と秩父を結ぶ秩父鉄道の延伸を援助し、秩父セメントの設立にも力を貸しました。
秩父や長瀞の発展に、栄一翁の貢献は多大なものがあったとされています。
【予告】
2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は鎌倉がメインの舞台となります。
年明けからは、かなり無謀な企てですが「鎌倉市の御朱印」にトライしてみたいと思います。
【 BGM 】
■ 潮見表 - 遊佐未森
■ 夢の途中 - KOKIA
■ far on the water - Kalafina
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔以下は旧記事へのリンクです〕
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3 からのつづきです。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
■ 荒神山 地蔵院 龍昌寺
熊谷市柿沼499
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・『新編武蔵風土記稿』の柿沼村の項に「京都智積院末 中興開山海寶慶長十九年六月十二日寂ス 本尊地蔵ハ恵心ノ作 荒神社 辨天社 稲荷社 聖天社 金毘羅社 観音堂 此堂焼失後イマダ再建ナラス」とあります。
・境内石碑には、慶長年間(1596-1615年)、海宝上人の開基で智積院直末の格院とあり、忍秩父観音霊場の第1番初願所であることからしても、相当の格式をもつ寺院と思われます。
・樹木が少なくすっきり明るい境内。本堂は入母屋造本瓦葺でがっしり大ぶりな流れ向拝を構えています。見事な本瓦葺や格調高い山号扁額から名刹の矜持が感じられます。
・御朱印は庫裡にて忍秩父三十四観音霊場第1番の御朱印を拝受しました。幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印も捺されているので、2札所兼用の御朱印と思われます。
・こちらの忍観音霊場の札所本尊の情報がなく、とりあえず聖観世音菩薩の御真言をあげて参拝しましたが、いただいた御朱印の種子は「キリーク」。ご住職に千手観音か如意輪観音かをお伺いすると、なんと如意輪観世音菩薩とのこと。初番から如意輪観音の観音霊場はあまり記憶にありません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第1番 如意輪観世音菩薩(大悲殿)


※ 幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印あり
■ 天神山 観音院 吉祥寺
熊谷市原島682
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第33番
・『新編武蔵風土記稿』の原島村の項に「埼玉郡上ノ村一乗院末 慶安二年境内観音堂領トシテ十石ノ御朱印ヲ賜フ 中興ノ僧ヲ榮快ト云寛文十三年(1673年)正月二十五日寂ス 本尊大日ヲ安ス 観音堂 十一面観音ヲ安ス 運慶ノ作ナリト云伝フ」とありますが、開基・開山、創建年代等は不明です。
・緑濃いよく整備された境内。山門は本瓦葺。本堂は寄棟造銅板葺で、端正な流れ向拝を置いています。
・御朱印は忍観音霊場のもので、当寺第33番と上奈良の第24番妙音寺を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第33番 十一面観世音菩薩


■ 熊谷山 報恩寺
公式Web
熊谷市円光2-8-1
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番
・当地の武将、熊谷直実ゆかりの曹洞宗の名刹で、創建について公式Webはつぎのように記しています。
・熊谷直実は一ノ谷の戦いで平家の御曹司、平敦盛を討ち取たことで自責と無常を覚え、京にのぼって法然上人に入門して僧侶(法力房蓮生)となりました。
熊谷に残された家族はこれを悲しみ、直実の妻は病をえて亡くなってしまいます。
そして残された直実の息女、玉津留姫のもとに直実他界の知らせが入りました。
姫は泣き暮らした果てに、仏さまのお力にすがり両親の冥福を祈るほかないと、建暦二年(1212年)に当寺を創建しました。
その後、関東管領上杉能憲が永和四年(1378年)に再建、管領職を継いだ上杉憲方も報恩寺の復興に力を注ぎました。この両者は「中興開基」という呼び名で、現在まで大切にまつられています。
寛永元年(1624年)、上之の龍淵寺第14世萬矢大拶禅師は、あらたに曹洞宗の寺院として開山しました。
・一方、熊谷市資料には「熊谷直実の子直家が、父の没後菩提の為に浄土宗寺院として創建したものと伝わります。」とあり、「本尊は熊谷直実の娘千代鶴姫玉鶴姫の開基・守佛であり、多くの信仰を集めてきました。」という含みのある表現をしています。
・さらに『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡成田龍淵寺末 当寺ハ昔熊谷直実ノ子直家 父ノ没後菩提ノ為ニ起立セル浄土門ノ草庵ニテ 直実カ木像ヲ置シカ 遥ノ後東照宮此邊御遊●之時 由緒ヲ御尋ノ上新ニ熊谷寺ヲ造立セサセラレテ 当所ハ猶其マゝニテオカレシテヲ 其後又一寺ニ取立テ報恩寺ト号ストイヘリ 此説熊谷寺ノ伝ヘト同シカラス 姑両説を記シオケリ 中興開山ヲ萬室察和尚ト云(略)本尊阿彌陀ヲ安ス 佛師安阿彌カ作ト云 其余直実カ女ナリシ千代鶴玉鶴ノ守佛ナリト云 薬師ヲモ安置セリ」とあります。
・たしかに熊谷寺の由緒とは「同シカラス」内容なので、興味のある方は読み比べてみては・・・。
・いずれにしても、徳川家康公も絡んだ熊谷寺との複雑な経緯が感じられます。
・当山の伽藍神として袖引稲荷が祀られ、こちらの御由緒も玉津留姫にかかわるものです。
・熊谷直実には美貌をうたわれたふたりの息女がおりました。姉が玉津留姫、妹が千代鶴姫と伝わります。
・この袖引稲荷は、玉津留姫が内池町の菩薩院にあったお稲荷さまが荒れ果てていたのに心を痛め当山にお移ししたものとされます。
・玉津留姫が戦乱で離れ離れになっていた妹の千代鶴姫に巡り会いたいとお稲荷さまに願をかけたところ夢の中に白狐に乗られた霊神が現れ「これより京に向いて行けば願いは叶うであろう。」とお告げがあり、京に向け出立すると焼津のあたりで袖を引くように千代鶴姫に出会ったため、お稲荷さまの神通力に感激し「袖引稲荷」と呼ぶようになったと伝わります。
・伽藍神の由緒譚の主役も玉津留姫ですから、やはりこのお寺は玉津留姫との所縁がすこぶる強いものとみられます。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。御朱印は御本尊のもののみで札所御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


■ 赤城久伊豆神社
熊谷市石原1007
御祭神:豊城入彦命、大己貴命、大山祇命
旧社格:旧石原村鎮守
元別当:羽黒山 不動院 真宗寺(熊谷市石原)
授与所:境内授与所
・赤城神社と久伊豆神社の合祀(合社)という、北関東ならではの神社です。
・『埼玉の神社』には、「『風土記稿』には『赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす』と載る。これは戦国末期、古くから当地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。」とあります。
・同書によると、赤城神社は、宮城村鎮座の赤城神社から勧請。久伊豆神社は、成田氏の崇敬する神社であった。両社合祀の経緯は「忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという。」とのことです。
・本殿は寛延三年(1750年)建立とされる二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められているとのこと。
秋山藤八正勝、石原吟八郎、前原藤次郎などの名工の名が棟札に残り、その力量を示す建造物として市指定文化財となっています。
・もともとの本殿・拝殿は赤城山に相対するように創建され、久伊豆神社合祀の際に建て替えられ、現在の本殿・拝殿は忍城に相対する形で建っているとのことです。
・参拝時ご不在でしたが、たしか境内にご神職の電話番号が貼り出されており、こちらに連絡すると、お出でになられて無事拝受できました。熊谷七福神(福禄寿)の御朱印は通常不授与の模様です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:赤城久伊豆神社 直書(筆書)


■ 雪渓山 普門院 松巖寺(松岩寺)
公式Web
熊谷市本石1-102
臨済宗妙心寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第2番
・情報があまりとれませんが、公式Webに「慶長元年(1596年)に喜庵西堂和尚によって開創された」とあり、『新編武蔵風土記稿』の石原村の項には「東漸寺ノ末ナリ 本尊観音ヲ安セリ 開山喜庵明暦二年(1656年)十二月七日寂ス」とあるので、江戸時代前期の開山とみられます。
・山門まわりは思いっきり和風の佇まいですが本堂はかなり個性的な意匠の近代建築で、そのコントラストがなかなか強烈です。
・御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受できました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第2番 聖観世音菩薩


■ (鎌倉町)愛宕神社・八坂神社
熊谷市鎌倉町44
御祭神:軻遇突智命、須佐之男命、大市姫命、菅原道真公、事代主命
旧社格:(熊谷うちわ祭りの祭神社)
元別当:大善院
授与所:古宮神社(池上)授与所
・「熊谷うちわ祭」で有名な市内中心部に御鎮座の神社です。
・『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、熊谷うちわ祭の公式Webなどから御由緒を辿ってみます。
・大永年間(1521-1528年)に本山派修験大善院三世行源法印(大膳院)が、山城国愛宕郡御鎮座の愛宕大神を勧請したのが創祀とされます。
・文禄年間(1592-1596年)に市神・八坂・伊奈利の三神を合祀し、「愛宕牛頭天王稲荷合社」として祀られるようになりました。八坂社は京都八坂神社からの勧請と伝わります。
・明治の神仏分離により別当大善院の管理を離れ、社号を愛宕神社に改号。
・昭和20年8月の空襲により当社の社殿も灰燼に帰しましたが、戦後、八木橋デパート前にあった旧社地から現社地に移転し、社殿が再建。
・もともと現社地には宇佐稲荷神社が御鎮座されていましたが、「愛宕様が移ってくるなら少しでも広い方がよかろう」ということで、同社が境内を譲って向かいの社地に遷られたといいます。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「本山派修験 葛飾郡幸手不動院配下 水原山ト号ス 本尊不動ヲ安置ス 愛宕牛頭天王稲荷合社」とあります。
・社号については「愛宕八坂神社」としている資料もありますが、埼玉県神社庁資料では「愛宕神社」となっています。
〔うちわ祭について〕
・江戸中期の寛延三年(1750年)、各寺社毎に行っていた祭りを町内統一の祭りとし、天保元年(1830年)、町衆により愛宕八坂神社の神輿が製作。全町合同の神輿渡御をともなう夏の祭礼は神輿祭りとして定着し、華やかさを増しました。
・もともと、この祭りは、町内各店が客に赤飯をふるまったことで「熊谷の赤飯ふるまい」として評判となっていたところ、明治24年頃(天保年間とも)から泉屋横町の料亭「泉州楼」の主人がうちわを配りはじめ、これがさらに人気を集めて「熊谷うちわ祭」として定着したといいます。
・平成元年建替落成の本殿は入母屋造銅板葺流れ向拝で、両社併記の扁額を掲げています。鳶職とゆかりのふかい神社で、鳶組合の寄進垣も置かれています。
・御朱印は、愛宕神社、八坂神社ともに古宮神社(池上)授与所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.御朱印揮毫:愛宕神社 直書(筆書)


2.御朱印揮毫:八坂神社 直書(筆書)


■ 星河山 千手院 石上寺
熊谷市鎌倉町36
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第3番、熊谷七福神(毘沙門天)
・「熊谷桜」で知られる寺院ですが、お寺としての公式情報は多くありません。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 開山榮光 寛文十一年(1671年)寂ス 開基ハ当所ノ名主新右衛門カ先祖 竹井新左衛門尉信武ナリ 寛永十五年(1638年)九月卒ス 則開山榮光ノ父ナリトイヘリ 本尊千手観音ヲ安置ス 聖徳太子ノ作ト云伝フ座身長一尺二寸 観音堂 毘沙門堂 地蔵堂 千體佛堂。伊勢両社 鹿島社 星川池」とあります。
・Wikipediaには「度重なる荒川の洪水を治めるため、熊谷を支配していた鉢形城主北条氏邦は、天正二年(1574年)松岩寺あたりから石上寺先あたりまで堤を築いた(北条堤)。現在も高所である。築堤後も堤の決壊に繰り返しみまわれ、その加護を願って堤の傍に建てられたのが石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。」との縁起が記載されています。
・当寺は早咲きの熊谷桜で有名です。桜の咲き駆け(早咲き)と源平合戦における熊谷直実公の先駆け(先陣)との掛詞を由来とするそうです。
・また、近年、約400本の白い曼珠沙華(ヒガンバナ)でも知られる花の寺です。
・参道階段の先に入母屋造本瓦葺の本堂。大棟に金色の鴟尾を置き、向拝の桁行五間の堂々たる伽藍です。
・御朱印は庫裡にて親切なご住職から拝受できました。山門横の掲示板に御朱印2種の見本が貼り出されていたので、御朱印に積極的なお寺様かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第3番 千手観世音菩薩(大悲殿)


2.熊谷七福神(毘沙門天)の御朱印

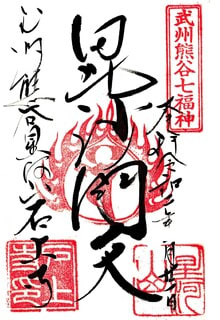
■ 熊野山 千形院 圓照寺
公式Web
熊谷市星川1-1
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:千形神社(熊谷市本町)、熊野神社(高城神社境内社)
・境内掲示および公式Webによると、天禄元年(970年)僧覚榮法師の創立で、熊谷市最古の名刹のようです。
・御本尊は阿弥陀如来。不動明王は「くまがやお不動様」といわれ、全国不動霊場に名をつらねているそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡下中条村常光院末 開山覚榮寂年ヲ伝ヘス 本尊彌陀ヲ安ス 住吉金比羅合社」とあります。
・熊谷の中心部、星川に面して祈願寺らしい華麗な伽藍を構えています。
・境内は広くはないですが、多くの仏像が安置され、それぞれの御前に御真言が掲げられています。
・御朱印は不動明王と聖徳皇太子の2種を授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.不動明王の御朱印


2.聖徳皇太子の御朱印


■ (宮町)高城神社
公式Web
熊谷市宮町2-93
御祭神:高皇産霊神
旧社格:県社、延喜式内社、熊谷総鎮守
元別当:星河山 石上寺(鎌倉町)
授与所:境内授与所
・奈良時代以前の創建と伝わる古社で、『延喜式神名帳』に「大里郡一座髙城神社」と記載されている式内社に比定されています。
・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の忍城攻めの際、当社も戦火にかかり社殿を焼失。寛文十一年(1671年)に忍城主・阿部豊後守忠秋により再建されています。
・熊谷総鎮守として地域の尊崇を集め、「節分祭」「胎内くぐり」「酉の市」などが催されています。
〔拝受御朱印〕
・参拝はしていますが、御朱印は拝受していないかもしれません。


■ 藤井山 源宗寺
熊谷市平戸611
曹洞宗
御本尊:薬師如来 観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第5番
・「平戸の大ぼとけ」として知られる曹洞宗寺院です。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「浄土宗 足立郡鴻巣宿勝願寺末 開山源宗寂年ヲ伝ヘス 開基ヲ藤井雅楽助ト云 寛永七年(1630年)六月卒ス 本尊薬師観音ノ二像ヲ安ス 共ニ開山源宗ノ作ナリト云」とあります。
・開創時は浄土宗、現在は曹洞宗なので、いずれかの時点で曹洞宗に改宗されたとみられますが、詳細は不明です。
・熊谷経済新聞(2021.12.9)の記事によると、当寺所蔵の木彫仏像坐像は高さ3.48メートルの薬師如来と、3.93メートルの観世音菩薩で、その大きさから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と呼ばれています。木造寄せ木造りの仏像としては国内最大級とされ、市有形文化財に指定されています。
・本堂は老朽化したため令和3年に再建されています。
・御朱印は忍秩父三十四観音霊場のものを東竹院にて拝受していますが、下記のとおり現在、東竹院は原則御朱印不授与なので、こちらの御朱印も拝受できるかはわかりません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第5番 南無薬師瑠璃光如来 観世音菩薩

※ 画像探索中です。
■ 佐谷田神社
熊谷市佐谷田310
御祭神:誉田別命
旧社格:旧佐谷田村鎮守
元別当:
旧佐谷田村八幡社:藤林山 地蔵院 永福寺(新義真言宗/佐谷田村)
旧戸出村神明社:薬師山 東福院 金錫寺(新義真言宗/戸出村)
旧平戸村他國明神社:平戸山 多寶院 超願寺(真言宗新義/平戸村)
・『埼玉の神社』によると、明治22年に佐谷田と戸出と平戸が合併して佐谷田村となり、これにともない佐谷田の八幡社に、明治40年に戸出の神明社、大正2年に平戸の他國明神社を合祀して成立した神社です。よって、『新編武蔵風土記稿』に当社の記載はありません。(平戸の他國明神社は、後に旧地に戻っています。「長崎平戸の神を祀り他国という」との口碑があるようです。)
・『新編武蔵風土記稿』の佐谷田村の項には「八幡社 (佐谷田)村ノ鎮守 永福寺持」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の戸出村の項には「神明社 社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 別当金錫寺 新義真言宗」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「他國明神社 村ノ鎮守ナリ 祭神詳ナラス 或云佳吉ヲ祀リシ社ナリト云、超願寺持」とあります。
・佐谷田の八幡社については『大里郡神社誌』に、享保七年(1722年)に宗源宣旨を受け正一位になったことや、寛政五年(1793年)に伯家に願い出て八幡宮の神号を受けた時の添え状の記載があります。
・御朱印は佐谷田神社より拝受しましたが、令和3年12月現在、佐谷田神社の本務神社は上之の上之村神社となっており、御朱印も上之村神社での授与かもしれません。(拝殿前書置きの可能性も。)
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:佐谷田神社 筆書


■ 梅籠山 久松寺 東竹院
熊谷市久下1834
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第4番、熊谷七福神(寿老人)
・源平合戦期の武将、久下次郎重光が開基、月擔承水法師が開山となり創建。深谷城主上杉三郎憲賢が中興開基し寛永十九年(1642年)に寺領三十石の御朱印拝領という名刹です。
・『新編武蔵風土記稿』の久下村の項には「下総國結城孝顕寺末 古は天台宗ナリシト云 本尊釋迦 開基ハ久下次郎重光、建久七年(1196年)七月卒ス 又久下権守直光 元久元年(1204年)四月卒ス コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト 東鑑ニ其コトハ見エス 直光ハ熊谷直実ノ姨母ノ夫ナリト載ス 開祖ハ月擔承水法師 安貞元年(1227年)八月示寂 中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郎憲賢ニテ永禄十一年(1568年)七月卒ス 此時ノ僧ヲ的翁文中ト云」との記載があります。
・久下氏については、熊谷市江南文化財センター資料「報告 梅籠山久松寺「東竹院」に関する歴史概要」に詳しく述べられていますが、この資料によると、「久下氏は武蔵国大里郡久下郷を名字の地とする中世武家」で、治承四年(1180)、源頼朝が挙兵すると、久下直光・重光父子は熊谷次郎直実とともに平家方で参戦した。のちに頼朝方に転じて活躍、一ノ谷の合戦などに戦功をあげ、頼朝より伊豆国玉川荘・美作国印庄・丹波国栗作郷などを与えられた。」とのことです。
・御朱印は現在、庫裡前に「御朱印不授与」の旨の掲示があり原則授与されていないそうですが、「忍秩父観音霊場」巡拝中の旨告げると、ご好意で授与いただけました。ただし、これも特例的なご対応で、霊場御朱印も原則不授与かもしれません。
・団体で御朱印の授与を求められることがあり、対応できないのでこのようなかたちにしている、とのことでした。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛


2.忍秩父三十四観音霊場第4番 南無釋迦牟尼佛


----------------------------
以降は、荒川を渡った旧・大里郡江南町、大里町の寺社です。
■ 龍谷山 静簡院
熊谷市成沢125(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番
・関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番の札所を務められる曹洞宗の寺院です。
・霊場ガイドおよび山内由緒書を参考に由緒をまとめてみます。
・古くは天台宗寺院の浄閑寺の名刹でしたが一時期衰退。
・大永五年(1525年)に成澤越前守隼人正義佑が当地に武蔵成澤城を築城しました。関東管領上杉憲政の麾下であった成澤氏が、甲斐の武田信玄の侵攻に対処するため活用したとみられています。
・義佑の戦死後、上杉一門武将が守備した関係から深谷城主上杉三郎憲盛によって静簡院が創建されたと伝わります。開基憲盛の墓が寺の裏に奥津城としてあり、浄閑寺跡の石垣も現存しているそうです。
・御本尊は釈迦如来で両脇仏に文殊菩薩・普賢菩薩を安置。内陣には四天王、大間には十六羅漢の額の彫刻があります。
・関東三十三観音霊場の札所本尊の観音様は、山内に露仏として安置されています。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釋迦如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番 徳王観音


■ 高根山 満讃寺
武州路十二支霊場Web
熊谷市小江川827(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州路十二支霊場 辰(普賢菩薩)
・武州路十二支霊場の公式Webによると、開山は江南町野原の文殊寺第五世霊因祖源大和尚。天正四年(1576年)稲垣若狭守重大の臣田村茂平重次を開基とし、弘化二年(1845年)当寺第十九世当付大和尚による中興と伝わります。
・御朱印は庫裡にて武州路十二支霊場拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.武州路十二支霊場 普賢菩薩


■ 東方山 保泉寺
熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。
・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。
・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。
・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内。
・こちらはご縁をいただいて御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 五台山 文殊寺
公式Web
熊谷市江南町野原623(旧・大里郡江南町)
曹洞宗
御本尊:文殊師利大菩薩
・「野原の文殊さま」と称され、「京都の切戸(天橋立)文殊」「山形の亀岡文殊」と並んで「日本三体文殊菩薩」のひとつとされる曹洞宗の名刹です。
・公式Webを参考に由緒などをまとめてみます。
・「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵を司る仏様で、古より学業成就の願掛けに多くの人々が訪れます。
・開山は崇芝性岱(そうししょうたい)大和尚(名応五年(1497年)寂)。
・古くは五台山 能満寺という天台宗の古刹でしたが、室町期の文明十三年(1481年)に焼失。二年後に比企郡高見の四ツ山城主、増田四郎重富が再建し、曹洞宗に改めて五台山 文殊寺を号したとされています。
・名刹らしく見どころの多い山内。山門(仁王門)は江戸中期の建築と推定され熊谷市の指定文化財に指定されています。
・御朱印は本堂横の授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 文殊師利大菩薩(文殊尊)


■ (高本)高城神社
熊谷市高本562(旧・大里郡大里町)
御祭神:高皇産霊命
旧社格:村社、延喜式内社(小)論社
元別当:地蔵院(元和四年(1618年)~)
授与所:神社そばのご神職宅
『埼玉の神社』を参考に、御由緒などをまとめてみます。
・創建年代等は不詳ながら、文久三年(1863年)、相上村吉見神社の社家徳永豊洲氏が当社旧社地の地中から「无邪志国・高城神社」とある古代の銅製の鈴を発見したとされ、延喜式神名帳の式内社に比定されています。
・当社の旧社地は村の北方(和田吉野川の流れに近い中街)でしたが川の氾濫で流れが変わって下流の中ノ森(高城街)に流され、これを神慮であるとしてこの地に御遷座となり、昭和45年、中ノ森が河川改修地域となった際に旧社地である中街の現社地へ再び御遷座されています。
・田畑のなかにお社が御鎮座。御遷座を示す説明板も設置されています。
・御朱印はすこし離れたご神職のご自宅そばにて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:高城神社 書置(筆書)


■ 吉見神社
熊谷市相上1(旧・大里郡大里町)
御祭神:天照大神
旧社格:郷社、旧上吉見領総鎮守、旧相上村鎮守
授与所:神社そばのご神職宅
・旧上吉見領二三か村のうちの上・中・下の恩田は「武州恩田御厨」といわれ、伊勢神宮の神領であったことが知られています。『埼玉の神社』では御厨で伊勢神宮を分祀する例は多く知られていることから、当社もこの例の一つとして天照大神を祀ったと考えられるとしています。
・いくつかの創祀伝承が伝わります。和銅六年(713年)御諸別王が当地を巡視した折、不毛の地であることを嘆かれ、各地から里人を移して多里郡(大里郡)を置き、豊かな地となった奉賽として、天照大神ゆかりの筬を御神体として天照大神を祀ったといいます。
・古社らしい厳かな境内。御朱印は、境内向かって右手のご神職宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:吉見神社 書置(筆書)


-----------------------
ここまでくれば東京方面への帰路、関越道・東松山ICも近いです。
結局4編構成となってしまったこの記事、やはり深谷・熊谷は御朱印王国であることを実感しました。
「青天を衝け」ですが、近代ものにしては視聴率健闘したようです。
個人的にはかなり面白く、最後まで視つづけた数少ない大河ドラマとなりました。
最後に、渋沢栄一翁ゆかりの御朱印をご紹介して、この記事を〆たいと思います。
■ 寶登山神社・寶登山神社奥宮
長瀞町長瀞1827
御祭神:神日本磐余彦尊、大山祇神、火産霊神
旧社格:県社、別表神社
元別当:會慶山 地蔵院 玉泉寺(長瀞町長瀞/真言宗智山派)
授与所:境内授与所
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:寶登山神社 直書(筆書)


「青淵ゆかりの地」の印判が捺されています。「青淵」とは渋沢栄一翁の号です。
御朱印揮毫:寶登山奥宮 書置(筆書)


「寶登山は千古の霊場」の印判が捺されています。
これは栄一翁が八十八歳のときに揮毫した軸にちなむもので、参道には栄一翁揮毫の石碑が建立されています。


【写真 上(左)】 栄一翁揮毫の石碑
【写真 下(右)】 宝登山山頂
栄一翁は熊谷と秩父を結ぶ秩父鉄道の延伸を援助し、秩父セメントの設立にも力を貸しました。
秩父や長瀞の発展に、栄一翁の貢献は多大なものがあったとされています。
【予告】
2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は鎌倉がメインの舞台となります。
年明けからは、かなり無謀な企てですが「鎌倉市の御朱印」にトライしてみたいと思います。
【 BGM 】
■ 潮見表 - 遊佐未森
■ 夢の途中 - KOKIA
■ far on the water - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
【旧記事】■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPしています。
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔村の鎮守十社めぐり〕
当初は「以下10社について御朱印を拝受していますが、長井神社と大杉神社以外は常時授与かどうか不明なのでとりあえずリストのみです。」としましたが、令和2年秋に案内パンフが作成され、実際に御朱印も拝受していますので、ご参考までにUPします。
なお、現時点では御朱印は原則不授与かもしれません。詳細は長井神社宮司様にご確認ください。


情報が少ないですが、現地掲示のほか、案内パンフ、『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、『新編武蔵風土記稿』などを参考にまとめてみます。
1.(日向)長井神社 熊谷市日向
2.(俵瀬)伊奈利神社 熊谷市俵瀬
3.神明社・大杉神社 熊谷市葛和田
4.(大野)伊奈利神社 熊谷市大野
5.(弁財)嚴島神社 熊谷市弁財
6.善ヶ島神社 熊谷市善ヶ島
7.(八ツ口)日枝神社 熊谷市八ツ口
8.江波神社 熊谷市江波
9.西城神社 熊谷市西城
10.八幡大神社 熊谷市上須戸
■ (日向)長井神社
熊谷市日向1090
御祭神:品陀別命、息長帯姫命
旧社格:村社、旧日向村鎮守
元別当:三学院(日向村、当山修験)
授与所:境内脇社務所
・江戸時代には八幡社と称された旧日向村の鎮守社。(明治9年現社号に改号)
・天喜五年(1057年)、源頼義公が安陪貞任討伐の折にこの地に滞留されたとき、竜海という池に棲み村人を悩ましていた大蛇の退治を島田大五郎道竿に命じた。頼義公より弓矢と太刀を下賜された道竿は、竜海から利根川まで堀(道竿堀/どうかんぼり)を掘り、池の水を利根川に落としてこの四丈もの大蛇を退治した。頼義公は東北地方平定の吉事として、大蛇を倒したところに当社を、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったといいます。
・暦応元年(1338年)、足利尊氏が再興、戦国時代には忍城主成田長泰が信仰した記録が残ります。
・『新編武蔵風土記稿』の日向村の項に八幡社があり、上記の「竜海伝説」が詳細に記載されています。
・本地堂の御本尊は阿弥陀如来で、これは八幡神の本地が阿弥陀如来とされたことと符合します。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:長井神社 筆書


■ (俵瀬)伊奈利神社
熊谷市俵瀬489
御祭神:
旧社格:旧俵瀬村鎮守
元別当:寶林山 妙音寺 成就院(俵瀬村、新義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・俵瀬は利根川と福川に挟まれた島状のエリアで、『新編武蔵風土記稿』には俵瀬村の項に稲荷社が記載されているものの「成就院持」としかありません。
・これにはさすがの『埼玉の神社』も困り果てたらしく、成就院の記載を引き「成就院は慶安四年(1651年)の草創と伝えている。当地が一村としての体裁を整え始めるのが寛永(1624-1645年)の末ごろと思われ、当社の創建も、別当成就院と前後して行われたものであろう。」と記されています。
・江戸時代には「稲荷社」と称し、明治初期に「伊奈利社」と改め、明治41年合祀政策により同大字の神明社、厳島神社を合祀し、大正2年には堤防工事に伴い利根川縁にあった当社を厳島神社の旧社地に御遷座と伝わります。
・厳つい石垣の上に入母屋造桟瓦葺でどっしりと鎮座するお社は、ながらく水害と闘ってきた俵瀬の地の鎮守社ならではのお姿に思えます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市俵瀬 伊奈利神社 筆書


■ (葛和田)神明社・大杉神社
熊谷市葛和田591 大杉神社は(葛和田)神明社の境内社
御祭神:天照皇大神、大杉大神
旧社格:旧葛和田村鎮守
元別当:瑠璃光山 東光院 醫王寺(葛和田村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・伊勢の御師が当地に逗留した折に奉齋した社であると伝わります。
・旧社地は現在利根川の川中にあり、数回の移転を経て高台の現社地(氷川神社の社地)に御遷座とのこと。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に神明社があり「氷川ヲ合殿トス 村ノ鎮守ナリ 別当醫王寺」とあります。
・境内社の大杉神社(あんば様)の祭礼は利根川の流れに大御輿・大杉御輿を乗り入れるもので、「葛和田の勇み御輿」「関東一のあばれ御輿」として広く知られています。
・江戸時代の葛和田の地は利根川の河岸場として賑わいました。あるとき、与助という腕のいい船頭が霞ヶ浦の西浦で暴風雨に襲われ窮まったとき、日頃から信仰している大杉明神に祈りをささげると神佑を得て難を逃れました。このご神徳への御礼と今後の船路安全祈念のため、茨城県稲敷の大杉神社から勧請し、御輿を造営したと伝わります。
・当初は利根川に注ぐ道竿堀の南に御鎮座でしたが、大正3年堤防工事に伴い現社地に御遷座・合祀されました。
・御朱印は(日向)長井神社社務所にて拝受しました。
・Web上では神明社の御朱印がみつかりますが、現在は大杉神社の御朱印のみ授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大杉大神 筆書




■ (大野)伊奈利神社
熊谷市大野751
御祭神:豊宇気比咩命
旧社格:旧村社、旧大野村鎮守
元別当:大野山 利劔寺 文殊院(葛和田(大野)村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・〔村の鎮守十社めぐり〕のなかではもっとも利根川に近く、利根川の堤防下に鎮座します。
・江戸期には大野村は葛和田村の一部とされ、『新編武蔵風土記稿』には葛和田村の項に「稲荷社二宇 一ハ文殊院 一ハ正泉寺持」とあり、『埼玉の神社』には文殊院が別当とあるので、こちらが該当とみられます。
・ただし、『埼玉の神社』には「宝暦六年(1756年)の伏見稲荷からの分霊証書に『武州 大野村鎮守』とあることから、当時既に『大野村』という名称が使われており、葛和田村から実質は独立していたことがわかる」とあります。
・上記のとおり、宝暦六年(1756年)には伏見稲荷からの分霊証書を受けて創祀しています。
・地形からしても、なにより水害防除が求められる地とみられ、『埼玉の神社』には「伊奈利社を(利根)川の側に勧請することによって水害から村を守ろうとした開発者の心情が推察される。」とあります。
・小山状の高台に鎮座し、参道右手が旧文殊院跡。その手前に大国主尊、参道階段右手に三峰社、拝殿左手には馬頭観世音菩薩、庚申様、青面金剛が祀られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市大野 伊奈利神社 筆書


■ (弁財)嚴島神社
熊谷市弁財174
御祭神:
旧社格:弁財地区鎮守
元別当:辨財山 醫王院 薬王寺(辨財村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「当地(弁財)は大昔利根川の流れの中にあったが、やがて流路が変わり、自然堤防を形作った所である。」とあり、河川とのかかわりから弁財天が祀られたとする一方、口碑に「当地の草分けであり、屋号を庄屋と呼ぶ大島清和家の先祖が祀った。」とあり、「同家は平家の落人であり、そのゆかりから嚴島神社を祀った。」という説にも触れています。
・『新編武蔵風土記稿』の辨財村の項に辨財天社があり「村名ナリシテ見レハ古社ナルヘケレト傳ヘテ失フ」とあります。
・(日向)長井神社縁起の竜海伝説では、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったとされ、この弁財天を当社とする説と(日向)長井神社境内の宇賀神(弁天様)とする説があるようです。
・『埼玉の神社』では、享保十六年(1731年)の利根川大洪水の折、当地に沼ができて、その後沼の主と呼ばれる大蛇が棲み、それが竜海伝説に重なったと指摘しています。
・こちらも社叢のなかに御鎮座。拝殿は石垣のうえに入母屋造桟瓦葺で、主屋根の軒に瓦屋根の向拝を重ねるようにせり出し変化のある意匠。
・弁財天や厳島社はもともと蛇とのゆかりがありますが、向拝の屋根飾りにも蛇の姿がみられます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:嚴島比賣 筆書


■ 善ヶ島神社
熊谷市善ヶ島197
御祭神:
旧社格:旧善ヶ島村鎮守
元別当:光明山 福壽院 龍泉寺(善ヶ島村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』『パンフ』には、当地は当初葦が生えた島で葦ヶ島と呼ばれたが、後に利根川の流れが変わり、近村と地続きになり善ヶ島と改めた。また、1500年頃の蔵王権現社の勧請が当社の起源とされ、当初は蔵王権現社、明治初期に御嶽神社と称し、明治42年に善ヶ島神社に改称といいます。
・明治41年には大字裏久保の愛宕神社と、上元割の阿夫利神社を合祀。地元では合祀社の阿夫利神社に因み「阿夫利様」と呼ばれることが多いそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の善ヶ島村の項に蔵王権現社があり「永正(1504-1521年)年中の勧請ト云 龍泉寺持 末社 天神 疱瘡神 摩陀羅神」とあります。
・金剛蔵王権現は修験系の尊格で、ことにの吉野の金峯山寺本堂(蔵王堂)の御本尊として知られています。
・当社の現在の主祭神は不明ですが、金剛蔵王権現は大己貴命、少彦名命、国常立尊、日本武尊、金山毘古命との習合例が多く、明治の神仏分離時、金剛蔵王権現を祀る堂祠は上記の神々を祭神とする神社となった例がみられます。
・末社に摩陀羅神の名がみられます。すこぶる複雑な性格をもたれる尊格として知られ、東日本で祀られる例は多くありません。
・別当龍泉寺は古義真言宗で赤岩光恩寺の末。赤岩光恩寺の寺伝には「推古天皇11年(603年)には秦河勝を勅使として仏舎利三粒が納められた」とあります。(秦河勝と摩陀羅神は強い関係があるとされる。)
・当社に摩陀羅神が祀られていた背景には、このような所縁が関連しているのかもしれません。
・現在も、複雑な由緒を想起させる境内社が複数ご鎮座されます。
・社叢のなか、入母屋造桟瓦葺向拝付設の社殿と境内社が御鎮座。
・鳥居、灯籠ともに大きく嵩が上げられ、拝殿も数段高く、水害防除が大切な地であることを物語っています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:善島神社 筆書


■ (八ツ口)日枝神社
熊谷市八ツ口922
御祭神:
旧社格:旧村社、旧八ツ口村鎮守
元別当:●源山 長昌寺(八ツ口村、禅宗臨済派)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「(別当の)長昌寺は、天文元年(1532年)に成田氏に従い武川の合戦で討死した山田弥次郎の菩提追福のために、その父山田伊平が、弥次郎の領地であったこの地に草創した寺院である。当社の成立背景には、長昌寺の僧とのかかわりが考えられるが、明らかにできない。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の八ツ口村の項に山王社があり「村ノ鎮守ニテ稲荷ヲ合殿トス 長昌寺持」とあります。
・元別当の長昌寺は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第88番の結願寺で、相応の寺格をお持ちかと思いますが、現在のところ御朱印は拝受しておりません。
・社頭に朱塗りの2つの鳥居。向かって左手が日枝神社、右手が八坂神社と伊奈利社です。
八坂神社の夏祭りの御輿渡御は、以前は「暴れ御輿」として広く知られていたようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市八ツ口 日枝神社 筆書

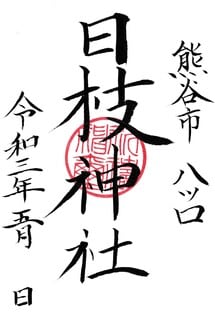
■ 江波神社
熊谷市江波315
御祭神:菅原道真公
旧社格:旧村社、旧江波村鎮守
元別当:福原山 寶蔵院(江波村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「明治四十一年の改正まで天神社であったことから、氏子にはいまだに天神様と呼ばれている。(中略)明治四十一年、字西嬉愛の宇知多神社(妙見社)と字道上の稲荷神社の無格社二社を合祀した。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の江波村の項に天神社があり「村ノ鎮守トス 寶蔵院持」とあります。
・一面の麦畑のなかに浮かぶように、切妻造瓦葺妻入りの社殿が御鎮座。向拝も切妻の屋根がかかり、めずらしい様式の社殿です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:江波神社 筆書


■ 西城神社
熊谷市西城2
御祭神:
旧社格:旧村社、旧西城村(本郷)鎮守
元別当:浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺(西城村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「西城の地名は、かつてこの地に左近衛少将藤原義孝の居舘があったことにちなむものといわれ、古来、西城の村は郭(くるわ)と呼ばれる幾つかの小さい集落に分かれ、神社の祭祀もまた郭ごとに鎮守として各々神社を祀っていた。明治維新の際、社格を定めるに当たり、(大天貘社は)村内の諸社の中で最も規模が大きく、村の中で最も早く開かれた本郷の鎮守であったことから、当社が西城村の村社になった。恐らく、明治9年に村社となった時に村名を採って西城神社と社名を改めたものであろう。明治42年には、字東田鎮座の稲荷神社と字鴉森鎮座の厳島神社を合祀し現在に至っている。」とあります。
・また同書には「境内にある勝根神社は、古くから当社の末社として祀られており、その祭神は大物主命である。当社(大天貘社)が元は本郷だけで祀る神社であったのに対し、勝根神社は初めから(西城)村全体で祀る神社」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の西城村の項に大天貘社があり「村ノ鎮守トス 長慶寺持」とあります。
・西城神社は入母屋造桟瓦葺、「西城神社」と彫り込まれた棟飾りは精緻で一見の価値があります。
・向かって左手に御鎮座の勝根神社は、切妻造桟瓦葺の整った社殿で「村全体で祀ってきた神社」としての重みを放たれています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:西城神社 筆書

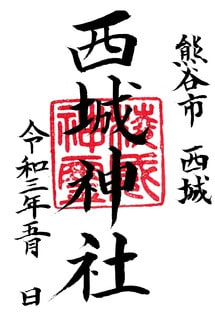
■ 八幡大神社
熊谷市上須戸838
御祭神:
旧社格:大字上須戸鎮守、(旧長井村総鎮守)
元別当:福原山 開城院 正法寺(上須戸村、天台宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「伝説によると、天喜五年(1057年)、源頼義が安倍貞任を討つために奥州へ下る途中、当地に逗留した。この折竜海という沼に棲む大蛇が村人を悩ますことを聞いたため、土地の島田大五郎道竿に命じて退治させた。頼義はこの大蛇退治を安倍氏征討の門出に吉事であると喜び、大蛇の棲んでいたところから、東・西・北に三本の矢を放ち、その落ちた所にそれぞれ八幡社を、沼の中央に大蛇慰霊のための弁天社を祀った。当社は、西に放たれた矢が落ちた所に祀られたという。」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の上須戸村の項に八幡社があり「八幡社 辨天社 何レモ社領ヲ附ラル年代下●出セリ 別当正法寺」とあります。
・『埼玉の神社』の内容は、(日向)長井神社の「竜海伝説」とほぼ同様で、このエリアに広く伝わっていたことが伺われます。
・うっそうと茂る社叢。木造朱塗りの両部鳥居、石造の明神鳥居の正面おくに入母屋造桟瓦葺平入り流れ向拝の八幡神社、向かって右手には切妻造桟瓦葺妻入りの八坂大神が御鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市上須戸 八幡大神社 筆書


■ 寶積山 白道院 大龍寺
公式Web
熊谷市葛和田898
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第15番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第21番
・名刹のようですが、現地、Webともに詳しい情報がとれませんでした。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に記載がありますので抜粋引用します。「館林町善導寺末 開山ハ幡随意上人元和元年正月示寂 開基ハ成田氏ノ臣嶋田采女正ナリ コノ子孫今村民六兵衛ナリト云 本尊阿弥陀ヲ安セリ 荒神社 愛宕社 不動堂 観音堂」。
・幡随意(ばんずいい)上人は、 慶長二十年(1615年)寂と伝わる浄土宗の名僧で、鎌倉光明寺で教学を修められ、後に京都百万遍知恩寺の三十三世住持。徳川家康公の信任厚く、駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創、熊谷の名刹、熊谷寺(ゆうこくじ)の中興など全国で寺院を創立・再興されました。
・当寺所蔵の「幡随意上人の書」、本堂に御座す「三十三体観音像」(元禄期、寄木造金泥)は市の文化財に指定されています。
・名刹らしい風趣のある山内。御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。御本尊および幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第15番 三十三体観世音菩薩


■ 瑠璃光山 浄光院 福生寺
熊谷市日向1154
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第34番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番
・こちらも御由緒詳細がとれませんが、山内石碑には「四九四年前に開創せられし名刹」とあり、『新編武蔵風土記稿』の日向村の項には「邑楽郡赤岩村光恩寺末 開山専祐寛永十八年(1641年)寂 本尊大日ヲ安セリ 薬師堂」とあります。
・重厚な山門、本堂、観音堂を擁して山内はよく整っています。
・こちらは忍秩父三十四観音霊場第34番の結願所で、札所本尊は馬頭観世音菩薩。御本尊の大日如来は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所本尊でもあり、こちらの御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第34番 馬頭観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番 大日如来

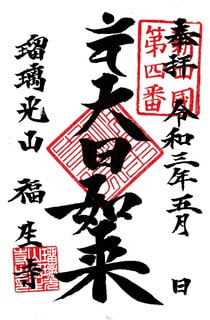
■ 浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺
公式Web
熊谷市西城93-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来・薬師如来?
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番
司元別当:西城神社(西城村、旧西城村(本郷)鎮守)
・こちらは詳細な公式Webをお持ちなので、そちらから引用させていただきます。
・南北朝の永和二年(1376年)、慶弘という僧が伝・行基作の薬師如来像を祀り開創。赤岩光恩寺の末寺で、歴代の住職が隠居されていました。
・薬師如来像は12年に一度、寅年の御開帳で信仰を集めているようです。
・本堂と薬師堂、薬師堂厨子は、2020年9月に市の有形文化財に指定されています。
・ともに、上州花輪村の名工・石原吟八郎のグループと、「歓喜天聖天堂」の棟梁の林兵庫正清を中心に建立。江戸期のこの地の彫物師集団の技巧を示す作品として評価されています。
・本堂には阿弥陀如来、薬師堂には薬師如来が御座します。
公式Webに「本堂の阿弥陀如像は、宝永年間(1704-1711年)に祀られた。平成26年遷座300年目に修復。本尊とご縁を結び、人生を輝いて全うできるように御手綱を握ってお参りができる」とあるので、当寺のいまの御本尊は阿弥陀如来とみられますが、宝永年間までの御本尊は薬師如来とみられ、現在でも御本尊のポジションなのかもしれません。
・仏教寺院、とくに密寺の御本尊のポジションは複雑で、観音堂、薬師堂、不動堂などで草創し、のちに本堂が建てられた場合などは、複数の御本尊がおられる場合もあるようです。(例えば、本堂御本尊は大日如来、薬師堂御本尊は薬師如来で、寺院としての御本尊は両尊併記となる。)
・弘法大師霊場の札所本尊は草創時の御本尊が札所本尊になられる場合も多く、こちらもその例ではないでしょうか。
・御朱印はご住職がご不在で書置もなかったので、ご親切な寺庭様にお願いして郵送をいただきました。なお、こちらは忍秩父三十四観音霊場第10番光明山 観音寺(上中条)の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番 薬師如来




■ 大慈山 薬師院 観音寺
熊谷市下奈良913
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第11番
・この寺社巡りも、下奈良エリアに至ってますますディープな世界に入っていきます(笑)
・忍秩父三十四観音霊場第11番のこの札所寺院は、現在無住のお堂で、境内掲示はなくWebでも情報がとれないので、『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項の記載を引用します。
「埼玉郡羽生村正覺院ノ末ナリ 本尊十一面観音安セリ 薬師堂」。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番の札所は福聚山 利永寺とされていますが、別の資料によると、もともとはこちらが第43番の札所であった可能性もあります。
・まわりにランドマークがないので説明しにくいですが、Googleマップの住所検索でヒットします。
・竹林を背にした奥まったところにあり、向拝柱はあるものの、切妻造妻入で一見お堂らしくないので、参道入口の如意輪観世音菩薩と地蔵菩薩の石仏がなければそれとわからないかもしれません。
・御朱印は、真言宗智山派関東十一談林の名刹、光明山 一乗院(熊谷市上之2891-1)で規定用紙のものを拝受できます。(一乗院の御朱印は授与されておりません。)
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第11番 十一面観世音菩薩(大悲閣)


■ 福聚山 阿弥陀院 利永寺
熊谷市下奈良796
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第12番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番
・こちらは、今回の記事のなかでもっともマニアックな札所かと思われます。記事UPは迷いましたが、確かに忍観音霊場の札所なのでご紹介します。
・参拝情報がほとんどなく、Googleマップで位置検索するととある企業の敷地を示すので、意を決してこちらの事務所にお伺いすると、こちらの敷地内に御座とのこと。
・ご丁寧にもご案内いただき、ようやく参拝が叶いました。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 本尊前(十一面観音)ニ同シ 観音堂 利永寺持」とあり、本堂(御本尊:十一面観世音菩薩)のほか、観音堂を擁していたかもしれません。
・整った宝形造で向拝を付設し、向拝見上げにはしっかり御詠歌の木板が掛かっていました。ただし、この木板の札番は「第七番」。こちらは忍観音霊場で第11番、幡羅郡新四国霊場で第43番のはずなので、この「第七番」というのはナゾです。
・こちらの御朱印はなかばあきらめていたのですが、一乗院様にお伺いすると、第11番観音寺のほか、こちらの御朱印(規定用紙)も授与されているとのことで、ありがたく拝受しました。
・ご紹介はしましたが、参拝時に一般企業さんのお手間をいただくこともあり、忍観音霊場巡拝者に限ってお伺いした方がよろしいかと思います。また、休業日や営業時間外の参拝も不可だと思います。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第12番 十一面観世音菩薩(大悲殿)

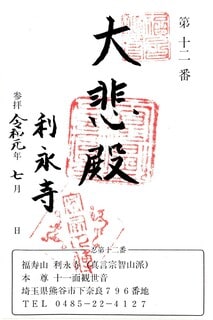
■ 萬頂山 集福寺
熊谷市下奈良551
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第13番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番
・山内掲示によると、永仁年間(1293-1299年)、由良法燈圓明國師によって臨済宗法燈派の本山として開かれ、天文年間(1532-1555年)、永平道元孫桂室秀芳大和尚によって曹洞宗に改められたという名刹です。
・同掲示には、(当寺)五世扶嶽太助大和尚は、後に「とげぬき地蔵」(江戸・巣鴨(当時は神田明神下)の萬頂山 高岩寺を開いたことで知られています、との記載があります。
・境内の諸堂は江戸時代後期の建立で、法堂、庫裡、仏殿、開山堂を回廊で結び、内部に鐘楼を設けた七堂伽藍の配置をとっているようです。
・幡羅郡新四国霊場の初番発願所を務められ、このことからも当地屈指の名刹であることがわかります。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項にも大きく記載され「相傳フ往昔ハ臨済派ニテ開山圓明國師(略)其後永正年中桂室秀芳ト云僧、曹洞派ニ改メシヨリ今開山トス(略)開基ハ式部大輔助高十代成田下総守親泰法名貞岡宗蓮菴主ト号ス 入道シテ当村ニ隠棲ヲ営ミ 即当寺ヲ造建シ大永四年六月八日卒ス 御打入ノ後 東照宮忍城ヨリ此辺御放鷹ノ時、当寺ヘ成ラセラレ住僧桂岩ヘ御目見仰付ラレ 其後慶長年中江戸ヘ召セレシ時 元神田蔵王権現ノ舊(旧)蹟ニ於テ寺地ヲ賜ハリ一寺ヲ草創シテ金峯山高林寺ト号シ蔵王権現ヲ鎮守トセリ 後替地ヲ給ヒ本郷ヘ遷リ 又駒込ヘ遷リテ 今ハ当寺ノ末トナレリ 本尊三尊ノ釋迦ヲ安セリ(以下略)」とあります。
・「金峯山 高林寺」とは、文京区向丘の金峰山 高林寺をさすとみられ、本郷区史のP.1247には、たしかに「高林寺 武州幡羅郡下奈良村集福寺末、金峰山と号ス」との記載があります。
・「七堂伽藍の名刹」だけあって、さすがに伽藍は整っています。
・庫裡にて拝受した御朱印は。忍観音霊場と幡羅郡新四国霊場のふたつの札所印が捺されていました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第13番 札所本尊不明 御朱印尊格は釋迦牟尼佛
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番 釋迦牟尼佛
1通で兼用。




■ 永昌山 常楽寺
熊谷市中奈良1956
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項には「奈良村集福寺末 開山ハ本尊(ママ)七世ノ僧宗察慶長年中(1596-1615年)創建ト云 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・おそらく本寺であった集福寺第七世の僧宗察が慶長年中(1596-1615年)に創建とみられます。
・また、山内の石碑には「当常楽寺ノ境内地ハ創立当時南ハ新井北ハ堀内東ハ後原ヲ境ニ凡ソ五千三百余坪アッタ」とあり、相当の大寺であったことが伺われます。
・参拝時ご不在でしたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番で、曹洞禅ナビで「御朱印対応あり」となっているので、郵送をお願いするとお送りいただけました。
・こちらの御朱印にも幡羅郡新四国霊場の札所印が捺されていました。「幻の霊場」ともいわれる幡羅郡新四国霊場ですが、意外に札所印が残っているようです。
・御本尊は釈迦如来のようですが、御朱印尊格は観世音菩薩となっています。禅宗寺院の観音様は聖観世音菩薩が多いですが、御朱印の主印に種子は確認できず聖観世音菩薩かどうかはわかりません。(観世音菩薩、大悲殿などの揮毫でも、朱印に種子があれば(=御寶印)、こちらで観音様の個別の尊格はわかります。)
・新四国霊場の札所本尊は御本尊の例が多いのですが、こちらはなんらかの由縁で観音様が札所本尊となられているのかもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番 釈迦如来


■ 奈良神社
熊谷市中奈良1969
御祭神:奈良別命
旧社格:延喜式内社(論社)、奈良四村の総鎮守
元別当:摩尼山 熊山院 長慶寺(中奈良、高野山真言宗)
授与所:境内拝殿前
・中奈良に御鎮座の古社で、『延喜式神名帳』の幡羅郡小社四座の一社(論社)とされます。
・『埼玉の神社』には、仁徳天皇の御世、下毛野君の祖で豊城入彦命の子孫とされる奈良別命が、下野国国造の任を終えたのち当地を開拓したことから、郷民がその徳を偲んで創祀とあります。
・また、当地に拠った奈良氏は、成田・別府・玉井氏などとならぶ名族で、当社を奉斎していたとみられています。
・中世、当社は熊野信仰の影響を受けて奈良神社から熊野神社に号を改めました。
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項の熊野社には「奈良四村ノ惣鎮守ナリ 本地彌陀・薬師・観音を安ス 古は修験圓蔵坊カ持ナリシガ 成田氏下野國烏山ニ移ル時圓蔵坊モ随テ移リ(略)今ハ長慶寺ノ持トナル 社内ニ奈良神社ヲ合セ祀ル 奈良神社ハ神名帳当郡四座ノ一ナリ想ニ舊章衰廃ノ後、熊野三社ヲ合祀シ」とあります。
・『埼玉の神社』では、「恐らく、古代に創建された奈良神社は廃絶したのではなく、中世、その時流に合った熊野信仰を収容することにより社名を変えて存続したのであろう。」とみなしています。
・また、「江戸後期になると、中世以来永く熊野神社としてきた当社は、復古の思想興隆により、社名を古代の奈良神社に復した。」とも記されています。
・古社の落ち着きを感じる境内。本殿の意匠も見事なものです。
・拝殿前に御朱印が置かれていたので、お代を賽銭箱に納めて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:奈良神社 書置(筆書)


■ 摩尼山 熊山院 長慶寺
熊谷市中奈良1995
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第25番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項に「紀伊國高野山清浄心院末(略)相傳フ当寺は古修験地ナリシガ 天正十八年(1590年)圓蔵坊ト云僧、成田氏ニ従ヒ下野國ニ移リシ後 長慶ト云僧今ノ宗ニ改メ造立セリト云(略)元空坊号ヲ継テ其頃当村ニ住シ後黒田村ヘ移シニヨリ 坊宇以下其ママ長慶(延寶四年(1676年)寂)譲受テ今ノ宗ノ一寺トセシニヤ 本尊地蔵ヲ安セリ」とあります。
・当初は(天台系)修験の圓蔵坊・元空坊が護持し、後に長慶が跡を継いで紀伊国の真言宗高野山浄心院の末寺となり、江戸期には奈良神社(熊野社)の別当を司りました
・『埼玉の神社』には「明治期に入ると、当社(奈良神社/熊野社)本殿の熊野神の本地である弥陀・薬師・観音の三尊は、長慶寺に移され、代わって神鏡が奉安された。」とあるので、熊野神は本地(弥陀・薬師・観音の三尊)として長慶寺に遷られたことになります。
・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂。忍観音霊場の札所本尊、如意輪観世音菩薩も本堂に御座とのことです。
・御朱印はご住職がいらっしゃれば庫裡にて拝受できるかと思いますが、ご不在がちのようで、書置もないので拝受はなかなかむずかしい札所です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第25番 如意輪観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番 地蔵菩薩


■ 福聚山 慈眼寺
熊谷市田島238
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第14番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番
司元別当:(田島村)稲荷社(旧田島村鎮守)
・こちらも無住の寺院で情報が少ないです。
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
・『新編武蔵風土記稿』の田島村の項に「弥藤五村観清寺末(略)古ハ観音ノ堂ナリシガ寛永年中(1624--1645年)●月堂開山シテ一寺トナセリ コノ人ハ慶安四年(1651年)寂セリト云 本尊十一面観音ヲ安ス」とあり、もとは観音堂として草創、寛永年中(1624--1645年)に寺院になったようです。
・入り組んだ路地のなか、集落に囲まれるようにあります。寄棟造桟瓦葺で右手に庫裡らしき建物を連接しています。
・向拝柱はなく中央サッシュ扉、上部に「慈眼寺」の寺号扁額を掲げています。
・参拝時ご不在でしたので郵送をお願いしお送りいただきました。郵送なので欲張らず忍観音霊場の御朱印のみお願いしましたが、御朱印には幡羅郡新四国霊場の札番揮毫もいただいておりました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第14番 十一面観世音菩薩
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番 十一面観世音菩薩
※1通に2札所併記。


■ 光明山 地蔵院 観音寺
熊谷市上中条2018
高野山真言宗
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第10番
・こちらも無住で情報が少ないです。
『新編武蔵風土記稿』の上中條村(埼玉郡忍領)の項に「邑楽郡赤岩村光恩寺末(略)慶安二年(1649年)観音堂領トシテ十六石六斗ノ御朱印ヲ附セラル 開山了空明應五年(1496年)寂セリ 本尊不動ヲ安ス 観音堂」とあります。
・現在の御本尊は聖観世音菩薩のようで、地元では「中条観音様」と呼ばれ、信仰を集めている模様です。
・境内入口の石碑に「聖観世音安産守護」、本堂扉に「腹帯子宝祈願」「安産祈願」の案内があるので、子宝・安産に霊験あらたかな観音様のようです。
・入母屋造銅板葺で切妻様の向拝を付設しています。照りの強い本棟の屋根と起り気味の向拝屋根が独特のコントラストを見せています。
・大棟と鬼板に聖観世音菩薩の種子「サ」が掲げられているので、やはり御本尊は聖観世音菩薩とみられます。向拝正面には「観世音」の扁額が掲げられています。
・木鼻側面貘と正面獅子の彩色が異なるなど芸が細かいです。
・現在無住で、御朱印は浄瑠璃山 長慶寺(熊谷市西城93-1)で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第10番 聖観世音菩薩


■ 龍智山 毘廬遮那寺 常光院
公式Web
熊谷市上中条1160
天台宗
御本尊:釈迦如来(三尊佛)
札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番
・公式Webの縁起より抜粋引用させていただきます。
「長承元年(1132年)、藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光公が武蔵国司として下向し、当地に館(中條館)を構え豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。常光公の孫の中條出羽守藤次家長公は、16歳で既に頼朝公の石橋山の合戦に扈従し信任が厚く、関東武士では唯一人貞永式目制定に参画、評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺院とし、比叡山から天台の名僧金海法印を迎えて、建久三年(1192年)開基」「文禄三年(1594年)には忍城主松平忠吉(家康公四男)が成田氏建立の下忍清水の聖天院を廃して常光院へ合併」「開基以来延暦寺直末で天台宗に属し、特に梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章『梶竪一葉紋』を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至り寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇」
・山門には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。
・境内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。
・本堂は元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺きのどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。
・「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種以上もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度の参拝の方がいいかもしれません。
なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)
本堂に御座します。

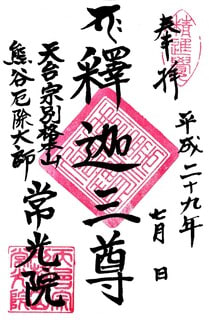
2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)
本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

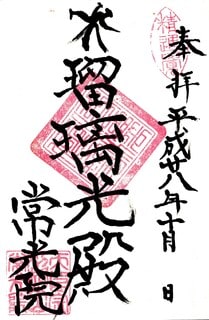
3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)
本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

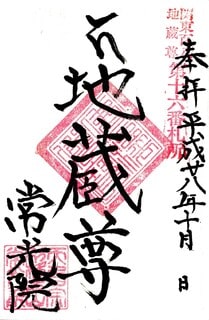
4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)
境内に露仏として奉安されています。

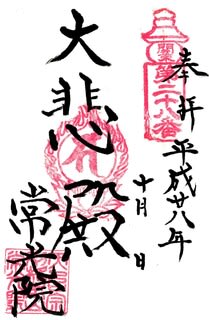
5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)
境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

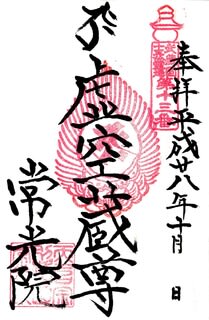
■ 伊弉諾神社 (いざなぎじんじゃ)
熊谷市上川上36
御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、大日孁貴命、猿田彦命、菅原道真公
旧社格:村社、旧上川上村鎮守
元別当:
授与所:古宮神社(池上)授与所
・社伝、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)などによると、中世、紀伊国熊野三所権現の勧請が創建で、当社、下川上の熊野社、大塚の熊野社の三社を総称して「熊野三所権現」と呼ぶとのこと。また、当社は「十二所権現」とも称されるようです。
・鎌倉期、征夷大将軍・宗尊親王が帰京した際、親王の供の平家ゆかりの宮田太郎貞明は北条氏の追及をおそれてこの地に逃れ当社の宮守りになった(『宮田氏家系図』)とされます。
・安政二年(1855)には、神祇管領から「伊弉諾神社熊野大権現」の幣帛を受けています。
・所蔵の黒馬図、相撲絵馬は市指定文化財に指定されています。
・古社にふさわしい厳かな境内。入母屋造桟瓦葺流れ向拝の端正な拝殿で、向拝には「伊弉諾神社」の扁額が掲げられています。
・御朱印は、古宮神社(熊谷市池上606)にて拝受しました。
・こちらは以前参拝し、その時は御朱印はないものと思っていましたが、いまは拝殿前に御朱印の案内が貼り出されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊弉諾神社 直書(筆書)


■ 太平山 龍淵寺
熊谷市上之336
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第8番
・名族成田家の菩提寺とされる名刹。
・境内掲示の寺伝・新編武蔵風土記稿などによると、開基は成田左京亮家時。応永十八年(1411年)和庵清順(わなんせいじゅん)大和尚により開創・開山。
・天正十九年(1591)、徳川家康公が遊猟の折に当寺へ立ち寄られ、時の住職呑雪和尚が家康公の三河時代の御乎習の御相手であったことがわかり、これを奇瑞として当寺に曹洞派の総録を許されましたが、呑雪和尚はあえてこの申し出を辞したと伝わります。
・本堂の後にあった小池は「龍ヶ淵」と呼ばれ、かつて龍が潜んでいましたが、開山の和尚清順が法力をもってこれを退けてこの地に当寺を建立したため「龍淵」を寺号としたと伝わります。
・成田氏系図をはじめ多くの文化財を蔵します。高浜虚子が当寺で詠んだ句碑も残されています。
・御朱印は庫裡にて御本尊のものを授与されています。忍観音霊場の御朱印は不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 古宮神社(こみやじんじゃ)
公式Web
熊谷市池上606
御祭神:石凝姥命、少彦名命、武甕槌命
旧社格:旧池上郷総鎮守
元別当:
授与所:境内授与所
・公式Web、境内由緒書、『埼玉の神社』などによると、古代、紀伊国秋月に御鎮座の旧宮幣大社、日前国懸神宮(ひのくま・くにかかすじんぐう)を勧請して創祀と伝わり、当初は社殿はなくいわゆる「磐座(いわくら)信仰」だったとみられています。
・社殿造立は、平安末期の長寛二年(1164年)。
・祭神の石凝姥命(いしこりどめのみこと)は、天孫降臨の際に邇邇芸命に随伴し、天児屋命、太玉命、天宇受売命、玉祖命と共に天降った五伴緒の一柱とされ、天照御大神が天岩戸にお隠れになったとき、日像鏡・日矛鏡を造られた神といわれています。
・西日本で祀られる例が多く、『埼玉の神社』には「なぜ、和歌山に祀られ鏡作部の遠祖とされる同神が、この地に勧請されたか不明であるが、埼玉地方は、武蔵国の古代文化の中心地の一つであり、近くには金錯銘鉄剣で有名な埼玉古墳群があることなどを考え合わせると、当地に神部(鏡作)ゆかりの人たちが住み、当社を祀ったとも考えられる。」とあります。
・室町期の文安二年(1445年)、相殿の神として少彦名命と武甕槌命を勧請したとされるので、創祀時の主祭神は石凝姥命とみられます。
・古くは岩倉社、又は岩倉大明神とも称し、『新編武蔵風土記稿』の池上村の項には「岩倉社」として記載されています。
・境内はよく整備され、明るい雰囲気のお社です。本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で多彩な棟飾りを配し、寺院建築のエッセンスが入っているかも。
・御朱印は境内の授与所にて拝受でき、親切なご神職が兼務社の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:古宮神社 直書(筆書)


■ 上之村神社
公式Web
熊谷市上之16
御祭神:事代主命、大山祇命、大己貴命
旧社格:郷社、上之村・箱田村・池上村三村の鎮守社
元別当:伊豆国 浄慶院 久見寺(上村、新義真言宗)
授与所:境内授与所
・公式Web、境内掲示、『埼玉の神社』などによると、創祀は平安時代以前とみられ、応永年間(1394-1428年)、成田五郎家時により再興とされます。
・明治2年に現在の上之村神社に改められるまでは、「久伊豆神社」ないし「久伊豆明神社」と号し、『新編武蔵風土記稿』の上村の項には「久伊豆社」として記載されています。
・『新編武蔵風土記稿』に「祭神ハ大山祇命ニテ 伊豆國三嶋社ヲ写シ祀ルトイヘト疑フヘシ 此久伊豆社ト云ハ騎西町塙ニ大社アリテ近郷往々是ヲ勧請スレハ 当社モ恐クハ彼ヲ写セシナラン」とあり、騎西ご鎮座の久伊豆神社の総社、玉敷神社からの勧請を示唆しています。
・御祭神は、江戸期は大山祇命でしたが、明治2年、主祭神を事代主命、相殿の神を大己貴命と大山祇命に改めています。
・また、別当の久見寺客殿に久伊豆の本地十一面観音が安置されていたとあり、神仏混淆の歴史が伺われます。
・当社ご鎮座の旧上(之)村は成田郷ともいわれた名族、成田氏の本貫で、当社は成田氏の尊崇篤く、後に徳川氏の尊崇を受けたと伝わります。なお、成田・別府・奈良・玉井氏は「武州四家」と呼ばれ、いずれも中世にこの地に勢力を張った名族とされています。
・当地有数の古社だけあって厳かな境内。木造の両部鳥居は寛文四年(1664年)建造の墨書が残り、市内最古の木造鳥居として市指定有形文化財に指定されています。
・応永年間(1394-1428年)、成田左京亮家時再建の本殿は一間社流造銅板葺で県指定文化財に指定されています。
・御朱印は参拝時たまたまご神職がいらしたのでいただけましたが、常駐ではありません。(公式Webにご在社予定が出ています。)
・熊谷七福神(恵比寿天)の御朱印は通常不授与かもしれませんが、御朱印には恵比寿様のお姿印が捺されていました。
・なお、兼務社として佐谷田神社、奈良神社(中奈良)、豊布都(とよふつ)神社(上奈良)、春日神社(小島)があり、それぞれWeb上で御朱印がみつかりますが、こちらで拝受できるかは不明です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:上之村神社 直書(筆書)


■ 大雷神社
熊谷市上之16
御祭神:大雷神
旧社格:上之村神社の境内社
元別当:
授与所:上之村神社境内授与所
・『新編武蔵風土記稿』に「末社 雷電 但馬国木田郡雷電社を勧請スト云伝フ(略)別当久見寺 客殿ニ雷電ノ本地馬頭観音を蔵ス」とあります。この地は雷の名所(?)ですが、どうしてわざわざ大雷神を但馬国(現・兵庫県)から勧請したのかはナゾです。
・上之村神社の摂社ですが、社号標、鳥居扁額ともに上之村神社と併記され、拝殿扁額も併記となっています。
・本殿は別で、こちらの本殿も県指定文化財に指定されています。
・この様な祭祀形態を配祀というか相殿というのかわかりませんが、本殿は分かれているので配祀なのかもしれません。
・「上之の雷電さま」と呼ばれ周辺住民の尊崇を集めています。利根川沿いのこのエリアはとくに雷が多く、随所で大雷神が祀られています。
・御朱印は、上之村神社境内授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大雷神社 直書(筆書)

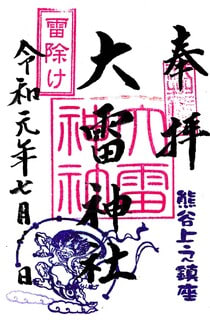
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4 へつづきます。
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔村の鎮守十社めぐり〕
当初は「以下10社について御朱印を拝受していますが、長井神社と大杉神社以外は常時授与かどうか不明なのでとりあえずリストのみです。」としましたが、令和2年秋に案内パンフが作成され、実際に御朱印も拝受していますので、ご参考までにUPします。
なお、現時点では御朱印は原則不授与かもしれません。詳細は長井神社宮司様にご確認ください。


情報が少ないですが、現地掲示のほか、案内パンフ、『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、『新編武蔵風土記稿』などを参考にまとめてみます。
1.(日向)長井神社 熊谷市日向
2.(俵瀬)伊奈利神社 熊谷市俵瀬
3.神明社・大杉神社 熊谷市葛和田
4.(大野)伊奈利神社 熊谷市大野
5.(弁財)嚴島神社 熊谷市弁財
6.善ヶ島神社 熊谷市善ヶ島
7.(八ツ口)日枝神社 熊谷市八ツ口
8.江波神社 熊谷市江波
9.西城神社 熊谷市西城
10.八幡大神社 熊谷市上須戸
■ (日向)長井神社
熊谷市日向1090
御祭神:品陀別命、息長帯姫命
旧社格:村社、旧日向村鎮守
元別当:三学院(日向村、当山修験)
授与所:境内脇社務所
・江戸時代には八幡社と称された旧日向村の鎮守社。(明治9年現社号に改号)
・天喜五年(1057年)、源頼義公が安陪貞任討伐の折にこの地に滞留されたとき、竜海という池に棲み村人を悩ましていた大蛇の退治を島田大五郎道竿に命じた。頼義公より弓矢と太刀を下賜された道竿は、竜海から利根川まで堀(道竿堀/どうかんぼり)を掘り、池の水を利根川に落としてこの四丈もの大蛇を退治した。頼義公は東北地方平定の吉事として、大蛇を倒したところに当社を、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったといいます。
・暦応元年(1338年)、足利尊氏が再興、戦国時代には忍城主成田長泰が信仰した記録が残ります。
・『新編武蔵風土記稿』の日向村の項に八幡社があり、上記の「竜海伝説」が詳細に記載されています。
・本地堂の御本尊は阿弥陀如来で、これは八幡神の本地が阿弥陀如来とされたことと符合します。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:長井神社 筆書


■ (俵瀬)伊奈利神社
熊谷市俵瀬489
御祭神:
旧社格:旧俵瀬村鎮守
元別当:寶林山 妙音寺 成就院(俵瀬村、新義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・俵瀬は利根川と福川に挟まれた島状のエリアで、『新編武蔵風土記稿』には俵瀬村の項に稲荷社が記載されているものの「成就院持」としかありません。
・これにはさすがの『埼玉の神社』も困り果てたらしく、成就院の記載を引き「成就院は慶安四年(1651年)の草創と伝えている。当地が一村としての体裁を整え始めるのが寛永(1624-1645年)の末ごろと思われ、当社の創建も、別当成就院と前後して行われたものであろう。」と記されています。
・江戸時代には「稲荷社」と称し、明治初期に「伊奈利社」と改め、明治41年合祀政策により同大字の神明社、厳島神社を合祀し、大正2年には堤防工事に伴い利根川縁にあった当社を厳島神社の旧社地に御遷座と伝わります。
・厳つい石垣の上に入母屋造桟瓦葺でどっしりと鎮座するお社は、ながらく水害と闘ってきた俵瀬の地の鎮守社ならではのお姿に思えます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市俵瀬 伊奈利神社 筆書


■ (葛和田)神明社・大杉神社
熊谷市葛和田591 大杉神社は(葛和田)神明社の境内社
御祭神:天照皇大神、大杉大神
旧社格:旧葛和田村鎮守
元別当:瑠璃光山 東光院 醫王寺(葛和田村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・伊勢の御師が当地に逗留した折に奉齋した社であると伝わります。
・旧社地は現在利根川の川中にあり、数回の移転を経て高台の現社地(氷川神社の社地)に御遷座とのこと。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に神明社があり「氷川ヲ合殿トス 村ノ鎮守ナリ 別当醫王寺」とあります。
・境内社の大杉神社(あんば様)の祭礼は利根川の流れに大御輿・大杉御輿を乗り入れるもので、「葛和田の勇み御輿」「関東一のあばれ御輿」として広く知られています。
・江戸時代の葛和田の地は利根川の河岸場として賑わいました。あるとき、与助という腕のいい船頭が霞ヶ浦の西浦で暴風雨に襲われ窮まったとき、日頃から信仰している大杉明神に祈りをささげると神佑を得て難を逃れました。このご神徳への御礼と今後の船路安全祈念のため、茨城県稲敷の大杉神社から勧請し、御輿を造営したと伝わります。
・当初は利根川に注ぐ道竿堀の南に御鎮座でしたが、大正3年堤防工事に伴い現社地に御遷座・合祀されました。
・御朱印は(日向)長井神社社務所にて拝受しました。
・Web上では神明社の御朱印がみつかりますが、現在は大杉神社の御朱印のみ授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大杉大神 筆書




■ (大野)伊奈利神社
熊谷市大野751
御祭神:豊宇気比咩命
旧社格:旧村社、旧大野村鎮守
元別当:大野山 利劔寺 文殊院(葛和田(大野)村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・〔村の鎮守十社めぐり〕のなかではもっとも利根川に近く、利根川の堤防下に鎮座します。
・江戸期には大野村は葛和田村の一部とされ、『新編武蔵風土記稿』には葛和田村の項に「稲荷社二宇 一ハ文殊院 一ハ正泉寺持」とあり、『埼玉の神社』には文殊院が別当とあるので、こちらが該当とみられます。
・ただし、『埼玉の神社』には「宝暦六年(1756年)の伏見稲荷からの分霊証書に『武州 大野村鎮守』とあることから、当時既に『大野村』という名称が使われており、葛和田村から実質は独立していたことがわかる」とあります。
・上記のとおり、宝暦六年(1756年)には伏見稲荷からの分霊証書を受けて創祀しています。
・地形からしても、なにより水害防除が求められる地とみられ、『埼玉の神社』には「伊奈利社を(利根)川の側に勧請することによって水害から村を守ろうとした開発者の心情が推察される。」とあります。
・小山状の高台に鎮座し、参道右手が旧文殊院跡。その手前に大国主尊、参道階段右手に三峰社、拝殿左手には馬頭観世音菩薩、庚申様、青面金剛が祀られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市大野 伊奈利神社 筆書


■ (弁財)嚴島神社
熊谷市弁財174
御祭神:
旧社格:弁財地区鎮守
元別当:辨財山 醫王院 薬王寺(辨財村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「当地(弁財)は大昔利根川の流れの中にあったが、やがて流路が変わり、自然堤防を形作った所である。」とあり、河川とのかかわりから弁財天が祀られたとする一方、口碑に「当地の草分けであり、屋号を庄屋と呼ぶ大島清和家の先祖が祀った。」とあり、「同家は平家の落人であり、そのゆかりから嚴島神社を祀った。」という説にも触れています。
・『新編武蔵風土記稿』の辨財村の項に辨財天社があり「村名ナリシテ見レハ古社ナルヘケレト傳ヘテ失フ」とあります。
・(日向)長井神社縁起の竜海伝説では、大蛇の出現したところに弁財天を祀ったとされ、この弁財天を当社とする説と(日向)長井神社境内の宇賀神(弁天様)とする説があるようです。
・『埼玉の神社』では、享保十六年(1731年)の利根川大洪水の折、当地に沼ができて、その後沼の主と呼ばれる大蛇が棲み、それが竜海伝説に重なったと指摘しています。
・こちらも社叢のなかに御鎮座。拝殿は石垣のうえに入母屋造桟瓦葺で、主屋根の軒に瓦屋根の向拝を重ねるようにせり出し変化のある意匠。
・弁財天や厳島社はもともと蛇とのゆかりがありますが、向拝の屋根飾りにも蛇の姿がみられます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:嚴島比賣 筆書


■ 善ヶ島神社
熊谷市善ヶ島197
御祭神:
旧社格:旧善ヶ島村鎮守
元別当:光明山 福壽院 龍泉寺(善ヶ島村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』『パンフ』には、当地は当初葦が生えた島で葦ヶ島と呼ばれたが、後に利根川の流れが変わり、近村と地続きになり善ヶ島と改めた。また、1500年頃の蔵王権現社の勧請が当社の起源とされ、当初は蔵王権現社、明治初期に御嶽神社と称し、明治42年に善ヶ島神社に改称といいます。
・明治41年には大字裏久保の愛宕神社と、上元割の阿夫利神社を合祀。地元では合祀社の阿夫利神社に因み「阿夫利様」と呼ばれることが多いそうです。
・『新編武蔵風土記稿』の善ヶ島村の項に蔵王権現社があり「永正(1504-1521年)年中の勧請ト云 龍泉寺持 末社 天神 疱瘡神 摩陀羅神」とあります。
・金剛蔵王権現は修験系の尊格で、ことにの吉野の金峯山寺本堂(蔵王堂)の御本尊として知られています。
・当社の現在の主祭神は不明ですが、金剛蔵王権現は大己貴命、少彦名命、国常立尊、日本武尊、金山毘古命との習合例が多く、明治の神仏分離時、金剛蔵王権現を祀る堂祠は上記の神々を祭神とする神社となった例がみられます。
・末社に摩陀羅神の名がみられます。すこぶる複雑な性格をもたれる尊格として知られ、東日本で祀られる例は多くありません。
・別当龍泉寺は古義真言宗で赤岩光恩寺の末。赤岩光恩寺の寺伝には「推古天皇11年(603年)には秦河勝を勅使として仏舎利三粒が納められた」とあります。(秦河勝と摩陀羅神は強い関係があるとされる。)
・当社に摩陀羅神が祀られていた背景には、このような所縁が関連しているのかもしれません。
・現在も、複雑な由緒を想起させる境内社が複数ご鎮座されます。
・社叢のなか、入母屋造桟瓦葺向拝付設の社殿と境内社が御鎮座。
・鳥居、灯籠ともに大きく嵩が上げられ、拝殿も数段高く、水害防除が大切な地であることを物語っています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:善島神社 筆書


■ (八ツ口)日枝神社
熊谷市八ツ口922
御祭神:
旧社格:旧村社、旧八ツ口村鎮守
元別当:●源山 長昌寺(八ツ口村、禅宗臨済派)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「(別当の)長昌寺は、天文元年(1532年)に成田氏に従い武川の合戦で討死した山田弥次郎の菩提追福のために、その父山田伊平が、弥次郎の領地であったこの地に草創した寺院である。当社の成立背景には、長昌寺の僧とのかかわりが考えられるが、明らかにできない。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の八ツ口村の項に山王社があり「村ノ鎮守ニテ稲荷ヲ合殿トス 長昌寺持」とあります。
・元別当の長昌寺は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第88番の結願寺で、相応の寺格をお持ちかと思いますが、現在のところ御朱印は拝受しておりません。
・社頭に朱塗りの2つの鳥居。向かって左手が日枝神社、右手が八坂神社と伊奈利社です。
八坂神社の夏祭りの御輿渡御は、以前は「暴れ御輿」として広く知られていたようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市八ツ口 日枝神社 筆書

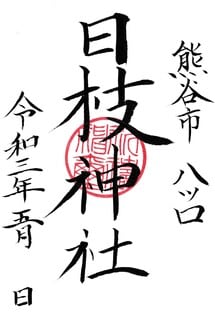
■ 江波神社
熊谷市江波315
御祭神:菅原道真公
旧社格:旧村社、旧江波村鎮守
元別当:福原山 寶蔵院(江波村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「明治四十一年の改正まで天神社であったことから、氏子にはいまだに天神様と呼ばれている。(中略)明治四十一年、字西嬉愛の宇知多神社(妙見社)と字道上の稲荷神社の無格社二社を合祀した。」とあります。
・同書によると、お産を軽くしてくれる有り難い御利益がある」として信仰を集めたようです。
・『新編武蔵風土記稿』の江波村の項に天神社があり「村ノ鎮守トス 寶蔵院持」とあります。
・一面の麦畑のなかに浮かぶように、切妻造瓦葺妻入りの社殿が御鎮座。向拝も切妻の屋根がかかり、めずらしい様式の社殿です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:江波神社 筆書


■ 西城神社
熊谷市西城2
御祭神:
旧社格:旧村社、旧西城村(本郷)鎮守
元別当:浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺(西城村、古義真言宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「西城の地名は、かつてこの地に左近衛少将藤原義孝の居舘があったことにちなむものといわれ、古来、西城の村は郭(くるわ)と呼ばれる幾つかの小さい集落に分かれ、神社の祭祀もまた郭ごとに鎮守として各々神社を祀っていた。明治維新の際、社格を定めるに当たり、(大天貘社は)村内の諸社の中で最も規模が大きく、村の中で最も早く開かれた本郷の鎮守であったことから、当社が西城村の村社になった。恐らく、明治9年に村社となった時に村名を採って西城神社と社名を改めたものであろう。明治42年には、字東田鎮座の稲荷神社と字鴉森鎮座の厳島神社を合祀し現在に至っている。」とあります。
・また同書には「境内にある勝根神社は、古くから当社の末社として祀られており、その祭神は大物主命である。当社(大天貘社)が元は本郷だけで祀る神社であったのに対し、勝根神社は初めから(西城)村全体で祀る神社」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の西城村の項に大天貘社があり「村ノ鎮守トス 長慶寺持」とあります。
・西城神社は入母屋造桟瓦葺、「西城神社」と彫り込まれた棟飾りは精緻で一見の価値があります。
・向かって左手に御鎮座の勝根神社は、切妻造桟瓦葺の整った社殿で「村全体で祀ってきた神社」としての重みを放たれています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:西城神社 筆書

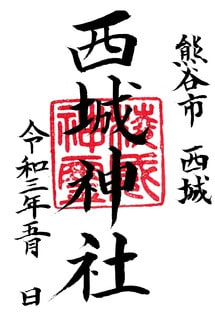
■ 八幡大神社
熊谷市上須戸838
御祭神:
旧社格:大字上須戸鎮守、(旧長井村総鎮守)
元別当:福原山 開城院 正法寺(上須戸村、天台宗)
授与所:(日向)長井神社社務所
・『埼玉の神社』には「伝説によると、天喜五年(1057年)、源頼義が安倍貞任を討つために奥州へ下る途中、当地に逗留した。この折竜海という沼に棲む大蛇が村人を悩ますことを聞いたため、土地の島田大五郎道竿に命じて退治させた。頼義はこの大蛇退治を安倍氏征討の門出に吉事であると喜び、大蛇の棲んでいたところから、東・西・北に三本の矢を放ち、その落ちた所にそれぞれ八幡社を、沼の中央に大蛇慰霊のための弁天社を祀った。当社は、西に放たれた矢が落ちた所に祀られたという。」とあります。
・『新編武蔵風土記稿』の上須戸村の項に八幡社があり「八幡社 辨天社 何レモ社領ヲ附ラル年代下●出セリ 別当正法寺」とあります。
・『埼玉の神社』の内容は、(日向)長井神社の「竜海伝説」とほぼ同様で、このエリアに広く伝わっていたことが伺われます。
・うっそうと茂る社叢。木造朱塗りの両部鳥居、石造の明神鳥居の正面おくに入母屋造桟瓦葺平入り流れ向拝の八幡神社、向かって右手には切妻造桟瓦葺妻入りの八坂大神が御鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊谷市上須戸 八幡大神社 筆書


■ 寶積山 白道院 大龍寺
公式Web
熊谷市葛和田898
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第15番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第21番
・名刹のようですが、現地、Webともに詳しい情報がとれませんでした。
・『新編武蔵風土記稿』の葛和田村の項に記載がありますので抜粋引用します。「館林町善導寺末 開山ハ幡随意上人元和元年正月示寂 開基ハ成田氏ノ臣嶋田采女正ナリ コノ子孫今村民六兵衛ナリト云 本尊阿弥陀ヲ安セリ 荒神社 愛宕社 不動堂 観音堂」。
・幡随意(ばんずいい)上人は、 慶長二十年(1615年)寂と伝わる浄土宗の名僧で、鎌倉光明寺で教学を修められ、後に京都百万遍知恩寺の三十三世住持。徳川家康公の信任厚く、駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創、熊谷の名刹、熊谷寺(ゆうこくじ)の中興など全国で寺院を創立・再興されました。
・当寺所蔵の「幡随意上人の書」、本堂に御座す「三十三体観音像」(元禄期、寄木造金泥)は市の文化財に指定されています。
・名刹らしい風趣のある山内。御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。御本尊および幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていないとのことです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第15番 三十三体観世音菩薩


■ 瑠璃光山 浄光院 福生寺
熊谷市日向1154
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第34番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番
・こちらも御由緒詳細がとれませんが、山内石碑には「四九四年前に開創せられし名刹」とあり、『新編武蔵風土記稿』の日向村の項には「邑楽郡赤岩村光恩寺末 開山専祐寛永十八年(1641年)寂 本尊大日ヲ安セリ 薬師堂」とあります。
・重厚な山門、本堂、観音堂を擁して山内はよく整っています。
・こちらは忍秩父三十四観音霊場第34番の結願所で、札所本尊は馬頭観世音菩薩。御本尊の大日如来は幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所本尊でもあり、こちらの御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第34番 馬頭観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第4番 大日如来

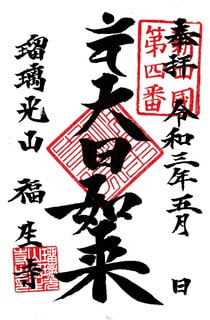
■ 浄瑠璃山 薬樹院 長慶寺
公式Web
熊谷市西城93-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来・薬師如来?
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番
司元別当:西城神社(西城村、旧西城村(本郷)鎮守)
・こちらは詳細な公式Webをお持ちなので、そちらから引用させていただきます。
・南北朝の永和二年(1376年)、慶弘という僧が伝・行基作の薬師如来像を祀り開創。赤岩光恩寺の末寺で、歴代の住職が隠居されていました。
・薬師如来像は12年に一度、寅年の御開帳で信仰を集めているようです。
・本堂と薬師堂、薬師堂厨子は、2020年9月に市の有形文化財に指定されています。
・ともに、上州花輪村の名工・石原吟八郎のグループと、「歓喜天聖天堂」の棟梁の林兵庫正清を中心に建立。江戸期のこの地の彫物師集団の技巧を示す作品として評価されています。
・本堂には阿弥陀如来、薬師堂には薬師如来が御座します。
公式Webに「本堂の阿弥陀如像は、宝永年間(1704-1711年)に祀られた。平成26年遷座300年目に修復。本尊とご縁を結び、人生を輝いて全うできるように御手綱を握ってお参りができる」とあるので、当寺のいまの御本尊は阿弥陀如来とみられますが、宝永年間までの御本尊は薬師如来とみられ、現在でも御本尊のポジションなのかもしれません。
・仏教寺院、とくに密寺の御本尊のポジションは複雑で、観音堂、薬師堂、不動堂などで草創し、のちに本堂が建てられた場合などは、複数の御本尊がおられる場合もあるようです。(例えば、本堂御本尊は大日如来、薬師堂御本尊は薬師如来で、寺院としての御本尊は両尊併記となる。)
・弘法大師霊場の札所本尊は草創時の御本尊が札所本尊になられる場合も多く、こちらもその例ではないでしょうか。
・御朱印はご住職がご不在で書置もなかったので、ご親切な寺庭様にお願いして郵送をいただきました。なお、こちらは忍秩父三十四観音霊場第10番光明山 観音寺(上中条)の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第46番 薬師如来




■ 大慈山 薬師院 観音寺
熊谷市下奈良913
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第11番
・この寺社巡りも、下奈良エリアに至ってますますディープな世界に入っていきます(笑)
・忍秩父三十四観音霊場第11番のこの札所寺院は、現在無住のお堂で、境内掲示はなくWebでも情報がとれないので、『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項の記載を引用します。
「埼玉郡羽生村正覺院ノ末ナリ 本尊十一面観音安セリ 薬師堂」。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番の札所は福聚山 利永寺とされていますが、別の資料によると、もともとはこちらが第43番の札所であった可能性もあります。
・まわりにランドマークがないので説明しにくいですが、Googleマップの住所検索でヒットします。
・竹林を背にした奥まったところにあり、向拝柱はあるものの、切妻造妻入で一見お堂らしくないので、参道入口の如意輪観世音菩薩と地蔵菩薩の石仏がなければそれとわからないかもしれません。
・御朱印は、真言宗智山派関東十一談林の名刹、光明山 一乗院(熊谷市上之2891-1)で規定用紙のものを拝受できます。(一乗院の御朱印は授与されておりません。)
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第11番 十一面観世音菩薩(大悲閣)


■ 福聚山 阿弥陀院 利永寺
熊谷市下奈良796
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第12番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番
・こちらは、今回の記事のなかでもっともマニアックな札所かと思われます。記事UPは迷いましたが、確かに忍観音霊場の札所なのでご紹介します。
・参拝情報がほとんどなく、Googleマップで位置検索するととある企業の敷地を示すので、意を決してこちらの事務所にお伺いすると、こちらの敷地内に御座とのこと。
・ご丁寧にもご案内いただき、ようやく参拝が叶いました。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 本尊前(十一面観音)ニ同シ 観音堂 利永寺持」とあり、本堂(御本尊:十一面観世音菩薩)のほか、観音堂を擁していたかもしれません。
・整った宝形造で向拝を付設し、向拝見上げにはしっかり御詠歌の木板が掛かっていました。ただし、この木板の札番は「第七番」。こちらは忍観音霊場で第11番、幡羅郡新四国霊場で第43番のはずなので、この「第七番」というのはナゾです。
・こちらの御朱印はなかばあきらめていたのですが、一乗院様にお伺いすると、第11番観音寺のほか、こちらの御朱印(規定用紙)も授与されているとのことで、ありがたく拝受しました。
・ご紹介はしましたが、参拝時に一般企業さんのお手間をいただくこともあり、忍観音霊場巡拝者に限ってお伺いした方がよろしいかと思います。また、休業日や営業時間外の参拝も不可だと思います。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第12番 十一面観世音菩薩(大悲殿)

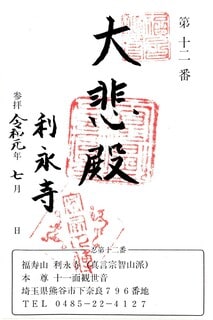
■ 萬頂山 集福寺
熊谷市下奈良551
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第13番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番
・山内掲示によると、永仁年間(1293-1299年)、由良法燈圓明國師によって臨済宗法燈派の本山として開かれ、天文年間(1532-1555年)、永平道元孫桂室秀芳大和尚によって曹洞宗に改められたという名刹です。
・同掲示には、(当寺)五世扶嶽太助大和尚は、後に「とげぬき地蔵」(江戸・巣鴨(当時は神田明神下)の萬頂山 高岩寺を開いたことで知られています、との記載があります。
・境内の諸堂は江戸時代後期の建立で、法堂、庫裡、仏殿、開山堂を回廊で結び、内部に鐘楼を設けた七堂伽藍の配置をとっているようです。
・幡羅郡新四国霊場の初番発願所を務められ、このことからも当地屈指の名刹であることがわかります。
・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項にも大きく記載され「相傳フ往昔ハ臨済派ニテ開山圓明國師(略)其後永正年中桂室秀芳ト云僧、曹洞派ニ改メシヨリ今開山トス(略)開基ハ式部大輔助高十代成田下総守親泰法名貞岡宗蓮菴主ト号ス 入道シテ当村ニ隠棲ヲ営ミ 即当寺ヲ造建シ大永四年六月八日卒ス 御打入ノ後 東照宮忍城ヨリ此辺御放鷹ノ時、当寺ヘ成ラセラレ住僧桂岩ヘ御目見仰付ラレ 其後慶長年中江戸ヘ召セレシ時 元神田蔵王権現ノ舊(旧)蹟ニ於テ寺地ヲ賜ハリ一寺ヲ草創シテ金峯山高林寺ト号シ蔵王権現ヲ鎮守トセリ 後替地ヲ給ヒ本郷ヘ遷リ 又駒込ヘ遷リテ 今ハ当寺ノ末トナレリ 本尊三尊ノ釋迦ヲ安セリ(以下略)」とあります。
・「金峯山 高林寺」とは、文京区向丘の金峰山 高林寺をさすとみられ、本郷区史のP.1247には、たしかに「高林寺 武州幡羅郡下奈良村集福寺末、金峰山と号ス」との記載があります。
・「七堂伽藍の名刹」だけあって、さすがに伽藍は整っています。
・庫裡にて拝受した御朱印は。忍観音霊場と幡羅郡新四国霊場のふたつの札所印が捺されていました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第13番 札所本尊不明 御朱印尊格は釋迦牟尼佛
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番 釋迦牟尼佛
1通で兼用。




■ 永昌山 常楽寺
熊谷市中奈良1956
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項には「奈良村集福寺末 開山ハ本尊(ママ)七世ノ僧宗察慶長年中(1596-1615年)創建ト云 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・おそらく本寺であった集福寺第七世の僧宗察が慶長年中(1596-1615年)に創建とみられます。
・また、山内の石碑には「当常楽寺ノ境内地ハ創立当時南ハ新井北ハ堀内東ハ後原ヲ境ニ凡ソ五千三百余坪アッタ」とあり、相当の大寺であったことが伺われます。
・参拝時ご不在でしたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番で、曹洞禅ナビで「御朱印対応あり」となっているので、郵送をお願いするとお送りいただけました。
・こちらの御朱印にも幡羅郡新四国霊場の札所印が捺されていました。「幻の霊場」ともいわれる幡羅郡新四国霊場ですが、意外に札所印が残っているようです。
・御本尊は釈迦如来のようですが、御朱印尊格は観世音菩薩となっています。禅宗寺院の観音様は聖観世音菩薩が多いですが、御朱印の主印に種子は確認できず聖観世音菩薩かどうかはわかりません。(観世音菩薩、大悲殿などの揮毫でも、朱印に種子があれば(=御寶印)、こちらで観音様の個別の尊格はわかります。)
・新四国霊場の札所本尊は御本尊の例が多いのですが、こちらはなんらかの由縁で観音様が札所本尊となられているのかもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番 釈迦如来


■ 奈良神社
熊谷市中奈良1969
御祭神:奈良別命
旧社格:延喜式内社(論社)、奈良四村の総鎮守
元別当:摩尼山 熊山院 長慶寺(中奈良、高野山真言宗)
授与所:境内拝殿前
・中奈良に御鎮座の古社で、『延喜式神名帳』の幡羅郡小社四座の一社(論社)とされます。
・『埼玉の神社』には、仁徳天皇の御世、下毛野君の祖で豊城入彦命の子孫とされる奈良別命が、下野国国造の任を終えたのち当地を開拓したことから、郷民がその徳を偲んで創祀とあります。
・また、当地に拠った奈良氏は、成田・別府・玉井氏などとならぶ名族で、当社を奉斎していたとみられています。
・中世、当社は熊野信仰の影響を受けて奈良神社から熊野神社に号を改めました。
・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項の熊野社には「奈良四村ノ惣鎮守ナリ 本地彌陀・薬師・観音を安ス 古は修験圓蔵坊カ持ナリシガ 成田氏下野國烏山ニ移ル時圓蔵坊モ随テ移リ(略)今ハ長慶寺ノ持トナル 社内ニ奈良神社ヲ合セ祀ル 奈良神社ハ神名帳当郡四座ノ一ナリ想ニ舊章衰廃ノ後、熊野三社ヲ合祀シ」とあります。
・『埼玉の神社』では、「恐らく、古代に創建された奈良神社は廃絶したのではなく、中世、その時流に合った熊野信仰を収容することにより社名を変えて存続したのであろう。」とみなしています。
・また、「江戸後期になると、中世以来永く熊野神社としてきた当社は、復古の思想興隆により、社名を古代の奈良神社に復した。」とも記されています。
・古社の落ち着きを感じる境内。本殿の意匠も見事なものです。
・拝殿前に御朱印が置かれていたので、お代を賽銭箱に納めて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:奈良神社 書置(筆書)


■ 摩尼山 熊山院 長慶寺
熊谷市中奈良1995
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第25番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項に「紀伊國高野山清浄心院末(略)相傳フ当寺は古修験地ナリシガ 天正十八年(1590年)圓蔵坊ト云僧、成田氏ニ従ヒ下野國ニ移リシ後 長慶ト云僧今ノ宗ニ改メ造立セリト云(略)元空坊号ヲ継テ其頃当村ニ住シ後黒田村ヘ移シニヨリ 坊宇以下其ママ長慶(延寶四年(1676年)寂)譲受テ今ノ宗ノ一寺トセシニヤ 本尊地蔵ヲ安セリ」とあります。
・当初は(天台系)修験の圓蔵坊・元空坊が護持し、後に長慶が跡を継いで紀伊国の真言宗高野山浄心院の末寺となり、江戸期には奈良神社(熊野社)の別当を司りました
・『埼玉の神社』には「明治期に入ると、当社(奈良神社/熊野社)本殿の熊野神の本地である弥陀・薬師・観音の三尊は、長慶寺に移され、代わって神鏡が奉安された。」とあるので、熊野神は本地(弥陀・薬師・観音の三尊)として長慶寺に遷られたことになります。
・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂。忍観音霊場の札所本尊、如意輪観世音菩薩も本堂に御座とのことです。
・御朱印はご住職がいらっしゃれば庫裡にて拝受できるかと思いますが、ご不在がちのようで、書置もないので拝受はなかなかむずかしい札所です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第25番 如意輪観世音菩薩


2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番 地蔵菩薩


■ 福聚山 慈眼寺
熊谷市田島238
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第14番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番
司元別当:(田島村)稲荷社(旧田島村鎮守)
・こちらも無住の寺院で情報が少ないです。
司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)
・『新編武蔵風土記稿』の田島村の項に「弥藤五村観清寺末(略)古ハ観音ノ堂ナリシガ寛永年中(1624--1645年)●月堂開山シテ一寺トナセリ コノ人ハ慶安四年(1651年)寂セリト云 本尊十一面観音ヲ安ス」とあり、もとは観音堂として草創、寛永年中(1624--1645年)に寺院になったようです。
・入り組んだ路地のなか、集落に囲まれるようにあります。寄棟造桟瓦葺で右手に庫裡らしき建物を連接しています。
・向拝柱はなく中央サッシュ扉、上部に「慈眼寺」の寺号扁額を掲げています。
・参拝時ご不在でしたので郵送をお願いしお送りいただきました。郵送なので欲張らず忍観音霊場の御朱印のみお願いしましたが、御朱印には幡羅郡新四国霊場の札番揮毫もいただいておりました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第14番 十一面観世音菩薩
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第27番 十一面観世音菩薩
※1通に2札所併記。


■ 光明山 地蔵院 観音寺
熊谷市上中条2018
高野山真言宗
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第10番
・こちらも無住で情報が少ないです。
『新編武蔵風土記稿』の上中條村(埼玉郡忍領)の項に「邑楽郡赤岩村光恩寺末(略)慶安二年(1649年)観音堂領トシテ十六石六斗ノ御朱印ヲ附セラル 開山了空明應五年(1496年)寂セリ 本尊不動ヲ安ス 観音堂」とあります。
・現在の御本尊は聖観世音菩薩のようで、地元では「中条観音様」と呼ばれ、信仰を集めている模様です。
・境内入口の石碑に「聖観世音安産守護」、本堂扉に「腹帯子宝祈願」「安産祈願」の案内があるので、子宝・安産に霊験あらたかな観音様のようです。
・入母屋造銅板葺で切妻様の向拝を付設しています。照りの強い本棟の屋根と起り気味の向拝屋根が独特のコントラストを見せています。
・大棟と鬼板に聖観世音菩薩の種子「サ」が掲げられているので、やはり御本尊は聖観世音菩薩とみられます。向拝正面には「観世音」の扁額が掲げられています。
・木鼻側面貘と正面獅子の彩色が異なるなど芸が細かいです。
・現在無住で、御朱印は浄瑠璃山 長慶寺(熊谷市西城93-1)で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第10番 聖観世音菩薩


■ 龍智山 毘廬遮那寺 常光院
公式Web
熊谷市上中条1160
天台宗
御本尊:釈迦如来(三尊佛)
札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番
・公式Webの縁起より抜粋引用させていただきます。
「長承元年(1132年)、藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光公が武蔵国司として下向し、当地に館(中條館)を構え豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。常光公の孫の中條出羽守藤次家長公は、16歳で既に頼朝公の石橋山の合戦に扈従し信任が厚く、関東武士では唯一人貞永式目制定に参画、評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺院とし、比叡山から天台の名僧金海法印を迎えて、建久三年(1192年)開基」「文禄三年(1594年)には忍城主松平忠吉(家康公四男)が成田氏建立の下忍清水の聖天院を廃して常光院へ合併」「開基以来延暦寺直末で天台宗に属し、特に梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章『梶竪一葉紋』を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至り寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇」
・山門には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。
・境内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。
・本堂は元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺きのどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。
・「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種以上もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度の参拝の方がいいかもしれません。
なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)
本堂に御座します。

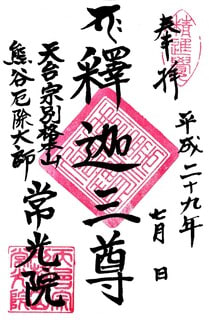
2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)
本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

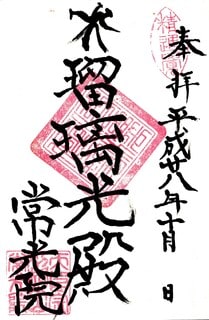
3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)
本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

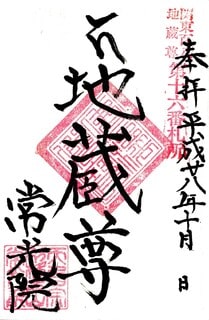
4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)
境内に露仏として奉安されています。

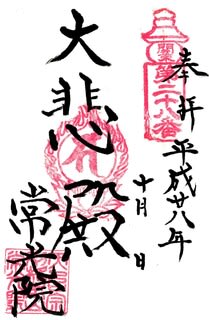
5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)
境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

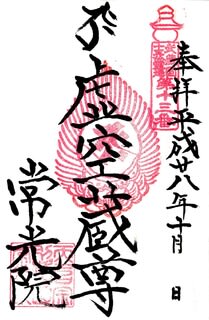
■ 伊弉諾神社 (いざなぎじんじゃ)
熊谷市上川上36
御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、大日孁貴命、猿田彦命、菅原道真公
旧社格:村社、旧上川上村鎮守
元別当:
授与所:古宮神社(池上)授与所
・社伝、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)などによると、中世、紀伊国熊野三所権現の勧請が創建で、当社、下川上の熊野社、大塚の熊野社の三社を総称して「熊野三所権現」と呼ぶとのこと。また、当社は「十二所権現」とも称されるようです。
・鎌倉期、征夷大将軍・宗尊親王が帰京した際、親王の供の平家ゆかりの宮田太郎貞明は北条氏の追及をおそれてこの地に逃れ当社の宮守りになった(『宮田氏家系図』)とされます。
・安政二年(1855)には、神祇管領から「伊弉諾神社熊野大権現」の幣帛を受けています。
・所蔵の黒馬図、相撲絵馬は市指定文化財に指定されています。
・古社にふさわしい厳かな境内。入母屋造桟瓦葺流れ向拝の端正な拝殿で、向拝には「伊弉諾神社」の扁額が掲げられています。
・御朱印は、古宮神社(熊谷市池上606)にて拝受しました。
・こちらは以前参拝し、その時は御朱印はないものと思っていましたが、いまは拝殿前に御朱印の案内が貼り出されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊弉諾神社 直書(筆書)


■ 太平山 龍淵寺
熊谷市上之336
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第8番
・名族成田家の菩提寺とされる名刹。
・境内掲示の寺伝・新編武蔵風土記稿などによると、開基は成田左京亮家時。応永十八年(1411年)和庵清順(わなんせいじゅん)大和尚により開創・開山。
・天正十九年(1591)、徳川家康公が遊猟の折に当寺へ立ち寄られ、時の住職呑雪和尚が家康公の三河時代の御乎習の御相手であったことがわかり、これを奇瑞として当寺に曹洞派の総録を許されましたが、呑雪和尚はあえてこの申し出を辞したと伝わります。
・本堂の後にあった小池は「龍ヶ淵」と呼ばれ、かつて龍が潜んでいましたが、開山の和尚清順が法力をもってこれを退けてこの地に当寺を建立したため「龍淵」を寺号としたと伝わります。
・成田氏系図をはじめ多くの文化財を蔵します。高浜虚子が当寺で詠んだ句碑も残されています。
・御朱印は庫裡にて御本尊のものを授与されています。忍観音霊場の御朱印は不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛


■ 古宮神社(こみやじんじゃ)
公式Web
熊谷市池上606
御祭神:石凝姥命、少彦名命、武甕槌命
旧社格:旧池上郷総鎮守
元別当:
授与所:境内授与所
・公式Web、境内由緒書、『埼玉の神社』などによると、古代、紀伊国秋月に御鎮座の旧宮幣大社、日前国懸神宮(ひのくま・くにかかすじんぐう)を勧請して創祀と伝わり、当初は社殿はなくいわゆる「磐座(いわくら)信仰」だったとみられています。
・社殿造立は、平安末期の長寛二年(1164年)。
・祭神の石凝姥命(いしこりどめのみこと)は、天孫降臨の際に邇邇芸命に随伴し、天児屋命、太玉命、天宇受売命、玉祖命と共に天降った五伴緒の一柱とされ、天照御大神が天岩戸にお隠れになったとき、日像鏡・日矛鏡を造られた神といわれています。
・西日本で祀られる例が多く、『埼玉の神社』には「なぜ、和歌山に祀られ鏡作部の遠祖とされる同神が、この地に勧請されたか不明であるが、埼玉地方は、武蔵国の古代文化の中心地の一つであり、近くには金錯銘鉄剣で有名な埼玉古墳群があることなどを考え合わせると、当地に神部(鏡作)ゆかりの人たちが住み、当社を祀ったとも考えられる。」とあります。
・室町期の文安二年(1445年)、相殿の神として少彦名命と武甕槌命を勧請したとされるので、創祀時の主祭神は石凝姥命とみられます。
・古くは岩倉社、又は岩倉大明神とも称し、『新編武蔵風土記稿』の池上村の項には「岩倉社」として記載されています。
・境内はよく整備され、明るい雰囲気のお社です。本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で多彩な棟飾りを配し、寺院建築のエッセンスが入っているかも。
・御朱印は境内の授与所にて拝受でき、親切なご神職が兼務社の御朱印も授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:古宮神社 直書(筆書)


■ 上之村神社
公式Web
熊谷市上之16
御祭神:事代主命、大山祇命、大己貴命
旧社格:郷社、上之村・箱田村・池上村三村の鎮守社
元別当:伊豆国 浄慶院 久見寺(上村、新義真言宗)
授与所:境内授与所
・公式Web、境内掲示、『埼玉の神社』などによると、創祀は平安時代以前とみられ、応永年間(1394-1428年)、成田五郎家時により再興とされます。
・明治2年に現在の上之村神社に改められるまでは、「久伊豆神社」ないし「久伊豆明神社」と号し、『新編武蔵風土記稿』の上村の項には「久伊豆社」として記載されています。
・『新編武蔵風土記稿』に「祭神ハ大山祇命ニテ 伊豆國三嶋社ヲ写シ祀ルトイヘト疑フヘシ 此久伊豆社ト云ハ騎西町塙ニ大社アリテ近郷往々是ヲ勧請スレハ 当社モ恐クハ彼ヲ写セシナラン」とあり、騎西ご鎮座の久伊豆神社の総社、玉敷神社からの勧請を示唆しています。
・御祭神は、江戸期は大山祇命でしたが、明治2年、主祭神を事代主命、相殿の神を大己貴命と大山祇命に改めています。
・また、別当の久見寺客殿に久伊豆の本地十一面観音が安置されていたとあり、神仏混淆の歴史が伺われます。
・当社ご鎮座の旧上(之)村は成田郷ともいわれた名族、成田氏の本貫で、当社は成田氏の尊崇篤く、後に徳川氏の尊崇を受けたと伝わります。なお、成田・別府・奈良・玉井氏は「武州四家」と呼ばれ、いずれも中世にこの地に勢力を張った名族とされています。
・当地有数の古社だけあって厳かな境内。木造の両部鳥居は寛文四年(1664年)建造の墨書が残り、市内最古の木造鳥居として市指定有形文化財に指定されています。
・応永年間(1394-1428年)、成田左京亮家時再建の本殿は一間社流造銅板葺で県指定文化財に指定されています。
・御朱印は参拝時たまたまご神職がいらしたのでいただけましたが、常駐ではありません。(公式Webにご在社予定が出ています。)
・熊谷七福神(恵比寿天)の御朱印は通常不授与かもしれませんが、御朱印には恵比寿様のお姿印が捺されていました。
・なお、兼務社として佐谷田神社、奈良神社(中奈良)、豊布都(とよふつ)神社(上奈良)、春日神社(小島)があり、それぞれWeb上で御朱印がみつかりますが、こちらで拝受できるかは不明です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:上之村神社 直書(筆書)


■ 大雷神社
熊谷市上之16
御祭神:大雷神
旧社格:上之村神社の境内社
元別当:
授与所:上之村神社境内授与所
・『新編武蔵風土記稿』に「末社 雷電 但馬国木田郡雷電社を勧請スト云伝フ(略)別当久見寺 客殿ニ雷電ノ本地馬頭観音を蔵ス」とあります。この地は雷の名所(?)ですが、どうしてわざわざ大雷神を但馬国(現・兵庫県)から勧請したのかはナゾです。
・上之村神社の摂社ですが、社号標、鳥居扁額ともに上之村神社と併記され、拝殿扁額も併記となっています。
・本殿は別で、こちらの本殿も県指定文化財に指定されています。
・この様な祭祀形態を配祀というか相殿というのかわかりませんが、本殿は分かれているので配祀なのかもしれません。
・「上之の雷電さま」と呼ばれ周辺住民の尊崇を集めています。利根川沿いのこのエリアはとくに雷が多く、随所で大雷神が祀られています。
・御朱印は、上之村神社境内授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:大雷神社 直書(筆書)

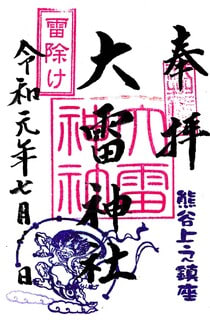
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4 へつづきます。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
【旧記事】■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPしています。
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔以下は旧記事へのリンクです〕
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1からのつづきです。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
■ (西島)瀧宮神社
公式Web
深谷市西島5-6-1
御祭神:天照大神、豊受大神、彦火火出見命
旧社格:深谷城裏鬼門守護神、旧西島村(内横町仲町)鎮守
元別当:瀧宮山 歓喜院 正覚寺(深谷市深谷町)
授与所:境内社務所
・社伝によると、この地に湧き出る湧水を神として祀り「瀧の宮大明神」と号したのが創祀といいます。
・康正二年(1456年)、上杉氏により深谷城が築かれると、西南に位置する当社を坤門(裏鬼門)の守護神として崇敬し、領国安寧を祈願しました。
・昭和27年(1952年)には深谷宿の守り神・市神様として住民の尊崇篤かった「三社天王」を深谷八坂神社として境内に御遷座。例祭の御輿渡御は「深谷のぎおん」として広く知られています。
・深谷を代表する神社で、御朱印はおおむね社務所にていただけるようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:瀧宮神社 直書(筆書)

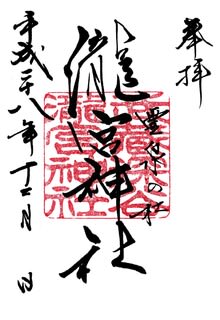
・当社は深谷駅南口のすぐそばに鎮座します。深谷駅の駅舎は、大正時代に竣工の東京駅・丸の内口駅舎が深谷の日本煉瓦製造の煉瓦を使用したことに因み、赤レンガ造をモチーフとしたデザインとなっており、深谷市内のみどころのひとつです。

■ 伊勢之宮神社
深谷市西大沼300
御祭神:天照大神、豊受大神
旧社格:- 氏子区域:東大沼、西大沼、栄町、錦町の四か町
元別当:西福院
授与所:(西島)瀧宮神社社務所
・創建は明らかでありませんが、『風土記稿』には「伊勢内宮 村民持、伊勢外宮 西福院持」とあることからかつては二社で、明治初期に一社になったとみられています。
・『埼玉の神社』によると、当地の東部に「田谷」という地があり、これは「旅尾」(御師がお祓大麻を旦那に配るために構えた宿舎)からの転訛とみられ、田谷周辺の村々も伊勢神宮を勧請していることから、当社も伊勢神宮の御師が創建に係わったものとみられています。
・御朱印は(西島)瀧宮神社社務所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊勢之宮神社 直書(筆書)

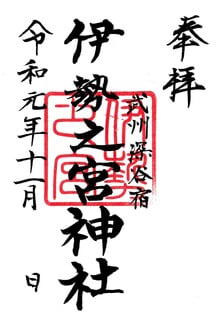
■ 深谷山 永明寺 高台院
深谷市田谷308
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
・上杉氏の家人、高橋永明が草創。永禄四年(1561年)、深谷城三代目城主上杉憲賢の菩提を弔うため、室の高泰姫によって再興されたと伝わる古刹。
・所蔵の「北亭為直画朱描鎮西八郎為朝像」は市の文化財に指定されています。
・札所ではありませんが、ご住職ご在院時には御朱印を授与いただけるようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

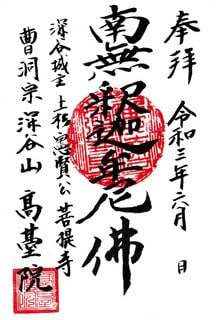
■ 永明稲荷神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市田谷308
御祭神:倉稲魂命、菅原道真公
旧社格:深谷城の戌亥の守護神、田谷地区鎮守
元別当:深谷山 高台院(高泰院) 永明寺(深谷市田谷)
授与所:楡山神社宮司様宅
・康正二年(1456年)、深谷城主上杉氏五代房憲(ないし家臣高橋永明)が築城時に、城の戌亥の守護として創祀と伝わります。
・上杉氏が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、一仏とは瑠璃光寺の寅薬師、三社とは末広稲荷(稲荷町)・永明稲荷・智方明神(本住町)をさすようです。
・明治45年(1912年)、稲荷町の稲荷神社に合祀されたものの社殿は残り、田谷地区の鎮守として独自に祭を催していることから合祀は書類上のものとされています。
・高台院所蔵の「狐開帳図絵馬(きつねかいちょうずえま)」(市指定文化財)は、もともとは永明稲荷神社に奉納されていたものです。
・高台院の奥ふかく、別当というより高台院の地主神的な位置にご鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:永明稲荷神社 直書(筆書)

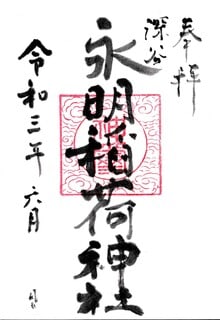
■ 延楽山 福壽院 金胎寺
深谷市本住町9-76
新義真言宗
御本尊:胎蔵界大日如来
司元別当:城内八幡宮・天満宮・管領稲荷社
・慶長九年(1604年)以前に、深谷城主上杉家の祈願寺として法印權大僧都日胤により開基されたという名刹。
・当時の深谷上杉家氏は湯殿山の信仰篤く、御本尊は湯殿山御分身の大日如来であったと伝わります。元禄十一年(1698年)、法印權大僧都快傳による中興開山の折に現在の御本尊大日如来を再鋳安置。
・別尊として奉安される不動明王は、明治22年(1889年)先師秋本一庵法印が下総国成田山より御分身を勧請され、深谷成田山とも称されます。
・札所ではありませんが名刹で、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 大日如来

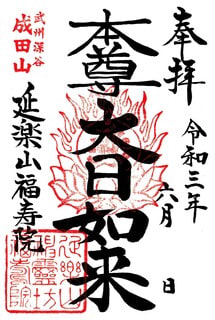
■ (稲荷町)稲荷神社(末広稲荷神社)
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市稲荷町3-2-58
御祭神:倉稲魂命
旧社格:村社、深谷城鬼門鎮護、旧末広村鎮守
元別当:東源寺・宝珠院
授与所:楡山神社宮司様宅
・社伝によると、上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、康正年間(1455-1456年)の城の鬼門守護として創祀とされます。
・「一仏三社」については康応年間(1389-1390)、深谷庁鼻和(こばなわ)に館を構えた上杉憲英が館の鎮護のために勧請という説もみられます。深谷城下の発展に伴い、稲荷町の鎮守として住民から厚く尊崇され今に至ります。
・維新後、無格社であった当社は田谷の稲荷神社(永明稲荷)を合祀し村社に列しましたが、この合祀は書類上のものとみられているようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:稲荷神社 直書(筆書)

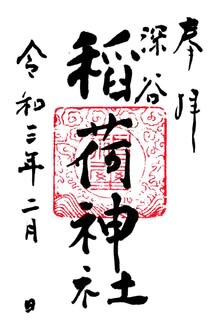
■ 深谷山 光明院 瑠璃光寺
公式Web
深谷市稲荷町北9-25
天台宗
御本尊:釈迦如来、元三大師
札所:関東九十一薬師霊場第39番、武蔵国十三佛霊場第12番、深谷七福神(大黒天/ハギの寺)
・寺伝によると、大同二年(807年)ないし承和二年(835年)、慈覚大師による開山・創建とされる名刹で、鎌倉時代にはすでに七堂伽藍を備えていたといいます。
・康正年間(1455-1456年)、当寺薬師堂の寅薬師を上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」の一仏、鬼門除けのお薬師様として信仰したことでも知られています。
・元和二年(1616年)徳川家康公逝去の後、家康公の遺骨を日光に奉遷する際に天海僧正が当寺で休憩、この縁から慶安二年(1649年)には寺領十石の御朱印状を受領しています。
・複数の現役霊場の札所で、御朱印は庫裡にて印判のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.関東九十一薬師霊場第39番 薬師如来

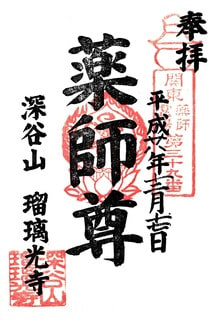
2.武蔵国十三佛霊場第12番 大日如来

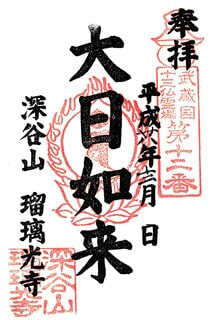
3.深谷七福神 大黒天

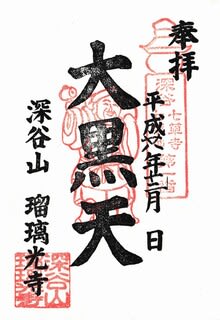
■ 楡山神社(にれやまじんじゃ)
公式Web
深谷市原郷336
御祭神:伊邪那美命
旧社格:県社、延喜式内社
元別当:東学院(本山派修験)・大乗院(本山派修験)・熊野山 能泉寺 正徳院(天台宗)
授与所:楡山神社宮司様宅
・五代孝昭天皇御代の御鎮座と伝わる古社で、延喜式の「武蔵国幡羅郡四座」の一社「楡山神社」に比定されています。
・幡羅郡の総鎮守、幡羅郡總社といわれ、幡羅大神とも称されました。
・旧原ノ郷村は平安時代中期の武将・幡羅太郎道宗が拠った地で、当社南西に史跡「幡羅太郎館趾」があります。
・康平年間(1058-1065年)、源義家公奥州征伐の際、幡羅太郎道宗の長男の成田助高は当社にて戦勝を祈願したといい、後に行田の忍城主となった成田家代々の崇敬篤かったといいます。
・中世には熊野信仰が入り、熊野社、熊野三社大権現などと号したようですが、村民は一貫して楡山神社と称して崇めたといいます。
・社号の由来は一帯に楡の木が多かったことにより、境内の楡の古木は御神木と崇められ、県文化財(天然記念物)に指定されています。
・原郷内の神社を多く境内社としています。また、市内各社の本務社を務められ、複数の御朱印を授与されています。
・御朱印はすこし離れた宮司様宅で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:楡山神社 直書(筆書)

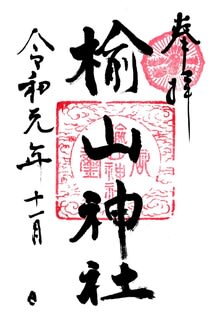
■ (原之郷)愛宕神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市原郷2031
御祭神:火産霊神(ほむすびのみこと)
旧社格:旧原ノ郷村木ノ本の鎮守
元別当:寶珠院 大沼坊(深谷村)
授与所:楡山神社宮司様宅
・旧中山道に面して広大な社地を有していたという愛宕神社で、火防の神様として信仰を集めたといいます。
・境内社として三峯社が鎮座します。
・御朱印は、楡山神社宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:武州原之郷 愛宕神社 直書(筆書)

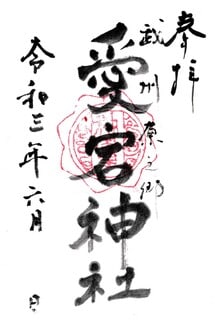
■ 熊野大神社
深谷市東方1709-2
御祭神:伊邪那美命、速玉男命、事解男命
旧社格:郷社、旧東方村鎮守
元別当:熊野山 弥勒院(深谷市東方)
授与所:境内社務所
・延長五年(927年)、この地に枇杷の木を棟木として小祠を建て、上野国碓氷郡熊野本宮より奉遷したのが創建という社伝があり、延喜式神名帳の「白髪神社」(小社)に比定する説もみられます。
・天文年間(1532-1555年)、深谷上杉氏の宿老、皿沼城主岡谷加賀守清英が篤く崇敬し社領を寄進、天正年間(1573-1592年)には深谷上杉氏の家臣秋元景朝・長朝父子が社殿造営とも伝わります。
・江戸期には東方城主として入った松平丹波守康長が崇敬。東方村の鎮守として祀られ、明治42年に地内の五社を合祀、大正13年には郷社に列格しています。
・天正年間 (1573-1592年)の建立と伝えられる本殿は、三間社、入母屋造銅瓦葺の総欅造で、市の文化財(建造物)に指定されています。
・御朱印は、隣接の宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊野大神社 直書(筆書)

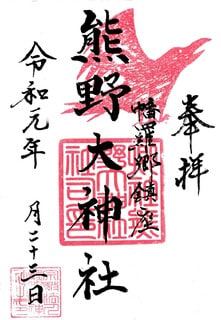
■ 東方山 全久院
深谷市東方2902-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:深谷七福神(寿老人/フジバカマの寺)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第50番(旧 風張寺)
・江戸時代、当地の領主であった松平丹後守康長が祖先戸田弾正左衛門宗光追福のため、三河国牛窪の全久院の寺号を写して草創と伝わります。
・名刹にふさわしく、「紙本着色不動明王三尊像」(室町末期作)、「地蔵尊立像」(室町以前作)などは市の文化財に指定されています。
・深谷七福神の寿老人の札所で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 寿老人
※深谷七福神のみの授与

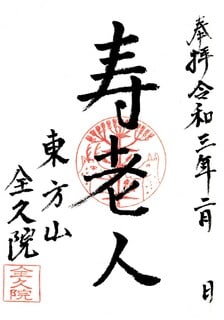
■ 吉祥山 丈六院 安楽寺
熊谷市西別府2044
臨済宗円覚寺派
御本尊:釈迦如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第22番
・養老年間(717-24年)、藤原不比等淡海による草創と伝わる古刹。
・草創時に丈六の釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来の三尊を安置、後に武蔵国国司(藤原)式部大輔任助の二男別府左衛門行隆が、六阿弥陀を加えて九品の本尊とし、その子孫の別府甲斐守頼重が再興したといいます。
・繁室玄茂和尚(文和二年(1353年)寂)の開山という伝もあります。
・『新編武蔵風土記稿』および『埼玉の神社(西別府湯殿神社の項)』によると、康暦二年(1380年)九月、乱を起こした下野守護小山義政征討のため足利左馬頭氏満が鎌倉を出立。別府の地に陣を構えて小山攻めの軍勢を催促するとともに丈六(院)に参詣念誦したところ、小山義政みずから当所に赴き降参したことは、ひとえに丈六の尊像の感應によるものと称揚されました。
・御朱印は庫裡にて授与いただけましたが、新型コロナ禍のなかでは原則授与を中止されているようです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第22番 九品佛
※御本尊の御朱印不授与


■ 福聚山 香林寺
熊谷市東別府799
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第23番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第61番、第6番(旧福泉寺・薬師如来)
・別府小太郎清重が父入道義重(法名香林寺義重道薫居士)追福のため建立と(開基は義重)いう寺伝があり、集福寺第二世要岩(弘治三年(1557年)十六日示寂)が開山という伝もあります。
・別府小太郎清重は平家物語に登場し、平家物語は延慶二年(1309年)以前に成立とみられているので、開基開山の年代が合いません。
・これについては、『新編武蔵風土記稿』も「清重の開基といはんには年代相あたらず、若くは天文(1532年-1555年)の頃、別府尾張守長清など、己が遠祖義重のために造立せしにや、さあれば開山開基の年代合へり」と指摘しています。
・香林寺は(東)別府城の城址とされる東別府神社のすぐそばにあり、香林寺を別府氏館跡とする史料もあるようです。
・別府城跡(県指定記念物(史跡))の掲示には「成田助高の二男次郎行高が別府に住み、その子太郎能幸は東別府に、二郎行助が西別府に数代相対して領知」とあるので、小太郎清重は能幸の流れの東別府氏とみられ、同掲示には「太郎能幸に初まった東別府家は、それから十一代目の尾張守長清まで続いたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の北条氏攻略に際し、敗軍側についたため家禄を失ってしまった。」ともあります。
・御朱印は、庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

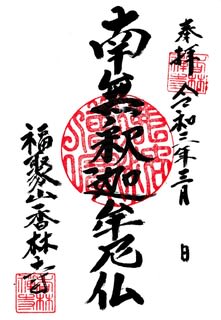
■ 瑠璃光山 薬師院 玉井寺
熊谷市玉井1888
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
司別当:玉井大神社:境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)
・埼玉県神社庁『埼玉の神社』の「玉井大神社」の項に、「玉井」および「玉井寺」についての記載もあるので抜粋引用します。
・桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧賢璟は、巡視の足を東国までのばしました。
・賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。
・この井戸「玉の井」は玉井寺の境内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。
・『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。
・玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。
・「玉の井」の脇には市指定記念物(史跡)の「玉井四朗の墓」があり、玉井寺は玉井四朗の屋敷跡と伝わります。
・玉井氏は、成田助高の子助実が玉井四郎と称したのをはじめとし、『保元物語』の白河殿夜討ちの条には、源義朝公に従った玉井四郎が軍功を立てたことが記されています。また、『郡村誌』には「往古元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な札所の御朱印を授与されています。
・布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番 阿弥陀如来

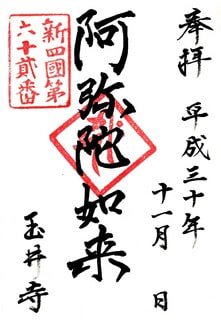
2.熊谷七福神 布袋尊


■ 開敷山 観音院 妙音寺
熊谷市上奈良702
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第24番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
・『新編武蔵風土記稿』によると、開山の頼尊は奈良三郎と伝わり、成田大夫助高の三男奈良三郎高長とみなしています。高長は入道して頼尊と号し当寺を開山されたとの由。
・境内の「奈良三郎の墓」は市指定記念物(史跡)に指定されています。
・如意輪観世音菩薩は行基の作と伝わります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第33番の吉祥寺(熊谷市原島682)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第24番 聖観世音菩薩


■ 増田山 観音堂
熊谷市下増田841
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第20番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
〔拝受御朱印〕
・第19番下増田観音寺からほど近く、県道263号弁財深谷線沿いにあるのでわかりやすいです。
・寺号標は「増田山観音堂」、門柱には「旧宝蔵院」と「牛頭天王分社」、観音堂扁額には「十一面観世音」「牛頭天王宮」。
・忍観音二十番霊場の立派な札所碑。宝形造の端正な観音堂には真如親王様のお大師さまが描かれた幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番の札所板も掲げられ、霊場札所の趣きがあります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第19番の下増田観音寺(熊谷市下増田866)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第20番 十一面観世音菩薩


■ 大悲山 慈眼院 観音寺
熊谷市下増田866
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第19番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第69番
・忍秩父三十四観音霊場には「観音寺」「観音堂」と号する札所がじつに5つ(6番行田市持田、10番上中条、11番下奈良、19番下増田、20番下増田(観音堂)、26番玉井(廃寺))もあり、場所が近いこともあって混乱します。
・こちらは第19番下増田の観音寺で、第20番下増田観音堂も護持されています。
・御朱印は忍秩父第19番、第20番(増田山観音堂)を拝受しました。本堂にあげていただき、たいへんご親切なご対応をいただきました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第19番 聖観世音菩薩


■ 寛平山 泉光寺
深谷市上敷免473
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀三尊
司別当:諏訪社(旧上鋪免村鎮守)
札所:深谷七福神(恵比寿天/オミナエシの寺)
・石碑によると、平安時代の寛平九年(897年)、良忍上人による開基。『新編武蔵風土記稿』には寛平山 稲荷坊 来迎院と号していたとあります。
・弘法大師とのゆかりがふかく、別尊の薬師如来はお大師さまのご開眼と伝わり、境内には三鈷の松があります。
・市指定文化財の「紙本着色愛宕大権現像」を所蔵されており、以前は愛宕信仰が入っていたのかもしれません。
・立派な鐘楼門、端正な入母屋造流れ向拝の本堂には御本尊の阿弥陀三尊が御座。本堂向かって右手の堂宇には恵比寿天が御座されています。
・深谷七福神の恵比寿天で女郎花(オミナエシ)の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 阿弥陀三尊


2.深谷七福神 恵比寿天


■ 瑠璃山 正伝院
深谷市高島161
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:深谷七福神(毘沙門天/クズの寺)
・弘仁年間(810-824年)、坂上田村麻呂の奥州征伐の際、小野岑守とその子小野篁((おののたかむら)が随行。この地にて篁が薬師如来の尊像を彫刻し、本尊として安置して開基と伝わる古刹です。
・寺宝の「釈迦涅槃図」(市指定文化財)は、幕末の文人、伊丹渓斎(いたみけいさい)の筆によるものです。
・深谷七福神の毘沙門天の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 毘沙門天


■ 蓮沼山 地蔵院 惣持寺
公式Web
深谷市蓮沼463
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番、深谷七福神(弁財天/オバナの寺)
・境内の縁起碑に、「當寺墓地の五輪塔(元禄八年(1696年)建立)「當寺廿傳慶基之表」に「夫武蔵國幡羅郡蓮沼山惣持寺者行基菩薩之草創年数978宗澄和尚之中興云々略」と刻記されていることから、草創は奈良時代初期の養老二年(718年)行基菩薩によって創建され、後弘安年間(1278-1288年)顕盛(勅号宗澄)により再興された、深谷市内最古の名刹である。」とあります。
・地蔵堂の御本尊は行基作と伝わりましたが文化四年(1807年)の火災で消失、現在の地蔵尊は”露天の雨乞い地蔵”として村人の信仰を集めているそうです。
・深谷七福神(弁財天)と幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所で、尊格揮毫は「弁財天」、主印は金剛界大日如来の種子「バン」の御寶印と弁財天の持物「琵琶」の印、「新四国第四十二番」の札所印があり、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番と深谷七福神(弁財天)を兼ねたような内容の御朱印となっています。
・新型コロナ禍中は御朱印不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番/深谷七福神(弁財天) 大日如来/弁財天

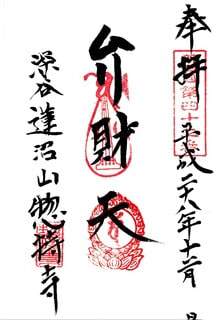
■ 能満山 定禅院 能護寺(あじさい寺)
熊谷市Web
熊谷市永井太田1141
高野山真言宗
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第25番
・天平十五年(743年)に国家安穏・万民豊楽と五穀豊穣祈願のため行基上人が開山し、後に弘法大師空海が再建され真言密教の道場として整えられたと伝わります。
・「妻沼のあじさい寺」として知られ、毎年6月には多くの参詣者を迎えます。
・現本堂は文化十一年(1814年)の再建で、内陣に大日如来、外陣に阿弥陀如来を安置した堂内の格天井(十六羅漢図)には、金井烏洲・岩崎榮益・樋口春翠などの彩色の花鳥獣が描かれています。
・虚空蔵堂には虚空蔵菩薩が祀られ、男女13歳厄除け祈願(十三参り)の寺として信仰を集めています。
・鐘楼の鐘は、元禄十四年(1701年)、諸八郎兵衛藤原正綱による鋳造で、乳の間に百字真言の梵字が鋳込まれているもの。市の文化財に指定されています。
・メジャー霊場「東国花の寺百ヶ寺霊場」の札所で、御朱印は庫裡にて拝受。御朱印尊格は「十三参り」の虚空蔵尊となっています。
〔拝受御朱印〕
1.東国花の寺百ヶ寺霊場第25番 虚空蔵菩薩


■ 寶珠山 光明禅寺 玉洞院
熊谷市妻沼2404
臨済宗円覚寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第16番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第86番
・開基は月峯常圓居士、開山を養嚴宗胡(文明九年(1477年)寂)とする曹洞宗寺院。
・『新編武蔵風土記稿』には鐘樓の銘文に「淀城主石川主殿頭憲之妻女、及び次男義孝、武運長久の誓の為に元禄三年(1690年)寄附する由を鐫す」とあります。
・石川憲之(1634-1707年)は、石川数正の叔父、石川家成の家を継いだ大久保忠隣の次男、石川忠総の孫にあたり、近江膳所藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家四代、山城淀藩初代藩主を務めました。憲之の妻女(正室)は羽林家の公家、梅園実清(1609-1662年)の息女で、その子石川義孝は山城淀藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家五代。
・妻女梅園氏、石川義孝ともに妻沼とのゆかりは確認できず、どうして当寺にこのような鐘銘が残っているのかも不明です。
御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受しました。幡羅郡新四国霊場については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第16番 聖観世音菩薩


■ 祥興山 真徳院 瑞林寺
熊谷市妻沼2485
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番
・『新編武蔵風土記稿』および境内記念碑によると、建久年間(1190-1199年)に天台宗寺院として創建。慶長六年(1598年)矢場村惠林寺第五世大庵文恕により曹洞宗に改められて開山、開基は大河内孫十郎政信と伝わります。
・大河内氏は摂津源氏源頼政流とされ、三河の吉良氏の家老の家柄でしたが、天正十五年(1587年)大河内秀綱の二男正綱が家康の命で長沢松平家庶流の松平正次の養子となり、子孫は大河内松平家と称します。武蔵野の名刹、平林寺は大河内大名家の墓所として知られています。
・こちらのWeb(大河内松平氏の研究)に「吉良家を去った大河内秀綱後は伊奈氏の配下で代官として活動している。『伊奈忠次文書集成』の中に、大河内秀綱に宛てた慶長年間の文書がある。文禄三年(1594年)、徳川家康が江戸から上州新田に向かうため、通り道にあたる妻沼の名主に人馬継立を命じる文書が大河内孫十郎(久綱)の名で発給されている。このころ既に久綱が代官だったことが知られる。」とあり、孫十郎(久綱)と孫十郎政信が同一人物であるかはわかりませんが、江戸時代初期に大河内氏が妻沼の地を代官差配していたことがうかがわれます。
・本堂向かって右手前の日限地蔵堂には赤い幟がならび、信仰を集めている感じがします。
・墓所には江戸時代の俳匠・有磯庵五渡(ありそあんごと)三代の墓があります。江戸時代の妻沼は芭蕉ゆかりの俳句のメッカで、各地の俳人たちは妻沼聖天の参詣と併せて妻沼の俳人と交流し、これを「妻沼詣」と称したと伝わります。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番の札所で、門前に御朱印のサンプルが掲示されています。庫裡にて「新四国第七十三番」の札所印入りの御朱印を拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番 釈迦牟尼佛


■ 聖天山 長楽寺 歓喜院(妻沼聖天山)
公式Web
熊谷市妻沼1627
高野山真言宗
御本尊:大聖歓喜天
札所:関東八十八箇所第88番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番、武州路十二支霊場 午(勢至菩薩)、東国花の寺百ヶ寺霊場第26番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番、第76番(旧宝蔵院)
・「日本三大聖天」のひとつ、「妻沼の聖天様」と呼ばれる関東を代表する名刹で、複数の霊場札所を務められます。
・名刹だけに記事ネタが多いですが、こちらでは簡単なご縁起と御朱印関連に絞ってご案内します。
・平安時代末期の武将斎藤別当実盛公(長井別当)が治承三年(1179年)、守り本尊の大聖歓喜天を祀る聖天宮を建立し、長井庄の総鎮守としたのが始まりとされます。
・実盛公は、源平争乱期に源義朝公、木曾義仲公、平維盛公と複雑な関係をもち、寿永二年(1183年)、平維盛公らと木曾義仲公追討のため出陣した加賀国篠原の戦いで奮戦し、ついに討ち取られました。この篠原の戦いの顛末は『平家物語』巻第七「実盛最期」として一章を成し、東国武士の機微を語るものとして広く知られています。
・建久八年(1197年)、良応僧都(実盛公の次男である実長(宗光))が聖天宮の別当(本坊)として歓喜院長楽寺を建立し、十一面観世音菩薩を本尊としたといいます。
・国宝の本殿は絢爛たる廟型式権現造で、「埼玉日光」ともいわれます。
・御朱印は境内授与所にていただけます。5つの札所を確認しており、うち4つを拝受しています。残りの幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番については不明です。
なお、札所御朱印ではない御本尊・大聖歓喜天の御朱印も授与されている模様です。
〔拝受御朱印〕
1.東国花の寺百ヶ寺霊場第26番 大聖歓喜天
札所本尊は御本尊。本殿が札所とみられます。


2.関東八十八箇所第88番 大聖歓喜天
本殿向かって左の大師堂が札所(第88番結願所)となっています。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所もこちらになります。


3.武州路十二支霊場 午 勢至菩薩
本殿向かって左の大師堂のお大師さまの右手(礼拝者からは左手)に御座す立像の勢至菩薩が札所本尊と思われます。大師堂内に単尊で勢至菩薩が安置される例は少ないと思われます。
当地は二十三夜月待講がさかんで、当山山内にも二十三夜塔が建立されています。そちらとの関連もあるのかもしれません。


4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番 聖観世音菩薩
中門そばの護摩堂の手前に御座す露仏の観音様が札所本尊です。


--------------------------------------
ここからは、いよいよ忍秩父観音霊場、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の核心部に入っていきます。小規模で無住の寺も多く、御朱印拝受難易度は高いです。
■ 大悲山 薬師院 観音寺
公式Web
熊谷市八木田198
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第18番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第44番、第67番(薬師堂)
・公式Webに、慶長年間(1596-1615年)のはじめ、澄海上人による開基とされ、徳川幕府よりご朱印を賜り、とあります。
・『新編武蔵風土記稿』には「大田村能護寺末大悲山薬師院ト号ス 慶安(1648-1652年)中寺領六石五斗ノ御朱印ヲ賜フ 開山澄海寂年知レス 本尊千手観音ヲ安ス」とあります。
村内の薬師堂と阿弥陀堂一宇も護持していたようです。
・忍秩父三十四観音霊場の観音堂は本堂とは別で、札所本尊は十一面観世音菩薩です。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていない模様です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第18番 十一面観世音菩薩


■ 禅源山 長井寺
熊谷市弥藤吾1979
臨済宗円覚寺派
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第17番
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 上野國那波郡矢場村泉福寺末 禅源山ト號ス 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・その他の由来などは不明です。
・現況は無住と思われ、御朱印は別途お願いし郵送いただきましたが、これはイレギュラー対応で原則不授与かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第17番 釈迦如来


■ 王子山 観清寺
熊谷市弥藤吾574-1
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第3番
・こちらは幡羅郡新四国霊場のみの札所なので、とくに情報が少ないです。
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 下奈良村集福寺末王子山ト號ス(中略)開山ハ本寺(集福寺)二世要岩春津弘治三年(1557年)示寂 本尊ハ釋迦文殊普賢ヲ安ス」とあります。
・予想以上の大寺で境内もよく整っています。御朱印は庫裡にて授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛


■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3へつづきます。
【 BGM 】
■ 夏影~Airness~ - 茶太ver
■ 春風 - Rihwa(カバー)
■ 夢暦 - 川江美奈子
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔以下は旧記事へのリンクです〕
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1からのつづきです。
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
■ (西島)瀧宮神社
公式Web
深谷市西島5-6-1
御祭神:天照大神、豊受大神、彦火火出見命
旧社格:深谷城裏鬼門守護神、旧西島村(内横町仲町)鎮守
元別当:瀧宮山 歓喜院 正覚寺(深谷市深谷町)
授与所:境内社務所
・社伝によると、この地に湧き出る湧水を神として祀り「瀧の宮大明神」と号したのが創祀といいます。
・康正二年(1456年)、上杉氏により深谷城が築かれると、西南に位置する当社を坤門(裏鬼門)の守護神として崇敬し、領国安寧を祈願しました。
・昭和27年(1952年)には深谷宿の守り神・市神様として住民の尊崇篤かった「三社天王」を深谷八坂神社として境内に御遷座。例祭の御輿渡御は「深谷のぎおん」として広く知られています。
・深谷を代表する神社で、御朱印はおおむね社務所にていただけるようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:瀧宮神社 直書(筆書)

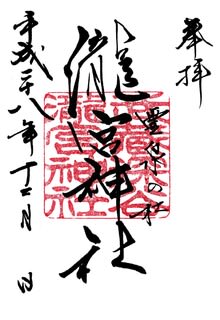
・当社は深谷駅南口のすぐそばに鎮座します。深谷駅の駅舎は、大正時代に竣工の東京駅・丸の内口駅舎が深谷の日本煉瓦製造の煉瓦を使用したことに因み、赤レンガ造をモチーフとしたデザインとなっており、深谷市内のみどころのひとつです。

■ 伊勢之宮神社
深谷市西大沼300
御祭神:天照大神、豊受大神
旧社格:- 氏子区域:東大沼、西大沼、栄町、錦町の四か町
元別当:西福院
授与所:(西島)瀧宮神社社務所
・創建は明らかでありませんが、『風土記稿』には「伊勢内宮 村民持、伊勢外宮 西福院持」とあることからかつては二社で、明治初期に一社になったとみられています。
・『埼玉の神社』によると、当地の東部に「田谷」という地があり、これは「旅尾」(御師がお祓大麻を旦那に配るために構えた宿舎)からの転訛とみられ、田谷周辺の村々も伊勢神宮を勧請していることから、当社も伊勢神宮の御師が創建に係わったものとみられています。
・御朱印は(西島)瀧宮神社社務所にて授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:伊勢之宮神社 直書(筆書)

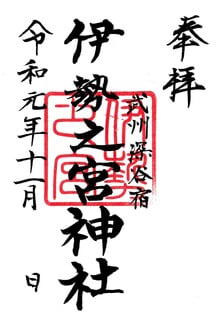
■ 深谷山 永明寺 高台院
深谷市田谷308
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
・上杉氏の家人、高橋永明が草創。永禄四年(1561年)、深谷城三代目城主上杉憲賢の菩提を弔うため、室の高泰姫によって再興されたと伝わる古刹。
・所蔵の「北亭為直画朱描鎮西八郎為朝像」は市の文化財に指定されています。
・札所ではありませんが、ご住職ご在院時には御朱印を授与いただけるようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

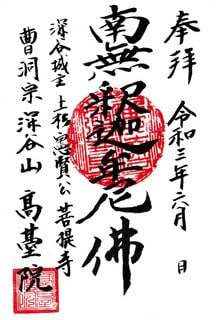
■ 永明稲荷神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市田谷308
御祭神:倉稲魂命、菅原道真公
旧社格:深谷城の戌亥の守護神、田谷地区鎮守
元別当:深谷山 高台院(高泰院) 永明寺(深谷市田谷)
授与所:楡山神社宮司様宅
・康正二年(1456年)、深谷城主上杉氏五代房憲(ないし家臣高橋永明)が築城時に、城の戌亥の守護として創祀と伝わります。
・上杉氏が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、一仏とは瑠璃光寺の寅薬師、三社とは末広稲荷(稲荷町)・永明稲荷・智方明神(本住町)をさすようです。
・明治45年(1912年)、稲荷町の稲荷神社に合祀されたものの社殿は残り、田谷地区の鎮守として独自に祭を催していることから合祀は書類上のものとされています。
・高台院所蔵の「狐開帳図絵馬(きつねかいちょうずえま)」(市指定文化財)は、もともとは永明稲荷神社に奉納されていたものです。
・高台院の奥ふかく、別当というより高台院の地主神的な位置にご鎮座されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:永明稲荷神社 直書(筆書)

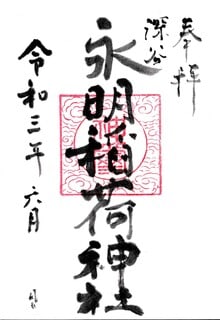
■ 延楽山 福壽院 金胎寺
深谷市本住町9-76
新義真言宗
御本尊:胎蔵界大日如来
司元別当:城内八幡宮・天満宮・管領稲荷社
・慶長九年(1604年)以前に、深谷城主上杉家の祈願寺として法印權大僧都日胤により開基されたという名刹。
・当時の深谷上杉家氏は湯殿山の信仰篤く、御本尊は湯殿山御分身の大日如来であったと伝わります。元禄十一年(1698年)、法印權大僧都快傳による中興開山の折に現在の御本尊大日如来を再鋳安置。
・別尊として奉安される不動明王は、明治22年(1889年)先師秋本一庵法印が下総国成田山より御分身を勧請され、深谷成田山とも称されます。
・札所ではありませんが名刹で、御朱印も快く授与いただけたのでご紹介します。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 大日如来

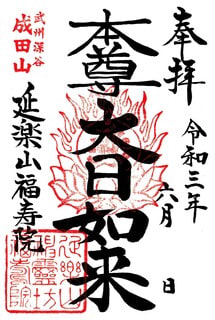
■ (稲荷町)稲荷神社(末広稲荷神社)
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市稲荷町3-2-58
御祭神:倉稲魂命
旧社格:村社、深谷城鬼門鎮護、旧末広村鎮守
元別当:東源寺・宝珠院
授与所:楡山神社宮司様宅
・社伝によると、上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」のひとつとされ、康正年間(1455-1456年)の城の鬼門守護として創祀とされます。
・「一仏三社」については康応年間(1389-1390)、深谷庁鼻和(こばなわ)に館を構えた上杉憲英が館の鎮護のために勧請という説もみられます。深谷城下の発展に伴い、稲荷町の鎮守として住民から厚く尊崇され今に至ります。
・維新後、無格社であった当社は田谷の稲荷神社(永明稲荷)を合祀し村社に列しましたが、この合祀は書類上のものとみられているようです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:稲荷神社 直書(筆書)

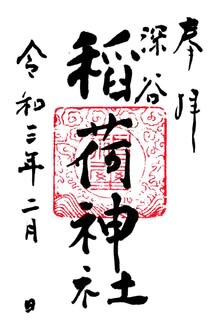
■ 深谷山 光明院 瑠璃光寺
公式Web
深谷市稲荷町北9-25
天台宗
御本尊:釈迦如来、元三大師
札所:関東九十一薬師霊場第39番、武蔵国十三佛霊場第12番、深谷七福神(大黒天/ハギの寺)
・寺伝によると、大同二年(807年)ないし承和二年(835年)、慈覚大師による開山・創建とされる名刹で、鎌倉時代にはすでに七堂伽藍を備えていたといいます。
・康正年間(1455-1456年)、当寺薬師堂の寅薬師を上杉房憲が深谷城の守護として祀った「一仏三社」の一仏、鬼門除けのお薬師様として信仰したことでも知られています。
・元和二年(1616年)徳川家康公逝去の後、家康公の遺骨を日光に奉遷する際に天海僧正が当寺で休憩、この縁から慶安二年(1649年)には寺領十石の御朱印状を受領しています。
・複数の現役霊場の札所で、御朱印は庫裡にて印判のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.関東九十一薬師霊場第39番 薬師如来

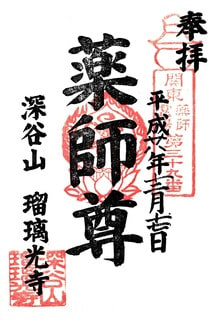
2.武蔵国十三佛霊場第12番 大日如来

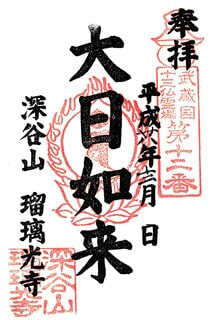
3.深谷七福神 大黒天

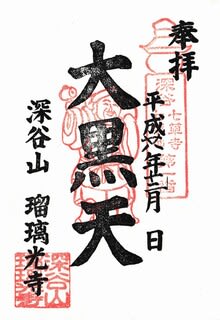
■ 楡山神社(にれやまじんじゃ)
公式Web
深谷市原郷336
御祭神:伊邪那美命
旧社格:県社、延喜式内社
元別当:東学院(本山派修験)・大乗院(本山派修験)・熊野山 能泉寺 正徳院(天台宗)
授与所:楡山神社宮司様宅
・五代孝昭天皇御代の御鎮座と伝わる古社で、延喜式の「武蔵国幡羅郡四座」の一社「楡山神社」に比定されています。
・幡羅郡の総鎮守、幡羅郡總社といわれ、幡羅大神とも称されました。
・旧原ノ郷村は平安時代中期の武将・幡羅太郎道宗が拠った地で、当社南西に史跡「幡羅太郎館趾」があります。
・康平年間(1058-1065年)、源義家公奥州征伐の際、幡羅太郎道宗の長男の成田助高は当社にて戦勝を祈願したといい、後に行田の忍城主となった成田家代々の崇敬篤かったといいます。
・中世には熊野信仰が入り、熊野社、熊野三社大権現などと号したようですが、村民は一貫して楡山神社と称して崇めたといいます。
・社号の由来は一帯に楡の木が多かったことにより、境内の楡の古木は御神木と崇められ、県文化財(天然記念物)に指定されています。
・原郷内の神社を多く境内社としています。また、市内各社の本務社を務められ、複数の御朱印を授与されています。
・御朱印はすこし離れた宮司様宅で拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:楡山神社 直書(筆書)

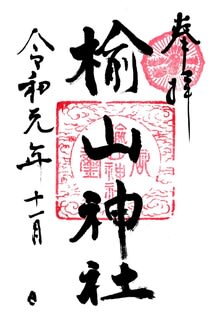
■ (原之郷)愛宕神社
楡山神社ホームページ掲載の由緒
深谷市原郷2031
御祭神:火産霊神(ほむすびのみこと)
旧社格:旧原ノ郷村木ノ本の鎮守
元別当:寶珠院 大沼坊(深谷村)
授与所:楡山神社宮司様宅
・旧中山道に面して広大な社地を有していたという愛宕神社で、火防の神様として信仰を集めたといいます。
・境内社として三峯社が鎮座します。
・御朱印は、楡山神社宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:武州原之郷 愛宕神社 直書(筆書)

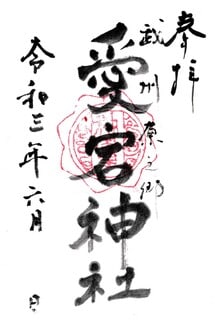
■ 熊野大神社
深谷市東方1709-2
御祭神:伊邪那美命、速玉男命、事解男命
旧社格:郷社、旧東方村鎮守
元別当:熊野山 弥勒院(深谷市東方)
授与所:境内社務所
・延長五年(927年)、この地に枇杷の木を棟木として小祠を建て、上野国碓氷郡熊野本宮より奉遷したのが創建という社伝があり、延喜式神名帳の「白髪神社」(小社)に比定する説もみられます。
・天文年間(1532-1555年)、深谷上杉氏の宿老、皿沼城主岡谷加賀守清英が篤く崇敬し社領を寄進、天正年間(1573-1592年)には深谷上杉氏の家臣秋元景朝・長朝父子が社殿造営とも伝わります。
・江戸期には東方城主として入った松平丹波守康長が崇敬。東方村の鎮守として祀られ、明治42年に地内の五社を合祀、大正13年には郷社に列格しています。
・天正年間 (1573-1592年)の建立と伝えられる本殿は、三間社、入母屋造銅瓦葺の総欅造で、市の文化財(建造物)に指定されています。
・御朱印は、隣接の宮司様宅にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:熊野大神社 直書(筆書)

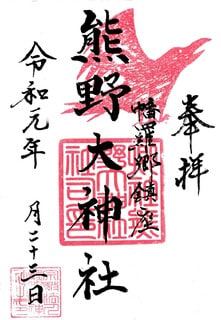
■ 東方山 全久院
深谷市東方2902-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:深谷七福神(寿老人/フジバカマの寺)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第50番(旧 風張寺)
・江戸時代、当地の領主であった松平丹後守康長が祖先戸田弾正左衛門宗光追福のため、三河国牛窪の全久院の寺号を写して草創と伝わります。
・名刹にふさわしく、「紙本着色不動明王三尊像」(室町末期作)、「地蔵尊立像」(室町以前作)などは市の文化財に指定されています。
・深谷七福神の寿老人の札所で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 寿老人
※深谷七福神のみの授与

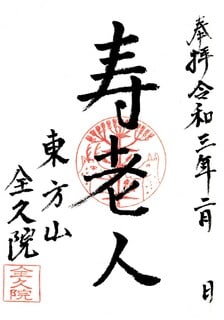
■ 吉祥山 丈六院 安楽寺
熊谷市西別府2044
臨済宗円覚寺派
御本尊:釈迦如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第22番
・養老年間(717-24年)、藤原不比等淡海による草創と伝わる古刹。
・草創時に丈六の釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来の三尊を安置、後に武蔵国国司(藤原)式部大輔任助の二男別府左衛門行隆が、六阿弥陀を加えて九品の本尊とし、その子孫の別府甲斐守頼重が再興したといいます。
・繁室玄茂和尚(文和二年(1353年)寂)の開山という伝もあります。
・『新編武蔵風土記稿』および『埼玉の神社(西別府湯殿神社の項)』によると、康暦二年(1380年)九月、乱を起こした下野守護小山義政征討のため足利左馬頭氏満が鎌倉を出立。別府の地に陣を構えて小山攻めの軍勢を催促するとともに丈六(院)に参詣念誦したところ、小山義政みずから当所に赴き降参したことは、ひとえに丈六の尊像の感應によるものと称揚されました。
・御朱印は庫裡にて授与いただけましたが、新型コロナ禍のなかでは原則授与を中止されているようです。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第22番 九品佛
※御本尊の御朱印不授与


■ 福聚山 香林寺
熊谷市東別府799
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:忍秩父三十四観音霊場第23番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第61番、第6番(旧福泉寺・薬師如来)
・別府小太郎清重が父入道義重(法名香林寺義重道薫居士)追福のため建立と(開基は義重)いう寺伝があり、集福寺第二世要岩(弘治三年(1557年)十六日示寂)が開山という伝もあります。
・別府小太郎清重は平家物語に登場し、平家物語は延慶二年(1309年)以前に成立とみられているので、開基開山の年代が合いません。
・これについては、『新編武蔵風土記稿』も「清重の開基といはんには年代相あたらず、若くは天文(1532年-1555年)の頃、別府尾張守長清など、己が遠祖義重のために造立せしにや、さあれば開山開基の年代合へり」と指摘しています。
・香林寺は(東)別府城の城址とされる東別府神社のすぐそばにあり、香林寺を別府氏館跡とする史料もあるようです。
・別府城跡(県指定記念物(史跡))の掲示には「成田助高の二男次郎行高が別府に住み、その子太郎能幸は東別府に、二郎行助が西別府に数代相対して領知」とあるので、小太郎清重は能幸の流れの東別府氏とみられ、同掲示には「太郎能幸に初まった東別府家は、それから十一代目の尾張守長清まで続いたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の北条氏攻略に際し、敗軍側についたため家禄を失ってしまった。」ともあります。
・御朱印は、庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

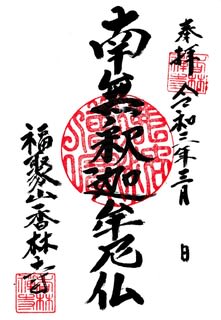
■ 瑠璃光山 薬師院 玉井寺
熊谷市玉井1888
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
司別当:玉井大神社:境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)
・埼玉県神社庁『埼玉の神社』の「玉井大神社」の項に、「玉井」および「玉井寺」についての記載もあるので抜粋引用します。
・桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧賢璟は、巡視の足を東国までのばしました。
・賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。
・この井戸「玉の井」は玉井寺の境内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。
・『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。
・玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。
・「玉の井」の脇には市指定記念物(史跡)の「玉井四朗の墓」があり、玉井寺は玉井四朗の屋敷跡と伝わります。
・玉井氏は、成田助高の子助実が玉井四郎と称したのをはじめとし、『保元物語』の白河殿夜討ちの条には、源義朝公に従った玉井四郎が軍功を立てたことが記されています。また、『郡村誌』には「往古元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な札所の御朱印を授与されています。
・布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番 阿弥陀如来

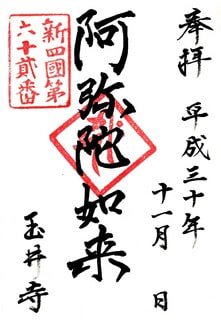
2.熊谷七福神 布袋尊


■ 開敷山 観音院 妙音寺
熊谷市上奈良702
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:忍秩父三十四観音霊場第24番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
・『新編武蔵風土記稿』によると、開山の頼尊は奈良三郎と伝わり、成田大夫助高の三男奈良三郎高長とみなしています。高長は入道して頼尊と号し当寺を開山されたとの由。
・境内の「奈良三郎の墓」は市指定記念物(史跡)に指定されています。
・如意輪観世音菩薩は行基の作と伝わります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第33番の吉祥寺(熊谷市原島682)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第24番 聖観世音菩薩


■ 増田山 観音堂
熊谷市下増田841
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第20番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番
〔拝受御朱印〕
・第19番下増田観音寺からほど近く、県道263号弁財深谷線沿いにあるのでわかりやすいです。
・寺号標は「増田山観音堂」、門柱には「旧宝蔵院」と「牛頭天王分社」、観音堂扁額には「十一面観世音」「牛頭天王宮」。
・忍観音二十番霊場の立派な札所碑。宝形造の端正な観音堂には真如親王様のお大師さまが描かれた幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番の札所板も掲げられ、霊場札所の趣きがあります。
・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第19番の下増田観音寺(熊谷市下増田866)にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第20番 十一面観世音菩薩


■ 大悲山 慈眼院 観音寺
熊谷市下増田866
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第19番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第69番
・忍秩父三十四観音霊場には「観音寺」「観音堂」と号する札所がじつに5つ(6番行田市持田、10番上中条、11番下奈良、19番下増田、20番下増田(観音堂)、26番玉井(廃寺))もあり、場所が近いこともあって混乱します。
・こちらは第19番下増田の観音寺で、第20番下増田観音堂も護持されています。
・御朱印は忍秩父第19番、第20番(増田山観音堂)を拝受しました。本堂にあげていただき、たいへんご親切なご対応をいただきました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第19番 聖観世音菩薩


■ 寛平山 泉光寺
深谷市上敷免473
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀三尊
司別当:諏訪社(旧上鋪免村鎮守)
札所:深谷七福神(恵比寿天/オミナエシの寺)
・石碑によると、平安時代の寛平九年(897年)、良忍上人による開基。『新編武蔵風土記稿』には寛平山 稲荷坊 来迎院と号していたとあります。
・弘法大師とのゆかりがふかく、別尊の薬師如来はお大師さまのご開眼と伝わり、境内には三鈷の松があります。
・市指定文化財の「紙本着色愛宕大権現像」を所蔵されており、以前は愛宕信仰が入っていたのかもしれません。
・立派な鐘楼門、端正な入母屋造流れ向拝の本堂には御本尊の阿弥陀三尊が御座。本堂向かって右手の堂宇には恵比寿天が御座されています。
・深谷七福神の恵比寿天で女郎花(オミナエシ)の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 阿弥陀三尊


2.深谷七福神 恵比寿天


■ 瑠璃山 正伝院
深谷市高島161
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所:深谷七福神(毘沙門天/クズの寺)
・弘仁年間(810-824年)、坂上田村麻呂の奥州征伐の際、小野岑守とその子小野篁((おののたかむら)が随行。この地にて篁が薬師如来の尊像を彫刻し、本尊として安置して開基と伝わる古刹です。
・寺宝の「釈迦涅槃図」(市指定文化財)は、幕末の文人、伊丹渓斎(いたみけいさい)の筆によるものです。
・深谷七福神の毘沙門天の寺で、御朱印は庫裡にて拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神 毘沙門天


■ 蓮沼山 地蔵院 惣持寺
公式Web
深谷市蓮沼463
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番、深谷七福神(弁財天/オバナの寺)
・境内の縁起碑に、「當寺墓地の五輪塔(元禄八年(1696年)建立)「當寺廿傳慶基之表」に「夫武蔵國幡羅郡蓮沼山惣持寺者行基菩薩之草創年数978宗澄和尚之中興云々略」と刻記されていることから、草創は奈良時代初期の養老二年(718年)行基菩薩によって創建され、後弘安年間(1278-1288年)顕盛(勅号宗澄)により再興された、深谷市内最古の名刹である。」とあります。
・地蔵堂の御本尊は行基作と伝わりましたが文化四年(1807年)の火災で消失、現在の地蔵尊は”露天の雨乞い地蔵”として村人の信仰を集めているそうです。
・深谷七福神(弁財天)と幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所で、尊格揮毫は「弁財天」、主印は金剛界大日如来の種子「バン」の御寶印と弁財天の持物「琵琶」の印、「新四国第四十二番」の札所印があり、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番と深谷七福神(弁財天)を兼ねたような内容の御朱印となっています。
・新型コロナ禍中は御朱印不授与とのことです。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第42番/深谷七福神(弁財天) 大日如来/弁財天

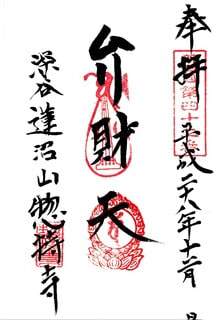
■ 能満山 定禅院 能護寺(あじさい寺)
熊谷市Web
熊谷市永井太田1141
高野山真言宗
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第75番、東国花の寺百ヶ寺霊場第25番
・天平十五年(743年)に国家安穏・万民豊楽と五穀豊穣祈願のため行基上人が開山し、後に弘法大師空海が再建され真言密教の道場として整えられたと伝わります。
・「妻沼のあじさい寺」として知られ、毎年6月には多くの参詣者を迎えます。
・現本堂は文化十一年(1814年)の再建で、内陣に大日如来、外陣に阿弥陀如来を安置した堂内の格天井(十六羅漢図)には、金井烏洲・岩崎榮益・樋口春翠などの彩色の花鳥獣が描かれています。
・虚空蔵堂には虚空蔵菩薩が祀られ、男女13歳厄除け祈願(十三参り)の寺として信仰を集めています。
・鐘楼の鐘は、元禄十四年(1701年)、諸八郎兵衛藤原正綱による鋳造で、乳の間に百字真言の梵字が鋳込まれているもの。市の文化財に指定されています。
・メジャー霊場「東国花の寺百ヶ寺霊場」の札所で、御朱印は庫裡にて拝受。御朱印尊格は「十三参り」の虚空蔵尊となっています。
〔拝受御朱印〕
1.東国花の寺百ヶ寺霊場第25番 虚空蔵菩薩


■ 寶珠山 光明禅寺 玉洞院
熊谷市妻沼2404
臨済宗円覚寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第16番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第86番
・開基は月峯常圓居士、開山を養嚴宗胡(文明九年(1477年)寂)とする曹洞宗寺院。
・『新編武蔵風土記稿』には鐘樓の銘文に「淀城主石川主殿頭憲之妻女、及び次男義孝、武運長久の誓の為に元禄三年(1690年)寄附する由を鐫す」とあります。
・石川憲之(1634-1707年)は、石川数正の叔父、石川家成の家を継いだ大久保忠隣の次男、石川忠総の孫にあたり、近江膳所藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家四代、山城淀藩初代藩主を務めました。憲之の妻女(正室)は羽林家の公家、梅園実清(1609-1662年)の息女で、その子石川義孝は山城淀藩第二代藩主、伊勢亀山藩石川家五代。
・妻女梅園氏、石川義孝ともに妻沼とのゆかりは確認できず、どうして当寺にこのような鐘銘が残っているのかも不明です。
御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受しました。幡羅郡新四国霊場については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第16番 聖観世音菩薩


■ 祥興山 真徳院 瑞林寺
熊谷市妻沼2485
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番
・『新編武蔵風土記稿』および境内記念碑によると、建久年間(1190-1199年)に天台宗寺院として創建。慶長六年(1598年)矢場村惠林寺第五世大庵文恕により曹洞宗に改められて開山、開基は大河内孫十郎政信と伝わります。
・大河内氏は摂津源氏源頼政流とされ、三河の吉良氏の家老の家柄でしたが、天正十五年(1587年)大河内秀綱の二男正綱が家康の命で長沢松平家庶流の松平正次の養子となり、子孫は大河内松平家と称します。武蔵野の名刹、平林寺は大河内大名家の墓所として知られています。
・こちらのWeb(大河内松平氏の研究)に「吉良家を去った大河内秀綱後は伊奈氏の配下で代官として活動している。『伊奈忠次文書集成』の中に、大河内秀綱に宛てた慶長年間の文書がある。文禄三年(1594年)、徳川家康が江戸から上州新田に向かうため、通り道にあたる妻沼の名主に人馬継立を命じる文書が大河内孫十郎(久綱)の名で発給されている。このころ既に久綱が代官だったことが知られる。」とあり、孫十郎(久綱)と孫十郎政信が同一人物であるかはわかりませんが、江戸時代初期に大河内氏が妻沼の地を代官差配していたことがうかがわれます。
・本堂向かって右手前の日限地蔵堂には赤い幟がならび、信仰を集めている感じがします。
・墓所には江戸時代の俳匠・有磯庵五渡(ありそあんごと)三代の墓があります。江戸時代の妻沼は芭蕉ゆかりの俳句のメッカで、各地の俳人たちは妻沼聖天の参詣と併せて妻沼の俳人と交流し、これを「妻沼詣」と称したと伝わります。
・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番の札所で、門前に御朱印のサンプルが掲示されています。庫裡にて「新四国第七十三番」の札所印入りの御朱印を拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第73番 釈迦牟尼佛


■ 聖天山 長楽寺 歓喜院(妻沼聖天山)
公式Web
熊谷市妻沼1627
高野山真言宗
御本尊:大聖歓喜天
札所:関東八十八箇所第88番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番、武州路十二支霊場 午(勢至菩薩)、東国花の寺百ヶ寺霊場第26番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番、第76番(旧宝蔵院)
・「日本三大聖天」のひとつ、「妻沼の聖天様」と呼ばれる関東を代表する名刹で、複数の霊場札所を務められます。
・名刹だけに記事ネタが多いですが、こちらでは簡単なご縁起と御朱印関連に絞ってご案内します。
・平安時代末期の武将斎藤別当実盛公(長井別当)が治承三年(1179年)、守り本尊の大聖歓喜天を祀る聖天宮を建立し、長井庄の総鎮守としたのが始まりとされます。
・実盛公は、源平争乱期に源義朝公、木曾義仲公、平維盛公と複雑な関係をもち、寿永二年(1183年)、平維盛公らと木曾義仲公追討のため出陣した加賀国篠原の戦いで奮戦し、ついに討ち取られました。この篠原の戦いの顛末は『平家物語』巻第七「実盛最期」として一章を成し、東国武士の機微を語るものとして広く知られています。
・建久八年(1197年)、良応僧都(実盛公の次男である実長(宗光))が聖天宮の別当(本坊)として歓喜院長楽寺を建立し、十一面観世音菩薩を本尊としたといいます。
・国宝の本殿は絢爛たる廟型式権現造で、「埼玉日光」ともいわれます。
・御朱印は境内授与所にていただけます。5つの札所を確認しており、うち4つを拝受しています。残りの幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第13番については不明です。
なお、札所御朱印ではない御本尊・大聖歓喜天の御朱印も授与されている模様です。
〔拝受御朱印〕
1.東国花の寺百ヶ寺霊場第26番 大聖歓喜天
札所本尊は御本尊。本殿が札所とみられます。


2.関東八十八箇所第88番 大聖歓喜天
本殿向かって左の大師堂が札所(第88番結願所)となっています。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の札所もこちらになります。


3.武州路十二支霊場 午 勢至菩薩
本殿向かって左の大師堂のお大師さまの右手(礼拝者からは左手)に御座す立像の勢至菩薩が札所本尊と思われます。大師堂内に単尊で勢至菩薩が安置される例は少ないと思われます。
当地は二十三夜月待講がさかんで、当山山内にも二十三夜塔が建立されています。そちらとの関連もあるのかもしれません。


4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第16番 聖観世音菩薩
中門そばの護摩堂の手前に御座す露仏の観音様が札所本尊です。


--------------------------------------
ここからは、いよいよ忍秩父観音霊場、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の核心部に入っていきます。小規模で無住の寺も多く、御朱印拝受難易度は高いです。
■ 大悲山 薬師院 観音寺
公式Web
熊谷市八木田198
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:忍秩父三十四観音霊場第18番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第44番、第67番(薬師堂)
・公式Webに、慶長年間(1596-1615年)のはじめ、澄海上人による開基とされ、徳川幕府よりご朱印を賜り、とあります。
・『新編武蔵風土記稿』には「大田村能護寺末大悲山薬師院ト号ス 慶安(1648-1652年)中寺領六石五斗ノ御朱印ヲ賜フ 開山澄海寂年知レス 本尊千手観音ヲ安ス」とあります。
村内の薬師堂と阿弥陀堂一宇も護持していたようです。
・忍秩父三十四観音霊場の観音堂は本堂とは別で、札所本尊は十一面観世音菩薩です。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国霊場の御朱印は授与されていない模様です。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第18番 十一面観世音菩薩


■ 禅源山 長井寺
熊谷市弥藤吾1979
臨済宗円覚寺派
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第17番
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 上野國那波郡矢場村泉福寺末 禅源山ト號ス 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。
・その他の由来などは不明です。
・現況は無住と思われ、御朱印は別途お願いし郵送いただきましたが、これはイレギュラー対応で原則不授与かもしれません。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第17番 釈迦如来


■ 王子山 観清寺
熊谷市弥藤吾574-1
曹洞宗
御本尊:釈迦三尊
札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第3番
・こちらは幡羅郡新四国霊場のみの札所なので、とくに情報が少ないです。
・『新編武蔵風土記稿』には「禅宗曹洞派 下奈良村集福寺末王子山ト號ス(中略)開山ハ本寺(集福寺)二世要岩春津弘治三年(1557年)示寂 本尊ハ釋迦文殊普賢ヲ安ス」とあります。
・予想以上の大寺で境内もよく整っています。御朱印は庫裡にて授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛


■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3へつづきます。
【 BGM 】
■ 夏影~Airness~ - 茶太ver
■ 春風 - Rihwa(カバー)
■ 夢暦 - 川江美奈子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 名曲の裏に名コード進行あり
最初聴いたとき、なにかの間違いかと思った曲も・・・。
ドミナントかかりまくりのメロ、炸裂する転調。
でも、破綻しそうでしない。
こういうのがプロのお仕事だと思う。
■ あなたに会えてよかった - 小泉今日子(カバー)
→コード
なにこのエグいイントロ・・・
想い出が 星になる~
A#dim A7 Gdim Dm F Fdim
↑ 怒濤のディミニッシュ攻撃
でも、アウトロはきっちりCのトニックで終わる(笑)
■ ただ泣きたくなるの - 中山美穂
→コード
■ Teenage Walk - 渡辺美里
→コード
■ 空に近い週末 - 今井美樹
→コード
■ Butterfly(バタフライ) - 木村カエラ(カバー)
→コード
歌い出しでいきなり転調かよ。
アウトロの「チョウは青い空を舞う」
G#m D# G#6 D# Fm7 D#sus4 D#
↑ 一歩間違えたら崩壊すると思う。よく収まったな~
■ 雪の華 - 中島美嘉 Cover.花たん(hanatan)
→コード
こんな繊細なコード進行だったんだ。
トーシロが下手に手だすと、たちまち崩壊する理由がわかる気がする。
■ CAN YOU CELEBRATE? - 安室奈美恵(カバー)
→コード
■ 熊田このはちゃんのテイク(限定リンク)
■ 時を刻む唄 - Lia
コード
■ Story Teller - kicco
1:46~「覚えてるかな~」のサビ、2:14~「僕の服の袖を~」の大サビのメロ展開がただものじゃない感。
■ 見えない月 - 藤田麻衣子
コード
アレンジの魔術師藤田麻衣子。オンコードが効き過ぎ・・・。
■ さよならメモリーズ - supercell(歌ってみた by 奏夢)
コード
サビのとっかかりが、アドナインス(add9) とサスフォー(sus4)
・言葉じゃうまく言えない想いを Eadd9 F#/E
・さよならメモリーズ D#sus4 D#7
3:48~ 「初めて見た 満開の桜」 Xメロ (B Eadd9 B F#sus4 F# F#7-9 B)
4:35~ 「一目見たときに思ったんだ~」 落ちサビ
Xメロ:Aメロ、Bメロやサビとはラインを変えたメロディ。これがなくても曲じたいは成り立つ。
落ちサビ:ラストのサビや大サビ前に挿入される、インストの音量を落としてボーカルを際立たせるサビ。
↑ by マキタスポーツ氏
■ 月のかほり - 夏川りみ
コード
やっぱりただことじゃないコード進行だった。
夏川りみのハイトーンは、ベタっとした曲よりもこういう浮遊感ある曲の方が向いていたような気がする。
6:09~
「生まれ変わったって・・・」
Bm7-5 Em7-5 Em/A Aadd9
ハーフデミニッシュ×2、オンコード、アドナイン
地上に降りてきそうで降りてこない(笑)
■ ebb and flow - LaLa (歌ってみた by LaLa)
コード
透明感あふれるメジャー・セブンス曲。
世はペンタ曲全盛だけど、アニメ・ゲーム曲ではさりげにセブンス系の佳曲が生み出されていたりする。
作曲は元I'veの中沢伴行氏。
■ ロッヂで待つクリスマス - 松任谷由実 / 歌おうfavorite songs 171
コード
ユーミンのかくれた名クリスマスソング。
ユーミンらしいこ洒落たメジャー・セブンス曲。
「窓もドアも越えて心は滑る」
AmM7 Am7 D7 Gmaj7 D7
↑ このコード進行すごすぎ。
ドミナントかかりまくりのメロ、炸裂する転調。
でも、破綻しそうでしない。
こういうのがプロのお仕事だと思う。
■ あなたに会えてよかった - 小泉今日子(カバー)
→コード
なにこのエグいイントロ・・・
想い出が 星になる~
A#dim A7 Gdim Dm F Fdim
↑ 怒濤のディミニッシュ攻撃
でも、アウトロはきっちりCのトニックで終わる(笑)
■ ただ泣きたくなるの - 中山美穂
→コード
■ Teenage Walk - 渡辺美里
→コード
■ 空に近い週末 - 今井美樹
→コード
■ Butterfly(バタフライ) - 木村カエラ(カバー)
→コード
歌い出しでいきなり転調かよ。
アウトロの「チョウは青い空を舞う」
G#m D# G#6 D# Fm7 D#sus4 D#
↑ 一歩間違えたら崩壊すると思う。よく収まったな~
■ 雪の華 - 中島美嘉 Cover.花たん(hanatan)
→コード
こんな繊細なコード進行だったんだ。
トーシロが下手に手だすと、たちまち崩壊する理由がわかる気がする。
■ CAN YOU CELEBRATE? - 安室奈美恵(カバー)
→コード
■ 熊田このはちゃんのテイク(限定リンク)
■ 時を刻む唄 - Lia
コード
■ Story Teller - kicco
1:46~「覚えてるかな~」のサビ、2:14~「僕の服の袖を~」の大サビのメロ展開がただものじゃない感。
■ 見えない月 - 藤田麻衣子
コード
アレンジの魔術師藤田麻衣子。オンコードが効き過ぎ・・・。
■ さよならメモリーズ - supercell(歌ってみた by 奏夢)
コード
サビのとっかかりが、アドナインス(add9) とサスフォー(sus4)
・言葉じゃうまく言えない想いを Eadd9 F#/E
・さよならメモリーズ D#sus4 D#7
3:48~ 「初めて見た 満開の桜」 Xメロ (B Eadd9 B F#sus4 F# F#7-9 B)
4:35~ 「一目見たときに思ったんだ~」 落ちサビ
Xメロ:Aメロ、Bメロやサビとはラインを変えたメロディ。これがなくても曲じたいは成り立つ。
落ちサビ:ラストのサビや大サビ前に挿入される、インストの音量を落としてボーカルを際立たせるサビ。
↑ by マキタスポーツ氏
■ 月のかほり - 夏川りみ
コード
やっぱりただことじゃないコード進行だった。
夏川りみのハイトーンは、ベタっとした曲よりもこういう浮遊感ある曲の方が向いていたような気がする。
6:09~
「生まれ変わったって・・・」
Bm7-5 Em7-5 Em/A Aadd9
ハーフデミニッシュ×2、オンコード、アドナイン
地上に降りてきそうで降りてこない(笑)
■ ebb and flow - LaLa (歌ってみた by LaLa)
コード
透明感あふれるメジャー・セブンス曲。
世はペンタ曲全盛だけど、アニメ・ゲーム曲ではさりげにセブンス系の佳曲が生み出されていたりする。
作曲は元I'veの中沢伴行氏。
■ ロッヂで待つクリスマス - 松任谷由実 / 歌おうfavorite songs 171
コード
ユーミンのかくれた名クリスマスソング。
ユーミンらしいこ洒落たメジャー・セブンス曲。
「窓もドアも越えて心は滑る」
AmM7 Am7 D7 Gmaj7 D7
↑ このコード進行すごすぎ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 日本神社の御朱印
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)をUP中ですが、深谷からもうすこし足を伸ばすとこのところ認知度が上がりつつある「日本神社」がありますので、こちらについてまとめてみます。
■ 日本神社
本庄市児玉町小平1578
御祭神:神武天皇
旧社格:旧小平村鎮守(石神社)
元別当:村民持(小平村)
授与所:東石清水八幡神社社務所(本庄市児玉町児玉198)、神社下の新井商店、宮司様宅(連絡先は現地に掲示)のいずれかで授与されている模様。
境内掲示の由緒書および『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)などから由緒をたどってみます。
延暦十年(791年)、坂上田村麻呂が蝦夷平定に赴く際に当地に立ち寄り、神武天皇を祀って戦勝を祈願、無事平定の後に社殿を建立したのが創祀とされます。
当初は神武神社と称していたといい、また鎮座地の小名を古くから神山と呼ぶことから、古来当地は信仰の対象とされてきたとみられています。
当地は従前、那珂郡小平村に属し、小平村の集落は東小平と西小平に分かれて、当社は西小平に御鎮座でした。
文化・文政期(1804年-1829年)に編まれた『新編武蔵風土記稿』の小平村の項(国立国会図書館DC)に「日本神社」の記載はなく、「石神社二宇 共に村ノ鎮守ニテ村民持以下三社持同シ 熊野社 稲荷社、駒形社」とあります。
『埼玉の神社』の石神神社(せきじんじんじゃ)の頁に「『風土記稿』小平村の項には『石神社二宇 共に村ノ鎮守ニテ村民持』と二社の石神社が記され、この内一社が当社(石神神社)であり、明治五年に村社となった。もう一社の石神社は無格社とされ、明治七年に神武天皇社(現日本神社)に合祀された。」とあります。
一方、境内由緒書には、「明治五年に東小平の石神神社が村社に列したが、当社は無格社とされた。『西小平にも石神神社に匹敵する大きな神社が欲しい』との地元の強い要望から、明治七年に西小平の各地に鎮座する稲荷神社・桜木神社・黒石神社・駒形神社・石神社・山神社の六つの無格社を、神武天皇を祀る当社に合祀」とあります。
以上から、江戸期から西小平に御鎮座の神武神社、ないし神武天皇社に小平村の鎮守社のひとつであった石神社ほか五社を合祀したということになります。
ちなみに『新編武蔵風土記稿』の小平村の項には、上記六社のうち、稲荷社、駒形社の名が見えます。
合祀以来、地元では当社を「合社様」、当社の鎮座する山を「合社山」と呼びましたが、明治十四年(1881年)に社名を日本神社と改めたとされます。
なお、日本神社と改めた理由については、具体的な史料が見つからず不明です。
大正二年(1913年)に村内各社を石神神社へ合祀した際、当社は合祀を拒否した模様で、「村社石神神社ヘ諸神合祀ノ際小平一同協議ノ上本社ハ旧来ノ通り祭置クコトトス」との一文を刻んだ大正五年(1916年)の社殿建設記念碑が境内に建っているそうです。
(筆者未確認)
社号を「日本神社」に改めたこと、合祀を拒んだことなどから、西小平の郷民の当社に対する強い尊崇の念がうかがわれます。
境内由緒書によると、御祭神は神武天皇。御神徳は武運、国土守護、災難除けです。
神武天皇(神日本磐余彦尊)を御祭神とする神社は、奈良の橿原神宮、宮崎の宮﨑神宮、奈良県御所市の神武天皇社、広島県府中町の多家神社 (埃宮)などが知られていますが、西日本メインのようです。
東日本では比較的めずらしいとみられ、Web検索では、茨城県ひたちなか市の橿原神宮、長瀞の寶登山神社、加須の神武天皇社、相模原市青根の神武天皇社、池袋の御嶽神社がヒットする程度です。

-----------------------------------
児玉町市街から県道287号長瀞児玉線県道を長瀞方面に進んだ所にあり、すぐ近くには児玉三十三ヶ所霊場発願寺の平等山 成身院(百体観世音)もあります。


【写真 上(左)】 新井商店と参道入口
【写真 下(右)】 参道入口


【写真 上(左)】 長々とつづく参道
【写真 下(右)】 門柱
駐車場はないですが、参道入口の新井商店周辺に若干のスペースはあります。
新井商店右手前に「日本神社 入口」の立派な石標が立っています。
ここから神社が鎮座する奥手の小山に向かって、参道が長々とのびています。
その先に門柱があり、「一般車両進入キンシ」の掲示があります。


【写真 上(左)】 参道登り口
【写真 下(右)】 参道-1


【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 参道-3
小山のふもとの登り口で向きを変えて左手の細い道に入りますが、「日本神社」のノボリが立っているので、迷うことはないかと。
細い登り坂がつづき、ついに急な階段となる、かなりハードな参道です。
階段の登り口あたりで、ようやく木の葉隠れに拝殿が見えてきます。


【写真 上(左)】 拝殿が見えてきました
【写真 下(右)】 鳥居
石の鳥居は貫の突き出しがない神明鳥居系で、そのおくに石灯籠一対、正面の拝殿前に狛犬一対。
向かって右手に社務所、左手に神楽殿。
南面で、拝殿前に樹木はないので明るく開けた感じの境内です。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 拝殿前


【写真 上(左)】 社務所
【写真 下(右)】 神楽殿
拝殿は切妻造桟瓦葺平入りで、大ぶりな巴紋の拝殿幕が掛けられています。
拝殿じたいの規模は大きくないですが、両翼に切妻造平入の境内社殿を配しているので、スケール感があります。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 斜めからの拝殿.


【写真 上(左)】 右手からの拝殿
【写真 下(右)】 左手からの拝殿
『埼玉の神社』によると、境内社の配置は向かって右手の拝殿側から順に、琴平社、黒石社、稲荷社3宇、桜木社、八坂神社。
左手の拝殿側から順に、石神社、駒形社、天神社、白山社、山神社、御嶽山神社、三笠山神社と並ばれます。


【写真 上(左)】 境内社
【写真 下(右)】 境内社
拝殿に向拝柱はなく、見上げに社号の扁額が掛けられています。
軒裏の垂木は粗で、太くがっしりとしたものです。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 扁額
本殿については詳細不明ですが、切妻造桟桟瓦葺の覆屋のなかに御鎮座のようです。
境内社殿に通常のダルマと青いダルマがいくつも置かれていました。
社名や武運の神様という御神徳にちなんで、サッカー日本代表チームをはじめオリンピック代表選手などが必勝祈願に参拝し、ダルマを奉納するそうです。
新型コロナ禍でなければ、東京五輪を前に、参拝客で大いに賑わったかもしれません。


【写真 上(左)】 青ダルマ
【写真 下(右)】 神楽殿欄間の龍の彫刻
※スポーツ関係者の参拝を報じる記事
同記事には「『日本』と名の付く神社は、神社庁に登録されている全国の神社では同神社のみ。「日本唯一の社」として同神社はスポーツ関係者らが必勝祈願に訪れる神社となった。2010(平成22)年のサッカー・ワールドカップで、児玉商工会青年部が青いだるまに祈念を込め代表チームに贈って以来、日本女子サッカー代表チーム、オリンピックに出場した三宅宏実選手など、スポーツ関係者が頻繁に参拝に訪れ『必勝祈願』を行うようになった。」とあります。
ダルマはお守りなどは、新井商店で販売されているようですが、参拝時は定休日だったので詳細不明です。
御朱印は、東石清水八幡神社社務所(本庄市児玉町児玉198)、宮司様宅(連絡先は現地に掲示)、神社下の新井商店のいずれかで授与されている模様ですが、直書いただきたい場合は八幡神社か宮司様宅、いずれかの選択になるようです。
ちなみに、わたしは八幡神社にて拝受しました。
日本神社の御朱印は2種類あり、同時にいただけます。
八幡神社の御朱印も数種類あり、見本が出ているのでいただきやすいです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:日本神社 直書(筆書)
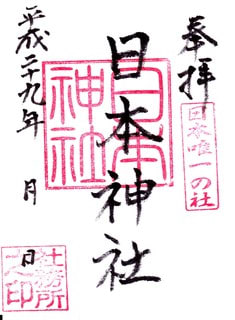

【写真 上(左)】 日本神社の御朱印(旧)
【写真 下(右)】 日本神社の御朱印(新)


【写真 上(左)】 東石清水八幡神社の八脚門
【写真 下(右)】 東石清水八幡神社の拝殿
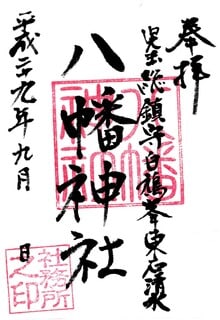

【写真 上(左)】 東石清水八幡神社の御朱印(旧)
【写真 下(右)】 東石清水八幡神社の絵御朱印
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 日本神社
本庄市児玉町小平1578
御祭神:神武天皇
旧社格:旧小平村鎮守(石神社)
元別当:村民持(小平村)
授与所:東石清水八幡神社社務所(本庄市児玉町児玉198)、神社下の新井商店、宮司様宅(連絡先は現地に掲示)のいずれかで授与されている模様。
境内掲示の由緒書および『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)などから由緒をたどってみます。
延暦十年(791年)、坂上田村麻呂が蝦夷平定に赴く際に当地に立ち寄り、神武天皇を祀って戦勝を祈願、無事平定の後に社殿を建立したのが創祀とされます。
当初は神武神社と称していたといい、また鎮座地の小名を古くから神山と呼ぶことから、古来当地は信仰の対象とされてきたとみられています。
当地は従前、那珂郡小平村に属し、小平村の集落は東小平と西小平に分かれて、当社は西小平に御鎮座でした。
文化・文政期(1804年-1829年)に編まれた『新編武蔵風土記稿』の小平村の項(国立国会図書館DC)に「日本神社」の記載はなく、「石神社二宇 共に村ノ鎮守ニテ村民持以下三社持同シ 熊野社 稲荷社、駒形社」とあります。
『埼玉の神社』の石神神社(せきじんじんじゃ)の頁に「『風土記稿』小平村の項には『石神社二宇 共に村ノ鎮守ニテ村民持』と二社の石神社が記され、この内一社が当社(石神神社)であり、明治五年に村社となった。もう一社の石神社は無格社とされ、明治七年に神武天皇社(現日本神社)に合祀された。」とあります。
一方、境内由緒書には、「明治五年に東小平の石神神社が村社に列したが、当社は無格社とされた。『西小平にも石神神社に匹敵する大きな神社が欲しい』との地元の強い要望から、明治七年に西小平の各地に鎮座する稲荷神社・桜木神社・黒石神社・駒形神社・石神社・山神社の六つの無格社を、神武天皇を祀る当社に合祀」とあります。
以上から、江戸期から西小平に御鎮座の神武神社、ないし神武天皇社に小平村の鎮守社のひとつであった石神社ほか五社を合祀したということになります。
ちなみに『新編武蔵風土記稿』の小平村の項には、上記六社のうち、稲荷社、駒形社の名が見えます。
合祀以来、地元では当社を「合社様」、当社の鎮座する山を「合社山」と呼びましたが、明治十四年(1881年)に社名を日本神社と改めたとされます。
なお、日本神社と改めた理由については、具体的な史料が見つからず不明です。
大正二年(1913年)に村内各社を石神神社へ合祀した際、当社は合祀を拒否した模様で、「村社石神神社ヘ諸神合祀ノ際小平一同協議ノ上本社ハ旧来ノ通り祭置クコトトス」との一文を刻んだ大正五年(1916年)の社殿建設記念碑が境内に建っているそうです。
(筆者未確認)
社号を「日本神社」に改めたこと、合祀を拒んだことなどから、西小平の郷民の当社に対する強い尊崇の念がうかがわれます。
境内由緒書によると、御祭神は神武天皇。御神徳は武運、国土守護、災難除けです。
神武天皇(神日本磐余彦尊)を御祭神とする神社は、奈良の橿原神宮、宮崎の宮﨑神宮、奈良県御所市の神武天皇社、広島県府中町の多家神社 (埃宮)などが知られていますが、西日本メインのようです。
東日本では比較的めずらしいとみられ、Web検索では、茨城県ひたちなか市の橿原神宮、長瀞の寶登山神社、加須の神武天皇社、相模原市青根の神武天皇社、池袋の御嶽神社がヒットする程度です。

-----------------------------------
児玉町市街から県道287号長瀞児玉線県道を長瀞方面に進んだ所にあり、すぐ近くには児玉三十三ヶ所霊場発願寺の平等山 成身院(百体観世音)もあります。


【写真 上(左)】 新井商店と参道入口
【写真 下(右)】 参道入口


【写真 上(左)】 長々とつづく参道
【写真 下(右)】 門柱
駐車場はないですが、参道入口の新井商店周辺に若干のスペースはあります。
新井商店右手前に「日本神社 入口」の立派な石標が立っています。
ここから神社が鎮座する奥手の小山に向かって、参道が長々とのびています。
その先に門柱があり、「一般車両進入キンシ」の掲示があります。


【写真 上(左)】 参道登り口
【写真 下(右)】 参道-1


【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 参道-3
小山のふもとの登り口で向きを変えて左手の細い道に入りますが、「日本神社」のノボリが立っているので、迷うことはないかと。
細い登り坂がつづき、ついに急な階段となる、かなりハードな参道です。
階段の登り口あたりで、ようやく木の葉隠れに拝殿が見えてきます。


【写真 上(左)】 拝殿が見えてきました
【写真 下(右)】 鳥居
石の鳥居は貫の突き出しがない神明鳥居系で、そのおくに石灯籠一対、正面の拝殿前に狛犬一対。
向かって右手に社務所、左手に神楽殿。
南面で、拝殿前に樹木はないので明るく開けた感じの境内です。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 拝殿前


【写真 上(左)】 社務所
【写真 下(右)】 神楽殿
拝殿は切妻造桟瓦葺平入りで、大ぶりな巴紋の拝殿幕が掛けられています。
拝殿じたいの規模は大きくないですが、両翼に切妻造平入の境内社殿を配しているので、スケール感があります。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 斜めからの拝殿.


【写真 上(左)】 右手からの拝殿
【写真 下(右)】 左手からの拝殿
『埼玉の神社』によると、境内社の配置は向かって右手の拝殿側から順に、琴平社、黒石社、稲荷社3宇、桜木社、八坂神社。
左手の拝殿側から順に、石神社、駒形社、天神社、白山社、山神社、御嶽山神社、三笠山神社と並ばれます。


【写真 上(左)】 境内社
【写真 下(右)】 境内社
拝殿に向拝柱はなく、見上げに社号の扁額が掛けられています。
軒裏の垂木は粗で、太くがっしりとしたものです。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 扁額
本殿については詳細不明ですが、切妻造桟桟瓦葺の覆屋のなかに御鎮座のようです。
境内社殿に通常のダルマと青いダルマがいくつも置かれていました。
社名や武運の神様という御神徳にちなんで、サッカー日本代表チームをはじめオリンピック代表選手などが必勝祈願に参拝し、ダルマを奉納するそうです。
新型コロナ禍でなければ、東京五輪を前に、参拝客で大いに賑わったかもしれません。


【写真 上(左)】 青ダルマ
【写真 下(右)】 神楽殿欄間の龍の彫刻
※スポーツ関係者の参拝を報じる記事
同記事には「『日本』と名の付く神社は、神社庁に登録されている全国の神社では同神社のみ。「日本唯一の社」として同神社はスポーツ関係者らが必勝祈願に訪れる神社となった。2010(平成22)年のサッカー・ワールドカップで、児玉商工会青年部が青いだるまに祈念を込め代表チームに贈って以来、日本女子サッカー代表チーム、オリンピックに出場した三宅宏実選手など、スポーツ関係者が頻繁に参拝に訪れ『必勝祈願』を行うようになった。」とあります。
ダルマはお守りなどは、新井商店で販売されているようですが、参拝時は定休日だったので詳細不明です。
御朱印は、東石清水八幡神社社務所(本庄市児玉町児玉198)、宮司様宅(連絡先は現地に掲示)、神社下の新井商店のいずれかで授与されている模様ですが、直書いただきたい場合は八幡神社か宮司様宅、いずれかの選択になるようです。
ちなみに、わたしは八幡神社にて拝受しました。
日本神社の御朱印は2種類あり、同時にいただけます。
八幡神社の御朱印も数種類あり、見本が出ているのでいただきやすいです。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:日本神社 直書(筆書)
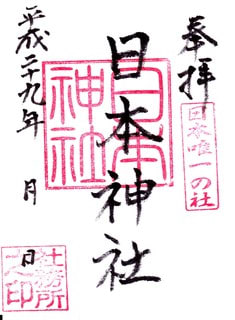

【写真 上(左)】 日本神社の御朱印(旧)
【写真 下(右)】 日本神社の御朱印(新)


【写真 上(左)】 東石清水八幡神社の八脚門
【写真 下(右)】 東石清水八幡神社の拝殿
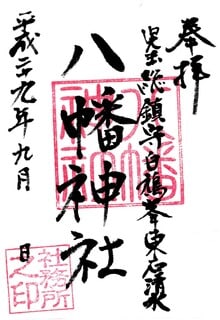

【写真 上(左)】 東石清水八幡神社の御朱印(旧)
【写真 下(右)】 東石清水八幡神社の絵御朱印
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 安定の昭和品質?
10日午後、NHKが総合で放送した「伝説のコンサート”わが愛しのキャンディーズ”リマスター版」、見忘れたけどかなり反響が大きかったようです。
→ 記事
■ 微笑がえし - キャンディーズ メモリーズ
※ 埋め込み不可なので、↑ リンクしてきいてね。
改めて聴いてみると、歌うまいわ。
ブレスがしっかりしているし、ビブラートもロングトーンも、ヒーカップさえ繰り出してる。
なんといっても、曲が抜群にいい。
メロディとハーモニーとリズムのバランスがしっかりとれていた時代。
この時代って、プロが2人以上で歌ったらハモりはお約束。
数十人で歌ってもユニゾンって、いまじゃふつうだもんね・・・。
そしてアレンジと演奏がしっかりしている。
プロがプロとしてきっちりお仕事してる。
だから難しい楽曲でも、難しくきこえずに自然に耳に入ってくる。
それと、ほしいところにほしい音を放り込んでくるこの感覚。
これが、安定の昭和品質のポイントなのか・・・?
1970年代後半、これからピークに向かう日本の歌謡・ポップス界。
その1978年(昭和53年)4月4日のタイミングでの引退か・・・。
いまから考えると、いろいろと思うところはありますわ。
↓ こういうのも、安定の昭和品質ならではか?
■ 【高画質】 久保田早紀 - 異邦人 (シルクロードのテーマ) 【夜のヒットスタジオ 生演奏】
1979年(昭和54年)10月1日リリース、登場2回目とのこと。
■ 世界でいちばん熱い夏 - プリンセスプリンセス
1987年(昭和62年)7月16日リリース。
初登場?ではんぱじゃない安定感! ザ・ベストテンのスタジオを完璧にライブ会場化してる。
やっぱりこれを超えるガールス・バンドは出ていないのでは?
(キャスターさん)「今日は岐阜から小田原への移動中ということでお越しいただけませんでした。」
(徹子さん)「あらぁ、だったらどっかのフラットフォームで歌っていただくとか、できなかったんでしょうかね~」
↑ いまだったら、ぜったいあり得ない発言。
■ チェリーブラッサム - 松田聖子
これ、ほんとに歌ってるよ。
それで、この安定のパフォーマンス。プロだわ・・・。
↑ いまだったら、ぜったいあり得ない中継(笑)
■ みずいろの雨 - 八神純子
1978年(昭和53年)9月5日リリース。
伸びまくるハイトーン! そして透明感。
こんな強引なハイトーン連打、たぶん自作じゃないとつくれないと思う(笑)
■ Teenage Walk - 渡辺美里
1986年(昭和61年)5月2日リリース。
初期の小室哲哉の作曲。
この意表をついた転調は、たしかにタダモノじゃない感を漂わせていた。
■ LOVE (抱きしめたい) - 沢田 研二
1978年(昭和53年)9月10日リリース。
この年の『第29回NHK紅白歌合戦』の大トリ曲。
そういえば、この頃の紅白って、ほとんどその年のヒット曲で構成できたもんな。
とゆ-か、だいたいの曲がスタンダード化してるし・・・。
■ YES MY LOVE - 矢沢永吉
1982年(昭和57年)2月20日リリース。
当時CMでヘビロテされてた。
オトナの余裕感。時代を物語ってる。
■ 君は薔薇より美しい - 布施 明(当時31歳)1979 OA
1979年(昭和54年)1月17日リリース。
声がいいわな。それと声量。
当時は 音楽的には、洋楽 > ニューミュージック > 歌謡曲 的なヒエラルキーあったような気もするけど、そいつはまちがいでした。
→ 記事
■ 微笑がえし - キャンディーズ メモリーズ
※ 埋め込み不可なので、↑ リンクしてきいてね。
改めて聴いてみると、歌うまいわ。
ブレスがしっかりしているし、ビブラートもロングトーンも、ヒーカップさえ繰り出してる。
なんといっても、曲が抜群にいい。
メロディとハーモニーとリズムのバランスがしっかりとれていた時代。
この時代って、プロが2人以上で歌ったらハモりはお約束。
数十人で歌ってもユニゾンって、いまじゃふつうだもんね・・・。
そしてアレンジと演奏がしっかりしている。
プロがプロとしてきっちりお仕事してる。
だから難しい楽曲でも、難しくきこえずに自然に耳に入ってくる。
それと、ほしいところにほしい音を放り込んでくるこの感覚。
これが、安定の昭和品質のポイントなのか・・・?
1970年代後半、これからピークに向かう日本の歌謡・ポップス界。
その1978年(昭和53年)4月4日のタイミングでの引退か・・・。
いまから考えると、いろいろと思うところはありますわ。
↓ こういうのも、安定の昭和品質ならではか?
■ 【高画質】 久保田早紀 - 異邦人 (シルクロードのテーマ) 【夜のヒットスタジオ 生演奏】
1979年(昭和54年)10月1日リリース、登場2回目とのこと。
■ 世界でいちばん熱い夏 - プリンセスプリンセス
1987年(昭和62年)7月16日リリース。
初登場?ではんぱじゃない安定感! ザ・ベストテンのスタジオを完璧にライブ会場化してる。
やっぱりこれを超えるガールス・バンドは出ていないのでは?
(キャスターさん)「今日は岐阜から小田原への移動中ということでお越しいただけませんでした。」
(徹子さん)「あらぁ、だったらどっかのフラットフォームで歌っていただくとか、できなかったんでしょうかね~」
↑ いまだったら、ぜったいあり得ない発言。
■ チェリーブラッサム - 松田聖子
これ、ほんとに歌ってるよ。
それで、この安定のパフォーマンス。プロだわ・・・。
↑ いまだったら、ぜったいあり得ない中継(笑)
■ みずいろの雨 - 八神純子
1978年(昭和53年)9月5日リリース。
伸びまくるハイトーン! そして透明感。
こんな強引なハイトーン連打、たぶん自作じゃないとつくれないと思う(笑)
■ Teenage Walk - 渡辺美里
1986年(昭和61年)5月2日リリース。
初期の小室哲哉の作曲。
この意表をついた転調は、たしかにタダモノじゃない感を漂わせていた。
■ LOVE (抱きしめたい) - 沢田 研二
1978年(昭和53年)9月10日リリース。
この年の『第29回NHK紅白歌合戦』の大トリ曲。
そういえば、この頃の紅白って、ほとんどその年のヒット曲で構成できたもんな。
とゆ-か、だいたいの曲がスタンダード化してるし・・・。
■ YES MY LOVE - 矢沢永吉
1982年(昭和57年)2月20日リリース。
当時CMでヘビロテされてた。
オトナの余裕感。時代を物語ってる。
■ 君は薔薇より美しい - 布施 明(当時31歳)1979 OA
1979年(昭和54年)1月17日リリース。
声がいいわな。それと声量。
当時は 音楽的には、洋楽 > ニューミュージック > 歌謡曲 的なヒエラルキーあったような気もするけど、そいつはまちがいでした。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
【旧記事】■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPしています。
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔以下は旧記事へのリンクです〕
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
大河ドラマ「青天を衝け」、近代もので渋め(?)の主人公にしては視聴率健闘しているようです。
また、先にUPした「血洗島 諏訪神社の御朱印」に多くのアクセスをいただきありがとうございます。
今後、新型コロナの状況がどうなるかわかりませんが、渋沢栄一翁の故郷の地、血洗島(深谷市)へのアプローチで拝受できる御朱印についてとりあげてみます。
(この他にも授与情報があって未拝受の寺社がいくつかあります。拝受次第、追加していきます。)
【エリア概要】
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛したと伝わります。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたとされています。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄え、城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く、人流が活発であったので、このエリアは北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、関越道「花園」IC周辺から順にご紹介していまきす。
■ 荒澤山 寿楽院
深谷市荒川983
高野山真言宗
御本尊:不動明王
司元別当:天神社(荒川地内)
・由緒は不詳だが、『風土記稿』には「天神社 寿楽院持」とあります。予想以上に広い境内で、道をはさんで立派な聖天宮が御座します。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。ご住職ご不在時は書置対応となる模様。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

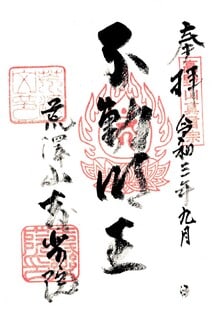
■ 光福山 医王院 長善寺
公式Web
深谷市小前田1452
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所:関東八十八箇所第85番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番
・鉢形城主北条氏邦の三男「光福丸」の菩提寺として知られる古刹で、2つのメジャー霊場の札所として参拝者を集めます。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第85番 大日如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番 聖観世音菩薩

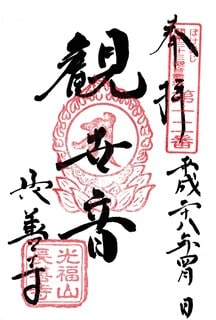
■ 吉祥山 應正寺
深谷市田中608-1
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第30番
・由緒は不詳ですが、入母屋造の立派な本堂と、二層の優れた意匠の観音堂があり、忍秩父三十四観音霊場第30番の札所はこちらの観音堂となっています。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。御本尊の御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

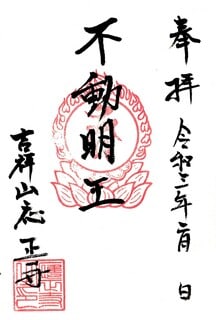
2.忍秩父三十四観音霊場第30番 十一面千手観世音菩薩

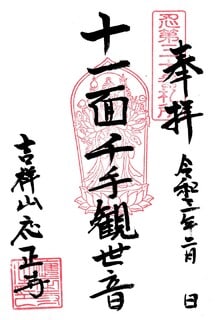
■ 根本山 光明院 正福寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市瀬山141
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東八十八箇所第84番、関東九十一薬師霊場 第35番、武州路十二支霊場 酉(不動明王) ※関東九十一薬師霊場第35番は境外の薬師堂
・永禄年間(1558-1570年)開基、慶長年間(1596-1604年)、重盛法印による開創と伝わる古刹。御本尊の阿弥陀如来は二尺四寸の木彫坐像で、安政二年(1855年)の作と伝わります。
・武州路十二支霊場の札所本尊、不動明王は、板木の記録によると「秀海」という行者が出羽三山へ三十三度尊像を背負って行き来され、霊験あらたかなお不動様として広く信仰され講も組織されたとのこと。
・関東九十一薬師霊場の札所本尊、薬師如来は東側に約600m離れた国道140号パイパス沿いにある境外仏堂の薬師堂(別名:踏鞴堂)に御座。一尺三寸木彫坐像の薬師如来は養老三年(717年)春日仏師一夜作と伝わり、現在の尊像は宝永七年(1710年)造顕とのこと。魔除、厄除、眼病除のお薬師様として広く信仰を集めているそうです。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。3つのメジャー霊場の札所だけに手慣れたご対応です。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第84番 阿弥陀如来

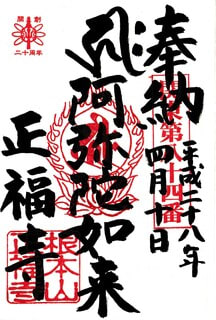
2.武州路十二支霊場(酉) 不動明王


3.関東九十一薬師霊場第35番 薬師如来 〔境外仏堂〕


■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)


公式Web
熊谷市三ケ尻3712
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番
・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。
・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。
・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。
・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。
・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。
〔拝受御朱印〕
1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

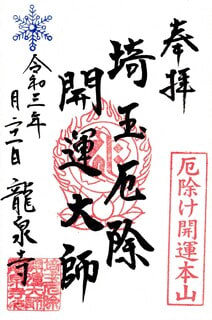
2.関東八十八箇所第83番 不動明王

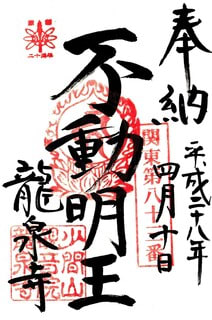
3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩
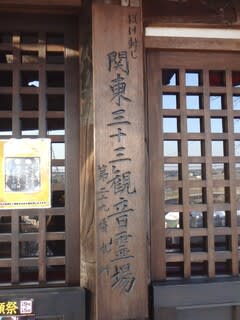
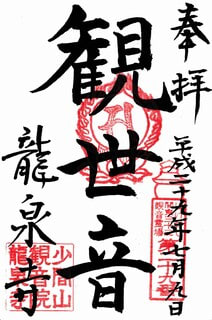
尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。
4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩
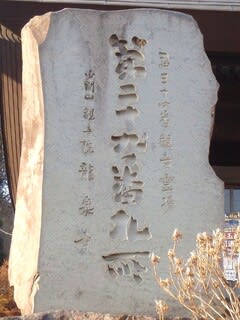
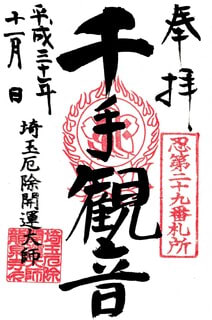
5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩
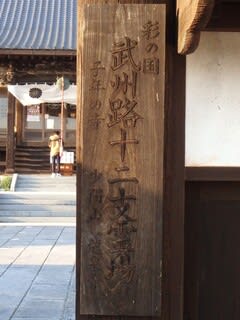

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。
6.「如月 花手水」の御朱印


7.切り絵御朱印

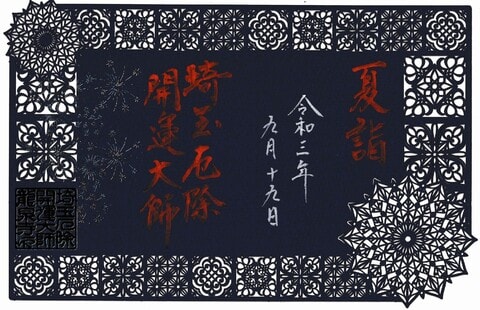
※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。
■ 田中神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命
旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)
元別当:寶珠山 延命寺(熊谷市三ケ尻)
授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所
・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。
・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。
・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。
・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)


■ (三ケ尻)八幡神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公
旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守
元別当:
授与所:境内社務所
・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。
・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。
・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

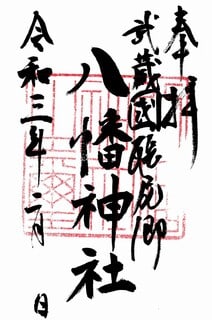
■ 青野山 清浄院 大正寺
熊谷市籠原南1-252
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番
・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。
・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。
奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。
・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。
・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。
・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。
・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

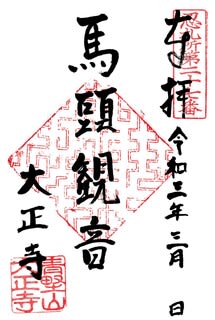
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王
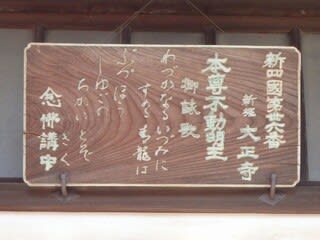
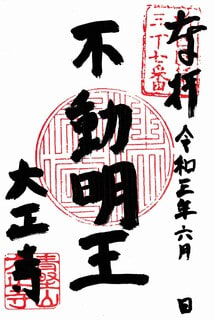

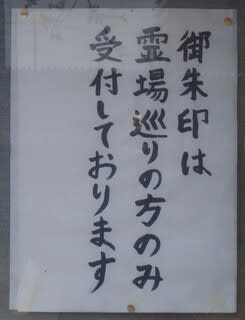
※霊場巡拝者にのみ授与
■ 狗門寺
熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)
真言宗豊山派?
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番
・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。
・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。
・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩
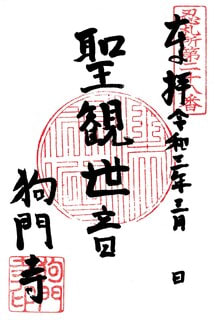
※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)
■ (上柴町)諏訪神社
深谷市上柴町東1-18
御祭神:建御名方命、美穂須須美命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、旧大字柴崎地区鎮守
元別当:月笑院
授与所:楡山神社宮司様宅
・文禄元年(1592年)頃、旧柴崎地区の開発者である柴崎淡路守(深谷城主上杉氏の家臣)の一族が氏神として祀ったことが創祀と伝わる柴崎地区の鎮守社。
・境内に御座す双体道祖神は、県内ではめずらしいものとされています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:諏訪神社 直書(筆書)

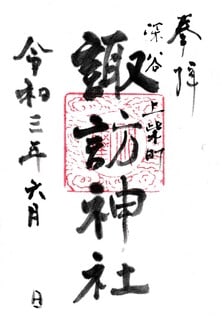
■ 大乗山 正法寺
公式Web
深谷市上柴町東2-2-2
日蓮宗
御本尊:
札所:
・このエリアでは数少ない日蓮宗寺院で、房総・勝浦の松部の地に妙潮寺の末寺として創建、その後、日蓮宗管長、久保田日亀大僧正のお力添えにより深谷に移転されました。
〔拝受御朱印〕
1.御首題

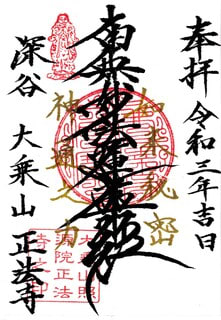
■ 武蔵國八海山神社
深谷市折之口73
御祭神:大己貴命、國常立尊、少彦名命
旧社格:
元別当:
授与所:境内社務所
・比較的新しい神社で、御朱印も快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八海山神社 直書(筆書)

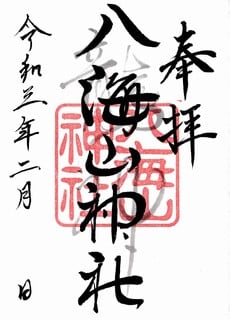
■ 境井山 寶泉寺
深谷市境220-1
曹洞宗
御本尊:
札所:深谷七福神(福禄寿)
・深谷七福神の一寺で福禄寿・キキョウの寺。
・慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いで手柄を立てた旗本吉田与右衛門政景氏は当地境および花園町永田に知行を拝領。人見福昌寺第九世実叟大存大和尚を開山に仰いで当山を建立開基と寺伝にあります。
・深谷七福神の福禄寿は、本堂手前左手に御座。
・七福神の御朱印は本堂内にて直書いただけましたが、御本尊の御朱印は授与されていないそうです。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神(福禄寿)


※御本尊の御朱印は不授与
■ 大谷山 地蔵院 宝積寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市大谷114
真言宗豊山派
御本尊:五智如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番、武州路十二支霊場 戌(阿弥陀如来)
・応永年間(1394-1428年)、地蔵菩薩を御本尊として盛谷山地蔵院宝錫寺と号し源照法印が開創。天正十年(1582年)、住職重任和尚が伽藍を整備され、五智如来を奉安されて、大谷山宝積寺と改称して中興と伝わる古刹。
・五智如来とは、大日如来が備えられる5つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智)を象徴する金剛界の五如来(いわゆる金剛界五仏)。
中尊(中央)は法界体性智の大日如来。東方は大円鏡智の阿しゅく如来ないし薬師如来、南方は平等性智の宝生如来、西方は妙観察智の阿弥陀如来、北方は成所作智の不空成就如来でそれぞれ象徴されます。(各尊格は宗派等により異なるようです。)
・関東三十三観音と武州路十二支霊場のふたつの現役霊場の札所を務められ、貴重な五智如来の御朱印も授与いただけます。御朱印は原則書き置きのようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 五智如来

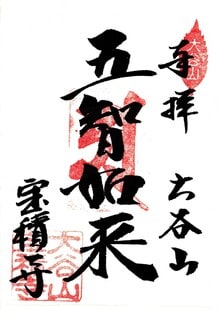
2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番 光明観世音菩薩


3.武州路十二支霊場(戌) 阿弥陀如来

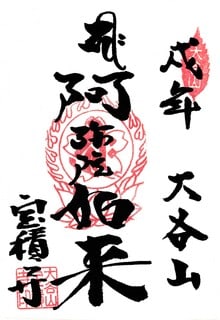
■ 足髙神社
深谷市武蔵野3283
御祭神:大物主之大神
旧社格:(氏子区域:旧武蔵野村下郷地区(旧猿喰土村))
元別当:地内観音寺→橋本家→高野家
授与所:境内社務所に案内あり
・既に室町末期には鉢形城主北条氏邦により、領内鬼門鎮護として奉祀されていたとされ、祭礼時、氏邦が神饌を奉るために使った膳が足高であったため、現社号になったと伝わります。
・通常は非駐在のようですが、社務所に掲出の連絡先にTELすると、書置の御朱印をお持ちいただけます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:足髙神社 書置(筆書)

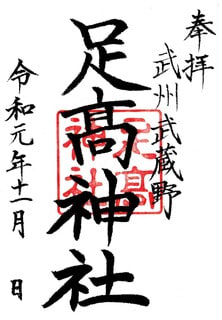
■ (武蔵野)八幡神社
深谷市武蔵野1862
御祭神:誉田別命
旧社格:旧武蔵野村中郷地区鎮守
元別当:常光寺(武蔵野)
授与所:足髙神社(足髙神社社務所に案内あり)
・鎌倉街道(県道小前田・児玉線)沿いに御鎮座の八幡神社。境内社、八坂社の御輿渡御は”暴れ御輿”として知られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

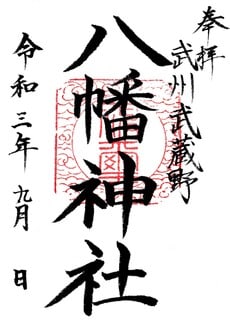
■ 十二社神社
深谷市武蔵野277-3
御祭神:天神七代地神五代の十二柱
旧社格:旧武蔵野村上郷地区鎮守
元別当:寿宝院
授与所:十二社神社(足髙神社社務所に案内あり)
・日本武尊が東征の折、当地にて兵馬・食糧の無事を祈るために創建と伝わります。
・昭和24年、新たな境内を設け旧本殿を移築して御遷座。新しい境内地ながら山林に囲まれ厳かな境内です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:十二社神社 書置(筆書)


■ 泰国山 人見院 一乗寺
深谷市人見1621-2
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:深谷七福神(布袋尊)
・深谷七福神の一寺で布袋尊・ナデシコの寺。
・正応二年(1289年)、人見四郎泰国による開基、一遍上人の開山とされ、鎌倉時代にこの地に勢力を張った武蔵野七党猪俣党の一族、人見氏の菩提寺です。
・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀三尊(六字御名号)


2.深谷七福神 布袋尊

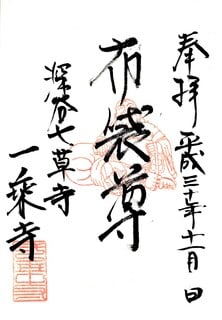
■ 人見山 昌福寺
深谷市人見1391-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
司元別当: 浅間神社(深谷市人見)
札所:
・延文二年(1357年)、深谷城初代城主として山内上杉家の上杉房憲が深谷に入ったのち、父祖の菩提を弔うため仙元山の麓に開基と伝わる曹洞宗の古刹。
・上杉房憲の墓所としても知られています。
・ご住職はお留守でしたが、寺庭さまから書置の御朱印を授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛

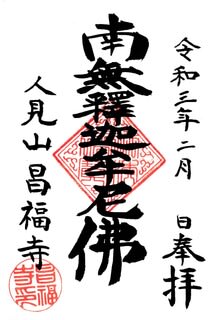
■ 浅間神社
深谷市人見1404
御祭神:木花咲耶姫命
旧社格:郷社
元別当: 人見山 昌福寺(熊谷市人見)
授与所:楡山神社宮司様宅
・標高98mの仙元山の山頂に鎮座する歴史ある浅間神社で、源頼朝が富士の巻狩りの際、その奉賽のために富士本宮から分祀した関八州八社の一社として伝わります。
・また、延文二年(1357年)、深谷城初代城主上杉房憲が昌福寺を開基した折、裏山の仙元山に深谷に入ったのち仙元大菩薩を勧請、後に村内富士講社が富士山本宮より勧請して合祀し、浅間神社と改めたという説もあります。
・深谷城主上杉家、江戸時代の領主・岡田家の篤い尊崇を受けたとされます。
・昭和五年(1930年)、地内の村社・無格社六社を合祀し郷社に列格、戦前には安産の神様として講が組織され、多くの参詣者を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:浅間神社 直書(筆書)

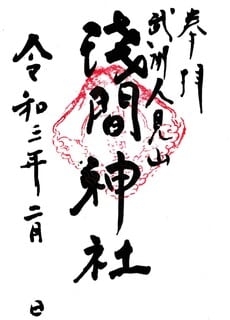
■ 上野台八幡神社
深谷市上野台3168
御祭神:品陀和気命
旧社格:郷社、氏子区域:上野台
元別当:如日山 蓮華院 光厳寺(深谷市上柴町)
授与所:境内
・天文十九年(1550年)、深谷城主上杉氏の家臣、岡谷加賀守清英が、崇敬篤い山城国石清水八幡宮を萱場村に勧請して創祀と伝わります。
・正徳年間(1711-1716年)、時の領主大久保忠義は、村役の嘆願により当地を寄進し萱場村からの御遷座をなしたとされます。
・上野台は、鼠、大台、小台、上宿、中宿、下宿、桜ヶ丘一、同二、泉台の九地区からなり、氏子区域はこの九地区で、多くの境内社はこの氏子区域内からの御遷座とのことです。
・「青天を衝け」にちなんだ御朱印が授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

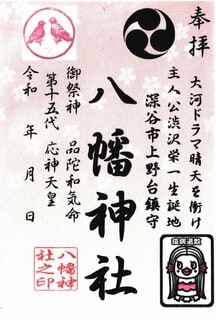


■ 教王山 佛母院 弘光寺
深谷市針ヶ谷1324
真言宗豊山派
御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
司元別当:八幡大神社(深谷市針ヶ谷)
札所:
・天平十七年(745年)、空阿の開基と伝わる古刹で、法院祐尊(応安三年(1370年)寂)を中興開山とします。
・法院祐尊が中興の際、鉢形城主北条氏邦に宛てた書状は貴重な中世文書とされ、深谷市の指定文化財となっています。
・は徳川家光公より三十石の朱印地を得て寺勢興隆し、末寺・配下寺院は75を数えたとされます。
・これほどの名刹で霊場札所となっていないのは不思議な感じもしますが、御本尊・不動明王の御朱印を授与されています。庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 不動明王


■ 八幡大神社
深谷市針ヶ谷258-1
御祭神:品陀和気命、比賣神、神功皇后
旧社格:村社、針ヶ谷鎮守
元別当:教王山 佛母院 弘光寺(深谷市針ヶ谷)
授与所:境内社務所
・社伝によると、天平十七年(745年)で山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請して創建。源頼朝公が伊豆に配流された折、源家再興のため当社を祈願所として定めたと伝わります。
・武蔵風土記等には、「山城国男山八幡宮を移し祀る 文明十一年建営修理」とあります。
・ことに戦時中は武の神として信仰を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡大神社 直書(筆書)


※ 針ヶ谷あたりから少しく足を伸ばすと、近年、人気上昇中の日本神社に参拝できます。
■ 日本神社の御朱印
(本庄市ですが、血洗島 諏訪神社に近いので・・・)
■ 滝瀬山 正法院 立岩寺
本庄市滝瀬1420
天台宗
御本尊:釈迦如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番
・慈覚大師円仁の開山と伝わる古刹。
・寺伝によると、嘉禎三年(1237年)地頭職滝瀬主人正光直の子三郎経氏が父の菩提のため堂宇を建立、父の法名から正法院と号しました。
・長禄三年(1459年)から文明九年(1477年)、古河公方足利成氏と関東管領上杉氏が戦った五十子合戦の折りに、古河公方勢の宿営となり兵火に焼かました。
・以降、草庵として継続し、寛文八年(1668年)ついに伽藍を再興、東叡山寛永寺より立岩寺寺号を賜わり、輪王寺宮一品法親王の寺号授与御達文を拝領、後に比叡山延暦寺の直末となった名刹です。
・「滝瀬の厄除お大師さま」として信仰を集め、正月三日の大祭にはだるま市も開かれて大勢の参詣者で賑わいます。ぼたん園があり、「ぼたん寺」としても知られています。
・御朱印は庫裡にて観音霊場の書置のものを授与いただけました。御本尊御朱印の授与については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番 聖観世音菩薩


■ 心王山 自心院 華蔵寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市横瀬1360
真言宗豊山派
御本尊:金剛界大日如来
司元別当:横瀬神社(深谷市横瀬)
札所:関東八十八箇所第87番、武州路十二支霊場 未(大日如来)
・寺伝によると、建久五年(1194年)新田義重公の三男、兼包公の開基、弘道上人の開山と伝わり、南北朝時代に祐遍和尚が中興、新田家代々の武運長久祈願の道場として知られています。
・大日堂に奉安される檜材寄木造りの胎蔵界大日如来(平安末期作)坐像は、義兼公守護仏と伝わり、大日堂とともに深谷市の有形文化財に指定されています。
・渋沢栄一翁との所縁がふかく、本堂左手には栄一翁お手植の赤松(二代目)があり、寺号額は栄一翁の揮毫とされています。
・10/10の「青天を衝け」の放送で、華蔵寺は栄一翁の生家である「中の家」の菩提寺として紹介されていました。華蔵寺併設の美術館では栄一翁揮毫の書が公開されています。 華蔵寺の御本尊「大日如来」や 華蔵寺が別当を勤めた「横瀬神社」などの揮毫が残り、栄一翁の神仏への信仰の篤さがうかがわれます。(→ こちら)


【写真 上(左)】 子爵澁澤榮一翁御手植の松(昭和二年(1927年)十一月二十二日)
【写真 下(右)】 澁澤榮一の落款がある寺号扁額
・山門、大日堂、薬師堂、毘沙門堂、閻魔堂、鐘楼門、心王殿と並び、伽藍は整っています。
・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第87番 大日如来

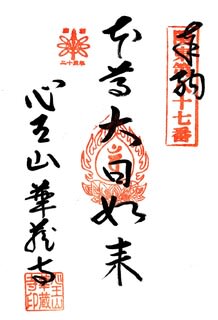
2.武州路十二支霊場(未) 大日如来
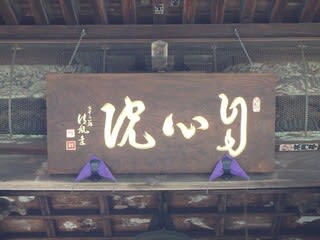
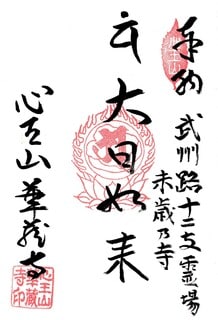
■ 諏訪神社
埼玉県深谷市血洗島117
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:
授与所:拝殿前
・渋沢栄一翁の郷里の鎮守社です。詳細は、→こちら(血洗島 諏訪神社の御朱印)をご覧ください。
〔拝受御朱印〕

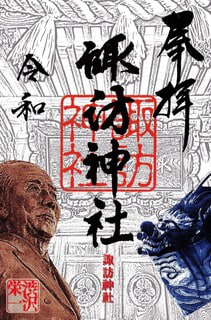
御朱印揮毫:諏訪神社 印刷
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2へつづく
【 BGM 】
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里
■ プラネテス - 黒石ひとみ(Hitomi)
■ Mirai 未来 - kalafina
1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!
さすがに梶浦由記さん
→ コード
以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)
〔最新記事〕
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。
■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)
■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)
-------------------------
〔以下は旧記事へのリンクです〕
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4
大河ドラマ「青天を衝け」、近代もので渋め(?)の主人公にしては視聴率健闘しているようです。
また、先にUPした「血洗島 諏訪神社の御朱印」に多くのアクセスをいただきありがとうございます。
今後、新型コロナの状況がどうなるかわかりませんが、渋沢栄一翁の故郷の地、血洗島(深谷市)へのアプローチで拝受できる御朱印についてとりあげてみます。
(この他にも授与情報があって未拝受の寺社がいくつかあります。拝受次第、追加していきます。)
【エリア概要】
東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。
ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。
---------------------------------
深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。
武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。
平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。
また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。
江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。
宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛したと伝わります。
また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。
江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。
熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたとされています。
また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。
このように古くから栄え、城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。
【深谷・熊谷と札所】
寺院が多く、人流が活発であったので、このエリアは北関東でも有数の霊場エリアとなっています。
観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。
日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。
「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。
三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。
(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)
「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。
また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。
深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。
深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。
幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。
なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。
熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。
有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。
妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。
神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。
----------------------------------------
それでは、関越道「花園」IC周辺から順にご紹介していまきす。
■ 荒澤山 寿楽院
深谷市荒川983
高野山真言宗
御本尊:不動明王
司元別当:天神社(荒川地内)
・由緒は不詳だが、『風土記稿』には「天神社 寿楽院持」とあります。予想以上に広い境内で、道をはさんで立派な聖天宮が御座します。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。ご住職ご不在時は書置対応となる模様。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

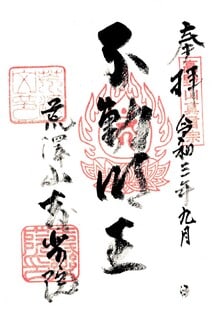
■ 光福山 医王院 長善寺
公式Web
深谷市小前田1452
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所:関東八十八箇所第85番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番
・鉢形城主北条氏邦の三男「光福丸」の菩提寺として知られる古刹で、2つのメジャー霊場の札所として参拝者を集めます。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第85番 大日如来


2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番 聖観世音菩薩

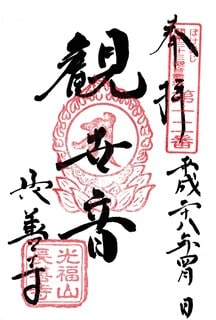
■ 吉祥山 應正寺
深谷市田中608-1
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第30番
・由緒は不詳ですが、入母屋造の立派な本堂と、二層の優れた意匠の観音堂があり、忍秩父三十四観音霊場第30番の札所はこちらの観音堂となっています。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。御本尊の御朱印も授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊 不動明王

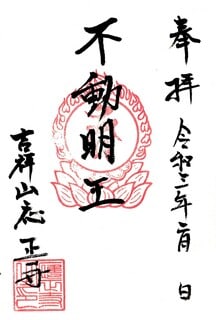
2.忍秩父三十四観音霊場第30番 十一面千手観世音菩薩

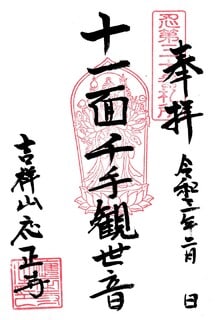
■ 根本山 光明院 正福寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市瀬山141
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東八十八箇所第84番、関東九十一薬師霊場 第35番、武州路十二支霊場 酉(不動明王) ※関東九十一薬師霊場第35番は境外の薬師堂
・永禄年間(1558-1570年)開基、慶長年間(1596-1604年)、重盛法印による開創と伝わる古刹。御本尊の阿弥陀如来は二尺四寸の木彫坐像で、安政二年(1855年)の作と伝わります。
・武州路十二支霊場の札所本尊、不動明王は、板木の記録によると「秀海」という行者が出羽三山へ三十三度尊像を背負って行き来され、霊験あらたかなお不動様として広く信仰され講も組織されたとのこと。
・関東九十一薬師霊場の札所本尊、薬師如来は東側に約600m離れた国道140号パイパス沿いにある境外仏堂の薬師堂(別名:踏鞴堂)に御座。一尺三寸木彫坐像の薬師如来は養老三年(717年)春日仏師一夜作と伝わり、現在の尊像は宝永七年(1710年)造顕とのこと。魔除、厄除、眼病除のお薬師様として広く信仰を集めているそうです。
・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。3つのメジャー霊場の札所だけに手慣れたご対応です。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第84番 阿弥陀如来

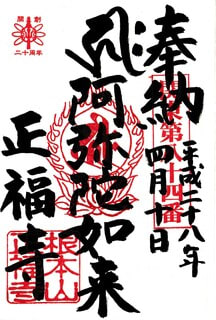
2.武州路十二支霊場(酉) 不動明王


3.関東九十一薬師霊場第35番 薬師如来 〔境外仏堂〕


■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)


公式Web
熊谷市三ケ尻3712
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番
・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。
・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。
・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。
・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。
・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。
〔拝受御朱印〕
1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

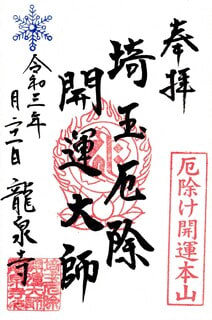
2.関東八十八箇所第83番 不動明王

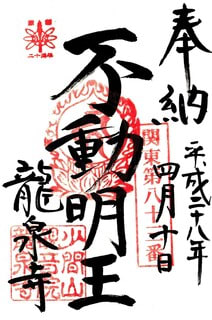
3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩
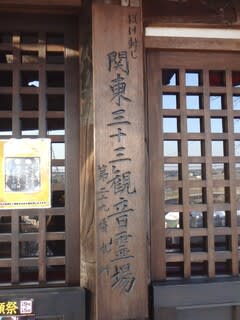
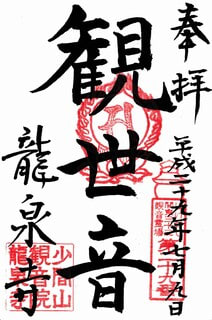
尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。
4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩
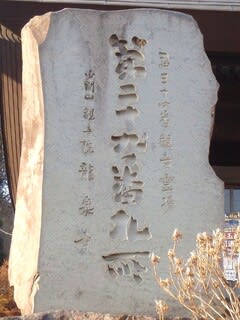
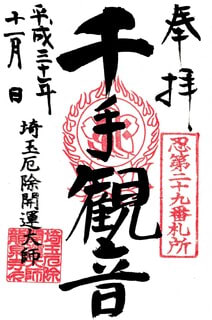
5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩
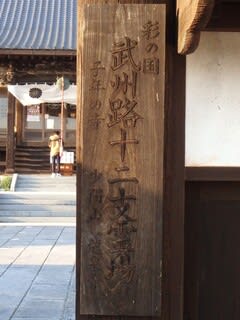

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。
6.「如月 花手水」の御朱印


7.切り絵御朱印

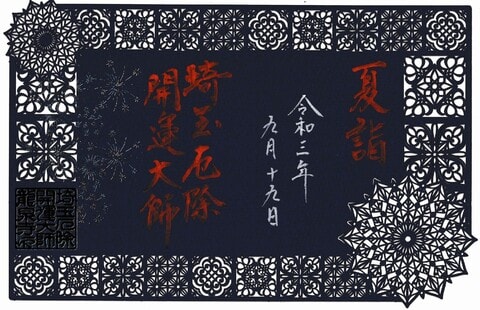
※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。
■ 田中神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命
旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)
元別当:寶珠山 延命寺(熊谷市三ケ尻)
授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所
・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。
・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。
・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。
・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)


■ (三ケ尻)八幡神社
熊谷市三ケ尻2924
御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公
旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守
元別当:
授与所:境内社務所
・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。
・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。
・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

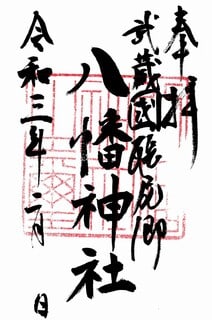
■ 青野山 清浄院 大正寺
熊谷市籠原南1-252
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番
・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。
・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。
奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。
・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。
・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。
・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。
・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

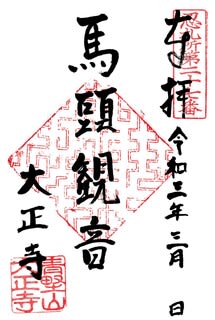
2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王
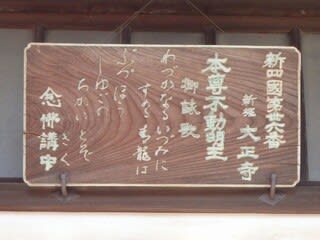
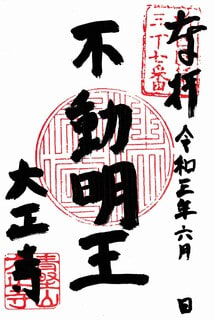

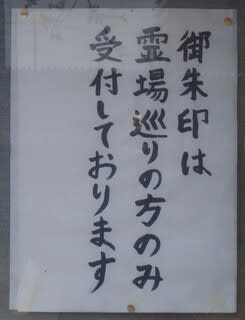
※霊場巡拝者にのみ授与
■ 狗門寺
熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)
真言宗豊山派?
御本尊:
札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番
・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。
・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。
・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。
〔拝受御朱印〕
1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩
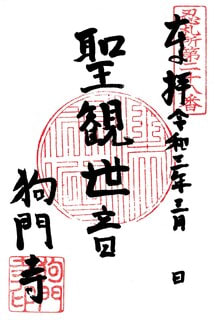
※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)
■ (上柴町)諏訪神社
深谷市上柴町東1-18
御祭神:建御名方命、美穂須須美命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、旧大字柴崎地区鎮守
元別当:月笑院
授与所:楡山神社宮司様宅
・文禄元年(1592年)頃、旧柴崎地区の開発者である柴崎淡路守(深谷城主上杉氏の家臣)の一族が氏神として祀ったことが創祀と伝わる柴崎地区の鎮守社。
・境内に御座す双体道祖神は、県内ではめずらしいものとされています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:諏訪神社 直書(筆書)

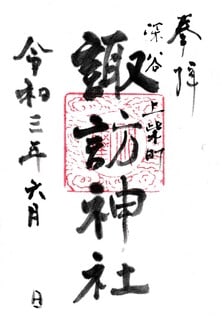
■ 大乗山 正法寺
公式Web
深谷市上柴町東2-2-2
日蓮宗
御本尊:
札所:
・このエリアでは数少ない日蓮宗寺院で、房総・勝浦の松部の地に妙潮寺の末寺として創建、その後、日蓮宗管長、久保田日亀大僧正のお力添えにより深谷に移転されました。
〔拝受御朱印〕
1.御首題

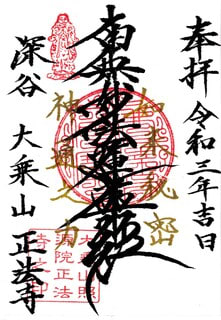
■ 武蔵國八海山神社
深谷市折之口73
御祭神:大己貴命、國常立尊、少彦名命
旧社格:
元別当:
授与所:境内社務所
・比較的新しい神社で、御朱印も快く授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八海山神社 直書(筆書)

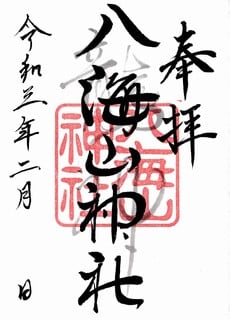
■ 境井山 寶泉寺
深谷市境220-1
曹洞宗
御本尊:
札所:深谷七福神(福禄寿)
・深谷七福神の一寺で福禄寿・キキョウの寺。
・慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いで手柄を立てた旗本吉田与右衛門政景氏は当地境および花園町永田に知行を拝領。人見福昌寺第九世実叟大存大和尚を開山に仰いで当山を建立開基と寺伝にあります。
・深谷七福神の福禄寿は、本堂手前左手に御座。
・七福神の御朱印は本堂内にて直書いただけましたが、御本尊の御朱印は授与されていないそうです。
〔拝受御朱印〕
1.深谷七福神(福禄寿)


※御本尊の御朱印は不授与
■ 大谷山 地蔵院 宝積寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市大谷114
真言宗豊山派
御本尊:五智如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番、武州路十二支霊場 戌(阿弥陀如来)
・応永年間(1394-1428年)、地蔵菩薩を御本尊として盛谷山地蔵院宝錫寺と号し源照法印が開創。天正十年(1582年)、住職重任和尚が伽藍を整備され、五智如来を奉安されて、大谷山宝積寺と改称して中興と伝わる古刹。
・五智如来とは、大日如来が備えられる5つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智)を象徴する金剛界の五如来(いわゆる金剛界五仏)。
中尊(中央)は法界体性智の大日如来。東方は大円鏡智の阿しゅく如来ないし薬師如来、南方は平等性智の宝生如来、西方は妙観察智の阿弥陀如来、北方は成所作智の不空成就如来でそれぞれ象徴されます。(各尊格は宗派等により異なるようです。)
・関東三十三観音と武州路十二支霊場のふたつの現役霊場の札所を務められ、貴重な五智如来の御朱印も授与いただけます。御朱印は原則書き置きのようです。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 五智如来

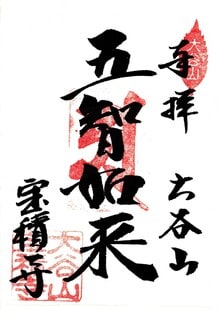
2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番 光明観世音菩薩


3.武州路十二支霊場(戌) 阿弥陀如来

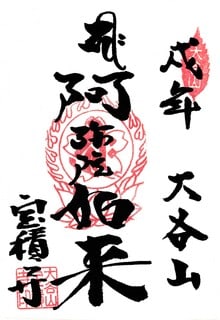
■ 足髙神社
深谷市武蔵野3283
御祭神:大物主之大神
旧社格:(氏子区域:旧武蔵野村下郷地区(旧猿喰土村))
元別当:地内観音寺→橋本家→高野家
授与所:境内社務所に案内あり
・既に室町末期には鉢形城主北条氏邦により、領内鬼門鎮護として奉祀されていたとされ、祭礼時、氏邦が神饌を奉るために使った膳が足高であったため、現社号になったと伝わります。
・通常は非駐在のようですが、社務所に掲出の連絡先にTELすると、書置の御朱印をお持ちいただけます。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:足髙神社 書置(筆書)

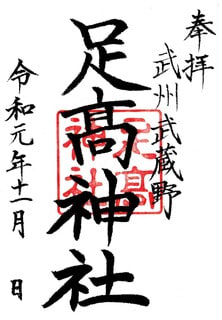
■ (武蔵野)八幡神社
深谷市武蔵野1862
御祭神:誉田別命
旧社格:旧武蔵野村中郷地区鎮守
元別当:常光寺(武蔵野)
授与所:足髙神社(足髙神社社務所に案内あり)
・鎌倉街道(県道小前田・児玉線)沿いに御鎮座の八幡神社。境内社、八坂社の御輿渡御は”暴れ御輿”として知られています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

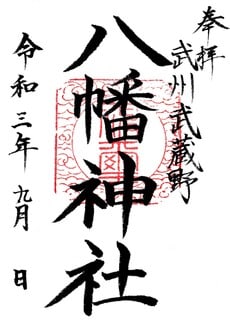
■ 十二社神社
深谷市武蔵野277-3
御祭神:天神七代地神五代の十二柱
旧社格:旧武蔵野村上郷地区鎮守
元別当:寿宝院
授与所:十二社神社(足髙神社社務所に案内あり)
・日本武尊が東征の折、当地にて兵馬・食糧の無事を祈るために創建と伝わります。
・昭和24年、新たな境内を設け旧本殿を移築して御遷座。新しい境内地ながら山林に囲まれ厳かな境内です。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:十二社神社 書置(筆書)


■ 泰国山 人見院 一乗寺
深谷市人見1621-2
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:深谷七福神(布袋尊)
・深谷七福神の一寺で布袋尊・ナデシコの寺。
・正応二年(1289年)、人見四郎泰国による開基、一遍上人の開山とされ、鎌倉時代にこの地に勢力を張った武蔵野七党猪俣党の一族、人見氏の菩提寺です。
・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 阿弥陀三尊(六字御名号)


2.深谷七福神 布袋尊

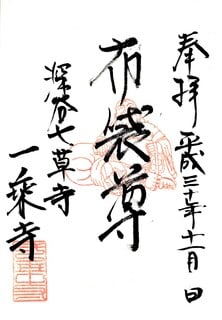
■ 人見山 昌福寺
深谷市人見1391-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
司元別当: 浅間神社(深谷市人見)
札所:
・延文二年(1357年)、深谷城初代城主として山内上杉家の上杉房憲が深谷に入ったのち、父祖の菩提を弔うため仙元山の麓に開基と伝わる曹洞宗の古刹。
・上杉房憲の墓所としても知られています。
・ご住職はお留守でしたが、寺庭さまから書置の御朱印を授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛

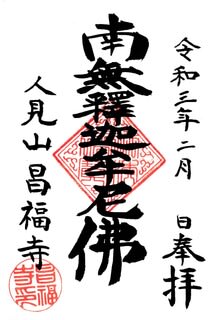
■ 浅間神社
深谷市人見1404
御祭神:木花咲耶姫命
旧社格:郷社
元別当: 人見山 昌福寺(熊谷市人見)
授与所:楡山神社宮司様宅
・標高98mの仙元山の山頂に鎮座する歴史ある浅間神社で、源頼朝が富士の巻狩りの際、その奉賽のために富士本宮から分祀した関八州八社の一社として伝わります。
・また、延文二年(1357年)、深谷城初代城主上杉房憲が昌福寺を開基した折、裏山の仙元山に深谷に入ったのち仙元大菩薩を勧請、後に村内富士講社が富士山本宮より勧請して合祀し、浅間神社と改めたという説もあります。
・深谷城主上杉家、江戸時代の領主・岡田家の篤い尊崇を受けたとされます。
・昭和五年(1930年)、地内の村社・無格社六社を合祀し郷社に列格、戦前には安産の神様として講が組織され、多くの参詣者を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:浅間神社 直書(筆書)

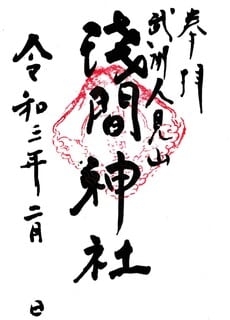
■ 上野台八幡神社
深谷市上野台3168
御祭神:品陀和気命
旧社格:郷社、氏子区域:上野台
元別当:如日山 蓮華院 光厳寺(深谷市上柴町)
授与所:境内
・天文十九年(1550年)、深谷城主上杉氏の家臣、岡谷加賀守清英が、崇敬篤い山城国石清水八幡宮を萱場村に勧請して創祀と伝わります。
・正徳年間(1711-1716年)、時の領主大久保忠義は、村役の嘆願により当地を寄進し萱場村からの御遷座をなしたとされます。
・上野台は、鼠、大台、小台、上宿、中宿、下宿、桜ヶ丘一、同二、泉台の九地区からなり、氏子区域はこの九地区で、多くの境内社はこの氏子区域内からの御遷座とのことです。
・「青天を衝け」にちなんだ御朱印が授与されています。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

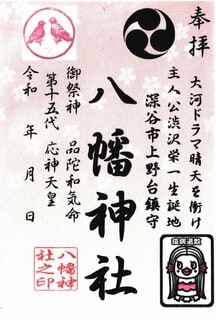


■ 教王山 佛母院 弘光寺
深谷市針ヶ谷1324
真言宗豊山派
御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
司元別当:八幡大神社(深谷市針ヶ谷)
札所:
・天平十七年(745年)、空阿の開基と伝わる古刹で、法院祐尊(応安三年(1370年)寂)を中興開山とします。
・法院祐尊が中興の際、鉢形城主北条氏邦に宛てた書状は貴重な中世文書とされ、深谷市の指定文化財となっています。
・は徳川家光公より三十石の朱印地を得て寺勢興隆し、末寺・配下寺院は75を数えたとされます。
・これほどの名刹で霊場札所となっていないのは不思議な感じもしますが、御本尊・不動明王の御朱印を授与されています。庫裡にて直書のものを拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.御本尊の御朱印 不動明王


■ 八幡大神社
深谷市針ヶ谷258-1
御祭神:品陀和気命、比賣神、神功皇后
旧社格:村社、針ヶ谷鎮守
元別当:教王山 佛母院 弘光寺(深谷市針ヶ谷)
授与所:境内社務所
・社伝によると、天平十七年(745年)で山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請して創建。源頼朝公が伊豆に配流された折、源家再興のため当社を祈願所として定めたと伝わります。
・武蔵風土記等には、「山城国男山八幡宮を移し祀る 文明十一年建営修理」とあります。
・ことに戦時中は武の神として信仰を集めたと伝わります。
〔拝受御朱印〕
御朱印揮毫:八幡大神社 直書(筆書)


※ 針ヶ谷あたりから少しく足を伸ばすと、近年、人気上昇中の日本神社に参拝できます。
■ 日本神社の御朱印
(本庄市ですが、血洗島 諏訪神社に近いので・・・)
■ 滝瀬山 正法院 立岩寺
本庄市滝瀬1420
天台宗
御本尊:釈迦如来
札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番
・慈覚大師円仁の開山と伝わる古刹。
・寺伝によると、嘉禎三年(1237年)地頭職滝瀬主人正光直の子三郎経氏が父の菩提のため堂宇を建立、父の法名から正法院と号しました。
・長禄三年(1459年)から文明九年(1477年)、古河公方足利成氏と関東管領上杉氏が戦った五十子合戦の折りに、古河公方勢の宿営となり兵火に焼かました。
・以降、草庵として継続し、寛文八年(1668年)ついに伽藍を再興、東叡山寛永寺より立岩寺寺号を賜わり、輪王寺宮一品法親王の寺号授与御達文を拝領、後に比叡山延暦寺の直末となった名刹です。
・「滝瀬の厄除お大師さま」として信仰を集め、正月三日の大祭にはだるま市も開かれて大勢の参詣者で賑わいます。ぼたん園があり、「ぼたん寺」としても知られています。
・御朱印は庫裡にて観音霊場の書置のものを授与いただけました。御本尊御朱印の授与については不明です。
〔拝受御朱印〕
1.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番 聖観世音菩薩


■ 心王山 自心院 華蔵寺
武州路十二支本尊霊場会のWeb
深谷市横瀬1360
真言宗豊山派
御本尊:金剛界大日如来
司元別当:横瀬神社(深谷市横瀬)
札所:関東八十八箇所第87番、武州路十二支霊場 未(大日如来)
・寺伝によると、建久五年(1194年)新田義重公の三男、兼包公の開基、弘道上人の開山と伝わり、南北朝時代に祐遍和尚が中興、新田家代々の武運長久祈願の道場として知られています。
・大日堂に奉安される檜材寄木造りの胎蔵界大日如来(平安末期作)坐像は、義兼公守護仏と伝わり、大日堂とともに深谷市の有形文化財に指定されています。
・渋沢栄一翁との所縁がふかく、本堂左手には栄一翁お手植の赤松(二代目)があり、寺号額は栄一翁の揮毫とされています。
・10/10の「青天を衝け」の放送で、華蔵寺は栄一翁の生家である「中の家」の菩提寺として紹介されていました。華蔵寺併設の美術館では栄一翁揮毫の書が公開されています。 華蔵寺の御本尊「大日如来」や 華蔵寺が別当を勤めた「横瀬神社」などの揮毫が残り、栄一翁の神仏への信仰の篤さがうかがわれます。(→ こちら)


【写真 上(左)】 子爵澁澤榮一翁御手植の松(昭和二年(1927年)十一月二十二日)
【写真 下(右)】 澁澤榮一の落款がある寺号扁額
・山門、大日堂、薬師堂、毘沙門堂、閻魔堂、鐘楼門、心王殿と並び、伽藍は整っています。
・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。
〔拝受御朱印〕
1.関東八十八箇所第87番 大日如来

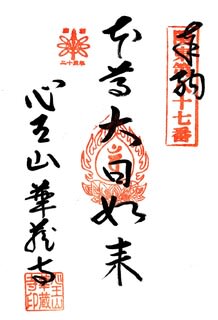
2.武州路十二支霊場(未) 大日如来
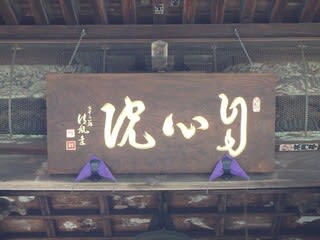
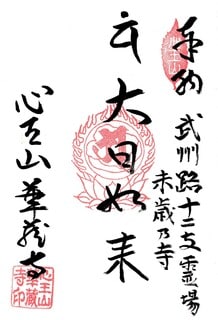
■ 諏訪神社
埼玉県深谷市血洗島117
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社
元別当:
授与所:拝殿前
・渋沢栄一翁の郷里の鎮守社です。詳細は、→こちら(血洗島 諏訪神社の御朱印)をご覧ください。
〔拝受御朱印〕

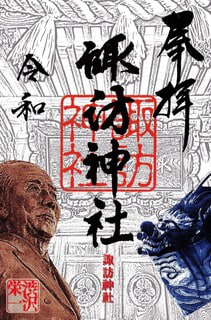
御朱印揮毫:諏訪神社 印刷
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2へつづく
【 BGM 】
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里
■ プラネテス - 黒石ひとみ(Hitomi)
■ Mirai 未来 - kalafina
1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!
さすがに梶浦由記さん
→ コード
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 4.目黄不動尊(最勝寺)
※ 現在、新型コロナウイルス感染拡大を受け、外出自粛が要請されています。また、寺社様によっては御朱印授与を休止されている可能性があります。ご留意願います。
こちらからつづく
■ 牛宝山 明王院 最勝寺〔目黄不動尊 / 江戸五色不動〕
江戸川区平井1-25-32(墨田区東駒形から移転)
天台宗
御本尊:釈迦如来・不動明王(目黄不動尊)
札所:江戸五色不動(目黄不動尊)、関東三十六不動霊場第19番、隅田川二十一ヵ所霊場第7番、新葛西三十三観音霊場第23番
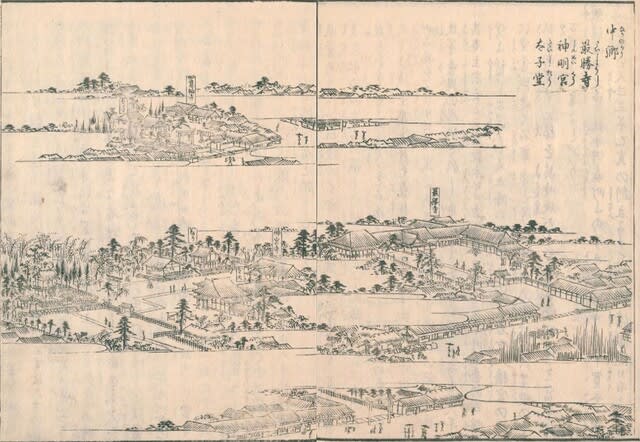
「中郷 最勝寺 神明宮 太子堂 / 江戸名所図会7巻[18]」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
天台宗東京教区Web、江戸川区史(第三巻)、江戸川区の文化財1集、同5集、および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などを参考に由緒、変遷などをまとめてみます。
〔最勝寺の縁起と変遷〕
最勝寺の縁起変遷は牛島の牛御前社や本所表町の東栄寺ともかかわる複雑なもので、長くなりますが適宜、寄り道をしてみます。
貞観二年(860年)、慈覚大師円仁が東国巡錫のみぎり隅田河畔の向島で釈迦如来と大日如来を手ずから刻まれ、これを本尊として一寺を建立したのが草創とされます。
慈覚大師は草創時に、郷土の守護として須佐之男命を勧請して牛御前社(現・牛嶋神社)に祀り、御本尊の大日如来を牛御前社の本地仏とされたといいます。
慈覚大師の高弟・良本阿闍梨は、元慶元年(877年)に寺構を整えて開山となり、「牛宝山」
と号しました。
江戸時代になってから本所表町(現・墨田区東駒形)に移転。
維新にいたるまで牛御前社(現・牛嶋神社)の別当をつとめたとされます。
本所表町(東駒形)の本寺には浅草寺参詣の人々が多く立ち寄ったほか、将軍家の鷹狩りの際にはしばしば立ち寄られて「仮の御殿」が置かれ「御殿山」と称されたといいます。
明治初年の神仏分離地に廃寺となった末寺の明王山 東栄寺から御本尊の目黄不動尊と二童子が遷られました。
大正2年(1913年)、隅田川の駒形橋架橋にともなう区画整理により現在地に移転、以降も江戸五色不動の「目黄不動尊」として信仰を集めます。
〔目黄不動尊の縁起と変遷〕
天台宗東京教区Webには以下のとおりあります。
「この不動明王像(目黄不動尊像)は、天平年間(729-766年)に良弁僧都(東大寺初代別当)が東国巡錫の折りに隅田川のほとりで不動明王を感得され、自らその御姿をきざまれたものであり、同時に一宇の堂舎を建立された。」
この由緒ある不動尊像は、最勝寺の末寺で本所表町にあった東栄寺の御本尊として奉られ、ことに将軍家光公の崇拝篤かったとされます。
家光公の治世、江戸府内に五色不動の霊場が設けられましたが、この時に「目黄不動」と称され、江戸の町を守護する不動尊として広く信仰されました。
明治の神仏分離により東栄寺は廃寺となり、本尊の不動明王像は本寺である駒形の最勝寺に遷座され、これより当寺は「明王院」と号します。
大正2年(1913年)、最勝寺の移転とともに「目黄不動尊」は駒形から現在地に移転し今日に至ります。
『関東三十六不動霊場ガイドブック』には「徳川氏の入府により、この良弁僧正御作の不動尊は、将軍家の信仰するところとなった。殊に三代将軍家光公の崇拝は篤く、仏教の大意に基づいて府内に五色不動(江戸五色不動)の霊場をもうけ、方位によって配置し、江戸城と江戸に入る街道の守護を祈願した。この時に本像が『目黄不動』と名付けられ、家光によって江戸の鬼門除けを祈願された。また『目黄』とは五色不動の中の中心的な意を持つ由緒あるものである。」とあります。
******************
〔日本最古の不動明王について〕
ここで気になったのは、「目黄不動」が天平年間(729-766年)、良弁僧都による謹刻という点です。
こちら(京都じっくり観光)のサイトによると、木造五大明王像(教王護国寺(東寺)講堂安置)は承和六年(839年)完成で日本最古の不動明王像とされています。
しかし『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)には「高野山南院の不動尊の木彫立像(浪切不動尊)は、寺伝によると、弘法大師が長安にあるとき、恵果阿闍梨から木材を与えられて自分で彫刻して、阿闍梨に開眼加持をしてもらった。」とあります。
弘法大師の長安入りは804年の12月、806年3月に長安を立たれているので、この浪切不動尊の造立は、遅くとも806年ということになり、東寺講堂の不動尊(839年)よりも早いことになります。( → 高野山南院の資料
Wikipediaによると、不動明王が説かれている大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の成立は7世紀、漢訳は724年とされています。
『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)によると、『不空羂索神変真言経』第九巻に「北面、西より第一は不動使者なり。左手に羂索を執り、右手に剣を持ち結跏趺坐す。」と記されているそうです。
『不空羂索神変真言経』は菩提流志の漢訳経が伝わっており、菩提流支(ぼだいるし)は、北インド出身の訳経僧で没年は527年とされます。
良弁僧都の生年は689-774年なので、上記より晩年にはすでに不動明王に関連する不空羂索神変真言経や大日経の漢訳は成されていることになります。
良弁僧都は天平勝宝4年(751年)、華厳宗大本山東大寺の初代別当となられていますが、その時点での華厳宗と不動明王を結びつける史料がみつかりません。
弘法大師空海は、弘仁元年(810年)に東大寺の別当に就任され、山内に真言院を建立されたと伝わります。
また、毘盧遮那仏(大仏)の前で毎朝あげられるお経は「理趣経」で、弘法大師空海の影響を伝えるものとして広く知られています。
ただし、良弁僧都の没年は774年、弘法大師空海の生年も774年なので、良弁僧都が弘法大師将来の純密系の不動明王を感得されたということは考えにくいです。
ただし、日本にはそれ以前に雑密が入ってきており、その流れのなかで不動明王が将来されていた可能性はあるのかもしれません。(参考 → 『純密と雑密』(三崎良周氏))
『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、天平年間(729-766年)、良弁僧都が東国を巡錫した折、隅田川のほとりの大樹のもとで休んでいると、夢に不動明王があらわれ「わが姿を三体刻み、一体をここに安置せよ」との霊告を得たためみずから御影を刻まれ御本尊とされました。
また、相模国の大山不動はこの内の一体であり、当寺の不動尊像と同木同作とあります。
もう一体は大山不動とゆかりが深く、良弁作の不動尊を御本尊とする埼玉・越谷の真大山 大聖寺の大相模不動尊なのかもしれません。
■ 大山不動尊(雨降山 大山寺)/神奈川県伊勢原市 真言宗大覚寺派
「晩年に大山に登られ、石像の不動明王を感得、謹刻。大山寺第三世は弘法大師が入られる。」(『関東三十六不動霊場ガイドブック』)
■ 大相模不動尊(真大山 大聖寺)/埼玉県越谷市 真言宗豊山派
「(西方村)不動堂 縁起ノ畧ニ往古良辨僧正相州大山開闢ノ時面ノアタリ 不動ノ霊容ヲ拝シ 其尊像ヲ刻マントテ 先其木ノ根本ヲモテ一刀三禮シ一像を彫刻シ 是ヲ大山根本不動ト名付ク」(『新編武蔵風土記稿 巻之205 埼玉群郡之7』(国会図書館DC))

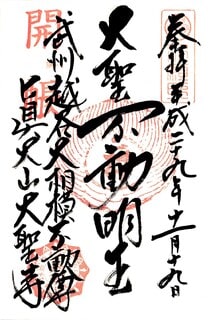
【写真 上(左)】 大山不動尊(雨降山 大山寺)の御朱印
【写真 下(右)】 大相模不動尊(真大山 大聖寺)の御朱印(酉年御開帳)
上記のほか、関東三十六不動霊場の札所に限っても、良弁僧都御作と伝わる不動明王は第15番の中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺)、第22番浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院)、第23番橋場不動尊(砂尾山 橋場寺)にみられます。
第17番等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院)は役小角(634-701年伝)御作、第10番の田無山 総持寺の不動尊は行基菩薩(668-749年)御作と伝わるので、最古の不動尊を辿るのは容易いことではないと思います。
******************
廃寺となった本所表町の東栄寺について、『寺社書上(御府内備考). [92] 本所寺社書上 五』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「本尊不動尊 丈四尺岩座四尺 作人不知 火焔八尺●寸」「二童子 作不知 丈●尺九寸」「御腹●●不動尊 丈二寸五● 座火焔●六寸 良辨僧正之作 但シ厨子入」
御本尊の不動尊は”作人不知”ですが、別尊の不動尊は”良辨僧正之作”となっています。
今となっては詳細は不明ですが、”良辨僧正之作”の「別尊の不動尊」が目黄不動尊なのかもしれません。
明治23年(1890年)刊の東京名所図会(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「同所表町に在り天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王は良弁僧都の作なり 当寺往古は牛御前の別当寺にして貞観年間慈覚大師の草創良本阿闍梨開山たり 寛永年間将軍家屡々此邊に遊猟せられしを以て当寺に仮殿●を営構せしと云へり 今尚ほ御殿跡と称する所ありとぞ」
明治23年時点において、良弁僧都作の不動明王(目黄不動尊)が御本尊として御座されていたことがわかります。
ただし、天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「牛寶山 最勝寺 明王院と号す 同●表町にあり天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王の像ハ良辨僧都の作なり 当寺ハ牛御前の別当寺にして貞観二年庚辰慈覚大師草創良本阿闍梨開山なり 寛永年間 大樹 此辺御遊猟の頃屢(しばしば)当寺へ入御あらせられしより其頃ハ假の御殿抔(など)営構なり●れたりとせり 今も御殿あとと称する地に山王権現を勧清す」
天保五-七年の時点ですでに「明王院」を号し、「良辨僧都作の不動明王」を御本尊としていたという記述は、他の資料と符合せずナゾが残ります。(ただし「明王院」は本所移転時に号したという説もあり。)
******************
最勝寺がかつて牛島の牛御前社(現在の牛嶋神社)の別当であったことは、複数の史料から裏付けられます。
天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「牛島神明宮 同●に並ぶ相伝ふ貞観年間の鎮座なりと別当を神宮寺と称して最勝寺より兼帯す 江戸名所記云 安徳帝の壽永年間本所の郷民夢をえて 伊勢大神宮虚空よりけり大光明の内に微妙の御声にて●●土安穏天人常充満と云 法義経壽量品の文を唱へ●いられ伊勢の大神宮なりとの●●ふところ夢覚なり●中の人民●に僧(中略)伊勢の御神を勧清し」


【写真 上(左)】 牛嶋神社
【写真 下(右)】 牛嶋神社の御朱印
新編武蔵風土記稿 巻之21 葛飾郡之2(国会図書館DC)には以下の記述があります。
「牛御前社 本所及牛嶋ノ鎮守ナリ 北本所表町最勝寺持 祭神素盞嗚尊ハ束帯坐像ノ画幅ナリ 王子権現ヲ相殿トス 本地大日ハ慈覚大師ノ作縁起アリ信シカタキ●多シ 其畧ニ、貞観二年慈覚大師当國弘通ノ時行暮テ傍ノ草庵ニ入シニ位冠セシ老翁アリ 云國土惱乱アラハワレ首ニ牛頭ヲ戴キ悪魔降伏ノ形相ヲ現シ國家を守護セントス 故ニ我形を写シテ汝ニ与ヘン我タメニ一宇ヲ造立セヨトテ去レリ コレ当社ノ神体ニテ老翁ハ神素盞嗚尊ノ権化ナリ 牛頭ヲ戴テ守護シ賜ハントノ誓ニマカセテ牛御前ト号シ 弟子良本ヲ留メテコノ像ヲ守ラシメ 本地大日ノ像ヲ作リ釋迦ノ石佛ヲ彫刻シテコレヲ留メ 大師ハ登山セリ 良本コレヨリ明王院ト号シ 牛御前ヲ渇仰シ 法華千部ヲ読誦シテ大師ノ残セル石佛ノ釋迦ヲ供養佛トス 其後人皇五十七代陽成院ノ御宇 清和天皇第七ノ皇子故有テ当國ニ遷され、元慶元年九月十五日当所ニ於テ薨セラレシヲ、良本崇ヒ社傍ニ葬シ参ラセ其霊ヲ相殿ニ祀レリ 今ノ王子権現是ナリ 治承四年源頼朝諸軍ヲ引率シ下総國ニ至ル時ニ 隅田川洪水陸地ニ漲リ渡ルヘキ便ナカリシニ 千葉介常胤当社ニ祈誓シ船筏ヲ設ケ大軍恙ナク渡リシカバ 頼朝感シテ明ル養和元年再ヒ社領ヲ寄附セシヨリ、代々國主領主ヨリモ神領ヲ附セラル 天文七年六月廿八日後奈良院牛御前ト勅号ヲ賜ヒ次第ニ氏子繁栄セリ 北條家ヨリモ神領免除ノ文書及神寶ヲ寄ス其目後ニ出ス 又建長年中浅草川ヨリ牛鬼ノ如キ異形ノモノ飛出シ 嶼中ヲ走セメクリ当社ニ飛入忽然トシテ行方ヲ知ラス 時ニ社壇ニ一ツノ玉ヲ落セリ 今社寶牛玉是ナリナト記シタレド 奮キコトナレハ慥(タシカ)ナラサルコト多シ」
内容がやや錯綜していますが、牛御前社と最勝寺は、慈覚大師ゆかりの寺社として草創時からふかいつながりをもっていたことが伺われます。
************************
最寄りはJR総武線「平井」駅南口から徒歩約16分(1.3㎞)です。
地図上では近くみえますが、意外に距離があります。
住所は江戸川区平井1丁目、荒川の流れにもほど近いところです。
すぐそばにある嘉桂山 成就寺も本所からの移転で、こちらも天台宗で慈覚大師ゆかりの寺院です。新葛西三十三観音霊場初番、大東京百観音霊場第96番の札所で、御本尊、阿弥陀如来の御朱印を拝受できました。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標-1
三間一戸の八脚門から屋根をとり、門柱を加えたような変わった山門(仁王門)で、両脇間には仁王尊が御座します。
本所にあった頃は三重建築の仁王門があり、朱塗りの色が美しく「赤門寺」と称されたそうです。
山門左手の寺号標には「南無妙法蓮華経 南無釋迦牟尼仏 南無阿弥陀仏」が併記されていますが、この様式の石碑はあまりみたことがありません。


【写真 上(左)】 寺号標-2
【写真 下(右)】 山内
広がりのある山内。正面に本堂、その右手に客殿と庫裡、その手前右手に不動堂、さらにその手前右に地蔵観音堂と最勝稲荷社。わかりやすく整った伽藍配置です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は入母屋像本瓦葺流れ向拝の堂々たるつくり。さすがに名刹です。
水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「牛寶山」の扁額を掲げています。
本堂にはおそらく御本尊の慈覚大師作の釈迦如来が御座します。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 客殿
本堂右手の客殿も破風屋根を構える風格あるつくり。


【写真 上(左)】 客殿と不動堂
【写真 下(右)】 不動堂


【写真 上(左)】 斜めからの不動堂
【写真 下(右)】 側面からの不動堂
不動堂は楼閣様式ですが、不勉強につき正確なつくりはわかりません。
向拝には水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「不動尊」の扁額を掲げています。
全体に本堂よりも複雑な意匠です。


【写真 上(左)】 不動堂向拝
【写真 下(右)】 不動堂向拝上部


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 不動堂賽銭箱の意匠
不動堂には良弁僧都作とされる不動明王(目黄不動尊)が御座され、こちらも御本尊の位置づけにあるようです。
この目黄不動尊像は、都内では高幡不動尊に次ぐほどの大きな像(像高127㎝)で、「木造不動明王坐像」として江戸川区の登録有形文化財(彫刻)に指定されています。
迦楼羅炎の勢いすさまじく、右手に剣、左手に羂索を掲げられ盤石のうえに御座され、二童子を従えています。


【写真 上(左)】 目黄不動明王の石標
【写真 下(右)】 関東三十六不動霊場札所標と本堂
慈覚大師作とされ、牛御前社の本地仏であった大日如来像は、不動堂に安置されているようです。


【写真 上(左)】 地蔵観音堂
【写真 下(右)】 最勝稲荷社
最勝稲荷社は牛御前社より御遷座と伝わり、家屋守護に霊験あらたかとのことです。
墓地には鳥亭焉馬(戯作者)、富田木歩(俳人)、柔道家徳三宝夫妻の墓があります。
御朱印は庫裡にて拝受できます。
関東三十六不動霊場の札所でもあり、手慣れたご対応です。
なお、隅田川二十一ヵ所霊場第7番、新葛西三十三観音霊場第23番の御朱印は授与されていない模様です。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目黄不動尊 江戸五色不動の印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動霊場第19番の御朱印〕


【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:目黄不動尊 関東三十六不動霊場第19番印判 法挟護童子の印判
************************
これで、現行の江戸五色不動のご紹介はとりあえず完結です。
関連して、以下のお不動さまについてもつづきで書きたいと思いますが、しばらく時間をおきます。
7.古碧山 龍巌寺 / 目黄不動尊
渋谷区神宮前2-3-8(墨田区東駒形から移転)
臨済宗南禅寺派 御本尊:釈迦如来
8.五大山 不動院 / 目黄不動尊
港区六本木3-15-4
高野山真言宗 御本尊:不動明王
9.石神井不動尊(亀頂山 密乗院 三寶寺)
練馬区石神井台1-15-6
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第11番
10.志村不動尊(寶勝山 蓮光寺 南蔵院)
板橋区蓮沼町48-8
真言宗智山派 御本尊:十一面観世音菩薩、不動明王
関東三十六不動霊場第12番
11.中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺)
中野区中央2-33-3
真言宗豊山派 御本尊:不動明王(五大明王)
関東三十六不動霊場第15番
12.等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院)
世田谷区等々力1-22-47
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第17番
13.深川不動尊/深川不動堂(成田山 新勝寺 東京別院)
江東区富岡1-17-13
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第20番
14.薬研堀不動尊/薬研堀不動院(川崎大師 東京別院)
中央区東日本橋2-6-8
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第21番
15.浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院)
台東区寿2-5-2
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第22番
16.橋場不動尊(砂尾山 橋場寺)
台東区橋場2-14-19
天台宗 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第23番
17.飛不動尊(龍光山 三高寺 正寶院)
台東区竜泉3-11-11
天台宗寺門系 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第24番
18.皿沼不動尊(皿沼山 永昌院)
足立区皿沼1-4-2
天台宗寺門系 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第25番
19.西新井大師不動明王(五智山 遍照院 總持寺)
足立区西新井1-15-1
真言宗豊山派 御本尊:弘法大師・十一面観世音菩薩
関東三十六不動霊場第26番
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 2.目黒不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊、4.目赤不動尊、5.目黄不動尊(永久寺)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 6.目黄不動尊(最勝寺)
こちらからつづく
■ 牛宝山 明王院 最勝寺〔目黄不動尊 / 江戸五色不動〕
江戸川区平井1-25-32(墨田区東駒形から移転)
天台宗
御本尊:釈迦如来・不動明王(目黄不動尊)
札所:江戸五色不動(目黄不動尊)、関東三十六不動霊場第19番、隅田川二十一ヵ所霊場第7番、新葛西三十三観音霊場第23番
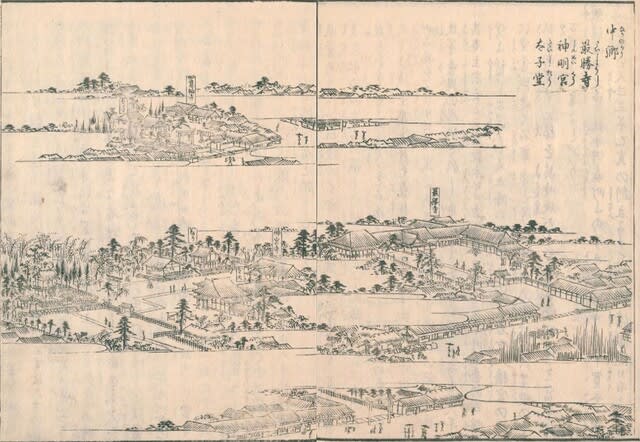
「中郷 最勝寺 神明宮 太子堂 / 江戸名所図会7巻[18]」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
天台宗東京教区Web、江戸川区史(第三巻)、江戸川区の文化財1集、同5集、および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などを参考に由緒、変遷などをまとめてみます。
〔最勝寺の縁起と変遷〕
最勝寺の縁起変遷は牛島の牛御前社や本所表町の東栄寺ともかかわる複雑なもので、長くなりますが適宜、寄り道をしてみます。
貞観二年(860年)、慈覚大師円仁が東国巡錫のみぎり隅田河畔の向島で釈迦如来と大日如来を手ずから刻まれ、これを本尊として一寺を建立したのが草創とされます。
慈覚大師は草創時に、郷土の守護として須佐之男命を勧請して牛御前社(現・牛嶋神社)に祀り、御本尊の大日如来を牛御前社の本地仏とされたといいます。
慈覚大師の高弟・良本阿闍梨は、元慶元年(877年)に寺構を整えて開山となり、「牛宝山」
と号しました。
江戸時代になってから本所表町(現・墨田区東駒形)に移転。
維新にいたるまで牛御前社(現・牛嶋神社)の別当をつとめたとされます。
本所表町(東駒形)の本寺には浅草寺参詣の人々が多く立ち寄ったほか、将軍家の鷹狩りの際にはしばしば立ち寄られて「仮の御殿」が置かれ「御殿山」と称されたといいます。
明治初年の神仏分離地に廃寺となった末寺の明王山 東栄寺から御本尊の目黄不動尊と二童子が遷られました。
大正2年(1913年)、隅田川の駒形橋架橋にともなう区画整理により現在地に移転、以降も江戸五色不動の「目黄不動尊」として信仰を集めます。
〔目黄不動尊の縁起と変遷〕
天台宗東京教区Webには以下のとおりあります。
「この不動明王像(目黄不動尊像)は、天平年間(729-766年)に良弁僧都(東大寺初代別当)が東国巡錫の折りに隅田川のほとりで不動明王を感得され、自らその御姿をきざまれたものであり、同時に一宇の堂舎を建立された。」
この由緒ある不動尊像は、最勝寺の末寺で本所表町にあった東栄寺の御本尊として奉られ、ことに将軍家光公の崇拝篤かったとされます。
家光公の治世、江戸府内に五色不動の霊場が設けられましたが、この時に「目黄不動」と称され、江戸の町を守護する不動尊として広く信仰されました。
明治の神仏分離により東栄寺は廃寺となり、本尊の不動明王像は本寺である駒形の最勝寺に遷座され、これより当寺は「明王院」と号します。
大正2年(1913年)、最勝寺の移転とともに「目黄不動尊」は駒形から現在地に移転し今日に至ります。
『関東三十六不動霊場ガイドブック』には「徳川氏の入府により、この良弁僧正御作の不動尊は、将軍家の信仰するところとなった。殊に三代将軍家光公の崇拝は篤く、仏教の大意に基づいて府内に五色不動(江戸五色不動)の霊場をもうけ、方位によって配置し、江戸城と江戸に入る街道の守護を祈願した。この時に本像が『目黄不動』と名付けられ、家光によって江戸の鬼門除けを祈願された。また『目黄』とは五色不動の中の中心的な意を持つ由緒あるものである。」とあります。
******************
〔日本最古の不動明王について〕
ここで気になったのは、「目黄不動」が天平年間(729-766年)、良弁僧都による謹刻という点です。
こちら(京都じっくり観光)のサイトによると、木造五大明王像(教王護国寺(東寺)講堂安置)は承和六年(839年)完成で日本最古の不動明王像とされています。
しかし『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)には「高野山南院の不動尊の木彫立像(浪切不動尊)は、寺伝によると、弘法大師が長安にあるとき、恵果阿闍梨から木材を与えられて自分で彫刻して、阿闍梨に開眼加持をしてもらった。」とあります。
弘法大師の長安入りは804年の12月、806年3月に長安を立たれているので、この浪切不動尊の造立は、遅くとも806年ということになり、東寺講堂の不動尊(839年)よりも早いことになります。( → 高野山南院の資料
Wikipediaによると、不動明王が説かれている大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の成立は7世紀、漢訳は724年とされています。
『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)によると、『不空羂索神変真言経』第九巻に「北面、西より第一は不動使者なり。左手に羂索を執り、右手に剣を持ち結跏趺坐す。」と記されているそうです。
『不空羂索神変真言経』は菩提流志の漢訳経が伝わっており、菩提流支(ぼだいるし)は、北インド出身の訳経僧で没年は527年とされます。
良弁僧都の生年は689-774年なので、上記より晩年にはすでに不動明王に関連する不空羂索神変真言経や大日経の漢訳は成されていることになります。
良弁僧都は天平勝宝4年(751年)、華厳宗大本山東大寺の初代別当となられていますが、その時点での華厳宗と不動明王を結びつける史料がみつかりません。
弘法大師空海は、弘仁元年(810年)に東大寺の別当に就任され、山内に真言院を建立されたと伝わります。
また、毘盧遮那仏(大仏)の前で毎朝あげられるお経は「理趣経」で、弘法大師空海の影響を伝えるものとして広く知られています。
ただし、良弁僧都の没年は774年、弘法大師空海の生年も774年なので、良弁僧都が弘法大師将来の純密系の不動明王を感得されたということは考えにくいです。
ただし、日本にはそれ以前に雑密が入ってきており、その流れのなかで不動明王が将来されていた可能性はあるのかもしれません。(参考 → 『純密と雑密』(三崎良周氏))
『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、天平年間(729-766年)、良弁僧都が東国を巡錫した折、隅田川のほとりの大樹のもとで休んでいると、夢に不動明王があらわれ「わが姿を三体刻み、一体をここに安置せよ」との霊告を得たためみずから御影を刻まれ御本尊とされました。
また、相模国の大山不動はこの内の一体であり、当寺の不動尊像と同木同作とあります。
もう一体は大山不動とゆかりが深く、良弁作の不動尊を御本尊とする埼玉・越谷の真大山 大聖寺の大相模不動尊なのかもしれません。
■ 大山不動尊(雨降山 大山寺)/神奈川県伊勢原市 真言宗大覚寺派
「晩年に大山に登られ、石像の不動明王を感得、謹刻。大山寺第三世は弘法大師が入られる。」(『関東三十六不動霊場ガイドブック』)
■ 大相模不動尊(真大山 大聖寺)/埼玉県越谷市 真言宗豊山派
「(西方村)不動堂 縁起ノ畧ニ往古良辨僧正相州大山開闢ノ時面ノアタリ 不動ノ霊容ヲ拝シ 其尊像ヲ刻マントテ 先其木ノ根本ヲモテ一刀三禮シ一像を彫刻シ 是ヲ大山根本不動ト名付ク」(『新編武蔵風土記稿 巻之205 埼玉群郡之7』(国会図書館DC))

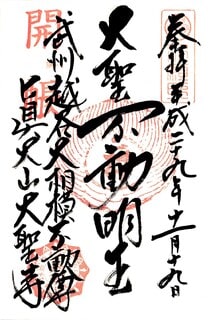
【写真 上(左)】 大山不動尊(雨降山 大山寺)の御朱印
【写真 下(右)】 大相模不動尊(真大山 大聖寺)の御朱印(酉年御開帳)
上記のほか、関東三十六不動霊場の札所に限っても、良弁僧都御作と伝わる不動明王は第15番の中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺)、第22番浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院)、第23番橋場不動尊(砂尾山 橋場寺)にみられます。
第17番等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院)は役小角(634-701年伝)御作、第10番の田無山 総持寺の不動尊は行基菩薩(668-749年)御作と伝わるので、最古の不動尊を辿るのは容易いことではないと思います。
******************
廃寺となった本所表町の東栄寺について、『寺社書上(御府内備考). [92] 本所寺社書上 五』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「本尊不動尊 丈四尺岩座四尺 作人不知 火焔八尺●寸」「二童子 作不知 丈●尺九寸」「御腹●●不動尊 丈二寸五● 座火焔●六寸 良辨僧正之作 但シ厨子入」
御本尊の不動尊は”作人不知”ですが、別尊の不動尊は”良辨僧正之作”となっています。
今となっては詳細は不明ですが、”良辨僧正之作”の「別尊の不動尊」が目黄不動尊なのかもしれません。
明治23年(1890年)刊の東京名所図会(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「同所表町に在り天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王は良弁僧都の作なり 当寺往古は牛御前の別当寺にして貞観年間慈覚大師の草創良本阿闍梨開山たり 寛永年間将軍家屡々此邊に遊猟せられしを以て当寺に仮殿●を営構せしと云へり 今尚ほ御殿跡と称する所ありとぞ」
明治23年時点において、良弁僧都作の不動明王(目黄不動尊)が御本尊として御座されていたことがわかります。
ただし、天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「牛寶山 最勝寺 明王院と号す 同●表町にあり天台宗にして東叡山に属す 本尊不動明王の像ハ良辨僧都の作なり 当寺ハ牛御前の別当寺にして貞観二年庚辰慈覚大師草創良本阿闍梨開山なり 寛永年間 大樹 此辺御遊猟の頃屢(しばしば)当寺へ入御あらせられしより其頃ハ假の御殿抔(など)営構なり●れたりとせり 今も御殿あとと称する地に山王権現を勧清す」
天保五-七年の時点ですでに「明王院」を号し、「良辨僧都作の不動明王」を御本尊としていたという記述は、他の資料と符合せずナゾが残ります。(ただし「明王院」は本所移転時に号したという説もあり。)
******************
最勝寺がかつて牛島の牛御前社(現在の牛嶋神社)の別当であったことは、複数の史料から裏付けられます。
天保五-七年(1834-1836年)版の『江戸名所図会 7巻18』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「牛島神明宮 同●に並ぶ相伝ふ貞観年間の鎮座なりと別当を神宮寺と称して最勝寺より兼帯す 江戸名所記云 安徳帝の壽永年間本所の郷民夢をえて 伊勢大神宮虚空よりけり大光明の内に微妙の御声にて●●土安穏天人常充満と云 法義経壽量品の文を唱へ●いられ伊勢の大神宮なりとの●●ふところ夢覚なり●中の人民●に僧(中略)伊勢の御神を勧清し」


【写真 上(左)】 牛嶋神社
【写真 下(右)】 牛嶋神社の御朱印
新編武蔵風土記稿 巻之21 葛飾郡之2(国会図書館DC)には以下の記述があります。
「牛御前社 本所及牛嶋ノ鎮守ナリ 北本所表町最勝寺持 祭神素盞嗚尊ハ束帯坐像ノ画幅ナリ 王子権現ヲ相殿トス 本地大日ハ慈覚大師ノ作縁起アリ信シカタキ●多シ 其畧ニ、貞観二年慈覚大師当國弘通ノ時行暮テ傍ノ草庵ニ入シニ位冠セシ老翁アリ 云國土惱乱アラハワレ首ニ牛頭ヲ戴キ悪魔降伏ノ形相ヲ現シ國家を守護セントス 故ニ我形を写シテ汝ニ与ヘン我タメニ一宇ヲ造立セヨトテ去レリ コレ当社ノ神体ニテ老翁ハ神素盞嗚尊ノ権化ナリ 牛頭ヲ戴テ守護シ賜ハントノ誓ニマカセテ牛御前ト号シ 弟子良本ヲ留メテコノ像ヲ守ラシメ 本地大日ノ像ヲ作リ釋迦ノ石佛ヲ彫刻シテコレヲ留メ 大師ハ登山セリ 良本コレヨリ明王院ト号シ 牛御前ヲ渇仰シ 法華千部ヲ読誦シテ大師ノ残セル石佛ノ釋迦ヲ供養佛トス 其後人皇五十七代陽成院ノ御宇 清和天皇第七ノ皇子故有テ当國ニ遷され、元慶元年九月十五日当所ニ於テ薨セラレシヲ、良本崇ヒ社傍ニ葬シ参ラセ其霊ヲ相殿ニ祀レリ 今ノ王子権現是ナリ 治承四年源頼朝諸軍ヲ引率シ下総國ニ至ル時ニ 隅田川洪水陸地ニ漲リ渡ルヘキ便ナカリシニ 千葉介常胤当社ニ祈誓シ船筏ヲ設ケ大軍恙ナク渡リシカバ 頼朝感シテ明ル養和元年再ヒ社領ヲ寄附セシヨリ、代々國主領主ヨリモ神領ヲ附セラル 天文七年六月廿八日後奈良院牛御前ト勅号ヲ賜ヒ次第ニ氏子繁栄セリ 北條家ヨリモ神領免除ノ文書及神寶ヲ寄ス其目後ニ出ス 又建長年中浅草川ヨリ牛鬼ノ如キ異形ノモノ飛出シ 嶼中ヲ走セメクリ当社ニ飛入忽然トシテ行方ヲ知ラス 時ニ社壇ニ一ツノ玉ヲ落セリ 今社寶牛玉是ナリナト記シタレド 奮キコトナレハ慥(タシカ)ナラサルコト多シ」
内容がやや錯綜していますが、牛御前社と最勝寺は、慈覚大師ゆかりの寺社として草創時からふかいつながりをもっていたことが伺われます。
************************
最寄りはJR総武線「平井」駅南口から徒歩約16分(1.3㎞)です。
地図上では近くみえますが、意外に距離があります。
住所は江戸川区平井1丁目、荒川の流れにもほど近いところです。
すぐそばにある嘉桂山 成就寺も本所からの移転で、こちらも天台宗で慈覚大師ゆかりの寺院です。新葛西三十三観音霊場初番、大東京百観音霊場第96番の札所で、御本尊、阿弥陀如来の御朱印を拝受できました。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標-1
三間一戸の八脚門から屋根をとり、門柱を加えたような変わった山門(仁王門)で、両脇間には仁王尊が御座します。
本所にあった頃は三重建築の仁王門があり、朱塗りの色が美しく「赤門寺」と称されたそうです。
山門左手の寺号標には「南無妙法蓮華経 南無釋迦牟尼仏 南無阿弥陀仏」が併記されていますが、この様式の石碑はあまりみたことがありません。


【写真 上(左)】 寺号標-2
【写真 下(右)】 山内
広がりのある山内。正面に本堂、その右手に客殿と庫裡、その手前右手に不動堂、さらにその手前右に地蔵観音堂と最勝稲荷社。わかりやすく整った伽藍配置です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は入母屋像本瓦葺流れ向拝の堂々たるつくり。さすがに名刹です。
水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「牛寶山」の扁額を掲げています。
本堂にはおそらく御本尊の慈覚大師作の釈迦如来が御座します。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 客殿
本堂右手の客殿も破風屋根を構える風格あるつくり。


【写真 上(左)】 客殿と不動堂
【写真 下(右)】 不動堂


【写真 上(左)】 斜めからの不動堂
【写真 下(右)】 側面からの不動堂
不動堂は楼閣様式ですが、不勉強につき正確なつくりはわかりません。
向拝には水引虹梁に木鼻、斗栱、蟇股、海老虹梁を備え、正面桟唐戸の上に「不動尊」の扁額を掲げています。
全体に本堂よりも複雑な意匠です。


【写真 上(左)】 不動堂向拝
【写真 下(右)】 不動堂向拝上部


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 不動堂賽銭箱の意匠
不動堂には良弁僧都作とされる不動明王(目黄不動尊)が御座され、こちらも御本尊の位置づけにあるようです。
この目黄不動尊像は、都内では高幡不動尊に次ぐほどの大きな像(像高127㎝)で、「木造不動明王坐像」として江戸川区の登録有形文化財(彫刻)に指定されています。
迦楼羅炎の勢いすさまじく、右手に剣、左手に羂索を掲げられ盤石のうえに御座され、二童子を従えています。


【写真 上(左)】 目黄不動明王の石標
【写真 下(右)】 関東三十六不動霊場札所標と本堂
慈覚大師作とされ、牛御前社の本地仏であった大日如来像は、不動堂に安置されているようです。


【写真 上(左)】 地蔵観音堂
【写真 下(右)】 最勝稲荷社
最勝稲荷社は牛御前社より御遷座と伝わり、家屋守護に霊験あらたかとのことです。
墓地には鳥亭焉馬(戯作者)、富田木歩(俳人)、柔道家徳三宝夫妻の墓があります。
御朱印は庫裡にて拝受できます。
関東三十六不動霊場の札所でもあり、手慣れたご対応です。
なお、隅田川二十一ヵ所霊場第7番、新葛西三十三観音霊場第23番の御朱印は授与されていない模様です。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目黄不動尊 江戸五色不動の印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動霊場第19番の御朱印〕


【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:目黄不動尊 関東三十六不動霊場第19番印判 法挟護童子の印判
************************
これで、現行の江戸五色不動のご紹介はとりあえず完結です。
関連して、以下のお不動さまについてもつづきで書きたいと思いますが、しばらく時間をおきます。
7.古碧山 龍巌寺 / 目黄不動尊
渋谷区神宮前2-3-8(墨田区東駒形から移転)
臨済宗南禅寺派 御本尊:釈迦如来
8.五大山 不動院 / 目黄不動尊
港区六本木3-15-4
高野山真言宗 御本尊:不動明王
9.石神井不動尊(亀頂山 密乗院 三寶寺)
練馬区石神井台1-15-6
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第11番
10.志村不動尊(寶勝山 蓮光寺 南蔵院)
板橋区蓮沼町48-8
真言宗智山派 御本尊:十一面観世音菩薩、不動明王
関東三十六不動霊場第12番
11.中野不動尊(明王山 聖無動院 寶仙寺)
中野区中央2-33-3
真言宗豊山派 御本尊:不動明王(五大明王)
関東三十六不動霊場第15番
12.等々力不動尊(瀧轟山 明王院 満願寺別院)
世田谷区等々力1-22-47
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第17番
13.深川不動尊/深川不動堂(成田山 新勝寺 東京別院)
江東区富岡1-17-13
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第20番
14.薬研堀不動尊/薬研堀不動院(川崎大師 東京別院)
中央区東日本橋2-6-8
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第21番
15.浅草寿不動尊(阿遮山 円満寺 不動院)
台東区寿2-5-2
真言宗智山派 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第22番
16.橋場不動尊(砂尾山 橋場寺)
台東区橋場2-14-19
天台宗 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第23番
17.飛不動尊(龍光山 三高寺 正寶院)
台東区竜泉3-11-11
天台宗寺門系 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第24番
18.皿沼不動尊(皿沼山 永昌院)
足立区皿沼1-4-2
天台宗寺門系 御本尊:不動明王
関東三十六不動霊場第25番
19.西新井大師不動明王(五智山 遍照院 總持寺)
足立区西新井1-15-1
真言宗豊山派 御本尊:弘法大師・十一面観世音菩薩
関東三十六不動霊場第26番
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 2.目黒不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊、4.目赤不動尊、5.目黄不動尊(永久寺)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 6.目黄不動尊(最勝寺)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊、4.目赤不動尊、5.目黄不動尊(永久寺)
※ 現在、新型コロナウイルス感染拡大を受け、外出自粛が要請されています。また、寺社様によっては御朱印授与を休止されている可能性があります。ご留意願います。
こちらからつづく
■ 神霊山 慈眼寺 金乗院〔目白不動尊 / 江戸五色不動〕
豊島区高田2-12-39(新長谷寺(現・文京区関口)から移転)
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩・断臂不動明王(目白不動尊)
元司別当:此花咲耶姫社など
札所:江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、御府内八十八箇所第38番(金乗院)、同 第54番(新長谷寺)、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場第14番、江戸八十八ヶ所霊場第38番(金乗院)、東京三十三観音霊場第23番(新長谷寺)

「目白不動堂 / 江戸名所図会. 十二」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂 / 江戸名所図会. 十二」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
寺伝・縁起書、および『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を築いたのが草創とされます。
当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。
『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国会図書館DC)には以下のとおりあります。
「金乗院 新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云」
江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。
戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。
目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおりあります。
「目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す
長谷小池坊の宿寺とす 本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆 縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰
ハ大師自ら護持なしたまふ その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると 当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む 大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり 此地麓●●堰口の流を帯ひ
水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり」
また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国会図書館DC)には「目白不動尊起立書 新長谷寺浄瀧院 本尊不動尊 弘法大師御作秘佛 開帳佛不動 前立不動」(縁起も記されていますが略)とあります。
『東京名所図会』(国会図書館DC)にも以下の記載があります。
「目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ」
目白不動堂奉安のお不動さまは高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。
縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。
大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。
不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。
大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。
後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。
元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、二代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。
大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。
寛永年間(1624-1644年)、三代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。
ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。
元禄年間(1688-1704年)には、五代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。
境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。
その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。
昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は金乗院に遷られました。
ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。
また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。
************************
最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。
メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。
目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。
宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。
「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」
現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。
宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。


【写真 上(左)】 宿坂
【写真 下(右)】 山門
宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。
二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。
右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。


【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板
約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門前の不動尊
山門周辺に御府内霊場第三十八番および五十四番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。
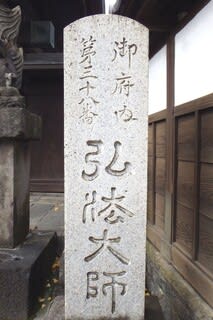

【写真 上(左)】 御府内霊場第三十八番の札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場第五十四番の札所標
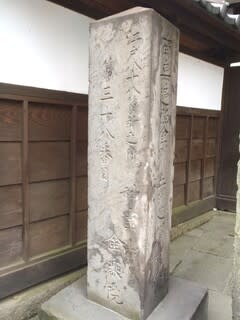

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標
「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。
「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。


【写真 上(左)】 金乗院の寺号標
【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標
石敷のすっきりとした境内。
山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂と不動堂
御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)
(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)
ちなみに御府内霊場88ヶ所のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。


【写真 上(左)】 本堂(斜めから)
【写真 下(右)】 本堂向拝露天
本堂は昭和46年(1971年)の再建、平成15年(2003年)の改修。
木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく、風格ある堂宇です。
水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。
御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。
金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。
本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。
不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。
「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。


【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申
【写真 下(右)】 不動堂参道
その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。
その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。
さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。
確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。
棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝
水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。
格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。
こちらの不動尊は御前立かと思われます。
整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 鐔塚
境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。
なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。
御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。
こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。
札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)
※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。
〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書
〔御府内八十八箇所第38番(金乗院)の御朱印/御朱印帳〕


【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:聖観世音菩薩・弘法大師 御府内八十八箇所第38番・54番印判 三十八番の揮毫
〔御府内八十八箇所第54番(新長谷寺)の御朱印/御朱印帳〕
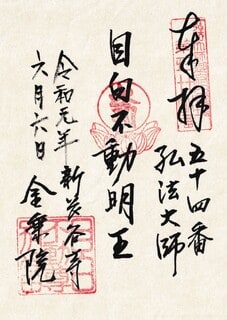
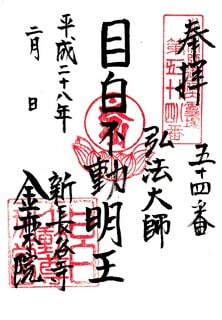
【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:目白不動明王・弘法大師 御府内八十八箇所第38番・54番印判 五十四番の揮毫
〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕
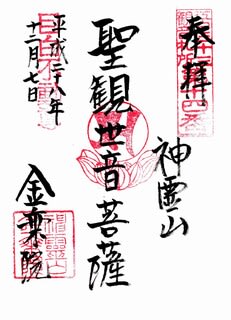
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)
■ 大聖山 東朝院 南谷寺〔目赤不動尊 / 江戸五色不動〕
文京区本駒込1-20-20
天台宗
御本尊:不動明王(目赤不動尊)
札所:江戸五色不動(目赤不動尊)、関東三十六不動霊場第13番
納経時にいただいた縁起書、境内掲示などから縁起を辿ってみます。
元和年間(1615年頃)、比叡山南谷に万行律師という不動尊への尊信篤い名僧がおり修行を重ねておられました。
ある夜、童子が夢枕に立ち「万行多年不動尊を尊信する事深切なり、伊賀の国の赤目山来たれ不動明王の霊験あらん」と告げて飛び去りました。
律師は童子のお告げに従ってすぐさま伊賀の赤目山に登り、絶頂の磐石に端座して不動真言を称え、印を結んで不動明王の御来迎を待ち奉りました。
三日三夜がたつと、虚空に声が響いてなにかが投げ入れられました。
拾い上げて見れば一寸二分の黄金の不動明王の尊像で、律師は礼拝恭敬して山をくだり比叡山南谷の庵室にこの尊像を安置しました。
暫くのち、律師は衆生済度を発念され不動尊像を護持して関東に向かい、下駒込の動坂(堂坂)の地に縁を得て、堂を建立して尊像を安置しました。
この不動尊に参詣祈願をなす者に奇瑞少なからず、衆生はこの地を「不動坂」と称えて群参したといいます。
寛永五年(1628年)、将軍家光公が鷹狩りの途中、不動尊の由来を聞き及んだところ、府内五不動の因縁を以って”赤目”を”目赤”と称える様にとの沙汰があり、以後目赤不動尊と称したとされます。
その後改めて上意があり、浅嘉町藤堂家屋敷跡(現在地)を拝領して堂宇を建立し、大聖山 東朝院と号して天台宗羽黒派に属しました。
このとき故有って、智證大師御作の不動明王の霊像を受得して御前立に安置、黄金の御本尊は後の厨子に秘仏として奉安したとされます。(御前立本尊の胎内に奉安とも)
万行大僧都が寂したのちも、目赤不動尊の御利益は著しく、参詣者は絶えず、天明八年(1788年)には東叡山寛永寺の直末となりました。その際、初代万行大僧都の遺徳を偲んで大聖山 南谷寺と号されました。
『江戸名所図会 巻之五』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「駒込淺香町にあり。伊州赤目山の住職萬行和尚回國の時供奉せし不動の尊像、屡(しばしば)霊験あるに仍て、其威霊を恐れ、別に今の像を彫刻して、彼像を腹籠とす。則ち赤目不動と號し、此所に一宇を建立せり。始めハ千駄木に草堂をむすびて安置ありしを、寛永の頃、大樹御放鷹の砌、今の所に地を賜ふ。千駄木に動坂の号あるは、不動坂の略語にて、草堂のありし旧地なり。後年終に目黒、目白に對して、目赤と改むるとぞ。」
また、『東京名所図会(国会図書館DC)』には以下の記載があります。
「大観音の西北淺嘉町大聖山南谷寺にあり 本尊不動尊ハ伊賀國赤目山の住職萬行和尚回國の時供奉らし尊像屢(しばしば)霊験あるにより別に今の像を腹籠となせり 依て赤目不動と呼びしを後ち目黒目白に對して目赤と改めしとぞ 始めハ千駄木にありしを寛永年間此地に移さると云ふ 千駄木に動坂と云へる所あるハ其旧地にして不動坂の略語なりと云ふ」
動坂にあったと伝わる南谷寺の旧地については → こちらで推測されています。
************************
最寄りはメトロ南北線「本駒込」駅。2番出口から本郷通りを渡って徒歩2分弱、通りに面しているので、すぐにわかります。
この辺りは寺院が多く、寺町の趣。メジャー霊場の札所も多くあります。


【写真 上(左)】 柱門
【写真 下(右)】 寺号板


【写真 上(左)】 右の門柱
【写真 下(右)】 左の門柱
道沿いのみかげ石の門柱、右に青文字で「大聖山 南谷寺」、左に「目赤不動尊」で字色のコントラストが効いています。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 初夏の本堂
伽藍配置は正面に本堂、右手に庫裡。その手前、参道右手にすこしく奥まって不動堂。
著名なお不動様や観音様を擁する寺院によくみられるかたちです。
緑が多く、落ち着いた転生の境内。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造本瓦葺で大棟両端に鴟尾を置き、やや起(むく)り気味の屋根です。
向拝柱はなく、正面桟唐戸で上部は連子、下部は入子板。その上に中央に蟇股、見上げに「大聖山」の扁額。
向拝左右に格子戸、菱格子欄間、連子窓、軒下には斗栱を連ね、趣きのある寺院建築です。
垂木は一軒。軒丸瓦に阿弥陀如来の種子「キリーク」、軒平瓦に花紋様など細やかな意匠。


【写真 上(左)】 軒瓦
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂には阿弥陀如来が御座します。
『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、当寺の御本尊は「黄金不動明王」とあります。
天台宗では著名な尊格を独立の堂宇(不動堂、観音堂など)に奉り、本堂に阿弥陀如来を奉る例がかなりあり、当寺もその例かもしれません。
そのような場合、阿弥陀如来の御朱印は非授与の場合が多いのですが、当寺も非授与のようです。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 六地蔵と不動堂
【写真 下(右)】 大日如来と不動堂
不動堂まわりに進むと、手前に六地蔵。
その先で本堂参道から不動堂参道を右に分け、左手に手水鉢と恵比寿像、右手に「目赤不動尊」の石標や石碑、智拳印を結ばれる金剛界大日如来像と並びます。
恵比寿像と大日如来像は、江戸時代中期頃の作風とされています。
江戸五色不動の6寺院が記された石標もありました。


【写真 上(左)】 大日如来
【写真 下(右)】 手水鉢と恵比寿様


【写真 上(左)】 目赤不動尊の石標
【写真 下(右)】 目赤不動尊の石碑


【写真 上(左)】 江戸五色不動の石碑
【写真 下(右)】 不動堂参道
その先が不動堂。
桟瓦葺の宝形造で頂に火焔宝珠、そこから隅棟、稚児棟を降ろしています。
棟には精緻な熨斗瓦、雁振瓦、鳥衾、鬼瓦を備え、全体に整った印象があります。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂の棟
身舎まわりに縁をまわして向拝は格子戸。その上の小壁に「目赤不動尊」の扁額と、左右にふたつの奉納額が掲げられています。
その上、二軒の垂木、軒平瓦、桟瓦、火焔宝珠と重なり、重厚感のある向拝。


【写真 上(左)】 斜めからの不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝


【写真 上(左)】 右奉納額
【写真 下(右)】 左奉納額
向拝の格子戸があいており、お不動様のおすがたが拝めます。
御内陣の目赤不動尊は、真紅の迦楼羅炎を背負われ、右手に劍、左手に羂索をもたれて盤石に御座す、力感あふれるおすがたです。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 関東三十六不動霊場札所板
関東三十六不動霊場の札所でもあり、御朱印は授与所にて快く授与いただけます。
繊細な筆致の御朱印です。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
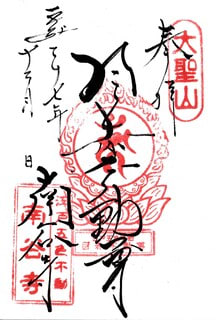
・御朱印尊格:目赤不動尊 江戸五色不動の印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動霊場第13番の御朱印〕

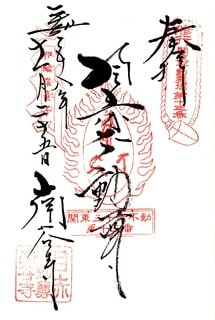
【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:目赤不動尊 関東三十六不動尊霊場第13番印判 伊醯羅童子の印判
■ 養光山 金碑院 永久寺〔目黄不動尊 / 江戸五色不動〕
台東区三ノ輪2-14-5
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:江戸五色不動(目黄不動尊)、東都北部三十三観音霊場第17番
天台宗東京教区Webによると草創は14世紀南北朝騒乱の頃、当時は真言宗で唯識院と号していたようです。
その後、白岩寺、大乗坊、蓮台寺と改号を重ね、宗派も真言宗から禅宗そして日蓮宗と変遷したようです。
下記の『寺社書上(御府内備考)』によると、道安和尚が堂宇を整えて禅宗白岩寺とし、四谷本源寺の弟子月窓が堂宇を修理し大乗坊 蓮台寺と号して日蓮宗となりました。
月窓の父の所縁により、将軍の命を受け月窓は日光御門主本照院宮の弟子となり、圭海(大僧都圭海法印)と称し、宗派を天台宗に改めて養光山 永久寺と号したとあります。
その後東叡山 浄円院と号を改めていたところ、寛文年間(1661-1673年)、幕臣の檀家山野嘉右衛門(号.藤原の永久)が諸堂を再建し、号の二字を以て永久寺と改めて中興の祖とされます。(永久寺改号のくだりが錯綜していて、詳細不明)
寛永年間(1624-1643年)の中ごろ、五街道の整備にともない街道の道中安全祈願が幕府より命じられ、上野寛永寺の天海大僧正の発願によって江戸府内の由緒ある古刹が五色不動として五街道沿いに定められたと伝わります。
その際、日光街道沿いの古刹、永久寺が目黄不動尊として定められたといいます。
『寺社書上(御府内備考). [118] 下谷寺社書上.四』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「往古真言宗ニテ号唯識院 道安和尚悉ク殿堂ヲ再造シテ禅閣トナシ白岩寺と改ム 亦衰微セシヲ四谷本源寺弟子月窓修理シテ大乗坊蓮台寺ト唱ヒ為ニ日蓮宗トナル 月窓父ハ七澤作左衛門清宗入道シテ(中略) 爰ニ蒙台命日光御門主本照院宮之御弟子トナリ 圭海ト名ス 天台宗ニ改メ養光山永久寺と号シ 其ノ後東叡山浄円院トナル 御朱印二百石御寄附アリ今ノ律院是ナリ 又同山内養寿院ト成ル ココニ当寺檀越山野加右衛門永久トイフ者(中略)当寺佛閣諸堂ヲ悉ク建立シ門前地等ヲ寄附シ(中略)実名永久之二字ヲ以永久寺ト号ス(中略)改称圭海法印 抑大僧都圭海法印者 大樹家綱公御母堂宝樹院殿同腹御実弟ニテ男女兄弟八人也 羽州羽黒山執行別当を兼帯シ 終ニ京都愛宕山長床坊住職シテ天台顕密ノ僧ト云々」
当寺の目黄不動尊の縁起がよくわからないのですが、境内掲示にあるとおり「寛永年間の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申により、(五色不動として)江戸府内の名ある不動尊を指定」というところによるのではないでしょうか。
当寺を天台宗に改めた圭海法印は将軍家ともかかわりをもつ相応の身分と考えられ、天台宗東京教区Webによると、宝物として慈覚大師御作の不動明王像、智證大師御真筆の不動尊一幅が記載されているので、目黄不動尊に指定される寺格・由緒は有していたものと考えられます。
なお、境内掲示には「不動尊信仰は、密教がさかんになった平安時代初期の頃から広まり、不動尊を身体ないしは目の色で描きわけることは、平安時代すでに存在したという。」という興味ぶかい記述があります。
************************
メトロ日比谷線「三ノ輪」駅3番出口至近です。
都営荒川線の終点「三ノ輪橋」駅からも近いので、1日結願ではない場合、目白不動尊から「学習院下」駅で乗車し、52分の都電の旅を楽しむという手もあります。これだけ乗って運賃170円は安いです。


【写真 上(左)】 門
【写真 下(右)】 寺号標
交通量の多い明治通り沿いにあります。
山門、通用門ともに閉扉され、ガードが堅い印象ですが、たしか右手の通用門が開いたかと思います。
アール・ヌーヴォー的なやわらかな曲線を用いた本堂。その下に桟瓦の屋根(本堂向拝の屋根?)が走る様は、意匠的になかなかインパクトがあります。
天台宗東京教区Webによると、御本尊は阿弥陀如来。宝物として運慶作の阿弥陀如来像が記載されているので、御本尊は運慶作かもしれません。
また、宝物として慈覚大師御作の不動明王像が記載されているので、目黄不動尊は慈覚大師の御作かもしれません。
智證大師御真筆の不動尊一幅も宝物とされています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂(手前)と不動堂(左奥)


【写真 上(左)】 目黄不動尊の石碑
【写真 下(右)】 不動堂
本堂向かって左手に不動堂。
こちらも意匠的に特徴があり。造りはよくわかりませんが銅板葺で、向拝柱を備えています。
不動堂左前に「目黄不動尊」の石碑。
格子戸越しに御内陣が拝せます。
目黄不動尊はご内陣中央に御座。
朱の迦楼羅炎を背負われ、右手に劍、左手に羂索をもたれる黒色の引き締まった立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 板碑
本堂前には板碑二体ありましたが、こちらは宝物の南北朝期の板碑二体かもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、Web情報によるとご不在の場合も。書置対応もされているようですが、事前確認がベターかもしれません。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目黄不動 「江戸五色不動」の印判 直書(筆書)
(つづく) → こちら
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 2.目黒不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊、4.目赤不動尊、5.目黄不動尊(永久寺)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 6.目黄不動尊(最勝寺)
こちらからつづく
■ 神霊山 慈眼寺 金乗院〔目白不動尊 / 江戸五色不動〕
豊島区高田2-12-39(新長谷寺(現・文京区関口)から移転)
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩・断臂不動明王(目白不動尊)
元司別当:此花咲耶姫社など
札所:江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、御府内八十八箇所第38番(金乗院)、同 第54番(新長谷寺)、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場第14番、江戸八十八ヶ所霊場第38番(金乗院)、東京三十三観音霊場第23番(新長谷寺)

「目白不動堂 / 江戸名所図会. 十二」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂 / 江戸名所図会. 十二」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
寺伝・縁起書、および『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を築いたのが草創とされます。
当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。
『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国会図書館DC)には以下のとおりあります。
「金乗院 新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云」
江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。
戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。
目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおりあります。
「目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す
長谷小池坊の宿寺とす 本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆 縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰
ハ大師自ら護持なしたまふ その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると 当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む 大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり 此地麓●●堰口の流を帯ひ
水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり」
また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国会図書館DC)には「目白不動尊起立書 新長谷寺浄瀧院 本尊不動尊 弘法大師御作秘佛 開帳佛不動 前立不動」(縁起も記されていますが略)とあります。
『東京名所図会』(国会図書館DC)にも以下の記載があります。
「目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ」
目白不動堂奉安のお不動さまは高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。
縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。
大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。
不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。
大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。
後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。
元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、二代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。
大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。
寛永年間(1624-1644年)、三代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。
ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。
元禄年間(1688-1704年)には、五代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。
境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。
その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。
昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は金乗院に遷られました。
ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。
また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。
************************
最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。
メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。
目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。
宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。
「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」
現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。
宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。


【写真 上(左)】 宿坂
【写真 下(右)】 山門
宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。
二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。
右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。


【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板
約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門前の不動尊
山門周辺に御府内霊場第三十八番および五十四番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。
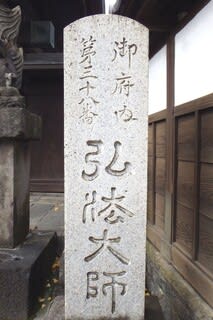

【写真 上(左)】 御府内霊場第三十八番の札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場第五十四番の札所標
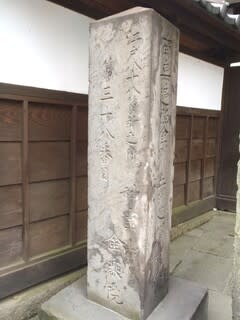

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標
「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。
「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。


【写真 上(左)】 金乗院の寺号標
【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標
石敷のすっきりとした境内。
山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂と不動堂
御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)
(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)
ちなみに御府内霊場88ヶ所のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。


【写真 上(左)】 本堂(斜めから)
【写真 下(右)】 本堂向拝露天
本堂は昭和46年(1971年)の再建、平成15年(2003年)の改修。
木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく、風格ある堂宇です。
水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。
御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。
金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。
本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。
不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。
「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。


【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申
【写真 下(右)】 不動堂参道
その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。
その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。
さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。
確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。
棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝
水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。
格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。
こちらの不動尊は御前立かと思われます。
整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 鐔塚
境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。
なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。
御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。
こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。
札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)
※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。
〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書
〔御府内八十八箇所第38番(金乗院)の御朱印/御朱印帳〕


【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:聖観世音菩薩・弘法大師 御府内八十八箇所第38番・54番印判 三十八番の揮毫
〔御府内八十八箇所第54番(新長谷寺)の御朱印/御朱印帳〕
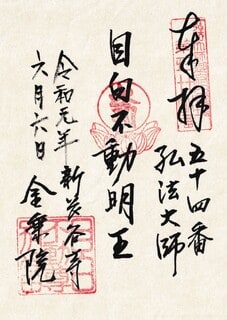
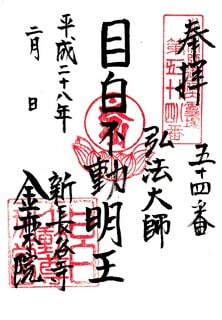
【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:目白不動明王・弘法大師 御府内八十八箇所第38番・54番印判 五十四番の揮毫
〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕
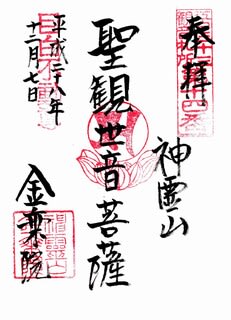
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)
■ 大聖山 東朝院 南谷寺〔目赤不動尊 / 江戸五色不動〕
文京区本駒込1-20-20
天台宗
御本尊:不動明王(目赤不動尊)
札所:江戸五色不動(目赤不動尊)、関東三十六不動霊場第13番
納経時にいただいた縁起書、境内掲示などから縁起を辿ってみます。
元和年間(1615年頃)、比叡山南谷に万行律師という不動尊への尊信篤い名僧がおり修行を重ねておられました。
ある夜、童子が夢枕に立ち「万行多年不動尊を尊信する事深切なり、伊賀の国の赤目山来たれ不動明王の霊験あらん」と告げて飛び去りました。
律師は童子のお告げに従ってすぐさま伊賀の赤目山に登り、絶頂の磐石に端座して不動真言を称え、印を結んで不動明王の御来迎を待ち奉りました。
三日三夜がたつと、虚空に声が響いてなにかが投げ入れられました。
拾い上げて見れば一寸二分の黄金の不動明王の尊像で、律師は礼拝恭敬して山をくだり比叡山南谷の庵室にこの尊像を安置しました。
暫くのち、律師は衆生済度を発念され不動尊像を護持して関東に向かい、下駒込の動坂(堂坂)の地に縁を得て、堂を建立して尊像を安置しました。
この不動尊に参詣祈願をなす者に奇瑞少なからず、衆生はこの地を「不動坂」と称えて群参したといいます。
寛永五年(1628年)、将軍家光公が鷹狩りの途中、不動尊の由来を聞き及んだところ、府内五不動の因縁を以って”赤目”を”目赤”と称える様にとの沙汰があり、以後目赤不動尊と称したとされます。
その後改めて上意があり、浅嘉町藤堂家屋敷跡(現在地)を拝領して堂宇を建立し、大聖山 東朝院と号して天台宗羽黒派に属しました。
このとき故有って、智證大師御作の不動明王の霊像を受得して御前立に安置、黄金の御本尊は後の厨子に秘仏として奉安したとされます。(御前立本尊の胎内に奉安とも)
万行大僧都が寂したのちも、目赤不動尊の御利益は著しく、参詣者は絶えず、天明八年(1788年)には東叡山寛永寺の直末となりました。その際、初代万行大僧都の遺徳を偲んで大聖山 南谷寺と号されました。
『江戸名所図会 巻之五』(国会図書館DC)に以下の記載があります。
「駒込淺香町にあり。伊州赤目山の住職萬行和尚回國の時供奉せし不動の尊像、屡(しばしば)霊験あるに仍て、其威霊を恐れ、別に今の像を彫刻して、彼像を腹籠とす。則ち赤目不動と號し、此所に一宇を建立せり。始めハ千駄木に草堂をむすびて安置ありしを、寛永の頃、大樹御放鷹の砌、今の所に地を賜ふ。千駄木に動坂の号あるは、不動坂の略語にて、草堂のありし旧地なり。後年終に目黒、目白に對して、目赤と改むるとぞ。」
また、『東京名所図会(国会図書館DC)』には以下の記載があります。
「大観音の西北淺嘉町大聖山南谷寺にあり 本尊不動尊ハ伊賀國赤目山の住職萬行和尚回國の時供奉らし尊像屢(しばしば)霊験あるにより別に今の像を腹籠となせり 依て赤目不動と呼びしを後ち目黒目白に對して目赤と改めしとぞ 始めハ千駄木にありしを寛永年間此地に移さると云ふ 千駄木に動坂と云へる所あるハ其旧地にして不動坂の略語なりと云ふ」
動坂にあったと伝わる南谷寺の旧地については → こちらで推測されています。
************************
最寄りはメトロ南北線「本駒込」駅。2番出口から本郷通りを渡って徒歩2分弱、通りに面しているので、すぐにわかります。
この辺りは寺院が多く、寺町の趣。メジャー霊場の札所も多くあります。


【写真 上(左)】 柱門
【写真 下(右)】 寺号板


【写真 上(左)】 右の門柱
【写真 下(右)】 左の門柱
道沿いのみかげ石の門柱、右に青文字で「大聖山 南谷寺」、左に「目赤不動尊」で字色のコントラストが効いています。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 初夏の本堂
伽藍配置は正面に本堂、右手に庫裡。その手前、参道右手にすこしく奥まって不動堂。
著名なお不動様や観音様を擁する寺院によくみられるかたちです。
緑が多く、落ち着いた転生の境内。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は寄棟造本瓦葺で大棟両端に鴟尾を置き、やや起(むく)り気味の屋根です。
向拝柱はなく、正面桟唐戸で上部は連子、下部は入子板。その上に中央に蟇股、見上げに「大聖山」の扁額。
向拝左右に格子戸、菱格子欄間、連子窓、軒下には斗栱を連ね、趣きのある寺院建築です。
垂木は一軒。軒丸瓦に阿弥陀如来の種子「キリーク」、軒平瓦に花紋様など細やかな意匠。


【写真 上(左)】 軒瓦
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂には阿弥陀如来が御座します。
『関東三十六不動霊場ガイドブック』によると、当寺の御本尊は「黄金不動明王」とあります。
天台宗では著名な尊格を独立の堂宇(不動堂、観音堂など)に奉り、本堂に阿弥陀如来を奉る例がかなりあり、当寺もその例かもしれません。
そのような場合、阿弥陀如来の御朱印は非授与の場合が多いのですが、当寺も非授与のようです。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 六地蔵と不動堂
【写真 下(右)】 大日如来と不動堂
不動堂まわりに進むと、手前に六地蔵。
その先で本堂参道から不動堂参道を右に分け、左手に手水鉢と恵比寿像、右手に「目赤不動尊」の石標や石碑、智拳印を結ばれる金剛界大日如来像と並びます。
恵比寿像と大日如来像は、江戸時代中期頃の作風とされています。
江戸五色不動の6寺院が記された石標もありました。


【写真 上(左)】 大日如来
【写真 下(右)】 手水鉢と恵比寿様


【写真 上(左)】 目赤不動尊の石標
【写真 下(右)】 目赤不動尊の石碑


【写真 上(左)】 江戸五色不動の石碑
【写真 下(右)】 不動堂参道
その先が不動堂。
桟瓦葺の宝形造で頂に火焔宝珠、そこから隅棟、稚児棟を降ろしています。
棟には精緻な熨斗瓦、雁振瓦、鳥衾、鬼瓦を備え、全体に整った印象があります。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂の棟
身舎まわりに縁をまわして向拝は格子戸。その上の小壁に「目赤不動尊」の扁額と、左右にふたつの奉納額が掲げられています。
その上、二軒の垂木、軒平瓦、桟瓦、火焔宝珠と重なり、重厚感のある向拝。


【写真 上(左)】 斜めからの不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝


【写真 上(左)】 右奉納額
【写真 下(右)】 左奉納額
向拝の格子戸があいており、お不動様のおすがたが拝めます。
御内陣の目赤不動尊は、真紅の迦楼羅炎を背負われ、右手に劍、左手に羂索をもたれて盤石に御座す、力感あふれるおすがたです。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 関東三十六不動霊場札所板
関東三十六不動霊場の札所でもあり、御朱印は授与所にて快く授与いただけます。
繊細な筆致の御朱印です。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
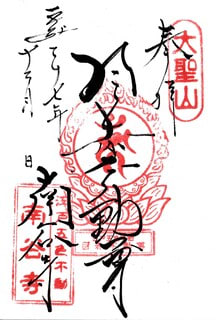
・御朱印尊格:目赤不動尊 江戸五色不動の印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動霊場第13番の御朱印〕

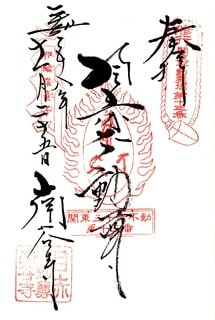
【写真 上(左)】 専用納経帳(直書)
【写真 下(右)】 御朱印帳(直書)
・御朱印尊格:目赤不動尊 関東三十六不動尊霊場第13番印判 伊醯羅童子の印判
■ 養光山 金碑院 永久寺〔目黄不動尊 / 江戸五色不動〕
台東区三ノ輪2-14-5
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:江戸五色不動(目黄不動尊)、東都北部三十三観音霊場第17番
天台宗東京教区Webによると草創は14世紀南北朝騒乱の頃、当時は真言宗で唯識院と号していたようです。
その後、白岩寺、大乗坊、蓮台寺と改号を重ね、宗派も真言宗から禅宗そして日蓮宗と変遷したようです。
下記の『寺社書上(御府内備考)』によると、道安和尚が堂宇を整えて禅宗白岩寺とし、四谷本源寺の弟子月窓が堂宇を修理し大乗坊 蓮台寺と号して日蓮宗となりました。
月窓の父の所縁により、将軍の命を受け月窓は日光御門主本照院宮の弟子となり、圭海(大僧都圭海法印)と称し、宗派を天台宗に改めて養光山 永久寺と号したとあります。
その後東叡山 浄円院と号を改めていたところ、寛文年間(1661-1673年)、幕臣の檀家山野嘉右衛門(号.藤原の永久)が諸堂を再建し、号の二字を以て永久寺と改めて中興の祖とされます。(永久寺改号のくだりが錯綜していて、詳細不明)
寛永年間(1624-1643年)の中ごろ、五街道の整備にともない街道の道中安全祈願が幕府より命じられ、上野寛永寺の天海大僧正の発願によって江戸府内の由緒ある古刹が五色不動として五街道沿いに定められたと伝わります。
その際、日光街道沿いの古刹、永久寺が目黄不動尊として定められたといいます。
『寺社書上(御府内備考). [118] 下谷寺社書上.四』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「往古真言宗ニテ号唯識院 道安和尚悉ク殿堂ヲ再造シテ禅閣トナシ白岩寺と改ム 亦衰微セシヲ四谷本源寺弟子月窓修理シテ大乗坊蓮台寺ト唱ヒ為ニ日蓮宗トナル 月窓父ハ七澤作左衛門清宗入道シテ(中略) 爰ニ蒙台命日光御門主本照院宮之御弟子トナリ 圭海ト名ス 天台宗ニ改メ養光山永久寺と号シ 其ノ後東叡山浄円院トナル 御朱印二百石御寄附アリ今ノ律院是ナリ 又同山内養寿院ト成ル ココニ当寺檀越山野加右衛門永久トイフ者(中略)当寺佛閣諸堂ヲ悉ク建立シ門前地等ヲ寄附シ(中略)実名永久之二字ヲ以永久寺ト号ス(中略)改称圭海法印 抑大僧都圭海法印者 大樹家綱公御母堂宝樹院殿同腹御実弟ニテ男女兄弟八人也 羽州羽黒山執行別当を兼帯シ 終ニ京都愛宕山長床坊住職シテ天台顕密ノ僧ト云々」
当寺の目黄不動尊の縁起がよくわからないのですが、境内掲示にあるとおり「寛永年間の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申により、(五色不動として)江戸府内の名ある不動尊を指定」というところによるのではないでしょうか。
当寺を天台宗に改めた圭海法印は将軍家ともかかわりをもつ相応の身分と考えられ、天台宗東京教区Webによると、宝物として慈覚大師御作の不動明王像、智證大師御真筆の不動尊一幅が記載されているので、目黄不動尊に指定される寺格・由緒は有していたものと考えられます。
なお、境内掲示には「不動尊信仰は、密教がさかんになった平安時代初期の頃から広まり、不動尊を身体ないしは目の色で描きわけることは、平安時代すでに存在したという。」という興味ぶかい記述があります。
************************
メトロ日比谷線「三ノ輪」駅3番出口至近です。
都営荒川線の終点「三ノ輪橋」駅からも近いので、1日結願ではない場合、目白不動尊から「学習院下」駅で乗車し、52分の都電の旅を楽しむという手もあります。これだけ乗って運賃170円は安いです。


【写真 上(左)】 門
【写真 下(右)】 寺号標
交通量の多い明治通り沿いにあります。
山門、通用門ともに閉扉され、ガードが堅い印象ですが、たしか右手の通用門が開いたかと思います。
アール・ヌーヴォー的なやわらかな曲線を用いた本堂。その下に桟瓦の屋根(本堂向拝の屋根?)が走る様は、意匠的になかなかインパクトがあります。
天台宗東京教区Webによると、御本尊は阿弥陀如来。宝物として運慶作の阿弥陀如来像が記載されているので、御本尊は運慶作かもしれません。
また、宝物として慈覚大師御作の不動明王像が記載されているので、目黄不動尊は慈覚大師の御作かもしれません。
智證大師御真筆の不動尊一幅も宝物とされています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂(手前)と不動堂(左奥)


【写真 上(左)】 目黄不動尊の石碑
【写真 下(右)】 不動堂
本堂向かって左手に不動堂。
こちらも意匠的に特徴があり。造りはよくわかりませんが銅板葺で、向拝柱を備えています。
不動堂左前に「目黄不動尊」の石碑。
格子戸越しに御内陣が拝せます。
目黄不動尊はご内陣中央に御座。
朱の迦楼羅炎を背負われ、右手に劍、左手に羂索をもたれる黒色の引き締まった立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 板碑
本堂前には板碑二体ありましたが、こちらは宝物の南北朝期の板碑二体かもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、Web情報によるとご不在の場合も。書置対応もされているようですが、事前確認がベターかもしれません。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目黄不動 「江戸五色不動」の印判 直書(筆書)
(つづく) → こちら
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 2.目黒不動尊
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊、4.目赤不動尊、5.目黄不動尊(永久寺)
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 6.目黄不動尊(最勝寺)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 朝霞五社巡り

埼玉県朝霞市の御朱印といえば、出雲大社埼玉分院が有名ですが、一昨年(2019年)?あたりから「朝霞五社巡り」が開創され、市内五社の御朱印が授与されています。
この五社にはこちらでご紹介した美女神社も含まれています。
五社は新河岸川をはさむかたちで鎮座し、武蔵野台地と新河岸川沿いの低湿地を行き来するルートとなるので、地勢的にも面白い神社巡りだと思います。
5社とは、宮戸神社、内間木神社、田島神明神社、美女神社、天明稲荷神社です。
5社の内4社は非常駐で、御朱印はまとめて天明稲荷神社で拝受できます。
5社すべてお参りすると、満願札も授与いただけます。
お納めは以前は1通300円でしたが、現在は500円となっています。
5社で2,500円ですが、書置タイプはすこぶる美しく、また満願札も授与いただけ、わたしの満願時にはお守り(大麻)もいただけたので、個人的には満足の神社巡りでした。

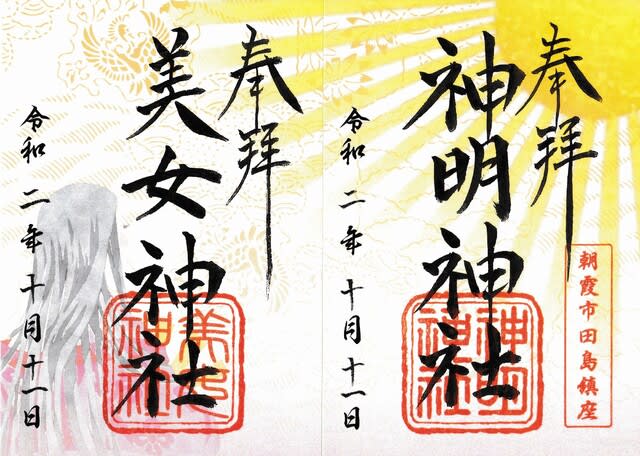


天明稲荷神社は、東武東上線「朝霞台」駅・JR武蔵野線「北朝霞」駅から歩ける距離です。(約20分)
徒歩で5社をゆっくり回ると2~3時間程度の所要かと思います。
車の場合は、天明稲荷神社に3台ほどのPがあり、ここから一番遠い内間木神社にも大きめのPがあります。
宮戸神社、田島神明神社には駐車スペースがありますが、美女神社にはPも駐車スペースもありません。
ご祈祷等によりPが満車となる可能性もありますので、天明稲荷神社様(TEL:048-471-3401)に事前確認がベターかと。
車の場合、短時間で結願してしまいますので、先日ご紹介した平林寺と組み合わせての寺社巡り&御朱印三昧も面白いかと思います。
なお、平林寺の御朱印は団体が入ると切れてしまう可能性があるので、AM平林寺、PM朝霞五社巡りがベターかと思います。(なお、平林寺は11月〜翌1月の期間中(混雑期)は、御朱印の授与はありません。)
今回、歩いて巡拝しましたので、途中の風景なども撮影しています。
まずは概要のみ先にUPし、詳細は追って追加していきます。
-----------------------------------------------------
1.宮戸神社(みやどじんじゃ)
埼玉県朝霞市宮戸4-3-1
御祭神:面足尊、伊弉諾尊、伊弉冉尊、稲倉魂命、高良玉垂姫命
旧社格:村社 旧宮戸村鎮守
元別当:薬王山 仏眼院 寶(法)蔵寺(朝霞市宮戸)
授与所:天明稲荷神社社務所
朱印揮毫:宮戸神社 書置ないし直書(筆書)
公式Web
「猫の足あと」様




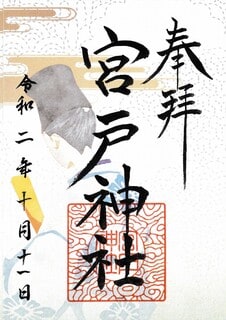

【写真 上(左)】 現在の書置御朱印
【写真 下(右)】 以前の揮毫御朱印
社伝および「猫の足あと」様の情報によると、中世に熊野信仰が高まった際に熊野社として創建したという説があり、公式Webには「古くは熊野権現様として親しまれ」と明記されています。
当社で祀られている伊弉諾尊・伊弉冉尊は熊野信仰の中心的な祭神で、熊野社説を裏付けるものとみられます。
面足尊は、『古事記』において神世七代の第六代の神とされ、人体の完備を神格化した神格とされます。
とくに、「オモダル」は「男子の顔つきが満ち足りていること」の意も含むとされ、言葉をくだくと”イケメン”の神様です。
朝霞五社巡りには、美女神社も入っていますので、イケメンと美女にゆかりのある神社を回ることになり、実際、天明稲荷神社では「美男守」「美女守」が頒布されています。
面足尊は、中世には神仏習合により第六天魔王の垂迹であるとされ、とくに修験道で信奉されました。志木町宗岡村字袋鎮座の天津神社を移転された際、その御祭神として遷座されたとされています。
明治四十年、神社合祀令により浜崎の氷川神社に田島の神明神社とともに三柱神社として合祀されましたが三柱神社の遥拝所として存続。
地元の強い要望により、昭和十七年、志木町宗岡村字袋鎮座の天津神社を移転して天津神社となり、翌十八年、宗岡村字下ノ谷鎮座の稲荷神社を合祀して宮戸神社と改称しました。
他地の御祭神、とくに氏神様の御遷座は容易ではないと思われますが、『埼玉の神社/埼玉県神社庁刊』にはこの時の経緯が詳細に記されているので以下に引用させていただきます。
(引用)-----------------------------
折しも隣村の宗岡村の字袋と字下ノ谷では、いずれも狭隘な境内を持つ無格社を祀っていたために合祀の対象となり、その回避策として今よりも広い境内地への移転が検討されていた。
大字宮戸と字袋・字下ノ谷の三者の利害の一致がその後の協議を円滑に進めていくことになった。
昭和十七年に宗岡村字袋の天津神社を大字宮戸の三柱神社遥拝所の地に迎え、翌十八年には宗岡村字下ノ谷の稲荷神社を天津神社に合祀したのを機に社号を宮戸神社に改め、村社に列した。
大字宮戸は三柱神社の氏子であったため、この移転及び合祀に関しては浜崎の人たちの合意を得る必要があった。
浜崎に対して、宮戸では宮戸神社を崇敬すると共に三柱神社も従来通り氏神として崇敬していく旨の協定を結び、移転願いに連署を求めた。
また、字袋と字下ノ谷とは、従来通りの形で氏子として存続していくことを約した。
(引用おわり)-----------------------------
昭和三十一年、浜崎の三柱神社より旧熊野権現社の御祭神を返還のうえ、宮戸神社に合祀しています。
『埼玉の神社/埼玉県神社庁刊』には、この際、宮戸地内から御遷座の駒形(高麗方)神社は本殿に、元別当の法藏寺の旧地薬師堂山に祀られていた日王子神社・白山神社、および稲荷神社などが境内に合祀されたとあります。
駒形(高麗方)神社の御祭神、高良玉垂姫命は福岡県久留米市の高良大社(旧国幣大社)の御祭神で、埼玉でも数社ある駒形神社で祀られていますが、北九州の御祭神がなぜ埼玉で祀られているのかはナゾとされているようです。(→参考Web)

浜崎氷川神社
現在の五柱の御祭神について、公式Webには下記の記載があります。
「御祭神は面足尊(旧天津神社祭神)、イザナギノミコト・イザナミノミコト(旧熊野神社祭神)、稲倉魂命(旧稲荷神社祭神)、高良玉垂姫命(旧高麗方神社祭神)」
朝霞五社巡りでは、宮戸神社が本務社で他の4社は兼務社にあたります。
ご神職は、兼務社の天明稲荷神社に常駐されているため、御朱印等は天明稲荷神社での授与となっています。
朝霞台の台地から下ってくる宮戸橋通りが新河岸川に差しかかる手前の、小高いところに御鎮座。いかにも神社的な立地です。
社頭に石造明神鳥居と「村社 宮戸神社」の社号標。
切割り状の参道石段。石段上の玉垣内にわかりにくいですが一対の狛犬。
右手に御神木、左手に大山阿夫利講の石尊大権現の石塔と力石。
少し進んで右手に手水舎、前方に石灯籠一対、狛犬一対。
入母屋造平入り銅板葺の拝殿と流造銅板葺の本殿を石の間(幣殿)で結ぶ権現造系のつくりだと思います。屋根勾配は急で、引き締まった感じの外観です。
どちらも妻部には鬼板と懸魚を置いています。
拝殿は流れ向拝で海老虹梁。海老虹梁と頭貫の端部に簡素な木鼻。
正面桟唐戸の上に社号「宮戸神社」の扁額。手挟に唐花文様の彫刻。軒天には二軒の平行垂木。
拝殿右手には手前から神明神社、御嶽神社、日王子神社、白山神社、天満宮、水神社、弁天神社、護国神社。本殿裏手には、新田組稲荷神社、宿組稲荷神社、久保組稲荷神社などの稲荷神社が境内社として鎮座しています。
昭和三十一年の本格再興ながら、いまでは地域の中核社らしく、多くの境内社を擁しています。


【写真 上(左)】 巡拝途中の風景
【写真 下(右)】 新河岸川
2.内間木神社(うちまきじんじゃ)
埼玉県朝霞市上内間木443
御祭神:日本武尊
旧社格:村社 上内間木地区の鎮守
授与所:天明稲荷神社社務所
朱印揮毫:内間木神社 書置ないし直書(筆書)
公式Web
「猫のあしあと」様




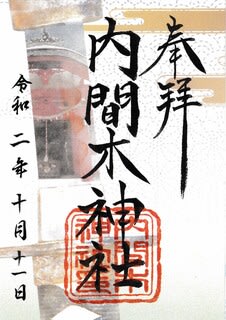

【写真 上(左)】 現在の書置御朱印
【写真 下(右)】 以前の揮毫御朱印
社伝および「猫の足あと」様の情報によると、内間木村が上下に分村した元禄年間(1688-1704年)以降に、本村(下内間木)の蔵王権現社を分祀し重殿権現社(じゅうどのごんげんしゃ)として創建したという説があります。
明治四十年、上内間木字屋敷添の稲荷社と字厩尻の厳島社を境内社として合祀しました。
蔵王権現は、とくに修験道で尊崇された尊格で、大己貴命、少彦名命、国常立尊、日本武尊、金山毘古命などと同一視され、古来、蔵王権現を祀る神社で上記の神を祭神とした事例は多くみられます。
当社もその例に当たる可能性があるかもしれません。
上内間木は荒川と新河岸川に挟まれた低湿地帯で、とくに寛永六年(1629年)に旧入間川が荒川の本流となり流量が増えた後は、度々水害に見舞われたといいます。
前稿で「反面、豊かな水と平坦な地形を活かして、新田開発が盛んに進められました。」と書きました。
ただし、これは宝永四年(1707年)検地の石高の大幅増から推測されるもので、少なくとも天正十九年(1591年)までは大きな石高の増加(=新田の開発)はなかったとみられています。
『風土記稿』には「当地は低湿地のために度々水害に遭い、水田を開くことができず、自然堤防上を利用して畑作を行っていた。」とあるようです。(出典:『埼玉の神社/埼玉県神社庁刊』)


【写真 上(左)】 (下内間木村)氷川神社
【写真 下(右)】 いまも湿地が広がる下内間木の川沿い
旧内間木村はもともとは下内間木村が本村で、上内間木村は分村とされています。
下内間木村の鎮守は氷川神社で、『埼玉の神社/埼玉県神社庁刊』の(下内間木村)氷川神社の項を引いてみると、
「恐らく(村の)開発当初は、自然堤防上に集落と畑がわずかに存在していたと思われる。」
「当地は三面が川に囲まれてはいるが水利の便が悪く、水害や干ばつに苦しむ状態が長く続いた。」という記述があります。
『風土記稿』の「水田を開くことができず」というのは、水利の便が悪いためであったと考えられます。
「川に囲まれた低湿の地だから水利には困らないだろう」というのは素人考えで、大河川や暴れ川から水を取り込むことは容易でなかったのでは。
そういえば隣の志木市の宗岡地区も三方を川に囲まれた低湿の地ですが、やはり水利が悪かったらしく、野火止用水を新河岸川の上を渡して(いろは樋)導水しています。
川の上をわざわざ掛け樋して用水を引いていたわけで、川からの直接導水のむずかしさがうかがわれます。
それほどの厳しい土地柄ゆえ、風雨順時や水害防除はなにを置いても重視されたと思われます。
『古事記』には、日本武尊は山や河の荒ぶる神を平定したとあるので、水害除けがなによりも大切なこの地の祭神として祀られたのかもしれません。
旧社殿には朝霞市の文化財に指定されている大絵馬が飾られていましたが、現在は朝霞市の博物館に保管されています。
なお、当社のすぐそばにある(安養院)阿弥陀堂は志木の宝幢寺(志木市柏町/真言宗智山派)の末で、本尊は阿弥陀如来。
北足立八十八ヶ所霊場第85番の札所に当たります。
位置関係からみて当社の元別当かとも思いましたが、関連する史料は見当たりませんでした。
通行量の多い県道に面した社頭に、社号「鎮守 内間木神社」の社号標。
ここから長々と敷石の参道が延びています。
しばらく行くと一の鳥居は石造明神鳥居で「内間木神社」の扁額。この鳥居の真下で参道軸を斜めに変え、拝殿に向かいます。
拝殿前、石段下に二の鳥居の石造明神鳥居。昇って石灯籠二対。
入母屋造平入り銅板葺の拝殿と流造銅板葺の本殿を石の間(幣殿)で結ぶ権現造系のつくり。石の間(幣殿)の奥行きが短く入母屋造と流造がつながった感じです。
拝殿と本殿妻部に鬼板と蕪懸魚、本殿屋根には千木と堅魚木を置いています。
青銅色の屋根、朱塗りの木部に重厚な唐破風が加わって華やかなイメージの社殿。
頭貫に彫刻された木鼻、中備に板蟇股、正面黒檀色の桟唐戸(閉扉)のうえに「内間木神社」の扁額。
拝殿右手前には弁天神社と稲荷神社。弁天神社は字厩尻の厳島社、稲荷神社は字屋敷添の稲荷社からの御遷座とみられます。
ともに入母屋造平入りで、弁天神社の黒茶色の屋根と稲荷神社の朱色の屋根がいいコントラストをみせています。
拝殿下に広めの駐車場が新設されています。
3.田島神明神社(たじましんめいじんじゃ)
埼玉県朝霞市田島224
御祭神:天照皇大神、面足尊
旧社格:村社 田島地区の鎮守
元別当:冨善寺(朝霞市田島)
授与所:天明稲荷神社社務所
朱印揮毫:神明神社 書置ないし直書(筆書)
公式Web
「猫のあしあと」様






【写真 上(左)】 現在の書置御朱印
【写真 下(右)】 以前の揮毫御朱印
社伝および「猫の足あと」様の情報によると、当社の元別当、富善寺の開基(元和三年(1617年)と同時期の創建と推定されています。
もともとは久保(現在の朝志ヶ丘)に神明社として鎮座し、この地に御遷座。(久保の住民もともに移住という説あり。)
明治四十年、神社合祀令により浜崎の氷川神社に宮戸の熊野神社とともに三柱神社として合祀されましたが三柱神社の遥拝所として存続。
鎮守を浜崎に遷された田島の住民は、宮戸の熊野神社同様、志木町宗岡村字袋の天津神社の御分霊をこの地に勧請し神社として再興。
さらにもともとの鎮守の御祭神の返還を切望していましたが、昭和三十一年についに返還を果たし、名実共に再興を遂げました。
田島地区は、新河岸川と黒目川の合流地点にある低湿地で、しばしば水害を被りました。
高台にある浜崎とは水害に対する危機感がまったく違っていたと思います。
元別当の冨善寺も低地にあるので、江戸期は神社・別当の総力をあげて水害に対処していたことも想像されます。
水害からの加護の意味も含め、どうしても地区内に鎮守を祀りたかった思いがうかがわれます。
以上の由緒から、天照皇大神はもともとの鎮守・神明神社の御祭神、面足尊は宗岡村字袋の天津神社からの御分霊ということがわかります。(境内由緒書にも明記)
朝霞田島団地の新河岸川寄りにあります。
すぐ北隣は新河岸川の旧河道と思われる池(三日月湖?)もあり、古来からの低湿の地であることがわかります。
団地側の社頭に石の門柱、そこから鳥居に向かって石敷きの参道が延びています。
石造の神明鳥居で「神明神社」の扁額。
灯籠、狛犬は置かれず、見通しのよいシンプルな参道。
拝殿は身舎桁行三間の神明造平入りでおそらく銅板葺。
ただし、向背に石の間(幣殿)と切妻造ないし流造の本殿があるので、正確には神明造ではないかもしれません。
拝殿、本殿ともに立派な金色の千木と堅魚木を備えています。
張り出しの向拝はなく、桟唐戸上部格子、下部入子板(閉扉)で、拝殿内部はうかがえません。 拝みに横文字で「神明神社」の扁額。
拝殿右手には水神宮の石碑。左手奥には秋葉神社、八坂神社、御嶽神社、榛名神社が鎮座する社殿。
その手前には赤い鳥居の稲荷神社。
飛地境内社として五社巡りの1社、美女神社があります。
4.美女神社(びじょじんじゃ)
埼玉県朝霞市田島2-16-33
御祭神:市杵島姫命
旧社格:- 、田島神明神社の飛地境内社
元別当:冨善寺(朝霞市田島)
授与所:天明稲荷神社社務所
朱印揮毫:美女神社 書置ないし直書(筆書)
公式Web
「猫のあしあと」様



美女神社の御朱印(新/カラー書置Vers.)
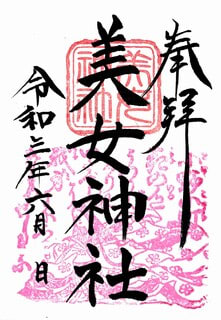
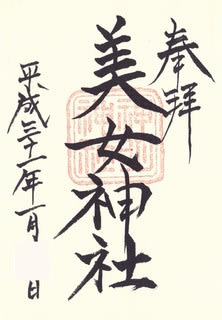
【写真 上(左)】 美女神社の御朱印(新/御朱印帳書入Vers.)
【写真 下(右)】 美女神社の御朱印(旧Vers.)
美女神社につきましては、別記事→こちらをご覧ください。
5.天明稲荷神社(てんめいいなりじんじゃ)
埼玉県朝霞市宮戸3-2-17
御祭神:大祖参神、天照大御神、月夜見神、彦火邇邇杵命、木花開耶姫命、宇迦御魂神
授与所:社務所
朱印揮毫:天明稲荷神社 書置ないし直書(筆書)
公式Web
「猫のあしあと」様




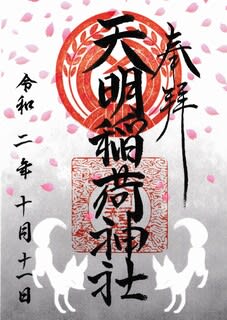

【写真 上(左)】 現在の書置御朱印
【写真 下(右)】 以前の揮毫御朱印
もとは柳澤清五郎の座敷神。由緒につきましては、公式Webをご覧ください。
御祭神の創祀については、よくわかりません。
大祖参神は、扶桑教(富士講系の教派神道の一派)では、天之御中主大神、高皇産霊大神、神皇産霊大神(造化三神)の総称とされるようです。
宮戸地区の高台に鎮座します。新河岸川からは直線距離で300mほどしかないのに、このあたりではもっとも高い場所かと思われます。
あたりは住宅が建て込み、アプローチの道も狭いですが、3台程度の駐車場があります。
社頭の石造の明神鳥居の奥には赤い鳥居が立ち並び、お狐さんの姿も見えて稲荷神社の空気感。
境内は広くはなく、屋敷神的な雰囲気を残しています。
参道わきにはたくさんのお狐さん。手水舎の水もお狐さんの口から出てきます。
拝殿前の石鳥居に「神明稲荷社」の扁額。
拝殿は新しく、流造銅板葺。海老虹梁、水引虹梁と木鼻に彫刻、中備に板蟇股。
身舎長押にも彫刻が施されています。
正面扉は一部格子窓なので、拝殿内部を拝せます。
御朱印は5社まとめて拝殿右手の授与所で拝受できます。
こちらは4回ほど御朱印を拝受していますが、ご対応いただいた方はいずれもご丁寧で親切でした。
授与所前には五社巡りの案内が掲示され、五社いずれの境内にも五社巡りの案内版が新設されていました。
このところ美女神社の参拝者が増えているようで、五社巡りにも力を入れられているようです。
ロケーションも御祭神も社殿もバラエティに富んでいて、充実の神社巡りをさせていただきました。
御朱印もすこぶる美しく、話題の美女神社も含むので、一度はトライされてはいかがでしょうか。
参考までに、これまでに朝霞市内で拝受した寺社御朱印もご紹介しようかと思いましたが、新型コロナウイルス感染急拡大の状況で、御朱印授与を中止されている可能性も高いので、今回は控えます。(出雲大社朝霞教会のみご紹介します。)
※朝霞市内の寺社では当初の予想以上に御朱印を拝受しています。
ただし市内にメジャー霊場の札所はなく、御朱印を拝受した寺社の多くはご不在再参拝ののち、御朱印帳をお預けしてご厚意で授与いただいたところがほとんどで、通常は授与されていない可能性もあると思います。
■ 出雲大社朝霞教会
公式Web
朝霞市本町2-20-18
御祭神:大国主大神
授与所:境内授与所


【写真 上(左)】 現在の境内
【写真 下(右)】 以前の境内
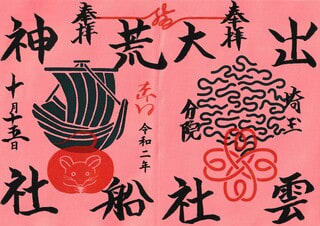
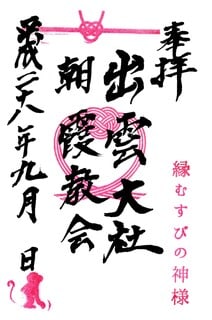
【写真 上(左)】 赤口の限定御朱印
【写真 下(右)】 以前の御朱印
絵御朱印・カラー御朱印マニアのあいだでは有名な神社です。
社伝(公式Web)によると、「当初、荒船神社として創建し、昭和五十八年には宗祠(出雲大社)よりご分霊をいただいて以来、埼玉県唯一の出雲大社として大国主大神をお祀りして参りました。」とのことです。
真新しい社殿の正面にかかる、全長約5mの大しめ縄は圧巻です。
以前は墨朱の片面御朱印も授与されていましたが、現在は両面のカラー絵御朱印がメインに授与されているようです。赤口の日には限定御朱印が授与されます。
なお、令和三年1月の御朱印頒布は1/12(火)からとのことです。(→詳細(公式Web))
■ 志木開運・招福七社参りもあります。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 塩船観音寺の御朱印
2021/05/02 UP
今年のつつじ祭りは開催されましたが、「新型コロナウィルス感染拡大の緊急事態につき」4/30で終了となっています。
今年は例年より10日ほど開花が早かったとのことで、すでに見頃は過ぎています。(→開花情報)
今後は6月~のあじさいへと移っていきます。





先日、参拝に行ってきました。
つつじの期間中は、駐車料金と拝観料がかかります。
弘誓閣横授与所での授与は休止していたようで、「白玉椿姫」など、こちらで授与の御朱印は授与されていなかったかもしれません。
なお、4月末時点で御朱印はすべて書置対応でした。
----------------------------
2017/08/07UP/202010/05更新UP/202011/03更新UP
東京都青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺。
真言宗醍醐派別格本山の格式を誇り、複数の霊場札所を兼ねるこの大寺は、華麗な筆遣いの御朱印でもよく知られています。
東京都青梅市塩船194
真言宗醍醐派 御本尊:十一面千手観世音菩薩
札所:関東八十八箇所第79番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第59番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第12番、武玉八十八ヶ所霊場第22番
公式Web
大化年間(645~650年)、若狭国の八百比丘尼が紫金の千手観音像を安置されたという開山伝承をもつ多摩有数の古刹で、数多くの文化財を有します。
天平年間、行基が「弘誓の舟」(仏が衆生を救おうとされる大きな願いの船)になぞられえて「塩船」と名付けられたとされる船形の独特な地形に建ち、その山肌を埋める約二万本のつつじの名所でもあります。


【写真 上(左)】 山内案内図
【写真 下(右)】 あじさいの名所でもあります


【写真 上(左)】 めずらしい船形地形
【写真 下(右)】 花の寺です
ちなみに、真言宗醍醐派は京都・醍醐寺を総本山とする古義真言宗の一派で、修験道の色彩が濃い宗派とされ、真言宗系修験道の主流をなす真言宗当山派の系譜につながるものとされます。
中世には武蔵七党の村山党の一族、金子氏、青梅勝沼城に拠った三田氏などの帰依を受け、三田氏と親交のあった連歌師宗長が当寺で連歌を詠むなど風流な歴史も伝わります。
関東八十八ヶ所霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場、奥多摩新四国八十八ヶ所霊場などの札所を兼ね、山内二箇所の授与所で授与される御朱印はそれぞれ異なるため、拝受できる御朱印の種類はWeb上でも錯綜していますが、数度にわたる参詣で、おそらく現在授与いただける御朱印はほぼ拝受できたような感じがするので、以下にご紹介してみます。
(なお、御朱印の授与内容はお寺さんのお考えやご事情により適宜定まるものなので、以降もこれらの御朱印が拝受可能かどうかはわかりません。)
【塩船観音寺の仏堂と御朱印】
山内入口から順に辿っていきます。諸堂の名称はおおむね公式Webに拠りました。


【写真 上(左)】 山門(仁王門)
【写真 下(右)】 山門(仁王門)の扁額
駐車場は広いですが、つつじの時期などは有料となるようです。
参道入口に「別格本山 塩船観音」の寺号標と重要文化財の茅葺きの山門(仁王門)。
山門は切妻造三間一戸藁葺の単層八脚門で、大棟に鰹木風の意匠と妻部に懸魚を備え、拝みに「大悲山」の扁額を掲げ、両脇間、菱格子の内に仁王尊が御座します。
天文二年(1533年)三田政定・綱定による修理の棟札が残ります。
力感あふれる仁王像(金剛力士像)は、東京都では鎌倉時代後期に仏師定快の工房で制作されたものと推定しています。(都指定有形文化財(彫刻))
【 明王院祈願堂 】
山門(仁王門)をくぐらずに右手の道を少し進むと、右手に「明王院祈願堂」があります。
寄棟造桟瓦葺のお堂で、変形千鳥破風的な向拝を置いています。
堂前の香炉に「千手観音御寶前」とあるのでいささか混乱しますが不動堂です。


【写真 上(左)】 明王院祈願堂
【写真 下(右)】 明王院祈願堂の御朱印
〔 明王院祈願堂の御朱印 〕
朱印尊格:明王院 書置(筆書)
札番:なし
・中央に不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)・揮毫と「明王院」の揮毫。
右上に奉拝印。左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
弘誓閣横授与所にて、1、4、7、10月の月限定で書置で授与されているようです。
【 阿弥陀堂 】
山門(仁王門)をくぐって参道を進むと正面が「阿弥陀堂」。
身舎桁行三間の寄棟造茅葺形銅板葺の内陣の四周に一間の庇を巡らせた阿弥陀堂形式の堂宇で、おそらく妻入りです。
東京都では室町時代後期の建築と推察しています。(重要文化財)
板張りで、装飾の少ない比較的簡素なつくりですが、きもちむくり気味の屋根のフォルムが引き締まって端正でバランスのよい堂宇です。
内部は天井の板張りがないので、かなり広く感じます。
堂宇の御本尊として阿弥陀三尊が御座します。
未確認ですが、阿弥陀三尊は他の仏堂に御座されないようなので、「阿弥陀三尊」は、こちらの御朱印かと思われます。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂
【写真 下(右)】 阿弥陀堂の御朱印
〔 阿弥陀堂の御朱印 〕
朱印尊格:阿弥陀三尊 書置(筆書)
札番:なし
中央に阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「阿弥陀三尊」の揮毫。右上に奉拝印、左には寺号と寺院印が捺されています。
「キリーク」の御寶印は、御本尊・千手観世音菩薩のものとはことなるデザインです。
本堂脇授与所にて、3、6、9、12月の月限定で書置で授与されているようです。
阿弥陀堂の左手を回り込んでさらに進むと、「塩船観音の大スギ(夫婦杉)」がそびえています。
二本のスギは都内でも有数の巨樹とされ、「高尾山の飯盛スギ」「奥多摩の氷川三本スギ」等とともに都の天然記念物に指定されています。
スギの横の石段をのぼると、正面に薬師堂が見えますが、本堂は右手の階段の上です。
階段手前に手水舎があります。
階段をのぼった正面に本堂、手前脇に御朱印授与所があります。左手の藁葺木部朱塗りの旧鐘楼も趣きがあります。


【写真 上(左)】 本堂下
【写真 下(右)】 本堂への参道


【写真 上(左)】 授与所前からの本堂
【写真 下(右)】 旧鐘楼
【 本堂 】
観音堂と書く資料もありますが、当寺の御本尊は観音様なので本堂=観音堂です。
寄棟造に苔むした茅葺、桁行・梁間ともに身舎五間のふところ深い仏殿です。
阿弥陀堂と同様、外観は簡素ですが、どっしりとした存在感を放つバランスのよい仏堂です。
国指定重要文化財で、室町時代後期の建築と推定されています。
こちらは有料で内部の拝観ができます。
向拝部正面の桟唐戸は上桟升格子中・下桟入子板で日中開戸を開放し、御内陣の様子が拝せます。扁額は閣号「圓通閣」。見上げれば垂木一連の上にぶ厚い茅葺。
須弥壇上の厨子内に御座す御本尊、十一面千手観世音菩薩は、文永元年(1264年)に、仏師法眼快勢・法橋快賢によりつくり始められたとされ、都の有形文化財に指定されています。
原則秘仏ですが、定期的な御開帳があります。
御真言は、千手観世音菩薩の「オン バザラ タラマ キリク」。
観世音(観自在)菩薩は三十三身に変化して衆生の危難苦悩を救われるとされ、千手観世音(観自在)菩薩は千の慈悲の眼で観て、千の慈悲の手(千手)でお救い下さる尊格とされます。
菩薩ながら数々の大寺の御本尊として御座される、力感あふれる仏さまです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の扁額
■ 本堂関連の御朱印
〔 御本尊・本堂の御朱印 / 通常御朱印 〕
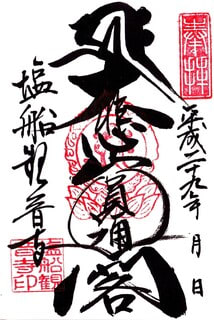
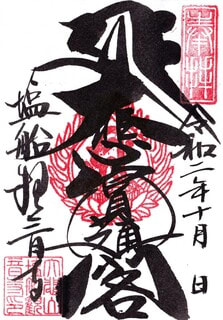
【写真 上(左)】 平成29年の御朱印
【写真 下(右)】 令和2年の御朱印
朱印尊格:大悲山圓通閣 直書(筆書)
札番:なし
通常御朱印の「大悲山圓通閣」は、御本尊・本堂をあらわす揮毫かと思われます。
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」、「大悲山圓通閣」の揮毫と「キリーク」の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、左に寺号と寺院印、右上に奉拝印が捺されています。
大悲とは衆生の苦しみを救おうとされる仏・菩薩の広大な慈悲の心で、当寺は大悲山を山号としています。
(「大悲殿」「大悲閣」はとくに観世音菩薩像を安置する仏堂を指し、観世音菩薩の御朱印を「大悲殿」「大悲閣」の主揮毫でいただくことも少なくありません。)
「圓通閣」は圓通大士(観世音菩薩)の御座す仏堂を指すので、この御朱印は山号+仏堂の主揮毫ですが、御本尊の種子の御寶印があり、御本尊の御朱印でもあると思います。
左に寺号と寺院印、右上に奉拝の印判が捺されています。
(関東周辺では主揮毫に山号が入る事例は少ないと思われます。)
御朱印界?ではすこぶる有名な御朱印で、さすがに流麗な筆致です。
↑ 【写真 上(左)】 が平成29年、【写真 下(右)】が令和2年の御朱印ですが、ほとんど筆致に差がないきわめて安定した揮毫です。
令和2年の御朱印では御寶印が火焔宝珠のみになり、寺院印もかわっています。
本堂脇授与所にて常時授与されています。
〔 御本尊の御朱印 / 関東八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
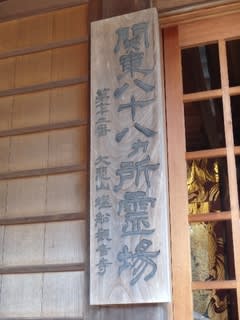

【写真 上(左)】 関東八十八ヶ所霊場の札所板
【写真 下(右)】 関東八十八ヶ所霊場の御朱印
朱印尊格:千手観世音 直書(筆書)
札番:関東八十八ヶ所霊場第72番
関東八十八ヶ所霊場の御朱印の「千手観世音」は、御本尊をあらわす揮毫かと思われます。
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手観世音」の揮毫右上に「関東第七十二番」の札所印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
左上にあるのはこの霊場の開創20周年特別巡礼記念印です。(平成28年)
通常御朱印「大悲山圓通閣」と札所御朱印「千手観世音」とで主揮毫が異なる例のひとつです。
本堂脇授与所にて常時授与されているようですが、見本が出ていないので霊場御朱印授与の申告が必要です。
〔 御本尊の御朱印 / 子年守本尊千手観音御朱印(限定) 〕

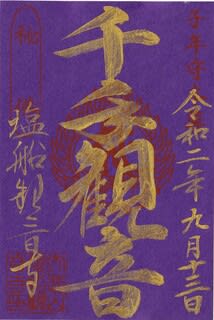
【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 子年守本尊千手観音御朱印
子年(令和二年)は御本尊・千手観世音菩薩が守り本尊となる、十二年に一度のご利益あらたかな年で、限定の特別御朱印が授与されています。
紺紙金泥の特別奉製で書置のみです。
朱印尊格:千手観音 書置(筆書)
札番:なし
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)「千手観音」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に「子年守本尊」、左上に「秘佛」の印判が捺されています。
なお、令和元年の限定御朱印として「観音妙智力」の紺紙金泥の御朱印が授与されていましたが、筆者は拝受しておりません。
〔 二十八部衆の御朱印(限定) 〕


【写真 上(左)】 二十八部衆の御朱印の案内
【写真 下(右)】 二十八部衆の御朱印
本堂内の二十八部衆像が令和2年3月19日に国指定重要文化財に指定されたことを祝し、限定御朱印が授与されています。(いつまでかは不明)
二十八部衆は御本尊・千手観世音菩薩の眷属で、 東西南北と上下に各四部、北東・東南・北西・西南に各一部ずつが配されて、千手観世音菩薩を守護します。
本堂の二十八部衆像のうち二十三体は鎌倉時代の文永五年(1267年)から弘安十一年(1288年)にかけて仏師定快とその一門によって造られ、残り五体は室町時代の永正九年(1512年)、鎌倉仏師弘円による造像とみられています。
朱印尊格:二十八部衆 書置(筆書)
札番:なし
中央に御本尊・千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+宝珠)。「二十八部衆」と種子「キリーク」の揮毫。
右上に奉拝印、左上に「令和重文」の記念印が捺され、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
お納めは500円ですが、「二十八部衆しおり」(一体)も授与いただけます。
〔 毘沙門天の御朱印 〕

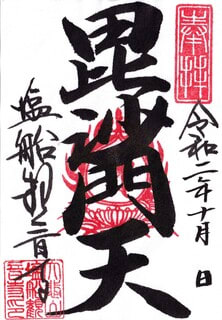
【写真 上(左)】 参道からの本堂
【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印
密寺では、千手観世音菩薩や十一面観世音菩薩の脇侍として、不動明王と毘沙門天を置く例が多くみられますが、こちらもその例です。
こちらの毘沙門天は仏師快勢一門により鎌倉時代に像立されたとみられ、青梅市の有形文化財に指定されています。
朱印尊格:毘沙門天 書置(筆書)
札番:なし
中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「毘沙門天」の揮毫。
右上に奉拝印、左に寺号と寺院印が捺されています。
本堂脇授与所にて、1、4、7、10月の月限定で書置で授与されているようです。
以上が、本堂に御座すとみられる尊格の御朱印です。
------------------------------------------
本堂は舟に例えると舳先ないし艫(船尾)の高みに当たり、ここから舷(舟べり)にあたる部分が尾根となって、艫(船尾)ないし舳先の高みにあたる場所(つつじ山)に御座する「塩船平和観音」に至ります。
尾根に向かわずに船底部分に降りると新護摩堂弘誓閣、本坊、交通安全祈願堂、売店・普門閣などがあります。
真言宗醍醐派系の寺院の多くは山の気が横溢するような一種独特な雰囲気をもち、ここ塩船観音寺も山門から本堂にかけては例外ではありません。
ただ、本堂から新護摩堂弘誓閣にかけては上に開けていくような地形のためか、どことなくあかるいイメージもあります。


【写真 上(左)】 本堂から弘誓閣方向
【写真 下(右)】 招福の鐘からの弘誓閣
【 塩船平和観音 】
当寺開創1350年の記念行事として、平成22年(2010年)に建立された聖観世音菩薩の立像です。つつじの季節には絶好の被写体ともなる有名な観音様です。
本堂から平和観音に向かう尾根上に、安産に霊験あらたかとされる児玉稲荷社、当山鎮守の山王七社権現社、有料で撞ける「招福の鐘」があります。


【写真 上(左)】 児玉稲荷社と山王七社権現社
【写真 下(右)】 招福の鐘
このお寺は船形地形なので風がよわいですが、ここまで来るとかなり風が通ります。
近くまで寄るとかなりの大きさの観音様です。
右手は施無畏印、左手与願印の持物、水瓶は下向きの注がれるかたちで、大慈大悲の功徳の妙薬「甘露水」が無限に注がれるさまをあらわしています。

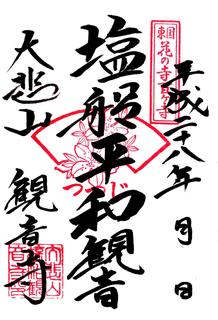
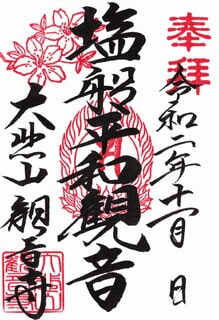
【写真 上(左)】 塩船平和観音(東国花の寺百ヶ寺霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 塩船平和観音の御朱印
〔 塩船平和観音の御朱印 / 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕
朱印尊格:塩船平和観音 直書(筆書)
札番:東国花の寺百ヶ寺霊場東京第12番
東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印の「塩船平和観音」は、こちらの尊格をあらわす揮毫となります。
中央に「塩船平和観音」の揮毫と花(つつじ)の印、右上に「東国花の寺百ヶ寺」の霊場印、左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
弘誓閣横授与所で揮毫授与いただきました。
〔 塩船平和観音の御朱印 〕
東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印ではない、「塩船平和観音の御朱印」も授与されています。
こちらは弘誓閣横授与所にて、2、5、8、11月の月限定で書置で授与され、中央の印が聖観世音菩薩の種子「サ」(蓮華座+火焔宝珠)となり、つつじの花判も入る華やかな印象の御朱印です。
【 新護摩堂弘誓閣 】
本堂から坂を下って開けたところにある護摩堂です。お堂前には不動明王が御座します。
平成10年(1998年)4月に落慶した祈願堂で、正式名は攝受院 護摩堂 弘誓閣。
弘誓とは、菩薩が悟りを開き衆生を救済されようとする決意、誓いを立てることとされます。
寄棟造銅板葺流れ向拝付き。照り屋根で荘厳な印象。向拝まわりの装飾は少ないですが、水引虹梁梁間の紋入蟇股、がっしりとした海老虹梁が目につきます。
向拝内身舎上部に「弘誓閣」の扁額。
身舎柱に「関東八十八ヶ所霊場」「東国花の寺百ヶ寺」の札所板が掲げられていて、こちらが霊場札所であることを示しています。
山内の掲示によると、弘誓閣の御本尊は、かつての本堂御本尊十一面千手観世音菩薩の御前立としてお祀りされていた尊像です。
よって、霊場巡拝の御真言も千手観世音菩薩の「オン バザラ タラマ キリク」です。
堂内西に不動明王、東にお大師様が御座し、東の間には八百比丘尼の尊像が安置されているそうです。


【写真 上(左)】 弘誓閣周辺
【写真 下(右)】 山腹からの弘誓閣
護摩堂(弘誓閣)向かって右(本坊内)に御朱印授与所があり、本堂横の授与所とは異なる御朱印が拝受できます。
(寺院印もこちらのものは山号入りで、本堂脇授与所のものとは異なります。)

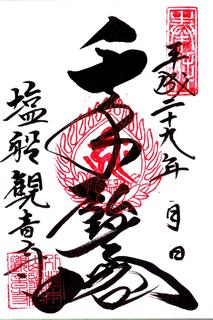
【写真 上(左)】 弘誓閣
【写真 下(右)】 千手弘誓閣の御朱印
〔 千手弘誓閣の御朱印 〕
朱印尊格:千手弘誓閣 直書(筆書)
札番:なし
中央に御本尊・千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
中央に「千手弘誓閣」の揮毫。右上に奉拝印、左に寺号と寺院印が捺されています。
真言密教の護摩堂の御本尊は不動明王が多いのですが、弘誓閣の御本尊は十一面千手観世音で御真言も千手観世音菩薩のものが掲出されています。
弘誓閣の御朱印尊格も「千手観世音菩薩」となっているかと思われます。
「大悲山圓通閣」「大悲山弘誓閣」とともに塩船観音寺を代表する御朱印とみられ、どっしり安定感のある素晴らしい筆致です。
※ 令和2年秋時点で弘誓閣横授与所の通常御朱印は「白玉椿姫」となっており、現在でも「千手弘誓閣」の御朱印をいただけるかは不明です。

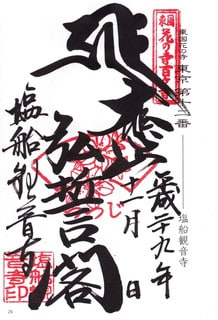
【写真 上(左)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の札所板
【写真 下(右)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
〔 大悲山弘誓閣の御朱印 / 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕
こちらは東国花の寺百ケ寺霊場の御朱印です。
「大悲山弘誓閣」は山号+仏堂の主揮毫だと思われます。
朱印尊格:大悲山弘誓閣 書置(筆書)
札番:東国花の寺百ヶ寺霊場東京第12番
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」、「大悲山弘誓閣」の揮毫と「つつじ」の花の印判。右上に印刷で霊場名と札番(東国花の寺東京第十二番)、「東国花の寺百ケ寺」の札所印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
なお、こちらは現在、霊場規定用紙書置きタイプの授与のみと思われます。
本堂脇授与所で授与いただきました。
Web上では東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印で、主揮毫が「大悲山弘誓閣」のものと「塩船平和観音」のものが見つかります。
これは断言できないのですが、「東国花の寺百ヶ寺」で申告した場合、本堂脇授与所では「大悲山弘誓閣」(現在・規定用紙書置)、弘誓閣横授与所では「塩船平和観音」(御朱印帳書入)の御朱印の授与となるような感じがします。
こちらはつつじの名所なので「花の寺」で授与を受ける参詣者が多く、しかも本堂脇授与所は山門寄りに位置する(=入り口に近い)ので、「大悲山弘誓閣」の御朱印拝受の方が多いのではないでしょうか。


【写真 上(左)】 弘誓閣の扁額
【写真 下(右)】 白玉椿姫の御朱印(以前)
〔 白玉椿姫の御朱印(以前) 〕
白玉椿姫は大化年間(645~650年)、当山を開山されたという八百比丘尼様の別名とされます。
八百比丘尼様のお像は弘誓閣内に御座されています。
朱印尊格:白玉椿姫 直書(筆書)
札番:なし
中央に三寶印と「白玉椿姫」の揮毫。右上に奉拝印、左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

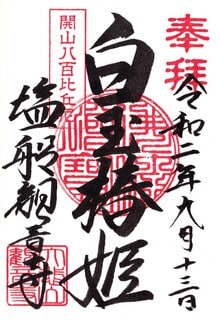
【写真 上(左)】 弘誓閣の向拝
【写真 下(右)】 白玉椿姫の御朱印(現行)
〔 白玉椿姫の御朱印(現行) 〕
「開山八百比丘尼」の印判が追加され、山号・寺号の揮毫が寺号のみになっています。寺院印もかわっています。


【写真 上(左)】 八百比丘尼様の説明
【写真 下(右)】 開山八百比丘尼の御朱印
〔 開山八百比丘尼の御朱印 〕
朱印尊格:開山八百比丘尼 直書(筆書)
札番:なし
Web上で「開山八百比丘尼」を主揮毫とする御朱印を確認していたので、お訊ねしたところいただけました。印判は「白玉椿姫」と同じものです。
現在、「白玉椿姫」の御朱印に「開山八百比丘尼」の印判が捺されますので、この「開山八百比丘尼」の御朱印は授与されていないかもしれません。
【 薬師堂 】
本堂階段下にあり、青梅市の有形文化財です。
桁行三間梁間二間の寄棟造藁葺。太い丸太の垂木が印象的です。
こちらも阿弥陀堂と同様、天井張りがないので、身舎の規模のわりに内部が広く感じます。
向拝部は桟唐戸上桟連子他入子板ですが、両開きで日中開扉されているので御本尊を直接拝めます。
御本尊として藤原仏とみられる木製の薬師如来立像が御座します。
寺伝によると、かつては脇侍として日光、月光両菩薩がおられたそうですが、いまは遺失しています。
ぼけ封じに霊験あらたかとされるお薬師様で、毎年9月の第二日曜日に薬師如来大祭 ~ぼけ封じ生姜まつり~ が行われます。
今年は9月13日の予定でしたが、新型コロナ感染拡大を受けて中止となっています。
ただし当日、ご縁日(大祭)の御朱印は授与されていました。

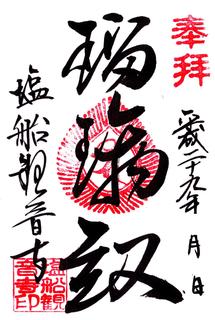
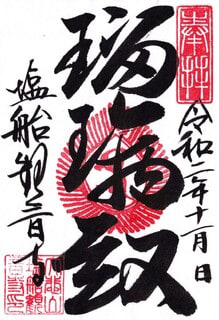
【写真 上(左)】 薬師堂の御朱印(平成29年)
【写真 下(右)】 薬師堂の御朱印(令和2年)
〔 薬師堂の御朱印 〕
朱印尊格:瑠璃殿 直書(筆書)
札番:なし
授与御朱印の「瑠璃殿」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に薬師如来の種子「バイ」の御寶印(火焔宝珠)と「瑠璃殿」の揮毫。
右上に奉拝印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
薬師如来は薬師瑠璃光如来とも称され、「瑠璃殿」は薬師如来が御座す仏堂を指します。上野・寛永寺の「瑠璃殿」の御朱印は有名です。
この御朱印はWeb上で発見し、本堂脇授与所で薬師如来(薬師堂)の御朱印の有無をお尋ねしたところ、この「瑠璃殿」の御朱印を拝受できました。
令和2年秋現在、月替わり御朱印となっており、本堂脇授与所にて2、5、8、11月の月限定で書置で授与されているようです。
令和2年の御朱印では、奉拝印と寺院印が変わっています。

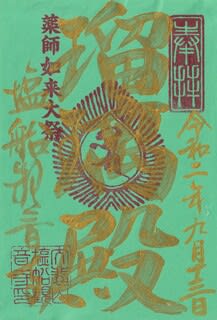
【写真 上(左)】 薬師如来大祭の案内
【写真 下(右)】 薬師堂(薬師如来大祭)の御朱印
〔 薬師堂(薬師如来大祭)の御朱印(限定) 〕
朱印尊格:瑠璃殿 書置(筆書)
札番:なし
緑紙に金泥奉製で書置のみです。
中央に薬師如来の種子「バイ」の御寶印(火焔宝珠)と「瑠璃殿」の揮毫。
右上に奉拝印、左上に「薬師如来大祭」の印判、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
【 大師堂 】
薬師堂の向かって右手のこぢんまりとしたお堂です。
薬師如来とお大師様が御座され、奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の第59番札所となっています。
切妻造妻入り桁行一間。梁に「弘法大師」の扁額、柱に「奥多摩新四國霊場第五十九番」の札所板を掲げています。堂内には御詠歌の掲出もあります。
札番が刻まれた石造台座のうえ、向かって左手にお大師さま、右手に薬師如来。
奥多摩霊場の尊像はかわいい感じのものが多いのですが、こちらのお像もそのようなイメージです。
たくさんのお供えがあり、大切に供養されていることがうかがえます。
奥多摩新四国八十八ヶ所霊場(奥多摩霊場新四国八十八札所)は、奥多摩(東京都西部・埼玉県西南部)地域にある弘法大師を巡拝する88か所の霊場で、昭和九年(1934年)に西多摩郡瑞穂町の武田弥兵衛らを中心とする大師講(東京善心講)によって彫られた88体の大師像および尊格が寺院などに安置され札所となって開創されました。
専用納経帳は昭和46年11月に発行されていますが、現在入手はむずかしくなっているかもしれません。(復刻版があるようです。)
個人宅納経もあるので御朱印帳や書置による授与は困難で、専用納経帳に捺印をいただく(もしくは自分で捺す)という形となります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の札所板

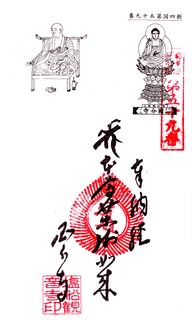
【写真 上(左)】 小さなお堂ですが華やぎがあります
【写真 下(右)】 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の御朱印
〔 大師堂の御朱印 / 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
朱印尊格:弘法大師・薬師如来 専用納経帳に捺印
札番:奥多摩新四国八十八ヶ所霊場第59番
御朱印は冊子版の専用納経帳にいただきました。
上に薬師如来と真如親王様のお大師様の御影。中央に薬師如来の種子「バイ」の御寶印(火焔宝珠)。「本尊 薬師如来」は印刷です。
右上に「奥多摩新四国第五十九番」の札所印、左に寺号(印刷)と寺院印という構成です。
なお、Webでは御朱印帳にいただいたとみられる奥多摩新四国八十八ヶ所霊場第59番の御朱印がみつかりますが、こちらの朱印揮毫も薬師如来となっています。
※現時点では、御朱印帳授与はされていない模様です。

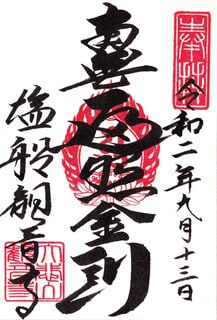
【写真 上(左)】 大師堂の扁額
【写真 下(右)】 お大師さまの御朱印
〔 お大師さまの御朱印 〕
朱印尊格:南無遍照金剛 書置(筆書)
札番:なし
お大師さまの種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、「南無遍照金剛」(御寶号)の揮毫。右上に奉拝印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
真言宗ならではのありがたい御朱印です。
弘誓閣横授与所にて3月、6月、9月、12月の月限定で書置で授与されているようです。
なお、お大師さまの種子は弥勒菩薩と同じ「ユ」ですが、これは、お大師さまのご誓願「われ、閉目ののちは兜率天に往生し、弥勒慈尊の御前に仕え、五十億余年ののち、必す慈尊とともに下生せん」(「高野山霊宝館公式Web」より)にちなみ、定められたとされています。
御朱印拝受のための参拝先は、弘誓閣か大師堂のいずれかだと思われますが、いずれにしても御朱印をいただく折には、御寶号「南無大師遍照金剛」のお唱えは必須かと。
■御朱印授与所
上記のとおり、本堂脇と弘誓閣横の二箇所あります。
○ 本堂脇授与所でいただいた御朱印
1.「大悲山圓通閣」(本堂)/通常御朱印
2.「千手観世音」(御本尊/関東八十八ヶ所霊場)
3.「瑠璃殿」(薬師堂)(2月、5月、8月、11月限定)
4.「本尊 薬師如来」(大師堂/奥多摩新四国八十八ヶ所霊場/専用納経帳に捺印)
5.「大悲山弘誓閣」(東国花の寺百ヶ寺霊場/規定用紙書置)
6.「毘沙門天」(1月、4月、7月、10月限定)
7.「阿弥陀三尊」(3月、6月、9月、12月限定)
8.「二十八部衆」(国指定重要文化財奉祝御朱印/限定)
9.「千手観世音」(子年守本尊千手観音御朱印/限定)
10.「瑠璃殿」(薬師堂)薬師大祭(薬師大祭限定授与)
○ 弘誓閣横授与所でいただいた御朱印
1.「白玉椿姫」(開山 八百比丘尼様の別名)/通常御朱印
2.「千手弘誓閣」(弘誓閣) ※ 現在の授与不明
3.「塩船平和観音」(東国花の寺百ヶ寺霊場)
4.「開山 八百比丘尼」 ※ 現在の授与不明
5.「南無遍照金剛」(3月、6月、9月、12月限定)
6.「明王殿」(不動明王)(1月、4月、7月、10月限定)
7.「塩船平和観音」(2月、5月、8月、11月限定)
原則、ともに1.の通常御朱印のみ御朱印書き入れ可です。
ただし、令和2年10月上旬時点では、新型コロナ感染拡大対策として通常御朱印も書置対応となっています。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
Ebb and Flow (凪のあすから) - LaLa
西風の贈り物 - 志方あきこ
SterCrew - みにゅ
抜群の美声。SterCrewのベストテイクでは? もう歌ってくれないのかな? 歌ってほしい曲がいっぱいある。
今年のつつじ祭りは開催されましたが、「新型コロナウィルス感染拡大の緊急事態につき」4/30で終了となっています。
今年は例年より10日ほど開花が早かったとのことで、すでに見頃は過ぎています。(→開花情報)
今後は6月~のあじさいへと移っていきます。





先日、参拝に行ってきました。
つつじの期間中は、駐車料金と拝観料がかかります。
弘誓閣横授与所での授与は休止していたようで、「白玉椿姫」など、こちらで授与の御朱印は授与されていなかったかもしれません。
なお、4月末時点で御朱印はすべて書置対応でした。
----------------------------
2017/08/07UP/202010/05更新UP/202011/03更新UP
東京都青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺。
真言宗醍醐派別格本山の格式を誇り、複数の霊場札所を兼ねるこの大寺は、華麗な筆遣いの御朱印でもよく知られています。
東京都青梅市塩船194
真言宗醍醐派 御本尊:十一面千手観世音菩薩
札所:関東八十八箇所第79番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所第59番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第12番、武玉八十八ヶ所霊場第22番
公式Web
大化年間(645~650年)、若狭国の八百比丘尼が紫金の千手観音像を安置されたという開山伝承をもつ多摩有数の古刹で、数多くの文化財を有します。
天平年間、行基が「弘誓の舟」(仏が衆生を救おうとされる大きな願いの船)になぞられえて「塩船」と名付けられたとされる船形の独特な地形に建ち、その山肌を埋める約二万本のつつじの名所でもあります。


【写真 上(左)】 山内案内図
【写真 下(右)】 あじさいの名所でもあります


【写真 上(左)】 めずらしい船形地形
【写真 下(右)】 花の寺です
ちなみに、真言宗醍醐派は京都・醍醐寺を総本山とする古義真言宗の一派で、修験道の色彩が濃い宗派とされ、真言宗系修験道の主流をなす真言宗当山派の系譜につながるものとされます。
中世には武蔵七党の村山党の一族、金子氏、青梅勝沼城に拠った三田氏などの帰依を受け、三田氏と親交のあった連歌師宗長が当寺で連歌を詠むなど風流な歴史も伝わります。
関東八十八ヶ所霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場、奥多摩新四国八十八ヶ所霊場などの札所を兼ね、山内二箇所の授与所で授与される御朱印はそれぞれ異なるため、拝受できる御朱印の種類はWeb上でも錯綜していますが、数度にわたる参詣で、おそらく現在授与いただける御朱印はほぼ拝受できたような感じがするので、以下にご紹介してみます。
(なお、御朱印の授与内容はお寺さんのお考えやご事情により適宜定まるものなので、以降もこれらの御朱印が拝受可能かどうかはわかりません。)
【塩船観音寺の仏堂と御朱印】
山内入口から順に辿っていきます。諸堂の名称はおおむね公式Webに拠りました。


【写真 上(左)】 山門(仁王門)
【写真 下(右)】 山門(仁王門)の扁額
駐車場は広いですが、つつじの時期などは有料となるようです。
参道入口に「別格本山 塩船観音」の寺号標と重要文化財の茅葺きの山門(仁王門)。
山門は切妻造三間一戸藁葺の単層八脚門で、大棟に鰹木風の意匠と妻部に懸魚を備え、拝みに「大悲山」の扁額を掲げ、両脇間、菱格子の内に仁王尊が御座します。
天文二年(1533年)三田政定・綱定による修理の棟札が残ります。
力感あふれる仁王像(金剛力士像)は、東京都では鎌倉時代後期に仏師定快の工房で制作されたものと推定しています。(都指定有形文化財(彫刻))
【 明王院祈願堂 】
山門(仁王門)をくぐらずに右手の道を少し進むと、右手に「明王院祈願堂」があります。
寄棟造桟瓦葺のお堂で、変形千鳥破風的な向拝を置いています。
堂前の香炉に「千手観音御寶前」とあるのでいささか混乱しますが不動堂です。


【写真 上(左)】 明王院祈願堂
【写真 下(右)】 明王院祈願堂の御朱印
〔 明王院祈願堂の御朱印 〕
朱印尊格:明王院 書置(筆書)
札番:なし
・中央に不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)・揮毫と「明王院」の揮毫。
右上に奉拝印。左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
弘誓閣横授与所にて、1、4、7、10月の月限定で書置で授与されているようです。
【 阿弥陀堂 】
山門(仁王門)をくぐって参道を進むと正面が「阿弥陀堂」。
身舎桁行三間の寄棟造茅葺形銅板葺の内陣の四周に一間の庇を巡らせた阿弥陀堂形式の堂宇で、おそらく妻入りです。
東京都では室町時代後期の建築と推察しています。(重要文化財)
板張りで、装飾の少ない比較的簡素なつくりですが、きもちむくり気味の屋根のフォルムが引き締まって端正でバランスのよい堂宇です。
内部は天井の板張りがないので、かなり広く感じます。
堂宇の御本尊として阿弥陀三尊が御座します。
未確認ですが、阿弥陀三尊は他の仏堂に御座されないようなので、「阿弥陀三尊」は、こちらの御朱印かと思われます。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂
【写真 下(右)】 阿弥陀堂の御朱印
〔 阿弥陀堂の御朱印 〕
朱印尊格:阿弥陀三尊 書置(筆書)
札番:なし
中央に阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「阿弥陀三尊」の揮毫。右上に奉拝印、左には寺号と寺院印が捺されています。
「キリーク」の御寶印は、御本尊・千手観世音菩薩のものとはことなるデザインです。
本堂脇授与所にて、3、6、9、12月の月限定で書置で授与されているようです。
阿弥陀堂の左手を回り込んでさらに進むと、「塩船観音の大スギ(夫婦杉)」がそびえています。
二本のスギは都内でも有数の巨樹とされ、「高尾山の飯盛スギ」「奥多摩の氷川三本スギ」等とともに都の天然記念物に指定されています。
スギの横の石段をのぼると、正面に薬師堂が見えますが、本堂は右手の階段の上です。
階段手前に手水舎があります。
階段をのぼった正面に本堂、手前脇に御朱印授与所があります。左手の藁葺木部朱塗りの旧鐘楼も趣きがあります。


【写真 上(左)】 本堂下
【写真 下(右)】 本堂への参道


【写真 上(左)】 授与所前からの本堂
【写真 下(右)】 旧鐘楼
【 本堂 】
観音堂と書く資料もありますが、当寺の御本尊は観音様なので本堂=観音堂です。
寄棟造に苔むした茅葺、桁行・梁間ともに身舎五間のふところ深い仏殿です。
阿弥陀堂と同様、外観は簡素ですが、どっしりとした存在感を放つバランスのよい仏堂です。
国指定重要文化財で、室町時代後期の建築と推定されています。
こちらは有料で内部の拝観ができます。
向拝部正面の桟唐戸は上桟升格子中・下桟入子板で日中開戸を開放し、御内陣の様子が拝せます。扁額は閣号「圓通閣」。見上げれば垂木一連の上にぶ厚い茅葺。
須弥壇上の厨子内に御座す御本尊、十一面千手観世音菩薩は、文永元年(1264年)に、仏師法眼快勢・法橋快賢によりつくり始められたとされ、都の有形文化財に指定されています。
原則秘仏ですが、定期的な御開帳があります。
御真言は、千手観世音菩薩の「オン バザラ タラマ キリク」。
観世音(観自在)菩薩は三十三身に変化して衆生の危難苦悩を救われるとされ、千手観世音(観自在)菩薩は千の慈悲の眼で観て、千の慈悲の手(千手)でお救い下さる尊格とされます。
菩薩ながら数々の大寺の御本尊として御座される、力感あふれる仏さまです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂の扁額
■ 本堂関連の御朱印
〔 御本尊・本堂の御朱印 / 通常御朱印 〕
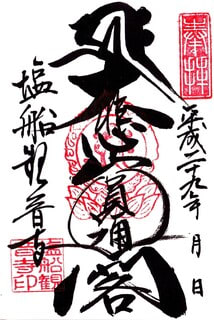
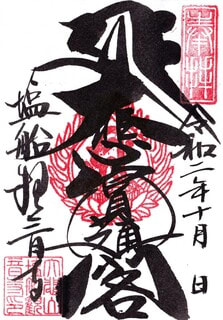
【写真 上(左)】 平成29年の御朱印
【写真 下(右)】 令和2年の御朱印
朱印尊格:大悲山圓通閣 直書(筆書)
札番:なし
通常御朱印の「大悲山圓通閣」は、御本尊・本堂をあらわす揮毫かと思われます。
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」、「大悲山圓通閣」の揮毫と「キリーク」の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、左に寺号と寺院印、右上に奉拝印が捺されています。
大悲とは衆生の苦しみを救おうとされる仏・菩薩の広大な慈悲の心で、当寺は大悲山を山号としています。
(「大悲殿」「大悲閣」はとくに観世音菩薩像を安置する仏堂を指し、観世音菩薩の御朱印を「大悲殿」「大悲閣」の主揮毫でいただくことも少なくありません。)
「圓通閣」は圓通大士(観世音菩薩)の御座す仏堂を指すので、この御朱印は山号+仏堂の主揮毫ですが、御本尊の種子の御寶印があり、御本尊の御朱印でもあると思います。
左に寺号と寺院印、右上に奉拝の印判が捺されています。
(関東周辺では主揮毫に山号が入る事例は少ないと思われます。)
御朱印界?ではすこぶる有名な御朱印で、さすがに流麗な筆致です。
↑ 【写真 上(左)】 が平成29年、【写真 下(右)】が令和2年の御朱印ですが、ほとんど筆致に差がないきわめて安定した揮毫です。
令和2年の御朱印では御寶印が火焔宝珠のみになり、寺院印もかわっています。
本堂脇授与所にて常時授与されています。
〔 御本尊の御朱印 / 関東八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
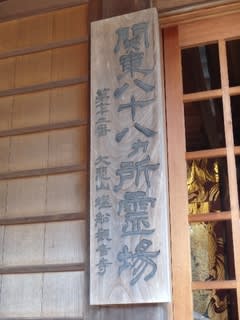

【写真 上(左)】 関東八十八ヶ所霊場の札所板
【写真 下(右)】 関東八十八ヶ所霊場の御朱印
朱印尊格:千手観世音 直書(筆書)
札番:関東八十八ヶ所霊場第72番
関東八十八ヶ所霊場の御朱印の「千手観世音」は、御本尊をあらわす揮毫かと思われます。
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手観世音」の揮毫右上に「関東第七十二番」の札所印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
左上にあるのはこの霊場の開創20周年特別巡礼記念印です。(平成28年)
通常御朱印「大悲山圓通閣」と札所御朱印「千手観世音」とで主揮毫が異なる例のひとつです。
本堂脇授与所にて常時授与されているようですが、見本が出ていないので霊場御朱印授与の申告が必要です。
〔 御本尊の御朱印 / 子年守本尊千手観音御朱印(限定) 〕

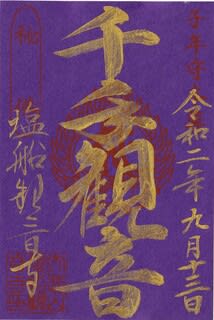
【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 子年守本尊千手観音御朱印
子年(令和二年)は御本尊・千手観世音菩薩が守り本尊となる、十二年に一度のご利益あらたかな年で、限定の特別御朱印が授与されています。
紺紙金泥の特別奉製で書置のみです。
朱印尊格:千手観音 書置(筆書)
札番:なし
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)「千手観音」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に「子年守本尊」、左上に「秘佛」の印判が捺されています。
なお、令和元年の限定御朱印として「観音妙智力」の紺紙金泥の御朱印が授与されていましたが、筆者は拝受しておりません。
〔 二十八部衆の御朱印(限定) 〕


【写真 上(左)】 二十八部衆の御朱印の案内
【写真 下(右)】 二十八部衆の御朱印
本堂内の二十八部衆像が令和2年3月19日に国指定重要文化財に指定されたことを祝し、限定御朱印が授与されています。(いつまでかは不明)
二十八部衆は御本尊・千手観世音菩薩の眷属で、 東西南北と上下に各四部、北東・東南・北西・西南に各一部ずつが配されて、千手観世音菩薩を守護します。
本堂の二十八部衆像のうち二十三体は鎌倉時代の文永五年(1267年)から弘安十一年(1288年)にかけて仏師定快とその一門によって造られ、残り五体は室町時代の永正九年(1512年)、鎌倉仏師弘円による造像とみられています。
朱印尊格:二十八部衆 書置(筆書)
札番:なし
中央に御本尊・千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+宝珠)。「二十八部衆」と種子「キリーク」の揮毫。
右上に奉拝印、左上に「令和重文」の記念印が捺され、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
お納めは500円ですが、「二十八部衆しおり」(一体)も授与いただけます。
〔 毘沙門天の御朱印 〕

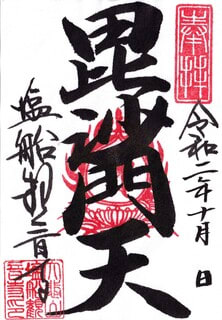
【写真 上(左)】 参道からの本堂
【写真 下(右)】 毘沙門天の御朱印
密寺では、千手観世音菩薩や十一面観世音菩薩の脇侍として、不動明王と毘沙門天を置く例が多くみられますが、こちらもその例です。
こちらの毘沙門天は仏師快勢一門により鎌倉時代に像立されたとみられ、青梅市の有形文化財に指定されています。
朱印尊格:毘沙門天 書置(筆書)
札番:なし
中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「毘沙門天」の揮毫。
右上に奉拝印、左に寺号と寺院印が捺されています。
本堂脇授与所にて、1、4、7、10月の月限定で書置で授与されているようです。
以上が、本堂に御座すとみられる尊格の御朱印です。
------------------------------------------
本堂は舟に例えると舳先ないし艫(船尾)の高みに当たり、ここから舷(舟べり)にあたる部分が尾根となって、艫(船尾)ないし舳先の高みにあたる場所(つつじ山)に御座する「塩船平和観音」に至ります。
尾根に向かわずに船底部分に降りると新護摩堂弘誓閣、本坊、交通安全祈願堂、売店・普門閣などがあります。
真言宗醍醐派系の寺院の多くは山の気が横溢するような一種独特な雰囲気をもち、ここ塩船観音寺も山門から本堂にかけては例外ではありません。
ただ、本堂から新護摩堂弘誓閣にかけては上に開けていくような地形のためか、どことなくあかるいイメージもあります。


【写真 上(左)】 本堂から弘誓閣方向
【写真 下(右)】 招福の鐘からの弘誓閣
【 塩船平和観音 】
当寺開創1350年の記念行事として、平成22年(2010年)に建立された聖観世音菩薩の立像です。つつじの季節には絶好の被写体ともなる有名な観音様です。
本堂から平和観音に向かう尾根上に、安産に霊験あらたかとされる児玉稲荷社、当山鎮守の山王七社権現社、有料で撞ける「招福の鐘」があります。


【写真 上(左)】 児玉稲荷社と山王七社権現社
【写真 下(右)】 招福の鐘
このお寺は船形地形なので風がよわいですが、ここまで来るとかなり風が通ります。
近くまで寄るとかなりの大きさの観音様です。
右手は施無畏印、左手与願印の持物、水瓶は下向きの注がれるかたちで、大慈大悲の功徳の妙薬「甘露水」が無限に注がれるさまをあらわしています。

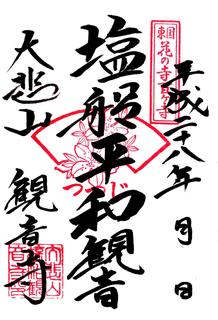
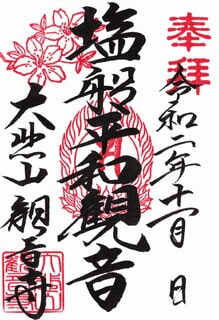
【写真 上(左)】 塩船平和観音(東国花の寺百ヶ寺霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 塩船平和観音の御朱印
〔 塩船平和観音の御朱印 / 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕
朱印尊格:塩船平和観音 直書(筆書)
札番:東国花の寺百ヶ寺霊場東京第12番
東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印の「塩船平和観音」は、こちらの尊格をあらわす揮毫となります。
中央に「塩船平和観音」の揮毫と花(つつじ)の印、右上に「東国花の寺百ヶ寺」の霊場印、左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
弘誓閣横授与所で揮毫授与いただきました。
〔 塩船平和観音の御朱印 〕
東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印ではない、「塩船平和観音の御朱印」も授与されています。
こちらは弘誓閣横授与所にて、2、5、8、11月の月限定で書置で授与され、中央の印が聖観世音菩薩の種子「サ」(蓮華座+火焔宝珠)となり、つつじの花判も入る華やかな印象の御朱印です。
【 新護摩堂弘誓閣 】
本堂から坂を下って開けたところにある護摩堂です。お堂前には不動明王が御座します。
平成10年(1998年)4月に落慶した祈願堂で、正式名は攝受院 護摩堂 弘誓閣。
弘誓とは、菩薩が悟りを開き衆生を救済されようとする決意、誓いを立てることとされます。
寄棟造銅板葺流れ向拝付き。照り屋根で荘厳な印象。向拝まわりの装飾は少ないですが、水引虹梁梁間の紋入蟇股、がっしりとした海老虹梁が目につきます。
向拝内身舎上部に「弘誓閣」の扁額。
身舎柱に「関東八十八ヶ所霊場」「東国花の寺百ヶ寺」の札所板が掲げられていて、こちらが霊場札所であることを示しています。
山内の掲示によると、弘誓閣の御本尊は、かつての本堂御本尊十一面千手観世音菩薩の御前立としてお祀りされていた尊像です。
よって、霊場巡拝の御真言も千手観世音菩薩の「オン バザラ タラマ キリク」です。
堂内西に不動明王、東にお大師様が御座し、東の間には八百比丘尼の尊像が安置されているそうです。


【写真 上(左)】 弘誓閣周辺
【写真 下(右)】 山腹からの弘誓閣
護摩堂(弘誓閣)向かって右(本坊内)に御朱印授与所があり、本堂横の授与所とは異なる御朱印が拝受できます。
(寺院印もこちらのものは山号入りで、本堂脇授与所のものとは異なります。)

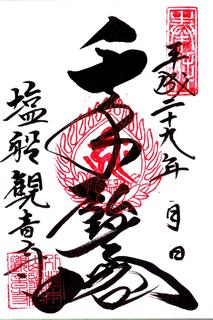
【写真 上(左)】 弘誓閣
【写真 下(右)】 千手弘誓閣の御朱印
〔 千手弘誓閣の御朱印 〕
朱印尊格:千手弘誓閣 直書(筆書)
札番:なし
中央に御本尊・千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
中央に「千手弘誓閣」の揮毫。右上に奉拝印、左に寺号と寺院印が捺されています。
真言密教の護摩堂の御本尊は不動明王が多いのですが、弘誓閣の御本尊は十一面千手観世音で御真言も千手観世音菩薩のものが掲出されています。
弘誓閣の御朱印尊格も「千手観世音菩薩」となっているかと思われます。
「大悲山圓通閣」「大悲山弘誓閣」とともに塩船観音寺を代表する御朱印とみられ、どっしり安定感のある素晴らしい筆致です。
※ 令和2年秋時点で弘誓閣横授与所の通常御朱印は「白玉椿姫」となっており、現在でも「千手弘誓閣」の御朱印をいただけるかは不明です。

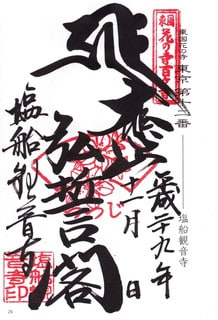
【写真 上(左)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の札所板
【写真 下(右)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
〔 大悲山弘誓閣の御朱印 / 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕
こちらは東国花の寺百ケ寺霊場の御朱印です。
「大悲山弘誓閣」は山号+仏堂の主揮毫だと思われます。
朱印尊格:大悲山弘誓閣 書置(筆書)
札番:東国花の寺百ヶ寺霊場東京第12番
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」、「大悲山弘誓閣」の揮毫と「つつじ」の花の印判。右上に印刷で霊場名と札番(東国花の寺東京第十二番)、「東国花の寺百ケ寺」の札所印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
なお、こちらは現在、霊場規定用紙書置きタイプの授与のみと思われます。
本堂脇授与所で授与いただきました。
Web上では東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印で、主揮毫が「大悲山弘誓閣」のものと「塩船平和観音」のものが見つかります。
これは断言できないのですが、「東国花の寺百ヶ寺」で申告した場合、本堂脇授与所では「大悲山弘誓閣」(現在・規定用紙書置)、弘誓閣横授与所では「塩船平和観音」(御朱印帳書入)の御朱印の授与となるような感じがします。
こちらはつつじの名所なので「花の寺」で授与を受ける参詣者が多く、しかも本堂脇授与所は山門寄りに位置する(=入り口に近い)ので、「大悲山弘誓閣」の御朱印拝受の方が多いのではないでしょうか。


【写真 上(左)】 弘誓閣の扁額
【写真 下(右)】 白玉椿姫の御朱印(以前)
〔 白玉椿姫の御朱印(以前) 〕
白玉椿姫は大化年間(645~650年)、当山を開山されたという八百比丘尼様の別名とされます。
八百比丘尼様のお像は弘誓閣内に御座されています。
朱印尊格:白玉椿姫 直書(筆書)
札番:なし
中央に三寶印と「白玉椿姫」の揮毫。右上に奉拝印、左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

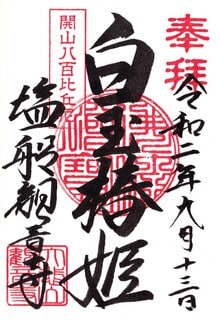
【写真 上(左)】 弘誓閣の向拝
【写真 下(右)】 白玉椿姫の御朱印(現行)
〔 白玉椿姫の御朱印(現行) 〕
「開山八百比丘尼」の印判が追加され、山号・寺号の揮毫が寺号のみになっています。寺院印もかわっています。


【写真 上(左)】 八百比丘尼様の説明
【写真 下(右)】 開山八百比丘尼の御朱印
〔 開山八百比丘尼の御朱印 〕
朱印尊格:開山八百比丘尼 直書(筆書)
札番:なし
Web上で「開山八百比丘尼」を主揮毫とする御朱印を確認していたので、お訊ねしたところいただけました。印判は「白玉椿姫」と同じものです。
現在、「白玉椿姫」の御朱印に「開山八百比丘尼」の印判が捺されますので、この「開山八百比丘尼」の御朱印は授与されていないかもしれません。
【 薬師堂 】
本堂階段下にあり、青梅市の有形文化財です。
桁行三間梁間二間の寄棟造藁葺。太い丸太の垂木が印象的です。
こちらも阿弥陀堂と同様、天井張りがないので、身舎の規模のわりに内部が広く感じます。
向拝部は桟唐戸上桟連子他入子板ですが、両開きで日中開扉されているので御本尊を直接拝めます。
御本尊として藤原仏とみられる木製の薬師如来立像が御座します。
寺伝によると、かつては脇侍として日光、月光両菩薩がおられたそうですが、いまは遺失しています。
ぼけ封じに霊験あらたかとされるお薬師様で、毎年9月の第二日曜日に薬師如来大祭 ~ぼけ封じ生姜まつり~ が行われます。
今年は9月13日の予定でしたが、新型コロナ感染拡大を受けて中止となっています。
ただし当日、ご縁日(大祭)の御朱印は授与されていました。

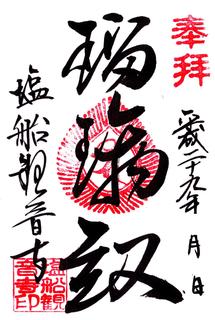
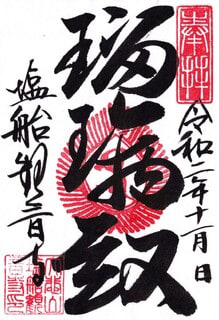
【写真 上(左)】 薬師堂の御朱印(平成29年)
【写真 下(右)】 薬師堂の御朱印(令和2年)
〔 薬師堂の御朱印 〕
朱印尊格:瑠璃殿 直書(筆書)
札番:なし
授与御朱印の「瑠璃殿」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に薬師如来の種子「バイ」の御寶印(火焔宝珠)と「瑠璃殿」の揮毫。
右上に奉拝印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
薬師如来は薬師瑠璃光如来とも称され、「瑠璃殿」は薬師如来が御座す仏堂を指します。上野・寛永寺の「瑠璃殿」の御朱印は有名です。
この御朱印はWeb上で発見し、本堂脇授与所で薬師如来(薬師堂)の御朱印の有無をお尋ねしたところ、この「瑠璃殿」の御朱印を拝受できました。
令和2年秋現在、月替わり御朱印となっており、本堂脇授与所にて2、5、8、11月の月限定で書置で授与されているようです。
令和2年の御朱印では、奉拝印と寺院印が変わっています。

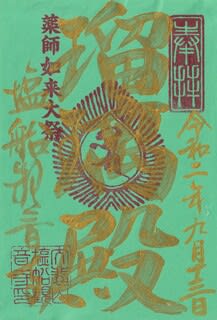
【写真 上(左)】 薬師如来大祭の案内
【写真 下(右)】 薬師堂(薬師如来大祭)の御朱印
〔 薬師堂(薬師如来大祭)の御朱印(限定) 〕
朱印尊格:瑠璃殿 書置(筆書)
札番:なし
緑紙に金泥奉製で書置のみです。
中央に薬師如来の種子「バイ」の御寶印(火焔宝珠)と「瑠璃殿」の揮毫。
右上に奉拝印、左上に「薬師如来大祭」の印判、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
【 大師堂 】
薬師堂の向かって右手のこぢんまりとしたお堂です。
薬師如来とお大師様が御座され、奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の第59番札所となっています。
切妻造妻入り桁行一間。梁に「弘法大師」の扁額、柱に「奥多摩新四國霊場第五十九番」の札所板を掲げています。堂内には御詠歌の掲出もあります。
札番が刻まれた石造台座のうえ、向かって左手にお大師さま、右手に薬師如来。
奥多摩霊場の尊像はかわいい感じのものが多いのですが、こちらのお像もそのようなイメージです。
たくさんのお供えがあり、大切に供養されていることがうかがえます。
奥多摩新四国八十八ヶ所霊場(奥多摩霊場新四国八十八札所)は、奥多摩(東京都西部・埼玉県西南部)地域にある弘法大師を巡拝する88か所の霊場で、昭和九年(1934年)に西多摩郡瑞穂町の武田弥兵衛らを中心とする大師講(東京善心講)によって彫られた88体の大師像および尊格が寺院などに安置され札所となって開創されました。
専用納経帳は昭和46年11月に発行されていますが、現在入手はむずかしくなっているかもしれません。(復刻版があるようです。)
個人宅納経もあるので御朱印帳や書置による授与は困難で、専用納経帳に捺印をいただく(もしくは自分で捺す)という形となります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の札所板

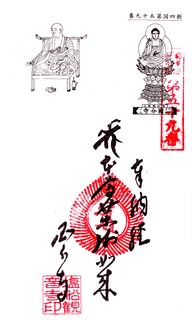
【写真 上(左)】 小さなお堂ですが華やぎがあります
【写真 下(右)】 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の御朱印
〔 大師堂の御朱印 / 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
朱印尊格:弘法大師・薬師如来 専用納経帳に捺印
札番:奥多摩新四国八十八ヶ所霊場第59番
御朱印は冊子版の専用納経帳にいただきました。
上に薬師如来と真如親王様のお大師様の御影。中央に薬師如来の種子「バイ」の御寶印(火焔宝珠)。「本尊 薬師如来」は印刷です。
右上に「奥多摩新四国第五十九番」の札所印、左に寺号(印刷)と寺院印という構成です。
なお、Webでは御朱印帳にいただいたとみられる奥多摩新四国八十八ヶ所霊場第59番の御朱印がみつかりますが、こちらの朱印揮毫も薬師如来となっています。
※現時点では、御朱印帳授与はされていない模様です。

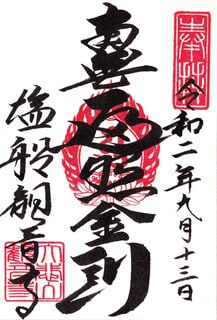
【写真 上(左)】 大師堂の扁額
【写真 下(右)】 お大師さまの御朱印
〔 お大師さまの御朱印 〕
朱印尊格:南無遍照金剛 書置(筆書)
札番:なし
お大師さまの種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、「南無遍照金剛」(御寶号)の揮毫。右上に奉拝印、左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
真言宗ならではのありがたい御朱印です。
弘誓閣横授与所にて3月、6月、9月、12月の月限定で書置で授与されているようです。
なお、お大師さまの種子は弥勒菩薩と同じ「ユ」ですが、これは、お大師さまのご誓願「われ、閉目ののちは兜率天に往生し、弥勒慈尊の御前に仕え、五十億余年ののち、必す慈尊とともに下生せん」(「高野山霊宝館公式Web」より)にちなみ、定められたとされています。
御朱印拝受のための参拝先は、弘誓閣か大師堂のいずれかだと思われますが、いずれにしても御朱印をいただく折には、御寶号「南無大師遍照金剛」のお唱えは必須かと。
■御朱印授与所
上記のとおり、本堂脇と弘誓閣横の二箇所あります。
○ 本堂脇授与所でいただいた御朱印
1.「大悲山圓通閣」(本堂)/通常御朱印
2.「千手観世音」(御本尊/関東八十八ヶ所霊場)
3.「瑠璃殿」(薬師堂)(2月、5月、8月、11月限定)
4.「本尊 薬師如来」(大師堂/奥多摩新四国八十八ヶ所霊場/専用納経帳に捺印)
5.「大悲山弘誓閣」(東国花の寺百ヶ寺霊場/規定用紙書置)
6.「毘沙門天」(1月、4月、7月、10月限定)
7.「阿弥陀三尊」(3月、6月、9月、12月限定)
8.「二十八部衆」(国指定重要文化財奉祝御朱印/限定)
9.「千手観世音」(子年守本尊千手観音御朱印/限定)
10.「瑠璃殿」(薬師堂)薬師大祭(薬師大祭限定授与)
○ 弘誓閣横授与所でいただいた御朱印
1.「白玉椿姫」(開山 八百比丘尼様の別名)/通常御朱印
2.「千手弘誓閣」(弘誓閣) ※ 現在の授与不明
3.「塩船平和観音」(東国花の寺百ヶ寺霊場)
4.「開山 八百比丘尼」 ※ 現在の授与不明
5.「南無遍照金剛」(3月、6月、9月、12月限定)
6.「明王殿」(不動明王)(1月、4月、7月、10月限定)
7.「塩船平和観音」(2月、5月、8月、11月限定)
原則、ともに1.の通常御朱印のみ御朱印書き入れ可です。
ただし、令和2年10月上旬時点では、新型コロナ感染拡大対策として通常御朱印も書置対応となっています。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
Ebb and Flow (凪のあすから) - LaLa
西風の贈り物 - 志方あきこ
SterCrew - みにゅ
抜群の美声。SterCrewのベストテイクでは? もう歌ってくれないのかな? 歌ってほしい曲がいっぱいある。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 血洗島 諏訪神社の御朱印
緊急事態宣言は解除されますが、引きつづき感染拡大防止策の徹底が要請されています。
参拝の際は、ご留意をお願いします。
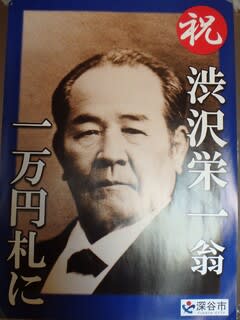

NHK大河ドラマ「青天を衝け」。近代ものにしては視聴率は好調のようです。
話題のスポットにはほとんど行かない性分ですが(笑)、東日本が舞台となるひさびさのの大河ドラマということもあって、先日、渋沢栄一翁の郷里である深谷市血洗島に行き、当地の鎮守社である諏訪神社に詣でて御朱印をいただいてきました。
埼玉県深谷市血洗島117
埼玉県神社庁資料
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社
授与所:拝殿前
朱印揮毫:諏訪神社 印刷
大河ドラマがらみだけあって、すでにWeb上でもかなりのコンテンツがみつかりますが、その多くは「大里郡神社誌」をベースにしているようなので原文からの引用をまじえてご紹介します。
『大里郡神社誌』(埼玉県神職会大里郡支会 編/昭和五年八月二十五日刊)
→ 国会図書館DC
----------- 以下(抜粋)引用 -----------
諏訪神社
舊(旧)榛澤郡血洗島村中南
・伝説によれば本社は舊(旧)諏訪大明神と称へ往古年代不詳、信州諏訪の里より遷し奉りしものなりと云ふ
・景行天皇の御宇日本武尊御東征凱旋の時此地を御通過あらせられ 祠前記念の植樹なりと伝ふる欅樹周囲四丈に余る老幹頗る古色を呈するものありけるが
・朱雀天皇の御代天慶の乱に六孫王経基官軍を率いて竹の幌(大字下手計附近の地)にありしが 之より先当諏訪神社に戦勝の祈願をなし大に戦勝を得たりと云ふ
・源平交戦の頃岡部六彌太忠澄 亦屢々茲に祈願して戦功を奏せしと云ふ
・慶長十九年岡部領となり領主安部攝津守在邑の時は 代々武の神と崇め叉戌亥の方角に当るを以て城郭の守護神として崇敬せられ 年々正月には領主自ら参拝して武運長久を祈願するを例とせりと云ふ
・明治三十七八(ママ)年戦役戦捷記念として本社の拡張を企図し当字出身たる渋澤子爵を始として氏子(中略)社殿の修築(同)を完成し
・舊(旧)村鎮守と奉称明治八年三月村社に列す 明治四十年十月三日神饌幣帛料供進神社に指定せらる
・元神社氏子区域血洗島一円戸数五十戸現在も同じ
・当社の氏子に生れ現在世界の偉人として仰がるゝ渋澤子爵の崇敬篤く 参拝は言う迄もなく多額の金員を寄附せられ 叉巨費を投じて現今の拝殿を造営し且つ幟及額等は自ら揮毫せられて寄進せらる
----------- (抜粋)引用おわり -----------
岡部六彌太忠澄は、武蔵七党のうち猪俣党の庶流岡部氏の当主で、保元の乱で源義朝に仕え、平治の乱では源義平の下で軍功をあげた十七騎の雄将として知られ、のちに源頼朝・源義経に仕えて一ノ谷の戦いで平忠度を討ち取った(『平家物語』)とされる武将です。
安部家は江戸期に一貫して岡部藩藩主を務めた家柄で、多くの当主は攝津守を称しました。
信濃の名族滋野氏・海野氏の流れとされ、駿河の安部谷に拠り戦国期当初は今川氏、のちに徳川の麾下に入り家康公の関東入国の際、岡部で五千石の旗本。
追って加増をうけ約二万石の大名家となりました。
所領は本領の武蔵国榛沢郡のほか、上野国新田郡、三河国八名郡、摂津国豊島郡、丹波国天田郡などに分散し、本領岡部の領地よりも他領の石高が高かったとされ、歴代当主の多くは大坂定番・加番などを務めていたため、関心は上方に向いていた節があります。
この点は、幕末の当主、信発が慶応四年(1868年)、新政府に対して本拠を三河半原藩に移すことを嘆願、許されて半原藩領主となったことからも伺えます。
このような、当主の岡部領への関心のうすさも、渋沢栄一の岡部藩への反発を招いた一因かもしれません。
渋沢家の出自についても少しく調べてみました。
(公財)渋沢栄一記念館の「デジタル版『渋沢栄一伝記資料』」には下記の記述があります。
〔竜門雑誌 第一六一号・第一八―一九頁 〔明治四三年一〇月〕 渋沢家の系図に就て〕
もともと「渋沢氏の先足利氏に出つると云ふ」という伝承があり、歴史家の織田完之氏がこれに疑問を呈して調査したところ
---------------------------
「足利一族には無之様被存候渋沢にて世に聞へたるもの甲州北巨摩郡渋沢村に出候」
〔系図〕
清和天皇 貞純親王 経基 満仲 頼任 頼義 新羅三郎義光 相模介義業 刑部三郎義清 逸見冠者清光 逸見上総介光長 武田大膳太夫信義 逸見太郎基義 逸見太郎惟義 逸見又太郎義重 逸見又太郎惟長 渋沢又二郎義継 巨摩郡渋沢村に居る 弟四人あり
「甲州より出て上杉に属し候者に相違無(略)市郎右衛門尉と申すは逸見郷住居の者にも有之候又天文前後の人に新十郎後に隼人正義頼又其子に小隼人高義と申人有(略)渋沢氏は足利一族には決して無之清和源氏新羅三郎の派即甲斐源氏と相見申候」
---------------------------
という調査結果がもたらされたようです。
※『青淵先生六十年史』(こちら)には、「渋澤氏の先足利氏に出ツルト云フ天正の頃渋澤隼人ト云フモノアリ武蔵国榛澤郡血洗島住ス蓋(?)渋澤氏ノ始祖タリ」とありますが、他の資料には渋沢家が清和(甲斐)源氏逸見氏流であることを伝えるものが複数みられます。
甲斐源氏説の渋沢家の動向については確実な史料は見当たらないようで、名字の地である甲斐国渋沢(現・山梨県北杜市)から一旦佐久に拠り、のちに血洗島に入植したという説、武田氏滅亡の折に甲斐から直接血洗島に入ったという説、さらには一時上杉家に属したという説もあり錯綜気味です。
こちらのWeb記事には、「逸見氏の一族又三郎義継は、旧渋沢村に移住し、以後、渋沢姓を名乗ったそうです。武田家滅亡後、織田信長が侵攻してきたため、渋沢一族は北杜市から佐久市、富岡市を経て深谷市血洗島へ逃れ、武士を捨て農業に従事したとのことでした。」という貴重な記載があります。
渋沢栄一翁とは経営理念の違いから対比されることの多い三菱財閥の創業者、岩崎弥太郎氏は甲斐源氏武田氏流といわれ、「鉄道王」といわれた根津嘉一郎氏も甲州出身、「地下鉄の父」と呼ばれる早川徳次氏のほか、若尾逸平氏、雨宮敬次郎氏など「甲州財閥」といわれる甲州出身の面々が数えられ、日本の資本主義の発展に甲州ゆかりの人々が名を連ねているのは興味ぶかいことです。
-------------------------


【写真 上(左)】 血洗島交差点
【写真 下(右)】 深谷ねぎ
血洗島は深谷市の北部、利根川にほど近いところにあります。
このインパクトある地名の由来については、こちらなどWeb上で多くの説がみられますので、そちらをご参照ください。
参拝時はからっ風の吹く強い冬型の日で、岡部から小山川を渡り、上手計・血洗島エリアに入ると北西風はさらに強さを増しました。
赤城山からここまで遮るものがなく、利根川に沿って「赤城おろし」がまともに吹き込むのでこのような強風になるのかもしれません。
深谷といえば「深谷ねぎ」が有名です。これは根深ねぎ(白ねぎ)系統で、寒さが増すほど味が乗るといわれます。
乾いた寒風にさらされると、ねぎは凍結から身を守るためアミノ酸を糖分に変え甘味が増すとされます。
「深谷ねぎ」のなかでも最上品の産地は旧豊里村の中瀬とも新戒ともいわれますが、どちらも血洗島のすぐとなりで、このあたり特有の冬場の強風が上質なねぎを生み出していることがうかがわれます。
また、白ねぎは「粘質が高くて硬く、かつ水はけが良い沃土」という相反するような土壌で味が高まるといわれ、このあたりの土質はこれに該当するともいわれます。
なお、このあたりの村の変遷は以下のようになっています。
明治22年(1889年)4月1日に上手計村、下手計村、大塚村、血洗島村、横瀬村、町田村、南阿賀野村、北阿賀野村の八箇村が合併し榛沢郡手計村となり翌年八基(やつもと)村と改称する。
昭和29年(1954年)11月3日に八基村と新会村が合併し豊里村を新設、さらに翌年豊里村が中瀬村と合併し豊里村となる。


【写真 上(左)】 中の家
【写真 下(右)】 中の家内部

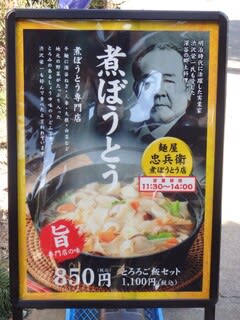
【写真 上(左)】 中の家横の稲荷社
【写真 下(右)】 深谷名物「煮ぼうとう」のお店もあります
はなしが逸れました。
諏訪神社は、渋沢栄一の生家「中の家(なかんち)」からほど近い場所に鎮座します。
社頭よこにPはありますが、「中の家」のPに駐車して歩いて参拝する人が多いようです。


【写真 上(左)】 社頭と社号標
【写真 下(右)】 深谷ねぎと諏訪神社


【写真 上(左)】 血洗島ふれあい会館
【写真 下(右)】 澁澤親子遺徳顕彰碑
社頭の社号標は渋沢栄一翁の揮毫とされているようです。
参道右手には「血洗島ふれあい会館」という、なかなかインパクトある名前の建物。
その先に「澁澤親子遺徳顕彰碑」。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鳥居


【写真 上(左)】 鳥居扁額
【写真 下(右)】 境内由緒書
鳥居は瓦屋根を配した木造の両部鳥居で、見上げ破風屋根の下に栄一翁揮毫の社号扁額。
参道途中に「宮城遙拝所」があります。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 渋沢青淵喜寿碑
参道左手に手水舎。
左手おくには栄一翁の喜寿を記念して建立された「渋沢青淵喜寿碑」があります。
拝殿前には栄一翁手植えの月桂樹と、翁の長女穂積歌子が父のために植えた橘が植わっています。
拝殿下に石灯籠一対。階段を登って狛犬一対。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 拝殿向拝
拝殿は、向拝はありますが構成は比較的シンプルで扁額もありません。
拝殿は、大正5年(1916年)栄一翁が喜寿を記念して造営寄進したものです。


【写真 上(左)】 本殿と天満宮(右)
【写真 下(右)】 本殿
拝殿と本殿は繋がっておらず、入母屋造瓦葺妻入りとみられる本殿は立派な向拝を備えています。
この本殿は明治49年(1907年)、栄一翁と血洗島村人の費用折半で造立されたもの。


【写真 上(左)】 本殿向拝-1
【写真 下(右)】 本殿向拝-2
入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁端部の木鼻は正面獅子、側面貘でともに立体感あふれる仕上がり。
向拝柱上部に端正な斗栱、水引虹梁に鳥を彫り込んだ彫刻、中備えの龍の彫刻はこれも見応えがあります。


【写真 上(左)】 本殿の向拝見上げ
【写真 下(右)】 本殿の木鼻彫刻
海老虹梁と立体感ある手挟。垂木は三軒(みのき)では?。
向拝正面の桟唐戸(閉扉)上段にお諏訪様の梶の葉紋。見上げの社号扁額は栄一翁の揮毫です。
脇障子の彫刻もなかなか見事なものです。


【写真 上(左)】 本殿扁額
【写真 下(右)】 向拝の軒天
この日は参拝客がぼちぼちいましたが、ほとんどの人は本殿まで回り込まず、拝殿で参拝して帰って行きます。
本殿は見応えがあるので、こちらの拝観もおすすめします。
境内社は本殿右脇に天満宮(一間社流造桟瓦葺)。左手に鎮座される石宮のうちどれかは八坂社のようです。
こちらは秋10月に催される獅子舞でも知られており「血洗島獅子舞」の名称で深谷市の無形民俗文化財に指定されています。
この獅子舞は栄一翁もふかく愛したと伝わります。
〔澁澤青淵翁喜壽碑 公爵 徳川慶久題額/抜粋〕
吾村は武蔵平野の小村ながら、翁の如き大人物を出したるを誇とすべし。
翁や青年の頃村を去りて国家の為に奔走し、今は世界の偉人として内外に瞻仰せらるれども、
我等は尚翁を吾村の父老として親しみ慕ひ、翁も亦喜びて何くれと村の事に尽すを楽となせり。
村社諏訪神社は、翁が幼少の時境内にて遊戯し、祭日には村の若者と共に、さゝらなど舞ひたる事あれば、
村に帰れば先づ社に詣づるを例とし、社殿の修理にも巨資を捐てゝ父老を奨励したり。
---------------------------------


【写真 上(左)】 本殿の脇障子
【写真 下(右)】 御朱印付のパンフ(拝殿前)
御朱印は拝殿前のプラケースの中に入っているパンフの一部がそれです。
一人1枚の限定配布(無料)ですが、私が参拝した日曜昼前にはすでに残数5枚でした。(補充のタイミングは不明)

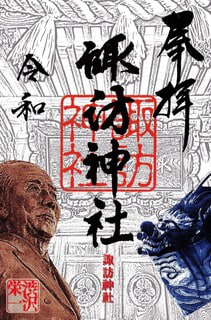
新一万円札の見本も刷られたパンフで、この一部の印刷御朱印を切り取って御朱印帳に貼り付けるというものです。
こういう方式ははじめてですが、印刷でも御朱印は御朱印なので、300円程度のお納めを受けてもいいような気はします。
たとえば拝殿前に整理券を置き、その整理券持参者に「中の家」の係員が御朱印付パンフを300円で交付するという方法も考えられるのでは?


【写真 上(左)】 下手計 鹿島神社
【写真 下(右)】 鹿島神社の拝殿扁額(栄一翁揮毫)
なお、下手計の鎮守社で、栄一翁の師、尾高藍香の頌徳碑や栄一翁揮毫の扁額がある鹿島神社は、以前御朱印を授与されていたというWeb情報がありますが、現在は授与されていないようです。
深谷市策定の「渋沢栄一翁と論語の里」整備活用計画という資料があります。
よくまとまっているのですが、やはりハードウェア偏重な感じがして、市内の回遊性を高めるソフト的な(具体的な)インパクトがあまり感じられません。(自治体の地域振興計画にありがちなパターン)
深谷は札所も多く、“秋の七草”巡りができる深谷七福神も開創されているので、これらと組み合わせた市内寺社のスタンプ(御朱印)ラリーなど設定すればかなりの参加者が見込めるかも。
(ちなみに深谷七福神は、ほとんどの札所で通年御朱印対応されています。)
今回、「中の家」周辺では「深谷七福神」の案内はまったくみあたらず、観光客の多くは認知しないまま帰っていくと思います。
周辺の熊谷、本庄、伊勢崎、太田などは首都圏でも有数の御朱印エリアで、とくに伊勢崎、熊谷には絵入り御朱印で有名な寺院が複数あるので、御朱印つながりで客足を引きやすいところです。
新型コロナの感染状況次第でしょうが、今後“秋の七草”に向けて御朱印絡みのあらたな集客策が打ち出されるかもしれません。
※別編で関越自動車道「花園IC」から血洗島に向かう途中で拝受できる御朱印をご紹介します。
↓
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)
【 BGM 】
Goodbye Yesterday - 今井美樹 from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO
参拝の際は、ご留意をお願いします。
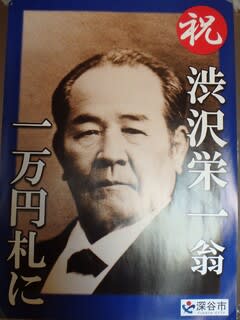

NHK大河ドラマ「青天を衝け」。近代ものにしては視聴率は好調のようです。
話題のスポットにはほとんど行かない性分ですが(笑)、東日本が舞台となるひさびさのの大河ドラマということもあって、先日、渋沢栄一翁の郷里である深谷市血洗島に行き、当地の鎮守社である諏訪神社に詣でて御朱印をいただいてきました。
埼玉県深谷市血洗島117
埼玉県神社庁資料
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社
授与所:拝殿前
朱印揮毫:諏訪神社 印刷
大河ドラマがらみだけあって、すでにWeb上でもかなりのコンテンツがみつかりますが、その多くは「大里郡神社誌」をベースにしているようなので原文からの引用をまじえてご紹介します。
『大里郡神社誌』(埼玉県神職会大里郡支会 編/昭和五年八月二十五日刊)
→ 国会図書館DC
----------- 以下(抜粋)引用 -----------
諏訪神社
舊(旧)榛澤郡血洗島村中南
・伝説によれば本社は舊(旧)諏訪大明神と称へ往古年代不詳、信州諏訪の里より遷し奉りしものなりと云ふ
・景行天皇の御宇日本武尊御東征凱旋の時此地を御通過あらせられ 祠前記念の植樹なりと伝ふる欅樹周囲四丈に余る老幹頗る古色を呈するものありけるが
・朱雀天皇の御代天慶の乱に六孫王経基官軍を率いて竹の幌(大字下手計附近の地)にありしが 之より先当諏訪神社に戦勝の祈願をなし大に戦勝を得たりと云ふ
・源平交戦の頃岡部六彌太忠澄 亦屢々茲に祈願して戦功を奏せしと云ふ
・慶長十九年岡部領となり領主安部攝津守在邑の時は 代々武の神と崇め叉戌亥の方角に当るを以て城郭の守護神として崇敬せられ 年々正月には領主自ら参拝して武運長久を祈願するを例とせりと云ふ
・明治三十七八(ママ)年戦役戦捷記念として本社の拡張を企図し当字出身たる渋澤子爵を始として氏子(中略)社殿の修築(同)を完成し
・舊(旧)村鎮守と奉称明治八年三月村社に列す 明治四十年十月三日神饌幣帛料供進神社に指定せらる
・元神社氏子区域血洗島一円戸数五十戸現在も同じ
・当社の氏子に生れ現在世界の偉人として仰がるゝ渋澤子爵の崇敬篤く 参拝は言う迄もなく多額の金員を寄附せられ 叉巨費を投じて現今の拝殿を造営し且つ幟及額等は自ら揮毫せられて寄進せらる
----------- (抜粋)引用おわり -----------
岡部六彌太忠澄は、武蔵七党のうち猪俣党の庶流岡部氏の当主で、保元の乱で源義朝に仕え、平治の乱では源義平の下で軍功をあげた十七騎の雄将として知られ、のちに源頼朝・源義経に仕えて一ノ谷の戦いで平忠度を討ち取った(『平家物語』)とされる武将です。
安部家は江戸期に一貫して岡部藩藩主を務めた家柄で、多くの当主は攝津守を称しました。
信濃の名族滋野氏・海野氏の流れとされ、駿河の安部谷に拠り戦国期当初は今川氏、のちに徳川の麾下に入り家康公の関東入国の際、岡部で五千石の旗本。
追って加増をうけ約二万石の大名家となりました。
所領は本領の武蔵国榛沢郡のほか、上野国新田郡、三河国八名郡、摂津国豊島郡、丹波国天田郡などに分散し、本領岡部の領地よりも他領の石高が高かったとされ、歴代当主の多くは大坂定番・加番などを務めていたため、関心は上方に向いていた節があります。
この点は、幕末の当主、信発が慶応四年(1868年)、新政府に対して本拠を三河半原藩に移すことを嘆願、許されて半原藩領主となったことからも伺えます。
このような、当主の岡部領への関心のうすさも、渋沢栄一の岡部藩への反発を招いた一因かもしれません。
渋沢家の出自についても少しく調べてみました。
(公財)渋沢栄一記念館の「デジタル版『渋沢栄一伝記資料』」には下記の記述があります。
〔竜門雑誌 第一六一号・第一八―一九頁 〔明治四三年一〇月〕 渋沢家の系図に就て〕
もともと「渋沢氏の先足利氏に出つると云ふ」という伝承があり、歴史家の織田完之氏がこれに疑問を呈して調査したところ
---------------------------
「足利一族には無之様被存候渋沢にて世に聞へたるもの甲州北巨摩郡渋沢村に出候」
〔系図〕
清和天皇 貞純親王 経基 満仲 頼任 頼義 新羅三郎義光 相模介義業 刑部三郎義清 逸見冠者清光 逸見上総介光長 武田大膳太夫信義 逸見太郎基義 逸見太郎惟義 逸見又太郎義重 逸見又太郎惟長 渋沢又二郎義継 巨摩郡渋沢村に居る 弟四人あり
「甲州より出て上杉に属し候者に相違無(略)市郎右衛門尉と申すは逸見郷住居の者にも有之候又天文前後の人に新十郎後に隼人正義頼又其子に小隼人高義と申人有(略)渋沢氏は足利一族には決して無之清和源氏新羅三郎の派即甲斐源氏と相見申候」
---------------------------
という調査結果がもたらされたようです。
※『青淵先生六十年史』(こちら)には、「渋澤氏の先足利氏に出ツルト云フ天正の頃渋澤隼人ト云フモノアリ武蔵国榛澤郡血洗島住ス蓋(?)渋澤氏ノ始祖タリ」とありますが、他の資料には渋沢家が清和(甲斐)源氏逸見氏流であることを伝えるものが複数みられます。
甲斐源氏説の渋沢家の動向については確実な史料は見当たらないようで、名字の地である甲斐国渋沢(現・山梨県北杜市)から一旦佐久に拠り、のちに血洗島に入植したという説、武田氏滅亡の折に甲斐から直接血洗島に入ったという説、さらには一時上杉家に属したという説もあり錯綜気味です。
こちらのWeb記事には、「逸見氏の一族又三郎義継は、旧渋沢村に移住し、以後、渋沢姓を名乗ったそうです。武田家滅亡後、織田信長が侵攻してきたため、渋沢一族は北杜市から佐久市、富岡市を経て深谷市血洗島へ逃れ、武士を捨て農業に従事したとのことでした。」という貴重な記載があります。
渋沢栄一翁とは経営理念の違いから対比されることの多い三菱財閥の創業者、岩崎弥太郎氏は甲斐源氏武田氏流といわれ、「鉄道王」といわれた根津嘉一郎氏も甲州出身、「地下鉄の父」と呼ばれる早川徳次氏のほか、若尾逸平氏、雨宮敬次郎氏など「甲州財閥」といわれる甲州出身の面々が数えられ、日本の資本主義の発展に甲州ゆかりの人々が名を連ねているのは興味ぶかいことです。
-------------------------


【写真 上(左)】 血洗島交差点
【写真 下(右)】 深谷ねぎ
血洗島は深谷市の北部、利根川にほど近いところにあります。
このインパクトある地名の由来については、こちらなどWeb上で多くの説がみられますので、そちらをご参照ください。
参拝時はからっ風の吹く強い冬型の日で、岡部から小山川を渡り、上手計・血洗島エリアに入ると北西風はさらに強さを増しました。
赤城山からここまで遮るものがなく、利根川に沿って「赤城おろし」がまともに吹き込むのでこのような強風になるのかもしれません。
深谷といえば「深谷ねぎ」が有名です。これは根深ねぎ(白ねぎ)系統で、寒さが増すほど味が乗るといわれます。
乾いた寒風にさらされると、ねぎは凍結から身を守るためアミノ酸を糖分に変え甘味が増すとされます。
「深谷ねぎ」のなかでも最上品の産地は旧豊里村の中瀬とも新戒ともいわれますが、どちらも血洗島のすぐとなりで、このあたり特有の冬場の強風が上質なねぎを生み出していることがうかがわれます。
また、白ねぎは「粘質が高くて硬く、かつ水はけが良い沃土」という相反するような土壌で味が高まるといわれ、このあたりの土質はこれに該当するともいわれます。
なお、このあたりの村の変遷は以下のようになっています。
明治22年(1889年)4月1日に上手計村、下手計村、大塚村、血洗島村、横瀬村、町田村、南阿賀野村、北阿賀野村の八箇村が合併し榛沢郡手計村となり翌年八基(やつもと)村と改称する。
昭和29年(1954年)11月3日に八基村と新会村が合併し豊里村を新設、さらに翌年豊里村が中瀬村と合併し豊里村となる。


【写真 上(左)】 中の家
【写真 下(右)】 中の家内部

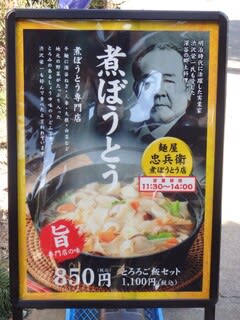
【写真 上(左)】 中の家横の稲荷社
【写真 下(右)】 深谷名物「煮ぼうとう」のお店もあります
はなしが逸れました。
諏訪神社は、渋沢栄一の生家「中の家(なかんち)」からほど近い場所に鎮座します。
社頭よこにPはありますが、「中の家」のPに駐車して歩いて参拝する人が多いようです。


【写真 上(左)】 社頭と社号標
【写真 下(右)】 深谷ねぎと諏訪神社


【写真 上(左)】 血洗島ふれあい会館
【写真 下(右)】 澁澤親子遺徳顕彰碑
社頭の社号標は渋沢栄一翁の揮毫とされているようです。
参道右手には「血洗島ふれあい会館」という、なかなかインパクトある名前の建物。
その先に「澁澤親子遺徳顕彰碑」。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鳥居


【写真 上(左)】 鳥居扁額
【写真 下(右)】 境内由緒書
鳥居は瓦屋根を配した木造の両部鳥居で、見上げ破風屋根の下に栄一翁揮毫の社号扁額。
参道途中に「宮城遙拝所」があります。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 渋沢青淵喜寿碑
参道左手に手水舎。
左手おくには栄一翁の喜寿を記念して建立された「渋沢青淵喜寿碑」があります。
拝殿前には栄一翁手植えの月桂樹と、翁の長女穂積歌子が父のために植えた橘が植わっています。
拝殿下に石灯籠一対。階段を登って狛犬一対。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 拝殿向拝
拝殿は、向拝はありますが構成は比較的シンプルで扁額もありません。
拝殿は、大正5年(1916年)栄一翁が喜寿を記念して造営寄進したものです。


【写真 上(左)】 本殿と天満宮(右)
【写真 下(右)】 本殿
拝殿と本殿は繋がっておらず、入母屋造瓦葺妻入りとみられる本殿は立派な向拝を備えています。
この本殿は明治49年(1907年)、栄一翁と血洗島村人の費用折半で造立されたもの。


【写真 上(左)】 本殿向拝-1
【写真 下(右)】 本殿向拝-2
入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁端部の木鼻は正面獅子、側面貘でともに立体感あふれる仕上がり。
向拝柱上部に端正な斗栱、水引虹梁に鳥を彫り込んだ彫刻、中備えの龍の彫刻はこれも見応えがあります。


【写真 上(左)】 本殿の向拝見上げ
【写真 下(右)】 本殿の木鼻彫刻
海老虹梁と立体感ある手挟。垂木は三軒(みのき)では?。
向拝正面の桟唐戸(閉扉)上段にお諏訪様の梶の葉紋。見上げの社号扁額は栄一翁の揮毫です。
脇障子の彫刻もなかなか見事なものです。


【写真 上(左)】 本殿扁額
【写真 下(右)】 向拝の軒天
この日は参拝客がぼちぼちいましたが、ほとんどの人は本殿まで回り込まず、拝殿で参拝して帰って行きます。
本殿は見応えがあるので、こちらの拝観もおすすめします。
境内社は本殿右脇に天満宮(一間社流造桟瓦葺)。左手に鎮座される石宮のうちどれかは八坂社のようです。
こちらは秋10月に催される獅子舞でも知られており「血洗島獅子舞」の名称で深谷市の無形民俗文化財に指定されています。
この獅子舞は栄一翁もふかく愛したと伝わります。
〔澁澤青淵翁喜壽碑 公爵 徳川慶久題額/抜粋〕
吾村は武蔵平野の小村ながら、翁の如き大人物を出したるを誇とすべし。
翁や青年の頃村を去りて国家の為に奔走し、今は世界の偉人として内外に瞻仰せらるれども、
我等は尚翁を吾村の父老として親しみ慕ひ、翁も亦喜びて何くれと村の事に尽すを楽となせり。
村社諏訪神社は、翁が幼少の時境内にて遊戯し、祭日には村の若者と共に、さゝらなど舞ひたる事あれば、
村に帰れば先づ社に詣づるを例とし、社殿の修理にも巨資を捐てゝ父老を奨励したり。
---------------------------------


【写真 上(左)】 本殿の脇障子
【写真 下(右)】 御朱印付のパンフ(拝殿前)
御朱印は拝殿前のプラケースの中に入っているパンフの一部がそれです。
一人1枚の限定配布(無料)ですが、私が参拝した日曜昼前にはすでに残数5枚でした。(補充のタイミングは不明)

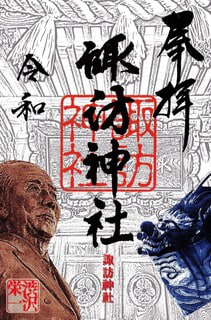
新一万円札の見本も刷られたパンフで、この一部の印刷御朱印を切り取って御朱印帳に貼り付けるというものです。
こういう方式ははじめてですが、印刷でも御朱印は御朱印なので、300円程度のお納めを受けてもいいような気はします。
たとえば拝殿前に整理券を置き、その整理券持参者に「中の家」の係員が御朱印付パンフを300円で交付するという方法も考えられるのでは?


【写真 上(左)】 下手計 鹿島神社
【写真 下(右)】 鹿島神社の拝殿扁額(栄一翁揮毫)
なお、下手計の鎮守社で、栄一翁の師、尾高藍香の頌徳碑や栄一翁揮毫の扁額がある鹿島神社は、以前御朱印を授与されていたというWeb情報がありますが、現在は授与されていないようです。
深谷市策定の「渋沢栄一翁と論語の里」整備活用計画という資料があります。
よくまとまっているのですが、やはりハードウェア偏重な感じがして、市内の回遊性を高めるソフト的な(具体的な)インパクトがあまり感じられません。(自治体の地域振興計画にありがちなパターン)
深谷は札所も多く、“秋の七草”巡りができる深谷七福神も開創されているので、これらと組み合わせた市内寺社のスタンプ(御朱印)ラリーなど設定すればかなりの参加者が見込めるかも。
(ちなみに深谷七福神は、ほとんどの札所で通年御朱印対応されています。)
今回、「中の家」周辺では「深谷七福神」の案内はまったくみあたらず、観光客の多くは認知しないまま帰っていくと思います。
周辺の熊谷、本庄、伊勢崎、太田などは首都圏でも有数の御朱印エリアで、とくに伊勢崎、熊谷には絵入り御朱印で有名な寺院が複数あるので、御朱印つながりで客足を引きやすいところです。
新型コロナの感染状況次第でしょうが、今後“秋の七草”に向けて御朱印絡みのあらたな集客策が打ち出されるかもしれません。
※別編で関越自動車道「花園IC」から血洗島に向かう途中で拝受できる御朱印をご紹介します。
↓
■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)
【 BGM 】
Goodbye Yesterday - 今井美樹 from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




