関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
「3密」をさけて「三密」を
最初に「3密(さんみつ)」の言葉をきいたとき、密教の「三密」を連想してしまいました。
「三密」とは仏教(密教)の重要な教えで、「行動・言葉・こころ」の3つを整えることとされます。
くわしくは→ こちらを。
密教修行における「三密」では、「身密」は印相を組まなくてはならないし、「口密」は御真言を唱えなければなりません。
「三昧耶戒」(密教独自の戒律)のこともあるので、素人が修するのはむずかしいと思いますが、
基本的な心構えは、こちらに書かれているとおりで、
日々実践できるかと思いますし、たしかにコロナ対策に通ずるところもあるかと思います。
「病気に苦しむ人々を助ける仏様」は薬師如来(薬師瑠璃光如来)で、いままさにそのご加護をいただきたい尊格です。
外出自粛で参拝はむずかしいと思いますが、
上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師様の御朱印をご紹介します。


【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)
【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)


【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)
【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)
せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。
薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。(現在閉院中、御朱印不授与の模様です。)


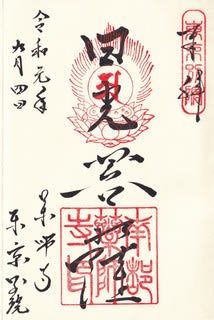
「三密」とは仏教(密教)の重要な教えで、「行動・言葉・こころ」の3つを整えることとされます。
くわしくは→ こちらを。
密教修行における「三密」では、「身密」は印相を組まなくてはならないし、「口密」は御真言を唱えなければなりません。
「三昧耶戒」(密教独自の戒律)のこともあるので、素人が修するのはむずかしいと思いますが、
基本的な心構えは、こちらに書かれているとおりで、
日々実践できるかと思いますし、たしかにコロナ対策に通ずるところもあるかと思います。
「病気に苦しむ人々を助ける仏様」は薬師如来(薬師瑠璃光如来)で、いままさにそのご加護をいただきたい尊格です。
外出自粛で参拝はむずかしいと思いますが、
上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師様の御朱印をご紹介します。


【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)
【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)


【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)
【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)
せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。
薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。(現在閉院中、御朱印不授与の模様です。)


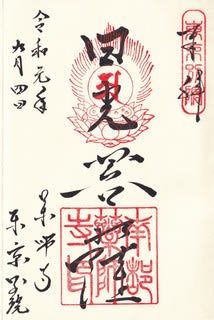
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
つづきです。
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社が多くなっています。参拝は、新型コロナ収束後にお願いします。
■〔 信玄公と甲府五山 〕
信玄公は神仏への信仰ふかく、宗派を越えて寺社を厚く保護されました。
「信玄」は、永禄二年(1559年)(天文二一年(1552年)説もあり)に39歳で出家された際の諱で、院号は法性院、道号は機山、別号は徳栄軒と伝わります。
『甲陽軍鑑』によると「玄」は中国の臨済義玄、日本では関山恵玄にゆかりで、得度式を務め「信玄」を授けたのは臨済宗長禅寺(甲府市愛宕町)の住持、岐秀元伯(ぎしゅう げんぱく)とされています。
岐秀元伯は京都妙心寺の学僧で、信玄の母大井夫人の招聘により鮎沢の(古)長禅寺、次いで愛宕の長善寺に住山されました。
岐秀元伯は信玄公の学問の師であったと伝わります。
伝灯は大応国師~大灯国師~妙心寺開山の関山慧玄と続く「応灯関」「関山禅」を嗣ぎ、とくに臨済宗妙心寺派への帰依が深かったとされます。
信玄公の葬儀で大導師を勤められた恵林寺の快川紹喜(かいせん じょうき)も臨済宗妙心寺派の高僧で、信玄公に「機山」の号を授けたとされます。
信玄公は京や鎌倉の五山制度にならい、甲府にも臨済宗寺院で五山を定めました。
長禅寺、東光寺、能成寺、円光院、法泉寺が甲府(府中)五山です。
円光寺の公式Web資料には、「信玄公は元より仏法信仰を重んじ臨済宗に帰依し、京都妙心寺の開山である開山国師の遺風を崇敬しておりました。その因縁により、京五山、鎌倉五山にならい、甲州の古刹の寺を城下に移しました。そして何れも妙心寺派に改め、それぞれに土地を寄付し、これらの寺を御城附御祈願所五山と号しました。」とあります。
また、法泉寺前掲示の甲府五山の説明書には、「戦国武将武田信玄公は臨済宗に深く帰依し、京都五山・鎌倉五山の制度にならって『甲府(府中)五山』を定めました。その五寺は、宝泉寺、長禅寺、東光寺、円光院、能成寺です。信玄は広く仏教を信仰し、宗旨のいかんを問わず、寺院・僧侶を崇敬保護したことが知られています。とりわけ臨済宗に対する帰依は深く、平素より多くの禅僧と親交を深めていました。諸国から禅宗の高僧を招いて師とし、その教えを民政や軍法に活かしたのです。代表的な高僧は、五山派の惟高妙安、策彦周良、妙心寺(関山)派の岐秀元伯、快川紹喜らです。特に岐秀は信玄幼少時からの参禅の師であり、学問・修養を通じて信玄の人格形成に深い影響を及ぼしたといわれ、信玄剃髪の際に大導師もつとめました。」とあります。
五山の所在地は甲府北部の住宅地から山手に点在し、「小松」といわれる一帯に宝泉寺、長善寺、円光院、「板垣」といわれる一帯に能成寺、東光寺があり、「北山野道」という遊歩コースが設けられています。
■ 瑞雲山 長禅寺








甲府市愛宕町208
臨済宗単立 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第58番、甲斐国三十三番観音札所第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第64番、府内観音札所第9番
※御朱印は不授与です。
信玄公の母、大井夫人(瑞雲院殿)の菩提寺で、岐秀元伯が開いたとされる臨済宗の名刹。
創建は天文二一年(1552年)と伝わり(『甲斐国志』)、甲府五山の主座(筆頭)とされます。
長禅寺の前身は、大井夫人の出である西郡の国人、大井氏領する巨摩郡相沢(現・南アルプス市鮎沢)の長善寺(現・古長禅寺)で、大井氏の菩提寺でした。(古長禅寺は後述します。)
大井夫人は西郡の国衆(国人領主)で、武田氏一門の大井信達公の息女。
駿河に近い西郡の大井信達公は今川氏と結んで信虎公と抗争を続けていましたが、永正十四年(1517年)に信虎公と和睦。
このとき大井夫人が信虎公の正室として嫁いだため、政略結婚の意味合いが強いものとみなされています。
信虎公との間に嫡男信玄公、信繁公、信廉公(逍遙軒信綱)および長女をもうけました。
信繁公、信廉公ともに能く信玄公を補佐されたと伝わり、二十四将に数えられています。
大井夫人は賢母で、悟渓宗頓(大徳寺五二世住持、妙心寺四派の一、東海派の開祖)の法統を嗣ぐ、尾張国瑞泉寺の岐秀元伯を長禅寺に招き、若き日の信玄公に「四書五経」「孫子」「呉子」などを学ばせたといわれます。
天文十年(1541年)の信玄公による信虎公駿河追放ののちも甲斐に留まられ、躑躅ヶ崎館北曲輪に居住されました。
天文二一年(1552年)に逝去。法名は瑞雲院殿月珠泉大姉。
葬儀の大導師を務められたのは岐秀元伯と伝わります(『高白斎記』)。
大井夫人逝去の後、西郡の鮎沢では墓所が遠いため、亡き母を開基に、導師の岐秀元伯を開山に請じて新たに長禅寺として開かれました。
本堂左手手前に大井夫人の霊廟があり、本堂左手の坂の上に墓所があります。
参拝時には落枝の危険で墓所参道は通行禁止となっていました。
非公開ですが、「絹本著色武田信虎夫人像」「紙本著色渡唐天神像」の文化財を所蔵しています。
「絹本著色武田信虎夫人像」は大井夫人(瑞雲院殿)の肖像画で、画人としても知られた信玄公の同母弟・信廉公(逍遥軒信綱・二十四将の一人)の筆によるもの。
信廉公21歳、天文二二年(1553年)の作とされます。
なお、名門大井氏は嫡流信業公の三弟と六弟が武藤姓を名乗り、関ヶ原の戦いの際、上田城で秀忠軍を釘付けにした真田昌幸は、永禄年間にこの大井氏流武藤家に養子に入っていたと伝わります。
「武藤三郎左衛門尉のときに実子の武藤与次が早世したため、真田昌幸を養子にとった」という説があり、武藤喜兵衛尉昌幸は二十四将のひとりに数えられることもあります。(→関連資料)
どことなく近寄りがたい威厳のある禅寺で、いくつかの霊場札所となっているものの、御朱印は一切授与されていないようです。
■ 法蓋山 東光寺(東光興国禅寺)








甲府市東光寺3-7-37
臨済宗妙心寺派 御本尊:薬師如来
札所:甲斐百八霊場第56番
朱印尊格:本尊 薬師如来 書置(印刷?)
札番:甲斐百八霊場第56番印判
・中央に札所本尊、薬師如来の種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に三寶印。中央に「本尊 薬師如来」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第五六番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
寺伝によると平安時代の保安二年(1121年)に源義光(新羅三郎)公が密教の祈願所として諸堂を整え、興国院と号したとされます。
その後鎌倉期に蘭渓道隆が禅宗寺院として再興、寺号を東光寺と改めました。
この寺に幽閉され終焉を遂げられた信玄公の長子義信公、諏訪から移られて自害された諏訪の領主諏訪頼重公の墓所であり、戦国の哀史を物語る史跡として訪れる人も多いようです。
〔武田義信公〕
義信公は、天文七年(1538年)信玄公の嫡男として生まれました。
母は信玄公の正室、公家の三条公頼公の息女の三条夫人です。
天文十九年(1550年)、若くして今川義元公の息女(従姉妹とも)を正室に迎えています。
初陣の知久氏攻めをはじめ、小諸城攻略、川中島での戦いなどでの華々しい武功が伝わります。
天文二二年(1553年)、将軍足利義藤(義輝)公より将軍家の通字である「義」の偏諱を受けて義信と名乗られ(『高白斎記』)、永禄元年(1558年)、信玄公が信濃守護に補任された際には「准三管領」としての待遇を受けており、武田家嫡男としての道を順調に歩まれていました。
永禄八年(1565年)10月、信玄公暗殺を企てた謀反にかかわったとされ甲府東光寺に幽閉。(『甲陽軍鑑』)
永禄十年(1567年)10月19日に東光寺で逝去されました。享年30歳。
同年11月には正室の今川氏は駿河へ帰国しています。
この事件は「義信事件」と通称され、信玄公をめぐる謎のひとつとされています。
経緯がこみ入っているので詳細は省きますが、『甲陽軍鑑』によると、義信公の傅役である飯富虎昌以下の側近が処刑され、八十騎の家臣団が追放処分になっているので、これを受けた武田家臣内紛説がみられます。
永禄三年(1560年)、桶狭間の戦いでの今川義元公の戦死、永禄四年(1561年)第4次川中島の戦いを経た北信地域の実質的な領有などを契機に信玄公は対外方針を転換し、永禄十一年(1568年)には今川氏の領国駿河への侵攻を始めています。
「義信事件」は駿河侵攻の3年前であり、今川氏に対する方針で親子、および家臣内で深刻な対立があり、これが事件の契機となったとする見解がみられます。
今川義元公の息女を正室としていた義信公が親今川派、「義信事件」後に駿河侵攻を進めた信玄公が反今川派という構図です。
また、永禄年間以降、信玄公と信長公とに同盟の動きがあり、信長公と敵対関係にあった今川氏との間に生じた軋轢を背景のひとつとみる説もあります。
信虎公の長女定恵院(信玄公の同母姉)は義元公の正室で、氏真公の母であり、娘の嶺松院は義信公の正室です。
永禄三年(1560年)5月、桶狭間の戦いで戦死した今川義元公の跡を継いだ氏真公は、家臣の掌握に苦しみ離反を招きました。当時今川家の食客となっていた信虎公は、今川家臣と謀って氏真公の追放を企図しましたが事前に露見し、駿府を追われ京に向かわれたとされます。
また、信虎公の子武田信友は今川家臣団に加わり、後に武田氏の駿河侵攻に呼応しています。
このあたりの今川家をめぐる複雑な事情も「義信事件」の背景にあるとみられます。
駿河に接する河内領の領主で武田御一門衆の穴山氏は、武田・今川の甲駿同盟を取次し、義信公と今川氏の婚姻も仲介しましたが、「義信事件」翌年の永禄九年(1566年)に当主穴山信君の弟、穴山彦八郎(信嘉、信邦)が身延山久遠寺塔頭において自害しており(『甲斐国志』)、これを対今川戦略対立説の論拠とする説もあります。
義信公の墓所は、本堂裏山の左手にひっそりとあります。
〔諏訪頼重公〕
諏訪頼重公は、諏訪氏第十九代当主で諏訪大社大祝。上原城城主であり、戦国大名として諏訪一円を治めました。
諏訪氏は神代以来の諏訪大社上社の大祝の家柄で、「神氏(みわし/じんし)」とも尊称された名族です。
信虎公の時代、諏訪氏は武田氏と抗争し、享禄元年(1528年)信虎公は諏訪に侵入して頼満公と対戦、享禄四年(1531年)には逆に頼満公が韮崎あたりまで兵を入れています。
諏訪氏との抗争を不利とみた信虎公は、天文四年(1535年)に頼満公と和睦(盟約)し、天文九年(1540年)には三女・禰々を頼満公の跡を継いだ頼重公に嫁がせています。
以降、小県郡侵攻などで武田家と連携していました。
甲斐から信濃へ向かうには、諏訪口(甲州街道)と佐久口(佐久甲州街道)の2つのルートがあります。
諏訪ルートは諏訪氏との盟約があってとれないので、信虎公の時代はもっぱら佐久ルートをもって信濃侵攻がなされました。
しかし、晴信公が当主となると方針を転じ、諏訪への侵攻を開始しました。
『甲陽軍艦』では、この時期の信玄公の戦として「瀬沢合戦」を記しています。
これは天文十一年(1542年)、信濃四将(中信の小笠原長時、北信の村上義清、木曽の木曽義康、諏訪の諏訪頼重)と信玄公の大合戦で、信濃勢一万六千を武田軍八千が瀬沢(現・長野県富士見町)で迎え撃ち、信濃勢は千六百二十一人の戦死者を出して敗走したというもの。
瀬沢周辺にはこれを示す史跡も残りますが、この戦いは『甲陽軍艦』のほかに確実な史料が認められないため、合戦そのものの存在が疑問視されています。
神代より、諏訪大社上社の大祝は諏訪氏、諏訪下社の大祝は代々金刺氏が継いできました。
この時代、金刺氏は諏訪氏の配下にありましたが、両氏は伝統的に対立関係にあったとされています。
また、諏訪氏の一族、伊那・高遠城主の高遠信濃守頼継も諏訪氏と対立関係にありました。
諏訪総領家の祖・安芸守信嗣は高遠氏の祖・信濃守頼継の弟であり、高遠氏が本来の上社大祝の家柄である、という自負があったためとみられています。
信玄公はこのような諏訪一族内の軋轢に乗じ、謀略の手を伸ばして金刺氏、高遠頼継をみかたにつけて諏訪に侵入しました。ときを合わせて高遠頼継も杖突峠を越えて諏訪に攻め入りました。
南方から武田、西方からは高遠勢の攻撃を受け苦境に陥った頼重公は、上原城を退き北方の桑原城に移りました。
桑原城にて、信玄公から「城を明け渡せば武田勢は甲斐に引き上げる」旨の和睦案を受けた頼重公はこれを容れ、城を渡して甲斐・府中に送られました。
頼重公は東光寺に幽閉され、その後自刃されました。
ときに頼重公27歳。辞世の句が残されています。
- おのづから 枯れ果てにけり 草の葉の 主あらばこそ 又も結ばめ -
これにより諏訪惣領家は滅亡したとされていますが、上社大祝は叔父諏訪満隣の家系が継ぎ、その子孫は近世に中興されて諏訪高島藩三万石の大名となっています。
頼重公の墓所は、本堂裏山の左手にあります。
桑原城址そばには、頼重公の家臣らが公の遺髪を埋めたと伝わる頼重院があり、供養塔が残されています。

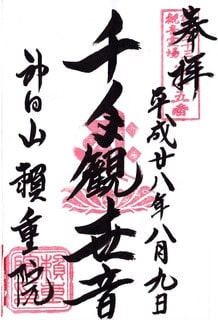
【写真 上(左)】 頼重院 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 頼重院 観音霊場の御朱印
信玄公はこののち頼重公の息女を側室として迎え、この側室は勝頼公を産んでいます。
よって頼重公は勝頼公の外祖父にあたります。
『甲陽軍艦』に「尋常かくれなき美人にてまします」と記されたこの美貌の側室(諏訪御料人)は、小説やドラマでは、湖衣姫(こいひめ)、由布姫(ゆぶひめ・ゆうひめ)として描かれています。
東光寺は甲府北部の住宅地の奥に、落ち着いたたたずまいをみせています。
室町時代の作とされる仏殿は、鎌倉禅宗様式の代表的な建築物として国の重要文化財に指定されています。
仏殿の御本尊は薬師如来。鎌倉時代作の檜材の坐像で、これを取り囲むように守護神である十二神将立像(檜材、伝鎌倉時代作)が安置されています。
本堂裏手には、蘭渓道隆(ないし当寺中興開山・大覚禅師)の作と伝わる北宋山水様式の池泉式庭園(東光寺庭園)が構えられ、鎌倉中期の特色を残す作例として知られています。
甲斐百八霊場第56番の札所であり、ご丁寧な対応にて御朱印をいただけました。
■ 定林山 能成寺(能成護国禅寺)





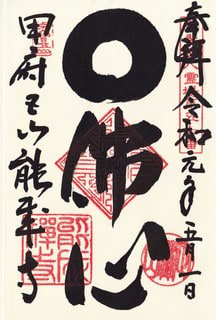
公式Web
甲府市東光寺町2153
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第57番
朱印尊格:釈迦如来(佛心) 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第57番印判
・中央に三寶印と「○」字と「佛心」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第五七番」の札所印。左下には「甲府五山」と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
南北朝時代の貞和年間(1345年~1349年)に天目山棲雲寺の業海本浄(ごっかい ほんじょう)の開山、甲斐国守護・武田信守公(能成寺殿)を開基として、小石和筋八代村(現在の笛吹市八代町)に創建された古刹です。
信玄公のとき西青沼(現在の甲府市宝)に移され、さらに文禄年間(1592年~1595年)、甲府城築城の折に現在地に移されました。
創建時の御本尊は三尊阿弥陀如来(安阿弥作)でしたが、現在は釈迦牟尼仏。
本堂上間の間に富士山大息合結縁地蔵尊が奉安されています。
信玄公により甲府五山に定められ、寺宝として信玄公の家督相続を知らせる「信玄公制札」などが残されています。
参道右手の駐車場あたりはかつて大池で、これを伝える「宿竜の碑」と芭蕉の句碑があります。
- 名月や池をめぐりて夜もすがら -
愛宕山の山腹にあるこの寺の境内は広くはないですが、全体にしっとりと落ち着いて甲府五山の格式を感じます。
甲斐百八霊場第57番の札所で、「佛心」という豪快な揮毫の御朱印を快く授与いただけました。
■ 瑞巖山 円光院(円光護持禅院)







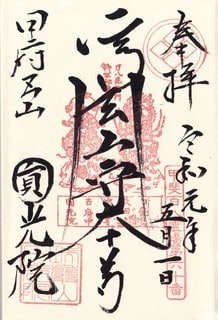
公式Web
甲府市岩窪町500
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第60番
朱印尊格:釈迦如来(佛心)
札番:甲斐百八霊場第60番印判
〔平成28年4月の御朱印〕
・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。
右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔令和元年5月の御朱印〕
・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩と刀八毘沙門天の御影の印と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。
右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。
信玄公開基、信玄公正室三条夫人の菩提寺として知られる名刹。
前身は小石和郷に甲斐源氏の始祖、逸見太郎清光(源清光)公が開創された清光寺で、室町期に甲斐守護武田信守公により再興され成就院となりました。
永禄三年(1560年)、信玄公が京より説三和尚を迎えて開山とし、当地に移され甲府五山の一つ円光禅院と改めました。
この時点では甲府成就院で、三条夫人(円光院殿)逝去ののち、その法名にちなんで円光院に改称されたという説もありますが、三条夫人墓所の説明書には「晴信公は夫人の生前、その牌所として府中五山の一、圓光院を宛て、夫人をその開基とした」とあるので、夫人の生前に円光院に改めたとみられます。(以上、境内由緒書などより)
三条夫人(三条の方)は、清華家の左大臣転法輪三条公頼公の次女で、母は高顕院。
姉は細川晴元室、妹は顕如の妻の如春尼という名流です。
天文五年(1536年)、今川義元公の媒酌で信玄公の正室として嫁し、義信公、黄梅院(北条氏政室)、海野信親(竜芳)公、信之、見性院(穴山梅雪室)の三男二女をもうけました。
三条夫人は度重なる不運に見舞われたと伝わります。
次男信親(竜芳)公は盲目。天文二十年(1551年)には父の公頼公が大寧寺の変(周防の大内義隆が家臣陶隆房の謀反で殺害)に巻き込まれて殺され、三男信之は夭折しました。
さらに永禄八年(1565年)の「義信事件」により長男義信公を失い、永禄十一年(1568年)、信玄公の駿河侵攻により黄梅院が北条氏から離縁され、その翌年に病死しました。
その人物像については諸説ありますが、Wikipedia記載の「円光院の葬儀記録」には、快川和尚の三条の方の人柄を称賛する「大変にお美しく、仏への信仰が篤く、周りにいる人々を包み込む、春の陽光のように温かくておだやかなお人柄で、信玄さまとの夫婦仲も、むつまじいご様子でした」と記された記録が残されているそうです。
境内にはこのようなお人柄を示す案内が掲出されていました。
三條夫人のお人柄の真実
西方一美人 円光如日 和気似春(快川国師の語)
これにより 暖かく穏やかな 三條夫人の婦徳高いお姿が偲ばれます。
元亀元年(1570年)7月に逝去。圓光院殿梅岑宗い大禅定尼と号されました。
本願寺の顕如(光佐)の正室は三条夫人の妹の如春尼であり、本願寺と信玄公との信長包囲同盟の裏には夫人の存在が大きかったと考えられています。
薄倖のイメージをまとわれる三条夫人ですが、その子信親(竜芳)公は穴山信君(梅雪)の娘を娶り、その子の信道公は出家して顕了道快と号し、その子武田信正公とともに紆余曲折を経て家系は存続し、江戸幕府には表高家として武田宗家の命脈を保ちました。(→関連記事)
境内の「三條氏墓の説明書」には、つぎのような記載があります。
「武田家の正統は信親公により今日に継続され、その原づくところが一向宗の僧となった信親公の嫡子信道公に在ることを思えば三條夫人が妹壻本願寺光左上人と武田氏との連携の楔として大きな役割を果たしたことと関連して夫人が武田家のために内外に於ける立場をより利用して大いに尽くされたことが偲ばれる」
三条夫人の菩提寺につき、ゆかりの宝物が所蔵されています。
夫人が武田家に嫁ぐ時に持参されたと伝わる三条家伝来の木造釈迦如来坐像、武田氏の家紋と夫人が皇室から使用を許された菊花紋と桐紋が彫られた愛用の鏡などです。
当寺には信玄公ゆかりの尊像も所蔵されています。
〔境内の解説書(抜粋)〕
刀八毘沙門天像及び勝軍地蔵像は、武田信玄公が殊に信仰した尊像で、もとは居館である躑躅が崎の館内の毘沙門堂に祀り、戦場行軍の際にも座右を離さなかったとされ、元亀四年(1573年)四月三河の軍陣で亡くなる際、馬場美濃守に命じて当寺の開山説三和尚に贈らせ、永く当寺の鎮護となしたとされる。本像は同一厨子内に、向かって右に獅子に乗る刀八毘沙門天像、左に白馬に乗る勝軍地蔵像が安置される。刀八毘沙門天像は、鎧を着用し、忿怒形の顔を正面とその左右、菩薩形の顔を頭上に表し、左右各五本ずつの腕を表す四面十臂の姿である。勝軍地蔵像は、鎧兜に袈裟を掛けた若々しい青年武将の姿で、左手を振り上げて持物を持ち、右手は腹前で剣を持つ。刀八毘沙門天像は毘沙門天、勝軍地蔵像は地蔵菩薩をそれぞれもととして我国で考案された軍神で、室町時代から戦国時代にかけて多くの武将の信仰を集めた。作者は京都の七條大仏師康清と伝えられる。康清は、信玄公造立の恵林寺の武田不動尊の作者であり、活気のある派手やかな作風は両像に共通するところである。」
普段は秘仏ですが、毎年4月の信玄公祭りの際には御開帳されます。
円光院から400mほど離れたところに「武田信玄公墓所」があります。
信玄公の御遺言どおりその死は三年間秘されましたが、その間ひそかに荼毘に附され、埋葬されたのが土屋右衛門の邸で、この場所が後に「武田信玄公墓所」となっています。
毎年4月12日の忌日の廻向そのほかの供養は、円光院により営まれています。
禅寺らしい整った境内。桜の名所としても知られています。
三条夫人の墓所は本堂左奥の高みにあり、宝篋印塔は信玄公の建立と伝わります。
甲斐百八霊場第60番の札所をつとめられ、御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。
■ 金剛福聚山 法泉寺





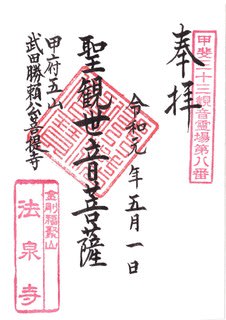
公式Web
甲府市和田町2595
臨済宗妙心寺派 御本尊:弥勒菩薩(釈迦牟尼佛)
札所:甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第62番
・中央に三寶印と札所本尊「南無釈迦牟尼佛」の揮毫。
右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印がありますが、本来は「甲斐百八霊場第六二番」の印判かと思われます。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
朱印尊格:聖観世音菩薩 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第62番
・中央に三寶印と札所本尊「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。
南北朝時代の元徳二年(1330年)、甲斐国守護・武田信武公が開基となり、夢窓国司の高弟であった月舟禅師を招いて創建された名刹。
経緯からすると月舟禅師が一世ですが、禅師は自ら二世を称して恩師の夢窓国師を開山とされました。
開山後は夢窓国師を中心とする五山派の官寺となりましたが、その後衰微していたところ、信玄公が快岳周悦を住職として招き再興・庇護したといわれます。
快岳禅師は武田家滅亡に際して帯那郷へ逃れ、妙心寺の南化和尚(後の定慧円明国師)の力添えを得て京より持ち帰った勝頼公の遺髪をこの寺に手厚く葬ったとされます。
〔宝泉寺境内由緒書より抜粋〕
「本山は臨済宗妙心寺派に属し、本尊は弥勒菩薩である 後醍醐天皇の元徳二年(1330年)、当寺の甲斐の国主武田信武公が夢窓国司弟子月舟禅師に帰依して当山を設立した 禅師が初祖であるが夢窓国師を開山とし自ら二世と称した また信成は武田家九世の王で足利尊氏に厚遇せられ室町幕府の創建に功のあった人で天下の副将軍といわれ当山にその墓がある 爾来信玄公に至る二百余年の事跡は明らかでない 信玄公は当山に寺領を寄進し本堂の大修理を行い 武田家の祈願所とし且つ甲府五山の一に列した 勝頼公・信玄公の志を継ぎ当山を庇護した 天正十年三月公が天目山にて討死し、その首級が京都六條河原にさらされた後京都妙心寺に葬られたが 当山の快岳和尚は妙心寺の南化和尚と謀り密かに公の首級を貰い受けて急ぎ帰山したが当山は織田軍の陣所に充てられ入れず且つ身辺の危険もあり●帯那町穴口の奥の山林中に隠れ首級を護った その時に穴口の三上●家の甚大なる協力があった 偶々信長の死により織田軍が撤兵したので帰山し 公の首級を葬り山桜を植えて標とした 同年七月入甲してきた徳川家康に召され武田家の事情を説明し また武川十二騎を説得してその旗下に服させる寺の功ありその翌年勝頼公を当山の中興開基とし菩提を弔うよう御下命があった 当山は往年は塔頭寺院四ヶ寺県下に末寺六十数ヶ寺を有し多数の修行僧が去来し中本山としての格式を備え」(以下略)
徳川家康公は、甲斐の内情に精通する快岳禅師を召し、徳川家に服従しなかった武川十二騎の説得を命じ、禅師はこれに成功しました。
この功績により寺領御朱印を賜るとともに、快岳禅師(ないしは勝頼公)を中興開基とし、勝頼公の菩提寺に定めたといいます。(以上寺伝等より)
なお、「武川十二騎」とは、現在の北杜市武川町周辺を本拠とする地域武士団「武川衆」をさし、甲斐一条氏の流れを汲む一団とされます。
主に諏訪口の国境を守り、武田家中でもその名を馳せていたと伝わります。武田家滅亡後、その多くは徳川家に属し、旗本となった例も少なくありません。
将軍綱吉公の側用人として大老格まで上り詰めた柳沢吉保は武川衆の末裔といわれ、信玄公の次男、信親(龍芳)公の子孫武田信興公を将軍綱吉公に引きあわせ、高家武田家の創設に尽力、甲斐国国中三郡(巨摩郡・山梨郡・八代郡)を領した際には領内の整備に務め、恵林寺で営まれた信玄公百三十三回忌の法要に関係するなど、甲斐国や武田遺臣の保護に注力したと伝わります。
整った境内に端正な本堂は、やはり五山の格式を感じます。
勝頼公の墓所は、信武公の墓所ととなりあって本堂左手の高みにあります。
由緒書には「本尊は弥勒菩薩」とありますが、甲府市教育委員会の説明書には「釈迦如来像(鎌倉末期作推定) 本像は寺伝に弥勒菩薩と称せられているが、むしろ、宝冠の釈迦または華厳の釈迦といわれるものに近い」とあり、御本尊は釈迦如来(もしくは弥勒菩薩)一尊であることがわかります。
甲斐百八霊場の御朱印尊格は御本尊のケースが多いですが、法泉寺の御朱印尊格は「南無釈迦牟尼佛」となっています。
甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番の札所で、御朱印は快く授与いただけました。
観音札所の御朱印をお願いすると、一瞬とまどわれた感じでしたが無事拝受できました。(観音霊場の巡拝者はすくないそうです。)
甲斐国三十三番観音札所の札所本尊は聖観世音菩薩で本堂に御座します。本堂軒の説明板には「弘法大師作」の掲示がありました。
本堂内には「夢窓国師坐像」(鎌倉時代末期作推定)も安置されています。
以上、甲府五山のご紹介でした。
鎌倉五山には手強いお寺さんがあるので甲府五山も身構えましたが(笑)、いずれも快く御朱印の授与をいただけました。
長禅寺様が非授与なのはご事情がおありなのでしょうが、やはり五山の御朱印を揃っていただきたい感じはします。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社が多くなっています。参拝は、新型コロナ収束後にお願いします。
■〔 信玄公と甲府五山 〕
信玄公は神仏への信仰ふかく、宗派を越えて寺社を厚く保護されました。
「信玄」は、永禄二年(1559年)(天文二一年(1552年)説もあり)に39歳で出家された際の諱で、院号は法性院、道号は機山、別号は徳栄軒と伝わります。
『甲陽軍鑑』によると「玄」は中国の臨済義玄、日本では関山恵玄にゆかりで、得度式を務め「信玄」を授けたのは臨済宗長禅寺(甲府市愛宕町)の住持、岐秀元伯(ぎしゅう げんぱく)とされています。
岐秀元伯は京都妙心寺の学僧で、信玄の母大井夫人の招聘により鮎沢の(古)長禅寺、次いで愛宕の長善寺に住山されました。
岐秀元伯は信玄公の学問の師であったと伝わります。
伝灯は大応国師~大灯国師~妙心寺開山の関山慧玄と続く「応灯関」「関山禅」を嗣ぎ、とくに臨済宗妙心寺派への帰依が深かったとされます。
信玄公の葬儀で大導師を勤められた恵林寺の快川紹喜(かいせん じょうき)も臨済宗妙心寺派の高僧で、信玄公に「機山」の号を授けたとされます。
信玄公は京や鎌倉の五山制度にならい、甲府にも臨済宗寺院で五山を定めました。
長禅寺、東光寺、能成寺、円光院、法泉寺が甲府(府中)五山です。
円光寺の公式Web資料には、「信玄公は元より仏法信仰を重んじ臨済宗に帰依し、京都妙心寺の開山である開山国師の遺風を崇敬しておりました。その因縁により、京五山、鎌倉五山にならい、甲州の古刹の寺を城下に移しました。そして何れも妙心寺派に改め、それぞれに土地を寄付し、これらの寺を御城附御祈願所五山と号しました。」とあります。
また、法泉寺前掲示の甲府五山の説明書には、「戦国武将武田信玄公は臨済宗に深く帰依し、京都五山・鎌倉五山の制度にならって『甲府(府中)五山』を定めました。その五寺は、宝泉寺、長禅寺、東光寺、円光院、能成寺です。信玄は広く仏教を信仰し、宗旨のいかんを問わず、寺院・僧侶を崇敬保護したことが知られています。とりわけ臨済宗に対する帰依は深く、平素より多くの禅僧と親交を深めていました。諸国から禅宗の高僧を招いて師とし、その教えを民政や軍法に活かしたのです。代表的な高僧は、五山派の惟高妙安、策彦周良、妙心寺(関山)派の岐秀元伯、快川紹喜らです。特に岐秀は信玄幼少時からの参禅の師であり、学問・修養を通じて信玄の人格形成に深い影響を及ぼしたといわれ、信玄剃髪の際に大導師もつとめました。」とあります。
五山の所在地は甲府北部の住宅地から山手に点在し、「小松」といわれる一帯に宝泉寺、長善寺、円光院、「板垣」といわれる一帯に能成寺、東光寺があり、「北山野道」という遊歩コースが設けられています。
■ 瑞雲山 長禅寺








甲府市愛宕町208
臨済宗単立 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第58番、甲斐国三十三番観音札所第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第64番、府内観音札所第9番
※御朱印は不授与です。
信玄公の母、大井夫人(瑞雲院殿)の菩提寺で、岐秀元伯が開いたとされる臨済宗の名刹。
創建は天文二一年(1552年)と伝わり(『甲斐国志』)、甲府五山の主座(筆頭)とされます。
長禅寺の前身は、大井夫人の出である西郡の国人、大井氏領する巨摩郡相沢(現・南アルプス市鮎沢)の長善寺(現・古長禅寺)で、大井氏の菩提寺でした。(古長禅寺は後述します。)
大井夫人は西郡の国衆(国人領主)で、武田氏一門の大井信達公の息女。
駿河に近い西郡の大井信達公は今川氏と結んで信虎公と抗争を続けていましたが、永正十四年(1517年)に信虎公と和睦。
このとき大井夫人が信虎公の正室として嫁いだため、政略結婚の意味合いが強いものとみなされています。
信虎公との間に嫡男信玄公、信繁公、信廉公(逍遙軒信綱)および長女をもうけました。
信繁公、信廉公ともに能く信玄公を補佐されたと伝わり、二十四将に数えられています。
大井夫人は賢母で、悟渓宗頓(大徳寺五二世住持、妙心寺四派の一、東海派の開祖)の法統を嗣ぐ、尾張国瑞泉寺の岐秀元伯を長禅寺に招き、若き日の信玄公に「四書五経」「孫子」「呉子」などを学ばせたといわれます。
天文十年(1541年)の信玄公による信虎公駿河追放ののちも甲斐に留まられ、躑躅ヶ崎館北曲輪に居住されました。
天文二一年(1552年)に逝去。法名は瑞雲院殿月珠泉大姉。
葬儀の大導師を務められたのは岐秀元伯と伝わります(『高白斎記』)。
大井夫人逝去の後、西郡の鮎沢では墓所が遠いため、亡き母を開基に、導師の岐秀元伯を開山に請じて新たに長禅寺として開かれました。
本堂左手手前に大井夫人の霊廟があり、本堂左手の坂の上に墓所があります。
参拝時には落枝の危険で墓所参道は通行禁止となっていました。
非公開ですが、「絹本著色武田信虎夫人像」「紙本著色渡唐天神像」の文化財を所蔵しています。
「絹本著色武田信虎夫人像」は大井夫人(瑞雲院殿)の肖像画で、画人としても知られた信玄公の同母弟・信廉公(逍遥軒信綱・二十四将の一人)の筆によるもの。
信廉公21歳、天文二二年(1553年)の作とされます。
なお、名門大井氏は嫡流信業公の三弟と六弟が武藤姓を名乗り、関ヶ原の戦いの際、上田城で秀忠軍を釘付けにした真田昌幸は、永禄年間にこの大井氏流武藤家に養子に入っていたと伝わります。
「武藤三郎左衛門尉のときに実子の武藤与次が早世したため、真田昌幸を養子にとった」という説があり、武藤喜兵衛尉昌幸は二十四将のひとりに数えられることもあります。(→関連資料)
どことなく近寄りがたい威厳のある禅寺で、いくつかの霊場札所となっているものの、御朱印は一切授与されていないようです。
■ 法蓋山 東光寺(東光興国禅寺)








甲府市東光寺3-7-37
臨済宗妙心寺派 御本尊:薬師如来
札所:甲斐百八霊場第56番
朱印尊格:本尊 薬師如来 書置(印刷?)
札番:甲斐百八霊場第56番印判
・中央に札所本尊、薬師如来の種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に三寶印。中央に「本尊 薬師如来」の揮毫。
右上に「甲斐百八霊場第五六番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
寺伝によると平安時代の保安二年(1121年)に源義光(新羅三郎)公が密教の祈願所として諸堂を整え、興国院と号したとされます。
その後鎌倉期に蘭渓道隆が禅宗寺院として再興、寺号を東光寺と改めました。
この寺に幽閉され終焉を遂げられた信玄公の長子義信公、諏訪から移られて自害された諏訪の領主諏訪頼重公の墓所であり、戦国の哀史を物語る史跡として訪れる人も多いようです。
〔武田義信公〕
義信公は、天文七年(1538年)信玄公の嫡男として生まれました。
母は信玄公の正室、公家の三条公頼公の息女の三条夫人です。
天文十九年(1550年)、若くして今川義元公の息女(従姉妹とも)を正室に迎えています。
初陣の知久氏攻めをはじめ、小諸城攻略、川中島での戦いなどでの華々しい武功が伝わります。
天文二二年(1553年)、将軍足利義藤(義輝)公より将軍家の通字である「義」の偏諱を受けて義信と名乗られ(『高白斎記』)、永禄元年(1558年)、信玄公が信濃守護に補任された際には「准三管領」としての待遇を受けており、武田家嫡男としての道を順調に歩まれていました。
永禄八年(1565年)10月、信玄公暗殺を企てた謀反にかかわったとされ甲府東光寺に幽閉。(『甲陽軍鑑』)
永禄十年(1567年)10月19日に東光寺で逝去されました。享年30歳。
同年11月には正室の今川氏は駿河へ帰国しています。
この事件は「義信事件」と通称され、信玄公をめぐる謎のひとつとされています。
経緯がこみ入っているので詳細は省きますが、『甲陽軍鑑』によると、義信公の傅役である飯富虎昌以下の側近が処刑され、八十騎の家臣団が追放処分になっているので、これを受けた武田家臣内紛説がみられます。
永禄三年(1560年)、桶狭間の戦いでの今川義元公の戦死、永禄四年(1561年)第4次川中島の戦いを経た北信地域の実質的な領有などを契機に信玄公は対外方針を転換し、永禄十一年(1568年)には今川氏の領国駿河への侵攻を始めています。
「義信事件」は駿河侵攻の3年前であり、今川氏に対する方針で親子、および家臣内で深刻な対立があり、これが事件の契機となったとする見解がみられます。
今川義元公の息女を正室としていた義信公が親今川派、「義信事件」後に駿河侵攻を進めた信玄公が反今川派という構図です。
また、永禄年間以降、信玄公と信長公とに同盟の動きがあり、信長公と敵対関係にあった今川氏との間に生じた軋轢を背景のひとつとみる説もあります。
信虎公の長女定恵院(信玄公の同母姉)は義元公の正室で、氏真公の母であり、娘の嶺松院は義信公の正室です。
永禄三年(1560年)5月、桶狭間の戦いで戦死した今川義元公の跡を継いだ氏真公は、家臣の掌握に苦しみ離反を招きました。当時今川家の食客となっていた信虎公は、今川家臣と謀って氏真公の追放を企図しましたが事前に露見し、駿府を追われ京に向かわれたとされます。
また、信虎公の子武田信友は今川家臣団に加わり、後に武田氏の駿河侵攻に呼応しています。
このあたりの今川家をめぐる複雑な事情も「義信事件」の背景にあるとみられます。
駿河に接する河内領の領主で武田御一門衆の穴山氏は、武田・今川の甲駿同盟を取次し、義信公と今川氏の婚姻も仲介しましたが、「義信事件」翌年の永禄九年(1566年)に当主穴山信君の弟、穴山彦八郎(信嘉、信邦)が身延山久遠寺塔頭において自害しており(『甲斐国志』)、これを対今川戦略対立説の論拠とする説もあります。
義信公の墓所は、本堂裏山の左手にひっそりとあります。
〔諏訪頼重公〕
諏訪頼重公は、諏訪氏第十九代当主で諏訪大社大祝。上原城城主であり、戦国大名として諏訪一円を治めました。
諏訪氏は神代以来の諏訪大社上社の大祝の家柄で、「神氏(みわし/じんし)」とも尊称された名族です。
信虎公の時代、諏訪氏は武田氏と抗争し、享禄元年(1528年)信虎公は諏訪に侵入して頼満公と対戦、享禄四年(1531年)には逆に頼満公が韮崎あたりまで兵を入れています。
諏訪氏との抗争を不利とみた信虎公は、天文四年(1535年)に頼満公と和睦(盟約)し、天文九年(1540年)には三女・禰々を頼満公の跡を継いだ頼重公に嫁がせています。
以降、小県郡侵攻などで武田家と連携していました。
甲斐から信濃へ向かうには、諏訪口(甲州街道)と佐久口(佐久甲州街道)の2つのルートがあります。
諏訪ルートは諏訪氏との盟約があってとれないので、信虎公の時代はもっぱら佐久ルートをもって信濃侵攻がなされました。
しかし、晴信公が当主となると方針を転じ、諏訪への侵攻を開始しました。
『甲陽軍艦』では、この時期の信玄公の戦として「瀬沢合戦」を記しています。
これは天文十一年(1542年)、信濃四将(中信の小笠原長時、北信の村上義清、木曽の木曽義康、諏訪の諏訪頼重)と信玄公の大合戦で、信濃勢一万六千を武田軍八千が瀬沢(現・長野県富士見町)で迎え撃ち、信濃勢は千六百二十一人の戦死者を出して敗走したというもの。
瀬沢周辺にはこれを示す史跡も残りますが、この戦いは『甲陽軍艦』のほかに確実な史料が認められないため、合戦そのものの存在が疑問視されています。
神代より、諏訪大社上社の大祝は諏訪氏、諏訪下社の大祝は代々金刺氏が継いできました。
この時代、金刺氏は諏訪氏の配下にありましたが、両氏は伝統的に対立関係にあったとされています。
また、諏訪氏の一族、伊那・高遠城主の高遠信濃守頼継も諏訪氏と対立関係にありました。
諏訪総領家の祖・安芸守信嗣は高遠氏の祖・信濃守頼継の弟であり、高遠氏が本来の上社大祝の家柄である、という自負があったためとみられています。
信玄公はこのような諏訪一族内の軋轢に乗じ、謀略の手を伸ばして金刺氏、高遠頼継をみかたにつけて諏訪に侵入しました。ときを合わせて高遠頼継も杖突峠を越えて諏訪に攻め入りました。
南方から武田、西方からは高遠勢の攻撃を受け苦境に陥った頼重公は、上原城を退き北方の桑原城に移りました。
桑原城にて、信玄公から「城を明け渡せば武田勢は甲斐に引き上げる」旨の和睦案を受けた頼重公はこれを容れ、城を渡して甲斐・府中に送られました。
頼重公は東光寺に幽閉され、その後自刃されました。
ときに頼重公27歳。辞世の句が残されています。
- おのづから 枯れ果てにけり 草の葉の 主あらばこそ 又も結ばめ -
これにより諏訪惣領家は滅亡したとされていますが、上社大祝は叔父諏訪満隣の家系が継ぎ、その子孫は近世に中興されて諏訪高島藩三万石の大名となっています。
頼重公の墓所は、本堂裏山の左手にあります。
桑原城址そばには、頼重公の家臣らが公の遺髪を埋めたと伝わる頼重院があり、供養塔が残されています。

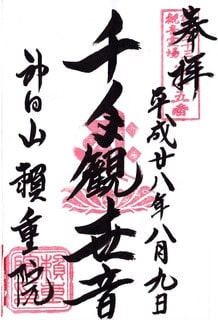
【写真 上(左)】 頼重院 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 頼重院 観音霊場の御朱印
信玄公はこののち頼重公の息女を側室として迎え、この側室は勝頼公を産んでいます。
よって頼重公は勝頼公の外祖父にあたります。
『甲陽軍艦』に「尋常かくれなき美人にてまします」と記されたこの美貌の側室(諏訪御料人)は、小説やドラマでは、湖衣姫(こいひめ)、由布姫(ゆぶひめ・ゆうひめ)として描かれています。
東光寺は甲府北部の住宅地の奥に、落ち着いたたたずまいをみせています。
室町時代の作とされる仏殿は、鎌倉禅宗様式の代表的な建築物として国の重要文化財に指定されています。
仏殿の御本尊は薬師如来。鎌倉時代作の檜材の坐像で、これを取り囲むように守護神である十二神将立像(檜材、伝鎌倉時代作)が安置されています。
本堂裏手には、蘭渓道隆(ないし当寺中興開山・大覚禅師)の作と伝わる北宋山水様式の池泉式庭園(東光寺庭園)が構えられ、鎌倉中期の特色を残す作例として知られています。
甲斐百八霊場第56番の札所であり、ご丁寧な対応にて御朱印をいただけました。
■ 定林山 能成寺(能成護国禅寺)





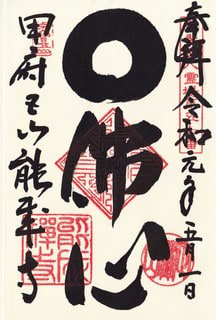
公式Web
甲府市東光寺町2153
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第57番
朱印尊格:釈迦如来(佛心) 直書(筆書)
札番:甲斐百八霊場第57番印判
・中央に三寶印と「○」字と「佛心」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第五七番」の札所印。左下には「甲府五山」と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
南北朝時代の貞和年間(1345年~1349年)に天目山棲雲寺の業海本浄(ごっかい ほんじょう)の開山、甲斐国守護・武田信守公(能成寺殿)を開基として、小石和筋八代村(現在の笛吹市八代町)に創建された古刹です。
信玄公のとき西青沼(現在の甲府市宝)に移され、さらに文禄年間(1592年~1595年)、甲府城築城の折に現在地に移されました。
創建時の御本尊は三尊阿弥陀如来(安阿弥作)でしたが、現在は釈迦牟尼仏。
本堂上間の間に富士山大息合結縁地蔵尊が奉安されています。
信玄公により甲府五山に定められ、寺宝として信玄公の家督相続を知らせる「信玄公制札」などが残されています。
参道右手の駐車場あたりはかつて大池で、これを伝える「宿竜の碑」と芭蕉の句碑があります。
- 名月や池をめぐりて夜もすがら -
愛宕山の山腹にあるこの寺の境内は広くはないですが、全体にしっとりと落ち着いて甲府五山の格式を感じます。
甲斐百八霊場第57番の札所で、「佛心」という豪快な揮毫の御朱印を快く授与いただけました。
■ 瑞巖山 円光院(円光護持禅院)







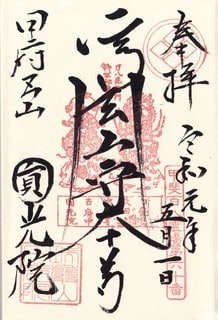
公式Web
甲府市岩窪町500
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第60番
朱印尊格:釈迦如来(佛心)
札番:甲斐百八霊場第60番印判
〔平成28年4月の御朱印〕
・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。
右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔令和元年5月の御朱印〕
・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩と刀八毘沙門天の御影の印と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。
右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。
信玄公開基、信玄公正室三条夫人の菩提寺として知られる名刹。
前身は小石和郷に甲斐源氏の始祖、逸見太郎清光(源清光)公が開創された清光寺で、室町期に甲斐守護武田信守公により再興され成就院となりました。
永禄三年(1560年)、信玄公が京より説三和尚を迎えて開山とし、当地に移され甲府五山の一つ円光禅院と改めました。
この時点では甲府成就院で、三条夫人(円光院殿)逝去ののち、その法名にちなんで円光院に改称されたという説もありますが、三条夫人墓所の説明書には「晴信公は夫人の生前、その牌所として府中五山の一、圓光院を宛て、夫人をその開基とした」とあるので、夫人の生前に円光院に改めたとみられます。(以上、境内由緒書などより)
三条夫人(三条の方)は、清華家の左大臣転法輪三条公頼公の次女で、母は高顕院。
姉は細川晴元室、妹は顕如の妻の如春尼という名流です。
天文五年(1536年)、今川義元公の媒酌で信玄公の正室として嫁し、義信公、黄梅院(北条氏政室)、海野信親(竜芳)公、信之、見性院(穴山梅雪室)の三男二女をもうけました。
三条夫人は度重なる不運に見舞われたと伝わります。
次男信親(竜芳)公は盲目。天文二十年(1551年)には父の公頼公が大寧寺の変(周防の大内義隆が家臣陶隆房の謀反で殺害)に巻き込まれて殺され、三男信之は夭折しました。
さらに永禄八年(1565年)の「義信事件」により長男義信公を失い、永禄十一年(1568年)、信玄公の駿河侵攻により黄梅院が北条氏から離縁され、その翌年に病死しました。
その人物像については諸説ありますが、Wikipedia記載の「円光院の葬儀記録」には、快川和尚の三条の方の人柄を称賛する「大変にお美しく、仏への信仰が篤く、周りにいる人々を包み込む、春の陽光のように温かくておだやかなお人柄で、信玄さまとの夫婦仲も、むつまじいご様子でした」と記された記録が残されているそうです。
境内にはこのようなお人柄を示す案内が掲出されていました。
三條夫人のお人柄の真実
西方一美人 円光如日 和気似春(快川国師の語)
これにより 暖かく穏やかな 三條夫人の婦徳高いお姿が偲ばれます。
元亀元年(1570年)7月に逝去。圓光院殿梅岑宗い大禅定尼と号されました。
本願寺の顕如(光佐)の正室は三条夫人の妹の如春尼であり、本願寺と信玄公との信長包囲同盟の裏には夫人の存在が大きかったと考えられています。
薄倖のイメージをまとわれる三条夫人ですが、その子信親(竜芳)公は穴山信君(梅雪)の娘を娶り、その子の信道公は出家して顕了道快と号し、その子武田信正公とともに紆余曲折を経て家系は存続し、江戸幕府には表高家として武田宗家の命脈を保ちました。(→関連記事)
境内の「三條氏墓の説明書」には、つぎのような記載があります。
「武田家の正統は信親公により今日に継続され、その原づくところが一向宗の僧となった信親公の嫡子信道公に在ることを思えば三條夫人が妹壻本願寺光左上人と武田氏との連携の楔として大きな役割を果たしたことと関連して夫人が武田家のために内外に於ける立場をより利用して大いに尽くされたことが偲ばれる」
三条夫人の菩提寺につき、ゆかりの宝物が所蔵されています。
夫人が武田家に嫁ぐ時に持参されたと伝わる三条家伝来の木造釈迦如来坐像、武田氏の家紋と夫人が皇室から使用を許された菊花紋と桐紋が彫られた愛用の鏡などです。
当寺には信玄公ゆかりの尊像も所蔵されています。
〔境内の解説書(抜粋)〕
刀八毘沙門天像及び勝軍地蔵像は、武田信玄公が殊に信仰した尊像で、もとは居館である躑躅が崎の館内の毘沙門堂に祀り、戦場行軍の際にも座右を離さなかったとされ、元亀四年(1573年)四月三河の軍陣で亡くなる際、馬場美濃守に命じて当寺の開山説三和尚に贈らせ、永く当寺の鎮護となしたとされる。本像は同一厨子内に、向かって右に獅子に乗る刀八毘沙門天像、左に白馬に乗る勝軍地蔵像が安置される。刀八毘沙門天像は、鎧を着用し、忿怒形の顔を正面とその左右、菩薩形の顔を頭上に表し、左右各五本ずつの腕を表す四面十臂の姿である。勝軍地蔵像は、鎧兜に袈裟を掛けた若々しい青年武将の姿で、左手を振り上げて持物を持ち、右手は腹前で剣を持つ。刀八毘沙門天像は毘沙門天、勝軍地蔵像は地蔵菩薩をそれぞれもととして我国で考案された軍神で、室町時代から戦国時代にかけて多くの武将の信仰を集めた。作者は京都の七條大仏師康清と伝えられる。康清は、信玄公造立の恵林寺の武田不動尊の作者であり、活気のある派手やかな作風は両像に共通するところである。」
普段は秘仏ですが、毎年4月の信玄公祭りの際には御開帳されます。
円光院から400mほど離れたところに「武田信玄公墓所」があります。
信玄公の御遺言どおりその死は三年間秘されましたが、その間ひそかに荼毘に附され、埋葬されたのが土屋右衛門の邸で、この場所が後に「武田信玄公墓所」となっています。
毎年4月12日の忌日の廻向そのほかの供養は、円光院により営まれています。
禅寺らしい整った境内。桜の名所としても知られています。
三条夫人の墓所は本堂左奥の高みにあり、宝篋印塔は信玄公の建立と伝わります。
甲斐百八霊場第60番の札所をつとめられ、御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。
■ 金剛福聚山 法泉寺





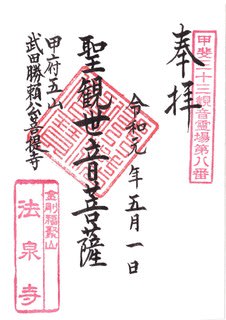
公式Web
甲府市和田町2595
臨済宗妙心寺派 御本尊:弥勒菩薩(釈迦牟尼佛)
札所:甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番
〔甲斐百八霊場の御朱印〕
朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第62番
・中央に三寶印と札所本尊「南無釈迦牟尼佛」の揮毫。
右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印がありますが、本来は「甲斐百八霊場第六二番」の印判かと思われます。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。
〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕
朱印尊格:聖観世音菩薩 書置(筆書)
札番:甲斐百八霊場第62番
・中央に三寶印と札所本尊「聖観世音菩薩」の揮毫。
右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。
南北朝時代の元徳二年(1330年)、甲斐国守護・武田信武公が開基となり、夢窓国司の高弟であった月舟禅師を招いて創建された名刹。
経緯からすると月舟禅師が一世ですが、禅師は自ら二世を称して恩師の夢窓国師を開山とされました。
開山後は夢窓国師を中心とする五山派の官寺となりましたが、その後衰微していたところ、信玄公が快岳周悦を住職として招き再興・庇護したといわれます。
快岳禅師は武田家滅亡に際して帯那郷へ逃れ、妙心寺の南化和尚(後の定慧円明国師)の力添えを得て京より持ち帰った勝頼公の遺髪をこの寺に手厚く葬ったとされます。
〔宝泉寺境内由緒書より抜粋〕
「本山は臨済宗妙心寺派に属し、本尊は弥勒菩薩である 後醍醐天皇の元徳二年(1330年)、当寺の甲斐の国主武田信武公が夢窓国司弟子月舟禅師に帰依して当山を設立した 禅師が初祖であるが夢窓国師を開山とし自ら二世と称した また信成は武田家九世の王で足利尊氏に厚遇せられ室町幕府の創建に功のあった人で天下の副将軍といわれ当山にその墓がある 爾来信玄公に至る二百余年の事跡は明らかでない 信玄公は当山に寺領を寄進し本堂の大修理を行い 武田家の祈願所とし且つ甲府五山の一に列した 勝頼公・信玄公の志を継ぎ当山を庇護した 天正十年三月公が天目山にて討死し、その首級が京都六條河原にさらされた後京都妙心寺に葬られたが 当山の快岳和尚は妙心寺の南化和尚と謀り密かに公の首級を貰い受けて急ぎ帰山したが当山は織田軍の陣所に充てられ入れず且つ身辺の危険もあり●帯那町穴口の奥の山林中に隠れ首級を護った その時に穴口の三上●家の甚大なる協力があった 偶々信長の死により織田軍が撤兵したので帰山し 公の首級を葬り山桜を植えて標とした 同年七月入甲してきた徳川家康に召され武田家の事情を説明し また武川十二騎を説得してその旗下に服させる寺の功ありその翌年勝頼公を当山の中興開基とし菩提を弔うよう御下命があった 当山は往年は塔頭寺院四ヶ寺県下に末寺六十数ヶ寺を有し多数の修行僧が去来し中本山としての格式を備え」(以下略)
徳川家康公は、甲斐の内情に精通する快岳禅師を召し、徳川家に服従しなかった武川十二騎の説得を命じ、禅師はこれに成功しました。
この功績により寺領御朱印を賜るとともに、快岳禅師(ないしは勝頼公)を中興開基とし、勝頼公の菩提寺に定めたといいます。(以上寺伝等より)
なお、「武川十二騎」とは、現在の北杜市武川町周辺を本拠とする地域武士団「武川衆」をさし、甲斐一条氏の流れを汲む一団とされます。
主に諏訪口の国境を守り、武田家中でもその名を馳せていたと伝わります。武田家滅亡後、その多くは徳川家に属し、旗本となった例も少なくありません。
将軍綱吉公の側用人として大老格まで上り詰めた柳沢吉保は武川衆の末裔といわれ、信玄公の次男、信親(龍芳)公の子孫武田信興公を将軍綱吉公に引きあわせ、高家武田家の創設に尽力、甲斐国国中三郡(巨摩郡・山梨郡・八代郡)を領した際には領内の整備に務め、恵林寺で営まれた信玄公百三十三回忌の法要に関係するなど、甲斐国や武田遺臣の保護に注力したと伝わります。
整った境内に端正な本堂は、やはり五山の格式を感じます。
勝頼公の墓所は、信武公の墓所ととなりあって本堂左手の高みにあります。
由緒書には「本尊は弥勒菩薩」とありますが、甲府市教育委員会の説明書には「釈迦如来像(鎌倉末期作推定) 本像は寺伝に弥勒菩薩と称せられているが、むしろ、宝冠の釈迦または華厳の釈迦といわれるものに近い」とあり、御本尊は釈迦如来(もしくは弥勒菩薩)一尊であることがわかります。
甲斐百八霊場の御朱印尊格は御本尊のケースが多いですが、法泉寺の御朱印尊格は「南無釈迦牟尼佛」となっています。
甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番の札所で、御朱印は快く授与いただけました。
観音札所の御朱印をお願いすると、一瞬とまどわれた感じでしたが無事拝受できました。(観音霊場の巡拝者はすくないそうです。)
甲斐国三十三番観音札所の札所本尊は聖観世音菩薩で本堂に御座します。本堂軒の説明板には「弘法大師作」の掲示がありました。
本堂内には「夢窓国師坐像」(鎌倉時代末期作推定)も安置されています。
以上、甲府五山のご紹介でした。
鎌倉五山には手強いお寺さんがあるので甲府五山も身構えましたが(笑)、いずれも快く御朱印の授与をいただけました。
長禅寺様が非授与なのはご事情がおありなのでしょうが、やはり五山の御朱印を揃っていただきたい感じはします。
~ つづきます ~
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
戦国時代を代表する武将、武田信玄公。
4月12日は信玄公のご命日で、例年、ご命日前の金~日曜には”信玄公祭り”、4月12日には”武田二十四将騎馬行列”が催されますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で見送り(延期か中止かは未定)となっています。

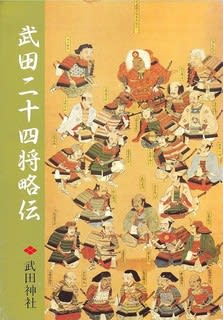
「武田二十四将」は戦国期に実在した職制ではなく、後世に武田氏の家臣として活躍した武将から23人ないし24人を選定したもので、江戸期以降、絵画や浄瑠璃を通じて広く親しまれたものです。
「二十四将図」に描かれる武将は諸本により異なりますが、武田神社で入手した「新編 武田二十四将 正伝」では、以下の24将が挙げられています。
〔武田家の四宿老〕
●甘利備前守虎泰
●板垣駿河守信方
●飯富兵部少輔虎昌
●高坂弾正忠昌信(春日虎綱)
●内藤修理亮昌豊(昌秀)
●馬場美濃守信春
●山県三郎右兵衛尉昌景
〔武田家の御一門衆〕
●穴山玄蕃頭信君
●一条右衛門太夫信龍(信竜)
●武田刑部少輔信廉
●武田典厩信繁
〔武田家の侍大将〕
●秋山伯耆守信友(虎繁)
●小山田左兵衛尉信茂
●真田弾正忠幸隆(幸綱)
●真田源太左衛門尉信綱
●土屋右衛門尉昌続
●原隼人昌胤
〔武田家の足軽大将〕
●小幡山城守虎盛(小畠虎盛)
●小幡豊後守昌盛
●三枝勘解由左右衛門尉守友(昌貞)
●多田淡路守満頼(三八郎)
●原美濃守虎胤
●横田備中守高松
●山本勘助晴幸
山梨県内には信玄公をはじめ「武田二十四将」ないしその一族ゆかりの寺社が多く存在します。
また、山梨県内の霊場として「甲斐百八霊場」「甲斐三十三観音霊場」「郡内三十三観音霊場」「甲斐八十八ヶ所霊場」などが開創され、多くの寺社で御朱印を拝受することができます。
じつは、筆者の家は「武田二十四将」の武将の末裔と伝わっているので、これまで山梨県内の「武田二十四将」ゆかりの史跡はそれなりにまわっています。
そんなこともあって、これから、信玄公と「武田二十四将」ゆかり寺社と御朱印をまとめてご紹介してみます。
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
4月12日は信玄公のご命日で、例年、ご命日前の金~日曜には”信玄公祭り”、4月12日には”武田二十四将騎馬行列”が催されますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で見送り(延期か中止かは未定)となっています。

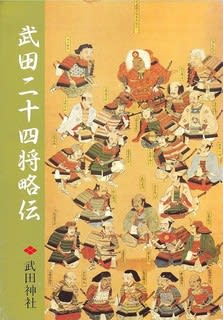
「武田二十四将」は戦国期に実在した職制ではなく、後世に武田氏の家臣として活躍した武将から23人ないし24人を選定したもので、江戸期以降、絵画や浄瑠璃を通じて広く親しまれたものです。
「二十四将図」に描かれる武将は諸本により異なりますが、武田神社で入手した「新編 武田二十四将 正伝」では、以下の24将が挙げられています。
〔武田家の四宿老〕
●甘利備前守虎泰
●板垣駿河守信方
●飯富兵部少輔虎昌
●高坂弾正忠昌信(春日虎綱)
●内藤修理亮昌豊(昌秀)
●馬場美濃守信春
●山県三郎右兵衛尉昌景
〔武田家の御一門衆〕
●穴山玄蕃頭信君
●一条右衛門太夫信龍(信竜)
●武田刑部少輔信廉
●武田典厩信繁
〔武田家の侍大将〕
●秋山伯耆守信友(虎繁)
●小山田左兵衛尉信茂
●真田弾正忠幸隆(幸綱)
●真田源太左衛門尉信綱
●土屋右衛門尉昌続
●原隼人昌胤
〔武田家の足軽大将〕
●小幡山城守虎盛(小畠虎盛)
●小幡豊後守昌盛
●三枝勘解由左右衛門尉守友(昌貞)
●多田淡路守満頼(三八郎)
●原美濃守虎胤
●横田備中守高松
●山本勘助晴幸
山梨県内には信玄公をはじめ「武田二十四将」ないしその一族ゆかりの寺社が多く存在します。
また、山梨県内の霊場として「甲斐百八霊場」「甲斐三十三観音霊場」「郡内三十三観音霊場」「甲斐八十八ヶ所霊場」などが開創され、多くの寺社で御朱印を拝受することができます。
じつは、筆者の家は「武田二十四将」の武将の末裔と伝わっているので、これまで山梨県内の「武田二十四将」ゆかりの史跡はそれなりにまわっています。
そんなこともあって、これから、信玄公と「武田二十四将」ゆかり寺社と御朱印をまとめてご紹介してみます。
---------------------------------------------------------
■ 目次
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
薬師丸ひろ子&カラバト
NHK「SONGS」の薬師丸ひろ子特集(総合 2020年1月25日(土)午後11:00 ~11:30)、録画して視てみました。
やっはり凄い!
1970~80年代に角川映画で主題歌を歌っていたときは、正直さほどうまいとは思わなかった。
それがここまで極められるとは・・・。
資質もあると思うけど、歌手って年齢を重ねるにしたがって、ここまで歌の質を高めていくことができるんだ・・・。
徹底した腹式の発声と、そこからつくりだされるたおやかなビブラートがポイントだと思うが、ごたくならべる気もなくなった。
ただただ聴き入るのみ。
■ 薬師丸ひろ子 「ここからの夜明け」
■ 薬師丸ひろ子 「時代」
女優だけあって表現力がハンパない。これはもはや日本の「宝」か。
ほんとうにいい歳のとり方をされてきたのだと思う。
---------------------------------------
本日(2020/01/26)のカラバト、別に記事立てる気も起こらないので、ここに書きます。
しかしま~、あいかわらずAIの採点基準ぜんぜんわからず。
決勝進出の3名、全員ボックス型Aビブラートって初めてみた。(優勝者は、意図的にAビブ使っている感じもしたけど。)
それにしても、ほんとに、これからもこの機械でいくつもりなのか・・・?
やっはり凄い!
1970~80年代に角川映画で主題歌を歌っていたときは、正直さほどうまいとは思わなかった。
それがここまで極められるとは・・・。
資質もあると思うけど、歌手って年齢を重ねるにしたがって、ここまで歌の質を高めていくことができるんだ・・・。
徹底した腹式の発声と、そこからつくりだされるたおやかなビブラートがポイントだと思うが、ごたくならべる気もなくなった。
ただただ聴き入るのみ。
■ 薬師丸ひろ子 「ここからの夜明け」
■ 薬師丸ひろ子 「時代」
女優だけあって表現力がハンパない。これはもはや日本の「宝」か。
ほんとうにいい歳のとり方をされてきたのだと思う。
---------------------------------------
本日(2020/01/26)のカラバト、別に記事立てる気も起こらないので、ここに書きます。
しかしま~、あいかわらずAIの採点基準ぜんぜんわからず。
決勝進出の3名、全員ボックス型Aビブラートって初めてみた。(優勝者は、意図的にAビブ使っている感じもしたけど。)
それにしても、ほんとに、これからもこの機械でいくつもりなのか・・・?
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印
このページ、一年も画像なしで放置しているのにけっこうアクセスをいただいています。
新たに寺社の追加&御朱印画像のみ追加してとりあえず再UPします。
熱海温泉と湯河原温泉は東京方面からのアプローチがかぶるので、ひとつにまとめました。
対象エリアは箱根方面へのアプローチを分けた、国道135号「早川」交差点以南から熱海市内までで、真鶴エリアを含みます。
非札所のご不在気味の寺社も含んでいます。念のため。
なお、たいていの寺社にはPがありますが、見当たらないところもあり、細い路地もあるので車での参拝要注意です。
(それと、休日の来宮神社のPはやたらに混みます。)
■ 湯河原温泉周辺&真鶴の御朱印
湯河原温泉周辺の御朱印スポットとしては五所神社が有名ですが、札所寺院がないこともあって、他にメジャーな授与寺院はみあたりません。
いくつかの寺社で拝受できるものの、ご不在気味の寺社も多く、拝受難易度は比較的高いものとみられます。
真鶴エリアでは貴船神社が有名で、御朱印帳も頒布されています。
寺院では足柄三十三観音霊場の札所がふたつ。この霊場は現在ほぼ完全に活動を停止しているとみられ、霊場会もありません。
札所印つきの御朱印を授与されるお寺さんがある一方、不授与のお寺さんもあってそれぞれ個別の対応となっているようです。
真鶴エリアのふたつの札所についてはWeb情報が見当たりませんでしたが、ご丁寧な対応にて拝受できましたのでご紹介します。
ただし、いずれも御朱印尊格は御本尊で、観音様での授与はありませんでした。
(この霊場はすべて浄土宗寺院で構成され、御本尊御朱印は「阿弥陀如来」ないし六字御名号「南無阿弥陀佛」になるようです。)
■ 熱海温泉周辺の御朱印
熱海市内には寺社が比較的多く鎮座し、温泉地としては効率的に御朱印をいただけるエリアです。
とくに、力感あふれる御朱印&御朱印帳の伊豆山神社、伊豆有数のパワスポとして人気の来宮神社など、御朱印好き(?)には欠かせないメジャーな神社があります。
熱海は観光で寺社巡りする人も多いらしく、熱海市観光協会も公式Webで「熱海御朱印ウォーク」を掲載していることもあってか、札所ではなくても御朱印を授与されるお寺さんが目立ちます。今回はこのような非札所の寺院もご紹介します。
ただし、ご不在の寺社も何軒かあったことをお断りしておきます。(何度目かの参拝で拝受)
熱海は伊東と異なり七福神は設定されていません。
札所としては、近年復興を果たした伊豆八十八ヶ所霊場がメインとなり、熱海市内に4箇寺の札所(第23番~第26番)があります。
ただし、伊豆八十八ヶ所霊場はけっこうマニアックな霊場で、御朱印拝受にもそれなりの作法が要ります。(専用納経帳が必要かどうかよくわからない札所が2ヶ所ある)
これに対して、熱海市観光協会の公式Web「熱海御朱印ウォーク」では、「御朱印をいただく際は、お寺様の仏事が優先ですので、無理のないようにし、第23番~26番札所で頂けなかった場合は熱海市観光協会までご相談ください。」というホスピタリティにあふれた(?)案内がなされています。(本来、自分で何とかすべきことだと思いますが・・・(笑))
なお、ユニークな絵御朱印で有名な函南の渓月山 長光寺も熱海のすぐ上なので併せてご紹介します。
まずは御朱印関連情報&御朱印画像をUPし、寺社各々のご紹介については順に追加補足していきます。
■薬王山 東善院 (厄よけ魚籃観音)
小田原市早川482
真言宗東寺派 御本尊:薬師如来
・魚籃大観音
※御本尊御朱印の授与は不明

■瑠璃山 真福寺 (早川観音)
小田原市早川892
真言宗東寺派 御本尊:不動明王
札所:小田急武相三十三観音霊場第27番
・聖観世音(小田急武相三十三観音霊場第27番)
※御本尊御朱印はWeb上ではみつかりますが、不授与とのこと

■紀伊神社
小田原市早川1183-1
早川の氏神様
・社号

■佐奈田霊社
小田原市石橋420
石橋山古戦場にある神仏習合の霊社。石橋山の戦いで討死した佐奈田与一義忠を祀る。
・社号

■貴船神社
真鶴町真鶴1117
旧郷社
・社号

●御朱印帳あり

■佛光山 亀宝院 発心寺
真鶴町真鶴638
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:足柄三十三観音霊場第30番
・南無阿弥陀佛(御名号)
※観音様の御朱印は不授与の模様
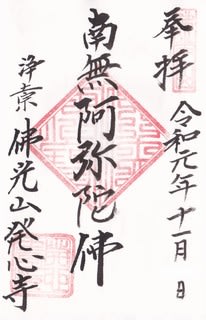
■港上山 来迎院 西念寺
真鶴町真鶴1925
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:足柄三十三観音霊場第29番
・南無阿弥陀佛(御名号)
※観音様の御朱印は不授与の模様

■子之神社
湯河原町福浦129
・社号
※事前連絡要? →公式Web

■千歳山 最上寺
湯河原町吉浜1412
日蓮宗
・御首題

■素鵞神社
湯河原町吉浜1056
・社号
※境内授与所に拝受希望者連絡先案内あり

■萬年山 城願寺
湯河原町城堀252
曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩
・観自在(御本尊)

■五所神社
湯河原町宮下359-1
旧郷社
・社号
※「湯河原七福神」の御朱印もあり

■青谷山 福泉寺
熱海市泉191-1
曹洞宗 御本尊:釈迦如来
・南無佛

■身延山湯河原別院 日蓮宗湯河原教会(椿寺)
熱海市泉232
日蓮宗
・妙法(御朱印)
※御朱印のみ授与か?

■大明王院熱海別院 (熱海身代り不動尊)
熱海市伊豆山836
真言宗醍醐派 御本尊:大日大聖身代り不動明王
・身代り不動尊

・神変大菩薩
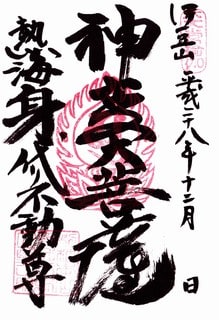
■伊豆山神社
熱海市伊豆山上野地708-1
別表神社 国幣小社
・社号


【写真 上(左)】 以前の御朱印
【写真 下(右)】 現在の御朱印(社号の揮毫なし)
●御朱印帳あり

■走湯山 般若院
熱海市伊豆山371-1
高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第24番
・無量寿殿(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
■日金山 東光寺
熱海市伊豆山968
真言宗
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第23番、駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)番外、駿豆両国横道三十三観音霊場(札番不明)
・日金地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
※参拝後、般若院にて拝受(通常、専用納経帳のみの授与かもしれません。)
■ 渓月山 長光寺
(函南町畑88-1)
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼如来
※御本尊の御朱印は不授与。
・お地蔵様&猫蔵様の絵御朱印

■来宮神社
熱海市西山町43-1
別表神社 旧村社
・社号


【写真 上(左)】 通常の御朱印
【写真 下(右)】 天皇陛下御即位奉祝の御朱印
●御朱印帳あり
■来宮弁財天
熱海市西山町43-1
来宮神社境内社
・社号

■湯前神社
熱海市上宿町4-12
別表神社 式内社論社・旧村社
・社号(来宮神社にて拝受)

■通廣山 大乗寺
熱海市上宿町13-43
日蓮宗
・御首題

■法界山 誓欣院
熱海市上宿町6-3
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
・南無阿弥陀佛(御名号)

■清水山 温泉寺
熱海市上宿町2-19
臨済宗妙心寺派 御本尊: 如意輪観世音菩薩
・如意輪観世音(御本尊)

■錦峰山 海蔵寺
熱海市水口町17-24
臨済宗妙心寺派
・南無十一面観世音菩薩

■護国山 興禅寺
熱海市桜木町5-8
臨済宗妙心寺派 御本尊:十一面観世音菩薩
・本尊 十一面観世音(伊豆八十八ヶ所霊場第25番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
■今宮神社
熱海市桜町3-29
・社号
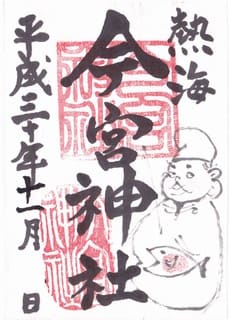
■法雨山 善修院
熱海市網代490-1
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
・本尊 釈迦牟尼佛(御本尊)

■根越山 長谷寺
熱海市網代542
曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩
・本尊 聖観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第26番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印(善修院にて拝受)
●鳳凰山 景徳院
熱海市上多賀948
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
・南無釋迦牟尼佛(御本尊)

□曽我浅間神社
熱海市上多賀1027-8
・社号
※アカオハーブ&ローズガーデン内、入園料要。未参拝/御朱印授与情報あり
-----------------------------------------
伊東温泉編も、リストだけ入れておきます。
■ 伊東温泉周辺の御朱印
【神社】
■葛見神社
伊東市馬場町1-16-40
延喜式内社(小)論社 旧郷社
・社号
■音無神社
伊東市音無町1-12
・社号
■新井神社
伊東市新井2-15-1
・恵比寿神(伊東温泉七福神)
※社号御朱印なし
■神祇大社
伊東市富戸1088-8
・社号
□八幡宮来宮神社
伊東市八幡野1
延喜式内社論社 旧郷社
・社号
※数日前に電話確認のうえ予約/未参拝
□富戸三島神社 (元御島神社)
伊東市富戸686
※未参拝/御朱印授与情報あり
【寺院】
■桃源山 松月院
伊東市湯川337
曹洞宗
・南無釈迦牟尼佛(御本尊)
・弁財尊天(伊東温泉七福神)
■宝珠山 最誓寺
伊東市音無町2-3
曹洞宗
・南無釈迦牟尼佛
・寿老神(伊東温泉七福神)
■海光山 佛現寺
伊東市物見が丘2-30
日蓮宗
・御首題
・毘沙門天王(伊東温泉七福神)
■朝光寺
伊東市岡416-01
日蓮宗
・御首題
・大黒天(伊東温泉七福神)
■水東山 林泉寺
伊東市荻90
曹洞宗
・南無釋迦牟尼佛(御本尊)
■稲荷山 東林寺
伊東市馬場町2-2-19
曹洞宗
・延命地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第27番)
・布袋尊(伊東温泉七福神)
■伊雄山 大江院
伊東市八幡野6-1
曹洞宗
・本尊 十一面観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第28番)
□俎岩山 蓮着寺
伊東市富戸835
法華宗陣門流
※未参拝/御首題授与情報あり
□うさみ観音寺
伊東市宇佐美3496-205
新法華宗
※未参拝/御朱印授与情報あり
※伊東市内には御首題を授与される日蓮宗の寺院が多数ありますが、現時点で全貌がはっきりしていないので、今回、ご紹介は控えます。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】(今井美樹特集!)
ふたりでスプラッシュ
Goodbye Yesterday Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB
このLIVE行った。最高の出来だった。
noctiluca
The Days I Spent With You (flow into space LIVE MIKI IMAI TOUR '93)
Pray/今井美樹
このページ、一年も画像なしで放置しているのにけっこうアクセスをいただいています。
新たに寺社の追加&御朱印画像のみ追加してとりあえず再UPします。
熱海温泉と湯河原温泉は東京方面からのアプローチがかぶるので、ひとつにまとめました。
対象エリアは箱根方面へのアプローチを分けた、国道135号「早川」交差点以南から熱海市内までで、真鶴エリアを含みます。
非札所のご不在気味の寺社も含んでいます。念のため。
なお、たいていの寺社にはPがありますが、見当たらないところもあり、細い路地もあるので車での参拝要注意です。
(それと、休日の来宮神社のPはやたらに混みます。)
■ 湯河原温泉周辺&真鶴の御朱印
湯河原温泉周辺の御朱印スポットとしては五所神社が有名ですが、札所寺院がないこともあって、他にメジャーな授与寺院はみあたりません。
いくつかの寺社で拝受できるものの、ご不在気味の寺社も多く、拝受難易度は比較的高いものとみられます。
真鶴エリアでは貴船神社が有名で、御朱印帳も頒布されています。
寺院では足柄三十三観音霊場の札所がふたつ。この霊場は現在ほぼ完全に活動を停止しているとみられ、霊場会もありません。
札所印つきの御朱印を授与されるお寺さんがある一方、不授与のお寺さんもあってそれぞれ個別の対応となっているようです。
真鶴エリアのふたつの札所についてはWeb情報が見当たりませんでしたが、ご丁寧な対応にて拝受できましたのでご紹介します。
ただし、いずれも御朱印尊格は御本尊で、観音様での授与はありませんでした。
(この霊場はすべて浄土宗寺院で構成され、御本尊御朱印は「阿弥陀如来」ないし六字御名号「南無阿弥陀佛」になるようです。)
■ 熱海温泉周辺の御朱印
熱海市内には寺社が比較的多く鎮座し、温泉地としては効率的に御朱印をいただけるエリアです。
とくに、力感あふれる御朱印&御朱印帳の伊豆山神社、伊豆有数のパワスポとして人気の来宮神社など、御朱印好き(?)には欠かせないメジャーな神社があります。
熱海は観光で寺社巡りする人も多いらしく、熱海市観光協会も公式Webで「熱海御朱印ウォーク」を掲載していることもあってか、札所ではなくても御朱印を授与されるお寺さんが目立ちます。今回はこのような非札所の寺院もご紹介します。
ただし、ご不在の寺社も何軒かあったことをお断りしておきます。(何度目かの参拝で拝受)
熱海は伊東と異なり七福神は設定されていません。
札所としては、近年復興を果たした伊豆八十八ヶ所霊場がメインとなり、熱海市内に4箇寺の札所(第23番~第26番)があります。
ただし、伊豆八十八ヶ所霊場はけっこうマニアックな霊場で、御朱印拝受にもそれなりの作法が要ります。(専用納経帳が必要かどうかよくわからない札所が2ヶ所ある)
これに対して、熱海市観光協会の公式Web「熱海御朱印ウォーク」では、「御朱印をいただく際は、お寺様の仏事が優先ですので、無理のないようにし、第23番~26番札所で頂けなかった場合は熱海市観光協会までご相談ください。」というホスピタリティにあふれた(?)案内がなされています。(本来、自分で何とかすべきことだと思いますが・・・(笑))
なお、ユニークな絵御朱印で有名な函南の渓月山 長光寺も熱海のすぐ上なので併せてご紹介します。
まずは御朱印関連情報&御朱印画像をUPし、寺社各々のご紹介については順に追加補足していきます。
■薬王山 東善院 (厄よけ魚籃観音)
小田原市早川482
真言宗東寺派 御本尊:薬師如来
・魚籃大観音
※御本尊御朱印の授与は不明

■瑠璃山 真福寺 (早川観音)
小田原市早川892
真言宗東寺派 御本尊:不動明王
札所:小田急武相三十三観音霊場第27番
・聖観世音(小田急武相三十三観音霊場第27番)
※御本尊御朱印はWeb上ではみつかりますが、不授与とのこと

■紀伊神社
小田原市早川1183-1
早川の氏神様
・社号

■佐奈田霊社
小田原市石橋420
石橋山古戦場にある神仏習合の霊社。石橋山の戦いで討死した佐奈田与一義忠を祀る。
・社号

■貴船神社
真鶴町真鶴1117
旧郷社
・社号

●御朱印帳あり

■佛光山 亀宝院 発心寺
真鶴町真鶴638
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:足柄三十三観音霊場第30番
・南無阿弥陀佛(御名号)
※観音様の御朱印は不授与の模様
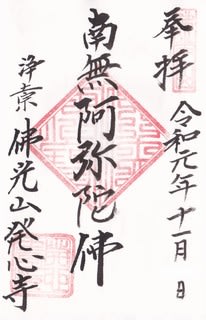
■港上山 来迎院 西念寺
真鶴町真鶴1925
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:足柄三十三観音霊場第29番
・南無阿弥陀佛(御名号)
※観音様の御朱印は不授与の模様

■子之神社
湯河原町福浦129
・社号
※事前連絡要? →公式Web

■千歳山 最上寺
湯河原町吉浜1412
日蓮宗
・御首題

■素鵞神社
湯河原町吉浜1056
・社号
※境内授与所に拝受希望者連絡先案内あり

■萬年山 城願寺
湯河原町城堀252
曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩
・観自在(御本尊)

■五所神社
湯河原町宮下359-1
旧郷社
・社号
※「湯河原七福神」の御朱印もあり

■青谷山 福泉寺
熱海市泉191-1
曹洞宗 御本尊:釈迦如来
・南無佛

■身延山湯河原別院 日蓮宗湯河原教会(椿寺)
熱海市泉232
日蓮宗
・妙法(御朱印)
※御朱印のみ授与か?

■大明王院熱海別院 (熱海身代り不動尊)
熱海市伊豆山836
真言宗醍醐派 御本尊:大日大聖身代り不動明王
・身代り不動尊

・神変大菩薩
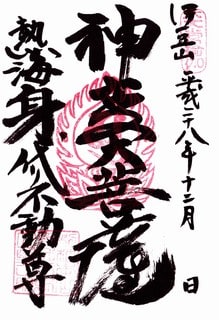
■伊豆山神社
熱海市伊豆山上野地708-1
別表神社 国幣小社
・社号


【写真 上(左)】 以前の御朱印
【写真 下(右)】 現在の御朱印(社号の揮毫なし)
●御朱印帳あり

■走湯山 般若院
熱海市伊豆山371-1
高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第24番
・無量寿殿(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
■日金山 東光寺
熱海市伊豆山968
真言宗
札所:伊豆八十八ヶ所霊場第23番、駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)番外、駿豆両国横道三十三観音霊場(札番不明)
・日金地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
※参拝後、般若院にて拝受(通常、専用納経帳のみの授与かもしれません。)
■ 渓月山 長光寺
(函南町畑88-1)
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼如来
※御本尊の御朱印は不授与。
・お地蔵様&猫蔵様の絵御朱印

■来宮神社
熱海市西山町43-1
別表神社 旧村社
・社号


【写真 上(左)】 通常の御朱印
【写真 下(右)】 天皇陛下御即位奉祝の御朱印
●御朱印帳あり
■来宮弁財天
熱海市西山町43-1
来宮神社境内社
・社号

■湯前神社
熱海市上宿町4-12
別表神社 式内社論社・旧村社
・社号(来宮神社にて拝受)

■通廣山 大乗寺
熱海市上宿町13-43
日蓮宗
・御首題

■法界山 誓欣院
熱海市上宿町6-3
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
・南無阿弥陀佛(御名号)

■清水山 温泉寺
熱海市上宿町2-19
臨済宗妙心寺派 御本尊: 如意輪観世音菩薩
・如意輪観世音(御本尊)

■錦峰山 海蔵寺
熱海市水口町17-24
臨済宗妙心寺派
・南無十一面観世音菩薩

■護国山 興禅寺
熱海市桜木町5-8
臨済宗妙心寺派 御本尊:十一面観世音菩薩
・本尊 十一面観世音(伊豆八十八ヶ所霊場第25番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印
■今宮神社
熱海市桜町3-29
・社号
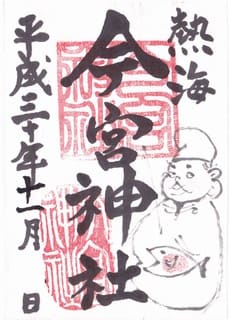
■法雨山 善修院
熱海市網代490-1
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
・本尊 釈迦牟尼佛(御本尊)

■根越山 長谷寺
熱海市網代542
曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩
・本尊 聖観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第26番)


【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印(善修院にて拝受)
●鳳凰山 景徳院
熱海市上多賀948
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛
・南無釋迦牟尼佛(御本尊)

□曽我浅間神社
熱海市上多賀1027-8
・社号
※アカオハーブ&ローズガーデン内、入園料要。未参拝/御朱印授与情報あり
-----------------------------------------
伊東温泉編も、リストだけ入れておきます。
■ 伊東温泉周辺の御朱印
【神社】
■葛見神社
伊東市馬場町1-16-40
延喜式内社(小)論社 旧郷社
・社号
■音無神社
伊東市音無町1-12
・社号
■新井神社
伊東市新井2-15-1
・恵比寿神(伊東温泉七福神)
※社号御朱印なし
■神祇大社
伊東市富戸1088-8
・社号
□八幡宮来宮神社
伊東市八幡野1
延喜式内社論社 旧郷社
・社号
※数日前に電話確認のうえ予約/未参拝
□富戸三島神社 (元御島神社)
伊東市富戸686
※未参拝/御朱印授与情報あり
【寺院】
■桃源山 松月院
伊東市湯川337
曹洞宗
・南無釈迦牟尼佛(御本尊)
・弁財尊天(伊東温泉七福神)
■宝珠山 最誓寺
伊東市音無町2-3
曹洞宗
・南無釈迦牟尼佛
・寿老神(伊東温泉七福神)
■海光山 佛現寺
伊東市物見が丘2-30
日蓮宗
・御首題
・毘沙門天王(伊東温泉七福神)
■朝光寺
伊東市岡416-01
日蓮宗
・御首題
・大黒天(伊東温泉七福神)
■水東山 林泉寺
伊東市荻90
曹洞宗
・南無釋迦牟尼佛(御本尊)
■稲荷山 東林寺
伊東市馬場町2-2-19
曹洞宗
・延命地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第27番)
・布袋尊(伊東温泉七福神)
■伊雄山 大江院
伊東市八幡野6-1
曹洞宗
・本尊 十一面観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第28番)
□俎岩山 蓮着寺
伊東市富戸835
法華宗陣門流
※未参拝/御首題授与情報あり
□うさみ観音寺
伊東市宇佐美3496-205
新法華宗
※未参拝/御朱印授与情報あり
※伊東市内には御首題を授与される日蓮宗の寺院が多数ありますが、現時点で全貌がはっきりしていないので、今回、ご紹介は控えます。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】(今井美樹特集!)
ふたりでスプラッシュ
Goodbye Yesterday Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB
このLIVE行った。最高の出来だった。
noctiluca
The Days I Spent With You (flow into space LIVE MIKI IMAI TOUR '93)
Pray/今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2021/0130・2019/08/31 補足UP
先にUPした「草津温泉周辺の御朱印」「四万温泉周辺の御朱印」の温泉&御朱印記事が予想外にアクセスをいただいているので、伊香保温泉版もつくってみました。
第1回目(草津温泉編)は、→こちら
第2回目(四万温泉編)は、→こちら
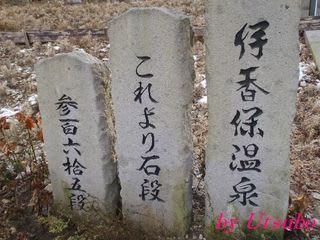

■ 伊香保温泉周辺の御朱印
伊香保温泉(→〔 温泉地巡り 〕)は平地に近く、関東有数の名刹、水澤観音とのゆかりも深く、行き帰りに寺社(御朱印)巡りしやすい温泉地です。
また、榛名山中には最近パワスポとしてとみに人気が高まっている榛名神社も鎮座し、伊香保温泉&榛名神社でツアーを組む向きも多いのでは?
今回は伊香保温泉の東京寄りの玄関口である関越道前橋ICから利根川右岸の渋川市域、そして榛名山周辺で御朱印を拝受できる寺社をご案内します。
帰路は榛名神社経由になることを想定し、国道406号の室田~並榎IC(国道17号との交差IC)沿いの寺社もご紹介します。
なお、一般に広く御朱印を授与されていないと思われる寺社については、今回もご紹介は割愛します。
群馬県央、前橋、高崎はいずれも城下町で寺社が多く、御朱印を授与される寺社も少なくないですが、両市中心部は利根川左岸にあたるので今回は対象外とします。
利根川右岸に限っても相当数の寺社があり、坂東三十三箇所(観音霊場)、東国花の寺百ヶ寺霊場、県内ではメジャーな新上州三十三観音霊場、上州七福神などの札所が点在します。
複数の現役霊場札所を兼ねるメジャーな寺院も多く、御朱印拝受のハードルは比較的低いエリアといえましょう。
宗派的には天台宗が多いエリアとなっています。
(1泊では制覇は無理です。燃えた方は(笑)、何回か泊まってあげてください。ちなみに伊香保は風情も泉質もよく、おすすめの温泉地です。)
メジャーな札所やパワスポが多いので記事ネタには事欠きません。
ボリュームが出たので、4編の構成となりました。
リストはつぎのとおりです。
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
1.青雲山 実相院 大福寺 (前橋市鳥羽町)
2.(中尾)飯玉神社 (高崎市中尾町)
3.鷲霊山 釈迦尊寺 (前橋市元総社町)
4.(上野国)総社神社 (前橋市元総社町)
5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺 (前橋市元総社町)
6.三鈷山 吉祥院 妙見寺 (高崎市引間町)
7.秋元山 江月院 光巌寺 (前橋市総社町)
8.氣雲山 春光院 元景寺 (前橋市総社町)
9.東向八幡宮 (高崎市箕郷町)
10.金富山 実相院 長純寺 (高崎市箕郷町)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)
12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)
13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)
14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)
15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)
16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)
17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
19.船尾山 等覚院 柳澤寺 (榛東村山子田)
20.五徳山 無量寿院 水澤寺 (渋川市伊香保町水沢)
21.伊香保神社 (渋川市伊香保町伊香保)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
22.榛名神社 (高崎市榛名山町)
23.大森神社 (高崎市下室田町)
24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)
25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)
26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)
27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)
29.白山神社 (高崎市白岩町)
30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)
31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)
32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)
33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)
34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)
35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)
36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)
37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)
38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)
39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)
40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)
41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)
42.菅原社 (高崎市金古町)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
43.如意山 宝蔵院 大乗寺 (高崎市棟高町)
44.烏子稲荷神社 (高崎市上小塙町)
45.新比叡山 本実成院 天竜護国寺(高崎市上並榎町)
46.我峰八幡神社 (高崎市我峰町)
47.上野國一社八幡宮 (高崎市八幡町)
48.神通山 遍照王院 大聖護国寺 (高崎市八幡町)
49.慈雲山 養寿院 福泉寺 (高崎市鼻高町)
50.少林山 達磨寺 (高崎市鼻高町)
【伊香保温泉周辺で拝受できる御朱印】
1.青雲山 実相院 大福寺
前橋市鳥羽町717
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東百八地蔵尊霊場第24番
札所本尊:地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第24番)

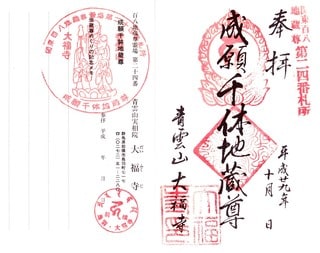
〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕
見開きの霊場規定用紙での授与となります。
中央に札所本尊、地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印、そして「成願千体地蔵尊」の揮毫。
右上に「関東百八地蔵尊第二十四番札所」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には寺院の情報と記念スタンプが捺されています。
まずは関越道前橋ICそばの寺院からご紹介します。
前橋ICから500mと離れていない至近に立地するこのお寺は、室町時代初期の応永元年(1394年)に総本山延暦寺の直末寺院として開山されたと伝わります。
「当時七堂伽藍壮麗にして、本堂間口二十間・奥行十八間、境内に不動堂、大師堂、薬師堂等を有し、仏教弘宣の大道場として近郷の尊崇をあつめた」(寺伝より)という大寺で、紆余曲折の歴史を辿りながらも法灯を絶やすことなく今に至ります。
比較的新しい伽藍につき、さびた風情はないものの、明るく開放的な雰囲気です。
関東百八地蔵尊霊場第24番の札所で、札所本尊である成願千体地蔵尊は昭和63年にご住職の発願によって建立され、「一願一体の『願掛け地蔵尊』」とも呼ばれて信仰を集めているそうです。
関東百八地蔵尊霊場は、かつて仙台市に存在した「佛教文化振興会」という組織がとりまとめたとみられる霊場で、現況、霊場会もとりまとめ役もいないなか、比較的御朱印授与率の高い霊場です。
霊場開創時に霊場(札所)印が整備されたらしく、札所印もいただきやすくなっています。
また、霊場開創時に専用納経帳も整備されたらしく、大判の専用納経帳用の書置御朱印が授与される場合があります。
とはいえ、汎用御朱印帳に授与いただける札所も少なくなく、札所(御朱印)対応は多種多様です。
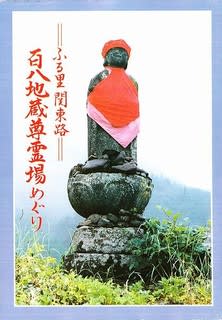
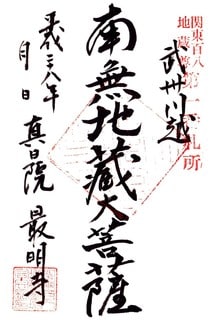
【写真 上(左)】 霊場の巡礼ガイド(平成2年1月、佛教文化振興会刊)
【写真 下(右)】 発願寺(初番)「瑶光山 真日院 最明寺」(川越市)の札所御朱印(現在、この御朱印は非授与のようです)
札所には相当数の名刹も入っていますが、納経所の御朱印見本で掲示される例はほとんどなく、こちらからお伺いしてはじめて授与いただける「裏メニュー」的なケースが多くなっています。
また、札所本尊のお地蔵様の御座所がわかりにくく(本堂でない場合が多い)、霊場ガイドを持っていない場合は、お寺さんに確認する必要があります。
そんなこんなで、かなりマニアックな霊場であることは間違いないかと・・・。
なお、札所本尊のお地蔵様は御本尊でないケースが多く、別に御本尊の御朱印をいただける場合とそうでない場合があります。
こちらのお寺様は地蔵霊場のみの授与とのことでした。
2.(中尾)飯玉神社
高崎市中尾町347
主祭神:宇気母智神(飯玉さま) 配祀:菅原道真公(天神さま)、建御名方神、須佐之男命、美留目之神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進社、中尾総鎮守


〔 御朱印 〕
中央に「飯玉神社」の神社印と揮毫。右下には「中尾総鎮守」の陰刻印が捺されています。
温泉好きのあいだでは有名な、高崎中尾温泉「天神の湯」のすぐ隣にある神社です。
じつに「延暦三年(784年)に勧請せり」と伝わる(公式Webより)古い由緒をもち、千葉上総介常重、足利幕府の管領上杉氏、高崎城主酒井左衛門尉など、歴代のこの地の支配者との関係も伝わっているようです。
明治後期に村内の菅原神社、諏訪神社を合祀し、神饌幣帛料を供進すべき指定神社になったといいます。
主祭神は、宇気母智神(うけもちのかみ)。配祀神は菅原道真公、建御名方神、須佐之男命、美留目之神です。
公式Webによると、「飯玉神社の主祭神である宇気母智神は、『食物の神様』であり、保食神とも記され、五穀を司る神と言われています。」
保食神(うけもちのかみ)は稲荷神社の祭神となられる場合がありますが、上武(上野國・武蔵國)一円では、稲荷神社(祭神 倉稲魂命(宇迦御魂命)と飯玉神社(祭神 保食神(宇気母智命)は明確に区別されているという説もあるようです。
また、豊受比売命が飯玉神社の祭神となられている例もありますが、豊受比売命も食物と関わりの強い神様ですから、飯玉神社と食物は切り離せない関係なのかもしれません。
境内に数台の駐車スペースがあります。
鳥居・参道から階段を昇って拝殿。小規模ながら風格のある拝殿です。
ご朱印は境内で書置きのものを拝受しました。
3.鷲霊山 釈迦尊寺
公式Web
前橋市元総社町2502−2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛

〔 御本尊の御朱印 〕
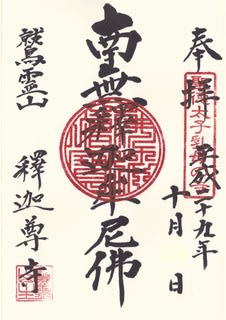
中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。右上には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
禅寺らしい端正な御朱印です。
〔 大黒天の御朱印 〕
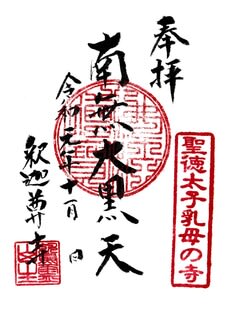
大黒天の御朱印も授与されています。
中央に三寶印と「南無大黒天」の揮毫。右には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
すこぶる古い来歴をもつ上州の名刹。
寺歴については、公式Webで詳細に説明されていますが、概略を抜粋引用しつつご紹介します。
三十一代用明天皇二年(587年)、蘇我馬子が物部守屋を滅ぼしたとき物部氏に加担した中臣羽鳥連と妻、玉照姫は上毛野国青海に流罪となりました。
玉照姫は聖徳太子の乳母で、太子の守仏、闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏を太子より授けられました。
天武天皇十五年(686年)、勅令による大赦で羽鳥連の孫青海羊太夫が上洛して勅赦を受けた際、定慧和尚が玉照姫の敬信した釈迦尊仏の由来を尊信し、翌年(687年)上野国蒼海に御下りになり七堂伽藍を建立、釈迦尊仏を安置され釈迦尊寺と号されました。
開基は青海羊太夫、開山は多武峯定慧和尚とされています。
当初は法相宗に属したとされますが、のち(文永年間(1264~1274年))に臨済宗門、鎌倉建長寺より蘭渓和尚が入られて再興。永禄元年(1558年)永源寺より芳伝和尚が入られ曹洞宗となり現在に至るようです。
江戸期には寛永三年四月、幕府より三百六十石余の御朱印寺とされています。
御本尊の闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏は平安時代末のものと推定され、秘仏となっています。
すこしく横道に逸れます。
古代、東国を代表する政治勢力として「毛野(けの/けぬ)」と「那須」があり、毛野は「上毛野(かみつけの/かみつけぬ)」「下毛野(しもつけの/しもつけぬ)」に二分されたといわれます。
このうち上毛野は上野國(上州)をさし、令制国の一つに定められたとされます。
令制国制のもとでは、令制国諸国は国力により四等級に分けられましたが、延喜式では上野國は最上の「大国」に充てられ、しかも、全国で3国しかない親王任国のひとつでした。
親王任国(常陸國、上総國、上野國)は、親王が国守に任じられる「大国」で、親王任国の筆頭官である親王は太守と称されました。(上野國の初代太守は桓武天皇の皇子葛井親王とされる。)
親王太守は現地へ赴任しない遙任のため、現地の実質的な国守は次官の介(すけ)となります。
なので原則、武士階級に「上野守」はおらず、「上野介」となります。(本多正純も、吉良義央も、小栗忠順もすべて「上野介」です。)
話が大逸れしましたが(笑)、何がいいたかったかというと、上野國は上代から東国で最も栄えた地域であり、西国との結びつきも強かったのでは、ということです。
そう考えると、聖徳太子の乳母・玉照姫にまつわる伝承もうなづけるものがあります。
また、仏教は欽明天皇の御代にわが国に伝わったとされますが(仏教公伝)、その際に積極的に仏教を迎え入れたのが崇仏派、仏教排斥に回ったのが排仏派で、崇仏派の代表格が蘇我氏、排仏派の代表格が物部氏とされます。
厩戸皇子(聖徳太子)は崇仏派で、玉照姫の夫羽鳥連は排仏派の物部氏に加担したとされていますから、聖徳太子の乳母・玉照姫の立ち位置は微妙なものであったのかもしれません。
そんなことをつらつらと想い起こさせてくれる、歴史をもったお寺さんです。
上代開基の寺院を物語るような、広々と明るい境内です。
札所ではありませんが、このような悠久の歴史をもつ古刹なのでご紹介しました。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。
いただいたのは御本尊の御朱印ですが、Webでは大黒天の御朱印もみつかるので、こちらも授与いただけるかもしれません。
4.(上野国)総社神社
公式Web
前橋市元総社町1-31-45
主祭神:磐筒男命、磐筒女命、経津主命、宇迦御魂命、須佐之男命
上野國総社 旧社格:県社

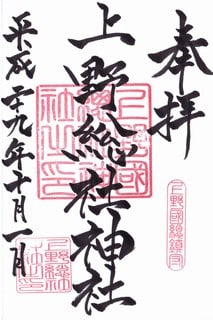
〔 御朱印 〕
中央に社名印の捺印と「上野総社神社」の揮毫。右に「上野國總鎮守」の印判。
左下に社名印が捺されています。
なお、最近の日付の御朱印では、主印として神紋印が捺されているようです。
諸説あるようですが、総社(惣社)とは、一般的には特定地域内の神社の祭神を集めて合祀した神社をさすとされます。
もともとは、律令制のもとで着任した国司は令制国内の一定の神社を早々に巡拝することが義務づけられていたが、国府の近くに総社を設け、そこに詣でることで巡拝を省く趣旨で置かれたという説があります。
また、地域内の神社を合祀した神社を称する例もあり、旧社格は、官幣小社から村社(ないし無格社)までと多岐にわたっています。
なお、全国総社会が組織され、専用御朱印帳も頒布されています。
総社神社公式Webには「上野総社神社は上野の総鎮守なり、上野総社 神社は国内総神社の神集ひ座す御神地なり、上野総社神社を参拝するは県内各神社を参拝するにひとし。」とあり、国司巡拝型の総社であったことがうかがわれます。
また同Webでは「崇神天皇の四十八年三月皇子豊城入彦命は東国平定の命を奉じ、上野にお下りになられるや、神代の時代に国土の平定に貢献された経津主命の御武勇を敬慕され、軍神としてその御神霊を奉祀して御武運の長久を祈られ、また、経津主命の親神(ご両親)である磐筒女命の御二方をも合祀せられた。これが当社の始まりである。」という創祀由緒、そして、「国司は国内各地の神社に幣束を捧げ、親しく巡拝していたが、人皇第五十六代清和天皇のころ国司は上野国内各社の神明帳を作り、国内十四郡に鎮座する総五百四十九社を勧請合祀」という合祀由緒も紹介されています。
大国、上野國の総社だけに、さすがに厳かな境内です。
御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れをいただきました。
5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺
前橋市元総社町1-31-38
天台宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:群馬郡三十三観音霊場第24番
札所本尊:千手千眼大悲観音(群馬郡三十三観音霊場第24番)

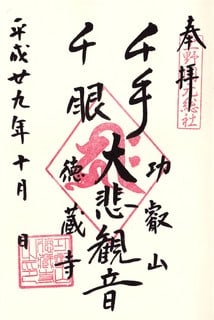
〔 御朱印 〕
群馬郡三十三観音霊場第24番の札所本尊と思われる千手千眼大悲観音の御朱印です。
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印と「千手千眼大悲観音」の揮毫。
右上には「上野国元総社」の印判。
尊格の左右に山号・寺号の揮毫と、左下には寺院印が捺されています。
室町時代の文明三年(1471年)足利八代将軍義政公の祈祷所として建立、往時には寺中七ケ院、末門十七ケ寺を擁して幕府から朱印十六石を下賜され、檀徒三百有余戸を有したとされる古刹。(寺伝より)
室町時代の製作と考えられる三面の懸仏(弥勒菩薩、薬師如来、観世音菩薩)が残されていることからも、古刹の歴史が裏付けられます。
江戸時代初期の慶長十二年(1607年)、惣社(総社)領主の秋元越中守が惣社城築城の際に一寺の建立を計りましたが、当時は新寺院の建立を幕府が禁じていたため、天海僧正の内意により、本地および寺中数箇寺を北側利根川沿いの惣社城周辺に移して光厳寺と号しました。
爾来、この地に本寺格の寺院はなくなりましたが、明治五年(1872年)、檀徒が旧徳蔵寺の再建を官に願い出て、また光厳寺とも折衝して独立し、然海法印を住職として再建がなったものと伝わります。
総社神社と隣り合う、いかにも別当寺的な立地で、総社神社の別当だったという説があります。
上記の歴史を考えると江戸時代を通して大社、総社神社の別当を勤めるのはむずかしかった感じもしますが、少なくとも光厳寺への移転前は勤められていた可能性はあるかもしれません。
こちらは群馬郡三十三観音霊場第24番の札所です。
群馬郡三十三観音霊場は、現在の渋川市、前橋市、高崎市、榛東村、利根川右岸に広がる古い霊場で、今回ご紹介するエリアとかぶります。
発願寺は宇輪寺(榛東村)、結願寺は布留山 石上寺(高碕市)で、小規模な観音堂を含み、現在は活動を完全に停止しています。
先日、発願寺の宇輪寺にも参拝しましたが無住でした。
ただし、札所の遺伝子が残っているのか、御朱印をいただけるお寺さんがいくつかあります。こちらもそのひとつです。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。
6.三鈷山 吉祥院 妙見寺
高崎市引間町213
天台宗
御本尊:釈迦如来、妙見菩薩
札所:群馬郡三十三観音霊場第23番

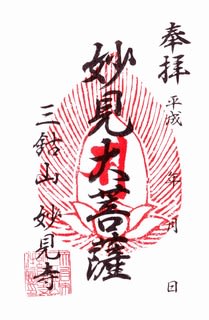
〔 御本尊の御朱印 〕
中央に御本尊、妙見菩薩の種子「ソ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「妙見大菩薩」の揮毫。
左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
創建は和銅七年(714年)、ないし霊亀元年(715年)と伝わる天台宗の古刹で、上野国国司・藤原忠明の開基とされています。
寺伝によると、延暦七年(797年)成立の「続日本紀」に妙見寺に関する記載があり、古くは「七星山息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰されてきたそうです。
境内の妙見社は日本三妙見のひとつとして知られ、この地方の妙見信仰の中心をなしていたという説があります。(→ 高崎市Web )
また、妙見寺は妙見社の元別当寺であったという見方もあるようです。
妙見信仰とは、中国の星宿思想から北極星を神格化ないし、菩薩として信仰するものとされます。(北斗七星との関連を指摘する説もあり。)
仏教においては妙見菩薩、神道においては天之御中主神が主な信仰の対象になります。
東日本の妙見信仰というと、まず坂東八平氏(平良文を祖として下総国、上総国、武蔵国、相模国などを領地とした、千葉・上総・三浦・土肥・秩父・大庭・梶原・長尾氏など)、ことに千葉氏が思い浮かびますが、どうして千葉から遠くはなれた群馬のこの地の妙見社が「日本三妙見」として崇められているのか、不思議な感じもします。
これについては、興味深い伝承が存在します。
平安時代の中ごろ、上野国花園村付近で、平氏(将門公、良文公・国香公)が相争う「染谷川の戦い」がありました。
この戦いの勝敗の鍵を握られたのが、この付近に鎮座されていた花園妙見(一説に羊妙見)とされ、平良文公を祖とする坂東八平氏は、これより妙見信仰の家系となったと伝わります。
千葉氏が信仰する千葉神社、秩父氏が信仰する秩父神社では、花園妙見との関連を示す資料がWeb上でもいくつかみつかります。(ex.『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)
とくに秩父神社については、「花園村から妙見社を勧請」と明記している資料があります。
妙見寺の妙見様と花園妙見が同一という決定的な史料は見当たらないようですが、深い関係にあったであろうことは想像されます。
榛名東麓には千葉氏ゆかりの伝承がいくつか残り、「19.船尾山 等覚院 柳澤寺」の縁起にも千葉氏が登場します。
なお、上記の『榛名山東南麓の千葉氏伝承』には、船尾山柳澤寺とのつながりが指摘される「独鈷山妙見院息災寺」について、「現在、高崎市引間町に『三鈷山吉祥院妙見寺』という寺院があり、これが『息災寺』の後身だと言われている。さらに、千葉氏の守護神である妙見大菩薩はこの寺から勧請されたとされている。」と述べられ、妙見寺は柳澤寺と息災寺を介してなんらかのつながりを有していたかもしれません。
妙見菩薩は「菩薩」を名乗られていますが、一般には天部に属するとされ、すこぶる複雑な尊格のようです。
また、天之御中主神も造化三神というすこぶる格の高い神格でありながら、ナゾの多い神様とされています。
星宿思想が絡む尊格は、複数の信仰が習合・混交していることもあって、複雑な性格をもたれるものが多く、生半可な知識では到底語れませんので、このくらいにしておきます。
なお、妙見菩薩を祀られる寺院は日蓮宗と天台宗で目立ち、こちらも天台宗寺院です。
御朱印は庫裡にて書置きのものを拝受しました。
7.秋元山 江月院 光巌寺
前橋市総社町総社1607
天台宗
御本尊:釋迦牟尼如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第22番、前橋四公御朱印巡り
札所本尊:釋迦牟尼如来(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕
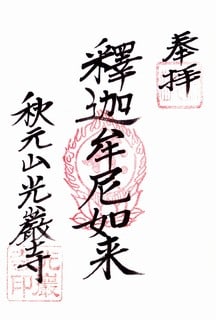
〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕
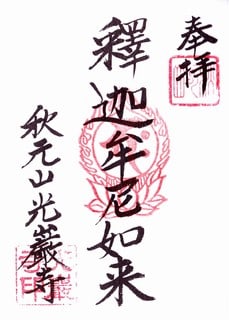
中央に御本尊、釋迦牟尼如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「釋迦牟尼如来」の揮毫。
左下には山号・寺号の揮毫と寺院印、右上には山号印が捺されています。
御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。
釈迦(如来)の御朱印は釈迦如来ないし(南無)釈迦牟尼佛での授与例が多く、釈迦如来は密教系、(南無)釈迦牟尼佛は禅宗系での授与が多くなっています。
この御朱印は複合形の「釈迦牟尼如来」で、数は多くないもののこの授与例もみられます。
なお、釈尊は仏教の開祖としての釈迦(ゴータマ・シッダルタ)、諸仏としての釈迦如来、本仏釈尊(久遠実成本仏)など、多様な性格、あるいはその存在を巡る解釈論(本仏論など)をもち、一言では語れない複雑な尊格です。
慶長六年(1601年)総社藩初代藩主の秋元長朝が徳蔵寺の亮應を招いて創建(開山)、以後秋元家の菩提寺としてつづく名刹。
秋元氏は名族宇都宮氏の流れとされ、戦国期の当主、長朝は関ヶ原の戦いの功績により慶長年間に一万石で総社藩に入り、利根川の右岸に総社城を築きました。
藩内の町割りを進めるなど名君の誉れが高かったと伝わりますが、二代泰朝の代に甲斐・谷村藩一万八千石に加増されて転封し、総社藩は廃藩となっています。
前橋市資料などによると、秋元氏は谷村藩に移封となったものの、光厳寺はこの地に留まり歴代秋元家の菩提を弔っているとの由。
また、慶安二年(1649年)には三代将軍家光公より16石の加増を受けて計46石。
この地域の天台宗の修業寺として寺運が隆盛したと伝わります。
境内は名家の菩提寺らしい落ち着いた空気に包まれています。
古い伽藍が多く残り、なかでも、薬医門は江戸時代初期に総社城の城門として建てられ、廃城になった際に移築したと推定される貴重な建物で、前橋市指定重要文化財に指定されています。
御朱印は庫裡にて拝受できます。
こちらは「前橋四公御朱印巡り」の一寺です。
「前橋四公御朱印巡り」は霊場とはいえないと思いますが、現在の前橋市域内で藩主を務めた酒井雅楽頭家、松平大和守家、秋元越中守家、牧野駿河守家ゆかりの6つの寺社を巡るイベントで、平成28年秋にはじまり毎秋開催、昨年平成30年秋で3回目となります。(平成30年は9/29~10/6の開催)
期間中、専用御朱印帳が配布され、これに捺印をいただく形で御朱印が授与されています。


【写真 上(左)】 四公祭ののぼり(光巌寺)
【写真 下(右)】 四公祭の専用御朱印帳
「前橋四公御朱印巡り」のほとんどの寺社は通常ご朱印も授与されていますが、専用御朱印帳とは尊格が異なるところもあり、御朱印収集的には貴重なイベントです。
前橋(厩橋)藩は、譜代(酒井雅楽頭家)、御家門(越前松平家)がおおむね十五万石の石高をもって封じられた上州屈指の大藩で、ゆかりの寺院の格式も高くなっています。
8.氣雲山 春光院 元景寺
前橋市総社町植野150
曹洞宗
御本尊:釋迦牟尼佛
札所:前橋四公御朱印巡り
札所本尊:釋迦牟尼佛(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕

〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕
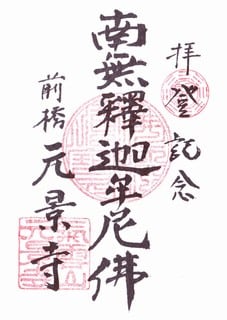
中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。
左下には寺号の揮毫と寺院印、右上に「拝登記念」の揮毫と寺号印?が捺されています。
御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。
「拝登(記念)」は、山岳信仰系の神社の御朱印でときおり見られますが(とくに富士塚のお山開きの御朱印に多い)、平地の寺院の御朱印ではめずらしいと思います。
利根川右岸にもほど近い、植野の地に構えるこちらも秋元氏ゆかりの名刹。
寺伝によると、開基は初代総社藩主秋元長朝で、父景朝の菩提を弔うため景朝の法名である「春光院殿気山元景大居士」から山号・院号・寺号が名づけられたとの由。
天正十五年(1587年)開創、天正十八年(1590年)に本堂が建立され、御本尊釈迦牟尼佛、脇侍文殊菩薩・普賢菩薩が安置されたと伝わります。
伽藍は、本堂・山門・鐘楼・庫裡・書院・位牌堂などからなります。
境内には、名君と伝わる総社藩初代藩主、秋元長朝の治世を物語る天狗岩伝説にまつわる羽階権現(はがいごんげん)が祀られ、長朝の功績を称える「力田遺愛碑」も建立されています。
このお寺には淀君にまつわる哀しい伝承と、淀君の墓と伝えられるものが残されています。
淀君は大阪夏の陣で秀頼と共に自害したとされますが、落ち延び説もあり、その落ち延び先として薩摩国と上野国厩橋の二つの説があるようです。
その上野国厩橋説にかかわるお寺ということでしょうか。
なお、境内掲出の寺伝には、「敷島公園内のお艶観音」との関係を示唆する内容が書かれています。
秋元家の墓のそばに、淀君の墓と伝えられるものが残されています。
戒名は、女性としては最高位の院殿・大姉号で、相当の高貴な身分の女性の墓所であることは間違いないとされています。(公式Webでは「伝・淀君(おえん)の墓」と表記されています。)
また、淀君所有とされる「正絹の大打掛」と「籠の引き戸」も伝えられているようです。
こちらも前橋四公御朱印巡りの一寺で、期間内は専用御朱印帳に授与いただけます。
御朱印は庫裡にて拝受、御朱印帳に書入れいただきました。
9.東向八幡宮
高崎市箕郷町西明屋4
主祭神:品陀和気命
旧社格:村社、箕輪城総鎮守

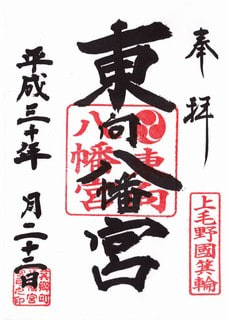
〔 御朱印 〕
中央に社名印の捺印と「東向八幡宮」の揮毫。右に「上毛野國箕輪」の印判。
左下には宮司印が捺されています。
旧箕郷町は平成18年に高崎市と合併し高崎市となりましたが、固有の歴史・文化を育んできたエリアです。
箕郷は上州の名族長野氏(皇別氏族、在原氏(在原業平)の流れで上野國守護代の家格であったとされる)の本拠地で、ことに箕郷城は名将の誉れ高い長野業正が拠った城として知られています。(箕郷城は「日本百名城」のひとつ。)
関東管領・山内上杉家に属した長野氏は、しばしば後北条氏の侵攻を受けましたが、業正は能く戦って譲らず領地を守りました。
また、武田信玄は信州経由で上州に侵攻し、箕郷城はその攻防の地となりましたが、やはり業正はこの領地を譲りませんでした。
しかし、業正亡きあとついに武田方の手に落ち、この地は武田方の上州経営の拠点として甘利昌忠、真田幸隆、浅利信種、内藤昌豊など錚々たる武田方の武将が城代として入りました。
武田氏滅亡後、滝川一益の統治下に入りましたが、本能寺の変により後北条氏の領地に、後北条氏没落後は12万石をもって井伊直政が入り箕郷藩を立藩したものの、慶長三年(1598年)高崎城に移封され箕輪藩は廃藩、城は廃城となりました。
このように箕輪城は「戦国時代の縮図」といわれるほどの歴史を刻みましたが、この箕輪城の総鎮守と伝わるのが東向八幡宮です。
室町時代中期の文明六年(1474年)、箕輪初代城主長野尚業が山城の石清水八幡宮より分霊勧請して創祀、箕輪城の総鎮守と成したと伝わります。
また、江戸期には阿房国勝山藩主酒井安芸守の飛地領地で、その病の平癒に霊験あらたかであったという伝承もあるようです。
境内はこぢんまりとしていますが、市指定重要文化財の「東向八幡宮の石幢」があります。珍しい十三仏の石幢で、神仏習合の歴史を物語るものかと。
御朱印は境内の社務所で、御朱印帳に書入れいただきました。
10.金富山 実相院 長純寺
高崎市箕郷町富岡852
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛

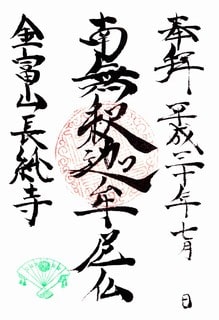
〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「南無釈迦牟尼仏」の揮毫。
左には山号、寺号の揮毫。通常、寺院印が捺される位置には長野氏の家紋「檜扇」紋が捺されています。
この地の名族、長野氏代々の菩提寺として伝わる曹洞宗の名刹。
高崎市資料によると、箕輪城主長野信業が明応六年(1497年)に箕郷町上芝に創建し、弘治三年(1557年)長野業政が現在地に移したと伝わります。
開山堂には市の指定重要文化財「長野業政公の像」が安置されています。
参道入口の閻魔大王や奪衣婆などの石仏はインパクトがあります。
閻魔大王は天台宗や浄土宗などの寺院にはよくおられますが、曹洞宗寺院では比較的めずらしいような感じもします。
御朱印は、2度目の参拝でご住職不在だったため郵送をお願いし拝受しました。
こちらはご不在がちの感じもありますが、名刹で「日本百名城」城主の菩提寺でもあるのでご紹介しました。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ サクラ色 (アンジェラ・アキ) - 熊田このは
■ ずっと二人で - BENI
■ 家に帰ろう ~マイ・スイート・ホーム~ - 竹内まりや feat. 山下達郎
また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。
以上、ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2021/0130・2019/08/31 補足UP
先にUPした「草津温泉周辺の御朱印」「四万温泉周辺の御朱印」の温泉&御朱印記事が予想外にアクセスをいただいているので、伊香保温泉版もつくってみました。
第1回目(草津温泉編)は、→こちら
第2回目(四万温泉編)は、→こちら
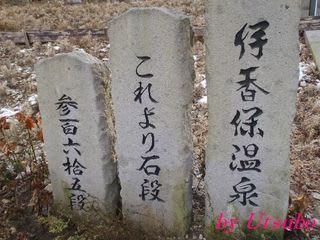

■ 伊香保温泉周辺の御朱印
伊香保温泉(→〔 温泉地巡り 〕)は平地に近く、関東有数の名刹、水澤観音とのゆかりも深く、行き帰りに寺社(御朱印)巡りしやすい温泉地です。
また、榛名山中には最近パワスポとしてとみに人気が高まっている榛名神社も鎮座し、伊香保温泉&榛名神社でツアーを組む向きも多いのでは?
今回は伊香保温泉の東京寄りの玄関口である関越道前橋ICから利根川右岸の渋川市域、そして榛名山周辺で御朱印を拝受できる寺社をご案内します。
帰路は榛名神社経由になることを想定し、国道406号の室田~並榎IC(国道17号との交差IC)沿いの寺社もご紹介します。
なお、一般に広く御朱印を授与されていないと思われる寺社については、今回もご紹介は割愛します。
群馬県央、前橋、高崎はいずれも城下町で寺社が多く、御朱印を授与される寺社も少なくないですが、両市中心部は利根川左岸にあたるので今回は対象外とします。
利根川右岸に限っても相当数の寺社があり、坂東三十三箇所(観音霊場)、東国花の寺百ヶ寺霊場、県内ではメジャーな新上州三十三観音霊場、上州七福神などの札所が点在します。
複数の現役霊場札所を兼ねるメジャーな寺院も多く、御朱印拝受のハードルは比較的低いエリアといえましょう。
宗派的には天台宗が多いエリアとなっています。
(1泊では制覇は無理です。燃えた方は(笑)、何回か泊まってあげてください。ちなみに伊香保は風情も泉質もよく、おすすめの温泉地です。)
メジャーな札所やパワスポが多いので記事ネタには事欠きません。
ボリュームが出たので、4編の構成となりました。
リストはつぎのとおりです。
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
1.青雲山 実相院 大福寺 (前橋市鳥羽町)
2.(中尾)飯玉神社 (高崎市中尾町)
3.鷲霊山 釈迦尊寺 (前橋市元総社町)
4.(上野国)総社神社 (前橋市元総社町)
5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺 (前橋市元総社町)
6.三鈷山 吉祥院 妙見寺 (高崎市引間町)
7.秋元山 江月院 光巌寺 (前橋市総社町)
8.氣雲山 春光院 元景寺 (前橋市総社町)
9.東向八幡宮 (高崎市箕郷町)
10.金富山 実相院 長純寺 (高崎市箕郷町)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)
12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)
13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)
14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)
15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)
16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)
17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)
18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
19.船尾山 等覚院 柳澤寺 (榛東村山子田)
20.五徳山 無量寿院 水澤寺 (渋川市伊香保町水沢)
21.伊香保神社 (渋川市伊香保町伊香保)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
22.榛名神社 (高崎市榛名山町)
23.大森神社 (高崎市下室田町)
24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)
25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)
26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)
27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)
29.白山神社 (高崎市白岩町)
30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)
31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)
32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)
33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)
34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)
35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)
36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)
37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)
38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)
39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)
40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)
41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)
42.菅原社 (高崎市金古町)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
43.如意山 宝蔵院 大乗寺 (高崎市棟高町)
44.烏子稲荷神社 (高崎市上小塙町)
45.新比叡山 本実成院 天竜護国寺(高崎市上並榎町)
46.我峰八幡神社 (高崎市我峰町)
47.上野國一社八幡宮 (高崎市八幡町)
48.神通山 遍照王院 大聖護国寺 (高崎市八幡町)
49.慈雲山 養寿院 福泉寺 (高崎市鼻高町)
50.少林山 達磨寺 (高崎市鼻高町)
【伊香保温泉周辺で拝受できる御朱印】
1.青雲山 実相院 大福寺
前橋市鳥羽町717
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東百八地蔵尊霊場第24番
札所本尊:地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第24番)

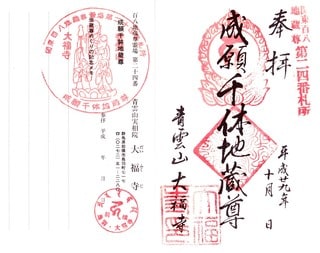
〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕
見開きの霊場規定用紙での授与となります。
中央に札所本尊、地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印、そして「成願千体地蔵尊」の揮毫。
右上に「関東百八地蔵尊第二十四番札所」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
裏面には寺院の情報と記念スタンプが捺されています。
まずは関越道前橋ICそばの寺院からご紹介します。
前橋ICから500mと離れていない至近に立地するこのお寺は、室町時代初期の応永元年(1394年)に総本山延暦寺の直末寺院として開山されたと伝わります。
「当時七堂伽藍壮麗にして、本堂間口二十間・奥行十八間、境内に不動堂、大師堂、薬師堂等を有し、仏教弘宣の大道場として近郷の尊崇をあつめた」(寺伝より)という大寺で、紆余曲折の歴史を辿りながらも法灯を絶やすことなく今に至ります。
比較的新しい伽藍につき、さびた風情はないものの、明るく開放的な雰囲気です。
関東百八地蔵尊霊場第24番の札所で、札所本尊である成願千体地蔵尊は昭和63年にご住職の発願によって建立され、「一願一体の『願掛け地蔵尊』」とも呼ばれて信仰を集めているそうです。
関東百八地蔵尊霊場は、かつて仙台市に存在した「佛教文化振興会」という組織がとりまとめたとみられる霊場で、現況、霊場会もとりまとめ役もいないなか、比較的御朱印授与率の高い霊場です。
霊場開創時に霊場(札所)印が整備されたらしく、札所印もいただきやすくなっています。
また、霊場開創時に専用納経帳も整備されたらしく、大判の専用納経帳用の書置御朱印が授与される場合があります。
とはいえ、汎用御朱印帳に授与いただける札所も少なくなく、札所(御朱印)対応は多種多様です。
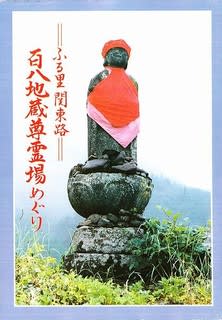
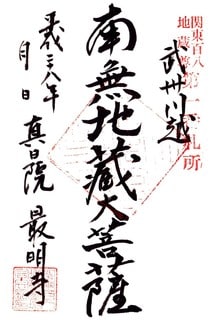
【写真 上(左)】 霊場の巡礼ガイド(平成2年1月、佛教文化振興会刊)
【写真 下(右)】 発願寺(初番)「瑶光山 真日院 最明寺」(川越市)の札所御朱印(現在、この御朱印は非授与のようです)
札所には相当数の名刹も入っていますが、納経所の御朱印見本で掲示される例はほとんどなく、こちらからお伺いしてはじめて授与いただける「裏メニュー」的なケースが多くなっています。
また、札所本尊のお地蔵様の御座所がわかりにくく(本堂でない場合が多い)、霊場ガイドを持っていない場合は、お寺さんに確認する必要があります。
そんなこんなで、かなりマニアックな霊場であることは間違いないかと・・・。
なお、札所本尊のお地蔵様は御本尊でないケースが多く、別に御本尊の御朱印をいただける場合とそうでない場合があります。
こちらのお寺様は地蔵霊場のみの授与とのことでした。
2.(中尾)飯玉神社
高崎市中尾町347
主祭神:宇気母智神(飯玉さま) 配祀:菅原道真公(天神さま)、建御名方神、須佐之男命、美留目之神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進社、中尾総鎮守


〔 御朱印 〕
中央に「飯玉神社」の神社印と揮毫。右下には「中尾総鎮守」の陰刻印が捺されています。
温泉好きのあいだでは有名な、高崎中尾温泉「天神の湯」のすぐ隣にある神社です。
じつに「延暦三年(784年)に勧請せり」と伝わる(公式Webより)古い由緒をもち、千葉上総介常重、足利幕府の管領上杉氏、高崎城主酒井左衛門尉など、歴代のこの地の支配者との関係も伝わっているようです。
明治後期に村内の菅原神社、諏訪神社を合祀し、神饌幣帛料を供進すべき指定神社になったといいます。
主祭神は、宇気母智神(うけもちのかみ)。配祀神は菅原道真公、建御名方神、須佐之男命、美留目之神です。
公式Webによると、「飯玉神社の主祭神である宇気母智神は、『食物の神様』であり、保食神とも記され、五穀を司る神と言われています。」
保食神(うけもちのかみ)は稲荷神社の祭神となられる場合がありますが、上武(上野國・武蔵國)一円では、稲荷神社(祭神 倉稲魂命(宇迦御魂命)と飯玉神社(祭神 保食神(宇気母智命)は明確に区別されているという説もあるようです。
また、豊受比売命が飯玉神社の祭神となられている例もありますが、豊受比売命も食物と関わりの強い神様ですから、飯玉神社と食物は切り離せない関係なのかもしれません。
境内に数台の駐車スペースがあります。
鳥居・参道から階段を昇って拝殿。小規模ながら風格のある拝殿です。
ご朱印は境内で書置きのものを拝受しました。
3.鷲霊山 釈迦尊寺
公式Web
前橋市元総社町2502−2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛

〔 御本尊の御朱印 〕
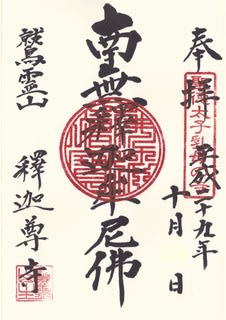
中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。右上には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
禅寺らしい端正な御朱印です。
〔 大黒天の御朱印 〕
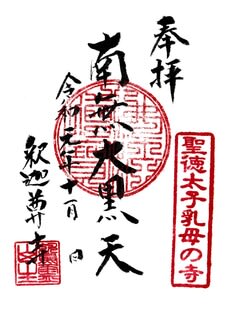
大黒天の御朱印も授与されています。
中央に三寶印と「南無大黒天」の揮毫。右には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
すこぶる古い来歴をもつ上州の名刹。
寺歴については、公式Webで詳細に説明されていますが、概略を抜粋引用しつつご紹介します。
三十一代用明天皇二年(587年)、蘇我馬子が物部守屋を滅ぼしたとき物部氏に加担した中臣羽鳥連と妻、玉照姫は上毛野国青海に流罪となりました。
玉照姫は聖徳太子の乳母で、太子の守仏、闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏を太子より授けられました。
天武天皇十五年(686年)、勅令による大赦で羽鳥連の孫青海羊太夫が上洛して勅赦を受けた際、定慧和尚が玉照姫の敬信した釈迦尊仏の由来を尊信し、翌年(687年)上野国蒼海に御下りになり七堂伽藍を建立、釈迦尊仏を安置され釈迦尊寺と号されました。
開基は青海羊太夫、開山は多武峯定慧和尚とされています。
当初は法相宗に属したとされますが、のち(文永年間(1264~1274年))に臨済宗門、鎌倉建長寺より蘭渓和尚が入られて再興。永禄元年(1558年)永源寺より芳伝和尚が入られ曹洞宗となり現在に至るようです。
江戸期には寛永三年四月、幕府より三百六十石余の御朱印寺とされています。
御本尊の闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏は平安時代末のものと推定され、秘仏となっています。
すこしく横道に逸れます。
古代、東国を代表する政治勢力として「毛野(けの/けぬ)」と「那須」があり、毛野は「上毛野(かみつけの/かみつけぬ)」「下毛野(しもつけの/しもつけぬ)」に二分されたといわれます。
このうち上毛野は上野國(上州)をさし、令制国の一つに定められたとされます。
令制国制のもとでは、令制国諸国は国力により四等級に分けられましたが、延喜式では上野國は最上の「大国」に充てられ、しかも、全国で3国しかない親王任国のひとつでした。
親王任国(常陸國、上総國、上野國)は、親王が国守に任じられる「大国」で、親王任国の筆頭官である親王は太守と称されました。(上野國の初代太守は桓武天皇の皇子葛井親王とされる。)
親王太守は現地へ赴任しない遙任のため、現地の実質的な国守は次官の介(すけ)となります。
なので原則、武士階級に「上野守」はおらず、「上野介」となります。(本多正純も、吉良義央も、小栗忠順もすべて「上野介」です。)
話が大逸れしましたが(笑)、何がいいたかったかというと、上野國は上代から東国で最も栄えた地域であり、西国との結びつきも強かったのでは、ということです。
そう考えると、聖徳太子の乳母・玉照姫にまつわる伝承もうなづけるものがあります。
また、仏教は欽明天皇の御代にわが国に伝わったとされますが(仏教公伝)、その際に積極的に仏教を迎え入れたのが崇仏派、仏教排斥に回ったのが排仏派で、崇仏派の代表格が蘇我氏、排仏派の代表格が物部氏とされます。
厩戸皇子(聖徳太子)は崇仏派で、玉照姫の夫羽鳥連は排仏派の物部氏に加担したとされていますから、聖徳太子の乳母・玉照姫の立ち位置は微妙なものであったのかもしれません。
そんなことをつらつらと想い起こさせてくれる、歴史をもったお寺さんです。
上代開基の寺院を物語るような、広々と明るい境内です。
札所ではありませんが、このような悠久の歴史をもつ古刹なのでご紹介しました。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。
いただいたのは御本尊の御朱印ですが、Webでは大黒天の御朱印もみつかるので、こちらも授与いただけるかもしれません。
4.(上野国)総社神社
公式Web
前橋市元総社町1-31-45
主祭神:磐筒男命、磐筒女命、経津主命、宇迦御魂命、須佐之男命
上野國総社 旧社格:県社

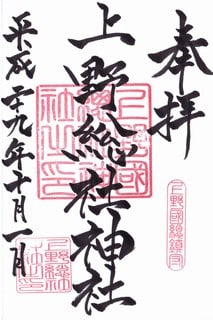
〔 御朱印 〕
中央に社名印の捺印と「上野総社神社」の揮毫。右に「上野國總鎮守」の印判。
左下に社名印が捺されています。
なお、最近の日付の御朱印では、主印として神紋印が捺されているようです。
諸説あるようですが、総社(惣社)とは、一般的には特定地域内の神社の祭神を集めて合祀した神社をさすとされます。
もともとは、律令制のもとで着任した国司は令制国内の一定の神社を早々に巡拝することが義務づけられていたが、国府の近くに総社を設け、そこに詣でることで巡拝を省く趣旨で置かれたという説があります。
また、地域内の神社を合祀した神社を称する例もあり、旧社格は、官幣小社から村社(ないし無格社)までと多岐にわたっています。
なお、全国総社会が組織され、専用御朱印帳も頒布されています。
総社神社公式Webには「上野総社神社は上野の総鎮守なり、上野総社 神社は国内総神社の神集ひ座す御神地なり、上野総社神社を参拝するは県内各神社を参拝するにひとし。」とあり、国司巡拝型の総社であったことがうかがわれます。
また同Webでは「崇神天皇の四十八年三月皇子豊城入彦命は東国平定の命を奉じ、上野にお下りになられるや、神代の時代に国土の平定に貢献された経津主命の御武勇を敬慕され、軍神としてその御神霊を奉祀して御武運の長久を祈られ、また、経津主命の親神(ご両親)である磐筒女命の御二方をも合祀せられた。これが当社の始まりである。」という創祀由緒、そして、「国司は国内各地の神社に幣束を捧げ、親しく巡拝していたが、人皇第五十六代清和天皇のころ国司は上野国内各社の神明帳を作り、国内十四郡に鎮座する総五百四十九社を勧請合祀」という合祀由緒も紹介されています。
大国、上野國の総社だけに、さすがに厳かな境内です。
御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れをいただきました。
5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺
前橋市元総社町1-31-38
天台宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:群馬郡三十三観音霊場第24番
札所本尊:千手千眼大悲観音(群馬郡三十三観音霊場第24番)

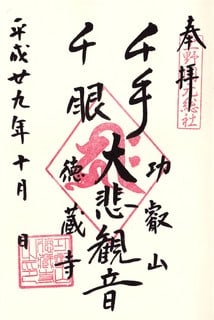
〔 御朱印 〕
群馬郡三十三観音霊場第24番の札所本尊と思われる千手千眼大悲観音の御朱印です。
中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印と「千手千眼大悲観音」の揮毫。
右上には「上野国元総社」の印判。
尊格の左右に山号・寺号の揮毫と、左下には寺院印が捺されています。
室町時代の文明三年(1471年)足利八代将軍義政公の祈祷所として建立、往時には寺中七ケ院、末門十七ケ寺を擁して幕府から朱印十六石を下賜され、檀徒三百有余戸を有したとされる古刹。(寺伝より)
室町時代の製作と考えられる三面の懸仏(弥勒菩薩、薬師如来、観世音菩薩)が残されていることからも、古刹の歴史が裏付けられます。
江戸時代初期の慶長十二年(1607年)、惣社(総社)領主の秋元越中守が惣社城築城の際に一寺の建立を計りましたが、当時は新寺院の建立を幕府が禁じていたため、天海僧正の内意により、本地および寺中数箇寺を北側利根川沿いの惣社城周辺に移して光厳寺と号しました。
爾来、この地に本寺格の寺院はなくなりましたが、明治五年(1872年)、檀徒が旧徳蔵寺の再建を官に願い出て、また光厳寺とも折衝して独立し、然海法印を住職として再建がなったものと伝わります。
総社神社と隣り合う、いかにも別当寺的な立地で、総社神社の別当だったという説があります。
上記の歴史を考えると江戸時代を通して大社、総社神社の別当を勤めるのはむずかしかった感じもしますが、少なくとも光厳寺への移転前は勤められていた可能性はあるかもしれません。
こちらは群馬郡三十三観音霊場第24番の札所です。
群馬郡三十三観音霊場は、現在の渋川市、前橋市、高崎市、榛東村、利根川右岸に広がる古い霊場で、今回ご紹介するエリアとかぶります。
発願寺は宇輪寺(榛東村)、結願寺は布留山 石上寺(高碕市)で、小規模な観音堂を含み、現在は活動を完全に停止しています。
先日、発願寺の宇輪寺にも参拝しましたが無住でした。
ただし、札所の遺伝子が残っているのか、御朱印をいただけるお寺さんがいくつかあります。こちらもそのひとつです。
御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。
6.三鈷山 吉祥院 妙見寺
高崎市引間町213
天台宗
御本尊:釈迦如来、妙見菩薩
札所:群馬郡三十三観音霊場第23番

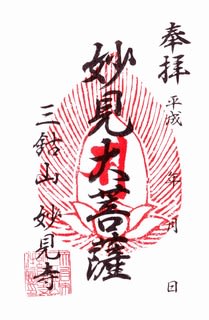
〔 御本尊の御朱印 〕
中央に御本尊、妙見菩薩の種子「ソ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「妙見大菩薩」の揮毫。
左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
創建は和銅七年(714年)、ないし霊亀元年(715年)と伝わる天台宗の古刹で、上野国国司・藤原忠明の開基とされています。
寺伝によると、延暦七年(797年)成立の「続日本紀」に妙見寺に関する記載があり、古くは「七星山息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰されてきたそうです。
境内の妙見社は日本三妙見のひとつとして知られ、この地方の妙見信仰の中心をなしていたという説があります。(→ 高崎市Web )
また、妙見寺は妙見社の元別当寺であったという見方もあるようです。
妙見信仰とは、中国の星宿思想から北極星を神格化ないし、菩薩として信仰するものとされます。(北斗七星との関連を指摘する説もあり。)
仏教においては妙見菩薩、神道においては天之御中主神が主な信仰の対象になります。
東日本の妙見信仰というと、まず坂東八平氏(平良文を祖として下総国、上総国、武蔵国、相模国などを領地とした、千葉・上総・三浦・土肥・秩父・大庭・梶原・長尾氏など)、ことに千葉氏が思い浮かびますが、どうして千葉から遠くはなれた群馬のこの地の妙見社が「日本三妙見」として崇められているのか、不思議な感じもします。
これについては、興味深い伝承が存在します。
平安時代の中ごろ、上野国花園村付近で、平氏(将門公、良文公・国香公)が相争う「染谷川の戦い」がありました。
この戦いの勝敗の鍵を握られたのが、この付近に鎮座されていた花園妙見(一説に羊妙見)とされ、平良文公を祖とする坂東八平氏は、これより妙見信仰の家系となったと伝わります。
千葉氏が信仰する千葉神社、秩父氏が信仰する秩父神社では、花園妙見との関連を示す資料がWeb上でもいくつかみつかります。(ex.『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)
とくに秩父神社については、「花園村から妙見社を勧請」と明記している資料があります。
妙見寺の妙見様と花園妙見が同一という決定的な史料は見当たらないようですが、深い関係にあったであろうことは想像されます。
榛名東麓には千葉氏ゆかりの伝承がいくつか残り、「19.船尾山 等覚院 柳澤寺」の縁起にも千葉氏が登場します。
なお、上記の『榛名山東南麓の千葉氏伝承』には、船尾山柳澤寺とのつながりが指摘される「独鈷山妙見院息災寺」について、「現在、高崎市引間町に『三鈷山吉祥院妙見寺』という寺院があり、これが『息災寺』の後身だと言われている。さらに、千葉氏の守護神である妙見大菩薩はこの寺から勧請されたとされている。」と述べられ、妙見寺は柳澤寺と息災寺を介してなんらかのつながりを有していたかもしれません。
妙見菩薩は「菩薩」を名乗られていますが、一般には天部に属するとされ、すこぶる複雑な尊格のようです。
また、天之御中主神も造化三神というすこぶる格の高い神格でありながら、ナゾの多い神様とされています。
星宿思想が絡む尊格は、複数の信仰が習合・混交していることもあって、複雑な性格をもたれるものが多く、生半可な知識では到底語れませんので、このくらいにしておきます。
なお、妙見菩薩を祀られる寺院は日蓮宗と天台宗で目立ち、こちらも天台宗寺院です。
御朱印は庫裡にて書置きのものを拝受しました。
7.秋元山 江月院 光巌寺
前橋市総社町総社1607
天台宗
御本尊:釋迦牟尼如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第22番、前橋四公御朱印巡り
札所本尊:釋迦牟尼如来(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕
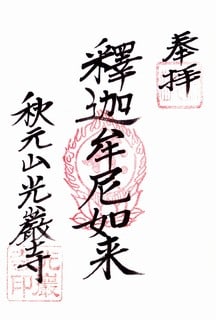
〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕
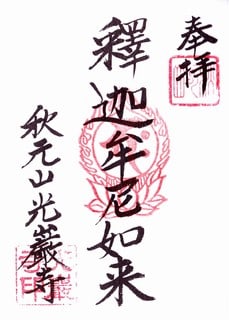
中央に御本尊、釋迦牟尼如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「釋迦牟尼如来」の揮毫。
左下には山号・寺号の揮毫と寺院印、右上には山号印が捺されています。
御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。
釈迦(如来)の御朱印は釈迦如来ないし(南無)釈迦牟尼佛での授与例が多く、釈迦如来は密教系、(南無)釈迦牟尼佛は禅宗系での授与が多くなっています。
この御朱印は複合形の「釈迦牟尼如来」で、数は多くないもののこの授与例もみられます。
なお、釈尊は仏教の開祖としての釈迦(ゴータマ・シッダルタ)、諸仏としての釈迦如来、本仏釈尊(久遠実成本仏)など、多様な性格、あるいはその存在を巡る解釈論(本仏論など)をもち、一言では語れない複雑な尊格です。
慶長六年(1601年)総社藩初代藩主の秋元長朝が徳蔵寺の亮應を招いて創建(開山)、以後秋元家の菩提寺としてつづく名刹。
秋元氏は名族宇都宮氏の流れとされ、戦国期の当主、長朝は関ヶ原の戦いの功績により慶長年間に一万石で総社藩に入り、利根川の右岸に総社城を築きました。
藩内の町割りを進めるなど名君の誉れが高かったと伝わりますが、二代泰朝の代に甲斐・谷村藩一万八千石に加増されて転封し、総社藩は廃藩となっています。
前橋市資料などによると、秋元氏は谷村藩に移封となったものの、光厳寺はこの地に留まり歴代秋元家の菩提を弔っているとの由。
また、慶安二年(1649年)には三代将軍家光公より16石の加増を受けて計46石。
この地域の天台宗の修業寺として寺運が隆盛したと伝わります。
境内は名家の菩提寺らしい落ち着いた空気に包まれています。
古い伽藍が多く残り、なかでも、薬医門は江戸時代初期に総社城の城門として建てられ、廃城になった際に移築したと推定される貴重な建物で、前橋市指定重要文化財に指定されています。
御朱印は庫裡にて拝受できます。
こちらは「前橋四公御朱印巡り」の一寺です。
「前橋四公御朱印巡り」は霊場とはいえないと思いますが、現在の前橋市域内で藩主を務めた酒井雅楽頭家、松平大和守家、秋元越中守家、牧野駿河守家ゆかりの6つの寺社を巡るイベントで、平成28年秋にはじまり毎秋開催、昨年平成30年秋で3回目となります。(平成30年は9/29~10/6の開催)
期間中、専用御朱印帳が配布され、これに捺印をいただく形で御朱印が授与されています。


【写真 上(左)】 四公祭ののぼり(光巌寺)
【写真 下(右)】 四公祭の専用御朱印帳
「前橋四公御朱印巡り」のほとんどの寺社は通常ご朱印も授与されていますが、専用御朱印帳とは尊格が異なるところもあり、御朱印収集的には貴重なイベントです。
前橋(厩橋)藩は、譜代(酒井雅楽頭家)、御家門(越前松平家)がおおむね十五万石の石高をもって封じられた上州屈指の大藩で、ゆかりの寺院の格式も高くなっています。
8.氣雲山 春光院 元景寺
前橋市総社町植野150
曹洞宗
御本尊:釋迦牟尼佛
札所:前橋四公御朱印巡り
札所本尊:釋迦牟尼佛(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕

〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕
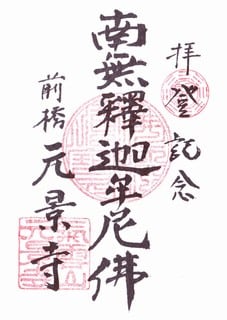
中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。
左下には寺号の揮毫と寺院印、右上に「拝登記念」の揮毫と寺号印?が捺されています。
御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。
「拝登(記念)」は、山岳信仰系の神社の御朱印でときおり見られますが(とくに富士塚のお山開きの御朱印に多い)、平地の寺院の御朱印ではめずらしいと思います。
利根川右岸にもほど近い、植野の地に構えるこちらも秋元氏ゆかりの名刹。
寺伝によると、開基は初代総社藩主秋元長朝で、父景朝の菩提を弔うため景朝の法名である「春光院殿気山元景大居士」から山号・院号・寺号が名づけられたとの由。
天正十五年(1587年)開創、天正十八年(1590年)に本堂が建立され、御本尊釈迦牟尼佛、脇侍文殊菩薩・普賢菩薩が安置されたと伝わります。
伽藍は、本堂・山門・鐘楼・庫裡・書院・位牌堂などからなります。
境内には、名君と伝わる総社藩初代藩主、秋元長朝の治世を物語る天狗岩伝説にまつわる羽階権現(はがいごんげん)が祀られ、長朝の功績を称える「力田遺愛碑」も建立されています。
このお寺には淀君にまつわる哀しい伝承と、淀君の墓と伝えられるものが残されています。
淀君は大阪夏の陣で秀頼と共に自害したとされますが、落ち延び説もあり、その落ち延び先として薩摩国と上野国厩橋の二つの説があるようです。
その上野国厩橋説にかかわるお寺ということでしょうか。
なお、境内掲出の寺伝には、「敷島公園内のお艶観音」との関係を示唆する内容が書かれています。
秋元家の墓のそばに、淀君の墓と伝えられるものが残されています。
戒名は、女性としては最高位の院殿・大姉号で、相当の高貴な身分の女性の墓所であることは間違いないとされています。(公式Webでは「伝・淀君(おえん)の墓」と表記されています。)
また、淀君所有とされる「正絹の大打掛」と「籠の引き戸」も伝えられているようです。
こちらも前橋四公御朱印巡りの一寺で、期間内は専用御朱印帳に授与いただけます。
御朱印は庫裡にて拝受、御朱印帳に書入れいただきました。
9.東向八幡宮
高崎市箕郷町西明屋4
主祭神:品陀和気命
旧社格:村社、箕輪城総鎮守

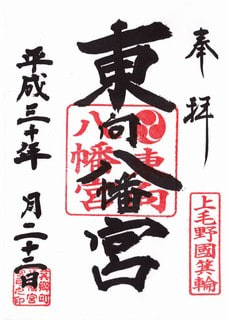
〔 御朱印 〕
中央に社名印の捺印と「東向八幡宮」の揮毫。右に「上毛野國箕輪」の印判。
左下には宮司印が捺されています。
旧箕郷町は平成18年に高崎市と合併し高崎市となりましたが、固有の歴史・文化を育んできたエリアです。
箕郷は上州の名族長野氏(皇別氏族、在原氏(在原業平)の流れで上野國守護代の家格であったとされる)の本拠地で、ことに箕郷城は名将の誉れ高い長野業正が拠った城として知られています。(箕郷城は「日本百名城」のひとつ。)
関東管領・山内上杉家に属した長野氏は、しばしば後北条氏の侵攻を受けましたが、業正は能く戦って譲らず領地を守りました。
また、武田信玄は信州経由で上州に侵攻し、箕郷城はその攻防の地となりましたが、やはり業正はこの領地を譲りませんでした。
しかし、業正亡きあとついに武田方の手に落ち、この地は武田方の上州経営の拠点として甘利昌忠、真田幸隆、浅利信種、内藤昌豊など錚々たる武田方の武将が城代として入りました。
武田氏滅亡後、滝川一益の統治下に入りましたが、本能寺の変により後北条氏の領地に、後北条氏没落後は12万石をもって井伊直政が入り箕郷藩を立藩したものの、慶長三年(1598年)高崎城に移封され箕輪藩は廃藩、城は廃城となりました。
このように箕輪城は「戦国時代の縮図」といわれるほどの歴史を刻みましたが、この箕輪城の総鎮守と伝わるのが東向八幡宮です。
室町時代中期の文明六年(1474年)、箕輪初代城主長野尚業が山城の石清水八幡宮より分霊勧請して創祀、箕輪城の総鎮守と成したと伝わります。
また、江戸期には阿房国勝山藩主酒井安芸守の飛地領地で、その病の平癒に霊験あらたかであったという伝承もあるようです。
境内はこぢんまりとしていますが、市指定重要文化財の「東向八幡宮の石幢」があります。珍しい十三仏の石幢で、神仏習合の歴史を物語るものかと。
御朱印は境内の社務所で、御朱印帳に書入れいただきました。
10.金富山 実相院 長純寺
高崎市箕郷町富岡852
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛

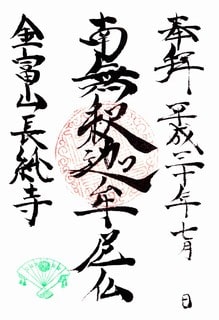
〔 御本尊の御朱印 〕
中央に三寶印と「南無釈迦牟尼仏」の揮毫。
左には山号、寺号の揮毫。通常、寺院印が捺される位置には長野氏の家紋「檜扇」紋が捺されています。
この地の名族、長野氏代々の菩提寺として伝わる曹洞宗の名刹。
高崎市資料によると、箕輪城主長野信業が明応六年(1497年)に箕郷町上芝に創建し、弘治三年(1557年)長野業政が現在地に移したと伝わります。
開山堂には市の指定重要文化財「長野業政公の像」が安置されています。
参道入口の閻魔大王や奪衣婆などの石仏はインパクトがあります。
閻魔大王は天台宗や浄土宗などの寺院にはよくおられますが、曹洞宗寺院では比較的めずらしいような感じもします。
御朱印は、2度目の参拝でご住職不在だったため郵送をお願いし拝受しました。
こちらはご不在がちの感じもありますが、名刹で「日本百名城」城主の菩提寺でもあるのでご紹介しました。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ サクラ色 (アンジェラ・アキ) - 熊田このは
■ ずっと二人で - BENI
■ 家に帰ろう ~マイ・スイート・ホーム~ - 竹内まりや feat. 山下達郎
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御朱印情報の関連記事
【御朱印帳の使い分け】
■ 御朱印帳の使い分け
【温泉地と御朱印シリーズ】
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
【名刹の御朱印情報】
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
【エリアの御朱印情報】
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 谷中の御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
【札所と御朱印】
■ 滝野川寺院めぐり-1
■ 根岸古寺めぐり
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 御朱印帳の使い分け
【温泉地と御朱印シリーズ】
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
【名刹の御朱印情報】
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
【エリアの御朱印情報】
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 谷中の御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
【札所と御朱印】
■ 滝野川寺院めぐり-1
■ 根岸古寺めぐり
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
■ 首都圏の札所と御朱印
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」展
上野の東京国立博物館の特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」(2019年3月26日(火) ~ 6月2日(日))に行ってきました。
平日だったこともあり、予想したほどの混雑はなく、楽しめました。


お大師様の足跡がたどれる丁寧な展開は好感がもてました。
後七日御修法がひとつのテーマになっていて、丁寧に説明されていた。
今回の改元にあたり、宮中と仏教の関係をとりあげた番組は結構あったけど、後七日御修法にふれていたものは意外に少なかった。
代表的な例だと思うのですが・・・。
前半部分では、
風信帖(ふうしんじょう)をまじかで目にできるとは、感無量です。
曼荼羅では、「種子曼荼羅」が地味ながらよかった。
それと、関東ではおそらく修することが許されなかったであろう大法関連の図像や別尊曼荼羅など。
さらに、表層が剥げて、いかにも「使われてきた感」のある巨大な敷曼荼羅。
後半の仏像系では、まず五大虚空蔵菩薩坐像。
獅子や象や孔雀の上に座していますが、文殊尊でも、普賢尊でも、孔雀明王でもなく、虚空蔵菩薩です。
こういう構成は関東ではほとんど目にすることはなく、インパクト大。
ただし、これに似た構成の五智如来はたしか板橋の安養院で見たことがある。(中央-大日如来(獅子)、東-阿閦如来(象)、南-宝生如来(馬)、西-阿弥陀如来(孔雀)、北-不空成就如来(迦楼羅))
メインの立体(羯磨)曼荼羅。
売りの”イケメン帝釈天”はやはりイケメンだと思う。それと象さんの存在感が凄かった。(この仏像のみ撮影可)
五(四)大明王では降三世明王が圧巻。背面の1面は東寺でも拝めないのでは?
五菩薩は、これも(関東では)なかなかお目にかかれないので貴重。
ただ、気になった点もありました。
立体曼荼羅なので、当然中心佛(大日如来や不動明王)が中心に位置しますが、こちらの出品がなく壁面に離れてつけたし的に掲出されていたこと。
やはり、東寺で見るのとは違うイメージになっていました。
でも、大日如来と不動明王は画像ながらも強いインパクトを放っていた。さすがに中心佛。
この2尊の実物が加わっていればさらに凄いことになっていたと思うが、さすがに中心佛は遷座できないのかも。
それと立体曼荼羅エリアの説明がお粗末。
たとえば、「五智如来の尊格のちがいは印相や持物でしか判断できない」と説明しながら、その印相や持物のしっかりとした説明がないなど。
曼荼羅にしても、これだけ大々的に出品しているのだから、大曼荼羅、三昧耶曼荼羅、法(種子)曼荼羅のわかりやすい説明があれば、ギャラリーの見方も変わるのでは?
でもでも、こういう素晴らしい宝物が東京でみられるとはありがたい。
仏像展は人気が高いようなので、次なる展開に期待したいところです。
平日だったこともあり、予想したほどの混雑はなく、楽しめました。


お大師様の足跡がたどれる丁寧な展開は好感がもてました。
後七日御修法がひとつのテーマになっていて、丁寧に説明されていた。
今回の改元にあたり、宮中と仏教の関係をとりあげた番組は結構あったけど、後七日御修法にふれていたものは意外に少なかった。
代表的な例だと思うのですが・・・。
前半部分では、
風信帖(ふうしんじょう)をまじかで目にできるとは、感無量です。
曼荼羅では、「種子曼荼羅」が地味ながらよかった。
それと、関東ではおそらく修することが許されなかったであろう大法関連の図像や別尊曼荼羅など。
さらに、表層が剥げて、いかにも「使われてきた感」のある巨大な敷曼荼羅。
後半の仏像系では、まず五大虚空蔵菩薩坐像。
獅子や象や孔雀の上に座していますが、文殊尊でも、普賢尊でも、孔雀明王でもなく、虚空蔵菩薩です。
こういう構成は関東ではほとんど目にすることはなく、インパクト大。
ただし、これに似た構成の五智如来はたしか板橋の安養院で見たことがある。(中央-大日如来(獅子)、東-阿閦如来(象)、南-宝生如来(馬)、西-阿弥陀如来(孔雀)、北-不空成就如来(迦楼羅))
メインの立体(羯磨)曼荼羅。
売りの”イケメン帝釈天”はやはりイケメンだと思う。それと象さんの存在感が凄かった。(この仏像のみ撮影可)
五(四)大明王では降三世明王が圧巻。背面の1面は東寺でも拝めないのでは?
五菩薩は、これも(関東では)なかなかお目にかかれないので貴重。
ただ、気になった点もありました。
立体曼荼羅なので、当然中心佛(大日如来や不動明王)が中心に位置しますが、こちらの出品がなく壁面に離れてつけたし的に掲出されていたこと。
やはり、東寺で見るのとは違うイメージになっていました。
でも、大日如来と不動明王は画像ながらも強いインパクトを放っていた。さすがに中心佛。
この2尊の実物が加わっていればさらに凄いことになっていたと思うが、さすがに中心佛は遷座できないのかも。
それと立体曼荼羅エリアの説明がお粗末。
たとえば、「五智如来の尊格のちがいは印相や持物でしか判断できない」と説明しながら、その印相や持物のしっかりとした説明がないなど。
曼荼羅にしても、これだけ大々的に出品しているのだから、大曼荼羅、三昧耶曼荼羅、法(種子)曼荼羅のわかりやすい説明があれば、ギャラリーの見方も変わるのでは?
でもでも、こういう素晴らしい宝物が東京でみられるとはありがたい。
仏像展は人気が高いようなので、次なる展開に期待したいところです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 東京都区内の如意輪観音の御朱印
今回は、すこし趣向を変えて尊格ベースでご紹介してみます。
如意輪観世音菩薩を選んだのは、ご紹介するに適当なボリュームということで他意はありません。
※おすがたはこちら(PDF)(「院政期真言密教をめぐる如意輪観音の造像と信仰」)に多数載っています。
【 如意輪観世音菩薩 】
六観音(聖観音、十一面観音、千手観音、馬頭観音、如意輪観音、准胝観音(天台宗系では不空羂索観音))の一尊に数えられ、天道に迷う衆生(天人)を救うとされる観音さま。
天道は人間道より上の世界で、「苦しみがほとんどない世界」とされます。
凡人には、このような世界から救われるというイメージはなかなか湧きにくいですが、とにかくそういうことになっています。(六道輪廻から救うということでは?)
「如意」とは如意宝珠、「輪」とは法輪をさし、儀軌(仏教の儀式規則)では、如意輪観世音を特徴づける持物とされます。
如意宝珠は「願いを遍くかなえるはたらき」、法輪は「煩悩を破砕して仏法を広めるはたらき」の象徴とされ、如意輪観世音菩薩はこのふたつの要素を兼ね備える尊格とされます。
片膝を立てて座る思惟六臂の像容が多く、どこかものうげで謎めいた表情をとるため、女性的な尊格ともいわれます。
ただし、如意宝珠や法輪を持たれない二臂像もみられます。(当初は半跏思惟二臂であったとする説あり。)
二臂像には半跏思惟二臂像と施無畏印・与願印像の2タイプあって、半跏思惟タイプは弥勒菩薩との識別が困難な作例もあります。
施無畏印・与願印像に至っては、他の尊格との識別はますます困難となり、どうして如意輪観音として伝わっているのかナゾとされている例もあるようです。
(二臂如意輪観音については、聖徳太子信仰との関連を指摘する説(ex.「院政期真言密教をめぐる如意輪観音の造像と信仰」(PDF))もあります。)
北関東などでは十九夜講(女人講や子安講とも呼ばれる月待念仏講)の御本尊とされ、お寺の境内に十九夜塔や地蔵菩薩などとともに露仏として多くみられますが、わたしの確認した範囲では如意宝珠や法輪(とくに法輪)を持つ例は少ないように思います。
かねがね不思議に思っていたので、あるお寺さんでご住職にお伺いしたところ、その仏像は如意輪観音ではなく「施楽観音」とのことで、さらにナゾが深まったような・・・(笑)
すこぶる密教的な尊格で、実際、密寺に御座される例が多くなっています。
種子はキリーク、御真言は「オン・ハンドメイ(マ)・シンダ・マニ・ジンバ・ラ・ウン」で、リズミカルでお唱えしやすいもの。
御縁日は毎月22日とされますが、18日に御開帳される例もあるようです。(護国寺など)
密寺の御本尊となられるケースも少なくなく、とくに真言宗豊山派大本山・護国寺の如意輪観世音菩薩はよく知られています。
札所本尊の例もあり、東京都区内でも複数の御朱印を拝受できます。
以下にこれまでに拝受した13の御朱印をご紹介します。
01.金剛山 円通院 観音寺(品川区大崎3-8-12)
天台宗 本尊:釈迦如来
東京三十三所観世音霊場第2番札所本尊

02.慈雲山 安楽寺 東陽院 (大田区仲六郷4-6-2)
真言宗智山派 本尊:如意輪観世音菩薩
玉川八十八ヶ所霊場第86番、東海三十三観音霊場第18番の各札所本尊
御朱印は玉川八十八ヶ所霊場第86番をご紹介。
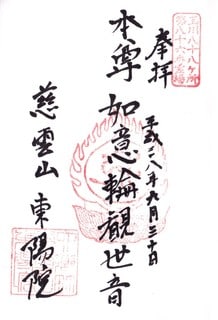
03.医王山 安養寺 / 古川薬師 (大田区西六郷2-33-10)
真言宗智山派 本尊:金剛界五智如来
東海三十三観音霊場第19番札所本尊

04.観谷山 福聚院 聖輪寺 (渋谷区千駄ヶ谷1-13-11)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
御府内八十八箇所第10番札所本尊

05.天沼山 蓮華寺 (杉並区本天沼2-17-8)
真言宗室生寺派 本尊 如意輪観世音菩薩
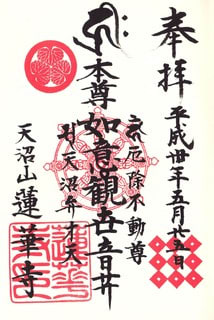
06.如意輪山 寶福寺 / 中野観音 (中野区南台3-43-2)
真言宗豊山派
江戸三十三観音札所第17番札所本尊
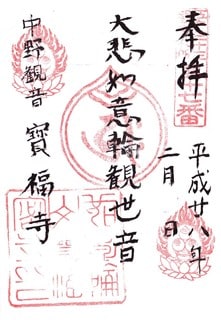
07.亀頂山 密乗院 三寶寺 / 石神井不動尊 (練馬区石神井台1-15-6)
真言宗智山派 本尊:不動明王
武蔵野三十三観音霊場第3番札所本尊

08.雙林山 月輪院 延命寺 (板橋区中台3-22-18)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第64番札所本尊

09.神齢山 悉地院 護国寺 (文京区大塚5-40-1)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
御府内八十八箇所第87番、江戸三十三観音札所第13番、東国花の寺百ヶ寺霊場第3番の各札所本尊
御朱印は御府内八十八箇所第87番をご紹介。

10.補陀落山 観音院 養福寺 (荒川区西日暮里3-3-8)
真言宗豊山派
豊島八十八ヶ所霊場第73番札所本尊
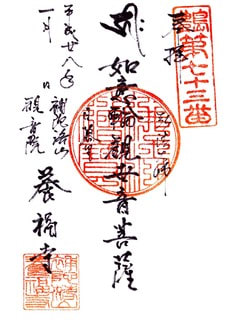
11.瑞光山 如意寺 密厳院 / 三河島大師 (荒川区荒川4-16-3)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第83番札所本尊

12.広幡山 観蔵院 (台東区元浅草3-18-5)
真言宗智山派 本尊:如意輪観世音菩薩
御府内八十八箇所第45番札所本尊

13.宝珠山 理性院 如意輪寺 / 牛島太子堂 (墨田区吾妻橋1-22-14)
天台宗
隅田川二十一ヵ所霊場第11番札所本尊

【 BGM 】
FictionJunction i reach for the sun
Yuki Kajiura - Credens justitiam
FictionJunction Everlasting song
如意輪観世音菩薩を選んだのは、ご紹介するに適当なボリュームということで他意はありません。
※おすがたはこちら(PDF)(「院政期真言密教をめぐる如意輪観音の造像と信仰」)に多数載っています。
【 如意輪観世音菩薩 】
六観音(聖観音、十一面観音、千手観音、馬頭観音、如意輪観音、准胝観音(天台宗系では不空羂索観音))の一尊に数えられ、天道に迷う衆生(天人)を救うとされる観音さま。
天道は人間道より上の世界で、「苦しみがほとんどない世界」とされます。
凡人には、このような世界から救われるというイメージはなかなか湧きにくいですが、とにかくそういうことになっています。(六道輪廻から救うということでは?)
「如意」とは如意宝珠、「輪」とは法輪をさし、儀軌(仏教の儀式規則)では、如意輪観世音を特徴づける持物とされます。
如意宝珠は「願いを遍くかなえるはたらき」、法輪は「煩悩を破砕して仏法を広めるはたらき」の象徴とされ、如意輪観世音菩薩はこのふたつの要素を兼ね備える尊格とされます。
片膝を立てて座る思惟六臂の像容が多く、どこかものうげで謎めいた表情をとるため、女性的な尊格ともいわれます。
ただし、如意宝珠や法輪を持たれない二臂像もみられます。(当初は半跏思惟二臂であったとする説あり。)
二臂像には半跏思惟二臂像と施無畏印・与願印像の2タイプあって、半跏思惟タイプは弥勒菩薩との識別が困難な作例もあります。
施無畏印・与願印像に至っては、他の尊格との識別はますます困難となり、どうして如意輪観音として伝わっているのかナゾとされている例もあるようです。
(二臂如意輪観音については、聖徳太子信仰との関連を指摘する説(ex.「院政期真言密教をめぐる如意輪観音の造像と信仰」(PDF))もあります。)
北関東などでは十九夜講(女人講や子安講とも呼ばれる月待念仏講)の御本尊とされ、お寺の境内に十九夜塔や地蔵菩薩などとともに露仏として多くみられますが、わたしの確認した範囲では如意宝珠や法輪(とくに法輪)を持つ例は少ないように思います。
かねがね不思議に思っていたので、あるお寺さんでご住職にお伺いしたところ、その仏像は如意輪観音ではなく「施楽観音」とのことで、さらにナゾが深まったような・・・(笑)
すこぶる密教的な尊格で、実際、密寺に御座される例が多くなっています。
種子はキリーク、御真言は「オン・ハンドメイ(マ)・シンダ・マニ・ジンバ・ラ・ウン」で、リズミカルでお唱えしやすいもの。
御縁日は毎月22日とされますが、18日に御開帳される例もあるようです。(護国寺など)
密寺の御本尊となられるケースも少なくなく、とくに真言宗豊山派大本山・護国寺の如意輪観世音菩薩はよく知られています。
札所本尊の例もあり、東京都区内でも複数の御朱印を拝受できます。
以下にこれまでに拝受した13の御朱印をご紹介します。
01.金剛山 円通院 観音寺(品川区大崎3-8-12)
天台宗 本尊:釈迦如来
東京三十三所観世音霊場第2番札所本尊

02.慈雲山 安楽寺 東陽院 (大田区仲六郷4-6-2)
真言宗智山派 本尊:如意輪観世音菩薩
玉川八十八ヶ所霊場第86番、東海三十三観音霊場第18番の各札所本尊
御朱印は玉川八十八ヶ所霊場第86番をご紹介。
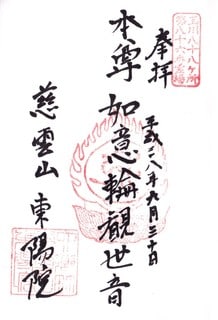
03.医王山 安養寺 / 古川薬師 (大田区西六郷2-33-10)
真言宗智山派 本尊:金剛界五智如来
東海三十三観音霊場第19番札所本尊

04.観谷山 福聚院 聖輪寺 (渋谷区千駄ヶ谷1-13-11)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
御府内八十八箇所第10番札所本尊

05.天沼山 蓮華寺 (杉並区本天沼2-17-8)
真言宗室生寺派 本尊 如意輪観世音菩薩
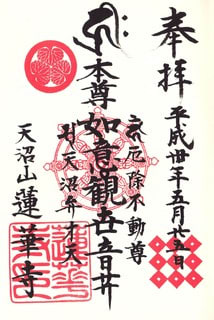
06.如意輪山 寶福寺 / 中野観音 (中野区南台3-43-2)
真言宗豊山派
江戸三十三観音札所第17番札所本尊
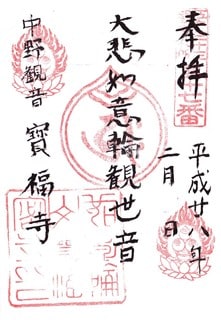
07.亀頂山 密乗院 三寶寺 / 石神井不動尊 (練馬区石神井台1-15-6)
真言宗智山派 本尊:不動明王
武蔵野三十三観音霊場第3番札所本尊

08.雙林山 月輪院 延命寺 (板橋区中台3-22-18)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第64番札所本尊

09.神齢山 悉地院 護国寺 (文京区大塚5-40-1)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
御府内八十八箇所第87番、江戸三十三観音札所第13番、東国花の寺百ヶ寺霊場第3番の各札所本尊
御朱印は御府内八十八箇所第87番をご紹介。

10.補陀落山 観音院 養福寺 (荒川区西日暮里3-3-8)
真言宗豊山派
豊島八十八ヶ所霊場第73番札所本尊
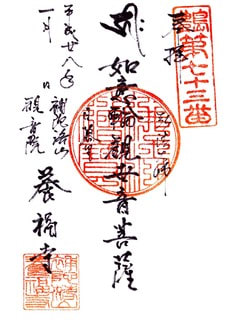
11.瑞光山 如意寺 密厳院 / 三河島大師 (荒川区荒川4-16-3)
真言宗豊山派 本尊:如意輪観世音菩薩
豊島八十八ヶ所霊場第83番札所本尊

12.広幡山 観蔵院 (台東区元浅草3-18-5)
真言宗智山派 本尊:如意輪観世音菩薩
御府内八十八箇所第45番札所本尊

13.宝珠山 理性院 如意輪寺 / 牛島太子堂 (墨田区吾妻橋1-22-14)
天台宗
隅田川二十一ヵ所霊場第11番札所本尊

【 BGM 】
FictionJunction i reach for the sun
Yuki Kajiura - Credens justitiam
FictionJunction Everlasting song
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
いろいろと
平成→令和の改元御朱印バトル(笑)を終えてさきほど帰ってきました。
おおむね山梨にいたのですが、ふつうのウィークエンドと混雑具合があきらかに違っていて、一定の神社に人出(というか御朱印ゲッター)が集中していたような気がする。
これはたぶん、ふだん御朱印をいただかないような人が、改元記念的に一気に御朱印ゲットに走ったためだと思う。(気持ちはわかります)
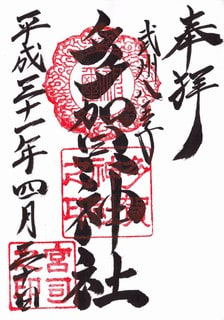

【写真 上(左)】 平成最終日の御朱印(多賀神社/東京都八王子市)
【写真 下(右)】 令和初日の御朱印(北口本宮浅間神社/山梨県富士吉田市)
たとえば令和初日の5月1日、甲斐一宮の浅間神社でも行列はさほどでもなく待ちは十数分程度。
穴切大神社や大井俣窪八幡神社では待ち時間ゼロ。
これに対して武田神社は日中は周辺大渋滞で近づくことさえできず、17時過ぎにリベンジしたところ「待ち時間1時間以上」とのことで参拝のみで撤収。
寺院はおおむね空いていて、甲府五山のいくつかのお寺でも待ち時間ゼロ。
改元はそうそうあることではないので、いろいろと貴重な体験をさせていただきました。
■ 乾徳山 恵林寺(山梨県甲州市)

改元記念御朱印が授与されていました。(左が通常御朱印、右が記念御朱印)
武田菱と花菱(武田氏の控え紋)の存在感。甲斐武田家の菩提寺ならでは。
■ 弟富士浅間神社(埼玉県秩父市)

左が通常御朱印、右が記念御朱印です。
新元号「令和」が主揮毫となる御朱印は、ほかの寺社でもいくつか拝受しました。
------------------------
4/29の熊田このはちゃん&富金原佑菜ちゃんのツーマンLIVE(@溝ノ口劇場)、
行ってきました。


両者対照的な歌い振りで、凄く面白い内容だった。
このはちゃんは、表現力がさらにスケールアップしていて、聴き手のこころをしっかり掴みにくる感じかな・・・。
今回はとくに「いつまでも聴いていたい感」がハンパなかった。
繰り返しますが、この子まだ高2(16歳)なんですが・・・。
今回もありがたいことに速攻で動画UPしていただいているので、見つかった動画を3曲ご紹介します。
熊田このは アイノカタチ / MISIA
中低音の力感が増して、声の艶はもはや凄絶の域。
熊田このは もののけ姫
ゆらぎを帯びた類なきスーパーソプラノ。
熊田このは&富金原佑菜 打上花火 DAOKO X 米津玄師
ボカロ的楽曲。黄金の世代だから歌いこなせる?
富金原佑菜ちゃん、多彩な声色を繰り出して四つに組んで譲らず。
※↑の内容、↓のページにもマルチポストします。
→特集
【関連記事】
■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
おおむね山梨にいたのですが、ふつうのウィークエンドと混雑具合があきらかに違っていて、一定の神社に人出(というか御朱印ゲッター)が集中していたような気がする。
これはたぶん、ふだん御朱印をいただかないような人が、改元記念的に一気に御朱印ゲットに走ったためだと思う。(気持ちはわかります)
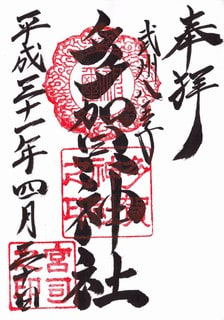

【写真 上(左)】 平成最終日の御朱印(多賀神社/東京都八王子市)
【写真 下(右)】 令和初日の御朱印(北口本宮浅間神社/山梨県富士吉田市)
たとえば令和初日の5月1日、甲斐一宮の浅間神社でも行列はさほどでもなく待ちは十数分程度。
穴切大神社や大井俣窪八幡神社では待ち時間ゼロ。
これに対して武田神社は日中は周辺大渋滞で近づくことさえできず、17時過ぎにリベンジしたところ「待ち時間1時間以上」とのことで参拝のみで撤収。
寺院はおおむね空いていて、甲府五山のいくつかのお寺でも待ち時間ゼロ。
改元はそうそうあることではないので、いろいろと貴重な体験をさせていただきました。
■ 乾徳山 恵林寺(山梨県甲州市)

改元記念御朱印が授与されていました。(左が通常御朱印、右が記念御朱印)
武田菱と花菱(武田氏の控え紋)の存在感。甲斐武田家の菩提寺ならでは。
■ 弟富士浅間神社(埼玉県秩父市)

左が通常御朱印、右が記念御朱印です。
新元号「令和」が主揮毫となる御朱印は、ほかの寺社でもいくつか拝受しました。
------------------------
4/29の熊田このはちゃん&富金原佑菜ちゃんのツーマンLIVE(@溝ノ口劇場)、
行ってきました。


両者対照的な歌い振りで、凄く面白い内容だった。
このはちゃんは、表現力がさらにスケールアップしていて、聴き手のこころをしっかり掴みにくる感じかな・・・。
今回はとくに「いつまでも聴いていたい感」がハンパなかった。
繰り返しますが、この子まだ高2(16歳)なんですが・・・。
今回もありがたいことに速攻で動画UPしていただいているので、見つかった動画を3曲ご紹介します。
熊田このは アイノカタチ / MISIA
中低音の力感が増して、声の艶はもはや凄絶の域。
熊田このは もののけ姫
ゆらぎを帯びた類なきスーパーソプラノ。
熊田このは&富金原佑菜 打上花火 DAOKO X 米津玄師
ボカロ的楽曲。黄金の世代だから歌いこなせる?
富金原佑菜ちゃん、多彩な声色を繰り出して四つに組んで譲らず。
※↑の内容、↓のページにもマルチポストします。
→特集
【関連記事】
■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 深大寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印〔再改訂版〕
20190424UP
先日さらに参拝し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。
-------------------
20180328UP
先日再訪し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。
多摩有数の古刹、深大寺。(浮岳山 昌楽院 深大寺)
天台宗別格本山の格式を誇り、その開創はじつに天平五年(733年)に溯るとされます。
国分寺崖線の崖面に立地し、湧水群と広大な武蔵野の雑木林を擁するその寺域はパワースポットの趣豊か。
深大寺蕎麦が名物で、参詣+蕎麦グルメの参拝客が多く訪れます。めずらしい”そば観世音菩薩”も御座します。


【写真 上(左)】 深大寺蕎麦ののぼりと山門
【写真 下(右)】 蕎麦屋が並びます


【写真 上(左)】 深大寺蕎麦
【写真 下(右)】 そば観世音
見どころも数多く、ゆったり時間をかけてのお参りをおすすめします。


【写真 上(左)】 鬼太郎茶屋-1
【写真 下(右)】 鬼太郎茶屋-2
2017年9月15日付で釈迦堂の釈迦如来倚像(白鳳仏)が国宝指定され、参拝客が急増しているようです。


【写真 上(左)】 国宝指定ののぼり
【写真 下(右)】 釈迦堂入口
こちらはメジャー霊場の札所ではなく、拝受できる御朱印や授与所はWeb情報でも錯綜気味ですが、2017年1月中旬時点(国宝指定前)と2018年3月時点(指定後)で拝受できた御朱印をご紹介します。
●朱印所
2017年1月時点では本堂右手の寺務所(旧庫裡)で御朱印を拝受できました。授与窓口では、白鳳佛、元三大師、毘沙門天の御朱印見本が掲示されていたかと思います。(毘沙門天の御朱印が通年授与かは不明)
2018年3月時点では朱印所は元三大師堂の右手に移動しています。
2018年3月時点で朱印所に掲出されていた御朱印見本は、1.無量壽、2.白鳳佛、3.元三大師の3種類でした。
2014年4月時点では、上記3種に加えて毎月17日限定授与の深沙大王の御朱印の案内もありました。
→ 限定押印の案内
いずれも朱印所では、丁寧な対応をいただきました。
なお、上記3種の朱印代は文化財保護に活用のため、2018年4月1日から1件300円から500円に改定されています。


【写真 上(左)】 新しい朱印所
【写真 下(右)】 以前の朱印所


【写真 上(左)】 御朱印の見本
【写真 下(右)】 朱印代改定のお知らせ
深沙大王の御朱印は2018年7月17日から9月末日までの毎日授与され、以降は毎月17日(深沙大王の御縁日)の限定授与となっています。
深沙大王の御朱印が授与されていることは知っていましたが、なかなか17日に参拝することができず、平成最後の御縁日である4月17日にようやく参拝しました。
このとき、授与所では「平成」をモチーフにしたダルマ印を限定で押印との案内が出ていました。
限定御朱印にはあまり興味がないのですが、「平成」モチーフとなると見逃せません。
いただける尊格すべての御朱印をいただいてしまいましたので(笑)、併せてご紹介します。
なお、この「平成だるま」の押印は今月(平成31年4月)一杯とのことです。(いつから授与されているかは不明。)
【深大寺の仏堂と御朱印】
深大寺の公式Webに詳しいのでざっくりと。
http://www.jindaiji.or.jp/
■本堂
御本尊の宝冠阿弥陀如来が御座します。



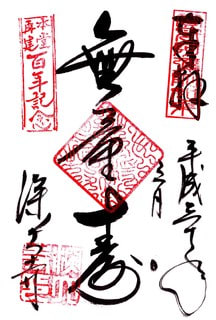
授与御朱印の「無量壽」は、こちらの御本尊をあらわす揮毫かと思われます。
阿弥陀如来の梵名”アミターバ”は「量り知れない光を持つ者」とされ、漢訳して「無量光仏」「無量寿(壽)仏」とも称されます。
中央に三寶印と「無量壽」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「寶冠阿彌陀如来」の印判が捺されています。
2018年3月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判が捺されていました。
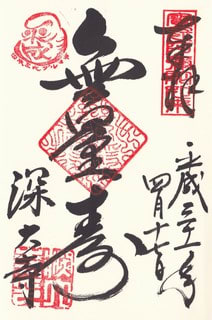
2019年4月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判がなくなり、「平成だるま」の捺印があります。
■元三大師堂
本堂の向かって左手の高台。
比叡山延暦寺中興の祖、元三大師の自刻像が御座します。この御堂御本尊は秘仏で50年に一度の御開帳。前回は1984年に御開帳されています。
中央の御本尊の厨子の向かって右に如意輪観世音菩薩、左に不動明王が御座します。
「元三大師は如意輪観音の化身とも言われ」(深大寺公式Webより)るため、如意輪観世音菩薩が御座されるのだと思います。


授与御朱印の「元三大師」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」と「元三大師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。

2019年4月時点の御朱印では「キリーク」の揮毫がなく、「厄除」の揮毫があります。また右上に「平成だるま」の捺印があります。


授与御朱印の「如意輪観音」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「如意輪観音」の揮毫、左に「客番」、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。
こちらは、札所の申告をせずにいただいた御朱印ですが、多摩川三十四観音霊場の客番を示すと思われる「客番」の揮毫がありました。

2019年4月時点の御朱印では「客番」の揮毫がなく、「平成だるま」の捺印があります。
調布七福神を除いて唯一の札所と思われる多摩川三十四観音霊場の客番札所の尊格もこちらの如意輪観世音菩薩かと思われます。
多摩川三十四観音霊場は後日参拝予定でしたが、客番札所であるこちらの御朱印授与が不明だったのでお伺いすると、すぐに規定用紙の御朱印をお出しいただいたので今回拝受となりました。(この霊場は原則規定用紙による授与のようです。)

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」「如意輪観世音」「厄除元三大師」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されている密度の濃い御朱印です。
「本尊」は、元三大師堂の御本尊ないし札所本尊をあらわすものかと思います。
隣には御詠歌が印刷されています。
■釈迦堂
本堂の向かって左手後方。
お堂本尊の釈迦如来倚像(白鳳仏)は、2017年9月15日付で国宝指定され、一気に脚光を浴びています。
この白鳳仏は、七世紀末製作の説がある東日本有数の古仏で、元三大師堂の壇の下から発見されたものです。めずらしい倚像は古仏に多い作例とされます。
2018年4月1日からは、千葉県龍角寺の薬師如来仏頭御分身像をお迎えして拝観料300円となります。以前は撮影可でしたがすでに撮影禁止となっており、つづいて拝観料。やはり国宝指定ともなると、いろいろと変わるものです。
中央に釈迦如来倚像(白鳳仏)が御座します。
2018年時点では、正面向かって右手に薬師如来立像(奈良県新薬師寺の香薬師御分身像)、左手に聖観世音菩薩(兵庫県鶴林寺の聖観音菩薩御分身像)が御座されます。
ふつう釈迦三尊は向かって右手に文殊菩薩、左手に普賢菩薩なので、この構成はいささか不思議な感じもします。




授与御朱印の「白鳳佛」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に三寶印と「白鳳佛」の揮毫。左に山号、寺号と寺院印、右上に「白鳳釋迦如来」の印判が捺されています。
2018年3月時点の御朱印では、「新国宝指定」の印判が捺されていました。

2019年4月時点の御朱印では「新国宝指定」の印判が「東日本最古の国宝佛」に替わり、「白鳳釋迦如来」の印判の位置に「平成だるま」の捺印があります。
2017年1月には、この堂内に毘沙門天が御座しました。
正面奥に白鳳仏。向かって右手手前に毘沙門天。
白鳳仏と毘沙門天、静と動の対比が圧巻です。
2018年3月時点では、おそらく堂内右手の厨子内に御座されていたと思うので、正月のみの御開帳かもしれません。
授与御朱印の「毘沙門天」(調布七福神)は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
(三天橋の先にも毘沙門天が御座され、こちらの尊格かもしれません。)
毘沙門天は、深大寺の縁起にまつわる尊格ともされています。


中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「毘沙門天」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に調布七福神の札所印が捺されています。
なお、この御朱印は正月のみの授与かと思われます。
■深沙堂
深大寺山内の西側に建つお堂です。このあたりは訪れる人もすくないですが、深大寺山内でも重要な位置づけにあるお堂です。
深沙大王(深沙大将)は大般若経を守護される十六善神の一尊であり、十六善神は護法善神(仏教の守護神)とされます。
護法善神の例にもれず複雑な性格をもたれるようですが、水とかかわりが深く、多聞天(毘沙門天)ないしは観世音菩薩の化身とされる説があります。
深大寺を開かれたとされる満功上人ゆかりの尊格で、かつては山内の鎮守社であったとの説もあります。
(なお、そばに鎮座する延喜式社、青渭神社のHPには「江戸時代深大寺村の総鎮守は、深大寺境内にある深沙大王堂であり、深大寺は当神社の別当寺であった。」と記載されています。)
深大寺のHPには「深大寺の寺号ももちろん、深沙大王に由来し」「(深沙)堂の背後には、この地の水源であり、深大寺の発祥にかかわる泉があります。」などの記載があることからみても、深大寺にとって深沙大王がいかに大きな存在であるかが窺いしれます。

中央に深沙大王の御影。左上に「開基上人自刻 水神●●深沙大王」の印判と寺号の揮毫と寺院印。
こちらも右上に「平成だるま」の捺印があります。
深沙大王は絶対秘仏ですが、「絶対秘仏の深沙大王像を忠実に模した御朱印です。」(HPより)とのことです。

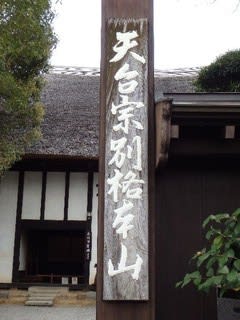
【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 天台宗別格本山です


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額
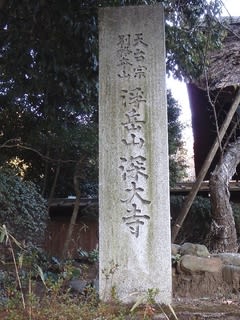

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 湧水エリアです
【写真 下(右)】 本堂の扁額


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 開山堂


【写真 上(左)】 境内絵図
【写真 下(右)】 延命観音


【写真 上(左)】 深沙堂
【写真 下(右)】 大黒天・恵比寿尊のお堂の素晴らしい彫刻

蕎麦屋の店先に井戸がありました。笹濁って明瞭な金気と土類臭があり、分析すれば温泉法規定に乗るのでは?
■祇園寺
深大寺の開基は伝・満功上人ですが、ここから南に1kmほどの須佐町に同じく開基を伝・満功上人とする天台宗の古刹、虎柏山 祇園寺があります。
ここは複数の霊場の札所で、御朱印を授与されているのでご紹介します。
虎柏山 日光院 祇園寺
調布市佐須町2-18-1
天台宗
御本尊 阿弥陀如来
札所
関東九十一薬師霊場第10番 札所本尊 薬師如来
関東百八地蔵尊霊場第101番 札所本尊 地蔵菩薩
調布七福神 福禄寿(こちらの御朱印も授与されています。)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 薬師堂


【写真 上(左)】 御本尊、阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 薬師霊場の御朱印
●御本尊 阿弥陀如来の御朱印
中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に仏師名(文化勲章を受章されている)の印が捺されています。
●薬師霊場の御朱印
薬師堂は享保年間(1716-36)建立とされ、御本尊薬師三尊は行基のお作と伝わる秘仏です。
中央に薬師如来の種子「バイ(ベイ)」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「須佐薬師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東九十一薬師霊場第拾番札所」の札所印が捺されています。
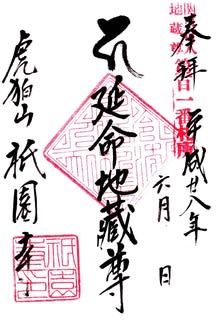
【写真 上(左)】 地蔵霊場のご朱印
●地蔵霊場の御朱印
中央に三寶印と地蔵菩薩の種子「カ」と「延命地蔵尊」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東百八地蔵尊第百一番札所」の札所印が捺されています。
札所本尊のお地蔵様は、山門脇の地蔵壇に御座される舟形光背石仏の「寛文の延命地蔵尊」です。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
花束 - 北乃きい
作曲小室哲哉、Back Vo.マキタソ(荒牧陽子)では悪かろうはずなし。
Open Your Mind - 石田燿子
一番の宝物 - karuta
ただ泣きたくなるの - bakiko(ruribitaki06072252)
20190424UP
先日さらに参拝し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。
-------------------
20180328UP
先日再訪し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。
多摩有数の古刹、深大寺。(浮岳山 昌楽院 深大寺)
天台宗別格本山の格式を誇り、その開創はじつに天平五年(733年)に溯るとされます。
国分寺崖線の崖面に立地し、湧水群と広大な武蔵野の雑木林を擁するその寺域はパワースポットの趣豊か。
深大寺蕎麦が名物で、参詣+蕎麦グルメの参拝客が多く訪れます。めずらしい”そば観世音菩薩”も御座します。


【写真 上(左)】 深大寺蕎麦ののぼりと山門
【写真 下(右)】 蕎麦屋が並びます


【写真 上(左)】 深大寺蕎麦
【写真 下(右)】 そば観世音
見どころも数多く、ゆったり時間をかけてのお参りをおすすめします。


【写真 上(左)】 鬼太郎茶屋-1
【写真 下(右)】 鬼太郎茶屋-2
2017年9月15日付で釈迦堂の釈迦如来倚像(白鳳仏)が国宝指定され、参拝客が急増しているようです。


【写真 上(左)】 国宝指定ののぼり
【写真 下(右)】 釈迦堂入口
こちらはメジャー霊場の札所ではなく、拝受できる御朱印や授与所はWeb情報でも錯綜気味ですが、2017年1月中旬時点(国宝指定前)と2018年3月時点(指定後)で拝受できた御朱印をご紹介します。
●朱印所
2017年1月時点では本堂右手の寺務所(旧庫裡)で御朱印を拝受できました。授与窓口では、白鳳佛、元三大師、毘沙門天の御朱印見本が掲示されていたかと思います。(毘沙門天の御朱印が通年授与かは不明)
2018年3月時点では朱印所は元三大師堂の右手に移動しています。
2018年3月時点で朱印所に掲出されていた御朱印見本は、1.無量壽、2.白鳳佛、3.元三大師の3種類でした。
2014年4月時点では、上記3種に加えて毎月17日限定授与の深沙大王の御朱印の案内もありました。
→ 限定押印の案内
いずれも朱印所では、丁寧な対応をいただきました。
なお、上記3種の朱印代は文化財保護に活用のため、2018年4月1日から1件300円から500円に改定されています。


【写真 上(左)】 新しい朱印所
【写真 下(右)】 以前の朱印所


【写真 上(左)】 御朱印の見本
【写真 下(右)】 朱印代改定のお知らせ
深沙大王の御朱印は2018年7月17日から9月末日までの毎日授与され、以降は毎月17日(深沙大王の御縁日)の限定授与となっています。
深沙大王の御朱印が授与されていることは知っていましたが、なかなか17日に参拝することができず、平成最後の御縁日である4月17日にようやく参拝しました。
このとき、授与所では「平成」をモチーフにしたダルマ印を限定で押印との案内が出ていました。
限定御朱印にはあまり興味がないのですが、「平成」モチーフとなると見逃せません。
いただける尊格すべての御朱印をいただいてしまいましたので(笑)、併せてご紹介します。
なお、この「平成だるま」の押印は今月(平成31年4月)一杯とのことです。(いつから授与されているかは不明。)
【深大寺の仏堂と御朱印】
深大寺の公式Webに詳しいのでざっくりと。
http://www.jindaiji.or.jp/
■本堂
御本尊の宝冠阿弥陀如来が御座します。



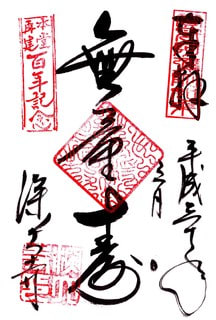
授与御朱印の「無量壽」は、こちらの御本尊をあらわす揮毫かと思われます。
阿弥陀如来の梵名”アミターバ”は「量り知れない光を持つ者」とされ、漢訳して「無量光仏」「無量寿(壽)仏」とも称されます。
中央に三寶印と「無量壽」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「寶冠阿彌陀如来」の印判が捺されています。
2018年3月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判が捺されていました。
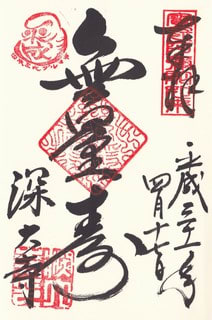
2019年4月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判がなくなり、「平成だるま」の捺印があります。
■元三大師堂
本堂の向かって左手の高台。
比叡山延暦寺中興の祖、元三大師の自刻像が御座します。この御堂御本尊は秘仏で50年に一度の御開帳。前回は1984年に御開帳されています。
中央の御本尊の厨子の向かって右に如意輪観世音菩薩、左に不動明王が御座します。
「元三大師は如意輪観音の化身とも言われ」(深大寺公式Webより)るため、如意輪観世音菩薩が御座されるのだと思います。


授与御朱印の「元三大師」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」と「元三大師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。

2019年4月時点の御朱印では「キリーク」の揮毫がなく、「厄除」の揮毫があります。また右上に「平成だるま」の捺印があります。


授与御朱印の「如意輪観音」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「如意輪観音」の揮毫、左に「客番」、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。
こちらは、札所の申告をせずにいただいた御朱印ですが、多摩川三十四観音霊場の客番を示すと思われる「客番」の揮毫がありました。

2019年4月時点の御朱印では「客番」の揮毫がなく、「平成だるま」の捺印があります。
調布七福神を除いて唯一の札所と思われる多摩川三十四観音霊場の客番札所の尊格もこちらの如意輪観世音菩薩かと思われます。
多摩川三十四観音霊場は後日参拝予定でしたが、客番札所であるこちらの御朱印授与が不明だったのでお伺いすると、すぐに規定用紙の御朱印をお出しいただいたので今回拝受となりました。(この霊場は原則規定用紙による授与のようです。)

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」「如意輪観世音」「厄除元三大師」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されている密度の濃い御朱印です。
「本尊」は、元三大師堂の御本尊ないし札所本尊をあらわすものかと思います。
隣には御詠歌が印刷されています。
■釈迦堂
本堂の向かって左手後方。
お堂本尊の釈迦如来倚像(白鳳仏)は、2017年9月15日付で国宝指定され、一気に脚光を浴びています。
この白鳳仏は、七世紀末製作の説がある東日本有数の古仏で、元三大師堂の壇の下から発見されたものです。めずらしい倚像は古仏に多い作例とされます。
2018年4月1日からは、千葉県龍角寺の薬師如来仏頭御分身像をお迎えして拝観料300円となります。以前は撮影可でしたがすでに撮影禁止となっており、つづいて拝観料。やはり国宝指定ともなると、いろいろと変わるものです。
中央に釈迦如来倚像(白鳳仏)が御座します。
2018年時点では、正面向かって右手に薬師如来立像(奈良県新薬師寺の香薬師御分身像)、左手に聖観世音菩薩(兵庫県鶴林寺の聖観音菩薩御分身像)が御座されます。
ふつう釈迦三尊は向かって右手に文殊菩薩、左手に普賢菩薩なので、この構成はいささか不思議な感じもします。




授与御朱印の「白鳳佛」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に三寶印と「白鳳佛」の揮毫。左に山号、寺号と寺院印、右上に「白鳳釋迦如来」の印判が捺されています。
2018年3月時点の御朱印では、「新国宝指定」の印判が捺されていました。

2019年4月時点の御朱印では「新国宝指定」の印判が「東日本最古の国宝佛」に替わり、「白鳳釋迦如来」の印判の位置に「平成だるま」の捺印があります。
2017年1月には、この堂内に毘沙門天が御座しました。
正面奥に白鳳仏。向かって右手手前に毘沙門天。
白鳳仏と毘沙門天、静と動の対比が圧巻です。
2018年3月時点では、おそらく堂内右手の厨子内に御座されていたと思うので、正月のみの御開帳かもしれません。
授与御朱印の「毘沙門天」(調布七福神)は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
(三天橋の先にも毘沙門天が御座され、こちらの尊格かもしれません。)
毘沙門天は、深大寺の縁起にまつわる尊格ともされています。


中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「毘沙門天」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に調布七福神の札所印が捺されています。
なお、この御朱印は正月のみの授与かと思われます。
■深沙堂
深大寺山内の西側に建つお堂です。このあたりは訪れる人もすくないですが、深大寺山内でも重要な位置づけにあるお堂です。
深沙大王(深沙大将)は大般若経を守護される十六善神の一尊であり、十六善神は護法善神(仏教の守護神)とされます。
護法善神の例にもれず複雑な性格をもたれるようですが、水とかかわりが深く、多聞天(毘沙門天)ないしは観世音菩薩の化身とされる説があります。
深大寺を開かれたとされる満功上人ゆかりの尊格で、かつては山内の鎮守社であったとの説もあります。
(なお、そばに鎮座する延喜式社、青渭神社のHPには「江戸時代深大寺村の総鎮守は、深大寺境内にある深沙大王堂であり、深大寺は当神社の別当寺であった。」と記載されています。)
深大寺のHPには「深大寺の寺号ももちろん、深沙大王に由来し」「(深沙)堂の背後には、この地の水源であり、深大寺の発祥にかかわる泉があります。」などの記載があることからみても、深大寺にとって深沙大王がいかに大きな存在であるかが窺いしれます。

中央に深沙大王の御影。左上に「開基上人自刻 水神●●深沙大王」の印判と寺号の揮毫と寺院印。
こちらも右上に「平成だるま」の捺印があります。
深沙大王は絶対秘仏ですが、「絶対秘仏の深沙大王像を忠実に模した御朱印です。」(HPより)とのことです。

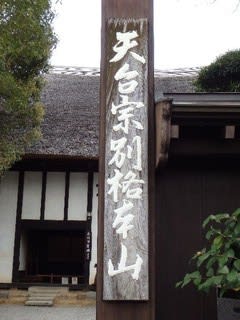
【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 天台宗別格本山です


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額
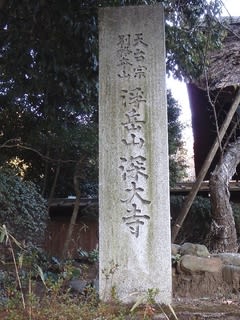

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 湧水エリアです
【写真 下(右)】 本堂の扁額


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 開山堂


【写真 上(左)】 境内絵図
【写真 下(右)】 延命観音


【写真 上(左)】 深沙堂
【写真 下(右)】 大黒天・恵比寿尊のお堂の素晴らしい彫刻

蕎麦屋の店先に井戸がありました。笹濁って明瞭な金気と土類臭があり、分析すれば温泉法規定に乗るのでは?
■祇園寺
深大寺の開基は伝・満功上人ですが、ここから南に1kmほどの須佐町に同じく開基を伝・満功上人とする天台宗の古刹、虎柏山 祇園寺があります。
ここは複数の霊場の札所で、御朱印を授与されているのでご紹介します。
虎柏山 日光院 祇園寺
調布市佐須町2-18-1
天台宗
御本尊 阿弥陀如来
札所
関東九十一薬師霊場第10番 札所本尊 薬師如来
関東百八地蔵尊霊場第101番 札所本尊 地蔵菩薩
調布七福神 福禄寿(こちらの御朱印も授与されています。)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 薬師堂


【写真 上(左)】 御本尊、阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 薬師霊場の御朱印
●御本尊 阿弥陀如来の御朱印
中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に仏師名(文化勲章を受章されている)の印が捺されています。
●薬師霊場の御朱印
薬師堂は享保年間(1716-36)建立とされ、御本尊薬師三尊は行基のお作と伝わる秘仏です。
中央に薬師如来の種子「バイ(ベイ)」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「須佐薬師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東九十一薬師霊場第拾番札所」の札所印が捺されています。
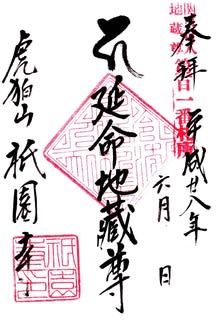
【写真 上(左)】 地蔵霊場のご朱印
●地蔵霊場の御朱印
中央に三寶印と地蔵菩薩の種子「カ」と「延命地蔵尊」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東百八地蔵尊第百一番札所」の札所印が捺されています。
札所本尊のお地蔵様は、山門脇の地蔵壇に御座される舟形光背石仏の「寛文の延命地蔵尊」です。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
花束 - 北乃きい
作曲小室哲哉、Back Vo.マキタソ(荒牧陽子)では悪かろうはずなし。
Open Your Mind - 石田燿子
一番の宝物 - karuta
ただ泣きたくなるの - bakiko(ruribitaki06072252)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 円覚寺の御朱印(25種)


鎌倉を代表する名刹、円覚寺(えんがくじ)は、正式には瑞鹿山 圓覚興聖禅寺と号します。
臨済宗円覚寺派の大本山で、鎌倉五山第二位の寺格を有します。
御本尊は寶冠釈迦如来、開基は北条時宗公、開山は無学祖元とされています。


鎌倉の大寺だけに複数の霊場の札所を兼ね、しかも期間限定御朱印もあるため、御朱印授与情報はWeb上でも錯綜していますが、ほぼほぼ拝受できた感じもあるので整理してご紹介します。
なお、山内仏閣等のご紹介については、すばらしいWeb記事がたくさんあるので、ここでは御朱印関係に絞ってのご紹介とします。
■公式Webの境内案内


【 円覚寺百観音霊場 】
臨済宗円覚寺派寺院の観音様を巡る霊場です。
初番発願寺は円覚寺、結願所は円覚寺境内の百観音となっています。
札所リスト(「旅人の記憶」様)
霊場創設は平成15年秋とみられます。
「(前略)私共、大本山円覚寺にも方丈前に石仏の百観音がありますが、あまり一般には知られておりません。そこで本山の参拝と共に、派内寺院の交流や檀信徒の布教伝導を目的とした、本派独自の観音霊場を発願いたしました。」(専用納経帳前文より)
「百観音霊場」となっていますが、実際の札所数は56で、56番から99番までは札所設定がなく、55番のつぎの100番で結願となります。
札所は神奈川県内のみならず、西伊豆から新潟、福島に及び、結願までの道のりはなかなか困難です。
百観音なのに100の札所がないことついては、何人かのご住職から理由を伺いましたが、ここでは触れません。
札所のうち、第2番~第5番は円覚寺境内の塔頭寺院となります。
内3つはこの霊場のみの札所なので、円覚寺の御朱印をコンプリートするには円覚寺百観音霊場を避けて通ることはできません。
初番発願寺は円覚寺で、こちらでは御朱印帳に授与いただくことはできません。
(専用納経帳にのみ授与との由。Web上では御朱印帳への拝受情報もありますが、わたしがお尋ねしたとき(2回)はいずれもそのようなご案内でした。)
専用納経帳は、授与所隣の頒布所で頒布されています。(平成31年3月上旬現在)
初版平成15年で版を重ねた感じもないので、残数はおそらく多くはなく、巡拝をめざす方は見かけたら即ゲットかと思います。(いくつかの札所寺院でも見かけています。)
円覚寺百観音霊場の御朱印は地方の札所では御朱印帳にいただけるケースも多いですが、円覚寺塔頭寺院では「専用納経帳にのみ授与」とされているところもあって、いずれにしてもこの専用納経帳の入手が第一歩かと思われます。
わたしの場合、連れと2名で参拝し「2名で巡拝させていただいておりますので、」という前置きのうえで、専用納経帳と御朱印帳2パターンの御朱印授与をお願いしています。
1名で2パターン拝受は、お寺さんによってはむずかしいかもしれません。
この観音霊場札所の寺院の多くは寺院御本尊が観世音菩薩ですが(御本尊=札所本尊)、御本尊が観世音菩薩以外の場合、御本尊の御朱印をいただけるケースは少ないと思います。
この霊場の札所は他霊場との重複も少ないので、ここは欲張らずに観音様の巡拝に徹するべきでしょうか。
御朱印については、はっきりと「円覚寺百観音霊場」巡拝者で、参拝を終えたことを告げて授与をお願いすれば、特段の問題なく拝受できるかと思います。(ただし、下記のとおり読経は必要かもしれません。また、ご住職がご不在・ご多忙のこともあるので出直し参拝の可能性は高いです。)
------------------------------
たいていの円覚寺御朱印情報では、通常御朱印の授与所は
1.総門横御朱印受付所
2.塔頭 佛日庵
3.弁天堂
の3ヶ所とされていますが、実際にはこれに黄梅院(百観音霊場第2番)、續燈庵(百観音霊場第3番)、壽徳庵(百観音霊場第5番)、龍隠庵(百観音霊場第6番)、雲頂庵(東国花の寺百ヶ寺霊場第100番)の5ヶ所が加わった計8ヶ所を確認しています。
なお、上記塔頭寺院のいくつかは山門手前、もしくは庫裡入口に「境内の拝観不可」「寺用以外の立ち入りはご遠慮ください」的な掲示がされています。
ただし、霊場巡拝者は例外で、入場しても咎められることはありません。
(拝観と巡拝(奉拝)、拝観客と信徒は異なるのですね。日本語はむずかしい(笑))


【写真 上(左)】 壽徳庵の立ち入り制限看板
【写真 下(右)】 雲頂庵の立ち入り制限看板
でも、それなりの度胸はいるかも・・・。
また、一般観光客をシャットアウトしているため境内はすこぶる静かなので、読経の声が庫裡に流れていく感じがあります。
なので、せめて延命十句観音経と御真言(百観音霊場の場合)くらいはあげたいところかも?
ちなみに、円覚寺百観音霊場専用納経帳に記載されている教典は、般若心経、大慈大悲観世音菩薩和讃、延命十句観音経、四弘誓願文、普回向です。
それでは、総門横御朱印受付所の御朱印から巡にご紹介していきます。
なお、御朱印の種類・内容は、寺社様のご事情により適宜変更となる可能性があります。
■通常御朱印
A.総門横御朱印受付所

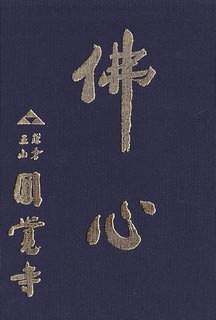
総門を抜け、拝観料を払った窓口の境内側にあります。たいてい混んでいて、参拝前に御朱印帳をお預けするかたちとなります。
そうなると、山内の他の授与所で御朱印帳書入れいただくことができなくなるので、円覚寺のオリジナル御朱印帳を購入してこれをお預けするか、御朱印帳を複数冊持参することになります。
こちらの御朱印帳は比較的紙質がよく、デザインも格調高いものです。
ただし、紙厚がやや薄く裏面に墨抜けする懸念があるので、わたしは片面使いとしました。
1.御本尊


仏殿(大光明寶殿)に御座す、丈六の釋迦如来像です。
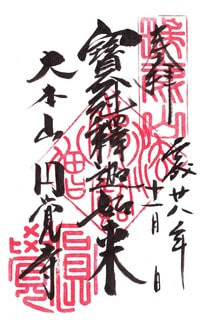
中央に三寶印と「寶冠釋迦如来」の揮毫。右上に山号印、左下に大本山、寺号の揮毫と寺院印。
禅宗大本山御本尊の御朱印だけあって、さすがに品格ある筆致です。
本来、山号の揮毫が入る場所に「大本山」が揮毫されるため、山号が右上印判になっているかと思います。
霊場無申告、ないし「鎌倉五山」での申告でこの御朱印の授与になるかと思われます。
2.寶雲閣(山門)
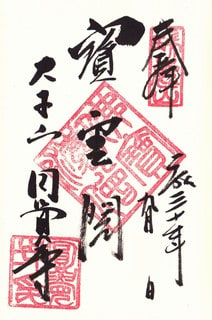
一部のマニア?で、「円覚寺の裏メニュー」ともいわれる御朱印です。
円覚寺では尊格や霊場の申告をせずに御朱印をいただくと、通常は御本尊「寶冠釋迦如来」になるようですが、まれに「寶雲閣」の御朱印を授与されることがあるのだとか。
この御朱印を拝受したときの記憶がなぜか欠落しているのですが、わたしも連れも、複数御朱印授与の寺院では無申告でのお願いはしないので、おそらく「寶雲閣」か「山門」で申告をしたのだと思います。
中央に三寶印と「寶雲閣」の揮毫。右上に山号印、左下に大本山、寺号の揮毫と寺院印。
ちなみに、「寶雲閣」とは、山(三)門上の楼閣をあらわします。
すこしく話が逸れますが、御朱印には閣号や殿号が揮毫されることがよくあります。
その多くは、尊格の御座す堂宇をあらわすもので、閣(殿)号はそのまま尊格に結びつきます。
たとえば、無量寿(光)殿-阿弥陀如来、瑠璃殿-薬師如来、大悲殿(閣)-観世音菩薩、圓通閣(殿)-観世音菩薩、大光普照殿-十一面観世音菩薩、阿遮羅殿-不動明王、大雄殿-禅宗系の本堂(禅宗系寺院の御本尊は釈迦牟尼佛が多いので、間接的に釈迦牟尼佛をあらわす場合が多い)などです。
しかしこの「寶雲閣」は直接には尊格には結びつかず、比較的めずらしいケースかもしれません。
3.東国花の寺百ヶ寺霊場第103番

この霊場の御朱印は御本尊が尊格となる場合が多いのですが、こちらもやはり御本尊「寶冠釋迦如来」でした。
円覚寺はこの霊場では鎌倉第11番、通しでは第103番の結願所となりますが、この霊場については巡拝の意識があまりないので、淡々と御朱印をいただきました。なお、花種は「桜・ぼたん」です。
この霊場の御朱印は規定用紙書置授与も多いですが、御朱印帳書入をいただけました。
中央に三寶印と「寶冠釋迦如来」の揮毫。右上に札所印、左下に大本山、寺号の揮毫と寺院印。そして「大本山」の揮毫の上に山号印が捺されています。
4つの印判が捺された華々しい印象の御朱印となっています。
4.円覚寺百観音霊場初番


円覚寺(選仏場)は、上記のとおり円覚寺百観音霊場の初番(発願)札所です。
選仏場とは「坐禅(道)場」のことで、仏殿が再建されるまでは御本尊宝冠釈迦如来像が御座されていたそうです。
現在は薬師如来像と観音菩薩像が御座され、札所本尊は、向かって右手に御座す大悲大慈観世音菩薩です。
水月観音的な気品のあるお姿ですが、尊格詳細はよくわかりません。
霊場については上述したので、ここでは御朱印のご紹介のみです。
専用納経帳にて拝受しています。
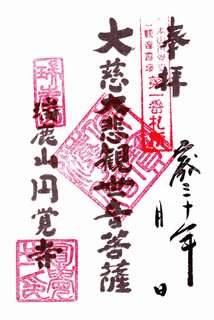
中央に「大慈大悲観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、寺号の揮毫印刷がデフォルトです。
こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左上に山号印、左下に寺院印をいただいて完成です。
円覚寺は、塔頭の佛日庵が鎌倉三十三観音霊場第33番の結願所になっていますが、円覚寺そのものは札所になっていません。
そんなこともあって、円覚寺の寺号でいただく観音様の御朱印は、なかなか感慨ぶかいものがあります。
5.円覚寺百観音霊場第100番(未拝受)


方丈前の石仏の百観音が第100番結願の尊格です。
この霊場はほぼ7割方巡拝済ですが、遠方の札所を残しているので結願はいましばらく先になりそうです。
なので、御朱印は未拝受です。

中央に「百観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、寺号の揮毫印刷がデフォルトです。
こちらに、印判をいただくことになります。
6.正續院(鎌倉二十四地蔵尊霊場第13番)


塔頭の正續院は、鎌倉二十四地蔵尊霊場第13番の札所(手引地蔵尊)ですが、通常非公開のため、御朱印は総門横御朱印受付所で授与されています。
宋から請来した仏舎利を納めるため、九代執権北条貞時が建立した祥勝院が前身の塔頭とされています。
塔頭ですが、「萬年山」という山号を有します。
舎利殿は国宝で、秋の一時期(11月前後/宝物風入)等に特別拝観できます。
特別拝観時には正續院内で限定御朱印も授与されますが、たしか、その授与所で地蔵尊霊場の御朱印を授けられていた記憶がないので、地蔵尊霊場の御朱印は常時総門横御朱印受付所での授与かと思われます。
なお、御本尊は文殊菩薩ですが、御本尊の御朱印は特別拝観時も授与されていません。

中央に三寶印と「南無地蔵尊」の揮毫。右上に札所印、左下に山号・院号(正續院)、大本山・寺号(円覚寺)の揮毫と寺院印。左上に山号印。
揮毫は山号+院号(正續院)・大本山+寺号(円覚寺)で、寺院印が円覚寺となっているところが見どころ(?)かと。
7、8.伝宗庵(鎌倉二十四地蔵尊霊場番外)


塔頭の伝宗庵は、第十一世南山士雲の塔所で、御本尊は地蔵菩薩(子安地蔵尊)です。
現在、境内には北鎌倉幼稚園が設置され、部外者が立ち入りできそうな雰囲気はありません。
現在、こちらの御本尊(札所本尊)の地蔵菩薩は、現在第18番寿福寺の地蔵菩薩とともに鎌倉国宝館に寄託されていますので、地蔵霊場結願のためには鎌倉国宝館に出向く必要があります。(遙拝という手もあるのかもしれませんが・・・。)
Web上では、こちらの御朱印を総門横御朱印受付所で拝受する際説明に苦労した、という記事が複数みつかりますが、わたしは専用納経帳で第23番まで集印した次の頁に「番外 伝宗庵様」という付箋をつけてお願いしたからか、別段問題なくいただけました。
ただし、混雑時に汎用の御朱印帳でお願いすると先様が混乱されるかもしれません。(第13番正續院と間違われたり、第14番の佛日庵を案内されるケースがあるらしい。番外まで参拝される方は少ないのかも・・・。)
----------------------------
先日、汎用御朱印帳にいただいてきました。
最初は第13番正續院と思われていた様でしたが、「伝宗庵様」と念押しするとご納得された様子で無事拝受できました。
「地蔵霊場 番外」のご認識は強くなく、「地蔵霊場」で申告すると第13番正續院となるおそれがあるので、ストレートに「伝宗庵」で申告した方がいいかもしれません。
いずれにしても、この御朱印は拝受者も多くなく、また取り違えもしやすいので、週末の混雑時は避けた方が無難かと思います。
ちなみに番外札所はもうひとつ明王院の「叶地蔵尊」があって、こちらも御朱印拝受可です。
またまた話が逸れますが、霊場のなかには「番外」「客番」「別格霊場」「掛所」などが設けられているケースがあって、御朱印を授与されている場合があります。
また、同番で複数の寺院がみつかることもあります。
資料によっては、これらの番外系札所がリストされていない場合もあるので、コンプリートをめざす向きは要注意です。
→御府内八十八箇所の例
専用納経帳と汎用御朱印帳で主印が違ったので2種に数えます。
【専用納経帳】
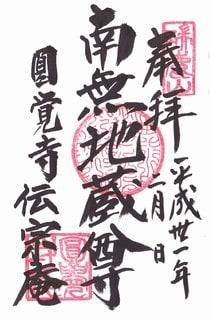
中央に三寶印(丸判)と「南無地蔵尊」の揮毫。右上に山号印(瑞鹿山)、左下に寺号庵号の揮毫と寺院印(円覚寺)が捺されています。
鎌倉二十四地蔵尊霊場にかかわるものは、印判、揮毫ともありません。
【御朱印帳】

中央に三寶印(角判)と「南無地蔵尊」の揮毫。右上に山号印(瑞鹿山)、左下に寺号庵号の揮毫と寺院印(円覚寺)が捺されています。
鎌倉二十四地蔵尊霊場にかかわるものは、印判、揮毫ともありません。
以上の8つが「総門横御朱印受付所」で一般参拝客が拝受できる御朱印かと思われます。
B.佛日庵




円覚寺開基の北条時宗公を祀る塔頭寺院です。
ここは別途に拝観料がかかりますが、複数の霊場の札所を兼ね、参拝者も多く、授与所の対応も親切で、おだやかに華やいだ雰囲気があります。
9.北条時宗公御廟
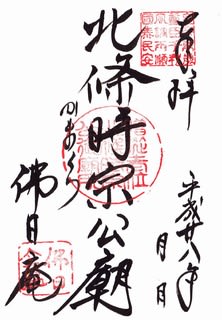
おそらく、霊場無申告だとこの御朱印になると思います。
尊格は、開基廟に御座す「北条時宗公像」です。
中央に御廟の丸印と「北条時宗公廟」の揮毫。(Web検索では「北条時宗公御廟」の御朱印もみつかりますが、いずれも日付の古いもので、現在は「北条時宗公廟」に統一されている模様。)
右上に捺されている「皇帝万歳 重臣千秋 風調雨順 国泰民安」の印は、弁天堂そばの鐘楼に鎮座する国宝の「洪鐘」(おおがね)の鐘銘(南宋から円覚寺に入られた僧、西澗子曇の銘とされる)由来のものと思われます。
左下には庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
10、11.円覚寺百観音霊場第4番
札所本尊は、開基廟に御座す十一面観世音菩薩で、鎌倉三十三観音霊場と同一の札所本尊です。(本堂には観音様は御座されていません。)
【専用納経帳】
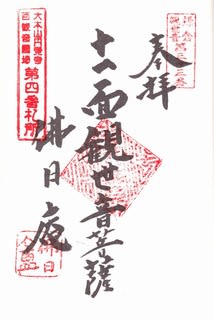
中央に「十一面観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に庵号の揮毫印刷がデフォルトです。
こちらに、中央に三寶印、上部に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。
なお、通常は右上の「鎌倉三十三観音霊場」の札所印はなく、こちらに円覚寺百観音霊場の札所印が捺されると思います。
【御朱印帳】
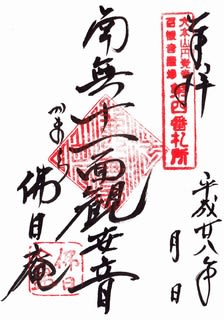
中央に三寶印と「南無十一面観世音」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
12、13.鎌倉三十三観音霊場第33番(結願所)
札所本尊は、10、11と同様、開基廟に御座す、十一面観世音菩薩です。
なお、平成31年3月時点で、札所本尊は開基廟改築のため、本堂に移られています。
本堂は堂内に上がれるので、間近で参拝できる貴重な機会だと思います。
【通常御朱印/御朱印帳】

中央に三寶印と「南無十一面観世音」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
円覚寺百観音霊場御朱印との違いは札所印のみです。
【結願御朱印/専用納経帳】

鎌倉三十三観音霊場は、正式には専用納経帳をつくって巡拝しました。
第1番杉本寺で発願し、こちらで結願しました。
中央に三寶印と「南無十一面観世音」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用納経帳で32の御朱印をご確認のうえ、左上に結願印をいただきました。
14.鎌倉二十四地蔵尊霊場第14番
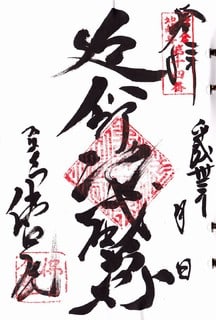
鎌倉の霊場は、観音様、地蔵尊の両霊場に、円覚寺百観音、坂東三十三箇所、東国花の寺、鎌倉十三仏、鎌倉・江ノ島七福神、鎌倉六阿弥陀、相州二十一ヶ所、さらには新四国東国八十八ヶ所が加わって、いよいよカオス的様相を呈するのですが、そのなかで円覚寺は比較的すっきりした方です。
それでも佛日庵は4種類の御朱印ですから、そろそろ頭がこんがらがってきます。
鎌倉二十四地蔵尊霊場第14番の札所本尊は本堂に御座す御本尊「地蔵菩薩坐像」で、御本尊=札所本尊です。
そうなると、非札所の御本尊の御朱印の有無が気になりますが、Web上では確認できませんでした。
おそらく授与所の混乱回避の意味合いもあって、御本尊(地蔵菩薩)の御朱印は、すべて札所印付きで授与されているものと思われます。
(札所認識のない方は「この第14番って何??」となるパターンですが、大寺では多くみられます。)
こちらは、御朱印帳、専用納経帳ともに拝受しています。(画像は専用納経帳のもの)
どちらも同一の内容で、中央に三寶印と「延命地蔵尊」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
上記のとおり、地蔵尊霊場の御朱印には本堂の参拝、御廟と観音霊場の御朱印には開基廟の参拝が必要となります。
こちらの札所様は寛容な感じがするので、そこまで見られていないかと思いますが、厳格なお寺さんではさりげにチェックが入ったりするので、札所尊格の御座所には留意が必要です。
とくに鎌倉地蔵尊霊場は境外仏堂が多いので要注意。「お地蔵様の場所はわかりましたか?」などと訊かれたりします(笑)
以上6つが「佛日庵」で拝受できる御朱印かと思われます。
C.弁天堂


15.洪鐘弁財天

弁天堂は江ノ島弁財天との所縁がふかい当山の鎮守社です。(当山公式Webより)
本堂に向かって右手の小高い丘の上にあります。お堂のよこに国宝の洪鐘(おおがね)が鎮座する鐘楼があります。
2度の失敗を重ねた洪鐘の鋳造を成就するため、時の執権・北条貞時公が七晩に渡って江の島弁財天に籠って祈願した結果成功し、これを謝して建てられたのが、洪鐘の向かいにある弁天堂といわれます。
弁財天は、妙音天、美音天とも呼ばれ、音とご縁のふかい尊格です。そんなこともあって、鐘と結びついたのかもしれません。
お堂右手の授与所での授与で、タイミングによっては書置になる場合があります。
中央に弁財天の種子「ソ」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「洪鐘弁財天」の揮毫。
右上に山号印、左下には大本山、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
円覚寺の御朱印の主印は、三寶印(佛法僧寶)が多く、御寶印タイプはめずらしいです。
こちらは弁財天の単一尊格のみの授与なので、尊格確定の御寶印を使われているのかもしれません。
16.開運弁財天

Webでは「開運大弁財天」の揮毫の御朱印もみつかります。
授与所の御朱印見本は「洪鐘弁財天」しか掲示されていないのですが、開運弁財天の御朱印についてお伺いすると授与可とのこと(この日は書置のみの授与でしたが、書置もありました。)
御朱印尊格は、おそらく洪鐘弁財天と同じかと思われます。
中央に弁財天の種子「ソ」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「開運弁財天」の揮毫。
右上に山号印、左下には大本山、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
15.「洪鐘弁財天」とは尊格揮毫の違いのみです。
以上2つが「弁天堂」で拝受できる御朱印かと思われます。
こちらは寺院境内の鎮守社。
神社と寺院の御朱印帳を分けている方は判断のしどころですが、わたしの場合、原則寺院境内の鎮守神や地主神の御朱印は寺院御朱印帳、神社境内鎮座の仏教系尊格の御朱印(七福神の弁財天、毘沙門天、大黒天など)は神社御朱印帳に拝受しているので、当山でも寺院御朱印帳への拝受としました。(書置でしたが寺院御朱印帳に貼込。)
D.雲頂庵


塔頭の雲頂庵は、空山円印(大覚禪師 蘭渓道隆の直弟)の開山で、御本尊は宝冠釈迦如来です。
塔頭ですが、「大機山」という山号を有します。
円覚寺塔頭のなかでは最も北側(大船寄り)に位置し、観光客はほとんど訪れないので、周辺はいたって閑静です。
円覚寺塔頭では唯一、東国花の寺百ヶ寺霊場の札所(第100番)となっています。
山門に「境内の拝観はできません」の掲示がありますが、霊場巡拝者は通門横の呼び鈴にて確認のうえ入場できます。
17.入三摩地
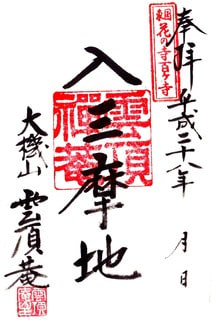
中央に寺院印と「入三摩地」の揮毫。右上に札所印、左下に山号、庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
主印に寺院印使用はめずらしいと思います。
「『三摩地』とは、悟りの意味に捉えて良いと思われます。『鎌倉五山記』等によると、雲頂菴の外門に『入三摩地』の扁額を掲げていたとあり、『新編 相模風土記稿』には、その扁額は後に雲頂菴の客殿に掲げられていたと記されています。つまり、この扁額があるところからは、心身ともに『悟りに入る』場所だという意味にとることができます。」(雲頂庵公式Webより)とのことで、揮毫はこれによるものと思われます。
禅宗系寺院の御朱印では、法典や語録由来の揮毫で授与される例は少なくありません。
18.望岳殿(規定用紙書置)


中央に三寶印と「望岳殿」の揮毫。右上に札所印、左下に山号、庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
「望岳殿」は、本堂裏山にある開山堂の堂名です。
富士山をはじめ西方の山々の眺めがいいことから号されたものと思われます。
御朱印に開山堂の堂名が揮毫される例はめずらしいと思います。
19.御本尊

Webで存在を確認していた御本尊の御朱印です。
書置はないようで、おそらくご住職がいらっしゃるときしか拝受できません。
中央に「入三摩地」の印と「寶冠釋迦如来」の揮毫。右上に札所印、左下に山号、庵号の揮毫と寺院印が捺されています。
御本尊の御朱印ですが、東国花の寺百ヶ寺霊場の札所印も捺されています。
以上3つが、「雲頂庵」で拝受した御朱印です。
20.黄梅院(円覚寺百観音霊場第2番)


塔頭の黄梅院は、円覚寺境内の最奥、最も高い場所にあります。
通常、このような場所は、奥の院、開山堂、地主神などが置かれるケースが多いですが、円覚寺では、塔頭、黄梅院となります。
夢窓疎石の塔所(開山塔)で、御本尊は千手観世音菩薩。この御本尊は円覚寺百観音霊場第2番の札所本尊でもあります。
塔頭ですが、「傳衣山」という山号を有します。
山門脇には「円覚寺百観音霊場第2番」を示す看板が掲げられています。
夢想疎石(国師)所縁ということもあってか、観光客が比較的多く訪れます。
しかし、庫裡入口には横棒が渡され、一般観光客は立ち入りできないようになっています。
掲示類はとくにありません。
このパターンはすこぶる敷居が高いですが、庫裡にお伺いしない限り御朱印は拝受できないので、よんどころなく横棒を外し、背後の観光客から「何この人??」的な視線を浴びながら庫裡に突入することになります(笑)
一度目はご不在、二度目は専用納経帳のみに捺印をいただいています。
Webでは御朱印帳記帳とみられる御朱印もみつかりますが、このときのやりとりをよく覚えていないので詳細不明。(たしか、ご法務でお忙しかったような記憶があるので、御朱印帳揮毫は遠慮したかもしれません。)
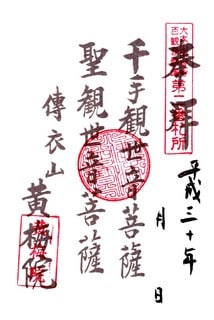
専用納経帳の御朱印は中央に「千手観世音菩薩」「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、院号の揮毫印刷がデフォルトです。
こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。
千手観世音菩薩はご本尊、聖観世音菩薩は本堂御座の室町期作の木造立像か、境内奥観音堂御座の木造立像のいずれかを示しているかと思われます。
21.續燈庵(円覚寺百観音霊場第3番)


塔頭、続燈庵は、第三十世大喜法忻(だいきほうきん)(仏満禅師)の創建で塔所でもあります。塔所ですが、大喜法忻の生前につくられた、いわゆる寿塔(祥光塔)の庵であったとされています。
開基は今川範国。塔頭ですが、「萬富山」という山号を有します。
御本尊の聖観世音菩薩は、南北朝時代の作とされ、円覚寺百観音霊場第3番の札所本尊でもあります。こちらの御本尊は東慶寺から移安されたものと伝わります。
参道入口は黄梅院に向かって左手。寺号標と山門とのあいだに木柵が置かれ、横棒が渡されて、「寺用で無い方は御遠慮下さい。」の掲示があります。
参道は趣きがあるので、観光客はこの木柵までは来るものの、木柵と掲示に阻まれて奥へ進む人はいません。
「百観音霊場巡拝」は「寺用」なので、躊躇なく奥へ進みます。
山門は常閉のようですが、右手通用門が開いていました。
境内は高台にあり、明るく開けた印象。幽邃の気ただよう黄梅院とは対照的な雰囲気です。
ここは2回参拝し、2回目は本堂内に上げていただけたので、勤行一式あげさせていただきました。
【専用納経帳】

中央に「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、庵号の揮毫印刷がデフォルトです。
こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。
【御朱印帳】
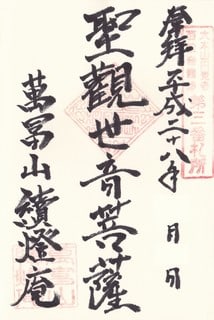
御朱印の内容は「専用納経帳」と同様です。
22.壽徳庵(円覚寺百観音霊場第5番)


塔頭、壽徳庵は円覚寺第六十六世月潭中円(げったんちゅうえん)禅師の建立で塔所とされます。
後に三浦道寸が中興開基となり、道寸の墓所でもあります。
専用納経帳には「南山 寿徳庵」と記載されていて、山門にも「南山」の扁額があるので「南山」が山号かと思います。
御本尊の聖観世音菩薩は、室町時代の作と伝わり、円覚寺百観音霊場第5番の札所本尊でもあります。
寺号標脇すぐから急階段の参道となります。
寺号標横には「円覚寺百観音霊場第5番」を示す看板が掲げられていますが、その奥には「ご用以外の方ご通行ご遠慮願います Private」の看板があり、階段を登った踊り場には木柵が設けられ、ここにも「墓参 ご用以外の方ご通行ご遠慮願います」の看板でガードが堅い印象です。
「百観音霊場巡拝」は「ご用」なので、躊躇なく奥へ進みます。
山門は常閉のようですが、右手通用門が開いていました。
いかにも禅寺らしい、清々しい雰囲気の境内。観光客の姿は当然見当たらず、静寂そのもので、落ち着いて参拝できました。
【専用納経帳】
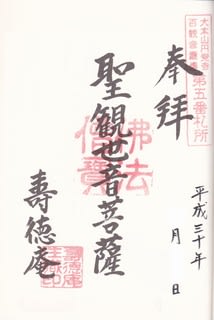
中央に「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に庵号の揮毫印刷がデフォルトです。
こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。
【御朱印帳】(書置)

御朱印の内容は「専用納経帳」と同様です。
23.龍隠庵(円覚寺百観音霊場第6番)


塔頭、龍隠庵は、円覚寺百二世大雅省音(たいがしょういん)の塔所です。当初は、法珠院の宿寮(龍隠軒)でしたが、1426年(応永33年)に塔頭に列せられたとされます。
御本尊の聖観世音菩薩は、円覚寺百観音霊場第6番の札所本尊でもあります。
こちらは、室町時代中期、山内上杉家の家宰を務め、名将の誉れも高かった武蔵国守護代、長尾忠政所縁の寺院と伝わります。
選仏場を過ぎた左手に参道入口があります。しばらく進むと尾根(切岸?)を巻くような階段が始まり、しばらく登ると到着です。
たいした登りではないですが、それでも比高を稼いでいて、円覚寺境内を見渡せます。
この位置から見下ろす山門や仏殿の眺めは貴重だと思います。
ふつう寺院は、参道を正面で受け、正面背後に山を背負うかたちが多いですが、こちらは、本堂が参道を横から受ける、いささか変わったかたちの境内です。
また、境内奥には鎌倉名物?の”やぐら”群があります。
本堂前に置かれた縁台には緋毛氈がひかれ、古都らしい雰囲気を醸し出しています。
円覚寺の塔頭のなかでは開かれた雰囲気のあるところで、何度か訪れていますが、いつも幾人かの参拝客が縁台でなごんでいます。御朱印も快くお受けいただけました。
【専用納経帳】

中央に「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に庵号の揮毫印刷がデフォルトです。
こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。
【御朱印帳】
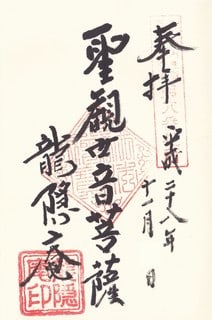
御朱印の内容は「専用納経帳」と同様です。
■限定御朱印
24.功徳林 / 大方丈


GW周辺や11月上旬の宝物風入(虫干し)の際に大方丈で授与される限定御朱印。
Webにて直近平成30年11月上旬の授与を確認しています。
授与所は大混雑するので、予め御朱印帳に記名しておいた方がよさそうです。
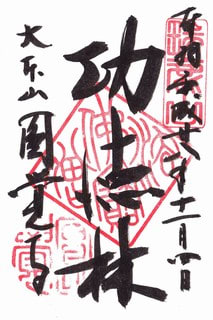
中央に三寶印と「功徳林」の揮毫。左下に大本山、寺号の揮毫。右上に山号印、左下に寺院印が捺されています。
「功徳林」の意味ですが、「功徳」は善行(善根)を積むこと、あるいそれを積むことにより得られる(神仏の)果報や恵みとされます。「林」は仏教では、人(僧)が集まるところ、転じて学寮、談所や結社などの意に使われます。壇林(談林)は僧の養成機関を指し、真言宗の関東十一談林、浄土宗の関東十八檀林などが知られています。
ここからすると、「功徳を積むために僧が集まるところ」「功徳を積んだ僧が集うところ」などの意味ではないかと。(まったくの私見ですが・・・)
なお、余談ですが、本駒込の吉祥寺(天台宗)は学寮「旃檀林」として栄え、御朱印も「旃檀林」で授与されています。
また、華厳経で十行(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧・方便・願・力・智の十波羅蜜を成就する利他の修行)を説くとされる、功徳林菩薩に因むものかもしれません。
25.舎利瞻禮 / 正續院舎利殿

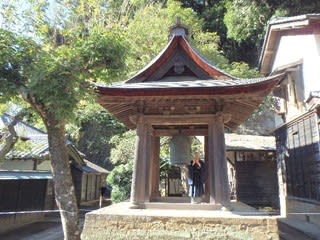
GW周辺や11月上旬の宝物風入(虫干し)の際等に塔頭正續院の舎利殿で授与される限定御朱印。
Webにて直近平成30年11月上旬の授与を確認しています。
境内は賑わっていましたが、波があるので、この波をうまくつかめば比較的ゆったりとした参拝ができます。
境内の鐘楼ではお坊様が鐘を撞かれ、一撞き毎に四弘誓願文を唱えられていました。
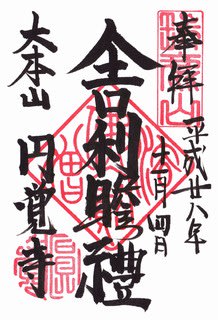
中央に三寶印と「舎利瞻禮」の揮毫。左下に大本山、寺号の揮毫。右上に山号印、左下に寺院印が捺されています。
「(仏)舎利」とは、釈迦牟尼(お釈迦様)の遺骨、「瞻禮」(せんらい)とは神仏を仰ぎ見て礼拝することなので、「舎利または舎利殿を仰ぎ礼拝する」の意味ではないかと。(これもまったくの私見ですが・・・)
以上、円覚寺では塔頭・限定御朱印を含め、少なくとも25種類の御朱印を確認しており、コンプリートには複数回の参拝を要すると思われます。
複数の塔頭や見どころをを擁する大寺で、高低差もあるため、参拝には時間を要します。
時間をかけてゆったりとした参拝をおすすめします。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
心の糸 - 池田綾子
Again - アンジェラ・アキ
Time To Say Goodbye - 熊田このは
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 高幡不動尊の御朱印
追加しました。
日野市にある金剛寺は、高幡不動尊の通称で広く知られる多摩屈指の古刹です。
正式には高幡山明王院金剛寺と号し、真言宗智山派別格本山の格式を有します。


開基は大宝年間(701年)以前、あるいは奈良時代、行基菩薩の開基とも伝えられ、平安時代に慈覚大師円仁が清和天皇の勅願により東関鎮護の霊場と定めて不動堂を建立し、不動明王をご安置されたのが始まりとされます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 手水舎
京王線「高幡不動」駅徒歩5分と交通の便がいいこともあって、参詣の人波が絶えない大寺です。
多摩丘陵が多摩川(浅川)に裾を落とす聖蹟桜ヶ丘から高幡不動にかけては、寺院が点在するところで、なかでも高幡不動尊は別格の規模を誇ります。
関東三大不動のひとつで、古くは「火防の不動尊」、また都内有数の交通安全祈願所であり、新選組副長、土方歳三の菩提寺としても知られるなど、参拝客を集める要素に事欠きません。
駅から門前にかけて、そして山内も賑わいをみせていますが、真言宗関東十一檀林の談義所として歴史を刻み、多摩丘陵の山気が降りてくるパワースポット的立地もあってか、どこか稟とした空気を感じます。


【写真 上(左)】 賑わう参道
【写真 下(右)】 土方歳三像


【写真 上(左)】 交通安全祈願殿
【写真 下(右)】 五重塔
真言宗の名刹だけに数多くの札所を兼ね、拝受できる御朱印書の種類も多いですが、これまたWeb情報でも内容が錯綜しています。
今回、ほぼ全容が明らかになった感じがするので、これまで3回の参拝で拝受できた御朱印をご紹介してみます。
なお、こちらの授与所は奥殿裏手の寺務局(納経所)1ヶ所で、週末などはすこぶる混雑します。(平日でも番号札制のようです。)
札所として、関東三十六不動尊霊場9番、多摩新四国八十八ヶ所霊場88番、武相二十八不動尊霊場28番、関東百八地蔵尊霊場100番、東国花の寺百ヶ寺霊場7番、日野七福神(弁財天)については御朱印を授与されています。
武玉八十八ヶ所霊場50番札所でもありますが、こちらは古い霊場で多くの札所は多摩新四国八十八ヶ所霊場に継承されている模様なので、おそらくこの霊場での御朱印は授与されていないと思われます。
ちなみに、多摩新四国八十八ヶ所霊場の霊場会とみられる龍華会本部は金剛寺内におかれ、金剛寺が中心的な役割を果たしていることがうかがわれます。
また、他所では入手がむずかしい多摩新四国八十八ヶ所霊場の公式ガイドブック(平成4年8月刊)もこちらの寺務局で入手できました。
このガイドには御本尊が記され、ふつうはこちらが札所本尊(御朱印尊格)となるようですが、金剛寺の「御本尊」欄は、「大日如来・不動明王」という含みのある記載で、拝受した御朱印尊格は不動明王でした。
札所ではない御本尊系の御朱印としては、御本尊大日如来、そして弘法大師の尊格御朱印を拝受できます。
これだけ種類があると、いわゆる「ご朱印ください!オファー」(札所や尊格指定なしで1つだけ拝受希望の場合)の御朱印はどうなるのかと思いますが、Web検索してみると、どうやら多摩新四国八十八ヶ所霊場の御朱印(尊格:不動明王)が授与されているようです。
やはり、ふつうの参拝客は「高幡不動尊にお参り」だと思うので、不動明王の御朱印となるのでしょう。(なぜ関東三十六不動ではなく多摩新四国なのかは不明。お大師様のお参りも忘れずに、ということでしょうか。)
【高幡不動尊の仏堂と御朱印】
仏堂については各種資料に詳しいのでざっくりと。
公式Webの「境内ご案内」
http://www.takahatafudoson.or.jp/?page_id=13
■不動堂
室町時代建立とされる堂々たる仁王門をくぐった正面。こちらはじつに鎌倉時代の建立とされます。お護摩はこちらのお堂で焚かれます。
こちらに御座す新丈六不動三尊は「平成12年から14年にかけて行われた1000年ぶりの修復作業の際、不動明王像不在のため、平安後期の様式を忠実に造立された身代わりの本尊として新たに創られた」(日野市観光協会Web)尊像のようです。


【写真 上(左)】 不動堂(武相不動尊霊場御開帳時)
【写真 下(右)】 回向柱と宝輪閣(お札所).
■奥殿
重要文化財の丈六不動三尊の他、数多くの文化財が収蔵されています。
高幡不動尊の札所御朱印は不動明王が尊格のものが多いですが、その札所尊格はこちらの丈六不動三尊と思われます。
不動堂の新丈六不動三尊は「身代わりの(札所)本尊」であり、先(2017年5月)の武相二十八不動尊霊場御開帳では、不動堂前に回向柱が立ち、縁の綱が不動堂内の新丈六不動三尊のお手に繋がり、さらに不動堂後ろ戸から伸びた縁の綱を奥殿向拝正面で受けそこからお手綱が下がっていました。この縁の綱が奥殿の丈六不動三尊のお手に繋がっていた模様です。
ここから拝察するに、やはり、不動堂・奥殿両堂のお不動様にお参りするのが筋のような気がします。


【写真 上(左)】 奥殿(武相不動尊霊場御開帳時)
【写真 下(右)】 奥殿の縁の綱


【写真 上(左)】 お手綱
【写真 下(右)】 奥殿の扁額
不動明王が御朱印尊格となる御朱印は、関東三十六不動尊霊場9番、多摩新四国八十八ヶ所霊場88番、武相二十八不動尊霊場28番、東国花の寺百ヶ寺霊場7番です。
御本尊が札所本尊となられる例の多い多摩新四国霊場、東国花の寺霊場でも、札所本尊(御朱印尊格)は不動明王でした。
なお、金剛寺の御本尊は大日如来のようです。
〔関東三十六不動尊霊場〕


【写真 上(左)】 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳揮毫の御朱印
授与御朱印の「不動明王」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・不動明王の揮毫と御寶印、左に召請光童子の印と山号と寺院印、右上に関東三十六不動尊霊場第9番の札所印が捺されています。
〔多摩新四国八十八ヶ所霊場(通常)〕

授与御朱印の「不動明王」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・不動明王の揮毫と御寶印、左に山号と寺院印、右上に多摩新四国第88番の札所印と「弘法大師御作」が揮毫されています。
〔多摩新四国八十八ヶ所霊場(結願)〕

多摩新四国八十八ヶ所霊場を結願したときの御朱印です。
専用納経帳ではなく、御朱印帳に拝受しています。
中央に不動明王の種子(カン)、「不動明王」の揮毫と御寶印(種子カン/蓮華座+火焔宝珠)、左に山号、寺号と寺院印、右上に多摩新四国第88番の札所印が揮毫されています。
結願で申告したためか、左上に「結願所」の印判とその横に「第八十八番」の揮毫をいただいています。
〔武相二十八不動尊霊場〕

授与御朱印の「厄除不動尊」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・厄除不動尊の揮毫と御寶印、左に結願所印、山号、寺号と寺院印、右上に武相不動尊第28番の札所印と酉年開帳の御開帳印が捺されています。
〔東国花の寺百ヶ寺霊場〕

授与御朱印の「不動明王」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・不動明王の揮毫と御寶印、左に山号と寺院印、右上に東国花の寺百ヶ寺の札所印と「弘法大師御作」が揮毫されています。
■大日堂
主参道に入り山手に向かうと山門があり、こちらをくぐると高幡山の総本堂、大日堂です。
山門右手には五部権現社が御座します。
金剛寺は正面と向かって左手が小高く、左手の高みは「不動ヶ丘」と呼ばれているようです。


【写真 上(左)】 大日堂山門
【写真 下(右)】 五部権現社
御本尊、大日如来が御座します。有名な鳴り龍もこの堂内にありますが、不動堂まわりにくらべると参拝客はすくなく、落ちついたただずまいとなっています。


【写真 上(左)】 大日堂
【写真 下(右)】 大日堂向拝


【写真 上(左)】 大日堂扁額
【写真 下(右)】 御朱印
授与御朱印の「大日如来」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・大日如来の揮毫と三寶印?、左に山号、寺号と寺院印、右上に清和天皇祈願所の印と鳴り龍の揮毫があります。
■大師堂
大日堂から五重塔に向かうと、聖天堂、大師堂、虚空蔵院と並びます。
寺内でも落ちつきのある不動ヶ丘中腹の高台で、じっくりとお参りができます。


【写真 上(左)】 大師堂参道
【写真 下(右)】 多摩新四国霊場の札所板


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂と聖天堂
弘法大師の御朱印は、こちらの参拝の証とみるべきでしょうか。
大師堂は専用の参道をもち、参道脇には多摩新四国八十八ヶ所霊場88番の札所板が掲げられていました。



【写真 上(左)】 御朱印
【写真 下(右)】 ご縁日の御朱印
授与御朱印の「弘法大師」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・弘法大師の揮毫と三寶印?、左に山号、寺号と寺院印、右上に山内八十八ヶ所巡拝の印が捺されています。
■千躰地蔵堂
五重塔の地下には無料休憩所があり、その横が千躰地蔵尊のお堂となっています。
目立たないお堂ですが弘法大師像、欄間彫刻など複数の見どころ(お参りどころ)があります。
こちらは関東百八地蔵尊霊場100番の札所となります。
なお、大日堂内にも北条氏ゆかりの延命地蔵尊が御座しますが、関東百八地蔵尊霊場ガイドブックには札所本尊が千躰地蔵尊と書かれ、寺務局でお伺いしても千躰地蔵尊とのお答えがあったので間違いないと思います。


授与御朱印の「千体地蔵尊」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・千体地蔵尊の揮毫と三寶印?、左に山号、寺号と寺院印、右上に関東百八地蔵尊第100番札所の札所印が捺されています。
■弁天堂
土方歳三像と交通安全祈願殿のあいだに弁天堂があります。弁天池にかかる赤い橋をわたっての参拝です。
こちらの弁天様は日野七福神の札所本尊で、御朱印は通年授与されているようです。

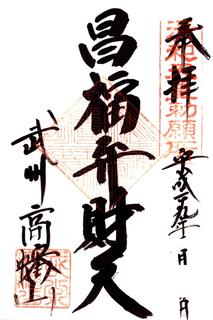
【写真 上(左)】 弁天堂
【写真 下(右)】 御朱印
授与御朱印の「昌福弁財天」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に昌福弁財天の揮毫と三寶印?、左に山号と寺院印、右上に清和天皇祈願所の印が捺されています。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
そらのおとしもの「帰るから」 - 吉田仁美&イカロス(早見沙織)
Afterglow - 黒埼真音
e x - MARINA feat. Hisho (from Bling Journal)
雪の音色 - 佐咲紗花
ナツノカゼ御来光 - 花たん
日野市にある金剛寺は、高幡不動尊の通称で広く知られる多摩屈指の古刹です。
正式には高幡山明王院金剛寺と号し、真言宗智山派別格本山の格式を有します。


開基は大宝年間(701年)以前、あるいは奈良時代、行基菩薩の開基とも伝えられ、平安時代に慈覚大師円仁が清和天皇の勅願により東関鎮護の霊場と定めて不動堂を建立し、不動明王をご安置されたのが始まりとされます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 手水舎
京王線「高幡不動」駅徒歩5分と交通の便がいいこともあって、参詣の人波が絶えない大寺です。
多摩丘陵が多摩川(浅川)に裾を落とす聖蹟桜ヶ丘から高幡不動にかけては、寺院が点在するところで、なかでも高幡不動尊は別格の規模を誇ります。
関東三大不動のひとつで、古くは「火防の不動尊」、また都内有数の交通安全祈願所であり、新選組副長、土方歳三の菩提寺としても知られるなど、参拝客を集める要素に事欠きません。
駅から門前にかけて、そして山内も賑わいをみせていますが、真言宗関東十一檀林の談義所として歴史を刻み、多摩丘陵の山気が降りてくるパワースポット的立地もあってか、どこか稟とした空気を感じます。


【写真 上(左)】 賑わう参道
【写真 下(右)】 土方歳三像


【写真 上(左)】 交通安全祈願殿
【写真 下(右)】 五重塔
真言宗の名刹だけに数多くの札所を兼ね、拝受できる御朱印書の種類も多いですが、これまたWeb情報でも内容が錯綜しています。
今回、ほぼ全容が明らかになった感じがするので、これまで3回の参拝で拝受できた御朱印をご紹介してみます。
なお、こちらの授与所は奥殿裏手の寺務局(納経所)1ヶ所で、週末などはすこぶる混雑します。(平日でも番号札制のようです。)
札所として、関東三十六不動尊霊場9番、多摩新四国八十八ヶ所霊場88番、武相二十八不動尊霊場28番、関東百八地蔵尊霊場100番、東国花の寺百ヶ寺霊場7番、日野七福神(弁財天)については御朱印を授与されています。
武玉八十八ヶ所霊場50番札所でもありますが、こちらは古い霊場で多くの札所は多摩新四国八十八ヶ所霊場に継承されている模様なので、おそらくこの霊場での御朱印は授与されていないと思われます。
ちなみに、多摩新四国八十八ヶ所霊場の霊場会とみられる龍華会本部は金剛寺内におかれ、金剛寺が中心的な役割を果たしていることがうかがわれます。
また、他所では入手がむずかしい多摩新四国八十八ヶ所霊場の公式ガイドブック(平成4年8月刊)もこちらの寺務局で入手できました。
このガイドには御本尊が記され、ふつうはこちらが札所本尊(御朱印尊格)となるようですが、金剛寺の「御本尊」欄は、「大日如来・不動明王」という含みのある記載で、拝受した御朱印尊格は不動明王でした。
札所ではない御本尊系の御朱印としては、御本尊大日如来、そして弘法大師の尊格御朱印を拝受できます。
これだけ種類があると、いわゆる「ご朱印ください!オファー」(札所や尊格指定なしで1つだけ拝受希望の場合)の御朱印はどうなるのかと思いますが、Web検索してみると、どうやら多摩新四国八十八ヶ所霊場の御朱印(尊格:不動明王)が授与されているようです。
やはり、ふつうの参拝客は「高幡不動尊にお参り」だと思うので、不動明王の御朱印となるのでしょう。(なぜ関東三十六不動ではなく多摩新四国なのかは不明。お大師様のお参りも忘れずに、ということでしょうか。)
【高幡不動尊の仏堂と御朱印】
仏堂については各種資料に詳しいのでざっくりと。
公式Webの「境内ご案内」
http://www.takahatafudoson.or.jp/?page_id=13
■不動堂
室町時代建立とされる堂々たる仁王門をくぐった正面。こちらはじつに鎌倉時代の建立とされます。お護摩はこちらのお堂で焚かれます。
こちらに御座す新丈六不動三尊は「平成12年から14年にかけて行われた1000年ぶりの修復作業の際、不動明王像不在のため、平安後期の様式を忠実に造立された身代わりの本尊として新たに創られた」(日野市観光協会Web)尊像のようです。


【写真 上(左)】 不動堂(武相不動尊霊場御開帳時)
【写真 下(右)】 回向柱と宝輪閣(お札所).
■奥殿
重要文化財の丈六不動三尊の他、数多くの文化財が収蔵されています。
高幡不動尊の札所御朱印は不動明王が尊格のものが多いですが、その札所尊格はこちらの丈六不動三尊と思われます。
不動堂の新丈六不動三尊は「身代わりの(札所)本尊」であり、先(2017年5月)の武相二十八不動尊霊場御開帳では、不動堂前に回向柱が立ち、縁の綱が不動堂内の新丈六不動三尊のお手に繋がり、さらに不動堂後ろ戸から伸びた縁の綱を奥殿向拝正面で受けそこからお手綱が下がっていました。この縁の綱が奥殿の丈六不動三尊のお手に繋がっていた模様です。
ここから拝察するに、やはり、不動堂・奥殿両堂のお不動様にお参りするのが筋のような気がします。


【写真 上(左)】 奥殿(武相不動尊霊場御開帳時)
【写真 下(右)】 奥殿の縁の綱


【写真 上(左)】 お手綱
【写真 下(右)】 奥殿の扁額
不動明王が御朱印尊格となる御朱印は、関東三十六不動尊霊場9番、多摩新四国八十八ヶ所霊場88番、武相二十八不動尊霊場28番、東国花の寺百ヶ寺霊場7番です。
御本尊が札所本尊となられる例の多い多摩新四国霊場、東国花の寺霊場でも、札所本尊(御朱印尊格)は不動明王でした。
なお、金剛寺の御本尊は大日如来のようです。
〔関東三十六不動尊霊場〕


【写真 上(左)】 専用納経帳の御朱印
【写真 下(右)】 御朱印帳揮毫の御朱印
授与御朱印の「不動明王」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・不動明王の揮毫と御寶印、左に召請光童子の印と山号と寺院印、右上に関東三十六不動尊霊場第9番の札所印が捺されています。
〔多摩新四国八十八ヶ所霊場(通常)〕

授与御朱印の「不動明王」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・不動明王の揮毫と御寶印、左に山号と寺院印、右上に多摩新四国第88番の札所印と「弘法大師御作」が揮毫されています。
〔多摩新四国八十八ヶ所霊場(結願)〕

多摩新四国八十八ヶ所霊場を結願したときの御朱印です。
専用納経帳ではなく、御朱印帳に拝受しています。
中央に不動明王の種子(カン)、「不動明王」の揮毫と御寶印(種子カン/蓮華座+火焔宝珠)、左に山号、寺号と寺院印、右上に多摩新四国第88番の札所印が揮毫されています。
結願で申告したためか、左上に「結願所」の印判とその横に「第八十八番」の揮毫をいただいています。
〔武相二十八不動尊霊場〕

授与御朱印の「厄除不動尊」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・厄除不動尊の揮毫と御寶印、左に結願所印、山号、寺号と寺院印、右上に武相不動尊第28番の札所印と酉年開帳の御開帳印が捺されています。
〔東国花の寺百ヶ寺霊場〕

授与御朱印の「不動明王」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・不動明王の揮毫と御寶印、左に山号と寺院印、右上に東国花の寺百ヶ寺の札所印と「弘法大師御作」が揮毫されています。
■大日堂
主参道に入り山手に向かうと山門があり、こちらをくぐると高幡山の総本堂、大日堂です。
山門右手には五部権現社が御座します。
金剛寺は正面と向かって左手が小高く、左手の高みは「不動ヶ丘」と呼ばれているようです。


【写真 上(左)】 大日堂山門
【写真 下(右)】 五部権現社
御本尊、大日如来が御座します。有名な鳴り龍もこの堂内にありますが、不動堂まわりにくらべると参拝客はすくなく、落ちついたただずまいとなっています。


【写真 上(左)】 大日堂
【写真 下(右)】 大日堂向拝


【写真 上(左)】 大日堂扁額
【写真 下(右)】 御朱印
授与御朱印の「大日如来」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・大日如来の揮毫と三寶印?、左に山号、寺号と寺院印、右上に清和天皇祈願所の印と鳴り龍の揮毫があります。
■大師堂
大日堂から五重塔に向かうと、聖天堂、大師堂、虚空蔵院と並びます。
寺内でも落ちつきのある不動ヶ丘中腹の高台で、じっくりとお参りができます。


【写真 上(左)】 大師堂参道
【写真 下(右)】 多摩新四国霊場の札所板


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂と聖天堂
弘法大師の御朱印は、こちらの参拝の証とみるべきでしょうか。
大師堂は専用の参道をもち、参道脇には多摩新四国八十八ヶ所霊場88番の札所板が掲げられていました。



【写真 上(左)】 御朱印
【写真 下(右)】 ご縁日の御朱印
授与御朱印の「弘法大師」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・弘法大師の揮毫と三寶印?、左に山号、寺号と寺院印、右上に山内八十八ヶ所巡拝の印が捺されています。
■千躰地蔵堂
五重塔の地下には無料休憩所があり、その横が千躰地蔵尊のお堂となっています。
目立たないお堂ですが弘法大師像、欄間彫刻など複数の見どころ(お参りどころ)があります。
こちらは関東百八地蔵尊霊場100番の札所となります。
なお、大日堂内にも北条氏ゆかりの延命地蔵尊が御座しますが、関東百八地蔵尊霊場ガイドブックには札所本尊が千躰地蔵尊と書かれ、寺務局でお伺いしても千躰地蔵尊とのお答えがあったので間違いないと思います。


授与御朱印の「千体地蔵尊」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に種子・千体地蔵尊の揮毫と三寶印?、左に山号、寺号と寺院印、右上に関東百八地蔵尊第100番札所の札所印が捺されています。
■弁天堂
土方歳三像と交通安全祈願殿のあいだに弁天堂があります。弁天池にかかる赤い橋をわたっての参拝です。
こちらの弁天様は日野七福神の札所本尊で、御朱印は通年授与されているようです。

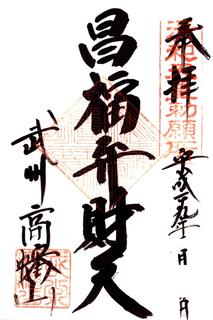
【写真 上(左)】 弁天堂
【写真 下(右)】 御朱印
授与御朱印の「昌福弁財天」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。
中央に昌福弁財天の揮毫と三寶印?、左に山号と寺院印、右上に清和天皇祈願所の印が捺されています。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
そらのおとしもの「帰るから」 - 吉田仁美&イカロス(早見沙織)
Afterglow - 黒埼真音
e x - MARINA feat. Hisho (from Bling Journal)
雪の音色 - 佐咲紗花
ナツノカゼ御来光 - 花たん
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 首都圏の札所と御朱印
少し内容を補強したのでリニューアルUPします。(20181002)
-----------------------------------
20160630UP
このところまったく更新がなくて申し訳ありません。
仕事があいかわらずなのと、寺社巡り(御朱印収集)に向かってしまったもので・・・。
御朱印は週末や仕事の合間(笑)に、かなり集めました。
もともと温泉巡りの前は、寺社巡りが趣味?だったので、ひとたび火がつくと抑えようがありませぬ。
とくに集めているのはお寺のもので、これは札所(霊場)の状況を押さえていないとうまく集めることができません。
札所(霊場)ごとにとりまとめたWebページはすばらしいものがいくつもあるので、「身近なエリアでどれだけ集められるか」という視点から、今後エリア毎にまとめていきたいと思います。
(別ブログを立ち上げようかとも思いましたが、当面このかたちでいきます。各地に温泉寺、温泉神社があったり、西国、坂東、秩父百観音巡礼のお礼参りは別所温泉の北向観音だったりで、もともと温泉と寺社はなじみが深いし、温泉と札所(霊場)巡りをあわせてレポすることも考えています。)
【 温泉にゆかりのある寺院と御朱印 】
●別所温泉北向観音堂


●熱海 温泉寺

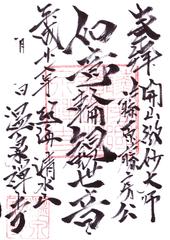
●清河寺(人気日帰り温泉「清河寺温泉」の地名の由来となるお寺)

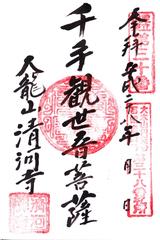
■ 御朱印収集のボーダーライン
近年、御朱印収集が大きなブームとなっています。
休日など、メジャーな寺社では女性を中心に受付窓口に長々と行列ができることもめずらしくありません。
大きな寺社では専用受付窓口があり、見本なども置いてあるので、手順的にはお守りやお札を求めるのと大差ありません。
ところが、少し小さめの寺社(とくにお寺)になるとそうはいきません。
専用の受付所がないので、原則、庫裡のベルを押しお寺の方をお呼びして授与をお願いすることになります。


【写真 上(左)】 浅草寺の朱印所(納経所)案内
【写真 下(右)】 川越喜多院の朱印所(納経所)案内
お寺によっては複数の御朱印を授与されるところがあるので、自分がどの尊格(=仏さま)、あるいは霊場の御朱印を拝受したいのか、事前に明確にしておく必要があります。
また、本堂内に上げていただけるお寺もあり、灯明をお入れいただき、その場で御朱印をお書きいただくということも・・・。
本来御朱印は納経や読経の証なので、こうなると読経、ないし勤行のひとつもあげないとどうにも収まらない局面となります。(数珠持参必須)
(なお、観光寺院や大きな寺社であっても、参拝(奉拝)もせずに御朱印のみをいただくことは「御朱印スタンプラリー」といわれ、心ない行為とされます。)
なので、このような「ベル押し系」のお寺は、御朱印初心者にとって大きなカベ(=御朱印収集のボーダーライン)となって立ちはだかります。
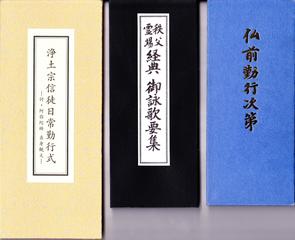
経本・勤行式
これからご紹介するお寺の9割以上は「ベル押し系」のお寺なので、拝受にあたってはここらへんの心構えが必要かと思います。
これまでの経験(数少ないですが)からすると、すくなくとも関東周辺では開経偈、般若心経、十句観音経、御本尊御真言(密教系)、光明真言(同)、御宝号(真言宗系)、六字名号(浄土教系)、普廻向などを宗派や御本尊に応じて唱えられればおおむね問題ないようにも思いました。
■ 宗派と御朱印
代表的な霊場である弘法大師霊場(八十八ヶ所)はお大師さまゆかりの札所を巡るため、おおむね真言宗系の寺院となります。
これに対して観音霊場(三十三ヶ所ないし三十四ヶ所)は観音さまを巡るため多彩な宗派のお寺が参画し、とくに、曹洞宗や臨済宗が目立ちます。(ちなみにメジャーな秩父観音霊場の札所の多くは曹洞宗となっています。)
天台宗は、薬師霊場や地蔵霊場などの札所が多いような感じがしています。
浄土宗にも円光大師霊場や関東十六壇林(巡り)などがありますが、札所の数は多くなく御朱印はややいただきにくくなっています。
(浄土)真宗系では宗旨諸々のこともあり、授与の事例は少なくなっています。
また、日蓮宗・法華宗系では、七福神巡りなどで授与する御朱印と御首題を明確に区別しており、授与にあたって独自の流儀もあるようなので、御首題の拝受には留意が必要です。
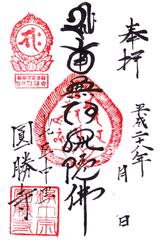
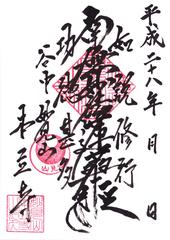

【写真 上(左)】 浄土宗の六字名号「南無阿弥陀佛」/駒込 圓勝寺
【写真 中(中)】 日蓮宗の御首題/谷中 本立寺
【写真 下(右)】 日蓮宗の御朱印/千葉中山 法華経寺
■ 霊場(札所)と御朱印
お寺であればあまねく御朱印をいただけるかというとそういうことはなく、むしろ御朱印を授与されるお寺は少数派ではないかと思います。
↑のように宗派ごとの対応のちがいもあるし、授与に比較的積極的な宗派のお寺でもいただけないことは多々あります。
檀家寺(観光寺院でも霊場札所でもないお寺)では、まずいただけないと考えた方がいいと思います。
(それ以前に関係者以外境内立ち入り不可のお寺も少なくない。)
これに対し、比較的敷居が低いのは、霊場札所のお寺です。
【 霊場を示す扁額や銘板 】


【写真 上(左)】 新四国相馬霊場第六十七番/柏 東海寺(布施弁天)薬師堂
【写真 下(右)】 関東八十八ヶ所第四十一番・東国花の寺百ヶ寺/茨城常総 無量寺
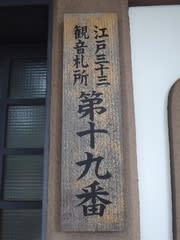
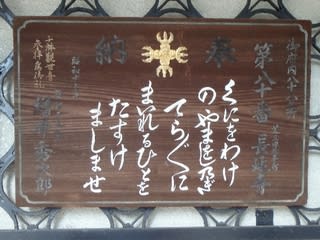
【写真 上(左)】 江戸三十三観音札所第十九番/杉並 東圓寺
【写真 下(右)】 御府内八十八ヶ所第八十番/三田 長延寺
霊場とは一定の尊格ゆかりの札所(お寺)を定めた参拝コースで、これを巡ることを巡礼、札所巡りなどといいます。大きなお寺はたいてい複数の霊場の札所となっています。
札所はお遍路さんなど檀家以外の参拝も見込んでいるため、御朱印を受けやすい傾向があります。
なので、御朱印収集ではこの札所(霊場)を回ることが基本となります。

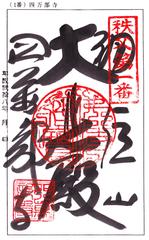
【写真 上(左)】 秩父三十四ヶ所観音霊場の第一番札所(発願寺) 四萬部寺(秩父)
【写真 下(右)】 四萬部寺の御朱印


【写真 上(左)】 御府内八十八ヶ所の第一番札所(発願寺) 高野山東京別院(高輪)
【写真 下(右)】 高野山東京別院の御朱印
(江戸三十三観音第二十九番、関東八十八ヶ所特別霊場の札番が併せて捺されています。)
メジャー霊場札所の多くでは、さして困難なく御朱印を拝受することができますが、むずかしいのは廃れた霊場やマイナーな霊場の札所です。
古い霊場で4つや5つもの重複札所になっていても、いまは御朱印を授与されていないお寺はざらにあります。
このようなお寺については、直接伺うか、あるいは諸先輩方のWeb情報を手がかりにしていくしか方法がありません。
こういうマニアックかつ流動的な情報は基本印刷物にはなじまないので、Web情報がすこぶる貴重なものとなります。
(本来、御朱印授与の有無で札所への参拝を決めるのは邪道だとは思いますが、古いものを含めるとあまりにも多くの札所があるので、どうしてもこのような流れになりがちか?)
■ 札所御朱印の例
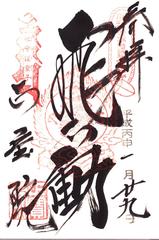
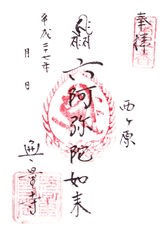

【写真 上(左)】 関東三十六不動尊霊場/台東 正宝院(飛不動尊)
【写真 中(中)】 江戸六阿弥陀/西ヶ原 無量寺
【写真 下(右)】 秩父十三佛霊場/小鹿野 宝円寺
■ 札所御朱印の例(希少霊場)


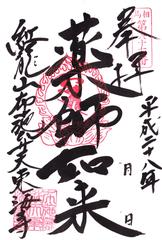
【写真 上(左)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所/青梅 金剛寺
【写真 中(中)】 足立坂東(北)三十三観音霊場/さいたま市西区 慈眼寺
【写真 下(右)】 新四国相馬霊場/柏 東海寺(布施弁天)薬師堂
代表的な霊場として弘法大師霊場(八十八ヶ所)と観音霊場(三十三ヶ所ないし三十四ヶ所)があり、他にも薬師、地蔵、不動、阿弥陀、十三佛、十二支守り本尊など多くの霊場があります。
大きなお寺では複数の札所を兼ねることが多いため、いきおい拝受可能なご朱印も多くなります。
これに加えて七福神巡りが絡んでくることもあり、パズル状態となるお寺も少なくありません。
いまは廃れてしまった霊場や一旦廃れたものの復活気味な霊場、また同じ霊場でも札所(お寺)によって対応の差があることも多く、御朱印収集を重ねるにつれ、おのずと霊場(札所)にも精通していくという流れになります。
このところ、御朱印授与の有無にかかわらず札所であれば参拝するようになり、廃寺や無住のお寺以外ではほとんど御朱印授与のお伺いをしていますが、マイナー霊場札所の対応は本当にまちまちで、御朱印だけでなく貴重な霊場の資料をいただけるお寺さんがある一方、霊場札所であることを認識されていないお寺さんも少なからずあります。
まったくの出たとこ勝負で、このあたりは、あたりまえに御朱印が拝受できるメジャー霊場にはない面白さ(?)があります。
■重複札所と御朱印の例-1(船尾山 等覚院 柳澤寺(群馬県榛東村))

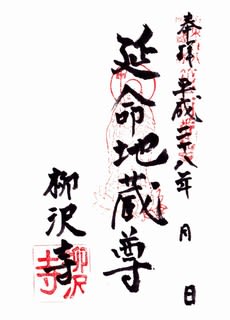
1.延命地蔵尊 / 関東百八地蔵尊霊場第34番
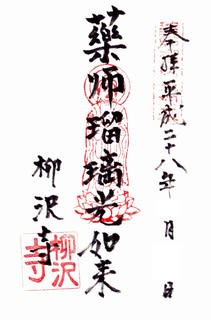
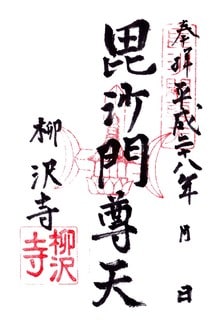
2.薬師瑠璃光如来 / 関東九十一薬師霊場第46番
3.毘沙門尊天 / 上州七福神(毘沙門天)
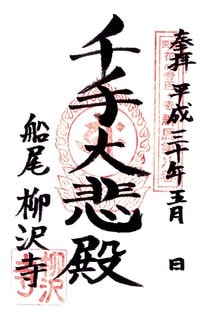
4.千手大悲殿(千手観世音菩薩) / 東国花の寺百ヶ寺霊場 群馬第8番
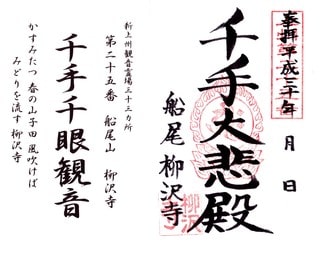

5.千手大悲殿(千手観世音菩薩) / 上州三十三観音霊場第25番
■重複札所と御朱印の例-2(子生山 東福寺(横浜市鶴見区鶴見))
じつに11もの札所印を連ねています。

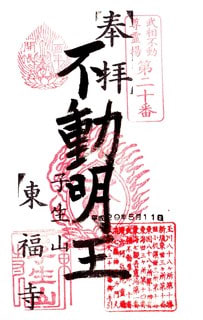
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
Erato - 志方あきこ
地上に降りるまでの夜 - 今井美樹
-----------------------------------
20160630UP
このところまったく更新がなくて申し訳ありません。
仕事があいかわらずなのと、寺社巡り(御朱印収集)に向かってしまったもので・・・。
御朱印は週末や仕事の合間(笑)に、かなり集めました。
もともと温泉巡りの前は、寺社巡りが趣味?だったので、ひとたび火がつくと抑えようがありませぬ。
とくに集めているのはお寺のもので、これは札所(霊場)の状況を押さえていないとうまく集めることができません。
札所(霊場)ごとにとりまとめたWebページはすばらしいものがいくつもあるので、「身近なエリアでどれだけ集められるか」という視点から、今後エリア毎にまとめていきたいと思います。
(別ブログを立ち上げようかとも思いましたが、当面このかたちでいきます。各地に温泉寺、温泉神社があったり、西国、坂東、秩父百観音巡礼のお礼参りは別所温泉の北向観音だったりで、もともと温泉と寺社はなじみが深いし、温泉と札所(霊場)巡りをあわせてレポすることも考えています。)
【 温泉にゆかりのある寺院と御朱印 】
●別所温泉北向観音堂


●熱海 温泉寺

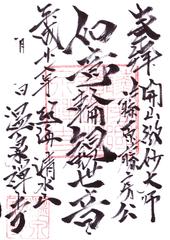
●清河寺(人気日帰り温泉「清河寺温泉」の地名の由来となるお寺)

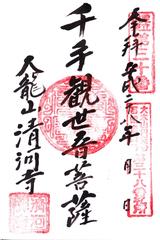
■ 御朱印収集のボーダーライン
近年、御朱印収集が大きなブームとなっています。
休日など、メジャーな寺社では女性を中心に受付窓口に長々と行列ができることもめずらしくありません。
大きな寺社では専用受付窓口があり、見本なども置いてあるので、手順的にはお守りやお札を求めるのと大差ありません。
ところが、少し小さめの寺社(とくにお寺)になるとそうはいきません。
専用の受付所がないので、原則、庫裡のベルを押しお寺の方をお呼びして授与をお願いすることになります。


【写真 上(左)】 浅草寺の朱印所(納経所)案内
【写真 下(右)】 川越喜多院の朱印所(納経所)案内
お寺によっては複数の御朱印を授与されるところがあるので、自分がどの尊格(=仏さま)、あるいは霊場の御朱印を拝受したいのか、事前に明確にしておく必要があります。
また、本堂内に上げていただけるお寺もあり、灯明をお入れいただき、その場で御朱印をお書きいただくということも・・・。
本来御朱印は納経や読経の証なので、こうなると読経、ないし勤行のひとつもあげないとどうにも収まらない局面となります。(数珠持参必須)
(なお、観光寺院や大きな寺社であっても、参拝(奉拝)もせずに御朱印のみをいただくことは「御朱印スタンプラリー」といわれ、心ない行為とされます。)
なので、このような「ベル押し系」のお寺は、御朱印初心者にとって大きなカベ(=御朱印収集のボーダーライン)となって立ちはだかります。
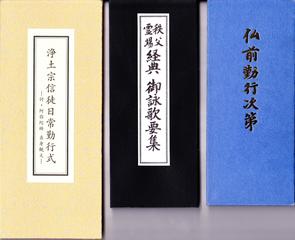
経本・勤行式
これからご紹介するお寺の9割以上は「ベル押し系」のお寺なので、拝受にあたってはここらへんの心構えが必要かと思います。
これまでの経験(数少ないですが)からすると、すくなくとも関東周辺では開経偈、般若心経、十句観音経、御本尊御真言(密教系)、光明真言(同)、御宝号(真言宗系)、六字名号(浄土教系)、普廻向などを宗派や御本尊に応じて唱えられればおおむね問題ないようにも思いました。
■ 宗派と御朱印
代表的な霊場である弘法大師霊場(八十八ヶ所)はお大師さまゆかりの札所を巡るため、おおむね真言宗系の寺院となります。
これに対して観音霊場(三十三ヶ所ないし三十四ヶ所)は観音さまを巡るため多彩な宗派のお寺が参画し、とくに、曹洞宗や臨済宗が目立ちます。(ちなみにメジャーな秩父観音霊場の札所の多くは曹洞宗となっています。)
天台宗は、薬師霊場や地蔵霊場などの札所が多いような感じがしています。
浄土宗にも円光大師霊場や関東十六壇林(巡り)などがありますが、札所の数は多くなく御朱印はややいただきにくくなっています。
(浄土)真宗系では宗旨諸々のこともあり、授与の事例は少なくなっています。
また、日蓮宗・法華宗系では、七福神巡りなどで授与する御朱印と御首題を明確に区別しており、授与にあたって独自の流儀もあるようなので、御首題の拝受には留意が必要です。
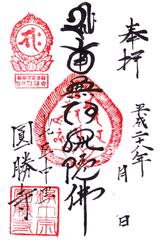
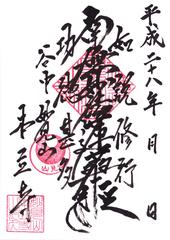

【写真 上(左)】 浄土宗の六字名号「南無阿弥陀佛」/駒込 圓勝寺
【写真 中(中)】 日蓮宗の御首題/谷中 本立寺
【写真 下(右)】 日蓮宗の御朱印/千葉中山 法華経寺
■ 霊場(札所)と御朱印
お寺であればあまねく御朱印をいただけるかというとそういうことはなく、むしろ御朱印を授与されるお寺は少数派ではないかと思います。
↑のように宗派ごとの対応のちがいもあるし、授与に比較的積極的な宗派のお寺でもいただけないことは多々あります。
檀家寺(観光寺院でも霊場札所でもないお寺)では、まずいただけないと考えた方がいいと思います。
(それ以前に関係者以外境内立ち入り不可のお寺も少なくない。)
これに対し、比較的敷居が低いのは、霊場札所のお寺です。
【 霊場を示す扁額や銘板 】


【写真 上(左)】 新四国相馬霊場第六十七番/柏 東海寺(布施弁天)薬師堂
【写真 下(右)】 関東八十八ヶ所第四十一番・東国花の寺百ヶ寺/茨城常総 無量寺
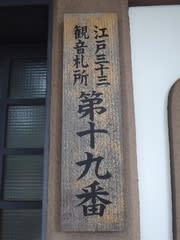
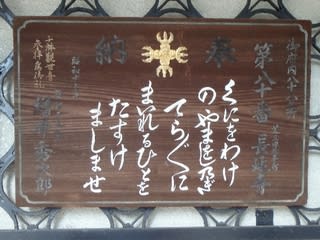
【写真 上(左)】 江戸三十三観音札所第十九番/杉並 東圓寺
【写真 下(右)】 御府内八十八ヶ所第八十番/三田 長延寺
霊場とは一定の尊格ゆかりの札所(お寺)を定めた参拝コースで、これを巡ることを巡礼、札所巡りなどといいます。大きなお寺はたいてい複数の霊場の札所となっています。
札所はお遍路さんなど檀家以外の参拝も見込んでいるため、御朱印を受けやすい傾向があります。
なので、御朱印収集ではこの札所(霊場)を回ることが基本となります。

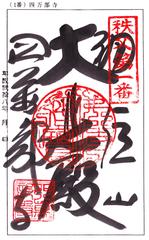
【写真 上(左)】 秩父三十四ヶ所観音霊場の第一番札所(発願寺) 四萬部寺(秩父)
【写真 下(右)】 四萬部寺の御朱印


【写真 上(左)】 御府内八十八ヶ所の第一番札所(発願寺) 高野山東京別院(高輪)
【写真 下(右)】 高野山東京別院の御朱印
(江戸三十三観音第二十九番、関東八十八ヶ所特別霊場の札番が併せて捺されています。)
メジャー霊場札所の多くでは、さして困難なく御朱印を拝受することができますが、むずかしいのは廃れた霊場やマイナーな霊場の札所です。
古い霊場で4つや5つもの重複札所になっていても、いまは御朱印を授与されていないお寺はざらにあります。
このようなお寺については、直接伺うか、あるいは諸先輩方のWeb情報を手がかりにしていくしか方法がありません。
こういうマニアックかつ流動的な情報は基本印刷物にはなじまないので、Web情報がすこぶる貴重なものとなります。
(本来、御朱印授与の有無で札所への参拝を決めるのは邪道だとは思いますが、古いものを含めるとあまりにも多くの札所があるので、どうしてもこのような流れになりがちか?)
■ 札所御朱印の例
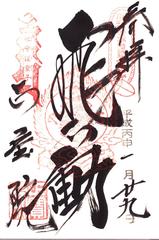
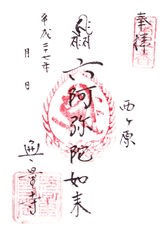

【写真 上(左)】 関東三十六不動尊霊場/台東 正宝院(飛不動尊)
【写真 中(中)】 江戸六阿弥陀/西ヶ原 無量寺
【写真 下(右)】 秩父十三佛霊場/小鹿野 宝円寺
■ 札所御朱印の例(希少霊場)


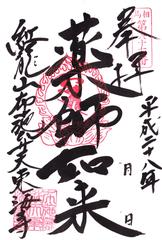
【写真 上(左)】 奥多摩新四国霊場八十八ヶ所/青梅 金剛寺
【写真 中(中)】 足立坂東(北)三十三観音霊場/さいたま市西区 慈眼寺
【写真 下(右)】 新四国相馬霊場/柏 東海寺(布施弁天)薬師堂
代表的な霊場として弘法大師霊場(八十八ヶ所)と観音霊場(三十三ヶ所ないし三十四ヶ所)があり、他にも薬師、地蔵、不動、阿弥陀、十三佛、十二支守り本尊など多くの霊場があります。
大きなお寺では複数の札所を兼ねることが多いため、いきおい拝受可能なご朱印も多くなります。
これに加えて七福神巡りが絡んでくることもあり、パズル状態となるお寺も少なくありません。
いまは廃れてしまった霊場や一旦廃れたものの復活気味な霊場、また同じ霊場でも札所(お寺)によって対応の差があることも多く、御朱印収集を重ねるにつれ、おのずと霊場(札所)にも精通していくという流れになります。
このところ、御朱印授与の有無にかかわらず札所であれば参拝するようになり、廃寺や無住のお寺以外ではほとんど御朱印授与のお伺いをしていますが、マイナー霊場札所の対応は本当にまちまちで、御朱印だけでなく貴重な霊場の資料をいただけるお寺さんがある一方、霊場札所であることを認識されていないお寺さんも少なからずあります。
まったくの出たとこ勝負で、このあたりは、あたりまえに御朱印が拝受できるメジャー霊場にはない面白さ(?)があります。
■重複札所と御朱印の例-1(船尾山 等覚院 柳澤寺(群馬県榛東村))

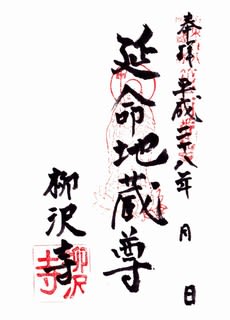
1.延命地蔵尊 / 関東百八地蔵尊霊場第34番
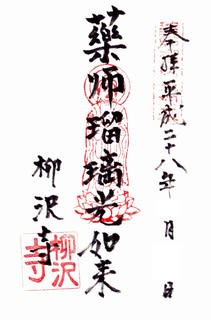
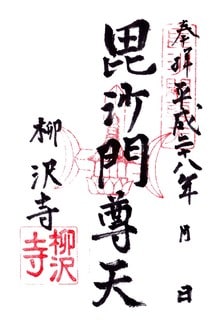
2.薬師瑠璃光如来 / 関東九十一薬師霊場第46番
3.毘沙門尊天 / 上州七福神(毘沙門天)
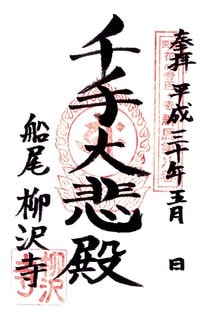
4.千手大悲殿(千手観世音菩薩) / 東国花の寺百ヶ寺霊場 群馬第8番
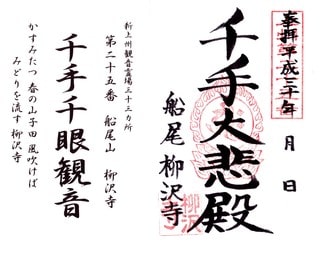

5.千手大悲殿(千手観世音菩薩) / 上州三十三観音霊場第25番
■重複札所と御朱印の例-2(子生山 東福寺(横浜市鶴見区鶴見))
じつに11もの札所印を連ねています。

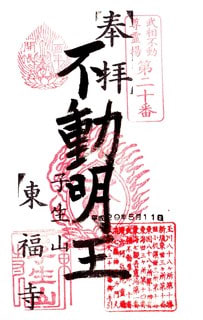
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
Erato - 志方あきこ
地上に降りるまでの夜 - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 根岸古寺めぐり
都内で御朱印集めを重ねていくと、古刹が集まっているのに不思議と御朱印授与情報が少ないエリアがあることが判ってきます。
その多くは真宗がメインのエリアで、これは教義上からみてもいたしかたないところでしょう。
これとは別に歴史ある札所が集まっていながら、御朱印授与情報が思うようにとれない地域があります。
台東区根岸エリアはその代表例といえましょう。
根岸は江戸期から知られた寺町で、かつては豊島郡金杉村根岸と呼ばれていました。
荒川辺八十八ヶ所、弘法大師御府内二十一ヶ所、江戸東方三十三観音、江戸東方四十八地蔵など古い霊場の札所は集まるものの、現役の御府内八十八箇所、豊島八十八ヶ所、江戸三十三観音などの霊場札所がないこと、加えて七福神札所をもたないことなどが、御朱印を拝受しにくい背景にあるかと思います。
ところが、ここ根岸には「根岸古寺めぐり」という9箇寺からなる寺院巡りのコースがあって、専用スタンプ(集印)帳方式で集印できるというのです。
Webで検索すると確かに「猫の足あと(東京寺社案内)」さんや「ニッポンの霊場」さんのWebに情報が載っています。
第1番 東光山 長命院 薬王寺の薬師如来 台東区根岸5-18-5
第2番 大空庵の虚空蔵菩薩 台東区根岸5-8-12
第3番 佛迎山 往生院 安楽寺の阿弥陀如来 台東区根岸4-1-3
第4番 東国山 中養院 西念寺の一刀三礼三尊佛 台東区根岸3-13-17
第5番 鐡砂山 観音院 世尊寺の大日如来 台東区根岸3-13-22
第6番 補陀洛山 千手院の千手観世音 台東区根岸3-12-48
第7番 法住山 要伝寺の六曼茶羅 台東区根岸3-4-14
第8番 寶鏡山 円光寺の釈迦牟尼佛 台東区根岸3-11-4
第9番 関妙山 善性寺の釈迦牟尼佛 荒川区東日暮里5-41-14
しかし、この専用スタンプ帳は画像検索でまったくヒットせず、どういうものか皆目不明でした。今回一念発起 (^^; してこの集印を結願したので、ご紹介してみます。
なお、御朱印(御首題)を拝受できたお寺さんもいくつかありますので、併せてご紹介します。
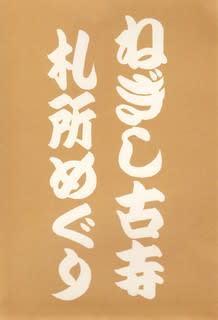

【写真 上(左)】 専用スタンプ(集印)帳の表紙
【写真 下(右)】 同 裏表紙

専用スタンプ(集印)帳とスタンプ(集印)
根岸は西を荒川区東日暮里、東を台東区下谷にはさまれた南北に細長い街区です。
寺院の少ない東日暮里から根岸に流れてくる参拝客は稀でしょう。
下谷は鬼子母神(真源寺)をはじめとする下谷七福神の札所や三島神社、小野照崎神社などもある御朱印エリア。寺社巡りの参詣者は概ね下谷で止まってしまうため、その奥の根岸にはなかなか足を向けにくいという状況があるかと思われます。
根岸へのアプローチ駅は三ノ輪(メトロ日比谷線・都営荒川線)、入谷(メトロ日比谷線)、JRの鶯谷ないしは日暮里となります。
大寺と整備された広幅員道、狭い路地と戸建住戸が複雑に入り混じる変わった感じの街区で、路地に迷い込むといきなり方向感を失うので要注意です。
一応札番が打たれているので、1番から順にご紹介していきます。
第1番
東光山 長命院 薬王寺 天台宗 台東区根岸5-18-5
御本尊:薬師如来 札所御縁佛?:背向地蔵尊
東都七薬師霊場6番、東都北部三十三観音霊場19番


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 背向地蔵尊


【写真 上(左)】 第一番の札所板
【写真 下(右)】 扁額
天海僧正開山と伝わり、東叡山寛永寺の末寺とされます。
御本尊の薬師如来は眼病に霊験あらたかとされ、日光街道に背を向けて安置される背面地蔵尊も知られています。
発願寺でスタンプ帳を入手しやすいと思われたここからスタートしましたが、見込みどおり無事ゲット。ただし現在、巡る人はきわめて少ないようです。
スタンプは庫裡にていただきました。併せて想定外の御朱印も拝受できました。ただしご住職は日々ご多忙のようで、原則不授与ながら今回たまたまタイミングが合ったのでいただけたのかもしれません。
境内には「根岸第一番札所」の札番が掲出されていました。
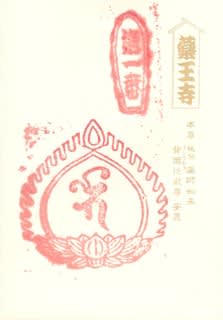
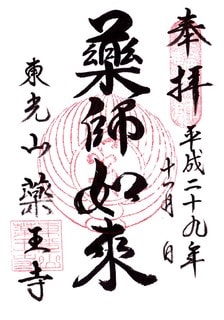
【根岸古寺めぐりの集印】
主印は薬師如来の種子「バイ」の御宝印(蓮華座+火炎宝珠)。右上に「第一番」の札所印。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
【薬王寺の御朱印】
御朱印帳に直接豪快な筆致の揮毫をいただけました。
中央に薬師如来の種子「バイ」の御宝印(宝珠)と揮毫、右上に三輪薬師の印判、左に山号・寺号と寺院印の捺印があります。
第2番
大空庵 真言宗霊雲寺派 台東区根岸5-18-5
御本尊:不詳 札所御縁佛?:虚空蔵菩薩
「根岸古寺めぐり」のなかでもっとも情報の少ないお寺さんです。
狭い路地を登っていったやや小高い一画に忽然とあらわれます。
小さなお堂ですが、「根岸第二番札所」の札番が掲出されているのですぐにそれとわかります。


【写真 上(左)】 こぢんまりとしたお堂です
【写真 下(右)】 お堂正面

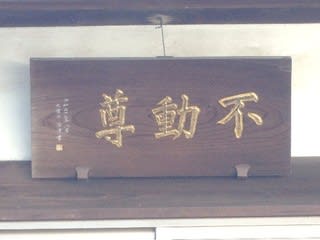
【写真 上(左)】 第二番の札所板
【写真 下(右)】 扁額
スタンプはお堂から少し離れた塀の脇にあります。
気づかずに隣の庫裡でお呼びすると、大黒さん?にスタンプを捺していただけました。
お堂の扁額は「不動尊」となっていますが、虚空蔵菩薩も堂内に御座されるそうです。
御朱印の有無についてはお伺いしませんでした。

【根岸古寺めぐりの集印】
主印は虚空蔵菩薩の種子「タラク」と寺院印が一体となった御宝印(火炎宝珠)。右上に「第二番」の札所印。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
第3番
佛迎山 往生院 安楽寺 浄土宗 台東区根岸4-1-3
御本尊:阿弥陀如来 札所御縁佛?:開運子育地蔵尊
江戸東方三十三観音霊場30番、江戸東方四十八地蔵霊場7番、近世江戸三十三観音霊場8番、坂東写東都三十三観音霊場23番、東都北部三十三観音霊場14番、江都三十三観音霊場5番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
複数の古い霊場の札所を兼ねており、山門から本堂までの距離をみてもかなりの大寺であったことが伺われます。
スタンプは庫裡にていただきました。併せてこちらでも想定外の御朱印を拝受できました。こちらのご住職も日々ご多忙のようで、大黒さんは「ちょうどいいタイミングで参拝にこられてよかった。」と仰られていました。
ご住職も大黒さんもおだやかでたいへん親切な対応をいただきました。感謝・合掌。
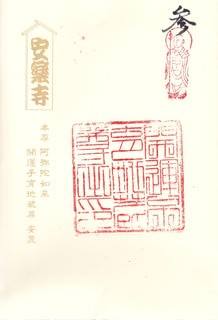

【根岸古寺めぐりの集印】
主印はおそらく開運子育地蔵尊(確証なし)の印。右上にお地蔵様のお姿印と「参」(第三番」をあらわす)の揮毫。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
【安楽寺の御朱印】
御朱印帳に直接揮毫をいただけました。
中央に三宝印とご本尊阿彌陀如来の揮毫、右上にお地蔵様のお姿印、左には山号・寺号とおそらく開運子育地蔵尊(確証なし)の捺印があります。
第4番
東国山 中養院 西念寺 浄土宗 台東区根岸3-13-17
御本尊:阿弥陀如来 札所御縁佛?:阿弥陀如来(一刀三礼三尊佛)
江戸東方四十八地蔵霊場6番


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
深川霊巌寺の末寺で、眼病に霊験あらたかな眼洗い地蔵尊で知られているようです。
スタンプは地蔵尊のよこに設置されています。
尊格・寺院名入のスタンプも用意され、セルフ捺印で御朱印?もいただけます。
セルフ捺印式集印の場合、お寺さんのお手を煩わすことがないので、お昼時でも参拝でき時間を有効に使える利点?がありますね。
なお、「根岸古寺めぐり」のスタンプ一式(朱肉やケース)は各寺統一されたもので、事務局が発足時に一括手配し、各札所に配られた可能性が高いです。

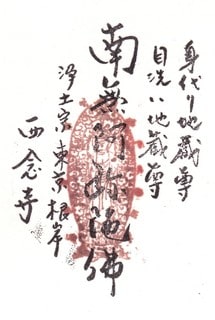
【根岸古寺めぐりの集印】
主印はおそらく施無畏与願印の阿弥陀如来立像のお姿印(不明瞭で確証なし)。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
【西念寺の御朱印】(セルフ捺印)
中央に施無畏与願印の阿弥陀如来立像のお姿印(不明瞭で確証なし)と南無阿弥陀仏の六字名号。右上に身代わり地蔵尊と目洗い地蔵尊の印判。左に宗派・寺号の捺印があります。
第5番
鐡砂山 観音院 世尊寺 真言宗豊山派 台東区根岸3-13-22
御本尊:大日如来 札所御縁佛?:子育地蔵尊 六地蔵の念仏車
荒川辺八十八ヶ所霊場1番、弘法大師御府内二十一ヶ所霊場12番


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 第五番札所板


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 御朱印所
今回、もっとも気になっていたお寺です。
豪族、豊島氏が応安5(1372)年創建したという古刹で御朱印状拝領の名刹でもあります。
文化年間(1804~)開創とされる荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番(発願寺)ですから、江戸期にはこのエリアで主導的な役割を担っていたことが伺われます。
山内はさすがに広めで、古色を帯びた大師堂、御本尊大日如来、お大師様の御遺告所蔵など、真言密教の保守本流的なお寺のようにも思われます。
また、弘法大師御府内二十一ヶ所霊場の札所でもあり、密教ファン?には多くの見どころがあります。
庫裡に伺い御朱印授与につきお伺いしましたが、揮毫のものは授与されておらず、古寺めぐりのスタンプにて、とのことでした。
たしかに、スタンプは御宝印で寺院名も捺せ、別に古寺めぐりの札番印(つぶれ気味だが)もありますから御朱印とみることもできるかもしれません。
スタンプは子育地蔵尊のよこに設置されています。境内に「根岸第五番札所」の札番も掲出されています。
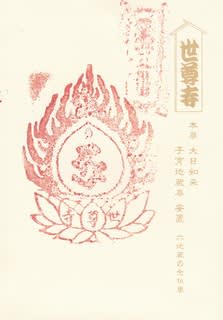
【根岸古寺めぐりの集印】
主印(蓮華座+火炎宝珠)の種子はやや不明瞭ですが、金剛界大日如来の荘厳体種子(五点具足婆字)「バーンク」と思われます。右上に不明瞭ながら「第五番」の札所印。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
第6番
補陀洛山 千手院 真言宗豊山派 台東区根岸3-12-48
御本尊:千手千眼観世音菩薩 札所御縁佛?:千手千眼観世音菩薩
荒川辺八十八ヶ所霊場88番、大東京百観音霊場28番、江戸東方三十三観音霊場29番


【写真 上(左)】 門
【写真 下(右)】 五智堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
文禄4(1595)年創建とされる古刹。緑豊かな山内はよく整備され、「下町の花のお寺」としても知られているようです。参拝客の受入れにも前向きなようで、わかりやすいHPも開設されています。
御本尊千手千眼観世音菩薩の御座される本堂の向かって左手前に五智堂があり、五智如来(阿しゅく如来、多宝如来、大日如来、阿弥陀如来、釈迦如来)が御座します。
HPでは「五智とは、真言密教の教主:大日如来に備わる五つの智慧のことで、五仏に配される。通常、五仏は大日如来、阿しゅく如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来であるが、当院では宝生如来は同体といわれる多宝如来、不空成就如来は同体といわれる釈迦如来に割り当てている。」と解説されています。
こちらは荒川辺八十八ヶ所霊場88番(結願寺)となっています。
荒川辺八十八ヶ所霊場は根岸の世尊寺で発願し、尾久、滝野川、江北、西新井、千住、綾瀬、掘切、八広、向島、亀戸、浅草などの札所を巡ったのち、同じく根岸の千手院で結願する訳で、江戸期に根岸の寺院が特別な地位を占めていたことが窺い知れます。
スタンプは五智堂のよこに設置されています。
ここは以前に御朱印を拝受しておりますので、今回庫裡にはお伺いしませんでした。

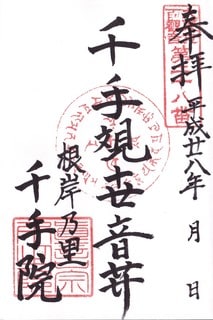
【根岸古寺めぐりの集印】
主印は千手観世音菩薩の種子「キリーク」と寺院印が一体となった御宝印(蓮華座)。右上に不明瞭だが「第六番」の札所印。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
【千手院の御朱印】
中央に梵字を組み合わせた御宝印と千手観世音菩薩の揮毫。右上に「大東京百観音第二十八番」の印判。左下には院号と寺院印の捺印があります。
こちらは根岸古寺めぐり6番、荒川辺八十八ヶ所霊場88番、江戸東方三十三観音霊場29番、を兼ねていますが、いずれも現役のメジャー霊場でなく、また、御本尊が観音様ということもあって、大東京百観音霊場が代表札所として表されているのではないでしょうか。
第7番
法住山 要伝寺 日蓮宗 台東区根岸3-4-14
御本尊:不詳 札所御縁佛?:六曼茶羅


【写真 上(左)】 門から本堂
【写真 下(右)】 扁額
日蓮宗寺院で、小湊誕生寺末のようです。
門の右手に浄行菩薩、その奥、本堂の向かって右には威厳あふれる風貌の日蓮大聖人のお像。その奥に二層の本堂。
境内は広くはないものの、趣があります。
こちらは以前に御首題を拝受しているので2度目の参拝となります。
スタンプは庫裡での捺印となります。
やはり現在、この寺めぐりをしている人は稀らしく、捺印される印判を迷われている感じがありましたが、無事拝受できました。
御首題をいただいたときも感じましたが、応対はとても親切です。

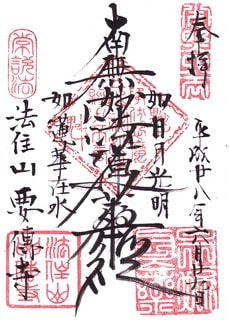
【根岸古寺めぐりの集印】
主印はすみません、不勉強でよくわかりませんが、御首題でいただいたものと同じ印だと思われます。左下に寺院名の印判。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
【要伝寺の御首題】
日蓮宗寺院なので御首題となります。御首題帳に揮毫をいただきました。
第8番
寶鏡山 円光寺 臨済宗妙心寺派 台東区根岸3-11-4
御本尊:釈迦牟尼佛 札所御縁佛?:禁酒地蔵
江戸三十三ヶ所弁財天霊場3番、弁財天百社参り65番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
「根岸古寺めぐり」唯一の禅寺です。
下町らしい細い路地に面し、山門は閉まっているのでいささか敷居は高いですが、間違いなく古寺めぐりの一寺なので臆することなく通用門から突入。
緑豊かな風趣ある境内。各所に羅漢さんがおられます。
本堂横には、禁酒を祈願する?、禁酒地蔵が御座しました。
スタンプは庫裡にていただきました。なお、御朱印は授与されていないそうです。

【根岸古寺めぐりの集印】
主印は三宝印。その上に寺院印が捺されています。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
第9番
関妙山 善性寺 日蓮宗 荒川区東日暮里5-41-14
御本尊:釈迦牟尼佛 日蓮大聖人 札所御縁佛?:釈迦牟尼佛 日蓮大聖人 不二大黒尊天


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 不二大黒尊天
結願寺はふたつめの日蓮宗寺院です。このお寺のみ住所が荒川区東日暮里でやや離れているので、1日結願をめざす場合はネックになるかもしれません。(というか、各寺ともご不在率が高そうなので、そもそも1日結願はむずかしい感じも・・・。)
日暮里駅そばで交通は至便です。
六代将軍徳川家宣公の生母長昌院の菩提寺で、家宣公の弟君松平清武公が隠棲され、しばしば将軍のお成りもあったとされて寺格が高そうです。
名横綱双葉山、石橋湛山元首相の墓所でもあるようです。
境内には安土桃山時代の作とも伝わる不二大黒天像も御座します。
日蓮宗東京都北部宗務所を務められているので日々ご多忙のようですが、スタンプと御首題(書置)は無事拝受できました。


【根岸古寺めぐりの集印】
主印は不二大黒尊天のお姿印。その上に寺院印の印判。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
【善性寺の御首題】
日蓮宗寺院なので御首題となります。書置の御首題を拝受しました。
なお、根岸ではこの他に、真言宗智山派の圓明山 宝福寺 西蔵院(台東区根岸3-12-38)の大日如来の御朱印もいただいています。
こちらは荒川辺八十八ヶ所霊場2番の札所で、根岸寺町の中心に位置する古刹ですが、どうして「根岸古寺めぐり」に参画していないかは不明です。

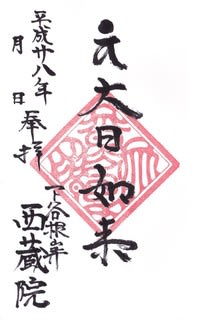
【写真 上(左)】 西蔵院
【写真 下(右)】 西蔵院の御朱印
今回の「根岸古寺めぐり」でナゾの多かった根岸エリアの寺院の御朱印状況が大分あきらかになってきました。
それにしても、最新情報がとれずほとんどあきらめていたこの寺巡りが、いまでも全寺集印して結願可能なことにはびっくりしました。
ただし、専用集印帳も相当年季入った感じだし、各寺の印判も疲れてきているものが目立ちます。札所さんでも半ば忘れられているような現況では、おそらくどちらも更新されることはないと思われ、今が貴重なチャンスかもしれません。
なお、老婆心ながら、日蓮宗寺院2寺を含むので、御首題も拝受されたい向きは、事前に御首題帳を用意された方がベターかと思います。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
I've Got a Feeling - Barclay James Harvest
Track No.9, Album: Victims of Circumstance (1984)
消えてしまえたならいいのに、なんて - めありー
YURI 夢を味方に(Yume wo Mikata ni) / Respect 絢香
これ相当な難曲。このくらいビブラート効かせないと最後までもたないかも・・・。
メトロノーム - pazi(ぱじ)
これは凄い。声質といい、ニュアンスの入り方といい、音のキレといいツボだがね
空奏列車がこれだから・・・。ただものじゃないとみた。
その多くは真宗がメインのエリアで、これは教義上からみてもいたしかたないところでしょう。
これとは別に歴史ある札所が集まっていながら、御朱印授与情報が思うようにとれない地域があります。
台東区根岸エリアはその代表例といえましょう。
根岸は江戸期から知られた寺町で、かつては豊島郡金杉村根岸と呼ばれていました。
荒川辺八十八ヶ所、弘法大師御府内二十一ヶ所、江戸東方三十三観音、江戸東方四十八地蔵など古い霊場の札所は集まるものの、現役の御府内八十八箇所、豊島八十八ヶ所、江戸三十三観音などの霊場札所がないこと、加えて七福神札所をもたないことなどが、御朱印を拝受しにくい背景にあるかと思います。
ところが、ここ根岸には「根岸古寺めぐり」という9箇寺からなる寺院巡りのコースがあって、専用スタンプ(集印)帳方式で集印できるというのです。
Webで検索すると確かに「猫の足あと(東京寺社案内)」さんや「ニッポンの霊場」さんのWebに情報が載っています。
第1番 東光山 長命院 薬王寺の薬師如来 台東区根岸5-18-5
第2番 大空庵の虚空蔵菩薩 台東区根岸5-8-12
第3番 佛迎山 往生院 安楽寺の阿弥陀如来 台東区根岸4-1-3
第4番 東国山 中養院 西念寺の一刀三礼三尊佛 台東区根岸3-13-17
第5番 鐡砂山 観音院 世尊寺の大日如来 台東区根岸3-13-22
第6番 補陀洛山 千手院の千手観世音 台東区根岸3-12-48
第7番 法住山 要伝寺の六曼茶羅 台東区根岸3-4-14
第8番 寶鏡山 円光寺の釈迦牟尼佛 台東区根岸3-11-4
第9番 関妙山 善性寺の釈迦牟尼佛 荒川区東日暮里5-41-14
しかし、この専用スタンプ帳は画像検索でまったくヒットせず、どういうものか皆目不明でした。今回一念発起 (^^; してこの集印を結願したので、ご紹介してみます。
なお、御朱印(御首題)を拝受できたお寺さんもいくつかありますので、併せてご紹介します。
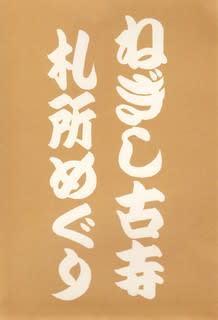

【写真 上(左)】 専用スタンプ(集印)帳の表紙
【写真 下(右)】 同 裏表紙

専用スタンプ(集印)帳とスタンプ(集印)
根岸は西を荒川区東日暮里、東を台東区下谷にはさまれた南北に細長い街区です。
寺院の少ない東日暮里から根岸に流れてくる参拝客は稀でしょう。
下谷は鬼子母神(真源寺)をはじめとする下谷七福神の札所や三島神社、小野照崎神社などもある御朱印エリア。寺社巡りの参詣者は概ね下谷で止まってしまうため、その奥の根岸にはなかなか足を向けにくいという状況があるかと思われます。
根岸へのアプローチ駅は三ノ輪(メトロ日比谷線・都営荒川線)、入谷(メトロ日比谷線)、JRの鶯谷ないしは日暮里となります。
大寺と整備された広幅員道、狭い路地と戸建住戸が複雑に入り混じる変わった感じの街区で、路地に迷い込むといきなり方向感を失うので要注意です。
一応札番が打たれているので、1番から順にご紹介していきます。
第1番
東光山 長命院 薬王寺 天台宗 台東区根岸5-18-5
御本尊:薬師如来 札所御縁佛?:背向地蔵尊
東都七薬師霊場6番、東都北部三十三観音霊場19番


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 背向地蔵尊


【写真 上(左)】 第一番の札所板
【写真 下(右)】 扁額
天海僧正開山と伝わり、東叡山寛永寺の末寺とされます。
御本尊の薬師如来は眼病に霊験あらたかとされ、日光街道に背を向けて安置される背面地蔵尊も知られています。
発願寺でスタンプ帳を入手しやすいと思われたここからスタートしましたが、見込みどおり無事ゲット。ただし現在、巡る人はきわめて少ないようです。
スタンプは庫裡にていただきました。併せて想定外の御朱印も拝受できました。ただしご住職は日々ご多忙のようで、原則不授与ながら今回たまたまタイミングが合ったのでいただけたのかもしれません。
境内には「根岸第一番札所」の札番が掲出されていました。
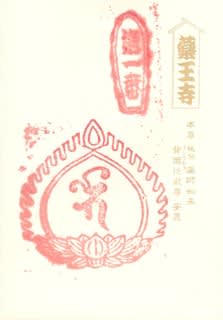
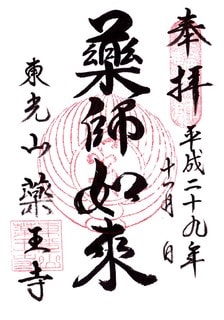
【根岸古寺めぐりの集印】
主印は薬師如来の種子「バイ」の御宝印(蓮華座+火炎宝珠)。右上に「第一番」の札所印。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
【薬王寺の御朱印】
御朱印帳に直接豪快な筆致の揮毫をいただけました。
中央に薬師如来の種子「バイ」の御宝印(宝珠)と揮毫、右上に三輪薬師の印判、左に山号・寺号と寺院印の捺印があります。
第2番
大空庵 真言宗霊雲寺派 台東区根岸5-18-5
御本尊:不詳 札所御縁佛?:虚空蔵菩薩
「根岸古寺めぐり」のなかでもっとも情報の少ないお寺さんです。
狭い路地を登っていったやや小高い一画に忽然とあらわれます。
小さなお堂ですが、「根岸第二番札所」の札番が掲出されているのですぐにそれとわかります。


【写真 上(左)】 こぢんまりとしたお堂です
【写真 下(右)】 お堂正面

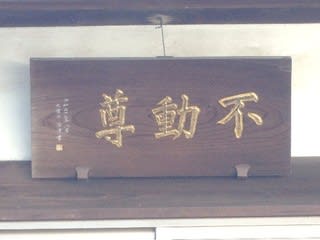
【写真 上(左)】 第二番の札所板
【写真 下(右)】 扁額
スタンプはお堂から少し離れた塀の脇にあります。
気づかずに隣の庫裡でお呼びすると、大黒さん?にスタンプを捺していただけました。
お堂の扁額は「不動尊」となっていますが、虚空蔵菩薩も堂内に御座されるそうです。
御朱印の有無についてはお伺いしませんでした。

【根岸古寺めぐりの集印】
主印は虚空蔵菩薩の種子「タラク」と寺院印が一体となった御宝印(火炎宝珠)。右上に「第二番」の札所印。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
第3番
佛迎山 往生院 安楽寺 浄土宗 台東区根岸4-1-3
御本尊:阿弥陀如来 札所御縁佛?:開運子育地蔵尊
江戸東方三十三観音霊場30番、江戸東方四十八地蔵霊場7番、近世江戸三十三観音霊場8番、坂東写東都三十三観音霊場23番、東都北部三十三観音霊場14番、江都三十三観音霊場5番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
複数の古い霊場の札所を兼ねており、山門から本堂までの距離をみてもかなりの大寺であったことが伺われます。
スタンプは庫裡にていただきました。併せてこちらでも想定外の御朱印を拝受できました。こちらのご住職も日々ご多忙のようで、大黒さんは「ちょうどいいタイミングで参拝にこられてよかった。」と仰られていました。
ご住職も大黒さんもおだやかでたいへん親切な対応をいただきました。感謝・合掌。
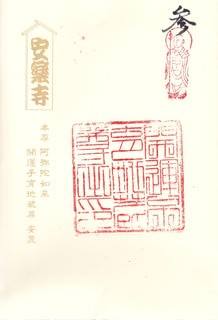

【根岸古寺めぐりの集印】
主印はおそらく開運子育地蔵尊(確証なし)の印。右上にお地蔵様のお姿印と「参」(第三番」をあらわす)の揮毫。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
【安楽寺の御朱印】
御朱印帳に直接揮毫をいただけました。
中央に三宝印とご本尊阿彌陀如来の揮毫、右上にお地蔵様のお姿印、左には山号・寺号とおそらく開運子育地蔵尊(確証なし)の捺印があります。
第4番
東国山 中養院 西念寺 浄土宗 台東区根岸3-13-17
御本尊:阿弥陀如来 札所御縁佛?:阿弥陀如来(一刀三礼三尊佛)
江戸東方四十八地蔵霊場6番


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
深川霊巌寺の末寺で、眼病に霊験あらたかな眼洗い地蔵尊で知られているようです。
スタンプは地蔵尊のよこに設置されています。
尊格・寺院名入のスタンプも用意され、セルフ捺印で御朱印?もいただけます。
セルフ捺印式集印の場合、お寺さんのお手を煩わすことがないので、お昼時でも参拝でき時間を有効に使える利点?がありますね。
なお、「根岸古寺めぐり」のスタンプ一式(朱肉やケース)は各寺統一されたもので、事務局が発足時に一括手配し、各札所に配られた可能性が高いです。

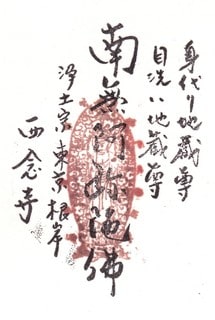
【根岸古寺めぐりの集印】
主印はおそらく施無畏与願印の阿弥陀如来立像のお姿印(不明瞭で確証なし)。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
【西念寺の御朱印】(セルフ捺印)
中央に施無畏与願印の阿弥陀如来立像のお姿印(不明瞭で確証なし)と南無阿弥陀仏の六字名号。右上に身代わり地蔵尊と目洗い地蔵尊の印判。左に宗派・寺号の捺印があります。
第5番
鐡砂山 観音院 世尊寺 真言宗豊山派 台東区根岸3-13-22
御本尊:大日如来 札所御縁佛?:子育地蔵尊 六地蔵の念仏車
荒川辺八十八ヶ所霊場1番、弘法大師御府内二十一ヶ所霊場12番


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 第五番札所板


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 御朱印所
今回、もっとも気になっていたお寺です。
豪族、豊島氏が応安5(1372)年創建したという古刹で御朱印状拝領の名刹でもあります。
文化年間(1804~)開創とされる荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番(発願寺)ですから、江戸期にはこのエリアで主導的な役割を担っていたことが伺われます。
山内はさすがに広めで、古色を帯びた大師堂、御本尊大日如来、お大師様の御遺告所蔵など、真言密教の保守本流的なお寺のようにも思われます。
また、弘法大師御府内二十一ヶ所霊場の札所でもあり、密教ファン?には多くの見どころがあります。
庫裡に伺い御朱印授与につきお伺いしましたが、揮毫のものは授与されておらず、古寺めぐりのスタンプにて、とのことでした。
たしかに、スタンプは御宝印で寺院名も捺せ、別に古寺めぐりの札番印(つぶれ気味だが)もありますから御朱印とみることもできるかもしれません。
スタンプは子育地蔵尊のよこに設置されています。境内に「根岸第五番札所」の札番も掲出されています。
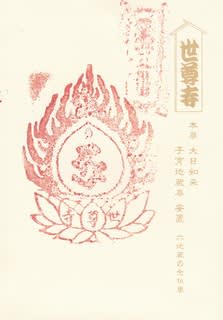
【根岸古寺めぐりの集印】
主印(蓮華座+火炎宝珠)の種子はやや不明瞭ですが、金剛界大日如来の荘厳体種子(五点具足婆字)「バーンク」と思われます。右上に不明瞭ながら「第五番」の札所印。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
第6番
補陀洛山 千手院 真言宗豊山派 台東区根岸3-12-48
御本尊:千手千眼観世音菩薩 札所御縁佛?:千手千眼観世音菩薩
荒川辺八十八ヶ所霊場88番、大東京百観音霊場28番、江戸東方三十三観音霊場29番


【写真 上(左)】 門
【写真 下(右)】 五智堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額
文禄4(1595)年創建とされる古刹。緑豊かな山内はよく整備され、「下町の花のお寺」としても知られているようです。参拝客の受入れにも前向きなようで、わかりやすいHPも開設されています。
御本尊千手千眼観世音菩薩の御座される本堂の向かって左手前に五智堂があり、五智如来(阿しゅく如来、多宝如来、大日如来、阿弥陀如来、釈迦如来)が御座します。
HPでは「五智とは、真言密教の教主:大日如来に備わる五つの智慧のことで、五仏に配される。通常、五仏は大日如来、阿しゅく如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来であるが、当院では宝生如来は同体といわれる多宝如来、不空成就如来は同体といわれる釈迦如来に割り当てている。」と解説されています。
こちらは荒川辺八十八ヶ所霊場88番(結願寺)となっています。
荒川辺八十八ヶ所霊場は根岸の世尊寺で発願し、尾久、滝野川、江北、西新井、千住、綾瀬、掘切、八広、向島、亀戸、浅草などの札所を巡ったのち、同じく根岸の千手院で結願する訳で、江戸期に根岸の寺院が特別な地位を占めていたことが窺い知れます。
スタンプは五智堂のよこに設置されています。
ここは以前に御朱印を拝受しておりますので、今回庫裡にはお伺いしませんでした。

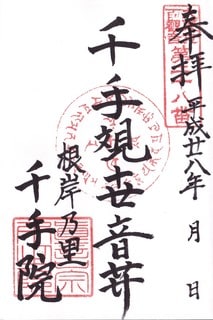
【根岸古寺めぐりの集印】
主印は千手観世音菩薩の種子「キリーク」と寺院印が一体となった御宝印(蓮華座)。右上に不明瞭だが「第六番」の札所印。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
【千手院の御朱印】
中央に梵字を組み合わせた御宝印と千手観世音菩薩の揮毫。右上に「大東京百観音第二十八番」の印判。左下には院号と寺院印の捺印があります。
こちらは根岸古寺めぐり6番、荒川辺八十八ヶ所霊場88番、江戸東方三十三観音霊場29番、を兼ねていますが、いずれも現役のメジャー霊場でなく、また、御本尊が観音様ということもあって、大東京百観音霊場が代表札所として表されているのではないでしょうか。
第7番
法住山 要伝寺 日蓮宗 台東区根岸3-4-14
御本尊:不詳 札所御縁佛?:六曼茶羅


【写真 上(左)】 門から本堂
【写真 下(右)】 扁額
日蓮宗寺院で、小湊誕生寺末のようです。
門の右手に浄行菩薩、その奥、本堂の向かって右には威厳あふれる風貌の日蓮大聖人のお像。その奥に二層の本堂。
境内は広くはないものの、趣があります。
こちらは以前に御首題を拝受しているので2度目の参拝となります。
スタンプは庫裡での捺印となります。
やはり現在、この寺めぐりをしている人は稀らしく、捺印される印判を迷われている感じがありましたが、無事拝受できました。
御首題をいただいたときも感じましたが、応対はとても親切です。

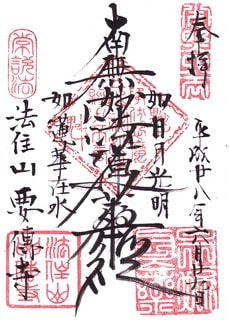
【根岸古寺めぐりの集印】
主印はすみません、不勉強でよくわかりませんが、御首題でいただいたものと同じ印だと思われます。左下に寺院名の印判。
左上に寺院名と尊格の印刷があります。
【要伝寺の御首題】
日蓮宗寺院なので御首題となります。御首題帳に揮毫をいただきました。
第8番
寶鏡山 円光寺 臨済宗妙心寺派 台東区根岸3-11-4
御本尊:釈迦牟尼佛 札所御縁佛?:禁酒地蔵
江戸三十三ヶ所弁財天霊場3番、弁財天百社参り65番


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
「根岸古寺めぐり」唯一の禅寺です。
下町らしい細い路地に面し、山門は閉まっているのでいささか敷居は高いですが、間違いなく古寺めぐりの一寺なので臆することなく通用門から突入。
緑豊かな風趣ある境内。各所に羅漢さんがおられます。
本堂横には、禁酒を祈願する?、禁酒地蔵が御座しました。
スタンプは庫裡にていただきました。なお、御朱印は授与されていないそうです。

【根岸古寺めぐりの集印】
主印は三宝印。その上に寺院印が捺されています。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
第9番
関妙山 善性寺 日蓮宗 荒川区東日暮里5-41-14
御本尊:釈迦牟尼佛 日蓮大聖人 札所御縁佛?:釈迦牟尼佛 日蓮大聖人 不二大黒尊天


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 不二大黒尊天
結願寺はふたつめの日蓮宗寺院です。このお寺のみ住所が荒川区東日暮里でやや離れているので、1日結願をめざす場合はネックになるかもしれません。(というか、各寺ともご不在率が高そうなので、そもそも1日結願はむずかしい感じも・・・。)
日暮里駅そばで交通は至便です。
六代将軍徳川家宣公の生母長昌院の菩提寺で、家宣公の弟君松平清武公が隠棲され、しばしば将軍のお成りもあったとされて寺格が高そうです。
名横綱双葉山、石橋湛山元首相の墓所でもあるようです。
境内には安土桃山時代の作とも伝わる不二大黒天像も御座します。
日蓮宗東京都北部宗務所を務められているので日々ご多忙のようですが、スタンプと御首題(書置)は無事拝受できました。


【根岸古寺めぐりの集印】
主印は不二大黒尊天のお姿印。その上に寺院印の印判。
右上に寺院名と尊格の印刷があります。
【善性寺の御首題】
日蓮宗寺院なので御首題となります。書置の御首題を拝受しました。
なお、根岸ではこの他に、真言宗智山派の圓明山 宝福寺 西蔵院(台東区根岸3-12-38)の大日如来の御朱印もいただいています。
こちらは荒川辺八十八ヶ所霊場2番の札所で、根岸寺町の中心に位置する古刹ですが、どうして「根岸古寺めぐり」に参画していないかは不明です。

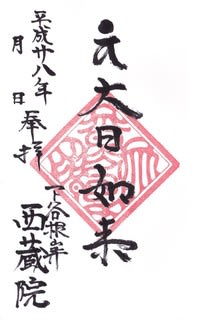
【写真 上(左)】 西蔵院
【写真 下(右)】 西蔵院の御朱印
今回の「根岸古寺めぐり」でナゾの多かった根岸エリアの寺院の御朱印状況が大分あきらかになってきました。
それにしても、最新情報がとれずほとんどあきらめていたこの寺巡りが、いまでも全寺集印して結願可能なことにはびっくりしました。
ただし、専用集印帳も相当年季入った感じだし、各寺の印判も疲れてきているものが目立ちます。札所さんでも半ば忘れられているような現況では、おそらくどちらも更新されることはないと思われ、今が貴重なチャンスかもしれません。
なお、老婆心ながら、日蓮宗寺院2寺を含むので、御首題も拝受されたい向きは、事前に御首題帳を用意された方がベターかと思います。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【 BGM 】
I've Got a Feeling - Barclay James Harvest
Track No.9, Album: Victims of Circumstance (1984)
消えてしまえたならいいのに、なんて - めありー
YURI 夢を味方に(Yume wo Mikata ni) / Respect 絢香
これ相当な難曲。このくらいビブラート効かせないと最後までもたないかも・・・。
メトロノーム - pazi(ぱじ)
これは凄い。声質といい、ニュアンスの入り方といい、音のキレといいツボだがね
空奏列車がこれだから・・・。ただものじゃないとみた。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




