関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第29番 大川山 龍豊院(りゅうほういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町大川278
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡
ここから東伊豆町に入ります。
東伊豆町は温泉のメッカで大川、北川、熱川、片瀬、白田、稲取と名だたる温泉地がつづきます。
温泉好きにとっては、つぎつぎと出てくる日帰り温泉を横目にみながらのきびしい(笑)順路となります。


【写真 上(左)】 大川温泉のサイン
【写真 下(右)】 大川温泉の案内図
大川にある龍豊院は、弘治元年(1555年)、真言宗寺院として建立。慶長年間(1596~1615年)(永禄(1558-1570年のはじめ頃とも)に、最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗、天明元年(1781年)、僧隆峯のときに法地(曹洞宗の寺格)となりました。
明治12年の火災により寺伝等を焼失し、詳細については記録が残っていないようです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「大川村 宮上最勝院末 本尊観世音 弘治元年(1555年)建立 真言ナリ 慶長ノ頃(1596~1615年)改宗ス 最勝院七世笑山ヲ開山トス 天明元年(1781年)僧隆峯法地トス」
山内に樹齢400年と推定される東伊豆町指定天然記念物の 枝垂れ桜があります。
単花弁の純粋種という珍しい品種とのことで、見頃は3月下旬です。
-------------------
伊豆大川温泉は山里に湯宿が点在しているイメージで、龍豊院はそのなかにあります。


【写真 上(左)】 参道から本堂
【写真 下(右)】 本堂
参道階段右手に枝垂れ桜、その奥右に重石塔、左に六地蔵を配して正面本堂は入母屋造桟瓦葺。
向拝に大がかりな唐破風を起こしています。
伊豆の寺院らしく身舎腰壁はなまこ壁、白壁を張り出した花頭窓も意匠的な面白さがあります。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 見事な彫刻-1
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五三の桐、鬼板は経の巻獅子口で五七の桐紋をおいています。
破風両端に立体感ある飾り懸魚をおき、躍動感のある向拝まわりです。


【写真 上(左)】 見事な彫刻-2
【写真 下(右)】 本堂扁額
正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で、見上げには龍に縁取られた豪壮な院号扁額が掲げられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 大川温泉 「磯の湯」の入湯レポ
■ 第30番 金澤山 自性院(じしょういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町奈良本98
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
東伊豆有数の温泉地、熱川にある札所です。
熱川は海側に大規模な温泉街を形成し、高温泉の櫓が湯けむりをあげていますが、山側の奈良本エリアにも多くの泉源があり、自家源泉の湯宿が点在します。
自性院はこの奈良本エリアにあります。
永正元年(1504年)に祖元によって開創、天正七年(1579年)に太田道灌の末孫太田持広が、最勝院十一世佛山長寿を招じて曹洞宗の法治になったと伝わります。
明治初頭の1870年に堂宇が全焼したため、詳細な寺伝は残っていないようです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「奈良本村 宮上最勝院末 本尊薬師 永正中僧祖元創立ス 天正七年(1579年)最勝院十一世佛山法地トス 同村廃瑞雲院ノ本尊薬師当寺ニ安ス」
なお、『豆州志稿』の廃瑞雲院の項には以下のとおりあります。
「野崎牛助家次ト大坂城ヨリノ落人ナリ子孫存ス 明治六年廃寺」
こちらのWeb記事(大坂の陣絵巻)には「(野崎家次)藤堂高虎に仕え500石を与えられる。大坂冬の陣では黒母衣衆として、夏の陣では鉄砲足軽の大将として従軍した。1635年に藤堂家を去り、1638年に死亡。」(同記事より引用)とありますが、大坂の陣(1615年)から20年も藤堂家に仕えたとすると「大坂城ヨリノ落人」とはいえず、別人かもしれません。
なお、自性院の本尊・薬師如来が瑞雲院から遷られた薬師如来であるかは不明です。
-------------------
石柱と階段を構える立派な参道。その先には切妻屋根桟瓦葺の四脚門で大棟に山号をおいています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
前庭芝生の開けた境内。
本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を起こしています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五七の桐と、龍豊院の構成に近いですが鬼板は経の巻獅子口ではありません。


【写真 上(左)】 中備の彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額
正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で両側には花頭窓。見上げには院号扁額が掲げられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
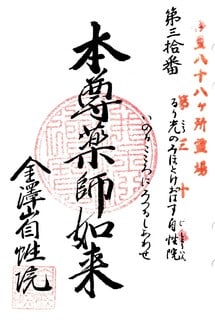

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 熱川温泉「高磯の湯」の入湯レポ(温泉みしゅらん/東伊豆の湯巡り)
■ 第31番 来宮山 東泉院(とうせんいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町白田76
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
渋い名湯を揃え、温泉マニアから一目おかれている白田温泉にある札所です。
北条氏直の外臣であった金指筑後守による開山で元は真言宗の寺院でした。
この金指筑後守が伊勢から来住して明応三年(1494年)に建立、本尊の聖観世音菩薩像は役小角の作と伝わります。
最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗しました。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「白田村 宮上最勝院末 本尊聖観音 開基乃金指筑後守ナリ 後裔尚アリ 最勝院七世の笑山ヲ開山トス」
-------------------
海岸にもほど近い民家の奥に一段高く山内を構えています。
海側からみると、山門と本堂がいいバランスを保っています。


【写真 上(左)】 サイン
【写真 下(右)】 参道
山門はがっしりとした銅板葺の四脚門で、山号扁額を掲げています。
本堂はおそらく寄棟造銅板葺で軒唐破風の向拝を起こしています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 露天


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁、繋ぎ虹梁ともに直線的で装飾はすくなく全体にスクエアな印象で、水柿色の向拝部がいいアクセントになっています。
正面には院号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 白田温泉 「白田川観光ホテル」の入湯レポ
※ 名湯でしたが、残念ながら休業中の情報があります。
■ 第32番 稲取山 善應院(ぜんのういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町稲取400-2
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:稲取八ヶ寺めぐり第4番
授与所:庫裡
「雛のつるし飾り」で有名な稲取の町には札所がふたつあります。
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、草創は嘉吉元年(1441年)で開基は真覚律師、鈴木三位大臣二十五代の子孫、熊野党水軍の鈴木孫七郎繁時の創立で当初は稲昌寺と号する真言宗高野山の末派でした。
元和二年(1616年)に駿州原田(現・富士市原田)永明寺六世(七世とも)大室存道和尚により曹洞宗に改宗して中興、善應院と号を改めました。
中興の大室存道和尚は、宗祖承陽大師十六世の法孫と伝わります。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「稲取村 曹洞宗 駿州原田永明寺末 本尊観世音 本庵ニシテ真言ナリ 駿州原田永明寺六世大室和尚寺主タル時 宗ヲ曹洞ニ改メ中興祖トナル 庵ヲ寺ニ取立ルハ鈴木氏ナル(中略)稲昌寺ト称ス 元和中僧大室曹洞宗トナシ善應院ト号スト」
-------------------
稲取の街中のこみ入ったところにあります。
道沿いが参道入口で、寺号標と豆国霊場八十八ヶ所の札所標。
広くはないですが、すっきりと手入れのいきとどいた山内です。


【写真 上(左)】 寺号標&札所標
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
参道階段をのぼった正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、正面見上げに院号の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 堂内の山号扁額
参拝後、御朱印を乞うと本堂を開けていただけました。
堂内見上げには山号の扁額が掲げられ、向拝上の院号扁額と二重扁額を構成しています。
そのおくには五色の向拝幕が掲げられて、質素な堂前とは対照的な華やぎのある堂内でした。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩
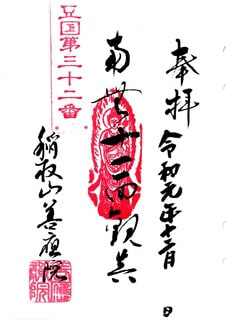

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
稲取は寺社が多く御朱印を介した観光振興に熱心なところで、しばしば御朱印イベントが催されているようです。
また、域内に「稲取八ヶ寺めぐり」というミニ霊場が設定されています。
■ 第33番 見海山 来迎院 正定寺(しょうじょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町稲取833-1-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:稲取八ヶ寺めぐり第6番
授与所:庫裡
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、創立は養和元年(1181年)で当初は合歓木というところにあり真言宗で来迎庵と号しました。
開山は源誉存応観智國師、開基は村木善左衛門とされています。
慶長三年(1598年)、華山和尚が正定寺と号を改め浄土宗に改宗しました。
海辺の寺院で、寛文十年(1670年)、台風の波浪(大津波とも)で堂宇などが流出という記録が残ります。
文化十二年(1815年)、徳本上人が伊豆相模を摂化の途次、当寺に留錫布教と伝わり、御名号一幅を残すといいます。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「稲取村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 養和中ヨリ至德迄ハ合歓木ト云処ニ在テ来迎庵ト云 真言宗ナリ 正長ヨリ文明中迄ハ臨済宗ト為リ 明應二年ニ至リ始テ建長寺ニ隷シ寺号トス 天文ノ末ヨリ永禄迄復真言ニ復リソレヨリ浄土ト為リ 天正ノ頃寺号ヲ正定ト改メ増上寺存應和尚ヲ祖トス 地蔵堂在境内」
伊豆は改宗の寺歴をもつ寺院が多いですが、こちらもめまぐるしい改宗の歴史が伝わります。
・養和年間(1181-1182年)~至德年間(1384-1387年) 真言宗
・正長年間(1428-1429年)~文明年間(1469-1487年) 臨済宗
・明應二年(1493年) 臨済宗建長寺派?
・天文年間(1532-1555年)~永禄年間(1558-1570年) 真言宗
・慶長三年(1598年)~現在 浄土宗
-------------------
稲取港の堤外そばの海べりにあり、「見海山」という山号がぴったりの立地です。
参拝時は北よりの海風が吹きつけていました。


【写真 上(左)】 稲取港
【写真 下(右)】 漁港お約束のぬこ(正定寺境内)


【写真 上(左)】 道祖神-1
【写真 下(右)】 道祖神-2
海側の駐車場から山内までの途中に道祖神のお社があります。
民族学者で歌人でもある折口信夫博士が椿を手草として持つこの道祖神をみて、椿を手にして各地を廻られた八百比丘尼の石像と見立てられたものです。
社前の説明書には「稲取東区の道祖神(伝 八百比丘尼)石像」と記され、背後の公園は「稲取漁港 八百比丘尼公園」です。
社内のいくつかの石像のうち、中央の像が八百比丘尼像とされ、東伊豆町の指定文化財に指定されています。
人魚の肉を食べたことで八百歳の歳月を生きたという八百比丘尼は、各地を巡廻され多くの逸話が残りますが、伊豆ではめずらしいようです。
なお、つつじで有名な青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺は、八百比丘尼の開山と伝わります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鐘楼
山門は南側にあり、柱二本の変わった形状です。その横に立派な鐘楼。
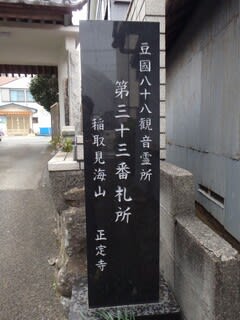

【写真 上(左)】 札所標-1
【写真 下(右)】 札所標-2


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は寄棟ないし宝形造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を構えています。
堂内に仁王像、御内陣の御本尊・阿弥陀如来も向拝から拝めます。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 正定寺大佛
道祖神側には、かなりの大きさの正定寺大仏が御座します。
御朱印は本堂内にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来

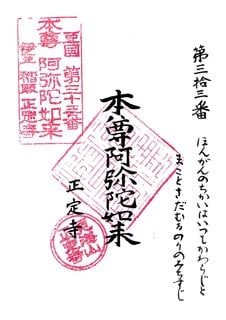
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
数百メートル南の高台には(稲取御鎮座)八幡神社がありますが、当寺との関係(別当)は確認できませんでした。
こちらの八幡神社は頼朝公とのゆかりが深く、頼朝公の守本尊が寄進されたとされ、頼朝公の水垢離の井戸も残ります。
常時かどうかは不明ですが、御朱印も授与されています。
■ 別格旧第31番 宝林山 称念寺(しょうねんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町浜334-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
伊豆八十八ヶ所霊場には2つの別格札所が設定されています。
旧8番の満行山 航浦院と旧31番の宝林山 称念寺です。
霊場札所の入替えがあった場合、旧札所は御朱印授与を止めてしまうケースが多いですが、こちらは2つの札所とも「別格札所」扱いになり御朱印も授与されています。
どうしてこういう状況になっているかはわかりませんが、ほとんどの伊豆八十八ヶ所関連ガイドでこの2つの別格札所は紹介されています。
結願の修禅寺奥の院の御朱印も拝受できるので、この霊場のコンプリート御朱印数は88(通常札所)+2(別格札所)+1(奥の院)で計91となります。
伊豆八十八ヶ所の東伊豆エリアの巡路は、北から海岸沿いを南下するとそのまま札番どおりの順打ちになります。
ところが稲取・河津に至ってこの法則が崩れます。
第32番善應院は第33番正定寺よりも南にあるので、順打ちすると北に戻ることになります。
第34番三養院も第33番稲取からいきなり天城方面(山寄り)に飛び、そこから第35番栖足寺、第36番乗安寺と山側から河津浜に下っていく道程となります。
このような札番構成は、かつて第2番弘道寺から天城越えして河津に入っていた名残かもしれず、旧31番の称念寺も白田の第31番東泉院から距離を置いた河津浜にあります。
称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。
その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。
文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。
しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈り鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せ空に舞い上がりました。
帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。
帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。
このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。
河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に奉安したそうです。
現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。
『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。
永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「濱村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 伊東祐親ノ嫡子川津三郎祐泰 谷津ニ居住シ其邸側ニ一宇ヲ創立シテ稱念庵ト号シ 阿彌陀ノ像ヲ安置ス 寶治中(1247-1249年)僧澄道中興シテ寺ト為ス 今其遺跡ヲ稱念庵屋敷ト云 永禄四年(1562年)誠譽上人ノ時谷津ヨリ此ニ移ス 或云縄地ト 川津祐泰ノ神版及其尊信セシ阿彌陀アリ 寺域有庚申堂」
河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。
祐泰をめぐる情勢については■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3の第27番 稲荷山 東林寺に書きましたので、さらっと抜粋再掲します。
藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。
「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。
非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。
「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。
■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)
-------------------
河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。
国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。


【写真 上(左)】 道沿いの札所案内
【写真 下(右)】 六地蔵
アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。
その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。
彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 向拝扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来
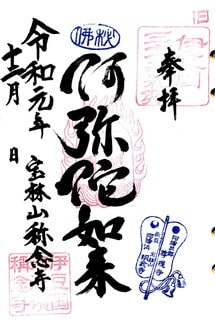

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ
■ 第34番 千手山 三養院(さんよういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町川津筏場807-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
第34番は河津桜や七滝で有名な河津町に位置します。
伊豆有数の観光地で、今井浜、河津、谷津、峰、湯ヶ野、小鍋、七滝、大滝などの名だたる温泉地が点在します。
河津町は伊豆横道三十三観音霊場のメインエリアで、御朱印授与寺院がかなりあります。
伊豆八十八ヶ所霊場の札所も5(うちひとつは別格)を数えます。
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。
開山当初は千手院(庵)と号しました。
天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。
この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。
なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「川津筏場村元矢野 曹洞宗 田方郡南條昌渓院末 本尊釋迦 竺庵和尚(昌渓院開山) 千手庵ヲ創ム 天正十八年(1590年)清水上野守夫妻其子能登守三人 下田城ヨリ逃レ来リ此ニ匿ル 能登守増廣シテ寺ト為ス 三人ヲ養シ故寺号ニ用ウトコレ俗間所傳ノ説ナリ 上野守ハ鵜島城主ナリ 豊臣氏ノ水軍之ヲ攻ム 上野守父子城ヲ棄テヽ遁レ 当所ニテ剃髪スト云 初字杉久保ノ地ニ在リ 寺跡今寺屋敷ト云フ 後現地ニ移ス 清水氏数世ノ神版アリ 清水家ノ墓アリ」
水戸黄門の師である東杲心越禅師(中国関羽将軍の末裔とされる)の筆になる扁額や、塗駕籠などが保存されています。
当山のそばにある「三養院の滝」(Takigirl様)は、かつては「河津七滝」のひとつに数えられていたそうです。
-------------------
峰温泉と湯ヶ野温泉のあいだ、河津川と佐野川の合流点近くで河津浜から天城越えに進んだ一番奥の札所。
第2番弘道寺から天城越えしてくると、最初に廻る南伊豆の札所ということになります。
(第35番の変更(栖足寺→慈眼院)により、最初に出てくる札所は慈眼院となっています。)


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 門柱と本堂
【写真 下(右)】 山内
風通しのよいあかるい高台。
門柱のさきに寄棟造桟葺の均整のとれた本堂。
大棟の意匠が精緻で、妻側には経の巻獅子口も備えています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 本堂
向拝柱はないですが、身舎腰壁と窓の造作が意匠的に呼応して引き締まった印象を与えます。
向拝見上げの扁額は読解できませんでした。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 本堂内
参拝後、庫裡で御朱印を乞うと本堂扉を開けていただけました。
本堂内向拝見上げには「選佛場」(僧の坐禅道場)の扁額が掲げられていました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釋迦如来
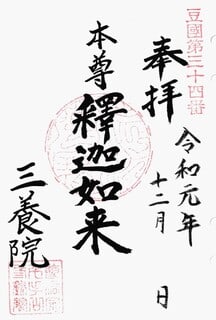
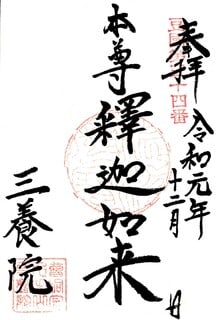
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ
■ (旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町谷津256
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:授与所 or 本堂内
河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。
公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。
徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。
応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。
『豆州志稿』は、第4代鎌倉公方足利持氏(1409-1439年)建立の鐘銘ありと伝えるので、相応の寺格を有していたのかもしれません。
寺号の「栖足」は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」の句よりとったものとされています。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「谷津村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 源持氏建ツト鐘銘ニ見ユ 鎌倉壽福寺開山覺昭禅師ヲ初祖トス 今建長寺ニ隷ス 小田原ノ属國タル時 毎歳六月朔日此寺ヨリ新米ヲ上ケキ」
河童の伝説については、公式Webをご覧ください。
-------------------
行基菩薩開湯の名湯として知られる谷津温泉は、以前から割烹旅館が点在するイメージで温泉街は形成されていません。
その谷津地区の河津川の河畔、「河津桜」の名所にもほど近い場所にあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 河童ののぼり
参道入口に和シックな寺号標。河童の絵入りののぼりが立ち、「河童の寺」をアピールしています。


【写真 上(左)】 河童の銅像
【写真 下(右)】 参道&寺号標
本堂背後に山を背負っていますが、山内は広々としています。
参道左手に河童の銅像。少し先の寺号標には「河童の寺」と刻まれています。
その先右手の小屋は、御朱印授与所のようですが御朱印は本堂内でも授与されているかも。


【写真 上(左)】 授与所
【写真 下(右)】 河童が逃げ込んだ井戸を再現
その先右手には、再現された「河童が逃げ込んだ井戸」。


【写真 上(左)】 河童くん
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂内
正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上に五三の桐の向拝幕をおろしています。
本堂扉は開け放たれ、中で参拝できます。
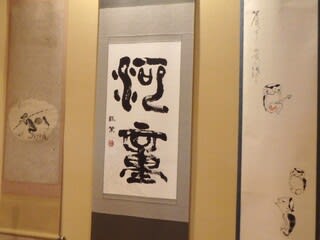

【写真 上(左)】 河童の掛軸
【写真 下(右)】 キュウリのお供え
こちらは個性ある絵御朱印でつとに有名です。
本堂内には絵御朱印の見本がならび、とくに「48種の花札柄御朱印」(書置)は、構図・色合いともにとても綺麗です。
オリジナル御朱印帳も頒布されています。
本堂内の天井絵も美しく彩色されているので、華やかな印象の本堂です。
片隅には河童好物のキュウリもお供えされていました。
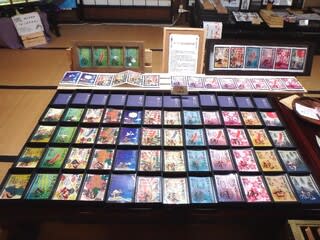

【写真 上(左)】 超カラフルな花札柄御朱印
【写真 下(右)】 天井絵も華やか
こちらは観光地にあり、絵御朱印でも有名なので参拝者が多いと思います。
御朱印授与はたしか本堂内で、ご親切な対応でした。
なお、公式Webによると、「毎週木曜日は住職が研修に参加の為、拝観、御朱印の受付は出来ませんのでご了承下さい。」とのことです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 活潑潑地
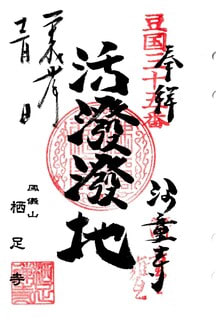

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっています。
公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印
※ 今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から梨本の慈眼院に変更されたようです。
慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますので、つぎ(Vol.5)にUPします。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5へ。
→ ■ 谷津温泉 「薬師の湯」の入湯レポ
【 BGM 】
■ 夏をかさねて - 今井美樹
■ Fantasy - Meiko Nakahara(中原めいこ)
いわゆるひとつのシティ・ポップですね。それにしてもこの再生数って・・・。
■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第29番 大川山 龍豊院(りゅうほういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町大川278
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡
ここから東伊豆町に入ります。
東伊豆町は温泉のメッカで大川、北川、熱川、片瀬、白田、稲取と名だたる温泉地がつづきます。
温泉好きにとっては、つぎつぎと出てくる日帰り温泉を横目にみながらのきびしい(笑)順路となります。


【写真 上(左)】 大川温泉のサイン
【写真 下(右)】 大川温泉の案内図
大川にある龍豊院は、弘治元年(1555年)、真言宗寺院として建立。慶長年間(1596~1615年)(永禄(1558-1570年のはじめ頃とも)に、最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗、天明元年(1781年)、僧隆峯のときに法地(曹洞宗の寺格)となりました。
明治12年の火災により寺伝等を焼失し、詳細については記録が残っていないようです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「大川村 宮上最勝院末 本尊観世音 弘治元年(1555年)建立 真言ナリ 慶長ノ頃(1596~1615年)改宗ス 最勝院七世笑山ヲ開山トス 天明元年(1781年)僧隆峯法地トス」
山内に樹齢400年と推定される東伊豆町指定天然記念物の 枝垂れ桜があります。
単花弁の純粋種という珍しい品種とのことで、見頃は3月下旬です。
-------------------
伊豆大川温泉は山里に湯宿が点在しているイメージで、龍豊院はそのなかにあります。


【写真 上(左)】 参道から本堂
【写真 下(右)】 本堂
参道階段右手に枝垂れ桜、その奥右に重石塔、左に六地蔵を配して正面本堂は入母屋造桟瓦葺。
向拝に大がかりな唐破風を起こしています。
伊豆の寺院らしく身舎腰壁はなまこ壁、白壁を張り出した花頭窓も意匠的な面白さがあります。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 見事な彫刻-1
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五三の桐、鬼板は経の巻獅子口で五七の桐紋をおいています。
破風両端に立体感ある飾り懸魚をおき、躍動感のある向拝まわりです。


【写真 上(左)】 見事な彫刻-2
【写真 下(右)】 本堂扁額
正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で、見上げには龍に縁取られた豪壮な院号扁額が掲げられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 大川温泉 「磯の湯」の入湯レポ
■ 第30番 金澤山 自性院(じしょういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町奈良本98
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡
東伊豆有数の温泉地、熱川にある札所です。
熱川は海側に大規模な温泉街を形成し、高温泉の櫓が湯けむりをあげていますが、山側の奈良本エリアにも多くの泉源があり、自家源泉の湯宿が点在します。
自性院はこの奈良本エリアにあります。
永正元年(1504年)に祖元によって開創、天正七年(1579年)に太田道灌の末孫太田持広が、最勝院十一世佛山長寿を招じて曹洞宗の法治になったと伝わります。
明治初頭の1870年に堂宇が全焼したため、詳細な寺伝は残っていないようです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「奈良本村 宮上最勝院末 本尊薬師 永正中僧祖元創立ス 天正七年(1579年)最勝院十一世佛山法地トス 同村廃瑞雲院ノ本尊薬師当寺ニ安ス」
なお、『豆州志稿』の廃瑞雲院の項には以下のとおりあります。
「野崎牛助家次ト大坂城ヨリノ落人ナリ子孫存ス 明治六年廃寺」
こちらのWeb記事(大坂の陣絵巻)には「(野崎家次)藤堂高虎に仕え500石を与えられる。大坂冬の陣では黒母衣衆として、夏の陣では鉄砲足軽の大将として従軍した。1635年に藤堂家を去り、1638年に死亡。」(同記事より引用)とありますが、大坂の陣(1615年)から20年も藤堂家に仕えたとすると「大坂城ヨリノ落人」とはいえず、別人かもしれません。
なお、自性院の本尊・薬師如来が瑞雲院から遷られた薬師如来であるかは不明です。
-------------------
石柱と階段を構える立派な参道。その先には切妻屋根桟瓦葺の四脚門で大棟に山号をおいています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
前庭芝生の開けた境内。
本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を起こしています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五七の桐と、龍豊院の構成に近いですが鬼板は経の巻獅子口ではありません。


【写真 上(左)】 中備の彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額
正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で両側には花頭窓。見上げには院号扁額が掲げられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来
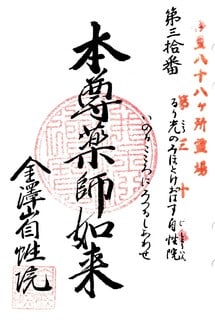

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 熱川温泉「高磯の湯」の入湯レポ(温泉みしゅらん/東伊豆の湯巡り)
■ 第31番 来宮山 東泉院(とうせんいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町白田76
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
渋い名湯を揃え、温泉マニアから一目おかれている白田温泉にある札所です。
北条氏直の外臣であった金指筑後守による開山で元は真言宗の寺院でした。
この金指筑後守が伊勢から来住して明応三年(1494年)に建立、本尊の聖観世音菩薩像は役小角の作と伝わります。
最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗しました。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「白田村 宮上最勝院末 本尊聖観音 開基乃金指筑後守ナリ 後裔尚アリ 最勝院七世の笑山ヲ開山トス」
-------------------
海岸にもほど近い民家の奥に一段高く山内を構えています。
海側からみると、山門と本堂がいいバランスを保っています。


【写真 上(左)】 サイン
【写真 下(右)】 参道
山門はがっしりとした銅板葺の四脚門で、山号扁額を掲げています。
本堂はおそらく寄棟造銅板葺で軒唐破風の向拝を起こしています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 露天


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁、繋ぎ虹梁ともに直線的で装飾はすくなく全体にスクエアな印象で、水柿色の向拝部がいいアクセントになっています。
正面には院号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 白田温泉 「白田川観光ホテル」の入湯レポ
※ 名湯でしたが、残念ながら休業中の情報があります。
■ 第32番 稲取山 善應院(ぜんのういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町稲取400-2
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:稲取八ヶ寺めぐり第4番
授与所:庫裡
「雛のつるし飾り」で有名な稲取の町には札所がふたつあります。
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、草創は嘉吉元年(1441年)で開基は真覚律師、鈴木三位大臣二十五代の子孫、熊野党水軍の鈴木孫七郎繁時の創立で当初は稲昌寺と号する真言宗高野山の末派でした。
元和二年(1616年)に駿州原田(現・富士市原田)永明寺六世(七世とも)大室存道和尚により曹洞宗に改宗して中興、善應院と号を改めました。
中興の大室存道和尚は、宗祖承陽大師十六世の法孫と伝わります。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「稲取村 曹洞宗 駿州原田永明寺末 本尊観世音 本庵ニシテ真言ナリ 駿州原田永明寺六世大室和尚寺主タル時 宗ヲ曹洞ニ改メ中興祖トナル 庵ヲ寺ニ取立ルハ鈴木氏ナル(中略)稲昌寺ト称ス 元和中僧大室曹洞宗トナシ善應院ト号スト」
-------------------
稲取の街中のこみ入ったところにあります。
道沿いが参道入口で、寺号標と豆国霊場八十八ヶ所の札所標。
広くはないですが、すっきりと手入れのいきとどいた山内です。


【写真 上(左)】 寺号標&札所標
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
参道階段をのぼった正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、正面見上げに院号の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 堂内の山号扁額
参拝後、御朱印を乞うと本堂を開けていただけました。
堂内見上げには山号の扁額が掲げられ、向拝上の院号扁額と二重扁額を構成しています。
そのおくには五色の向拝幕が掲げられて、質素な堂前とは対照的な華やぎのある堂内でした。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩
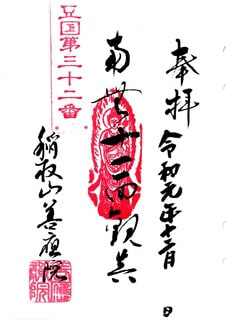

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
稲取は寺社が多く御朱印を介した観光振興に熱心なところで、しばしば御朱印イベントが催されているようです。
また、域内に「稲取八ヶ寺めぐり」というミニ霊場が設定されています。
■ 第33番 見海山 来迎院 正定寺(しょうじょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
東伊豆町稲取833-1-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:稲取八ヶ寺めぐり第6番
授与所:庫裡
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、創立は養和元年(1181年)で当初は合歓木というところにあり真言宗で来迎庵と号しました。
開山は源誉存応観智國師、開基は村木善左衛門とされています。
慶長三年(1598年)、華山和尚が正定寺と号を改め浄土宗に改宗しました。
海辺の寺院で、寛文十年(1670年)、台風の波浪(大津波とも)で堂宇などが流出という記録が残ります。
文化十二年(1815年)、徳本上人が伊豆相模を摂化の途次、当寺に留錫布教と伝わり、御名号一幅を残すといいます。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「稲取村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 養和中ヨリ至德迄ハ合歓木ト云処ニ在テ来迎庵ト云 真言宗ナリ 正長ヨリ文明中迄ハ臨済宗ト為リ 明應二年ニ至リ始テ建長寺ニ隷シ寺号トス 天文ノ末ヨリ永禄迄復真言ニ復リソレヨリ浄土ト為リ 天正ノ頃寺号ヲ正定ト改メ増上寺存應和尚ヲ祖トス 地蔵堂在境内」
伊豆は改宗の寺歴をもつ寺院が多いですが、こちらもめまぐるしい改宗の歴史が伝わります。
・養和年間(1181-1182年)~至德年間(1384-1387年) 真言宗
・正長年間(1428-1429年)~文明年間(1469-1487年) 臨済宗
・明應二年(1493年) 臨済宗建長寺派?
・天文年間(1532-1555年)~永禄年間(1558-1570年) 真言宗
・慶長三年(1598年)~現在 浄土宗
-------------------
稲取港の堤外そばの海べりにあり、「見海山」という山号がぴったりの立地です。
参拝時は北よりの海風が吹きつけていました。


【写真 上(左)】 稲取港
【写真 下(右)】 漁港お約束のぬこ(正定寺境内)


【写真 上(左)】 道祖神-1
【写真 下(右)】 道祖神-2
海側の駐車場から山内までの途中に道祖神のお社があります。
民族学者で歌人でもある折口信夫博士が椿を手草として持つこの道祖神をみて、椿を手にして各地を廻られた八百比丘尼の石像と見立てられたものです。
社前の説明書には「稲取東区の道祖神(伝 八百比丘尼)石像」と記され、背後の公園は「稲取漁港 八百比丘尼公園」です。
社内のいくつかの石像のうち、中央の像が八百比丘尼像とされ、東伊豆町の指定文化財に指定されています。
人魚の肉を食べたことで八百歳の歳月を生きたという八百比丘尼は、各地を巡廻され多くの逸話が残りますが、伊豆ではめずらしいようです。
なお、つつじで有名な青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺は、八百比丘尼の開山と伝わります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 鐘楼
山門は南側にあり、柱二本の変わった形状です。その横に立派な鐘楼。
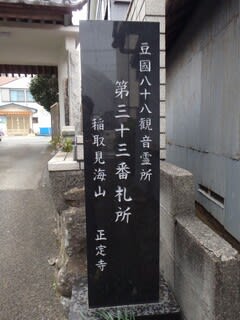

【写真 上(左)】 札所標-1
【写真 下(右)】 札所標-2


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は寄棟ないし宝形造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を構えています。
堂内に仁王像、御内陣の御本尊・阿弥陀如来も向拝から拝めます。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 正定寺大佛
道祖神側には、かなりの大きさの正定寺大仏が御座します。
御朱印は本堂内にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来

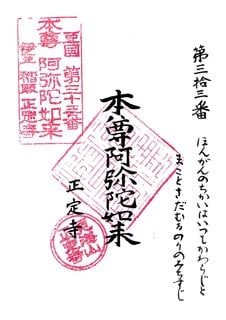
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
数百メートル南の高台には(稲取御鎮座)八幡神社がありますが、当寺との関係(別当)は確認できませんでした。
こちらの八幡神社は頼朝公とのゆかりが深く、頼朝公の守本尊が寄進されたとされ、頼朝公の水垢離の井戸も残ります。
常時かどうかは不明ですが、御朱印も授与されています。
■ 別格旧第31番 宝林山 称念寺(しょうねんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町浜334-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡
伊豆八十八ヶ所霊場には2つの別格札所が設定されています。
旧8番の満行山 航浦院と旧31番の宝林山 称念寺です。
霊場札所の入替えがあった場合、旧札所は御朱印授与を止めてしまうケースが多いですが、こちらは2つの札所とも「別格札所」扱いになり御朱印も授与されています。
どうしてこういう状況になっているかはわかりませんが、ほとんどの伊豆八十八ヶ所関連ガイドでこの2つの別格札所は紹介されています。
結願の修禅寺奥の院の御朱印も拝受できるので、この霊場のコンプリート御朱印数は88(通常札所)+2(別格札所)+1(奥の院)で計91となります。
伊豆八十八ヶ所の東伊豆エリアの巡路は、北から海岸沿いを南下するとそのまま札番どおりの順打ちになります。
ところが稲取・河津に至ってこの法則が崩れます。
第32番善應院は第33番正定寺よりも南にあるので、順打ちすると北に戻ることになります。
第34番三養院も第33番稲取からいきなり天城方面(山寄り)に飛び、そこから第35番栖足寺、第36番乗安寺と山側から河津浜に下っていく道程となります。
このような札番構成は、かつて第2番弘道寺から天城越えして河津に入っていた名残かもしれず、旧31番の称念寺も白田の第31番東泉院から距離を置いた河津浜にあります。
称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。
その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。
文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。
しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈り鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せ空に舞い上がりました。
帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。
帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。
このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。
河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に奉安したそうです。
現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。
『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。
永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「濱村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 伊東祐親ノ嫡子川津三郎祐泰 谷津ニ居住シ其邸側ニ一宇ヲ創立シテ稱念庵ト号シ 阿彌陀ノ像ヲ安置ス 寶治中(1247-1249年)僧澄道中興シテ寺ト為ス 今其遺跡ヲ稱念庵屋敷ト云 永禄四年(1562年)誠譽上人ノ時谷津ヨリ此ニ移ス 或云縄地ト 川津祐泰ノ神版及其尊信セシ阿彌陀アリ 寺域有庚申堂」
河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。
祐泰をめぐる情勢については■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3の第27番 稲荷山 東林寺に書きましたので、さらっと抜粋再掲します。
藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。
「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。
非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。
「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。
■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)
-------------------
河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。
国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。


【写真 上(左)】 道沿いの札所案内
【写真 下(右)】 六地蔵
アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。
その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。
彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 木鼻の獅子
【写真 下(右)】 向拝扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来
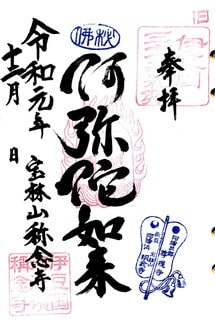

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ
■ 第34番 千手山 三養院(さんよういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町川津筏場807-1
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡
第34番は河津桜や七滝で有名な河津町に位置します。
伊豆有数の観光地で、今井浜、河津、谷津、峰、湯ヶ野、小鍋、七滝、大滝などの名だたる温泉地が点在します。
河津町は伊豆横道三十三観音霊場のメインエリアで、御朱印授与寺院がかなりあります。
伊豆八十八ヶ所霊場の札所も5(うちひとつは別格)を数えます。
現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。
開山当初は千手院(庵)と号しました。
天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。
この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。
なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「川津筏場村元矢野 曹洞宗 田方郡南條昌渓院末 本尊釋迦 竺庵和尚(昌渓院開山) 千手庵ヲ創ム 天正十八年(1590年)清水上野守夫妻其子能登守三人 下田城ヨリ逃レ来リ此ニ匿ル 能登守増廣シテ寺ト為ス 三人ヲ養シ故寺号ニ用ウトコレ俗間所傳ノ説ナリ 上野守ハ鵜島城主ナリ 豊臣氏ノ水軍之ヲ攻ム 上野守父子城ヲ棄テヽ遁レ 当所ニテ剃髪スト云 初字杉久保ノ地ニ在リ 寺跡今寺屋敷ト云フ 後現地ニ移ス 清水氏数世ノ神版アリ 清水家ノ墓アリ」
水戸黄門の師である東杲心越禅師(中国関羽将軍の末裔とされる)の筆になる扁額や、塗駕籠などが保存されています。
当山のそばにある「三養院の滝」(Takigirl様)は、かつては「河津七滝」のひとつに数えられていたそうです。
-------------------
峰温泉と湯ヶ野温泉のあいだ、河津川と佐野川の合流点近くで河津浜から天城越えに進んだ一番奥の札所。
第2番弘道寺から天城越えしてくると、最初に廻る南伊豆の札所ということになります。
(第35番の変更(栖足寺→慈眼院)により、最初に出てくる札所は慈眼院となっています。)


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 門柱と本堂
【写真 下(右)】 山内
風通しのよいあかるい高台。
門柱のさきに寄棟造桟葺の均整のとれた本堂。
大棟の意匠が精緻で、妻側には経の巻獅子口も備えています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 本堂
向拝柱はないですが、身舎腰壁と窓の造作が意匠的に呼応して引き締まった印象を与えます。
向拝見上げの扁額は読解できませんでした。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 本堂内
参拝後、庫裡で御朱印を乞うと本堂扉を開けていただけました。
本堂内向拝見上げには「選佛場」(僧の坐禅道場)の扁額が掲げられていました。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釋迦如来
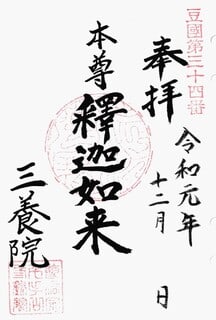
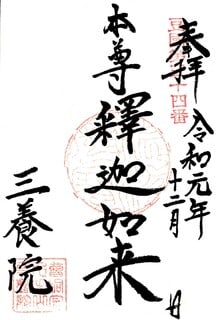
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ
■ (旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
河津町谷津256
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:授与所 or 本堂内
河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。
公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。
徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。
応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。
『豆州志稿』は、第4代鎌倉公方足利持氏(1409-1439年)建立の鐘銘ありと伝えるので、相応の寺格を有していたのかもしれません。
寺号の「栖足」は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」の句よりとったものとされています。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「谷津村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 源持氏建ツト鐘銘ニ見ユ 鎌倉壽福寺開山覺昭禅師ヲ初祖トス 今建長寺ニ隷ス 小田原ノ属國タル時 毎歳六月朔日此寺ヨリ新米ヲ上ケキ」
河童の伝説については、公式Webをご覧ください。
-------------------
行基菩薩開湯の名湯として知られる谷津温泉は、以前から割烹旅館が点在するイメージで温泉街は形成されていません。
その谷津地区の河津川の河畔、「河津桜」の名所にもほど近い場所にあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 河童ののぼり
参道入口に和シックな寺号標。河童の絵入りののぼりが立ち、「河童の寺」をアピールしています。


【写真 上(左)】 河童の銅像
【写真 下(右)】 参道&寺号標
本堂背後に山を背負っていますが、山内は広々としています。
参道左手に河童の銅像。少し先の寺号標には「河童の寺」と刻まれています。
その先右手の小屋は、御朱印授与所のようですが御朱印は本堂内でも授与されているかも。


【写真 上(左)】 授与所
【写真 下(右)】 河童が逃げ込んだ井戸を再現
その先右手には、再現された「河童が逃げ込んだ井戸」。


【写真 上(左)】 河童くん
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂内
正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上に五三の桐の向拝幕をおろしています。
本堂扉は開け放たれ、中で参拝できます。
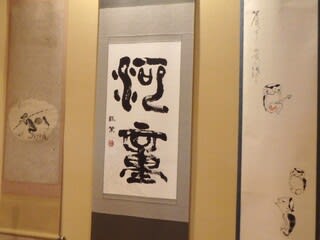

【写真 上(左)】 河童の掛軸
【写真 下(右)】 キュウリのお供え
こちらは個性ある絵御朱印でつとに有名です。
本堂内には絵御朱印の見本がならび、とくに「48種の花札柄御朱印」(書置)は、構図・色合いともにとても綺麗です。
オリジナル御朱印帳も頒布されています。
本堂内の天井絵も美しく彩色されているので、華やかな印象の本堂です。
片隅には河童好物のキュウリもお供えされていました。
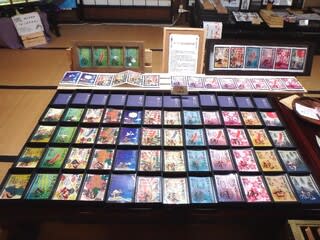

【写真 上(左)】 超カラフルな花札柄御朱印
【写真 下(右)】 天井絵も華やか
こちらは観光地にあり、絵御朱印でも有名なので参拝者が多いと思います。
御朱印授与はたしか本堂内で、ご親切な対応でした。
なお、公式Webによると、「毎週木曜日は住職が研修に参加の為、拝観、御朱印の受付は出来ませんのでご了承下さい。」とのことです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 活潑潑地
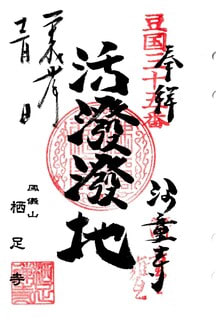

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっています。
公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印
※ 今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から梨本の慈眼院に変更されたようです。
慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますので、つぎ(Vol.5)にUPします。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5へ。
→ ■ 谷津温泉 「薬師の湯」の入湯レポ
【 BGM 】
■ 夏をかさねて - 今井美樹
■ Fantasy - Meiko Nakahara(中原めいこ)
いわゆるひとつのシティ・ポップですね。それにしてもこの再生数って・・・。
■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉殿の御家人
2022/07/18 UP
現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、意外に対象となる寺社がありません。
とくに鎌倉時代初期に開創の寺院はかなりの古刹なので、そうそうみつかるものではありません。
そこで、御家人の範囲を広げることにしました。
ボリュームのある■ 建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩をベースに以下のリストを加えてエリア別にシャッフルしてみました。
なんと計445名になりました。
1.建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩 → 原典(国会図書館D.C)
2.文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)
3.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)
4.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原典(国会図書館D.C)
5.建久元年(1190年)十一月十一日 六條若宮・石淸水八幡宮御參供奉者 → 原典(国会図書館D.C)
原典の『吾妻鏡』は通称表記が多く、表記ゆれも多いのでほとんどパズル状態になりました(笑)。
あくまでも御家人のリストがメインなので、内容については掘り下げておらず、これを保証するものではありません。
かなりの誤認や誤記があるかと思いますが、これについては記事を書いていくなかで整理・訂正していきたいと思います。
なお、このバージョンの内容は下記の方法で収集しました。
1.原則としてWeb検索によりました。
2.検索情報元は史料(『吾妻鏡』『玉葉』など)、物語(『源平盛衰記』『源平闘諍録』など)、系図類(『尊卑文脈』『続群書類従』『新訂寛政重修諸家譜』、各家系図など)、および市町村資料です。
3.ただし市町村資料(現地教育委員会等の掲示含む)は「~といわれています。」「~とみられます。」などの推定調が目立ちました。
4.どうしても調べがつかなかった御家人は末尾にまとめてあります。
それではリストいきます。
なお、表中★がついている御家人は、「十三人の合議制」の構成メンバーです。







■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
---------------------------------
2022/04/29 UP
現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、思いつくままに漫然と書いていくのもどうかと思いましたので、まずは対象者がどれだけいるのか調べてみました。
対象は鎌倉幕府草創期の「御家人」としました。
「御家人」にはどういう人々が名を連ねていたのでしょうか。
Wikipediaによると「鎌倉幕府が成立すると鎌倉殿と主従関係を結び従者となった者を、鎌倉殿への敬意を表す『御』をつけて御家人と呼ぶようになった。」とあります。
鎌倉幕府の記録とされる『吾妻鏡』には、頼朝に従った武者たちを名簿的にあらわした記事がいくつかあります。
たとえば、
1.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原本(国会図書館D.C)
2.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)
鎌倉幕府成立の時期についてはさまざまな説がありますが、文治元年(1185年)が有力説で、1.2の記事はいずれもこれより後です。
またこの時期は1190年代からの有力武家の大粛清前で、多くの武将が顔を揃えています。
1.は公的な行事、2.は出陣リストなので、これをミックスすることで文官・武官、そして武官で奥州出兵に参加しなかった顔ぶれもおさえることができます。
2.には144人の名前が挙げられているのでこちらをベースとし、2.に記載されていない人々を1.から補足するかたちをとりました。
なお、「御家人は(鎌倉殿のもとでは)平等」という建前はありますが、やはり厳然と序列はあったようです。
1.で「列御後人々」にリストされた面々が、2.ではほぼ番号順にならんでいます。
なので、やはりどちらも序列順に記載されたものと思われます。
リストの作成そのものが主目的ではなく、「『鎌倉殿の13人』の御朱印」を書くための整理リスト的なものなので、ネタ元はほとんどWeb検索で深掘りはしていません。
よって間違いや異説もあるかと思いますが、とりあえず概略的に一気にまとめてみました。
※ 表中★マークは「13人の合議制」参画メンバーです。
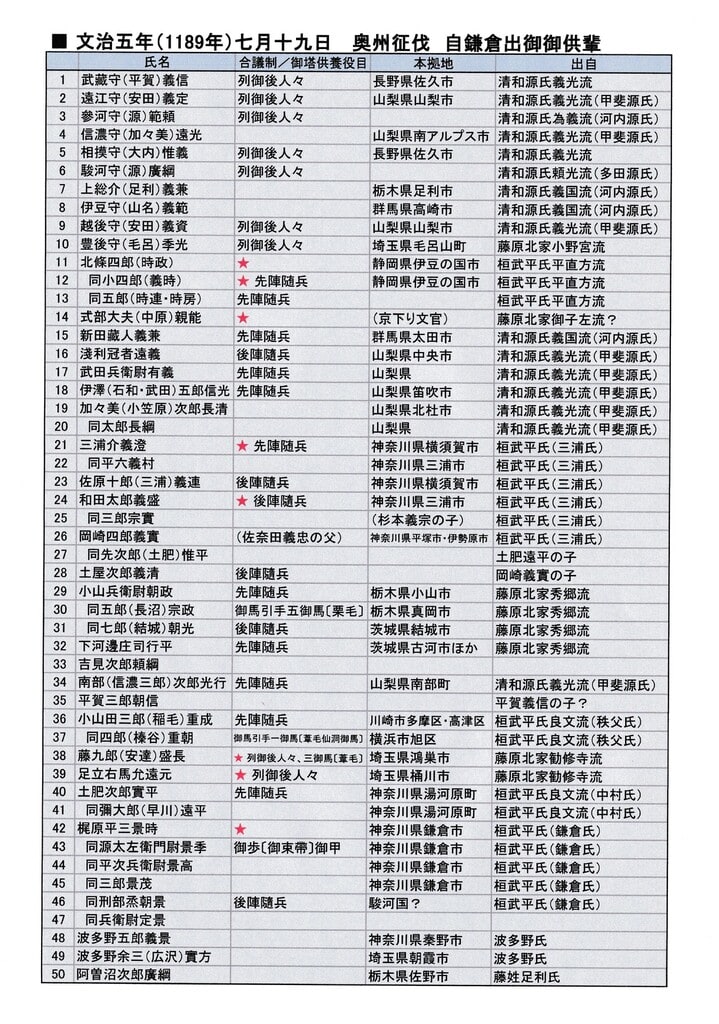



※ 文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩に記載されていない人物のみ
これをみると序列上位はほとんど清和源氏で占められています。
頼朝公の実弟の範頼公の上に信濃源氏の平賀義信、甲斐源氏の安田義定がいます。
また、北條時政の上にも加々美、大内、足利、山名などの錚々たる清和源氏の武将がいます。
もしもこれらの甲斐、信濃、上野・下野の清和源氏が結束して頼朝公と事を構えたら、頼朝公でも、ましてや北条氏でもいかんともしがたかったとみられます。
(誰が主導権を握るかの問題はありますが。)
頼朝公、あるいは北条氏がこれら清和源氏の勢力削減に注力したのは、このような緊迫した力関係があったためとみられます。
じっさい、一時的に粛清によって彼らの力を弱めたとはいえ、鎌倉幕府(北条氏)は、足利氏・新田氏など、清和源氏を中心とした勢力に滅ぼされています。
また、源平合戦は「東国の源氏と西国の平氏のたたかい」と見る向きも多いかと思いますが、上の表をみると「坂東八平氏」と称される桓武平氏の流れ、藤原氏、そして「武蔵七党」といわれる武士団が多いことがわかります。
なので、源平合戦は実質的には西日本の公家的な武士団と東日本の武家的な(主従関係の堅固な)武士団の戦いとみることができるかもしれません。
今後はこの顔ぶれのうち、所縁の寺社の御朱印をいただいている例からUPしていきたいと思います。
(頼朝公に敵対した武将もとりあげます。)
------------------------------
上の表で、本拠地とみられる場所を現在の市町名で載せてみました。
鎌倉周辺に限らず、広く東日本一帯に広がっていることがわかります。
今回のGWで、これらの武将ゆかりの地を回ってみるのも面白いかもしれません。
【 BGM 】
■ By your side - 西野カナ
■ 君がいない世界は切なくて - CHIHIRO feat. KEN THE 390
■ Over and Over - Every Little Thing
■ Butterfly - 木村カエラ(Cover)
■ For Our Days - 川田まみ (LIVE)
現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、意外に対象となる寺社がありません。
とくに鎌倉時代初期に開創の寺院はかなりの古刹なので、そうそうみつかるものではありません。
そこで、御家人の範囲を広げることにしました。
ボリュームのある■ 建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩をベースに以下のリストを加えてエリア別にシャッフルしてみました。
なんと計445名になりました。
1.建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩 → 原典(国会図書館D.C)
2.文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)
3.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)
4.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原典(国会図書館D.C)
5.建久元年(1190年)十一月十一日 六條若宮・石淸水八幡宮御參供奉者 → 原典(国会図書館D.C)
原典の『吾妻鏡』は通称表記が多く、表記ゆれも多いのでほとんどパズル状態になりました(笑)。
あくまでも御家人のリストがメインなので、内容については掘り下げておらず、これを保証するものではありません。
かなりの誤認や誤記があるかと思いますが、これについては記事を書いていくなかで整理・訂正していきたいと思います。
なお、このバージョンの内容は下記の方法で収集しました。
1.原則としてWeb検索によりました。
2.検索情報元は史料(『吾妻鏡』『玉葉』など)、物語(『源平盛衰記』『源平闘諍録』など)、系図類(『尊卑文脈』『続群書類従』『新訂寛政重修諸家譜』、各家系図など)、および市町村資料です。
3.ただし市町村資料(現地教育委員会等の掲示含む)は「~といわれています。」「~とみられます。」などの推定調が目立ちました。
4.どうしても調べがつかなかった御家人は末尾にまとめてあります。
それではリストいきます。
なお、表中★がついている御家人は、「十三人の合議制」の構成メンバーです。







■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
---------------------------------
2022/04/29 UP
現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、思いつくままに漫然と書いていくのもどうかと思いましたので、まずは対象者がどれだけいるのか調べてみました。
対象は鎌倉幕府草創期の「御家人」としました。
「御家人」にはどういう人々が名を連ねていたのでしょうか。
Wikipediaによると「鎌倉幕府が成立すると鎌倉殿と主従関係を結び従者となった者を、鎌倉殿への敬意を表す『御』をつけて御家人と呼ぶようになった。」とあります。
鎌倉幕府の記録とされる『吾妻鏡』には、頼朝に従った武者たちを名簿的にあらわした記事がいくつかあります。
たとえば、
1.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原本(国会図書館D.C)
2.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)
鎌倉幕府成立の時期についてはさまざまな説がありますが、文治元年(1185年)が有力説で、1.2の記事はいずれもこれより後です。
またこの時期は1190年代からの有力武家の大粛清前で、多くの武将が顔を揃えています。
1.は公的な行事、2.は出陣リストなので、これをミックスすることで文官・武官、そして武官で奥州出兵に参加しなかった顔ぶれもおさえることができます。
2.には144人の名前が挙げられているのでこちらをベースとし、2.に記載されていない人々を1.から補足するかたちをとりました。
なお、「御家人は(鎌倉殿のもとでは)平等」という建前はありますが、やはり厳然と序列はあったようです。
1.で「列御後人々」にリストされた面々が、2.ではほぼ番号順にならんでいます。
なので、やはりどちらも序列順に記載されたものと思われます。
リストの作成そのものが主目的ではなく、「『鎌倉殿の13人』の御朱印」を書くための整理リスト的なものなので、ネタ元はほとんどWeb検索で深掘りはしていません。
よって間違いや異説もあるかと思いますが、とりあえず概略的に一気にまとめてみました。
※ 表中★マークは「13人の合議制」参画メンバーです。
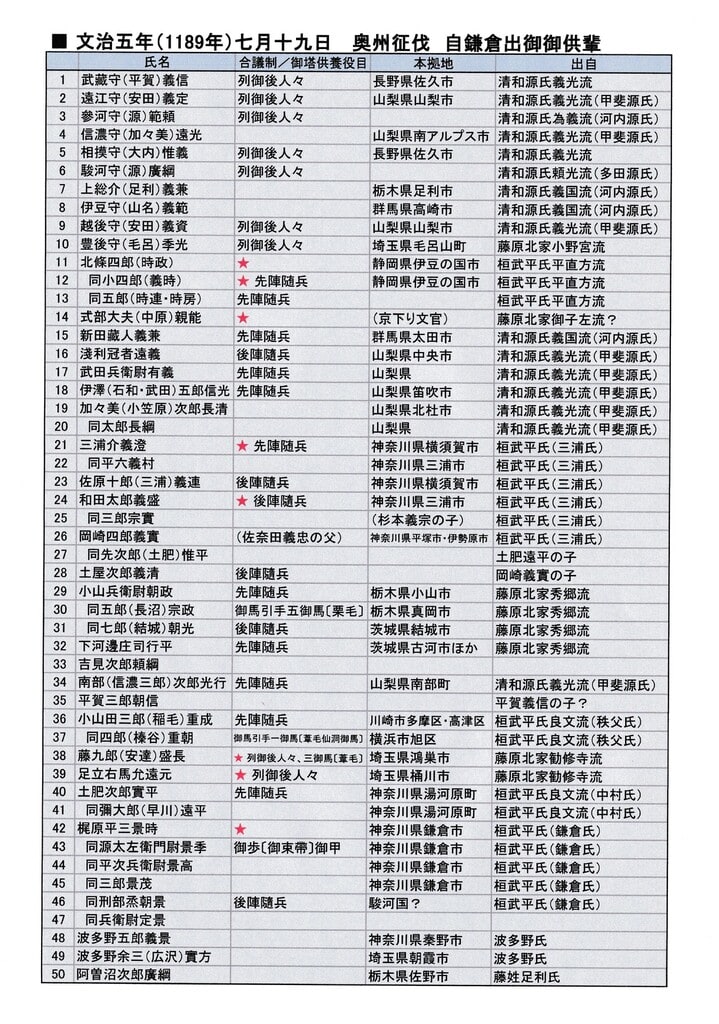



※ 文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩に記載されていない人物のみ
これをみると序列上位はほとんど清和源氏で占められています。
頼朝公の実弟の範頼公の上に信濃源氏の平賀義信、甲斐源氏の安田義定がいます。
また、北條時政の上にも加々美、大内、足利、山名などの錚々たる清和源氏の武将がいます。
もしもこれらの甲斐、信濃、上野・下野の清和源氏が結束して頼朝公と事を構えたら、頼朝公でも、ましてや北条氏でもいかんともしがたかったとみられます。
(誰が主導権を握るかの問題はありますが。)
頼朝公、あるいは北条氏がこれら清和源氏の勢力削減に注力したのは、このような緊迫した力関係があったためとみられます。
じっさい、一時的に粛清によって彼らの力を弱めたとはいえ、鎌倉幕府(北条氏)は、足利氏・新田氏など、清和源氏を中心とした勢力に滅ぼされています。
また、源平合戦は「東国の源氏と西国の平氏のたたかい」と見る向きも多いかと思いますが、上の表をみると「坂東八平氏」と称される桓武平氏の流れ、藤原氏、そして「武蔵七党」といわれる武士団が多いことがわかります。
なので、源平合戦は実質的には西日本の公家的な武士団と東日本の武家的な(主従関係の堅固な)武士団の戦いとみることができるかもしれません。
今後はこの顔ぶれのうち、所縁の寺社の御朱印をいただいている例からUPしていきたいと思います。
(頼朝公に敵対した武将もとりあげます。)
------------------------------
上の表で、本拠地とみられる場所を現在の市町名で載せてみました。
鎌倉周辺に限らず、広く東日本一帯に広がっていることがわかります。
今回のGWで、これらの武将ゆかりの地を回ってみるのも面白いかもしれません。
【 BGM 】
■ By your side - 西野カナ
■ 君がいない世界は切なくて - CHIHIRO feat. KEN THE 390
■ Over and Over - Every Little Thing
■ Butterfly - 木村カエラ(Cover)
■ For Our Days - 川田まみ (LIVE)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)から
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ
13.鷲峰山 覚園寺(かくおんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市二階堂421
真言宗泉涌寺派
御本尊:薬師如来
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番
建保六年(1218年)、薬師如来の眷属・十二神将のうちの「戌神」(伐折羅大将)が北条義時公の夢に現れ、これにより義時公が建立した大倉薬師堂が覚園寺の草創とされます。
永仁四年(1296年)、九代執権北条貞時公は外敵退散を祈念して大倉薬師堂を正式の寺に改めた(覚園寺の創建)といいます
開基は北条貞時公、開山は京・泉涌寺の智海心慧律師とされます。

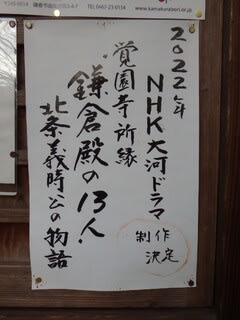
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 大河ドラマ関連の掲示
現在は真言宗泉涌寺派となっていますが、当初は北京系律の本拠地で、律を中心に天台、東密(真言)、禅、浄土の四宗兼学の道場であったと伝わります。
元弘三年(1333年)、後醍醐天皇が勅願寺とされ、足利氏も祈願所として保護した名刹です。
『新編相模國風土記稿』の覚園寺の項に「覺園寺。鷲峰山 眞言院ト号ス。四宗兼学。京師泉涌寺末。本尊薬師。長八尺。運慶作。鎌倉志ニハ。宅間作ト云ヘリ。及日光。月光。十二神。各長五尺。宅間作。古昔大倉薬師堂。或ハ大倉新御堂ト称セリ。(略)此堂ハ建保六年(1218年)七月。北條義霊夢ニ因テ創立アリシ所ナリ。(略)永仁四年(1296年)。北條貞時本願主トナリ。一寺トナシテ。今ノ山寺号を負セ。僧智海ヲ延テ。開山始祖トス。(略)元弘三年(1333年)十二月、綸旨ヲ下サレ。勅願寺トセラル。延元元年(1336年)足利直義祈祷ヲ命ス。」とあり、後醍醐帝から勅願寺を賜り足利直義も祈祷を請じたことがわかります。
同書には「地蔵堂 舊クヨリ黒地蔵ト呼称シ。又里俗ハ火燒地蔵ト唱フ。此堂舊クハ鎌倉海濱ニ在シヲ。理智光寺開山僧願行。此ニ移セシナリ。時ニ此像霊佛ニシテ奇瑞多カリシ事。(略)住吉社。村の鎮守トス。神明宮。春日社。棟立井。山上ニアリ。古伝ニ弘法大師井ヲ穿テ。閼伽ノ料トセシト云フ。鎌倉十井ノ一ナリ。弘法大師護摩壇蹟。寺後ノ山上ニ平石アリ。其石上ニ護摩ヲ燒シ蹟ト云フ穴アリ。(略)塔頭。昔時四宇アリ。持寶院。龍泉院。比奈寺。五峰寺等ナリ。今ハ其遺●定カナラス。」とあり、弘法大師に所縁の深い寺院であること、また黒地蔵の堂宇は、もとは鎌倉の浜辺にあったことを示唆しています。
また、『新編鎌倉志』には「本尊、薬師、日光、月光、十二神何れも宅間法眼作と云ふ。(略)薬師堂谷(やくしどうがやつ)と有は此地の事なり。健保六年(1218年)七月九日右京兆義時、大倉郷に一堂を建立し、運慶が所造の薬師の像を安置す。(略)建長三年(1251年)十月、薬師堂谷焼亡、二階堂に及ぶ。南の方宇佐美判官が荏柄の家より到るとあり。義時建立の薬師堂、号大倉大御堂とあり。然れば当寺建立の前より薬師堂有しと見へたり。」とあり、永仁四年(1296年)の北條貞時による当寺創建の前に、義時建立の薬師堂(大倉大御堂)があったことを記しています。
入口正面の愛染堂と堂内の諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初胡桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項に「覚園寺域内左方ニアリ。古ハ胡桃ヶ谷(浄妙寺村ノ麓)ニ在シトソ。故ニ胡桃山 千秋大楽寺と号ス。此ニ移セシ年代伝ハラス。開山ハ公珍ト云フ。本尊不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク。暦應四年(1341年)二月。基氏ノ慈母。十三年ノ忌ニ佛事ヲ執行ス。永享元年(1429年)二月回禄ニ罹レリ。鎌倉九代後記曰。永享元年二月永安寺並大楽寺炎上。按スルニ此所ヨリ永安寺二程近シ。サテハ此頃。既ニ当所ニ移レルコト識ルヘシ。」とあり、不動尊像は大山寺と所縁をもたれること、大楽寺の焼失と移転の経緯などが記されています。
胡桃ヶ谷は浄明寺と瑞泉寺の中間あたりで、永安寺は瑞泉寺総門近くにあったとされます。
これに、↑ の『新編相模國風土記稿』『新編鎌倉志』の記述を重ね合わせると、胡桃ヶ谷の大楽寺は永享元年(1429年)に大火で焼失し、覚園寺のある薬師堂谷(覚園寺の左方)に移転、明治初年に廃寺となり覚園寺に吸収され、堂宇や尊像は覚園寺愛染堂として遺された、という流れも考えられます。
----------
覚園寺には広めの駐車場がありますが、やはりアクセス道が狭いのと、鎌倉宮あたりからの道行きは雰囲気もあるので、徒歩でのアクセスをおすすめします。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内入口
鎌倉宮の社頭を左に折れて北側に向かう小川沿いの道を進みます。
途中、蒲原有明旧居跡 (川端康成仮寓跡)があります。
この道は鎌倉有数のハイキングコース・天園ハイキングコースの登り口にもあたるので、週末など、かなりの数ハイカーが入り込みます。
進むにつれて、正面の風格ある山門が近づいてきます。
参道をまっすぐに受けずやや斜に受ける階段と山門が、かえって安定感を感じさせる粋な構えです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の寺号提灯
石段の上に構える山門は、桟瓦葺切妻屋根の四脚門。本柱からの腕木、肘木の持ち出しが長く、実質は棟門ないし高麗門と見る専門家もいるようです。


【写真 上(左)】 山門から
【写真 下(右)】 庫裡?
こちらをくぐって右手に、北条氏の「三つ鱗」紋が掲げられた庫裡?。
適度に木々が茂った山内は、四季折々に落ち着いた風情を楽しめます。


【写真 上(左)】 早春の山内
【写真 下(右)】 梅雨の山内


【写真 上(左)】 秋の山内-1
【写真 下(右)】 秋の山内-2
正面の仏殿が本堂のようにみえますが、こちらは愛染堂で、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
その右手には客殿らしき建物があります。


【写真 上(左)】 愛染堂と客殿?
【写真 下(右)】 客殿?


【写真 上(左)】 梅雨の愛染堂
【写真 下(右)】 秋の愛染堂
愛染堂手前右に手水舎、左手には鐘楼。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 愛染堂
【写真 下(右)】 愛染堂向拝
銅板葺入母屋造(違うかもしれぬ)で、軒を重ねて向拝が張り出されています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ梁で、その両よこには端正な花頭窓はあるものの、全体にスクエアできっちりまとまった印象です。


【写真 上(左)】 よこからの向拝
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
向かって右の向拝柱には「第十一佛阿閃如来」の鎌倉十三仏霊場の札所板。
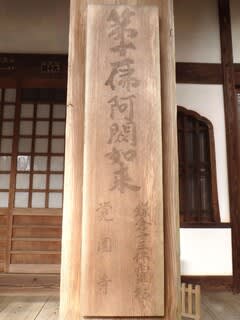

【写真 上(左)】 鎌倉十三霊場仏の札所板
【写真 下(右)】 露天
向拝正面は4枚の腰付き格子硝子扉の引き違いで、正面がわずかに開かれていますが、中は暗くてはっきりとは見えません。
向拝の掲示によると、中尊が愛染明王(鎌倉時代後期)、左脇侍(向かって右)に不動明王(鎌倉時代後期)、右脇侍(向かって左)に阿閃如来(鎌倉時代)という構成で、阿閃如来は鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊です。
『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項には「(本尊)不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク」とあります。
大楽寺は室町時代の永享元年(1429年)2月に焼失していますが、上記の尊像は焼失を免れたのかもしれません。
北条義時公所縁の寺院なので、堂前には”鎌倉殿の13人”関連の掲示がありました。


【写真 上(左)】 ”鎌倉殿の13人”関連掲示
【写真 下(右)】 愛染堂と拝観受付
愛染堂前を左手に進むと、本堂エリアの拝観受付です。
新型コロナ禍前は、入山料500円で本堂エリア内のご案内をいただけるシステムでしたが、現在は随時拝観できるようになっています。
詳細は→こちら。


【写真 上(左)】 拝観受付と本堂エリア
【写真 下(右)】 本堂(山門前掲示板より)
正直に白状すると(笑)、筆者は本堂エリアの拝観はしたことがなく、御本尊も地蔵尊も拝観受付手前からの遙拝です。
なので、現時点ではこのエリアのご案内をする資格はありません。
機会をみてじっくり拝観し、追記したいと思います。
なお、拝観料をおさめた先の境内(本堂エリア内)での写真動画撮影、写生、飲食はできません。
本堂エリア内には、御本尊薬師如来(薬師三尊)と十二神将が御座す本堂(薬師堂)、旧内海家住宅、十三佛やぐら、千躰地蔵尊、黒地蔵尊の地蔵堂、六地蔵尊などの見どころがあります。
詳細については公式Webをご覧ください。

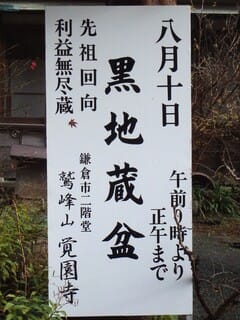
【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 「黒地蔵盆」の案内
黒地蔵尊は鎌倉時代の作といわれ、地獄で業火に焼かれる罪人の苦しみを和らげようと、獄卒の代わりに火焚きをしたために焼け焦げてしまったという縁起が伝わります。
そばにある千躰地蔵尊は黒地蔵尊の分身とされ、毎年8月10日の深夜に行われる「黒地蔵盆」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。
『新編鎌倉志』には「(覚園寺)地蔵堂 地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ。【鎌倉年中行事】には黒地蔵と有て、(足利)持氏参詣の事みへたり。相伝ふ、此地蔵、地獄を廻り、罪人の苦みを見てたへかね。自ら獄卒にかはり火を燒、罪人の焔をやめらるゝとなり。是故に、毎年七月十三日の夜、男女参詣す。数度彩色を加へけれども、又一夜の内に本の如黒くなるとなん。(略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、黒地蔵尊の縁起を伝えています。
御朱印は拝観受付にて拝受できます。
こちら様もご親切なご対応です。
こちらの札所は、鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の3つ。
別に御本尊・薬師如来の御朱印を授与されているので、御朱印は4種となります。
無申告の場合の御朱印は不明ですが、相州二十一ヶ所霊場の御朱印は申告制だと思います。
〔 御本尊・薬師如来の御朱印 〕

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
鎌倉二十四地蔵霊場第3番の札所本尊は、地蔵堂に御座す「黒地蔵尊」です。

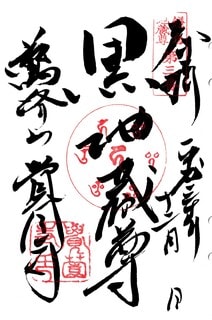
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は御寶印で、円のなか中央に地蔵菩薩の種子「カ」、周囲はおそらく六地蔵尊の種子と思われます。
〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕
相州二十一ヶ所霊場第3番の札所本尊はお大師さまと思われますが、御座所はよくわかりません。
愛染堂前と拝観受付前で、御宝号、光明真言などをお唱えしました。

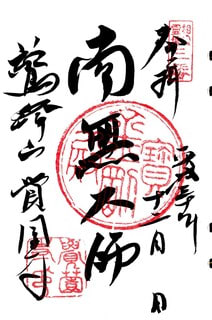
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳
〔 鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の御朱印 〕
鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊は、愛染堂に御座す阿閃如来です。

●主印は阿閃如来の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
14.(西御門/大蔵)白旗神社(にしみかどしらはたじんじゃ)
鎌倉市西御門2ー1
御祭神:源頼朝公
頼朝公が鎌倉入りして設けた御所(居宅)は現在の清泉小学校(雪ノ下三丁目)あたりとみられ、「大倉御所」といわれます。
頼朝公がこの御所で施政したため大倉幕府とも呼ばれますが、この時代に「幕府」の呼称はなかったというのが通説です。
白旗神社はこの大倉御所跡のちょうど北側に御鎮座で、社頭前からの50数段の階段をのぼったところが頼朝公の墓所です。
こちらの白旗神社は、鶴岡八幡宮境内社の白旗神社と区別するため(西御門)白旗神社とも呼ばれますが、ここでは白旗神社と表記します。


【写真 上(左)】 大倉御所跡からの参道
【写真 下(右)】 社頭
白旗神社御鎮座の地はすこぶる複雑な変遷を辿っているので、まずは概略を記した現地掲示を引用します。
「この地はもと源頼朝公居館(幕府)の北隅で持仏堂があり、石橋山の合戦にあたって髻の中に納めて戦ったという小さな観音像が安置され頼朝公が篤く信仰していた。正治元年(一一九九)一月十三日頼朝公が亡くなるとここに葬り法華堂と呼ばれ毎年命日には将軍が参詣し仏事を執り行い多くの武将も参列した。その後鶴岡八幡宮の供僧『相承院』が奉仕して祭祀を続け、明治維新に際し寺は白旗神社に改められ源頼朝公を祭神として今日に至っている。現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和四十五年に源頼朝公報恩会の方々の篤志によって造営されたものである。」(白旗神社)
「この平場は鎌倉幕府を開いた源頼朝の法華堂(墳墓堂)が建っていた跡です。(略)建久10年(1199)に頼朝が53歳で没すると、法華堂は幕府創始者の墳墓堂として、のちの時代の武士たちからもあつい信仰を集めました。鎌倉幕府滅亡後も法華堂は存続しましたが、17世紀の初頭までには堂舎がなくなり、石造りの墓塔が建てられました。現在の墓域は、安永8年(1779)に薩摩藩主島津重豪によって整備されたものです。」(頼朝公墓所)
白旗神社の創立は明治5年なので、それ以前の文献に白旗神社の記述はなく、法華堂と記されています。
『新編鎌倉志』の法華堂の項には「西御門の東の岡なり。相傳、頼朝持佛堂の名也。【東鑑】に、文治四年(1188年)四月廿三日、御持佛堂に於て、法華経講読始行せらるとあり此所歟。同年七月十八日、頼朝、専光坊に仰て曰。奥州征伐の為に潜に立願あり。汝留守に候じ、此亭の後の山に梵字を草創すべし。年来の本尊正観音の像を安置し奉ん為なり。同年八月八日御亭の後山に攀登り、梵字営作を始む。先白地に假柱四本を立、観音堂の号を授くとあり。今雪下相承院領するなり。頼朝の守本尊正観音銀像も、相承院にあり。今此には彌陀、幷如意輪観音・地蔵像あり。地蔵は、本報恩寺の本尊なりしを、何れかの時か此に移す。(略)此法華堂を、右大将家法華堂と云なり。」とあります。
また、『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。正治元年(1199年)正月十三日頼朝薨ス(略)同二年正月十三日頼朝の小祥ニヨリ。法会ヲ行ハル。此時始テ法華堂ノ称アリ。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)(略)相承ヲ別当タリ。」
「什寶。正観音像一軀 銀佛ニテ立身長二寸頼朝ノ守護佛。髻観音ナリ。」とあります。
一方、頼朝公墓所(頼朝墓)についてみてみると、
『新編鎌倉志』には「法華堂の後の山にあり。【東鑑脱漏】に、法華堂西の岳上に、右幕下の御廟を安ず」とあり、『新編相模国風土記稿』には「堂後ノ山上に五輪塔一基ヲ建ツ。」とあります。
法華堂と頼朝公墓所(頼朝墓)の位置関係がどうもわかりにくいので、上記資料を参考に年表風にまとめてみました。
1.文治四年(1188年)4月23日、御持佛堂に於て法華経講読始行。
2.同年8月8日御亭(御持佛堂)の後山に梵字営作。假柱四本を立て観音堂の号を授く。
(この観音堂に頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)を奉安?。持佛堂とも称す?。)
(もとの御持佛堂には阿彌陀三尊、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安?)
3.正治元年(1199年)正月13日頼朝公薨す。後に頼朝公御廟を安ず。(→頼朝公墓所)
4.正治二年(1200年)正月13日の法会時、もとの御持佛堂(?)を法華堂と改める。
5.同時期に観音堂(持佛堂)は墳墓堂と改める。
6.法華堂は、鶴岡八幡宮寺の僧坊「相承院」が護持する。
7.17世紀の初頭までに墳墓堂が失われる。
8.安永8年(1779年)頼朝公墓所が薩摩藩主島津重豪によって整備される。
9.明治初年の神仏分離令施行に伴い法華堂は撤去され、明治5年10月白旗神社が建立。
10.現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和45年に造営。
上記のうち、1.4.9.10が現在の白旗神社、2.3.5.7.8が現在の頼朝公墓所を示すとみられますが、頼朝公墓所の広さからみると、堂宇は一旦墓所周辺(山上)に整備され、のちに一部が現社地に移動したのかもしれません。
なお、頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)は、現在扇ガ谷の鎌倉歴史文化交流館で展示されている模様です。(同館twitterより)
頼朝公墓所の下の公ゆかりの法華堂ですから、神社創立の際に御祭神を頼朝公とし、白旗神社を号したことは自然な流れとみられますが、「猫の足あと」様Webページ掲載の「神奈川県神社誌」には、以下のような文章があります。
「然しながら頼朝公を白旗大明神として祀ったのは相当古く、応安六年(一三七三)十一月十五日西御門の報恩寺(廃寺)境内に洞(堂?)が祀られていたと記録にある。」
報恩寺、白旗明神社ともに記録があります。
■『新編鎌倉志』
○報恩寺舊跡 附白旗明神社
「報恩寺舊跡は、西御門の西の谷にあり。当寺の本尊、今法華堂にあり。」
○白旗明神社
「寺滅して社も又亡ぶ。義堂祭白旗神文あり。其略に云、應安六年(1373年)冬、南陽山報恩護國禅寺、白旗大明神靈祠成るとあり。」
■『新編相模国風土記稿』
●報恩寺廃蹟
「南陽山報恩護國寺ト号セシ禅刹ニテ。應安四年(1371年)上杉兵部大輔能憲ノ起立ナリ。(略)其後何レノ頃廃寺トナリシヤ詳ナラス。当時(寺?)ノ本尊地蔵ハ。今法華堂ニ安セリ。境内ニ。白旗明神社在シトナリ。是モ寺滅シ頃。共ニ廃セシナルヘシ。今址タニナシ。應安六年(1373年)十一月起立セシモノナリ。」
報恩寺(廃寺)は法華堂の西側にあり、御本尊地蔵菩薩は廃寺ののちに法華堂に遷られたとされますが、その報恩寺内に應安六年(1373年)の時点で白旗明神社が祀られていたというのです。
こちらの御祭神は不明ですが、上記の「神奈川県神社誌」の文章は、この報恩廃寺の白旗明神社と(西御門)白旗神社の関係性を示唆するものともみられます。
また、報恩寺から法華堂に遷られた地蔵菩薩等は、明治のはじめに法華堂が廃されたときに満光山 来迎寺に遷られたとされています。
詳細はつぎの「15.満光山 来迎寺」をご覧ください。


【写真 上(左)】 正面階段上が頼朝公墓所
【写真 下(右)】 社頭(通常)
海がわから広がる鎌倉の平地が、北山にさしかかるところにあります。
週末は観光客のすがたもちらほら見られますが、ごったがえす若宮大路あたりと比べると落ち着いた趣。
あたりにどこかもの寂びた空気がただよっているのは、山裾という場所柄だけでなく、頼朝公の墓所であること、宝治元年(1247年)の宝治合戦で三浦一族500余名が自刃したという凄絶な歴史も影を落としているのかもしれません。
なお、宝治合戦で三浦一族が籠もった法華堂は、ここから少し東の山腹にある「法華堂跡」(北条義時法華堂跡)という説もあります。
こちらは『吾妻鏡』に「頼朝の法華堂の東の山をもって墳墓となす」と記された地とみられています。
北条義時法華堂跡の山上に、大江広元の墓所があります。


【写真 上(左)】 社頭(正月)-1
【写真 下(右)】 社頭(正月)-2


【写真 上(左)】 正月の拝殿
【写真 下(右)】 本殿
社頭に石灯籠一対、狛犬一対、鳥居は貫の突き出しのない神明鳥居系。
拝殿は銅板葺の神明造、本殿は銅板葺の一間社流造とみられます。


【写真 上(左)】 拝殿扁額
【写真 下(右)】 幟
境内にはためく幟には「白旗大明神」、拝殿向拝の扁額には「白旗明神」とあり、往年の神仏習合の歴史を伝えているかのよう。
法華堂の護持を司っていた相承院(頓覚坊)は『鶴岡八幡宮寺供僧次第』などにみられる「鶴岡二十五坊」のひとつです。
階段上の頼朝公墓所は相当な広さがあり、かつて堂宇があったことをうかがわせます。
墓石や手水石には源氏の「笹竜胆」紋だけでなく、なぜか薩摩の島津家の「轡十文字」紋がみられます。
幕末に墓所が荒れた際、頼朝公の子孫を称する薩摩藩主・島津重豪が整備して「轡十文字」を刻んだものとされています。(島津氏整備・寄進の石碑もあります。)
白旗神社は通常非常駐で、御朱印の授与は原則正月三が日に限られ、書置ながら鎌倉屈指のレア御朱印として知られています
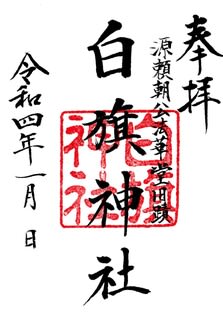
(西御門)白旗神社の御朱印
15.満光山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市西御門1-11-1
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第5番、鎌倉二十四地蔵霊場第2番、鎌倉十三仏霊場第10番、鎌倉郡三十三観音霊場第8番
鶴岡八幡宮の東側、西御門にある時宗寺院で、複数の現役霊場の札所を兼務されています。
鎌倉には来迎寺を号する寺院が西御門と材木座にあり、区別するためからか西御門来迎寺(にしみかどらいこうじ)と呼ばれます。
寺伝(公式Web)によると、永仁元年(1293年)の鎌倉大地震で亡くなった村民を供養するため一向上人により創建。
『新編鎌倉志』の来迎寺の項には「高松寺の南隣なり。時宗、一遍上人開基、藤澤清浄光寺の末寺なり。」とあります。
また、『新編相模国風土記稿』には「時宗。藤澤清浄光寺末。一遍の創建ナリ。本尊阿彌陀ヲ安ス。」とあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 八雲神社
横浜国大附属鎌倉中学校の東側の路地を山側に向かいます。
この路地は山裾で行き止まりとなり、みどころは来迎寺のほかには石川邸(旧里見邸)くらいしかないので、週末でも閑静な住宅街です。
T字路の右手に八雲神社、そのよこの階段の上が来迎寺です。
こちらの(西御門)八雲神社は『新編相模国風土記稿』記載の「字大門の天王社」とみられていますが、来迎寺との関係は定かではありません。
西御門の氏神社で、旧村社に列格していたとされます。
また、頼朝公起立と伝わる太平寺(廃寺)はこのあたりと伝わり、来迎寺の参道脇に「大平寺跡」の石碑が建っています。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 札所標
参道階段右手には、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三仏の札所標。
真新しい階段を昇ると視界が開け、左手に庫裡。もうひと昇りすると本堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
参道階段は東向きで、本堂前で南面する本堂に向きを変える曲がり参道です。
本堂は入母屋造本瓦葺の堂々たる構えで、軒下に向拝柱を置いています。
水引虹梁両端に草花紋様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
本瓦葺の軒丸瓦には時宗の宗紋「隅切三(すみきりさん)」が置かれ、向拝正面桟唐戸の上には山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
山内掲示によると、本堂には御本尊阿弥陀如来と地蔵菩薩像、如意輪観世音菩薩像が奉安されています。
御本尊の阿弥陀如来は鎌倉十三仏霊場第10番の札所本尊です。
地蔵菩薩像は廃寺となった報恩寺の御本尊で宅間浄宏の作と伝わり、岩を模した台座のうえに御座されることから「岩上地蔵尊」と呼ばれ、鎌倉二十四地蔵霊場第2番の札所本尊です。
中世禅刹で流行した「法衣垂下」の技法を用いた代表作として知られています。
如意輪観世音菩薩像は「鎌倉でもっとも美しい仏像」と賞される名作で、鎌倉特有の技法とされる「土紋」が鮮やかなことで知られ、鎌倉三十三観音霊場第5番の札所本尊です。
〔 関連記事 〕
■ 東京都区内の如意輪観音の御朱印
『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)」とあり、地蔵尊は報恩寺→法華堂→来迎寺と遷られたのではないでしょうか。
来迎寺の公式Webには、「客仏として如意輪観世音菩薩、岩上地蔵菩薩、跋陀婆羅尊者が祀られています。客仏の三体は源頼朝公の持仏堂の後身である法華堂(現在の源頼朝公の墓所付近)に安置されておりましたが、明治初年の神仏分離令を機に来迎寺へ移されました。」と明記されています。
ちなみに跋陀婆羅尊者は、寺院(とくに禅刹)の浴室の守護神とされます。
如意輪観世音菩薩像と岩上地蔵菩薩像は県指定文化財、跋陀婆羅尊者像は市指定文化財に指定されている、知る人ぞ知る「仏像の寺」です。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、新型コロナ禍中は事前確認してからの参拝がベターかもしれません。
〔 御本尊・阿弥陀如来(鎌倉十三仏霊場第10番)の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
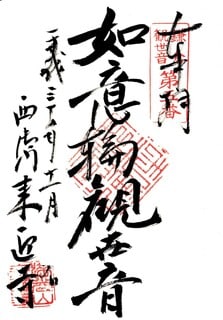

【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
16.鶴岡八幡宮
鎌倉市雪ノ下2-1-31
御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后
旧社格:旧国幣中社、別表神社
元別当:(八幡宮寺)
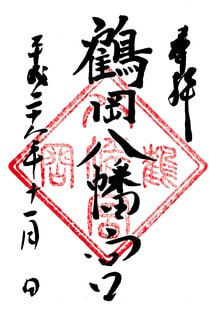
17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社
鎌倉市雪ノ下2-1-31
御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后
旧社格:鶴岡八幡宮境内社、旧柳営社合祀
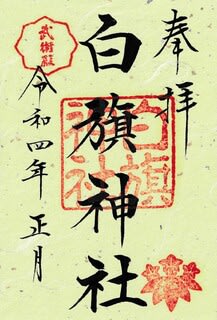
※正月のみの限定授与です。
18.旗上辨財天社
鎌倉市雪ノ下2-1-31
御祭神:辨財天
旧社格:鶴岡八幡宮境内社
札所:鎌倉・江ノ島七福神(辨財天)

16.鶴岡八幡宮、17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社、18.旗上辨財天社については、ものすごい量の史料が存在するので、別稿でまとめます。
19.巌窟堂 岩谷不動尊(いわやふどうそん)
不動茶屋のWeb
鎌倉市雪ノ下2-2-21
宗派不明
御本尊:不動明王
札所:
鎌倉ガイドでもあまり紹介されないお不動さまですが、古い歴史をもち、以前は巌窟(イハヤ)不動尊と呼ばれていました。
『新編鎌倉志』の巌窟不動の項には「巌窟(イハヤ)不動は、松源寺の西、山の根にあり。窟の中に、石像の不動あり。弘法の作と云ふ。【東鑑】に、文治四年(1188年)正月一日、佐野太郎基綱が巌窟の下の宅焼亡。鶴岡の近所たるに因て、二品頼朝宮中に参給ふとあり。此所の事あらん。此前の道を巌窟小路と云ふ。(中略)【東鑑】には、巌堂とあり。俗、或は岩井堂と云ふ。巌窟堂、今は教圓坊と云僧持分なり。昔は等覺院の持分なりけるにや。」とあります。
『鎌倉攬勝考』の巌窟不動尊の項には「【東鑑】に、窟堂又は岩屋堂、或は岩井堂と有るも、此所の事なり。日金地蔵のにしの山麓にて、窟中に石像の不動あり。弘法大師のさくといふ。此前の道路を岩屋小路と唱ふ。【東鑑】に、建長四年(1251年)五月五日、将軍家(宗譽)御方違の評定有て、亀が谷の方角を見定可申由仰にて、行義・行方・景頼等、彼六人を具して、巌窟のうしろの山上へ登るとあるも此地なり。昔は等覺院といふが別当なりしが、今は散圓坊といふ庵室の持とす。むかし等覺院別当のときは、日金堂をも兼持せしといふ。●に、等覺院といふは、十二院のうちなる巌覺院なるべし。」とあります。
以上から、弘法大師の御作と伝わる由緒正しい不動尊であることがわかります。
また、『新編相模国風土記稿』には「村西ニ巌窟アリ。濶三間許。高七尺。其中巌面ニ。不動ノ像。弘法ノ畵ク所ト云。ヲ彫ルノミ。今ハ堂宇ナシ。(中略)建久三年(1192年)五月。南御堂ニシテ。後白河法皇ノ御佛事。百僧供ヲ修セラレシ時。僧衆ノ内ニ。当堂ノ住侶ヲ加ラル。(中略)鎌倉志ニハ。巌窟不動ト挙。俗或ハ岩井堂ト云。今ハ教圓坊持ナリ。昔ハ等覺院鶴岡供僧。」とあります。
『吾妻鏡』(建久三年五月八日条)には、南御堂(勝長寿院)で行われた後白河法皇の四十九日法要には僧百が勤修し、その内訳は「鶴岡八幡宮供僧二十口、六所宮(六所社)二口、伊豆山(権現)十八口、筥根山(箱根権現)十八口、大山寺(阿夫利神社)三口、観音寺(不詳)三口、勝長壽院十三口、高麗寺(大磯・高来神社)三口、岩殿寺(逗子・岩殿寺?)二口、大倉観音堂(杉本寺)一口、巌窟一口、慈光寺(都幾川・慈光寺)十口、眞慈悲寺(日野・眞慈悲寺?)三口、浅草寺三口、弓削寺(小田原・飯泉観音?)二口、国分寺(海老名・国分寺?)三口也」と記され、巌窟堂が関東の大寺と並ぶ格式(ないし役割)をもっていたことがうかがえます。
『鎌倉攬勝考』の日金地蔵堂の項には「岩屋堂の東にて、山の半腹にあり。本尊地蔵、運慶作。右大将家、豆州謫居の頃より、御誓願有て、爰(ここ)に移し給ふといふ。別当日金山彌勒院松源寺といふ。真言新義。御室御所の末なり。」とあります。
こちらは、頼朝公が伊豆の日金山から勧請した日金地蔵尊(日金山松源寺)のとなりで、この界隈は頼朝公の信仰の場であった可能性がありますが、松源寺は廃寺となり、現在、日金地蔵尊は横須賀の東漸寺に遷られています。(→■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3)


【写真 上(左)】 横大路(窟小路)と入口
【写真 下(右)】 参道入口
鶴岡八幡宮から扇ガ谷に抜ける横大路(窟小路)は観光客の姿もみられますが、小町通りほどの雑踏はなく、落ち着いたたたずまいです。


【写真 上(左)】 石碑
【写真 下(右)】 境内
岩谷不動尊はこの道の北(山側)の小径を入った不動茶屋横に御座します。
横大路(窟小路)沿いの門柱には「巌窟不動尊」、その横には「不動茶屋」の幟、ラーメンが売りらしく、美味しそうなメニューも掲出されています。
左に古色を帯びた「不動尊」の石碑、右手に整然と庚申様や板碑、石塔が並ぶブロック塀沿いに進むと、そのおくに木の鳥居と不動堂。
左手の覆堂のなかにもお不動さまが御座しています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 不動堂
堂宇の背後は岩壁でやぐららしきものもみえます。
周囲はほの暗く、パワスポ的雰囲気が感じられます。
御本尊は石佛の不動明王立像です。
不動茶屋のWebには「この像は弘法大師の作とも言われています。永い年月の間にお不動様の像も風化し、後に石の像が作られ今に至っております。」とあります。
こちらのお不動様は、古くは背後の岩窟のなかに祀られていたようです。
御朱印は不動茶屋にて書置のものを拝受しましたが、当然のことながら営業時間内しか拝受できません。
〔 御本尊・岩谷不動尊の御朱印 〕

これでA.朝夷奈口はひとまず校了です。
つぎは南側のB.名越口に進みます。
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ。
【 BGM 】
■ 地上に降りるまでの夜 - 今井美樹
→ ■ 今井美樹の名バラード25曲!
■ 永遠 ~小さな光~ - 詩月カオリ
■ YOU ARE NOT ALONE - 杏里
→ ■ 杏里の名バラード20曲!
■ 夢の途中 - KOKIA
→ ■ KOKIAの名バラード12曲
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ
13.鷲峰山 覚園寺(かくおんじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市二階堂421
真言宗泉涌寺派
御本尊:薬師如来
札所:鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番
建保六年(1218年)、薬師如来の眷属・十二神将のうちの「戌神」(伐折羅大将)が北条義時公の夢に現れ、これにより義時公が建立した大倉薬師堂が覚園寺の草創とされます。
永仁四年(1296年)、九代執権北条貞時公は外敵退散を祈念して大倉薬師堂を正式の寺に改めた(覚園寺の創建)といいます
開基は北条貞時公、開山は京・泉涌寺の智海心慧律師とされます。

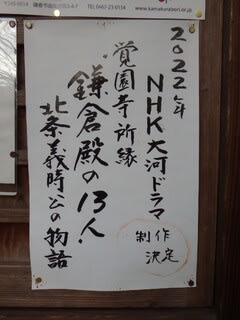
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 大河ドラマ関連の掲示
現在は真言宗泉涌寺派となっていますが、当初は北京系律の本拠地で、律を中心に天台、東密(真言)、禅、浄土の四宗兼学の道場であったと伝わります。
元弘三年(1333年)、後醍醐天皇が勅願寺とされ、足利氏も祈願所として保護した名刹です。
『新編相模國風土記稿』の覚園寺の項に「覺園寺。鷲峰山 眞言院ト号ス。四宗兼学。京師泉涌寺末。本尊薬師。長八尺。運慶作。鎌倉志ニハ。宅間作ト云ヘリ。及日光。月光。十二神。各長五尺。宅間作。古昔大倉薬師堂。或ハ大倉新御堂ト称セリ。(略)此堂ハ建保六年(1218年)七月。北條義霊夢ニ因テ創立アリシ所ナリ。(略)永仁四年(1296年)。北條貞時本願主トナリ。一寺トナシテ。今ノ山寺号を負セ。僧智海ヲ延テ。開山始祖トス。(略)元弘三年(1333年)十二月、綸旨ヲ下サレ。勅願寺トセラル。延元元年(1336年)足利直義祈祷ヲ命ス。」とあり、後醍醐帝から勅願寺を賜り足利直義も祈祷を請じたことがわかります。
同書には「地蔵堂 舊クヨリ黒地蔵ト呼称シ。又里俗ハ火燒地蔵ト唱フ。此堂舊クハ鎌倉海濱ニ在シヲ。理智光寺開山僧願行。此ニ移セシナリ。時ニ此像霊佛ニシテ奇瑞多カリシ事。(略)住吉社。村の鎮守トス。神明宮。春日社。棟立井。山上ニアリ。古伝ニ弘法大師井ヲ穿テ。閼伽ノ料トセシト云フ。鎌倉十井ノ一ナリ。弘法大師護摩壇蹟。寺後ノ山上ニ平石アリ。其石上ニ護摩ヲ燒シ蹟ト云フ穴アリ。(略)塔頭。昔時四宇アリ。持寶院。龍泉院。比奈寺。五峰寺等ナリ。今ハ其遺●定カナラス。」とあり、弘法大師に所縁の深い寺院であること、また黒地蔵の堂宇は、もとは鎌倉の浜辺にあったことを示唆しています。
また、『新編鎌倉志』には「本尊、薬師、日光、月光、十二神何れも宅間法眼作と云ふ。(略)薬師堂谷(やくしどうがやつ)と有は此地の事なり。健保六年(1218年)七月九日右京兆義時、大倉郷に一堂を建立し、運慶が所造の薬師の像を安置す。(略)建長三年(1251年)十月、薬師堂谷焼亡、二階堂に及ぶ。南の方宇佐美判官が荏柄の家より到るとあり。義時建立の薬師堂、号大倉大御堂とあり。然れば当寺建立の前より薬師堂有しと見へたり。」とあり、永仁四年(1296年)の北條貞時による当寺創建の前に、義時建立の薬師堂(大倉大御堂)があったことを記しています。
入口正面の愛染堂と堂内の諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初胡桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項に「覚園寺域内左方ニアリ。古ハ胡桃ヶ谷(浄妙寺村ノ麓)ニ在シトソ。故ニ胡桃山 千秋大楽寺と号ス。此ニ移セシ年代伝ハラス。開山ハ公珍ト云フ。本尊不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク。暦應四年(1341年)二月。基氏ノ慈母。十三年ノ忌ニ佛事ヲ執行ス。永享元年(1429年)二月回禄ニ罹レリ。鎌倉九代後記曰。永享元年二月永安寺並大楽寺炎上。按スルニ此所ヨリ永安寺二程近シ。サテハ此頃。既ニ当所ニ移レルコト識ルヘシ。」とあり、不動尊像は大山寺と所縁をもたれること、大楽寺の焼失と移転の経緯などが記されています。
胡桃ヶ谷は浄明寺と瑞泉寺の中間あたりで、永安寺は瑞泉寺総門近くにあったとされます。
これに、↑ の『新編相模國風土記稿』『新編鎌倉志』の記述を重ね合わせると、胡桃ヶ谷の大楽寺は永享元年(1429年)に大火で焼失し、覚園寺のある薬師堂谷(覚園寺の左方)に移転、明治初年に廃寺となり覚園寺に吸収され、堂宇や尊像は覚園寺愛染堂として遺された、という流れも考えられます。
----------
覚園寺には広めの駐車場がありますが、やはりアクセス道が狭いのと、鎌倉宮あたりからの道行きは雰囲気もあるので、徒歩でのアクセスをおすすめします。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内入口
鎌倉宮の社頭を左に折れて北側に向かう小川沿いの道を進みます。
途中、蒲原有明旧居跡 (川端康成仮寓跡)があります。
この道は鎌倉有数のハイキングコース・天園ハイキングコースの登り口にもあたるので、週末など、かなりの数ハイカーが入り込みます。
進むにつれて、正面の風格ある山門が近づいてきます。
参道をまっすぐに受けずやや斜に受ける階段と山門が、かえって安定感を感じさせる粋な構えです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の寺号提灯
石段の上に構える山門は、桟瓦葺切妻屋根の四脚門。本柱からの腕木、肘木の持ち出しが長く、実質は棟門ないし高麗門と見る専門家もいるようです。


【写真 上(左)】 山門から
【写真 下(右)】 庫裡?
こちらをくぐって右手に、北条氏の「三つ鱗」紋が掲げられた庫裡?。
適度に木々が茂った山内は、四季折々に落ち着いた風情を楽しめます。


【写真 上(左)】 早春の山内
【写真 下(右)】 梅雨の山内


【写真 上(左)】 秋の山内-1
【写真 下(右)】 秋の山内-2
正面の仏殿が本堂のようにみえますが、こちらは愛染堂で、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。
その右手には客殿らしき建物があります。


【写真 上(左)】 愛染堂と客殿?
【写真 下(右)】 客殿?


【写真 上(左)】 梅雨の愛染堂
【写真 下(右)】 秋の愛染堂
愛染堂手前右に手水舎、左手には鐘楼。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 愛染堂
【写真 下(右)】 愛染堂向拝
銅板葺入母屋造(違うかもしれぬ)で、軒を重ねて向拝が張り出されています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ梁で、その両よこには端正な花頭窓はあるものの、全体にスクエアできっちりまとまった印象です。


【写真 上(左)】 よこからの向拝
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
向かって右の向拝柱には「第十一佛阿閃如来」の鎌倉十三仏霊場の札所板。
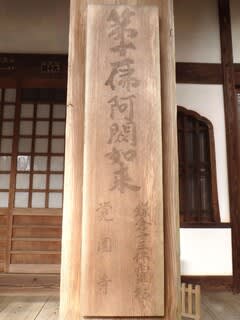

【写真 上(左)】 鎌倉十三霊場仏の札所板
【写真 下(右)】 露天
向拝正面は4枚の腰付き格子硝子扉の引き違いで、正面がわずかに開かれていますが、中は暗くてはっきりとは見えません。
向拝の掲示によると、中尊が愛染明王(鎌倉時代後期)、左脇侍(向かって右)に不動明王(鎌倉時代後期)、右脇侍(向かって左)に阿閃如来(鎌倉時代)という構成で、阿閃如来は鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊です。
『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項には「(本尊)不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク」とあります。
大楽寺は室町時代の永享元年(1429年)2月に焼失していますが、上記の尊像は焼失を免れたのかもしれません。
北条義時公所縁の寺院なので、堂前には”鎌倉殿の13人”関連の掲示がありました。


【写真 上(左)】 ”鎌倉殿の13人”関連掲示
【写真 下(右)】 愛染堂と拝観受付
愛染堂前を左手に進むと、本堂エリアの拝観受付です。
新型コロナ禍前は、入山料500円で本堂エリア内のご案内をいただけるシステムでしたが、現在は随時拝観できるようになっています。
詳細は→こちら。


【写真 上(左)】 拝観受付と本堂エリア
【写真 下(右)】 本堂(山門前掲示板より)
正直に白状すると(笑)、筆者は本堂エリアの拝観はしたことがなく、御本尊も地蔵尊も拝観受付手前からの遙拝です。
なので、現時点ではこのエリアのご案内をする資格はありません。
機会をみてじっくり拝観し、追記したいと思います。
なお、拝観料をおさめた先の境内(本堂エリア内)での写真動画撮影、写生、飲食はできません。
本堂エリア内には、御本尊薬師如来(薬師三尊)と十二神将が御座す本堂(薬師堂)、旧内海家住宅、十三佛やぐら、千躰地蔵尊、黒地蔵尊の地蔵堂、六地蔵尊などの見どころがあります。
詳細については公式Webをご覧ください。

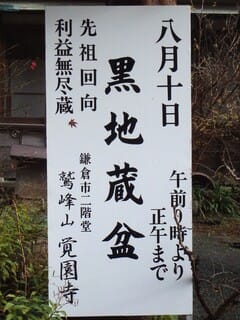
【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 「黒地蔵盆」の案内
黒地蔵尊は鎌倉時代の作といわれ、地獄で業火に焼かれる罪人の苦しみを和らげようと、獄卒の代わりに火焚きをしたために焼け焦げてしまったという縁起が伝わります。
そばにある千躰地蔵尊は黒地蔵尊の分身とされ、毎年8月10日の深夜に行われる「黒地蔵盆」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。
『新編鎌倉志』には「(覚園寺)地蔵堂 地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ。【鎌倉年中行事】には黒地蔵と有て、(足利)持氏参詣の事みへたり。相伝ふ、此地蔵、地獄を廻り、罪人の苦みを見てたへかね。自ら獄卒にかはり火を燒、罪人の焔をやめらるゝとなり。是故に、毎年七月十三日の夜、男女参詣す。数度彩色を加へけれども、又一夜の内に本の如黒くなるとなん。(略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、黒地蔵尊の縁起を伝えています。
御朱印は拝観受付にて拝受できます。
こちら様もご親切なご対応です。
こちらの札所は、鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の3つ。
別に御本尊・薬師如来の御朱印を授与されているので、御朱印は4種となります。
無申告の場合の御朱印は不明ですが、相州二十一ヶ所霊場の御朱印は申告制だと思います。
〔 御本尊・薬師如来の御朱印 〕

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕
鎌倉二十四地蔵霊場第3番の札所本尊は、地蔵堂に御座す「黒地蔵尊」です。

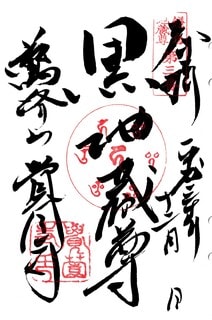
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は御寶印で、円のなか中央に地蔵菩薩の種子「カ」、周囲はおそらく六地蔵尊の種子と思われます。
〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕
相州二十一ヶ所霊場第3番の札所本尊はお大師さまと思われますが、御座所はよくわかりません。
愛染堂前と拝観受付前で、御宝号、光明真言などをお唱えしました。

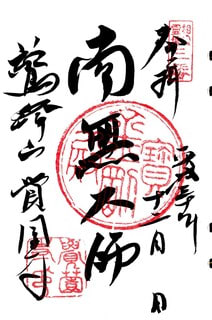
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳
〔 鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の御朱印 〕
鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊は、愛染堂に御座す阿閃如来です。

●主印は阿閃如来の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
14.(西御門/大蔵)白旗神社(にしみかどしらはたじんじゃ)
鎌倉市西御門2ー1
御祭神:源頼朝公
頼朝公が鎌倉入りして設けた御所(居宅)は現在の清泉小学校(雪ノ下三丁目)あたりとみられ、「大倉御所」といわれます。
頼朝公がこの御所で施政したため大倉幕府とも呼ばれますが、この時代に「幕府」の呼称はなかったというのが通説です。
白旗神社はこの大倉御所跡のちょうど北側に御鎮座で、社頭前からの50数段の階段をのぼったところが頼朝公の墓所です。
こちらの白旗神社は、鶴岡八幡宮境内社の白旗神社と区別するため(西御門)白旗神社とも呼ばれますが、ここでは白旗神社と表記します。


【写真 上(左)】 大倉御所跡からの参道
【写真 下(右)】 社頭
白旗神社御鎮座の地はすこぶる複雑な変遷を辿っているので、まずは概略を記した現地掲示を引用します。
「この地はもと源頼朝公居館(幕府)の北隅で持仏堂があり、石橋山の合戦にあたって髻の中に納めて戦ったという小さな観音像が安置され頼朝公が篤く信仰していた。正治元年(一一九九)一月十三日頼朝公が亡くなるとここに葬り法華堂と呼ばれ毎年命日には将軍が参詣し仏事を執り行い多くの武将も参列した。その後鶴岡八幡宮の供僧『相承院』が奉仕して祭祀を続け、明治維新に際し寺は白旗神社に改められ源頼朝公を祭神として今日に至っている。現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和四十五年に源頼朝公報恩会の方々の篤志によって造営されたものである。」(白旗神社)
「この平場は鎌倉幕府を開いた源頼朝の法華堂(墳墓堂)が建っていた跡です。(略)建久10年(1199)に頼朝が53歳で没すると、法華堂は幕府創始者の墳墓堂として、のちの時代の武士たちからもあつい信仰を集めました。鎌倉幕府滅亡後も法華堂は存続しましたが、17世紀の初頭までには堂舎がなくなり、石造りの墓塔が建てられました。現在の墓域は、安永8年(1779)に薩摩藩主島津重豪によって整備されたものです。」(頼朝公墓所)
白旗神社の創立は明治5年なので、それ以前の文献に白旗神社の記述はなく、法華堂と記されています。
『新編鎌倉志』の法華堂の項には「西御門の東の岡なり。相傳、頼朝持佛堂の名也。【東鑑】に、文治四年(1188年)四月廿三日、御持佛堂に於て、法華経講読始行せらるとあり此所歟。同年七月十八日、頼朝、専光坊に仰て曰。奥州征伐の為に潜に立願あり。汝留守に候じ、此亭の後の山に梵字を草創すべし。年来の本尊正観音の像を安置し奉ん為なり。同年八月八日御亭の後山に攀登り、梵字営作を始む。先白地に假柱四本を立、観音堂の号を授くとあり。今雪下相承院領するなり。頼朝の守本尊正観音銀像も、相承院にあり。今此には彌陀、幷如意輪観音・地蔵像あり。地蔵は、本報恩寺の本尊なりしを、何れかの時か此に移す。(略)此法華堂を、右大将家法華堂と云なり。」とあります。
また、『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。正治元年(1199年)正月十三日頼朝薨ス(略)同二年正月十三日頼朝の小祥ニヨリ。法会ヲ行ハル。此時始テ法華堂ノ称アリ。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)(略)相承ヲ別当タリ。」
「什寶。正観音像一軀 銀佛ニテ立身長二寸頼朝ノ守護佛。髻観音ナリ。」とあります。
一方、頼朝公墓所(頼朝墓)についてみてみると、
『新編鎌倉志』には「法華堂の後の山にあり。【東鑑脱漏】に、法華堂西の岳上に、右幕下の御廟を安ず」とあり、『新編相模国風土記稿』には「堂後ノ山上に五輪塔一基ヲ建ツ。」とあります。
法華堂と頼朝公墓所(頼朝墓)の位置関係がどうもわかりにくいので、上記資料を参考に年表風にまとめてみました。
1.文治四年(1188年)4月23日、御持佛堂に於て法華経講読始行。
2.同年8月8日御亭(御持佛堂)の後山に梵字営作。假柱四本を立て観音堂の号を授く。
(この観音堂に頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)を奉安?。持佛堂とも称す?。)
(もとの御持佛堂には阿彌陀三尊、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安?)
3.正治元年(1199年)正月13日頼朝公薨す。後に頼朝公御廟を安ず。(→頼朝公墓所)
4.正治二年(1200年)正月13日の法会時、もとの御持佛堂(?)を法華堂と改める。
5.同時期に観音堂(持佛堂)は墳墓堂と改める。
6.法華堂は、鶴岡八幡宮寺の僧坊「相承院」が護持する。
7.17世紀の初頭までに墳墓堂が失われる。
8.安永8年(1779年)頼朝公墓所が薩摩藩主島津重豪によって整備される。
9.明治初年の神仏分離令施行に伴い法華堂は撤去され、明治5年10月白旗神社が建立。
10.現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和45年に造営。
上記のうち、1.4.9.10が現在の白旗神社、2.3.5.7.8が現在の頼朝公墓所を示すとみられますが、頼朝公墓所の広さからみると、堂宇は一旦墓所周辺(山上)に整備され、のちに一部が現社地に移動したのかもしれません。
なお、頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)は、現在扇ガ谷の鎌倉歴史文化交流館で展示されている模様です。(同館twitterより)
頼朝公墓所の下の公ゆかりの法華堂ですから、神社創立の際に御祭神を頼朝公とし、白旗神社を号したことは自然な流れとみられますが、「猫の足あと」様Webページ掲載の「神奈川県神社誌」には、以下のような文章があります。
「然しながら頼朝公を白旗大明神として祀ったのは相当古く、応安六年(一三七三)十一月十五日西御門の報恩寺(廃寺)境内に洞(堂?)が祀られていたと記録にある。」
報恩寺、白旗明神社ともに記録があります。
■『新編鎌倉志』
○報恩寺舊跡 附白旗明神社
「報恩寺舊跡は、西御門の西の谷にあり。当寺の本尊、今法華堂にあり。」
○白旗明神社
「寺滅して社も又亡ぶ。義堂祭白旗神文あり。其略に云、應安六年(1373年)冬、南陽山報恩護國禅寺、白旗大明神靈祠成るとあり。」
■『新編相模国風土記稿』
●報恩寺廃蹟
「南陽山報恩護國寺ト号セシ禅刹ニテ。應安四年(1371年)上杉兵部大輔能憲ノ起立ナリ。(略)其後何レノ頃廃寺トナリシヤ詳ナラス。当時(寺?)ノ本尊地蔵ハ。今法華堂ニ安セリ。境内ニ。白旗明神社在シトナリ。是モ寺滅シ頃。共ニ廃セシナルヘシ。今址タニナシ。應安六年(1373年)十一月起立セシモノナリ。」
報恩寺(廃寺)は法華堂の西側にあり、御本尊地蔵菩薩は廃寺ののちに法華堂に遷られたとされますが、その報恩寺内に應安六年(1373年)の時点で白旗明神社が祀られていたというのです。
こちらの御祭神は不明ですが、上記の「神奈川県神社誌」の文章は、この報恩廃寺の白旗明神社と(西御門)白旗神社の関係性を示唆するものともみられます。
また、報恩寺から法華堂に遷られた地蔵菩薩等は、明治のはじめに法華堂が廃されたときに満光山 来迎寺に遷られたとされています。
詳細はつぎの「15.満光山 来迎寺」をご覧ください。


【写真 上(左)】 正面階段上が頼朝公墓所
【写真 下(右)】 社頭(通常)
海がわから広がる鎌倉の平地が、北山にさしかかるところにあります。
週末は観光客のすがたもちらほら見られますが、ごったがえす若宮大路あたりと比べると落ち着いた趣。
あたりにどこかもの寂びた空気がただよっているのは、山裾という場所柄だけでなく、頼朝公の墓所であること、宝治元年(1247年)の宝治合戦で三浦一族500余名が自刃したという凄絶な歴史も影を落としているのかもしれません。
なお、宝治合戦で三浦一族が籠もった法華堂は、ここから少し東の山腹にある「法華堂跡」(北条義時法華堂跡)という説もあります。
こちらは『吾妻鏡』に「頼朝の法華堂の東の山をもって墳墓となす」と記された地とみられています。
北条義時法華堂跡の山上に、大江広元の墓所があります。


【写真 上(左)】 社頭(正月)-1
【写真 下(右)】 社頭(正月)-2


【写真 上(左)】 正月の拝殿
【写真 下(右)】 本殿
社頭に石灯籠一対、狛犬一対、鳥居は貫の突き出しのない神明鳥居系。
拝殿は銅板葺の神明造、本殿は銅板葺の一間社流造とみられます。


【写真 上(左)】 拝殿扁額
【写真 下(右)】 幟
境内にはためく幟には「白旗大明神」、拝殿向拝の扁額には「白旗明神」とあり、往年の神仏習合の歴史を伝えているかのよう。
法華堂の護持を司っていた相承院(頓覚坊)は『鶴岡八幡宮寺供僧次第』などにみられる「鶴岡二十五坊」のひとつです。
階段上の頼朝公墓所は相当な広さがあり、かつて堂宇があったことをうかがわせます。
墓石や手水石には源氏の「笹竜胆」紋だけでなく、なぜか薩摩の島津家の「轡十文字」紋がみられます。
幕末に墓所が荒れた際、頼朝公の子孫を称する薩摩藩主・島津重豪が整備して「轡十文字」を刻んだものとされています。(島津氏整備・寄進の石碑もあります。)
白旗神社は通常非常駐で、御朱印の授与は原則正月三が日に限られ、書置ながら鎌倉屈指のレア御朱印として知られています
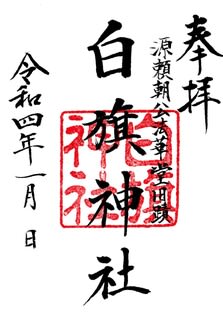
(西御門)白旗神社の御朱印
15.満光山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市西御門1-11-1
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第5番、鎌倉二十四地蔵霊場第2番、鎌倉十三仏霊場第10番、鎌倉郡三十三観音霊場第8番
鶴岡八幡宮の東側、西御門にある時宗寺院で、複数の現役霊場の札所を兼務されています。
鎌倉には来迎寺を号する寺院が西御門と材木座にあり、区別するためからか西御門来迎寺(にしみかどらいこうじ)と呼ばれます。
寺伝(公式Web)によると、永仁元年(1293年)の鎌倉大地震で亡くなった村民を供養するため一向上人により創建。
『新編鎌倉志』の来迎寺の項には「高松寺の南隣なり。時宗、一遍上人開基、藤澤清浄光寺の末寺なり。」とあります。
また、『新編相模国風土記稿』には「時宗。藤澤清浄光寺末。一遍の創建ナリ。本尊阿彌陀ヲ安ス。」とあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 八雲神社
横浜国大附属鎌倉中学校の東側の路地を山側に向かいます。
この路地は山裾で行き止まりとなり、みどころは来迎寺のほかには石川邸(旧里見邸)くらいしかないので、週末でも閑静な住宅街です。
T字路の右手に八雲神社、そのよこの階段の上が来迎寺です。
こちらの(西御門)八雲神社は『新編相模国風土記稿』記載の「字大門の天王社」とみられていますが、来迎寺との関係は定かではありません。
西御門の氏神社で、旧村社に列格していたとされます。
また、頼朝公起立と伝わる太平寺(廃寺)はこのあたりと伝わり、来迎寺の参道脇に「大平寺跡」の石碑が建っています。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 札所標
参道階段右手には、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三仏の札所標。
真新しい階段を昇ると視界が開け、左手に庫裡。もうひと昇りすると本堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
参道階段は東向きで、本堂前で南面する本堂に向きを変える曲がり参道です。
本堂は入母屋造本瓦葺の堂々たる構えで、軒下に向拝柱を置いています。
水引虹梁両端に草花紋様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
本瓦葺の軒丸瓦には時宗の宗紋「隅切三(すみきりさん)」が置かれ、向拝正面桟唐戸の上には山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
山内掲示によると、本堂には御本尊阿弥陀如来と地蔵菩薩像、如意輪観世音菩薩像が奉安されています。
御本尊の阿弥陀如来は鎌倉十三仏霊場第10番の札所本尊です。
地蔵菩薩像は廃寺となった報恩寺の御本尊で宅間浄宏の作と伝わり、岩を模した台座のうえに御座されることから「岩上地蔵尊」と呼ばれ、鎌倉二十四地蔵霊場第2番の札所本尊です。
中世禅刹で流行した「法衣垂下」の技法を用いた代表作として知られています。
如意輪観世音菩薩像は「鎌倉でもっとも美しい仏像」と賞される名作で、鎌倉特有の技法とされる「土紋」が鮮やかなことで知られ、鎌倉三十三観音霊場第5番の札所本尊です。
〔 関連記事 〕
■ 東京都区内の如意輪観音の御朱印
『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)」とあり、地蔵尊は報恩寺→法華堂→来迎寺と遷られたのではないでしょうか。
来迎寺の公式Webには、「客仏として如意輪観世音菩薩、岩上地蔵菩薩、跋陀婆羅尊者が祀られています。客仏の三体は源頼朝公の持仏堂の後身である法華堂(現在の源頼朝公の墓所付近)に安置されておりましたが、明治初年の神仏分離令を機に来迎寺へ移されました。」と明記されています。
ちなみに跋陀婆羅尊者は、寺院(とくに禅刹)の浴室の守護神とされます。
如意輪観世音菩薩像と岩上地蔵菩薩像は県指定文化財、跋陀婆羅尊者像は市指定文化財に指定されている、知る人ぞ知る「仏像の寺」です。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、新型コロナ禍中は事前確認してからの参拝がベターかもしれません。
〔 御本尊・阿弥陀如来(鎌倉十三仏霊場第10番)の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕
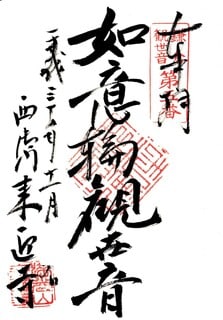

【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
16.鶴岡八幡宮
鎌倉市雪ノ下2-1-31
御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后
旧社格:旧国幣中社、別表神社
元別当:(八幡宮寺)
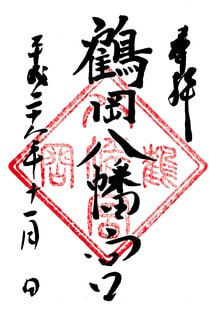
17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社
鎌倉市雪ノ下2-1-31
御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后
旧社格:鶴岡八幡宮境内社、旧柳営社合祀
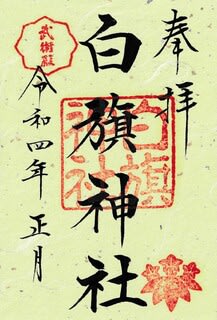
※正月のみの限定授与です。
18.旗上辨財天社
鎌倉市雪ノ下2-1-31
御祭神:辨財天
旧社格:鶴岡八幡宮境内社
札所:鎌倉・江ノ島七福神(辨財天)

16.鶴岡八幡宮、17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社、18.旗上辨財天社については、ものすごい量の史料が存在するので、別稿でまとめます。
19.巌窟堂 岩谷不動尊(いわやふどうそん)
不動茶屋のWeb
鎌倉市雪ノ下2-2-21
宗派不明
御本尊:不動明王
札所:
鎌倉ガイドでもあまり紹介されないお不動さまですが、古い歴史をもち、以前は巌窟(イハヤ)不動尊と呼ばれていました。
『新編鎌倉志』の巌窟不動の項には「巌窟(イハヤ)不動は、松源寺の西、山の根にあり。窟の中に、石像の不動あり。弘法の作と云ふ。【東鑑】に、文治四年(1188年)正月一日、佐野太郎基綱が巌窟の下の宅焼亡。鶴岡の近所たるに因て、二品頼朝宮中に参給ふとあり。此所の事あらん。此前の道を巌窟小路と云ふ。(中略)【東鑑】には、巌堂とあり。俗、或は岩井堂と云ふ。巌窟堂、今は教圓坊と云僧持分なり。昔は等覺院の持分なりけるにや。」とあります。
『鎌倉攬勝考』の巌窟不動尊の項には「【東鑑】に、窟堂又は岩屋堂、或は岩井堂と有るも、此所の事なり。日金地蔵のにしの山麓にて、窟中に石像の不動あり。弘法大師のさくといふ。此前の道路を岩屋小路と唱ふ。【東鑑】に、建長四年(1251年)五月五日、将軍家(宗譽)御方違の評定有て、亀が谷の方角を見定可申由仰にて、行義・行方・景頼等、彼六人を具して、巌窟のうしろの山上へ登るとあるも此地なり。昔は等覺院といふが別当なりしが、今は散圓坊といふ庵室の持とす。むかし等覺院別当のときは、日金堂をも兼持せしといふ。●に、等覺院といふは、十二院のうちなる巌覺院なるべし。」とあります。
以上から、弘法大師の御作と伝わる由緒正しい不動尊であることがわかります。
また、『新編相模国風土記稿』には「村西ニ巌窟アリ。濶三間許。高七尺。其中巌面ニ。不動ノ像。弘法ノ畵ク所ト云。ヲ彫ルノミ。今ハ堂宇ナシ。(中略)建久三年(1192年)五月。南御堂ニシテ。後白河法皇ノ御佛事。百僧供ヲ修セラレシ時。僧衆ノ内ニ。当堂ノ住侶ヲ加ラル。(中略)鎌倉志ニハ。巌窟不動ト挙。俗或ハ岩井堂ト云。今ハ教圓坊持ナリ。昔ハ等覺院鶴岡供僧。」とあります。
『吾妻鏡』(建久三年五月八日条)には、南御堂(勝長寿院)で行われた後白河法皇の四十九日法要には僧百が勤修し、その内訳は「鶴岡八幡宮供僧二十口、六所宮(六所社)二口、伊豆山(権現)十八口、筥根山(箱根権現)十八口、大山寺(阿夫利神社)三口、観音寺(不詳)三口、勝長壽院十三口、高麗寺(大磯・高来神社)三口、岩殿寺(逗子・岩殿寺?)二口、大倉観音堂(杉本寺)一口、巌窟一口、慈光寺(都幾川・慈光寺)十口、眞慈悲寺(日野・眞慈悲寺?)三口、浅草寺三口、弓削寺(小田原・飯泉観音?)二口、国分寺(海老名・国分寺?)三口也」と記され、巌窟堂が関東の大寺と並ぶ格式(ないし役割)をもっていたことがうかがえます。
『鎌倉攬勝考』の日金地蔵堂の項には「岩屋堂の東にて、山の半腹にあり。本尊地蔵、運慶作。右大将家、豆州謫居の頃より、御誓願有て、爰(ここ)に移し給ふといふ。別当日金山彌勒院松源寺といふ。真言新義。御室御所の末なり。」とあります。
こちらは、頼朝公が伊豆の日金山から勧請した日金地蔵尊(日金山松源寺)のとなりで、この界隈は頼朝公の信仰の場であった可能性がありますが、松源寺は廃寺となり、現在、日金地蔵尊は横須賀の東漸寺に遷られています。(→■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3)


【写真 上(左)】 横大路(窟小路)と入口
【写真 下(右)】 参道入口
鶴岡八幡宮から扇ガ谷に抜ける横大路(窟小路)は観光客の姿もみられますが、小町通りほどの雑踏はなく、落ち着いたたたずまいです。


【写真 上(左)】 石碑
【写真 下(右)】 境内
岩谷不動尊はこの道の北(山側)の小径を入った不動茶屋横に御座します。
横大路(窟小路)沿いの門柱には「巌窟不動尊」、その横には「不動茶屋」の幟、ラーメンが売りらしく、美味しそうなメニューも掲出されています。
左に古色を帯びた「不動尊」の石碑、右手に整然と庚申様や板碑、石塔が並ぶブロック塀沿いに進むと、そのおくに木の鳥居と不動堂。
左手の覆堂のなかにもお不動さまが御座しています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 不動堂
堂宇の背後は岩壁でやぐららしきものもみえます。
周囲はほの暗く、パワスポ的雰囲気が感じられます。
御本尊は石佛の不動明王立像です。
不動茶屋のWebには「この像は弘法大師の作とも言われています。永い年月の間にお不動様の像も風化し、後に石の像が作られ今に至っております。」とあります。
こちらのお不動様は、古くは背後の岩窟のなかに祀られていたようです。
御朱印は不動茶屋にて書置のものを拝受しましたが、当然のことながら営業時間内しか拝受できません。
〔 御本尊・岩谷不動尊の御朱印 〕

これでA.朝夷奈口はひとまず校了です。
つぎは南側のB.名越口に進みます。
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ。
【 BGM 】
■ 地上に降りるまでの夜 - 今井美樹
→ ■ 今井美樹の名バラード25曲!
■ 永遠 ~小さな光~ - 詩月カオリ
■ YOU ARE NOT ALONE - 杏里
→ ■ 杏里の名バラード20曲!
■ 夢の途中 - KOKIA
→ ■ KOKIAの名バラード12曲
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ ウクライナ難民支援御朱印 ~ 西上州の御朱印めぐり ~
2022/06/23 UP
いよいよ終盤。6/30までの授与(予定)です。
気合い入れれば2日で結願できると思います。
時間と興味のある方はぜひぜひどうぞ。
----------------------
2022/06/10 UP
群馬県の西部(西毛エリア・西上州)の安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町の曹洞宗18箇寺で現在ウクライナ難民支援御朱印が授与されています。
御朱印デザインはウクライナ国旗の青と黄を基調としたもの。
御朱印揮毫は各寺院とも「消災妙吉祥陀羅尼」の一節で、18箇寺巡拝の結願で「消災妙吉祥陀羅尼」が完成することになります。
御朱印代は、すべてウクライナ難民支援の浄財となります。
結願でお納めする金額(=ウクライナ難民支援に使われる金額)は、合計5,400円以上となります。
公式Web
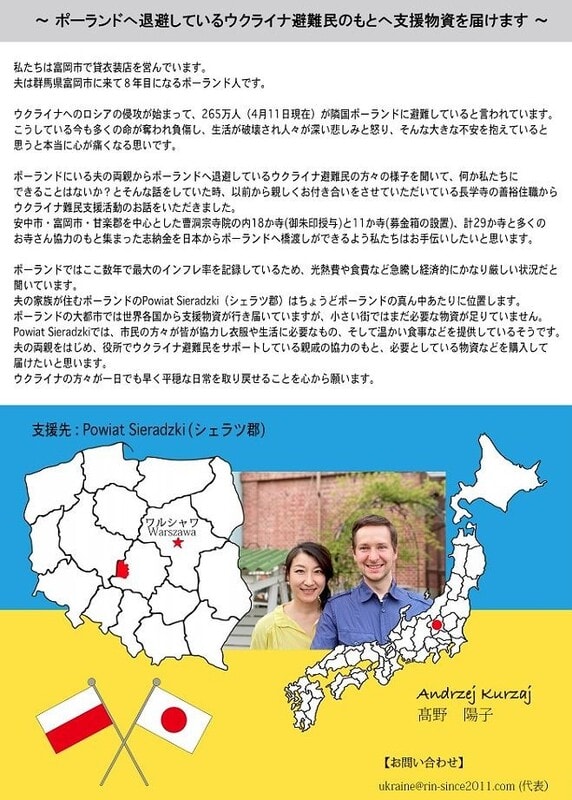
↑ 当プロジェクト発足の経緯
1.期間:2022年4月8日~6月30日(予定)
2.御朱印代:300円以上
3.御朱印:原則書置にて授与
4.専用納経帳や台紙はとくにありません。
【記事】
上毛新聞Web
東京新聞Web
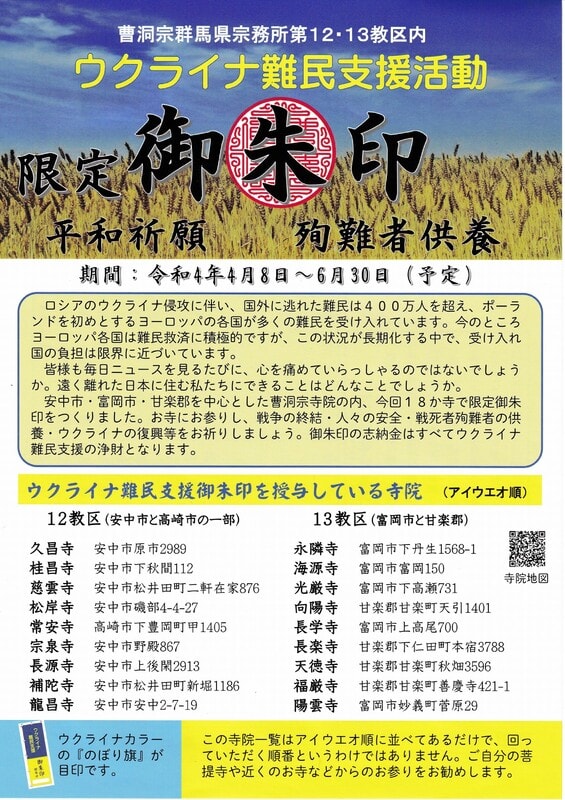
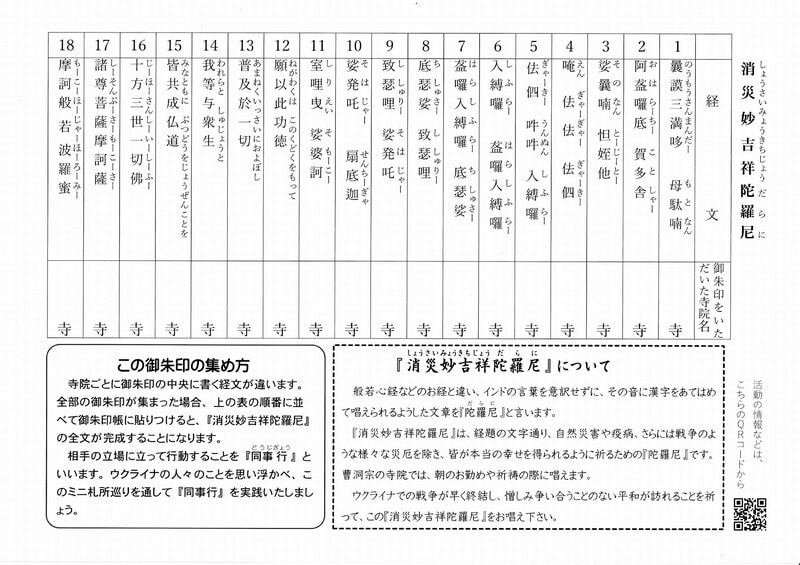
【写真 上(左)】 チラシ表面
【写真 下(右)】 チラシ裏面

地図
西上州(安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町・藤岡市)には、上野国一宮の一之宮貫前神社、運気上昇のパワスポとして知られる中之嶽神社、数多くの兼務社の御朱印を授与されている鷺宮 咲前神社(さきさきじんじゃ)などの神社があり、北関東有数のメジャー霊場、新上州・観音霊場三十三ヵ所の札所を8箇所数えるという、北関東屈指の御朱印エリアです。
西上州観光連盟は、域内の寺社や御朱印を紹介するリーフレット「西上州ご朱印めぐり にしじょたび」を作成・配布するなど、西上州は寺社や御朱印めぐりによる観光振興に積極的なエリアとして知られています。
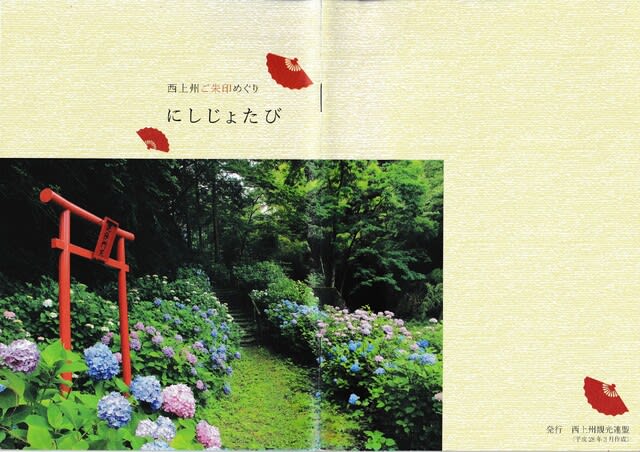
このような素地もあって、「御朱印」を契機とする人道支援策が企画・発案されたのかもしれません。
→ 西上州ご朱印めぐりのリスト(「ニッポンの霊場」様)
先日、結願しました。
雰囲気のある禅刹が多く、まわっていて心なごみます。
天気がよければ、新緑の妙義山や浅間山を間近に望みながらの巡拝ができます。
すべての寺院に駐車スペースがありますので、車での巡拝に問題なしです。
というか、山中のお寺さまもいくつかあるので、車じゃないと巡拝結願はむずかしいかと思います。


まわり始めると札番?は自然にわかるのですが、発願前には札番はわからない、という面白い霊場?でもあります。
また、非札所でこれまで御朱印情報がなかったお寺さまの御朱印を拝受できるチャンスでもあります。
ウクライナ支援御朱印の主印は三寶印ないし御寶印で、揮毫は経文なので完璧な御朱印ですが、こちらとは別に御本尊・別尊の尊格御朱印を授与されている寺院もあります。


【写真 上(左)】 幟
【写真 下(右)】 御朱印揃え
ご参考までに18寺院すべての写真と御朱印をUPします。
順番は「消災妙吉祥陀羅尼」の経文に沿いました。
1.正寿山 永隣寺

公式Web
富岡市下丹生1568-1
御本尊:十一面観世音菩薩
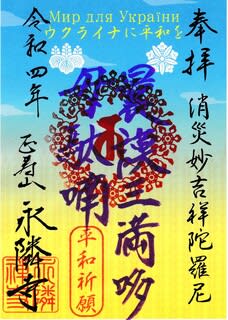
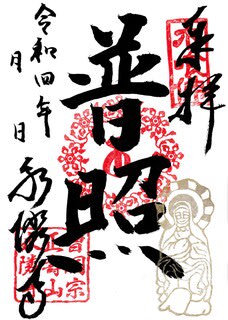
・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
2.熊峯山 桂昌寺

安中市Web資料(PDF)
安中市下秋間112
御本尊:釈迦牟尼仏
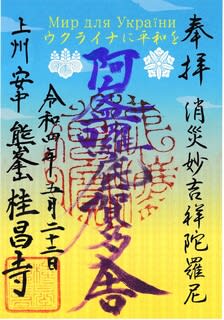

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
・不動明王の御朱印も授与されています。
3.中法山 海源寺

公式Web
富岡市富岡150
御本尊:釈迦如来
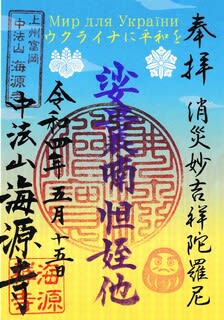

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
4.月桂山 久昌寺

公式Web
安中市原市2989
御本尊:薬師如来
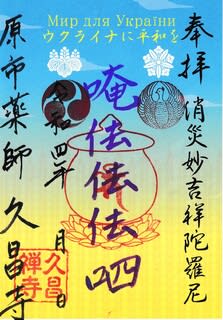
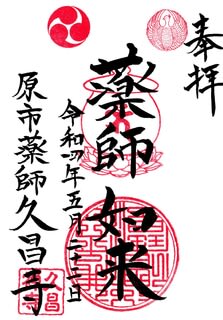
・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。
5.友月山 向陽寺

甘楽町Web資料
甘楽町天引1401
御本尊:釈迦牟尼仏?
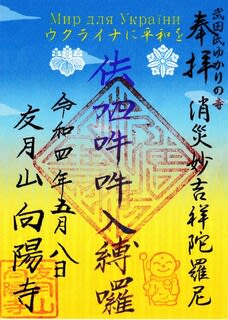
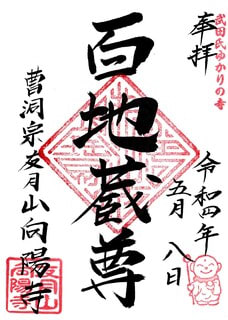
・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
6.大泉山 補陀寺

群馬県Web資料
安中市松井田町新堀1186
御本尊:釈迦如来
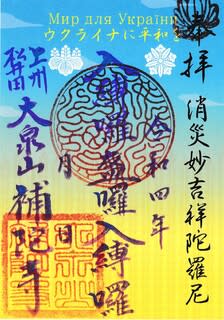

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
・松井田城の御城印も授与されています。
7.白龍山 慈雲寺

安中市松井田町二軒在家876
御本尊:釈迦牟尼仏
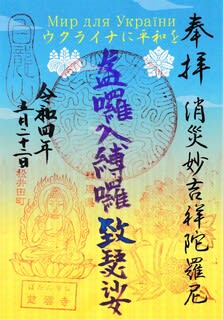
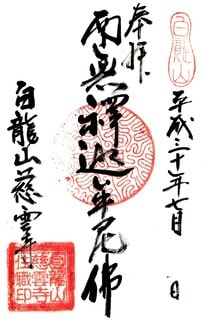
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
8.鳳来山 光厳寺

公式Web
富岡市下高瀬731
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:上野之國三十四カ所観音霊場第3番
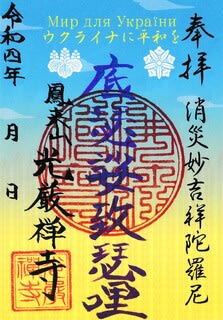
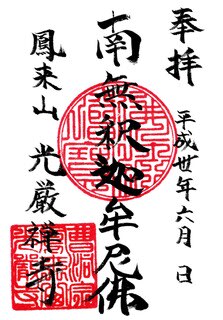
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点では尊格御朱印は原則不授与となっている模様です。
9.薬王山 宗泉寺

公式Web
安中市野殿867
御本尊:釈迦牟尼仏

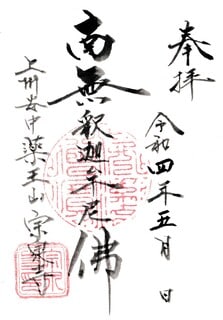
・尊格御朱印は書置のものを拝受できましたが、常時ご用意されているかは不明です。
10.金鶏山 陽雲寺

富岡市妙義商工会Web
富岡市妙義町菅原29
御本尊:釈迦牟尼仏

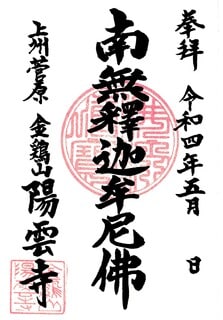
・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
11.祝融山 神泉院 長学寺

公式Web
富岡市上高尾700
御本尊:釈迦牟尼仏
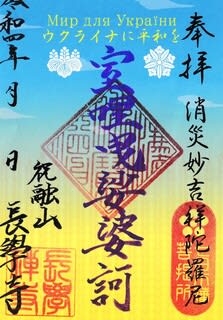
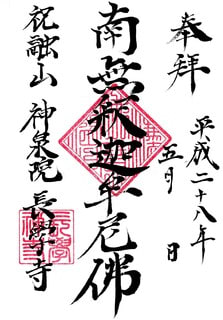
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
12.八幡山 月光院 常安寺

公式Web
高崎市下豊岡町甲1405
御本尊:釈迦牟尼仏
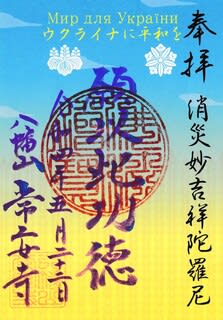
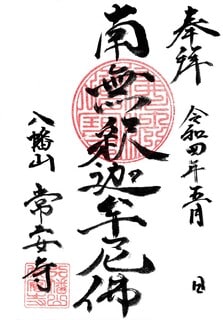
・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。
13.礒明山 松岸寺

安中市Web資料
安中市磯部4-4-27
御本尊:釈迦牟尼仏
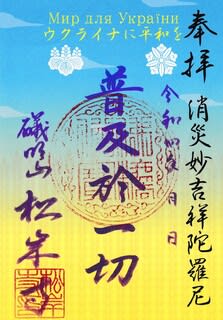

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
14.弘誓山 長楽寺

下仁田町Web資料
下仁田町本宿3788
御本尊:釈迦如来
札所:東国花の寺百ヶ寺霊場第31番
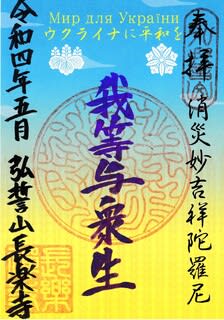
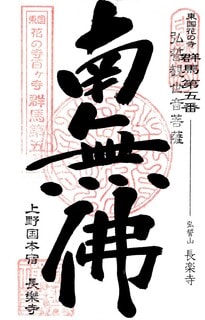
・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。
15.青木山 護国院 長源寺

安中市上後閑2913
御本尊:釈迦如来
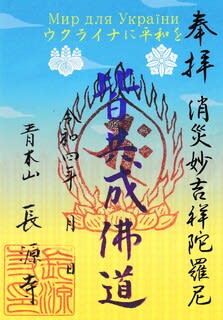
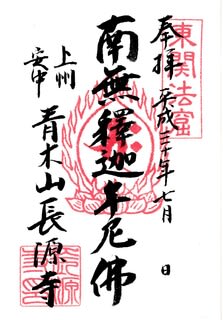
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
16.金谷山 天徳寺

甘楽町秋畑3596
御本尊:釈迦如来・阿弥陀如来
札所:小幡七福神(弁財天)


・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
・御本尊御朱印は不授与の模様です。
17.洞谷山 角峯院 龍昌寺

公式Web
安中市安中2-7-19
御本尊:釈迦牟尼仏

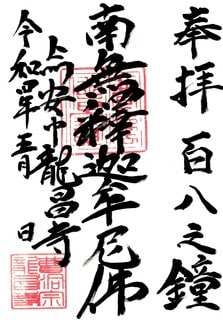
・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
18.泉谷山 福厳寺

公式Web
甘楽町善慶寺421-1
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:小幡七福神(毘沙門天)
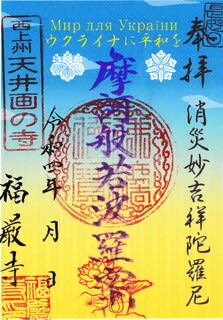
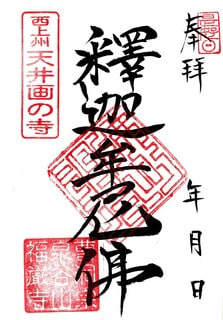
・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。複数の御朱印を書置にて授与されています。
まだまだ期間はありますので、興味のある方はトライされてみてはいかがでしょうか。
【 BGM 】 ~ 日本の歌姫特集 ~
■ Over and Over - Every Little Thing
■ Hello,my friend - 松任谷由実
■ ヒカリヘ - miwa
■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)
■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV)
■ Fly High - milet
■ 潮見表 - 遊佐未森
■ 未来/mirai - Kalafina
■ 孤独な生きもの - KOKIA
■ Pray - 今井美樹
→ ■ 歌の女神が舞い降りた国 / 美メロ&ハイトーン&透明感の癒し曲50曲
いよいよ終盤。6/30までの授与(予定)です。
気合い入れれば2日で結願できると思います。
時間と興味のある方はぜひぜひどうぞ。
----------------------
2022/06/10 UP
群馬県の西部(西毛エリア・西上州)の安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町の曹洞宗18箇寺で現在ウクライナ難民支援御朱印が授与されています。
御朱印デザインはウクライナ国旗の青と黄を基調としたもの。
御朱印揮毫は各寺院とも「消災妙吉祥陀羅尼」の一節で、18箇寺巡拝の結願で「消災妙吉祥陀羅尼」が完成することになります。
御朱印代は、すべてウクライナ難民支援の浄財となります。
結願でお納めする金額(=ウクライナ難民支援に使われる金額)は、合計5,400円以上となります。
公式Web
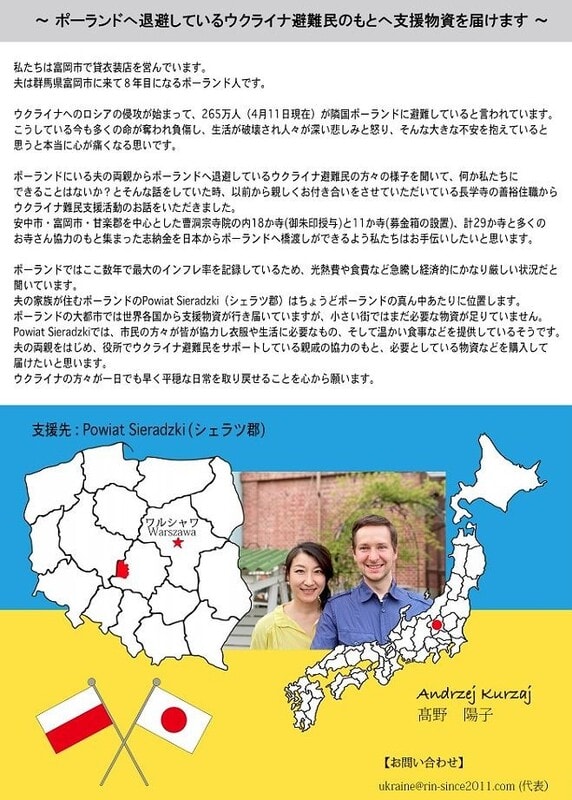
↑ 当プロジェクト発足の経緯
1.期間:2022年4月8日~6月30日(予定)
2.御朱印代:300円以上
3.御朱印:原則書置にて授与
4.専用納経帳や台紙はとくにありません。
【記事】
上毛新聞Web
東京新聞Web
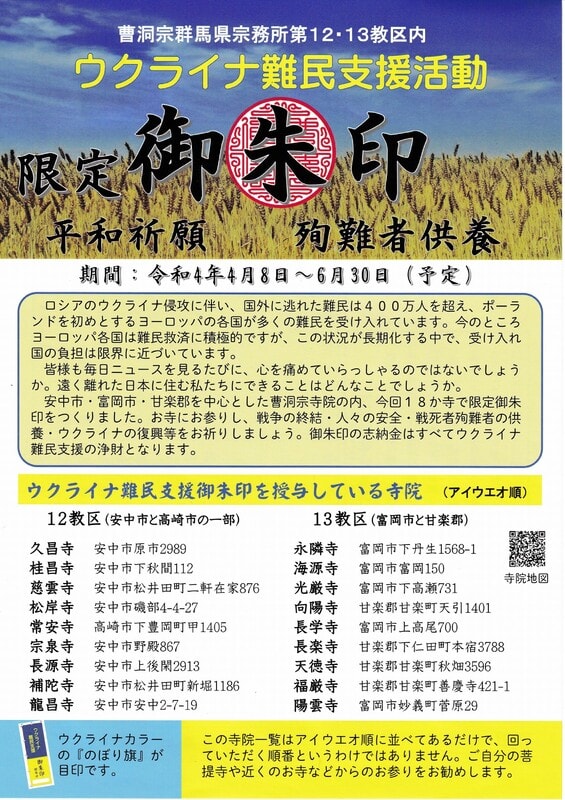
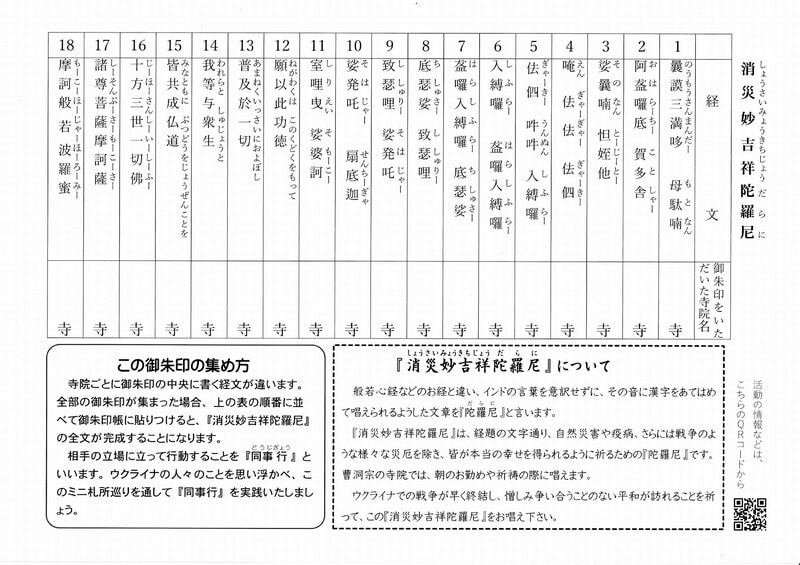
【写真 上(左)】 チラシ表面
【写真 下(右)】 チラシ裏面

地図
西上州(安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町・藤岡市)には、上野国一宮の一之宮貫前神社、運気上昇のパワスポとして知られる中之嶽神社、数多くの兼務社の御朱印を授与されている鷺宮 咲前神社(さきさきじんじゃ)などの神社があり、北関東有数のメジャー霊場、新上州・観音霊場三十三ヵ所の札所を8箇所数えるという、北関東屈指の御朱印エリアです。
西上州観光連盟は、域内の寺社や御朱印を紹介するリーフレット「西上州ご朱印めぐり にしじょたび」を作成・配布するなど、西上州は寺社や御朱印めぐりによる観光振興に積極的なエリアとして知られています。
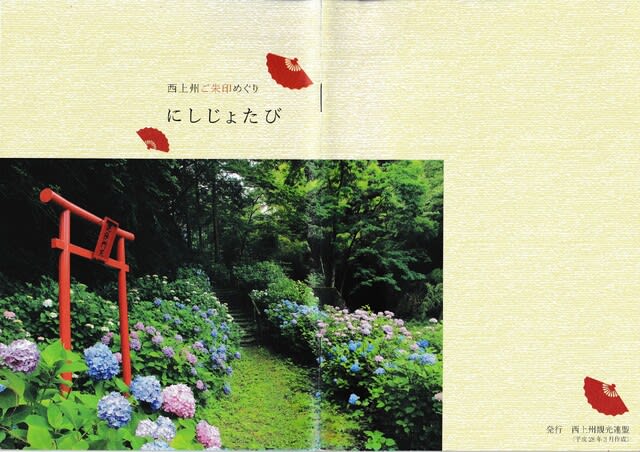
このような素地もあって、「御朱印」を契機とする人道支援策が企画・発案されたのかもしれません。
→ 西上州ご朱印めぐりのリスト(「ニッポンの霊場」様)
先日、結願しました。
雰囲気のある禅刹が多く、まわっていて心なごみます。
天気がよければ、新緑の妙義山や浅間山を間近に望みながらの巡拝ができます。
すべての寺院に駐車スペースがありますので、車での巡拝に問題なしです。
というか、山中のお寺さまもいくつかあるので、車じゃないと巡拝結願はむずかしいかと思います。


まわり始めると札番?は自然にわかるのですが、発願前には札番はわからない、という面白い霊場?でもあります。
また、非札所でこれまで御朱印情報がなかったお寺さまの御朱印を拝受できるチャンスでもあります。
ウクライナ支援御朱印の主印は三寶印ないし御寶印で、揮毫は経文なので完璧な御朱印ですが、こちらとは別に御本尊・別尊の尊格御朱印を授与されている寺院もあります。


【写真 上(左)】 幟
【写真 下(右)】 御朱印揃え
ご参考までに18寺院すべての写真と御朱印をUPします。
順番は「消災妙吉祥陀羅尼」の経文に沿いました。
1.正寿山 永隣寺

公式Web
富岡市下丹生1568-1
御本尊:十一面観世音菩薩
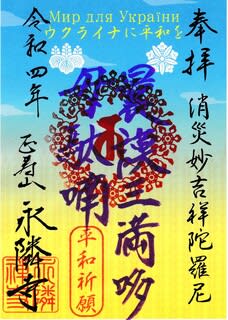
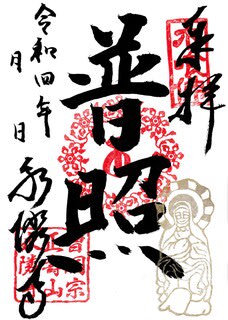
・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
2.熊峯山 桂昌寺

安中市Web資料(PDF)
安中市下秋間112
御本尊:釈迦牟尼仏
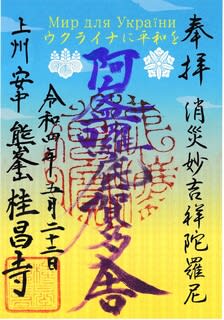

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
・不動明王の御朱印も授与されています。
3.中法山 海源寺

公式Web
富岡市富岡150
御本尊:釈迦如来
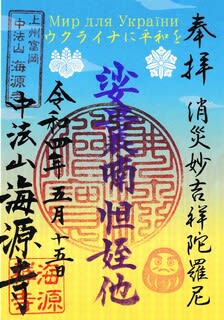

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
4.月桂山 久昌寺

公式Web
安中市原市2989
御本尊:薬師如来
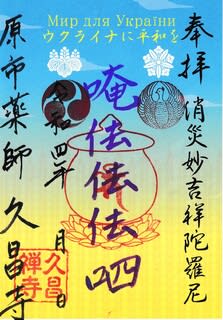
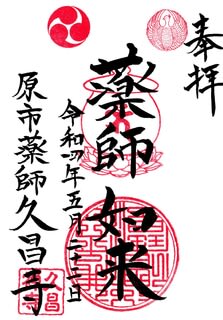
・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。
5.友月山 向陽寺

甘楽町Web資料
甘楽町天引1401
御本尊:釈迦牟尼仏?
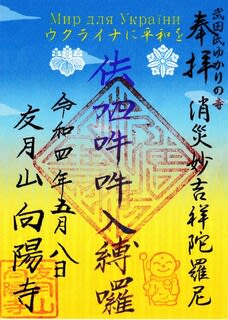
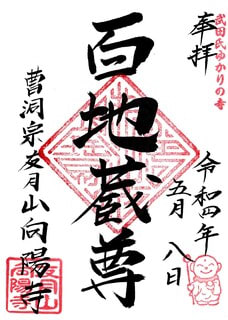
・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
6.大泉山 補陀寺

群馬県Web資料
安中市松井田町新堀1186
御本尊:釈迦如来
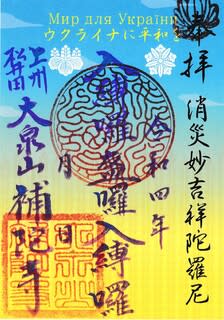

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。
・松井田城の御城印も授与されています。
7.白龍山 慈雲寺

安中市松井田町二軒在家876
御本尊:釈迦牟尼仏
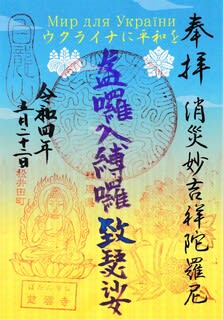
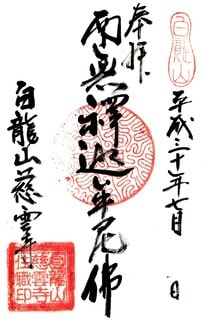
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
8.鳳来山 光厳寺

公式Web
富岡市下高瀬731
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:上野之國三十四カ所観音霊場第3番
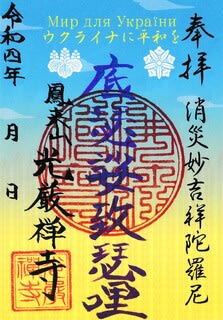
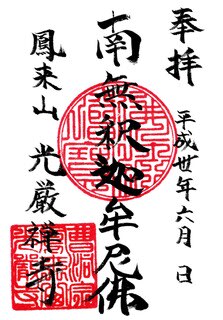
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点では尊格御朱印は原則不授与となっている模様です。
9.薬王山 宗泉寺

公式Web
安中市野殿867
御本尊:釈迦牟尼仏

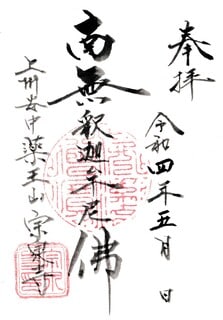
・尊格御朱印は書置のものを拝受できましたが、常時ご用意されているかは不明です。
10.金鶏山 陽雲寺

富岡市妙義商工会Web
富岡市妙義町菅原29
御本尊:釈迦牟尼仏

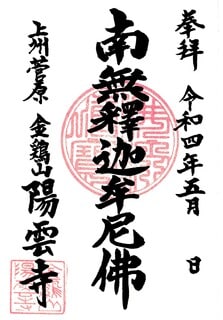
・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
11.祝融山 神泉院 長学寺

公式Web
富岡市上高尾700
御本尊:釈迦牟尼仏
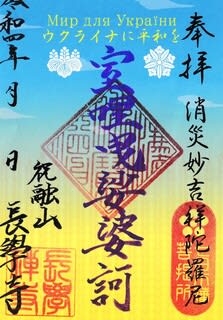
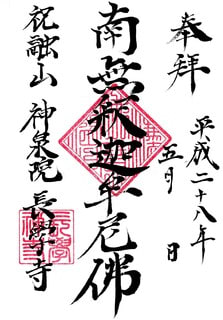
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
12.八幡山 月光院 常安寺

公式Web
高崎市下豊岡町甲1405
御本尊:釈迦牟尼仏
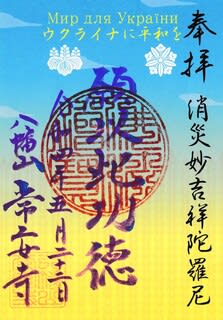
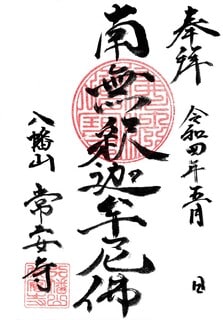
・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。
13.礒明山 松岸寺

安中市Web資料
安中市磯部4-4-27
御本尊:釈迦牟尼仏
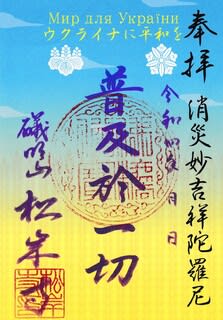

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
14.弘誓山 長楽寺

下仁田町Web資料
下仁田町本宿3788
御本尊:釈迦如来
札所:東国花の寺百ヶ寺霊場第31番
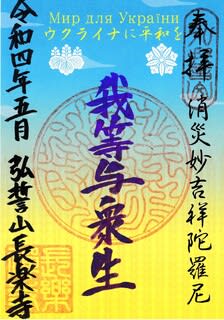
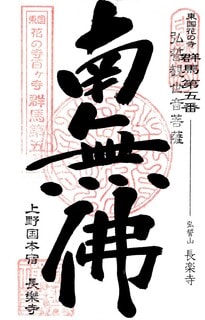
・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。
15.青木山 護国院 長源寺

安中市上後閑2913
御本尊:釈迦如来
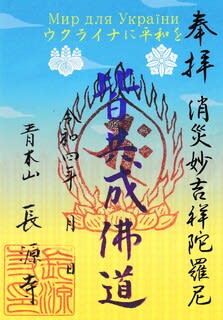
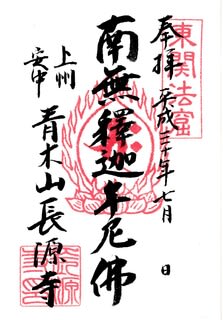
・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
16.金谷山 天徳寺

甘楽町秋畑3596
御本尊:釈迦如来・阿弥陀如来
札所:小幡七福神(弁財天)


・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。
・御本尊御朱印は不授与の模様です。
17.洞谷山 角峯院 龍昌寺

公式Web
安中市安中2-7-19
御本尊:釈迦牟尼仏

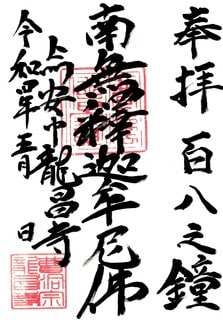
・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。
18.泉谷山 福厳寺

公式Web
甘楽町善慶寺421-1
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:小幡七福神(毘沙門天)
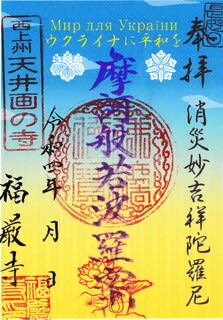
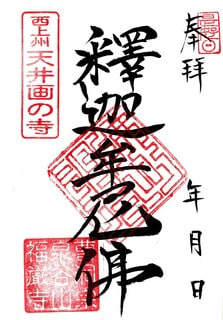
・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。複数の御朱印を書置にて授与されています。
まだまだ期間はありますので、興味のある方はトライされてみてはいかがでしょうか。
【 BGM 】 ~ 日本の歌姫特集 ~
■ Over and Over - Every Little Thing
■ Hello,my friend - 松任谷由実
■ ヒカリヘ - miwa
■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)
■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV)
■ Fly High - milet
■ 潮見表 - 遊佐未森
■ 未来/mirai - Kalafina
■ 孤独な生きもの - KOKIA
■ Pray - 今井美樹
→ ■ 歌の女神が舞い降りた国 / 美メロ&ハイトーン&透明感の癒し曲50曲
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2
文字数オーバーしたので、Vol.2をつくりました。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1から
今回、この記事を書いていて感じたのは、史料・物語の扱いのむずかしさです。
鎌倉幕府草創期関連のメジャー史料として『吾妻鏡』があり、メジャーな軍記物語として『平家物語』(源平盛衰記)、『義経記』などがあります。
多くの人はこの時代について、これらの書物が合体した内容でイメージされているのではないでしょうか。(「鎌倉殿の13人」も『吾妻鏡』をベースに構成されているらしい。)
筆者は歴史を専攻したわけでも、歴史家でもないので、「史学」の外からなんのしがらみもなく眺めることができるのですが、「歴史」がわかりにくく、堅苦しくなっている理由のひとつに、”史料批判”あるいは”一次資料原理主義”があるのでは? と感じています。
”史料批判”の定義からして何説かありそうですが(笑)、まぁ、史料の正統性(信頼性)や妥当性について吟味評価すること、あるいは歴史にかかわる論述がこのような「正統な史料」にもとづいてなされているかを評価(批評)すること、というほどの意味ではないでしょうか。
なので、”一次資料”にもとづかない説は、それが卓越した内容を含んでいても、学問の世界では「根拠の正統性に欠ける」として顧みられない、あるいは”(学説ではなく)単なる歴史小説”として揶揄される傾向があるように感じています。
ふつう”一次史料”とは、当事者がリアルタイムで遺した手紙、文書、日記、あるいは公文書などで、後日や後世の編纂が入っていないものをいいます。(この時期でいうと『玉葉』(九条兼実)や『明月記』(藤原定家))
(”一次史料”は史料的価値が定まっているので使いやすいのだと思う。でも、手紙や日記には筆者の個人的主観が入っているので、かならずしも100%史実ではないような気もするが・・・。)
※ ご参考→「図書館司書のための歴史史料探索ガイド」(土屋直之氏/PDF)
『吾妻鏡』は二次史料(後世の編纂書物)とされ、異本もあるので「研究・解釈」する余地が多くあり「『吾妻鏡』の解釈・研究」についての研究があるほどです。
なので、ひとつの記述について、複数の解釈があることはめずらしくありません。
江戸期くらいになると一次資料はふんだんにありますが、鎌倉時代あたりではどうしても『吾妻鏡』などの二次(編纂)史料を使わざるを得ない(一次史料だけでは論理構成できない)、という背景もあるようです。
『吾妻鏡』は”史料”で、『平家物語』『義経記』は”物語”ですから、”史料批判”の立場からするとこれらの物語の記述などはとるに足らないものかもしれませんが、これらが人々に植え付けてきた”源平合戦”のイメージは否定できないものがあるかと。
じっさい、現地掲示板などでは、”史料”と”物語”混在の内容がけっこうみられたりします。(現地案内板は、それを読む民間人にとってはある意味「史実」。)
これらを整合して書こうとすると膨大な労力と時間がかかり、さらに対象となる御家人が150人近くもいるとなるとキリがないので、あくまでもWebや現地案内板などでメインとなっている内容(事実上の通説?)をかいつまんで、概要的にさらっとまとめていきたいと思います。
と、愚にもつかない言い訳をしつつ(笑)、さらにつづけます。
14.稲荷山 東林寺 〔工藤氏・伊東氏・曾我氏〕
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆・伊東観光ガイド
静岡県伊東市馬場町2-2-19
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩(阿弥陀三尊とも)
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:葛見神社(伊東市馬場町)
他札所:伊豆八十八ヶ所霊場第27番、伊豆二十一ヶ所霊場第17番、伊豆伊東六阿弥陀霊場第2番、伊東温泉七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
藤原南家の流れとされる工藤氏は、平安時代から鎌倉時代にかけて東伊豆で勢力を張り、当初は久須見氏(大見・宇佐見・伊東などからなる久須見荘の領主)を称したともいいますが、のちに伊東氏、河津氏、狩野氏など地名を苗字とするようになりました。
東伊豆における工藤(久須見)氏の流れは諸説あるようですが、これがはっきりしないと菩提寺である東林寺の縁起や『曽我物語』の経緯がわかりません。
いささか長くなりますが整理してみます。
工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸をもうけたことを知った祐親は激怒し千鶴丸を殺害、さらに頼朝公の殺害をも図ったとされます。
このとき、頼朝公の乳母・比企尼と、その三女を妻としていた次男の祐清が危機を頼朝公に知らせ、頼朝公は伊豆山神社に逃げ込んで事なきを得たといいます。
なお、北条時政の正室は伊東祐親の娘で、鎌倉幕府第二代執権・北条義時は祐親の孫にあたるので、鎌倉幕府における伊東祐親の存在はすこぶる大きなものがあったとみられます。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため当寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
なお、当寺は久安年間(1145-1150年)、真言宗寺院として開かれ、当初は久遠寺と号しました。
天文七年(1538年)に長源寺三世圓芝春徳大和尚が曹洞宗に改宗しています。
治承四年(1180年)頼朝公が挙兵すると、伊東祐親は大庭景親らと協力して石橋山の戦いでこれを撃破しました。
しかし頼朝公が坂東を制圧したのちは追われる身となり、富士川の戦いの後に捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられ、義澄の助命嘆願により命を赦されたものの、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」といい、養和二年(1182年)2月、自害して果てたとされます。
以後、東林寺は伊東家累代の菩提寺となりました。
また、伊東氏の尊崇篤い葛見神社の別当もつとめていました。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
(なお、平賀氏は清和(河内)源氏義光流の信濃源氏の名族で、源氏御門葉、御家人筆頭として鎌倉幕府草創期に隆盛を誇りました。
この時期の当主は平賀義信とその子惟義で、惟義は一時期近畿6ヶ国の守護を任されましたが、以降は執権北条氏に圧され、惟義の後を継いだ惟信は、承久三年(1221年)の承久の乱で京方に付き平賀氏は没落しました。)
工藤祐経の子・祐時は伊東氏を称し、日向国の伊東氏はその子孫とされています。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
伊東市街の山寄りに鎮まる旧郷社・葛見神社のさらに奥側にあります。
伊豆半島の温泉地の寺院は路地奥にあるものが多いですが、こちらは比較的開けたところにあり、車でのアクセスも楽です。
伊東氏の菩提寺で、伊東温泉七福神の札所でもあるので観光スポットにもなっている模様。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
山門は切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で、「東林寺」の寺号板と「稲荷山」の扁額。
山内向かって左手に鐘楼、正面に入母屋造桟瓦葺唐破風向拝付きの本堂。
大がかりな唐破風で、鬼板に経の巻獅子口。刻まれた紋は伊東氏の紋としてしられる「庵に木瓜」紋です。
兎の毛通しの拝み懸魚には立体感あふれる天女の彫刻。
水引向拝両端には正面獅子の木鼻、側面に貘ないし像の木鼻。
中備には迫力ある龍の彫刻を置き、向拝上部に「東林禅寺」の寺号扁額が掛かります。
本堂には御本尊のほか、伊東祐親・河津祐泰・曽我兄弟の位牌や伊東祐親の木像、頼朝公と祐親の三女八重姫との間に生まれた千鶴丸の木像を安置しているそうです。
本堂向かって右の一間社流造の祠は伊東七福神の「布袋尊」です。
堂前に樹木は少なく、すっきり開けたイメージのある山内です。
河津三郎の墓、曽我兄弟の供養塔は鐘楼左の参道上にあり、東林寺の向かいの丘の上には伊東祐親の墓所と伝わる五輪塔(伊東市指定文化財)があるそうです。
御朱印は右手の庫裡にて拝受しました。

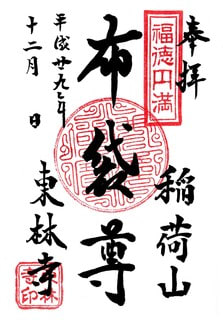
【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 伊東七福神(布袋尊)の御朱印
→ ■ 伊東温泉 「いな葉」の入湯レポ
→ ■ 伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」の入湯レポ
15.葛見神社 〔伊東氏〕
伊豆・伊東観光ガイド
静岡県伊東市馬場町1-16-40
御祭神:葛見神、倉稲魂命、大山祇命
旧社格:延喜式内社(小)論社、旧郷社
元別当:稲荷山 東林寺(伊東市馬場町、曹洞宗)
葛見神社は伊東市馬場町に御鎮座の古社で、東林寺にもほど近いところにご鎮座です。
創建は不詳ですが延長五年(927年)編纂の延喜式神名帳に記された式内社「久豆弥神社」とされているので、社暦はそうとうに古そうです。
境内由緒書には「伊東家守護神、往古、伊豆の東北部を葛見の荘と称し、当神社はこの荘名を負い、凡そ九百年の昔、葛見の荘の初代地頭工藤祐高公(伊東家次・・・伊東家の祖)が社殿を造営し、守護神として京都伏見稲荷を勧請合祀してから、伊東家の厚い保護と崇敬を受けて神威を高めてきました。」とあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
平安時代から当地に拠った工藤氏、伊東氏の崇敬篤く、伊東氏の菩提寺・東林寺はその別当でした。
主祭神は葛見神。伏見稲荷大社の分霊を勧請合祀しています。
伊豆屈指の名社で、明治初頭に郷社に列格しています。


【写真 上(左)】 大樟
【写真 下(右)】 御朱印
延喜式内社だけあり、境内はさすがに神さびた空気が感じられます。
境内の大樟は樹齢千数百年ともいわれ、治承四年(1180年)、石橋山の戦いで破れ窮地におちいった頼朝公が根本の空洞で身を隠したとも伝わり国指定天然記念物に指定されています。
御朱印は社務所にて拝受しましたが、常時授与されているかは不明です。
16.飯室山 大福寺
〔浅利冠者義遠(義成)〕
浅利与一没後800年 特設ページ(山梨県中央市)
山梨県中央市大鳥居1621
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩(創立御本尊は不動明王)
札所:甲斐国三十三番観音札所第11番、甲斐百八霊場武州八十八霊場第49番
浅利与一は、『平家物語』の源平合戦最後のハイライト、壇ノ浦の戦いで「遠矢」を放った弓の名手として知られています。
源平合戦で与一を名乗り「三与一」と賞された3人の武将は、佐奈田(真田)与一、那須与一、そして浅利与一(余一)で、いずれも単なる「弓の名手」ではなく、れっきとした武家の統領とみられます。
浅利与一の正式な名は浅利(冠者)義遠(義成とも)。
清和源氏義光流の逸見清光の子とされ、兄弟には逸見光長、武田信義、加賀美遠光、安田義定など、錚々たる顔ぶれの甲斐源氏が揃います。
源平合戦では富士川の戦いから壇ノ浦の戦いまで転戦し、奥州出兵にも参加、↓で板額御前が捕えられた建仁元年(1201年)の城氏の乱にも出兵しています。
有名な「遠矢」の場面については→こちら(中央市Web史料)をご覧ください。
また、義遠は越後の豪族城氏の女傑、板額御前を娶ったことでも知られています。
板額御前については→こちら(中央市Web史料)でくわしく紹介されています。
二代将軍源頼家公治世の建仁元年(1201年)、城小太郎資盛の反乱で弓の名手として活躍した資盛の叔母、板額御前は敗戦後捕らえられ鎌倉に送られました。
剛勇だけでなく美貌も謳われた板額御前は、頼家公以下御家人居並ぶなかに引き出されましたが、いささかも臆することなく毅然たる態度を崩さなかったそうです。
その翌日、義遠はこの板額を嫁に貰い受けたい旨を頼家公に願い出て許され、板額は義遠の室となって甲斐に居住し、浅利氏の跡継ぎを設けたと伝わります。
木曽義仲の側妾・巴御前と並ぶ女傑として賞され、「巴板額」(ともえはんがく)ということばが伝わります。
鎌倉幕府草創期、安田義定、一条忠頼、逸見有義、板垣兼信、秋山光朝など甲斐源氏の主要メンバーがつぎつぎと排斥されていくなかで、御家人中枢の立場を守り抜き、しかも敵将の息女の貰い受けを将軍に直訴するとは、甲斐源氏の一員としての微妙な立場を考えると、ある意味際立った立ち回りともいえます。
義遠は壇ノ浦の勲功もあってか奥羽比内郡地頭職を拝領しており、浅利氏は比内地方(秋田県北部)にも定着しました。
また、子孫の浅利信種は戦国期に活躍、奉行、箕輪城の城代、西上州への侵攻と勤め、後北条氏との三増峠の戦いで討死。
家督は嫡男の昌種が引き継ぎ、のちに浅利同心衆は土屋昌続に仕えて、昌続が天目山の「片手千人切り」で奮戦戦死したのち、嫡男の土屋忠直は大名に取り立てられ土屋家は明治まで大名家として存続しました。
浅利氏の本拠は甲斐国八代郡浅利郷(いまの山梨県中央市(旧増富村))で、義遠の墓所は浅利山 法久寺および飯室山 大福寺とされ、大福寺は御朱印を拝受しているのでこちらをご紹介します。


【写真 上(左)】 大福寺の本堂
【写真 下(右)】 大福寺本堂の扁額
大福寺は天平十一年(739年)行基の開創とされる古刹。
あたりは浅利義遠の舘で、建暦元年(1211年)、浅利家の菩提寺として伽藍を再建、寺領を寄進したとも伝わります。
甲州武田家の祖・武田信義の孫(義遠の甥)、飯室禅師光厳の再興ともいいます。
シルクの里公園に隣接し、本堂と観音堂は点在気味に離れてややとりとめのない印象ですが、かつては七堂伽藍を整えたという名刹です。
平安期作とされる「木造聖観音及び諸尊像」および「木造薬師如来坐像」は県指定有形文化財。
義遠の墓所とされる「浅利与一層塔」も県指定有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 大福寺の観音堂
【写真 下(右)】 大福寺の薬師堂
本堂は朱塗り柱が印象的な近代建築で扁額は山号寺号。
観音堂は入母屋造銅板葺妻入りとみられ、妻方向に桟瓦葺の向拝を付設するいささか変わった形状ながら、観音霊場札所らしい華やいだ雰囲気をまとっています。
御朱印は本堂よこの庫裡にて拝受できますが、ご不在の場合もあるようです。
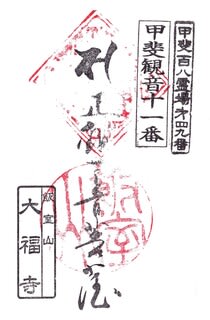

【写真 上(左)】 甲斐国三十三番観音札所の御朱印
【写真 下(右)】 甲斐百八霊場武州八十八霊場の御朱印
17.金色山 吉祥院 大悲願寺
〔平山左衛門尉季重〕
東京都あきる野市横沢134
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第59番、東国花の寺百ヶ寺霊場第10番、武玉八十八ヶ所霊場第1番、秋川三十四所霊場第21番、武蔵五日市七福神(大黒天)
源平合戦での活躍で知られる鎌倉武士をもう一人。平山左衛門尉季重です。
鎌倉殿の御家人には、「武蔵七党」と呼ばれる武蔵国を中心とした同族的武士団の面々も多くみられます。
諸説ありますが「武蔵七党」とは、おおむね横山党、猪俣党、野与党、村山党、西党(西野党)、児玉党、丹党(丹治党)、私市党、綴党などをさすようです。
平山季重は西党(日奉氏)に属した武将で、多西郡舟木田荘平山郷(現東京都日野市平山周辺)を領したといいます。
保元元年(1156年)の保元の乱で源義朝公、平治元年(1159年)の平治の乱では義朝公の長男義平公に従い平重盛軍と対峙しました。
義朝公敗死後は平家方となりましたが頼朝公挙兵に呼応し、富士川の戦い、佐竹氏征伐にも従軍し戦功を挙げています。
源平合戦では宇治川の戦い、一ノ谷の戦いでは義経公配下として奇襲に加わり、勝利のきっかけを作ったとされます。
屋島の戦い、壇ノ浦の戦いでも奮闘して武名を高めましたが、戦後、後白河法皇の右衛門尉任官に応じたため頼朝公の怒りを買い、公から罵られたという記述が残っています。
しかし、大事には至らず筑前国原田荘の地頭職を拝領、奥州合戦でもふたたび戦功を挙げて鎌倉幕府の中枢に入りました。
建久三年(1192年)の源実朝公誕生の際には、”鳴弦”の大役を務めています。


【写真 上(左)】 日野宮神社
【写真 下(右)】 日野宮神社の御朱印
西党の党祖、日奉宗頼は高皇産霊尊の子孫といわれ、日野市の日野宮神社に御祭神として祀られています。
このような家柄、そして源平合戦での華々しい戦歴から「弓の弦を強く引き鳴らして魔を祓う儀式」、鳴弦(めいげん)の役を命じられたのかもしれません。


【写真 上(左)】 宗印寺の山門
【写真 下(右)】 宗印寺の本堂
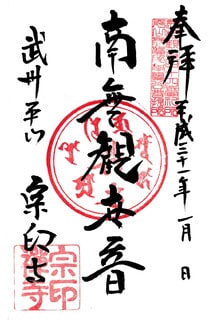

【写真 上(左)】 宗印寺の御本尊(武相卯歳四十八観音霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 宗印寺の日野七福神(布袋尊)の御朱印
季重の墓所は日野市平山の大沢山 宗印寺とされますが、ここでは開基に頼朝公も絡んだとされる、あきる野市の金色山 大悲願寺をご紹介します。


【写真 上(左)】 大悲願寺の本堂
【写真 下(右)】 大悲願寺の仁王門天井絵
大悲願寺は聖徳太子が全国行脚の際、この地に一宇の草堂を建てたのが草創という伝承もありますが、建久二年(1191年)源頼朝公が檀越(施主)となり、僧澄秀を開山として平山季重が創建とされます。
関東管領足利基氏・氏満父子から寺領二十石の寄進、徳川家康公からも二十石の御朱印を受け、近隣に末寺32ヶ寺を擁したという寺歴をみても、源頼朝公の関与があった可能性があります。
『新編武蔵風土記稿』の多磨郡小宮領横澤村の項には「開基ハ右大将賴朝ナリトイヘド タシカナル證迹ハナシ サレド貞治ノ頃平氏重(平山季重?)カ書寫シテヲサメシ大般若アルヲモテ フルキ寺ナルコトシルヘシ」
山林を背に伽藍が壮麗な並びます。
本堂は元禄年間の築で、入母屋茅葺型銅板葺。説明板には「書院造り風の方丈系講堂様式」で「内部は六間取形式」とあります。
名刹の本堂にふさわしい堂々たる構えで都の指定有形文化財。


【写真 上(左)】 大悲願寺の観音堂
【写真 下(右)】 大悲願寺観音堂の向拝上部
向かって左奥の観音堂は寛政年間の築で、寄棟造茅葺型銅板葺に復原され、彫刻類も新たに彩色が施されて見事です。
とくに正面欄間の地獄極楽彫刻が見どころとされます。
堂内の「伝阿弥陀如来三尊像」は平安末期~鎌倉の作とみられ、国指定重要文化財に指定されています。
他にも仁王門格天井の天井絵、中門(朱雀門)、五輪地蔵、梵鐘など多くの見どころがあります。


【写真 上(左)】 大悲願寺の多摩新四国霊場の御朱印
【写真 下(右)】 大悲願寺の東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
御朱印は雰囲気ある庫裡で拝受できます。
複数の霊場の札所ですが、現在は多摩新四国八十八ヶ所と東国花の寺百ヶ寺の2種類が授与されている模様です。
18.古尾谷八幡神社/寳聚山 東漸寺 灌頂院
〔源頼朝公・古尾谷氏〕
別記事、■ 源頼朝公ゆかりの寺社をみると、源頼朝公ゆかりの寺社は鎌倉・三浦半島を中心に相当数みられます。
ところが神奈川県外となると、その数はぐっと少なくなります。
埼玉県に至っては、ほとんどWebではヒットしません。
埼玉県内には、比企氏、畠山氏、熊谷氏、河越氏、武蔵七党など有力御家人が多く、寺社の創再建はこれらの武家たちが担っていたからかもしれません。
---------------------------
ところが、再建ながら頼朝公が直々に関与したと伝わる寺社が、埼玉県川越市にあります。
古尾谷八幡神社と、その別当、寳聚山 灌頂院です。
古尾谷八幡神社
埼玉県川越市古谷本郷1408
御祭神:品陀和気命、息長帯姫命、比売神
旧社格:県社、旧古尾谷庄総鎮守
元別当:寳聚山 東漸寺 灌頂院(川越市古谷本郷、天台宗)
寳聚山 東漸寺 灌頂院
埼玉県川越市古谷本郷1428
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:古尾谷八幡神社(川越市古谷本郷)
札所:小江戸川越古寺巡礼第4番
ともに川越市古谷本郷の地に隣接してあります。
〔 古尾谷八幡神社 〕


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿前配布の由来書には下記のとおりあります。
「創建 貞観四年(863年)比叡山延暦寺第三代坐主円仁来り法を修するの時、神霊を感じ神社を建て、これを天皇陛下に申し上げ石清水八幡宮の分霊を奉じ来たりてお祀りした。(略)当時、古尾谷庄は石清水八幡宮の荘園であった。」
「再建 元暦元年(1184年)源頼朝公古尾谷八幡神社に来り霊場を見、旧記を聞き、祭田を復し祭典を興した。文治五年(1190年)奥羽征伐の際陣中守護を当社に祈り鎮定の後社殿を再建した。」
『新編武蔵風土記稿』の入間郡古谷本郷の項には、「当社ハ元暦元年源頼朝勧請シ玉ヘルヨシ」とあります。
『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)には「古尾谷荘は鎌倉期に京都の石清水八幡宮の荘園とされたが、これは源氏の八幡信仰と深くかかわり、開発は在地領主である古尾谷氏であると思われる。古尾谷氏については、鎌倉幕府の御家人として登場し、吾妻鏡には承久の乱の折宇治川の合戦で活躍している。また、この後も古尾谷氏は当地の領主を務め、中世当社の盛衰はこの古尾谷氏とともにあった。社記によれば、天長年間慈覚大師が当地に巡錫し灌頂院を興し、貞観年中再び訪れて神霊を感じ、石清水八幡宮の分霊を祀ったのに始まると伝え、祭神は、品陀和気命・息長帯姫命・比売神である。元暦元年に源頼朝は天慶の乱により荒廃した社域を見て、当社の旧記を尋ね、由緒ある社であるので崇敬すべしとして、祭田を復旧して絶えた祭祀の復興を計り、また、文治五年には奥羽征討のため陣中祈願を行い、鎮定後、社殿を造営する。次いで弘安元年、藤原時景は社殿を再営、梵鐘を鋳造して社頭に掛けた。」とあります。
『入間郡誌』にも「元暦元年源頼朝祭田を復し、祭典を起し、文治二年奥羽征討の際来て祈願する所あり。凱旋後大に宮殿を造立せり。それより弘安元年、藤原時景と云ふ者、暫く此地を領し、社殿の頽廃を復し、梵鐘を鋳て社頭に掲げたり」
さらに、古尾谷八幡神社旧本殿(川越市Web)には、「古尾谷八幡神社は、貞観年間(859から877)に、石清水八幡宮の分霊を祀ったのがはじまりと伝えられ、古尾谷庄13か村の総鎮守として古くから崇敬されてきた。文治5年(1189)源頼朝が社殿を新たに造営し、弘安元年(1278)に藤原時景が復旧」とあり、ここでも頼朝公の関与が明記されています。
〔 寳聚山 東漸寺 灌頂院 〕


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
『新編武蔵風土記稿』の入間郡古谷本郷の項には、「(八幡社)別当灌頂院 天台宗 上野國世良田長楽寺ノ末 寳聚山東漸寺ト号ス、開山ハ聾義法印トノミ記シアリ(略)本尊彌陀ヲ安ス」とあります。
『入間郡誌』にも「慈覚大師、東国に来り、此地に於て灌頂修行し、此寺を立て其開山となり傍に八幡祠を立つ。(略)元暦四年頼朝堂宇坊舎を再興し」とあります。
また、『平成小江戸川越 古寺巡礼』(百瀬千又氏編)には「天長年間(824-833年)慈覚大師円仁の開創といわれ(略)源頼朝の手によって再建されたという。文治五年(1189年)の頃である。正応年間には古谷の地頭といわれた藤原時景によって再建となった。」とあります。
藤原時景と古尾谷氏の関係がどうもはっきりしないのですが、世の中には奇特な方がおられて、古尾谷荘について現地調査をふまえた詳細な記事をまとめられているので一部引用させていただきます。(出典はこちら(何となく古谷?それぞれの古尾谷氏…⑤))
「藤原時景が古尾谷左衛門尉時景だと分かったのは埼玉県名字辞典の古尾谷氏の項です。〔辞典からの引用:古尾谷 内藤氏流古尾谷氏 入間郡古尾谷荘より起る 内藤系図に『関白道長-(略-左衛門尉時景(弘安八年卒))』〕
上記から、藤原時景=古尾谷左衛門尉時景(御家人として、『吾妻鑑』に記載あり)であることがわかります。
『平成小江戸川越 古寺巡礼』(百瀬千又氏編)には「古尾谷八幡神社、灌頂院、そしてその塔頭などは地理的条件も含め古谷の豪族であった古尾谷氏の領地で、また、それをつかさどっていた別当寺の長官職は、藤原時景だったのではないかと推定され、広大な土地を所有し、頼朝の信任が厚かった古尾谷荘の地頭藤原氏と思われてくる。」とあります。
---------------------------
頼朝公が武蔵の一地方の社寺の再建にかかわった(とされる)理由について、
1.古尾谷荘は鎌倉期に京都の石清水八幡宮の荘園であったこと。
2.古尾谷八幡神社は、石清水八幡宮からの勧請であること。
3.領主の藤原時景(古尾谷氏)が頼朝公から信任を得ていた可能性があること。
などが想定されますが、この時期、頼朝公の関心が大きく川越に向いていたことも背景にあるのかもしれません。
有力御家人、河越重頼の動静です。
河越氏は桓武平氏良文流で坂東八平氏のひとつに数えられる名族。
秩父平氏の宗家筋とされ、「武蔵国留守所総検校職」として武蔵国内の武士を統率・動員する権限を有していたとされます。
鎌倉幕府草創期の当主は河越重頼で「武蔵国留守所総検校職」に任じられ、妻は頼朝公の乳母・比企尼の次女(河越尼)で頼家公の乳母。
しかも義経公に娘(郷御前)を嫁がせていたという、きわめてデリケートな立場でした。
血筋からも、立場的にも武蔵国の武将たちに大きな影響力をもっていたと考えられ、頼朝公にとって目をはなせない存在であったことは容易に想像できます。
〔 河越重頼関連年表 〕
永暦元年(1160年)
・河越氏、所領を後白河上皇に寄進し荘官となる。上皇は京の新日吉山王社へ寄進し新日吉社領河越荘と称される。
治承四年(1180年)8月
・頼朝公挙兵。重頼は畠山重忠、江戸重長ら武蔵国武士団とともに衣笠城を攻め、頼朝公方の三浦義明を討ち取る。
治承四年(1180年)10月
・頼朝公武蔵国入国を受け、畠山重忠・江戸重長らとともに頼朝公配下となる。
寿永三年(1184年)8月
・義経公とともに後白河法皇から任官を受け、重頼と弟・重経も頼朝公の怒りを買う。
寿永三年(1184年)9月
・頼朝公の命により、娘(郷御前)が京に上って義経公に嫁ぎ舅となる。
文治元年(1185年)
・義経公が後白河法皇から頼朝公追討の院宣を受け、舅の重頼も頼朝公から敵対視される。
文治元年(1185年)
・義経公の縁戚であることを理由に伊勢国香取五カ郷を没収。その後、重頼は嫡男重房と共に誅殺され、武蔵国留守所惣検校職は畠山重忠に移る。
文治三年(1187年)10月
・頼朝公は重頼誅殺を悼み、河越氏本領の河越荘を後家の河越尼に安堵。
頼朝公の古尾谷八幡神社・灌頂院への関与は元暦元年(1184年)~文治五年(1190年)とみられるので、上の年表からもみてきわめてデリケートなタイミングといえます。
古尾谷氏の舘は川越市古谷上の現・善仲寺にあったとされ、河越氏の館(川越市上戸、現・常楽寺附近とされる)とはさほど離れていません。
これはまったくの憶測ですが、頼朝公、河越氏、古尾谷氏を巡ってなんらかの交渉があり、それが古尾谷八幡神社・灌頂院の再興となってあらわれたのかもしれません。
記事が長くなったので、両寺社のご紹介は控えますが、いずれも長い歴史と格式が感じられるたたずまいです。
御朱印については、灌頂院は不授与。古尾谷八幡神社については通常無人で、タイミングに恵まれれば拝受できるかと思います。


【写真 上(左)】 灌頂院の御朱印不授与掲示
【写真 下(右)】 古尾谷八幡神社の御朱印
19.超越山 来迎院 西光寺
〔葛西三郎清重〕
東京都葛飾区四つ木1-25-8
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第33番、荒綾八十八ヶ所霊場第34番、(京成)東三十三観音霊場第31番、新葛西三十三観音霊場第14番
葛西氏は桓武平氏良文流の秩父氏(坂東八平氏の一)の一族豊島氏の庶流。
鎌倉幕府草創期の豊島氏の当主、豊島清元(清光)の三男、三郎清重は葛西御厨を継いで葛西氏を称しました。
治承四年(1180年)、源頼朝公の旗揚げには父・清元とともに隅田川で参陣。
この時点での秩父氏一族の動静は複雑で、江戸重長は頼朝公の参陣要求になかなか応じず、公は江戸重長の所領を召し上げて同族の葛西清重に与えようとしました。
これに対して清重は「一族(江戸氏)の所領を賜うのは本望ではなく、他者に賜るように」と頼朝公に言上したといいます。
これを聞いた頼朝公は怒りをあらわし清重の所領も没収すると脅しましたが、清重は「受けるべきものでないものを受けるのは義にあらず」ときっぱり拒絶しました。
頼朝公は清重の毅然たる態度に感じ入り、これに免じて江戸重長を赦したといいます。(以上『沙石集』より)
この逸話の背景については諸説ありますが、おおむね頼朝公の葛西清重に対する信頼をあらわすもの、また、葛西清重が頼朝公と秩父一族の融和に奔走したことを示すものとみられています。
常陸国の佐竹氏討伐の帰途、頼朝公は清重の館に立ち寄り、清重は丁重にもてなして頼朝公とのきずなを強め、清重は頼朝公寝所警護役に選ばれています。
元暦元年(1184年)夏の平氏討伐には源範頼公に従軍。
九州で活躍し頼朝公から御書を賜り、文治五年(1189年)には奥州藤原氏討伐に従軍し、阿津賀志山の戦いで抜け駆けの先陣を果たし、さらに武名を高めました。
奥州討伐後、清重は勲功抜群として胆沢郡、磐井郡、牡鹿郡など奥州の地に所領を賜り、奥州総奉行に任じられ、陸奥国の御家人統率を任されています。
のちに奥州で勢力を伸ばした葛西氏は清重の流れと伝わります。
以後は鎌倉に戻り幕府の重臣として職責を果たしましたが、奥州総奉行も兼務。頼朝公からの厚い信任は以後もかわらず、幕府内の立場を確かなものにしています。
頼朝公没後は北条氏と歩調を合わせ、北条方からも信任を得て壱岐守にも任じられています。
有力御家人の粛清、失脚あいつぐなかで一貫して時の権力者から信任を得、存在感を保ったことは、清重のただならぬ政治力を示すものかと思われます。
晩年、清重は関東教化で訪れた親鸞聖人に帰依して出家しました。
嘉禄元年(1225年)、親鸞聖人が渋江郷の清重の館(現・西光寺とされる)に立ち寄られた際に雨が降り止まず、聖人は五十三日間も足止めされ、その間に清重は存分に聖人の教えを受けて発心し、聖人に帰依して西光坊定蓮と改め、居館を雨降山 西光寺と号したとされます。
親鸞聖人は清重に阿弥陀如来の絵像を与え、清重(西光坊)自刻の聖徳太子像の像内には親鸞聖人御作といわれる阿弥陀如来像が入っているそうです。
西光寺は草創時は真宗でしたが、のちに戦火や水害で寺運衰退し、寛永年間(1634-1643年)に天台宗の僧が再興、山号を超越山と改めたとされますが、天台宗改宗後も親鸞聖人ゆかりの報恩講式という法要が毎春催されているそうです。
なお、墨田区東向島にある曹洞宗 晴河山 法泉寺も葛西清重ゆかりの寺院で、清重が両親供養のために建立したとされています。(戦国時代に真言宗から曹洞宗に改宗)

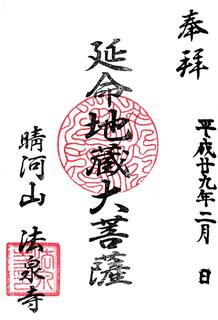
【写真 上(左)】 法泉寺本堂
【写真 下(右)】 法泉寺の御朱印
---------------------------
荒川の流れにもほど近い葛飾区四つ木。
下町らしい入り組んだ路地のなかに、それでもかなりの寺域を保ってあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は本瓦葺きの重厚な四脚門。門の横には「葛西三郎清重の遺跡(居館跡)」の説明書がありました。
正面の本堂も入母屋造本瓦葺流れ向拝の堂々たる構えで、向拝には「超越山」の山号扁額が掲げられています。
本堂向かって右手奥には南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第33番の大師堂があり、お大師さまが大切に供養されていました。


【写真 上(左)】 清重稲荷社
【写真 下(右)】 清重稲荷社の扁額
山門をくぐって右手の地主神とみられる稲荷社の扁額には「清重稲荷」とありました。
また、西光寺から少しはなれた住宅地のなかに「清重塚」があり、こちらは清重夫妻の墓所という言い伝えがあります。
葛飾区の古刹は複数の霊場札所となっている例が多いですが、こちらも4つの霊場の札所となっています。
霊場の御朱印は不授与のようですが、庫裡にて御本尊の御朱印が授与されています。

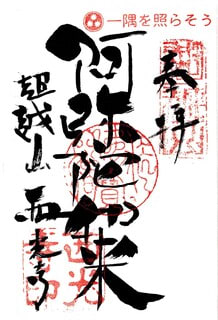
【写真 上(左)】 本堂の扁額
【写真 下(右)】 西光寺の御朱印
20.龍ヶ崎鎮守 八坂神社
〔下河辺氏・下河辺四郎政義〕
公式Web
茨城県龍ヶ崎市上町4279
御祭神:建速須佐鳴神、奇稲田姫神
旧社格:龍ヶ崎鎮守
元別当:
下河辺氏(しもこうべ し)は、藤原北家秀郷流で下野国の有力豪族、小山政光の弟行義が下総国葛飾郡下河辺荘を本貫地として独立し、下河辺を名乗ったのがはじまりとされます。
鎌倉幕府草創期の下河辺氏は「下河辺庄司」とも呼ばれ、現在の茨城県古河市・境町・五霞町・坂東市、埼玉県加須市まで広がる下河辺荘の庄司として勢力を張りました。
下河辺荘は鳥羽院から美福門院、そして鳥羽帝の皇女、八条院暲子内親王と引き継がれ、のちに大覚寺統の主要な経済基盤になったとされる「八条院領」の一画をなし、上方との関係がふかいところでした。
下河辺荘が「八条院領」となった経緯については、在地領主の下河辺氏が美福門院ないし八条院に寄進したともいわれ、諸説あるようです。
清和源氏の嫡流、摂津(多田)源氏の源(馬場)仲政は下総守に任ぜられ、その子(源三位)頼政も一時期任地の下総に下向したとされ、そのときに頼政と下河辺氏が主従関係を結んだともみられています。
以降、頼政と行義の主従関係はつづき、治承四年(1180年)、行義は上方で頼政とともに以仁王挙兵に呼応したとされます。
『平家物語』巻四には頼政が敗死したのち、頼政の首を「下河辺藤三郎清親」が隠したとあり、この「下河辺藤三郎清親」は下河辺行義(行吉)とみられています。
茨城県古河市の頼政神社には、頼政の郎党、あるいは下河辺行義が頼政の首をこの地に葬ったとする伝承があります。
また、茨城県龍ヶ崎市にも頼政神社があり、龍ヶ崎市の資料には「頼政は自害する際に家臣・下河辺行吉に自分の首を東国へ運んで葬るように命じました。鎌倉時代になって下河辺が一族の守護神として、頼政神社を建てたと伝えられています。」と記されています。
源頼朝公は行義の子・行平をはじめ、下河辺一族を優遇しましたが、下河辺氏が源三位頼政や八条院領とふかいつながりをもつことも、その背景にあったかもしれません。
また、下河辺荘は利根川、隅田川、荒川に挟まれた関東有数の低湿の地にあり、低湿地や河辺の戦いに長けた下河辺衆は鎌倉軍にとって貴重な存在だったのかもしれません。
下河辺行平は源平合戦で華々しい戦功をあげ、頼朝公から「日本無双の弓取」と称賛されて、准門葉(源氏一門に準ずる扱い)ともされたという有力御家人でしたが、行平ゆかりの寺社がどうにも判然としません。
行平の弟、下河辺四郎政義は龍ヶ崎の八坂神社を草創と伝わるので、まずは龍ヶ崎八坂神社をご紹介とします。
下河辺政義は寿永二年(1183年)、小山氏一門、兄・行平とともに野木宮合戦(頼朝公と志田義広党の戦い)に参加して凱旋。
その後、頼朝公の近臣として仕え、合戦の功と頼朝公への忠勤により常陸国南部を与えられたともいわれます。(諸説あり)
源平合戦では行平とともに範頼軍に属し、九州で活躍しました。
よく知られているのが、吾妻鑑にある鹿島神社神主中臣親広との御前対決です。
『吾妻鑑. 上』の文治元年(1185年)八月大廿一日辛未の項には以下のとおりあります。
「鹿島社神主中臣親廣與下河邊四郎政義、被召御前遂一决、是常陸國橘郷者、被奉寄彼社領訖、而政義以當國南郡惣地頭職、稱在郡内、押領件郷、令譴責神主妻子等、剩可從所勘之由取祭文之旨、親廣訴申之、政義雌伏、頗失陳詞、爲眼代等所爲歟之由稱之、仍停止向後濫妨、任先例可令勤行神事之趣、神主蒙恩裁、退出之後、政義猶候御前之間、仰云、政義向戰塲殊施武勇對、親廣失度歟、尤●之云々、政義申云、鹿島者守勇士之神也、爭無怖畏之思哉、仍雖有所存、故不能陳謝云々」
常陸国橘郷(現在の小美玉市付近)は鹿島神宮社領でしたが、下河辺政義は常陸国南郡の総地頭職なので、この地は郡内にあるとして年貢を取り立て郷民に労働を強要しました。
鹿島神宮神主の中臣親広はこれを頼朝公に訴え、公の御前で中臣神主と下河辺政義の対決となりました。
政義に弁明の言葉はなく、これを受けた頼朝公は今後は(政義に)横領を止めさせるので、神事に励むよう裁決を下しました。
中臣神主が退出した後も政義は御前に留まっていたので、頼朝公が「政義は戦場では並みはずれた武勇を奮うのに、神主に対しては神妙であったな。」と笑うと、政義は「鹿島神宮は武勇の士を守られる神様なので、武士の私がこの神と争うとは畏れ多いこと。私にも言い分はありますが、あえて申し述べませんでした。」と応えました。
ここから、頼朝公が政義を「並みはずれた勇士」と認めていたことがわかります。
また、武勇の士、政義といえども、鹿島神の神威の前ではなすすべがなかったことを物語っています。
文治元年(1185年)秋、源義経公謀反の際、義経公に娘を嫁がせた河越重頼は誅殺されましたが、政義は河越重頼の娘を妻としていた関係から連座して領地を没収されています。
その後も史料に御家人としての活動がみられることから、赦免され復帰したものとされますが、往時の勢力は保てず、下河辺荘は北条氏の支配下に入ったとみられています。
『寛政重修諸家譜』などによると、下河辺政義の子・小川政平の末裔は大和国長谷川に住んで長谷川氏を名乗り、今川義元に仕えたのちに高田藩家臣、徳川家の旗本として存続。
『鬼平犯科帳』の主人公「鬼平」として知られる火付盗賊改の長谷川宣以(平蔵)は、この流れと伝わります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 境内
龍ヶ崎の鎮守、八坂神社は下河辺政義の草創と伝えられます。
社伝(公式Web)には「当神社は源頼朝の家臣下河辺政義公が、文治2年(1186年)に領地龍ヶ崎市貝原塚の領民を引き連れ、沼沢の地であった根町を干拓した際に、貝原塚の鎮守神社である八坂大神の分御霊を祀ったのが草創と伝えられます。」と明記されています。

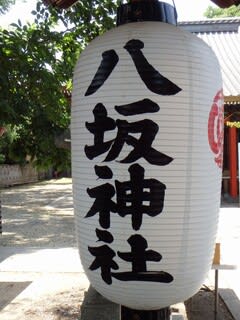
【写真 上(左)】 鳥居と拝殿
【写真 下(右)】 社号提灯
龍ヶ崎の中心部に御鎮座。地域の中核社らしく、どことなく華やいだ境内です。
本殿の華麗な彫刻は元禄文化の粋をあらわすものとされ、市の文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 拝殿の彫刻
【写真 下(右)】 八坂神社の御朱印
祇園祭で有名な神社で、月替わり御朱印やオリジナル御朱印帳を頒布されるなど、御朱印授与にも積極的です。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3へ。
〔 関連記事 〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ True Companion - The Rippingtons
■ Somethin' - Lalah Hathaway
■ "Stay Awhile" & "Still They Ride" Steve Perry- Journey
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1から
今回、この記事を書いていて感じたのは、史料・物語の扱いのむずかしさです。
鎌倉幕府草創期関連のメジャー史料として『吾妻鏡』があり、メジャーな軍記物語として『平家物語』(源平盛衰記)、『義経記』などがあります。
多くの人はこの時代について、これらの書物が合体した内容でイメージされているのではないでしょうか。(「鎌倉殿の13人」も『吾妻鏡』をベースに構成されているらしい。)
筆者は歴史を専攻したわけでも、歴史家でもないので、「史学」の外からなんのしがらみもなく眺めることができるのですが、「歴史」がわかりにくく、堅苦しくなっている理由のひとつに、”史料批判”あるいは”一次資料原理主義”があるのでは? と感じています。
”史料批判”の定義からして何説かありそうですが(笑)、まぁ、史料の正統性(信頼性)や妥当性について吟味評価すること、あるいは歴史にかかわる論述がこのような「正統な史料」にもとづいてなされているかを評価(批評)すること、というほどの意味ではないでしょうか。
なので、”一次資料”にもとづかない説は、それが卓越した内容を含んでいても、学問の世界では「根拠の正統性に欠ける」として顧みられない、あるいは”(学説ではなく)単なる歴史小説”として揶揄される傾向があるように感じています。
ふつう”一次史料”とは、当事者がリアルタイムで遺した手紙、文書、日記、あるいは公文書などで、後日や後世の編纂が入っていないものをいいます。(この時期でいうと『玉葉』(九条兼実)や『明月記』(藤原定家))
(”一次史料”は史料的価値が定まっているので使いやすいのだと思う。でも、手紙や日記には筆者の個人的主観が入っているので、かならずしも100%史実ではないような気もするが・・・。)
※ ご参考→「図書館司書のための歴史史料探索ガイド」(土屋直之氏/PDF)
『吾妻鏡』は二次史料(後世の編纂書物)とされ、異本もあるので「研究・解釈」する余地が多くあり「『吾妻鏡』の解釈・研究」についての研究があるほどです。
なので、ひとつの記述について、複数の解釈があることはめずらしくありません。
江戸期くらいになると一次資料はふんだんにありますが、鎌倉時代あたりではどうしても『吾妻鏡』などの二次(編纂)史料を使わざるを得ない(一次史料だけでは論理構成できない)、という背景もあるようです。
『吾妻鏡』は”史料”で、『平家物語』『義経記』は”物語”ですから、”史料批判”の立場からするとこれらの物語の記述などはとるに足らないものかもしれませんが、これらが人々に植え付けてきた”源平合戦”のイメージは否定できないものがあるかと。
じっさい、現地掲示板などでは、”史料”と”物語”混在の内容がけっこうみられたりします。(現地案内板は、それを読む民間人にとってはある意味「史実」。)
これらを整合して書こうとすると膨大な労力と時間がかかり、さらに対象となる御家人が150人近くもいるとなるとキリがないので、あくまでもWebや現地案内板などでメインとなっている内容(事実上の通説?)をかいつまんで、概要的にさらっとまとめていきたいと思います。
と、愚にもつかない言い訳をしつつ(笑)、さらにつづけます。
14.稲荷山 東林寺 〔工藤氏・伊東氏・曾我氏〕
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆・伊東観光ガイド
静岡県伊東市馬場町2-2-19
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩(阿弥陀三尊とも)
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:葛見神社(伊東市馬場町)
他札所:伊豆八十八ヶ所霊場第27番、伊豆二十一ヶ所霊場第17番、伊豆伊東六阿弥陀霊場第2番、伊東温泉七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
藤原南家の流れとされる工藤氏は、平安時代から鎌倉時代にかけて東伊豆で勢力を張り、当初は久須見氏(大見・宇佐見・伊東などからなる久須見荘の領主)を称したともいいますが、のちに伊東氏、河津氏、狩野氏など地名を苗字とするようになりました。
東伊豆における工藤(久須見)氏の流れは諸説あるようですが、これがはっきりしないと菩提寺である東林寺の縁起や『曽我物語』の経緯がわかりません。
いささか長くなりますが整理してみます。
工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸をもうけたことを知った祐親は激怒し千鶴丸を殺害、さらに頼朝公の殺害をも図ったとされます。
このとき、頼朝公の乳母・比企尼と、その三女を妻としていた次男の祐清が危機を頼朝公に知らせ、頼朝公は伊豆山神社に逃げ込んで事なきを得たといいます。
なお、北条時政の正室は伊東祐親の娘で、鎌倉幕府第二代執権・北条義時は祐親の孫にあたるので、鎌倉幕府における伊東祐親の存在はすこぶる大きなものがあったとみられます。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため当寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
なお、当寺は久安年間(1145-1150年)、真言宗寺院として開かれ、当初は久遠寺と号しました。
天文七年(1538年)に長源寺三世圓芝春徳大和尚が曹洞宗に改宗しています。
治承四年(1180年)頼朝公が挙兵すると、伊東祐親は大庭景親らと協力して石橋山の戦いでこれを撃破しました。
しかし頼朝公が坂東を制圧したのちは追われる身となり、富士川の戦いの後に捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられ、義澄の助命嘆願により命を赦されたものの、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」といい、養和二年(1182年)2月、自害して果てたとされます。
以後、東林寺は伊東家累代の菩提寺となりました。
また、伊東氏の尊崇篤い葛見神社の別当もつとめていました。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
(なお、平賀氏は清和(河内)源氏義光流の信濃源氏の名族で、源氏御門葉、御家人筆頭として鎌倉幕府草創期に隆盛を誇りました。
この時期の当主は平賀義信とその子惟義で、惟義は一時期近畿6ヶ国の守護を任されましたが、以降は執権北条氏に圧され、惟義の後を継いだ惟信は、承久三年(1221年)の承久の乱で京方に付き平賀氏は没落しました。)
工藤祐経の子・祐時は伊東氏を称し、日向国の伊東氏はその子孫とされています。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
伊東市街の山寄りに鎮まる旧郷社・葛見神社のさらに奥側にあります。
伊豆半島の温泉地の寺院は路地奥にあるものが多いですが、こちらは比較的開けたところにあり、車でのアクセスも楽です。
伊東氏の菩提寺で、伊東温泉七福神の札所でもあるので観光スポットにもなっている模様。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額
山門は切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で、「東林寺」の寺号板と「稲荷山」の扁額。
山内向かって左手に鐘楼、正面に入母屋造桟瓦葺唐破風向拝付きの本堂。
大がかりな唐破風で、鬼板に経の巻獅子口。刻まれた紋は伊東氏の紋としてしられる「庵に木瓜」紋です。
兎の毛通しの拝み懸魚には立体感あふれる天女の彫刻。
水引向拝両端には正面獅子の木鼻、側面に貘ないし像の木鼻。
中備には迫力ある龍の彫刻を置き、向拝上部に「東林禅寺」の寺号扁額が掛かります。
本堂には御本尊のほか、伊東祐親・河津祐泰・曽我兄弟の位牌や伊東祐親の木像、頼朝公と祐親の三女八重姫との間に生まれた千鶴丸の木像を安置しているそうです。
本堂向かって右の一間社流造の祠は伊東七福神の「布袋尊」です。
堂前に樹木は少なく、すっきり開けたイメージのある山内です。
河津三郎の墓、曽我兄弟の供養塔は鐘楼左の参道上にあり、東林寺の向かいの丘の上には伊東祐親の墓所と伝わる五輪塔(伊東市指定文化財)があるそうです。
御朱印は右手の庫裡にて拝受しました。

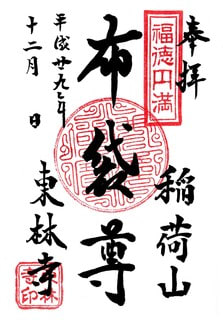
【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 伊東七福神(布袋尊)の御朱印
→ ■ 伊東温泉 「いな葉」の入湯レポ
→ ■ 伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」の入湯レポ
15.葛見神社 〔伊東氏〕
伊豆・伊東観光ガイド
静岡県伊東市馬場町1-16-40
御祭神:葛見神、倉稲魂命、大山祇命
旧社格:延喜式内社(小)論社、旧郷社
元別当:稲荷山 東林寺(伊東市馬場町、曹洞宗)
葛見神社は伊東市馬場町に御鎮座の古社で、東林寺にもほど近いところにご鎮座です。
創建は不詳ですが延長五年(927年)編纂の延喜式神名帳に記された式内社「久豆弥神社」とされているので、社暦はそうとうに古そうです。
境内由緒書には「伊東家守護神、往古、伊豆の東北部を葛見の荘と称し、当神社はこの荘名を負い、凡そ九百年の昔、葛見の荘の初代地頭工藤祐高公(伊東家次・・・伊東家の祖)が社殿を造営し、守護神として京都伏見稲荷を勧請合祀してから、伊東家の厚い保護と崇敬を受けて神威を高めてきました。」とあります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
平安時代から当地に拠った工藤氏、伊東氏の崇敬篤く、伊東氏の菩提寺・東林寺はその別当でした。
主祭神は葛見神。伏見稲荷大社の分霊を勧請合祀しています。
伊豆屈指の名社で、明治初頭に郷社に列格しています。


【写真 上(左)】 大樟
【写真 下(右)】 御朱印
延喜式内社だけあり、境内はさすがに神さびた空気が感じられます。
境内の大樟は樹齢千数百年ともいわれ、治承四年(1180年)、石橋山の戦いで破れ窮地におちいった頼朝公が根本の空洞で身を隠したとも伝わり国指定天然記念物に指定されています。
御朱印は社務所にて拝受しましたが、常時授与されているかは不明です。
16.飯室山 大福寺
〔浅利冠者義遠(義成)〕
浅利与一没後800年 特設ページ(山梨県中央市)
山梨県中央市大鳥居1621
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩(創立御本尊は不動明王)
札所:甲斐国三十三番観音札所第11番、甲斐百八霊場武州八十八霊場第49番
浅利与一は、『平家物語』の源平合戦最後のハイライト、壇ノ浦の戦いで「遠矢」を放った弓の名手として知られています。
源平合戦で与一を名乗り「三与一」と賞された3人の武将は、佐奈田(真田)与一、那須与一、そして浅利与一(余一)で、いずれも単なる「弓の名手」ではなく、れっきとした武家の統領とみられます。
浅利与一の正式な名は浅利(冠者)義遠(義成とも)。
清和源氏義光流の逸見清光の子とされ、兄弟には逸見光長、武田信義、加賀美遠光、安田義定など、錚々たる顔ぶれの甲斐源氏が揃います。
源平合戦では富士川の戦いから壇ノ浦の戦いまで転戦し、奥州出兵にも参加、↓で板額御前が捕えられた建仁元年(1201年)の城氏の乱にも出兵しています。
有名な「遠矢」の場面については→こちら(中央市Web史料)をご覧ください。
また、義遠は越後の豪族城氏の女傑、板額御前を娶ったことでも知られています。
板額御前については→こちら(中央市Web史料)でくわしく紹介されています。
二代将軍源頼家公治世の建仁元年(1201年)、城小太郎資盛の反乱で弓の名手として活躍した資盛の叔母、板額御前は敗戦後捕らえられ鎌倉に送られました。
剛勇だけでなく美貌も謳われた板額御前は、頼家公以下御家人居並ぶなかに引き出されましたが、いささかも臆することなく毅然たる態度を崩さなかったそうです。
その翌日、義遠はこの板額を嫁に貰い受けたい旨を頼家公に願い出て許され、板額は義遠の室となって甲斐に居住し、浅利氏の跡継ぎを設けたと伝わります。
木曽義仲の側妾・巴御前と並ぶ女傑として賞され、「巴板額」(ともえはんがく)ということばが伝わります。
鎌倉幕府草創期、安田義定、一条忠頼、逸見有義、板垣兼信、秋山光朝など甲斐源氏の主要メンバーがつぎつぎと排斥されていくなかで、御家人中枢の立場を守り抜き、しかも敵将の息女の貰い受けを将軍に直訴するとは、甲斐源氏の一員としての微妙な立場を考えると、ある意味際立った立ち回りともいえます。
義遠は壇ノ浦の勲功もあってか奥羽比内郡地頭職を拝領しており、浅利氏は比内地方(秋田県北部)にも定着しました。
また、子孫の浅利信種は戦国期に活躍、奉行、箕輪城の城代、西上州への侵攻と勤め、後北条氏との三増峠の戦いで討死。
家督は嫡男の昌種が引き継ぎ、のちに浅利同心衆は土屋昌続に仕えて、昌続が天目山の「片手千人切り」で奮戦戦死したのち、嫡男の土屋忠直は大名に取り立てられ土屋家は明治まで大名家として存続しました。
浅利氏の本拠は甲斐国八代郡浅利郷(いまの山梨県中央市(旧増富村))で、義遠の墓所は浅利山 法久寺および飯室山 大福寺とされ、大福寺は御朱印を拝受しているのでこちらをご紹介します。


【写真 上(左)】 大福寺の本堂
【写真 下(右)】 大福寺本堂の扁額
大福寺は天平十一年(739年)行基の開創とされる古刹。
あたりは浅利義遠の舘で、建暦元年(1211年)、浅利家の菩提寺として伽藍を再建、寺領を寄進したとも伝わります。
甲州武田家の祖・武田信義の孫(義遠の甥)、飯室禅師光厳の再興ともいいます。
シルクの里公園に隣接し、本堂と観音堂は点在気味に離れてややとりとめのない印象ですが、かつては七堂伽藍を整えたという名刹です。
平安期作とされる「木造聖観音及び諸尊像」および「木造薬師如来坐像」は県指定有形文化財。
義遠の墓所とされる「浅利与一層塔」も県指定有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 大福寺の観音堂
【写真 下(右)】 大福寺の薬師堂
本堂は朱塗り柱が印象的な近代建築で扁額は山号寺号。
観音堂は入母屋造銅板葺妻入りとみられ、妻方向に桟瓦葺の向拝を付設するいささか変わった形状ながら、観音霊場札所らしい華やいだ雰囲気をまとっています。
御朱印は本堂よこの庫裡にて拝受できますが、ご不在の場合もあるようです。
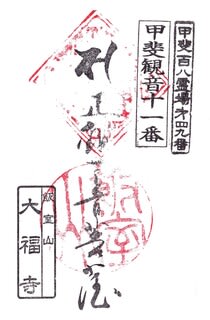

【写真 上(左)】 甲斐国三十三番観音札所の御朱印
【写真 下(右)】 甲斐百八霊場武州八十八霊場の御朱印
17.金色山 吉祥院 大悲願寺
〔平山左衛門尉季重〕
東京都あきる野市横沢134
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第59番、東国花の寺百ヶ寺霊場第10番、武玉八十八ヶ所霊場第1番、秋川三十四所霊場第21番、武蔵五日市七福神(大黒天)
源平合戦での活躍で知られる鎌倉武士をもう一人。平山左衛門尉季重です。
鎌倉殿の御家人には、「武蔵七党」と呼ばれる武蔵国を中心とした同族的武士団の面々も多くみられます。
諸説ありますが「武蔵七党」とは、おおむね横山党、猪俣党、野与党、村山党、西党(西野党)、児玉党、丹党(丹治党)、私市党、綴党などをさすようです。
平山季重は西党(日奉氏)に属した武将で、多西郡舟木田荘平山郷(現東京都日野市平山周辺)を領したといいます。
保元元年(1156年)の保元の乱で源義朝公、平治元年(1159年)の平治の乱では義朝公の長男義平公に従い平重盛軍と対峙しました。
義朝公敗死後は平家方となりましたが頼朝公挙兵に呼応し、富士川の戦い、佐竹氏征伐にも従軍し戦功を挙げています。
源平合戦では宇治川の戦い、一ノ谷の戦いでは義経公配下として奇襲に加わり、勝利のきっかけを作ったとされます。
屋島の戦い、壇ノ浦の戦いでも奮闘して武名を高めましたが、戦後、後白河法皇の右衛門尉任官に応じたため頼朝公の怒りを買い、公から罵られたという記述が残っています。
しかし、大事には至らず筑前国原田荘の地頭職を拝領、奥州合戦でもふたたび戦功を挙げて鎌倉幕府の中枢に入りました。
建久三年(1192年)の源実朝公誕生の際には、”鳴弦”の大役を務めています。


【写真 上(左)】 日野宮神社
【写真 下(右)】 日野宮神社の御朱印
西党の党祖、日奉宗頼は高皇産霊尊の子孫といわれ、日野市の日野宮神社に御祭神として祀られています。
このような家柄、そして源平合戦での華々しい戦歴から「弓の弦を強く引き鳴らして魔を祓う儀式」、鳴弦(めいげん)の役を命じられたのかもしれません。


【写真 上(左)】 宗印寺の山門
【写真 下(右)】 宗印寺の本堂
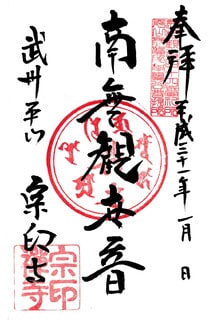

【写真 上(左)】 宗印寺の御本尊(武相卯歳四十八観音霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 宗印寺の日野七福神(布袋尊)の御朱印
季重の墓所は日野市平山の大沢山 宗印寺とされますが、ここでは開基に頼朝公も絡んだとされる、あきる野市の金色山 大悲願寺をご紹介します。


【写真 上(左)】 大悲願寺の本堂
【写真 下(右)】 大悲願寺の仁王門天井絵
大悲願寺は聖徳太子が全国行脚の際、この地に一宇の草堂を建てたのが草創という伝承もありますが、建久二年(1191年)源頼朝公が檀越(施主)となり、僧澄秀を開山として平山季重が創建とされます。
関東管領足利基氏・氏満父子から寺領二十石の寄進、徳川家康公からも二十石の御朱印を受け、近隣に末寺32ヶ寺を擁したという寺歴をみても、源頼朝公の関与があった可能性があります。
『新編武蔵風土記稿』の多磨郡小宮領横澤村の項には「開基ハ右大将賴朝ナリトイヘド タシカナル證迹ハナシ サレド貞治ノ頃平氏重(平山季重?)カ書寫シテヲサメシ大般若アルヲモテ フルキ寺ナルコトシルヘシ」
山林を背に伽藍が壮麗な並びます。
本堂は元禄年間の築で、入母屋茅葺型銅板葺。説明板には「書院造り風の方丈系講堂様式」で「内部は六間取形式」とあります。
名刹の本堂にふさわしい堂々たる構えで都の指定有形文化財。


【写真 上(左)】 大悲願寺の観音堂
【写真 下(右)】 大悲願寺観音堂の向拝上部
向かって左奥の観音堂は寛政年間の築で、寄棟造茅葺型銅板葺に復原され、彫刻類も新たに彩色が施されて見事です。
とくに正面欄間の地獄極楽彫刻が見どころとされます。
堂内の「伝阿弥陀如来三尊像」は平安末期~鎌倉の作とみられ、国指定重要文化財に指定されています。
他にも仁王門格天井の天井絵、中門(朱雀門)、五輪地蔵、梵鐘など多くの見どころがあります。


【写真 上(左)】 大悲願寺の多摩新四国霊場の御朱印
【写真 下(右)】 大悲願寺の東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
御朱印は雰囲気ある庫裡で拝受できます。
複数の霊場の札所ですが、現在は多摩新四国八十八ヶ所と東国花の寺百ヶ寺の2種類が授与されている模様です。
18.古尾谷八幡神社/寳聚山 東漸寺 灌頂院
〔源頼朝公・古尾谷氏〕
別記事、■ 源頼朝公ゆかりの寺社をみると、源頼朝公ゆかりの寺社は鎌倉・三浦半島を中心に相当数みられます。
ところが神奈川県外となると、その数はぐっと少なくなります。
埼玉県に至っては、ほとんどWebではヒットしません。
埼玉県内には、比企氏、畠山氏、熊谷氏、河越氏、武蔵七党など有力御家人が多く、寺社の創再建はこれらの武家たちが担っていたからかもしれません。
---------------------------
ところが、再建ながら頼朝公が直々に関与したと伝わる寺社が、埼玉県川越市にあります。
古尾谷八幡神社と、その別当、寳聚山 灌頂院です。
古尾谷八幡神社
埼玉県川越市古谷本郷1408
御祭神:品陀和気命、息長帯姫命、比売神
旧社格:県社、旧古尾谷庄総鎮守
元別当:寳聚山 東漸寺 灌頂院(川越市古谷本郷、天台宗)
寳聚山 東漸寺 灌頂院
埼玉県川越市古谷本郷1428
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:古尾谷八幡神社(川越市古谷本郷)
札所:小江戸川越古寺巡礼第4番
ともに川越市古谷本郷の地に隣接してあります。
〔 古尾谷八幡神社 〕


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿前配布の由来書には下記のとおりあります。
「創建 貞観四年(863年)比叡山延暦寺第三代坐主円仁来り法を修するの時、神霊を感じ神社を建て、これを天皇陛下に申し上げ石清水八幡宮の分霊を奉じ来たりてお祀りした。(略)当時、古尾谷庄は石清水八幡宮の荘園であった。」
「再建 元暦元年(1184年)源頼朝公古尾谷八幡神社に来り霊場を見、旧記を聞き、祭田を復し祭典を興した。文治五年(1190年)奥羽征伐の際陣中守護を当社に祈り鎮定の後社殿を再建した。」
『新編武蔵風土記稿』の入間郡古谷本郷の項には、「当社ハ元暦元年源頼朝勧請シ玉ヘルヨシ」とあります。
『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)には「古尾谷荘は鎌倉期に京都の石清水八幡宮の荘園とされたが、これは源氏の八幡信仰と深くかかわり、開発は在地領主である古尾谷氏であると思われる。古尾谷氏については、鎌倉幕府の御家人として登場し、吾妻鏡には承久の乱の折宇治川の合戦で活躍している。また、この後も古尾谷氏は当地の領主を務め、中世当社の盛衰はこの古尾谷氏とともにあった。社記によれば、天長年間慈覚大師が当地に巡錫し灌頂院を興し、貞観年中再び訪れて神霊を感じ、石清水八幡宮の分霊を祀ったのに始まると伝え、祭神は、品陀和気命・息長帯姫命・比売神である。元暦元年に源頼朝は天慶の乱により荒廃した社域を見て、当社の旧記を尋ね、由緒ある社であるので崇敬すべしとして、祭田を復旧して絶えた祭祀の復興を計り、また、文治五年には奥羽征討のため陣中祈願を行い、鎮定後、社殿を造営する。次いで弘安元年、藤原時景は社殿を再営、梵鐘を鋳造して社頭に掛けた。」とあります。
『入間郡誌』にも「元暦元年源頼朝祭田を復し、祭典を起し、文治二年奥羽征討の際来て祈願する所あり。凱旋後大に宮殿を造立せり。それより弘安元年、藤原時景と云ふ者、暫く此地を領し、社殿の頽廃を復し、梵鐘を鋳て社頭に掲げたり」
さらに、古尾谷八幡神社旧本殿(川越市Web)には、「古尾谷八幡神社は、貞観年間(859から877)に、石清水八幡宮の分霊を祀ったのがはじまりと伝えられ、古尾谷庄13か村の総鎮守として古くから崇敬されてきた。文治5年(1189)源頼朝が社殿を新たに造営し、弘安元年(1278)に藤原時景が復旧」とあり、ここでも頼朝公の関与が明記されています。
〔 寳聚山 東漸寺 灌頂院 〕


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
『新編武蔵風土記稿』の入間郡古谷本郷の項には、「(八幡社)別当灌頂院 天台宗 上野國世良田長楽寺ノ末 寳聚山東漸寺ト号ス、開山ハ聾義法印トノミ記シアリ(略)本尊彌陀ヲ安ス」とあります。
『入間郡誌』にも「慈覚大師、東国に来り、此地に於て灌頂修行し、此寺を立て其開山となり傍に八幡祠を立つ。(略)元暦四年頼朝堂宇坊舎を再興し」とあります。
また、『平成小江戸川越 古寺巡礼』(百瀬千又氏編)には「天長年間(824-833年)慈覚大師円仁の開創といわれ(略)源頼朝の手によって再建されたという。文治五年(1189年)の頃である。正応年間には古谷の地頭といわれた藤原時景によって再建となった。」とあります。
藤原時景と古尾谷氏の関係がどうもはっきりしないのですが、世の中には奇特な方がおられて、古尾谷荘について現地調査をふまえた詳細な記事をまとめられているので一部引用させていただきます。(出典はこちら(何となく古谷?それぞれの古尾谷氏…⑤))
「藤原時景が古尾谷左衛門尉時景だと分かったのは埼玉県名字辞典の古尾谷氏の項です。〔辞典からの引用:古尾谷 内藤氏流古尾谷氏 入間郡古尾谷荘より起る 内藤系図に『関白道長-(略-左衛門尉時景(弘安八年卒))』〕
上記から、藤原時景=古尾谷左衛門尉時景(御家人として、『吾妻鑑』に記載あり)であることがわかります。
『平成小江戸川越 古寺巡礼』(百瀬千又氏編)には「古尾谷八幡神社、灌頂院、そしてその塔頭などは地理的条件も含め古谷の豪族であった古尾谷氏の領地で、また、それをつかさどっていた別当寺の長官職は、藤原時景だったのではないかと推定され、広大な土地を所有し、頼朝の信任が厚かった古尾谷荘の地頭藤原氏と思われてくる。」とあります。
---------------------------
頼朝公が武蔵の一地方の社寺の再建にかかわった(とされる)理由について、
1.古尾谷荘は鎌倉期に京都の石清水八幡宮の荘園であったこと。
2.古尾谷八幡神社は、石清水八幡宮からの勧請であること。
3.領主の藤原時景(古尾谷氏)が頼朝公から信任を得ていた可能性があること。
などが想定されますが、この時期、頼朝公の関心が大きく川越に向いていたことも背景にあるのかもしれません。
有力御家人、河越重頼の動静です。
河越氏は桓武平氏良文流で坂東八平氏のひとつに数えられる名族。
秩父平氏の宗家筋とされ、「武蔵国留守所総検校職」として武蔵国内の武士を統率・動員する権限を有していたとされます。
鎌倉幕府草創期の当主は河越重頼で「武蔵国留守所総検校職」に任じられ、妻は頼朝公の乳母・比企尼の次女(河越尼)で頼家公の乳母。
しかも義経公に娘(郷御前)を嫁がせていたという、きわめてデリケートな立場でした。
血筋からも、立場的にも武蔵国の武将たちに大きな影響力をもっていたと考えられ、頼朝公にとって目をはなせない存在であったことは容易に想像できます。
〔 河越重頼関連年表 〕
永暦元年(1160年)
・河越氏、所領を後白河上皇に寄進し荘官となる。上皇は京の新日吉山王社へ寄進し新日吉社領河越荘と称される。
治承四年(1180年)8月
・頼朝公挙兵。重頼は畠山重忠、江戸重長ら武蔵国武士団とともに衣笠城を攻め、頼朝公方の三浦義明を討ち取る。
治承四年(1180年)10月
・頼朝公武蔵国入国を受け、畠山重忠・江戸重長らとともに頼朝公配下となる。
寿永三年(1184年)8月
・義経公とともに後白河法皇から任官を受け、重頼と弟・重経も頼朝公の怒りを買う。
寿永三年(1184年)9月
・頼朝公の命により、娘(郷御前)が京に上って義経公に嫁ぎ舅となる。
文治元年(1185年)
・義経公が後白河法皇から頼朝公追討の院宣を受け、舅の重頼も頼朝公から敵対視される。
文治元年(1185年)
・義経公の縁戚であることを理由に伊勢国香取五カ郷を没収。その後、重頼は嫡男重房と共に誅殺され、武蔵国留守所惣検校職は畠山重忠に移る。
文治三年(1187年)10月
・頼朝公は重頼誅殺を悼み、河越氏本領の河越荘を後家の河越尼に安堵。
頼朝公の古尾谷八幡神社・灌頂院への関与は元暦元年(1184年)~文治五年(1190年)とみられるので、上の年表からもみてきわめてデリケートなタイミングといえます。
古尾谷氏の舘は川越市古谷上の現・善仲寺にあったとされ、河越氏の館(川越市上戸、現・常楽寺附近とされる)とはさほど離れていません。
これはまったくの憶測ですが、頼朝公、河越氏、古尾谷氏を巡ってなんらかの交渉があり、それが古尾谷八幡神社・灌頂院の再興となってあらわれたのかもしれません。
記事が長くなったので、両寺社のご紹介は控えますが、いずれも長い歴史と格式が感じられるたたずまいです。
御朱印については、灌頂院は不授与。古尾谷八幡神社については通常無人で、タイミングに恵まれれば拝受できるかと思います。


【写真 上(左)】 灌頂院の御朱印不授与掲示
【写真 下(右)】 古尾谷八幡神社の御朱印
19.超越山 来迎院 西光寺
〔葛西三郎清重〕
東京都葛飾区四つ木1-25-8
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第33番、荒綾八十八ヶ所霊場第34番、(京成)東三十三観音霊場第31番、新葛西三十三観音霊場第14番
葛西氏は桓武平氏良文流の秩父氏(坂東八平氏の一)の一族豊島氏の庶流。
鎌倉幕府草創期の豊島氏の当主、豊島清元(清光)の三男、三郎清重は葛西御厨を継いで葛西氏を称しました。
治承四年(1180年)、源頼朝公の旗揚げには父・清元とともに隅田川で参陣。
この時点での秩父氏一族の動静は複雑で、江戸重長は頼朝公の参陣要求になかなか応じず、公は江戸重長の所領を召し上げて同族の葛西清重に与えようとしました。
これに対して清重は「一族(江戸氏)の所領を賜うのは本望ではなく、他者に賜るように」と頼朝公に言上したといいます。
これを聞いた頼朝公は怒りをあらわし清重の所領も没収すると脅しましたが、清重は「受けるべきものでないものを受けるのは義にあらず」ときっぱり拒絶しました。
頼朝公は清重の毅然たる態度に感じ入り、これに免じて江戸重長を赦したといいます。(以上『沙石集』より)
この逸話の背景については諸説ありますが、おおむね頼朝公の葛西清重に対する信頼をあらわすもの、また、葛西清重が頼朝公と秩父一族の融和に奔走したことを示すものとみられています。
常陸国の佐竹氏討伐の帰途、頼朝公は清重の館に立ち寄り、清重は丁重にもてなして頼朝公とのきずなを強め、清重は頼朝公寝所警護役に選ばれています。
元暦元年(1184年)夏の平氏討伐には源範頼公に従軍。
九州で活躍し頼朝公から御書を賜り、文治五年(1189年)には奥州藤原氏討伐に従軍し、阿津賀志山の戦いで抜け駆けの先陣を果たし、さらに武名を高めました。
奥州討伐後、清重は勲功抜群として胆沢郡、磐井郡、牡鹿郡など奥州の地に所領を賜り、奥州総奉行に任じられ、陸奥国の御家人統率を任されています。
のちに奥州で勢力を伸ばした葛西氏は清重の流れと伝わります。
以後は鎌倉に戻り幕府の重臣として職責を果たしましたが、奥州総奉行も兼務。頼朝公からの厚い信任は以後もかわらず、幕府内の立場を確かなものにしています。
頼朝公没後は北条氏と歩調を合わせ、北条方からも信任を得て壱岐守にも任じられています。
有力御家人の粛清、失脚あいつぐなかで一貫して時の権力者から信任を得、存在感を保ったことは、清重のただならぬ政治力を示すものかと思われます。
晩年、清重は関東教化で訪れた親鸞聖人に帰依して出家しました。
嘉禄元年(1225年)、親鸞聖人が渋江郷の清重の館(現・西光寺とされる)に立ち寄られた際に雨が降り止まず、聖人は五十三日間も足止めされ、その間に清重は存分に聖人の教えを受けて発心し、聖人に帰依して西光坊定蓮と改め、居館を雨降山 西光寺と号したとされます。
親鸞聖人は清重に阿弥陀如来の絵像を与え、清重(西光坊)自刻の聖徳太子像の像内には親鸞聖人御作といわれる阿弥陀如来像が入っているそうです。
西光寺は草創時は真宗でしたが、のちに戦火や水害で寺運衰退し、寛永年間(1634-1643年)に天台宗の僧が再興、山号を超越山と改めたとされますが、天台宗改宗後も親鸞聖人ゆかりの報恩講式という法要が毎春催されているそうです。
なお、墨田区東向島にある曹洞宗 晴河山 法泉寺も葛西清重ゆかりの寺院で、清重が両親供養のために建立したとされています。(戦国時代に真言宗から曹洞宗に改宗)

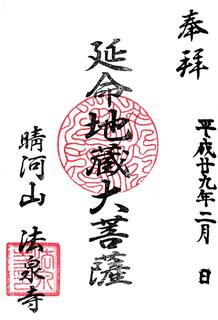
【写真 上(左)】 法泉寺本堂
【写真 下(右)】 法泉寺の御朱印
---------------------------
荒川の流れにもほど近い葛飾区四つ木。
下町らしい入り組んだ路地のなかに、それでもかなりの寺域を保ってあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は本瓦葺きの重厚な四脚門。門の横には「葛西三郎清重の遺跡(居館跡)」の説明書がありました。
正面の本堂も入母屋造本瓦葺流れ向拝の堂々たる構えで、向拝には「超越山」の山号扁額が掲げられています。
本堂向かって右手奥には南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第33番の大師堂があり、お大師さまが大切に供養されていました。


【写真 上(左)】 清重稲荷社
【写真 下(右)】 清重稲荷社の扁額
山門をくぐって右手の地主神とみられる稲荷社の扁額には「清重稲荷」とありました。
また、西光寺から少しはなれた住宅地のなかに「清重塚」があり、こちらは清重夫妻の墓所という言い伝えがあります。
葛飾区の古刹は複数の霊場札所となっている例が多いですが、こちらも4つの霊場の札所となっています。
霊場の御朱印は不授与のようですが、庫裡にて御本尊の御朱印が授与されています。

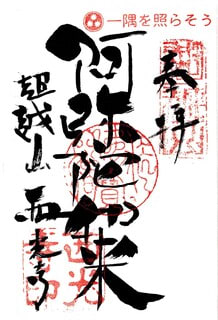
【写真 上(左)】 本堂の扁額
【写真 下(右)】 西光寺の御朱印
20.龍ヶ崎鎮守 八坂神社
〔下河辺氏・下河辺四郎政義〕
公式Web
茨城県龍ヶ崎市上町4279
御祭神:建速須佐鳴神、奇稲田姫神
旧社格:龍ヶ崎鎮守
元別当:
下河辺氏(しもこうべ し)は、藤原北家秀郷流で下野国の有力豪族、小山政光の弟行義が下総国葛飾郡下河辺荘を本貫地として独立し、下河辺を名乗ったのがはじまりとされます。
鎌倉幕府草創期の下河辺氏は「下河辺庄司」とも呼ばれ、現在の茨城県古河市・境町・五霞町・坂東市、埼玉県加須市まで広がる下河辺荘の庄司として勢力を張りました。
下河辺荘は鳥羽院から美福門院、そして鳥羽帝の皇女、八条院暲子内親王と引き継がれ、のちに大覚寺統の主要な経済基盤になったとされる「八条院領」の一画をなし、上方との関係がふかいところでした。
下河辺荘が「八条院領」となった経緯については、在地領主の下河辺氏が美福門院ないし八条院に寄進したともいわれ、諸説あるようです。
清和源氏の嫡流、摂津(多田)源氏の源(馬場)仲政は下総守に任ぜられ、その子(源三位)頼政も一時期任地の下総に下向したとされ、そのときに頼政と下河辺氏が主従関係を結んだともみられています。
以降、頼政と行義の主従関係はつづき、治承四年(1180年)、行義は上方で頼政とともに以仁王挙兵に呼応したとされます。
『平家物語』巻四には頼政が敗死したのち、頼政の首を「下河辺藤三郎清親」が隠したとあり、この「下河辺藤三郎清親」は下河辺行義(行吉)とみられています。
茨城県古河市の頼政神社には、頼政の郎党、あるいは下河辺行義が頼政の首をこの地に葬ったとする伝承があります。
また、茨城県龍ヶ崎市にも頼政神社があり、龍ヶ崎市の資料には「頼政は自害する際に家臣・下河辺行吉に自分の首を東国へ運んで葬るように命じました。鎌倉時代になって下河辺が一族の守護神として、頼政神社を建てたと伝えられています。」と記されています。
源頼朝公は行義の子・行平をはじめ、下河辺一族を優遇しましたが、下河辺氏が源三位頼政や八条院領とふかいつながりをもつことも、その背景にあったかもしれません。
また、下河辺荘は利根川、隅田川、荒川に挟まれた関東有数の低湿の地にあり、低湿地や河辺の戦いに長けた下河辺衆は鎌倉軍にとって貴重な存在だったのかもしれません。
下河辺行平は源平合戦で華々しい戦功をあげ、頼朝公から「日本無双の弓取」と称賛されて、准門葉(源氏一門に準ずる扱い)ともされたという有力御家人でしたが、行平ゆかりの寺社がどうにも判然としません。
行平の弟、下河辺四郎政義は龍ヶ崎の八坂神社を草創と伝わるので、まずは龍ヶ崎八坂神社をご紹介とします。
下河辺政義は寿永二年(1183年)、小山氏一門、兄・行平とともに野木宮合戦(頼朝公と志田義広党の戦い)に参加して凱旋。
その後、頼朝公の近臣として仕え、合戦の功と頼朝公への忠勤により常陸国南部を与えられたともいわれます。(諸説あり)
源平合戦では行平とともに範頼軍に属し、九州で活躍しました。
よく知られているのが、吾妻鑑にある鹿島神社神主中臣親広との御前対決です。
『吾妻鑑. 上』の文治元年(1185年)八月大廿一日辛未の項には以下のとおりあります。
「鹿島社神主中臣親廣與下河邊四郎政義、被召御前遂一决、是常陸國橘郷者、被奉寄彼社領訖、而政義以當國南郡惣地頭職、稱在郡内、押領件郷、令譴責神主妻子等、剩可從所勘之由取祭文之旨、親廣訴申之、政義雌伏、頗失陳詞、爲眼代等所爲歟之由稱之、仍停止向後濫妨、任先例可令勤行神事之趣、神主蒙恩裁、退出之後、政義猶候御前之間、仰云、政義向戰塲殊施武勇對、親廣失度歟、尤●之云々、政義申云、鹿島者守勇士之神也、爭無怖畏之思哉、仍雖有所存、故不能陳謝云々」
常陸国橘郷(現在の小美玉市付近)は鹿島神宮社領でしたが、下河辺政義は常陸国南郡の総地頭職なので、この地は郡内にあるとして年貢を取り立て郷民に労働を強要しました。
鹿島神宮神主の中臣親広はこれを頼朝公に訴え、公の御前で中臣神主と下河辺政義の対決となりました。
政義に弁明の言葉はなく、これを受けた頼朝公は今後は(政義に)横領を止めさせるので、神事に励むよう裁決を下しました。
中臣神主が退出した後も政義は御前に留まっていたので、頼朝公が「政義は戦場では並みはずれた武勇を奮うのに、神主に対しては神妙であったな。」と笑うと、政義は「鹿島神宮は武勇の士を守られる神様なので、武士の私がこの神と争うとは畏れ多いこと。私にも言い分はありますが、あえて申し述べませんでした。」と応えました。
ここから、頼朝公が政義を「並みはずれた勇士」と認めていたことがわかります。
また、武勇の士、政義といえども、鹿島神の神威の前ではなすすべがなかったことを物語っています。
文治元年(1185年)秋、源義経公謀反の際、義経公に娘を嫁がせた河越重頼は誅殺されましたが、政義は河越重頼の娘を妻としていた関係から連座して領地を没収されています。
その後も史料に御家人としての活動がみられることから、赦免され復帰したものとされますが、往時の勢力は保てず、下河辺荘は北条氏の支配下に入ったとみられています。
『寛政重修諸家譜』などによると、下河辺政義の子・小川政平の末裔は大和国長谷川に住んで長谷川氏を名乗り、今川義元に仕えたのちに高田藩家臣、徳川家の旗本として存続。
『鬼平犯科帳』の主人公「鬼平」として知られる火付盗賊改の長谷川宣以(平蔵)は、この流れと伝わります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 境内
龍ヶ崎の鎮守、八坂神社は下河辺政義の草創と伝えられます。
社伝(公式Web)には「当神社は源頼朝の家臣下河辺政義公が、文治2年(1186年)に領地龍ヶ崎市貝原塚の領民を引き連れ、沼沢の地であった根町を干拓した際に、貝原塚の鎮守神社である八坂大神の分御霊を祀ったのが草創と伝えられます。」と明記されています。

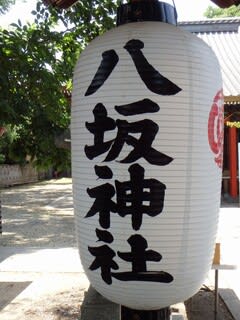
【写真 上(左)】 鳥居と拝殿
【写真 下(右)】 社号提灯
龍ヶ崎の中心部に御鎮座。地域の中核社らしく、どことなく華やいだ境内です。
本殿の華麗な彫刻は元禄文化の粋をあらわすものとされ、市の文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 拝殿の彫刻
【写真 下(右)】 八坂神社の御朱印
祇園祭で有名な神社で、月替わり御朱印やオリジナル御朱印帳を頒布されるなど、御朱印授与にも積極的です。
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3へ。
〔 関連記事 〕
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3
■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4
■ 鎌倉殿の御家人
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ True Companion - The Rippingtons
■ Somethin' - Lalah Hathaway
■ "Stay Awhile" & "Still They Ride" Steve Perry- Journey
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
新型コロナ禍で、寺社様によっては御朱印授与を休止されている場合があります。
ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/01/25 補足UP
2021/01/31 補足UP
2022/01/15 補足UP
2022/06/03 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
43.如意山 宝蔵院 大乗寺(高崎市棟高町)
44.烏子稲荷神社 (高崎市上小塙町)
45.新比叡山 本実成院 天竜護国寺(高崎市上並榎町)
46.我峰八幡神社 (高崎市我峰町)
47.上野國一社八幡宮 (高崎市八幡町)
48.神通山 遍照王院 大聖護国寺 (高崎市八幡町)
49.慈雲山 養寿院 福泉寺 (高崎市鼻高町)
50.少林山 達磨寺 (高崎市鼻高町)
51.八幡山 月光院 常安寺 (高崎市下豊岡甲)
43.如意山 宝蔵院 大乗寺
高崎市棟高町2234
真言宗豊山派
御本尊:
開山、沿革などは不詳ですが、高崎市の指定重要文化財である「農耕図屏風」を所蔵する寺院として知られています。
「農耕図屏風」は、源信寿(みなもとののぶひさ)の筆による「農事一式の図」六曲一双の屏風です。
江戸前期の農作業を描写したもので、脱穀に「くるり棒」(回転式の稲打ち棒)を使わず、二股の自然木を利用している様子が時代を反映するものとされます。
女が頭上に舟・えび・うさぎ等の型を乗せて、五穀豊穣を祝う踊りの姿などが見どころとされます。
大乗寺のそばにある高崎市立堤ヶ岡小学校は大乗寺山内の発育小学校が発祥、堤ヶ岡幼稚園、堤ヶ岡保育園ともに大乗寺を母体としているそうで、児童教育とゆかりの深いお寺さんと思われます。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内
堤ヶ岡幼稚園横が参道入口で、山号標と寺号標が建っています。
その先の山門は桟瓦葺で、薬医門形式と思われます。
本堂と左手に宝形造桟瓦葺向拝付きのお堂があります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺で、正面に軒唐破風の立派な向拝を起こしています。
大棟の棟飾りは経の巻獅子口。
水引虹梁両端、正面と側面に雲形の木鼻。中備に花紋様の板蟇股。頭貫上の斗栱は斗が5つです。
唐破風下に大瓶束笈形を置き、兎毛通に蕪懸魚、破風上の鬼板に経の巻獅子口を置いているので、下から水引虹梁、板蟇股、虹梁、大瓶束笈形、蕪懸魚、経の巻獅子口という見どころの多い構成となっています。
向拝見上げの扁額は「如意山」の山号です。
霊場札所ではないですが御朱印を授与いただけました。
ただし、ご不在や法事によりいただけない場合もあり、3度目の参拝で授与いただけました。
〔 不動明王の御朱印 〕

中央に不動明王の種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
44.烏子稲荷神社
高崎市上小塙町564
御祭神:宇迦之御魂命、大日霊命、素戔嗚命、菅原道真公
神饌幣帛料供進社
「すないご」という難読の社号をもつ稲荷神社です。
境内由緒書きなどを参考に、創祀・沿革をまとめてみます。
延暦二年(783年)に公卿の藤原金善という人が、山城国(現 京都府)の藤ノ森稲荷神社の御分霊をこの地に勧請したのが創祀とされます。
この地は古くは須苗郷(須苗子・烏子)と呼ばれ、当社は須苗郷(すないご・ごう)の総鎮守として崇敬されてきました。
戦国時代、甲斐の武田信玄公が箕輪城攻略の際に戦勝祈願をし、大願成就の後、武田家臣の浦野家、新井家とゆかりをもち、後世まで関係を保っているようです。
江戸時代には徳川家より代々御朱印を頂いています。
明治三十九年(1906年)、神饌幣帛料を共進しうべき神社に指定。
社殿は六世紀前半の上小塙稲荷山古墳の上に祀られ、本殿裏には巨大な石で築かれた石室があります。
「上小塙稲荷山古墳」は高崎市の指定史跡に指定され、石室の穴は都に通じているとか、白狐が住んでいるなどともいわれて稲荷信仰の対象となっていました。
そのために、古墳が状態よく保存されていたものと評価されています。
社宝として所蔵されている須恵器類も附指定されています。
平地のなかにこんもり丸く盛り上がった社叢は、いかにも古墳を思わせるもの。
かなり離れたところ(北部環状線沿い)に朱塗りの大鳥居を構えています。


【写真 上(左)】 社頭から境内
【写真 下(右)】 境内案内図
参道階段下に駐車場。右手に社務所。参道手前に石灯籠一対。すでにこのあたりから神さびた雰囲気をまとっています。


【写真 上(左)】 身代り達磨
【写真 下(右)】 弁天様
社務所のそばには、身体の痛いところをさすると痛みがなおるという「身代り達磨」。
左手の池に御座す弁天様は、もともと古墳外堀に祀られて霊験確かな弁天様として信仰を集めていたところ、外堀改修工事に際しご神像の奉納がなされて現在の位置に御遷座されたとのこと。


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 産泰様
参道階段手前に狛犬一対。その先左手に手水舎と朱塗りの台輪鳥居で鳥居扁額は「稲荷大神」。
鳥居左手には朱の鳥居が連なる参道?があり、稲荷神社らしい空気感。
階段途中にも石造の台輪鳥居があり、その先左手には子授り、子育て、安産の神様、産泰様のお社が鎮座しています。
産泰様の手前には、高崎城主・安藤対馬守が参詣のおりにお手植えされたという「逆さもみじ」があります。この木は逆さに挿したのに根付いた生命の強い木とされ、諸願成就の所以となっています。


【写真 上(左)】 神楽殿
【写真 下(右)】 拝殿
階段の左手奥には朱塗りで均整のとれた神楽殿。
階段正面が拝殿で、位置的に屋根構造がうまく確認できないのですが、おそらく入母屋造瓦葺唐破風向拝付きで、妻入りかもしれません。
朱塗りの柱が意匠的に効いた、華やかな印象の社殿です。


【写真 上(左)】 頭貫の彫刻
【写真 下(右)】 中備の彫刻
朱塗りの向拝柱の上に古色を帯びた水引虹梁を置き、両端に精緻な彫刻木鼻(正面獅子、側面象鼻)を備えています。
中備にはボリューム感のある龍の彫刻。唐破風軒の懸魚部にも彫刻を置いています。
唐破風の鬼板は、綾筋付きの経の巻獅子口のようにも見えました。
十八世紀末の築と推定される本殿は、「烏子稲荷神社本殿」として高崎市の指定文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 烏子天神
正面はよく見えないのですが、境内説明板によると一間社入母屋造で現在は銅板葺。
組物は三手先詰組、蛇腹支輪。
向拝に虹梁形頭貫で連三斗積上、木鼻は正面を獅子、側面を象鼻。頭貫おくに力感あふれる海老虹梁。
中備に蟇股。向拝正面打越二軒繁垂木。
妻飾りは虹梁大瓶束式笈形付。屋根に千木と堅魚木を置いています。
脇障子の透かし彫りも見事なもので、すこぶる存在感のある本殿です。
本殿右手に鎮座する天神様のお社は、一間の切妻造銅版葺正面桟唐戸で「烏子天神」の扁額を掲げています。
御朱印は社務所にて揮毫のものをいただけました。
〔 御朱印 〕

揮毫は「烏子稲荷神社」で、神社印が捺されています。
45.新比叡山 本実成院 天龍護国寺
高崎市上並榎町922
天台宗
御本尊:釈迦如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第31番
山内掲示板などから開山・沿革をまとめてみます。
貞観六年(864年)、比叡山延暦寺に模して建立され、延暦寺第三代座主の円仁(慈覚大師)が開山された天台宗の名刹です。
往時は境内に僧坊三百余を擁し、関東を代表する大伽藍であったと伝わります。
寺格は高く、歴代髙﨑藩主の祈願所として安藤家や松平家などから崇敬され、本堂の軒瓦には葵の御紋が刻まれています。
寺宝に延長六年(928年)の勅命による小野道風真筆「天龍護国寺」の勅額があり、これは醍醐天皇が下賜されたものと伝わります。
「天竜護国寺の寺号勅額」として市指定重要文化財に指定されているこの額の裏面には、次のように書かれています。
醍醐天皇依勅定
延長六戌子歳従四位上小野道風書
其後額之縁再興元和六庚申年
高崎城主安藤対馬守重信
また、文化元年(1804年)著名な絵師、神宮寺守満による「並榎八景絵巻」も残されており、その絵巻には当寺の住職一元上人を中心に高崎の風流人が詠んだ漢詩と和歌が添えられています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 本堂
参道入口に山号標と寺号標。参道両側な広大な墓地で、正面、階段上に山門、くぐると正面が本堂です。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
入母屋造桟瓦葺で正面に唐破風の向拝をおく、整った伽藍です。
唐破風鬼板には、金剛界大日如来の種子「バン」とみられる梵字をおいています。
水引虹梁まわりはシンプルで、向拝見上げに寺号の扁額。これは小野道風真筆の勅額かと思われます。


【写真 上(左)】 唐破風まわり
【写真 下(右)】 扁額
山内のすぐ西側には日枝神社が鎮座します。
貞観年間(859-877年)に当寺の鎮守として近江国坂本の日吉大社から勧請と伝えられています。


【写真 上(左)】 日枝神社拝殿
【写真 下(右)】 日枝神社扁額
御朱印は趣きのある庫裡にて、揮毫のものを授与いただけました。
〔 厄除 元三大師の御朱印 〕

中央に御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「厄除 元三大師」の揮毫。
右上には菊花紋の印。左下に山号、院号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
御寶印の種子は、金剛界大日如来の種子「バン」のように思われます。
元三大師は如意輪観音の化身とされ、元三大師の御朱印では如意輪観音の種子「キリーク」が用いられることがありますが(例.深大寺)、他の例もあるようです。
天台宗の宗旨本尊として、釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来などが挙げられますが(資料によってことなる模様)、こちらでは宗旨本尊として金剛界大日如来の種子を使われているのかもしれません。(筆者の根拠のない憶測です)
46.我峰八幡神社
高崎市我峰町263
御祭神:品陀和気命(応神天皇)、息長足姫命(神功皇后)、建御名方命、八坂売命(素戔嗚尊)、大日孁命(天照大御神)、宇迦之御魂命、豊宇気毘売命(豊受大神)
旧社格:村社、神饌幣帛料供進社
境内掲示の由緒書などより。
創祀は明らかでないようですが、「口碑によれば、現社殿の前の神殿の奥に天平元年(729年)と記したる木札ありと言われ、また鎌倉時代の設立とも言伝える。」とのこと。
社殿横を流れる烏川の水流は当社付近で一大深淵をなし、無数の鮭がここに集まりこれより上流には遡らないことから「鮭の森」と呼ばれ、参拝者が多く訪れました。
古来より勝利の神として尊崇され、雛供養、人形供養の神社としてもよく知られています。
境内にある經塚は、永禄四年(1562年)の武田勢による箕輪城攻略の折に、住吉城(箕輪城の支城のひとつ)の城主・清水小内記藤原正智が宝物・経典を埋蔵した場所と云われています。
現在、この場所には息長足姫命(神功皇后)のお社が鎮座され、雛供養がおこなわれているようです。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 鳥居
境内はかなり広く、社頭に「八幡神社」の社号標と、すこし離れて茅の輪が設えられた朱塗りの明神鳥居。
鳥居から先は社叢におおわれ、朱塗りの灯籠が並んで神域ならではの厳粛な気がただよいます。
境内は清々しく整い、地元の方々の尊崇の篤さがうかがわれます。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿はおそらく入母屋造桟瓦の妻入りで、妻部の鬼板と懸魚部の彩色彫刻が見事。
水引虹梁両端木鼻と中備に彫刻を備え、正面桟唐戸の小ぶりながら端正に整った社殿で、本殿は拝殿内部に鎮座されているようです。
向拝見上げの扁額は「八幡神社」。


【写真 上(左)】 息長足姫命(神功皇后)のお社
【写真 下(右)】 鮭の森大神
参道向かって左には上記の息長足姫命(神功皇后)のお社と「鮭の森大神」が鎮座しています。
こちらは通常非常駐のようで、御朱印はすこし離れた社務所(ご神職宅/高崎市我峰町72)で授与いただけます。
〔 御朱印 〕

「鮭乃森大神」「我峰八幡神社」のふたつの揮毫と3つの印判(神璽印、神社印、宝珠印)が捺された華々しい印象の御朱印です。
47.上野國一社八幡宮
公式Web
高崎市八幡町655
主祭神:品陀和気命、息長足姫命、玉依姫命
旧社格:郷社
御朱印揮毫:上野國一社八幡宮
ふるくから「一国一社の八幡宮」として、広く尊崇を集めてきた八幡様です。
公式Web、境内掲示などから由緒・略歴などをまとめてみます。
平安時代の天徳元年(957年)に京都の石清水八幡宮を勧請して創祀。
尚武の神として代々源氏の崇敬が深く、源頼義・源義家(八幡太郎)は奥州征伐の折に当社に必勝祈願し、戦勝の結果、社殿を改築したと伝わります。
「永承年間の改築」という説があるので、永承年間(1046-1053年)の改築は源頼義の前九年の役(1051-1062年)、源義家は後三年の役(1083-1087年)の際のもので、おのおの別の改築かもしれません。
また、永承年間(1046-1053年)は未だ前九年の役が真っ盛りですから、永承年間に源頼義が必勝祈願し、その勝利ののちに頼義の子義家(八幡太郎)が改築したのかもしれません。
源頼朝は鎌倉に幕府を開くと、当社に神田百町を寄進し社殿の改築などを行いました。
新田氏、足利氏、武田氏(信玄公)、豊臣秀吉、徳川家康などの武家・武将からも厚く尊崇を受けたと伝わります。
江戸時代に入っても徳川家光以来、社領百石の朱印地を受けて興隆。
江戸期は神仏混淆の色合いが強まり、別当神徳寺をはじめ社僧・神主・社家合わせて28家(24家とも)を数え、毎年75回の神事を営んだといいます。
明治初期の神仏分離ののち、明治5年7月に郷社に列せられ、「八幡の八幡様」(やわたのはちまんさま)とも呼ばれて広く尊崇を集めて今日に至っています。
「一国一社の八幡宮」とは、ふつう国府八幡宮をさします。
国府(こくぶ)八幡宮(府中八幡宮/国分八幡宮)とは、令制国の国府の近くに創建された八幡宮で、国衙(国司の役所)の鎮守や国分寺の鎮守として伝わるものがあります。
関東周辺の国府八幡宮(論社を含む)は、
武蔵国:武蔵国府八幡宮 (東京都府中市)
相模国:平塚八幡宮 (神奈川県平塚市)
伊豆国:八幡宮来宮神社 (静岡県伊東市)
安房国:鶴谷八幡宮 (千葉県館山市)
上総国:飯香岡八幡宮 (千葉県市原市)
下総国:葛飾八幡宮 (千葉県市川市)
甲斐国:大井俣窪八幡神社 (山梨県山梨市)/八幡神社 (山梨県甲府市)
下野国:下野國一社八幡宮 (栃木県足利市)
とされています。
上野国については、上野國一社八幡宮(当社)とする説と、当社が国府(現・前橋市元総社町)から離れていることから、国府に近い前橋八幡宮を比定する説もあるようです。

境内案内図


【写真 上(左)】 社号標
【写真 下(右)】 神門(旧仁王門)
境内は南に碓井川を見下ろす高台に広がり、川寄りの神門(旧仁王門)からの登り参道です。
なお、大鳥居は国道18号(旧中山道)の八幡大門交差点そばにあるそうです。
神門(旧仁王門)は切妻造銅板葺三間一戸の八脚単層門で、脇間には真新しい仁王像が鎮座しています。扁額は読解不能。
神門手前には「上野國一社八幡宮」の社号標。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 一の鳥居
階段の上に一の鳥居。石造の両部鳥居で「八幡大御神」の扁額。
そのすぐ先に江戸時代中期の造営とされる随神門。切妻造銅板葺木部朱塗り、三間一戸の八脚単層門で、脇間には随身像(神像)が安置されています。
あざやかな朱塗り、むくり気味の屋根で勢いを感じるつくり。


【写真 上(左)】 随神門
【写真 下(右)】 鐘楼と随神門
随神門の右手に神楽殿、左手に唐破風屋根の手水舎と鐘楼。
いずれも朱塗りで意匠を凝らしたもので、華やいだ雰囲気の境内。


【写真 上(左)】 神楽殿と鐘楼
【写真 下(右)】 拝殿
随神門正面が拝殿。
拝殿前の唐銅燈籠は高崎出身の豪商野澤屋(茂木)惣兵衛(惣兵衛)が大旦那となり、主に糸繭商人に浄財を募って慶応三年(1867年)に奉納されたもので、高崎市の指定重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 唐銅燈籠と拝殿
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
入母屋造銅瓦葺で正面に千鳥破風、その前面に唐破風付きの流れ向拝を置いています。
後背の幣殿、本殿が一体となる権現造の様式で、宝暦七年(1757年)、御鎮座八百年を記念して新築されたものです。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天井絵と奉納額
向拝は4本の向拝柱を擁し、水引虹梁には立体感あふれる彫刻が施されています。
見上げれば、二連の破風(唐破風と千鳥破風)の変化に富んだ構成も見応えがあります。
ふところが深く内陣寄りには拝殿幕が張られています。
彩色天井絵や奉納額も見事なものです。


【写真 上(左)】 拝殿~本殿の見事な意匠
【写真 下(右)】 本殿身舎の斗栱
側面の仕上げが豪華です。
彩色の桟唐戸、花頭窓、幣殿~本殿の木鼻や斗栱、脇障子の精緻な彫刻、二色塗りの二軒繁垂木など、寺社建築の合わせワザが展開されています。
なんとなく、神社の建築としては異色な感じがしたのですが、この拝殿内部は旧護摩堂とのこと。
神仏混淆式の建物として、高崎市の指定重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 天満宮
【写真 下(右)】 向拝の彫刻と斗栱
拝殿向かって右には天満宮が鎮座します。
入母屋造妻入り金属板葺で正面唐破風向拝付。
入母屋の屋根勾配が急で、妻入りの棟飾りと向拝の唐破風がコントラストをなす華麗な社殿で、これはかつての本地堂とのこと。
向拝や身舎まわりの木鼻や斗栱の構成も見事です。
なお、「本地垂迹資料便覧」様によると、当社の本地仏は阿弥陀如来・観世音菩薩・大勢至菩薩の阿弥陀三尊で、本地堂には阿弥陀三尊が安置されていたようです。
境内には参拝順路が設定され、これに従うと拝殿、本殿、本殿背後の摂社二十二社、東照宮(疫斎神)、御輿庫、地主稲荷社、日枝社(山王宮)と巡拝することができます。
地主稲荷社は当社の元宮で、例祭に頒布される餅は「子授け餅」(はらみもち)として、子宝に恵まれる奇瑞のあるものとして知られています。
さすがに「一国一社の八幡宮」だけあって、境内は見どころにあふれています。
とくに神仏混淆の遺構を辿るには、最適な神社ではないでしょうか。
〔 御朱印 〕

授与所にて御朱印に書き入れいただきました。
社号の揮毫、社号印、鎮座地の印で構成されています。
48.神通山 遍照王院 大聖護国寺
公式Web
高崎市八幡町675-1
真言宗豊山派
御本尊:愛染明王・不動明王
札所:


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 愛染明王の御朱印
開山は健保四年(1216年)、地方本寺として五十三ヶ寺を有していたという名刹です。
公式Webによると、定弘和尚が高野山清浄心院より御本尊愛染明王及び不動明王を奉じられて開山。
上野国和田城主和田八郎信業、北条氏政、徳川家康公等の尊崇を受け御朱印を授かっているとのことです。
五代将軍綱吉公の母君桂昌院は当山二十四世亮賢和尚への信頼篤く、延宝二年(1674)、当寺に多くの仏像を寄進し伽藍を建立、仏具などを奉納しました。
また、天和元年(1681年)亮賢和尚を護持僧として幕府所属の高田薬園の地に招き、堂宇を建立し、桂昌院の念持仏、天然琥珀如意輪観世音菩薩像を本尊として神齢山 悉地院 護国寺が創建されました。
この由緒は護国寺の公式Webにも明記され、そのなかで当寺は「上野国碓井八幡宮の別当、大聖護国寺」と記載されています。
また、山内由緒書にも「寛永年間までは隣接する上野国一社八幡宮の別当寺でした。」とあります。
当寺は、上野國一社八幡宮のすぐとなりにあり、上野國一社八幡宮は「碓井八幡宮」とも称されたことから、すくなくとも寛永年間までは隣上野國一社八幡宮の別当であったものとみられます。
(なお、上野國一社八幡宮の境内由緒書には「明治維新まで別当神徳寺ほか社僧・社家合わせて二十四家による神仏混淆の神事を執行す)とあるので、寛永年間までの別当は大聖護国寺、それ以降は神徳寺となった可能性があります。)


【写真 上(左)】 不動明王の御朱印
【写真 下(右)】 阿弥陀如来の御朱印
境内は名刹らしくよく整っています。
堂宇のほとんどは開放され、仏像を間近で拝めます。
音羽の護国寺も本堂内にあげていただけますから、このあたりは護国寺の伝統なのかもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、筆者参拝時は「拝観・御朱印受付は、金・土・日・月10時から4時までです」との掲示がありました。
49.慈雲山 養寿院 福泉寺
公式Web
高崎市鼻高町707
天台宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:
絵御朱印で有名な天台宗寺院です。
筆者は「武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印」という記事をとりまとめ中で、こちらにはこれまで未参拝で気になっていましたが、ようやく参拝が叶いました。
いただいた由緒書と山内の供養塔建立の説明板には以下のとおりあります。
・福泉寺東側は、箕輪城の出城(内出)があった所とされ、永禄年間、武田軍の六回に及ぶ箕輪城攻撃の際、武田信玄公がその本陣に使用し、激闘がおこなわれたとも言われています。
・福泉寺には、この合戦の戦死者を供養する供養塔が建立されています。
・説明板の日付は昭和56年(1981年)秋、そこから450年前の開創ということなので、1531年、室町時代の享禄年間ということになります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御本尊 聖観世音菩薩の御朱印
山内には多くの供養佛(露仏)が並びます。
本堂はいささか無機質な建物ですが、花手水などが山内各所に配されて手入れが行き届いた印象です。

人気の「風林火山」の絵御朱印
当寺では、上記の所縁から武田信玄公の「風林火山」の絵御朱印を授与されています。
絵御朱印にはさほど興味がない筆者ですが、この「風林火山」の御朱印はすばらしいもので、御本尊、聖観世音菩薩の御朱印とともに拝受しました。
さすがに絵御朱印で人気のお寺さんらしく、私が参拝したときも先客が2組ほどいました。
御朱印授与日・時間は公式Web(インスタ)で随時案内されているようです。
50.少林山 達磨寺
公式Web
高崎市鼻高町296
黄檗宗
御本尊:北辰鎮宅霊符尊
札所:


高崎の縁起だるま発祥の寺として知られる名刹てす。
公式Webなどから由緒をとりまとめてみます。
室町時代末期より、鼻高村の高台には行基菩薩の彫刻とされる観音様を祀る観音堂がありました。
延宝年間(1673-1681年)に大雨で碓氷川が氾濫したとき、香りを放つ古木が流れつき観音堂に納められました。
一了居士という行者の夢枕に達磨大師が立たれ、この霊木で達磨大師の像を彫るようお告げがあり、一了居士は、沐浴斎戒、一刀三礼で達磨大師の坐禅像を彫りあげました。
この観音堂のあたりはいつしか“達磨出現の霊地”として「少林山」と崇められ、時の領主・酒井雅楽頭忠挙公は厩橋城(前橋城)の裏鬼門を護る寺として、水戸光圀公の帰依された僧・東皐心越禅師を開山と仰ぎ、弟子の天湫和尚を水戸から請じて、元禄十年(1697年)少林山 達磨寺を開創しました。
以降、衆生の尊崇篤く、享保十一年(1726年)には水戸徳川家から三葉葵の紋と丸に水の徽章を賜い、永世の祈願所とされました。
山上に、達磨堂、霊符堂、観音堂と並びます。
御本尊は、北斗星を神格化した北辰鎮宅霊符尊です。
達磨寺は前橋城から見て南西に鎮座し、前橋城の裏鬼門を守護する寺として創建されたこともあり、現在も関東隋一の方位除・八方除の祈願所として参拝客を集めています。
御朱印は、原則として写経納経者にのみ授与されますが、山内の瑞雲閣に十文字写経の用紙が用意されており、こちらを写経して納めることでも授与いただけます。
オリジナルの御朱印帳も頒布されています。
51.八幡山 月光院 常安寺
公式Web
高崎市下豊岡甲1405
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
信濃国の名族滋野氏は小県郡、佐久郡を中心に勢力を張り、分流した海野氏・根津氏・望月氏は「滋野三家」と呼ばれ、滋野氏嫡流の家柄とされました。
禰津(根津)氏は滋野重道の二男道直が禰津を称したのが始まりとされ、以降、信濃の名族として諏訪氏と姻戚関係にあったとされます。
また、真田氏の出自はナゾが多いですが、滋野氏の流れで、禰津氏の支流という見方が有力のようです。
禰津氏の本拠は禰津古御館ないし禰津(祢津)城(現・長野県東御市)で、古くから武勇の家柄として名を馳せ、保元・平治の乱や源平合戦での活躍が伝わります。
南北朝期には南朝方にくみしたとされ、ここでも数々の戦功が伝わります。
「滋野三家」の結束は堅く、室町期にも小県郡、佐久郡、更級郡、上野国吾妻郡にまで及ぶ勢力を有していたとみられます。
天文十年(1541年)春、甲斐の武田信虎公が村上義清、諏訪頼重と謀り小県郡へ侵攻(海野平の戦い)。
滋野一族は手痛い敗北を被りましたが、禰津元直は諏訪神氏の姻戚であったことから本領を安堵されています。
禰津元直は天文十一年(1543年)正式に武田氏に臣従、同年末には元直の娘・禰津御寮人が晴信(信玄)公に嫁ぎ、武田信清をもうけています。(『高白斎記』)
元直ののち禰津氏家督は紆余曲折を経て、次男の政直(松鴎軒常安)が継ぎ、常安は武田氏の先方衆として真田氏など滋野一族と連携して上野国方面に進出しました。
常安は北信濃の飯山城の城代も任されていたため、天正十年(1582年)春の織田・徳川連合軍の甲州征伐でも命を落とさず、徳川家康公に臣従。
常安は徳川家家臣となった際に「禰津」から「根津」に名字をかえたとされます。
家康公の関東移封後、上野国豊岡に5千石の所領を得、これを継いだ常安の甥、信政は慶長七年(1602年)5千石の加増を受け、一万石の大名として上野豊岡藩を立藩しました。
しかし寛永三年(1626年)、三代藩主・吉直が若くして死去すると無嗣断絶となり、上野豊岡藩は惜しくも廃藩となりました。
禰津(根津)氏はふるくから鷹匠の家柄として知られていたため、廃藩後根津一族は幕臣となり、鷹匠元締めをつとめたと伝わります。
上野豊岡陣屋跡は、現在の常安寺付近と伝わります。
常安寺の公式Webによると、当寺は祢津(根津)常安が生前に自らの供養のため元亀元年(1570年)に豊岡陣屋内に箕郷の金龍寺二世大雲吟撮大和尚を開山として開基。
みずからの名から常安寺と号したといいます。
常安(禰津公)の墓所は長野県東御市の定律院とされますが、常安寺にも墓石が残ります。


【写真 上(左)】 公道まで延びる参道
【写真 下(右)】 山門
倉渕方面からの烏川と、碓井から流れ下る碓井川が合流し、中山道と三国街道が分岐する地勢的な要衝で、そんなこともあって豊岡陣屋が置かれたものと思われます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 本堂
山門は明治中期の火災を免れた唯一の遺構で、切妻屋根桟瓦葺の四脚門。
妻側にかかる唐破風風のやわらかな曲線が個性的で見上げに山号の扁額。


【写真 上(左)】 庭園からの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は入母屋造桟葺流れ向拝で、大がかりな軒唐破風を構えています。
水引虹梁両端に禅宗様の木鼻、中備に板蟇股。水引虹梁斗栱は左右各二連で複雑な意匠。
身舎側に海老虹梁、向拝見上げに院号扁額を掲げています。
大棟や唐破風まわりに掲げられた紋は、おそらく禰津氏の家紋「丸に月の字」と思われます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 本堂向拝唐破風
本堂向かって右に地蔵菩薩坐像、左には阿弥陀如来坐像が御座し、おのおの献花がそえられて華やぎのある堂前です。
閻魔様とゆかりのふかい寺院で、本堂内には閻魔大王像、山内には奪衣婆像も奉安されています。
こちらは札所ではなく、これまでノーマーク。ウクライナ難民支援御朱印関連で参拝しましたが、ウクライナ支援御朱印のほかに御本尊の御朱印も拝受できました。
ただし、書置のご用意はない模様で、ご住職ご不在時には拝受できないかもしれません。
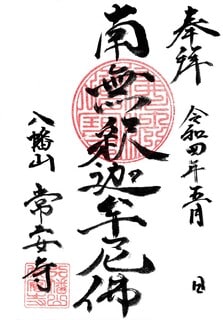
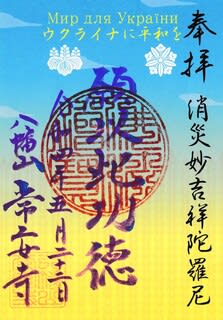
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 ウクライナ難民支援御朱印(期間限定)
※尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。
これで「伊香保温泉周辺の御朱印」はひとまず完結ですが、エリア内で御朱印を拝受した場合は適宜追加していきます。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ 茜色の約束 - 森恵
■ Mirai 未来 - Kalafina
■ This Love - Angela Aki
■ 日本代表史上最高のゴール
↑ これは凄い!
ご留意をお願いします。
-----------------------------------------
2019/01/25 補足UP
2021/01/31 補足UP
2022/01/15 補足UP
2022/06/03 補足UP
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
43.如意山 宝蔵院 大乗寺(高崎市棟高町)
44.烏子稲荷神社 (高崎市上小塙町)
45.新比叡山 本実成院 天竜護国寺(高崎市上並榎町)
46.我峰八幡神社 (高崎市我峰町)
47.上野國一社八幡宮 (高崎市八幡町)
48.神通山 遍照王院 大聖護国寺 (高崎市八幡町)
49.慈雲山 養寿院 福泉寺 (高崎市鼻高町)
50.少林山 達磨寺 (高崎市鼻高町)
51.八幡山 月光院 常安寺 (高崎市下豊岡甲)
43.如意山 宝蔵院 大乗寺
高崎市棟高町2234
真言宗豊山派
御本尊:
開山、沿革などは不詳ですが、高崎市の指定重要文化財である「農耕図屏風」を所蔵する寺院として知られています。
「農耕図屏風」は、源信寿(みなもとののぶひさ)の筆による「農事一式の図」六曲一双の屏風です。
江戸前期の農作業を描写したもので、脱穀に「くるり棒」(回転式の稲打ち棒)を使わず、二股の自然木を利用している様子が時代を反映するものとされます。
女が頭上に舟・えび・うさぎ等の型を乗せて、五穀豊穣を祝う踊りの姿などが見どころとされます。
大乗寺のそばにある高崎市立堤ヶ岡小学校は大乗寺山内の発育小学校が発祥、堤ヶ岡幼稚園、堤ヶ岡保育園ともに大乗寺を母体としているそうで、児童教育とゆかりの深いお寺さんと思われます。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山内
堤ヶ岡幼稚園横が参道入口で、山号標と寺号標が建っています。
その先の山門は桟瓦葺で、薬医門形式と思われます。
本堂と左手に宝形造桟瓦葺向拝付きのお堂があります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺で、正面に軒唐破風の立派な向拝を起こしています。
大棟の棟飾りは経の巻獅子口。
水引虹梁両端、正面と側面に雲形の木鼻。中備に花紋様の板蟇股。頭貫上の斗栱は斗が5つです。
唐破風下に大瓶束笈形を置き、兎毛通に蕪懸魚、破風上の鬼板に経の巻獅子口を置いているので、下から水引虹梁、板蟇股、虹梁、大瓶束笈形、蕪懸魚、経の巻獅子口という見どころの多い構成となっています。
向拝見上げの扁額は「如意山」の山号です。
霊場札所ではないですが御朱印を授与いただけました。
ただし、ご不在や法事によりいただけない場合もあり、3度目の参拝で授与いただけました。
〔 不動明王の御朱印 〕

中央に不動明王の種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「不動明王」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
44.烏子稲荷神社
高崎市上小塙町564
御祭神:宇迦之御魂命、大日霊命、素戔嗚命、菅原道真公
神饌幣帛料供進社
「すないご」という難読の社号をもつ稲荷神社です。
境内由緒書きなどを参考に、創祀・沿革をまとめてみます。
延暦二年(783年)に公卿の藤原金善という人が、山城国(現 京都府)の藤ノ森稲荷神社の御分霊をこの地に勧請したのが創祀とされます。
この地は古くは須苗郷(須苗子・烏子)と呼ばれ、当社は須苗郷(すないご・ごう)の総鎮守として崇敬されてきました。
戦国時代、甲斐の武田信玄公が箕輪城攻略の際に戦勝祈願をし、大願成就の後、武田家臣の浦野家、新井家とゆかりをもち、後世まで関係を保っているようです。
江戸時代には徳川家より代々御朱印を頂いています。
明治三十九年(1906年)、神饌幣帛料を共進しうべき神社に指定。
社殿は六世紀前半の上小塙稲荷山古墳の上に祀られ、本殿裏には巨大な石で築かれた石室があります。
「上小塙稲荷山古墳」は高崎市の指定史跡に指定され、石室の穴は都に通じているとか、白狐が住んでいるなどともいわれて稲荷信仰の対象となっていました。
そのために、古墳が状態よく保存されていたものと評価されています。
社宝として所蔵されている須恵器類も附指定されています。
平地のなかにこんもり丸く盛り上がった社叢は、いかにも古墳を思わせるもの。
かなり離れたところ(北部環状線沿い)に朱塗りの大鳥居を構えています。


【写真 上(左)】 社頭から境内
【写真 下(右)】 境内案内図
参道階段下に駐車場。右手に社務所。参道手前に石灯籠一対。すでにこのあたりから神さびた雰囲気をまとっています。


【写真 上(左)】 身代り達磨
【写真 下(右)】 弁天様
社務所のそばには、身体の痛いところをさすると痛みがなおるという「身代り達磨」。
左手の池に御座す弁天様は、もともと古墳外堀に祀られて霊験確かな弁天様として信仰を集めていたところ、外堀改修工事に際しご神像の奉納がなされて現在の位置に御遷座されたとのこと。


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 産泰様
参道階段手前に狛犬一対。その先左手に手水舎と朱塗りの台輪鳥居で鳥居扁額は「稲荷大神」。
鳥居左手には朱の鳥居が連なる参道?があり、稲荷神社らしい空気感。
階段途中にも石造の台輪鳥居があり、その先左手には子授り、子育て、安産の神様、産泰様のお社が鎮座しています。
産泰様の手前には、高崎城主・安藤対馬守が参詣のおりにお手植えされたという「逆さもみじ」があります。この木は逆さに挿したのに根付いた生命の強い木とされ、諸願成就の所以となっています。


【写真 上(左)】 神楽殿
【写真 下(右)】 拝殿
階段の左手奥には朱塗りで均整のとれた神楽殿。
階段正面が拝殿で、位置的に屋根構造がうまく確認できないのですが、おそらく入母屋造瓦葺唐破風向拝付きで、妻入りかもしれません。
朱塗りの柱が意匠的に効いた、華やかな印象の社殿です。


【写真 上(左)】 頭貫の彫刻
【写真 下(右)】 中備の彫刻
朱塗りの向拝柱の上に古色を帯びた水引虹梁を置き、両端に精緻な彫刻木鼻(正面獅子、側面象鼻)を備えています。
中備にはボリューム感のある龍の彫刻。唐破風軒の懸魚部にも彫刻を置いています。
唐破風の鬼板は、綾筋付きの経の巻獅子口のようにも見えました。
十八世紀末の築と推定される本殿は、「烏子稲荷神社本殿」として高崎市の指定文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 烏子天神
正面はよく見えないのですが、境内説明板によると一間社入母屋造で現在は銅板葺。
組物は三手先詰組、蛇腹支輪。
向拝に虹梁形頭貫で連三斗積上、木鼻は正面を獅子、側面を象鼻。頭貫おくに力感あふれる海老虹梁。
中備に蟇股。向拝正面打越二軒繁垂木。
妻飾りは虹梁大瓶束式笈形付。屋根に千木と堅魚木を置いています。
脇障子の透かし彫りも見事なもので、すこぶる存在感のある本殿です。
本殿右手に鎮座する天神様のお社は、一間の切妻造銅版葺正面桟唐戸で「烏子天神」の扁額を掲げています。
御朱印は社務所にて揮毫のものをいただけました。
〔 御朱印 〕

揮毫は「烏子稲荷神社」で、神社印が捺されています。
45.新比叡山 本実成院 天龍護国寺
高崎市上並榎町922
天台宗
御本尊:釈迦如来
札所:群馬郡三十三観音霊場第31番
山内掲示板などから開山・沿革をまとめてみます。
貞観六年(864年)、比叡山延暦寺に模して建立され、延暦寺第三代座主の円仁(慈覚大師)が開山された天台宗の名刹です。
往時は境内に僧坊三百余を擁し、関東を代表する大伽藍であったと伝わります。
寺格は高く、歴代髙﨑藩主の祈願所として安藤家や松平家などから崇敬され、本堂の軒瓦には葵の御紋が刻まれています。
寺宝に延長六年(928年)の勅命による小野道風真筆「天龍護国寺」の勅額があり、これは醍醐天皇が下賜されたものと伝わります。
「天竜護国寺の寺号勅額」として市指定重要文化財に指定されているこの額の裏面には、次のように書かれています。
醍醐天皇依勅定
延長六戌子歳従四位上小野道風書
其後額之縁再興元和六庚申年
高崎城主安藤対馬守重信
また、文化元年(1804年)著名な絵師、神宮寺守満による「並榎八景絵巻」も残されており、その絵巻には当寺の住職一元上人を中心に高崎の風流人が詠んだ漢詩と和歌が添えられています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 本堂
参道入口に山号標と寺号標。参道両側な広大な墓地で、正面、階段上に山門、くぐると正面が本堂です。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
入母屋造桟瓦葺で正面に唐破風の向拝をおく、整った伽藍です。
唐破風鬼板には、金剛界大日如来の種子「バン」とみられる梵字をおいています。
水引虹梁まわりはシンプルで、向拝見上げに寺号の扁額。これは小野道風真筆の勅額かと思われます。


【写真 上(左)】 唐破風まわり
【写真 下(右)】 扁額
山内のすぐ西側には日枝神社が鎮座します。
貞観年間(859-877年)に当寺の鎮守として近江国坂本の日吉大社から勧請と伝えられています。


【写真 上(左)】 日枝神社拝殿
【写真 下(右)】 日枝神社扁額
御朱印は趣きのある庫裡にて、揮毫のものを授与いただけました。
〔 厄除 元三大師の御朱印 〕

中央に御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「厄除 元三大師」の揮毫。
右上には菊花紋の印。左下に山号、院号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
御寶印の種子は、金剛界大日如来の種子「バン」のように思われます。
元三大師は如意輪観音の化身とされ、元三大師の御朱印では如意輪観音の種子「キリーク」が用いられることがありますが(例.深大寺)、他の例もあるようです。
天台宗の宗旨本尊として、釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来などが挙げられますが(資料によってことなる模様)、こちらでは宗旨本尊として金剛界大日如来の種子を使われているのかもしれません。(筆者の根拠のない憶測です)
46.我峰八幡神社
高崎市我峰町263
御祭神:品陀和気命(応神天皇)、息長足姫命(神功皇后)、建御名方命、八坂売命(素戔嗚尊)、大日孁命(天照大御神)、宇迦之御魂命、豊宇気毘売命(豊受大神)
旧社格:村社、神饌幣帛料供進社
境内掲示の由緒書などより。
創祀は明らかでないようですが、「口碑によれば、現社殿の前の神殿の奥に天平元年(729年)と記したる木札ありと言われ、また鎌倉時代の設立とも言伝える。」とのこと。
社殿横を流れる烏川の水流は当社付近で一大深淵をなし、無数の鮭がここに集まりこれより上流には遡らないことから「鮭の森」と呼ばれ、参拝者が多く訪れました。
古来より勝利の神として尊崇され、雛供養、人形供養の神社としてもよく知られています。
境内にある經塚は、永禄四年(1562年)の武田勢による箕輪城攻略の折に、住吉城(箕輪城の支城のひとつ)の城主・清水小内記藤原正智が宝物・経典を埋蔵した場所と云われています。
現在、この場所には息長足姫命(神功皇后)のお社が鎮座され、雛供養がおこなわれているようです。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 鳥居
境内はかなり広く、社頭に「八幡神社」の社号標と、すこし離れて茅の輪が設えられた朱塗りの明神鳥居。
鳥居から先は社叢におおわれ、朱塗りの灯籠が並んで神域ならではの厳粛な気がただよいます。
境内は清々しく整い、地元の方々の尊崇の篤さがうかがわれます。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿はおそらく入母屋造桟瓦の妻入りで、妻部の鬼板と懸魚部の彩色彫刻が見事。
水引虹梁両端木鼻と中備に彫刻を備え、正面桟唐戸の小ぶりながら端正に整った社殿で、本殿は拝殿内部に鎮座されているようです。
向拝見上げの扁額は「八幡神社」。


【写真 上(左)】 息長足姫命(神功皇后)のお社
【写真 下(右)】 鮭の森大神
参道向かって左には上記の息長足姫命(神功皇后)のお社と「鮭の森大神」が鎮座しています。
こちらは通常非常駐のようで、御朱印はすこし離れた社務所(ご神職宅/高崎市我峰町72)で授与いただけます。
〔 御朱印 〕

「鮭乃森大神」「我峰八幡神社」のふたつの揮毫と3つの印判(神璽印、神社印、宝珠印)が捺された華々しい印象の御朱印です。
47.上野國一社八幡宮
公式Web
高崎市八幡町655
主祭神:品陀和気命、息長足姫命、玉依姫命
旧社格:郷社
御朱印揮毫:上野國一社八幡宮
ふるくから「一国一社の八幡宮」として、広く尊崇を集めてきた八幡様です。
公式Web、境内掲示などから由緒・略歴などをまとめてみます。
平安時代の天徳元年(957年)に京都の石清水八幡宮を勧請して創祀。
尚武の神として代々源氏の崇敬が深く、源頼義・源義家(八幡太郎)は奥州征伐の折に当社に必勝祈願し、戦勝の結果、社殿を改築したと伝わります。
「永承年間の改築」という説があるので、永承年間(1046-1053年)の改築は源頼義の前九年の役(1051-1062年)、源義家は後三年の役(1083-1087年)の際のもので、おのおの別の改築かもしれません。
また、永承年間(1046-1053年)は未だ前九年の役が真っ盛りですから、永承年間に源頼義が必勝祈願し、その勝利ののちに頼義の子義家(八幡太郎)が改築したのかもしれません。
源頼朝は鎌倉に幕府を開くと、当社に神田百町を寄進し社殿の改築などを行いました。
新田氏、足利氏、武田氏(信玄公)、豊臣秀吉、徳川家康などの武家・武将からも厚く尊崇を受けたと伝わります。
江戸時代に入っても徳川家光以来、社領百石の朱印地を受けて興隆。
江戸期は神仏混淆の色合いが強まり、別当神徳寺をはじめ社僧・神主・社家合わせて28家(24家とも)を数え、毎年75回の神事を営んだといいます。
明治初期の神仏分離ののち、明治5年7月に郷社に列せられ、「八幡の八幡様」(やわたのはちまんさま)とも呼ばれて広く尊崇を集めて今日に至っています。
「一国一社の八幡宮」とは、ふつう国府八幡宮をさします。
国府(こくぶ)八幡宮(府中八幡宮/国分八幡宮)とは、令制国の国府の近くに創建された八幡宮で、国衙(国司の役所)の鎮守や国分寺の鎮守として伝わるものがあります。
関東周辺の国府八幡宮(論社を含む)は、
武蔵国:武蔵国府八幡宮 (東京都府中市)
相模国:平塚八幡宮 (神奈川県平塚市)
伊豆国:八幡宮来宮神社 (静岡県伊東市)
安房国:鶴谷八幡宮 (千葉県館山市)
上総国:飯香岡八幡宮 (千葉県市原市)
下総国:葛飾八幡宮 (千葉県市川市)
甲斐国:大井俣窪八幡神社 (山梨県山梨市)/八幡神社 (山梨県甲府市)
下野国:下野國一社八幡宮 (栃木県足利市)
とされています。
上野国については、上野國一社八幡宮(当社)とする説と、当社が国府(現・前橋市元総社町)から離れていることから、国府に近い前橋八幡宮を比定する説もあるようです。

境内案内図


【写真 上(左)】 社号標
【写真 下(右)】 神門(旧仁王門)
境内は南に碓井川を見下ろす高台に広がり、川寄りの神門(旧仁王門)からの登り参道です。
なお、大鳥居は国道18号(旧中山道)の八幡大門交差点そばにあるそうです。
神門(旧仁王門)は切妻造銅板葺三間一戸の八脚単層門で、脇間には真新しい仁王像が鎮座しています。扁額は読解不能。
神門手前には「上野國一社八幡宮」の社号標。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 一の鳥居
階段の上に一の鳥居。石造の両部鳥居で「八幡大御神」の扁額。
そのすぐ先に江戸時代中期の造営とされる随神門。切妻造銅板葺木部朱塗り、三間一戸の八脚単層門で、脇間には随身像(神像)が安置されています。
あざやかな朱塗り、むくり気味の屋根で勢いを感じるつくり。


【写真 上(左)】 随神門
【写真 下(右)】 鐘楼と随神門
随神門の右手に神楽殿、左手に唐破風屋根の手水舎と鐘楼。
いずれも朱塗りで意匠を凝らしたもので、華やいだ雰囲気の境内。


【写真 上(左)】 神楽殿と鐘楼
【写真 下(右)】 拝殿
随神門正面が拝殿。
拝殿前の唐銅燈籠は高崎出身の豪商野澤屋(茂木)惣兵衛(惣兵衛)が大旦那となり、主に糸繭商人に浄財を募って慶応三年(1867年)に奉納されたもので、高崎市の指定重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 唐銅燈籠と拝殿
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
入母屋造銅瓦葺で正面に千鳥破風、その前面に唐破風付きの流れ向拝を置いています。
後背の幣殿、本殿が一体となる権現造の様式で、宝暦七年(1757年)、御鎮座八百年を記念して新築されたものです。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天井絵と奉納額
向拝は4本の向拝柱を擁し、水引虹梁には立体感あふれる彫刻が施されています。
見上げれば、二連の破風(唐破風と千鳥破風)の変化に富んだ構成も見応えがあります。
ふところが深く内陣寄りには拝殿幕が張られています。
彩色天井絵や奉納額も見事なものです。


【写真 上(左)】 拝殿~本殿の見事な意匠
【写真 下(右)】 本殿身舎の斗栱
側面の仕上げが豪華です。
彩色の桟唐戸、花頭窓、幣殿~本殿の木鼻や斗栱、脇障子の精緻な彫刻、二色塗りの二軒繁垂木など、寺社建築の合わせワザが展開されています。
なんとなく、神社の建築としては異色な感じがしたのですが、この拝殿内部は旧護摩堂とのこと。
神仏混淆式の建物として、高崎市の指定重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 天満宮
【写真 下(右)】 向拝の彫刻と斗栱
拝殿向かって右には天満宮が鎮座します。
入母屋造妻入り金属板葺で正面唐破風向拝付。
入母屋の屋根勾配が急で、妻入りの棟飾りと向拝の唐破風がコントラストをなす華麗な社殿で、これはかつての本地堂とのこと。
向拝や身舎まわりの木鼻や斗栱の構成も見事です。
なお、「本地垂迹資料便覧」様によると、当社の本地仏は阿弥陀如来・観世音菩薩・大勢至菩薩の阿弥陀三尊で、本地堂には阿弥陀三尊が安置されていたようです。
境内には参拝順路が設定され、これに従うと拝殿、本殿、本殿背後の摂社二十二社、東照宮(疫斎神)、御輿庫、地主稲荷社、日枝社(山王宮)と巡拝することができます。
地主稲荷社は当社の元宮で、例祭に頒布される餅は「子授け餅」(はらみもち)として、子宝に恵まれる奇瑞のあるものとして知られています。
さすがに「一国一社の八幡宮」だけあって、境内は見どころにあふれています。
とくに神仏混淆の遺構を辿るには、最適な神社ではないでしょうか。
〔 御朱印 〕

授与所にて御朱印に書き入れいただきました。
社号の揮毫、社号印、鎮座地の印で構成されています。
48.神通山 遍照王院 大聖護国寺
公式Web
高崎市八幡町675-1
真言宗豊山派
御本尊:愛染明王・不動明王
札所:


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 愛染明王の御朱印
開山は健保四年(1216年)、地方本寺として五十三ヶ寺を有していたという名刹です。
公式Webによると、定弘和尚が高野山清浄心院より御本尊愛染明王及び不動明王を奉じられて開山。
上野国和田城主和田八郎信業、北条氏政、徳川家康公等の尊崇を受け御朱印を授かっているとのことです。
五代将軍綱吉公の母君桂昌院は当山二十四世亮賢和尚への信頼篤く、延宝二年(1674)、当寺に多くの仏像を寄進し伽藍を建立、仏具などを奉納しました。
また、天和元年(1681年)亮賢和尚を護持僧として幕府所属の高田薬園の地に招き、堂宇を建立し、桂昌院の念持仏、天然琥珀如意輪観世音菩薩像を本尊として神齢山 悉地院 護国寺が創建されました。
この由緒は護国寺の公式Webにも明記され、そのなかで当寺は「上野国碓井八幡宮の別当、大聖護国寺」と記載されています。
また、山内由緒書にも「寛永年間までは隣接する上野国一社八幡宮の別当寺でした。」とあります。
当寺は、上野國一社八幡宮のすぐとなりにあり、上野國一社八幡宮は「碓井八幡宮」とも称されたことから、すくなくとも寛永年間までは隣上野國一社八幡宮の別当であったものとみられます。
(なお、上野國一社八幡宮の境内由緒書には「明治維新まで別当神徳寺ほか社僧・社家合わせて二十四家による神仏混淆の神事を執行す)とあるので、寛永年間までの別当は大聖護国寺、それ以降は神徳寺となった可能性があります。)


【写真 上(左)】 不動明王の御朱印
【写真 下(右)】 阿弥陀如来の御朱印
境内は名刹らしくよく整っています。
堂宇のほとんどは開放され、仏像を間近で拝めます。
音羽の護国寺も本堂内にあげていただけますから、このあたりは護国寺の伝統なのかもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、筆者参拝時は「拝観・御朱印受付は、金・土・日・月10時から4時までです」との掲示がありました。
49.慈雲山 養寿院 福泉寺
公式Web
高崎市鼻高町707
天台宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:
絵御朱印で有名な天台宗寺院です。
筆者は「武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印」という記事をとりまとめ中で、こちらにはこれまで未参拝で気になっていましたが、ようやく参拝が叶いました。
いただいた由緒書と山内の供養塔建立の説明板には以下のとおりあります。
・福泉寺東側は、箕輪城の出城(内出)があった所とされ、永禄年間、武田軍の六回に及ぶ箕輪城攻撃の際、武田信玄公がその本陣に使用し、激闘がおこなわれたとも言われています。
・福泉寺には、この合戦の戦死者を供養する供養塔が建立されています。
・説明板の日付は昭和56年(1981年)秋、そこから450年前の開創ということなので、1531年、室町時代の享禄年間ということになります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 御本尊 聖観世音菩薩の御朱印
山内には多くの供養佛(露仏)が並びます。
本堂はいささか無機質な建物ですが、花手水などが山内各所に配されて手入れが行き届いた印象です。

人気の「風林火山」の絵御朱印
当寺では、上記の所縁から武田信玄公の「風林火山」の絵御朱印を授与されています。
絵御朱印にはさほど興味がない筆者ですが、この「風林火山」の御朱印はすばらしいもので、御本尊、聖観世音菩薩の御朱印とともに拝受しました。
さすがに絵御朱印で人気のお寺さんらしく、私が参拝したときも先客が2組ほどいました。
御朱印授与日・時間は公式Web(インスタ)で随時案内されているようです。
50.少林山 達磨寺
公式Web
高崎市鼻高町296
黄檗宗
御本尊:北辰鎮宅霊符尊
札所:


高崎の縁起だるま発祥の寺として知られる名刹てす。
公式Webなどから由緒をとりまとめてみます。
室町時代末期より、鼻高村の高台には行基菩薩の彫刻とされる観音様を祀る観音堂がありました。
延宝年間(1673-1681年)に大雨で碓氷川が氾濫したとき、香りを放つ古木が流れつき観音堂に納められました。
一了居士という行者の夢枕に達磨大師が立たれ、この霊木で達磨大師の像を彫るようお告げがあり、一了居士は、沐浴斎戒、一刀三礼で達磨大師の坐禅像を彫りあげました。
この観音堂のあたりはいつしか“達磨出現の霊地”として「少林山」と崇められ、時の領主・酒井雅楽頭忠挙公は厩橋城(前橋城)の裏鬼門を護る寺として、水戸光圀公の帰依された僧・東皐心越禅師を開山と仰ぎ、弟子の天湫和尚を水戸から請じて、元禄十年(1697年)少林山 達磨寺を開創しました。
以降、衆生の尊崇篤く、享保十一年(1726年)には水戸徳川家から三葉葵の紋と丸に水の徽章を賜い、永世の祈願所とされました。
山上に、達磨堂、霊符堂、観音堂と並びます。
御本尊は、北斗星を神格化した北辰鎮宅霊符尊です。
達磨寺は前橋城から見て南西に鎮座し、前橋城の裏鬼門を守護する寺として創建されたこともあり、現在も関東隋一の方位除・八方除の祈願所として参拝客を集めています。
御朱印は、原則として写経納経者にのみ授与されますが、山内の瑞雲閣に十文字写経の用紙が用意されており、こちらを写経して納めることでも授与いただけます。
オリジナルの御朱印帳も頒布されています。
51.八幡山 月光院 常安寺
公式Web
高崎市下豊岡甲1405
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
信濃国の名族滋野氏は小県郡、佐久郡を中心に勢力を張り、分流した海野氏・根津氏・望月氏は「滋野三家」と呼ばれ、滋野氏嫡流の家柄とされました。
禰津(根津)氏は滋野重道の二男道直が禰津を称したのが始まりとされ、以降、信濃の名族として諏訪氏と姻戚関係にあったとされます。
また、真田氏の出自はナゾが多いですが、滋野氏の流れで、禰津氏の支流という見方が有力のようです。
禰津氏の本拠は禰津古御館ないし禰津(祢津)城(現・長野県東御市)で、古くから武勇の家柄として名を馳せ、保元・平治の乱や源平合戦での活躍が伝わります。
南北朝期には南朝方にくみしたとされ、ここでも数々の戦功が伝わります。
「滋野三家」の結束は堅く、室町期にも小県郡、佐久郡、更級郡、上野国吾妻郡にまで及ぶ勢力を有していたとみられます。
天文十年(1541年)春、甲斐の武田信虎公が村上義清、諏訪頼重と謀り小県郡へ侵攻(海野平の戦い)。
滋野一族は手痛い敗北を被りましたが、禰津元直は諏訪神氏の姻戚であったことから本領を安堵されています。
禰津元直は天文十一年(1543年)正式に武田氏に臣従、同年末には元直の娘・禰津御寮人が晴信(信玄)公に嫁ぎ、武田信清をもうけています。(『高白斎記』)
元直ののち禰津氏家督は紆余曲折を経て、次男の政直(松鴎軒常安)が継ぎ、常安は武田氏の先方衆として真田氏など滋野一族と連携して上野国方面に進出しました。
常安は北信濃の飯山城の城代も任されていたため、天正十年(1582年)春の織田・徳川連合軍の甲州征伐でも命を落とさず、徳川家康公に臣従。
常安は徳川家家臣となった際に「禰津」から「根津」に名字をかえたとされます。
家康公の関東移封後、上野国豊岡に5千石の所領を得、これを継いだ常安の甥、信政は慶長七年(1602年)5千石の加増を受け、一万石の大名として上野豊岡藩を立藩しました。
しかし寛永三年(1626年)、三代藩主・吉直が若くして死去すると無嗣断絶となり、上野豊岡藩は惜しくも廃藩となりました。
禰津(根津)氏はふるくから鷹匠の家柄として知られていたため、廃藩後根津一族は幕臣となり、鷹匠元締めをつとめたと伝わります。
上野豊岡陣屋跡は、現在の常安寺付近と伝わります。
常安寺の公式Webによると、当寺は祢津(根津)常安が生前に自らの供養のため元亀元年(1570年)に豊岡陣屋内に箕郷の金龍寺二世大雲吟撮大和尚を開山として開基。
みずからの名から常安寺と号したといいます。
常安(禰津公)の墓所は長野県東御市の定律院とされますが、常安寺にも墓石が残ります。


【写真 上(左)】 公道まで延びる参道
【写真 下(右)】 山門
倉渕方面からの烏川と、碓井から流れ下る碓井川が合流し、中山道と三国街道が分岐する地勢的な要衝で、そんなこともあって豊岡陣屋が置かれたものと思われます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 本堂
山門は明治中期の火災を免れた唯一の遺構で、切妻屋根桟瓦葺の四脚門。
妻側にかかる唐破風風のやわらかな曲線が個性的で見上げに山号の扁額。


【写真 上(左)】 庭園からの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は入母屋造桟葺流れ向拝で、大がかりな軒唐破風を構えています。
水引虹梁両端に禅宗様の木鼻、中備に板蟇股。水引虹梁斗栱は左右各二連で複雑な意匠。
身舎側に海老虹梁、向拝見上げに院号扁額を掲げています。
大棟や唐破風まわりに掲げられた紋は、おそらく禰津氏の家紋「丸に月の字」と思われます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 本堂向拝唐破風
本堂向かって右に地蔵菩薩坐像、左には阿弥陀如来坐像が御座し、おのおの献花がそえられて華やぎのある堂前です。
閻魔様とゆかりのふかい寺院で、本堂内には閻魔大王像、山内には奪衣婆像も奉安されています。
こちらは札所ではなく、これまでノーマーク。ウクライナ難民支援御朱印関連で参拝しましたが、ウクライナ支援御朱印のほかに御本尊の御朱印も拝受できました。
ただし、書置のご用意はない模様で、ご住職ご不在時には拝受できないかもしれません。
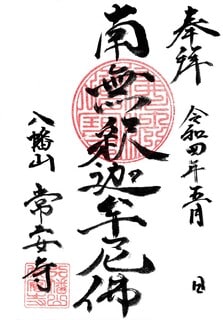
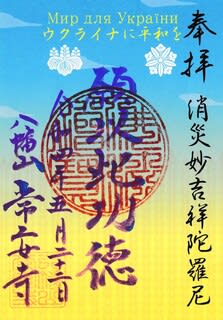
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 ウクライナ難民支援御朱印(期間限定)
※尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。
これで「伊香保温泉周辺の御朱印」はひとまず完結ですが、エリア内で御朱印を拝受した場合は適宜追加していきます。
→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)へ
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)
■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)
■ 御朱印情報の関連記事
【 BGM 】
■ 茜色の約束 - 森恵
■ Mirai 未来 - Kalafina
■ This Love - Angela Aki
■ 日本代表史上最高のゴール
↑ これは凄い!
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第23番 日金山 東光寺(とうこうじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市観光ガイド
熱海市伊豆山968
真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)番外、駿豆両国横道三十三観音霊場番外
授与所:第24番般若院にて授与


第23番の日金山 東光寺からは東伊豆に入ります。
伊豆山は古来からの神仏混淆の霊地で、こちらにあるふたつの札所(第23番日金山 東光寺、第24番走湯山 般若院)は、いずれもただならぬ縁起由緒をもたれます。
膨大な情報がありしかも錯綜気味なので、主に山内掲示、『豆州志稿』『走湯山縁起』にもとづきまとめてみます。
なお、この両札所は令和3年7月伊豆山土砂災害の被災地に近く、以前と状況が変わっているかもしれません。
応神天皇二年(271年)、伊豆山の浜辺(大磯町唐ヶ浜とも)に、光りを放つ不思議な円鏡が現れて波間を飛び交い、やがて西の峰に飛んでいきました。それはさながら日輪のようで、西の峰は火を吹き上たように見えたので「日が峰」と呼ばれ、いつしか「日金山」と呼ぶようになりました。
応神天皇四年(273年)、松葉仙人(勧請仙人)がこの不思議な鏡を崇め奉り、社殿を造立して祀ったのが開山と伝わります。
現地掲示『伊豆開山の三仙人』によると、仁徳天皇七十一年(383年)巨樹の空洞から蘭脱仙人(木生仙人)が出現され災害や疫病を鎮めて霊験をあらわし伊豆辺路(伊豆半島一周の修行路)を開かれました。
敏達天皇四年(575年)、大地震とともに金地仙人が出現され、高麗伝来の国書を読み解かれたといいます。
三仙人の廟所とされる石塔は、文化十年(1813年)頃、般若院別当・周道によって造成されたと伝わり、東光寺の奥に祀られています。
同掲示には「仙人開山の伝承は、仏教公伝(538年説が有力とされる)以前から伊豆山が神仙の鎮まる霊場であったことを主張しているのであろう。」と記されています。
同掲示によると、平安時代、初めて富士登山に成功(富士禅定)し富士修験の開祖とされる末代上人(1103年-)は走湯山の出身で、伊豆・箱根二所権現をも草創され、焔熱で地獄の様相を示していた熱海の衆生を救うため、日金山に地蔵菩薩を安置したとあります。
末代上人が開いた富士登山道は村山口と呼ばれ、末代上人は没後村山浅間社の境内に大棟梁権現として祀られるとともに、村山の地は代々走湯山領として存続したとされ、走湯山と富士山のつながりがうかがわれます。
『走湯権現当峰辺路本縁起集』でも、伊豆山と富士山を両界曼荼羅の入口と出口に位置づけており、往古より両山一体の修験道場と考えられていたという説があります。
また、推古天皇の世(594年)、「走湯権現」の神号を賜り、承和三年(836年)には甲斐國の僧、賢安が日金山本宮から神霊を現在の伊豆山神社のある地に遷したといわれています。(走湯山縁起云云)
源頼朝公の尊崇篤く、御本尊の延命地蔵菩薩像は頼朝公の建立によるとされます。
(頼朝公は、走湯権現、箱根権現を篤く尊崇し、鎌倉将軍家としても奉幣しました(二所奉幣)。)
さて、『豆州志稿』です。
「伊豆山村日金山 今称日金地蔵堂 往昔延喜式内火牟須比命神社(今伊豆山神社)鎮座ノ地也 伝云松葉仙人ナル者始テ此ニ奉祠スト寺後ニ其墳墓アリ 地蔵ヲ祀ル」(地蔵ノ銅像ヲ安ス 貞享(1684-1688)中般若院ノ僧聖算造ル所也(略)粟田口東光寺ノ善祐僧此辺ニサマヨヒ歩キテ住ナレシ 舊院ノユカシサニ 假初ノ庵ヲ繕ヒ現在ノ迷妄ヲ果シ将来ノ快楽ヲ願ヒテ此佛像ヲ据置侍リシニヤト 東光ノ寺名同ク寺ヲ建シ事至テ古シト云伝フレハ 此説是トスベシ 其後源頼朝堂宇ホ再建シ寺領ヲ附セリト云 七坊アリ今四坊存ス皆妻帯僧也 新編鎌倉志曰松源寺ハ日金山ト号ス 本尊ハ地蔵也 頼朝卿伊豆ニ配流ノ時伊豆ノ日金ニ祈テ 我世ニ出デナバ必地蔵ヲ勧請セント約セシ故玆ニ移スト 北條盛衰記ニ日金山ノ麓ニテ朝比奈弥太郎鬼ニ遇フ事ヲ記ス 世俗死者ノ霊魂日金地蔵ノ許ニ至ルト云(略)寺前ニ閻王及生死河婆ノ石像アリ古色●スベシ」とあります。
『豆州志稿』には「往昔延喜式内火牟須比命神社(今伊豆山神社)鎮座ノ地也」とあり、東光寺の山内が当初の伊豆山神社御鎮座の地であったことを示しています。
草創については、松葉仙人によるもの、粟田口東光寺ノ善祐僧によるものの二説を伝えています。
また、『豆州志稿』の「伊豆権現」(伊豆山神社)の項には「往古日金峰ニ鎮座スト云 日金は火ガ峰ノ義ニシテ此神鎮座ヨリ起レル称呼ナル可シ 其後山上ヨリ牟須夫(ムスブノ)峰ニ遷ス 牟須夫ノ称ハ神名ノ遺レルナラム 今之ヲ本宮ト云 次ニ現地ニ移シテ新宮ト称ス 然ルニ山上舊址ニ小祠在リシヲ又遷シテ新宮ノ摂社ト為シ雷電権現或ハ若宮ト称ス(略)現今日金峰ノ舊址ニ日金地蔵堂アリ 伊豆山ノ地名モ日金峰移ヨリセルニテ 日金峰ヲ往古伊豆ノ多可禰ト称ス」とあります。
「日金山」を十国峠とみる説もあります。
十国峠と東光寺はアプローチが異なるのでずいぶんと離れているイメージがありますが、じっさいは東光寺から十国峠まではひと登りで、この一帯が「日金山」とされていたものと思われます。
『豆州志稿』の内容を整理すると、「伊豆権現」(伊豆山神社)は往古は日金山に御鎮座で、のちに牟須夫峰(現在の伊豆山神社本宮社)に御遷座され、ここから現・伊豆山神社の社地に「新宮」として遷られたということになります。
源頼朝公との所縁は、公が御本尊の延命地蔵菩薩像を建立されたこと、日金山に出世を祈願され、成就のあかつきには地蔵尊建立の願をかけ、鎌倉松源寺に地蔵尊を勧請されたことなどが伝わります。
松源寺については、『新編鎌倉志』に記載があります。
「松源寺は日金山と号す。銕観音の西、巌窟堂の山の中壇にあり、本尊は地蔵、運慶が作。相伝ふ、頼朝卿、伊豆に配流の時、伊豆日金に祈て、我世に出ば必ず地蔵を勧請せんと約せし故に、こゝに移すと云ふ。」
現在の巌窟不動尊(不動茶屋・鎌倉市雪ノ下/横大路)の東側にあった松源寺は明治初期に廃寺となり、現在松源寺の御本尊であった日金地蔵尊は、横須賀市武の松得山 東漸寺に遷られて、鎌倉二十四地蔵霊場唯一の鎌倉市外の札所となっています。
『こころの旅』には、「鎌倉時代から室町時代にかけて、この寺には七つの子坊があったが、江戸時代には道正坊、源秀坊、箱根坊、相模坊、土沢坊の五坊になり、現在は道正坊だけが残っている。」とあります。
また、『霊場めぐり』によると、昔日、箱根伊豆両権現の参詣が盛んな頃は経由地に当たっていたため殷賑を極めたそうで、箱根伊豆両権現詣と連動した修験系の一大聖地であった可能性があります。
古来、駿豆地方の死者は日金山に登るため、彼岸に日金山に行くと会いたい人の姿を目にすることができるとされ、お彼岸に先祖供養のため登拝するならわしがあります。
また、朝比奈弥太郎が鬼と出会った地という伝説も残り、伊豆屈指のパワスポとして知られています。
-------------------


日金山の成り立ちから考えると、東光寺の表参道は伊豆山や湯河原などからの登山ルートと思われます。
じっさい、日金山中には多くの石仏が遺され、湯河原から登る「石仏ハイキングコース」が設定されています。
また、伊豆山神社から本宮、岩戸山を経て東光寺に至る「岩戸山ハイキングコース」もあります。
車でのアプローチは熱海峠からになりますが、距離は短いもののかなりの悪路で神経を使います。
暗い山道をトラバース気味に抜けて山上の広場に出ると、ここはもう東光寺の山内です。
箱根から伊豆にかけての尾根筋は明るい草原が多いですが、このあたりは木々がうっそうと茂っています。
伊豆有数のパワスポということもあってか、霊気あふれる山内です。
こちらはどうも山内の様子をあれこれレポするようなお寺さまではないような気がします。
公式Webをご参照願います。
なお、御本尊の地蔵菩薩は「銅造延命地蔵菩薩像及脇童子造」として、熱海市の指定文化財となっています。
像高324センチの半跏造で、錫杖、宝珠を持たれ反花蓮華座、輪光輪のおすがたとのこと。
御朱印は通常は無住のようで、第24番般若院で拝受できますが、非巡拝者が御朱印帳に授与いただけるかは不明です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 日金地蔵尊 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

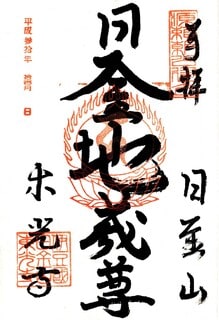
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第24番 走湯山 般若院(はんにゃいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市伊豆山371-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:熱海三弘法大師霊場第3番、熱海六観音霊場第6番
授与所:庫裡


伊豆山にある真言宗の名刹。
伊豆山権現(伊豆山神社)の別当坊であった走湯山 東明寺が前身で、徳川家の厚い崇敬を受け、院号の「般若院」は徳川家康公による命名とされています。
弘法大師との所縁がふかく、大師堂には弘法大師自ら刻まれたとされる等身大の大師像が安置されているそうです。
「明治の神仏分離によって伊豆山神社内から現在地に移った」とされています。
神仏習合の権現社では世俗にかかる対応は別当が担っていた例があり、伊豆山権現にかかわる頼朝公や北条政子の逸話の舞台は、あるいは東明寺(般若院)であったのかもしれません。
「鎌倉殿の13人」で北条政子らが伊豆山(権現)で掃除する場面が出てきましたが、その舞台は東明寺(般若院)あるいはその支坊であった可能性があります。
長瀞の寶登山神社と別当・玉泉寺は神仏習合がよく遺っている例(→ 寶登山神社公式Web)とされ、じっさい参拝してみると、素人目にはどこが神社とお寺の境界か、皆目わからない感じがあります。
往年の伊豆山権現もこのようなかたちであったと思われます。
「権現」とは”仮に示現すること”をあらわし、仏や菩薩が衆生利益のために仮に(権現として)あらわれることをいいます。
『神仏習合の歴史探訪』(川口謙二氏・東京美術刊)によると「神号に権現と付すのは『最勝王経』に『世尊金剛体、権現現於化身』とあることから出たとされている。」とのことで、いわゆる「本地垂迹(ほんちすいじゃく)論」にもとづくものです。
別当は一山(山内の諸寺諸社)の寺務を意味し、のちに神社(権現社)の事(寺)務を職掌する寺院ないしその長官の意になりました。
また、別当(寺)や神宮寺で仏事を行う僧を、社僧、供僧などと呼びました。
よく、神社とお寺の区別で鳥居、狛犬、墓地の有無などがいわれますが、例外はたくさんあります。
もともと江戸時代までは神仏習合があたりまえの考えだったので、その名残りはいくらも遺っているということかと。
〔 関連記事 〕
■ 御朱印帳の使い分け
伊豆山権現の別当実務は東明寺の支院である密厳院が担っていたという説があり、じっさい伊豆山権現関連の文書には「密厳院」の名がよく出てきます。
般若院(東明寺)の草創は定かではありませんが、平安時代に伊豆山権現法学のために建てられた観音堂が草創という説があります。
『吾妻鏡』によると、治承四年(1180年)、頼朝公は挙兵を前に伊豆山権現の覚淵を北条邸に呼び、法華経千回誦ができなくなったことにつき相談しています。
覚淵が創建したのが東明寺の支院、密厳院ともいわれます。
密厳院は天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めで北条方についたため攻められて全山焼亡しましたが、その後東明寺には家康公は高野山の僧快運を招聘して中興開山とし、「般若院」の院号を与え、戦火で荒廃した伊豆山権現の復興にあたったとされます。(『こころの旅』)
『こころの旅』には、「伊豆山権現の御法楽のため、承和三年(836年)僧賢安が千手観音をまつる堂宇を創建したのが始まりと伝えられる。」とあります。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「伊豆山村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 古ハ密厳院東明寺ト云(略)創立年代不詳弘仁(810年-824年)中僧空海此地ニ留錫シ 承和(834-848年)中甲州僧賢安亦来住スト云 今僧桓舜(天喜五年(1057年)寂)ヲ中興開山ト称ス(略)古来伊豆権現(今県社伊豆山神社)ノ別当也 往昔ハ頗大刹ニシテ巨多ノ支坊ヲ有シ(略)三千八百ノ支坊ヲ領シタリト云 僧徒常ニ群衆シタリキ 明治維新ノ初 別当職ヲ解キ同村成就坊ヲ併セテ境内ニ移転ス 従来古義真言宗関東五刹ノ一ト称ス 院内ニ護摩堂清瀧権現祠(主ハ即唐土清瀧寺ノ伽藍神ニシテ空海ノ持来ル所也 祈雨則應アリト云)アリ 又古佛数十躯ヲ蔵ム 供僧十二坊 眞乗。福壽。本地。善満。寶蔵。泉蔵。定蔵。圓蔵。行學。日下。常心。岸坊。ト云 山伏七坊 圓光。西蔵。寶珠。歓喜。常福。定光。圓秀。ト云 承仕四戸倶ニ伊豆権現ニ奉仕ス 明治ノ初皆廃ス 甞テ(かつて)源頼朝及夫人平政子当山二寄寓ス(略)足利尊氏ノ子竹若当院ニ居住ス」
これによると、密厳院は東明寺の支院ではなく、東明寺の院号であった可能性があります。
支坊3,800というものすごい規模感で、徳川家の尊崇を受け「古義真言宗関東五刹ノ一」とされていたことからも、伊豆有数の名刹であったことがうかがわれます。
-------------------


伊豆山の南側の高台にあります。
山門は谷側でここから参道階段を登りますが、駐車場は高台の庫裡横にあります。
ここからは相模湾を間近に見下ろせます。
海とのかかわりふかい伊豆八十八ヶ所霊場ですが、ここまでは中伊豆だったので、ここ第24番ではじめて海を間近に見ることになります。
駐車場のそばに眺めのよい足湯があります。
すぐお隣りにあった、温泉マニアのあいだで「伝説の名湯」として知られる共同浴場「般若院浴場」は2005年4月に閉鎖されてしまいましたが、これと同じ源泉を使っているとみられます。


【写真 上(左)】 足湯
【写真 下(右)】 ありし日の「般若院浴場」
■ 伊豆山温泉 「般若院浴場」の入湯レポ
ちなみに伊豆山温泉は、すばらしい泉質が味わえる伊豆屈指の名湯です。
詳細については、こちら→〔 温泉地巡り 〕 伊豆山温泉をご覧くださいませ。
駐車場から庫裡経由でいくと、堂宇裏をまわりこむかたちで全容がわかりにくいので、一旦道路沿いに山門までくだってここからのお参りをおすすめします。
山門は両側に石標で、右が山号院号標、左が「弘法大師霊場」の石標。
さすがに温泉のメッカ伊豆山。さりげに参道脇に温泉櫓があります。
階段をのぼりきると正面に重厚感あふれる本堂。
入母屋造で大がかりな唐破風向拝、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上に「走湯山」の山号扁額。さすがに名刹らしいたたずまいを見せています。
本堂に安置の「木造伊豆山権現立像」は鎌倉時代の作で伊豆山権現にあったものとされ、国の重要文化財に指定されています。
本堂に相対す鐘楼よこには修行大師像。
本堂向かって左手の高みに大師堂。お大師さま自らが厄除けのため刻まれたとされる等身大のお像が安置されているそうです。
入母屋造流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上には「弘法大師」の扁額が掲げられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)
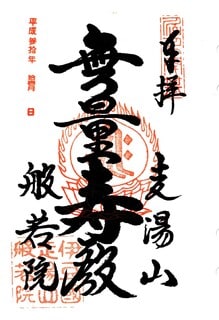

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 伊豆山温泉 「伊豆山浜浴場」の入湯レポ
→ ■ 伊豆山温泉(走り湯) 「偕楽園」の入湯レポ
■ 第25番 護国山 興禅寺(こうぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市桜木町5-8
臨済宗妙心寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:熱海三弘法大師霊場第2番、熱海六観音霊場第2番
授与所:庫裡


熱海市街には御朱印をいただける寺院がけっこうありますが、伊豆八十八ヶ所の札所はこちらだけです。
→ ■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印
境内説明板には「開山は微妙大師藤原藤房卿で暦應四年(1341年)の創建」とあります。
巡拝ガイド類によると、暦應四年(1341年)、藤原藤房卿が祝髪して授翁を名乗られこの地で創建。
御本尊の十一面観世音菩薩は、授翁禅師の護身仏と伝わります。
藤原藤房卿は万里小路藤房ともいい、後醍醐天皇に近侍して討幕計画に参画した公卿です。
江戸時代の儒学者安東省菴が、平重盛・楠木正成とともに日本三忠臣の1人に数えたほど帝に貢献したと伝わります。官位は正二位中納言。
元弘の変で天皇を奉じ笠置山に逃れるも北条方に捕らえられ、元弘二年(1332年)下総国(常陸国藤沢城とも)に流されたといいます。
元弘三年(1333年)、後醍醐帝の建武の新政により京に戻られ、新政権の要職に就いたものの、突如、世を儚んで京の岩倉に隠れたのち出家され、行方知れずとなりました。
天皇の忠臣で、高貴の身でありながら突如出家・行方知れずとなったことから、各地に藤房卿所縁の伝承が残ります。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「海岸山 興禅寺 熱海村 西京妙心寺末 本尊十一面観世音 推妙心寺二世敕謚神光寂照禅師為初祖 禅師即藤原藤房卿也 明治十二年更ニ圓鑑國師ノ号ヲ敕賜ス 妙心寺伝誦ス 従二位藤原藤房卿遁世薙染シ開山國師ノ衣鉢ヲ伝フ 無幾シテ又寺ヲ棄テヽ漫遊シ不知所終ト 興禅寺ニテ相伝フ 授翁ト云僧熱海ニ至リ温泉ニ浴ス 村人其徳ニ懐キ為ニ温泉寺ヲ構造シテ之ニ居ラシム 又興禅寺ヲ創メコレカ祖ト為ル ソレヨリ東ニ赴クト(略)天授授翁宗弼禅師嗣開山 姓藤氏勧修寺大臣家花族也(略)授翁ハ即藤房卿出世ノ号ナル事ヲ 増鑑ニ天皇隠岐ノ島ニ流サレ玉フ時 萬里小路中納言藤房ハ常陸國ヘ遣ハサル 季房宰相モカシラオロシタリシカドナホ 下野國ヘ流サルト按スルニ 季房ハ失ハレ藤房ハ帰リ上ル事ヲ記セリ 弟季房薦福ノ為ナトニ下野ニ下リシニヤ 只憾ラクハ興禅寺今都テ舊記ノ依據スベキナシ 寛永(1624-1645年)中雲居禅師来住ス 之ヲ中興トス 本尊長三寸八分開祖ノ護念佛ナリト云 又雲居ノ自賛ノ画像ヲ蔵ス 梵鐘ハ寛永十年(1633年)藤堂和泉守高次ノ寄附也」
『豆州志稿』は、授翁禅師(藤原藤房卿)が熱海の地で当寺と温泉寺を開創と伝えていますが、「只憾ラクハ興禅寺今都テ舊記ノ依據スベキナシ」と旧記なきことを惜しんでいます。
また、当初の山号は海岸山であったようです。
中世の一時期荒廃しましたが、寛永年間(1624-1645年)雲居禅師が来住されて中興を果たしました。
-------------------


熱海市街南側の高台にあります。
歓楽色のつよい熱海の街並みも、このあたりまでくるとさすがに落ち着きをみせています。
参道階段の上に切妻屋根瓦葺の豪壮な薬医門。門柱右に寺号、左に伊豆八十八ヶ所の札所板、見上げに山号扁額を掲げています。
門扉には下り藤紋が掲げられていますが、こちらは藤房卿ゆかりのものでしょうか。
山門をくぐるとすぐに本堂。
銅板葺。露盤に相輪を立ち上げる宝形造にも思えますが、それにしては桁行きがあり、寄棟造かもしれません。
向拝柱はなく正面鉄扉のうえに扁額を掲げていますが、筆者は不勉強につき解読できません ^^;)
御本尊の十一面観世音菩薩は授翁禅師の護身仏と伝わり、境内掲示には「当寺は創建の因縁により十一面観世音菩薩をおまつりしてあります。」との説明。


本堂向かって右手に諸仏が御座し、「興禅寺南無金剛當り不動尊」は高く迦楼羅炎を背負われ、右手には龍王が巻き付いた倶利伽羅剣を掲げ、盤石に趺坐して御座す迫力のお不動さまです。
諸仏のおくには半僧坊大権現のお堂。堂前の縁起書によると「創立時に遠州奥山方廣寺派大本山の方廣寺の守護神半僧坊大権現の分霊が奉祀されて興禅寺の守護神となり給う鎮座す」とのことです。
枝垂桜で知られる寺院で、以前は天然記念物の金木犀(キンモクセイ)がありましたが枯死してしまい、現在は二代目とのこと。
かつての金木犀の巨木は、花時には花の香りが熱海の沖合を通る船まで届いて灯台の役目を果たしていたという風流な逸話が伝わります。
御朱印は境内左手の庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印は「興禅寺南無金剛當り不動」の印で、いささか変わった様式です。御朱印朱印帳Vers.には半僧坊大権現の羽団扇紋の印も捺されています。
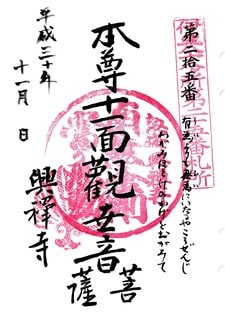
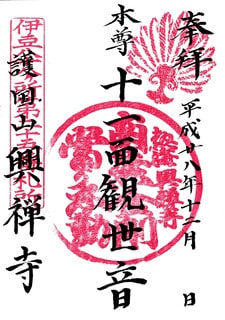
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
熱海温泉の温泉レポはけっこうあります。
→ こちらをご覧くださいませ。
伊豆東海岸に入ると札所間の距離が急に長くなります。
熱海市街を過ぎて稲取までは、伊豆多賀、網代、宇佐美、伊東、川奈・富戸、城ヶ島・対馬、赤沢、大川、北川、熱川、片瀬、白田と名だたる温泉地がつづきますが、この間、伊豆八十八ヶ所の札所はわずか6を数えるのみです。
巡拝途中にはこれらの温泉に泊まることになりますが、札所が少ないので泊数も少なくなり、その少ない宿泊をどの温泉宿にとるかというのも、この霊場の楽しみのひとつです。
(ただし温泉好きがトライした場合、名湯群を横目に先を急ぐので心理的にはかなりきびしいものあり。東伊豆で不用意に立ち寄り湯トラップにはまったりすると、その先の南伊豆で時間切れ必至となるので要注意です(笑))
■ 第26番 根越山 長谷寺(ちょうこくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市網代542
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
鎮守:秋葉山三天坊
他札所:-
授与所:庫裡ないし善修院(熱海市網代490-1)


ひもので有名な網代にある、伊豆の海と所縁のふかい寺院です。
行基上人(668-749年)が網代の浜、屏風ヶ岩で修行されていたとき、浜に漂着した霊木をみつけました。
上人はこの霊木が、大和の長谷観音像を彫した木の末木であることを知り、観音像を彫り、洞窟の中に安置して立ち去られたといいます。
里人たちはこの観音像を年久しく信奉し、この洞窟を”観音窟”と称し、海に働く人々は”観音山”と呼んで崇めていたところ、大永元年(1521年)、善修院開山の大祝和尚がいまの地に移し、地名(根越)を山号とし、長谷寺と号したと伝わります。
この観音像は、奈良・鎌倉の長谷観音とともに「一本三体観音」とされる由緒あるお像です。
古くは真言宗の寺で、堂内には弘法大師のお像が安置され、庭には高さ五尺幅六尺程の石面に、弘法大師の爪彫りという阿弥陀如来の線画があるそうです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「網代村 網代村善修院末 本尊聖観世音 大永(1521-1528年)中、善修院開山大祝創立ス 本寺(善修院)ノ奥ノ院也 本尊観世音ハ元本(網代)村屏風ノ南岩窟ニ在リキ 大祝茲(ここ)ニ移ス 世俗穴観音ト云」
いまは木々がうっそうと茂っていますが、『霊場めぐり』には「根越山の中腹にある南東に開けた谷あいで伊豆の海に面し、目前には初島を始めとし、伊豆大島、伊東の岬、また遠くに房総半島の山を一望する静かな景勝の地である。」と記されています。
その昔、境内に燈明松、立燈松という二本の古松があり、風雨暗夜で陸地がわからないとき、船人たちが御本尊の名号を唱えるとたちまち二本の松に火が上り、船は無事港に入ることができたといいます。
-------------------
山内には石造の観音像群や、熱海俳壇の祖・東海呑吐(無壁庵)の句碑があります。
~ 散る時ははてしれなくて秋の月 ~ 東海吞吐
〔 観世音菩薩像三十三体 修復記念碑 〕
「往時網代の郷は 伊豆の一寒村にて小漁港にすぎず 住民は平和な明け暮れを過ごしていた 江戸は徳川氏の開府により人口が密集し 物資の消費は膨大となり 全国からの舟航により集荷され 網代の港はその寄港地として また避難港としてにぎわい 一時は『京 大阪 江戸 網代』とまで呼称されるに至った 当時 網代に寄港した船舶の船主 船頭等相寄って 本観世音菩薩像三十三体を建立し 海上安全と豊漁とを祈願した しかるに明治以降 文明開化によって帆船は蒸気船に替わり 網代の港もその使命を終え」 いつしか本菩薩像の存在も 時代の推移とともに忘却され 荒廃するに任された ここにおいて 網代漁業株式会社これを惜しみ 往時を懐古するとともに 海上の安全と大漁とを祈念して 本仏像を修復し 記念碑をこの地に建つ」
〔 熱海市指定文化財 彫刻 石像三十三所供養観音像 / 熱海市教育委員会 〕
「この石仏群は、三尊仏・三十三所供養観音(聖・千手・十一面・如意輪・馬頭・准胝観音等)仏像、供養塔等、一揃いの珍しい野仏である。江戸時代に網代が津(港)として栄えた頃 観音信仰をする地元民により建立されたものである。供養塔に「寛政」・「嘉永」の刻銘がある。」
また、山内の少し北側には、江戸城増修築のための石丁場跡があります。
〔 江戸城増修築のための石丁場跡 〕
徳川家康、秀忠、家光の三代にわたる慶長十一年(1606年)より寛永十三年(1636年)にかけて江戸城の大規模な増修築をはかった際、諸国の大名に命じて城郭の分担箇所の工事を督励するとともに、伊豆の国より石材の運搬に当たらせた。石材の採掘は相模の国の真鶴から伊豆の稲取にかけて行われたが、当時大名が義務として提供する石の割当ては、十万石につき100人持ちの石1020玉ずつであったことから九端帆石船3000艘も伊豆と江戸の間を月2回ずつ往復したといわれている。(以下略)
-------------------
東京方面からだと、国道135号、立岩(網代)トンネルを抜けた少し先を鋭角に右折して山内に入ります。寺号標は建っていますが、角度的にブラインドで気づきにくいです。
また、ナビによってはとんでもないルートを案内されるので要注意です。


急坂を登り、さらに急な石段参道を登ると正面に寺号扁額を掲げた山門。複雑な意匠でつくりは不明です。
山門をくぐると視界が広がり、正面に山を背負った本堂、右手には太子堂などの堂宇がならびます。
山内掲示によると、この太子堂は工芸技芸の祖として尊崇される聖徳太子の遺徳を偲び、網代職工組合にて大正12年建立されたものとのこと。


【写真 上(左)】 太子堂
【写真 下(右)】 本堂
曹洞宗寺院ですが、山内は木々が生い茂り、多くの石仏がならんで修験的な雰囲気も感じられます。伊豆にはこの長谷寺のように、もと密寺でのちに禅寺となった寺院が少なくないですが、いずれも独特な雰囲気をまとっています。
本堂はおそらく宝形造とみられ、棟の頂部に露盤、伏鉢、宝珠を置いています。
本瓦葺の重厚な構えで、朱塗りの向拝柱や欄干が意匠的によく効いています。
建物は比較的新しいものと思われますが、木端や中備えの彫刻は古色を帯び、これは旧堂宇からの移設かもしれません。


向拝見上げに寺号扁額。
向拝扉は1度目の参拝では閉扉、2度目は開いていました。開扉時でも御内陣は暗く、詳細をうかがうことはできません。
御朱印は、庫裡にどなたかおられる場合にはこちらで拝受、ご不在の場合はすこし離れた善修院(熱海市網代490-1)での拝受となります。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳(長谷寺庫裡にて拝受)
【写真 下(右)】 御朱印帳(善修院にて拝受)
→ ■ 南熱海網代温泉 「竹林庵みずの」の入湯レポ
→ ■ あじろ温泉「平鶴」の入湯レポ
■ 第27番 稲荷山 東林寺(とうりんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆・伊東観光ガイド
伊東市馬場町2-2-19
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩(阿弥陀三尊とも)
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:葛見神社(伊東市馬場町)
他札所:伊豆二十一ヶ所霊場第17番、伊豆伊東六阿弥陀霊場第2番、伊東温泉七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
ここから伊東市内に入ります。
伊東は寺院メインの伊東温泉七福神が設定されているほど寺院の多いところですが、伊東市内の伊豆八十八ヶ所の札所はわずかに2つしかありません。
こちらは伊東の名族、伊東氏所縁の名刹です。
久安年間(1145-1150年)、真言宗寺院として開かれ久遠寺と号しました。
藤原南家の流れとされる工藤氏は、平安時代から鎌倉時代にかけて東伊豆で勢力を張り、
当初は久須見氏(大見・宇佐見・伊東などからなる久須見荘の領主)を称したともいいますが、のちに伊東氏、河津氏、狩野氏など地名を苗字とするようになりました。
東伊豆における工藤(久須見)氏の流れは諸説あるようですが、これがはっきりしないと東林寺の縁起や『曽我物語』の経緯がわかりません。
いささか長くなりますが整理してみます。
工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸をもうけたことを知った祐親は激怒し千鶴丸を殺害、さらに頼朝公の殺害をも図ったとされます。
このとき、頼朝公の乳母・比企尼と、その三女を妻としていた次男の祐清が危機を頼朝公に知らせ、頼朝公は伊豆山神社に逃げ込んで事なきを得たといいます。
なお、北条時政の正室は伊東祐親の娘で、鎌倉幕府第二代執権・北条義時は祐親の孫にあたるので、鎌倉幕府における伊東祐親の存在はすこぶる大きなものがあったとみられます。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため当寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
治承四年(1180年)頼朝公が挙兵すると、伊東祐親は大庭景親らと協力して石橋山の戦いでこれを撃破しました。
しかし頼朝公が坂東を制圧したのちは追われる身となり、富士川の戦いの後に捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられ、義澄の助命嘆願により命を赦されたものの、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」といい、養和二年(1182年)2月、自害して果てたとされます。
以後、東林寺は伊東家累代の菩提寺となりました。
また、伊東氏の尊崇篤い葛見神社の別当もつとめられていました。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
(なお、平賀氏は清和(河内)源氏義光流の信濃源氏の名族で、源氏御門葉、御家人筆頭として鎌倉幕府草創期に隆盛を誇りました。
この時期の当主は平賀義信とその子惟義で、惟義は一時期近畿6ヶ国の守護を任されましたが、以降は執権北条氏に圧され、惟義の後を継いだ惟信は、承久三年(1221年)の承久の乱で京方に付き平賀氏は没落しました。)
工藤祐経の子・祐時は伊東氏を称し、日向国の伊東氏はその子孫とされています。
天文七年(1538年)に長源寺三世圓芝春徳大和尚が曹洞宗に改宗しています。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「岡村 田方郡中長源寺末 本尊地蔵 大永(1521-1528年)中、善修院開山大祝創立ス 本寺(善修院)ノ奥ノ院也 初久遠寺ト称スト云 相伝フ伊東祐親建ツト 祐親東林院寂心ト称ス法謚ス 祐親寿永二年(1182年)2月15日鎌倉ニ於テ死ヲ賜ル 当村其居住ノ地也(略)圓芝和尚永禄九年(1566年)帰寂今開祖トス コレ必改宗ノ祖也 元真言宗也 曾我勲功記曰 伊東家継ノ後 妻玉江終ニ空クナリニケリ 即菩提寺久遠院ニ送リテ葬禮ノ儀ヲ営ミケル云々ト 当寺ニ日向國伊東家ノ文書数十通 三島旅館ヨリ贈リシ文書ニテ皆同文ナリ 伊東家ハ工藤祐経ノ裔ナリ 祐経ノ子祐時日向地頭職ニ補セラレ 爾後子孫日向ニ住酢ス」。
河津三郎祐泰は当代きっての相撲の名手として知られ、相撲の中興の祖ともされます。
相撲の大ワザ「河津掛け」は祐泰が編み出したものと伝えられ、昭和34年、東林寺にて横綱栃錦の奉納土俵入りがおこなわれています。同年、時津風理事長(元双葉山)の手により除幕された日本相撲協会建立の相撲塚も境内にあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
伊東市街の山寄りに鎮まる旧郷社・葛見神社のさらに奥側にあります。
伊豆半島の温泉地の寺院は路地奥にあるものが多いですが、こちらは比較的開けたところにあり、車でのアクセスも楽です。
伊東氏の菩提寺で、伊東温泉七福神の札所でもあるので観光スポットにもなっている模様。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 布袋尊
山門は切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で、「東林寺」の寺号板と「稲荷山」の扁額。
山内向かって左手に鐘楼、正面に入母屋造桟瓦葺唐破風向拝付きの本堂。
大がかりな唐破風で、鬼板に経の巻獅子口。刻まれた紋は伊東氏の紋としてしられる「庵に木瓜」紋です。
兎の毛通しの拝み懸魚には立体感あふれる天女の彫刻。
水引向拝両端には正面獅子の木鼻、側面に貘ないし像の木鼻。
中備には迫力ある龍の彫刻を置き、向拝上部に「東林禅寺」の寺号扁額が掛かります。
本堂には御本尊のほか、伊東祐親・河津祐泰・曽我兄弟の位牌や伊東祐親の木像、頼朝公と祐親の三女八重姫との間に生まれた千鶴丸の木像を安置しているそうです。
本堂向かって右の一間社流造の祠は伊東七福神の「布袋尊」です。
堂前に樹木は少なく、すっきり開けたイメージのある山内です。
河津三郎の墓、曽我兄弟の供養塔は鐘楼左の参道上にあり、東林寺の向かいの丘の上には伊東祐親の墓所と伝わる五輪塔(伊東市指定文化財)があるそうです。
御朱印は右手の庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 延命地蔵尊


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊東七福神(布袋尊)の御朱印 〕
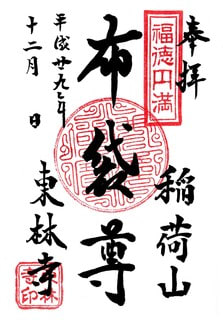
→ ■ 伊東温泉 「いな葉」の入湯レポ
→ ■ 伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」の入湯レポ
■ 第28番 伊雄山 大江院(だいこういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊東市八幡野6-1
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
伊東市南部の八幡野にある曹洞宗寺院です。
草創は真言宗で圓光庵 蓮台寺、俗称を大江庵と号しましたが、天文九年(1540年)、宮上の最勝院十二世台翁宗銀和尚により曹洞宗に改宗し、伊雄山 大江院と号を改めました。
情報の少ない寺院ですが、明治45年の日付が記された「伊豆八十八ヶ所納経帳」が当寺で発見され、「伊豆八十八ヶ所霊場」復興の契機となりました。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「八幡野村 宮上最勝院末 本尊観世音 元真言ナリ 圓光庵蓮臺寺ト称ス 又大江庵トモ云 天文九年(1540年)臺翁和尚ノ時 宗ト号トヲ易フ 元和(1615-1624年)中僧秀天中興ス 寺域ニ清泉有リ 頼朝鬢水ト称ス」
-------------------
伊東の南、大室山の東麓に広がる台地は東伊豆ではめずらしい広がりをもち、「伊豆高原」と呼ばれて別荘地や小規模な宿泊施設、ギャラリーなどが点在しています。
老舗の温泉地でもないのに、なぜか高級宿のメッカという、不思議なエリアでもあります。
八幡野は「伊豆高原」の南端に位置し、北に大室山、南に城ヶ崎海岸をのぞむ立地です。
大室山はふるくから山そのものが御神体と崇められ、城ヶ崎海岸はおよそ4000年前、大室山の噴火で海へ流れ込んだ溶岩が冷え固まって形成されたという断崖絶壁です。
このような壮大な歴史を反映してか、あたりにはどこかスピリチュアルな雰囲気がただよっています。
大江院はパワスポとして知られる旧郷社、八幡宮来宮神社のすぐそばに位置します。
八幡宮来宮神社は延暦年中(782-806年)に八幡宮と来宮神社が合祀されて創建と伝わり、式内社「伊波久良和気命神社」の有力論社に比定されています。


【写真 上(左)】 八幡宮来宮神社の社頭
【写真 下(右)】 八幡宮来宮神社の参道
位置関係からみて大江院は八幡宮来宮神社の別当ではないかと思いましたが、それを示す史料はみつかりませんでした。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道
入口左手に伊豆八十八ヶ所の札所を示す寺号標。
参道両側に六地蔵や石仏群が並び、その先に門柱。さらに進むと左手に山林を背負って本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂はおそらく寄棟造銅板葺。向拝柱はなく禅刹らしい簡素なたたずまい。
屋根端部の照りが効いて、端正な印象の建物です。
向拝正面格子扉のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
御本尊・札所本尊ともに十一面観世音菩薩。
曹洞宗で御本尊が十一面観世音菩薩の寺院は、もと真言宗の例がみられますが、こちらもその一例です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 宇佐美温泉 「宇佐美ヘルスセンター」の入湯レポ
※ 名湯でしたが、残念ながら閉館の情報があります。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4へ。
【 BGM 】
■ おもかげ (produced by Vaundy) / THE FIRST TAKE - milet×Aimer×幾田りら
■ The Days I Spent with You - 今井美樹
■ Memorial Story~夏に背を向けて~Heaven Beach - 杏里
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第23番 日金山 東光寺(とうこうじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市観光ガイド
熱海市伊豆山968
真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)番外、駿豆両国横道三十三観音霊場番外
授与所:第24番般若院にて授与


第23番の日金山 東光寺からは東伊豆に入ります。
伊豆山は古来からの神仏混淆の霊地で、こちらにあるふたつの札所(第23番日金山 東光寺、第24番走湯山 般若院)は、いずれもただならぬ縁起由緒をもたれます。
膨大な情報がありしかも錯綜気味なので、主に山内掲示、『豆州志稿』『走湯山縁起』にもとづきまとめてみます。
なお、この両札所は令和3年7月伊豆山土砂災害の被災地に近く、以前と状況が変わっているかもしれません。
応神天皇二年(271年)、伊豆山の浜辺(大磯町唐ヶ浜とも)に、光りを放つ不思議な円鏡が現れて波間を飛び交い、やがて西の峰に飛んでいきました。それはさながら日輪のようで、西の峰は火を吹き上たように見えたので「日が峰」と呼ばれ、いつしか「日金山」と呼ぶようになりました。
応神天皇四年(273年)、松葉仙人(勧請仙人)がこの不思議な鏡を崇め奉り、社殿を造立して祀ったのが開山と伝わります。
現地掲示『伊豆開山の三仙人』によると、仁徳天皇七十一年(383年)巨樹の空洞から蘭脱仙人(木生仙人)が出現され災害や疫病を鎮めて霊験をあらわし伊豆辺路(伊豆半島一周の修行路)を開かれました。
敏達天皇四年(575年)、大地震とともに金地仙人が出現され、高麗伝来の国書を読み解かれたといいます。
三仙人の廟所とされる石塔は、文化十年(1813年)頃、般若院別当・周道によって造成されたと伝わり、東光寺の奥に祀られています。
同掲示には「仙人開山の伝承は、仏教公伝(538年説が有力とされる)以前から伊豆山が神仙の鎮まる霊場であったことを主張しているのであろう。」と記されています。
同掲示によると、平安時代、初めて富士登山に成功(富士禅定)し富士修験の開祖とされる末代上人(1103年-)は走湯山の出身で、伊豆・箱根二所権現をも草創され、焔熱で地獄の様相を示していた熱海の衆生を救うため、日金山に地蔵菩薩を安置したとあります。
末代上人が開いた富士登山道は村山口と呼ばれ、末代上人は没後村山浅間社の境内に大棟梁権現として祀られるとともに、村山の地は代々走湯山領として存続したとされ、走湯山と富士山のつながりがうかがわれます。
『走湯権現当峰辺路本縁起集』でも、伊豆山と富士山を両界曼荼羅の入口と出口に位置づけており、往古より両山一体の修験道場と考えられていたという説があります。
また、推古天皇の世(594年)、「走湯権現」の神号を賜り、承和三年(836年)には甲斐國の僧、賢安が日金山本宮から神霊を現在の伊豆山神社のある地に遷したといわれています。(走湯山縁起云云)
源頼朝公の尊崇篤く、御本尊の延命地蔵菩薩像は頼朝公の建立によるとされます。
(頼朝公は、走湯権現、箱根権現を篤く尊崇し、鎌倉将軍家としても奉幣しました(二所奉幣)。)
さて、『豆州志稿』です。
「伊豆山村日金山 今称日金地蔵堂 往昔延喜式内火牟須比命神社(今伊豆山神社)鎮座ノ地也 伝云松葉仙人ナル者始テ此ニ奉祠スト寺後ニ其墳墓アリ 地蔵ヲ祀ル」(地蔵ノ銅像ヲ安ス 貞享(1684-1688)中般若院ノ僧聖算造ル所也(略)粟田口東光寺ノ善祐僧此辺ニサマヨヒ歩キテ住ナレシ 舊院ノユカシサニ 假初ノ庵ヲ繕ヒ現在ノ迷妄ヲ果シ将来ノ快楽ヲ願ヒテ此佛像ヲ据置侍リシニヤト 東光ノ寺名同ク寺ヲ建シ事至テ古シト云伝フレハ 此説是トスベシ 其後源頼朝堂宇ホ再建シ寺領ヲ附セリト云 七坊アリ今四坊存ス皆妻帯僧也 新編鎌倉志曰松源寺ハ日金山ト号ス 本尊ハ地蔵也 頼朝卿伊豆ニ配流ノ時伊豆ノ日金ニ祈テ 我世ニ出デナバ必地蔵ヲ勧請セント約セシ故玆ニ移スト 北條盛衰記ニ日金山ノ麓ニテ朝比奈弥太郎鬼ニ遇フ事ヲ記ス 世俗死者ノ霊魂日金地蔵ノ許ニ至ルト云(略)寺前ニ閻王及生死河婆ノ石像アリ古色●スベシ」とあります。
『豆州志稿』には「往昔延喜式内火牟須比命神社(今伊豆山神社)鎮座ノ地也」とあり、東光寺の山内が当初の伊豆山神社御鎮座の地であったことを示しています。
草創については、松葉仙人によるもの、粟田口東光寺ノ善祐僧によるものの二説を伝えています。
また、『豆州志稿』の「伊豆権現」(伊豆山神社)の項には「往古日金峰ニ鎮座スト云 日金は火ガ峰ノ義ニシテ此神鎮座ヨリ起レル称呼ナル可シ 其後山上ヨリ牟須夫(ムスブノ)峰ニ遷ス 牟須夫ノ称ハ神名ノ遺レルナラム 今之ヲ本宮ト云 次ニ現地ニ移シテ新宮ト称ス 然ルニ山上舊址ニ小祠在リシヲ又遷シテ新宮ノ摂社ト為シ雷電権現或ハ若宮ト称ス(略)現今日金峰ノ舊址ニ日金地蔵堂アリ 伊豆山ノ地名モ日金峰移ヨリセルニテ 日金峰ヲ往古伊豆ノ多可禰ト称ス」とあります。
「日金山」を十国峠とみる説もあります。
十国峠と東光寺はアプローチが異なるのでずいぶんと離れているイメージがありますが、じっさいは東光寺から十国峠まではひと登りで、この一帯が「日金山」とされていたものと思われます。
『豆州志稿』の内容を整理すると、「伊豆権現」(伊豆山神社)は往古は日金山に御鎮座で、のちに牟須夫峰(現在の伊豆山神社本宮社)に御遷座され、ここから現・伊豆山神社の社地に「新宮」として遷られたということになります。
源頼朝公との所縁は、公が御本尊の延命地蔵菩薩像を建立されたこと、日金山に出世を祈願され、成就のあかつきには地蔵尊建立の願をかけ、鎌倉松源寺に地蔵尊を勧請されたことなどが伝わります。
松源寺については、『新編鎌倉志』に記載があります。
「松源寺は日金山と号す。銕観音の西、巌窟堂の山の中壇にあり、本尊は地蔵、運慶が作。相伝ふ、頼朝卿、伊豆に配流の時、伊豆日金に祈て、我世に出ば必ず地蔵を勧請せんと約せし故に、こゝに移すと云ふ。」
現在の巌窟不動尊(不動茶屋・鎌倉市雪ノ下/横大路)の東側にあった松源寺は明治初期に廃寺となり、現在松源寺の御本尊であった日金地蔵尊は、横須賀市武の松得山 東漸寺に遷られて、鎌倉二十四地蔵霊場唯一の鎌倉市外の札所となっています。
『こころの旅』には、「鎌倉時代から室町時代にかけて、この寺には七つの子坊があったが、江戸時代には道正坊、源秀坊、箱根坊、相模坊、土沢坊の五坊になり、現在は道正坊だけが残っている。」とあります。
また、『霊場めぐり』によると、昔日、箱根伊豆両権現の参詣が盛んな頃は経由地に当たっていたため殷賑を極めたそうで、箱根伊豆両権現詣と連動した修験系の一大聖地であった可能性があります。
古来、駿豆地方の死者は日金山に登るため、彼岸に日金山に行くと会いたい人の姿を目にすることができるとされ、お彼岸に先祖供養のため登拝するならわしがあります。
また、朝比奈弥太郎が鬼と出会った地という伝説も残り、伊豆屈指のパワスポとして知られています。
-------------------


日金山の成り立ちから考えると、東光寺の表参道は伊豆山や湯河原などからの登山ルートと思われます。
じっさい、日金山中には多くの石仏が遺され、湯河原から登る「石仏ハイキングコース」が設定されています。
また、伊豆山神社から本宮、岩戸山を経て東光寺に至る「岩戸山ハイキングコース」もあります。
車でのアプローチは熱海峠からになりますが、距離は短いもののかなりの悪路で神経を使います。
暗い山道をトラバース気味に抜けて山上の広場に出ると、ここはもう東光寺の山内です。
箱根から伊豆にかけての尾根筋は明るい草原が多いですが、このあたりは木々がうっそうと茂っています。
伊豆有数のパワスポということもあってか、霊気あふれる山内です。
こちらはどうも山内の様子をあれこれレポするようなお寺さまではないような気がします。
公式Webをご参照願います。
なお、御本尊の地蔵菩薩は「銅造延命地蔵菩薩像及脇童子造」として、熱海市の指定文化財となっています。
像高324センチの半跏造で、錫杖、宝珠を持たれ反花蓮華座、輪光輪のおすがたとのこと。
御朱印は通常は無住のようで、第24番般若院で拝受できますが、非巡拝者が御朱印帳に授与いただけるかは不明です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 日金地蔵尊 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

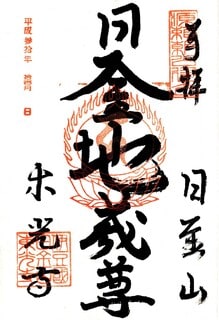
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第24番 走湯山 般若院(はんにゃいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市伊豆山371-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:熱海三弘法大師霊場第3番、熱海六観音霊場第6番
授与所:庫裡


伊豆山にある真言宗の名刹。
伊豆山権現(伊豆山神社)の別当坊であった走湯山 東明寺が前身で、徳川家の厚い崇敬を受け、院号の「般若院」は徳川家康公による命名とされています。
弘法大師との所縁がふかく、大師堂には弘法大師自ら刻まれたとされる等身大の大師像が安置されているそうです。
「明治の神仏分離によって伊豆山神社内から現在地に移った」とされています。
神仏習合の権現社では世俗にかかる対応は別当が担っていた例があり、伊豆山権現にかかわる頼朝公や北条政子の逸話の舞台は、あるいは東明寺(般若院)であったのかもしれません。
「鎌倉殿の13人」で北条政子らが伊豆山(権現)で掃除する場面が出てきましたが、その舞台は東明寺(般若院)あるいはその支坊であった可能性があります。
長瀞の寶登山神社と別当・玉泉寺は神仏習合がよく遺っている例(→ 寶登山神社公式Web)とされ、じっさい参拝してみると、素人目にはどこが神社とお寺の境界か、皆目わからない感じがあります。
往年の伊豆山権現もこのようなかたちであったと思われます。
「権現」とは”仮に示現すること”をあらわし、仏や菩薩が衆生利益のために仮に(権現として)あらわれることをいいます。
『神仏習合の歴史探訪』(川口謙二氏・東京美術刊)によると「神号に権現と付すのは『最勝王経』に『世尊金剛体、権現現於化身』とあることから出たとされている。」とのことで、いわゆる「本地垂迹(ほんちすいじゃく)論」にもとづくものです。
別当は一山(山内の諸寺諸社)の寺務を意味し、のちに神社(権現社)の事(寺)務を職掌する寺院ないしその長官の意になりました。
また、別当(寺)や神宮寺で仏事を行う僧を、社僧、供僧などと呼びました。
よく、神社とお寺の区別で鳥居、狛犬、墓地の有無などがいわれますが、例外はたくさんあります。
もともと江戸時代までは神仏習合があたりまえの考えだったので、その名残りはいくらも遺っているということかと。
〔 関連記事 〕
■ 御朱印帳の使い分け
伊豆山権現の別当実務は東明寺の支院である密厳院が担っていたという説があり、じっさい伊豆山権現関連の文書には「密厳院」の名がよく出てきます。
般若院(東明寺)の草創は定かではありませんが、平安時代に伊豆山権現法学のために建てられた観音堂が草創という説があります。
『吾妻鏡』によると、治承四年(1180年)、頼朝公は挙兵を前に伊豆山権現の覚淵を北条邸に呼び、法華経千回誦ができなくなったことにつき相談しています。
覚淵が創建したのが東明寺の支院、密厳院ともいわれます。
密厳院は天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めで北条方についたため攻められて全山焼亡しましたが、その後東明寺には家康公は高野山の僧快運を招聘して中興開山とし、「般若院」の院号を与え、戦火で荒廃した伊豆山権現の復興にあたったとされます。(『こころの旅』)
『こころの旅』には、「伊豆山権現の御法楽のため、承和三年(836年)僧賢安が千手観音をまつる堂宇を創建したのが始まりと伝えられる。」とあります。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「伊豆山村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 古ハ密厳院東明寺ト云(略)創立年代不詳弘仁(810年-824年)中僧空海此地ニ留錫シ 承和(834-848年)中甲州僧賢安亦来住スト云 今僧桓舜(天喜五年(1057年)寂)ヲ中興開山ト称ス(略)古来伊豆権現(今県社伊豆山神社)ノ別当也 往昔ハ頗大刹ニシテ巨多ノ支坊ヲ有シ(略)三千八百ノ支坊ヲ領シタリト云 僧徒常ニ群衆シタリキ 明治維新ノ初 別当職ヲ解キ同村成就坊ヲ併セテ境内ニ移転ス 従来古義真言宗関東五刹ノ一ト称ス 院内ニ護摩堂清瀧権現祠(主ハ即唐土清瀧寺ノ伽藍神ニシテ空海ノ持来ル所也 祈雨則應アリト云)アリ 又古佛数十躯ヲ蔵ム 供僧十二坊 眞乗。福壽。本地。善満。寶蔵。泉蔵。定蔵。圓蔵。行學。日下。常心。岸坊。ト云 山伏七坊 圓光。西蔵。寶珠。歓喜。常福。定光。圓秀。ト云 承仕四戸倶ニ伊豆権現ニ奉仕ス 明治ノ初皆廃ス 甞テ(かつて)源頼朝及夫人平政子当山二寄寓ス(略)足利尊氏ノ子竹若当院ニ居住ス」
これによると、密厳院は東明寺の支院ではなく、東明寺の院号であった可能性があります。
支坊3,800というものすごい規模感で、徳川家の尊崇を受け「古義真言宗関東五刹ノ一」とされていたことからも、伊豆有数の名刹であったことがうかがわれます。
-------------------


伊豆山の南側の高台にあります。
山門は谷側でここから参道階段を登りますが、駐車場は高台の庫裡横にあります。
ここからは相模湾を間近に見下ろせます。
海とのかかわりふかい伊豆八十八ヶ所霊場ですが、ここまでは中伊豆だったので、ここ第24番ではじめて海を間近に見ることになります。
駐車場のそばに眺めのよい足湯があります。
すぐお隣りにあった、温泉マニアのあいだで「伝説の名湯」として知られる共同浴場「般若院浴場」は2005年4月に閉鎖されてしまいましたが、これと同じ源泉を使っているとみられます。


【写真 上(左)】 足湯
【写真 下(右)】 ありし日の「般若院浴場」
■ 伊豆山温泉 「般若院浴場」の入湯レポ
ちなみに伊豆山温泉は、すばらしい泉質が味わえる伊豆屈指の名湯です。
詳細については、こちら→〔 温泉地巡り 〕 伊豆山温泉をご覧くださいませ。
駐車場から庫裡経由でいくと、堂宇裏をまわりこむかたちで全容がわかりにくいので、一旦道路沿いに山門までくだってここからのお参りをおすすめします。
山門は両側に石標で、右が山号院号標、左が「弘法大師霊場」の石標。
さすがに温泉のメッカ伊豆山。さりげに参道脇に温泉櫓があります。
階段をのぼりきると正面に重厚感あふれる本堂。
入母屋造で大がかりな唐破風向拝、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上に「走湯山」の山号扁額。さすがに名刹らしいたたずまいを見せています。
本堂に安置の「木造伊豆山権現立像」は鎌倉時代の作で伊豆山権現にあったものとされ、国の重要文化財に指定されています。
本堂に相対す鐘楼よこには修行大師像。
本堂向かって左手の高みに大師堂。お大師さま自らが厄除けのため刻まれたとされる等身大のお像が安置されているそうです。
入母屋造流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
正面桟唐戸の上には「弘法大師」の扁額が掲げられています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)
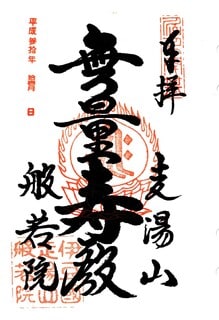

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 伊豆山温泉 「伊豆山浜浴場」の入湯レポ
→ ■ 伊豆山温泉(走り湯) 「偕楽園」の入湯レポ
■ 第25番 護国山 興禅寺(こうぜんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市桜木町5-8
臨済宗妙心寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:熱海三弘法大師霊場第2番、熱海六観音霊場第2番
授与所:庫裡


熱海市街には御朱印をいただける寺院がけっこうありますが、伊豆八十八ヶ所の札所はこちらだけです。
→ ■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印
境内説明板には「開山は微妙大師藤原藤房卿で暦應四年(1341年)の創建」とあります。
巡拝ガイド類によると、暦應四年(1341年)、藤原藤房卿が祝髪して授翁を名乗られこの地で創建。
御本尊の十一面観世音菩薩は、授翁禅師の護身仏と伝わります。
藤原藤房卿は万里小路藤房ともいい、後醍醐天皇に近侍して討幕計画に参画した公卿です。
江戸時代の儒学者安東省菴が、平重盛・楠木正成とともに日本三忠臣の1人に数えたほど帝に貢献したと伝わります。官位は正二位中納言。
元弘の変で天皇を奉じ笠置山に逃れるも北条方に捕らえられ、元弘二年(1332年)下総国(常陸国藤沢城とも)に流されたといいます。
元弘三年(1333年)、後醍醐帝の建武の新政により京に戻られ、新政権の要職に就いたものの、突如、世を儚んで京の岩倉に隠れたのち出家され、行方知れずとなりました。
天皇の忠臣で、高貴の身でありながら突如出家・行方知れずとなったことから、各地に藤房卿所縁の伝承が残ります。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「海岸山 興禅寺 熱海村 西京妙心寺末 本尊十一面観世音 推妙心寺二世敕謚神光寂照禅師為初祖 禅師即藤原藤房卿也 明治十二年更ニ圓鑑國師ノ号ヲ敕賜ス 妙心寺伝誦ス 従二位藤原藤房卿遁世薙染シ開山國師ノ衣鉢ヲ伝フ 無幾シテ又寺ヲ棄テヽ漫遊シ不知所終ト 興禅寺ニテ相伝フ 授翁ト云僧熱海ニ至リ温泉ニ浴ス 村人其徳ニ懐キ為ニ温泉寺ヲ構造シテ之ニ居ラシム 又興禅寺ヲ創メコレカ祖ト為ル ソレヨリ東ニ赴クト(略)天授授翁宗弼禅師嗣開山 姓藤氏勧修寺大臣家花族也(略)授翁ハ即藤房卿出世ノ号ナル事ヲ 増鑑ニ天皇隠岐ノ島ニ流サレ玉フ時 萬里小路中納言藤房ハ常陸國ヘ遣ハサル 季房宰相モカシラオロシタリシカドナホ 下野國ヘ流サルト按スルニ 季房ハ失ハレ藤房ハ帰リ上ル事ヲ記セリ 弟季房薦福ノ為ナトニ下野ニ下リシニヤ 只憾ラクハ興禅寺今都テ舊記ノ依據スベキナシ 寛永(1624-1645年)中雲居禅師来住ス 之ヲ中興トス 本尊長三寸八分開祖ノ護念佛ナリト云 又雲居ノ自賛ノ画像ヲ蔵ス 梵鐘ハ寛永十年(1633年)藤堂和泉守高次ノ寄附也」
『豆州志稿』は、授翁禅師(藤原藤房卿)が熱海の地で当寺と温泉寺を開創と伝えていますが、「只憾ラクハ興禅寺今都テ舊記ノ依據スベキナシ」と旧記なきことを惜しんでいます。
また、当初の山号は海岸山であったようです。
中世の一時期荒廃しましたが、寛永年間(1624-1645年)雲居禅師が来住されて中興を果たしました。
-------------------


熱海市街南側の高台にあります。
歓楽色のつよい熱海の街並みも、このあたりまでくるとさすがに落ち着きをみせています。
参道階段の上に切妻屋根瓦葺の豪壮な薬医門。門柱右に寺号、左に伊豆八十八ヶ所の札所板、見上げに山号扁額を掲げています。
門扉には下り藤紋が掲げられていますが、こちらは藤房卿ゆかりのものでしょうか。
山門をくぐるとすぐに本堂。
銅板葺。露盤に相輪を立ち上げる宝形造にも思えますが、それにしては桁行きがあり、寄棟造かもしれません。
向拝柱はなく正面鉄扉のうえに扁額を掲げていますが、筆者は不勉強につき解読できません ^^;)
御本尊の十一面観世音菩薩は授翁禅師の護身仏と伝わり、境内掲示には「当寺は創建の因縁により十一面観世音菩薩をおまつりしてあります。」との説明。


本堂向かって右手に諸仏が御座し、「興禅寺南無金剛當り不動尊」は高く迦楼羅炎を背負われ、右手には龍王が巻き付いた倶利伽羅剣を掲げ、盤石に趺坐して御座す迫力のお不動さまです。
諸仏のおくには半僧坊大権現のお堂。堂前の縁起書によると「創立時に遠州奥山方廣寺派大本山の方廣寺の守護神半僧坊大権現の分霊が奉祀されて興禅寺の守護神となり給う鎮座す」とのことです。
枝垂桜で知られる寺院で、以前は天然記念物の金木犀(キンモクセイ)がありましたが枯死してしまい、現在は二代目とのこと。
かつての金木犀の巨木は、花時には花の香りが熱海の沖合を通る船まで届いて灯台の役目を果たしていたという風流な逸話が伝わります。
御朱印は境内左手の庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印は「興禅寺南無金剛當り不動」の印で、いささか変わった様式です。御朱印朱印帳Vers.には半僧坊大権現の羽団扇紋の印も捺されています。
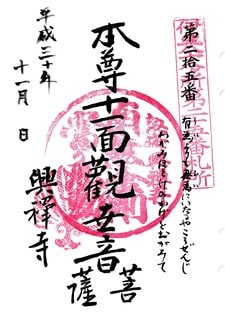
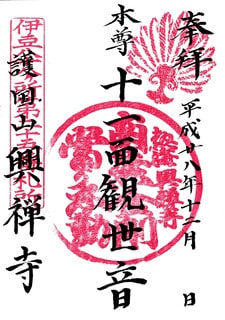
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
熱海温泉の温泉レポはけっこうあります。
→ こちらをご覧くださいませ。
伊豆東海岸に入ると札所間の距離が急に長くなります。
熱海市街を過ぎて稲取までは、伊豆多賀、網代、宇佐美、伊東、川奈・富戸、城ヶ島・対馬、赤沢、大川、北川、熱川、片瀬、白田と名だたる温泉地がつづきますが、この間、伊豆八十八ヶ所の札所はわずか6を数えるのみです。
巡拝途中にはこれらの温泉に泊まることになりますが、札所が少ないので泊数も少なくなり、その少ない宿泊をどの温泉宿にとるかというのも、この霊場の楽しみのひとつです。
(ただし温泉好きがトライした場合、名湯群を横目に先を急ぐので心理的にはかなりきびしいものあり。東伊豆で不用意に立ち寄り湯トラップにはまったりすると、その先の南伊豆で時間切れ必至となるので要注意です(笑))
■ 第26番 根越山 長谷寺(ちょうこくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
熱海市網代542
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
鎮守:秋葉山三天坊
他札所:-
授与所:庫裡ないし善修院(熱海市網代490-1)


ひもので有名な網代にある、伊豆の海と所縁のふかい寺院です。
行基上人(668-749年)が網代の浜、屏風ヶ岩で修行されていたとき、浜に漂着した霊木をみつけました。
上人はこの霊木が、大和の長谷観音像を彫した木の末木であることを知り、観音像を彫り、洞窟の中に安置して立ち去られたといいます。
里人たちはこの観音像を年久しく信奉し、この洞窟を”観音窟”と称し、海に働く人々は”観音山”と呼んで崇めていたところ、大永元年(1521年)、善修院開山の大祝和尚がいまの地に移し、地名(根越)を山号とし、長谷寺と号したと伝わります。
この観音像は、奈良・鎌倉の長谷観音とともに「一本三体観音」とされる由緒あるお像です。
古くは真言宗の寺で、堂内には弘法大師のお像が安置され、庭には高さ五尺幅六尺程の石面に、弘法大師の爪彫りという阿弥陀如来の線画があるそうです。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「網代村 網代村善修院末 本尊聖観世音 大永(1521-1528年)中、善修院開山大祝創立ス 本寺(善修院)ノ奥ノ院也 本尊観世音ハ元本(網代)村屏風ノ南岩窟ニ在リキ 大祝茲(ここ)ニ移ス 世俗穴観音ト云」
いまは木々がうっそうと茂っていますが、『霊場めぐり』には「根越山の中腹にある南東に開けた谷あいで伊豆の海に面し、目前には初島を始めとし、伊豆大島、伊東の岬、また遠くに房総半島の山を一望する静かな景勝の地である。」と記されています。
その昔、境内に燈明松、立燈松という二本の古松があり、風雨暗夜で陸地がわからないとき、船人たちが御本尊の名号を唱えるとたちまち二本の松に火が上り、船は無事港に入ることができたといいます。
-------------------
山内には石造の観音像群や、熱海俳壇の祖・東海呑吐(無壁庵)の句碑があります。
~ 散る時ははてしれなくて秋の月 ~ 東海吞吐
〔 観世音菩薩像三十三体 修復記念碑 〕
「往時網代の郷は 伊豆の一寒村にて小漁港にすぎず 住民は平和な明け暮れを過ごしていた 江戸は徳川氏の開府により人口が密集し 物資の消費は膨大となり 全国からの舟航により集荷され 網代の港はその寄港地として また避難港としてにぎわい 一時は『京 大阪 江戸 網代』とまで呼称されるに至った 当時 網代に寄港した船舶の船主 船頭等相寄って 本観世音菩薩像三十三体を建立し 海上安全と豊漁とを祈願した しかるに明治以降 文明開化によって帆船は蒸気船に替わり 網代の港もその使命を終え」 いつしか本菩薩像の存在も 時代の推移とともに忘却され 荒廃するに任された ここにおいて 網代漁業株式会社これを惜しみ 往時を懐古するとともに 海上の安全と大漁とを祈念して 本仏像を修復し 記念碑をこの地に建つ」
〔 熱海市指定文化財 彫刻 石像三十三所供養観音像 / 熱海市教育委員会 〕
「この石仏群は、三尊仏・三十三所供養観音(聖・千手・十一面・如意輪・馬頭・准胝観音等)仏像、供養塔等、一揃いの珍しい野仏である。江戸時代に網代が津(港)として栄えた頃 観音信仰をする地元民により建立されたものである。供養塔に「寛政」・「嘉永」の刻銘がある。」
また、山内の少し北側には、江戸城増修築のための石丁場跡があります。
〔 江戸城増修築のための石丁場跡 〕
徳川家康、秀忠、家光の三代にわたる慶長十一年(1606年)より寛永十三年(1636年)にかけて江戸城の大規模な増修築をはかった際、諸国の大名に命じて城郭の分担箇所の工事を督励するとともに、伊豆の国より石材の運搬に当たらせた。石材の採掘は相模の国の真鶴から伊豆の稲取にかけて行われたが、当時大名が義務として提供する石の割当ては、十万石につき100人持ちの石1020玉ずつであったことから九端帆石船3000艘も伊豆と江戸の間を月2回ずつ往復したといわれている。(以下略)
-------------------
東京方面からだと、国道135号、立岩(網代)トンネルを抜けた少し先を鋭角に右折して山内に入ります。寺号標は建っていますが、角度的にブラインドで気づきにくいです。
また、ナビによってはとんでもないルートを案内されるので要注意です。


急坂を登り、さらに急な石段参道を登ると正面に寺号扁額を掲げた山門。複雑な意匠でつくりは不明です。
山門をくぐると視界が広がり、正面に山を背負った本堂、右手には太子堂などの堂宇がならびます。
山内掲示によると、この太子堂は工芸技芸の祖として尊崇される聖徳太子の遺徳を偲び、網代職工組合にて大正12年建立されたものとのこと。


【写真 上(左)】 太子堂
【写真 下(右)】 本堂
曹洞宗寺院ですが、山内は木々が生い茂り、多くの石仏がならんで修験的な雰囲気も感じられます。伊豆にはこの長谷寺のように、もと密寺でのちに禅寺となった寺院が少なくないですが、いずれも独特な雰囲気をまとっています。
本堂はおそらく宝形造とみられ、棟の頂部に露盤、伏鉢、宝珠を置いています。
本瓦葺の重厚な構えで、朱塗りの向拝柱や欄干が意匠的によく効いています。
建物は比較的新しいものと思われますが、木端や中備えの彫刻は古色を帯び、これは旧堂宇からの移設かもしれません。


向拝見上げに寺号扁額。
向拝扉は1度目の参拝では閉扉、2度目は開いていました。開扉時でも御内陣は暗く、詳細をうかがうことはできません。
御朱印は、庫裡にどなたかおられる場合にはこちらで拝受、ご不在の場合はすこし離れた善修院(熱海市網代490-1)での拝受となります。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳(長谷寺庫裡にて拝受)
【写真 下(右)】 御朱印帳(善修院にて拝受)
→ ■ 南熱海網代温泉 「竹林庵みずの」の入湯レポ
→ ■ あじろ温泉「平鶴」の入湯レポ
■ 第27番 稲荷山 東林寺(とうりんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆・伊東観光ガイド
伊東市馬場町2-2-19
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩(阿弥陀三尊とも)
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:葛見神社(伊東市馬場町)
他札所:伊豆二十一ヶ所霊場第17番、伊豆伊東六阿弥陀霊場第2番、伊東温泉七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
ここから伊東市内に入ります。
伊東は寺院メインの伊東温泉七福神が設定されているほど寺院の多いところですが、伊東市内の伊豆八十八ヶ所の札所はわずかに2つしかありません。
こちらは伊東の名族、伊東氏所縁の名刹です。
久安年間(1145-1150年)、真言宗寺院として開かれ久遠寺と号しました。
藤原南家の流れとされる工藤氏は、平安時代から鎌倉時代にかけて東伊豆で勢力を張り、
当初は久須見氏(大見・宇佐見・伊東などからなる久須見荘の領主)を称したともいいますが、のちに伊東氏、河津氏、狩野氏など地名を苗字とするようになりました。
東伊豆における工藤(久須見)氏の流れは諸説あるようですが、これがはっきりしないと東林寺の縁起や『曽我物語』の経緯がわかりません。
いささか長くなりますが整理してみます。
工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸をもうけたことを知った祐親は激怒し千鶴丸を殺害、さらに頼朝公の殺害をも図ったとされます。
このとき、頼朝公の乳母・比企尼と、その三女を妻としていた次男の祐清が危機を頼朝公に知らせ、頼朝公は伊豆山神社に逃げ込んで事なきを得たといいます。
なお、北条時政の正室は伊東祐親の娘で、鎌倉幕府第二代執権・北条義時は祐親の孫にあたるので、鎌倉幕府における伊東祐親の存在はすこぶる大きなものがあったとみられます。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため当寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。
治承四年(1180年)頼朝公が挙兵すると、伊東祐親は大庭景親らと協力して石橋山の戦いでこれを撃破しました。
しかし頼朝公が坂東を制圧したのちは追われる身となり、富士川の戦いの後に捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられ、義澄の助命嘆願により命を赦されたものの、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」といい、養和二年(1182年)2月、自害して果てたとされます。
以後、東林寺は伊東家累代の菩提寺となりました。
また、伊東氏の尊崇篤い葛見神社の別当もつとめられていました。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。
(なお、平賀氏は清和(河内)源氏義光流の信濃源氏の名族で、源氏御門葉、御家人筆頭として鎌倉幕府草創期に隆盛を誇りました。
この時期の当主は平賀義信とその子惟義で、惟義は一時期近畿6ヶ国の守護を任されましたが、以降は執権北条氏に圧され、惟義の後を継いだ惟信は、承久三年(1221年)の承久の乱で京方に付き平賀氏は没落しました。)
工藤祐経の子・祐時は伊東氏を称し、日向国の伊東氏はその子孫とされています。
天文七年(1538年)に長源寺三世圓芝春徳大和尚が曹洞宗に改宗しています。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「岡村 田方郡中長源寺末 本尊地蔵 大永(1521-1528年)中、善修院開山大祝創立ス 本寺(善修院)ノ奥ノ院也 初久遠寺ト称スト云 相伝フ伊東祐親建ツト 祐親東林院寂心ト称ス法謚ス 祐親寿永二年(1182年)2月15日鎌倉ニ於テ死ヲ賜ル 当村其居住ノ地也(略)圓芝和尚永禄九年(1566年)帰寂今開祖トス コレ必改宗ノ祖也 元真言宗也 曾我勲功記曰 伊東家継ノ後 妻玉江終ニ空クナリニケリ 即菩提寺久遠院ニ送リテ葬禮ノ儀ヲ営ミケル云々ト 当寺ニ日向國伊東家ノ文書数十通 三島旅館ヨリ贈リシ文書ニテ皆同文ナリ 伊東家ハ工藤祐経ノ裔ナリ 祐経ノ子祐時日向地頭職ニ補セラレ 爾後子孫日向ニ住酢ス」。
河津三郎祐泰は当代きっての相撲の名手として知られ、相撲の中興の祖ともされます。
相撲の大ワザ「河津掛け」は祐泰が編み出したものと伝えられ、昭和34年、東林寺にて横綱栃錦の奉納土俵入りがおこなわれています。同年、時津風理事長(元双葉山)の手により除幕された日本相撲協会建立の相撲塚も境内にあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内
伊東市街の山寄りに鎮まる旧郷社・葛見神社のさらに奥側にあります。
伊豆半島の温泉地の寺院は路地奥にあるものが多いですが、こちらは比較的開けたところにあり、車でのアクセスも楽です。
伊東氏の菩提寺で、伊東温泉七福神の札所でもあるので観光スポットにもなっている模様。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂扁額


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 布袋尊
山門は切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で、「東林寺」の寺号板と「稲荷山」の扁額。
山内向かって左手に鐘楼、正面に入母屋造桟瓦葺唐破風向拝付きの本堂。
大がかりな唐破風で、鬼板に経の巻獅子口。刻まれた紋は伊東氏の紋としてしられる「庵に木瓜」紋です。
兎の毛通しの拝み懸魚には立体感あふれる天女の彫刻。
水引向拝両端には正面獅子の木鼻、側面に貘ないし像の木鼻。
中備には迫力ある龍の彫刻を置き、向拝上部に「東林禅寺」の寺号扁額が掛かります。
本堂には御本尊のほか、伊東祐親・河津祐泰・曽我兄弟の位牌や伊東祐親の木像、頼朝公と祐親の三女八重姫との間に生まれた千鶴丸の木像を安置しているそうです。
本堂向かって右の一間社流造の祠は伊東七福神の「布袋尊」です。
堂前に樹木は少なく、すっきり開けたイメージのある山内です。
河津三郎の墓、曽我兄弟の供養塔は鐘楼左の参道上にあり、東林寺の向かいの丘の上には伊東祐親の墓所と伝わる五輪塔(伊東市指定文化財)があるそうです。
御朱印は右手の庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 延命地蔵尊


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊東七福神(布袋尊)の御朱印 〕
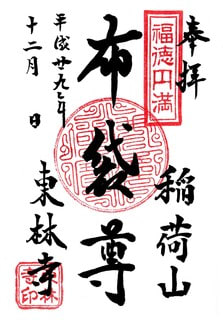
→ ■ 伊東温泉 「いな葉」の入湯レポ
→ ■ 伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」の入湯レポ
■ 第28番 伊雄山 大江院(だいこういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊東市八幡野6-1
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡
伊東市南部の八幡野にある曹洞宗寺院です。
草創は真言宗で圓光庵 蓮台寺、俗称を大江庵と号しましたが、天文九年(1540年)、宮上の最勝院十二世台翁宗銀和尚により曹洞宗に改宗し、伊雄山 大江院と号を改めました。
情報の少ない寺院ですが、明治45年の日付が記された「伊豆八十八ヶ所納経帳」が当寺で発見され、「伊豆八十八ヶ所霊場」復興の契機となりました。
『豆州志稿』には以下のとおりあります。
「八幡野村 宮上最勝院末 本尊観世音 元真言ナリ 圓光庵蓮臺寺ト称ス 又大江庵トモ云 天文九年(1540年)臺翁和尚ノ時 宗ト号トヲ易フ 元和(1615-1624年)中僧秀天中興ス 寺域ニ清泉有リ 頼朝鬢水ト称ス」
-------------------
伊東の南、大室山の東麓に広がる台地は東伊豆ではめずらしい広がりをもち、「伊豆高原」と呼ばれて別荘地や小規模な宿泊施設、ギャラリーなどが点在しています。
老舗の温泉地でもないのに、なぜか高級宿のメッカという、不思議なエリアでもあります。
八幡野は「伊豆高原」の南端に位置し、北に大室山、南に城ヶ崎海岸をのぞむ立地です。
大室山はふるくから山そのものが御神体と崇められ、城ヶ崎海岸はおよそ4000年前、大室山の噴火で海へ流れ込んだ溶岩が冷え固まって形成されたという断崖絶壁です。
このような壮大な歴史を反映してか、あたりにはどこかスピリチュアルな雰囲気がただよっています。
大江院はパワスポとして知られる旧郷社、八幡宮来宮神社のすぐそばに位置します。
八幡宮来宮神社は延暦年中(782-806年)に八幡宮と来宮神社が合祀されて創建と伝わり、式内社「伊波久良和気命神社」の有力論社に比定されています。


【写真 上(左)】 八幡宮来宮神社の社頭
【写真 下(右)】 八幡宮来宮神社の参道
位置関係からみて大江院は八幡宮来宮神社の別当ではないかと思いましたが、それを示す史料はみつかりませんでした。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道
入口左手に伊豆八十八ヶ所の札所を示す寺号標。
参道両側に六地蔵や石仏群が並び、その先に門柱。さらに進むと左手に山林を背負って本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂はおそらく寄棟造銅板葺。向拝柱はなく禅刹らしい簡素なたたずまい。
屋根端部の照りが効いて、端正な印象の建物です。
向拝正面格子扉のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
御本尊・札所本尊ともに十一面観世音菩薩。
曹洞宗で御本尊が十一面観世音菩薩の寺院は、もと真言宗の例がみられますが、こちらもその一例です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 宇佐美温泉 「宇佐美ヘルスセンター」の入湯レポ
※ 名湯でしたが、残念ながら閉館の情報があります。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4へ。
【 BGM 】
■ おもかげ (produced by Vaundy) / THE FIRST TAKE - milet×Aimer×幾田りら
■ The Days I Spent with You - 今井美樹
■ Memorial Story~夏に背を向けて~Heaven Beach - 杏里
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印
字数オーバーにつき、分離しました。
(参考/近接市町)
※中武蔵七十二薬師霊場御開帳関連(2022年4月7日~13日御開帳)の御朱印は後日追加します。
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印
■ 水光山 不動院 大應寺


富士見市水子1765
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:武州路十二支霊場(巳 普賢菩薩)

朱印尊格:本尊 不動明王
主印:種子「カン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:本尊 普賢尊(普賢菩薩)
主印:種子/不詳 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
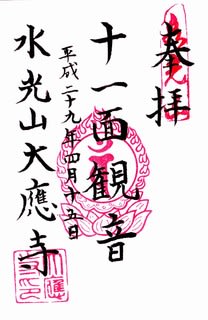
朱印尊格:十一面観音
主印:種子「バン」・金剛界大日如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
※薬師如来の御朱印も拝受できます。
■ 水宮神社


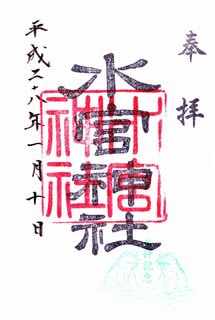
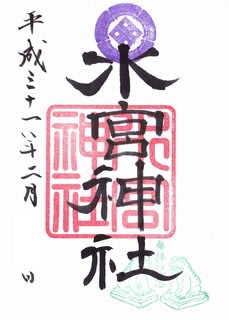
富士見市水子1762
御祭神:天照大神、素戔鳴命、木花開耶姫命、誉田別命、大國主命、罔象女神
元別当:神仏習合/摩訶山般若院
授与所:当社授与所
朱印揮毫:水宮神社(印判書置/直書)
※週末はタイミングにより書入御朱印拝受可の模様
■ (水子)氷川神社


富士見市水子5050
御祭神:素盞嗚尊、奇稲田姫尊
旧社格:旧水子村総鎮守
元別当:福性寺
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:水子 氷川神社 直書(筆書)
■ (北側・上水子ノ)氷川神社

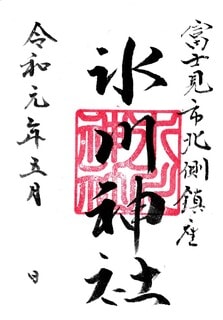
富士見市水子1399
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:旧水子第一区の鎮守
元別当:
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:富士見市北側鎮座 氷川神社 直書(筆書)
■ 智永山 性蓮寺

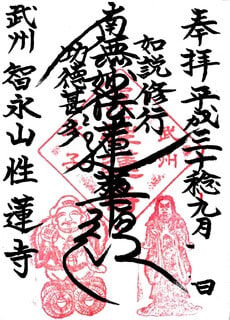
富士見市水子5082
日蓮宗
御首題
■ (針ヶ谷ノ)氷川神社


富士見市針ケ谷1-39-2
御祭神:素盞嗚尊
旧社格:村社、旧針ケ谷村鎮守
元別当:西光院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:針ヶ谷 氷川神社 直書(筆書)
■ (山形)氷川神社


富士見市下南畑153
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:下南畑の旧山形地区鎮守
元別当:西廓山 万蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:山形 氷川神社 直書(筆書)
■ 富士見市下南畑の曹洞宗寺院
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
朱印尊格:聖観世音菩薩 札番:なし 直書(筆書)
※御朱印非掲載
■ 寳瀧山 延命院 瑠璃光寺(鶴馬薬師)


富士見市諏訪1-8-3
天台宗
御本尊:薬師如来
札所:関東九十一薬師霊場第31番
朱印尊格:薬師如来
主印:種子「バイ」・薬師如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東九十一薬師霊場第31番印判
印刷書置
■ 氷川神社

富士見市諏訪1-13-24
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:村社、旧鶴間村上組鎮守
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)、来迎寺、三光院?
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ 諏訪神社

富士見市諏訪2-15-34
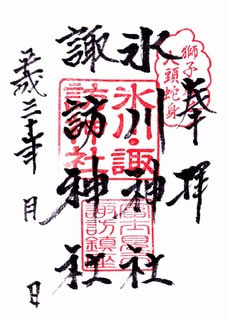
御祭神:建御名方之命
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ (勝瀬)榛名神社


富士見市勝瀬791
御祭神:埴上姫命、豊受姫命
旧社格:村社、勝瀬総鎮守
元別当:萬寶院
授与所:宮司様宅(当社からは離れています)
朱印揮毫:榛名神社(筆書)
■ 見峰山 大願寺


富士見市勝瀬字寺山470-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
朱印尊格:瑞光観音
主印:聖観世音菩薩御影印
札所印:なし
直書(筆書)
■ 三富山 多福寺


三芳町上富1542
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:関東百八地蔵尊霊場第8番
朱印尊格:子育地蔵尊(地蔵菩薩)
主印:三寶印
札所印:なし
印刷(規定)
※御本尊の御朱印は授与なし
■ 慈眼山 喜見院 満福寺


鶴ヶ島市太田ヶ谷487
天台宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所:武蔵国十三仏霊場第5番(地蔵菩薩)

朱印尊格:千手観世音菩薩
主印:種子「キリーク」・千手観音 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:地蔵尊(地蔵菩薩)
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:武蔵国十三仏霊場第5番印判
直書(筆書)
■ (鶴ヶ島)白鬚神社


鶴ヶ島市脚折町6-10-20
御祭神:猿田彦命、武内宿禰命
旧社格:村社 旧脚折七村の総鎮守
元別当:
授与所:境内社務所(授与は不定期の模様)
朱印揮毫:直書(筆書)
・埼玉県中部には白鬚神社が数多く鎮座しますが、こちらもその一社。
奈良時代の創建と伝えられ、この地に居住した高句麗人たちが築いた神社と伝わります。
江戸期頃までは和田、高倉、大六道(上新田)、小六道(中新田)、太田ヶ谷、針うり、脚折の旧脚折七村の総鎮守の総鎮守として重きをなし、旧村社の社格を有します。
境内の宝物殿には十一面観音菩薩立像が収蔵され、かつての神仏習合の名残りがうかがえます。境内の御神木「脚折のケヤキ」は樹齢900年以上とされ、県の指定天然記念物に指定されています。
国の選択無形民俗文化財「脚折雨乞」所縁の神社としても知られています。
▲高徳神社
鶴ヶ島市太田ヶ谷617
旧社格:村社
・規模の大きな神社で、初詣客で賑わっていましたが、御朱印の授与はされていないそうです。
■ 慈眼山 圓通寺


川島町畑中761
信貴山真言宗
御本尊:馬頭観世音菩薩
札所:関東八十八箇所霊場第74番、東国花の寺百ヶ寺霊場第18番

朱印尊格:馬頭尊(馬頭観世音菩薩)
主印:種子「ウン」・馬頭観世音菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東八十八箇所霊場第74番印判
直書(筆書)
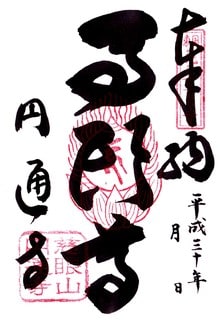
朱印尊格:馬頭尊(馬頭観世音菩薩)
主印:種子「ウン」・馬頭観世音菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:東国花の寺百ヶ寺霊場印判
直書(筆書)
■ 常楽山 養竹院


川島町表9
臨済宗円覚寺派 御本尊:薬師如来
札所:円覚寺百観音霊場第39番

朱印尊格:南無千手観世音(千手観世音菩薩)
主印:三寶印
札所印:円覚寺百観音霊場第39番印判
印判【御朱印帳に捺印】
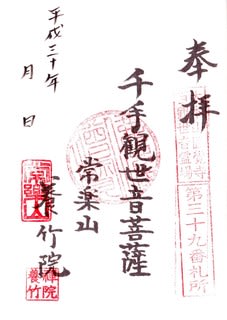
朱印尊格:千手観世音菩薩
主印:三寶印
札所印:円覚寺百観音霊場第39番印判
印判【専用納経帳に捺印】
■ 清月山 元光院 金剛寺


川島町中山1198
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州八十八霊場第55番 ※比企氏菩提寺
朱印尊格:南無阿弥陀如来
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
■ 加限山 潮音寺(正直観音)


川島町正直214
真言宗智山派
御本尊:
札所:比企西国三十三観音第7番
朱印尊格:正直観音
札所印:比企西国三十三観音第7番
直書(筆書)
■ 由城山 福聚院 慈眼寺


坂戸市中小坂285
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:武州八十八霊場第64番
〔 御本尊(武州八十八霊場)の御朱印 〕

朱印尊格:十一面観世音菩薩
主印:種子、梵字および十一面観世音菩薩の御影
札所印:武州札所第六十四番
郵送(筆書)
〔 閻魔様の御朱印 〕

朱印尊格:閻魔大王
主印:種子、梵字および閻魔大王の御影
札所印:武州札所第六十四番
郵送(筆書)
※ご不在でしたが、たいへんご丁寧な郵送対応をいただきました。
(幻の)武州八十八霊場の札所印をいただいたのはこちらが初めてです。
■ 大宮住吉神社


坂戸市塚越254
御祭神:表筒男命、中筒男命、底筒男命、
旧社格:郷社 北武蔵十二郡の総社
授与所:ご神職宅(本殿向かって右手の鳥居の近く)
朱印揮毫:直書(筆書)
■ 東照宮

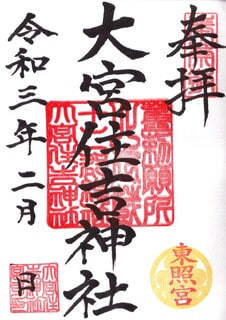
坂戸市塚越254(大宮住吉神社境内)
授与所:ご神職宅(本殿向かって右手の鳥居の近く)
朱印揮毫:直書(筆書)
■ 坂戸神社


坂戸市日の出町7-26
御祭神:白髪武広国押稚日和根子天皇ほか
旧社格:村社、旧坂戸村鎮守
元別当:白髭山 常福寺
授与所:勝呂神社にて拝受(宮司様宅)
朱印揮毫:坂戸神社 直書(筆書)
■ 勝呂神社


坂戸市石井226
御祭神:菊理姫命、伊邪那岐命、伊邪那美命
旧社格:村社、旧石井村鎮守、勝呂郷総鎮守
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:勝呂神社 直書(筆書)
■ 毘廬山 源光院 宗福寺


坂戸市石井1905
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:なし
朱印尊格:南無阿弥陀如来
主印:三寶印
札所印:なし
書置(筆書)
■ 龍護山 實相院 大智寺


坂戸市石井2331
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:武州八十八霊場第29番、中武蔵七十二薬師霊場第23番
朱印尊格:大日如来
主印:三昧耶形の印?
札所印:なし
直書(筆書)
■ 天神山 成就院


坂戸市赤尾1769
曹洞宗
御本尊:
札所:なし
朱印尊格:光輪大黒天
主印:種子「マ」・大黒天 (蓮華座)
札所印:なし
直書(筆書)
■ 長溪山 永源寺


坂戸市仲町12-69
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:なし
朱印尊格:降誕釈尊(釈迦牟尼佛)
主印:三寶印(蓮華座+火焔宝珠型)
札所印:なし
直書(筆書)
■ 坂戸市東部曹洞宗寺院
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:薬師瑠璃光如来 札番:なし 直書(筆書)
○中武蔵七十二薬師霊場札所
※御朱印非掲載
所沢市バージョンもあります。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【BGM】
堤防 - 二名敦子
G
雨のウエンズデイ - 大滝詠一
元気を出して - 竹内まりや
(参考/近接市町)
※中武蔵七十二薬師霊場御開帳関連(2022年4月7日~13日御開帳)の御朱印は後日追加します。
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印
■ 水光山 不動院 大應寺


富士見市水子1765
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:武州路十二支霊場(巳 普賢菩薩)

朱印尊格:本尊 不動明王
主印:種子「カン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:本尊 普賢尊(普賢菩薩)
主印:種子/不詳 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
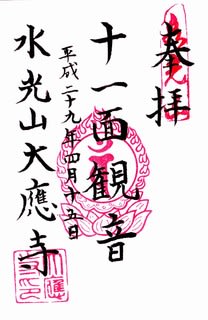
朱印尊格:十一面観音
主印:種子「バン」・金剛界大日如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
※薬師如来の御朱印も拝受できます。
■ 水宮神社


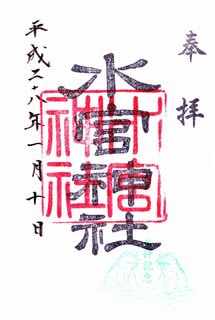
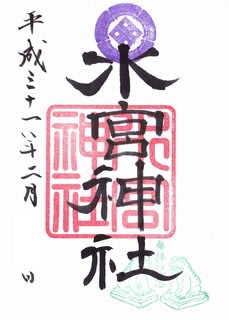
富士見市水子1762
御祭神:天照大神、素戔鳴命、木花開耶姫命、誉田別命、大國主命、罔象女神
元別当:神仏習合/摩訶山般若院
授与所:当社授与所
朱印揮毫:水宮神社(印判書置/直書)
※週末はタイミングにより書入御朱印拝受可の模様
■ (水子)氷川神社


富士見市水子5050
御祭神:素盞嗚尊、奇稲田姫尊
旧社格:旧水子村総鎮守
元別当:福性寺
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:水子 氷川神社 直書(筆書)
■ (北側・上水子ノ)氷川神社

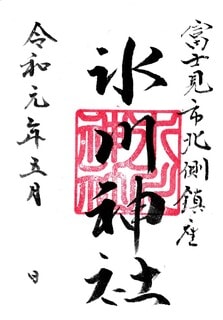
富士見市水子1399
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:旧水子第一区の鎮守
元別当:
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:富士見市北側鎮座 氷川神社 直書(筆書)
■ 智永山 性蓮寺

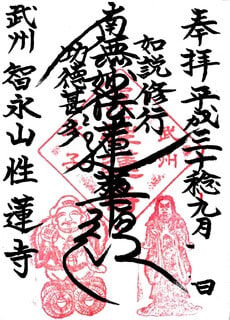
富士見市水子5082
日蓮宗
御首題
■ (針ヶ谷ノ)氷川神社


富士見市針ケ谷1-39-2
御祭神:素盞嗚尊
旧社格:村社、旧針ケ谷村鎮守
元別当:西光院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:針ヶ谷 氷川神社 直書(筆書)
■ (山形)氷川神社


富士見市下南畑153
御祭神:健速素盞嗚命
旧社格:下南畑の旧山形地区鎮守
元別当:西廓山 万蔵院
授与所:水宮神社授与所
朱印揮毫:山形 氷川神社 直書(筆書)
■ 富士見市下南畑の曹洞宗寺院
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
朱印尊格:聖観世音菩薩 札番:なし 直書(筆書)
※御朱印非掲載
■ 寳瀧山 延命院 瑠璃光寺(鶴馬薬師)


富士見市諏訪1-8-3
天台宗
御本尊:薬師如来
札所:関東九十一薬師霊場第31番
朱印尊格:薬師如来
主印:種子「バイ」・薬師如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東九十一薬師霊場第31番印判
印刷書置
■ 氷川神社

富士見市諏訪1-13-24
御祭神:素戔嗚尊
旧社格:村社、旧鶴間村上組鎮守
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)、来迎寺、三光院?
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ 諏訪神社

富士見市諏訪2-15-34
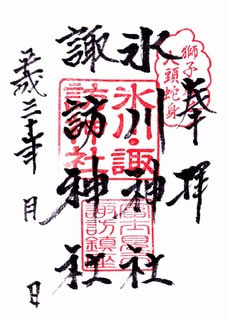
御祭神:建御名方之命
元別当:寳瀧山 瑠璃光寺(富士見市諏訪)
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:氷川神社 諏訪神社 直書(筆書)
■ (勝瀬)榛名神社


富士見市勝瀬791
御祭神:埴上姫命、豊受姫命
旧社格:村社、勝瀬総鎮守
元別当:萬寶院
授与所:宮司様宅(当社からは離れています)
朱印揮毫:榛名神社(筆書)
■ 見峰山 大願寺


富士見市勝瀬字寺山470-2
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
朱印尊格:瑞光観音
主印:聖観世音菩薩御影印
札所印:なし
直書(筆書)
■ 三富山 多福寺


三芳町上富1542
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:関東百八地蔵尊霊場第8番
朱印尊格:子育地蔵尊(地蔵菩薩)
主印:三寶印
札所印:なし
印刷(規定)
※御本尊の御朱印は授与なし
■ 慈眼山 喜見院 満福寺


鶴ヶ島市太田ヶ谷487
天台宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所:武蔵国十三仏霊場第5番(地蔵菩薩)

朱印尊格:千手観世音菩薩
主印:種子「キリーク」・千手観音 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:地蔵尊(地蔵菩薩)
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:武蔵国十三仏霊場第5番印判
直書(筆書)
■ (鶴ヶ島)白鬚神社


鶴ヶ島市脚折町6-10-20
御祭神:猿田彦命、武内宿禰命
旧社格:村社 旧脚折七村の総鎮守
元別当:
授与所:境内社務所(授与は不定期の模様)
朱印揮毫:直書(筆書)
・埼玉県中部には白鬚神社が数多く鎮座しますが、こちらもその一社。
奈良時代の創建と伝えられ、この地に居住した高句麗人たちが築いた神社と伝わります。
江戸期頃までは和田、高倉、大六道(上新田)、小六道(中新田)、太田ヶ谷、針うり、脚折の旧脚折七村の総鎮守の総鎮守として重きをなし、旧村社の社格を有します。
境内の宝物殿には十一面観音菩薩立像が収蔵され、かつての神仏習合の名残りがうかがえます。境内の御神木「脚折のケヤキ」は樹齢900年以上とされ、県の指定天然記念物に指定されています。
国の選択無形民俗文化財「脚折雨乞」所縁の神社としても知られています。
▲高徳神社
鶴ヶ島市太田ヶ谷617
旧社格:村社
・規模の大きな神社で、初詣客で賑わっていましたが、御朱印の授与はされていないそうです。
■ 慈眼山 圓通寺


川島町畑中761
信貴山真言宗
御本尊:馬頭観世音菩薩
札所:関東八十八箇所霊場第74番、東国花の寺百ヶ寺霊場第18番

朱印尊格:馬頭尊(馬頭観世音菩薩)
主印:種子「ウン」・馬頭観世音菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東八十八箇所霊場第74番印判
直書(筆書)
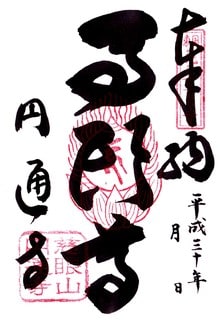
朱印尊格:馬頭尊(馬頭観世音菩薩)
主印:種子「ウン」・馬頭観世音菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:東国花の寺百ヶ寺霊場印判
直書(筆書)
■ 常楽山 養竹院


川島町表9
臨済宗円覚寺派 御本尊:薬師如来
札所:円覚寺百観音霊場第39番

朱印尊格:南無千手観世音(千手観世音菩薩)
主印:三寶印
札所印:円覚寺百観音霊場第39番印判
印判【御朱印帳に捺印】
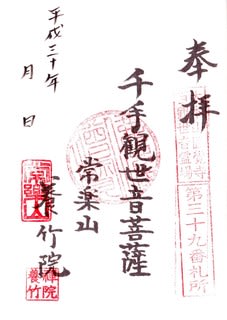
朱印尊格:千手観世音菩薩
主印:三寶印
札所印:円覚寺百観音霊場第39番印判
印判【専用納経帳に捺印】
■ 清月山 元光院 金剛寺


川島町中山1198
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所:武州八十八霊場第55番 ※比企氏菩提寺
朱印尊格:南無阿弥陀如来
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
■ 加限山 潮音寺(正直観音)


川島町正直214
真言宗智山派
御本尊:
札所:比企西国三十三観音第7番
朱印尊格:正直観音
札所印:比企西国三十三観音第7番
直書(筆書)
■ 由城山 福聚院 慈眼寺


坂戸市中小坂285
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:武州八十八霊場第64番
〔 御本尊(武州八十八霊場)の御朱印 〕

朱印尊格:十一面観世音菩薩
主印:種子、梵字および十一面観世音菩薩の御影
札所印:武州札所第六十四番
郵送(筆書)
〔 閻魔様の御朱印 〕

朱印尊格:閻魔大王
主印:種子、梵字および閻魔大王の御影
札所印:武州札所第六十四番
郵送(筆書)
※ご不在でしたが、たいへんご丁寧な郵送対応をいただきました。
(幻の)武州八十八霊場の札所印をいただいたのはこちらが初めてです。
■ 大宮住吉神社


坂戸市塚越254
御祭神:表筒男命、中筒男命、底筒男命、
旧社格:郷社 北武蔵十二郡の総社
授与所:ご神職宅(本殿向かって右手の鳥居の近く)
朱印揮毫:直書(筆書)
■ 東照宮

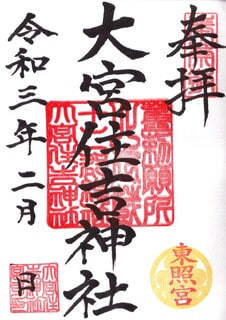
坂戸市塚越254(大宮住吉神社境内)
授与所:ご神職宅(本殿向かって右手の鳥居の近く)
朱印揮毫:直書(筆書)
■ 坂戸神社


坂戸市日の出町7-26
御祭神:白髪武広国押稚日和根子天皇ほか
旧社格:村社、旧坂戸村鎮守
元別当:白髭山 常福寺
授与所:勝呂神社にて拝受(宮司様宅)
朱印揮毫:坂戸神社 直書(筆書)
■ 勝呂神社


坂戸市石井226
御祭神:菊理姫命、伊邪那岐命、伊邪那美命
旧社格:村社、旧石井村鎮守、勝呂郷総鎮守
授与所:宮司様宅
朱印揮毫:勝呂神社 直書(筆書)
■ 毘廬山 源光院 宗福寺


坂戸市石井1905
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:なし
朱印尊格:南無阿弥陀如来
主印:三寶印
札所印:なし
書置(筆書)
■ 龍護山 實相院 大智寺


坂戸市石井2331
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:武州八十八霊場第29番、中武蔵七十二薬師霊場第23番
朱印尊格:大日如来
主印:三昧耶形の印?
札所印:なし
直書(筆書)
■ 天神山 成就院


坂戸市赤尾1769
曹洞宗
御本尊:
札所:なし
朱印尊格:光輪大黒天
主印:種子「マ」・大黒天 (蓮華座)
札所印:なし
直書(筆書)
■ 長溪山 永源寺


坂戸市仲町12-69
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所:なし
朱印尊格:降誕釈尊(釈迦牟尼佛)
主印:三寶印(蓮華座+火焔宝珠型)
札所印:なし
直書(筆書)
■ 坂戸市東部曹洞宗寺院
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
朱印尊格:薬師瑠璃光如来 札番:なし 直書(筆書)
○中武蔵七十二薬師霊場札所
※御朱印非掲載
所沢市バージョンもあります。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【BGM】
堤防 - 二名敦子
G
雨のウエンズデイ - 大滝詠一
元気を出して - 竹内まりや
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
2022/05/03 UP
御朱印を追加し、近接市町のデータを分離しました。
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印
※ 埼玉県所沢市の札所と御朱印もつくりました。
---------------------------------------------
(2021-04-16 )
(2021/04/16 御朱印追加)
(2021/03/13 御朱印追加)
(2021/01/01 御朱印追加)
(2020/02/01 御朱印追加)
埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)からつづく
[周辺エリア]
1.北・東部
■ 山田八幡神社


川越市山田340
御祭神:誉田別尊(応神天皇)、比賣神(玉依日女命)、息長帯姫命(神功皇后)、天津日高穂々出見尊
旧社格:村社、旧府川村と旧志垂村の鎮守
授与所:当社授与所
・日本武尊が東国平定の時に剣を祀ったのが始まりと伝え、昔境内より出土した鉄剣を社宝としている。後醍醐天皇の時に宗長親王が都から逃げ延びて来られ、京の石清水八幡宮を合祀してから八幡様になったと伝えている。当社社家は「原摂津」と称し、摂津より隠棲、志を垂れるとして、地名を『志垂』とした。天長年間(824~834)摂津に大洪水ありし時使者を遣ったとの口碑あり、原家はその頃の移住と考えられる。(社伝・公式Webより)
・兼務社等14社を詣でる「開運十四社詣」を主宰され、14社の御朱印を授与されている。(令和元年7月情報)
・小規模な神社が多く、ナビでは到達不可なところがいくつかありましたので、アクセス情報をつけてあります。(概ねGoogleマップで検索可能)

朱印揮毫:山田八幡神社 書置(筆書)
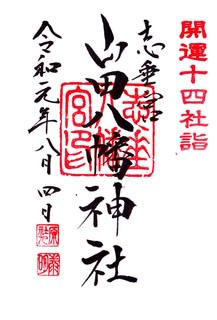
朱印揮毫:山田八幡神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
■ 金鶏神社


川越市山田340
御祭神:天照皇大神、源義家公 ほか
山田八幡神社の境内末社
授与所:山田八幡神社授与所
朱印揮毫:金鶏神社 直書(筆書)
・昭和二年、安岡正篤が都内に創設した金鶏学院に祀られていた社が嵐山町の日本農士学校に遷座された後、縁あって当地に遷座された。とくに学問の神として多くの崇敬を集めている。
■ (北山田)八幡神社


川越市山田225-1
主祭神:誉田別尊
旧社格:村社、旧網代村鎮守
元別当:教學院
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:北山田 八幡神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・当地網代村の村民太郎左衛門が日吉山王権現を勧請、江戸期には山王社と称し網代村の鎮守として祀られていた。(社伝)
・合祀・改号の社歴を有し、登記(社号)は赤城神社が残るとの説あり。(向小久保の八幡神社と宿粒の八幡神社を合祀しているため、八幡神社と号しているとのWeb情報あり。)
■ (福田)赤城神社


川越市福田425-1
主祭神:
旧社格:村社、旧福田村鎮守
元別当:星行院
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:福田 赤城神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・川越市北端の福田地区に、元別当の星行院と並んで鎮座。
・「明治42年、北山田八幡神社(赤城神社)に合祀されることになり、当社社殿は北山田八幡神社(赤城神社)へ移築され、北山田八幡神社(赤城神社)が赤城神社となりました。昭和33年、地元の強い要望により、当地へ還座しています。」とのWeb情報あり。
■ 天王山 清流院 淨國寺


川越市山田420
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第19番
朱印尊格:阿弥陀如来(阿弥陀佛)
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
・鎌倉時代中期の正応二年(1289年)、時宗の遊行二祖である真教上人による開創との寺伝がある古刹。(真教上人による改宗説もあり。) 本山清浄光寺(遊行寺)の直末。
・「夜泣き子育て地蔵尊」は、広く信仰を集めてきたという。
■ (石田)藤宮神社


川越市石田783
主祭神:天児屋根命、藤原鎌足公
元別当:大正寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:石田 藤宮神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ非表示 → 地図
・川越市無形文化財の「筒がゆの神事」や、石田獅子(干しもん獅子)と呼ばれる獅子舞で知られる。奥行きが深く、社叢を背負って神さびた境内。
■ 星光山 新善光寺 一乗院


川越市鴨田716
天台宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:全国善光寺会、関東百八地蔵尊霊場第2番、小江戸川越古寺巡礼第1番
・小仙波の中院の末寺で、鎌倉時代後期の永仁四年(1296年)、喜多院・中院を再興された尊海僧正の創建と伝わる古刹。正式名称は星光山新善光寺一乗法華教院。
・御本尊の阿弥陀如来は、「(善光寺)日本四八体金仏」のひとつとされる秘仏。

朱印尊格:阿彌陀如来
主印:種子「キリーク」・阿弥陀如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
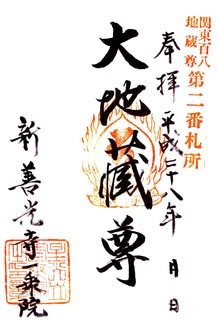
朱印尊格:大地蔵尊(地蔵菩薩)
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東百八地蔵尊霊場第2番印判
直書(筆書)
■ (鴨田)八幡神社


川越市鴨田1072
主祭神:
旧鴨田村鎮守
元別当:一乗院
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:鴨田 八幡神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ名称非表示だが表示ポイントは一致
・長禄二年(1458年)、太田道灌が河越城築城の際、城中鬼門鎮護のために勧請と伝わる。本殿は十八世紀後期の造営と考えられる一間社流造、こけら葺、千鳥破風・軒唐破風付の市指定・建造物。
■ (鹿飼)神明神社


川越市鹿飼404
主祭神:
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:鹿飼 神明神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ名称非表示だが表示ポイントは一致
・鳥居扁額は「神明宮」。由緒書掲示なし。
■ (石田本郷)稲荷神社


川越市石田本郷697-1
主祭神:
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:石田本郷 稲荷神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ非表示 → 地図
・吉野中の西。芳野神社と並んで鎮座。山田八幡神社の祭典奉仕神社。由緒書掲示なし。
■ (本郷新田)天満天神社


川越市石田本郷新田1242
主祭神:菅原道真公
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:本郷新田 天満天神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ非表示 → 地図
・入間川南岸の低地に一段高く鎮座。鳥居扁額は「神明宮」。拝殿扁額に道真公の”飛梅伝説”にまつわる「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」の句。
■ 古谷神社


川越市古谷上3564
主祭神:大己貴命、豊城入彦命、彦狭島命
旧古谷上村邊の鎮守(赤城社)
授与所:古尾谷八幡神社宮司様宅
朱印揮毫:古谷神社 直書(筆書)
・旧古谷上村の開発に際し、上州赤城神社を勧請して創祀の説あり。
■ 古尾谷八幡神社


川越市古谷本郷1408
主祭神:品陀和気命、息長帯姫命、比売神
旧社格:県社、旧古尾谷庄総鎮守
元別当:灌頂院
授与所:当社宮司様宅 →連絡先
朱印揮毫:古尾谷八幡神社 直書(筆書)・宮司様宅にて/神社印は八幡神社社務所にて
・慈覚大師が天長年間に巡錫した際に灌頂院を創建、再訪の際に石清水八幡宮の分霊を祀り、貞観四年(863年)創建と伝わる、旧古尾谷庄の総鎮守。(社記)
・当地の領主であった古尾谷氏にまつわるいくつかの伝承あり。
[周辺エリア]
2.北・西部
■ (今成)熊野神社


川越市今成3-1-3
御祭神:健速須佐之男命、奇稲田比賣命
旧社格:村社、旧今成村鎮守
元別当:安楽寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:今成 熊野神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・永禄年間、北条の家臣川田備前守今成所縁の神社。川田今成が当所に入った際、宿とした蓮馨寺の守護神として祀られていた熊野神社を当地に分霊勧請して創祀したと伝わる。
■ 金縄山 廣巖院 安楽寺


川越市今成3-18-6
天台宗
御本尊:釈迦牟尼如来
札所:関東九十一薬師霊場第30番、小江戸川越古寺巡礼第49番
・奈良時代、行基菩薩の開創と伝わる名刹。行基菩薩所縁の薬師如来は「今成のお薬師様」として広く信仰を集めてきたとされる。

朱印尊格:釋迦牟尼佛
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:薬師如来
主印:三寶印
札所印:関東九十一薬師霊場第30番印判
直書(筆書)
■ (小ヶ谷)白山神社


川越市小ヶ谷156
御祭神:菊理姫命、伊弉諾尊、伊弉冉尊
旧社格:村社、旧小ヶ谷村鎮守
元別当:圓福寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:小ヶ谷 白山神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・古来水害の多かった小ヶ谷に加賀國・越前國の一ノ宮白山神社より白山妙理権現の御神体を分霊して水神として祭祀したのを始めとし、川越城主松平伊豆守信綱が当地周辺の開発に際して入植してきた村民により鎮守として祀られた神社。
■ 瑶光山 真日院 最明寺


川越市小ケ谷61
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東百八地蔵尊霊場第1番、小江戸川越古寺巡礼第13番
・源氏二代将軍源頼家の二男千寿丸が落ち延びて出家し、瑶光房道円と名を改めこの地で草庵を結んだ。鎌倉幕府執政北条相模守平時頼が出家して最明寺入道学了道崇と改名し、諸国行脚の旅に出た際、当地において千寿丸(瑶光房)に参会し、時頼自ら寄付して弘長二年(1262年)に建立・創建し、瑶光房を別当職に任じ、七百石の御朱印地を賜ったとされる名刹。(寺伝より)

朱印尊格:阿弥陀如来
主印:種子「キリーク」・阿弥陀如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
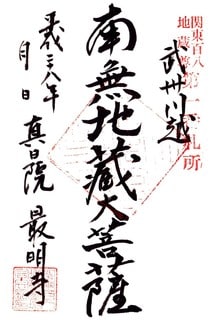
朱印尊格:南無地蔵大菩薩(地蔵菩薩)
主印:三寶印
札所印:関東百八地蔵尊霊場第1番印判
直書(筆書) ※現在この御朱印は授与されておりません。

朱印尊格:南無地蔵大菩薩(地蔵菩薩)
主印:三寶印
札所印:なし
書置(筆書)

朱印尊格:観世音菩薩(聖観世音菩薩)
主印:三寶印
札所印:なし
書置(筆書)
〔 『鬼滅の刃』関連の御朱印 〕
こちらのお寺様と『鬼滅の刃』の関係については、こちらの情報くらいしか入手できていませんが、とにかく『鬼滅の刃』関連の限定御朱印を授与されています。
(2021年1月末までとのこと。→情報元)





『鬼滅の刃』関連の限定御朱印
※ 関東百八地蔵尊霊場第1番および小江戸川越古寺巡礼第13番の御朱印は授与されておりません。
■ 的場山 法城寺


川越市的場1902
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:小江戸川越古寺巡礼第37番
朱印尊格:南無十一面観世音菩薩
主印:三寶印
札所印:小江戸川越古寺巡礼
郵送(筆書/規定用紙?)
・平安時代中期、北条頼平の家臣神山七左右衛門が頼平の菩提を弔うため開基と伝わる古刹。もともと北条寺と称したが、北条をはばかり、宝常寺→法城寺と改めたという。天満宮との関係が深く、当寺の境内に鎮座の天満宮を太田道灌が川越城中に勧請し、現在の三芳野神社につながる流れとされている。
※ご住職はご多忙のようですが、快く郵送にてご対応いただきました。専用用紙らしき大判の用紙で、やはり「小江戸川越古寺巡礼」の専用納経帳は存在するかもしれません。
■ 河越山 三芳野院 常楽寺


川越市上戸194
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第19番
朱印尊格:阿弥陀如来
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
・中世、武蔵の有力な豪族であった河越氏が拠点とした河越館の跡地の一角にある古刹。河越氏館内の仏堂が浄興寺という密寺となり、嘉元三年(1305年)、法印寛慶が遊行三祖智得上人に帰依して時宗に改宗、常楽寺に号を改めたと伝わる。
■ (小室)氷川神社


川越市小室298
御祭神:健速須佐之男命・奇稲田比賣命
旧社格:村社、旧小室村鎮守
元別当:法心寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:小室 氷川神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・長禄元年(1457年)川越築城に際し、水野多宮守重が当所に移住して氷川神社を勧請して創祀と伝わる鎮守社。
■ 尾崎神社

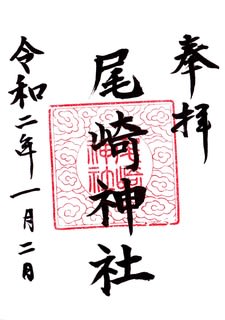
川越市笠幡1280
御祭神:素盞鳴命・奇稲田姫命
旧社格:不明 川越笠幡郷総社
元別当:
授与所:尾崎神社(正月3ヶ日のみ?)
朱印揮毫:直書(筆書)
・「日本武尊東征の折、台地はずれの見晴らしのよい所ゆえ尾崎の宮と称えて二神を祀った」と伝わる(HP「由緒・神社創建」より)歴史のある神社で、緑深い境内には数多くの境内社が鎮座まします。
公式HPによると、「川越笠幡郷総社」とされ、兼務社は14社(大町「鏡神社」、上野「白鬚神社」、吉田「白髭神社」、安比奈「八幡神社」、小堤「八幡神社」、的場上組「八幡神社」、的場下組「八坂神社」、倉ヶ谷戸「箱根神社」、新町「三島日光神社」、下広谷南「白山神社」、小堤後「白山神社」、的場中組「愛宕神社」、上戸「日枝神社」、太田ケ谷・三ツ木・藤金・上広谷・五味ヶ谷「高徳神社」)を数えますが、当社の御朱印授与も限定的なようなので、兼務社の御朱印拝受もむずかしいものとみられます。
■ 萬霊山 法護院 延命寺


川越市笠幡4451
天台宗
御本尊:地蔵菩薩(延命地蔵尊)
札所:武蔵国十三仏霊場第4番(普賢菩薩)、小江戸川越古寺巡礼第3番
・南北朝時代初期の興国年間(1340~1345年)、元二遍公和尚が曹洞宗寺院(興学寺)として創立、慶長年間(1596~1614年)、宗賢法師のとき天台宗に改め、宗賢法師と法縁のあった天海僧正により延命寺の号を賜り、法孫、豪海が住職になったと伝わる古刹。

朱印尊格:延命地蔵尊
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:普賢菩薩
主印:種子「アン」・普賢菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:武蔵国十三仏霊場第4番印判
直書(筆書)
[周辺エリア]
3.南部
■ (藤間)諏訪神社


川越市藤間346
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、藤間地区の産土神
授与所:直書(筆書)・古尾谷八幡神社宮司様宅にて/神社印は諏訪神社社務所にて
朱印揮毫:藤間諏訪神社 直書(筆書)
・「神社史」によると慶長十七年(1612年)の創建とあるが、それ以前から藤間大明神として祀られていたと伝わる当地の産土神。
▲ 寺尾山 蓮乗院 勝福寺

川越市寺尾640
天台宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:小江戸川越古寺巡礼第60番
・Web上では拝受御朱印がみつかりますが、授与されていないそうです。
■ 本宮山 地蔵院 西福寺


川越市南大塚23
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第12番
朱印尊格:南無阿彌陀佛
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
・開山開基は不明だが、寺伝によると寛永十年(1633年)に中興開山という天台宗寺院で、かつては喜多院の末寺であったという。「餅つき踊り」で知られる。
■ (中台)八雲神社


川越市今福2728
御祭神:スサノオノミコト
旧社格:
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:中台 八雲神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・「王蔵流」を称する”中台の祭りばやし”で知られる神社。こんもりと丸い小山の上に鎮座し富士塚を連想させるが、古墳(円墳)とみられている。境内には雷電社も鎮座している。
■ 梅雲山 寛窓寺 明見院


川越市今福677
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:武蔵国十三仏霊場第2番(釈迦如来)、小江戸川越古寺巡礼第41番
・寛文三年(1663年)、髙関和尚により創建されたと伝わる天台宗寺院。文久初年(1861)頃に寺子屋が開かれ、明治まで続いたとされる。

朱印尊格:阿弥陀如来
主印:種子「キリーク」・阿弥陀如来(中央)/種子「サ」・観音菩薩(左脇侍)/種子「サク」・勢至菩薩(右脇侍)の三尊 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:釋迦如来
主印:種子「バク」・釈迦如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:武蔵国十三仏霊場第2番印判
直書(筆書)
■ (中福)稲荷神社

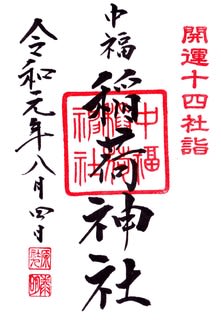
川越市中福2
御祭神:豊受気毘売神、倉稲魂命
旧社格:村社、旧砂久保村鎮守
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:中福 稲荷神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・川越藩主松平伊豆守信綱が新田奉行中沢弥兵衛に命じて当地の開拓に当たらせた際、開拓安全を祈願して城内三芳野天神境内社三芳野稲荷を当地・砂久保村名主尾崎六右衛門邸内に移して創祀。承応三年(1654年)、現鎮座地を社地と定めて起工・遷座して村の鎮守と仰ぎ三芳野稲荷神社と号した。”どんど稲荷”として知られる。(社記)
▲ 鷲嶽山 蓮光寺
川越市渋井248
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第48番
・Web上では拝受御朱印がみつかりますが、いまは授与されていないそうです。
■ 中武蔵七十二薬師霊場御開帳関連の御朱印
2022年4月7日~13日に御開帳された寅薬師の御朱印です。
寅年春の御開帳時のみ授与の可能性があります。
■ 正進庵薬師堂

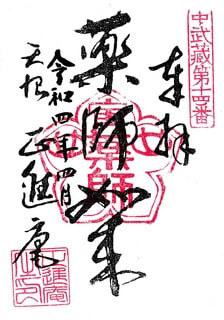
川越市天沼新田144-1
宗派不詳
御本尊:薬師如来
札所:中武蔵七十二薬師霊場第14番
・天沼新田公民館に併設されている寅薬師霊場の札所。旧称は天沼薬師堂。
朱印尊格:薬師如来
主印:寅薬師
札所印:印判
印判紙
■ 観音寺


川越市鯨井1840
宗派不詳
御本尊:薬師如来
札所:中武蔵七十二薬師霊場第15番
・観音寺じたいは廃寺だが、薬師堂は現存。鯨井八坂神社内。
朱印尊格:薬師如来
主印:種子 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:印判
印判
■ 薬樹山 瑠璃光院 永命寺


川越市下小阪688
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:中武蔵七十二薬師霊場第16番、武州八十八霊場第63番、小江戸川越古寺巡礼第51番
・寅薬師霊場では醫王堂(薬師堂)が御開帳。御本尊、不動明王の御朱印も拝受できました。
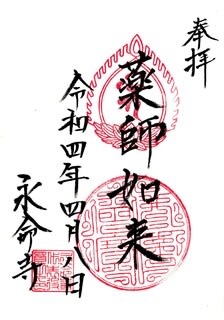
朱印尊格:薬師如来
主印:種子「バイ」・薬師如来 (蓮華座+火焔宝珠)、三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
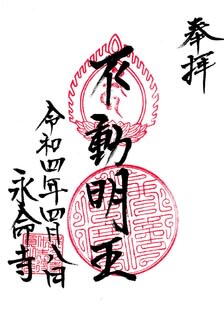
朱印尊格:不動明王
主印:種子「カン/カーン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)、三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
所沢市バージョンもあります。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【BGM】
堤防 - 二名敦子
G
雨のウエンズデイ - 大滝詠一
元気を出して - 竹内まりや
御朱印を追加し、近接市町のデータを分離しました。
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
■ 埼玉県川越市の近接市町の御朱印
※ 埼玉県所沢市の札所と御朱印もつくりました。
---------------------------------------------
(2021-04-16 )
(2021/04/16 御朱印追加)
(2021/03/13 御朱印追加)
(2021/01/01 御朱印追加)
(2020/02/01 御朱印追加)
埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)からつづく
[周辺エリア]
1.北・東部
■ 山田八幡神社


川越市山田340
御祭神:誉田別尊(応神天皇)、比賣神(玉依日女命)、息長帯姫命(神功皇后)、天津日高穂々出見尊
旧社格:村社、旧府川村と旧志垂村の鎮守
授与所:当社授与所
・日本武尊が東国平定の時に剣を祀ったのが始まりと伝え、昔境内より出土した鉄剣を社宝としている。後醍醐天皇の時に宗長親王が都から逃げ延びて来られ、京の石清水八幡宮を合祀してから八幡様になったと伝えている。当社社家は「原摂津」と称し、摂津より隠棲、志を垂れるとして、地名を『志垂』とした。天長年間(824~834)摂津に大洪水ありし時使者を遣ったとの口碑あり、原家はその頃の移住と考えられる。(社伝・公式Webより)
・兼務社等14社を詣でる「開運十四社詣」を主宰され、14社の御朱印を授与されている。(令和元年7月情報)
・小規模な神社が多く、ナビでは到達不可なところがいくつかありましたので、アクセス情報をつけてあります。(概ねGoogleマップで検索可能)

朱印揮毫:山田八幡神社 書置(筆書)
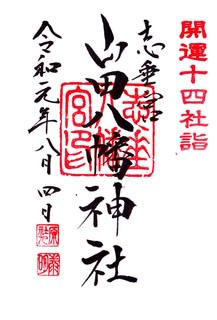
朱印揮毫:山田八幡神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
■ 金鶏神社


川越市山田340
御祭神:天照皇大神、源義家公 ほか
山田八幡神社の境内末社
授与所:山田八幡神社授与所
朱印揮毫:金鶏神社 直書(筆書)
・昭和二年、安岡正篤が都内に創設した金鶏学院に祀られていた社が嵐山町の日本農士学校に遷座された後、縁あって当地に遷座された。とくに学問の神として多くの崇敬を集めている。
■ (北山田)八幡神社


川越市山田225-1
主祭神:誉田別尊
旧社格:村社、旧網代村鎮守
元別当:教學院
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:北山田 八幡神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・当地網代村の村民太郎左衛門が日吉山王権現を勧請、江戸期には山王社と称し網代村の鎮守として祀られていた。(社伝)
・合祀・改号の社歴を有し、登記(社号)は赤城神社が残るとの説あり。(向小久保の八幡神社と宿粒の八幡神社を合祀しているため、八幡神社と号しているとのWeb情報あり。)
■ (福田)赤城神社


川越市福田425-1
主祭神:
旧社格:村社、旧福田村鎮守
元別当:星行院
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:福田 赤城神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・川越市北端の福田地区に、元別当の星行院と並んで鎮座。
・「明治42年、北山田八幡神社(赤城神社)に合祀されることになり、当社社殿は北山田八幡神社(赤城神社)へ移築され、北山田八幡神社(赤城神社)が赤城神社となりました。昭和33年、地元の強い要望により、当地へ還座しています。」とのWeb情報あり。
■ 天王山 清流院 淨國寺


川越市山田420
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第19番
朱印尊格:阿弥陀如来(阿弥陀佛)
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
・鎌倉時代中期の正応二年(1289年)、時宗の遊行二祖である真教上人による開創との寺伝がある古刹。(真教上人による改宗説もあり。) 本山清浄光寺(遊行寺)の直末。
・「夜泣き子育て地蔵尊」は、広く信仰を集めてきたという。
■ (石田)藤宮神社


川越市石田783
主祭神:天児屋根命、藤原鎌足公
元別当:大正寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:石田 藤宮神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ非表示 → 地図
・川越市無形文化財の「筒がゆの神事」や、石田獅子(干しもん獅子)と呼ばれる獅子舞で知られる。奥行きが深く、社叢を背負って神さびた境内。
■ 星光山 新善光寺 一乗院


川越市鴨田716
天台宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:全国善光寺会、関東百八地蔵尊霊場第2番、小江戸川越古寺巡礼第1番
・小仙波の中院の末寺で、鎌倉時代後期の永仁四年(1296年)、喜多院・中院を再興された尊海僧正の創建と伝わる古刹。正式名称は星光山新善光寺一乗法華教院。
・御本尊の阿弥陀如来は、「(善光寺)日本四八体金仏」のひとつとされる秘仏。

朱印尊格:阿彌陀如来
主印:種子「キリーク」・阿弥陀如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)
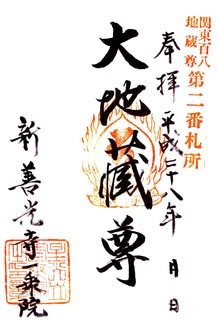
朱印尊格:大地蔵尊(地蔵菩薩)
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:関東百八地蔵尊霊場第2番印判
直書(筆書)
■ (鴨田)八幡神社


川越市鴨田1072
主祭神:
旧鴨田村鎮守
元別当:一乗院
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:鴨田 八幡神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ名称非表示だが表示ポイントは一致
・長禄二年(1458年)、太田道灌が河越城築城の際、城中鬼門鎮護のために勧請と伝わる。本殿は十八世紀後期の造営と考えられる一間社流造、こけら葺、千鳥破風・軒唐破風付の市指定・建造物。
■ (鹿飼)神明神社


川越市鹿飼404
主祭神:
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:鹿飼 神明神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ名称非表示だが表示ポイントは一致
・鳥居扁額は「神明宮」。由緒書掲示なし。
■ (石田本郷)稲荷神社


川越市石田本郷697-1
主祭神:
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:石田本郷 稲荷神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ非表示 → 地図
・吉野中の西。芳野神社と並んで鎮座。山田八幡神社の祭典奉仕神社。由緒書掲示なし。
■ (本郷新田)天満天神社


川越市石田本郷新田1242
主祭神:菅原道真公
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:本郷新田 天満天神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
○Googleマップ非表示 → 地図
・入間川南岸の低地に一段高く鎮座。鳥居扁額は「神明宮」。拝殿扁額に道真公の”飛梅伝説”にまつわる「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」の句。
■ 古谷神社


川越市古谷上3564
主祭神:大己貴命、豊城入彦命、彦狭島命
旧古谷上村邊の鎮守(赤城社)
授与所:古尾谷八幡神社宮司様宅
朱印揮毫:古谷神社 直書(筆書)
・旧古谷上村の開発に際し、上州赤城神社を勧請して創祀の説あり。
■ 古尾谷八幡神社


川越市古谷本郷1408
主祭神:品陀和気命、息長帯姫命、比売神
旧社格:県社、旧古尾谷庄総鎮守
元別当:灌頂院
授与所:当社宮司様宅 →連絡先
朱印揮毫:古尾谷八幡神社 直書(筆書)・宮司様宅にて/神社印は八幡神社社務所にて
・慈覚大師が天長年間に巡錫した際に灌頂院を創建、再訪の際に石清水八幡宮の分霊を祀り、貞観四年(863年)創建と伝わる、旧古尾谷庄の総鎮守。(社記)
・当地の領主であった古尾谷氏にまつわるいくつかの伝承あり。
[周辺エリア]
2.北・西部
■ (今成)熊野神社


川越市今成3-1-3
御祭神:健速須佐之男命、奇稲田比賣命
旧社格:村社、旧今成村鎮守
元別当:安楽寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:今成 熊野神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・永禄年間、北条の家臣川田備前守今成所縁の神社。川田今成が当所に入った際、宿とした蓮馨寺の守護神として祀られていた熊野神社を当地に分霊勧請して創祀したと伝わる。
■ 金縄山 廣巖院 安楽寺


川越市今成3-18-6
天台宗
御本尊:釈迦牟尼如来
札所:関東九十一薬師霊場第30番、小江戸川越古寺巡礼第49番
・奈良時代、行基菩薩の開創と伝わる名刹。行基菩薩所縁の薬師如来は「今成のお薬師様」として広く信仰を集めてきたとされる。

朱印尊格:釋迦牟尼佛
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:薬師如来
主印:三寶印
札所印:関東九十一薬師霊場第30番印判
直書(筆書)
■ (小ヶ谷)白山神社


川越市小ヶ谷156
御祭神:菊理姫命、伊弉諾尊、伊弉冉尊
旧社格:村社、旧小ヶ谷村鎮守
元別当:圓福寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:小ヶ谷 白山神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・古来水害の多かった小ヶ谷に加賀國・越前國の一ノ宮白山神社より白山妙理権現の御神体を分霊して水神として祭祀したのを始めとし、川越城主松平伊豆守信綱が当地周辺の開発に際して入植してきた村民により鎮守として祀られた神社。
■ 瑶光山 真日院 最明寺


川越市小ケ谷61
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:関東百八地蔵尊霊場第1番、小江戸川越古寺巡礼第13番
・源氏二代将軍源頼家の二男千寿丸が落ち延びて出家し、瑶光房道円と名を改めこの地で草庵を結んだ。鎌倉幕府執政北条相模守平時頼が出家して最明寺入道学了道崇と改名し、諸国行脚の旅に出た際、当地において千寿丸(瑶光房)に参会し、時頼自ら寄付して弘長二年(1262年)に建立・創建し、瑶光房を別当職に任じ、七百石の御朱印地を賜ったとされる名刹。(寺伝より)

朱印尊格:阿弥陀如来
主印:種子「キリーク」・阿弥陀如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
書置(筆書)
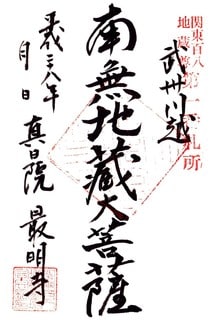
朱印尊格:南無地蔵大菩薩(地蔵菩薩)
主印:三寶印
札所印:関東百八地蔵尊霊場第1番印判
直書(筆書) ※現在この御朱印は授与されておりません。

朱印尊格:南無地蔵大菩薩(地蔵菩薩)
主印:三寶印
札所印:なし
書置(筆書)

朱印尊格:観世音菩薩(聖観世音菩薩)
主印:三寶印
札所印:なし
書置(筆書)
〔 『鬼滅の刃』関連の御朱印 〕
こちらのお寺様と『鬼滅の刃』の関係については、こちらの情報くらいしか入手できていませんが、とにかく『鬼滅の刃』関連の限定御朱印を授与されています。
(2021年1月末までとのこと。→情報元)





『鬼滅の刃』関連の限定御朱印
※ 関東百八地蔵尊霊場第1番および小江戸川越古寺巡礼第13番の御朱印は授与されておりません。
■ 的場山 法城寺


川越市的場1902
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:小江戸川越古寺巡礼第37番
朱印尊格:南無十一面観世音菩薩
主印:三寶印
札所印:小江戸川越古寺巡礼
郵送(筆書/規定用紙?)
・平安時代中期、北条頼平の家臣神山七左右衛門が頼平の菩提を弔うため開基と伝わる古刹。もともと北条寺と称したが、北条をはばかり、宝常寺→法城寺と改めたという。天満宮との関係が深く、当寺の境内に鎮座の天満宮を太田道灌が川越城中に勧請し、現在の三芳野神社につながる流れとされている。
※ご住職はご多忙のようですが、快く郵送にてご対応いただきました。専用用紙らしき大判の用紙で、やはり「小江戸川越古寺巡礼」の専用納経帳は存在するかもしれません。
■ 河越山 三芳野院 常楽寺


川越市上戸194
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第19番
朱印尊格:阿弥陀如来
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
・中世、武蔵の有力な豪族であった河越氏が拠点とした河越館の跡地の一角にある古刹。河越氏館内の仏堂が浄興寺という密寺となり、嘉元三年(1305年)、法印寛慶が遊行三祖智得上人に帰依して時宗に改宗、常楽寺に号を改めたと伝わる。
■ (小室)氷川神社


川越市小室298
御祭神:健速須佐之男命・奇稲田比賣命
旧社格:村社、旧小室村鎮守
元別当:法心寺
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:小室 氷川神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・長禄元年(1457年)川越築城に際し、水野多宮守重が当所に移住して氷川神社を勧請して創祀と伝わる鎮守社。
■ 尾崎神社

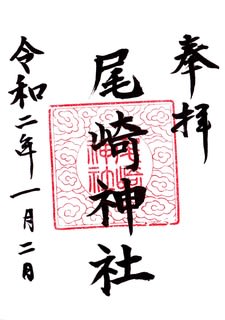
川越市笠幡1280
御祭神:素盞鳴命・奇稲田姫命
旧社格:不明 川越笠幡郷総社
元別当:
授与所:尾崎神社(正月3ヶ日のみ?)
朱印揮毫:直書(筆書)
・「日本武尊東征の折、台地はずれの見晴らしのよい所ゆえ尾崎の宮と称えて二神を祀った」と伝わる(HP「由緒・神社創建」より)歴史のある神社で、緑深い境内には数多くの境内社が鎮座まします。
公式HPによると、「川越笠幡郷総社」とされ、兼務社は14社(大町「鏡神社」、上野「白鬚神社」、吉田「白髭神社」、安比奈「八幡神社」、小堤「八幡神社」、的場上組「八幡神社」、的場下組「八坂神社」、倉ヶ谷戸「箱根神社」、新町「三島日光神社」、下広谷南「白山神社」、小堤後「白山神社」、的場中組「愛宕神社」、上戸「日枝神社」、太田ケ谷・三ツ木・藤金・上広谷・五味ヶ谷「高徳神社」)を数えますが、当社の御朱印授与も限定的なようなので、兼務社の御朱印拝受もむずかしいものとみられます。
■ 萬霊山 法護院 延命寺


川越市笠幡4451
天台宗
御本尊:地蔵菩薩(延命地蔵尊)
札所:武蔵国十三仏霊場第4番(普賢菩薩)、小江戸川越古寺巡礼第3番
・南北朝時代初期の興国年間(1340~1345年)、元二遍公和尚が曹洞宗寺院(興学寺)として創立、慶長年間(1596~1614年)、宗賢法師のとき天台宗に改め、宗賢法師と法縁のあった天海僧正により延命寺の号を賜り、法孫、豪海が住職になったと伝わる古刹。

朱印尊格:延命地蔵尊
主印:種子「カ」・地蔵菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:普賢菩薩
主印:種子「アン」・普賢菩薩 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:武蔵国十三仏霊場第4番印判
直書(筆書)
[周辺エリア]
3.南部
■ (藤間)諏訪神社


川越市藤間346
御祭神:建御名方命
旧社格:村社、藤間地区の産土神
授与所:直書(筆書)・古尾谷八幡神社宮司様宅にて/神社印は諏訪神社社務所にて
朱印揮毫:藤間諏訪神社 直書(筆書)
・「神社史」によると慶長十七年(1612年)の創建とあるが、それ以前から藤間大明神として祀られていたと伝わる当地の産土神。
▲ 寺尾山 蓮乗院 勝福寺

川越市寺尾640
天台宗
御本尊:阿弥陀三尊
札所:小江戸川越古寺巡礼第60番
・Web上では拝受御朱印がみつかりますが、授与されていないそうです。
■ 本宮山 地蔵院 西福寺


川越市南大塚23
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第12番
朱印尊格:南無阿彌陀佛
主印:三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
・開山開基は不明だが、寺伝によると寛永十年(1633年)に中興開山という天台宗寺院で、かつては喜多院の末寺であったという。「餅つき踊り」で知られる。
■ (中台)八雲神社


川越市今福2728
御祭神:スサノオノミコト
旧社格:
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:中台 八雲神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・「王蔵流」を称する”中台の祭りばやし”で知られる神社。こんもりと丸い小山の上に鎮座し富士塚を連想させるが、古墳(円墳)とみられている。境内には雷電社も鎮座している。
■ 梅雲山 寛窓寺 明見院


川越市今福677
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:武蔵国十三仏霊場第2番(釈迦如来)、小江戸川越古寺巡礼第41番
・寛文三年(1663年)、髙関和尚により創建されたと伝わる天台宗寺院。文久初年(1861)頃に寺子屋が開かれ、明治まで続いたとされる。

朱印尊格:阿弥陀如来
主印:種子「キリーク」・阿弥陀如来(中央)/種子「サ」・観音菩薩(左脇侍)/種子「サク」・勢至菩薩(右脇侍)の三尊 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:なし
直書(筆書)

朱印尊格:釋迦如来
主印:種子「バク」・釈迦如来 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:武蔵国十三仏霊場第2番印判
直書(筆書)
■ (中福)稲荷神社

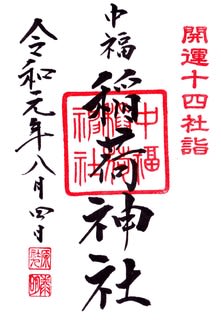
川越市中福2
御祭神:豊受気毘売神、倉稲魂命
旧社格:村社、旧砂久保村鎮守
授与所:山田八幡神社(開運十四社詣)
朱印揮毫:中福 稲荷神社 直書(筆書) ※「開運十四社詣」の印判
・川越藩主松平伊豆守信綱が新田奉行中沢弥兵衛に命じて当地の開拓に当たらせた際、開拓安全を祈願して城内三芳野天神境内社三芳野稲荷を当地・砂久保村名主尾崎六右衛門邸内に移して創祀。承応三年(1654年)、現鎮座地を社地と定めて起工・遷座して村の鎮守と仰ぎ三芳野稲荷神社と号した。”どんど稲荷”として知られる。(社記)
▲ 鷲嶽山 蓮光寺
川越市渋井248
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第48番
・Web上では拝受御朱印がみつかりますが、いまは授与されていないそうです。
■ 中武蔵七十二薬師霊場御開帳関連の御朱印
2022年4月7日~13日に御開帳された寅薬師の御朱印です。
寅年春の御開帳時のみ授与の可能性があります。
■ 正進庵薬師堂

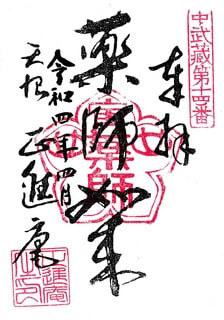
川越市天沼新田144-1
宗派不詳
御本尊:薬師如来
札所:中武蔵七十二薬師霊場第14番
・天沼新田公民館に併設されている寅薬師霊場の札所。旧称は天沼薬師堂。
朱印尊格:薬師如来
主印:寅薬師
札所印:印判
印判紙
■ 観音寺


川越市鯨井1840
宗派不詳
御本尊:薬師如来
札所:中武蔵七十二薬師霊場第15番
・観音寺じたいは廃寺だが、薬師堂は現存。鯨井八坂神社内。
朱印尊格:薬師如来
主印:種子 (蓮華座+火焔宝珠)
札所印:印判
印判
■ 薬樹山 瑠璃光院 永命寺


川越市下小阪688
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:中武蔵七十二薬師霊場第16番、武州八十八霊場第63番、小江戸川越古寺巡礼第51番
・寅薬師霊場では醫王堂(薬師堂)が御開帳。御本尊、不動明王の御朱印も拝受できました。
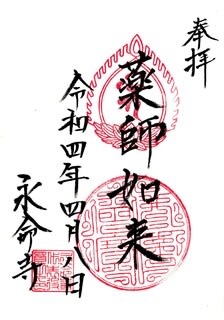
朱印尊格:薬師如来
主印:種子「バイ」・薬師如来 (蓮華座+火焔宝珠)、三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
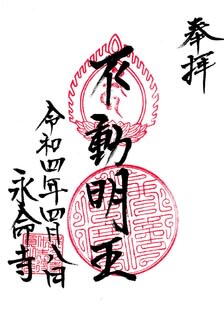
朱印尊格:不動明王
主印:種子「カン/カーン」・不動明王 (蓮華座+火焔宝珠)、三寶印
札所印:なし
直書(筆書)
所沢市バージョンもあります。
【関連ページ】
■ 御朱印帳の使い分け
■ 高幡不動尊の御朱印
■ 塩船観音寺の御朱印
■ 深大寺の御朱印
■ 円覚寺の御朱印(25種)
■ 草津温泉周辺の御朱印
■ 四万温泉周辺の御朱印
■ 伊香保温泉周辺の御朱印
■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印
■ 根岸古寺めぐり
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印
■ 東京都港区の札所と御朱印
■ 東京都渋谷区の札所と御朱印
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印
■ 東京都文京区の札所と御朱印
■ 東京都台東区の札所と御朱印
■ 首都圏の札所と御朱印
■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)
■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)
【BGM】
堤防 - 二名敦子
G
雨のウエンズデイ - 大滝詠一
元気を出して - 竹内まりや
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 2022年のJ-POP-2
■ milet「Walkin' In My Lane」MUSIC VIDEO (フジテレビ系木曜劇場「やんごとなき一族」主題歌 先行配信中)
↑ これもなかなかいいですね。
■ Milet メドレー ヒット曲 2022 - Milet 新曲 人気曲 2022. vol 1
Miletは、メロやアンサンブルの素晴らしさを改めて呼び覚ましてくれたアーティストだと思う。
もっと売れると思ったけどね・・・
■ オリコンデイリーシングルランキング2022年04月28日付
■ オリコン月間アルバムランキング
↑ ため息しか出んわ・・・。
NHKBSプレミアムの『MUST BE UKTV』、このところ毎日聴いています。
で、やっぱりいま聴き返してみても、いちばんメロディ(というかアンサンブル)が輝いていたのは1980年代前半だと思う。
そしてここで完成されたひとつのPOPSの頂点を、じつのところもっともよく引き継いでいるのはJ-POPだと思う。
なにせこの国は、なにものも滅ぼさない国だから・・・。
カノン進行使ったヒット曲をこんなにたくさんもってるのは、日本だけだと思うけどね、いい悪いは別にして。
■ カノン進行を使った曲集 全23曲 繋げて歌ってみた by KAT
J-POP(どっちかというと売れてないやつ)のメロと女性ボーカルの美しさは、いまや世界屈指だと思う。
■ Jason Scheff - Over And Over (Cover ELT)
■ Every Little Thing - Over and Over (1999.01.26)
↑ 往年のAORの名手Jason Scheffでも、1999年の時点では、もはや日本の歌姫に及ばないことがわかる。
■ Butterfly(バタフライ) - 木村カエラ(カバー)
コード
2009年の時点で、こんなメロ(コード進行)創り出せて、しかもヒットするのはもはやひょっとして日本だけでは?
と思った曲。
■ 島津心美 - Dreamin'/ JASMINE
2022年の小学生の歌姫。この子はきっと伸びる。
--------------------------
2022/03/13 UP
さっき、TVKで久しぶりに最新のビルボード聴いてみました。
一時期Silk Sonicが健闘してたので、淡い期待を抱きつつ。
でも、ダメでしたね。ぜんぜん。
8割の曲が同じに聴こえた。情けないほどの金太郎飴チャート。
1980年代にこんな名曲たちを生み出していた米国の音楽シーン。
あれは夢まぼろしだったのか?
それにくらべて、このところの日本の曲、かなりいいとこついてる。
1980年代の再評価も進んでるし、邦楽のYouTubeのコメント欄が、このところ外国語で埋め尽くされてる理由がわかる気がする。
このところ書き散らした最近の曲を中心に、振り返りつつまとめてみました。
■ milet「One Reason」MUSIC VIDEO (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)
この時代に、「歌だけで、音として聴いてもらいたい」、こう言い切れるアーティストが出てくるとは・・・。
これ、ひょっとして6拍子?
■ 緑黄色社会『キャラクター』Official Video / Ryokuoushoku Shakai – Character
まさかこんな新曲が、新型コロナ禍真っ最中のこの状況で聴けるとは・・・
「応援ソング」ちゅう曲調じゃないわな、これ。
いきなりのワウワウ・ギター、カッティングギターにストリングス、つづいてピッキングギターにホンキートンクなピアノ、そして華&色気を帯びたヴォーカル。
ハンドクラップにキメのリズム。
でもって弾みまくるベース、StuffのGordon Edwardsかよ(笑)
まだ4つ打ちっぽさ残してるけど、これで腕利きのドラムス入ったら完璧なグルーヴ・ユニットかと思う。
ほら、2:38~のダンス、ヨコノリでしょ(笑) 2:45~ バックビートだし。
↓こんなのもあるし、
■ milet×Aimer×幾田りら - おもかげ (produced by Vaundy) / THE FIRST TAKE
いまが旬の3人のハモリ。
■ 鈴木愛理 - 君の知らない物語(カバー)
supercellの超難曲に生歌唱で突っ込むとは・・・。
しかも破綻せず歌い切ってるのにはびっくり。
やっぱりJ-POPの流れ、ここにきて確実に変わってきてると思う。
アニソンやバーチャル系も、じつは実力派ごろごろだったりします。
よくわからんので、それほど聴き込んでないけど・・・。
↓
■ 人気の声優ユニット
■ ワルキューレ GIRAFFE BLUES( 3rd LIVE/day 2 )
↓ ちょっと探すとこんなのがいきなり引っかかってきたりする。びっくり。
■ 葵井歌菜 声優が「君の知らない物語」/supercell ドラムを叩きながら歌ってみた Drum cover
ハイハットのこなしとフェミニンな美声のコントラスト。たまらん。
■【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」
架空ユニットなんだけど、さりげに楽器うまかったりする・・・。
これ、音源入っていないとしたらかなり凄いと思う。
■ 【公式ライブ映像】Morfonica「ハーモニー・デイ」(BanG Dream! 9th☆LIVE「Mythology」より)【期間限定】
これも安定のパフォーマンス。
■ 【組曲】花譜×佐倉綾音 #92.5「あさひ」【オリジナルMV】
なんか、やりたい放題の曲構成じゃな。
びみょーなモチーフみたいだけど聴き応えあり。
■ ClariS 『ケアレス』 Music Video
安定のClariS。こういう包み込むような女性ヴォーカルは日本ならでは?
■ 愛美「カザニア」
このリズム。hiphopのワンパタビートにはまり込んだ米国じゃ、創り出せないよきっと(笑)
■ 約束 (Yakusoku) - 如月千早(今井麻美) // covered by 凪原涼菜
バーチャルアーティストだけど、実在のシンガーらしい。
なんというか、聴きすすむほどにじわじわと声質のよさが伝わってくる。
------------------------------
J-POP(セツナ系) → アニソンの逆襲パターンも・・・。
■ SoulJa - SoulJa / Way to Love~最後の恋~feat.唐沢美帆
↓
未来のひとへ / TRUE 5th Anniversary Live Sound! vol.3 ~with Strings〜 TRUE(← 唐沢美帆)
セツナ系聴いて育った世代の逆襲も、そろそろあるかもよ。
■【2021年版】ハロプロ歌姫ランキングBEST15
でもって「ハロプロ全員歌うまい説」あり。全員じゃないとは思うが。
小学生にしてからが、すでにこのレベルだから・・・。 ↓
■ 島津心美ちゃん 「誰より好きなのに (古内東子)」2021/07/22 Kokomi 11th Birthday Live 溝ノ口劇場
強弱が効いてて歌いまわしがやたらにエモーショナル。そして歌にスケール感がある。
この子本当に小学生か?
■ 加藤礼愛ちゃん 11/25(木)21:00〜フジTV【千鳥クセスゴ】出演💄『HALO』(カトレア.Kato Leia.12yrs) BEYONCE cover
この子の歌声聴いてると、
「最高の楽器は人の生の声」とか「優秀な男性ボーカルが10人束になってかかっても、1人の才能ある女性ボーカルには及ばない」
などという音楽格言が想い浮かんでくる。
なんというか、もって生まれたボーカリストとしての格の高さを感じる。
カラバトU-18絡み、そしてひょっとしてバンドリとハロプロのレベル、かなりの高みにあるのでは・・・。
いまの米国の金太郎飴チャートじゃ、及びもつかないレベルの高さか(笑)
やっぱりこの国、歌の女神が舞い降りた国かも?
↑ これもなかなかいいですね。
■ Milet メドレー ヒット曲 2022 - Milet 新曲 人気曲 2022. vol 1
Miletは、メロやアンサンブルの素晴らしさを改めて呼び覚ましてくれたアーティストだと思う。
もっと売れると思ったけどね・・・
■ オリコンデイリーシングルランキング2022年04月28日付
■ オリコン月間アルバムランキング
↑ ため息しか出んわ・・・。
NHKBSプレミアムの『MUST BE UKTV』、このところ毎日聴いています。
で、やっぱりいま聴き返してみても、いちばんメロディ(というかアンサンブル)が輝いていたのは1980年代前半だと思う。
そしてここで完成されたひとつのPOPSの頂点を、じつのところもっともよく引き継いでいるのはJ-POPだと思う。
なにせこの国は、なにものも滅ぼさない国だから・・・。
カノン進行使ったヒット曲をこんなにたくさんもってるのは、日本だけだと思うけどね、いい悪いは別にして。
■ カノン進行を使った曲集 全23曲 繋げて歌ってみた by KAT
J-POP(どっちかというと売れてないやつ)のメロと女性ボーカルの美しさは、いまや世界屈指だと思う。
■ Jason Scheff - Over And Over (Cover ELT)
■ Every Little Thing - Over and Over (1999.01.26)
↑ 往年のAORの名手Jason Scheffでも、1999年の時点では、もはや日本の歌姫に及ばないことがわかる。
■ Butterfly(バタフライ) - 木村カエラ(カバー)
コード
2009年の時点で、こんなメロ(コード進行)創り出せて、しかもヒットするのはもはやひょっとして日本だけでは?
と思った曲。
■ 島津心美 - Dreamin'/ JASMINE
2022年の小学生の歌姫。この子はきっと伸びる。
--------------------------
2022/03/13 UP
さっき、TVKで久しぶりに最新のビルボード聴いてみました。
一時期Silk Sonicが健闘してたので、淡い期待を抱きつつ。
でも、ダメでしたね。ぜんぜん。
8割の曲が同じに聴こえた。情けないほどの金太郎飴チャート。
1980年代にこんな名曲たちを生み出していた米国の音楽シーン。
あれは夢まぼろしだったのか?
それにくらべて、このところの日本の曲、かなりいいとこついてる。
1980年代の再評価も進んでるし、邦楽のYouTubeのコメント欄が、このところ外国語で埋め尽くされてる理由がわかる気がする。
このところ書き散らした最近の曲を中心に、振り返りつつまとめてみました。
■ milet「One Reason」MUSIC VIDEO (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)
この時代に、「歌だけで、音として聴いてもらいたい」、こう言い切れるアーティストが出てくるとは・・・。
これ、ひょっとして6拍子?
■ 緑黄色社会『キャラクター』Official Video / Ryokuoushoku Shakai – Character
まさかこんな新曲が、新型コロナ禍真っ最中のこの状況で聴けるとは・・・
「応援ソング」ちゅう曲調じゃないわな、これ。
いきなりのワウワウ・ギター、カッティングギターにストリングス、つづいてピッキングギターにホンキートンクなピアノ、そして華&色気を帯びたヴォーカル。
ハンドクラップにキメのリズム。
でもって弾みまくるベース、StuffのGordon Edwardsかよ(笑)
まだ4つ打ちっぽさ残してるけど、これで腕利きのドラムス入ったら完璧なグルーヴ・ユニットかと思う。
ほら、2:38~のダンス、ヨコノリでしょ(笑) 2:45~ バックビートだし。
↓こんなのもあるし、
■ milet×Aimer×幾田りら - おもかげ (produced by Vaundy) / THE FIRST TAKE
いまが旬の3人のハモリ。
■ 鈴木愛理 - 君の知らない物語(カバー)
supercellの超難曲に生歌唱で突っ込むとは・・・。
しかも破綻せず歌い切ってるのにはびっくり。
やっぱりJ-POPの流れ、ここにきて確実に変わってきてると思う。
アニソンやバーチャル系も、じつは実力派ごろごろだったりします。
よくわからんので、それほど聴き込んでないけど・・・。
↓
■ 人気の声優ユニット
■ ワルキューレ GIRAFFE BLUES( 3rd LIVE/day 2 )
↓ ちょっと探すとこんなのがいきなり引っかかってきたりする。びっくり。
■ 葵井歌菜 声優が「君の知らない物語」/supercell ドラムを叩きながら歌ってみた Drum cover
ハイハットのこなしとフェミニンな美声のコントラスト。たまらん。
■【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」
架空ユニットなんだけど、さりげに楽器うまかったりする・・・。
これ、音源入っていないとしたらかなり凄いと思う。
■ 【公式ライブ映像】Morfonica「ハーモニー・デイ」(BanG Dream! 9th☆LIVE「Mythology」より)【期間限定】
これも安定のパフォーマンス。
■ 【組曲】花譜×佐倉綾音 #92.5「あさひ」【オリジナルMV】
なんか、やりたい放題の曲構成じゃな。
びみょーなモチーフみたいだけど聴き応えあり。
■ ClariS 『ケアレス』 Music Video
安定のClariS。こういう包み込むような女性ヴォーカルは日本ならでは?
■ 愛美「カザニア」
このリズム。hiphopのワンパタビートにはまり込んだ米国じゃ、創り出せないよきっと(笑)
■ 約束 (Yakusoku) - 如月千早(今井麻美) // covered by 凪原涼菜
バーチャルアーティストだけど、実在のシンガーらしい。
なんというか、聴きすすむほどにじわじわと声質のよさが伝わってくる。
------------------------------
J-POP(セツナ系) → アニソンの逆襲パターンも・・・。
■ SoulJa - SoulJa / Way to Love~最後の恋~feat.唐沢美帆
↓
未来のひとへ / TRUE 5th Anniversary Live Sound! vol.3 ~with Strings〜 TRUE(← 唐沢美帆)
セツナ系聴いて育った世代の逆襲も、そろそろあるかもよ。
■【2021年版】ハロプロ歌姫ランキングBEST15
でもって「ハロプロ全員歌うまい説」あり。全員じゃないとは思うが。
小学生にしてからが、すでにこのレベルだから・・・。 ↓
■ 島津心美ちゃん 「誰より好きなのに (古内東子)」2021/07/22 Kokomi 11th Birthday Live 溝ノ口劇場
強弱が効いてて歌いまわしがやたらにエモーショナル。そして歌にスケール感がある。
この子本当に小学生か?
■ 加藤礼愛ちゃん 11/25(木)21:00〜フジTV【千鳥クセスゴ】出演💄『HALO』(カトレア.Kato Leia.12yrs) BEYONCE cover
この子の歌声聴いてると、
「最高の楽器は人の生の声」とか「優秀な男性ボーカルが10人束になってかかっても、1人の才能ある女性ボーカルには及ばない」
などという音楽格言が想い浮かんでくる。
なんというか、もって生まれたボーカリストとしての格の高さを感じる。
カラバトU-18絡み、そしてひょっとしてバンドリとハロプロのレベル、かなりの高みにあるのでは・・・。
いまの米国の金太郎飴チャートじゃ、及びもつかないレベルの高さか(笑)
やっぱりこの国、歌の女神が舞い降りた国かも?
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
寅薬師霊場御開帳 ~ 12年に一度の御朱印 ~
2022/04/23 追加UP
2022/04/19 追加UP
2.武南十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/30
・札所数12、開帳数12、御朱印授与数12
・札所詳細は猫の足あと様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:30 御朱印各300円
・専用納経帳あり(1,000円) 第1番貴雲寺様にて頒布されています。
・横浜市港北区、神奈川区を中心とする寅薬師霊場です。こちらも御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。


【写真 上(左)】 チラシ
【写真 下(右)】 専用納経帳
・結願しました。
・雰囲気のある落ち着いた趣きのお寺さまが多いですが、敷居は高くなくご対応は親切です。
・宗派は古義真言宗と曹洞宗が多いですが、結願の三宝寺様は浄土宗です。
・多くの札所で回向柱と縁の綱が設けられ、御開帳ならではの華やいだ雰囲気が味わえます。
・第10番からの東神奈川周辺の札所へのアプローチは狭い路地となり、駐車場がないところもあるので車参拝は要注意です。(近くにコインパーキングがあります。)
・御朱印は原則規定用紙での授与となりますが、御朱印帳貼付用の書置御朱印をご用意されている札所も多く、御朱印帳に捺印いただけた札所もありました。
・4/30(土)までの御開帳です。お時間がある方はぜひどうぞ。


【写真 上(左)】 第1番貴雲寺-1
【写真 下(右)】 第1番貴雲寺-2
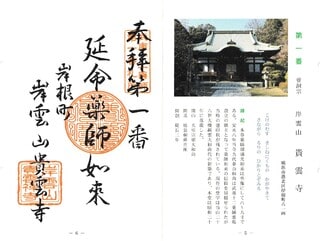
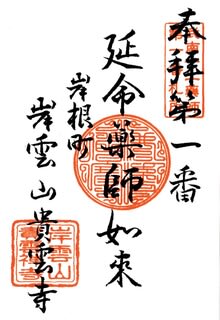
【写真 上(左)】 第1番貴雲寺の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 第1番貴雲寺の御朱印(御朱印帳貼付用)

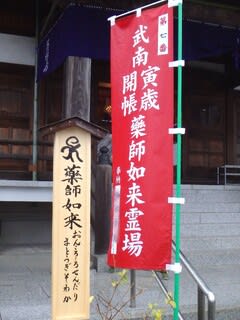
【写真 上(左)】 第7番金剛寺-1
【写真 下(右)】 第7番金剛寺-2


【写真 上(左)】 第7番金剛寺の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 第7番金剛寺の御朱印(御朱印帳貼付用)


【写真 上(左)】 第12番三宝寺-1
【写真 下(右)】 第12番三宝寺-2


【写真 上(左)】 第12番三宝寺の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 第12番三宝寺の御朱印(御朱印帳貼付用)
8.武相寅歳薬師如来霊場
・御開帳期間:4/9~5/8
→ 公式Web
・結願していますが、この霊場についてはご紹介を控えます。


【写真 上(左)】 第1番舊城寺の薬師堂(発願所)
【写真 下(右)】 第25番寶帒寺の薬師堂(結願所)
なお、新型コロナ禍で本年4/18~5/18に延期予定となっておりました三浦三十三観音霊場の丑年中開帳は中止となった模様です。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
僧侶のみならず、在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
宗派は違っても、御開帳の回向柱にはおおむねこのような願いが揮毫されています。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
-----------------------
2022/04/17 追加UP
1.都筑橘樹十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/20
・札所数12、開帳数9、御朱印授与数12
・札所詳細は公式Webをご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00 御朱印各300円
・納経帳(御朱印帳)は表紙のみ頒布あり(100円)
・横浜市都筑区、港北区を中心とする寅薬師霊場です。御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・宗派は真言宗、天台宗、曹洞宗、浄土宗と多彩です。
・御朱印は原則規定用紙での授与となります。
・結願しました。
第4番 清光寺(勝田会館)
第8番 自性院
第9番 慈眼寺
は非開帳で参拝不可ですが、3箇寺とも御朱印(置き紙)は第11番東照寺様にて拝受できます。
・実質9の札所巡りなので、車であれば1日結願できるかと思います。
・ほのぼのとした小規模な札所と、歴史の香り高い名刹が参画される充実の霊場で、各札所のご対応も親切できもちのよい巡拝ができます。
・御開帳はあと3日(4/20まで)。時間がとれる方はぜひどうぞ。

納経帳(御朱印帳)の表紙


【写真 上(左)】 第1番蓮華寺-1
【写真 下(右)】 第1番蓮華寺-2
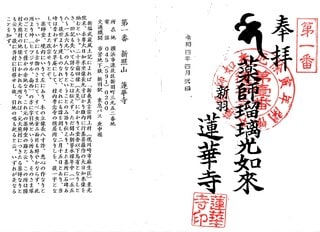

【写真 上(左)】 第1番蓮華寺の御朱印(規定用紙)
【写真 下(右)】 第1番蓮華寺の御朱印(御朱印帳印判捺)


【写真 上(左)】 第7番正覚寺-1
【写真 下(右)】 第7番正覚寺-2


【写真 上(左)】 第7番正覚寺の御朱印(規定用紙)
【写真 下(右)】 第7番正覚寺の御朱印(御朱印帳貼付用)


【写真 上(左)】 第12番大乗寺-1
【写真 下(右)】 第12番大乗寺-2


【写真 上(左)】 第12番大乗寺の御朱印(規定用紙)
【写真 下(右)】 第12番大乗寺の御朱印(御朱印帳印判捺)
-----------------------
2022/04/11・13 追加UP
下記の情報を更新しました。
7.相模二十一薬師霊場 → 明日4/12まで
6.中武蔵七十二薬師霊場 → 明後日4/13まで
4.武蔵(関東)東向 足立十二薬師霊場(北部) → 4/14まで
12年に一度の貴重な機会です。
時間がとれる方はぜひどうぞ。
-----------------------
2022/04/09 追加UP
中武蔵七十二薬師霊場、打ち始めましたので情報UPします。
6.中武蔵七十二薬師霊場
・御開帳期間:4/7~4/13
・札所数72、開帳数不明、御朱印授与数(お札含む)61程度
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間(予定):8:30(一部9:00)~16:30
・専用納経帳:なし(書置または御朱印帳への捺印(揮毫?)が原則)
・埼玉県坂戸市、東松山市、鶴ヶ島市、川越市、滑川町、吉見町、毛呂山町、川島町にまたがる寅薬師霊場です。
・薬師堂、無住寺院、通常は御朱印不授与のお寺様が多く、御朱印はすこぶるレアです。
・御開帳時以外にこの霊場の御朱印を授与されているのは、第47番正法寺様のほか数箇寺に留まるとみられます。
・第1番龍福寺様(坂戸市戸口453)で頒布されている御開帳ガイドによると、今回、じつに51の札所で御朱印授与を予定されている模様です。
・小規模なお堂や公民館でも檀家さんが詰められて御開帳いただいているところがあります。ありがたいことです。
・実際にまわり始めてみて、ほぼガイド通りの御朱印を拝受できています。
・御朱印形状は御朱印帳揮毫、御朱印帳印判捺、揮毫書置、印判紙、印刷紙とすこぶる多彩で、御朱印の見本市のようです。ほとんど御朱印帳で受けることができます。
・兼務札所の武州八十八霊場の御朱印も授与されているところがありました。
・開けた平地の道程で交通量も少ないので、予想以上のペースで回れます。
・散りぎわの桜と菜の花のコントラストが見事です。札所のご対応も親切で気持ちのよい巡拝ができます。おすすめです。
・72の札所、結願しました。(1ヶ所御本尊不明の札所があるので正確には71) 予想以上に御朱印をいただけました。後日とりまとめてUPします。
・(4/9追加情報)
ガイドでは「授与なし」「不明(授与についての記載なし)」となっているいくつかの札所で御朱印を拝受できています。
一方で、御朱印ではなくお札の授与となっている札所もあります。
一日で御朱印数を稼ぐとしたら、おそらく坂戸市内巡拝の効率がいいと思います。(札所密度が高く授与率も高いです。)
・(4/10・12追加情報)
ガイドでは「授与なし」「不明(授与についての記載なし)」となっているいくつかの札所で御朱印を拝受できています。
→ 現時点で確認できているのは下記札所です。
21番、35番、37番、42番(46番にて)、44番、49番(お札)、50番、64番、67番、69番、71番

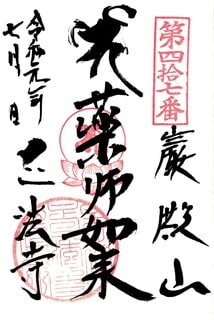
【写真 上(左)】 御開帳ガイド
【写真 下(右)】 第47番正法寺の札所御朱印


【写真 上(左)】 第1番龍福寺
【写真 下(右)】 第10番元町薬師堂


【写真 上(左)】 第1番龍福寺の御朱印
【写真 下(右)】 第2番澤木薬師堂の御朱印


【写真 上(左)】 第4番大薬寺の御朱印
【写真 下(右)】 第5番智福寺の御朱印


【写真 上(左)】 第6番大栄寺の御朱印
【写真 下(右)】 第7番長福寺(新町薬師堂)の御朱印


【写真 上(左)】 第16番永命寺
【写真 下(右)】 第45番(毛塚)薬師堂
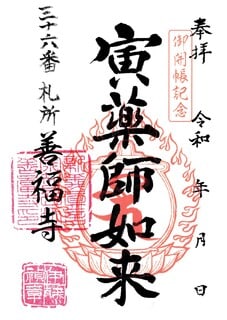

【写真 上(左)】 第36番善福寺の御朱印
【写真 下(右)】 第65番福聚寺(曹源寺)の御朱印


【写真 上(左)】 第69番西明寺の御朱印
【写真 下(右)】 第72番慶徳寺(結願所)の御朱印
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子(カバー)
■ さくらとことり - はな
■今井美樹 - ひとひら
-----------------------
2022/04/07 UP
さらに情報を追加しました。
7.相模二十一薬師霊場
・御開帳期間:4/8~4/12
・札所数21、開帳数不明(18程度?)、御朱印授与数不明
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:おおむね9:00~16:00
・専用納経帳:なし
・神奈川県平塚市、秦野市、伊勢原市、二宮町、大磯町にまたがる寅薬師霊場です。
・基本的には御開帳霊場で、御朱印はレアと思われます。
・御朱印帳書入(印判捺)いただける札所がけっこうあります。
・範囲が比較的広く期間が短いので、全札所巡拝はかなり気合いが要りそうです。


【写真 上(左)】 第1番等覚院藤巻寺
【写真 下(右)】 第7番王福寺(縁の綱二本です)


【写真 上(左)】 第1番等覚院藤巻寺の御朱印
【写真 下(右)】 第9番楊谷寺の御朱印


【写真 上(左)】 第13番薬王寺の御朱印
【写真 下(右)】 第15番東光寺(矢名薬師)の御朱印
-----------------------
2022/04/04 UP
情報を追加しました。
本日、仕事を午前中で切り上げ(笑)、大雨のなか巡拝してきました。
5.稲毛七薬師霊場
・御開帳期間:4/3(4)~4/10
・札所数7、開帳数7、御朱印授与数7
・札所詳細は第2番影向寺様公式Webをご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00
・専用納経帳:なし
・川崎市高津区、宮前区、横浜市港北区、鶴見区にまたがる寅薬師霊場です。
・臨済宗妙心寺派寺院がひとつありますが、他の6札所はすべて天台宗で、台密(天台密教)の色彩の強い薬師霊場です。
・すべての札所で御開帳され、書置御朱印を授与されています。
・他札所を兼務される寺院もありますが、御開帳期間中は七薬師霊場の御朱印のみの授与かもしれません。
・稲毛七薬師霊場と札所が重複する霊場に多摩七薬師霊場がありますが、現在活動していない模様で、御朱印もほぼ授与されていないようです。
・すべての札所に駐車場があり、車であれば1日で結願できるかと思います。


【写真 上(左)】 パンフレット
【写真 下(右)】 御開帳案内


【写真 上(左)】 第4番西光院
【写真 下(右)】 第7番薬師院


【写真 上(左)】 第1番塩谷寺薬師堂の御朱印
【写真 下(右)】 第7番薬師院の御朱印
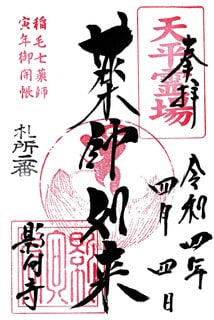

【写真 上(左)】 第2番影向寺の御開帳御朱印
【写真 下(右)】 同 通常御朱印
・御開帳御朱印には「稲毛七薬師 寅年御開帳」の御開帳印が捺されます。
-----------------------
2022/04/03 UP
情報を追加しました。
さいたま市内には寅薬師霊場かふたつあり、いずれも一部札所で御開帳されます。
3.武蔵(関東)東向 足立十二薬師霊場(南部)
・御開帳期間:4/3~4/9
・札所数13、開帳数(回向柱のみ含む)7、御朱印授与数5or6
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00
・専用納経帳なし
・さいたま市浦和区、桜区、南区、戸田市を中心とする寅薬師霊場です。御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・御朱印は原則書置での授与のようですが、御朱印帳に捺印いただけた札所もありました。
第1番 文蔵薬師堂 さいたま市南区文蔵4-7-5
御開帳なし、御朱印不授与
第2番 成就院(上寺薬師堂) さいたま市浦和区常盤1-4-23
御開帳?、回向柱、御朱印あり
第3番 上ノ宮薬師堂 さいたま市桜区西堀2-3-9
御開帳、回向柱、御朱印あり?
※筆者は管理寺院にて御朱印を拝受しましたが、原則不授与かもしれません。
第4番 根岸薬師堂 さいたま市南区根岸4-2-7
御開帳、回向柱、御朱印あり
第5番 医王寺(白幡薬師堂) さいたま市南区白幡2-16-8
御開帳(4/3午後限定かも)、御朱印不授与
第6番 下戸田薬師堂 戸田市下戸田1-5-10
回向柱、御朱印あり(正覚院/戸田市中町2-14-3にて授与)
第7番 薬王院 さいたま市桜区田島5-15-5
御開帳、回向柱、御朱印あり
第8番 宝泉寺 さいたま市南区鹿手袋6-3-15
御開帳なし、御朱印不授与
第9番 東光寺 さいたま市南区内谷4-17-7
御開帳なし、御朱印不授与
第9番 美女木薬師堂 戸田市美女木3-18-11
御開帳なし、御朱印不授与
第10番 慈眼寺 戸田市笹目5-12-11
御開帳なし、御朱印不授与
第11番 岸町薬師堂(岸高野薬師) さいたま市浦和区岸町7-9-25
御開帳、回向柱、御朱印あり
第12番 中上薬師堂 蕨市北町(中上)
所在不明
※上記は4/3時点の情報です。変更があるかもしれません。


【写真 上(左)】 第2番成就院の御開帳案内
【写真 下(右)】 第3番上ノ宮薬師堂


【写真 上(左)】 第4番根岸薬師堂
【写真 下(右)】 第7番薬王院


【写真 上(左)】 第2番成就院の御朱印
【写真 下(右)】 第6番下戸田薬師堂の御朱印
4.武蔵(関東)東向 足立十二薬師霊場(北部)
・御開帳期間:4/8~4/14(御開帳した札所は少なく、御開帳札所も4/8のみが多かった模様です。)
・札所数12(+特番1)
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:不明
・専用納経帳:なし
・さいたま市浦和区、緑区を中心とする寅薬師霊場です。
・一部札所様の御開帳情報は得ていますが、南部以上に小規模な薬師堂が多くそれらの御開帳情報はGetできていません。
・今回御開帳した札所は少なく、御開帳札所も4/8の1日のみが多かった模様です。
・そのなかで孤軍奮闘?されていたのが第4番東泉寺様で、回向柱、縁の綱、御開帳幟などを取り揃え、お薬師様を供養されていました。
御開帳期間もしっかり1週間とられ(以前はどの札所も1週間程度のご開帳だったらしい)、霊場札所の鑑のような存在です。


【写真 上(左)】 第1番三宝薬師堂(宿区自治会館)
【写真 下(右)】 第4番東泉寺


【写真 上(左)】 第3番報恩寺の御朱印
【写真 下(右)】 第4番東泉寺の御朱印

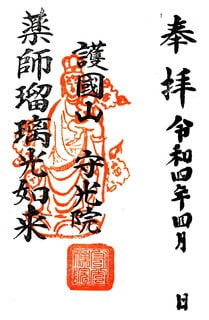
【写真 上(左)】 第6番寶性寺の御朱印
【写真 下(右)】 特番守光院の御朱印
-----------------------
2022/04/02 UP
寅年の4月。
12年に一度の寅薬師さまの御開帳が各地で催されています。
まずは横浜市の寅薬師ふたつをご紹介します。(時間がないのでまずは簡単に)
1.都筑橘樹十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/20
・札所数12、開帳数9、御朱印授与数12
・札所詳細は公式Webをご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00 御朱印各300円
・御朱印帳は表紙のみ頒布あり(100円)
・横浜市都筑区、港北区を中心とする寅薬師霊場です。御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・御朱印は原則規定用紙での授与となります。


【写真 上(左)】 第1番蓮華寺
【写真 下(右)】 第7番正覺寺


【写真 上(左)】 御朱印帳の表紙
【写真 下(右)】 第1番蓮華寺の御朱印
2.武南十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/30
・札所数12、開帳数12、御朱印授与数12
・札所詳細は猫の足あと様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:30 御朱印各300円
・専用納経帳あり(1,000円) 第1番貴雲寺様にて頒布されています。
・横浜市港北区、神奈川区を中心とする寅薬師霊場です。こちらも御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・御朱印は原則規定用紙での授与となりますが、御朱印帳に捺印いただけた札所もありました。


【写真 上(左)】 第1番貴雲寺
【写真 下(右)】 第5番長王寺
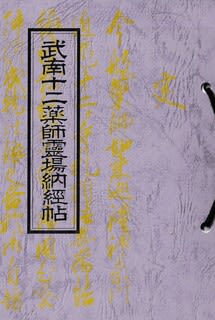

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 第1番貴雲寺の御朱印
【 BGM 】
■ milet「One Reason」MUSIC VIDEO (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)
この時代に、「歌だけで、音として聴いてもらいたい」、こう言い切れるアーティストが出てくるとは・・・。
そして、閉塞感ただようこの時代に、これほどの壮大な曲を創りだせるとは・・・。
【milet】平原綾香との音楽対談 / miletが「地響き」と称する平原の歌声の秘密/ 平原が制作した楽曲で「生きててよかった」と思った曲【J-WAVE・WOW MUSIC】
■ 2022年のJ-POP-2
■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)
スケール感ある曲2曲追加です。
■ 夢の途中 - KOKIA
→ ■ KOKIAの名バラード12曲
■ far on the water - kalafina
→ ■ 伝説のユニットkalafina
→ ■ 梶浦サウンド総ざらい!(&「炎」-homura)
2022/04/19 追加UP
2.武南十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/30
・札所数12、開帳数12、御朱印授与数12
・札所詳細は猫の足あと様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:30 御朱印各300円
・専用納経帳あり(1,000円) 第1番貴雲寺様にて頒布されています。
・横浜市港北区、神奈川区を中心とする寅薬師霊場です。こちらも御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。


【写真 上(左)】 チラシ
【写真 下(右)】 専用納経帳
・結願しました。
・雰囲気のある落ち着いた趣きのお寺さまが多いですが、敷居は高くなくご対応は親切です。
・宗派は古義真言宗と曹洞宗が多いですが、結願の三宝寺様は浄土宗です。
・多くの札所で回向柱と縁の綱が設けられ、御開帳ならではの華やいだ雰囲気が味わえます。
・第10番からの東神奈川周辺の札所へのアプローチは狭い路地となり、駐車場がないところもあるので車参拝は要注意です。(近くにコインパーキングがあります。)
・御朱印は原則規定用紙での授与となりますが、御朱印帳貼付用の書置御朱印をご用意されている札所も多く、御朱印帳に捺印いただけた札所もありました。
・4/30(土)までの御開帳です。お時間がある方はぜひどうぞ。


【写真 上(左)】 第1番貴雲寺-1
【写真 下(右)】 第1番貴雲寺-2
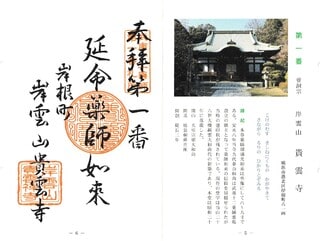
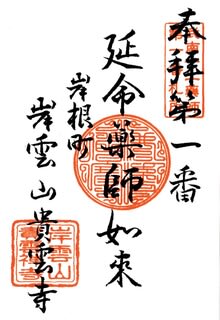
【写真 上(左)】 第1番貴雲寺の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 第1番貴雲寺の御朱印(御朱印帳貼付用)

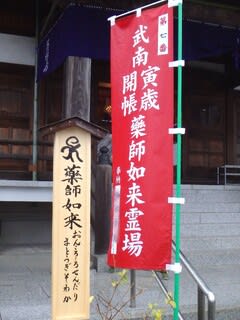
【写真 上(左)】 第7番金剛寺-1
【写真 下(右)】 第7番金剛寺-2


【写真 上(左)】 第7番金剛寺の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 第7番金剛寺の御朱印(御朱印帳貼付用)


【写真 上(左)】 第12番三宝寺-1
【写真 下(右)】 第12番三宝寺-2


【写真 上(左)】 第12番三宝寺の御朱印(専用納経帳)
【写真 下(右)】 第12番三宝寺の御朱印(御朱印帳貼付用)
8.武相寅歳薬師如来霊場
・御開帳期間:4/9~5/8
→ 公式Web
・結願していますが、この霊場についてはご紹介を控えます。


【写真 上(左)】 第1番舊城寺の薬師堂(発願所)
【写真 下(右)】 第25番寶帒寺の薬師堂(結願所)
なお、新型コロナ禍で本年4/18~5/18に延期予定となっておりました三浦三十三観音霊場の丑年中開帳は中止となった模様です。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
僧侶のみならず、在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
宗派は違っても、御開帳の回向柱にはおおむねこのような願いが揮毫されています。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
-----------------------
2022/04/17 追加UP
1.都筑橘樹十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/20
・札所数12、開帳数9、御朱印授与数12
・札所詳細は公式Webをご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00 御朱印各300円
・納経帳(御朱印帳)は表紙のみ頒布あり(100円)
・横浜市都筑区、港北区を中心とする寅薬師霊場です。御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・宗派は真言宗、天台宗、曹洞宗、浄土宗と多彩です。
・御朱印は原則規定用紙での授与となります。
・結願しました。
第4番 清光寺(勝田会館)
第8番 自性院
第9番 慈眼寺
は非開帳で参拝不可ですが、3箇寺とも御朱印(置き紙)は第11番東照寺様にて拝受できます。
・実質9の札所巡りなので、車であれば1日結願できるかと思います。
・ほのぼのとした小規模な札所と、歴史の香り高い名刹が参画される充実の霊場で、各札所のご対応も親切できもちのよい巡拝ができます。
・御開帳はあと3日(4/20まで)。時間がとれる方はぜひどうぞ。

納経帳(御朱印帳)の表紙


【写真 上(左)】 第1番蓮華寺-1
【写真 下(右)】 第1番蓮華寺-2
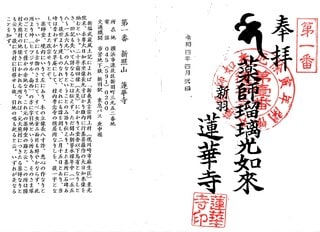

【写真 上(左)】 第1番蓮華寺の御朱印(規定用紙)
【写真 下(右)】 第1番蓮華寺の御朱印(御朱印帳印判捺)


【写真 上(左)】 第7番正覚寺-1
【写真 下(右)】 第7番正覚寺-2


【写真 上(左)】 第7番正覚寺の御朱印(規定用紙)
【写真 下(右)】 第7番正覚寺の御朱印(御朱印帳貼付用)


【写真 上(左)】 第12番大乗寺-1
【写真 下(右)】 第12番大乗寺-2


【写真 上(左)】 第12番大乗寺の御朱印(規定用紙)
【写真 下(右)】 第12番大乗寺の御朱印(御朱印帳印判捺)
-----------------------
2022/04/11・13 追加UP
下記の情報を更新しました。
7.相模二十一薬師霊場 → 明日4/12まで
6.中武蔵七十二薬師霊場 → 明後日4/13まで
4.武蔵(関東)東向 足立十二薬師霊場(北部) → 4/14まで
12年に一度の貴重な機会です。
時間がとれる方はぜひどうぞ。
-----------------------
2022/04/09 追加UP
中武蔵七十二薬師霊場、打ち始めましたので情報UPします。
6.中武蔵七十二薬師霊場
・御開帳期間:4/7~4/13
・札所数72、開帳数不明、御朱印授与数(お札含む)61程度
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間(予定):8:30(一部9:00)~16:30
・専用納経帳:なし(書置または御朱印帳への捺印(揮毫?)が原則)
・埼玉県坂戸市、東松山市、鶴ヶ島市、川越市、滑川町、吉見町、毛呂山町、川島町にまたがる寅薬師霊場です。
・薬師堂、無住寺院、通常は御朱印不授与のお寺様が多く、御朱印はすこぶるレアです。
・御開帳時以外にこの霊場の御朱印を授与されているのは、第47番正法寺様のほか数箇寺に留まるとみられます。
・第1番龍福寺様(坂戸市戸口453)で頒布されている御開帳ガイドによると、今回、じつに51の札所で御朱印授与を予定されている模様です。
・小規模なお堂や公民館でも檀家さんが詰められて御開帳いただいているところがあります。ありがたいことです。
・実際にまわり始めてみて、ほぼガイド通りの御朱印を拝受できています。
・御朱印形状は御朱印帳揮毫、御朱印帳印判捺、揮毫書置、印判紙、印刷紙とすこぶる多彩で、御朱印の見本市のようです。ほとんど御朱印帳で受けることができます。
・兼務札所の武州八十八霊場の御朱印も授与されているところがありました。
・開けた平地の道程で交通量も少ないので、予想以上のペースで回れます。
・散りぎわの桜と菜の花のコントラストが見事です。札所のご対応も親切で気持ちのよい巡拝ができます。おすすめです。
・72の札所、結願しました。(1ヶ所御本尊不明の札所があるので正確には71) 予想以上に御朱印をいただけました。後日とりまとめてUPします。
・(4/9追加情報)
ガイドでは「授与なし」「不明(授与についての記載なし)」となっているいくつかの札所で御朱印を拝受できています。
一方で、御朱印ではなくお札の授与となっている札所もあります。
一日で御朱印数を稼ぐとしたら、おそらく坂戸市内巡拝の効率がいいと思います。(札所密度が高く授与率も高いです。)
・(4/10・12追加情報)
ガイドでは「授与なし」「不明(授与についての記載なし)」となっているいくつかの札所で御朱印を拝受できています。
→ 現時点で確認できているのは下記札所です。
21番、35番、37番、42番(46番にて)、44番、49番(お札)、50番、64番、67番、69番、71番

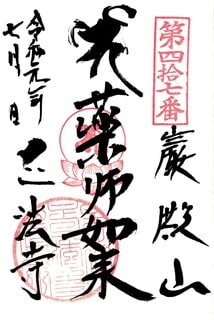
【写真 上(左)】 御開帳ガイド
【写真 下(右)】 第47番正法寺の札所御朱印


【写真 上(左)】 第1番龍福寺
【写真 下(右)】 第10番元町薬師堂


【写真 上(左)】 第1番龍福寺の御朱印
【写真 下(右)】 第2番澤木薬師堂の御朱印


【写真 上(左)】 第4番大薬寺の御朱印
【写真 下(右)】 第5番智福寺の御朱印


【写真 上(左)】 第6番大栄寺の御朱印
【写真 下(右)】 第7番長福寺(新町薬師堂)の御朱印


【写真 上(左)】 第16番永命寺
【写真 下(右)】 第45番(毛塚)薬師堂
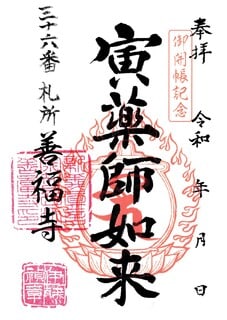

【写真 上(左)】 第36番善福寺の御朱印
【写真 下(右)】 第65番福聚寺(曹源寺)の御朱印


【写真 上(左)】 第69番西明寺の御朱印
【写真 下(右)】 第72番慶徳寺(結願所)の御朱印
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子(カバー)
■ さくらとことり - はな
■今井美樹 - ひとひら
-----------------------
2022/04/07 UP
さらに情報を追加しました。
7.相模二十一薬師霊場
・御開帳期間:4/8~4/12
・札所数21、開帳数不明(18程度?)、御朱印授与数不明
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:おおむね9:00~16:00
・専用納経帳:なし
・神奈川県平塚市、秦野市、伊勢原市、二宮町、大磯町にまたがる寅薬師霊場です。
・基本的には御開帳霊場で、御朱印はレアと思われます。
・御朱印帳書入(印判捺)いただける札所がけっこうあります。
・範囲が比較的広く期間が短いので、全札所巡拝はかなり気合いが要りそうです。


【写真 上(左)】 第1番等覚院藤巻寺
【写真 下(右)】 第7番王福寺(縁の綱二本です)


【写真 上(左)】 第1番等覚院藤巻寺の御朱印
【写真 下(右)】 第9番楊谷寺の御朱印


【写真 上(左)】 第13番薬王寺の御朱印
【写真 下(右)】 第15番東光寺(矢名薬師)の御朱印
-----------------------
2022/04/04 UP
情報を追加しました。
本日、仕事を午前中で切り上げ(笑)、大雨のなか巡拝してきました。
5.稲毛七薬師霊場
・御開帳期間:4/3(4)~4/10
・札所数7、開帳数7、御朱印授与数7
・札所詳細は第2番影向寺様公式Webをご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00
・専用納経帳:なし
・川崎市高津区、宮前区、横浜市港北区、鶴見区にまたがる寅薬師霊場です。
・臨済宗妙心寺派寺院がひとつありますが、他の6札所はすべて天台宗で、台密(天台密教)の色彩の強い薬師霊場です。
・すべての札所で御開帳され、書置御朱印を授与されています。
・他札所を兼務される寺院もありますが、御開帳期間中は七薬師霊場の御朱印のみの授与かもしれません。
・稲毛七薬師霊場と札所が重複する霊場に多摩七薬師霊場がありますが、現在活動していない模様で、御朱印もほぼ授与されていないようです。
・すべての札所に駐車場があり、車であれば1日で結願できるかと思います。


【写真 上(左)】 パンフレット
【写真 下(右)】 御開帳案内


【写真 上(左)】 第4番西光院
【写真 下(右)】 第7番薬師院


【写真 上(左)】 第1番塩谷寺薬師堂の御朱印
【写真 下(右)】 第7番薬師院の御朱印
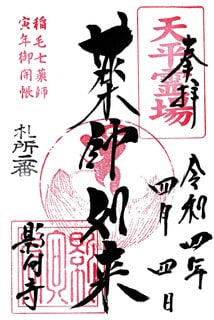

【写真 上(左)】 第2番影向寺の御開帳御朱印
【写真 下(右)】 同 通常御朱印
・御開帳御朱印には「稲毛七薬師 寅年御開帳」の御開帳印が捺されます。
-----------------------
2022/04/03 UP
情報を追加しました。
さいたま市内には寅薬師霊場かふたつあり、いずれも一部札所で御開帳されます。
3.武蔵(関東)東向 足立十二薬師霊場(南部)
・御開帳期間:4/3~4/9
・札所数13、開帳数(回向柱のみ含む)7、御朱印授与数5or6
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00
・専用納経帳なし
・さいたま市浦和区、桜区、南区、戸田市を中心とする寅薬師霊場です。御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・御朱印は原則書置での授与のようですが、御朱印帳に捺印いただけた札所もありました。
第1番 文蔵薬師堂 さいたま市南区文蔵4-7-5
御開帳なし、御朱印不授与
第2番 成就院(上寺薬師堂) さいたま市浦和区常盤1-4-23
御開帳?、回向柱、御朱印あり
第3番 上ノ宮薬師堂 さいたま市桜区西堀2-3-9
御開帳、回向柱、御朱印あり?
※筆者は管理寺院にて御朱印を拝受しましたが、原則不授与かもしれません。
第4番 根岸薬師堂 さいたま市南区根岸4-2-7
御開帳、回向柱、御朱印あり
第5番 医王寺(白幡薬師堂) さいたま市南区白幡2-16-8
御開帳(4/3午後限定かも)、御朱印不授与
第6番 下戸田薬師堂 戸田市下戸田1-5-10
回向柱、御朱印あり(正覚院/戸田市中町2-14-3にて授与)
第7番 薬王院 さいたま市桜区田島5-15-5
御開帳、回向柱、御朱印あり
第8番 宝泉寺 さいたま市南区鹿手袋6-3-15
御開帳なし、御朱印不授与
第9番 東光寺 さいたま市南区内谷4-17-7
御開帳なし、御朱印不授与
第9番 美女木薬師堂 戸田市美女木3-18-11
御開帳なし、御朱印不授与
第10番 慈眼寺 戸田市笹目5-12-11
御開帳なし、御朱印不授与
第11番 岸町薬師堂(岸高野薬師) さいたま市浦和区岸町7-9-25
御開帳、回向柱、御朱印あり
第12番 中上薬師堂 蕨市北町(中上)
所在不明
※上記は4/3時点の情報です。変更があるかもしれません。


【写真 上(左)】 第2番成就院の御開帳案内
【写真 下(右)】 第3番上ノ宮薬師堂


【写真 上(左)】 第4番根岸薬師堂
【写真 下(右)】 第7番薬王院


【写真 上(左)】 第2番成就院の御朱印
【写真 下(右)】 第6番下戸田薬師堂の御朱印
4.武蔵(関東)東向 足立十二薬師霊場(北部)
・御開帳期間:4/8~4/14(御開帳した札所は少なく、御開帳札所も4/8のみが多かった模様です。)
・札所数12(+特番1)
・札所詳細はニッポンの霊場様をご参照ください。
・御朱印対応時間:不明
・専用納経帳:なし
・さいたま市浦和区、緑区を中心とする寅薬師霊場です。
・一部札所様の御開帳情報は得ていますが、南部以上に小規模な薬師堂が多くそれらの御開帳情報はGetできていません。
・今回御開帳した札所は少なく、御開帳札所も4/8の1日のみが多かった模様です。
・そのなかで孤軍奮闘?されていたのが第4番東泉寺様で、回向柱、縁の綱、御開帳幟などを取り揃え、お薬師様を供養されていました。
御開帳期間もしっかり1週間とられ(以前はどの札所も1週間程度のご開帳だったらしい)、霊場札所の鑑のような存在です。


【写真 上(左)】 第1番三宝薬師堂(宿区自治会館)
【写真 下(右)】 第4番東泉寺


【写真 上(左)】 第3番報恩寺の御朱印
【写真 下(右)】 第4番東泉寺の御朱印

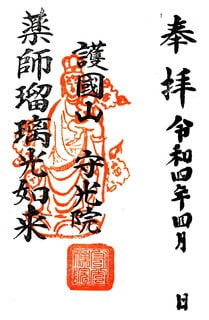
【写真 上(左)】 第6番寶性寺の御朱印
【写真 下(右)】 特番守光院の御朱印
-----------------------
2022/04/02 UP
寅年の4月。
12年に一度の寅薬師さまの御開帳が各地で催されています。
まずは横浜市の寅薬師ふたつをご紹介します。(時間がないのでまずは簡単に)
1.都筑橘樹十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/20
・札所数12、開帳数9、御朱印授与数12
・札所詳細は公式Webをご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:00 御朱印各300円
・御朱印帳は表紙のみ頒布あり(100円)
・横浜市都筑区、港北区を中心とする寅薬師霊場です。御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・御朱印は原則規定用紙での授与となります。


【写真 上(左)】 第1番蓮華寺
【写真 下(右)】 第7番正覺寺


【写真 上(左)】 御朱印帳の表紙
【写真 下(右)】 第1番蓮華寺の御朱印
2.武南十二薬師霊場
・御開帳期間:4/1~4/30
・札所数12、開帳数12、御朱印授与数12
・札所詳細は猫の足あと様をご参照ください。
・御朱印対応時間:9:00~16:30 御朱印各300円
・専用納経帳あり(1,000円) 第1番貴雲寺様にて頒布されています。
・横浜市港北区、神奈川区を中心とする寅薬師霊場です。こちらも御開帳霊場でこの霊場のみの札所もあるので、12年に一度の授与となるお寺さまもありそうです。
・御朱印は原則規定用紙での授与となりますが、御朱印帳に捺印いただけた札所もありました。


【写真 上(左)】 第1番貴雲寺
【写真 下(右)】 第5番長王寺
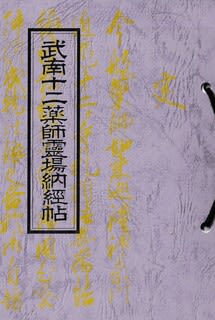

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 第1番貴雲寺の御朱印
【 BGM 】
■ milet「One Reason」MUSIC VIDEO (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)
この時代に、「歌だけで、音として聴いてもらいたい」、こう言い切れるアーティストが出てくるとは・・・。
そして、閉塞感ただようこの時代に、これほどの壮大な曲を創りだせるとは・・・。
【milet】平原綾香との音楽対談 / miletが「地響き」と称する平原の歌声の秘密/ 平原が制作した楽曲で「生きててよかった」と思った曲【J-WAVE・WOW MUSIC】
■ 2022年のJ-POP-2
■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)
スケール感ある曲2曲追加です。
■ 夢の途中 - KOKIA
→ ■ KOKIAの名バラード12曲
■ far on the water - kalafina
→ ■ 伝説のユニットkalafina
→ ■ 梶浦サウンド総ざらい!(&「炎」-homura)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 川越の桜と甲州武田氏ゆかりのお寺
本日は午後から川越に行き、4月の寅薬師御開帳につかう御朱印帳を喜多院で仕込んできました。
花曇りで写真はいまいちでしたが、桜はほぼ満開でした。


【写真 上(左)】 喜多院の桜-1
【写真 下(右)】 喜多院の桜-2
喜多院は桜の名所で、それなりに人出はありました。ただ、新型コロナ禍の前に比べるとやはり寂しい感じです。


【写真 上(左)】 三芳野神社の桜
【写真 下(右)】 新河岸川の桜
新河岸川は川越氷川神社下あたりが桜の名所で、桜のトンネルができていました。
新河岸川のそばにある、甲州武田氏ゆかりの寺院にも詣でてきました。
■ 至誠山 成就院 眞行寺
川越市宮元町1-2
真宗大谷派(お東)
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第15番
※真宗寺院につき、おそらく御朱印は不授与かと思います。


開基は武田信玄公の妹、眞行尼(八重姫)。
八重姫は戦乱のなかで若くして出家し、甲斐で真言古義の草庵を結んで成就院至誠眞行尼と号されたといいます。
信玄公の正室、三条の方の妹・如春尼は本願寺第11世・顕如上人の正室で、眞行尼はこの縁で一時石山本願寺に入られたとも伝わります。
寺伝(*)によると、甲斐に帰国後も戦乱はやまず、天文二十二年(1553年)眞行尼は戦乱を避け、武田一門の岩崎兵庫、若山主計を伴って上吉田村(東松山の北)に移住。川島虫塚に移られ、永禄二年(1559年)川越に入って草庵を開かれ、天正元年(1573年)至誠山 成就院 眞行寺を創建されました。
眞行尼が甲斐を出られた天文二十二年(1553年)は、晴信公、駿河の今川義元公、相模の北条氏康公の甲相駿三国同盟が結ばれる前年で、信玄公の妹君がこの時期にわざわざ他国の武州に入られた理由については、いろいろな説が展開されているようです。
眞行尼が川越で草庵を結ばれた永禄二年(1559年)は信玄公出家と同年、眞行寺創建の天正元年(1573年)は信玄公逝去の年で、信玄公とのふかいゆかりが感じられます。
天正十年(1582年)、第二世として武田勝頼公の次男靖清(幼名:靖千代、善西大師)が入られ、この時に本願寺末寺になったとされます。
天正十年は天目山の戦いで甲州武田氏が滅亡した年で、勝頼公には出家した男子が伝わるので、こちらが靖清(靖千代)かもしれません。
以来、武田ゆかりの者は川越を中心に街道沿いに落居したとされます。
山内はさほど広くはないですが、基壇の上に入母屋造銅板葺流れ向拝の端正な本堂。
向拝扉と大棟には、黄金色の武田菱(割り菱)が燦然と輝いていました。
*)寺伝:「平成 小江戸川越 古寺巡礼」(百瀬千又氏編纂)より
【 関連記事 】
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
【 BGM 】
■ ひらひら ひらら - ClariS
よくはわからんが、なにかと話題の多い女子2人組ユニット。
佐久間 誠氏作の流麗なメロに、フェミニンで透明感あるハイトーンが冴えわたる名曲。
花曇りで写真はいまいちでしたが、桜はほぼ満開でした。


【写真 上(左)】 喜多院の桜-1
【写真 下(右)】 喜多院の桜-2
喜多院は桜の名所で、それなりに人出はありました。ただ、新型コロナ禍の前に比べるとやはり寂しい感じです。


【写真 上(左)】 三芳野神社の桜
【写真 下(右)】 新河岸川の桜
新河岸川は川越氷川神社下あたりが桜の名所で、桜のトンネルができていました。
新河岸川のそばにある、甲州武田氏ゆかりの寺院にも詣でてきました。
■ 至誠山 成就院 眞行寺
川越市宮元町1-2
真宗大谷派(お東)
御本尊:阿弥陀如来
札所:小江戸川越古寺巡礼第15番
※真宗寺院につき、おそらく御朱印は不授与かと思います。


開基は武田信玄公の妹、眞行尼(八重姫)。
八重姫は戦乱のなかで若くして出家し、甲斐で真言古義の草庵を結んで成就院至誠眞行尼と号されたといいます。
信玄公の正室、三条の方の妹・如春尼は本願寺第11世・顕如上人の正室で、眞行尼はこの縁で一時石山本願寺に入られたとも伝わります。
寺伝(*)によると、甲斐に帰国後も戦乱はやまず、天文二十二年(1553年)眞行尼は戦乱を避け、武田一門の岩崎兵庫、若山主計を伴って上吉田村(東松山の北)に移住。川島虫塚に移られ、永禄二年(1559年)川越に入って草庵を開かれ、天正元年(1573年)至誠山 成就院 眞行寺を創建されました。
眞行尼が甲斐を出られた天文二十二年(1553年)は、晴信公、駿河の今川義元公、相模の北条氏康公の甲相駿三国同盟が結ばれる前年で、信玄公の妹君がこの時期にわざわざ他国の武州に入られた理由については、いろいろな説が展開されているようです。
眞行尼が川越で草庵を結ばれた永禄二年(1559年)は信玄公出家と同年、眞行寺創建の天正元年(1573年)は信玄公逝去の年で、信玄公とのふかいゆかりが感じられます。
天正十年(1582年)、第二世として武田勝頼公の次男靖清(幼名:靖千代、善西大師)が入られ、この時に本願寺末寺になったとされます。
天正十年は天目山の戦いで甲州武田氏が滅亡した年で、勝頼公には出家した男子が伝わるので、こちらが靖清(靖千代)かもしれません。
以来、武田ゆかりの者は川越を中心に街道沿いに落居したとされます。
山内はさほど広くはないですが、基壇の上に入母屋造銅板葺流れ向拝の端正な本堂。
向拝扉と大棟には、黄金色の武田菱(割り菱)が燦然と輝いていました。
*)寺伝:「平成 小江戸川越 古寺巡礼」(百瀬千又氏編纂)より
【 関連記事 】
■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)
■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)
【 BGM 】
■ ひらひら ひらら - ClariS
よくはわからんが、なにかと話題の多い女子2人組ユニット。
佐久間 誠氏作の流麗なメロに、フェミニンで透明感あるハイトーンが冴えわたる名曲。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)から
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)へ
9.荏柄天神社(えがらてんじんしゃ)
公式Web
神奈川県神社庁Web
鎌倉市二階堂74
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社、旧二階堂村鎮守
元別当:一乗院(真言宗)
古くは荏柄山天満宮とも呼ばれ、福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮とともに「三古天神社」と称される名社です。
公式Webの社伝などによると、「長治元年(1104年)、一天俄かにかきくもり、雷雨とともに黒袍の束帯姿の天神画像が天降り、神験をおそれた里人等が降臨の地に社殿を建てその画像を納め祀った」ことが縁起と伝わります。
治承四年(1180年)、大蔵の地に幕府を開いた頼朝公は鬼門に位置する当社を崇敬し社殿を造立。
以後、歴代将軍家をはじめ幕府の尊社として篤く崇敬され、「吾妻鏡」には将軍頼家公が大江広元を奉幣使として派遣し、菅公御神忌三百年祭が盛大に催されたことなどが記されています。
また、建保元年(1212年)、渋河兼守が冤罪を訴え当社に献じた和歌十首が源實朝公の知るところとなり罪を許された逸話は、和歌の徳を語るもの、天神信仰の一端を示すものとして広く知られています。
『新編相模國風土記稿』には「勧請ノ年代ヲ伝ヘス。頼朝初メテ大蔵ノ地ニ舘造営ノ時。当社ヲ以テ鬼門ノ鎮神トス。」「本社中央ニ菅公束帯ノ座像ヲ置キ 右方ニ天拝山祈誓ノ立像。左方ニ本地佛十一面観音ノ像ヲ置ク」とあります。
また、『新編鎌倉志』には「当社は頼朝卿の時より有なり。しかれども祝融の災ひ度々にて、記録不伝、文献微とすべきなし。別当を一乗院と云ふ。真言宗、洛の東寺の末寺なり。(略)天神自画像【大日記】に、長享元年(1487年)、荏柄天神、駿河より還座、自筆の書画とあり。是ならん。」とあり、中世は神仏習合の天神社として信仰を集めたことがうかがわれます。
↑の「荏柄天神、駿河より還座」については、「神奈川県神社庁Web」に記載がありました。
康正元年(1455年)、今川範忠が公方足利成氏を攻めて鎌倉へ入った際、当社の社壇は破られ御神体は駿河へ持ち去られましたが、その後御神体は自ら当社へ戻られたと伝わります。
中世~江戸期には足利、北条、豊臣、徳川各武家の尊崇篤く、維新後の明治6年には村内の熊野社を合祀し二階堂村の鎮守として村社に列格。
学問の神、努力を重ねるものを助ける神として、人々の尊崇を集めて今日に至ります。
境内は国指定史跡、本殿は国指定重要文化財に指定されており、弘長元年(1261年)銘の「木造天神坐像及び木造天神立像」も国重要文化財に指定されるほか、多くの社宝を所蔵します。
----------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 社号標
金沢街道大御堂橋あたりに一之鳥居があり、ここから長い参道がはじまります。
途中、2本の松が交差するところに社号標とその先に鳥居。
そこからはもう、境内下の急な参道階段が見えています。
階段上のちょっとかわった様式の門は、不勉強につき名称はわかりません。
門扉に天満宮の神紋「星梅鉢紋」と頭上には「天満宮」の扁額。
門をくぐると正面が朱塗りの拝殿。向かって左に授与所、社務所、かっぱ筆塚、絵筆塚。
右手には手水舎と御輿庫、そして樹齢900年とも伝わる御神木の大銀杏がならびます。


拝殿は入母屋造銅板葺平入りで朱塗りの身舎や斗栱があざやか。
拝殿扉にも「星梅鉢紋」が彫りこまれています。
国の重要文化財の本殿は、拝殿裏手に回り込めないので詳細不明ですが、「文化遺産オンライン」によると、「寛永元年(1624年)の鶴岡八幡宮若宮の社殿造営に伴い若宮の旧本殿を移築して再興されたもの」で、「若宮は正和五年(1315年)再建後維持されていることから、この本殿(の造営)は14世紀に遡る可能性がある」とのこと。
三間社流造銅板葺。「三間社としては大型で,内外ともに細部の意匠も優れ,中世鎌倉における社殿の様式を知る上で欠くことのできない貴重な遺構」とのことです。
御朱印は授与所にて拝受。御朱印帳も頒布されています。
〔 荏柄天神社の御朱印 〕

10.鎌倉宮(かまくらぐう)
公式Web
鎌倉市Web
鎌倉市二階堂154
御祭神:護良親王
旧社格:官幣中社
元別当:
近代社格制度で官幣中社に列格した、すこぶる社格の高い神社です。
一般に官幣社は天皇・皇族を祀るなど朝廷にご縁のある神社が多く列格していますが、こちらも御祭神を大塔宮護良親王とし、明治2年に明治天皇の勅命をうけて創設されています。
護良親王は後醍醐天皇の皇子で、6歳の頃、尊雲法親王として天台宗三門跡の梶井門跡(三千院門跡)に入られました。
幼少より英邁の才をあらわされて衆徒の尊崇を集め、20歳の若さで天台座主に就かれて「大塔宮」と呼ばれ、のちに還俗され「護良親王」となられました。
その優れた機知や武芸については、数々の逸話が伝わります。
元弘元年(1331年)8月、後醍醐天皇が鎌倉幕府討幕の元弘の乱を起こされますが、事前に漏洩し大塔宮は逮捕され死罪が申し渡されました。
その後脱出され、山城国鷲峰山~奈良・般若寺~吉野郡十津川村~吉野と潜伏・転戦、元弘三年(1333年)のはじめ、吉野金峯山城にて千早城の楠木正成と呼応して挙兵されました。
吉野山で二階堂道蘊率いる幕府軍と戦い、劣勢となった護良親王が自害されようとしたとき、村上義光公が身代わりとなり、親王は高野山へ落ちられました。
その後も護良親王は鎌倉が敵であることを示す令旨を撒布され、倒幕をうながされました。
元弘三年(1333年)4月、隠岐島を脱出された後醍醐天皇は船上山で挙兵され、同年5月後醍醐天皇の綸旨に呼応した足利、赤松、千種らの軍勢が京の六波羅探題を攻め落とし、新田義貞は鎌倉を攻めて、ここに鎌倉幕府は倒れました。
倒幕後の建武の新政のなか、後醍醐天皇と護良親王は確執を生じ、護良親王は政治の表舞台には立たれませんでした。
その理由についてはいろいろと推測されていますが、ここでは触れません。
護良親王はははやくから足利高氏(尊氏)の野心を見抜かれ、度々高氏(尊氏)を牽制されて、御自らを「将軍宮」と称されました。
後醍醐帝も一旦は護良親王の主張を容れられ、元弘三年(1333年)6月護良親王は征夷大将軍、兵部卿に任ぜられました。
護良親王は征夷大将軍任命後も足利勢への警戒を解かれず、北畠親房・顕家と連携して足利勢に備えました。
一方、後醍醐天皇の側室・阿野廉子は子の義良親王(後の後村上天皇)を帝にするため、護良親王とは一貫して対立関係にあり、足利勢とは利害が一致していました。
護良親王は後醍醐帝に対して帝位簒奪の誤解を釈明され、尊氏追討の勅語を願うも容れられず、ついに征夷大将軍を解かれて、建武元年(1334年)11月鎌倉へ送られ、尊氏の弟直義の監視のもと、二階堂の東光寺内の土牢に幽閉の御身となられたといいます。
(現在の鎌倉宮の社地は、当時は東光寺の山内でした。)
建武二年(1335年)、北条高時の遺児、時行を奉じた中先代の乱が勃発し、勢力を増しました。
前征夷大将軍の護良親王と北条執権高時の遺児・時行が結べば、護良宮将軍と執権・時行の名分が整ってしまうため、これをおそれた直義の命を受けた淵辺義博により襲われ、護良親王は格闘の末にその生涯を閉じられました。
享年は数え28歳と伝わります。
護良親王が予想された通り、その後足利尊氏は勢力を拡大し、朝廷を圧倒して足利(室町)幕府を開くことになりました。
護良親王は、側室である藤原保藤の娘の南御方に弔われたと伝わります。
護良親王と南御方の子は鎌倉の妙法寺を開いた日叡で、父母の菩提を弔いました。
また、護良親王の妹が後醍醐帝の命を受け東慶寺五代目の尼僧として入られ、用堂尼と呼ばれました。
東慶寺には、護良親王の幼名「尊雲法親王」が書かれた位牌が祀られているといいます。
護良親王の公式の墓所は、鎌倉宮から少しはなれた二階堂の理智光寺跡とみられています。
『新編相模國風土記稿』の東光寺蹟の項に「覚園寺南東ノ山麓ニアリテ。醫王山ト号セシ。一宇ノ禅刹ナリ。
蚤 (はや)ク廃シテ。(略)建武二年五月。足利直義。大塔宮ヲ東國ニ下シ。土牢ヲ構ヘテ禁獄セシハ即此所ナリ。淵邊伊賀守義博直義ノ内命ヲ承ケ。爰(ここ)に来タリテ宮ヲ弑ス。」「大塔宮土籠跡 前(東光寺)寺廃跡北方ノ山腹ニアリ。窟中二段ニ穿テリ。是建武二年直義大塔宮ヲ禁獄セシ所ト」とあります。
『新編相模國風土記稿』の理智光寺の項には「護良親王石塔。山上ニアリ。建武二年当寺住僧宮ノ屍ヲ埋葬セシ所ナリ。佛壇ニ碑アリ。没故兵部卿親王尊霊ト記シ。寺伝ニ此位牌始浄光明寺ノ慈恩院ニアリシヲ。当寺ニアルヘキモノナリトテ。慈恩院ヨリ送レリト云フ。」とあります。
また、『新編鎌倉志』には「大塔宮の土籠は、覚園寺の南東、二階堂村山の麓に有。(略)【太平記】に、建武元年5月3日、大塔宮を、足利直義うけ取、鎌倉ヘ下し奉て、二階堂谷に土籠を塗てぞ置参せける。後に●起に及て直義、淵邊伊賀守義博直義に命じて云、始終●とならせらるべきは、兵部卿親王也。御邊は急ぎ薬師谷馳帰て、宮を刺殺し●せよと下知せられければ、義博畏て承候とて建武二年七月二十三日に弑し奉る。(略)理致光院の長老、葬禮の事営むとあり。則ち此所なり。石塔は理智光寺の山上にあり。」とあります。
護良親王には、雛鶴姫という寵姫がおられたと伝わります。
雛鶴姫についてはいろいろな説があり、都留市資料では「北畠親房の娘」とされています。
雛鶴姫は護良親王の首級を奉じて京(十津川村とも)に向かう途中、山梨県上野原市無生野で哀しい最後を遂げられたという伝承があります。
冨士山下宮小室浅間神社にも護良親王所縁の伝承があり、郡内~富士五湖地方には親王所縁の史跡や神社がいくつか存在します。
山梨県上野原市無生野の「無生野の大念仏」は、護良親王と雛鶴姫を追善供養するために始まったと伝えられています。
なお、「大塔宮」の読みですが、鎌倉宮では「おおとうのみや」としているようですが、地元の通称は「だいとうのみや」のようです。
----------
(以下「左」「右」はすべて「本殿に向かって左・右」を示します。)


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 露天
金沢街道「岐れ道」交差点から北東に入る道の正面に御鎮座です。
この道は鎌倉宮社頭に向けて一直線に伸び、さながら参道のようです。
大がかりな鳥居を構える堂々たる社頭は、さすがに官幣中社の風格。
鳥居はおそらく外宮宗鳥居系で、貫の突き抜けがなく、柱の転び(傾斜)もほとんどなく、笠木は反増。
笠木・島木ともに両端が斜下となる襷墨(たすきずみ)で、島木に花菱紋らしき紋所を3つ置いています。
特徴的なのは鳥居の色で、笠木のみ朱であとは白色です。
Webでひいたところ、社務所で質問された奇特な方がおられました。(→ こちらの記事(ブログ「歩きましょ」様))
こちらの記事によると「赤は『赤誠』(せきせい)といって、『誠』を表し、白は『純粋』を表している」(以上引用)とのことです。
また、このブログには「岐れ道」からの直線道について「明治天皇が行幸するために作られ、ぴったり400mとのこと。」という貴重な情報も載せられていました。
Web情報おそるべし。
鳥居前右に「官幣中社鎌倉宮」の社号標と灯籠一対。鳥居の先の境内には玉垣がめぐらされ、鳥居傍の河津桜はかなり有名なようです。
こちらは鎌倉にはめずらしく広い駐車場があります。
大型バスも停められ、歴史的にも重要な名社なので、秋など修学旅行生がたくさん入り込みます。
参道はゆるい左カーブを描き、階段先右手に立派な手水舎。
そこからさらに階段をのぼって社頭の鳥居と同系の鳥居があります。
社域の左右と社殿の背後に整った社叢を配し、おごそかな境内。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 手水舎から鳥居
手水舎の右手には、厄を落とす「厄割り石」があります。
境内のあちこちに、護良親王が兜のなかに忍ばせ御身の無事を祈られた「獅子頭守」が飾られています。
手水舎のそばには、護良親王の弟宮、征西大将軍懐良親王が「筑後川の戦い」(正平十四年(1359年))に勝利された際、両軍の犠牲者への手向けとしてお手植えされ、のちに九州から移植された「将軍梅」が植えられています。


【写真 上(左)】 将軍梅-1
【写真 下(右)】 将軍梅-2
拝殿はおそらく入母屋造銅板葺妻入で向拝を付設、身舎はなく柱のみで向拝から相の間と本殿を拝せます。
拝殿は舞台のようで舞殿を兼ねているのかもしれません。
(ちなみに秋に催される有名な薪能(たきぎのう)では、別に舞台が設けられるようです。)


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 本殿
本殿は銅板葺神明造の堂々たる社殿。棟には千木、鰹木を置いています。
拝殿右手が拝観受付で、入場すると土牢、宝物殿、御神苑などを拝観できますが、今後は社務所(授与所)が拝観受付になるかもしれません。


【写真 上(左)】 宝物殿
【写真 下(右)】 南方社と本殿


【写真 上(左)】 南方社遙拝所から土牢への道
【写真 下(右)】 土牢
拝殿右手おくに村上社が御鎮座。拝殿左手には南方社が御鎮座で、こちらはつぎにご案内します。
有料拝観ゾーンには土牢や宝物殿などがあり、護良親王所縁の史跡や宝物などを拝観できます。
御朱印は境内右手の授与所にて拝受しました。
こちらは月替わり御朱印を授与され、書置御朱印の紙質にもこだわられるなど御朱印授与に積極的です。
授与所のご対応もとても親切です。
通常御朱印はすべて両面見開きで、現在下記3パターンとなっているようです。
番号つきの見本があるので、お願いしやすいです。
1.鎌倉宮と南方社・村上社

右に「鎌倉宮」の揮毫と社印、左に「大塔宮鎌倉宮」・「摂社村上社」・「摂社南方社」の印判の御朱印。
2.南方社と村上社

鎌倉宮拝殿の向かって左右のおくに御鎮座の二社の御朱印です。
こちらの二社については、つぎでご紹介しています。
3.明治大帝と神鹿さん
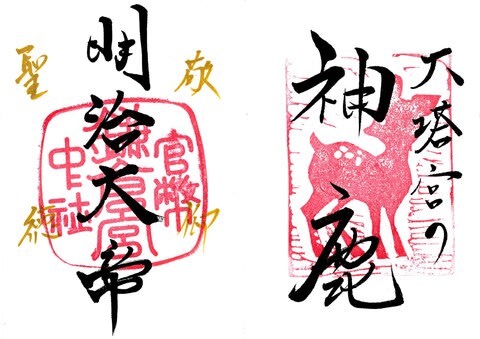
かつて鎌倉宮では鹿が「神鹿」(しんろく)として飼われていたそうで、3頭の剥製が参拝者無料休憩所に残っています。
社務所前広場の紅葉の枝などにも神鹿さんのフィギュアがいます。
「明治大帝」(明治天皇)と「神鹿」の御朱印がセットとなっている理由はわかりませんが、明治天皇の勅命により創設という由緒からの授与かと思います。
明治天皇は官幣大社で勅祭社でもある明治神宮の御祭神ですから、当然このセット御朱印の主尊格は「明治大帝」ということになるのかと。

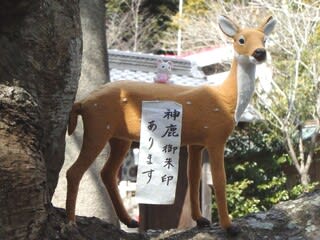
【写真 上(左)】 神鹿さん-1
【写真 下(右)】 神鹿さん-2


【写真 上(左)】 授与所前の紅葉
【写真 下(右)】 獅子頭守
11.南方社・村上社
鎌倉市二階堂154
御祭神:持明院南御方(南方社)・村上義日(義光)公(村上社)
旧社格:鎌倉宮境内社(摂社)
【南方社】(みなみのかたしゃ)
鎌倉宮の摂社で、鎌倉宮拝殿向かって左手おくの玉垣内に御鎮座です。
護良親王は、側室である藤原保藤の娘の南御方に弔われたと伝わります。
護良親王と南御方の子は鎌倉の妙法寺を開かれた日叡で、父母の菩提を弔いました。
南御方については史料が少ないようですが、いただいた由緒書によると、持明院藤原保藤卿の息女で「新按察使典待(しんあぜちのすけ)」と呼ばれ、鎌倉では常に親王の側にあって身の回りの世話をされながら、親王のお気持ちをなぐさめられたとの由。
由緒書には「別名の『鶴舞姫』にもちなみ」とあり、南御方と鶴舞姫を同一人物とされています。
また、境内掲示の由緒書には「親王のご最期にあたっては、理智光寺の長老と共に、丁寧に弔いをされました後、上洛し後醍醐天皇へ親王のご最期の仔細を報告されました。」とあります。
鎌倉宮では3月3日に「南方祭」を斉行しています。
なお、静岡県駿東郡清水町長沢の智方神社の御祭神は護良親王で、南御方所縁の神社でもあるようです。
鎌倉宮本殿よこの玉垣内に御鎮座なので、有料拝観ゾーン内の玉垣外遙拝所からの遙拝となります。
銅板葺神明造の端正な社殿です。


【写真 上(左)】 南方社遙拝所
【写真 下(右)】 南方社社殿
【村上社】(むらかみしゃ)
村上義光公は村上義日ともいい、出自は信濃源氏村上氏の流れとされ大塔宮護良親王に仕え、元弘の乱の吉野城の戦いで親王の身代わりとなり壮絶な討死を遂げられました。
左馬権頭。明治時代に従三位を追贈。
元弘三年(1333年)、二階堂勢六万の攻撃を受けて護良親王軍が拠る吉野城が落城した際、義光公とその次男の義隆は力闘ののち討死しました。
その奮戦ぶりが境内由緒書に記されているので引用します。
「村上義満公は、護良親王の忠臣にして元弘三年(1333年)正月吉野城落城の折、最早これまでと覚悟を決めた護良親王は別れの酒宴をされました。そこへ村上義光公が鎧に十六本もの矢を突き立てた凄まじい姿で駆けつけ、親王の錦の御鎧直垂をお脱ぎいただき自分が着用して『天照大御神の子孫、神武天皇より九十五代の後醍醐天皇の皇子兵部卿親王護良、逆臣の為に只今自害する有様を見て、汝らが武運尽きて腹を切らんとする時の手本とせよ』と告げて腹を一文字に掻き切り、壮絶な最期をとげ、その間に親王は、南に向かって落ちのびました。」
義光公の子の義隆も共に討ち死にを覚悟しましたが、義光公はこれを止め親王を守るよう言いつけました。
その後、義隆は親王を落ち延びさせるべく奮闘し、満身創痍となって力尽き自害したと伝わります。
村上義光公の墓と伝わる宝篋印塔が吉野蔵王堂の北西にあります。
大和高取藩士内藤景文が天明三年(1783年)に建てたとされる「村上義光忠烈碑」も同所にあります。
村上社は、厄除・病気平癒の神様として「身代りさま」と呼ばれて尊崇を集めています。
鎌倉宮拝殿の右手に御鎮座。拝殿手前には義光公のお像が御座します。
社殿は銅板葺で、おそらく神明造と思われます。


【写真 上(左)】 村上社-1
【写真 下(右)】 村上社-2
南方社と村上社の御朱印はセットで、鎌倉宮境内授与所で授与されています。

12.錦屏山 瑞泉寺(ずいせんじ)
公式Web
東国花の寺 百ヶ寺公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市二階堂710
臨済宗円覚寺派
御本尊:釋迦牟尼佛
札所:鎌倉三十三観音霊場第6番、鎌倉二十四地蔵霊場第7番、円覚寺百観音霊場第9番、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番
鎌倉宮の右脇の道を山の方に分け入ったあたりは紅葉ヶ谷(もみじがやつ)と呼ばれる谷戸で、中世いくつかの寺院がおかれました。
永福寺、理智光寺、瑞泉寺などで、もっともおくにある瑞泉寺は夢窓国師の名跡をいまに伝える古刹です。
嘉暦二年(1327年)、鎌倉幕府の幕臣、二階堂道蘊が夢窓疎石を開山として創建、当初は瑞泉院と号しました。
足利尊氏の四男、初代鎌倉公方・足利基氏が夢窓疎石に帰依して中興、寺号を瑞泉寺と改め、以後、鎌倉公方足利家の菩提寺となりました。
夢窓疎石(国師)は鎌倉時代末から南北朝時代の臨済宗の名僧で、その法統は複雑なのでここでは触れませんが、後醍醐帝から尊崇を受け「夢窓国師」の国師号を下賜、以降、七つの国師号を授与されて後世「七朝帝師」と称えられました。
足利尊氏・直義兄弟も深く帰依して『夢中問答集』などの共著を遺され、尊氏からは「仁山」、直義からは「古山」の法号を贈られました。
優れた作庭家としても名を遺され、禅庭・枯山水の完成者として知られています。
さらに、五山文学の詩人で、和歌でも勅撰和歌集に入集するなど、文学史上にも名跡を残した当代一流の文化人として、その名声はいまにつづきます。
(鎌倉時代末期から室町時代、禅刹では漢詩文学が栄えて「五山文学」と呼ばれましたが、鎌倉における拠点のひとつが瑞泉寺とされています。)
『新編相模國風土記稿』の瑞泉寺項に「圓覚寺塔頭に属ス。関東十刹ノ内第二ナリ。嘉暦二年起立ス。開山は疎石。(略)(足利)基氏逝シテ当山に葬ル。(略)天正十九年(1591年)以来。圓覚寺領ノ内ヲ配当アリ。当寺住持職ハ圓覚寺西堂ノ僧ヲモテ補セラル。(略)本尊釋迦ヲ安ス。座像七寸許。本堂ニハ当時(足利)氏満筆。大雄寶殿ノ四字ヲ扁セシト云フ。今ハ亡セリ。(略)開山堂 中央ニ開山無窓。千手観音(古昔客殿ニ 是客殿ノ本尊ナルヘシ。)右ニ基氏。左に氏満等ノ木像ヲ置ク。今堂宇破壊セシカハ此諸像ヲ本堂中ニ●置ス。座禅堂。辨天社。鐘楼。塔頭廃跡。」
「遍界一覧亭跡 本堂北方ノ高山ヲ云フ。頂上ニ亭跡アリ。嘉暦三年ノ建立ナリ。夢窓国師此亭ニシテ詩ヲ賦シ又歌ヲ詠セリ。基氏此亭ニテ櫻花紅葉等ヲ翫テ詩ヲ賦シ。又五山ノ僧徒等カ亭席ニテノ詩文書許多アリ。(略)元禄ノ頃。水戸光圀卿ヨリ。山上ニ一堂ヲ建立アリテ千手観音ヲ安ス。」
また、『新編鎌倉志』には「関東十刹の内なり。源基氏の建立なり(略)開山は、夢窓国師、本尊は釋迦(作者不知)」とあります。
『新編鎌倉志』は徳川光圀公の編纂とされ、光圀公は「遍界一覧亭」を再建されたとも伝わります。
瑞泉寺は、康暦年間(1379-1381年)に準十刹第三位、至徳四年(1387年)には関東十刹に列せられた名刹です。
関東十刹(じっせつ)とは五山制度に基づく臨済宗の寺格で、五山に次ぎ、諸山の上に位置します。
時代により変遷し、その総数は中世末までに60に達したとみられています。
『禅宗寺院の官寺機構』(今枝愛真氏著/PDF)によると、康暦二年(1380年)、足利義満公は十刹および準十刹の16ヶ寺を定めています。
〔十刹〕
・等持寺(等持院) 京都市北区 天龍寺派 足利氏菩提寺
・禅興寺 鎌倉市山ノ内/廃寺 臨済宗 執権北条時頼私邸の最明寺を再興
・聖福寺 福岡市博多区 妙心寺派 「扶桑最初禅窟」
・東勝寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条氏菩提寺
・(鎌倉)万寿寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条貞時の創建
・長楽寺 群馬県太田市 天台宗 世良田義季(得川義季)の創建
・真如寺 京都市北区 相国寺派 開山は無学祖元
・北禅寺(山城国安国寺) 京都市四条大宮 臨済宗 足利直義の開基
・(豊後)万寿寺 大分市 妙心寺派 開山は直翁智侃和尚(足利泰氏の子)
・清見寺 静岡市清水区 妙心寺派
〔準十刹〕
・臨川寺 京都市右京区 天龍寺派 開山は夢窓疎石
・寶幢寺 京都市嵯峨北堀町/廃寺 臨済宗 足利義満の開基
・瑞泉寺 鎌倉市二階堂 円覚寺派 開山は夢窓疎石
・普門寺 京都市東山区/廃寺 臨済宗
・寶林寺 兵庫県上郡町 真言宗 赤松則祐の開基
・国清寺 静岡県伊豆の国市韮山町 円覚寺派 上杉憲顕の開基
瑞泉寺は鎌倉公方の菩提寺、夢窓派禅林の拠点として栄えましたが、第五代鎌倉公方足利成氏の代、永享十一年(1439年)の永享の乱により鎌倉公方が廃止(以降、古河公方として存続)されるとともに寺勢は衰え、夢窓派禅林の拠点も円覚寺黄梅院に移りました。
江戸時代に入ると徳川家のもとで復興が始まり、元禄二年(1689年)には水戸光圀公により堂宇が再建されています。
鎌倉三十三観音霊場第6番、鎌倉二十四地蔵霊場第7番、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番、円覚寺百観音霊場第9番の4つの現役霊場の札所を兼ね、歴史の香り高い花の寺ということもあって、多くの拝観客を集めています。
----------
瑞泉寺には数台の駐車スペースはありますが、アクセス道が狭いのと、鎌倉宮あたりからの道行きは見どころも多いので、徒歩でのアクセスをおすすめします。


【写真 上(左)】 アプローチの標識
【写真 下(右)】 永福寺跡
鎌倉宮の社頭前をクランクして、二階堂川の谷沿いを山手に歩いていきます。
右手に折れて理智光寺橋をわたると、理智光寺跡で護良親王の墓所があります。
左手は源頼朝公建立の永福寺跡。
奥州攻めで亡くなった武将等の鎮魂のため平泉の中尊寺二階大堂などを模して建立され、建久五年(1194年)に二階堂・薬師堂・阿弥陀堂の三堂が完成し、鎌倉幕府から手厚く保護されましたが、応永十二年(1405年)に焼失し、以後は再建されませんでした。
史跡に指定され発掘調査が行われて、現在旧山内の一部が一般公開されています。
瑞泉寺の創建は嘉暦二年(1327年)なので、創建時には永福寺は現存していたことになります。


【写真 上(左)】 通玄橋
【写真 下(右)】 総門手前の参道
まっすぐ進むとすぐに通仙橋。
二階堂川はここから左手に折れて北方に向かいますが、瑞泉寺への道は通仙橋を渡ってまっすぐです。
通仙橋の先で道は狭まり、左手に寺号標が建っています。


【写真 上(左)】 総門
【写真 下(右)】 総門の寺号標
その先には総門。切妻屋根の四脚門で、本瓦葺はさすがに名刹の風格。
その先は道が広くなって、すぐに拝観受付です。


【写真 上(左)】 拝観受付
【写真 下(右)】 左手が梅林
瑞泉寺は100本以上もの梅が咲く梅の寺で、拝観受付先の左手は梅林となっています。
梅林を過ぎると参道階段のはじまりです。


【写真 上(左)】 階段登り口
【写真 下(右)】 参道階段
「史跡瑞泉寺境内 名勝瑞泉寺庭園」「夢窓国師古道場」の石碑、うっそうと茂る木々、苔むした階段など、俄然雰囲気が出てきます。
すこしくのぼると分岐があり、左手が急階段、右手は緩い階段となっています。
左手がいわゆる「男坂」、右手が「女坂」かと思われ、ふたつの階段は山門前で合流します。


【写真 上(左)】 吉田松陰先生碑
【写真 下(右)】 山門手前
山門左手前には吉田松陰留跡碑があります。
瑞泉寺は文学の寺でもあり、山崎方代、吉野秀雄、久保田万太郎、高浜虚子、大宅壮一などの歌碑・句碑・評論碑などが山内各所に置かれています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内図
山門は切妻屋根本瓦葺の薬医門ないし四脚門で、左右に塀をまわしています。


【写真 上(左)】 山門先から山内
【写真 下(右)】 左手に鐘楼


【写真 上(左)】 茶室と庫裡
【写真 下(右)】 茶室の円窓
山門をくぐると一挙に視界が開けます。
右手に庫裡と、おそらくは書院、客殿。手前の円窓を配した瀟洒な建物は、茶室・保寿庵(非公開)と思われます。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 庫裡
その左奥の楼閣は本堂。背後の小高い山(錦屏山)のうえに徧界一覧亭が望めます。
よく手入れされた趣きある庭園で、本堂向かって左手は梅林となっています。


【写真 上(左)】 山内-2
【写真 下(右)】 徧界一覧亭の屋根
「瑞泉寺境内」として、国の史跡に指定されています。
ほとんどの堂宇や建物は大正以降の再建ないし、ほかからの移築とみられますがいずれも趣きがあります。
瑞泉寺は古来「瑞泉蘭若」と称されました。自身が気に入って住まう庵、というほどの意味だそうです。


【写真 上(左)】 紫陽花
【写真 下(右)】 紅葉ヶ谷の紅葉
瑞泉寺は花の寺で、早春の梅のほか、春のミツマタ・藤、夏の紫陽花、桔梗、秋の冬櫻、紅葉、冬の水仙、椿など、四季おりおりの花を楽しむことができます。


【写真 上(左)】 本堂(大雄寶殿)-1
【写真 下(右)】 本堂(大雄寶殿)-2
本堂(佛殿)は、「大雄寶殿」(だいゆうほうでん)と称します。
大雄寶殿(だいゆう(だいおう)ほうでん)とは、主に禅宗寺院で金堂、本堂に相当する建物の称号です。
「大雄」とは釈尊のことで、ふつう御本尊が釈迦無尼仏(釈迦如来)の場合に使われます。
とくに黄檗宗でよく使われ、黄檗宗寺院では「大雄寶殿」の御朱印を授与されるところが少なくありません。
瑞泉寺の御本尊の御朱印も「大雄寶殿」の揮毫で授与されます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂前掲示
すこしく話が逸れますが、御朱印には閣号や殿号が揮毫されることがよくあります。
その多くは、尊格の御座す堂宇をあらわすもので、閣(殿)号はそのまま尊格に結びつきます。
たとえば、無量寿(光)殿-阿弥陀如来、瑠璃殿-薬師如来、大悲殿(閣)-観世音菩薩、圓通閣(殿)-観世音菩薩、大光普照殿-十一面観世音菩薩、阿遮羅殿-不動明王などで、大雄寶殿も大雄=釈尊なのでこの系統です。
本堂(大雄寶殿)は銅板葺二層の楼閣建築(高楼)で、上層は露盤に宝珠を置いた宝形造と思われます。
向拝柱はなく、古色を帯びた桟唐戸。
小壁の連子と端部を垂直に切り落とした花頭窓が直線的に呼応して、すこぶる端正なイメージの身舎まわりです。
桟唐戸おくの格子戸が少し開かれ、堂内諸尊をうかがうことができます。
本堂前の掲示によると、堂内中央に御本尊の釋迦牟尼佛、向かって左に阿弥陀如来と千手観世音菩薩、右には開山夢想国師の坐像が奉安されています。
千手観世音菩薩は「水戸黄門様奉安」とあり、『新編相模國風土記稿』には「遍界一覧亭跡 元禄ノ頃。水戸光圀卿ヨリ。山上ニ一堂ヲ建立アリテ千手観音ヲ安ス。」とあるので、もとは徧界一覧亭に奉安されていた尊像とみられます。
こちらは鎌倉市指定有形文化財です。
ふたつの観音霊場の札所本尊で、尊像の左手には「大本山円覚寺百観音霊場第九番札所」の札所板が掲げられています。
木造夢窓国師坐像は、南北朝期の頂相彫刻(禅師の肖像彫刻)の秀作として国の重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 斜め左からの本堂
【写真 下(右)】 本堂から地蔵堂
本堂(大雄寶殿)を右手に回り込んだおくのお堂はおそらく地蔵堂。
「どこもく地蔵尊」が奉安され、鎌倉二十四地蔵霊場第7番の札所となっています。
桟瓦葺宝形造の均整のとれたお堂で、向拝桟唐戸が開かれているのでお地蔵さまを拝めます。


【写真 上(左)】 地蔵堂-1
【写真 下(右)】 地蔵堂-2
堂前に札所板&説明板が掲げられていました。
むかし扇ガ谷の辻にお地蔵様が御座し、こちらの堂守が貧窮して逃亡を図ったところ夢にこちらの地蔵尊があらわれ「どこも どこも」と宣いました。堂守が八幡宮寺の僧にこの意味を問うたところ「これ、どこも苦なり」(人生はどこに逃げ出しても苦労はついてまわるもの)と諭され、堂守は改心して一生堂守として地蔵尊を守り通したといいます。
立像の地蔵尊で、堂内には諸佛が奉安されています。


【写真 上(左)】 庭園-1
【写真 下(右)】 庭園-2
地蔵堂の右手、本堂の裏手が国名勝の「瑞泉寺庭園」です。
夢窓疎石の築とされる岩盤を掘り込んで作られた禅宗様庭園で、(方丈)書院庭園の起源ともみられています。
また、鎌倉にのこる鎌倉時代の唯一の庭園とされています。
この庭園をみたとき、やや粗削りな、というかどこかとりとめのない印象を受けました。
復興庭園ということもあるのでしょうが、どうやらその理由は作庭の意図にありそうです。
公式Webには「北隅の岩盤の正面に大きな洞(天女洞)を彫って水月観の道場となし、東側には坐禅のための窟(坐禅窟・葆光窟)を穿ちました。天女洞の前には池を掘って貯清池と名づけ、池の中央は掘り残して島となしました。水流を東側に辿れば滝壺に水分け石があり、垂直の岩壁は滝、その上方をさらに辿れば貯水槽があって天水を蓄え、要に応じて水を落とせば坐雨観泉となるしつらえ」とあります。
つまり、道場としての庭園であり、(手前(堂宇側)から鑑賞するのではなく)座禅を組む洞側からの景色をふまえて作庭されているようなのです。
この点は、公式Webの天女洞からの景色の写真をみるとよくわかります。


【写真 上(左)】 庭園-3
【写真 下(右)】 庭園-4
本堂の背後、錦屏山の山上にある徧界一覧亭(昭和10年再建)への道は整っているようですが、現在は非公開。
亭からの眺望は、相模湾を池と見立てる壮大なものといわれます。
中興開基・足利基氏の御廟は、本堂右手おくの高みにあるようです。
御朱印は庫裡にて拝受できます。
すこぶるご親切なご対応で、頭が下がります。
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第6番、鎌倉二十四地蔵霊場第7番、円覚寺百観音霊場第9番、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番の4つ。
別に御本尊(大雄寶殿)の御朱印を授与されているので、御朱印は5種となります。
無申告の場合、おそらく御本尊「大雄寶殿」の授与になるかと思います。
〔 御本尊・大雄寶殿の御朱印 〕
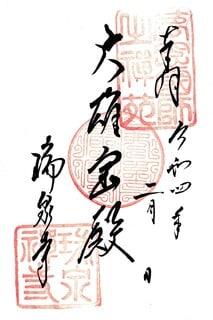
本堂(大雄寶殿)に御座す釋迦牟尼佛です。
本堂内には「大雄寶殿」の扁額が掲げられています。
鎌倉三十三観音霊場第6番の札所本尊は、本堂(大雄寶殿)に御座す千手観世音菩薩です。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉二十四地蔵霊場第7番の札所本尊は、地蔵堂に御座す「どこもく地蔵尊」です。
堂前には札所板&縁起書も掲げられています。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
円覚寺百観音霊場第9番札所本尊は、本堂(大雄寶殿)に御座す千手観世音菩薩です。
堂内尊像よこに札所板が掲げられています。
〔 円覚寺百観音霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳
こちらは、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番(鎌倉4番)の札所でもあります。
御朱印尊格は「大雄寶殿」なので、札所本尊は御本尊・釋迦牟尼佛と思われます。
花種は梅で花期は1月中旬~3月上旬です。
〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)へつづく。
【 BGM 】
■ One Reason - milet
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka
■ symphonia - kalafina
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)へつづく。
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)へ
9.荏柄天神社(えがらてんじんしゃ)
公式Web
神奈川県神社庁Web
鎌倉市二階堂74
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社、旧二階堂村鎮守
元別当:一乗院(真言宗)
古くは荏柄山天満宮とも呼ばれ、福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮とともに「三古天神社」と称される名社です。
公式Webの社伝などによると、「長治元年(1104年)、一天俄かにかきくもり、雷雨とともに黒袍の束帯姿の天神画像が天降り、神験をおそれた里人等が降臨の地に社殿を建てその画像を納め祀った」ことが縁起と伝わります。
治承四年(1180年)、大蔵の地に幕府を開いた頼朝公は鬼門に位置する当社を崇敬し社殿を造立。
以後、歴代将軍家をはじめ幕府の尊社として篤く崇敬され、「吾妻鏡」には将軍頼家公が大江広元を奉幣使として派遣し、菅公御神忌三百年祭が盛大に催されたことなどが記されています。
また、建保元年(1212年)、渋河兼守が冤罪を訴え当社に献じた和歌十首が源實朝公の知るところとなり罪を許された逸話は、和歌の徳を語るもの、天神信仰の一端を示すものとして広く知られています。
『新編相模國風土記稿』には「勧請ノ年代ヲ伝ヘス。頼朝初メテ大蔵ノ地ニ舘造営ノ時。当社ヲ以テ鬼門ノ鎮神トス。」「本社中央ニ菅公束帯ノ座像ヲ置キ 右方ニ天拝山祈誓ノ立像。左方ニ本地佛十一面観音ノ像ヲ置ク」とあります。
また、『新編鎌倉志』には「当社は頼朝卿の時より有なり。しかれども祝融の災ひ度々にて、記録不伝、文献微とすべきなし。別当を一乗院と云ふ。真言宗、洛の東寺の末寺なり。(略)天神自画像【大日記】に、長享元年(1487年)、荏柄天神、駿河より還座、自筆の書画とあり。是ならん。」とあり、中世は神仏習合の天神社として信仰を集めたことがうかがわれます。
↑の「荏柄天神、駿河より還座」については、「神奈川県神社庁Web」に記載がありました。
康正元年(1455年)、今川範忠が公方足利成氏を攻めて鎌倉へ入った際、当社の社壇は破られ御神体は駿河へ持ち去られましたが、その後御神体は自ら当社へ戻られたと伝わります。
中世~江戸期には足利、北条、豊臣、徳川各武家の尊崇篤く、維新後の明治6年には村内の熊野社を合祀し二階堂村の鎮守として村社に列格。
学問の神、努力を重ねるものを助ける神として、人々の尊崇を集めて今日に至ります。
境内は国指定史跡、本殿は国指定重要文化財に指定されており、弘長元年(1261年)銘の「木造天神坐像及び木造天神立像」も国重要文化財に指定されるほか、多くの社宝を所蔵します。
----------


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 社号標
金沢街道大御堂橋あたりに一之鳥居があり、ここから長い参道がはじまります。
途中、2本の松が交差するところに社号標とその先に鳥居。
そこからはもう、境内下の急な参道階段が見えています。
階段上のちょっとかわった様式の門は、不勉強につき名称はわかりません。
門扉に天満宮の神紋「星梅鉢紋」と頭上には「天満宮」の扁額。
門をくぐると正面が朱塗りの拝殿。向かって左に授与所、社務所、かっぱ筆塚、絵筆塚。
右手には手水舎と御輿庫、そして樹齢900年とも伝わる御神木の大銀杏がならびます。


拝殿は入母屋造銅板葺平入りで朱塗りの身舎や斗栱があざやか。
拝殿扉にも「星梅鉢紋」が彫りこまれています。
国の重要文化財の本殿は、拝殿裏手に回り込めないので詳細不明ですが、「文化遺産オンライン」によると、「寛永元年(1624年)の鶴岡八幡宮若宮の社殿造営に伴い若宮の旧本殿を移築して再興されたもの」で、「若宮は正和五年(1315年)再建後維持されていることから、この本殿(の造営)は14世紀に遡る可能性がある」とのこと。
三間社流造銅板葺。「三間社としては大型で,内外ともに細部の意匠も優れ,中世鎌倉における社殿の様式を知る上で欠くことのできない貴重な遺構」とのことです。
御朱印は授与所にて拝受。御朱印帳も頒布されています。
〔 荏柄天神社の御朱印 〕

10.鎌倉宮(かまくらぐう)
公式Web
鎌倉市Web
鎌倉市二階堂154
御祭神:護良親王
旧社格:官幣中社
元別当:
近代社格制度で官幣中社に列格した、すこぶる社格の高い神社です。
一般に官幣社は天皇・皇族を祀るなど朝廷にご縁のある神社が多く列格していますが、こちらも御祭神を大塔宮護良親王とし、明治2年に明治天皇の勅命をうけて創設されています。
護良親王は後醍醐天皇の皇子で、6歳の頃、尊雲法親王として天台宗三門跡の梶井門跡(三千院門跡)に入られました。
幼少より英邁の才をあらわされて衆徒の尊崇を集め、20歳の若さで天台座主に就かれて「大塔宮」と呼ばれ、のちに還俗され「護良親王」となられました。
その優れた機知や武芸については、数々の逸話が伝わります。
元弘元年(1331年)8月、後醍醐天皇が鎌倉幕府討幕の元弘の乱を起こされますが、事前に漏洩し大塔宮は逮捕され死罪が申し渡されました。
その後脱出され、山城国鷲峰山~奈良・般若寺~吉野郡十津川村~吉野と潜伏・転戦、元弘三年(1333年)のはじめ、吉野金峯山城にて千早城の楠木正成と呼応して挙兵されました。
吉野山で二階堂道蘊率いる幕府軍と戦い、劣勢となった護良親王が自害されようとしたとき、村上義光公が身代わりとなり、親王は高野山へ落ちられました。
その後も護良親王は鎌倉が敵であることを示す令旨を撒布され、倒幕をうながされました。
元弘三年(1333年)4月、隠岐島を脱出された後醍醐天皇は船上山で挙兵され、同年5月後醍醐天皇の綸旨に呼応した足利、赤松、千種らの軍勢が京の六波羅探題を攻め落とし、新田義貞は鎌倉を攻めて、ここに鎌倉幕府は倒れました。
倒幕後の建武の新政のなか、後醍醐天皇と護良親王は確執を生じ、護良親王は政治の表舞台には立たれませんでした。
その理由についてはいろいろと推測されていますが、ここでは触れません。
護良親王はははやくから足利高氏(尊氏)の野心を見抜かれ、度々高氏(尊氏)を牽制されて、御自らを「将軍宮」と称されました。
後醍醐帝も一旦は護良親王の主張を容れられ、元弘三年(1333年)6月護良親王は征夷大将軍、兵部卿に任ぜられました。
護良親王は征夷大将軍任命後も足利勢への警戒を解かれず、北畠親房・顕家と連携して足利勢に備えました。
一方、後醍醐天皇の側室・阿野廉子は子の義良親王(後の後村上天皇)を帝にするため、護良親王とは一貫して対立関係にあり、足利勢とは利害が一致していました。
護良親王は後醍醐帝に対して帝位簒奪の誤解を釈明され、尊氏追討の勅語を願うも容れられず、ついに征夷大将軍を解かれて、建武元年(1334年)11月鎌倉へ送られ、尊氏の弟直義の監視のもと、二階堂の東光寺内の土牢に幽閉の御身となられたといいます。
(現在の鎌倉宮の社地は、当時は東光寺の山内でした。)
建武二年(1335年)、北条高時の遺児、時行を奉じた中先代の乱が勃発し、勢力を増しました。
前征夷大将軍の護良親王と北条執権高時の遺児・時行が結べば、護良宮将軍と執権・時行の名分が整ってしまうため、これをおそれた直義の命を受けた淵辺義博により襲われ、護良親王は格闘の末にその生涯を閉じられました。
享年は数え28歳と伝わります。
護良親王が予想された通り、その後足利尊氏は勢力を拡大し、朝廷を圧倒して足利(室町)幕府を開くことになりました。
護良親王は、側室である藤原保藤の娘の南御方に弔われたと伝わります。
護良親王と南御方の子は鎌倉の妙法寺を開いた日叡で、父母の菩提を弔いました。
また、護良親王の妹が後醍醐帝の命を受け東慶寺五代目の尼僧として入られ、用堂尼と呼ばれました。
東慶寺には、護良親王の幼名「尊雲法親王」が書かれた位牌が祀られているといいます。
護良親王の公式の墓所は、鎌倉宮から少しはなれた二階堂の理智光寺跡とみられています。
『新編相模國風土記稿』の東光寺蹟の項に「覚園寺南東ノ山麓ニアリテ。醫王山ト号セシ。一宇ノ禅刹ナリ。
蚤 (はや)ク廃シテ。(略)建武二年五月。足利直義。大塔宮ヲ東國ニ下シ。土牢ヲ構ヘテ禁獄セシハ即此所ナリ。淵邊伊賀守義博直義ノ内命ヲ承ケ。爰(ここ)に来タリテ宮ヲ弑ス。」「大塔宮土籠跡 前(東光寺)寺廃跡北方ノ山腹ニアリ。窟中二段ニ穿テリ。是建武二年直義大塔宮ヲ禁獄セシ所ト」とあります。
『新編相模國風土記稿』の理智光寺の項には「護良親王石塔。山上ニアリ。建武二年当寺住僧宮ノ屍ヲ埋葬セシ所ナリ。佛壇ニ碑アリ。没故兵部卿親王尊霊ト記シ。寺伝ニ此位牌始浄光明寺ノ慈恩院ニアリシヲ。当寺ニアルヘキモノナリトテ。慈恩院ヨリ送レリト云フ。」とあります。
また、『新編鎌倉志』には「大塔宮の土籠は、覚園寺の南東、二階堂村山の麓に有。(略)【太平記】に、建武元年5月3日、大塔宮を、足利直義うけ取、鎌倉ヘ下し奉て、二階堂谷に土籠を塗てぞ置参せける。後に●起に及て直義、淵邊伊賀守義博直義に命じて云、始終●とならせらるべきは、兵部卿親王也。御邊は急ぎ薬師谷馳帰て、宮を刺殺し●せよと下知せられければ、義博畏て承候とて建武二年七月二十三日に弑し奉る。(略)理致光院の長老、葬禮の事営むとあり。則ち此所なり。石塔は理智光寺の山上にあり。」とあります。
護良親王には、雛鶴姫という寵姫がおられたと伝わります。
雛鶴姫についてはいろいろな説があり、都留市資料では「北畠親房の娘」とされています。
雛鶴姫は護良親王の首級を奉じて京(十津川村とも)に向かう途中、山梨県上野原市無生野で哀しい最後を遂げられたという伝承があります。
冨士山下宮小室浅間神社にも護良親王所縁の伝承があり、郡内~富士五湖地方には親王所縁の史跡や神社がいくつか存在します。
山梨県上野原市無生野の「無生野の大念仏」は、護良親王と雛鶴姫を追善供養するために始まったと伝えられています。
なお、「大塔宮」の読みですが、鎌倉宮では「おおとうのみや」としているようですが、地元の通称は「だいとうのみや」のようです。
----------
(以下「左」「右」はすべて「本殿に向かって左・右」を示します。)


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 露天
金沢街道「岐れ道」交差点から北東に入る道の正面に御鎮座です。
この道は鎌倉宮社頭に向けて一直線に伸び、さながら参道のようです。
大がかりな鳥居を構える堂々たる社頭は、さすがに官幣中社の風格。
鳥居はおそらく外宮宗鳥居系で、貫の突き抜けがなく、柱の転び(傾斜)もほとんどなく、笠木は反増。
笠木・島木ともに両端が斜下となる襷墨(たすきずみ)で、島木に花菱紋らしき紋所を3つ置いています。
特徴的なのは鳥居の色で、笠木のみ朱であとは白色です。
Webでひいたところ、社務所で質問された奇特な方がおられました。(→ こちらの記事(ブログ「歩きましょ」様))
こちらの記事によると「赤は『赤誠』(せきせい)といって、『誠』を表し、白は『純粋』を表している」(以上引用)とのことです。
また、このブログには「岐れ道」からの直線道について「明治天皇が行幸するために作られ、ぴったり400mとのこと。」という貴重な情報も載せられていました。
Web情報おそるべし。
鳥居前右に「官幣中社鎌倉宮」の社号標と灯籠一対。鳥居の先の境内には玉垣がめぐらされ、鳥居傍の河津桜はかなり有名なようです。
こちらは鎌倉にはめずらしく広い駐車場があります。
大型バスも停められ、歴史的にも重要な名社なので、秋など修学旅行生がたくさん入り込みます。
参道はゆるい左カーブを描き、階段先右手に立派な手水舎。
そこからさらに階段をのぼって社頭の鳥居と同系の鳥居があります。
社域の左右と社殿の背後に整った社叢を配し、おごそかな境内。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 手水舎から鳥居
手水舎の右手には、厄を落とす「厄割り石」があります。
境内のあちこちに、護良親王が兜のなかに忍ばせ御身の無事を祈られた「獅子頭守」が飾られています。
手水舎のそばには、護良親王の弟宮、征西大将軍懐良親王が「筑後川の戦い」(正平十四年(1359年))に勝利された際、両軍の犠牲者への手向けとしてお手植えされ、のちに九州から移植された「将軍梅」が植えられています。


【写真 上(左)】 将軍梅-1
【写真 下(右)】 将軍梅-2
拝殿はおそらく入母屋造銅板葺妻入で向拝を付設、身舎はなく柱のみで向拝から相の間と本殿を拝せます。
拝殿は舞台のようで舞殿を兼ねているのかもしれません。
(ちなみに秋に催される有名な薪能(たきぎのう)では、別に舞台が設けられるようです。)


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 本殿
本殿は銅板葺神明造の堂々たる社殿。棟には千木、鰹木を置いています。
拝殿右手が拝観受付で、入場すると土牢、宝物殿、御神苑などを拝観できますが、今後は社務所(授与所)が拝観受付になるかもしれません。


【写真 上(左)】 宝物殿
【写真 下(右)】 南方社と本殿


【写真 上(左)】 南方社遙拝所から土牢への道
【写真 下(右)】 土牢
拝殿右手おくに村上社が御鎮座。拝殿左手には南方社が御鎮座で、こちらはつぎにご案内します。
有料拝観ゾーンには土牢や宝物殿などがあり、護良親王所縁の史跡や宝物などを拝観できます。
御朱印は境内右手の授与所にて拝受しました。
こちらは月替わり御朱印を授与され、書置御朱印の紙質にもこだわられるなど御朱印授与に積極的です。
授与所のご対応もとても親切です。
通常御朱印はすべて両面見開きで、現在下記3パターンとなっているようです。
番号つきの見本があるので、お願いしやすいです。
1.鎌倉宮と南方社・村上社

右に「鎌倉宮」の揮毫と社印、左に「大塔宮鎌倉宮」・「摂社村上社」・「摂社南方社」の印判の御朱印。
2.南方社と村上社

鎌倉宮拝殿の向かって左右のおくに御鎮座の二社の御朱印です。
こちらの二社については、つぎでご紹介しています。
3.明治大帝と神鹿さん
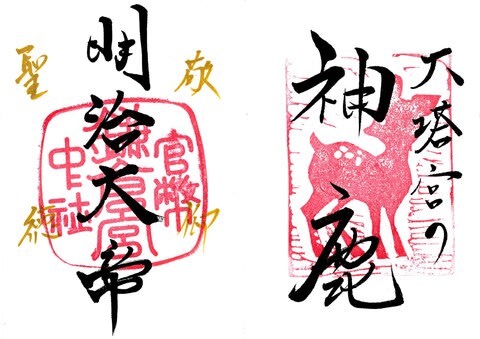
かつて鎌倉宮では鹿が「神鹿」(しんろく)として飼われていたそうで、3頭の剥製が参拝者無料休憩所に残っています。
社務所前広場の紅葉の枝などにも神鹿さんのフィギュアがいます。
「明治大帝」(明治天皇)と「神鹿」の御朱印がセットとなっている理由はわかりませんが、明治天皇の勅命により創設という由緒からの授与かと思います。
明治天皇は官幣大社で勅祭社でもある明治神宮の御祭神ですから、当然このセット御朱印の主尊格は「明治大帝」ということになるのかと。

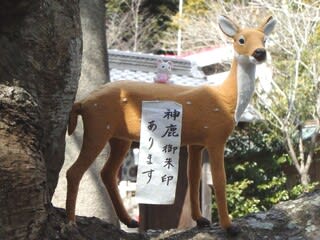
【写真 上(左)】 神鹿さん-1
【写真 下(右)】 神鹿さん-2


【写真 上(左)】 授与所前の紅葉
【写真 下(右)】 獅子頭守
11.南方社・村上社
鎌倉市二階堂154
御祭神:持明院南御方(南方社)・村上義日(義光)公(村上社)
旧社格:鎌倉宮境内社(摂社)
【南方社】(みなみのかたしゃ)
鎌倉宮の摂社で、鎌倉宮拝殿向かって左手おくの玉垣内に御鎮座です。
護良親王は、側室である藤原保藤の娘の南御方に弔われたと伝わります。
護良親王と南御方の子は鎌倉の妙法寺を開かれた日叡で、父母の菩提を弔いました。
南御方については史料が少ないようですが、いただいた由緒書によると、持明院藤原保藤卿の息女で「新按察使典待(しんあぜちのすけ)」と呼ばれ、鎌倉では常に親王の側にあって身の回りの世話をされながら、親王のお気持ちをなぐさめられたとの由。
由緒書には「別名の『鶴舞姫』にもちなみ」とあり、南御方と鶴舞姫を同一人物とされています。
また、境内掲示の由緒書には「親王のご最期にあたっては、理智光寺の長老と共に、丁寧に弔いをされました後、上洛し後醍醐天皇へ親王のご最期の仔細を報告されました。」とあります。
鎌倉宮では3月3日に「南方祭」を斉行しています。
なお、静岡県駿東郡清水町長沢の智方神社の御祭神は護良親王で、南御方所縁の神社でもあるようです。
鎌倉宮本殿よこの玉垣内に御鎮座なので、有料拝観ゾーン内の玉垣外遙拝所からの遙拝となります。
銅板葺神明造の端正な社殿です。


【写真 上(左)】 南方社遙拝所
【写真 下(右)】 南方社社殿
【村上社】(むらかみしゃ)
村上義光公は村上義日ともいい、出自は信濃源氏村上氏の流れとされ大塔宮護良親王に仕え、元弘の乱の吉野城の戦いで親王の身代わりとなり壮絶な討死を遂げられました。
左馬権頭。明治時代に従三位を追贈。
元弘三年(1333年)、二階堂勢六万の攻撃を受けて護良親王軍が拠る吉野城が落城した際、義光公とその次男の義隆は力闘ののち討死しました。
その奮戦ぶりが境内由緒書に記されているので引用します。
「村上義満公は、護良親王の忠臣にして元弘三年(1333年)正月吉野城落城の折、最早これまでと覚悟を決めた護良親王は別れの酒宴をされました。そこへ村上義光公が鎧に十六本もの矢を突き立てた凄まじい姿で駆けつけ、親王の錦の御鎧直垂をお脱ぎいただき自分が着用して『天照大御神の子孫、神武天皇より九十五代の後醍醐天皇の皇子兵部卿親王護良、逆臣の為に只今自害する有様を見て、汝らが武運尽きて腹を切らんとする時の手本とせよ』と告げて腹を一文字に掻き切り、壮絶な最期をとげ、その間に親王は、南に向かって落ちのびました。」
義光公の子の義隆も共に討ち死にを覚悟しましたが、義光公はこれを止め親王を守るよう言いつけました。
その後、義隆は親王を落ち延びさせるべく奮闘し、満身創痍となって力尽き自害したと伝わります。
村上義光公の墓と伝わる宝篋印塔が吉野蔵王堂の北西にあります。
大和高取藩士内藤景文が天明三年(1783年)に建てたとされる「村上義光忠烈碑」も同所にあります。
村上社は、厄除・病気平癒の神様として「身代りさま」と呼ばれて尊崇を集めています。
鎌倉宮拝殿の右手に御鎮座。拝殿手前には義光公のお像が御座します。
社殿は銅板葺で、おそらく神明造と思われます。


【写真 上(左)】 村上社-1
【写真 下(右)】 村上社-2
南方社と村上社の御朱印はセットで、鎌倉宮境内授与所で授与されています。

12.錦屏山 瑞泉寺(ずいせんじ)
公式Web
東国花の寺 百ヶ寺公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市二階堂710
臨済宗円覚寺派
御本尊:釋迦牟尼佛
札所:鎌倉三十三観音霊場第6番、鎌倉二十四地蔵霊場第7番、円覚寺百観音霊場第9番、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番
鎌倉宮の右脇の道を山の方に分け入ったあたりは紅葉ヶ谷(もみじがやつ)と呼ばれる谷戸で、中世いくつかの寺院がおかれました。
永福寺、理智光寺、瑞泉寺などで、もっともおくにある瑞泉寺は夢窓国師の名跡をいまに伝える古刹です。
嘉暦二年(1327年)、鎌倉幕府の幕臣、二階堂道蘊が夢窓疎石を開山として創建、当初は瑞泉院と号しました。
足利尊氏の四男、初代鎌倉公方・足利基氏が夢窓疎石に帰依して中興、寺号を瑞泉寺と改め、以後、鎌倉公方足利家の菩提寺となりました。
夢窓疎石(国師)は鎌倉時代末から南北朝時代の臨済宗の名僧で、その法統は複雑なのでここでは触れませんが、後醍醐帝から尊崇を受け「夢窓国師」の国師号を下賜、以降、七つの国師号を授与されて後世「七朝帝師」と称えられました。
足利尊氏・直義兄弟も深く帰依して『夢中問答集』などの共著を遺され、尊氏からは「仁山」、直義からは「古山」の法号を贈られました。
優れた作庭家としても名を遺され、禅庭・枯山水の完成者として知られています。
さらに、五山文学の詩人で、和歌でも勅撰和歌集に入集するなど、文学史上にも名跡を残した当代一流の文化人として、その名声はいまにつづきます。
(鎌倉時代末期から室町時代、禅刹では漢詩文学が栄えて「五山文学」と呼ばれましたが、鎌倉における拠点のひとつが瑞泉寺とされています。)
『新編相模國風土記稿』の瑞泉寺項に「圓覚寺塔頭に属ス。関東十刹ノ内第二ナリ。嘉暦二年起立ス。開山は疎石。(略)(足利)基氏逝シテ当山に葬ル。(略)天正十九年(1591年)以来。圓覚寺領ノ内ヲ配当アリ。当寺住持職ハ圓覚寺西堂ノ僧ヲモテ補セラル。(略)本尊釋迦ヲ安ス。座像七寸許。本堂ニハ当時(足利)氏満筆。大雄寶殿ノ四字ヲ扁セシト云フ。今ハ亡セリ。(略)開山堂 中央ニ開山無窓。千手観音(古昔客殿ニ 是客殿ノ本尊ナルヘシ。)右ニ基氏。左に氏満等ノ木像ヲ置ク。今堂宇破壊セシカハ此諸像ヲ本堂中ニ●置ス。座禅堂。辨天社。鐘楼。塔頭廃跡。」
「遍界一覧亭跡 本堂北方ノ高山ヲ云フ。頂上ニ亭跡アリ。嘉暦三年ノ建立ナリ。夢窓国師此亭ニシテ詩ヲ賦シ又歌ヲ詠セリ。基氏此亭ニテ櫻花紅葉等ヲ翫テ詩ヲ賦シ。又五山ノ僧徒等カ亭席ニテノ詩文書許多アリ。(略)元禄ノ頃。水戸光圀卿ヨリ。山上ニ一堂ヲ建立アリテ千手観音ヲ安ス。」
また、『新編鎌倉志』には「関東十刹の内なり。源基氏の建立なり(略)開山は、夢窓国師、本尊は釋迦(作者不知)」とあります。
『新編鎌倉志』は徳川光圀公の編纂とされ、光圀公は「遍界一覧亭」を再建されたとも伝わります。
瑞泉寺は、康暦年間(1379-1381年)に準十刹第三位、至徳四年(1387年)には関東十刹に列せられた名刹です。
関東十刹(じっせつ)とは五山制度に基づく臨済宗の寺格で、五山に次ぎ、諸山の上に位置します。
時代により変遷し、その総数は中世末までに60に達したとみられています。
『禅宗寺院の官寺機構』(今枝愛真氏著/PDF)によると、康暦二年(1380年)、足利義満公は十刹および準十刹の16ヶ寺を定めています。
〔十刹〕
・等持寺(等持院) 京都市北区 天龍寺派 足利氏菩提寺
・禅興寺 鎌倉市山ノ内/廃寺 臨済宗 執権北条時頼私邸の最明寺を再興
・聖福寺 福岡市博多区 妙心寺派 「扶桑最初禅窟」
・東勝寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条氏菩提寺
・(鎌倉)万寿寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条貞時の創建
・長楽寺 群馬県太田市 天台宗 世良田義季(得川義季)の創建
・真如寺 京都市北区 相国寺派 開山は無学祖元
・北禅寺(山城国安国寺) 京都市四条大宮 臨済宗 足利直義の開基
・(豊後)万寿寺 大分市 妙心寺派 開山は直翁智侃和尚(足利泰氏の子)
・清見寺 静岡市清水区 妙心寺派
〔準十刹〕
・臨川寺 京都市右京区 天龍寺派 開山は夢窓疎石
・寶幢寺 京都市嵯峨北堀町/廃寺 臨済宗 足利義満の開基
・瑞泉寺 鎌倉市二階堂 円覚寺派 開山は夢窓疎石
・普門寺 京都市東山区/廃寺 臨済宗
・寶林寺 兵庫県上郡町 真言宗 赤松則祐の開基
・国清寺 静岡県伊豆の国市韮山町 円覚寺派 上杉憲顕の開基
瑞泉寺は鎌倉公方の菩提寺、夢窓派禅林の拠点として栄えましたが、第五代鎌倉公方足利成氏の代、永享十一年(1439年)の永享の乱により鎌倉公方が廃止(以降、古河公方として存続)されるとともに寺勢は衰え、夢窓派禅林の拠点も円覚寺黄梅院に移りました。
江戸時代に入ると徳川家のもとで復興が始まり、元禄二年(1689年)には水戸光圀公により堂宇が再建されています。
鎌倉三十三観音霊場第6番、鎌倉二十四地蔵霊場第7番、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番、円覚寺百観音霊場第9番の4つの現役霊場の札所を兼ね、歴史の香り高い花の寺ということもあって、多くの拝観客を集めています。
----------
瑞泉寺には数台の駐車スペースはありますが、アクセス道が狭いのと、鎌倉宮あたりからの道行きは見どころも多いので、徒歩でのアクセスをおすすめします。


【写真 上(左)】 アプローチの標識
【写真 下(右)】 永福寺跡
鎌倉宮の社頭前をクランクして、二階堂川の谷沿いを山手に歩いていきます。
右手に折れて理智光寺橋をわたると、理智光寺跡で護良親王の墓所があります。
左手は源頼朝公建立の永福寺跡。
奥州攻めで亡くなった武将等の鎮魂のため平泉の中尊寺二階大堂などを模して建立され、建久五年(1194年)に二階堂・薬師堂・阿弥陀堂の三堂が完成し、鎌倉幕府から手厚く保護されましたが、応永十二年(1405年)に焼失し、以後は再建されませんでした。
史跡に指定され発掘調査が行われて、現在旧山内の一部が一般公開されています。
瑞泉寺の創建は嘉暦二年(1327年)なので、創建時には永福寺は現存していたことになります。


【写真 上(左)】 通玄橋
【写真 下(右)】 総門手前の参道
まっすぐ進むとすぐに通仙橋。
二階堂川はここから左手に折れて北方に向かいますが、瑞泉寺への道は通仙橋を渡ってまっすぐです。
通仙橋の先で道は狭まり、左手に寺号標が建っています。


【写真 上(左)】 総門
【写真 下(右)】 総門の寺号標
その先には総門。切妻屋根の四脚門で、本瓦葺はさすがに名刹の風格。
その先は道が広くなって、すぐに拝観受付です。


【写真 上(左)】 拝観受付
【写真 下(右)】 左手が梅林
瑞泉寺は100本以上もの梅が咲く梅の寺で、拝観受付先の左手は梅林となっています。
梅林を過ぎると参道階段のはじまりです。


【写真 上(左)】 階段登り口
【写真 下(右)】 参道階段
「史跡瑞泉寺境内 名勝瑞泉寺庭園」「夢窓国師古道場」の石碑、うっそうと茂る木々、苔むした階段など、俄然雰囲気が出てきます。
すこしくのぼると分岐があり、左手が急階段、右手は緩い階段となっています。
左手がいわゆる「男坂」、右手が「女坂」かと思われ、ふたつの階段は山門前で合流します。


【写真 上(左)】 吉田松陰先生碑
【写真 下(右)】 山門手前
山門左手前には吉田松陰留跡碑があります。
瑞泉寺は文学の寺でもあり、山崎方代、吉野秀雄、久保田万太郎、高浜虚子、大宅壮一などの歌碑・句碑・評論碑などが山内各所に置かれています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山内図
山門は切妻屋根本瓦葺の薬医門ないし四脚門で、左右に塀をまわしています。


【写真 上(左)】 山門先から山内
【写真 下(右)】 左手に鐘楼


【写真 上(左)】 茶室と庫裡
【写真 下(右)】 茶室の円窓
山門をくぐると一挙に視界が開けます。
右手に庫裡と、おそらくは書院、客殿。手前の円窓を配した瀟洒な建物は、茶室・保寿庵(非公開)と思われます。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 庫裡
その左奥の楼閣は本堂。背後の小高い山(錦屏山)のうえに徧界一覧亭が望めます。
よく手入れされた趣きある庭園で、本堂向かって左手は梅林となっています。


【写真 上(左)】 山内-2
【写真 下(右)】 徧界一覧亭の屋根
「瑞泉寺境内」として、国の史跡に指定されています。
ほとんどの堂宇や建物は大正以降の再建ないし、ほかからの移築とみられますがいずれも趣きがあります。
瑞泉寺は古来「瑞泉蘭若」と称されました。自身が気に入って住まう庵、というほどの意味だそうです。


【写真 上(左)】 紫陽花
【写真 下(右)】 紅葉ヶ谷の紅葉
瑞泉寺は花の寺で、早春の梅のほか、春のミツマタ・藤、夏の紫陽花、桔梗、秋の冬櫻、紅葉、冬の水仙、椿など、四季おりおりの花を楽しむことができます。


【写真 上(左)】 本堂(大雄寶殿)-1
【写真 下(右)】 本堂(大雄寶殿)-2
本堂(佛殿)は、「大雄寶殿」(だいゆうほうでん)と称します。
大雄寶殿(だいゆう(だいおう)ほうでん)とは、主に禅宗寺院で金堂、本堂に相当する建物の称号です。
「大雄」とは釈尊のことで、ふつう御本尊が釈迦無尼仏(釈迦如来)の場合に使われます。
とくに黄檗宗でよく使われ、黄檗宗寺院では「大雄寶殿」の御朱印を授与されるところが少なくありません。
瑞泉寺の御本尊の御朱印も「大雄寶殿」の揮毫で授与されます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂前掲示
すこしく話が逸れますが、御朱印には閣号や殿号が揮毫されることがよくあります。
その多くは、尊格の御座す堂宇をあらわすもので、閣(殿)号はそのまま尊格に結びつきます。
たとえば、無量寿(光)殿-阿弥陀如来、瑠璃殿-薬師如来、大悲殿(閣)-観世音菩薩、圓通閣(殿)-観世音菩薩、大光普照殿-十一面観世音菩薩、阿遮羅殿-不動明王などで、大雄寶殿も大雄=釈尊なのでこの系統です。
本堂(大雄寶殿)は銅板葺二層の楼閣建築(高楼)で、上層は露盤に宝珠を置いた宝形造と思われます。
向拝柱はなく、古色を帯びた桟唐戸。
小壁の連子と端部を垂直に切り落とした花頭窓が直線的に呼応して、すこぶる端正なイメージの身舎まわりです。
桟唐戸おくの格子戸が少し開かれ、堂内諸尊をうかがうことができます。
本堂前の掲示によると、堂内中央に御本尊の釋迦牟尼佛、向かって左に阿弥陀如来と千手観世音菩薩、右には開山夢想国師の坐像が奉安されています。
千手観世音菩薩は「水戸黄門様奉安」とあり、『新編相模國風土記稿』には「遍界一覧亭跡 元禄ノ頃。水戸光圀卿ヨリ。山上ニ一堂ヲ建立アリテ千手観音ヲ安ス。」とあるので、もとは徧界一覧亭に奉安されていた尊像とみられます。
こちらは鎌倉市指定有形文化財です。
ふたつの観音霊場の札所本尊で、尊像の左手には「大本山円覚寺百観音霊場第九番札所」の札所板が掲げられています。
木造夢窓国師坐像は、南北朝期の頂相彫刻(禅師の肖像彫刻)の秀作として国の重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 斜め左からの本堂
【写真 下(右)】 本堂から地蔵堂
本堂(大雄寶殿)を右手に回り込んだおくのお堂はおそらく地蔵堂。
「どこもく地蔵尊」が奉安され、鎌倉二十四地蔵霊場第7番の札所となっています。
桟瓦葺宝形造の均整のとれたお堂で、向拝桟唐戸が開かれているのでお地蔵さまを拝めます。


【写真 上(左)】 地蔵堂-1
【写真 下(右)】 地蔵堂-2
堂前に札所板&説明板が掲げられていました。
むかし扇ガ谷の辻にお地蔵様が御座し、こちらの堂守が貧窮して逃亡を図ったところ夢にこちらの地蔵尊があらわれ「どこも どこも」と宣いました。堂守が八幡宮寺の僧にこの意味を問うたところ「これ、どこも苦なり」(人生はどこに逃げ出しても苦労はついてまわるもの)と諭され、堂守は改心して一生堂守として地蔵尊を守り通したといいます。
立像の地蔵尊で、堂内には諸佛が奉安されています。


【写真 上(左)】 庭園-1
【写真 下(右)】 庭園-2
地蔵堂の右手、本堂の裏手が国名勝の「瑞泉寺庭園」です。
夢窓疎石の築とされる岩盤を掘り込んで作られた禅宗様庭園で、(方丈)書院庭園の起源ともみられています。
また、鎌倉にのこる鎌倉時代の唯一の庭園とされています。
この庭園をみたとき、やや粗削りな、というかどこかとりとめのない印象を受けました。
復興庭園ということもあるのでしょうが、どうやらその理由は作庭の意図にありそうです。
公式Webには「北隅の岩盤の正面に大きな洞(天女洞)を彫って水月観の道場となし、東側には坐禅のための窟(坐禅窟・葆光窟)を穿ちました。天女洞の前には池を掘って貯清池と名づけ、池の中央は掘り残して島となしました。水流を東側に辿れば滝壺に水分け石があり、垂直の岩壁は滝、その上方をさらに辿れば貯水槽があって天水を蓄え、要に応じて水を落とせば坐雨観泉となるしつらえ」とあります。
つまり、道場としての庭園であり、(手前(堂宇側)から鑑賞するのではなく)座禅を組む洞側からの景色をふまえて作庭されているようなのです。
この点は、公式Webの天女洞からの景色の写真をみるとよくわかります。


【写真 上(左)】 庭園-3
【写真 下(右)】 庭園-4
本堂の背後、錦屏山の山上にある徧界一覧亭(昭和10年再建)への道は整っているようですが、現在は非公開。
亭からの眺望は、相模湾を池と見立てる壮大なものといわれます。
中興開基・足利基氏の御廟は、本堂右手おくの高みにあるようです。
御朱印は庫裡にて拝受できます。
すこぶるご親切なご対応で、頭が下がります。
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第6番、鎌倉二十四地蔵霊場第7番、円覚寺百観音霊場第9番、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番の4つ。
別に御本尊(大雄寶殿)の御朱印を授与されているので、御朱印は5種となります。
無申告の場合、おそらく御本尊「大雄寶殿」の授与になるかと思います。
〔 御本尊・大雄寶殿の御朱印 〕
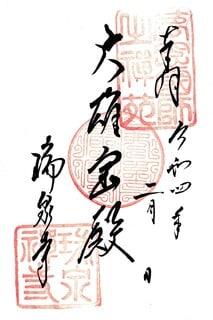
本堂(大雄寶殿)に御座す釋迦牟尼佛です。
本堂内には「大雄寶殿」の扁額が掲げられています。
鎌倉三十三観音霊場第6番の札所本尊は、本堂(大雄寶殿)に御座す千手観世音菩薩です。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉二十四地蔵霊場第7番の札所本尊は、地蔵堂に御座す「どこもく地蔵尊」です。
堂前には札所板&縁起書も掲げられています。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
円覚寺百観音霊場第9番札所本尊は、本堂(大雄寶殿)に御座す千手観世音菩薩です。
堂内尊像よこに札所板が掲げられています。
〔 円覚寺百観音霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳
こちらは、東国花の寺百ヶ寺霊場第96番(鎌倉4番)の札所でもあります。
御朱印尊格は「大雄寶殿」なので、札所本尊は御本尊・釋迦牟尼佛と思われます。
花種は梅で花期は1月中旬~3月上旬です。
〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)へつづく。
【 BGM 】
■ One Reason - milet
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka
■ symphonia - kalafina
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)へつづく。
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第10番 長谷山 蔵春院(ぞうしゅんいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報サイト
伊豆の国市田京949-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡


第10番蔵春院は、第9番澄楽寺からほど近い田京(たきょう)の地にあります。
寺伝には、「関東管領足利持氏は、時の将軍足利義教公に反抗し自ら鎌倉将軍と名乗ったため幕府は追討を計り、持氏の家臣である上杉憲実に討伐の命を下した。憲実はやむなく持氏を鎌倉永安寺に攻めて自害させたが、憲実は主君を死に追いやったことを悔い管領職を譲って出家。主君の菩提を弔うため寺院建立を決意し、多福院(大仁町白山堂)に止錫中の春屋宗能禅師を尋ねて懇請し、白山堂の豪氏宮内五左ヱ門の協力を得て今の地に(永享十一年(1439年))長谷山蔵春院を建立」とあります。
↑の出来事は「永享の乱」と思われるので、Wikipediaなどで「永享の乱」をひくと、やや異なった内容があるのでとりまとめてみます。↓
永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏は前関東管領上杉憲実と対立し、憲実を支持した将軍足利義教公は足利満直、駿河守護今川範忠、上杉持房・教朝らを出兵させた。
持氏軍は敗れ、持氏は鎌倉に引く途中で憲実の家宰・長尾忠政に憲実・義教との折衝を依頼、鎌倉称名寺で出家し永安寺に幽閉された。
憲実は持氏の助命を懇願したが義教公は許さず、憲実に持氏の追討を命じたため憲実はやむなく永安寺を攻撃、持氏は自害した。(永享の乱)。
寺伝とWikipedia等で持氏と憲実の関係は若干異なりますが、「憲実は持氏の助命を懇願したもののやむなく持氏を追討」という点では符合し、憲実が持氏の菩提を弔うために蔵春院を建立、という趣意は同じかと思います。
山号、寺号は持氏の法名蔵春院殿陽山継公大禅定門によるものとされます。
憲実から寺院建立を懇請された宗能禅師が造立の際、この地に棲んでいた悪龍を鎮めたという龍神伝説が残ります。
宗能禅師は自らは開山を称せず、本師である大綱明宗大和尚を勧請して開山とし、後事を実山永秀に託して小田原最乗寺に住され第五世となりました。
『豆州志稿』には「田京村 下總州國府臺總寧寺末 本尊釋迦如 永享十一年(1439年)、上杉安房守憲実持氏
将軍ヲ追薦シ施地建寺開基トス 寺伝曰上杉憲実白山堂ノ処士宮内氏ニ●リテ創建シ足利持氏ヲ開基トスト 憲実当国ニ遁栖ノ事諸書ニ見ユ 開山大綱和尚二世春屋和尚三世実山和尚因テ三古佛道場ト称ス 実山此ニ住ム事数年 長享丁未歳(元年/1487年)示寂 実山ノ時持氏の子成氏ヨリ寺領ヲ寄スト云 持氏の古碑 法名長春院殿陽山継公大禅定門 及守佛(地蔵ノ木像長六寸手ニ寶珠ヲ持ツ)ヲ置ク 有佛殿祖師堂衆寮庫裏浴室鐘楼門 元末寺八十余ヶ寺アリ 今四十七ヶ寺ヲ有シ中本寺格也」とあり、おおむね寺伝と合致しています。
-------------------


瓦葺の楼門は三間一戸の八脚門で、上層に鐘楼を置いています。
本堂は昭和53年落慶。入母屋造桟瓦葺で降棟に照りのある勢いを感じるつくり。
向拝柱はなく向拝正面は桟唐戸で左右に花頭窓、上部に「長谷山」の山号扁額を掲げています。
本堂向かって右手前の観音堂に御座す観世音菩薩は、従前は山中にあって「長谷観音」(ちょうこくかんのん)と呼ばれ、歴代住職が石仏観音を中心に西国観音霊場より請来した三十三観音を参拝路に安置していることもあって多くの信者を集めていたそうですが、堂宇焼失により、現在はこの場所に御座されているそうです。
御朱印は庫裡にて拝受。鎌倉の影響が強い由緒を受けてか、御本尊、札所本尊ともに釈迦牟尼佛となっています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印
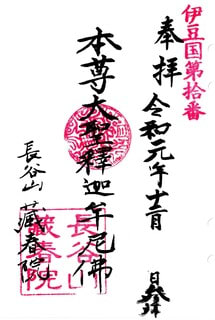
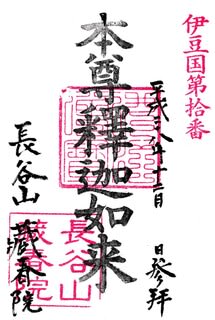
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第11番 天與山 長源寺(ちょうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市観光ガイド
伊豆の国市中492-2
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡

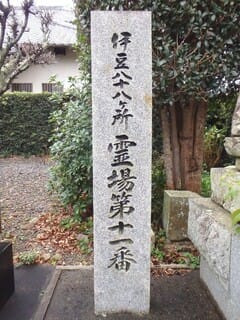
第11番長源寺は第10番蔵春院からほど近く、韮山反射炉のそばにあります。
創建年代などは不詳ですが当初真言宗であったようです。
北條早雲が榛原の石雲院より当寺に虚庵玄充を招き、当初は石雲院末でしたが虚庵が修禅寺第二世として普住したため以降は修禅寺末になったと伝わります。
『霊場めぐり』には、「信濃国の真田家の分家真田河内守信豊を開基とし、下田鵜島城主清水河内守正令唐の尽力により伽藍が整備された」とあります。
また、『豆州志稿』には「中村 修善寺修禅寺末 本尊釋迦如 開山虚庵和尚天文元年(1532年)化ス 修禅寺中興僧隆渓ヨリ開山虚庵ニ贈レル書ニ 文龜四年(1504年)三月トアリ 当時ノ創立歟」とあります。
境内には東司(トイレ)の不浄を清める烏枢沙摩明王が祀られるお堂もあり、毎年8月に例祭も執り行われています。
なお、こちらでは烏枢沙摩明王の御朱印は授与されていない模様です。
烏枢沙摩明王の御朱印はすこぶるめずらしく、筆者が拝受した範囲では伊豆市市山の金龍山 明徳寺のみです。ただし、明徳寺でもメインの御朱印は大黒天(伊豆天城七福神)と御本尊の釈迦如来で、烏枢沙摩明王の御朱印を常時授与されているかは不明です。
-------------------

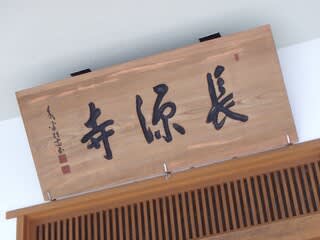
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その先で直角に向きを変えて本堂に向かいます。
車両の出入りが不便な旧地から昭和40年、当地に移転したため堂宇は新しいもの。
近代建築ながら、入母屋造本瓦葺に付設の向拝を張り出す堂々たる構えです。
蔵造りの別堂には烏枢沙摩明王が祀られています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来
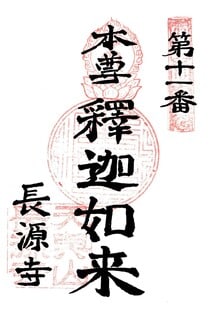
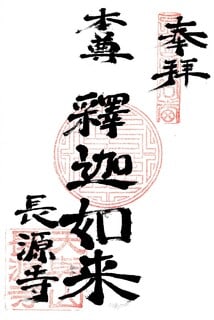
【写真 上(左)】 専用納経帳
・主印は三寶印と御寶印。御寶印の種子は「キャ」にも見えます。
【写真 下(右)】 御朱印帳
・主印は三寶印
→ ■ 韮山温泉 「天城荘」の入湯レポ
■ 第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(ちょうおんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市古奈13
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:伊豆長岡温泉七福神(福禄寿)
授与所:庫裡


第12番長温寺は、古奈温泉のほぼ中心にあり、めずらしい林号を号すお寺です。
古奈温泉といってもピンとこない方も多いかと思いますが、もともと伊豆長岡温泉の発祥は源氏山の東側の古奈温泉で、西側の伊豆長岡温泉は新興温泉地とされます。
伊豆の国市観光協会発行の「古奈温泉ものがたり」(PDF)には「古奈温泉は、平安・鎌倉時代に遡り、弘法大師が伊豆を訪れた頃の発祥と言われ、(中略)源頼朝も湯浴みをしたと伝えられています。修善寺温泉・伊豆山温泉とともに伊豆三大古湯と言われ、『吾妻鏡』には、伊豆国小名温泉や、北条古那温泉などの表記があり、南北朝時代に「古奈湯」と記されています。明治40年に西隣りの長岡地区に温泉が発見され次々に宿屋ができ、合わせて伊豆長岡温泉として発展してきました。」とあります。


【写真 上(左)】 古奈の温泉街
【写真 下(右)】 湯谷神社


【写真 上(左)】 古奈の元湯-1
【写真 下(右)】 古奈の元湯-2
長温寺のそばに御鎮座の湯谷神社は、ここから温泉が湧き出たという由緒から古奈温泉の産土神とされています。
御祭神は大己貴命、少彦名命と、温泉地の湯元神社に多く祀られる御祭神です。
湯谷神社参道脇の「古奈の元湯」はいまは枯渇してしまいましたが、いまでも遺構を残しています。
なお、長温寺は位置関係、および山号「湯谷山」から湯谷神社の元別当とも思いましたが、確実な史料は確認できておりません。
巡礼ガイドによると、仁安二年(1167年)、古奈治郎義光、同五郎義定の両将は敗戦しこの地に逃れて天野原で討死、義光が守護仏として護持していた薬師如来をこの地に祭祀したとのこと。
永禄五年(1562年)、僧・瓶山により開創、元和六年(1620年)には梅原源左衛門が再興し、真珠院第九世柳岩玄絮を請して開山し曹洞宗となったとあります。
『豆州志稿』には「古奈村 中條眞珠院末 本尊薬師 永禄五年(1562年)瓶山開林 寺伝曰初真言宗ニシテ長御寺ト号ス 御元和中梅原源左衛門再興 眞珠院九世柳岩ヲ祖トシ改宗ス 此時ヨリ長温寺ト更ムト」とあります。
-------------------


温泉街の路地のおく、こぢんまりとした境内ですが、しっとりと落ち着いた趣きがあります。
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、木鼻、蟇股、海老虹梁を備え、「薬王山」の扁額を掲げています。
御本尊、札所本尊は温泉地のお寺にふさわしく薬師如来です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。こちらは伊豆長岡温泉(源氏山)七福神の福禄寿ですが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印
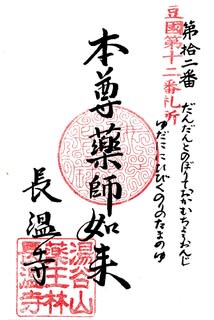
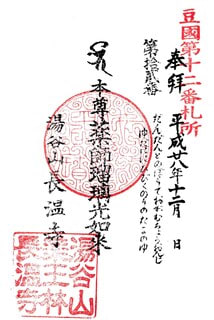
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)の入湯レポ
■ 第13番 巨徳山 北條寺(ほうじょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市観光協会Web
伊豆の国市南江間862-1
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第16番、駿豆両国横道三十三観音霊場第8番、中伊豆観音札所第20番
授与所:庫裡


北条氏の館(北条氏邸・円成寺跡)にもほど近い、源頼朝公の正室・北条政子の弟である北条義時(江間小四郎)が創建した寺院です。
義時の嫡子安千代が領内の大池で大蛇に襲われ命を落とした際に、この北條寺を墓所とし七堂伽藍を建立、運慶に仏像を作らせたといいます。
この運慶作の祈願仏が「木造阿弥陀如来座像」(桧材寄木造、国重要美術品、県文化財)として知られており、仏殿の御本尊です。
御本尊の聖観世音菩薩は南北朝期の作とされ、中国宋風の像容で県文化財に指定されています。
鎌倉極楽寺にあったものを北条政子が奉納したとも伝わります。
『豆州志稿』には「南江間村 鎌倉建長寺末 本尊観世音 本観音堂也相伝フ観音ハ天竺ヨリ唐ニ渡リ 智證大師(円珍)東帰ノ時齋来ル其佛 鎌倉(極楽寺ニ安置セシ也)ニ在リシヲ二位禅尼命シテ此ニ贈ル佛造 黒色ニシテ油ノ浮カ如シ伽羅木也ト云(略)北條義時ノ草創ニシテ観音ノ像長一尺余ト有リ 曆應貞和ノ頃(1338-1350年)寺ヲ建立ス 建長寺七十九世大雲ヲ開山トス 初実成寺ト称ス(略)境内ニ北條義時夫妻ノ墓ト云アリ 義時法名北條寺殿寛海大禅定門ト云 当村ハ其郷里ナリ」とあり、北条政子や北条義時ゆかりの名刹であることがわかります。
境内の「小四郎山」と呼ばれる丘の上には、義時夫妻の墓所があります。
ロウバイと白いヒガンバナが有名な花の寺でもあります。
-------------------

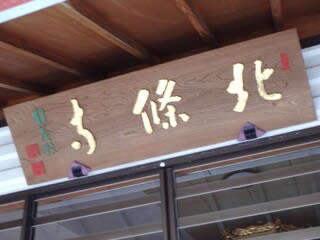
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、大棟両端に金色の鴟尾を置いています。
朱塗りの柱が効いて引き締まった印象の仏堂で、向拝に水引虹梁を置き、正面サッシュ扉の上に「北條寺」の寺号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第16番の御朱印も拝受しています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
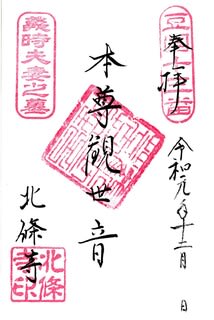

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印
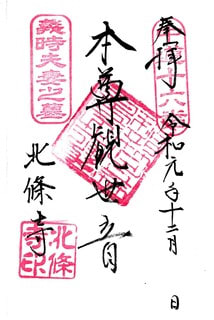
御朱印帳
■ 第14番 龍泉山 慈光院(じこういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市韮山多田937
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第11番、中伊豆観音札所第16番
授与所:庫裡


第14番慈光院は韮山市街の東の山ぎわにあります。
当初は光明遍照金剛楳(梅)林寺 槑(梅)香院と号した真言宗寺院でしたが、永正七年(1510年)曹洞宗に改宗、再興されたといいます。
永正七年の再興に際しての逸話が伝わります。
往時、このあたりに村人から恐れられた龍が住んでおり、多田入道実正(日下部乃梅原入道伊豆乃真実正とも)が、五人張の強弓をもってこれを退治しましたが、それ以来村内に悪疫が流行して村人を悩ませました。
これを龍の祟りとみた実正は龍の霊を祭り供養するために龍の戒名をつけ、弘法大師の御作と伝わる延命地蔵尊を御本尊とし、昌渓院二世菅谷宋儔を開山として請し、龍の戒名から龍泉山 慈光院と号したといいます。
『豆州志稿』には「韮山多田 南條昌渓院末 本尊阿彌陀 昌渓院二世曹谷和尚(永正十三年(1516年)取滅)應請卓錫ス 二世密栄ノ時寺号トス 此村梅原氏ノ先祖(梅原内膳実正法名牛鍬院殿弓兵多田大膳定門)蛇ヲ)射殺ス因テ寺ニ蛇足ト蛇鱗トヲ蔵ム 廃正法寺本尊観世音当寺ニ安ス」とあり、こちらでは蛇にかかわる所縁が記されています。
-------------------


本堂は入母屋造桟瓦葺で、大がかりな唐破風を張り出した向拝を置いています。
水引虹梁端部に雲形の木鼻、中備に板蟇股、身舎方に海老虹梁を配し、向拝見上げに「慈光院」の寺号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受。こちらは伊豆中道三十三観音霊場第11番でもあり、札所本尊聖観世音菩薩の御朱印も拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印
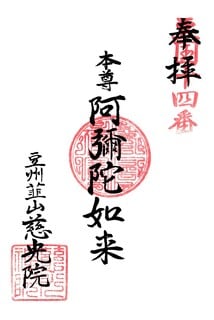

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印
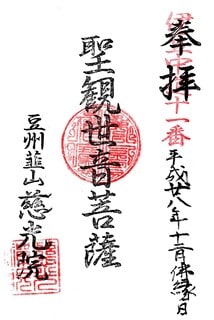
御朱印帳
→ ■ 畑毛温泉 「富士見館」の入湯レポ
■ 第15番 華頂峰 高岩院(こうがんいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市奈古谷68
臨済宗円覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡(要事前連絡?)
かつて五山十刹のひとつにも数えられた名刹、国清寺の78を数えた塔頭のひとつです。
国清寺は慶安二年(1362年)、仏真禅師を開山に律宗寺院として修善寺城主畠山国清が創建、応安元年(1368年)には関東管領上杉憲顕が開基中興、無礙妙謙師(円覚寺第三十六世)を開山に請じて臨済宗寺院になったと伝わる名刹です。
全盛期には末寺300を擁し、足利義満公の時代には関東十刹の六番目に加えられたともいわれます。
関東十刹(じっせつ)とは、五山制度に基づく臨済宗の寺格で、五山に次ぎ、諸山の上に位置します。
時代により変遷し、その総数は中世末までに60に達したとみられています。
『禅宗寺院の官寺機構』(今枝愛真氏著/PDF)によると、康暦二年(1380年)、足利義満公は十刹および準十刹の16ヶ寺を定めています。
〔十刹〕
・等持寺(等持院) 京都市北区 天龍寺派 足利氏菩提寺
・禅興寺 鎌倉市山ノ内/廃寺 臨済宗 執権北条時頼私邸の最明寺を再興
・聖福寺 福岡市博多区 妙心寺派 「扶桑最初禅窟」
・東勝寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条氏菩提寺
・(鎌倉)万寿寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条貞時の創建
・長楽寺 群馬県太田市 天台宗 世良田義季(得川義季)の創建
・真如寺 京都市北区 相国寺派 開山は無学祖元
・北禅寺(山城国安国寺) 京都市四条大宮 臨済宗 足利直義の開基
・(豊後)万寿寺 大分市 妙心寺派 開山は直翁智侃和尚(足利泰氏の子)
・清見寺 静岡市清水区 妙心寺派
〔準十刹〕
・臨川寺 京都市右京区 天龍寺派 開山は夢窓疎石
・寶幢寺 京都市嵯峨北堀町/廃寺 臨済宗 足利義満の開基
・瑞泉寺 鎌倉市二階堂 円覚寺派 開山は夢窓疎石
・普門寺 京都市東山区/廃寺 臨済宗
・寶林寺 兵庫県上郡町 真言宗 赤松則祐の開基
・国清寺 静岡県伊豆の国市韮山町 円覚寺派 上杉憲顕の開基
同書の国清寺の項には「応安二年(1369年)以前諸山(空華集十九疏) 至徳元年(1387年)春十刹か(鎌倉五山記)」とあります。
国清寺の本尊聖観世音菩薩は、平安時代末に伊豆に流されてきた文覚が承安三年(1173年)籠居したという奈古屋寺の本尊だったとも伝わります。
また、奈古屋寺の鎮守・毘沙門堂(授福寺)の本尊毘沙門天・金剛力士像は運慶の作ともいわれます。
北面武士の遠藤盛遠は出家して文覚となり、神護寺再興を後白河天皇に強訴したため伊豆国に配流。奈古屋寺に住持して、蛭ヶ島に配流の身であった源頼朝に源氏再興を説いたとされ、その荒法師ぶりは平家物語をはじめ数々の作品にとり上げられています。
国清寺には天狗にまつわる伝説がいくつか残されています。
「天狗にさらわれた一兆さん」はとくに有名で、一兆和尚は高岩院住職となりました。
なお、国清寺は円覚寺百観音霊場第30番、伊豆中道三十三観音霊場第10番の札所ですが、伊豆八十八ヶ所の札所ではありません。
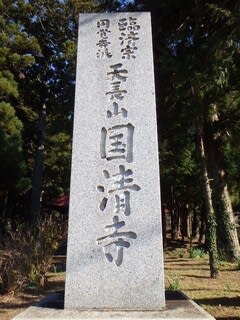

【写真 上(左)】 国清寺の寺号標
【写真 下(右)】 国清寺本堂
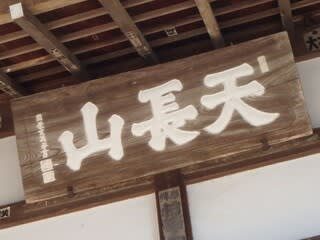
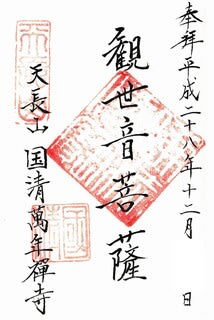
【写真 上(左)】 国清寺の扁額
【写真 下(右)】 国清寺の御朱印
**********

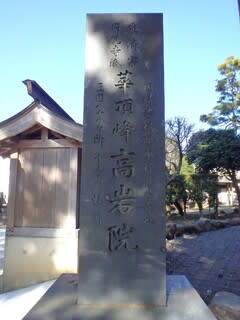
高岩院について、『霊場めぐり』には下記のとおりあります。
・高岩院は国清寺の塔中として代々奉行職を司っていた。
・創建は、国清寺とおなじ貞治元年(1362年)、開基は畠山道譽夫人(松寿院殿)、上杉憲顕夫人(華頂院殿)の両名、開山は亀州妙智禅師。
-------------------

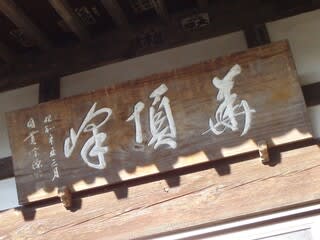
国清寺の参道左手、塔頭らしい位置に一堂を構えています。
寄棟造桟瓦葺、向拝柱のないシンプルな本堂で、向拝見上げには「華頂峰」の山号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受しましたが(国清寺の庫裡だったかも?)、ご不在気味のようで、要事前連絡かもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印
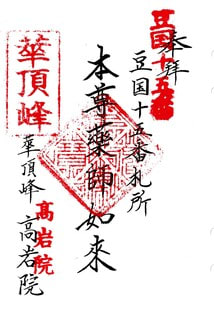
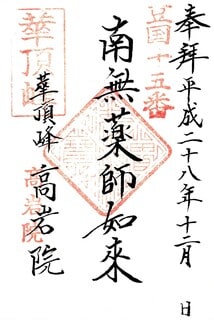
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第16番 金寶山 興聖寺(こうしょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
函南町塚本431
臨済宗円覚寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡


『豆州志稿』に「塚本村 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 亦創始ヲ知ラス或日明應文亀(1501-1504年)ノ頃南渓和尚建ツト」とあり、ガイド2冊にも延徳元年(1489年)、南渓によって創建された寺院という以外の沿革は記されていません。
冠の中にクルス(十字架)が付けられ、江戸時代の隠れ切支丹との関係も論じられる「マリア観音像」、琳派絵師の作とされる雌雄一対の鹿ともみじが描かれた杉戸襖絵は、ともに函南町有形文化財に指定されています。
-------------------

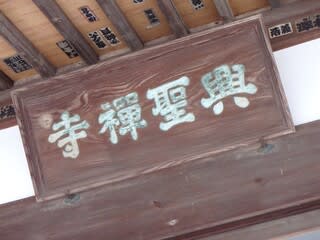
山内入口に伊豆八十八所霊場の札所碑。その先の石標は達筆すぎて読めません(笑)
背後にこんもりと小山を背負った本堂で、手前に聖観世音菩薩の立像が御座。
寄棟造桟瓦葺で向拝を付設し、水引虹梁まわりは比較的シンプル。格子扉のうえに寺号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

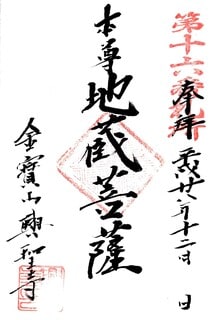
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 竹倉温泉 「錦昌館」の入湯レポ
■ 第17番 明王山 泉福寺(せんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市長伏66
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:-
授与所:庫裡


第17番泉福寺から三島市内に入ります。
『霊場めぐり』などによると、創立年代等不明ですが僧快任を中興祖とし、初めは元屋敷にあったものを元久八年(元久四年とも)に中ノ坪に遷し、さらに寛保二年(1742年)に現在地へ移転とあります。
『豆州志稿』にも「長伏村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 創立不詳 僧快任ヲ中興トス 初字元屋舗ニ在リキ元久四年(1207年)字中ノ坪ニ遷シ寛保二年(1742年)復現地ニ転ス」とあります。
-------------------


山内入口に寺号標と伊豆八十八所霊場の札所碑。
その先にどっしりとした大棟、降棟、掛瓦を置いた桟瓦葺の山門。
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。向拝サッシュ扉の上に寺号扁額を掲げています。
境内左手の観音堂は、三島の楽寿園(元小松宮別邸)内の愛染院(三島大社別当)に御座の千手観世音菩薩を遷して奉安とのことです。(町内にあった旧法覚寺の御本尊を安置という説もあり。)
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)
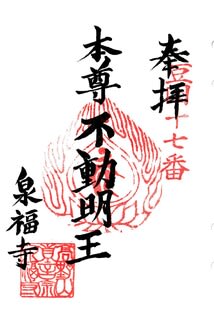
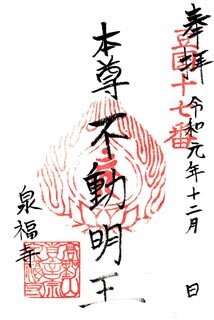
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第18番 龍泰山 宗徳院(そうとくいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市資料
三島市松本414
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡


山内由緒書などによると、延喜年間(901-902年)、真言宗の僧(弘法大師空海とも)がこの地に霊感を得て、地蔵菩薩を御本尊として奉安し真言宗寺院として創建。
源頼朝公が挙兵後、鎌倉に入るまでの百日間、三島大社に日参するとともに、当寺御本尊の延命地蔵菩薩を源氏旗揚げの祈願佛として詣でたといわれています。
天正(1573-1592年)の初期、武田の残党道乗、道吉の2名がこの地で開墾に当たりましたが、追手が迫り同寺境内にて自刃。両名菩提のため、天正三年(1575年)韮山町南條昌渓院六世麒庵東麟禅師を請し曹洞宗寺院として開山。
『豆州志稿』には「松本村 田方郡南條昌渓院末 本尊地蔵 天正三年(1575年)創立僧東麟ヲ開山トス 松本村廃萬年寺ノ本尊観世音当寺に安ス」とあります。
-------------------


門前の川に架かる橋は「駒爪橋」といい、頼朝公が乗った馬の爪痕が残されたことに由来するそうです。
山内に頼朝公の祠があるようですが、うかつにも写真を撮りわすれました。
入口手前に寺号標。寄棟屋根銅板葺の山門には山号扁額。
相輪を備えた宝形造銅板葺の本堂で、向拝上に院号扁額を置いています。
本堂には御本尊の地蔵菩薩を奉安。明治初年に廃寺となった旧萬年寺の御本尊聖観世音菩薩を御本尊脇仏として併祀。
弘法大師のお像と頼朝公の木造も奉安されているようです。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

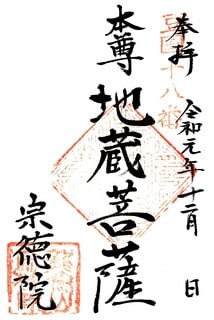
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第19番 君澤山 連馨寺(れんけいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市観光ガイド
三島市資料
三島市広小路町1-39
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第3番、中伊豆観音札所第2番、駿河一国百地蔵尊霊場第96番
授与所:庫裡


三島の街なか、広小路にある名刹。順打ちでいくとはじめての浄土宗寺院になります。
正應二年(1289年)、浄土宗の僧星誉上人により開創。
豊臣秀吉の小田原征伐の際の三島焼き払いで焼失した他、類焼や震災などにより寺伝等が焼失し沿革は不明となっています。
昔、寺の裏に蓮沼池という池があり、蓮の花の香りが漂ったことから蓮馨寺と号したといいます。
『豆州志稿』には「三島町六反田 本尊阿彌陀 西京知恩院末 享禄天文ノ間明譽上人建ツ 観音堂在門前」とあります。
-------------------

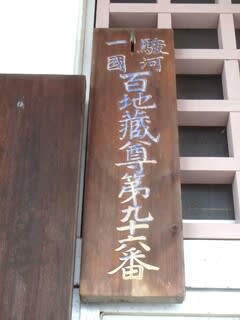
繁華街に面した参道入口から本堂にかけて参道が延びています。
山門入って右手には松尾芭蕉の墓があり、「いざともに ほむぎくらわん くさまくら」の芭蕉の句が刻まれています。当寺の住職が芭蕉の弟子だったという縁で建てられたとのことです。
参道に沿って左手に日限地蔵尊、観音堂などが並びます。
日限地蔵尊は聖徳太子御作とも伝わり、毎年8月23日には日限地蔵尊大祭が営まれます。
こちらの日限地蔵尊にはつぎのような縁起が伝わっています。
江戸の昔、三島宿に向かう一人の旅人が物盗りに襲われ、刀で斬りつけられて気を失ってしまいました。翌朝気がつくと傍らに袈裟懸けに斬られた石のお地蔵さまが横たわっていました。旅人はこのお地蔵さまが身代わりになってくれたと悟り、近くの連馨寺に運び手厚くお祀りしました。
当初は「身代わり地蔵」といわれたこのお地蔵さまは、いつしか日を限ってお願いすると願いが叶うという「日限地蔵尊」として信仰を集め、横浜・日限山の福徳院、長野・岡谷の平福寺に御分身されお祀りされています。
この三体の地蔵尊は「三大日限地蔵尊」と称され多くの信仰を集めたとのこと。
こちらの日限地蔵尊は、駿河一国百地蔵尊霊場第96番の札所となっています。
-------------------


本堂は階段の上に入母屋造本瓦葺、重厚な向拝を備えた堂々たる伽藍で、向拝に寺号扁額を掲げています。
本堂右手の聖徳太子堂は、大正11年、地元技術諸職48名の発起により大和法隆寺より御分身を勧請し建立されたもの。
由緒書きにはありませんが、その背景には日限地蔵尊が聖徳太子御作と伝わっていることもあるのだと思われます。
・御朱印は庫裡にて拝受しましたが、観音霊場の御朱印は授与されていないとのことです。(地蔵尊霊場については訊きわすれました。)
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印
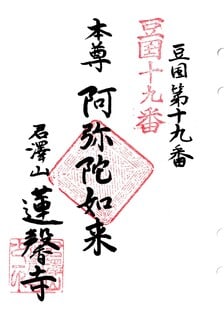
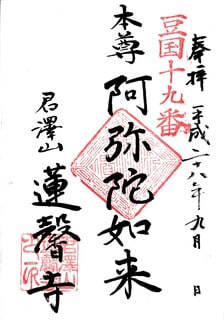
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ (湯郷)三島温泉 「湯郷三島温泉」の入湯レポ
■ 第20番 福翁山 養徳寺(ようとくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市資料
函南町平井1126
臨済宗円覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:円覚寺百観音霊場第27番、中伊豆観音札所第13番
授与所:庫裡


嘉應元年(1387年)、用固という僧によって開創。 寛政元年(1789年)の火災により堂塔、寺伝などをすべて焼失したため、詳細な沿革は不明となっていますが、寛政元年(1789年)牛窓和尚が本堂庫裡再建と伝わります。
『円覚寺百観音霊場 御納経帳』には、「開創以来過去数百年、その間幾多の盛衰、興廃あり、後人の亀鑑となるべき歴代の法躅、先哲の遺芳等多くあったと思われるがその記録のないのが惜しまれる」とあります。
『豆州志稿』には「平井村 奈古谷國清寺末 本尊十一面観世音 本養徳院ト云 天正(1573-1592)の頃ヨリ寺号ヲナシテ國清寺ニ隷ス 嘉應中僧用固創立ス後 享保七年(1722年)僧一渓中興ス 廃薬王寺ノ本尊当寺ニ安す」とあります。
-------------------


畑毛温泉にもほど近い、函南の山里にあります。
参道入口に寺号標。その先に切妻屋根銅板葺の薬医門。
山門を抜けると右手に枯山水の石庭が広がりそのおくに本堂。
入母屋造銅板葺で桁行きのある端正な伽藍です。
御朱印は庫裡にて拝受。円覚寺百観音霊場の御朱印も拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

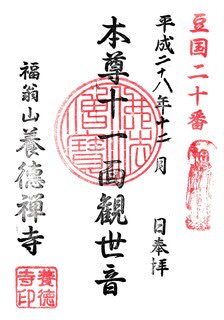
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 円覚寺百観音霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

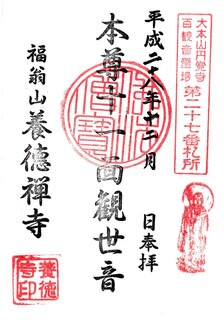
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第21番 圓通山 龍澤寺(りゅうたくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市観光ガイド
三島市資料
三島市沢地326
臨済宗妙心寺派
御本尊:子安観世音菩薩
札所本尊:子安観世音菩薩
他札所:中伊豆観音札所第6番
授与所:庫裡


宝暦十一年(1761年)、白隠禅師により開山されたという臨済宗妙心寺派の名刹。
当寺住職は代々老師として称えられ、開山白隠老師をはじめ、東嶺老師、明治の星定老師、大正昭和の玄峰老師はわけても名声高く、各界の名士が参禅しました。
「今白隠」とも賞された山本玄峰老師の大正期の復興により、国内有数の禅道場として名を高めたとされます。
『豆州志稿』には「澤地村 西京妙心寺末 本尊子安観世音 舊愛宕山下ニ在リテ弘法大師開基ノ由 國初ノ頃三島心経寺ノ天外和尚済門ヲ開ク 寶暦十年今ノ地ニ移シ駿州原驛松隠寺ノ白隠禅師ヲ祖トシ妙心寺に隷ス」とあります。
山内には本堂、庫裏、禅堂、経堂、鐘楼、不動堂、開山堂などが軒を連ね、開山堂内には白隠、東嶺、星定、玄峰の4老師像が安置されています。
星定老師像は鏝細工の名工、入江長八の作として知られ、白隠禅師が83歳の時に自ら描かれたという「紙本著色白隠自画像」は県指定文化財となっています。
毎年11月23日の観楓祭には所蔵の宝物が一般公開され、多くの拝観客が訪れます。
-------------------


三島市街の北東の山裾にあり、龍澤禅寺とも呼ばれます。
伊豆八十八ヶ所霊場はこの龍澤寺がもっとも北の札所で、ここで方向を転じ東海岸沿いを南伊豆に向かって南下していきます。
山内は石垣の上に築かれ、さながら城郭のよう。
うっそうと古木の茂る階段をのぼると、獅子・貘の木鼻と中備に龍の彫刻を置いた二軒垂木の風格ある山門。
山内には鐘楼、経堂、開山堂、本堂、禅堂、庫裏などが整然と並びます。
どこを切りとっても絵になり、これはインバウンド客にも人気が高そう。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
いまも禅道場として修行僧の修行の場となっており、接心修行時にはお遍路であっても境内に入場できなくなるので要注意です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 子安観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
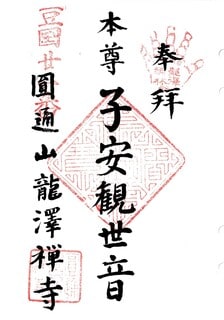
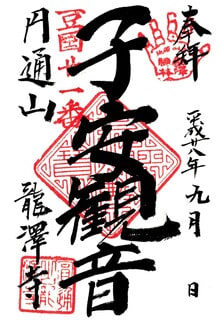
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第22番 龍泉山 宗福寺(そうふくじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市塚原新田69-1
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡


天正十八年(1590年)豊臣秀吉が小田原を攻めた際、出城となった山中城で出た戦没者を追悼するため、延寶元年(1673年)、法華寺三世橘庵明洲により創建された曹洞宗寺院です。
『豆州志稿』には「塚原新田 三島法華寺末 本尊阿彌陀 当地ハ天正十八年(1590年)ノ古戦場ナレハ戦死者追福ノ為ニ延寶元年(1673年)法華寺三世明洲創立ス」とあります。
山中城は永禄年間(1558-1570年)に北条氏康により小田原の西の防衛を担うため、箱根山中腹の標高580mの地に、東海道を取り込む形で構えられたといいます。
「山中城合戦 戦国時代最大の攻城戦」(三島市資料)によると、天正十八年(1590年)、全国制覇を目論む豊臣秀吉は後北条氏の征伐(小田原征伐)に向かいました。
3月29日早朝、山中城を豊臣軍約七万の軍勢が取り囲みました。
右翼に池田輝正勢、左翼に徳川家康勢、中央に総大将の豊臣秀次以下、中村一氏、一柳直末、山内一豊、堀尾吉晴などが三手に分かれて布陣したといいます。
後北条方は城主の松田康長、援将の北条氏勝、間宮康敏、松田康郷、蔭山氏広以下約四千で迎え撃ったとされます。
後北条方は善戦したものの衆寡敵せず、正午過ぎには山中城は落城したとされ、激戦を物語るように、両軍の戦死者は二千にも達したと伝わります。
「戦国時代最大の攻城戦」といわれる所以です。
北条氏滅亡とともに山中城は廃城となりました。
秀吉はここまで力攻めを嫌った武将でしたが、このような激しい城攻めとなったのは、天下人たる実力を世に示す必要があったこと、秀吉に対して戦功をあげるため、武将達が奮戦したことによるとみられています。
宗福寺のある塚原新田は東海道の箱根越えの登り口に当たっているため、この地に創建されたと考えられます。
-------------------

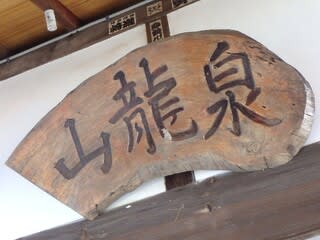
東海道から1本北側に入った道沿いにあります。
山門は切妻屋根銅板葺でおそらく薬医門
正面に入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。照りむくりがなく、直線的な屋根勾配。
水引虹梁まわりもスクエアでシンプル。向拝見上げに山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂よこの庫裡にて拝受しました。
ここから札所は伊豆東海岸に移ります。
続行の場合は、伊豆縦貫自動車道~熱函道路~熱海峠のルートがとれますが、第23番東光寺まではかなり距離があり熱海峠~東光寺は悪路のうえに、東光寺の御朱印は伊豆山の般若院(第24番)での拝受となるので、ひとまず区切りとするタイミングかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

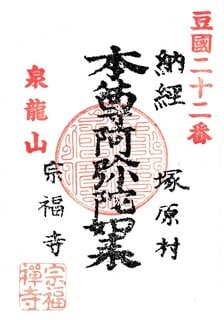
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3へ。
【 BGM 】
■ One Reason - milet
■ 春に落ちて - 鹿乃 / Kano
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第10番 長谷山 蔵春院(ぞうしゅんいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報サイト
伊豆の国市田京949-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡


第10番蔵春院は、第9番澄楽寺からほど近い田京(たきょう)の地にあります。
寺伝には、「関東管領足利持氏は、時の将軍足利義教公に反抗し自ら鎌倉将軍と名乗ったため幕府は追討を計り、持氏の家臣である上杉憲実に討伐の命を下した。憲実はやむなく持氏を鎌倉永安寺に攻めて自害させたが、憲実は主君を死に追いやったことを悔い管領職を譲って出家。主君の菩提を弔うため寺院建立を決意し、多福院(大仁町白山堂)に止錫中の春屋宗能禅師を尋ねて懇請し、白山堂の豪氏宮内五左ヱ門の協力を得て今の地に(永享十一年(1439年))長谷山蔵春院を建立」とあります。
↑の出来事は「永享の乱」と思われるので、Wikipediaなどで「永享の乱」をひくと、やや異なった内容があるのでとりまとめてみます。↓
永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏は前関東管領上杉憲実と対立し、憲実を支持した将軍足利義教公は足利満直、駿河守護今川範忠、上杉持房・教朝らを出兵させた。
持氏軍は敗れ、持氏は鎌倉に引く途中で憲実の家宰・長尾忠政に憲実・義教との折衝を依頼、鎌倉称名寺で出家し永安寺に幽閉された。
憲実は持氏の助命を懇願したが義教公は許さず、憲実に持氏の追討を命じたため憲実はやむなく永安寺を攻撃、持氏は自害した。(永享の乱)。
寺伝とWikipedia等で持氏と憲実の関係は若干異なりますが、「憲実は持氏の助命を懇願したもののやむなく持氏を追討」という点では符合し、憲実が持氏の菩提を弔うために蔵春院を建立、という趣意は同じかと思います。
山号、寺号は持氏の法名蔵春院殿陽山継公大禅定門によるものとされます。
憲実から寺院建立を懇請された宗能禅師が造立の際、この地に棲んでいた悪龍を鎮めたという龍神伝説が残ります。
宗能禅師は自らは開山を称せず、本師である大綱明宗大和尚を勧請して開山とし、後事を実山永秀に託して小田原最乗寺に住され第五世となりました。
『豆州志稿』には「田京村 下總州國府臺總寧寺末 本尊釋迦如 永享十一年(1439年)、上杉安房守憲実持氏
将軍ヲ追薦シ施地建寺開基トス 寺伝曰上杉憲実白山堂ノ処士宮内氏ニ●リテ創建シ足利持氏ヲ開基トスト 憲実当国ニ遁栖ノ事諸書ニ見ユ 開山大綱和尚二世春屋和尚三世実山和尚因テ三古佛道場ト称ス 実山此ニ住ム事数年 長享丁未歳(元年/1487年)示寂 実山ノ時持氏の子成氏ヨリ寺領ヲ寄スト云 持氏の古碑 法名長春院殿陽山継公大禅定門 及守佛(地蔵ノ木像長六寸手ニ寶珠ヲ持ツ)ヲ置ク 有佛殿祖師堂衆寮庫裏浴室鐘楼門 元末寺八十余ヶ寺アリ 今四十七ヶ寺ヲ有シ中本寺格也」とあり、おおむね寺伝と合致しています。
-------------------


瓦葺の楼門は三間一戸の八脚門で、上層に鐘楼を置いています。
本堂は昭和53年落慶。入母屋造桟瓦葺で降棟に照りのある勢いを感じるつくり。
向拝柱はなく向拝正面は桟唐戸で左右に花頭窓、上部に「長谷山」の山号扁額を掲げています。
本堂向かって右手前の観音堂に御座す観世音菩薩は、従前は山中にあって「長谷観音」(ちょうこくかんのん)と呼ばれ、歴代住職が石仏観音を中心に西国観音霊場より請来した三十三観音を参拝路に安置していることもあって多くの信者を集めていたそうですが、堂宇焼失により、現在はこの場所に御座されているそうです。
御朱印は庫裡にて拝受。鎌倉の影響が強い由緒を受けてか、御本尊、札所本尊ともに釈迦牟尼佛となっています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印
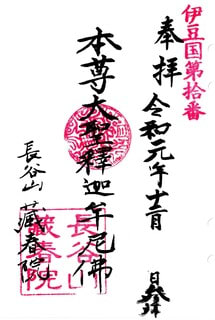
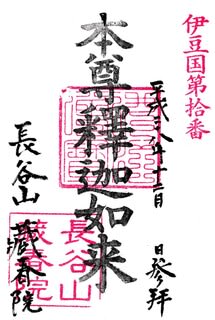
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第11番 天與山 長源寺(ちょうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市観光ガイド
伊豆の国市中492-2
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:-
授与所:庫裡

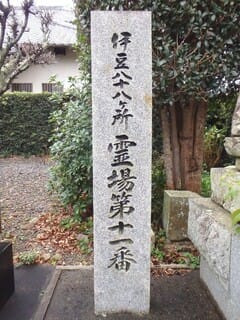
第11番長源寺は第10番蔵春院からほど近く、韮山反射炉のそばにあります。
創建年代などは不詳ですが当初真言宗であったようです。
北條早雲が榛原の石雲院より当寺に虚庵玄充を招き、当初は石雲院末でしたが虚庵が修禅寺第二世として普住したため以降は修禅寺末になったと伝わります。
『霊場めぐり』には、「信濃国の真田家の分家真田河内守信豊を開基とし、下田鵜島城主清水河内守正令唐の尽力により伽藍が整備された」とあります。
また、『豆州志稿』には「中村 修善寺修禅寺末 本尊釋迦如 開山虚庵和尚天文元年(1532年)化ス 修禅寺中興僧隆渓ヨリ開山虚庵ニ贈レル書ニ 文龜四年(1504年)三月トアリ 当時ノ創立歟」とあります。
境内には東司(トイレ)の不浄を清める烏枢沙摩明王が祀られるお堂もあり、毎年8月に例祭も執り行われています。
なお、こちらでは烏枢沙摩明王の御朱印は授与されていない模様です。
烏枢沙摩明王の御朱印はすこぶるめずらしく、筆者が拝受した範囲では伊豆市市山の金龍山 明徳寺のみです。ただし、明徳寺でもメインの御朱印は大黒天(伊豆天城七福神)と御本尊の釈迦如来で、烏枢沙摩明王の御朱印を常時授与されているかは不明です。
-------------------

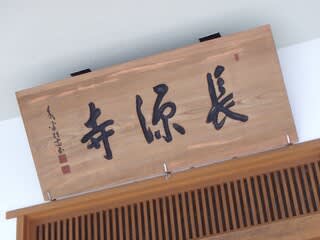
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その先で直角に向きを変えて本堂に向かいます。
車両の出入りが不便な旧地から昭和40年、当地に移転したため堂宇は新しいもの。
近代建築ながら、入母屋造本瓦葺に付設の向拝を張り出す堂々たる構えです。
蔵造りの別堂には烏枢沙摩明王が祀られています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦如来
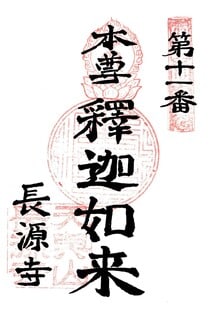
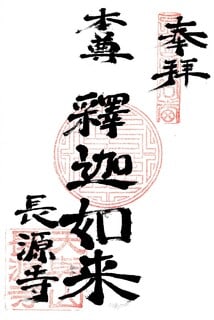
【写真 上(左)】 専用納経帳
・主印は三寶印と御寶印。御寶印の種子は「キャ」にも見えます。
【写真 下(右)】 御朱印帳
・主印は三寶印
→ ■ 韮山温泉 「天城荘」の入湯レポ
■ 第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(ちょうおんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市古奈13
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:伊豆長岡温泉七福神(福禄寿)
授与所:庫裡


第12番長温寺は、古奈温泉のほぼ中心にあり、めずらしい林号を号すお寺です。
古奈温泉といってもピンとこない方も多いかと思いますが、もともと伊豆長岡温泉の発祥は源氏山の東側の古奈温泉で、西側の伊豆長岡温泉は新興温泉地とされます。
伊豆の国市観光協会発行の「古奈温泉ものがたり」(PDF)には「古奈温泉は、平安・鎌倉時代に遡り、弘法大師が伊豆を訪れた頃の発祥と言われ、(中略)源頼朝も湯浴みをしたと伝えられています。修善寺温泉・伊豆山温泉とともに伊豆三大古湯と言われ、『吾妻鏡』には、伊豆国小名温泉や、北条古那温泉などの表記があり、南北朝時代に「古奈湯」と記されています。明治40年に西隣りの長岡地区に温泉が発見され次々に宿屋ができ、合わせて伊豆長岡温泉として発展してきました。」とあります。


【写真 上(左)】 古奈の温泉街
【写真 下(右)】 湯谷神社


【写真 上(左)】 古奈の元湯-1
【写真 下(右)】 古奈の元湯-2
長温寺のそばに御鎮座の湯谷神社は、ここから温泉が湧き出たという由緒から古奈温泉の産土神とされています。
御祭神は大己貴命、少彦名命と、温泉地の湯元神社に多く祀られる御祭神です。
湯谷神社参道脇の「古奈の元湯」はいまは枯渇してしまいましたが、いまでも遺構を残しています。
なお、長温寺は位置関係、および山号「湯谷山」から湯谷神社の元別当とも思いましたが、確実な史料は確認できておりません。
巡礼ガイドによると、仁安二年(1167年)、古奈治郎義光、同五郎義定の両将は敗戦しこの地に逃れて天野原で討死、義光が守護仏として護持していた薬師如来をこの地に祭祀したとのこと。
永禄五年(1562年)、僧・瓶山により開創、元和六年(1620年)には梅原源左衛門が再興し、真珠院第九世柳岩玄絮を請して開山し曹洞宗となったとあります。
『豆州志稿』には「古奈村 中條眞珠院末 本尊薬師 永禄五年(1562年)瓶山開林 寺伝曰初真言宗ニシテ長御寺ト号ス 御元和中梅原源左衛門再興 眞珠院九世柳岩ヲ祖トシ改宗ス 此時ヨリ長温寺ト更ムト」とあります。
-------------------


温泉街の路地のおく、こぢんまりとした境内ですが、しっとりと落ち着いた趣きがあります。
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、木鼻、蟇股、海老虹梁を備え、「薬王山」の扁額を掲げています。
御本尊、札所本尊は温泉地のお寺にふさわしく薬師如来です。
御朱印は庫裡にて拝受しました。こちらは伊豆長岡温泉(源氏山)七福神の福禄寿ですが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印
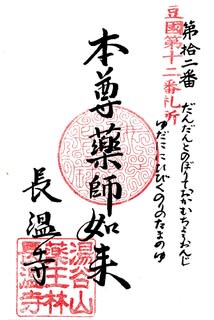
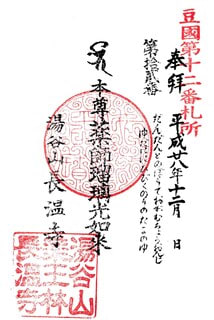
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)の入湯レポ
■ 第13番 巨徳山 北條寺(ほうじょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市観光協会Web
伊豆の国市南江間862-1
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第16番、駿豆両国横道三十三観音霊場第8番、中伊豆観音札所第20番
授与所:庫裡


北条氏の館(北条氏邸・円成寺跡)にもほど近い、源頼朝公の正室・北条政子の弟である北条義時(江間小四郎)が創建した寺院です。
義時の嫡子安千代が領内の大池で大蛇に襲われ命を落とした際に、この北條寺を墓所とし七堂伽藍を建立、運慶に仏像を作らせたといいます。
この運慶作の祈願仏が「木造阿弥陀如来座像」(桧材寄木造、国重要美術品、県文化財)として知られており、仏殿の御本尊です。
御本尊の聖観世音菩薩は南北朝期の作とされ、中国宋風の像容で県文化財に指定されています。
鎌倉極楽寺にあったものを北条政子が奉納したとも伝わります。
『豆州志稿』には「南江間村 鎌倉建長寺末 本尊観世音 本観音堂也相伝フ観音ハ天竺ヨリ唐ニ渡リ 智證大師(円珍)東帰ノ時齋来ル其佛 鎌倉(極楽寺ニ安置セシ也)ニ在リシヲ二位禅尼命シテ此ニ贈ル佛造 黒色ニシテ油ノ浮カ如シ伽羅木也ト云(略)北條義時ノ草創ニシテ観音ノ像長一尺余ト有リ 曆應貞和ノ頃(1338-1350年)寺ヲ建立ス 建長寺七十九世大雲ヲ開山トス 初実成寺ト称ス(略)境内ニ北條義時夫妻ノ墓ト云アリ 義時法名北條寺殿寛海大禅定門ト云 当村ハ其郷里ナリ」とあり、北条政子や北条義時ゆかりの名刹であることがわかります。
境内の「小四郎山」と呼ばれる丘の上には、義時夫妻の墓所があります。
ロウバイと白いヒガンバナが有名な花の寺でもあります。
-------------------

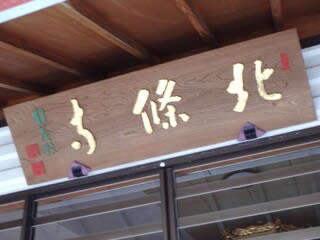
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、大棟両端に金色の鴟尾を置いています。
朱塗りの柱が効いて引き締まった印象の仏堂で、向拝に水引虹梁を置き、正面サッシュ扉の上に「北條寺」の寺号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第16番の御朱印も拝受しています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
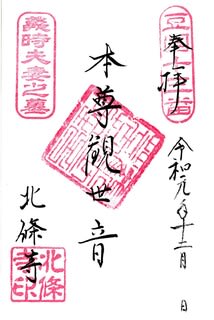

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印
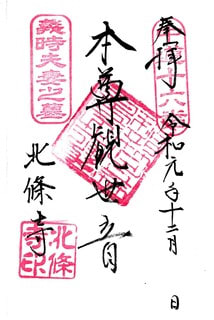
御朱印帳
■ 第14番 龍泉山 慈光院(じこういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市韮山多田937
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第11番、中伊豆観音札所第16番
授与所:庫裡


第14番慈光院は韮山市街の東の山ぎわにあります。
当初は光明遍照金剛楳(梅)林寺 槑(梅)香院と号した真言宗寺院でしたが、永正七年(1510年)曹洞宗に改宗、再興されたといいます。
永正七年の再興に際しての逸話が伝わります。
往時、このあたりに村人から恐れられた龍が住んでおり、多田入道実正(日下部乃梅原入道伊豆乃真実正とも)が、五人張の強弓をもってこれを退治しましたが、それ以来村内に悪疫が流行して村人を悩ませました。
これを龍の祟りとみた実正は龍の霊を祭り供養するために龍の戒名をつけ、弘法大師の御作と伝わる延命地蔵尊を御本尊とし、昌渓院二世菅谷宋儔を開山として請し、龍の戒名から龍泉山 慈光院と号したといいます。
『豆州志稿』には「韮山多田 南條昌渓院末 本尊阿彌陀 昌渓院二世曹谷和尚(永正十三年(1516年)取滅)應請卓錫ス 二世密栄ノ時寺号トス 此村梅原氏ノ先祖(梅原内膳実正法名牛鍬院殿弓兵多田大膳定門)蛇ヲ)射殺ス因テ寺ニ蛇足ト蛇鱗トヲ蔵ム 廃正法寺本尊観世音当寺ニ安ス」とあり、こちらでは蛇にかかわる所縁が記されています。
-------------------


本堂は入母屋造桟瓦葺で、大がかりな唐破風を張り出した向拝を置いています。
水引虹梁端部に雲形の木鼻、中備に板蟇股、身舎方に海老虹梁を配し、向拝見上げに「慈光院」の寺号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受。こちらは伊豆中道三十三観音霊場第11番でもあり、札所本尊聖観世音菩薩の御朱印も拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印
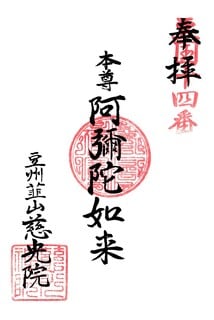

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印
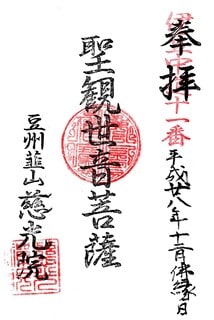
御朱印帳
→ ■ 畑毛温泉 「富士見館」の入湯レポ
■ 第15番 華頂峰 高岩院(こうがんいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市奈古谷68
臨済宗円覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:-
授与所:庫裡(要事前連絡?)
かつて五山十刹のひとつにも数えられた名刹、国清寺の78を数えた塔頭のひとつです。
国清寺は慶安二年(1362年)、仏真禅師を開山に律宗寺院として修善寺城主畠山国清が創建、応安元年(1368年)には関東管領上杉憲顕が開基中興、無礙妙謙師(円覚寺第三十六世)を開山に請じて臨済宗寺院になったと伝わる名刹です。
全盛期には末寺300を擁し、足利義満公の時代には関東十刹の六番目に加えられたともいわれます。
関東十刹(じっせつ)とは、五山制度に基づく臨済宗の寺格で、五山に次ぎ、諸山の上に位置します。
時代により変遷し、その総数は中世末までに60に達したとみられています。
『禅宗寺院の官寺機構』(今枝愛真氏著/PDF)によると、康暦二年(1380年)、足利義満公は十刹および準十刹の16ヶ寺を定めています。
〔十刹〕
・等持寺(等持院) 京都市北区 天龍寺派 足利氏菩提寺
・禅興寺 鎌倉市山ノ内/廃寺 臨済宗 執権北条時頼私邸の最明寺を再興
・聖福寺 福岡市博多区 妙心寺派 「扶桑最初禅窟」
・東勝寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条氏菩提寺
・(鎌倉)万寿寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条貞時の創建
・長楽寺 群馬県太田市 天台宗 世良田義季(得川義季)の創建
・真如寺 京都市北区 相国寺派 開山は無学祖元
・北禅寺(山城国安国寺) 京都市四条大宮 臨済宗 足利直義の開基
・(豊後)万寿寺 大分市 妙心寺派 開山は直翁智侃和尚(足利泰氏の子)
・清見寺 静岡市清水区 妙心寺派
〔準十刹〕
・臨川寺 京都市右京区 天龍寺派 開山は夢窓疎石
・寶幢寺 京都市嵯峨北堀町/廃寺 臨済宗 足利義満の開基
・瑞泉寺 鎌倉市二階堂 円覚寺派 開山は夢窓疎石
・普門寺 京都市東山区/廃寺 臨済宗
・寶林寺 兵庫県上郡町 真言宗 赤松則祐の開基
・国清寺 静岡県伊豆の国市韮山町 円覚寺派 上杉憲顕の開基
同書の国清寺の項には「応安二年(1369年)以前諸山(空華集十九疏) 至徳元年(1387年)春十刹か(鎌倉五山記)」とあります。
国清寺の本尊聖観世音菩薩は、平安時代末に伊豆に流されてきた文覚が承安三年(1173年)籠居したという奈古屋寺の本尊だったとも伝わります。
また、奈古屋寺の鎮守・毘沙門堂(授福寺)の本尊毘沙門天・金剛力士像は運慶の作ともいわれます。
北面武士の遠藤盛遠は出家して文覚となり、神護寺再興を後白河天皇に強訴したため伊豆国に配流。奈古屋寺に住持して、蛭ヶ島に配流の身であった源頼朝に源氏再興を説いたとされ、その荒法師ぶりは平家物語をはじめ数々の作品にとり上げられています。
国清寺には天狗にまつわる伝説がいくつか残されています。
「天狗にさらわれた一兆さん」はとくに有名で、一兆和尚は高岩院住職となりました。
なお、国清寺は円覚寺百観音霊場第30番、伊豆中道三十三観音霊場第10番の札所ですが、伊豆八十八ヶ所の札所ではありません。
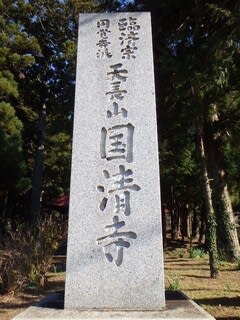

【写真 上(左)】 国清寺の寺号標
【写真 下(右)】 国清寺本堂
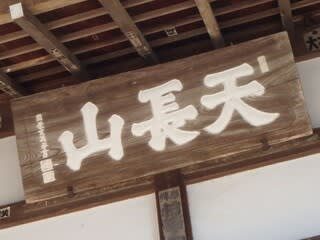
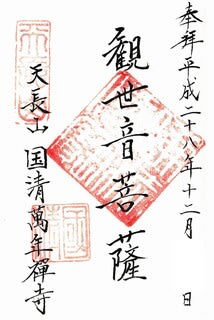
【写真 上(左)】 国清寺の扁額
【写真 下(右)】 国清寺の御朱印
**********

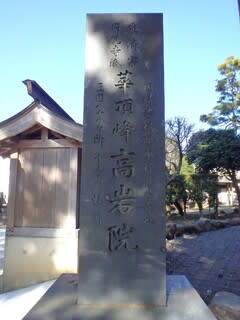
高岩院について、『霊場めぐり』には下記のとおりあります。
・高岩院は国清寺の塔中として代々奉行職を司っていた。
・創建は、国清寺とおなじ貞治元年(1362年)、開基は畠山道譽夫人(松寿院殿)、上杉憲顕夫人(華頂院殿)の両名、開山は亀州妙智禅師。
-------------------

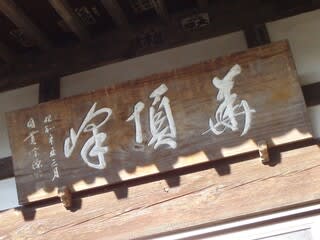
国清寺の参道左手、塔頭らしい位置に一堂を構えています。
寄棟造桟瓦葺、向拝柱のないシンプルな本堂で、向拝見上げには「華頂峰」の山号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受しましたが(国清寺の庫裡だったかも?)、ご不在気味のようで、要事前連絡かもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印
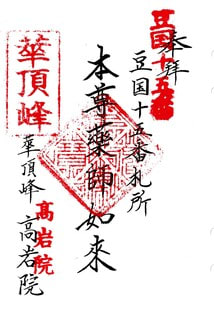
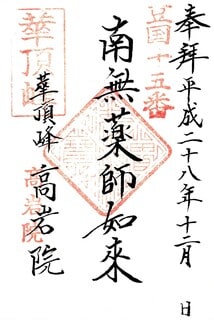
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第16番 金寶山 興聖寺(こうしょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
函南町塚本431
臨済宗円覚寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡


『豆州志稿』に「塚本村 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 亦創始ヲ知ラス或日明應文亀(1501-1504年)ノ頃南渓和尚建ツト」とあり、ガイド2冊にも延徳元年(1489年)、南渓によって創建された寺院という以外の沿革は記されていません。
冠の中にクルス(十字架)が付けられ、江戸時代の隠れ切支丹との関係も論じられる「マリア観音像」、琳派絵師の作とされる雌雄一対の鹿ともみじが描かれた杉戸襖絵は、ともに函南町有形文化財に指定されています。
-------------------

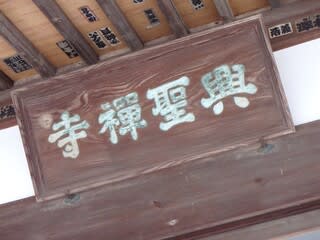
山内入口に伊豆八十八所霊場の札所碑。その先の石標は達筆すぎて読めません(笑)
背後にこんもりと小山を背負った本堂で、手前に聖観世音菩薩の立像が御座。
寄棟造桟瓦葺で向拝を付設し、水引虹梁まわりは比較的シンプル。格子扉のうえに寺号扁額を掲げています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

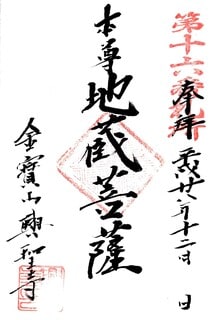
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 竹倉温泉 「錦昌館」の入湯レポ
■ 第17番 明王山 泉福寺(せんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市長伏66
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:-
授与所:庫裡


第17番泉福寺から三島市内に入ります。
『霊場めぐり』などによると、創立年代等不明ですが僧快任を中興祖とし、初めは元屋敷にあったものを元久八年(元久四年とも)に中ノ坪に遷し、さらに寛保二年(1742年)に現在地へ移転とあります。
『豆州志稿』にも「長伏村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 創立不詳 僧快任ヲ中興トス 初字元屋舗ニ在リキ元久四年(1207年)字中ノ坪ニ遷シ寛保二年(1742年)復現地ニ転ス」とあります。
-------------------


山内入口に寺号標と伊豆八十八所霊場の札所碑。
その先にどっしりとした大棟、降棟、掛瓦を置いた桟瓦葺の山門。
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。向拝サッシュ扉の上に寺号扁額を掲げています。
境内左手の観音堂は、三島の楽寿園(元小松宮別邸)内の愛染院(三島大社別当)に御座の千手観世音菩薩を遷して奉安とのことです。(町内にあった旧法覚寺の御本尊を安置という説もあり。)
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)
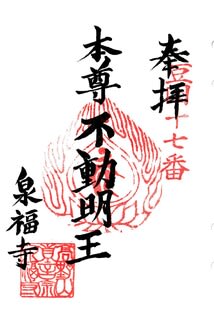
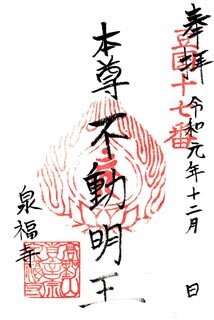
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第18番 龍泰山 宗徳院(そうとくいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市資料
三島市松本414
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:-
授与所:庫裡


山内由緒書などによると、延喜年間(901-902年)、真言宗の僧(弘法大師空海とも)がこの地に霊感を得て、地蔵菩薩を御本尊として奉安し真言宗寺院として創建。
源頼朝公が挙兵後、鎌倉に入るまでの百日間、三島大社に日参するとともに、当寺御本尊の延命地蔵菩薩を源氏旗揚げの祈願佛として詣でたといわれています。
天正(1573-1592年)の初期、武田の残党道乗、道吉の2名がこの地で開墾に当たりましたが、追手が迫り同寺境内にて自刃。両名菩提のため、天正三年(1575年)韮山町南條昌渓院六世麒庵東麟禅師を請し曹洞宗寺院として開山。
『豆州志稿』には「松本村 田方郡南條昌渓院末 本尊地蔵 天正三年(1575年)創立僧東麟ヲ開山トス 松本村廃萬年寺ノ本尊観世音当寺に安ス」とあります。
-------------------


門前の川に架かる橋は「駒爪橋」といい、頼朝公が乗った馬の爪痕が残されたことに由来するそうです。
山内に頼朝公の祠があるようですが、うかつにも写真を撮りわすれました。
入口手前に寺号標。寄棟屋根銅板葺の山門には山号扁額。
相輪を備えた宝形造銅板葺の本堂で、向拝上に院号扁額を置いています。
本堂には御本尊の地蔵菩薩を奉安。明治初年に廃寺となった旧萬年寺の御本尊聖観世音菩薩を御本尊脇仏として併祀。
弘法大師のお像と頼朝公の木造も奉安されているようです。
・御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

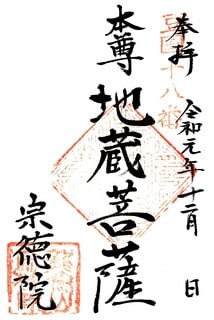
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第19番 君澤山 連馨寺(れんけいじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市観光ガイド
三島市資料
三島市広小路町1-39
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第3番、中伊豆観音札所第2番、駿河一国百地蔵尊霊場第96番
授与所:庫裡


三島の街なか、広小路にある名刹。順打ちでいくとはじめての浄土宗寺院になります。
正應二年(1289年)、浄土宗の僧星誉上人により開創。
豊臣秀吉の小田原征伐の際の三島焼き払いで焼失した他、類焼や震災などにより寺伝等が焼失し沿革は不明となっています。
昔、寺の裏に蓮沼池という池があり、蓮の花の香りが漂ったことから蓮馨寺と号したといいます。
『豆州志稿』には「三島町六反田 本尊阿彌陀 西京知恩院末 享禄天文ノ間明譽上人建ツ 観音堂在門前」とあります。
-------------------

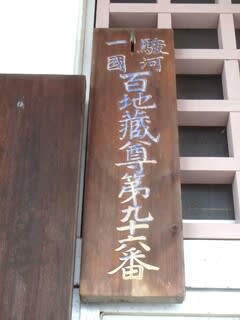
繁華街に面した参道入口から本堂にかけて参道が延びています。
山門入って右手には松尾芭蕉の墓があり、「いざともに ほむぎくらわん くさまくら」の芭蕉の句が刻まれています。当寺の住職が芭蕉の弟子だったという縁で建てられたとのことです。
参道に沿って左手に日限地蔵尊、観音堂などが並びます。
日限地蔵尊は聖徳太子御作とも伝わり、毎年8月23日には日限地蔵尊大祭が営まれます。
こちらの日限地蔵尊にはつぎのような縁起が伝わっています。
江戸の昔、三島宿に向かう一人の旅人が物盗りに襲われ、刀で斬りつけられて気を失ってしまいました。翌朝気がつくと傍らに袈裟懸けに斬られた石のお地蔵さまが横たわっていました。旅人はこのお地蔵さまが身代わりになってくれたと悟り、近くの連馨寺に運び手厚くお祀りしました。
当初は「身代わり地蔵」といわれたこのお地蔵さまは、いつしか日を限ってお願いすると願いが叶うという「日限地蔵尊」として信仰を集め、横浜・日限山の福徳院、長野・岡谷の平福寺に御分身されお祀りされています。
この三体の地蔵尊は「三大日限地蔵尊」と称され多くの信仰を集めたとのこと。
こちらの日限地蔵尊は、駿河一国百地蔵尊霊場第96番の札所となっています。
-------------------


本堂は階段の上に入母屋造本瓦葺、重厚な向拝を備えた堂々たる伽藍で、向拝に寺号扁額を掲げています。
本堂右手の聖徳太子堂は、大正11年、地元技術諸職48名の発起により大和法隆寺より御分身を勧請し建立されたもの。
由緒書きにはありませんが、その背景には日限地蔵尊が聖徳太子御作と伝わっていることもあるのだと思われます。
・御朱印は庫裡にて拝受しましたが、観音霊場の御朱印は授与されていないとのことです。(地蔵尊霊場については訊きわすれました。)
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印
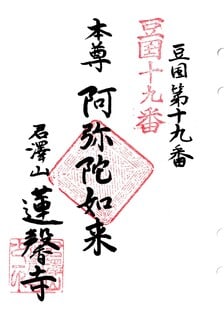
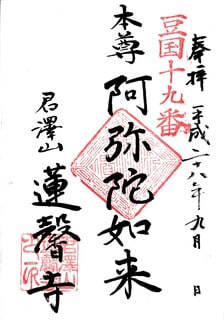
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ (湯郷)三島温泉 「湯郷三島温泉」の入湯レポ
■ 第20番 福翁山 養徳寺(ようとくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市資料
函南町平井1126
臨済宗円覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:円覚寺百観音霊場第27番、中伊豆観音札所第13番
授与所:庫裡


嘉應元年(1387年)、用固という僧によって開創。 寛政元年(1789年)の火災により堂塔、寺伝などをすべて焼失したため、詳細な沿革は不明となっていますが、寛政元年(1789年)牛窓和尚が本堂庫裡再建と伝わります。
『円覚寺百観音霊場 御納経帳』には、「開創以来過去数百年、その間幾多の盛衰、興廃あり、後人の亀鑑となるべき歴代の法躅、先哲の遺芳等多くあったと思われるがその記録のないのが惜しまれる」とあります。
『豆州志稿』には「平井村 奈古谷國清寺末 本尊十一面観世音 本養徳院ト云 天正(1573-1592)の頃ヨリ寺号ヲナシテ國清寺ニ隷ス 嘉應中僧用固創立ス後 享保七年(1722年)僧一渓中興ス 廃薬王寺ノ本尊当寺ニ安す」とあります。
-------------------


畑毛温泉にもほど近い、函南の山里にあります。
参道入口に寺号標。その先に切妻屋根銅板葺の薬医門。
山門を抜けると右手に枯山水の石庭が広がりそのおくに本堂。
入母屋造銅板葺で桁行きのある端正な伽藍です。
御朱印は庫裡にて拝受。円覚寺百観音霊場の御朱印も拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

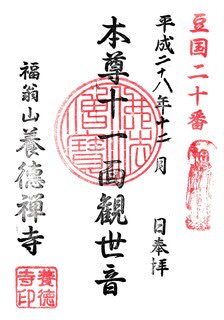
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 円覚寺百観音霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

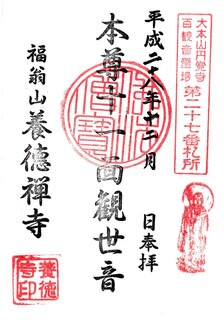
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第21番 圓通山 龍澤寺(りゅうたくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市観光ガイド
三島市資料
三島市沢地326
臨済宗妙心寺派
御本尊:子安観世音菩薩
札所本尊:子安観世音菩薩
他札所:中伊豆観音札所第6番
授与所:庫裡


宝暦十一年(1761年)、白隠禅師により開山されたという臨済宗妙心寺派の名刹。
当寺住職は代々老師として称えられ、開山白隠老師をはじめ、東嶺老師、明治の星定老師、大正昭和の玄峰老師はわけても名声高く、各界の名士が参禅しました。
「今白隠」とも賞された山本玄峰老師の大正期の復興により、国内有数の禅道場として名を高めたとされます。
『豆州志稿』には「澤地村 西京妙心寺末 本尊子安観世音 舊愛宕山下ニ在リテ弘法大師開基ノ由 國初ノ頃三島心経寺ノ天外和尚済門ヲ開ク 寶暦十年今ノ地ニ移シ駿州原驛松隠寺ノ白隠禅師ヲ祖トシ妙心寺に隷ス」とあります。
山内には本堂、庫裏、禅堂、経堂、鐘楼、不動堂、開山堂などが軒を連ね、開山堂内には白隠、東嶺、星定、玄峰の4老師像が安置されています。
星定老師像は鏝細工の名工、入江長八の作として知られ、白隠禅師が83歳の時に自ら描かれたという「紙本著色白隠自画像」は県指定文化財となっています。
毎年11月23日の観楓祭には所蔵の宝物が一般公開され、多くの拝観客が訪れます。
-------------------


三島市街の北東の山裾にあり、龍澤禅寺とも呼ばれます。
伊豆八十八ヶ所霊場はこの龍澤寺がもっとも北の札所で、ここで方向を転じ東海岸沿いを南伊豆に向かって南下していきます。
山内は石垣の上に築かれ、さながら城郭のよう。
うっそうと古木の茂る階段をのぼると、獅子・貘の木鼻と中備に龍の彫刻を置いた二軒垂木の風格ある山門。
山内には鐘楼、経堂、開山堂、本堂、禅堂、庫裏などが整然と並びます。
どこを切りとっても絵になり、これはインバウンド客にも人気が高そう。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
いまも禅道場として修行僧の修行の場となっており、接心修行時にはお遍路であっても境内に入場できなくなるので要注意です。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 子安観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
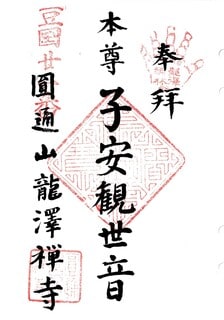
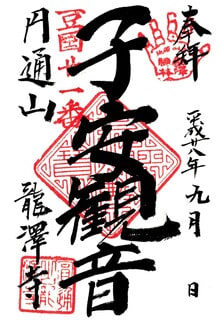
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第22番 龍泉山 宗福寺(そうふくじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
三島市塚原新田69-1
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:-
授与所:庫裡


天正十八年(1590年)豊臣秀吉が小田原を攻めた際、出城となった山中城で出た戦没者を追悼するため、延寶元年(1673年)、法華寺三世橘庵明洲により創建された曹洞宗寺院です。
『豆州志稿』には「塚原新田 三島法華寺末 本尊阿彌陀 当地ハ天正十八年(1590年)ノ古戦場ナレハ戦死者追福ノ為ニ延寶元年(1673年)法華寺三世明洲創立ス」とあります。
山中城は永禄年間(1558-1570年)に北条氏康により小田原の西の防衛を担うため、箱根山中腹の標高580mの地に、東海道を取り込む形で構えられたといいます。
「山中城合戦 戦国時代最大の攻城戦」(三島市資料)によると、天正十八年(1590年)、全国制覇を目論む豊臣秀吉は後北条氏の征伐(小田原征伐)に向かいました。
3月29日早朝、山中城を豊臣軍約七万の軍勢が取り囲みました。
右翼に池田輝正勢、左翼に徳川家康勢、中央に総大将の豊臣秀次以下、中村一氏、一柳直末、山内一豊、堀尾吉晴などが三手に分かれて布陣したといいます。
後北条方は城主の松田康長、援将の北条氏勝、間宮康敏、松田康郷、蔭山氏広以下約四千で迎え撃ったとされます。
後北条方は善戦したものの衆寡敵せず、正午過ぎには山中城は落城したとされ、激戦を物語るように、両軍の戦死者は二千にも達したと伝わります。
「戦国時代最大の攻城戦」といわれる所以です。
北条氏滅亡とともに山中城は廃城となりました。
秀吉はここまで力攻めを嫌った武将でしたが、このような激しい城攻めとなったのは、天下人たる実力を世に示す必要があったこと、秀吉に対して戦功をあげるため、武将達が奮戦したことによるとみられています。
宗福寺のある塚原新田は東海道の箱根越えの登り口に当たっているため、この地に創建されたと考えられます。
-------------------

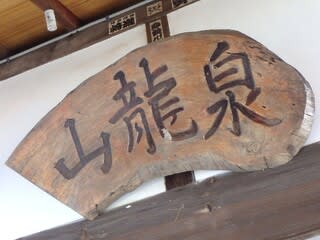
東海道から1本北側に入った道沿いにあります。
山門は切妻屋根銅板葺でおそらく薬医門
正面に入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。照りむくりがなく、直線的な屋根勾配。
水引虹梁まわりもスクエアでシンプル。向拝見上げに山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂よこの庫裡にて拝受しました。
ここから札所は伊豆東海岸に移ります。
続行の場合は、伊豆縦貫自動車道~熱函道路~熱海峠のルートがとれますが、第23番東光寺まではかなり距離があり熱海峠~東光寺は悪路のうえに、東光寺の御朱印は伊豆山の般若院(第24番)での拝受となるので、ひとまず区切りとするタイミングかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

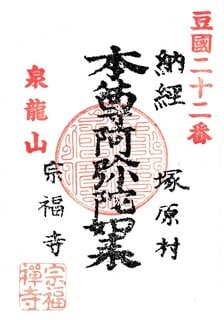
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3へ。
【 BGM 】
■ One Reason - milet
■ 春に落ちて - 鹿乃 / Kano
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)から
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へ
5.(浄明寺)熊野神社
神奈川県神社庁資料
鎌倉市浄明寺3-8-55
御祭神:天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命
旧社格:村社、浄明寺(村)の鎮守
元別当:
浄妙寺の西北に御鎮座の熊野神社。
朝比奈切通しそばにも熊野神社がありますがこちらは横浜市金沢区の所在で、当社とは別のお社です。
境内由来書などになると、応永年間(1394-1427年)および永正年間(1504-1520年)に社殿を再建したと伝えられ、明治6年、国より正式に浄明寺地区の鎮守として公認されています。
7月の祭礼(夏祭り)には「湯花神楽」「鎌倉神楽」といわれる神楽が数年おきに奏され、「火の神水の神を招神して感謝し、除災招福を祈り弓矢の威力で悪魔調伏を行います。」(境内由来書)とのこと。
『新編鎌倉志』の大休寺の項に「熊野山と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。」とあり、位置的にこちらとの関連を連想しましたが、境内由来書には「相模風土記稿に『熊野神社は村の鎮守なり』と記録されてあります。」「このお宮は古くから浄明寺地区の氏神様として信仰されてきました。」とあるので、『新編相模國風土記稿』の熊野社「泉水ヶ谷字東之澤。寶生庵跡ノ東ニアリ。此谷ヲ御坊ト云フ。村ノ鎮守ナリ。」がこちらに比定されているようです。
(神奈川県神社庁資料も上記『新編相模國風土記稿』の記事を引用されています。)
ただし、下の『新編鎌倉志』の浄妙寺山内図(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)をみると、あきらかに熊野神社は大休寺の西に位置しているので、大休寺の項の「此西の方に熊野の祠あり。」の”祠”もまた、熊野神社をさしているのかもしれません。
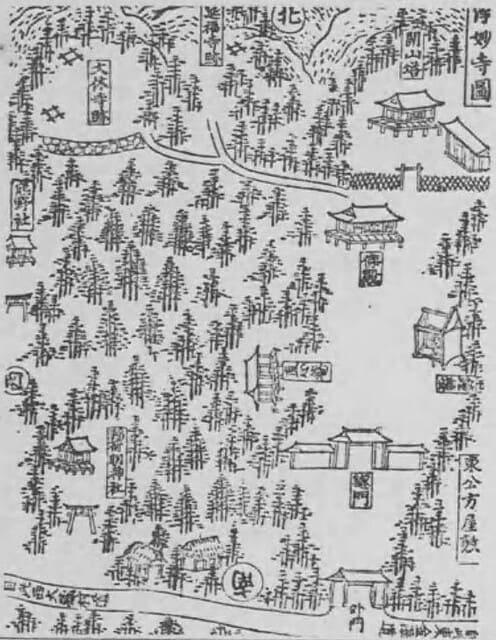
1.十二社神社の記事でも書きましたが、「熊野三所権現」とは、ふつうスサノオ、イザナギ、イザナミをさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。
これに対してこちらの御祭神は境内由来書に「天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命」とあり、天宇須女命(アメノウズメ)が筆頭に記されています。
天宇須女命は瓊々杵尊命(瓊瓊杵尊)の天孫降臨の際に従われた五伴緒(いつとものお・天児屋命、布刀玉命、天宇受売命、伊斯許理度売命、玉祖命)の一柱で、天照大神の岩戸隠れの際に活躍された神様です。
天照大神、瓊々杵尊命ともに「熊野十二所権現」にあらわれておわすので、その所縁で天宇須女命が御祭神になられているのかもしれませんが、もっとふかい所縁があるのかもしれず、よくわかりません。
----------


【写真 上(左)】 浄妙寺山門下からのアプローチ
【写真 下(右)】 参道手前
浄妙寺の山門下を左手にまわり込む路地に入ります。
道幅は狭く、この先に神社があるとは思えない道です。
しばらく行くと左手に鳥居が見えてきて、この先のゲートで道は行き止まりになっています。(この先は「石窯ガーデンテラス」(浄妙寺)の敷地。)


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 参道1
社頭に社号標と木製の神明鳥居で、ここから熊野神社の長い階段が始まります。
お隣の民家との境には風流な光悦垣が結われています。
途中いくつかの踊り場を設けながら、参道階段は山肌を急角度でのぼっていきます。


【写真 上(左)】 参道2
【写真 下(右)】 手水舎


【写真 上(左)】 参道からの社殿
【写真 下(右)】 社殿
しばらく行くと屋根付きの手水舎。そこから数段でようやく拝殿です。
石灯籠二対の先に、切妻造桟瓦葺流れ向拝の拝殿。
そのよこに隣接する切妻造桟瓦葺の建物は社務所でしょうか。
アプローチルートが行き止まりということもあり、辺りは静寂につつまれています。
周囲はうっそうと茂る社叢で、神々しい空気が感じられます。
拝殿側面(妻部)に大きな開口部があり、ここは神楽殿になるのかも。


【写真 上(左)】 左手からの社殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
向拝は水引虹梁両端にシンプルな木鼻、頭貫上に斗栱、中備に彫刻。
向拝正面は桟唐戸。向拝上には「熊野神社」の社号扁額が掲げられています。
本殿は拝殿おくに隣接し、切妻屋根瓦葺の覆屋は大棟に経の巻獅子口、妻部に蕪懸魚を置いています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 御朱印
通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。
6.長盛山 松久寺
鎌倉市浄明寺5-9-36
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:東京二十五社天神霊場第6番(花城天神)
金沢街道沿いに案内看板が出ていて以前から気になっていた、鎌倉市内では稀少な曹洞宗寺院です。
先般、Web検索してみると、なんと御朱印授与されているとのことで急遽参拝しました。
由緒書も公式情報も得られていませんが、複数のWeb情報はほぼ下記の内容で一致しています。
「明暦元年(1655年)、心霊牛道(暉山吐光禅師)が開かれ、もとは東京都港区高輪一丁目(以前の白金丹波町)にあったが首都高建設の予定地となったため、昭和41年に現在地に移転。平成28年から一般開放されている模様。」
御本尊は、御朱印拝受時のヒアリングによると地蔵菩薩とのことです。
江戸時代前期の白金の寺院であれば、名所図会類に載っている可能性があるので辿っていくと、たしかに見つかりました。
たとえば、『江戸切絵図』うち『目黒白金絵図』(人文学オープンデータ共同利用センターWeb)に、「松久寺」の文字が見えます。高輪清正公覚林寺のそばです。
いくつかの絵図類で辿れましたが、いずれも天満宮との関連で紹介されています。
『新撰 東京名所図会 第三十四編』のP.28に、つぎの記載があります。
「白金丹波町三番地即ち樹木谷なる松久寺といへる禅刹に菅公の祠あり。もと花城天満宮といひ。俗に厄除天満宮と称せり。新編江戸志に。社伝を載せていふ。仁和二年(886年)菅家御年四十二歳。正月十六日。讃岐守に任し給ふ折から。手つから刻ませ給ふ。同御腹こもり本地十一面観世音。一刀三禮の御同作なり。其の後(延喜元年(901年))、太宰府へ流遷の比。河内國土師里御叔母君覺壽院の所へ立より給ひ。此尊像をかたみに進せらる。文禄の比故りて加藤家山田氏の家にむかへ奉り。其後檀家の因縁に依て当寺に安置し奉ると。」
『江戸名所図会』にも同様の記載があり、挿絵も載せられています。
かつて、江戸ないし東京二十五社天神(霊場)という天神さま巡りがあり、第6番に「花城天神」がリストされているので、江戸でも有名な天神さまであったとみられます。(出所:「ニッポンの霊場」様)
そういうことであれば、当然参拝時に「花城天神」の所在についてお訊きしていたはずですが、なんにせよこれを調べたのが参拝後なので後の祭り。
ただし、いくつかのWeb情報には「本堂内に御鎮座」とあります。
なお、開山の心霊牛道(暉山吐光禅師)についてはコトバンクに記載があります。港区・愛宕の名刹青松寺の住持であられたようです。
----------


【写真 上(左)】 駐車場手前の入口
【写真 下(右)】 駐車場奥の入口
金沢街道、泉水橋信号から南の路地に入ります。鎌倉には幾度となく来ていますが、この路地に入るのはこれが初めてです。
民家が密集したかなり入り組んだ路地で、この先にお寺があるのか不安になりますが、案内看板が出ているのでこれに従い進みます。
路地を右に曲がって少し行くといきなり視界が広がって、鎌倉の寺院とは思えない広い駐車場があります。
駐車場の手前に寺号標と門柱があり、こちらが三門かと思いましたが、駐車場先にも寺号標と掲示板のある入口があって山内入口の構成がよくわかりません。


【写真 上(左)】 坂道の参道-1
【写真 下(右)】 坂道の参道-2
ここから石敷きの坂道を登っていきます。
紅葉が綺麗な時季でしたが、観光客のすがたはまったく見当たらない静かな山内。
坂の途中にはベンチが置かれ、おだやかな表情の石仏が御座す道の両辺もすっきりとして整備が行き届いた印象です。
さらに行くと階段があり、その上に近代建築の瀟洒な建物が見えてきます。
登り切ると門が開け放たれ、その先に受付らしきものがあります。


【写真 上(左)】 石仏-1
【写真 下(右)】 石仏-2


【写真 上(左)】 階段下から
【写真 下(右)】 受付
情報が少なく、以前は拝観不可だったという話もあって、正直おそるおそるの参拝でしたが、予想以上に開かれたイメージがありました。
受付に女性の方がいらしたので、素通りするのもどうかと思ってお声がけし、ついでに御朱印についてお伺いすると、本日は書置ですがお出しできます、との快いお返事。
御朱印の見本があったので1種選んでお願いし、正面の本堂に向かいます。
前庭左手に「三郎地蔵尊」と十三重石宝塔。右手の建物は客殿でしょうか。


【写真 上(左)】 三郎地蔵尊
【写真 下(右)】 本堂
うっそうと茂る木々を背に、寄棟造本瓦葺と思われる堂々たる本堂。
向拝扉は開け放たれ、五色の向拝幕が張り巡らされて華々しい印象です。
堂内はすこぶる整備された空間で、正面に黄金に輝く地蔵菩薩が御座します。
受付手前を左に進むと赤い鳥居のお稲荷様が御鎮座。こちらは地主神でしょうか。

御朱印は数種あるようでいずれも尊格は地蔵菩薩。
豪快な筆致の絵御朱印で、これは絵御朱印マニアに人気がありそうです。
書置を用意されているようなので、ご住職ご不在時でも拝受できそうです。
7.功臣山 報国寺(報国建忠禅寺)
公式Web
鎌倉市浄明寺2-7-4
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)
「竹の寺」として人気の高い臨済宗建長寺派の寺院です。
公式Webなどから、由緒をまとめてみます。
建武元年(1334年)、仏乗禅師天岸慧広(てんがん えこう)により開山。
天岸慧広は南宋出身の臨済宗の高僧・無学祖元(仏光国師)に師事し、高峰顕日(仏国禅師)の法を嗣ぐとされる禅師です。
元応二年(1320年)元に渡られ、元徳元年(1329年)帰国。自筆の作とされる『東帰集』は「五山文学」の代表作として知られています。
『東帰集』(伝仏乗禅師筆)は、国の重要文化財に指定され、『絹本著色佛乗禅師像』および『堆朱印櫃入木印』(「天岸」「慧広」の木印)が附指定されています。
また、当寺は運朝作とされる開山仏乗禅師坐像(鎌倉市指定文化財)を所蔵されています。
開基は足利尊氏公の祖父家時公(報国寺殿義恩)とされていますが、宅間上杉家の祖、上杉重兼が開基という説もみられます。
なお、このあたりは”宅間谷戸”と呼ばれ、鎌倉幕府の絵師、宅間為行や宅間法眼一派(宅磨派)の絵仏師達が住していました。(宅間上杉家と宅間法眼一派の関係は不明。)
『新編鎌倉志』には「本尊、釋迦・文殊・普賢・迦葉・阿難、迦葉は、詫間法眼が作也。詫間の迦葉と云伝へて名佛也。此辺を詫間が谷と云なり。詫間が旧居か。」とあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉憲実の対立などから永享の乱がおこり、室町幕府の援護を受けた上杉憲実が足利持氏を破りました。
足利持氏勢は鎌倉の永安寺(現・世田谷区大蔵)に入り、憲実は幕府に持氏の助命と嫡子義久の関東公方就任を再三嘆願したものの将軍義教公は許さず憲実に持氏殺害を厳命、憲実はやむなく永安寺を攻め、持氏は永安寺、義久は報国寺において自害したとされます。
関東管領の憲実にとって、鎌倉府の長官である鎌倉公方の持氏は主筋にあたり、主筋を討ったことを憂いた憲実は、乱後伊豆国清寺に退き出家、後年は諸国遍歴の旅に出て長門国大寧寺で逝去と伝わります。
足利義久は関東公方・足利持氏の嫡男で、「大若君」と尊称されました。
永享十年(1438年)鶴岡八幡宮で加冠元服。源義家公の先例にならい八幡太郎を称したとされる、押しも押されぬ源氏の御曹司です。
享年は17とされますが、諸説あるようです。
没後、報国寺は義久の菩提を弔い、菩提寺となりました。
『新編相模國風土記稿』には、以下のとおりあります。
「永享ノ乱ニ。持氏ノ息義久。十歳ナリシカ。当寺ニ在テ自害セリ。永享十一年二月十日。持氏御自害同廿八日若君義久十歳ニナラセ給ヒケルヲ。奉討ヘキ由聞エケレハ。報国寺ニ御座セシカ。」
「佛殿 本尊釋迦 長二尺二寸余定朝作 文殊普賢迦葉。阿難 各長三尺五寸許等ノ像ヲ安ス。共ニ詫間法眼カ作ニテ。迦葉ノ像。最其名高シ故ニ世俗当寺ヲ詫間寺又迦葉寺ナト呼ヘリ 開基伊豫守家時ノ像ヲモ置ケリ。是ハ旧休耕庵ニ安セシ像ナリ。」
「地蔵堂・出世地蔵ト云フ 諏訪社。稲荷社。八幡宮。三峯社 以上境内四方ノ鎮守トス。足利家時墓 祖塔休耕庵 開山塔・本堂ノ西ニアリ。太子堂・泉水谷ニアリ。」
足利持氏・義久の没後鎌倉公方は一旦断絶、後に持氏の遺児成氏が幕府から鎌倉公方就任を許されて鎌倉公方は復活するものの、享徳三年(1455年)からの享徳の乱を受け、以降は下総国古河を本拠とし「古河公方」を名乗りました。
----------
金沢街道「報国寺入口」信号から南側に入ってすぐ。あたりは閑静な住宅地です。
宅間派の芸術家が住んだという歴史があるためか、家々の佇まいにもどこか瀟洒な風があります。
こちらのお寺はとくに女性に人気が高く、週末などは着物姿の女子も多くみられます。


【写真 上(左)】 参道から山門
【写真 下(右)】 山門
山門前からすでに整備された参道が延びています。
山門は切妻屋根本瓦葺で、重厚な大棟・降棟を備えた本柱二、控柱二の薬医門。
山門脇の寺号標は「報国建忠禅寺」と正式寺号が刻まれています。
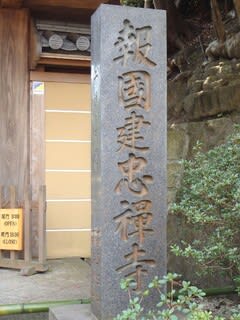

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道と庭園
山門をくぐると左手に美しく砂紋が描かれた枯山水が広がります。
地表をおおう緑の苔と枯山水の対比があざやか。
枯山水のむこうの石上に御座す半跏思惟像は弥勒菩薩ではなく、観音さまのような感じがします。


【写真 上(左)】 砂紋
【写真 下(右)】 半跏思惟像
ゆるやかにカーブを描く石敷きの参道を進み石段をのぼると、やにわに視界が開けて正面が本堂。左手に鐘楼、右手には迦葉堂。


【写真 上(左)】 本堂下の階段-1
【写真 下(右)】 本堂下の階段-2


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 観音霊場札所板
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に二連の海老虹梁(?)、中備に龍の彫刻。
向拝正面の障子戸は開け放たれ、上部には寺号扁額が掲げられています。
両側の細かな連子が意匠的に効いて引き締まった印象の向拝。
御本尊の釈迦牟尼佛は鎌倉時代作とされ、鎌倉市指定文化財です。


【写真 上(左)】 迦葉堂-1
【写真 下(右)】 迦葉堂-2
迦葉堂はおそらく入母屋造銅板葺妻入り、階段をのぼっての参拝です。
こちらにはおそらく伝・詫間法眼作の迦葉尊者像が奉安。
迦葉(摩訶迦葉)はインド僧で、釈尊が悟りを開かれてから弟子となった十大弟子の一人です。
また詫間法眼は、鎌倉時代末から室町時代前半の鎌倉地方造仏界で主流を担った「詫間派仏所」を代表する仏師とされ、その精妙巧緻な表現には宋元美術の影響が認められ、南北朝時代の制作と推定されています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 石塔群
鐘楼の左にある石塔群は、新田義貞鎌倉攻めの際の北條勢新田勢両軍戦死者の供養塔といわれています。


【写真 上(左)】 賑わう山内
【写真 下(右)】 本堂と迦葉堂
本堂左手に「竹の庭」の拝観受付があり、本堂裏手を回り込むと庭園。庭園は、開山の天岸慧広禅師作と伝わるもの。春先に咲くサンシュユが有名です。


【写真 上(左)】 「竹の庭」への道すじ
【写真 下(右)】 庭園
竹林右手の岩肌にはやぐらが掘られて、たくさんの五輪塔が並びます。
開基の家時公と、この地で自刃した足利義久の墓があるとされます。


【写真 上(左)】 庭園とサンシュユ
【写真 下(右)】 お地蔵さまとやぐら


【写真 上(左)】 苔庭のお地蔵さま
【写真 下(右)】 苔庭と竹林
苔庭の向こうが竹林。みごとな孟宗竹が空に向かってすくすくと伸びています。
その中を小道が通っているので、竹林の絶好の撮影ポイントです。


【写真 上(左)】 竹林-1
【写真 下(右)】 竹林-2


【写真 上(左)】 竹林-3
【写真 下(右)】 竹林-4
そして竹林のおくに人気の茶席「休耕庵」。


【写真 上(左)】 休耕庵-1
【写真 下(右)】 休耕庵-2
孟宗竹の竹林「竹の庭」と茶席「休耕庵」は鎌倉観光のハイライトのひとつで、Web記事があふれんばかりにあるので、こまかい説明は省略します。
なお、「休耕庵」は、慧広禅師の塔頭の号からとられたものとみられます。
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の3つ。
別に御本尊の御朱印を授与されているので御朱印は4種となります。
御本尊、釈迦如来の御朱印はおそらく申告制で、Webの画像検索からすると無申告ではおそらく鎌倉観音霊場の「聖大悲殿」の授与になるかと思います。
〔 御本尊・釈迦如来の御朱印 〕

鎌倉三十三観音霊場第10番の札所本尊は本堂別間に御座す聖観世音菩薩です。
本堂向拝には、観音霊場の札所板が掲げられています。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

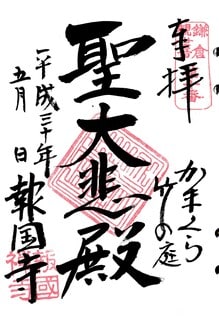
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉十三仏霊場第8番(釈迦如来)も観音霊場札所本尊の観音さまとみられます。
〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕

●主印は聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多く、こちらもその様式です。
こちらは、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の札所でもあります。
札所本尊は聖観世音菩薩で、おそらく鎌倉観音霊場、鎌倉十三仏霊場と同じ観音さまかと思われます。
花種はサンシュユで花期は2月~3月。
春のボケ・バラ、夏のイワタバコ、冬のフユザクラ・ツバキも見どころの花の寺です。
〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕

●主印は三寶印、揮毫は「聖大悲殿」で「鎌倉第五番」の揮毫があります。
繊細かつ風雅な趣きをもつ女性ごのみのお寺さまで、明るく開けた4.浄妙寺とは対照的。
鎌倉デートで、浄妙寺のつぎに報国寺をセッティングすれば、さらにポイントを稼げるのでは(笑)
8.大蔵山 観音院 杉本寺
公式Web
鎌倉市二階堂903
天台宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番
鎌倉最古の寺ともいわれる鎌倉を代表する古刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)を務められるメジャー寺院です。
天平三年(731年)、東国巡錫中の行基菩薩が当地にて観音様の霊感を感得し自ら一刀三礼で十一面観世音菩薩を刻され、本尊として奉安したのが草創とされます。
天平六年(734年)、聖武天皇后の光明皇后の発願により、藤原北家の祖、右大臣藤原房前公と行基菩薩が本堂を建立して創建。開山は行基菩薩と伝わります。
仁寿元年(851年)、慈覚大師円仁が参詣され、自ら十一面観世音菩薩を刻まれて安置。
寛和二年(986年)には花山法皇の命を受けた恵心僧都源信が熊野権現のお導きにより十一面観世音菩薩を刻して奉安し、そののち花山法皇も巡礼されたといいます。
『新編鎌倉志』には「杉本観音堂は街道より北にあり。(略)坂東巡礼札所の第一なり。開山は行基なり。此寺は天台宗にて、叡山の末寺なり。中比衰微して(略)本尊十一面観音慈覚作。右も十一面行基作。左も十一面慧心作。前にも又十一面あり運慶作。釋迦天竺佛。毘沙門宅間作。」とあります。
山内掲示には「鎌倉、室町時代の大火、兵火に遭い、江戸期に於いては、一時期無住の時もあり、後の明治の排仏毀釈、又震災等により寺運も衰微し、七堂伽藍も観音堂等を除き、悉く焼失倒壊してしまいました。(略)昭和四十八年より伽藍復興大勧進(略)多くの皆様のご協力、ご協賛により浄財を得まして左記のごとく円成の運びと相成りました。」とあり、観音堂以外の堂宇はおおむね昭和の円成とみられます。
----------

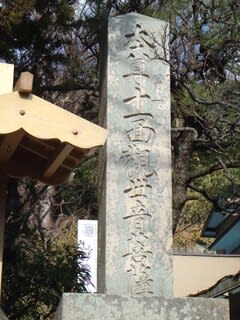
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
金沢街道に面した山内入口。街道の歩道からすぐに参道階段がはじまります。
右手に寺号標、参道階段両脇には「十一面杉本観音」の幟が立ち並び、はやくも霊場札所の趣きゆたか。
左の石標には「坂東第一番杉本寺観世音菩薩」、右の石標には「本尊十一面観世音菩薩」とあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 拝観受付と参道


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門扁額


【写真 上(左)】 仁王尊
【写真 下(右)】 仁王尊
しばらく登ると左手に拝観受付、その先の階段上には仁王門がそびえています。
江戸時代中期の築とされる切妻造茅葺両脇間一戸の八脚門で、左右に運慶作とも伝わる金剛力士(仁王)像を安置し、見上げに「大蔵山」の山号扁額。


【写真 上(左)】 仁王門から「苔の階段」
【写真 下(右)】 「苔の階段」
仁王門を抜けると見どころのひとつ、すり減って苔むした鎌倉石の石段参道(通称「苔の階段」)ですが、現在は通行禁止となっています。


【写真 上(左)】 大蔵辯財天-1
【写真 下(右)】 大蔵辯財天-2
右手には大蔵辯財天が御座します。
鳥居があるので「ここって神社?、お寺?」状態になりますが、当寺は中世~江戸期に神仏習合したともみられ、厳密な区別はむずかしいかもしれません。
「大蔵辯財天」の扁額が掛かった石造台輪鳥居の正面に大きな石の香炉。そのおくに銅板葺一間社流造のお社(堂宇)。
左手の池は洞窟を構えて、いかにも弁天様の境内らしい雰囲気を醸しています。
『新編相模國風土記稿』の観音堂の項に「辨天社 巌穴ニ安置ス。」とあるので、もともとはこの洞窟に祀られていたのかもしれません。
公式Webによると、「大蔵辯財天」をお参りすると大きな蔵が建つ程富に恵まれるという言い伝えがあるそうです。
「苔の階段」は登れないので、これを左の階段からまわりこむかたちでのアプローチ。
天台宗の寺院らしく、階段の途中に伝教大師童形像が御座します。
もうひと登りでT字路になり、左は小道、右手が本堂。
小道をすこし行った高みからは鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)がよく見えます。


【写真 上(左)】 衣張山
【写真 下(右)】 左手からの本堂
本堂(観音堂)は、寄棟造茅葺方五間(桁行・梁間ともに五間)、身舎の四面に庇を廻らす密教仏堂です。
棟札から、延宝六年(1678年)の建立とみられ、県指定文化財に指定されています。
方五間なので堂内は外陣、内陣にわかれ、通常は内陣に上がって参拝できますが、新型コロナ禍では外陣からの参拝となります。


【写真 上(左)】 右手からの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
堂内は撮影禁止ですが、公式Webに詳細の本堂内配置図があるので、こちらに沿ってご案内します。
堂内手前右手は納経所。数多い御朱印はすべてこちらでの授与となります。
格子戸の奥の内陣向かって左は行基菩薩御作(素木一木造、平安)、中央が円仁慈覚大師御作(寄木造漆箔、鎌倉)、向かって右は源信恵心僧都御作(寄木造漆箔、鎌倉)の十一面観世音菩薩の秘仏本尊三体(三尊同殿)で、慈覚大師御作と源信恵心僧都御作は国の重要文化財に指定されています。
毎月1日と18日に秘仏本尊御開帳のWeb情報もありますが、現況は定かではありません。
鎌倉時代の火災の折、御本尊三体は自ら山内の大杉の下に火を避けられたので、それより「杉(の)本(の)観音」と呼ばれたと伝わります。
また、礼を欠き、信心なき者が門前を乗馬のまま通り過ぎると落馬するというので、建長寺開山の大覚禅師(蘭渓道隆)が祈願され、自らの袈裟で行基菩薩御作の十一面観世音菩薩のお顔を覆ったところ、以降落馬する者がなくなったといいます。
このため行基菩薩御作のお像は「覆面観音」「下馬観音」とも呼ばれて市の指定文化財となっています。
頼朝公寄進の御前立の十一面観世音菩薩(伝・運慶作)は、常時御開扉されています。
このほか、本堂時計まわり、御本尊に向かって左手におびんづるさま、伝・運慶作の地蔵菩薩立像、伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像、新十一面観音。
御本尊に向かって右手に毘沙門天(宅間法眼作)、不動明王と伝・運慶作の観音三十三応現身。
本尊御前立は十一面観世音菩薩像、不動明王と毘沙門天は脇立の位置づけのようで、これは密教寺院の十一面観世音の堂宇でよくみられる様式です。
ほの暗い堂内には焼香の煙が絶えず、ときおり参拝団の読経の声が聞こえたりして、さすがに坂東霊場発願所らしい趣きがあります。


【写真 上(左)】 鐘楼堂
【写真 下(右)】 本堂右手
本堂向かって右手には鐘楼堂、五輪塔群、地蔵尊、右手おくの権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。
中世、杉本寺および背後の大蔵山には杉本城が築かれていました。
三浦氏嫡流三浦義明の長子で杉本氏の祖・杉本義宗が六浦道(金沢街道)・朝比奈口を抑える要衝のこの地に築城し、次男の義茂が入城。
源頼朝公が挙兵すると、三浦一族は源氏方につき居城の衣笠城を出立して石橋山に向かいましたが頼朝公の敗戦を聞いて衣笠城に篭城。攻め寄せた平家方の畠山重忠軍勢と衣笠城攻防戦を繰り広げ三浦義明は戦死しました。
三浦(杉本)義茂はこの戦の際、杉本城内から繰り出し畠山勢に攻めかかったと伝わります。
その後杉本城は継続しましたが、南北朝時代の建武四年(1337年)、この城に拠った北朝方の鎌倉府執事斯波家長が、朝比奈口から攻め入った南朝方の北畠顕家軍に攻められて破れ(杉本城の戦い)、杉本城は落城・破却されたとみられています。
本堂右手の五輪塔群は、杉本城の戦いで戦死した斯波家長と家臣の供養塔ともいわれています。


【写真 上(左)】 五輪塔群
【写真 下(右)】 覆屋の地蔵尊
そのお隣の覆屋のなかに地蔵尊が七体、覆屋の外にも一体が御座します。


【写真 上(左)】 身代地蔵尊御前立
【写真 下(右)】 権現社
本堂向かって右奥のやぐらを背にした権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。
石造の両部鳥居のおくに入母屋造銅板葺妻入りのお社(堂宇)。
恵心僧都源信は熊野権現のお導きにより御本尊十一面観世音菩薩を刻まれたとされるので、そちらとのゆかりがあるのかもしれません。
さて、ようやく御朱印です。
こちらの御朱印はたいへんに込み入っているので、丁寧に(笑)いきます。
札所としては鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の5札所、いずれも現役霊場です。
こちらの納経所(授与所)ですが、基本、お一人で書かれているようでグループ客が入ると一気に行列となります。(とくに行楽シーズンの週末)
いただける御朱印の種類は多いですが、発願札所がふたつもあるのでここは欲張らずに都度参拝がベターかも。
なお、新型コロナ禍のなかでは原則紙御朱印対応となり、授与時間も短くなるので要注意です。
とくに、発願参拝でどうしても御朱印帳に直書きいただきたい場合は、平日に事前確認のうえ参拝されたほうがいいかもしれません。
(今年は新型コロナ禍再燃のマイナス効果と、「鎌倉殿の13人」のプラス効果のせめぎ合いで、鎌倉観光の人出がまったく読めません。先日参拝したときはメジャー寺院もがらがらで無人の写真撮り放題でしたが、新型コロナ禍が首尾よく収まってリベンジ観光客が一気に吹き出すと、たいへんなことになるかもしれません。)
鎌倉三十三観音霊場第1番(発願)の札所本尊は、御本尊の十一面観世音菩薩です。
発願印は申告すればいただけますが、御朱印帳の途中の頁にいただけるかは定かではありません。
御朱印帳の最初の頁ならば大丈夫かと思いますが、導入編でも書いたとおり、鎌倉三十三観音霊場は専用納経帳での巡拝をおすすめします。(いまはどうかわかりませんが、専用納経帳でないと御朱印拝受がむずかしい札所があります。)
こちらでは数種類の紐綴じ型の納経帳を頒布されており、こちらで納経帳を入手すればスムーズに発願印を拝受できます。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。
鎌倉二十四地蔵霊場第4番の札所本尊「身代地蔵尊」は、本堂向かって左奥の伝・運慶作の地蔵菩薩立像で、本堂右手の覆屋内の七体並ぶ地蔵尊の一番右のおおぶりのお地蔵さまがお前立ちとされているようです。
杉本城を築城したとされる杉本(三浦)義宗に向けて放たれた矢がこちらの地蔵尊に当たり、地蔵尊の傷跡から血がにじみでたという伝承があり、地蔵尊が義宗の身代わりになられたことから「身代地蔵尊」と呼ばれるようです。
『新編相模國風土記稿』には、仁王門の左手に地蔵堂が描かれ、「地蔵堂 或伝ニ。此石佛ヲ。杉本太郎義宗カ。身代ノ地蔵トモ云フ。按スルニ。延元二年(1337年)斯波三郎。此ニテ自●セシ。斯波家長等カ為ニ。造建セシ。石佛ナルヘシ」とあるので、もともと「身代地蔵尊」は仁王門横の地蔵堂に御座していたのかもしれません。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場第4番(身代地蔵尊)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。
鎌倉二十四地蔵霊場第6番の札所本尊「尼将軍地蔵尊」は、本堂向かって左奥、「身代地蔵尊」の右隣の伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像です。
「身代地蔵尊」が第4番、第5番光触寺の「塩嘗地蔵尊」をはさんで第6番がこちらで、順打ち巡拝をむずかしいものにしています。
「尼将軍」といえば北条政子ですが、どうやら北条政子とのゆかりは不明のようです。
しかし、御朱印揮毫はしっかり「尼将軍地蔵尊」で、鎌倉らしい御朱印のひとつといえましょう。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場第6番(尼将軍地蔵尊)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。
相州二十一ヶ所霊場は、鎌倉の弘法大師霊場です。
鎌倉のかなりの観光寺院が札所となっていますが、御朱印見本に掲示されることはほとんどなく、鎌倉の御朱印ガイド類にもほとんど載っていません。
いわば「知る人ぞ知る鎌倉の霊場」で、しかも弘法大師霊場でありながら真言宗以外の札所も多くなっています。
どうしてこういう霊場が成立したのかは、いわく経緯がありそうですがここでは省略し、発願寺の宝戒寺で書きます。(丁寧にいきます。とかいいながらとりあえず逃げる(笑))
〔 相州二十一ヶ所霊場第2番の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は「阿字印」にも見えますが、違うかもしれません。
超メジャー霊場、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)の札所で、札所本尊は御本尊の十一面観世音菩薩です。
坂東三十三箇所(観音霊場)は超メジャー霊場なので、こちらについてのご説明は省略です。(丁寧にいきます。とかいいながらまたしても逃げる(笑))
こちらも発願印をいただけますが、鎌倉観音霊場と同様申告制だと思います。
なお、霊場無申告の場合の御朱印ですが、Web画像検索の結果からすると、おそらく鎌倉観音霊場のものになるのでは?(坂東三十三箇所かもしれぬ。)
いずれにしても、御本尊十一面観世音菩薩の御朱印になります。
〔 坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。
本堂内に御座す毘沙門天(大蔵毘沙門天)の御朱印も授与されていますが、こちらは申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。
〔 大蔵毘沙門天の御朱印 〕

●主印は毘沙門天の種子「バイ・ベイ」の御寶印(蓮華座)とみられます。
仁王門右手の「大蔵辯財天」の御朱印も授与されていますが、こちらも申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。
〔 大蔵辯財天の御朱印 〕

●主印は弁財天の種子「ソ」の御寶印(蓮華座)と思われます。
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へつづく。
【 BGM 】
■ One Reason - milet
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka
■ symphonia - kalafina
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へ
5.(浄明寺)熊野神社
神奈川県神社庁資料
鎌倉市浄明寺3-8-55
御祭神:天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命
旧社格:村社、浄明寺(村)の鎮守
元別当:
浄妙寺の西北に御鎮座の熊野神社。
朝比奈切通しそばにも熊野神社がありますがこちらは横浜市金沢区の所在で、当社とは別のお社です。
境内由来書などになると、応永年間(1394-1427年)および永正年間(1504-1520年)に社殿を再建したと伝えられ、明治6年、国より正式に浄明寺地区の鎮守として公認されています。
7月の祭礼(夏祭り)には「湯花神楽」「鎌倉神楽」といわれる神楽が数年おきに奏され、「火の神水の神を招神して感謝し、除災招福を祈り弓矢の威力で悪魔調伏を行います。」(境内由来書)とのこと。
『新編鎌倉志』の大休寺の項に「熊野山と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。」とあり、位置的にこちらとの関連を連想しましたが、境内由来書には「相模風土記稿に『熊野神社は村の鎮守なり』と記録されてあります。」「このお宮は古くから浄明寺地区の氏神様として信仰されてきました。」とあるので、『新編相模國風土記稿』の熊野社「泉水ヶ谷字東之澤。寶生庵跡ノ東ニアリ。此谷ヲ御坊ト云フ。村ノ鎮守ナリ。」がこちらに比定されているようです。
(神奈川県神社庁資料も上記『新編相模國風土記稿』の記事を引用されています。)
ただし、下の『新編鎌倉志』の浄妙寺山内図(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)をみると、あきらかに熊野神社は大休寺の西に位置しているので、大休寺の項の「此西の方に熊野の祠あり。」の”祠”もまた、熊野神社をさしているのかもしれません。
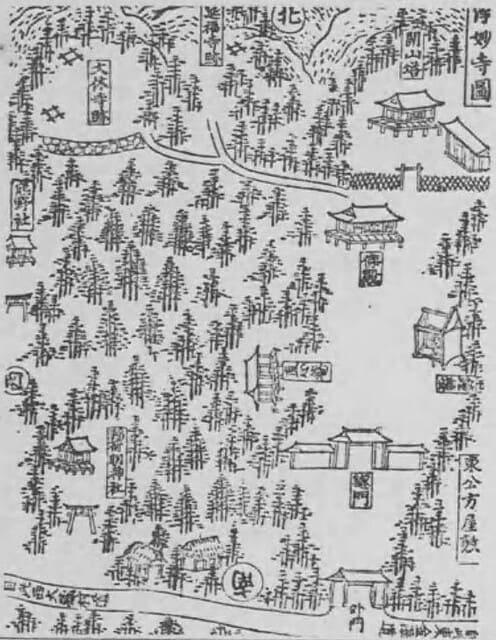
1.十二社神社の記事でも書きましたが、「熊野三所権現」とは、ふつうスサノオ、イザナギ、イザナミをさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。
これに対してこちらの御祭神は境内由来書に「天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命」とあり、天宇須女命(アメノウズメ)が筆頭に記されています。
天宇須女命は瓊々杵尊命(瓊瓊杵尊)の天孫降臨の際に従われた五伴緒(いつとものお・天児屋命、布刀玉命、天宇受売命、伊斯許理度売命、玉祖命)の一柱で、天照大神の岩戸隠れの際に活躍された神様です。
天照大神、瓊々杵尊命ともに「熊野十二所権現」にあらわれておわすので、その所縁で天宇須女命が御祭神になられているのかもしれませんが、もっとふかい所縁があるのかもしれず、よくわかりません。
----------


【写真 上(左)】 浄妙寺山門下からのアプローチ
【写真 下(右)】 参道手前
浄妙寺の山門下を左手にまわり込む路地に入ります。
道幅は狭く、この先に神社があるとは思えない道です。
しばらく行くと左手に鳥居が見えてきて、この先のゲートで道は行き止まりになっています。(この先は「石窯ガーデンテラス」(浄妙寺)の敷地。)


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 参道1
社頭に社号標と木製の神明鳥居で、ここから熊野神社の長い階段が始まります。
お隣の民家との境には風流な光悦垣が結われています。
途中いくつかの踊り場を設けながら、参道階段は山肌を急角度でのぼっていきます。


【写真 上(左)】 参道2
【写真 下(右)】 手水舎


【写真 上(左)】 参道からの社殿
【写真 下(右)】 社殿
しばらく行くと屋根付きの手水舎。そこから数段でようやく拝殿です。
石灯籠二対の先に、切妻造桟瓦葺流れ向拝の拝殿。
そのよこに隣接する切妻造桟瓦葺の建物は社務所でしょうか。
アプローチルートが行き止まりということもあり、辺りは静寂につつまれています。
周囲はうっそうと茂る社叢で、神々しい空気が感じられます。
拝殿側面(妻部)に大きな開口部があり、ここは神楽殿になるのかも。


【写真 上(左)】 左手からの社殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
向拝は水引虹梁両端にシンプルな木鼻、頭貫上に斗栱、中備に彫刻。
向拝正面は桟唐戸。向拝上には「熊野神社」の社号扁額が掲げられています。
本殿は拝殿おくに隣接し、切妻屋根瓦葺の覆屋は大棟に経の巻獅子口、妻部に蕪懸魚を置いています。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 御朱印
通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。
6.長盛山 松久寺
鎌倉市浄明寺5-9-36
曹洞宗
御本尊:地蔵菩薩
札所:東京二十五社天神霊場第6番(花城天神)
金沢街道沿いに案内看板が出ていて以前から気になっていた、鎌倉市内では稀少な曹洞宗寺院です。
先般、Web検索してみると、なんと御朱印授与されているとのことで急遽参拝しました。
由緒書も公式情報も得られていませんが、複数のWeb情報はほぼ下記の内容で一致しています。
「明暦元年(1655年)、心霊牛道(暉山吐光禅師)が開かれ、もとは東京都港区高輪一丁目(以前の白金丹波町)にあったが首都高建設の予定地となったため、昭和41年に現在地に移転。平成28年から一般開放されている模様。」
御本尊は、御朱印拝受時のヒアリングによると地蔵菩薩とのことです。
江戸時代前期の白金の寺院であれば、名所図会類に載っている可能性があるので辿っていくと、たしかに見つかりました。
たとえば、『江戸切絵図』うち『目黒白金絵図』(人文学オープンデータ共同利用センターWeb)に、「松久寺」の文字が見えます。高輪清正公覚林寺のそばです。
いくつかの絵図類で辿れましたが、いずれも天満宮との関連で紹介されています。
『新撰 東京名所図会 第三十四編』のP.28に、つぎの記載があります。
「白金丹波町三番地即ち樹木谷なる松久寺といへる禅刹に菅公の祠あり。もと花城天満宮といひ。俗に厄除天満宮と称せり。新編江戸志に。社伝を載せていふ。仁和二年(886年)菅家御年四十二歳。正月十六日。讃岐守に任し給ふ折から。手つから刻ませ給ふ。同御腹こもり本地十一面観世音。一刀三禮の御同作なり。其の後(延喜元年(901年))、太宰府へ流遷の比。河内國土師里御叔母君覺壽院の所へ立より給ひ。此尊像をかたみに進せらる。文禄の比故りて加藤家山田氏の家にむかへ奉り。其後檀家の因縁に依て当寺に安置し奉ると。」
『江戸名所図会』にも同様の記載があり、挿絵も載せられています。
かつて、江戸ないし東京二十五社天神(霊場)という天神さま巡りがあり、第6番に「花城天神」がリストされているので、江戸でも有名な天神さまであったとみられます。(出所:「ニッポンの霊場」様)
そういうことであれば、当然参拝時に「花城天神」の所在についてお訊きしていたはずですが、なんにせよこれを調べたのが参拝後なので後の祭り。
ただし、いくつかのWeb情報には「本堂内に御鎮座」とあります。
なお、開山の心霊牛道(暉山吐光禅師)についてはコトバンクに記載があります。港区・愛宕の名刹青松寺の住持であられたようです。
----------


【写真 上(左)】 駐車場手前の入口
【写真 下(右)】 駐車場奥の入口
金沢街道、泉水橋信号から南の路地に入ります。鎌倉には幾度となく来ていますが、この路地に入るのはこれが初めてです。
民家が密集したかなり入り組んだ路地で、この先にお寺があるのか不安になりますが、案内看板が出ているのでこれに従い進みます。
路地を右に曲がって少し行くといきなり視界が広がって、鎌倉の寺院とは思えない広い駐車場があります。
駐車場の手前に寺号標と門柱があり、こちらが三門かと思いましたが、駐車場先にも寺号標と掲示板のある入口があって山内入口の構成がよくわかりません。


【写真 上(左)】 坂道の参道-1
【写真 下(右)】 坂道の参道-2
ここから石敷きの坂道を登っていきます。
紅葉が綺麗な時季でしたが、観光客のすがたはまったく見当たらない静かな山内。
坂の途中にはベンチが置かれ、おだやかな表情の石仏が御座す道の両辺もすっきりとして整備が行き届いた印象です。
さらに行くと階段があり、その上に近代建築の瀟洒な建物が見えてきます。
登り切ると門が開け放たれ、その先に受付らしきものがあります。


【写真 上(左)】 石仏-1
【写真 下(右)】 石仏-2


【写真 上(左)】 階段下から
【写真 下(右)】 受付
情報が少なく、以前は拝観不可だったという話もあって、正直おそるおそるの参拝でしたが、予想以上に開かれたイメージがありました。
受付に女性の方がいらしたので、素通りするのもどうかと思ってお声がけし、ついでに御朱印についてお伺いすると、本日は書置ですがお出しできます、との快いお返事。
御朱印の見本があったので1種選んでお願いし、正面の本堂に向かいます。
前庭左手に「三郎地蔵尊」と十三重石宝塔。右手の建物は客殿でしょうか。


【写真 上(左)】 三郎地蔵尊
【写真 下(右)】 本堂
うっそうと茂る木々を背に、寄棟造本瓦葺と思われる堂々たる本堂。
向拝扉は開け放たれ、五色の向拝幕が張り巡らされて華々しい印象です。
堂内はすこぶる整備された空間で、正面に黄金に輝く地蔵菩薩が御座します。
受付手前を左に進むと赤い鳥居のお稲荷様が御鎮座。こちらは地主神でしょうか。

御朱印は数種あるようでいずれも尊格は地蔵菩薩。
豪快な筆致の絵御朱印で、これは絵御朱印マニアに人気がありそうです。
書置を用意されているようなので、ご住職ご不在時でも拝受できそうです。
7.功臣山 報国寺(報国建忠禅寺)
公式Web
鎌倉市浄明寺2-7-4
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦如来
札所:鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)
「竹の寺」として人気の高い臨済宗建長寺派の寺院です。
公式Webなどから、由緒をまとめてみます。
建武元年(1334年)、仏乗禅師天岸慧広(てんがん えこう)により開山。
天岸慧広は南宋出身の臨済宗の高僧・無学祖元(仏光国師)に師事し、高峰顕日(仏国禅師)の法を嗣ぐとされる禅師です。
元応二年(1320年)元に渡られ、元徳元年(1329年)帰国。自筆の作とされる『東帰集』は「五山文学」の代表作として知られています。
『東帰集』(伝仏乗禅師筆)は、国の重要文化財に指定され、『絹本著色佛乗禅師像』および『堆朱印櫃入木印』(「天岸」「慧広」の木印)が附指定されています。
また、当寺は運朝作とされる開山仏乗禅師坐像(鎌倉市指定文化財)を所蔵されています。
開基は足利尊氏公の祖父家時公(報国寺殿義恩)とされていますが、宅間上杉家の祖、上杉重兼が開基という説もみられます。
なお、このあたりは”宅間谷戸”と呼ばれ、鎌倉幕府の絵師、宅間為行や宅間法眼一派(宅磨派)の絵仏師達が住していました。(宅間上杉家と宅間法眼一派の関係は不明。)
『新編鎌倉志』には「本尊、釋迦・文殊・普賢・迦葉・阿難、迦葉は、詫間法眼が作也。詫間の迦葉と云伝へて名佛也。此辺を詫間が谷と云なり。詫間が旧居か。」とあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山門
永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉憲実の対立などから永享の乱がおこり、室町幕府の援護を受けた上杉憲実が足利持氏を破りました。
足利持氏勢は鎌倉の永安寺(現・世田谷区大蔵)に入り、憲実は幕府に持氏の助命と嫡子義久の関東公方就任を再三嘆願したものの将軍義教公は許さず憲実に持氏殺害を厳命、憲実はやむなく永安寺を攻め、持氏は永安寺、義久は報国寺において自害したとされます。
関東管領の憲実にとって、鎌倉府の長官である鎌倉公方の持氏は主筋にあたり、主筋を討ったことを憂いた憲実は、乱後伊豆国清寺に退き出家、後年は諸国遍歴の旅に出て長門国大寧寺で逝去と伝わります。
足利義久は関東公方・足利持氏の嫡男で、「大若君」と尊称されました。
永享十年(1438年)鶴岡八幡宮で加冠元服。源義家公の先例にならい八幡太郎を称したとされる、押しも押されぬ源氏の御曹司です。
享年は17とされますが、諸説あるようです。
没後、報国寺は義久の菩提を弔い、菩提寺となりました。
『新編相模國風土記稿』には、以下のとおりあります。
「永享ノ乱ニ。持氏ノ息義久。十歳ナリシカ。当寺ニ在テ自害セリ。永享十一年二月十日。持氏御自害同廿八日若君義久十歳ニナラセ給ヒケルヲ。奉討ヘキ由聞エケレハ。報国寺ニ御座セシカ。」
「佛殿 本尊釋迦 長二尺二寸余定朝作 文殊普賢迦葉。阿難 各長三尺五寸許等ノ像ヲ安ス。共ニ詫間法眼カ作ニテ。迦葉ノ像。最其名高シ故ニ世俗当寺ヲ詫間寺又迦葉寺ナト呼ヘリ 開基伊豫守家時ノ像ヲモ置ケリ。是ハ旧休耕庵ニ安セシ像ナリ。」
「地蔵堂・出世地蔵ト云フ 諏訪社。稲荷社。八幡宮。三峯社 以上境内四方ノ鎮守トス。足利家時墓 祖塔休耕庵 開山塔・本堂ノ西ニアリ。太子堂・泉水谷ニアリ。」
足利持氏・義久の没後鎌倉公方は一旦断絶、後に持氏の遺児成氏が幕府から鎌倉公方就任を許されて鎌倉公方は復活するものの、享徳三年(1455年)からの享徳の乱を受け、以降は下総国古河を本拠とし「古河公方」を名乗りました。
----------
金沢街道「報国寺入口」信号から南側に入ってすぐ。あたりは閑静な住宅地です。
宅間派の芸術家が住んだという歴史があるためか、家々の佇まいにもどこか瀟洒な風があります。
こちらのお寺はとくに女性に人気が高く、週末などは着物姿の女子も多くみられます。


【写真 上(左)】 参道から山門
【写真 下(右)】 山門
山門前からすでに整備された参道が延びています。
山門は切妻屋根本瓦葺で、重厚な大棟・降棟を備えた本柱二、控柱二の薬医門。
山門脇の寺号標は「報国建忠禅寺」と正式寺号が刻まれています。
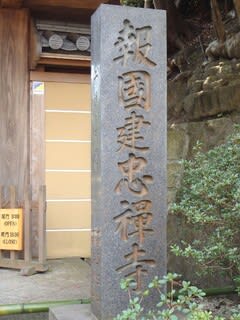

【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道と庭園
山門をくぐると左手に美しく砂紋が描かれた枯山水が広がります。
地表をおおう緑の苔と枯山水の対比があざやか。
枯山水のむこうの石上に御座す半跏思惟像は弥勒菩薩ではなく、観音さまのような感じがします。


【写真 上(左)】 砂紋
【写真 下(右)】 半跏思惟像
ゆるやかにカーブを描く石敷きの参道を進み石段をのぼると、やにわに視界が開けて正面が本堂。左手に鐘楼、右手には迦葉堂。


【写真 上(左)】 本堂下の階段-1
【写真 下(右)】 本堂下の階段-2


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 観音霊場札所板
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に二連の海老虹梁(?)、中備に龍の彫刻。
向拝正面の障子戸は開け放たれ、上部には寺号扁額が掲げられています。
両側の細かな連子が意匠的に効いて引き締まった印象の向拝。
御本尊の釈迦牟尼佛は鎌倉時代作とされ、鎌倉市指定文化財です。


【写真 上(左)】 迦葉堂-1
【写真 下(右)】 迦葉堂-2
迦葉堂はおそらく入母屋造銅板葺妻入り、階段をのぼっての参拝です。
こちらにはおそらく伝・詫間法眼作の迦葉尊者像が奉安。
迦葉(摩訶迦葉)はインド僧で、釈尊が悟りを開かれてから弟子となった十大弟子の一人です。
また詫間法眼は、鎌倉時代末から室町時代前半の鎌倉地方造仏界で主流を担った「詫間派仏所」を代表する仏師とされ、その精妙巧緻な表現には宋元美術の影響が認められ、南北朝時代の制作と推定されています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 石塔群
鐘楼の左にある石塔群は、新田義貞鎌倉攻めの際の北條勢新田勢両軍戦死者の供養塔といわれています。


【写真 上(左)】 賑わう山内
【写真 下(右)】 本堂と迦葉堂
本堂左手に「竹の庭」の拝観受付があり、本堂裏手を回り込むと庭園。庭園は、開山の天岸慧広禅師作と伝わるもの。春先に咲くサンシュユが有名です。


【写真 上(左)】 「竹の庭」への道すじ
【写真 下(右)】 庭園
竹林右手の岩肌にはやぐらが掘られて、たくさんの五輪塔が並びます。
開基の家時公と、この地で自刃した足利義久の墓があるとされます。


【写真 上(左)】 庭園とサンシュユ
【写真 下(右)】 お地蔵さまとやぐら


【写真 上(左)】 苔庭のお地蔵さま
【写真 下(右)】 苔庭と竹林
苔庭の向こうが竹林。みごとな孟宗竹が空に向かってすくすくと伸びています。
その中を小道が通っているので、竹林の絶好の撮影ポイントです。


【写真 上(左)】 竹林-1
【写真 下(右)】 竹林-2


【写真 上(左)】 竹林-3
【写真 下(右)】 竹林-4
そして竹林のおくに人気の茶席「休耕庵」。


【写真 上(左)】 休耕庵-1
【写真 下(右)】 休耕庵-2
孟宗竹の竹林「竹の庭」と茶席「休耕庵」は鎌倉観光のハイライトのひとつで、Web記事があふれんばかりにあるので、こまかい説明は省略します。
なお、「休耕庵」は、慧広禅師の塔頭の号からとられたものとみられます。
こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の3つ。
別に御本尊の御朱印を授与されているので御朱印は4種となります。
御本尊、釈迦如来の御朱印はおそらく申告制で、Webの画像検索からすると無申告ではおそらく鎌倉観音霊場の「聖大悲殿」の授与になるかと思います。
〔 御本尊・釈迦如来の御朱印 〕

鎌倉三十三観音霊場第10番の札所本尊は本堂別間に御座す聖観世音菩薩です。
本堂向拝には、観音霊場の札所板が掲げられています。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

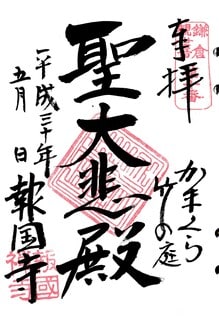
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
鎌倉十三仏霊場第8番(釈迦如来)も観音霊場札所本尊の観音さまとみられます。
〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕

●主印は聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多く、こちらもその様式です。
こちらは、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の札所でもあります。
札所本尊は聖観世音菩薩で、おそらく鎌倉観音霊場、鎌倉十三仏霊場と同じ観音さまかと思われます。
花種はサンシュユで花期は2月~3月。
春のボケ・バラ、夏のイワタバコ、冬のフユザクラ・ツバキも見どころの花の寺です。
〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕

●主印は三寶印、揮毫は「聖大悲殿」で「鎌倉第五番」の揮毫があります。
繊細かつ風雅な趣きをもつ女性ごのみのお寺さまで、明るく開けた4.浄妙寺とは対照的。
鎌倉デートで、浄妙寺のつぎに報国寺をセッティングすれば、さらにポイントを稼げるのでは(笑)
8.大蔵山 観音院 杉本寺
公式Web
鎌倉市二階堂903
天台宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番
鎌倉最古の寺ともいわれる鎌倉を代表する古刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)を務められるメジャー寺院です。
天平三年(731年)、東国巡錫中の行基菩薩が当地にて観音様の霊感を感得し自ら一刀三礼で十一面観世音菩薩を刻され、本尊として奉安したのが草創とされます。
天平六年(734年)、聖武天皇后の光明皇后の発願により、藤原北家の祖、右大臣藤原房前公と行基菩薩が本堂を建立して創建。開山は行基菩薩と伝わります。
仁寿元年(851年)、慈覚大師円仁が参詣され、自ら十一面観世音菩薩を刻まれて安置。
寛和二年(986年)には花山法皇の命を受けた恵心僧都源信が熊野権現のお導きにより十一面観世音菩薩を刻して奉安し、そののち花山法皇も巡礼されたといいます。
『新編鎌倉志』には「杉本観音堂は街道より北にあり。(略)坂東巡礼札所の第一なり。開山は行基なり。此寺は天台宗にて、叡山の末寺なり。中比衰微して(略)本尊十一面観音慈覚作。右も十一面行基作。左も十一面慧心作。前にも又十一面あり運慶作。釋迦天竺佛。毘沙門宅間作。」とあります。
山内掲示には「鎌倉、室町時代の大火、兵火に遭い、江戸期に於いては、一時期無住の時もあり、後の明治の排仏毀釈、又震災等により寺運も衰微し、七堂伽藍も観音堂等を除き、悉く焼失倒壊してしまいました。(略)昭和四十八年より伽藍復興大勧進(略)多くの皆様のご協力、ご協賛により浄財を得まして左記のごとく円成の運びと相成りました。」とあり、観音堂以外の堂宇はおおむね昭和の円成とみられます。
----------

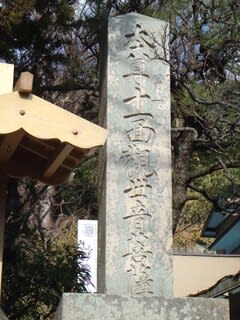
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
金沢街道に面した山内入口。街道の歩道からすぐに参道階段がはじまります。
右手に寺号標、参道階段両脇には「十一面杉本観音」の幟が立ち並び、はやくも霊場札所の趣きゆたか。
左の石標には「坂東第一番杉本寺観世音菩薩」、右の石標には「本尊十一面観世音菩薩」とあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 拝観受付と参道


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門扁額


【写真 上(左)】 仁王尊
【写真 下(右)】 仁王尊
しばらく登ると左手に拝観受付、その先の階段上には仁王門がそびえています。
江戸時代中期の築とされる切妻造茅葺両脇間一戸の八脚門で、左右に運慶作とも伝わる金剛力士(仁王)像を安置し、見上げに「大蔵山」の山号扁額。


【写真 上(左)】 仁王門から「苔の階段」
【写真 下(右)】 「苔の階段」
仁王門を抜けると見どころのひとつ、すり減って苔むした鎌倉石の石段参道(通称「苔の階段」)ですが、現在は通行禁止となっています。


【写真 上(左)】 大蔵辯財天-1
【写真 下(右)】 大蔵辯財天-2
右手には大蔵辯財天が御座します。
鳥居があるので「ここって神社?、お寺?」状態になりますが、当寺は中世~江戸期に神仏習合したともみられ、厳密な区別はむずかしいかもしれません。
「大蔵辯財天」の扁額が掛かった石造台輪鳥居の正面に大きな石の香炉。そのおくに銅板葺一間社流造のお社(堂宇)。
左手の池は洞窟を構えて、いかにも弁天様の境内らしい雰囲気を醸しています。
『新編相模國風土記稿』の観音堂の項に「辨天社 巌穴ニ安置ス。」とあるので、もともとはこの洞窟に祀られていたのかもしれません。
公式Webによると、「大蔵辯財天」をお参りすると大きな蔵が建つ程富に恵まれるという言い伝えがあるそうです。
「苔の階段」は登れないので、これを左の階段からまわりこむかたちでのアプローチ。
天台宗の寺院らしく、階段の途中に伝教大師童形像が御座します。
もうひと登りでT字路になり、左は小道、右手が本堂。
小道をすこし行った高みからは鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)がよく見えます。


【写真 上(左)】 衣張山
【写真 下(右)】 左手からの本堂
本堂(観音堂)は、寄棟造茅葺方五間(桁行・梁間ともに五間)、身舎の四面に庇を廻らす密教仏堂です。
棟札から、延宝六年(1678年)の建立とみられ、県指定文化財に指定されています。
方五間なので堂内は外陣、内陣にわかれ、通常は内陣に上がって参拝できますが、新型コロナ禍では外陣からの参拝となります。


【写真 上(左)】 右手からの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
堂内は撮影禁止ですが、公式Webに詳細の本堂内配置図があるので、こちらに沿ってご案内します。
堂内手前右手は納経所。数多い御朱印はすべてこちらでの授与となります。
格子戸の奥の内陣向かって左は行基菩薩御作(素木一木造、平安)、中央が円仁慈覚大師御作(寄木造漆箔、鎌倉)、向かって右は源信恵心僧都御作(寄木造漆箔、鎌倉)の十一面観世音菩薩の秘仏本尊三体(三尊同殿)で、慈覚大師御作と源信恵心僧都御作は国の重要文化財に指定されています。
毎月1日と18日に秘仏本尊御開帳のWeb情報もありますが、現況は定かではありません。
鎌倉時代の火災の折、御本尊三体は自ら山内の大杉の下に火を避けられたので、それより「杉(の)本(の)観音」と呼ばれたと伝わります。
また、礼を欠き、信心なき者が門前を乗馬のまま通り過ぎると落馬するというので、建長寺開山の大覚禅師(蘭渓道隆)が祈願され、自らの袈裟で行基菩薩御作の十一面観世音菩薩のお顔を覆ったところ、以降落馬する者がなくなったといいます。
このため行基菩薩御作のお像は「覆面観音」「下馬観音」とも呼ばれて市の指定文化財となっています。
頼朝公寄進の御前立の十一面観世音菩薩(伝・運慶作)は、常時御開扉されています。
このほか、本堂時計まわり、御本尊に向かって左手におびんづるさま、伝・運慶作の地蔵菩薩立像、伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像、新十一面観音。
御本尊に向かって右手に毘沙門天(宅間法眼作)、不動明王と伝・運慶作の観音三十三応現身。
本尊御前立は十一面観世音菩薩像、不動明王と毘沙門天は脇立の位置づけのようで、これは密教寺院の十一面観世音の堂宇でよくみられる様式です。
ほの暗い堂内には焼香の煙が絶えず、ときおり参拝団の読経の声が聞こえたりして、さすがに坂東霊場発願所らしい趣きがあります。


【写真 上(左)】 鐘楼堂
【写真 下(右)】 本堂右手
本堂向かって右手には鐘楼堂、五輪塔群、地蔵尊、右手おくの権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。
中世、杉本寺および背後の大蔵山には杉本城が築かれていました。
三浦氏嫡流三浦義明の長子で杉本氏の祖・杉本義宗が六浦道(金沢街道)・朝比奈口を抑える要衝のこの地に築城し、次男の義茂が入城。
源頼朝公が挙兵すると、三浦一族は源氏方につき居城の衣笠城を出立して石橋山に向かいましたが頼朝公の敗戦を聞いて衣笠城に篭城。攻め寄せた平家方の畠山重忠軍勢と衣笠城攻防戦を繰り広げ三浦義明は戦死しました。
三浦(杉本)義茂はこの戦の際、杉本城内から繰り出し畠山勢に攻めかかったと伝わります。
その後杉本城は継続しましたが、南北朝時代の建武四年(1337年)、この城に拠った北朝方の鎌倉府執事斯波家長が、朝比奈口から攻め入った南朝方の北畠顕家軍に攻められて破れ(杉本城の戦い)、杉本城は落城・破却されたとみられています。
本堂右手の五輪塔群は、杉本城の戦いで戦死した斯波家長と家臣の供養塔ともいわれています。


【写真 上(左)】 五輪塔群
【写真 下(右)】 覆屋の地蔵尊
そのお隣の覆屋のなかに地蔵尊が七体、覆屋の外にも一体が御座します。


【写真 上(左)】 身代地蔵尊御前立
【写真 下(右)】 権現社
本堂向かって右奥のやぐらを背にした権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。
石造の両部鳥居のおくに入母屋造銅板葺妻入りのお社(堂宇)。
恵心僧都源信は熊野権現のお導きにより御本尊十一面観世音菩薩を刻まれたとされるので、そちらとのゆかりがあるのかもしれません。
さて、ようやく御朱印です。
こちらの御朱印はたいへんに込み入っているので、丁寧に(笑)いきます。
札所としては鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の5札所、いずれも現役霊場です。
こちらの納経所(授与所)ですが、基本、お一人で書かれているようでグループ客が入ると一気に行列となります。(とくに行楽シーズンの週末)
いただける御朱印の種類は多いですが、発願札所がふたつもあるのでここは欲張らずに都度参拝がベターかも。
なお、新型コロナ禍のなかでは原則紙御朱印対応となり、授与時間も短くなるので要注意です。
とくに、発願参拝でどうしても御朱印帳に直書きいただきたい場合は、平日に事前確認のうえ参拝されたほうがいいかもしれません。
(今年は新型コロナ禍再燃のマイナス効果と、「鎌倉殿の13人」のプラス効果のせめぎ合いで、鎌倉観光の人出がまったく読めません。先日参拝したときはメジャー寺院もがらがらで無人の写真撮り放題でしたが、新型コロナ禍が首尾よく収まってリベンジ観光客が一気に吹き出すと、たいへんなことになるかもしれません。)
鎌倉三十三観音霊場第1番(発願)の札所本尊は、御本尊の十一面観世音菩薩です。
発願印は申告すればいただけますが、御朱印帳の途中の頁にいただけるかは定かではありません。
御朱印帳の最初の頁ならば大丈夫かと思いますが、導入編でも書いたとおり、鎌倉三十三観音霊場は専用納経帳での巡拝をおすすめします。(いまはどうかわかりませんが、専用納経帳でないと御朱印拝受がむずかしい札所があります。)
こちらでは数種類の紐綴じ型の納経帳を頒布されており、こちらで納経帳を入手すればスムーズに発願印を拝受できます。
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。
鎌倉二十四地蔵霊場第4番の札所本尊「身代地蔵尊」は、本堂向かって左奥の伝・運慶作の地蔵菩薩立像で、本堂右手の覆屋内の七体並ぶ地蔵尊の一番右のおおぶりのお地蔵さまがお前立ちとされているようです。
杉本城を築城したとされる杉本(三浦)義宗に向けて放たれた矢がこちらの地蔵尊に当たり、地蔵尊の傷跡から血がにじみでたという伝承があり、地蔵尊が義宗の身代わりになられたことから「身代地蔵尊」と呼ばれるようです。
『新編相模國風土記稿』には、仁王門の左手に地蔵堂が描かれ、「地蔵堂 或伝ニ。此石佛ヲ。杉本太郎義宗カ。身代ノ地蔵トモ云フ。按スルニ。延元二年(1337年)斯波三郎。此ニテ自●セシ。斯波家長等カ為ニ。造建セシ。石佛ナルヘシ」とあるので、もともと「身代地蔵尊」は仁王門横の地蔵堂に御座していたのかもしれません。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場第4番(身代地蔵尊)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。
鎌倉二十四地蔵霊場第6番の札所本尊「尼将軍地蔵尊」は、本堂向かって左奥、「身代地蔵尊」の右隣の伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像です。
「身代地蔵尊」が第4番、第5番光触寺の「塩嘗地蔵尊」をはさんで第6番がこちらで、順打ち巡拝をむずかしいものにしています。
「尼将軍」といえば北条政子ですが、どうやら北条政子とのゆかりは不明のようです。
しかし、御朱印揮毫はしっかり「尼将軍地蔵尊」で、鎌倉らしい御朱印のひとつといえましょう。
〔 鎌倉二十四地蔵霊場第6番(尼将軍地蔵尊)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。
相州二十一ヶ所霊場は、鎌倉の弘法大師霊場です。
鎌倉のかなりの観光寺院が札所となっていますが、御朱印見本に掲示されることはほとんどなく、鎌倉の御朱印ガイド類にもほとんど載っていません。
いわば「知る人ぞ知る鎌倉の霊場」で、しかも弘法大師霊場でありながら真言宗以外の札所も多くなっています。
どうしてこういう霊場が成立したのかは、いわく経緯がありそうですがここでは省略し、発願寺の宝戒寺で書きます。(丁寧にいきます。とかいいながらとりあえず逃げる(笑))
〔 相州二十一ヶ所霊場第2番の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は「阿字印」にも見えますが、違うかもしれません。
超メジャー霊場、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)の札所で、札所本尊は御本尊の十一面観世音菩薩です。
坂東三十三箇所(観音霊場)は超メジャー霊場なので、こちらについてのご説明は省略です。(丁寧にいきます。とかいいながらまたしても逃げる(笑))
こちらも発願印をいただけますが、鎌倉観音霊場と同様申告制だと思います。
なお、霊場無申告の場合の御朱印ですが、Web画像検索の結果からすると、おそらく鎌倉観音霊場のものになるのでは?(坂東三十三箇所かもしれぬ。)
いずれにしても、御本尊十一面観世音菩薩の御朱印になります。
〔 坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。
本堂内に御座す毘沙門天(大蔵毘沙門天)の御朱印も授与されていますが、こちらは申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。
〔 大蔵毘沙門天の御朱印 〕

●主印は毘沙門天の種子「バイ・ベイ」の御寶印(蓮華座)とみられます。
仁王門右手の「大蔵辯財天」の御朱印も授与されていますが、こちらも申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。
〔 大蔵辯財天の御朱印 〕

●主印は弁財天の種子「ソ」の御寶印(蓮華座)と思われます。
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へつづく。
【 BGM 】
■ One Reason - milet
■ 最高の片想い - Sachi Tainaka
■ symphonia - kalafina
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




