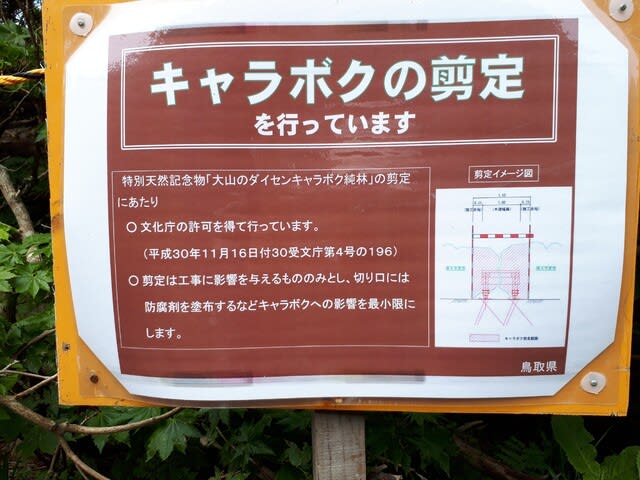猛暑続きの毎日。下界はとにかく暑い。それにコロナの影響もあるから山や海へ逃れる人は多い。オリンピックはテレビ観戦だけれど健康的にはどうだろうか。
そろそろ台風のシーズンだが、こらから一雨ごとに涼しくなる。8月に入って猛暑続きだが、やはり高山は涼しくていい。山陰の名峰大山は、1700mほどの山だけれどシーズンを通じアルプス的な感じを体験できる。そのせいか、年々登山者が増える傾向にある。下山キャンプ場も、その人気を当て込んでか大がかりな整備が進められているが一向にオープンの気配がない。モンベルが関係しているらしいが、国立公園だからもっと情報公開をすべきだろうにと思う。登山者を無視した開発行為と言われても仕方がない。






 暑いので八つ当たりしているかもしれないが・・・?
暑いので八つ当たりしているかもしれないが・・・?
今日は、またまた先般のユートピア付近の写真を紹介します。
これがユートピア(小屋)付近。左に三鈷峰、バック右手が船上山。はるかに日本海を望む。

静かないい小屋だが、近くに水がない。ここに泊まり写真を写す人もいるが、水の関係でせいぜい1泊だろう。水は、元谷まで降りなければいけないから往復すれば3時間はかかる。
この日、大きな3脚を担いだ写真家(?)の方と話したが、昨年よかったので今年も撮りに来たとのこと。ただし、昨年は、水がなくなり困ったそうです。下山する人に分けてもらえないかと頼んだが、ダメだったそうです。翌朝早めに元谷へ下ったと言っておられた。今年は、4リットルを担いできたそうです。
小屋の周りには花々が咲き乱れる。バックは縦走路。

烏ケ山(せん) 路傍に咲く


オトギリソウが咲くにはまだ早いが・・・。

振り子沢。残雪期には絶好のスキーポイントとなるのだが。下部が地獄谷でさらに下ると一向平キャンプ場へでる。沢に咲くのは、クガイソウ、シシウド、大山ギボウシなど。

フウロとシモツケソウ ダイモンジソウ


これはシモツケ

*シモツケソウとシモツケは花がよく似ているが、シモツケは木です。
シモツケソウとダイモンジソウ 大山オダマキ


縦走路から少し外れると可憐な花々がひっそりと咲いている。ダイセンオダマキもそうだが、花が黄色なのが特徴。大山寺周辺で見かけるオダマキは栽培種のようで花も紫。この日、このダイセンオダマキを目標に登ってきた人もいた。
このコオニユリも来年も見られるだろうか。

この回はこれまで。