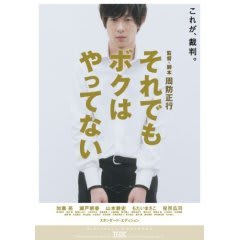
2007年/日本/143分
監督: 周防正行
製作: 亀山千広
脚本: 周防正行
撮影: 栢野直樹
出演: 加瀬亮/金子徹平 瀬戸朝香/須藤莉子 山本耕史/斉藤達雄 もたいまさこ/金子豊子
たとえば、突然、学校の先生をやってくださいと言われたら? もちろん、誰でもすぐに教壇に立って授業ができるわけではないでしょう。でも、少なくとも、すべての大人は、「学校」という場所をある程度知っています。児童・生徒として、あるいは自分の子どもの通う学校として。
これが、「学校」ではなくて「裁判所」だとしたら。おおかたの人は、裁判の傍聴はおろか、裁判所なんて行ったこともないでしょう。「教室」ならなんとなく雰囲気はわかっても、「法廷」はテレビでしか見たことないし、その形態や雰囲気なんてまったく知らない。そういう場所で、突然「裁判員」をやってくださいと言われても…。
来年から始まることになっている裁判員制度に対して、多くの人が「できればやりたくない」と考えているのも、仕事などで時間が取れないからというだけでなく、裁判所というところの雰囲気をそもそも知らないというあたりにも理由がありそうです。
裁判員制度については「その2」で触れるとして、日本の裁判制度そのものに多くの問題があるという認識からこの映画は作られました。周防正行監督の映画づくりのセンスの良さに、2年間かけたという綿密な下調べがあれば、いい映画ができないわけがありません。日本の裁判制度について、一から丁寧に教えてくれるだけでなく、まったく堅苦しさを感じさせない手法には爽快感すらあります。
テーマとして掲げられているのは「痴漢冤罪事件」。実際にそうした事案があったことも影響しているのでしょうが、「痴漢」という恥ずべき行為は、「犯罪」としては非常に微妙なところにあります。要するに、「やった」「やらない」の決定的な証拠が見つけにくい、ということです。特に、「やっていない」方については、「やっていない」ことを証明するのは至難の業。この映画は、そうした事実も具体的に教えてくれます。
周防正行著『それでもボクはやってない─日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり!』(幻冬舎)も読んでみました。邦画に関して原作以外の関連本を読むことはあまりないのですが(伊丹十三の『お葬式』以来かも)、前半の「シナリオ完全収録」はともかく、後半に収められている元裁判官・木谷明氏と周防監督の対談はとてもおもしろかった。木谷氏は、この映画制作にあたって、周防監督が参考にしたという『刑事裁判の心』という本の著者ですが、「プロ」が見ても、この映画には感動させられたらしい。対談は、映画のシーンをもとに、周防氏が現在の裁判制度について疑問を投げかけ、それに木谷氏が答えるという形で進んでいきます。周防監督は、実際の裁判も数々傍聴し、本もたくさん読んでいるので、専門的な用語を駆使して「プロ」とも議論できるわけですが、私には意味のわからない言葉もけっこうありました。それでも、警察での取調べの録音・録画のこととか供述調書の「読み聞かせ」の問題、裁判官の「心証」、法廷での挨拶のことなど、興味深い内容が目白押しです。特に、裁判官の「心証」が判決に影響することもままあるというくだりには、そうなのか!と思いました。裁判って、あくまでも「事実」の積み上げの上に白か黒かの判断が下されるものだと思っていましたが、「心証の雪崩現象」さえあるという。裁判官も人間。人が人を裁くというのは、げに難しい。
この本には、オミット・シーン(編集段階でカットされたシーン)に対する監督の弁明も逐一掲載されています。いい映画はみんなそうなのでしょうけど、こうして並べられると、もったいないシーン、見てみたかったシーンがたくさんありますね。なぜオミットしたか。オミットされたシーンのほとんどは、映画全体の「流れ」を踏まえた上で削られていることがわかります。たとえば、緊迫した法廷の場面が続く中に、公園の陽だまりでのんびり会話するシーンが入ってくると、見ている方の緊張感がそがれる、といった理由です。その会話自体が、裁判に対するとても重要な考えを述べているとしても、全体の流れの方を優先させるということですね。ただ、証拠をすべて開示する云々のあたり、映画を観ている時にはよくわからないなとちょっと引っかかりがあったのですが、やっぱりその説明シーンがオミットされていたことがわかりました。映画全体の時間もあるし、映画の編集も大変な作業だなと思いました。
この映画で描かれる「痴漢冤罪」だろうが何だろうが、日本の刑事事件に関わる、警察、検察、裁判官といった機関の抱える自己矛盾をえぐり出しているところが、この映画の最大の功績ではないでしょうか。どの機関も結局は「国家機関」。警察が逮捕・送検し、検察が立件した事案を、裁判官が法廷で「無罪」とするのは、国家権力に対して反旗を翻すことになる…というセリフ、ああなるほどなと思います。裁判官も国家公務員。裁判官が無罪判決を下すのは、よっぽどの覚悟が必要なんですね。
映画では、被告に対して温情的だった最初の裁判官が更迭されたというような設定でしたが、「疑わしきは罰せず」という原則は、裁判官にとってはそれほど重要ではないのかなと思いました。警察は「疑わしい」から逮捕して身柄を拘束し検察に送るわけで、その時点ではあくまでも「疑わしい」に過ぎない。だから「容疑者」なわけです(法律上は「被疑者」)。検察は、送検されてきた事案を審議し、裁判にかけるかどうかを判断します。いよいよ裁判にかけるとなれば、容疑者は「被告」となります。本当に犯罪を犯したかどうかを判断する、つまり「有罪」か「無罪」かという判断を下すのはあくまでも裁判官です。
ところが実際には、「容疑者」「にすぎない」はずの人間をマスコミはあたかも「有罪者」のように扱う例がとても多い。地下鉄サリン事件の時の河野さんなんかはその最たる例でしょう。記憶に新しいところでは、香川の祖母と孫の殺害事件では、容疑者ですらない父親に対する報道姿勢が問題になりました。たとえ、現行犯だったり、明らかな証拠があって本人も犯行を認めていたとしても、「容疑者」はまだ「有罪者」ではない。
先日、日本新聞協会は、事件報道の新たな指針を公表しました(2008年1月16日)。要するに、被疑者や被告を犯人と断定するような印象を与える報道はしないという内容。一般市民が裁判に関わる裁判員制度で、マスコミ報道が裁判員に先入観を与えないようにということなのでしょうが、裁判員制度があろうがなかろうが、それは当然のことです。
ま、裁判の被告になる、ということ自体が何かしらあやしいからだと言う意見も確かにごもっとも。火のないところに煙は立たず。しかし、この映画の主人公、金子徹平の場合、火がなくても煙が立ってしまったのです。彼の落ち度はゼロです。ただ電車に乗っていただけ。それなのにそれなのに、いきなり逮捕されるわ、留置場に入れられるわ、警察や検察にさんざん罵倒されるわ、家宅捜索はされるわ、なんやかんやで1年間ものあいだ、彼は「被疑者」もしくは「被告」と呼ばれることになるのです。運が悪いでは済まされない、と思う。少なくとも、警察がきちんとした取調べをしていれば、本来、立件まで行かない事案ではないか。しかし、実際は全くその逆で、被害者の供述が優先され、ろくに証拠調べもされない。脅し、懐柔、泣き落とし。手を変え品を変え、警察は容疑者を「落と」そうとしてきます。やったと認めれば示談になって釈放されるという。もちろん裁判にもならない。最初に徹平のもとにやってきた「当番弁護士」さえ、そんなことを言うのですから目も当てられない。「裁判は大変だ。多分、君には想像できないくらいに。」
こんなふうにして、やってもいないのに「やりました」と自白した人はいったいどのくらいいるのでしょう。痴漢なら示談で済むかもしれませんが、これが殺人だったら、やったと認めたから釈放、というわけにはいきません。これまで起こった数々の冤罪事件は、こんなおかしな仕組みの中で生まれてきたのですね。
おかしな仕組みと言えば、何の前触れもなく、途中で裁判官が替わったのにはびっくりしました。これはそう珍しいことではないのだとか。国家公務員である裁判官にも当然「人事異動」があるわけですね。学校に置き換えてみると、クラス担任が途中で替わるみたいなものか。よほどのことがない限り、ありえないことですが。裁判の場合、裁判官が替わることで、展開がずいぶん変わることもあるようです。この映画の場合がまさにそうです。最初の大森裁判官、すごくよかったですね。演じているのは正名僕蔵という俳優。根っからの裁判官という雰囲気、気に入りました。この映画を観たあと、たまたまテレビドラマに出ている正名氏を発見しましたが、全然別の役柄で驚きましたが。で、替わった裁判官が小日向文世演ずる室山裁判官。小日向氏にありがちなタイプの役柄。全体にこの映画のキャスティングは見事ですが、特にこの二人の裁判官は、それぞれのタイプを見事に体現してくれていたと思います。
キャスティングついでに言えば、この映画でも竹中直人がチョイ役で登場。徹平の住むアパートの管理人という、まあどうでもいい役なのですが、彼のこういう使い方、最近とみに多いような気がするのですが、これってどうなのでしょうね。どんな役でも「竹中風」にしてしまう彼の芸達者ぶりには感服しますが、ちょっと食傷気味かもしれません。
(その2に続く…)
「それでもボクはやってない」≫Amazon.co.jp
監督: 周防正行
製作: 亀山千広
脚本: 周防正行
撮影: 栢野直樹
出演: 加瀬亮/金子徹平 瀬戸朝香/須藤莉子 山本耕史/斉藤達雄 もたいまさこ/金子豊子
たとえば、突然、学校の先生をやってくださいと言われたら? もちろん、誰でもすぐに教壇に立って授業ができるわけではないでしょう。でも、少なくとも、すべての大人は、「学校」という場所をある程度知っています。児童・生徒として、あるいは自分の子どもの通う学校として。
これが、「学校」ではなくて「裁判所」だとしたら。おおかたの人は、裁判の傍聴はおろか、裁判所なんて行ったこともないでしょう。「教室」ならなんとなく雰囲気はわかっても、「法廷」はテレビでしか見たことないし、その形態や雰囲気なんてまったく知らない。そういう場所で、突然「裁判員」をやってくださいと言われても…。
来年から始まることになっている裁判員制度に対して、多くの人が「できればやりたくない」と考えているのも、仕事などで時間が取れないからというだけでなく、裁判所というところの雰囲気をそもそも知らないというあたりにも理由がありそうです。
裁判員制度については「その2」で触れるとして、日本の裁判制度そのものに多くの問題があるという認識からこの映画は作られました。周防正行監督の映画づくりのセンスの良さに、2年間かけたという綿密な下調べがあれば、いい映画ができないわけがありません。日本の裁判制度について、一から丁寧に教えてくれるだけでなく、まったく堅苦しさを感じさせない手法には爽快感すらあります。
テーマとして掲げられているのは「痴漢冤罪事件」。実際にそうした事案があったことも影響しているのでしょうが、「痴漢」という恥ずべき行為は、「犯罪」としては非常に微妙なところにあります。要するに、「やった」「やらない」の決定的な証拠が見つけにくい、ということです。特に、「やっていない」方については、「やっていない」ことを証明するのは至難の業。この映画は、そうした事実も具体的に教えてくれます。
周防正行著『それでもボクはやってない─日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり!』(幻冬舎)も読んでみました。邦画に関して原作以外の関連本を読むことはあまりないのですが(伊丹十三の『お葬式』以来かも)、前半の「シナリオ完全収録」はともかく、後半に収められている元裁判官・木谷明氏と周防監督の対談はとてもおもしろかった。木谷氏は、この映画制作にあたって、周防監督が参考にしたという『刑事裁判の心』という本の著者ですが、「プロ」が見ても、この映画には感動させられたらしい。対談は、映画のシーンをもとに、周防氏が現在の裁判制度について疑問を投げかけ、それに木谷氏が答えるという形で進んでいきます。周防監督は、実際の裁判も数々傍聴し、本もたくさん読んでいるので、専門的な用語を駆使して「プロ」とも議論できるわけですが、私には意味のわからない言葉もけっこうありました。それでも、警察での取調べの録音・録画のこととか供述調書の「読み聞かせ」の問題、裁判官の「心証」、法廷での挨拶のことなど、興味深い内容が目白押しです。特に、裁判官の「心証」が判決に影響することもままあるというくだりには、そうなのか!と思いました。裁判って、あくまでも「事実」の積み上げの上に白か黒かの判断が下されるものだと思っていましたが、「心証の雪崩現象」さえあるという。裁判官も人間。人が人を裁くというのは、げに難しい。
この本には、オミット・シーン(編集段階でカットされたシーン)に対する監督の弁明も逐一掲載されています。いい映画はみんなそうなのでしょうけど、こうして並べられると、もったいないシーン、見てみたかったシーンがたくさんありますね。なぜオミットしたか。オミットされたシーンのほとんどは、映画全体の「流れ」を踏まえた上で削られていることがわかります。たとえば、緊迫した法廷の場面が続く中に、公園の陽だまりでのんびり会話するシーンが入ってくると、見ている方の緊張感がそがれる、といった理由です。その会話自体が、裁判に対するとても重要な考えを述べているとしても、全体の流れの方を優先させるということですね。ただ、証拠をすべて開示する云々のあたり、映画を観ている時にはよくわからないなとちょっと引っかかりがあったのですが、やっぱりその説明シーンがオミットされていたことがわかりました。映画全体の時間もあるし、映画の編集も大変な作業だなと思いました。
この映画で描かれる「痴漢冤罪」だろうが何だろうが、日本の刑事事件に関わる、警察、検察、裁判官といった機関の抱える自己矛盾をえぐり出しているところが、この映画の最大の功績ではないでしょうか。どの機関も結局は「国家機関」。警察が逮捕・送検し、検察が立件した事案を、裁判官が法廷で「無罪」とするのは、国家権力に対して反旗を翻すことになる…というセリフ、ああなるほどなと思います。裁判官も国家公務員。裁判官が無罪判決を下すのは、よっぽどの覚悟が必要なんですね。
映画では、被告に対して温情的だった最初の裁判官が更迭されたというような設定でしたが、「疑わしきは罰せず」という原則は、裁判官にとってはそれほど重要ではないのかなと思いました。警察は「疑わしい」から逮捕して身柄を拘束し検察に送るわけで、その時点ではあくまでも「疑わしい」に過ぎない。だから「容疑者」なわけです(法律上は「被疑者」)。検察は、送検されてきた事案を審議し、裁判にかけるかどうかを判断します。いよいよ裁判にかけるとなれば、容疑者は「被告」となります。本当に犯罪を犯したかどうかを判断する、つまり「有罪」か「無罪」かという判断を下すのはあくまでも裁判官です。
ところが実際には、「容疑者」「にすぎない」はずの人間をマスコミはあたかも「有罪者」のように扱う例がとても多い。地下鉄サリン事件の時の河野さんなんかはその最たる例でしょう。記憶に新しいところでは、香川の祖母と孫の殺害事件では、容疑者ですらない父親に対する報道姿勢が問題になりました。たとえ、現行犯だったり、明らかな証拠があって本人も犯行を認めていたとしても、「容疑者」はまだ「有罪者」ではない。
先日、日本新聞協会は、事件報道の新たな指針を公表しました(2008年1月16日)。要するに、被疑者や被告を犯人と断定するような印象を与える報道はしないという内容。一般市民が裁判に関わる裁判員制度で、マスコミ報道が裁判員に先入観を与えないようにということなのでしょうが、裁判員制度があろうがなかろうが、それは当然のことです。
ま、裁判の被告になる、ということ自体が何かしらあやしいからだと言う意見も確かにごもっとも。火のないところに煙は立たず。しかし、この映画の主人公、金子徹平の場合、火がなくても煙が立ってしまったのです。彼の落ち度はゼロです。ただ電車に乗っていただけ。それなのにそれなのに、いきなり逮捕されるわ、留置場に入れられるわ、警察や検察にさんざん罵倒されるわ、家宅捜索はされるわ、なんやかんやで1年間ものあいだ、彼は「被疑者」もしくは「被告」と呼ばれることになるのです。運が悪いでは済まされない、と思う。少なくとも、警察がきちんとした取調べをしていれば、本来、立件まで行かない事案ではないか。しかし、実際は全くその逆で、被害者の供述が優先され、ろくに証拠調べもされない。脅し、懐柔、泣き落とし。手を変え品を変え、警察は容疑者を「落と」そうとしてきます。やったと認めれば示談になって釈放されるという。もちろん裁判にもならない。最初に徹平のもとにやってきた「当番弁護士」さえ、そんなことを言うのですから目も当てられない。「裁判は大変だ。多分、君には想像できないくらいに。」
こんなふうにして、やってもいないのに「やりました」と自白した人はいったいどのくらいいるのでしょう。痴漢なら示談で済むかもしれませんが、これが殺人だったら、やったと認めたから釈放、というわけにはいきません。これまで起こった数々の冤罪事件は、こんなおかしな仕組みの中で生まれてきたのですね。
おかしな仕組みと言えば、何の前触れもなく、途中で裁判官が替わったのにはびっくりしました。これはそう珍しいことではないのだとか。国家公務員である裁判官にも当然「人事異動」があるわけですね。学校に置き換えてみると、クラス担任が途中で替わるみたいなものか。よほどのことがない限り、ありえないことですが。裁判の場合、裁判官が替わることで、展開がずいぶん変わることもあるようです。この映画の場合がまさにそうです。最初の大森裁判官、すごくよかったですね。演じているのは正名僕蔵という俳優。根っからの裁判官という雰囲気、気に入りました。この映画を観たあと、たまたまテレビドラマに出ている正名氏を発見しましたが、全然別の役柄で驚きましたが。で、替わった裁判官が小日向文世演ずる室山裁判官。小日向氏にありがちなタイプの役柄。全体にこの映画のキャスティングは見事ですが、特にこの二人の裁判官は、それぞれのタイプを見事に体現してくれていたと思います。
キャスティングついでに言えば、この映画でも竹中直人がチョイ役で登場。徹平の住むアパートの管理人という、まあどうでもいい役なのですが、彼のこういう使い方、最近とみに多いような気がするのですが、これってどうなのでしょうね。どんな役でも「竹中風」にしてしまう彼の芸達者ぶりには感服しますが、ちょっと食傷気味かもしれません。
(その2に続く…)
「それでもボクはやってない」≫Amazon.co.jp





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます