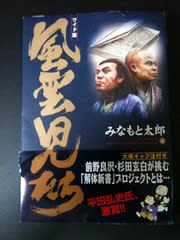
「風雲児たち(4)」SPコミックス
みなもと太郎/リイド社
ギャグ漫画だったはずの「風雲児たち」に挿入された、超シリアスな話「宝暦治水伝」を読んで泣いてしまった。3巻目の後半から4巻目の前半に続くこのお話の主人公は薩摩藩家老の平田靱負という人物。靱負は「ゆきえ」と読む。へぇぇ、ワシの名前と同じ読み方じゃん。っていうか男でもそういう名前あるんだぁ~と素直に驚いた。
宝暦治水工事は、1753年の話だから、一気に時代が下って、徳川吉宗も通り越して、9代将軍徳川家重の時代の話だ。徳川幕府は薩摩藩の財力を恐れて、毎年氾濫による被害が多発していた木曽三川の分流工事を薩摩藩に命じたのである。いわば幕府による露骨な弾圧政策であり、薩摩藩をつぶしに来ていることは誰の目にも明らかであった。当時の薩摩は琉球との貿易はあったが、参勤交代等の費用もかさみ、当時の薩摩藩はすでに借金体質であったのに、縁もゆかりもない濃尾の治水工事をさせられるのである。工事費・宿泊費・食費・交通費すべて自前である。農民の家に泊まらされ、農民に食費・布団代すべて自前で払わなければならない。しかも農民には肉や魚を出してはいけないと厳しいお達しがあった。工事も難癖をつけてやりなおさせたり、夜ひそかに壊させたりした。濃尾の民は木曾三川の氾濫に非常に苦しんでいたが、そんなエピソードを聞くと、幕府が濃尾の民のためではなく、薩摩いじめのためにこの工事をやらせていたのは明らかである。工事に派遣された薩摩藩士達の過労や伝染病による死亡が相次ぎ、また幕府に抗議して切腹する薩摩藩士達も続出した。でも死をもって抗議した彼らの死は事故死として処理されたのである。
当初の工事費は最初15万両と言っていたのに、30万両になり、さらに20万両追加になった。平田靱負は大阪の豪商に借金を重ねてなんとかやりくりするが、1年3ヶ月ほどでようやく工事が完成した暁には、平田は藩への多大な負担の責任を取り自害してしまった。
誰が聞いても怒りのあまり幕府を倒しに行きたくなるような話であるが、当の薩摩では、この話は幕府を刺激せぬよう封印されていた。この工事で世話になった濃尾の民達がこの話を語りついで今に伝えたのだという。そんな話を分かりやすく表に出してくれただけでも、「風雲児たち」は意義深いものだなぁとつくづく思った。
みなもと太郎/リイド社
ギャグ漫画だったはずの「風雲児たち」に挿入された、超シリアスな話「宝暦治水伝」を読んで泣いてしまった。3巻目の後半から4巻目の前半に続くこのお話の主人公は薩摩藩家老の平田靱負という人物。靱負は「ゆきえ」と読む。へぇぇ、ワシの名前と同じ読み方じゃん。っていうか男でもそういう名前あるんだぁ~と素直に驚いた。
宝暦治水工事は、1753年の話だから、一気に時代が下って、徳川吉宗も通り越して、9代将軍徳川家重の時代の話だ。徳川幕府は薩摩藩の財力を恐れて、毎年氾濫による被害が多発していた木曽三川の分流工事を薩摩藩に命じたのである。いわば幕府による露骨な弾圧政策であり、薩摩藩をつぶしに来ていることは誰の目にも明らかであった。当時の薩摩は琉球との貿易はあったが、参勤交代等の費用もかさみ、当時の薩摩藩はすでに借金体質であったのに、縁もゆかりもない濃尾の治水工事をさせられるのである。工事費・宿泊費・食費・交通費すべて自前である。農民の家に泊まらされ、農民に食費・布団代すべて自前で払わなければならない。しかも農民には肉や魚を出してはいけないと厳しいお達しがあった。工事も難癖をつけてやりなおさせたり、夜ひそかに壊させたりした。濃尾の民は木曾三川の氾濫に非常に苦しんでいたが、そんなエピソードを聞くと、幕府が濃尾の民のためではなく、薩摩いじめのためにこの工事をやらせていたのは明らかである。工事に派遣された薩摩藩士達の過労や伝染病による死亡が相次ぎ、また幕府に抗議して切腹する薩摩藩士達も続出した。でも死をもって抗議した彼らの死は事故死として処理されたのである。
当初の工事費は最初15万両と言っていたのに、30万両になり、さらに20万両追加になった。平田靱負は大阪の豪商に借金を重ねてなんとかやりくりするが、1年3ヶ月ほどでようやく工事が完成した暁には、平田は藩への多大な負担の責任を取り自害してしまった。
誰が聞いても怒りのあまり幕府を倒しに行きたくなるような話であるが、当の薩摩では、この話は幕府を刺激せぬよう封印されていた。この工事で世話になった濃尾の民達がこの話を語りついで今に伝えたのだという。そんな話を分かりやすく表に出してくれただけでも、「風雲児たち」は意義深いものだなぁとつくづく思った。


























子供向けに『千本松原』という本があって、推薦図書として読み、社会見学でも現場へ行きました。
「濃尾」というより、「濃」である美濃の人間に語り継がれてます。
「尾」は尾張徳川家なので、同じ川の堤防(輪中堤)でも、美濃側は尾張側より低くしなければならない決まりでした。
このご縁で、鹿児島県と岐阜県は姉妹県で、また単独にこの輪中地域の市町村と鹿児島市とでも姉妹都市として今でも繋がっています。
そういえばmnakaさんも岐阜でしたね。
>鹿児島県と岐阜県は姉妹県で、また単独にこの輪中地域の市町村と鹿児島市とでも姉妹都市として今でも繋がっています。
悲劇的で過酷な状態の中で生まれた人の和が、時代を超えて今もつながっているという事実には感銘を覚えます。
そういえば、風評被害に苦しむ会津の観光業界を現代の薩摩と長州が助けようとしているという記事も最近見ました。風雲児たちを読んでるだけに、そういう時代を超えた話を聞くと胸が熱くなります。