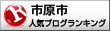先日、市民ネットの環境部会が中心となり、市民の皆さんを募って視察に行ってきました。
お目当ては、御宿町にある、公益財団法人「海洋生物環境研究所」です。


日本の火力発電所や原子力発電所は、冷却水に海水を利用しているためにその多くが海岸に位置しています。発電所からの排水は約7℃上昇するとされており、ここ海生研は、この温排水が海域環境や生物に与える影響を調査研究する機関として、昭和50年に設立されました。
そのほか、海域の富栄養化、土砂の海域流出、紫外線増加、磯焼けなど、沿岸海域の様々な環境問題を扱っています。
しかし、福島原発の事故以来、何といっても放射能汚染の影響の調査が重要調査項目となりました。
全国各地から毎日送られてくる魚介類のサンプルをゲルマニウム半導体検出器で測定し、結果を公表しています。
さて、まず施設内を案内していただきました。
海生研では、とても高い飼育技術レベルを誇っています。
室内外にずらりと並ぶ水槽


毎日届けられる魚介類(平均50サンプル)は、放射能測定のために解体され、細かく刻まれていきます。

気を付けること
「サンプルを取り違えない」「腸内の泥を混入させない」(^.^)

ここで活躍しているパートの女性の皆さんは、地元で漁業を営んでいる家の方が多いそうです。
魚の扱いはお手の物ですね♪
刻まれたサンプルは、このように容器に詰められ・・・

ここで測定されます。

一通り案内していただいた後は、研究員の方々に放射性物質のイロハから測定結果の分析まで、とてもわかりやすく丁寧に説明していただきました。


福島原発の事故から2年以上経過した現在、海水魚は食品の基準値100ベクレルを超えることはないのですが、いまだに淡水魚ではまれに超えることがあるそうです。
短い時間で十分な質疑応答ができませんでしたが、とても充実した視察でした。
オマケの写真です。
研究所から見渡せる外房の海。(この日は霧が濃くて上手に撮れませんでした・・・)

「ドン・ロドリゴ上陸」記念碑。
今から400年前、メキシコにむかう帆船が嵐に巻きこまれて遭難しここ御宿に流れ着いた際、地元の人々が317名の乗組員の命を救ったという有名な実話の舞台です。

まだまだあるのですが、その他の写真は次の機会に・・・。

海生研の皆さん、たいへんお世話になりました。視察に参加された皆さん、お疲れ様でした!
お目当ては、御宿町にある、公益財団法人「海洋生物環境研究所」です。


日本の火力発電所や原子力発電所は、冷却水に海水を利用しているためにその多くが海岸に位置しています。発電所からの排水は約7℃上昇するとされており、ここ海生研は、この温排水が海域環境や生物に与える影響を調査研究する機関として、昭和50年に設立されました。
そのほか、海域の富栄養化、土砂の海域流出、紫外線増加、磯焼けなど、沿岸海域の様々な環境問題を扱っています。
しかし、福島原発の事故以来、何といっても放射能汚染の影響の調査が重要調査項目となりました。
全国各地から毎日送られてくる魚介類のサンプルをゲルマニウム半導体検出器で測定し、結果を公表しています。
さて、まず施設内を案内していただきました。
海生研では、とても高い飼育技術レベルを誇っています。
室内外にずらりと並ぶ水槽


毎日届けられる魚介類(平均50サンプル)は、放射能測定のために解体され、細かく刻まれていきます。

気を付けること
「サンプルを取り違えない」「腸内の泥を混入させない」(^.^)

ここで活躍しているパートの女性の皆さんは、地元で漁業を営んでいる家の方が多いそうです。
魚の扱いはお手の物ですね♪
刻まれたサンプルは、このように容器に詰められ・・・

ここで測定されます。

一通り案内していただいた後は、研究員の方々に放射性物質のイロハから測定結果の分析まで、とてもわかりやすく丁寧に説明していただきました。


福島原発の事故から2年以上経過した現在、海水魚は食品の基準値100ベクレルを超えることはないのですが、いまだに淡水魚ではまれに超えることがあるそうです。
短い時間で十分な質疑応答ができませんでしたが、とても充実した視察でした。
オマケの写真です。
研究所から見渡せる外房の海。(この日は霧が濃くて上手に撮れませんでした・・・)

「ドン・ロドリゴ上陸」記念碑。
今から400年前、メキシコにむかう帆船が嵐に巻きこまれて遭難しここ御宿に流れ着いた際、地元の人々が317名の乗組員の命を救ったという有名な実話の舞台です。

まだまだあるのですが、その他の写真は次の機会に・・・。

海生研の皆さん、たいへんお世話になりました。視察に参加された皆さん、お疲れ様でした!




















 k
k