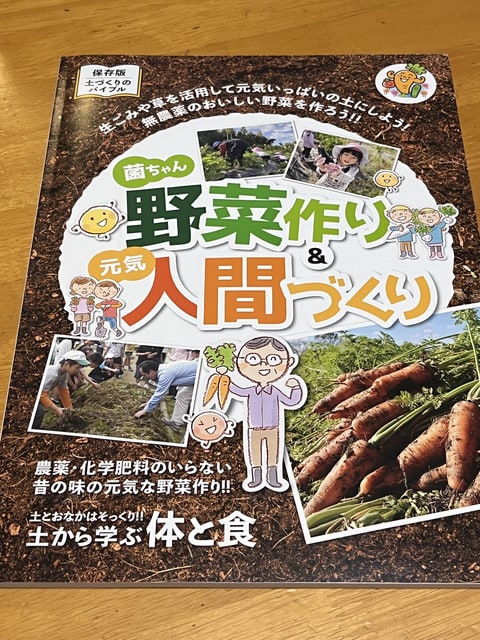特集テーマは、「覚悟を決める」
今月号も学びが多かった。
例えば、田中真澄氏の「人生100年時代を生きる心得」
氏は、次のように書いている。
「100歳人の研究ではっきり分かったことが一つあります。それは100歳まで心身ともに元気で生き抜いた人は、亡くなる直前まで自分の仕事に従事しているという事実です。この事実を、人生100年の人生計画を立てる際の基本的な条件として活かすべきです。
私はこれまでの講演や拙著の中で「辞書から<余生>という言葉を消し、そこに<就寝現役>と書き添えましょう」と言い続けてきたのは、「人生100年」と「終身現役」は密接不可分の関係にあると考えてきたからです。
田中氏の言葉から思い出すのは、私の父母である。
自分の父(85歳)と母(81歳)は、いまだに現役の専業農家として働いている。
55歳の私よりも体力があるのではないかと思うくらい元気である。
このまま仕事をすれば、きっと元気だろうと思う。
逆に、仕事を辞めれば(多分辞めないが)すぐに気力体力共に衰えそうな気がする。
多胡輝氏の本で、「キョウイク」と「キョウヨウ」が大事だという言葉に共通するところがあるかもしれない。
詳しくは、以下のブログに書いたので、よろしかったらお読みください。
ボケないためには、「キョウヨウ」と「キョウイク」がなくちゃいけない?
さて、100歳まで仕事をするために大事な条件があると考えている。
それは、「仕事が道楽になっている」である。
このブログのタイトルにもしている「仕事の道楽化」である。
本田静六氏は、次のように述べている。
私の体験によれば、人生の最大幸福はその職業の道楽化にある。
富も名誉も美衣美食も、職業道楽の愉快さには遠く及ばない。
職業道楽化とは、学者が言うところの、職業の芸術化、趣味化、遊戯化、スポーツ化もしくは享楽化であるが、私はこれを手っ取り早く「道楽化」と称する。
名人と仰がれるような画家、彫刻家、音楽家、文士などが、その職業を苦労とせずに楽しみながら道楽でやっているのと同様に、すべての人がそれぞれ自分の職業あるいは仕事を道楽にするということである。
この8月号には、仕事の道楽化をされている方がいる。
それは、ピアニストの室井摩耶子氏である。百一歳、現役のピアニストである。
室井氏はいう。
今も毎日ひいています。この頃は朝十時くらいまで寝ている日もありますが、この自宅で今言ったような練習をしたり、音楽雑誌の原稿を書いたりして、気がつけば夜中の二時(笑)
この「気がつけば夜中の二時」は、仕事が道楽になっているからこそ言える言葉だろう。
私も室井氏のように「気がつけば夜中の二時」になるくらい仕事を楽しめるようになりたい。