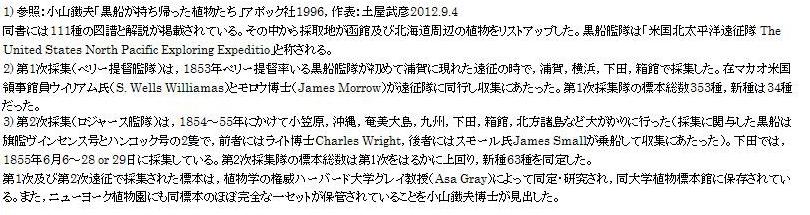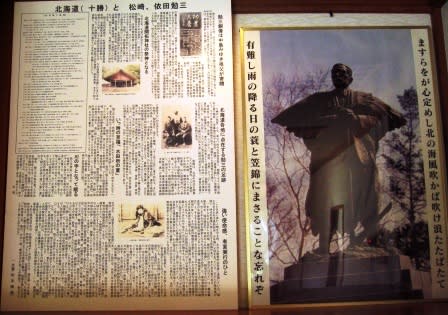ペリーが箱館から持ち帰った植物標本
箱館を訪れたペリー提督は,箱館について「入港しやすさ,その安全さからみて世界最良の港の一つである。位置といい外観といい彼の有名なジブラルタルと似ているのに驚いた」と記している。ジブラルタルは大西洋と地中海を繋ぐ狭い海峡を俯瞰し,町の小高い丘からは対岸アフリカの海岸を見下ろすことのできる重要な軍港であるが,箱館も,孤立した丘(函館山)があって,その麓や斜面には家屋が建っており,一方の高地(横津岳に延びる丘陵)とつながる低い地峡(現在の市街地)は,イギリスの軍港とスペイン領とを分かつ中立地のようであった・・・と続く(参照:在NY日本国総領事館「ペリー提督日本遠征記のエピソード」から)。港は津軽海峡の要諦でもある。
この箱館は,嘉永7年(1854)締結された日米和親条約で,下田と共に開国の港に指定された歴史の町である。函館は今もその面影が残し,世界に誇れる美しさを維持している。

さて本論であるが,開国に向けた激動の歴史の裏側で,黒船艦隊に乗船したプラント・ハンター(植物収集家)が,函館及び北海道周辺からも多数の植物標本を持ち帰っていることを多くの人は知らない。ここでは,小山鐵夫博士1)が解説している111種の中から,採集地が函館及び北海道周辺のものを抽出して表示した(黒船艦隊が函館及び北海道周辺から持ち帰った植物標本)1) 。この他にも,多くの種子や標本が持ち帰られたと言われている。
ところで,黒船艦隊の植物採集以前にも,日本の植物がヨーロッパに紹介されている。以下は,歴史に刻まれた代表的な植物学者たちである。
◆ケンペル(Engelbelt Kaempfer):オランダ商館付きドイツ人医師,博物学者,1690-92年日本に滞在,将軍にも謁見。1712年に出版した「廻国奇観」の中に,日本の植物324種を記載。日本を初めて体系的に記述した「日本誌」の原著者。
◆ツンベルク(Carl P. Thunberg):スウエーデンの植物学者,医学者,リンネに師事し後継者と称されたウプサラ大学教授。1775-76年オランダ商館付き医師として出島に滞在。1784年「日本植物誌」を発刊,812種(うち新属26,新種418)の日本産植物を記載。
◆シーボルト(Philipp F. von Siebold):ドイツ人医師,博物学者,オランダ商館医として1823-29,1859-62年出島に滞在,伊藤圭介,水谷豊文らと多くの植物を採集。
◆ツッカリーニ(Joseph G. Zuccarini):ドイツの植物学者,ミュンヘン大学教授。シーボルト標本を研究し,共著で「日本植物誌第一巻」を出版。ミケル(Friedrik A. W. Miquel):ライデン大学教授,「日本植物誌第二巻」を出版。シーボルトが収集した標本は12,000点,日本植物誌の記載は2,300種になるという。
開国から明治維新に至る激動期にも多くの植物学者が日本を訪れた。
◆マキシモヴィッチ(Carl J. Maximowicz):ロシアの植物学者,1860-64年日本に滞在。日本の開国を知るや函館を訪れ,須川長之助を助手に雇い採集を行った。後にロシアのサンペテルブルグ植物園長。340種を発表。黎明期の日本植物学を育てた(日本の植物学者の植物同定にも協力している)。
◆サヴアチエ(A. L. Savatier):フランス人医師,1873-76年日本に滞在。フランシエ(Adrien R. Franchet)はサヴァチエと共著で「日本植物目録」二巻を出版,2,547種が掲載されている。
これ以降,わが国の植物学は牧野富太郎を初め日本の研究者に引き継がれていく。
江戸から明治初期にかけて,ヨーロッパの医師や植物学者が東洋(日本)で植物採集を行ったのは,「薬と言えば生薬」の時代であった背景がある。結果として,ヨーロッパの一流研究者の訪日は,先駆者として日本植物学の黎明期に貢献したことにもなる。わが国の野山に多く存在する植物の名(学名)に,前述の研究者の名前が付されていることを目にすることが出来る。
この時代の植物採集が先進国の資源戦争であった一面は拭いきれないが,幸いなことは,採集された多くの標本や原本が散逸することなく,各国の植物館・博物館に保存されていることだろう。彼らの業績は,少なくとも明治の植物学者たちに引き継がれている。
註1)小山鐵夫「黒船が持ち帰った植物たち」アポック社1996