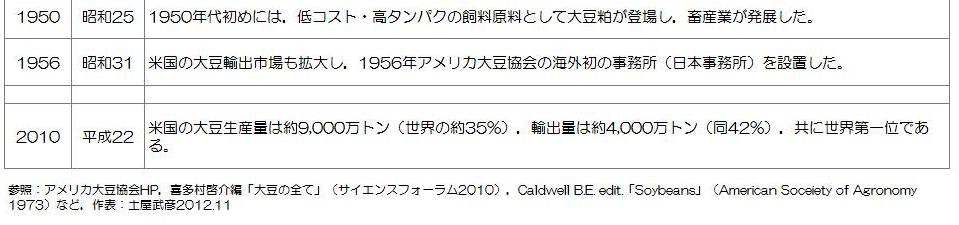北海道に「インゲンマメ」が導入され,栽培が本格化したのは明治時代である。その後多くの品種が育成され,北海道優良品種として普及奨励された品種は現在までに50品種(手亡7,金時14,白金時4,長鶉4,中長鶉5,大福5,虎豆3,その他8)を数える。
それら品種の来歴と特性を紹介しよう(添付)。
◆明治,大正時代に優良品種とされた12品種
北海道への開拓移民が持参し,或いは明治政府が海外(アメリカ合衆国等)から取り寄せた品種が広まり在来種として栽培されていたものを,北海道農事試験場は品種比較試験を行い優良品種として普及奨励した。明治,大正時代に栽培されたこれらの品種は,北海道インゲンマメの先駆けである。
「大手亡」:十勝地方で栽培されていた在来種「新白(しんじろ)」を1923年(大2)十勝支場が大正村(現,帯広市)から取り寄せ,品種比較試験の結果優良品種に認定した。福山(1918)によると,「Kady Washington bean(別称Large White)」「Frenchi White bean」に類似するという。
「金時」:1903年(明36)頃に「朝鮮紅豆」と称して栽培されていた在来種。北海道農事試験場本場が品種比較試験を行い優良品種に認定された。福山(1918)によれば北米の「Dwarf Red Cranberry」であろうという。「Low's Champion」と異名同種。その後,金時類の新たな品種が出ると,「本金」「本金時」の名で呼ばれた。
「長金時」:原名は「Carter's Canadian Wonder」。日本への導入時期は不明である。
「手無長鶉」:明治年間に栽培がみられた在来種。1906年(明39)北海道農事試験場では良種として本品種を掲載している。
「中長鶉」:開拓使時代に札幌農学校で輸入したものであろうとされる。大正時代に入り,半つる性の「中長鶉」「手無長鶉」が広まった。1918年(大7)北海道農事試験場では良種として本品種を掲載している。
「大福」:北海道で古くから栽培されていた。北海道農事試験場本場が品種比較試験を行い優良品種に認定した。
「中福」:北海道で古くから栽培されていたが来歴不詳。福山(1918)によれば「スノーフレーク・フイールド」に類似するという。
「デトロイトワックス」:原名「Detroit Wax」は北米産軟莢種,導入経路は不明である。
「黒手無」:北米産「Cylinder Black Wax」。「シリンダー・ブラック・ワックス」と命名されたが,翌1915年「黒手無」に改称した。
「フラジオーレ」:ドイツ原産「Flageolet Wax」。導入経路は不明。1909年(明42)北海道農事試験場は良種と紹介している。
「ビルマ」:来歴不詳,優良品種決定年には既に7,000haの作付けがあった。粗放栽培で良く生育し「バカマメ」と呼ばれた。
「鶉」:通称「丸鶉」と呼ばれ,1906年(M39)に北海道農事試験場では良種と紹介している。
◆現在の優良品種12品種
インゲンマメの育種は,北海道立総合研究機構十勝農業試験場が実施している(わが国唯一の育種センターである)。また,高級菜豆の育種は同中央農業試験場が担当した。1954年(昭29)から交雑育種が始められ,以降は交雑育種が主流となっている。北海道開拓当時の品種に比べると,農業特性としては格段の改良がなされている。
「姫手亡」:1976 年(昭51)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(十育A-19(Sanilac Pea Bean/改良大手亡)/Improved White Navy)し選抜育成した。中生,叢生,多収。
「雪手亡」:1992年(平4)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(十育A52号/82HW・B1F1)し選抜育成した。中生,叢生,炭そ病抵抗性,多収。
「絹てぼう」:2004年(平16)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(十系A216/十系A212号)し選抜育成した。中生,叢生,炭そ病抵抗性,大粒,加工適性良。
「大正金時」:1957年(昭32)優良品種に決定,1935年幕別町途別の中村宇太郎が「金時」として帯広市の種苗商から購入し栽培したものの中から硬莢種1株を見つけ増殖した早生種を1937年十勝支場が「鶴金時」として導入したが,この時の試験では優良品種にならなかった。1941年大正村上似平の水野利三郎が本品種を購入増殖し広まった結果,1955年には銘柄設定され,十勝支場が改めて品種比較試験をした結果優良品種に決定した。早生,わい性,大粒。
「北海金時」:1979 年(昭54)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(昭和金時/a-32(大正金時/紅金時のF7系統))し選抜育成した。早生の晩,わい性,大粒,多収。
「福勝」:1994 年(平6)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(大正金時/福白金時)し選抜育成した。早生,わい性,大粒,多収。
「福良金時」:2002 年(平14)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(十育B62号(福勝)/十系B203号)し選抜育成した。早生,わい性,大粒,多収,成熟期の葉落ち良。
「福寿金時」:2010年(平22)優良品種に決定,十勝農試が大福のインゲン黄化病抵抗性導入を目標に人工交配(福勝*7/大福,福勝を6回戻し交配,DNAマーカー選抜)し育成した。早生,わい性,大粒,多収,黄化病抵抗性極強。
「福白金時」:1973年(昭48)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(十育B-11号(後の昭和金時)/5823-C-B-4(虎豆/大正白金の後代系統))し選抜育成した。早生の晩,わい性,大粒,多収。
「福粒中長」:1972 年(昭47)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(大正金時/中長鶉(上士幌)後の改良中長)し選抜育成した。中生,半つる性,大粒,多収。
「福うずら」:1998年(平10)優良品種に決定,十勝農試が人工交配(十系D5号/十系B157号)し選抜育成した。早生の晩,わい性,大粒,多収。
「洞爺大福」:1994年(平6)優良品種に決定,中央農試が人工交配(B019/大福*4)し選抜育成した。早生の晩,つる性,大粒,規格内収量多。
「福虎豆」:1988年(昭63)優良品種に決定,中央農試が人工交配(虎豆(端野系)/Concord Poleし選抜育成した。なお虎豆(端野系)は端野町で「虎豆」から選抜された早生種で中央農試が1976年に取り寄せたものである。早生の晩,つる性,良質,良食味。
◆インゲンマメ(菜豆)品種の分類
北海道ではインゲンマメ(Phaseolus vulgaris L.)のことを「菜豆(さいとう)」と呼ぶことが多い。さらに,手竹を立てて栽培する蔓性のインゲンは「高級菜豆(こうきゅうさいとう)」と呼び,この高級菜豆には別種の「花豆」も含まれる。
また,豆としての流通上は「手亡」「金時」「鶉」「虎豆」「大福」などの名称が使われる。こうなると,素人には何が何だかわからない。インゲンマメの種類について補完しておこう。
1) 用途による分類
海外でも用途と草型によって分類されるが,わが国でも同様で,用途の面から生食用(軟莢種)と子実用(硬莢種),草型の面からは“わい性”と“つる性”に大別する。
即ち,用途での分類は,若莢を利用する種類と完熟種子を利用する種類に分かれる。
Ⅰ 若莢を利用する→野菜(サヤインゲン)
Ⅱ 子実を利用する→マメ類
若莢を利用する用途の品種はサヤインゲンと通称され,野菜に分類される。家庭菜園などで多く植えられ,全国に栽培がみられる。生産量の多い都道府県は千葉県(5,840t),北海道(4,040t),鹿児島(3,630t),福島(3,270t)などで,全国集計では42,600t(2011)の生産量がある。
一方,子実生産を目的にする場合はマメ類に分類され,主産地は北海道で(全国の95%生産),9,240tの生産量がある(2011)。
世界の生産状況をみると,ヨーロッパ,アメリカおよびその他温帯の国々では,主として若さやを野菜としてまた冷凍の缶詰にする目的で栽培され,中央アメリカおよび熱帯アメリカの一部では子実生産が行われている。
2) 草型など形態による分類
わい性~半蔓性で栽培に手竹を用いない「(普通)菜豆」と,蔓(つる)性で手竹栽培する「高級菜豆」に大きく分けられる。高級菜豆といっても,何が高級なのか曖昧だ。栽培に手間がかかりコスト高,高価格になるからなのか。味が高級なのか・・・。
高級菜豆には,(普通)菜豆と同じ「インゲンマメ(Phaseolus vulgaris L.)」と「ベニバナインゲン(花豆,Phaseolus coccineus L.)」の異なる二種が含まれる。
さらに,(普通)菜豆は「手亡」「金時」「白金時」「中長鶉」に,高級菜豆は「大福」「虎豆」「白花豆」「紫花豆」に分類される。主な特性と用途は以下のとおりである。
Ⅱ-1菜豆(Phaseolus vulgaris L.)
Ⅱ-1-1手亡類:種皮色白,百粒重30~40g,用途は白餡,煮豆,きんとんなど
Ⅱ-1-2金時類:種皮色赤紫,百粒重60g以上,用途は煮豆など
Ⅱ-1-3白金時類:種皮色白,百粒重60g以上,用途は煮豆など
Ⅱ-1-4中長鶉類:種皮色普斑紋(淡褐地+赤紫斑),百粒重60g以上,用途は煮豆,惣菜など
Ⅱ-2a高級菜豆(Phaseolus vulgaris L. 手竹を用いる)。
Ⅱ-2a -1大福類:種皮色白,百粒重65g以上,用途は煮豆,きんとん,菓子原料など
Ⅱ-2a -2虎豆類:種皮色扁斑紋(白地+臍周辺に黄褐色斑),百粒重65g以上,用途は煮豆,惣菜など。国産豆類中最も良食味とされる。
Ⅱ-2b高級菜豆(花豆,Phaseolus coccineus L. 手竹を用いる)。
Ⅱ-2b-1白花豆類:種皮色白,百粒重150g以上,用途は煮豆,甘納豆など
Ⅱ-2b-2紫花豆類:種皮色普斑紋(淡紫赤地+黒斑),百粒重150g以上,用途は煮豆,惣菜など
参照
日本豆類基金協会1991「北海道における豆類の品種(増補版)」
地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部HP
農林水産省登録品種データベース



















 写真は、日本豆類基金協会「北海道における豆類の品種」
写真は、日本豆類基金協会「北海道における豆類の品種」