今日は、映画サービスデー
12月1日の〈映画の日〉が拡大され、
隔月や毎月の1日も1000円で鑑賞!
となったこともあった。

一部ヒット作を除けば
スクリーンで映画を観る人は減り、
物価高騰の波も当然影響して
1000円は映画の日のみになって久しい。
他の月の1日は1200〜1300円前後に
そのかわり館ごとに、曜日や
50歳以上を含む2人組の割引など
努力は講じられている。
いずれにしろ、今日は標題の
韓国映画『大統領暗殺裁判
〜16日間の真実』を観る予定である。
宣伝の惹句にも〈魂の遺作〉とあるが、
愚直な軍人役のイ・ソンギュン、
最期の出演映画となってしまった。
カンヌのパルムドールを獲得し、
米アカデミーでは4部門受賞の
『パラサイト 半地下の家族』で
大邸宅で暮らすIT企業社長、
TVドラマ『コーヒープリンス1号店』では
主人公の従兄でミュージシャン、
韓国版『白い巨塔』では〝良い医者〟
・・・主人公・財前五郎のライバルで、
田宮二郎に対し山本學、唐沢寿明には
江口洋介が扮した里見脩二に当たる役を
担った180cmの男優は48歳で亡くなった。
一昨年12月27日に。
筆者にとっての イ・ソンギュン
イ・ソンギュン は
は
何を置いても『マイ・ディア・ミスター
〜私のおじさん〜』に尽きる


IUとの上司と部下の関係みならず、
冴えない兄と弟(パク・ホサン、
ソン・セビョク)とのやりとり、
さらには皆が集まる呑み屋のママ役
オ・ナラとの距離感!
 ⋯⋯おっと、今日観に行くのは
⋯⋯おっと、今日観に行くのは
1979年、朴正煕(パク・チョンヒ)
大統領暗殺の裁判を題材にした
チュ・チャンミンがメガホンの映画だ。
17世紀初頭、国王とその影武者となった
道化師をイ・ビョンホンが演じた
『王になった男』を撮ったチュ監督は
連続ドラマ『濁流』の公開も間近。

さて、パク大統領暗殺の混乱のなか
次の独裁者誕生を描くのが『ソウルの春』。
そちらは既に鑑賞済み。
実在の全斗煥(チョン・ドゥファン)を
モデルとした軍人をファン・ジョンミンが怪演し、
話題になったが、『大統領〜』では
同じキャラクターをユ・ジェミョンが!
山本五十六を、三船敏郎(1968年東宝)や
役所広司(2011年東映)が演じたように。
タイプの異なる名優2人の「悪」の見較べも
大いに楽しみ。
午後2時から観るので感想などはまだない。











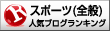





 )、
)、


 」に溢れた作品だった。
」に溢れた作品だった。 )
)





 薔薇や憂鬱同様に読めるけれど⋯
薔薇や憂鬱同様に読めるけれど⋯



 8月13日のこと。
8月13日のこと。



 発行は国語の教科書で有名な
発行は国語の教科書で有名な










 夏休み中の日曜日だったからか、
夏休み中の日曜日だったからか、 売れた
売れた
 キッラキラ
キッラキラ











