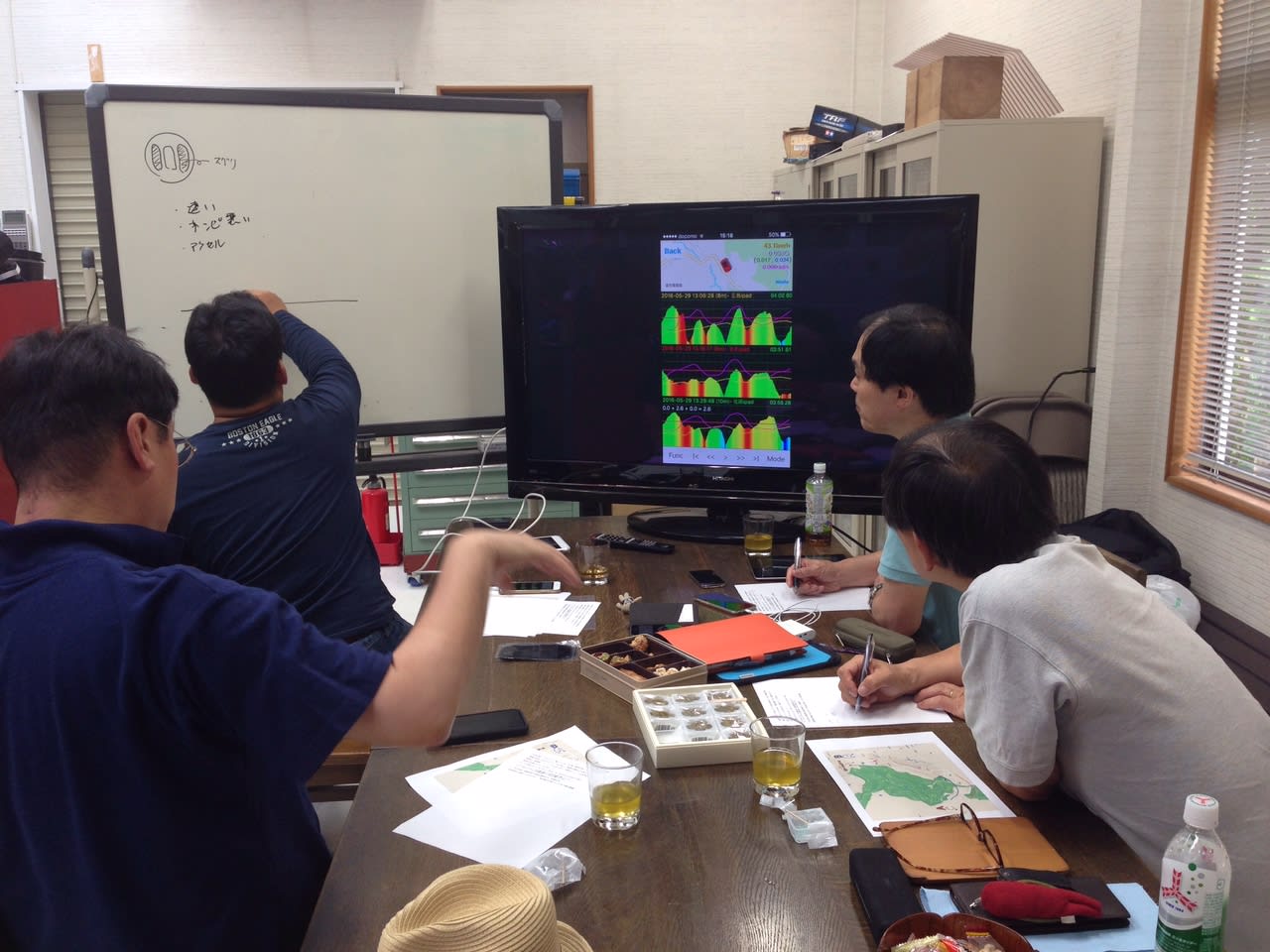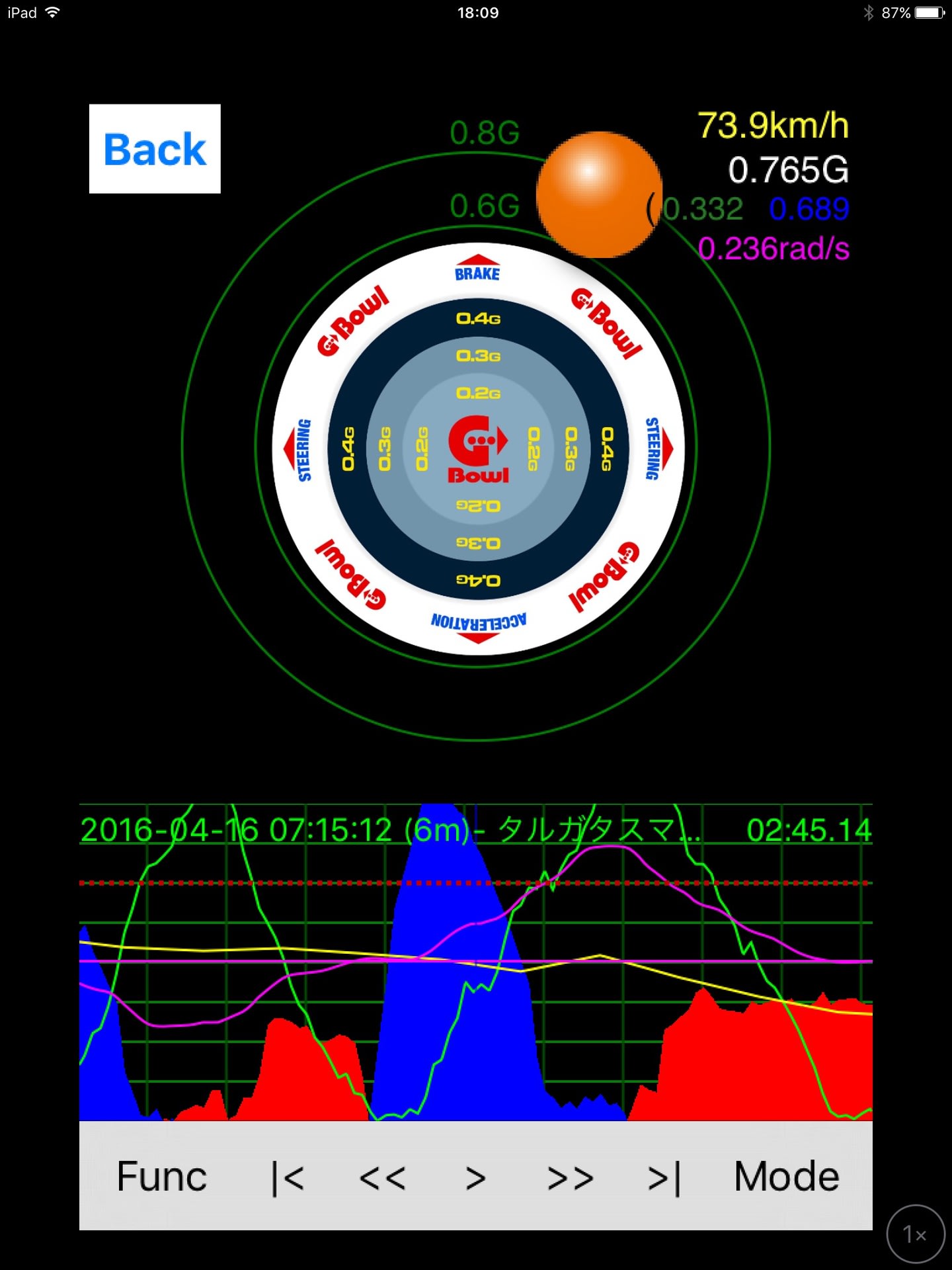FD3Sの前後重量バランスはほぼ50:50。
これはクルマが「停止」している時の、タイヤの下に体重計を置いて計った静荷重(輪荷重)です。
(ないしはコーナーウエイトとも呼ばれます)
輪荷重は、クルマが動けば刻々と変わります。
ブレーキをかければ荷重移動でフロント寄りの60:40とか、加速をすれば後ろ寄りの40:60といったバランスになります。
「静荷重」に対して動き回る荷重・・・「動荷重」
50:50を境に加減速をするたびに、シーソーのように前に行ったり後ろ寄りになったりするということです。
もちろん旋回時は左右でアンバランスになります。
輪荷重については様々なシーンが考えられるものの、組み込むスプリングはおおよそ輪荷重(静荷重)に合わせて選びます。
荷重配分が60:40のフロントエンジンのクルマは、リヤよりも硬いスプリングをフロントに組み込みます。
40:60のミッドシップカーはリヤが重いのでリヤにフロントよりも硬いスプリングを組みます。
フロントの重いFR車あるいはFF車でも、前後のスプリングレートがあまり違わないクルマもあったりします。
さすがにミッドシップ車は前後同じレートにはできません。
どんなクルマであれ限界特性は必ず安定方向であること、つまりアンダーステアーを基本に考えるからです。
こういった考えに当てはめていくと、今回のFD3Sのように50:50のクルマは前後同じ硬さを中心として、
フロントがやや硬めでも、リヤが硬めでも許容範囲に入ると考えることができます。
つづく
これはクルマが「停止」している時の、タイヤの下に体重計を置いて計った静荷重(輪荷重)です。
(ないしはコーナーウエイトとも呼ばれます)
輪荷重は、クルマが動けば刻々と変わります。
ブレーキをかければ荷重移動でフロント寄りの60:40とか、加速をすれば後ろ寄りの40:60といったバランスになります。
「静荷重」に対して動き回る荷重・・・「動荷重」
50:50を境に加減速をするたびに、シーソーのように前に行ったり後ろ寄りになったりするということです。
もちろん旋回時は左右でアンバランスになります。
輪荷重については様々なシーンが考えられるものの、組み込むスプリングはおおよそ輪荷重(静荷重)に合わせて選びます。
荷重配分が60:40のフロントエンジンのクルマは、リヤよりも硬いスプリングをフロントに組み込みます。
40:60のミッドシップカーはリヤが重いのでリヤにフロントよりも硬いスプリングを組みます。
フロントの重いFR車あるいはFF車でも、前後のスプリングレートがあまり違わないクルマもあったりします。
さすがにミッドシップ車は前後同じレートにはできません。
どんなクルマであれ限界特性は必ず安定方向であること、つまりアンダーステアーを基本に考えるからです。
こういった考えに当てはめていくと、今回のFD3Sのように50:50のクルマは前後同じ硬さを中心として、
フロントがやや硬めでも、リヤが硬めでも許容範囲に入ると考えることができます。
つづく