
レース専用のダンパーは、フルハードからフルソフトまでの調整ダイヤルの可動範囲の中央あたりのどこかに
実戦で使われるであろう標準的な減衰値が設定されます。
そこから柔らかくしたい硬くしたいの振り幅があって、
バネレート、気候、ダウンフォース、タイヤ個々、エアー圧、サーキット路面など
に合わせて調整式ダンパーは本領発揮。
ところがサーキットの現場で、"伸び側フルハード" "圧側フルハードから2クリック戻し"
しかもダンパーの銘柄が変わっても、サーキットが変わってもドライバーが変わっても
調整ダイアルの位置は同じ!?という調整パターンを見かけます。
ちなみにですが、レーシングカー用のダンパーをテスターにかける場合は、
必ず調整ダイヤルのフルソフトから始めて、減衰値を見極めてから徐々にハードな方向を測定します。
フルハードではダンパーテスターを破壊しかねないほどの「高減衰」が仕込まれているからです。
論外に硬いバネでも選ばない限り、レース専用ダンパーのフルハードが必要になることはありません。
DTMのマシン&レースでは少々の小競り合い程度で車両どうしが接触してもスピンしないし、
コースから弾き出されてもすぐに戻ってきて、格闘技らしいそれが見世物になっているところがあります。
*主催者も容認しているようで、滅多にペナルティーの対象にならないことと、
ドライバーが逆手にとって無茶している様にも見えません。
国内のそれはというと接触するとあっという間にスピンして一巻の終わり。
あまりにも"粘り気のない"挙動で、同じカテゴリーのレースカーに見えません。
タイヤは垂直荷重でグリップを得るので、グリップを失うということは
その時にタイヤ荷重がかかっていないということ。
荷重が抜ける理由は、フルハードのダンパーのせいでタイヤが車体側に拘束され、
バネ下の振動数では動かず、横から体当たりされるとタイヤ荷重が戻るまでの
わずかな間合いでスピンに至ります。
しゃがみこんでいる人が肩を押されると、足を伸ばす前にゴロンと転がるのに似ています。
LSDが左右輪の自由な回転を拘束して、デファレンシャルギヤの働きを消すように、
フルハード、つまり過減衰のダンパーはサスペンションの可動ストロークを
封じ込めてタイヤの接地性を失わせます。
減衰力の適値を探すのがサスペンションチューニング、減衰力調整式ダンパーはそのためのものです。
実戦で使われるであろう標準的な減衰値が設定されます。
そこから柔らかくしたい硬くしたいの振り幅があって、
バネレート、気候、ダウンフォース、タイヤ個々、エアー圧、サーキット路面など
に合わせて調整式ダンパーは本領発揮。
ところがサーキットの現場で、"伸び側フルハード" "圧側フルハードから2クリック戻し"
しかもダンパーの銘柄が変わっても、サーキットが変わってもドライバーが変わっても
調整ダイアルの位置は同じ!?という調整パターンを見かけます。
ちなみにですが、レーシングカー用のダンパーをテスターにかける場合は、
必ず調整ダイヤルのフルソフトから始めて、減衰値を見極めてから徐々にハードな方向を測定します。
フルハードではダンパーテスターを破壊しかねないほどの「高減衰」が仕込まれているからです。
論外に硬いバネでも選ばない限り、レース専用ダンパーのフルハードが必要になることはありません。
DTMのマシン&レースでは少々の小競り合い程度で車両どうしが接触してもスピンしないし、
コースから弾き出されてもすぐに戻ってきて、格闘技らしいそれが見世物になっているところがあります。
*主催者も容認しているようで、滅多にペナルティーの対象にならないことと、
ドライバーが逆手にとって無茶している様にも見えません。
国内のそれはというと接触するとあっという間にスピンして一巻の終わり。
あまりにも"粘り気のない"挙動で、同じカテゴリーのレースカーに見えません。
タイヤは垂直荷重でグリップを得るので、グリップを失うということは
その時にタイヤ荷重がかかっていないということ。
荷重が抜ける理由は、フルハードのダンパーのせいでタイヤが車体側に拘束され、
バネ下の振動数では動かず、横から体当たりされるとタイヤ荷重が戻るまでの
わずかな間合いでスピンに至ります。
しゃがみこんでいる人が肩を押されると、足を伸ばす前にゴロンと転がるのに似ています。
LSDが左右輪の自由な回転を拘束して、デファレンシャルギヤの働きを消すように、
フルハード、つまり過減衰のダンパーはサスペンションの可動ストロークを
封じ込めてタイヤの接地性を失わせます。
減衰力の適値を探すのがサスペンションチューニング、減衰力調整式ダンパーはそのためのものです。


















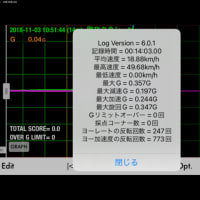

メーカーもなぜそんなハードな減衰値を設定したのか疑問です。
フルハードを選択する理由は単純です。
例えばAB二種類のバネがあったら硬い方。
減衰力調整が二段調整ならハードな方。
車高はこれ以上ないところまで下げる。
車高を下げてサスペンションを固めれば速く走れるはず⋯と思い込んでいる誰かがやっていることです。
フルハードを選択しているのはダイヤルを捻る人の"心情"であって、コースとか状況ではありません。
メーカーも・・・の下は。
サスペンションセッティングで使うをバネ準備するとしたら、使わないかもしれないソフトなものからこれはないだろう、でも一応、のハードなものまで必ず準備します。
ダンパーも同じで、調整ダイアルの中に必要な減衰値を入れれば、使わないであろう範囲が端っこにあって当然です。
そして何より、ダンパーを手にするのは"プロ"のエンジニア⋯
危険なほどの減衰値が仕込まれていたとしても、適値を探し出す当たり前のテストを行えばフルハードには行きつかないはずです。
もしもフルハードが答えに近いとなったら、もっとハードを試してみたくなるはずです。
でも事前テストを経て準備されたダンパーではおそらく起きないことかと。